ここ数ヶ月間、コツコツと準備をして来た行事があった。日印交流年の一環として行われる「子供の日祭り(Childresn's Day of Japan
"Hum Punchi Eik Dall Kei")」である。「Hum Punchi Eik Dall Kei(हम पंछी
एक डाल के)」とは、「我らひとつの枝の小鳥たち」という意味。 主催はインド日本文化評議会(ICJC)のラージ・ブッディラージャー会長。イベントは3日間に渡って国際交流基金ニューデリー日本文化センターで行われる。本日5月5日の子供の日には、日本とインドの子守唄と童謡をテーマとした詩会、デリー日本人学校の有志が結成したデリー和太鼓クラブのパフォーマンス、日本とインドの玩具の展覧会のオープニング・セレモニーが行われた。7日と8日には、折り紙のデモンストレーションとワークショップが予定されている。僕が主に関わっていたのは、詩会であった。
日本とインドの伝統的またはオリジナルの子守唄や童謡を集め、詩会で発表するというのがコンセプトであった。日印交流のイベントであり、両国からの出席者が予定されていたので、日本語の詩歌を英語またはヒンディー語に、インドの詩歌を日本語に翻訳する必要があった。僕はその仕事を担当していた。
まず、子供の日のイベントということで、日本の行事に関連した歌を集めた。「たのしいひなまつり」「こいのぼり」「お正月」「たなばたさま」である。子守唄では、「江戸子守唄」「ゆりかごの歌」「五木の子守唄」など、童謡では四季をイメージして、「春が来た」「海」「赤とんぼ」「雪」などの他、日印交流史上、象徴的な存在となっている象をテーマにした「ぞうさん」を取り上げた(以下の囲みを参照)。また、僕を含めた日本人参加者がオリジナルの詩を披露した。
8.上野動物園とインド象
(1)戦後の寄贈
ネルー首相が1949年、東京の小学生の要望に応えて上野動物園にインド象(ネルー首相の令嬢の名をとり「インディラ」と命名)を贈ったことは有名。敗戦のショックが癒えぬ日本人、とりわけ子供達にとって明るいニュースであった。上野動物園には戦時中、軍部の命令により三匹の象を含む動物達が餓死或いは毒殺に追いやられたという悲痛な過去がある。心ある人は、「象」という動物を介して戦争の悲惨さ、平和の有難さを痛感したに違いない。象の寄贈自体は小さな出来事でも、それがその時代に持っていた意味には極めて重いものがあった。
(2)現在も続く交流
「インディラ」は老衰のため1983年8月に死亡したが、その死は新聞等で大きく報じられ、多くの人々により悼まれた。1984年中曽根総理訪印を機に、インディラ・ガンジー首相よりインディラに代わるものとして2頭の子象「アーシャー」(希望)と「ダヤー」(慈悲)が上野動物園に寄贈された。
また、2000年1月のフェルナンデス国防相の訪日に際し、新たな子象「スーリヤ」(太陽)の寄贈の申し出がなされた。「スーリヤ」は、2001年4月に上野動物園に到着した。
(引用元:外務省:インド話題集)
一方、インドの詩歌からは、まずヤジュルヴェーダからサンスクリット語の子守唄を取り上げ、次にブラジ語とアワディー語の中世の詩を選んだ。スールダースの「スールサーガル」から数節、トゥルスィーダースの「カヴィターワリー」から数節を取り上げた。その後、現代の文学者や詩人たちから、自作の子守唄や童謡を集めた。シェールジャング・ガルグ、クルディープ・ディーパー、ラージャー・クグシャール、ウルミル・サティヤブーシャン、ラージ・ブッディラージャーなどの詩を集めた。ちなみに、日本の童謡「ぞうさん」の返答として、シェールジャング・ガルグの童謡「हाथी
की बात(象さんの話)」を盛り込んだ。
हाथी की बात
शेरजंग गर्ग
हाथी की है बात महान
हाथी के हैं दाँत महान
भीतर भीतर खाने के हैं
बाहर सेर्फ़ दिखाने के हैं
* * *
象さんの話
シェールジャング・ガルグ
象さんはとってもすごい
象さんの歯はとってもすごい
中には食べるための歯
外には飾りのための歯
日本の「ぞうさん」が鼻を題材にしている一方、シェールジャング・ガルグの「象さんの話」が歯(牙)を題材にしているところが面白い。
これらの詩歌とその翻訳を編集したものを一冊のパンフレットにした。これが完成したのは5月に入ってからであった。
それらの詩歌の編集を行っていて気付いたのだが、インドには、「インド人なら誰でも知ってる童謡」みたいなものがほとんどない。映画音楽を除けば、インドには全国的に広く知られている歌があまりないのである。誰でも知ってるような伝統的な詩歌をなるべく取り上げたかったのだが、ヒンディー語ではそういうものが出て来なかった。仕方なくブラジ語やアワディー語など、現在ではヒンディー語の方言として扱われている言語の文学作品から抽出した。おそらくインドでは「童謡」という分野はあまり認知されていないのだろう。よって、今回の詩会は、普段あまりクローズアップされることに少ない童謡詩人に焦点を当てることができたのではないかと思う。
また、「日本人なら誰でも知ってる童謡」は、案外最近になって作られたものが多かった。著作権があるものも少なくなかった。日本人の間でそれらの歌が一般によく知れ渡っているのは、テレビの影響や、教育の均等性によるものだと考えられる。
招待状を70通ほど送付したようなので、会場には一応70席用意したが、それらが全て埋まるほど人は集まらなかった。だが、ウルミル・サティヤブーシャン以外、詩を取り上げた詩人は皆出席した。最初に日本の子守唄や童謡の歌唱、朗読を行った。その後、インドの子守唄と童謡の朗読があった。
ところで、主催者のブッディラージャー女史から、僕もひとつオリジナルの子守唄か童謡を作るように催促された。詩歌の翻訳はお安い御用であったが、詩作は難航した。そもそも子守唄や童謡は子供を持っている人が自分の経験などを元に作るべきものだ。そうでなかったら子供自身が作るべきである。子供でも子持ちでもない僕には、困難な課題となった。しばらく頭を悩ませていた。だが、幸いにして、親しいインド人の友人に1歳半くらいの子供がおり、その子と遊ぶ機会に恵まれていた。その体験を元に、ひとつヒンディー語の詩をひねり出してみた。
他の年の子供のことはよく知らないが、1歳~2歳くらいの子供は、目の前のもの全てを玩具だと思っているようだ。玩具ももちろん玩具だが、それ以外の普通の品物も玩具なのである。眼鏡、コップ、TVのリモコン、クッション、椅子、携帯電話、メジャー、雑巾、マウス、とにかく目に見えるもの何でも触って確かめようとする。そして、大人たちが使っているように使おうとする。僕自身ですら玩具だと思われているようだ。その結果、僕が子供と遊んであげているのに、実際は子供が僕で遊んでいることになっているのである。また、子供は動くものに敏感に反応する。インドの家だと、日本の都会の家に比べていろんな動物や虫がやって来るので、友達がいっぱいだ。日本にはいろいろな玩具が売られているが、結局、その年の子供はどんなものでも玩具にしてしまうし、自分で楽しむ方法を知っているから、わざわざ玩具らしい玩具を与える必要ないんじゃないかと思った。そんな様子を詩にしてみた。
हम बच्चे दुनिया से खेलेंगे
हम बच्चे दुनिया से खेलेंगे
हम समझे दुनिया खिलौना है
क्यों हमें खिलौने देते हैं
उँगली खिलौना है, नाक खिलौना है
बाल खिलौना है, सब खिलौना है
आप हमें नहीं खिलाते हैं
हम ही आपको खिलाते हैं
देखना खेल है, सूँघना खेल है
छूना खेल है, सब खेल है
हमें गाना सुनाते हैं हँसाते हैं
पर ख़ुशियाँ हम देते हैं
कबूतर दोस्त है, छिपकली दोस्त है
चूहा दोस्त है, सब दोस्त है
बचे हुए को बच्चे कहते हैं
हम आपको सिखाते हैं
हम बच्चे दुनिया से खेलेंगे
हम बच्चे सपने से भी खेलेंगे...
* * *
僕たち子供たち 世界で遊ぶんだ
僕たち子供たち
世界で遊ぶんだ
僕たちは知ってる 世界が玩具だってことを
どうして僕たちに玩具をくれるの?
指も玩具だし、鼻も玩具だし
髪も玩具だし、全てが玩具
僕たちが遊んでもらってるんだじゃないよ
僕たちが遊んであげてるんだよ
見ることも遊びだし、嗅ぐことも遊びだし
触ることも遊びだし、全てが遊び
歌を歌ってくれても、笑わせてくれても
喜びは僕たちが与えてる
鳩も友達だし、イモリも友達だし
鼠も友達だし、全てが友達
残った存在を子供と言う
僕たちがみんなを教えてる
僕たち子供たち
世界で遊ぶんだ
僕たち子供たち
夢でも遊ぶんだ・・・
日本語訳、下から6行目の「残った存在を子供と言う」だけ解説が必要だろう。ヒンディー語では子供のことを「バッチャー」と言うが、この言葉は「後に残った」という意味の「バチャー」という単語に似ている。そのことを言っている。通常、人間で「後に残る」のは老人である。だが、よく言われることではあるが、子供というのは哲学者として生まれて来るのだと思う。純粋かつ偉大な存在なのである。その純粋さ、偉大さを失ってしまった大人から見れば、子供らしさを失っていない子供というのは「まだ残っている」存在なのである。と言う訳で、「残った存在を子供と言う」という一節を書いた。日本語ではうまく表現できないので、こうやって長々と説明しないといけないが、ヒンディー語では分かってもらえただろう。
全然自信作ではなかったのだが、なぜか出席者に大好評。どうも僕の意図した内容とは別の受け止め方をされているような気もして複雑な気分だったのだが、文学者から詩を褒めてもらって悪い気はしない。日本人がヒンディー語で詩を作っているという物珍しさから、お世辞で褒めてくれているのだと思うが、嬉しかった。
詩会の後は、会場のすぐそばにあるヴィクラム・ホテルで昼食を食べた。その後、4時からデリー和太鼓クラブのパフォーマンスがあった。日本人学校の教師や生徒の親で結成された同クラブは、インドのマンゴーツリーを使って和太鼓をワンセット作り、日々鍛錬に励んでいるようだ。クラブを称しているだけあり、文化祭などのために間に合わせで結成したような和太鼓グループとは違う、素人離れした調和と迫力があった。しかも本格的な和太鼓演奏に加え、インド人向けにボリウッドのヒット曲をアレンジした演目も用意していたりして、なかなか心憎い演出をしていた。
和太鼓演奏の後は、地階ギャラリーの展覧会のオープニング・セレモニーが行われた。地階には、ひな祭り用のひな壇、端午の節句用の鎧兜、こいのぼりなどに加え、インドと日本の玩具が展示されている。この展示は5月7日と8日にかけて開催されている。
何はともあれ、詩会が終わったことでひとつ肩の重荷が下りた気分だ。差し当たって残っている重荷は論文提出のみ。既に原稿は完成しており、指導教官のチェックも終わり、論文提出手続きのためのサイン集めも完了(インドの大学では、何らかの手続きをする際、まるでドラクエのフラグ立てように、偉い人のサイン集めに奔走しなければならない)。後は製本して提出するだけの段階まで来ているので、これが完了するのも時間の問題である。
【追記1】5月7日付けのヒンディー語新聞ダイニク・ジャーグランの折込紙「ジャーグラン・シティー」の2ページ目に、5日の「子供の日祭り」の記事が写真付きで掲載された。

写真は左からアルカカット、デリー大学の留学生、
ブッディラージャー女史、日本大使館の菊池実カウンセラー
記事の内容は以下の通りである。
■・・・心の秘密を打ち明けるでしょう
「小さな人形がやって来た、まだとってもまごついている、その内しゃべるようになるでしょう、心の秘密を打ち明けるでしょう・・・」日本の子供の日に、ラージパト・ナガルのジャパン・ファウンデーションのオーディトリアムで開催されたプログラム「Hum
Punchi Eik Dall Kei」において、詩人たちがこのような詩を詠んだ。
プログラムでは、日本語とヒンディー語に翻訳された詩も詠まれた。文学者ドクター・ラージ・ブッディラージャーは、「母性愛は、たとえ日本であってもインドであっても変わらない」と語った。
彼女は、「2007年は『日印交流年』とされている。私たちは、インド人と日本人をより近付けるため、重要な仕事をしている」と語った。
このプログラムには、インド大使アルジュン・アスラーニー、ラジオ局のアルジュン・セーティヤー、ヨーガ教師プレーム・バーティヤー、DKククレージャーなどが出席した。
ちなみに僕はタイムズ・オブ・インディア紙の折込紙デリー・タイムスのページ3(セレブリティーのパーティー特集ページ)に載ることを人生最大の目標のひとつとしているが、とりあえず大手ヒンディー語紙のページ2に載ることができて、有意義な一歩を踏み出すことができたと思っている。
【追記2】5月7日付けのヒンディー語紙ナヴバーラト・タイムスにも子供の日祭りの記事が掲載されていた。ナヴバーラト・タイムスは大手英字新聞タイムズ・オブ・インディアと同じグループである。だが、写真なしの非常に小さな記事であった。ナヴバーラト・タイムスから来ていた記者とは僕が話したため、その内容がそのまま掲載されていた感じであった。
■日本の子供の日にイベント
インド日本文化評議会と日本大使館共催の日本の子供の日を祝うイベントがジャパン・ファウンデーションで行われた。榎日本大使婦人とラージKブッディラージャー女史が開会式を行った。JNUでヒンディー文学の研究をする日本人留学生アルカカット(本名掲載)が、童謡「僕たち子供たち、世界で遊ぶんだ」を日本語とヒンディー語で詠んだ。ヒンディー詩人ラージャー・クグシャール、クルディープ・カウル、シェールジャング・ガルグも詩を詠んだ。それらの詩の日本語訳も詠まれた。ブッディラージャー女史は、「『Hum
Punchi Eik Dall Kei』という題名のこのイベントは、両国の相互理解を深めるために催された」と語った。
この他、国会議員に読まれているヴァンデーマータラムという新聞にもこのイベントの記事が掲載されたようだが、今のところ入手できていない。
「これでインディア」はインドの情報満載だが、食に関する情報だけは弱いと言われている。それもそのはず、作者の僕自身があまり食に興味がないので、こうなってしまうのである。本日の日記の題名は「インドの食」。だが、タンドゥーリー・チキンとか、カーコーリー・カバーブとか、ハイダラーバーディー・ビリヤーニーとか、そういう話ではない。もっと哲学的な食の話をしようと思う。
インドの挨拶は「ナマステー」「ナマスカール」だと一般に言われている。確かに、これらの言葉を知っていれば、とりあえずインド人とのコミュニケーションの掴みはOKだ。だが、比較的よく知られているように、これらの挨拶は主にヒンドゥー教徒の間で使われる。イスラーム教徒には「アッサラーム・アライクム」や「アーダーブ・アルズ」という挨拶が効果的だし、スィク教徒には「サト・スリー・アカール」と言えば受けがいい。しかし、普通の日本人には相手の宗教が何かを判断するのは難しいので、とりあえず「ナマステー」「ナマスカール」を使うのが無難であろう。
「ラームラーム」「スィヤーラーム」「ハリ・オーム」「ジャイ・クリシュナ」「ラーデーラーデー」「シヴシヴマハーデーヴ」「マーター・キ・ジャイ」などなど、ヒンドゥー教の神様の名前を唱えて挨拶とすることもある。ヒンドゥー教の聖地に行くと、これらの挨拶を使う人が増える傾向にある。だが、「ナマステー」「ナマスカール」と合わせて、これらの挨拶は決して古いものではない。これらの挨拶はつまり、「私はヒンドゥー教徒である」、もっと言えば、「私はイスラーム教徒ではない」と主張しているのであり、ヒンドゥー教とイスラーム教の間の溝が深まったときから生まれたものと考えられる。
「カェセー・ハェン?」「キャー・ハール・ハェ?」などという挨拶もある。「お元気ですか?」みたいな意味のフレーズである。しかし、これらも英語の「How
Are You?」の訳であり、やはり古いものではない。
本当にインドで使われていた挨拶は、「カーナー・カーヤー?」である。「食べ物は食べたかい?」という意味だ。食事を取るべきときにちゃんと何か食べたかどうか、この質問ほどその人のその日の状況を表すバロメーターはない。何か不幸があったり、悩みがあったり、問題があったりしたとき、人は食べることを忘れてしまうものだ。もちろん、経済的に困窮していれば食事もできない。それに、「お元気ですか?」と聞かれて正直に自分の境遇を話す人はあまりいない。「Everybody
Says I'm Fine」(2001年)という映画があったが、誰でも言葉だけは「元気です」と答えるものだ。「カーナー・カーヤー?」はただ馬鹿みたいに食事をしたかどうかを聞いているのではなく、その日食事ができるだけの幸せがあったかどうかを聞いているのである。
インドの村では、チューラーという竃で料理をする。チューラーからは煙が出る。村の地主は、食事時になると高いところから村の各家庭から煙が出ているかを確認する(通常、地主の家が村で一番高い建物だ)。煙が出ていれば問題なし。もし煙が出ていない家庭があれば、そこでは何か問題が起こっているということである。煙が出ていないのを見つけると、地主は召使いに命じて何があったか聞きに行かせる。インドでは、食という生きていく上で最も重要な行為に対する重きがとてもよく残っているように思われる。
こういう考え方はインドだけかと思っていたが、中国に詳しい友人の話では、中国でも食べ物を食べたかという質問が挨拶になっているらしい。多分「ニーハオ」もそれほど古い伝統を持った挨拶ではないのだろう。食文化という観点ではインドと中国は全く正反対だが、その根本には共通点があるかもしれない。日本でも昔はそのような習慣があったかもしれないが、現在の日本ではあまりに食が軽視されてしまっており、そのような印象は受けない。街へ出れば簡単に外食できるし、コンビニへ行けばいろいろな弁当が手に入るし、スーパーマーケットでは手軽なレトルト食品が手に入る。このような環境で、「食べ物は食べた?」という挨拶は意味を成さない。その上、グルメグルメとうるさく言う人がおり、食べることは当たり前、うまいもの、珍しいものを食べることが偉いこと、素晴らしいこと、のような風潮がある。グルメというのは結局、食を軽視する文化のように思える。食べ物に関して重要なのは2点のみ。ひとつは、子供の頃から食べているものが一番うまいということ、もうひとつは、腹が減っているときに食べるものは何でもうまいということである。食に関して、それ以外の理論をあれこれこね回す人間は信用ならないし、信用してはならない。インドでも都市部を中心に先進国風の食文化が浸透して来たが、それでもまだまだ古くストイックな食文化が頑張っている。インド料理の豊富さは、頑固さから来ているのだと最近感じる。決してグルメのためにバラエティーを作っているのではなく、その土地の風土と季節に応じた料理をそれぞれの地域で守って来ているだけだ。まず大事なのは、食べること。「カーナー・カーヤー?」この挨拶ほど人を思いやる言葉は存在しないだろう。
と言うわけで、「これでインディア」に食に関する情報が少ないのも、インドの食哲学の根本を捉えているからだと思っていただきたい。
| ◆ |
5月11日(金) Life In A... Metro |
◆ |
ここ1週間何かと忙しくて、先週公開された「Yatra」は見逃してしまった。だが、本日より公開の「Life In A... Metro」は見逃すまいと、暇を作って公開初日に映画館に見に行った。
題名:Life In A... Metro
読み:ライフ・イン・ア・メトロ
意味:大都市の生活
邦題:ある都市の物語
監督:アヌラーグ・バス
制作:ロニー・スクリューワーラー
音楽:プリータム
作詞:サイード・カドリー、アミターブ・ヴァルマー
出演:ダルメーンドラ、ナフィーサー・アリー、シャイニー・アーフージャー、シルパー・シェッティー、コーンコナー・セーンシャルマー、カンガナー・ラーナーウト、ケー・ケー・メーナン、シャルマン・ジョーシー、イルファーン・カーンなど
備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左上から時計回りに、コーンコナー・セーンシャルマー、シャイニー・アーフージャー、シルパー・シェッティー、カンガナー・ラーナウト、イルファーン・カーン、ケー・ケー・メーナン、シャルマン・ジョーシー
| あらすじ |
ムンバイー。ランジート(ケー・ケー・メーナン)とシカー(シルパー・シェッティー)夫妻は、表向きは仲のいい夫婦を演じていたが、実際は喧嘩ばかりしていた。シカーはかつてのバラタナーティヤムの師匠ヴァイジャンティー(ナフィーサー・アリー)の世話をしていたが、それ以外は退屈な主婦業をしていた。ヴァイジャンティーの夫は既に死去しており、老人ホームに住んでいた。そんなとき、ヴァイジャンティーの元に一通の手紙が届く。かつての恋人アモール(ダルメーンドラ)であった。アモールは数十年前に米国へ行ってしまったが、死期が迫っているのを知り、最期のときをヴァイジャンティーと共に過ごすためにインドに戻って来ようとしていた。2人は時を越えて再会し、失われた青春を取り戻すかのように共に時間を過ごす。
ランジートはコールセンターの社長を務めていた。そこで働くラーフル(シャルマン・ジョーシー)は、父親の遺産で立派なマンションの一室に住んでいた。だが、そのマンションの鍵はオフィスの上司たちの間で争奪戦となっていた。自分の恋人と一夜を楽しむためである。ラーフルはマンションの鍵を使ってオフィスで人脈を築いていた。だが、彼には意中の女性がいた。同じオフィスで働くOLネーハー(カンガナー・ラーナウト)である。内気なラーフルであったが、ネーハーに少しずつアプローチする。だがある日、社長ランジートの愛人がネーハーであることに気付いてしまう。
ネーハーは、シュルティー(コーンコナー・セーンシャルマー)という奥手の女の子とルームシェアして住んでいた。シュルティーはシカーの妹で、ラジオ局に勤めていた。彼女は結婚を考えており、結婚紹介サイトを使って結婚相手を探していた。あるとき彼女は、デーブー(イルファーン・カーン)というちょっと変な男性に出会う。だが、おっぱいを凝視するデーブーの性癖に嫌気が差した彼女はデーブーを拒否する。しかし、その後もデーブーと再会を繰り返すようになる。シュルティーはラジオ局のDJに恋しており、彼とデートもするが、ある日彼がゲイであることが分かってしまう。それを機にラジオ局を辞め、新しい仕事を探していた。面接先で働いていたのがデーブーであった。デーブーは彼女を採用させ、その後2人の関係は次第に縮まって行く。
シカーはバス停でアーカーシュ(シャイニー・アーフージャー)という男性と出会う。アーカーシュは演劇にのめり込むあまり、妻に逃げられてしまった過去を持っていた。バス停での出会いを繰り返す内に、2人の仲は接近する。シカーは不倫に対する罪悪感から自分の行動を制止しながらも、彼の家まで行ってしまう。だが、罪悪感を振り払うことはできず、シカーは突然逃げ出す。
ランジートの愛人をしていたネーハーは、次第に本当の愛を求めるようになる。割り切った関係を望んでいたランジートはネーハーを見捨てようとする。それにショックを受けたネーハーは洗剤を飲んで自殺を図る。マンションに帰って来たラーフルはネーハーを発見し、病院へ連れて行く。ネーハーは一命を取り留める。このときランジートはバンガロールに出張中ですぐには戻れなかった。ラーフルはネーハーの看病をし、退院後も数日間自宅に泊める。ルームメイトがずっと行方不明なのを心配したシュルティーはラーフルの家を探し出し、ネーハーを連れ帰る。このとき出張から帰って来たランジートと出くわしてしまう。シュルティーは、ネーハーの付き合っている相手が自分の姉の夫であることを知る。
家に帰ったランジートは、シカーが泣いているのを見て、シュルティーが全てを暴露したものだと勘違いし、全てを明かしてしまう。だが、シカーは自分が不倫の寸前まで行ったことで泣いていたのだった。夫の不倫の話を聞いたシカーは、自分の間違いの話をし出す。それに怒ったランジートは家を出て行ってしまう。
ランジートとネーハーの関係はまだ続いていた。だが、ラーフルは次第に自分の間違いを自覚し始める。自身の昇進のために愛を犠牲にすることはもはやできなかった。ラーフルはランジートに鍵を貸すのを拒否し、退職願いを出す。それを知ったネーハーは、ラーフルの愛こそ本物の愛であると感じ、ランジートから逃げ出してラーフルを追い掛ける。ラーフルはチャーチゲート駅へ向かっていた。
アモールとヴァイジャンティーは初めて一夜を同じベットで過ごす。だが翌朝、ヴァイジャンティーは突然倒れてしまう。救急車で運ばれるヴァイジャンティーだったが、途中で渋滞にはまってしまい、そのまま息を引き取ってしまう。シカーとシュルティーも病院を訪れる。アモールは2人に、「あのとき頭の言うことではなく、心の言うことを聞いていれば、どんな幸せな時間を過ごせたことだろう」と語る。
デーブーは既に親の決めた相手と結婚をすることを決めており、結婚式も近付いていた。だが、シュルティーは次第にデーブーの人柄に惹かれるようになる。シュルティーはデーブーの結婚式の日に一大決心をし、結婚式会場に飛んで行って、愛の告白をする。驚いたデーブーはいい加減な返事しかできなかった。シュルティーはすぐに会場を後にし、オートリクシャーに乗って去って行くが、馬に乗ったデーブーは彼女の後を追い掛ける。シュルティーはチャーチゲート駅に向かっていた。
アーカーシュは演劇の夢を諦め、ドバイで働くことを決めた。その前にシカーに一目会いたくて彼女にメッセージを送る。「僕と一緒に行くためでもいい、僕を引き止めるためでもいい、とにかく来てくれ。」アーカーシュはチャーチゲート駅で彼女が来るのを待っていた。シカーはアーカーシュに会いに行こうとするが、そのときランジートが家に帰って来る。ネーハーに逃げられ、散々な目に遭ったランジートはひどい格好をしていた。それを見たシカーは、家族を捨てることはできないと実感する。それでもシカーはチャーチゲート駅を訪れ、アーカーシュに「新しい人生、頑張って」と声を掛ける。その言葉を聞いたアーカーシュは泣き崩れる。
そのときチャーチゲート駅では、デーブーとシュルティー、ラーフルとネーハーが抱き合っていた。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
2007年のボリウッドの流行はオムニバス。「Life In A... Metro」もその例に漏れず、オムニバス形式の映画である。だが、今年公開され、僕が鑑賞したオムニバス形式の映画の中では最高の出来であった。登場人物とそれぞれのストーリーが関連性を持っており、影響を及ぼし合っている。セリフも非常に良かった。きっと都市部を中心にヒットするだろう。
アヌラーグ・バス監督は、「Murder」(2004年)や「Gangster」(2006年)の監督であり、都会を舞台にした狂おしい大人の恋愛を描くのが得意である。「Life
In A... Metro」も、ムンバイーを舞台にした大人向けの恋愛映画に仕上がっていた。
あらすじは上の通りである。多少時間軸に前後はあるが、読めば大体の流れは掴めるだろう。登場人物の人間関係は複雑に絡み合っているが、核となっているのはランジートとシカーの家庭であり、この映画の最も優れた小話もこの2人の間の話だった。言わばW不倫の話であるが、一方でランジートは愛人ネーハーを部下のラーフルに取られて失望のまま家族のもとに戻り、他方でシカーは恋し始めていたアーカーシュを勇気を持ってドバイに送り出してやはり家族を優先することを決意した。「結婚後の恋愛は結婚が勝つ」というインド映画の大原則を守るストーリーであった。特にシカーとアーカーシュの仲はインド人の価値観を傷付けないように繊細に描かれており、その点で不倫を美しくまとめすぎてしまってインド人観客からそっぽを向かれた「Kabhi
Alvida Naa Kehna」(2006年)よりも優れていた。
傑作恋愛映画に優れた名台詞は付き物であるが、「Life In A... Metro」のセリフも心に残るものが多かった。その内のいくつかはあらすじの中で取り上げたが、他にもいくつか印象に残ったものを挙げておく。ラーフルの言葉「都会は僕たちに多くのものを与えてくれるが、僕たちから多くのものを奪って行きもする。」ヴァイジャンティーがシカーに言ったセリフ「恋愛は香り。いつでも心を開いておくべきよ。」医者がラーフルに言ったセリフ「若さと石油はいつまでもあるわけじゃない。無駄にするんじゃない。」特にムンバイーの海岸でのデーブーとシュルティーの会話が良かった。シュルティーはデーブーに、理想の男性の条件についてあれこれ語る。「ハンサムで、頭が良くて、旅行好きで、ユーモアがあって・・・」それを聞いたデーブーは彼女に言う。「オレの友達に、高級スポーツカーを買っておきながら、5年間ずっと車庫に入れたままの奴がいるんだ。どうしてそんなことしてるか知りたいだろ?そいつは、街中の信号が青になったときに車庫から出して運転するって言うんだ。どう思う?」シュルティーは答える「そんなの馬鹿げてるわ。外に出なければ信号が青かどうか分からないじゃない。」デーブーは我が意を得たりの表情で言う。「その通り!結婚もそんなもんさ!」
「Life In A... Metro」には新世代の演技派俳優が多数出演している。シャイニー・アーフージャー、ケー・ケー・メーナン、イルファーン・カーン、コーンコナー・セーンシャルマーなどである。この4人の演技は文句なく素晴らしかった。特にイルファーン・カーンのとぼけた演技が最高。英国でリアリティーショーに出演したり、リチャード・ギアにキスをされたりと、最近何かとお騒がせのシルパー・シェッティーも、本業の方できちんとした仕事を見せていた。ヒロイン女優から演技派女優へ脱皮しようという努力が伺われた。「Rang De Basanti」(2006年)でブレイクしたシャルマン・ジョーシーや、「Gangster」のヒロイン、カンガナー・ラーナウトも若手ながら素晴らしい演技をしていた。特にカンガナーは、「Shakalaka Boom Boom」(2007年)からまたガラリとイメージが変わっていた。これらの俳優に加え、ダルメーンドラとナフィーサー・アリーという往年の名優が出演して渋い演技を見せており、映画を引き締めていた。ダルメーンドラとナフィーサーがキスをするシーンがあるが、これはインド映画史上最高齢のキスなのではなかろうか?
「Life In A... Metro」の音楽はユニークである。まず、この映画のために音楽監督プリータム・チャクラボルティーを中心とした男性シンガーロックバンド「バンド・メトロ」が結成された。メンバーは、バングラデシュ人のジェームス、ソーハム・チャクラボルティー、スハイル・カウルである。おかげでインド映画には珍しくロック色の強い曲が多い。それに加え、KKやアドナーン・サーミーも歌を歌っている。そしてさらに特徴的なのが、音楽が挿入されるシーンでこのバンド・メトロが登場してギターを演奏しながら歌を歌うことである。この手法は「メリーに首ったけ」(1998年)というハリウッド映画で見たことがある。だが、「Life
In A... Metro」では、狙ってやっているのか知らないが、むさ苦しい男どもがむさ苦しく歌うので笑いが堪え切れず、何度見ても飽きなかった。面白い試みである。ちなみにジェームスは「Gangster」で「Bheegi
Bheegi」を歌っていたバングラデシュ人ロックシンガーである。
それにしても、インド映画ではゲイの描かれ方が偏見に満ちていることが多い。この作品でも、シュルティーは恋人のDJと上司のゲイ現場を目撃し、DJとの結婚をキャンセルすると同時にラジオ局も辞めてしまう。
「Life In A... Metro」は最近ボリウッドで流行かつ失敗続きのオムニバス形式映画ながら、非常によく出来た作品である。俳優たちの演技の質も高い。サントラも大ヒット中。見て損はない。
| ◆ |
5月13日(日) アーリヤサマージの集会に潜入 |
◆ |
アーリヤサマージという宗教団体がある。1875年にダヤーナンド・サラスワティーによって設立されたアーリヤサマージは、「ヴェーダに帰れ」をスローガンに掲げ、ヒンドゥー教の宗教改革や社会改革を推進した。現在でもアーリヤサマージは存続しており、インドはもとより世界各地に寺院が散在している。今日は、ITO近くにあるヒンディー・バヴァンで行われたアーリヤサマージ関連の集会に潜り込むことになった。と言うより、主催者のダルシャン・アグニホートリー氏になぜか招待されたのである。
本日の集会は、スワーミー・ディークシャーナンド・サラスワティーという人物の4周忌記念式典のようだった。式典には学者、文学者、教育者、政治家、実業家などの知識人が多数参加していた。ヒンディー・バヴァンのセミナーホールが満席になるくらい多くの人々が来ていた。僕はなぜか「日本の文学者」として招待されていた。どこかで大きな誤解があったようだ。観客席で見物する積もりだったが、僕も壇上の席に座らされた。
出席していた政治家は、デリー市長のアールティー・メヘラー(主賓)や、スバーシュ・アーリヤ(賓客)、ヴィジェーンドラ・グプター(賓客)などであった。皆、インド人民党(BJP)の政治家である。3人とも、選挙のときなどに張り出される看板によく出て来る顔で、見覚えがあった。議長はヒーロー・ホンダのブリジモーハン・ムンジャール会長が務めていた。
主要演説者として出席していたのが、シャームスィン・シャシ氏であった。その長身の姿を見た瞬間に思い出した。この人には以前会ったことがある!デリーでは毎年、外国人留学生を対象としたヒンドゥー・ヘリテージ・セミナーが行われている。これは、デリー大学、ジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)、ケーンドリーヤ・ヒンディー・サンスターンなどに留学している外国人学生をリシケーシュやハリドワールへ呼んで行うセミナーである。主催はヒンドゥー・ヘリテージ・プラティシュタンという組織だが、世界ヒンドゥー協会(VHP)が後援をしており、右翼色の強い行事である。だが、外国人にはそんなことはあまり関係ない。その雰囲気は簡単に言ってしまえば修学旅行のようなもので、非常に楽しいイベントだ。僕も2002年に参加した。そのときに講師として出席していたのがシャームスィン・シャシ氏であった。実は僕はあのとき、バスでリシケーシュまで移動した他の学生たちと違い、講師たちが乗る自動車でリシケーシュまで行った。だから、シャシ氏とも話す機会がたくさんあった。
シャシ氏との思い出で忘れられないのは、デリーからリシケーシュへ向かう途中での出来事である。その日、不幸にも、デリー~リシケーシュ間の幹線が、マーヤーワティー政権(当時)に抗議する農民たちによって遮断されてしまっており、一時はリシケーシュに辿り着けないのではないかという状態になっていた。もう真夜中になっていた。とりあえず僕たちの乗った自動車は道中のダーバー(安食堂)に駐車し、状況を見守ることにした。そのとき一人の男が僕たちに近付いて来た。農民によって遮断された道を通らずに向こうまで行くことができる抜け道を知っていると言う。その男の風貌はいかにも怪しかった。こうやって土地に不慣れな旅行者を人のいない場所に連れ込んで身包みを剥ぐ強盗は少なくない。僕たちは用心した。だが、このまま待っていても埒が明かないので、最終的にはその男を信じることにした。自動車にその男を乗せ、道案内をさせた。自動車は幹線を外れ、サトウキビ畑の中を突っ切る田舎道を進み出した。外からは甘い匂いが漂って来た。遠くに見える製糖工場から匂って来るようだった。その匂いは頭に絡みつく眠気と融合し、不思議な陶酔感となって僕の体内を駆け巡っていた。その男は自分のことをミュージシャンだと紹介し、道中あれこれどうでもいいような話をしていた。そして案の定、お金の話をし出した。確か200ルピーとか300ルピーとか、そのぐらいの道案内代を要求し始めた。結局いくらか支払ったと思う。自動車は無事に遮断地帯の向こう側まで辿り着いた。その中で今でもよく覚えているのは、終始冷静であったシャシ氏の言動である。口癖は「チャロー・コーイー・バート・ナヒーン(まあどうってことない)」であった。リシケーシュに到着できない可能性があっても、「チャロー・コーイー・バート・ナヒーン、朝までには道が開くだろう」と呑気だったし、怪しげな男が高額なガイド料を求めて来ても、「チャロー・コーイー・バート・ナヒーン、まあ50ルピーで満足しておきなさい」と動じなかったり、その飄々とした振る舞いはとても面白く、頼もしく、そして尊敬できた。以後、僕もいろいろな場面で「チャロー・コーイー・バート・ナヒーン」を多用するようになった。しかも、微笑ましいことに、シャシ氏は自分の業績をまとめた小さなパンフレットを常に持ち歩いており、会う人会う人に配っているのである。今回の集会でも彼はせっせとパンフレットを配っていた。それを見て心の中で笑ってしまった。ああ、変わってないんだな、と。リシケーシュ以来、シャシ氏とは会っていなかった。だから、シャシ氏との突然の再会はとても嬉しかった。シャシ氏も僕のことを何となく覚えていてくれた。
もうひとつ嬉しいことがあった。この集会の冒頭では、ガウタム・ナガルにあるグルクル(ヒンドゥー教の伝統的教育を行う機関)の学生たちがヴェーダの詠唱を行っていた。知る人ぞ知る、ガウタム・ナガルは僕がインド留学生活を始めた当初に住んでいた思い出深い場所である。ガウタム・ナガルにグルクルがあることも知っていた。何を隠そう、家を探していたとき、このグルクルのすぐ近くの物件も見ていたのである。もしそこに住むことにしていたら、グルクルを見下ろす場所に住むことになっていた。わざわざアーリヤサマージの集会に呼ばれるくらいなので、どうもガウタム・ナガルのグルクルはけっこう名を知られているらしい。いかなる場所でも、ガウタム・ナガルの名前を聞くのは嬉しいことである。あそこから僕の真のインド体験が始まったし、ガウタム・ナガルに住んだ最初の2年半で僕はインドを理解する上で最も大切なものの大半を吸収したと感じている。学生寮に住むのもいいし、高級住宅地に住むのもまたひとつのインド体験ではあるが、やはり庶民の真っ只中に住むことほどインドの理解に役立つことはない。
僕も演説を余儀なくされた。まず、僕は文学者ではなく、ただの学生であることをはっきりさせ、その後、アーリヤサマージについて知っていることや体験したことを簡単に話した。そしてお世辞ながら「ヒンディー語はマスターしたので、これからはヴェーダを学びたいと思います」と言っておいた。今までヒンディー語の演説はいろいろ聞いて来たので、僕もけっこうヒンディー語で演説できるようになっていた。後は拳を振り上げながらヒトラーのように力強い演説ができるようになれば完璧であろう。「ヴァイディク・ダルム・キ・ジャイ(ヴェーダ教万歳!)」
訳の分からないまま招待され、訳の分からないまま壇上に座らされ、訳の分からないまま演説させられたが、この集会で最も興味を引かれたのは彼らの使うヒンディー語であった。やはり多くの演説者は、シュッド・ヒンディーと呼ばれるサンスクリット語の借用語を重度に利用したヒンディー語を使っていた。ジャイデーヴ・アーリヤという人物からは、ラージバーシャー・サンガルシュ・サミティ(公用語闘争委員会)が発行する小冊子をもらった。彼らはヒンディー語を真の意味での公用語とするために活動しているようであった。つまりそれは英語への反対運動でもある。マハートマー・ガーンディーの発言を引用したりしていたが、ガーンディーは彼らの使っているような難解な言語に反対していたのであり、お門違いのように感じた。ヒンディー語が公用語とされながらも実質的に公用語になり切れていない理由が未だに理解されていないのではないかと不安になったと同時に、彼らの活動に非常に興味が沸いた。
とは言え、インド人からヒンディー語に対する愛情を感じたのは久し振りのことであった。集会の後はビュッフェ形式の夕食となったが、その際にいろいろな人が僕に話し掛けて来た。中には、僕がヒンディー語で演説したのを見ていながら、わざわざ英語で話してくるインド人もいた。そういう人に対し、周りの人が、「この人はヒンディー語が話せるのにどうして英語で話すんだ。恥ずかしい!」と反対の声を上げていた。それは日頃から僕が思っていたことでもあり、そういうことを考えるインド人がいてくれてとても嬉しかった。英語はインド人の母語でもないし、僕の母語でもない。できることならヒンディー語で話しかけてもらいたいものである。
最近どうもボリウッドに元気がない。期待作が期待ほどの興行成績を上げず、駄作の洪水となっている。今日もひとつ、駄作を見てしまった。
題名:Raqeeb
読み:ラキーブ
意味:ライバル
邦題:ラキーブ
監督:アヌラーグ・スィン(新人)
制作:ラージ・カンワル
音楽:プリータム
作詞:サミール
出演:ラーフル・カンナー、ジミー・シェールギル、シャルマン・ジョーシー、タヌシュリー・ダッターなど
備考:PVRベンガルール・ヨーロッパで鑑賞。
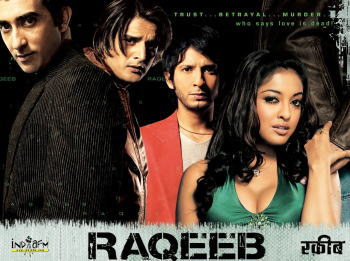
左から、ラーフル・カンナー、ジミー・シェールギル、
シャルマン・ジョーシー、タヌシュリー・ダッター
| あらすじ |
IT企業を経営するレモ(ラーフル・カンナー)は、14年前のトラウマからうまく対人関係を築けないでいた。14年前、彼は両親を事故で失ってしまっていた。レモの会社で働くスィッダールト(シャルマン・ジョーシー)だけが彼の友人であった。スィッダールトはある日、悪戯心からレモをチャット相手の女性と引き合わせる。それがソフィー(タヌシュリー・ダッター)であった。レモはソフィーに惹かれ、やがて2人は結婚する。
だが、ソフィーにはサニー(ジミー・シェールギル)という恋人がいた。サニーは売れない舞台俳優であった。ソフィーはサニーに、レモと結婚したのはただの財産目当てであり、レモを殺すようにけしかける。躊躇するサニーに、ソフィーは完璧な殺人計画を吹き込む。レモは喘息に悩まされており、薬を摂取しなければならない身体であった。それを利用し、空の銃でレモを威嚇してショック死させることを提案する。その通りにしたサニーであったが、銃にはなぜか実弾が込められていた。撃たれたレモは死んでしまう。しかも、サニーは殺人犯として逮捕されてしまう。
レモの死後、ソフィーは気分転換のためにバカンスへ出掛ける。そこで待っていたのはスィッダールトであった。実は全てスィッダールトとソフィーが仕組んだことであった。スィッダールトは、レモの会社を売り払って巨額の金を手に入れようとしていた。だが、彼は金のために全てを計画したわけではなかった。実は、スィッダールトは、レモの異父兄弟であった。スィッダールトの父親は、別の金持ちの女性と結婚し、家庭を持っていた。その子供がレモであった。ある日それを知ったスィッダールトの母親は夫を銃で撃つと同時に、ショックから植物人間となってしまう。しかも病院へ搬送される途中に事故に遭い、スィッダールトとレモの父とレモの母親は死んでしまう。スィッダールトはレモに復讐するために全てを仕組んだのであった。
全ての計画は完璧に進んだかのように見えた。ところが、スィッダールトとソフィーは、死んだはずのレモを見たり、牢屋にいるはずのサニーを見たりして、恐怖に怯えるようになる。レモの墓を掘り起こしてみると、棺桶にレモはいなかった。教会の中ではレモが待っていた。レモは事前に2人の計画を察知し、サニーと協力してスィッダールトとソフィーをはめたのであった。乱闘の末にスィッダールトとソフィーは死んでしまう。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
スリルとサスペンスが主題の映画ではあるが、同じような展開のサスペンス映画はハリウッドでもボリウッドでも腐るほど作られて来た。どんでん返しとそのまたどんでん返しも、どこかで見たな、ぐらいの感想でしかない。しかも、細かいところを見ていくと不整合な点が多い。後はタヌシュリー・ダッターの色気頼みであるが、彼女も醜く太ってしまっており、下層の庶民に人気の出そうな女優になってしまっていた。
大きな見所だったのは、「ボディー・ダブルか本物か」であった。タヌシュリー・ダッターは公開直前になって、「私の了解なしに監督が濡れ場シーンを『ボディー・ダブル(代役)』を使って撮影し、映画のプロモーションに利用している」と主張し、制作サイドを糾弾し始めた。一方、プロデューサーのラージ・カンワルは、「最初タヌシュリーがためらっていたのは事実だが、最終的に彼女自身が濡れ場を演じた」と彼女の主張を全面否定した。本当にそんな問題の濡れ場シーンがあるのかどうか、興味津々だったのだが、ほとんどそのようなシーンはなかった。シャルマン・ジョーシーとタヌシュリー・ダッターが一緒にバスタブに浸かっているシーンが最もエロチックだったが、ちゃんとタヌシュリーの顔も映っており、ボディー・ダブルとは思えなかった。結局、一連の騒動は客寄せのために行われているのではないかと思われた。
ラーフル・カンナー、ジミー・シェールギル、シャルマン・ジョーシーという、全くキャリアの異なる男優3人の異色の取り合わせは新鮮であった。ラーフル・カンナーは、往年の名優ヴィノード・カンナーの息子で、アクシャイ・カンナーの兄である。ただし、アクシャイよりも映画デビューは遅く、出演作も多くない。顔がお坊ちゃま過ぎるためか、使いにくい俳優となっているように思える。弟が演技派としての基盤を築き出しているのに比べ、低迷していると言わざるをえない。ジミー・シェールギルは「Mohabbatein」(2000年)に登場した3羽ガラスの一人で、「Munnabhai」シリーズのおかげか病的なイメージがつきまとう俳優になってしまった。「Raqeeb」でも精神的に異常がありそうな演技をしていたが、俳優としては徐々に成功の階段を登っていると言っていい。ただ、まだ1人立ちできるだけの力量はない。シャルマン・ジョーシーは「Style」(2001年)できっかけを掴み、「Rang
De Basanti」(2006年)でブレイクした男優だ。この3人の中では最も将来性がある。「Life In A... Metro」(2007年)でも好演していた。「Raqeeb」では、あんな純朴そうな顔をしておいて実は悪役という、なかなか憎い役をもらっていた。
ジャールカンド州ジャムシェードプル生まれのベンガル人で、2004年のミス・インディアとなったタヌシュリー・ダッターは、「Aashiq Banaya
Aapne」(2005年)で「シリアル・キサー(連続キス魔)」の異名を持つイムラーン・ハーシュミーの相手役を務め、ホットなデビューを果たした。「Bhagam
Bhag」(2006年)でゲスト出演した際には自慢のムチムチボディーを活かしたダンスを踊っていたのだが、ここに来てムチムチが度を越えて来たように思える。踊りも全然踊れていなかった。ボージプリー映画界ではまだ需要があるかもしれないが、モデル体型の女優が幅を利かせている最近のボリウッドでタヌシュリーがヒロイン女優として活躍するのはかなり難しい。グラマー女優として覚醒するか、それとも必死にダイエットすべきであろう。
舞台は無国籍であったが、一応インドなのだろう。だが、ロケの大部分はタイで行われたと思われる。プーケット島周辺の美しい島々やビーチが頻繁に背景に登場した。
音楽はプリータムだが、取り上げる価値のある曲はなかった。ミュージカルシーンへの移行の仕方も不自然な部分が多く、一昔前の映画のようであった。
「Raqeeb」は、よくある筋のサスペンス映画である。俳優や音楽も魅力に欠けるため、結果的にほとんど取り得のない駄作となってしまっている。わざわざ見る必要はない。
| ◆ |
5月22日(火) Ek Chalis Ki Last Local |
◆ |
現在ボリウッドには、「デーオール」姓を持つ俳優が4人活躍している。サニー、ボビー、イーシャー、そしてアバイである。彼らは、往年の名優ダルメーンドラ(本名ダルメーンドラ・スィン・デーオール)の血を引いている。サニーとボビーは前妻プラカーシュ・カウルとの間に出来た息子で、イーシャーは現在の妻ヘーマー・マーリニーとの間に出来た娘である。そして2005年に「Socha
Na Tha」でデビューしたアバイは甥に当たる。サニーはボリウッド男優の人気ランキングを付けたら必ず上位に来るほどの人気を誇る筋肉派男優であり、ボビーも、長年何のためにいるかよく分からなかったが、最近になってやっと演技力を伸ばして来ている。イーシャーも一応人気女優の一人と言っていい。だが、アバイだけはどうもパッとしない。サニーやボビーのようなマッチョタイプの男優になれそうでもないし、演技力も冴えないし、ヒーロー男優としてのカリスマ性にも欠けるし、どちらかというとトゥシャール・カプールのような内気そうなキャラが似合う押しの弱い男優である。とは言え、ダルメーンドラの七光りのおかげか、彼の主演作はコンスタントに作られている。先週の金曜日から公開の新作ヒンディー語映画「Ek
Chalis Ki Last Local」もアバイ・デーオール主演の映画である。それだけだったら見に行かなかったのだが、「2時間半で2500万ルピー」というキャッチコピーに何か惹かれるものを感じ、映画館に足を運んだ。人気TVドラマ「24」みたいな、リアルタイムの映画かと思ったのである。
題名:Ek Chalis Ki Last Local
読み:エーク・チャーリース・キ・ラスト・ローカル
意味:1時40分発の最終電車
邦題:ラストトレイン
監督:サンジャイ・カンドゥーリー(新人)
制作:カルテット・フィルムス
音楽:サンデーシュ・シャンドリヤー、アンクル、テクノ・フランコルシ、ズルフィー、アキール、サンジーヴ、アマル・モーヒレー(BGM)
作詞:メヘブーブ、アンクル・ティワーリー、ズルフィー
振付:ガネーシュ・アーチャーリヤ、サンジャイ・カンドゥーリー
出演:アバイ・デーオール、ネーハー・ドゥーピヤー、スネーハル・ダービー、ディーパク・シルケー、アショーク・サマルト、ヴィナイ・アプテーなど
備考:PVRベンガルール・クラシックで鑑賞。
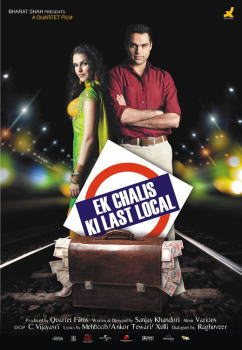
ネーハー・ドゥーピヤー(左)とアバイ・デーオール(右)
| あらすじ |
ムンバイーのコールセンターで働くニーレーシュ(アバイ・デーオール)は、友人たちと夜遅くまで飲んでいたため、午前1時40分カルラー駅発の最終電車に乗り遅れてしまった。始発までは2時間半あった。プラットフォームで待つこともできなかった。財布にはたったの70ルピー。駅の外に出てみたが、オートリクシャーやタクシーはストライキのため全く動いていなかった。途方に暮れていると、同じヴィクローリー方面へ向かう女性と出会った。名前はマドゥ(ネーハー・ドゥーピヤー)。ニーレーシュはマドゥと共に歩き出した。
しかし、深夜のムンバイーの町は危険で一杯だった。雨も散発的に降っていた。2人はバーに入って一夜を明かすことにする。だが、バーには途中で目を付けられたチンピラたちも入って来た。ニーレーシュは警戒しながらも席に着く。そのバーでニーレーシュはかつてのルームメイト、パトリックと偶然再会する。パトリックは裏の世界で大金を稼いでおり、バーの奥にある賭博場で賭博をしようとしていた。トランプのプロであったニーレーシュは、マドゥに断って賭博場へ行く。そこでは、マフィアのボス、ポーナッパ(ヴィナイ・アプテー)など、ムンバイーの大物たちが賭博をしていた。ニーレーシュはトランプの才能を活かして大金を稼ぐ。だが、熱中する余り、マドゥのことを忘れてしまっていた。途中で席を立ってバーへ行くと、マドゥがいなくなっていた。焦って探し回るニーレーシュ。女性用トイレの中から悲鳴が聞こえたので踏み込むと、マドゥがチンピラにレイプされそうになっていた。チンピラはナイフを取り出してニーレーシュに向かって来るが、足を滑らせて頭を打ち、死んでしまう。ニーレーシュは殺人犯と思われ、従業員に取り押さえられる。
実はそのチンピラはポーナッパの弟だった。また、マドゥは普通の女の子ではなく、最終電車に乗り遅れた男を狙う売春婦で、ポーナッパの弟とグルであった。怒ったポーナッパはニーレーシュを殺そうとするが、そのときマルヴァンカル(アショーク・サマルト)ら警察官が踏み込んで来る。だが、マルヴァンカルは金のみで動く汚職警官であった。ポーナッパから50万ルピーの賄賂を受け取ったマルヴァンカルは、パトリック、ニーレーシュ、マドゥの3人を連行する。
マドゥは途中、トイレに行きたいと言い訳をして隙を見て逃げ出す。マルヴァンカルの部下2人がそれを追う。その失態をからかったパトリックは、マルヴァンカルに殺されてしまう。恐れをなしたニーレーシュも隙を見て逃げ出し、マドゥと合流して身を潜めるが、マルヴァンカルに見つかってしまう。だが、このときニーレーシュとマドゥの間には信頼感が生まれる。
マドゥはマルヴァンカルに賄賂を払うため、親代わりのヒジュラー、ハビーバー(スネーハル・ダービー)の家に警官たちを連れて行く。だが、ハビーバーの手元には持ち合わせがなかった。そこで、ハビーバーも一緒に、愛人で、ポーナッパのライバルのマフィア、マンゲーシュ・チルケー(ディーパク・シルケー)のアジトへ行く。男色のマンゲーシュは、ニーレーシュとマドゥを解放するための賄賂8万ルピーを肩代わりすることに同意する。だが、その代わり、ニーレーシュが体を捧げなくてはならなくなった。ニーレーシュは縄で縛られる。
そこへ、マンゲーシュの手下の女がやって来る。その女は、ポーナッパの手下が実行した誘拐の身代金2500万ルピーを横取りして持って来た。マンゲーシュは嬉々としてその金を受け取り、ニーレーシュに襲い掛かろうとする。ところがそこへ、今度はポーナッパがやって来る。解放されたマドゥが、ポーナッパにマンゲーシュの居所を教えたのだった。ポーナッパはマンゲーシュの手下やマルヴァンカルを殺害し、マンゲーシュの部屋までやって来た。マンゲーシュは手足を打ち抜かれ、瀕死の状態となる。また、ニーレーシュも殺されそうになるが、寸前にマンゲーシュが最後の力を振り絞ってポーナッパを射殺する。
こうしてニーレーシュはたった1人の生存者となった。彼の手元には2500万ルピーが入った鞄が残った。最終電車に乗り遅れたために一夜にして大金持ちになったニーレーシュであったが、マドゥのことが忘れられなかった。3週間後、彼は午前1時40分の最終電車が出た後のカルラー駅で、マドゥと再会する。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
インターバルを含め2時間半ほどの映画で、映画の主要部分もキャッチコピー通り2時間半の時間が過ぎ去ったが、かと言ってそのリアルタイム性が映画の重要な要素になっている訳でもなかった。ネーハー・ドゥーピヤーはまだしも、アバイ・デーオールがあまりに大根役者で、ただでさえ冗漫な展開に全く緊迫感が張り詰めなかった。それでも脇役陣は個性的な俳優が多く、所々で光るものもあった。サンジャイ・カンドゥーリー監督は新人のようだが、実験的で斬新な作品を作ろうとする意気込みは十分に感じられた。
インドには先進諸国の大都市並みに電車網・鉄道網の発達した都市はまだ存在しないが、それでもムンバイーはインドで最も鉄道が通勤客の足になっている都市である。よって、日本のように「終電を逃してしまった、どうしよう」みたいなこともありうる訳だ。幸い、インドにはオートリクシャーのような比較的安い交通手段もあるため、終電を逃したとしても日本ほどダメージは大きくない。しかし、深夜、駅に取り残されてしまう恐怖は日本の比ではない。この「Ek
Chalis Ki Last Local」は、終電を逃したある中産階級の男が、始発の時間までに直面する様々なトラブルを題材にした映画である。このミクロな着眼点はインド映画では珍しい。タクシーを使って帰ればいいじゃないか、という突っ込みに対しては、所持金が70ルピーしかなかったことと、タクシーがストライキをしていたことの二つの言い訳が用意されていた。
様々なトラブル、と言っても、主人公ニーレーシュにとって終電を乗り逃したことは、まるで吉と凶の両面を持った1枚のコインがクルクル回るように、不運であったり幸運であったり、目まぐるしく変化する。終電を逃し、警察から駅を追い出され、自らの不運を呪っていたニーレーシュは、駅前で美しい女性マドゥと出会うことになり、一転して自分の幸運にほくそ笑む。だが、それがとんでもない展開へとつながっていく。賭博場で大金を儲けたまではよかったが、殺人犯と間違われて逮捕されたり、友人を目の前で殺されたり、カマを掘られそうになったり、挙句の果てに殺される寸前まで行くが、最終的には漁夫の利で2500万ルピーを手に入れる。
前半は非常に冗漫で退屈だが、後半になると物語は大きく揺さぶられ、なかなかスリリングな展開になる。ニーレーシュが2500万ルピーを手に入れるまでの経緯もよく筋が通されていた。だが、もう少しいいエンディングにもできたのではないかと思う。ニーレーシュは2500万ルピーの入った鞄を持って始発列車に乗るが、そこへ運悪く乗客の荷物検査をする警官がやって来る。怖気づいたニーレーシュは鞄を座席に置いたまま走っている列車から駅のプラットフォームに飛び降りる。せっかく手にした大金も水の泡かと思われたが、爆弾が入っていると勘違いした警官はその鞄を外に放り出しており、駅の線路の上に転がっていた。こうして再びニーレーシュはその金を手にする。だが、これは最上のエンディングではなかった。ニーレーシュは最後に2500万ルピーを手にしてはならなかったと思う。お金は手に入らなかったがマドゥとは再会できた、というエンディングが最も妥当だったと思う。また、最後、ニーレーシュは列車に引かれそうになるのだが、なぜか助かる。どうやって助かったのかは全く説明されていなかったのも不満だった。
アバイ・デーオールは全く駄目だ。きっと根がいい奴なのだろうが、素朴で馬鹿正直な男以外、彼に似合う役は今のところない。この映画のニーレーシュは、コールセンターに務めるごく普通の中産階級の男だったが、中産階級らしいガツガツしたトゲトゲしさが感じられず、お坊ちゃまそのままであった。このまま彼の主演作が続くと、いい作品も駄作になってしまう。もし俳優として続けていくつもりがあるなら、かつてのアビシェーク・バッチャン並みの大改造が必要であろう。
ネーハー・ドゥーピヤー・・・ああ、かわいそうなネーハー・ドゥーピヤー・・・。2002年のミス・インディアの彼女は、知的な女性の役が似合うと思うのだが、「Julie」(2004年)や「Sheesha」(2005年)で際どい役を演じてしまったばかりに、そういうイメージがしつこく付きまとうことになってしまった。「Ek
Chalis Ki Last Local」ではやっと普通のヒロインの役がもらえたかと思って個人的に密かに祝福ムードだったが、蓋を開けてみてビックリ、実は終電を逃した男を狙う売春婦の役であった・・・。やはりボリウッドはイメージ先行の業界のようだ。女優が一度堕ちた役を演じると、清純派には二度と戻れない世界のようだ。だが、彼女の演技に汚点はなかった。
脇役陣は普段あまり見ない顔ぶれが多かったが、非常に力強い演技をする俳優が多かった。汚職警官マルヴァンカルを演じたアショーク・サマルト、男色マフィアを演じたディーパク・シルケー、南インド丸出しマフィアのポーナッパを演じたヴィナイ・アプテー、迫力あるヒジュラー、ハビーバーを演じたスネーハル・ダービーなどなど、アバイ・デーオールの欠点を補っていた。
詳しい背景は不明だが、このボリウッド映画、なぜか南インドのエッセンスが込められていた。賭博場にはアイヤッパンやミーナークシーなど、南インドの神様のポスターが飾られていたし、マルヴァンカルの部下の一人はタミル映画のスーパースター、ラジニーカーントの物真似に凝っていて、途中、ラジニーカーント映画のパロディーシーンもあった。
「Ek Chalis Ki Last Local」は、実験的な試みが感じられる意欲的な作品だが、娯楽作品としての質は高くない。アバイ・デーオールの大根役者振りもマイナス要因である。同日に公開された「Raqeeb」よりは面白いが、見ても見なくてもどちらでもいい映画だと言える。
| ◆ |
5月24日(木) Good Boy Bad Boy |
◆ |
最近、デリーの酷暑から一時的に逃れ、バンガロールに滞在している。僕の映画ライフは、デリーではPVR系列の映画館に多大に依存しているが、ここバンガロールでも同じくPVR系列のPVRベンガルールが行きつけの映画館だ。PVRベンガルールは、バンガロールで最も流行っているモール、フォーラムに併設されている。フォーラムの土日の混雑振りは半端ではない。グルガーオンのモールでもこれほど混雑していないのではないかというくらいだ。また、今回久し振りにバンガロールに来たところ、カンナダ映画が無理に振興されているのが気になった。映画の料金はヒンディー語映画、英語映画、カンナダ語映画で異なり、カンナダ語映画が最も安く、英語映画が最も高くなっている。チケットの値段の差は税金の差から来ている。このバイアスは元からだったのだが、最近カンナダ語映画以外への税金がますます値上げされたようだ。また、カーヴェーリー河問題のせいでカルナータカ州内では反タミルの動きが強まっており、それは映画界にも影響を与えている。バンガロールではタミル語映画の上映機会がめっきり減ってしまったと言う。
しかし、PVRベンガルールで驚くのは、どんなにつまらない映画でも大体満席になることである。平日なのにも関わらず。もちろん、今インドは夏休みに当たる期間にあり、特別なのだろうが、それでもデリーの映画館の状況を見慣れていると異常に思える。デリーでは、つまらない映画は、まだそのつまらなさが知れ渡っていないはずの初日でも閑古鳥が鳴くことがほとんどである。その点でデリーの観客の方がシビアだ。だが、どうもバンガロールは爆発的に増加する人口に対して映画館の数が足りていないようだ。駄作でも満員御礼の秘密は、映画館の数の少なさにあると考えて良さそうである。
今日は、2週間前に公開された「Good Boy Bad Boy」を見た。僕は見る前から駄作と判断してスキップしようと思っていたのだが、時間があったことと、タイミングが合ったことから、この映画も見てみることにした。だが、この映画も満席。そして意外にも割と面白い映画だった。
題名:Good Boy Bad Boy
読み:グッド・ボーイ・バッド・ボーイ
意味:いい子悪い子
邦題:グッド・ボーイ・バッド・ボーイ
監督:アシュヴィニー・チャウドリー
制作:ラージュー・ファールーキー
音楽:ヒメーシュ・レーシャミヤー
作詞:サミール
振付:レモ、サロージ・カーン
出演:トゥシャール・カプール、イムラーン・ハーシュミー、イーシャー・シャルヴァーニー、タヌシュリー・ダッター、パレーシュ・ラーワル
備考:PVRベンガルール・ヨーロッパで鑑賞。

左から、トゥシャール・カプール、タヌシュリー・ダッター、パレーシュ・ラーワル、イーシャー・シャルヴァーニー、イムラーン・ハーシュミー
| あらすじ |
ラージュー・マロートラー(イムラーン・ハーシュミー)は既に3回も大学を退学になったバッド・ボーイであった。官僚の父親は息子の出来の悪さに頭を痛めていた。一方、ラージャン・マロートラー(トゥシャール・カプール)は典型的な優等生。しかし、酒場を経営する父親は息子の生真面目さを心配していた。2人は同じ大学に通っていた。ラージューは優等生の女の子ラシュミー(イーシャー・シャルヴァーニー)に惚れており、事あるごとにアタックしていたが、全く相手にされなかった。また、不良少女のディンキー(タヌシュリー・ダッター)は、真面目なラージャンに色目を使っていた。
ある日、大学に新しい学長アワスティー(パレーシュ・ラーワル)がやって来る。アワスティーは風紀の乱れた大学を立て直すため、新制度を導入する。それは、成績に従って生徒を3つのグループに分けるというものであった。成績70%以上の学生はAグループ、50~70%の学生はBグループ、50%以下の学生はCグループに振り分けられた。92%の成績のラージャンは当然Aグループに行くはずで、35%のラージューはCグループのはずだった。ところが2人の名前が紛らわしかったため、入れ替わってしまう。ラージューはラシュミーと同じクラスになれたことを喜び、ラージャンは、落第生のラージューが勉強する気になっているのを見て応援することに決めた。こうしてラージューとラージャンは秘密を共有する親友となった。
ラシュミーは次第にラージューに惹かれるようになり、ラージャンもディンキーの押しに押されるようになる。だが、アワスティー学長はラージューとラージャンの入れ替わりに気付いていた。しかもラシュミーはアワスティー学長の娘であった。しかしながら、彼はそのまま黙って様子を見守っていた。
ラージューとラージャンの大学は、大学対抗フェスティバルに参加することになった。アワスティー学長はラージャンをダンス部門の代表に、ラージューをクイズ部門の代表に選出する。勉強嫌いのラージューにクイズなど答えられるわけがなく、運動神経ゼロのラージャンにダンスができるはずがなかった。困り果てたラージューとラージャンは入れ替わりのことについて学長に謝りに行くが、学長は彼らを臆病者呼ばわりして追い返す。仕方なく、ラージューは必死に勉強し、ラージャンは必死にダンスを習う。
フェスティバル当日。ラージャンは練習の成果を披露し、見事ダンス部門で優勝する。また、ラージューも苦しみながらクイズを答え、優勝する。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
真面目な親に不良の息子が生まれ、その息子が優等生の女の子に恋をする。一方、不真面目な親に優等生の息子が生まれ、その息子が不良の女の子に恋をする。そしてグッド・ボーイとバッド・ボーイが入れ替わって今までとは違った人生を歩み始める。そんな「王子と乞食」の現代版のような作品であった。展開が分かりやすく、テンポも良かったので、単純な娯楽映画を求める人には打ってつけの映画となっていた。佳作と言っていいだろう。
ほとんど深く批評する必要のない娯楽映画ではあるが、学生を成績によって3つのグループに分けるという試みは、もしかしたら近年インド中で大きな問題になっている保留制度を暗に風刺しているのかもしれない。エンディングで、その試みを提案したアワスティー学長は、「どんな生徒も我が校の宝だ」みたいなまとめ方をしていた。だが、これはおそらく深読みし過ぎであろう。
イムラーン・ハーシュミーとトゥシャール・カプールの凸凹コンビは面白かった。最近のボリウッド映画をマメに見ている人なら、「Good Boy Bad
Boy」という題名と、この2人の男優の名前を聞いただけで、「グッド・ボーイ=トゥシャール・カプール、バッド・ボーイ=イムラーン・ハーシュミーだろう」と容易に想像が付くことだろう。それほど大衆の一般的なイメージをうまく活かした配役であった。やはりトゥシャール・カプールは生真面目な優男の役が似合う。と言うかそれしかできない。このまま変な欲を出さずにこの路線で行けば、少しは生き残って行くチャンスはあるだろう。イムラーン・ハーシュミーも相変わらずイムラーン・ハーシュミーであった。しかも音楽はヒメーシュ・レーシャミヤー。イムラーンとヒメーシュのコンビは最強であるが、この映画の音楽はそれほどヒットしていないようだ。
それにしても、この映画を見てひとつ「なるほど」と思ったことがあった。それは、先月公開された「Kya Love Story Hai」で主演したトゥシャール・カプールが、やたらとイムラーン・ハーシュミーの真似をしているように思えてならなかったのだが、それはおそらく「Good Boy Bad Boy」の撮影時に彼から直接「イムラーン道」を学んだのだろう、ということだ。
女優陣は添え物に過ぎなかったが、やはりグッド・ボーイとバッド・ボーイに合わせて、グッド・ガール、バッド・ガールのイメージが強い若手女優2人が登場。ただし、グッド・ボーイ×バッド・ガール、バッド・ボーイ×グッド・ガールという捻った組み合わせであった。元々プロのダンサーで、美貌や演技力は二の次のまま映画デビューしたイーシャー・シャルヴァーニーだが、今回は自慢のダンスはほとんど披露しておらず、グッド・ガールのヒロイン女優としての地盤固めに動き出しているように感じた。髪型も以前より魅力的になっており、ヒット作に恵まれれば有望な女優になれるだろう。一方、セクシーなイメージが先行するタヌシュリー・ダッターはバッド・ガールの役。先日公開された「Raqeeb」より存在感のない役ではあったが、美しさは「Good
Boy Bad Boy」の方が上だった。彼女は今のところ微妙な位置にいる女優だ。このままだと悪女役の女優になってしまうだろう。
脇役出演のコメディアン、パレーシュ・ラーワルは、今回はコメディー色をぐっと抑えた落ち着いた演技を見せていて、若手俳優4人を前面に押し出した学園物映画をグッと引き締めていた。
バッド・ボーイのラージュー・マロートラー(イムラーン・ハーシュミー)よりもさらにあくどいバッド・ボーイズが映画の真の悪役として暗躍するのはご愛嬌であろう。
「Good Boy Bad Boy」は見た目駄作ではあるが、普通に楽しめる娯楽映画であった。やはり無理に見る価値のある映画ではないが、暇つぶしには悪くないオプションである。
本日からアミターブ・バッチャン主演の映画が2本同時公開された。実話を元にしたアクション映画「Shootout At Lokhandwala」と、年齢差ロマンス映画「Cheeni
Kum」である。アミターブ・バッチャンが一時体調を崩して入院したとき、映画界の中では「アミターブ・バッチャンへの極度の依存をやめるべきだ」という議論が沸き起こったのだが、相変わらずボリウッドはアミターブ・バッチャンの起用を減らしていない。今日は「Cheeni
Kum」を鑑賞した。
題名:Cheeni Kum
読み:チーニー・カム
意味:砂糖控えめ
邦題:シュガーレス・ラブ
監督:Rバールキー(新人)
制作:スニール・マンチャンダー
音楽:イライヤラージャー
作詞:サミール、マノージ・タパーリヤー
出演:アミターブ・バッチャン、タッブー、パレーシュ・ラーワル、ゾーラー・セヘガル、スウィーニー・カーラー
備考:PVRベンガルール・クラシックで鑑賞。

左から、パレーシュ・ラーワル、アミターブ・バッチャン、タッブー
| あらすじ |
ブッダデーヴ・グプター(アミターブ・バッチャン)は、ロンドンで最高のインド料理レストラン「スパイス6」を経営する、頑固で傲慢なシェフ(64歳独身)だった。ブッダデーヴは母親(ゾーラー・セヘガル)と共に暮らしていたが、毎日口論が絶えなかった。唯一心を開いていたのは、隣に住む少女セクシー(スウィーニー・カーラー)であった。セクシーは血液ガンを患っており、余命はあとわずかであった。
ある日、ブッダデーヴのレストランに、デリーからやって来たインド人観光客ニーナー・ヴァルマー(タッブー)がやって来る。ニーナーは、ハイダラーバーディー・ザフラーニー・プラーオの味を「甘すぎる」と文句をつける。プライドを傷付けられたブッダデーヴは、これこそ最高のハイダラーバーディー・ザフラーニー・プラーオだと言い張る。ところが翌日、ニーナーは自分でハイダラーバーディー・ザフラーニー・プラーオを作って持って来る。その完璧な味に驚いたブッダデーヴは、自分の誤りを認める。実は、コックの1人が塩と砂糖を間違えて入れてしまったのだった。ブッダデーヴは一気にニーナーに惹かれるが、なかなか彼女に謝ることができなかった。ニーナーは、レストランの近くにある友人シャーリニーの家に泊まっており、その後も2人は出会いを繰り返す。ニーナーは34歳独身であった。
ロンドンの天気は変わりやすい。傘の貸し借りを繰り返す内に2人は惹かれ合い、結婚を考えるようになる。ブッダデーヴの母親は歓迎するが、ニーナーの父親オームプラカーシュ・ヴァルマー(パレーシュ・ラーワル)を説得するのは難しそうだった。そのとき突然、ニーナーの父親が入院してしまう。ニーナーはインドに帰ることになった。
ニーナーの後を追ってデリーに来たブッダデーヴは、無事に退院したオームプラカーシュと出会う。クリケットの大ファンで、ガーンディー主義に傾倒するオームプラカーシュは、ブッダデーヴを老人として扱う。彼はなかなか結婚のことを切り出せなかった。だが、いざその話をすると、オームプラカーシュは驚き呆れ、怒り、卒倒し、最後にはサティヤーグラハ(断食)を始めてしまう。彼は、娘がブッダデーヴとの結婚を諦めなければ何も食べないと言い張る。糖尿病を患っていたオームプラカーシュは、食事をしなければ命が危なかった。
ブッダデーヴは必死にオームプラカーシュを説得する。最後にはオームプラカーシュも諦め、娘の結婚を認める。こうして64歳のブッダデーヴと34歳のニーナーは結婚することになった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
「Nishabd」(2007年)で18歳の少女に恋する60歳既婚男性の役を演じたアミターブ・バッチャンは、今度は34歳の独身女性に恋する64歳独身男性の役を演じた。「Nishabd」はロリコンだけでなく不倫の要素も含まれており、法律的・社会的にタブー色が強かったが、「Cheeni
Kum」では、30歳の年齢差ながら、どちらも独身であるため、普通にロマンス・コメディーに仕上げることが出来ていた。
題名の「Cheeni Kum(砂糖控えめ)」は、いくつかの意味を含んでいる。まず、64歳のブッダデーヴと34歳のニーナーの出会いは、ハイダラーバーディー・ザフラーニー・プラーオの甘さを巡って起こる。ブッダデーヴは自分のレストランの料理の味に自信を持っており、最初はニーナーの「ハイダラーバーディー・ザフラーニー・プラーオはこんなに甘くない」という苦情を否定するが、実はコックの1人が塩と間違えて砂糖を入れてしまい、甘くなってしまっていたのだった。次に、ブッダデーヴとニーナーの会話の中で、コーヒーに砂糖を入れるか否かが話題に上る。ブッダデーヴは「砂糖はコーヒーの味を台無しにする」と言うが、ニーナーは「私は砂糖が好きなの」と言って砂糖を入れる。また、「Cheeni
Kum」は、ブッダデーヴの頑固一徹の性格も象徴している。そしておまけに、ニーナーの父親オームプラカーシュが患っている糖尿病も関連しており、砂糖という一般的な食材で見事に映画をひとつにまとめている。
だが、ブッダデーヴがシェフということもあり、砂糖以外にも料理が映画の隠し味になっていた。例えばニーナーはヴェジタリアンのブッダデーヴをからかって「ガースプース(雑草)」と呼び、ブッダデーヴはそれに対抗してニーナーを「タングリー・カバーブ(鶏もも肉のカバーブ)」と呼ぶ。ブッダデーヴはオームプラカーシュに好印象を与えるため、手料理をご馳走するが、そのとき彼はてっきりオームプラカーシュがガーンディー主義者なのを見て菜食主義者だと思い、ヴェジタリアン料理のみを作る。だが、実はオームプラカーシュは口先だけのガーンディー主義者で、火曜日以外は毎日欠かさずチキンを食べていたのであった。最後、仕方なくブッダデーヴとニーナーの結婚を認めたオームプラカーシュ。彼はロンドンに来てブッダデーヴのレストラン「スパイス6」で食事を食べる。まだ納得の行かない顔をしているオームプラカーシュに対し、ブッダデーヴの母親は、「最近では嫁の手料理が食べられるだけでも幸せ者なのに、娘婿の手料理が食べられるなんてね!」とからかう。
しかし、どちらかというと砂糖や料理よりも映画の展開の中で重要な小道具となっていたのは傘であった。ニーナーは傘を持っておらず、突然降り出すロンドンの雨に慣れていなかった。そこでブッダデーヴは彼女に何度も傘を貸す。もちろん、傘を返しに来る彼女にもう一度会えるのを期待して。だが、突然デリーに帰ってしまったニーナーは、ブッダデーヴの傘も持って行ってしまう。オームプラカーシュが結婚を認めたとき、ニーナーはブッダデーヴに電話をし、「傘を返しに行く」と伝える。このように、傘が2人の間で恋愛の成就の象徴となっていた。だが、傘は余りに映画やドラマで小道具として使われすぎており、傘を題名にしてもインパクトは薄かっただろう。よって、「Cheeni
Kum」という題名の方がベターであることは変わらない。ちなみに、ヒンディー語で傘のことを「チャトリー」と言うが、これはコンドームのことも意味する。ちゃんとこのことを踏まえたギャグも映画中に出て来ていた。
その他、映画の伏線となっていたのはジムと鉄柱とクリケット。ブッダデーヴの母親は彼に毎日毎日ジムへ行けジムへ行けとしつこく言う。ブッダデーヴはそれを無視するが、ニーナーと出会い、彼女にボーイフレンドがいないことが分かると、急にジムへ行き出す。ある日、ブッダデーヴはニーナーを母親に引き合わせる。母親は「ほれ見なさい、ジムへ行って2日で彼女が出来たよ」と喜ぶ。後半、デリーのシーンになると、クトゥブ・ミーナール・コンプレックスにある鉄柱が重要な役割を果たす。これは有名な話であるが、鉄柱に背を付けて後ろで両手を結ぶことができると願い事が叶うと言われている。ただし現在では鉄柱の周囲に柵が巡らされてしまっており、通常の観光客はそれを試すことができないようになっている。だが、撮影のためだろう、アミターブ・バッチャンは柵の中に入ることが出来ていた。最初試したとき、ブッダデーヴは後ろで両手を合わせることが出来なかった。だが、オームプラカーシュにニーナーとの結婚の話を切り出し、拒否された後、もう一度試してみる。そのとき、母親の手助けもあって、彼は手を合わせることに成功する。その途端、抗議の断食中だったオームプラカーシュも2人の結婚を認める。そのとき母親はまた、「ほれ見なさい、ジムへ行きなさいと言ったでしょ」とからかう。オームプラカーシュはクリケットの大ファンであった。2人の結婚を認めたものの、まだ煮え切らない思いのオームプラカーシュを見たブッダデーヴは、ロンドンへやって来た彼に対し、「インド対イングランドのクリケットのチケットが2枚ある」とつぶやく。それを聞いたオームプラカーシュはコロッと態度を変える。これが映画の最終的なオチになっていた。
セクシーの存在も重要であったが、僕は必ずしもこの映画に必要はなかったと思った。敢えて言うなら、砂糖控えめの恋愛映画に、苦味を加えていた。セクシーはまだ幼少ながらやたらとませた女の子で、要所要所でブッダデーヴに大人顔負けのアドバイスを与える。彼女は血液ガンという難病を患っていた。そして、ブッダデーヴがニーナーとの結婚を成就させた瞬間に、彼女は死んでしまう。ブッダデーヴは、クトゥブの鉄柱の力を、セクシーの回復ではなく、自分の結婚というセルフィッシュな目的のために使ってしまったことを悔いる。悲しみに沈むブッダデーヴを、ニーナーは「涙を流すのは悲しみを減らすということ。セクシーのことを大切に思っていたなら、涙を流すべきじゃないわ」と言って慰める。セクシーの存在や死がなければ、この映画はもっと明るい映画になりえていたし、セクシーの役割を母親が担うこともできた。だが、敢えてこの苦味を加えたのは意味深い。「Cheeni
Kum」は新感覚ボリウッド映画の部類に入るが、この苦味の存在が、伝統的な「ナヴァラサ」理論の踏襲になるのだろうか。
アミターブ・バッチャンとタッブーは非常に相性が良かった。2人とも確かな演技力を持っているし、雰囲気も似ている。後ろ髪を縛ったアミターブはキュートだったし、タッブーの美しい髪が印象的だった。95歳のゾーラー・セヘガルもお茶目だったし、パレーシュ・ラーワルの偽善者臭がプンプンする演技も良かった。映画中で徹底的に強調されたアミターブやパレーシュの子供っぽさは、「男は大人になるのに時間がかかる」というタッブーのセリフに集約されていたように思える。
ロンドンの他、デリーで撮影が行われており、大統領官邸、インド門、クトゥブ・ミーナールなど、デリーの名所がいくつか映し出されていた。ところでタッブーがクトゥブの鉄柱のことを「アショーカ王の柱」と説明するシーンがあったが、あれはアショーカ王とは全く関係ない。事実誤認である。
音楽はタミルを中心に南インドで活躍する音楽監督イライヤラージャー。シュレーヤー・ゴーシャルの歌うテーマ曲「Cheeni Kum」が映画の雰囲気を盛り上げており、最も素晴らしい。映画監督はRバールキー(バーラクリシュナン)というタミル人。もともとTVCMの監督をしており、「Cheeni
Kum」が映画監督デビュー作となる。その関係で、最近はあまりヒンディー語映画に音楽を提供することが少ないイライヤラージャーが音楽を担当することになったのだろう。
「Cheeni Kum」は、アミターブ・バッチャンとタッブーの「シュガーレス」なロマンスが見所の見事なラブコメ映画である。2007年のボリウッドは大きなヒット作に恵まれていないものの、「Bheja
Fly」、「Life In A... Metro」と都会向けの新感覚映画が意外な成功をしており、「Cheeni Kum」もそれに続くことになるだろう。
インドでスパと言えば、ヨーガの故郷と呼ばれるウッタラーカンド州リシケーシュの高級スパリゾート、アーナンダ・スパや、アーユルヴェーダ発祥の地として知られるケーララ州のリゾートホテルのスパが思い浮かぶ。それらは、欧米の外国人観光客や、昨今の健康ブームに乗った裕福なインド人の間で人気が高い。僕は今までアーユルヴェーダを体験したことはないが、高価な代金を支払っているだけあり、効果はあるのだろう。だが、金持ちから金を取ることを目的に運営されているスパに全幅の信頼を置くことはできない。しかも、それらのスパは女性客をメインターゲットに売り出されているように思える。もっと、庶民でも手軽に楽しめるスパがインドにはあるはずだ、そして真の男のためのスパがあるはずだ、前々から漠然とそういうことを思っていた。その期待に応えてくれそうだったのが、「南のスパ」と呼ばれるクットララム(Kuttralam/Kuttalam/Courtallam)であった。何かの雑誌でクットララムの豪快な写真を見て以来、いつか行ってみたいと思っていた。
クットララムは、タミル・ナードゥ州南部、ティルネルヴェリ県に位置している。ケーララ州の州境近くにあり、最寄りの空港はケーララ州の州都ティルヴァナンタプラム(旧名トリヴァンドラム)になる。クットララムは滝で有名な場所で、周辺にはいくつもの滝がある。それだけなら何ら特別なことはない。インドにはたくさんの滝があり、インド人も滝が大好きだ。特に観光資源に乏しい場所では苦し紛れになけなしの滝を観光スポットまたはピクニック・スポットとして売り出している。だが、クットララムの滝はただの観賞用ではない。その水には薬用効果があると言われている。なぜなら河が薬草の生い茂る森の中を流れているからだ。それが「南のスパ」と言われている由縁である。シーズンになると、その薬用の滝を浴びに各地から多くの人々が訪れるそうだ。外国人にはまだ知れ渡っていないため(ロンリー・プラネットにも載っていない)、訪れるのはほとんどがインド人。滝を浴びると言っても、水着で浴びるわけではない。男性はドーティー(腰巻)、女性はサーリーやサルワール・カミーズを着て浴びる。これぞ生粋のインド、天然のスパである。

シーズン中のクットララムのメイン・フォール
クットララムのシーズンは6月~9月。だが、今年はモンスーンの到来が例年より早めとのことで、もしかしたら5月末にはシーズンが始まっているのではないか、そしてあわよくば空いているのではないか、との期待があった。よって、冒険ではあったが、一般的なシーズンより一足先にクットララムへ行ってみることにした。
5月26日にバンガロールからキングフィッシャー航空IT2413に乗ってティルヴァナンタプラムへ。ティルヴァナンタプラムに来たのは2、3回目になる。翌日、ティルヴァナンタプラムのKSRTCバススタンドの10番プラットフォームから6時55分に発車しているテンカーシ行きのバスに乗った(54ルピー)。テンカーシはクットララムまでのアクセス拠点となる町である。テン=南、カーシ=カーシー=ヴァーラーナスィーであり、つまり「南のヴァーラーナスィー」と呼ばれる巡礼地だ。ティルヴァナンタプラムのバススタンドからは、朝から1時間に1本ほどの割合でテンカーシ行きのバスが出ている。
ティルヴァナンタプラムを出たバスは、西ガート山脈をグングン上って行った。だが、10時半頃だっただろうか、途中の山中でバスは停車してしまい、乗客は皆バスを降り出した。そして坂道を徒歩で下って行った。ここはまだテンカーシではなさそうだ。車掌に尋ねてみると、ケーララ州とタミル・ナードゥ州の州境らしい。道は途中で石のブロックが置かれて塞がれており、そこから先は二輪車以外通行できないようになっていた。数分歩いて山を下り、線路の下をくぐると、先にはバスとジープが待っていた。バスは既に一杯になっていたのでジープに乗り込んだ(10ルピー)。ジープに乗って10分ほどでテンカーシのバススタンドに到着した。
さて、既にタミル・ナードゥ州である。南インドでは、街中の看板に使われている文字の変化で州が変わったことが分かる。ケーララ州の州公用語であるマラヤーラム語の文字と、タミル・ナードゥ州の州公用語であるタミル語の文字はよく似ているのだが、タミル文字の方がより角ばっている。昔取った杵柄でタミル文字はある程度読むことができるので、バスの前面にタミル文字で書かれている行き先を頼りにクットララム行きのバスを探した。すると、クットララムと書かれたバスがちょうど発車しようとしていたのでそれに乗り込んだ(3.5ルピー)。テンカーシからクットララムまでは5kmほどで、すぐに到着した。11時半頃であった。
バスを降りると、そこはちょっとした商店とゲストハウスが並ぶだけの田舎町であった。オートワーラーや客引きが寄って来たが、ほとんどタミル語しか通じないので、何を言っているのかよく分からない。僕の数少ないタミル語の語彙を総動員して何とかコミュニケーションを取ってみると、どうも「タンニール・イッライ(தண்ணீர்
இல்லை)」、つまり「水がない」と言っているように聞こえた。やはりまだ来るには早過ぎたか・・・。一気に脱力感が襲って来る。しかし、クットララムに数ある滝の中で、ファイブ・フォールスという滝だけは水があるようだったので、まずはそこに行ってどんな感じか見てみることにした。クットララムの市街地からファイブ・フォールスまでは5kmほどで、オートで40ルピーであった。
ファイブ・フォールスの前はかなり大きな駐車場となっており、シーズン中は多くの人々が詰め掛けるであろうことが推測された。滝の前には寺院があり、その前には果物屋が並んでいた。特に大量のマンゴーが売られていた。ちょっとした期待を胸に滝の方へ行ってみたが・・・やっぱりほとんど水がない。ファイブ・フォールスはその名の通り、滝が5つに分かれて流れ落ちているポイントである。だが、今は隅の方でちょっとだけチョロチョロと水が流れ落ちているだけであった。それでもインド人が服を着たまま楽しそうに水を浴びていた。

ファイブ・フォールス
まだ水はないとのことだったが、メイン・フォールにも行ってみた。メイン・フォールはその名の通り、クットララム最大の滝であり、最大の見所であり、最大の滝浴びポイントである。メイン・フォールはクットララムの市街地のすぐそばにある。滝のすぐそばにかなり大きな寺院があり、市街地から寺院までは供え物などを売る店や巡礼宿が並ぶ参道となっている。だが、その多くはまだ閉まっていた。寺院の奥へ行くと、岩肌がむき出しになった断崖絶壁が現れた。これがメイン・フォールである。ただ、言われていた通り、水は一滴も流れていなかった。

水のないメイン・フォール
ここで豪快に滝に打たれたかった・・・。ケーララ州の方では既に雨が頻繁に降っていたが、ここまでは雨雲が届いていないのだろうか?カラッと晴れた青空がこんなに恨めしく思えたことはない。だが、水がないおかげで、岩肌に彫られたシヴァリンガはよく見えた。聞くところによると、例年シーズンは6月中頃から始まるようである。それ以降に来れば、怒涛の滝に打たれることが出来そうだ。

無数のシヴァリンガが岩肌に彫られている
ところで、クットララムの滝は男女別に水を浴びられるようになっている。シーズン時の写真から察するに、滝に向かって左側が男性用、右側が女性用となっている。滝のそばには必ず警察のポストがあり、滝浴びに来た人々の様子を監視できるようになっていた。滝のそばにはロッカーや着替え室もあった。割と施設は充実している。
クットララムのもうひとつのスペシャリティーはオイル・マッサージである。滝のそばには「Malish(マッサージ)」と書かれたマッサージ所があり、オイル・マッサージを受けることができる。ただ、現在はまだどこも開業していなかった。マッサージ師は全て男性で、ほとんど露天での営業であり、女性がマッサージを受けられる環境ではない。これが、クットララムが「男のスパ」である由縁である。オイル・マッサージを受けた後に滝で水を浴びると、何歳も若返った気分になるらしい。
水があったらクットララムで宿泊して全ての滝で打たれようと思っていたが、こんな状態であるし、暑さもだいぶ厳しかったため、すぐに立ち去ることにした。しかし、そのままティルヴァナンタプラムに引き返す気にもなれなかった。またタミル・ナードゥ州とケーララ州の州境でバスを乗り換えなければならないだろうし、ティルヴァナンタプラムで行こうと思っていた場所はほとんど月曜日が休日で、日曜日の今戻ると明日やることがないのである。だが、クットララムの町で「コッラムまで何km」の道標を目にし、ここからコッラム(旧名クイロン)まで行けることが分かった。地図で確認してみると、ティルヴァナンタプラムへ行くよりも楽に行けそうだった。コッラムはケーララ州名物バックウォーター・クルーズの拠点となる町。インドはかなり旅行して来たが、実は今までバックウォーターを一度も体験したことがなかった。よって、予定を急遽変更し、コッラムまで行ってバックウォーターをすることにした。
オートでテンカーシまで戻ると、またもちょうどコッラム行きのバスが発車しようとしていたところであった(57ルピー)。だが、そのバスもやはり来たときと同じ州境の道を通った。しかし、今回はバスを降りて歩く必要はなかった。いつの間にか州境は開いており、自動車が通れるようになっていた。ここの州境のシステムがよく分からない。午前中は州境が閉まっているということであろうか?
コッラムには4時間ほどで到着。早速バススタンドのそばにあるDTPCインフォメーション・センターで、明日のカヌーボート・ツアーズの予約をした(1人300ルピー)。カヌーボートだと、一般のバックウォーター・クルーズでは入って行けないような細い水路を通ってバックウォーターを楽しむことができるらしい。コッラムでは、バススタンドから徒歩5分ほどの場所にあるホテル・スダルシャンに宿泊した(ACなし部屋で1泊税込500ルピーほど)。
バックウォーターを非常に楽しみにしていたのだが、翌日は1日中雨であった。カヌーボート・ツアーズは屋根のないカヌーに乗ってのツアーなので、雨天では非常に困難である。午前9時発と午後2時発の便があり、午後の便まで待ってみたが、雨は止まなかった。よって、ツアーはキャンセルせざるをえなかった。新聞によると、ちょうどこの日(5月28日)、ケーララ州に南西モンスーンが到来したとのこと。クットララムでは水がなくて滝に打たれることができず、コッラムでは雨のせいでバックウォーターが楽しめなかった。自然の厳しさを痛感した次第である。
仕方がないので、コッラムでも何もせずにティルヴァナンタプラムに戻った(24ルピー)。
| ◆ |
5月29日(火) カラリパヤットとパドマナーバプラム |
◆ |
まだインドに留学する前だったが、伊藤武氏の「図説インド神秘事典」という本を読んでインド拳法の存在を知った。インドと拳法と言うと、当時は人気格闘ゲーム、ストリート・ファイター2のダルシムぐらいしか思い付かなかったが、ケーララ州には、どうやら古代または中世から伝わるマーシャルアーツ、カラリパヤットが存在するらしい。しかもそれは、少林拳、空手、截拳道など、アジアの拳法の起源とも言えるものらしい。それを知って以来、いつかこの目で見てみたいと思っていた。カラリパヤットに一番近い動きを最も手軽に見ることができるのは、おそらくボリウッド映画「Asoka」(2001年)であろう。同映画の戦争シーンの中で、兵士たちが奇妙な動きをして戦っていた。日本や欧米で作られる時代劇映画の戦争シーンとは明らかに趣きが違った。今思えば、あれはカラリパヤットを参考に撮影されたのであろう。今回、せっかくケーララ州までやって来たので、カラリパヤットの道場を見学してみようと思った。
カラリパヤットの道場はカラリと呼ばれる。カラリパヤットまたはカラリパヤットゥとは、マラヤーラム語で「カラリで訓練された武術」という意味のようだ。カラリはケーララ中に存在するらしいが、外国人観光客が見学しやすいのは、ティルヴァナンタプラムにあるCVNカラリであろう。英領インド時代に消滅しかけたカラリパヤットを復興させたCVナーラヤナン・ナーイルによって設立された、ケーララ州で最も権威のあるカラリである。ロンリー・プラネットにも紹介されている。カラリパヤットは武術であると同時に医術でもあるため、CVNカラリは道場と診療所を兼ねている。診療所の訪問時間は午前10時~午後1時、午後5時~6時半であるが、道場で早朝午前7時~8時半に行われる武術のトレーニングを見学することもできる。どうやら本当は前もってパーミッションを取っておく必要があるようだが、当日突然行っても見学させてもらえた。

CVNカラリ
CVNカラリで見学したカラリパヤットのトレーニングと、後でティルヴァナンタプラムの空港の書店で手に入れたPバーラクリシュナン著「Kalarippayattu:
History and Methods of Practising the Martial Art of Kerala」という本の記述を交えて、カラリパヤットについて簡単に説明しようと思う。
まず、カラリパヤットとは厳密には拳法ではないことを押さえておく必要がある。前述の通り、カラリパヤットを学ぶ上で武術と医術を切り離して考えることはできない。自身の体を動かすことによって、人間の体の構造を理解し、体を自在にコントロールすることを習得するのである。また、武術の修練において、素手での動きに加え、棒、棍棒、槍など、各種武器の取り扱いのマスターが重視される。特異なのは、身の回りのもの全てを武器にして戦うことも教えられることだ。それはジャッキー・チェンの映画を想起させる。よって、素手で戦うときは周囲に何もない緊急事態であり、そういう意味でカラリパヤットは素手での拳法を中心に据えた武術ではない。自衛と敵の撃破を優先した実践的な技術である。実際に見たカラリパヤットのトレーニングは柔軟体操の練習のようでもあり、行ったり来たりの反復練習からは水泳の練習に似ているようにも見えた。人間の体を極限まで理解して自由自在に動かすと同時に治療方法も習得することから、カラリパヤットはカタカリやテイヤムのような古典舞踊、アーユルヴェーダのような伝統医学、またヨーガと源を一にするものと考えられている。
伝説によると、カラリパヤットはパラシュラーマ神によって伝えられたと言う。ケーララ州とパラシュラーマの関係は深い。アラビア海と西ガート山脈に挟まれた南北に細長いケーララ州は、パラシュラーマによって創られたという伝説がある。パラシュラーマは、手に斧を持ったブラーフマン(バラモン)の姿で現される神様であるが、彼がその斧でアラビア海を押し出したことにより、ケーララの土地が出来上がったと言われている。ケーララ州の州公用語となっているマラヤーラム語は「マラ(山)+アラム(海)」から成る言葉であるが、この言葉はケーララ州の地理をよく表している。ちなみにケーララとは、「ケーラ(ココナッツ・ツリー)の土地」という意味である。パラシュラーマは新しく創造された土地にブラーフマンを呼び、統治階級とした。通常、インドで統治階級はクシャトリヤであるが、パラシュラーマはクシャトリヤとライバル関係にあり、クシャトリヤではなく、僧侶階級のブラーフマンに統治の役割を与えた。その際、パラシュラーマは最も統治能力に長けた4氏族のブラーフマンを選び、彼らに武術を教えた。パラシュラーマから武術を教わった4人のブラーフマンは、さらに21人の弟子に武術を教えた。その21人がケーララ中に21のカラリを創設した。よって、カラリパヤットには4つの流派があり、カラリを開いた21人がカラリパヤットの21グルと呼ばれている。後世にはカラリの数は108に増えたとも言われている。
また、カラリパヤットの源流は古代インドの聖典ヴェーダにも求めることができる。ヴェーダには一般にリグヴェーダ、サーマヴェーダ、ヤジュルヴェーダ、アタルヴァヴェーダの4つがある。また、各ヴェーダにはウパヴェーダという、本ヴェーダから派生して出来た準ヴェーダが存在する。ヤジュルヴェーダのウパヴェーダのひとつが、ダヌルヴェーダである。ダヌルヴェーダには武器の取り扱いの知識がまとめられており、カラリパヤットの原型を見ることが出来る。
ところで、マラヤーラム語で首領のことをナーヤカと呼ぶ。ナーヤカの複数形はナーヤカンマルである。ナーヤカンマルが訛ってナーヤルまたはナーイルになった。カラリの主はナーヤルと呼ばれた。また、クルプ、ナンビアル、パニッカルという姓名の氏族もナーヤルと同様のステータスを与えられ、やがて彼らは戦士階級を形成して行った。ナーヤルの中でも特に、権威のあるカラリの主や、一定のカラリのグループを束ねるリーダーは、グルッカルと呼ばれた。ナーヤルは日本の中世の武士の御恩と奉公の関係のように、領主から土地を与えられる代わりに、領土の安全保障と兵役を担った。ナーヤルの男子は7歳頃からカラリで訓練を受けた。彼らはまるで骨がないかのように自由に体を曲げることが出来た。彼らは素手でも優れたレスラーであったが、武器を持ったときに最高のスキルを発揮した。彼らは腰巻以外、体に何も身に付けてらず、そのままほぼ裸に近い格好で戦争にも出陣した。そして誰よりも多くの敵兵を殺した。
カラリパヤット全盛時代には、ナーヤル同士の決闘も行われていたらしい。領主同士の間で何か諍いが起こると、各領主お抱えのナーヤル同士が領主に代わって決闘を行った。決闘用に登用された戦士はチェカヴァンと呼ばれ、最高のステータスを与えられた。アンカカラリと呼ばれる特別な決闘場(64フィート×32フィート)が造営され、公衆の面前でアンカチェカヴァンと呼ばれる決闘が行われた。当然、決闘はどちらかの死によって決着がつく。そもそも決闘に負けた後に生きていることは大きな恥とされており、どちらかが死ななければ決闘は終わらなかった。この決闘の伝統には、領主同士の大規模な戦争の勃発と多大な死傷者の回避というメリットがあった。
カラリパヤットと同様の武術は古代、インド各地に存在したと考えられるが、特にケーララ地方で隆盛し、今まで温存されたのには地理的な要因がある。北インドは広大な平原地帯であり、戦争は騎兵隊、象兵隊、戦車隊、歩兵隊から成る大規模な軍隊同士で行われることが常だった。だが、ケーララ地方はアラビア海と西ガート山脈に挟まれた狭い森林地帯であり、戦争時にそのような大規模な軍隊を動員することは現実的ではなかった。代わりに少数精鋭によるゲリラ戦が好まれた。カラリパヤットの使い手たちが侵略者を敗走させ、王国を救った英雄譚は尽きない。例えばコーリコード(カリカット)の民たちは、王の留守を狙って攻めてきたポルトガル人たちをカラリパヤットによって撃退した。ナポレオンをワーテルローの戦いで破った英国の英雄「ドゥーク・オブ・ウェリントン」ことロード・ウェルズリーは、コッタヤムのケーララ・ヴァルマー・パラッスィ・ラージャー王を攻略する際、マシンガンなど近代的兵器を装備した300人の兵士たちを、王直属の60人の剣士たちによって全滅させられるという辛酸を嘗めさせられている。さらに、トラヴァンコール王国のマールターンダ・ヴァルマー王の兵士たちはオランダ軍を撃退し、敵将を捕えるという手柄まで立てている(マールターンダ王に関しては後述)。ケーララ地方は英領インド時代にも独立を保ち、ケーララの人々はそれを非常に誇りにしている。ケーララ地方の王朝が外からの侵略者を度々撃退して来たのは、一撃必殺の最強の武術カラリパヤットがあったからだと考えられている。
上で決闘用のアンカカラリの話が出て来たが、日々の練習のために建てられるカラリは、チェルカラリまたはクリカラリと呼ばれる。地面を長方形に掘って造られるため、半地下のような構造になっている。ティルヴァナンタプラムのCVNカラリもやはり伝統に則って半地下の構造であった。大きさは42フィート×21フィートで、各辺が正確に東西南北を向いており、入り口は必ず東になる。他にもカラリの建築様式には細かい規定がなされている。最も特徴的なのは南西の角に作られる祭壇プータラである。プータラは7段の弓形をしており、7段目にはカラリの神であるカラリ・パラデーヴァタの像が置かれる。プータラの北側、西壁の前にはガナパティ、つまりガネーシャの像が置かれ、その北はナーガの祭壇となっている。そのさらに北には2つの四角形の祭壇が置かれる。ひとつは4流派と21グルの祭壇で、もうひとつはそのカラリのグルのための祭壇である。さらに、北西、北東、南東の角にも小さな祭壇が置かれるが、これらは戦いと武器の神々に捧げられたものである。また、CVNカラリでは、パラシュラーマの像や、ドゥルガー女神、ラクシュミー女神、サラスワティー女神の絵も飾られていた。このように、カラリは道場でありながら寺院のような性格も持ち合わせている。
カラリに入場する者は必ず右足から入り、地面を右手で触れて額に持って行く動作をする。そしてまずはオイルを体中に塗る。そして、個人個人の信条や宗教に合わせてカラリに祀られている神々の礼拝を行い、練習を始める。練習は柔軟体操のような個人で行う型と、武器を使った2人で行う型がある。個人練習は同じ動作の反復練習である。足を頭上まで蹴り上げるような動作や、飛び上がったりしゃがんだりの繰り返しなどを行う。練習は必ず東から西へ向かって始められ、西壁まで到達したら反転して東へ向かい、東壁に到達して1セット完了となる。一方、武器を使った練習はカラリの中心で行われる。CVNカラリでは、背丈ほどある長い棒を使った練習と、杵のような形の短い棒を使った練習を見ることができた。特に面白かったのは棒術の方であった。棒にはたっぷりとオイルが塗られ、手と手の間を自在に滑って相手に繰り出される。まるで棒の長さが2倍になったかのような巧みな棒さばきであった。カラリパヤットでは順に様々な武器の使い方を伝授される。武器の種類は流派によって異なるが、Pバーラクリシュナン著「Kalarippayattu」には、長棒、短棒、曲刀、棍棒、短剣、剣と盾、槍の使い方が記述されていた。また、布や素手による戦い方にも言及があった。カラリパヤットでは一般にこれらの武器の使い方をマスターすることで免許皆伝となるが、さらにマルマと呼ばれる秘孔の知識が奥義として存在する。マルマは秘伝であり、カラリの後継者に選ばれた一番弟子にしか伝授されないとされる。マルマは一撃で相手を気絶させたり死に至らしめたりするポイントで、体中に107ヶ所ある。「Kalarippayattu」にはマルマの場所の説明があったが、それと同時に「著者や出版社は、これらの記述の実践によって発生した障害、症状、死亡のいかなる責任も持たない」と注意書きがしてあった。マルマの知識は、マッサージを施す際にも必須となる。
CVNカラリには白人や子供の訓練生もいた。グルは英語も達者で、ここなら外国人でも容易にトレーニングをすることができそうだった。ただし、多くのカラリでは短期のみのトレーニングは通常受理していないようだ。ある程度マーシャルアーツの経験があり、長期的に真剣に訓練したい者のみを受け容れているようであった。また、CVNカラリは写真撮影禁止であり、カラリの内部や訓練の様子を撮影することはできなかった。
ちなみに、カラリパヤットやインド武術に関しては、印度武術王国という日本語のウェブサイトが詳しい。

カラリパヤット
CVNカラリを見学した後、ティルヴァナンタプラムのKSRTCバススタンドから出ているカンニャークマーリー行きのバスに乗って、トラヴァンコール王国の旧都パドマナーバプラムへ向かった。パドマナーバプラムは1500年から1790年に至るまで、ケーララ州南部からタミル・ナードゥ州南部にかけての地域を支配したトラヴァンコール(ティルヴィタンクール)王国の首都だった場所で、代々の王が住んだ宮殿が残っている。現存している宮殿の最古の部分は1555年の建造で、その敷地面積は186エーカーに及ぶ。典型的なケーララ様式の木造建築で、アジア最大の木造宮殿とも言われる。現在パドマナーバプラムはタミル・ナードゥ州カンニャークマーリー県に編入されているが、パドマナーバプラム宮殿だけはケーララ州の管轄という変則的な体制となっている。パドマナーバプラムはティルヴァナンタプラムから約60kmの地点にあり、ティルヴァナンタプラム~カンニャークマーリー間を走るバスで簡単にアクセスできる。パドマナーバプラムへのアクセス拠点となるのは、両都市の間にあるタッカライという町である。ティルヴァナンタプラムからタッカライのバススタンドまではバスで約2時間だった。バススタンドからはオートで宮殿まで行くことができる(20ルピー)。宮殿の入場料には外国人料金があり、外国人観光客は200ルピーを払わなければならない。また、入場料とは別にカメラ持ち込みのために25ルピー、ビデオ撮影のために1200ルピーの追加料金が必要である。その上、荷物の持ち込みは禁止の上に、訪問者は必ず靴を脱がなければならず、チケットカウンターの横にクロークルームや靴を預ける場所が用意されている。
パドマナーバプラム宮殿の起源は14世紀まで遡る。当時この地域はカルクラムと呼ばれており、地方領主によって14世紀に泥を塗り固めて建設された宮殿はダルパクランガラと呼ばれた。18世紀にトラヴァンコール王国の王となったマールターンダ・ヴァルマーは、泥で出来た城壁を花崗岩の城壁に変え、宮殿を建て直し、宮殿とその周辺地域の名称をパドマナーバプラムと改名した。マールターンダ・ヴァルマーは優れた王で、周辺の王国を次々と併合し、小国だったトラヴァンコール王国を、南インドを代表する王国にまで拡張した。特に1741年にオランダ東インド会社の軍隊を打ち負かしたことが歴史に名高い。マールターンダ・ヴァルマーはオランダの将軍シュタッフス・ドラノイを捕虜としただけでなく、彼を自軍の最高司令官に任命し、軍隊の近代化を進めた。パドマナーバプラム宮殿には、マールターンダ・ヴァルマーが建造した建物が多く残っている。

パドマナーバプラム宮殿の城門(左)と玄関前の広場
堅牢な城壁で守られた宮殿の門を通り、チケットを買って靴を脱いだ後、パディップラと呼ばれる西向きの玄関をくぐると、まずはプームカムと呼ばれる謁見の間がある。切妻部や柱には繊細な彫刻が彫られており、木製の天井にも90種類の花の彫刻が施されている。また、壁にはオナヴィルと呼ばれる、支配下国の君主から贈られた挨拶状が飾られ、床には花崗岩で出来た7つのベッドが置かれている。また、中央部には騎馬兵の彫刻が彫られた青銅製のランプが吊り下げられている。トラヴァンコール王国には遠く中国からも使節や商人がやって来ており、ベッドは中国人から贈られたものとされている。瓦葺きの勾配屋根や切妻、木製の柱が林立する内部などは、日本の木造建築ともよく似ている。

プームカム(左)と騎馬兵の彫刻が彫られた青銅製のランプ(右)
プームカムの上階はマントラシャーラーと呼ばれる会議室で、王はここで大臣たちや領主たちと重要な決議を行った。プームカムからマントラシャーラーへ上がる階段は非常に細く、敵の大群が突然襲って来ても、一度にマントラシャーラーへ上がれないように工夫されている。やはり天井、壁、窓を成す木造部分は繊細な彫刻が施されている。また、マントラシャーラーの周辺はエアダクトが巡らされており、ハーブの芳香を含んだ冷たい風が吹き込むようになっている。床は黒光りして、窓から差し込む光を反射しているが、これはライム、ココナッツの皮、ココナッツ汁、卵、砂、ラテライト、ハーブを混ぜ合わせて作られている。

マントラシャーラー
マントラシャーラーの南には、78m×6mの大きさの長方形をした2階建て建築物がある。これはウットゥプラと呼ばれるダイニングホールで、毎日ここで2千人のブラーフマンに餐食が行われたと言う。1階と2階ではランクが違い、高貴なブラーフマンは2階で食事をした。

ウットゥプラ
順路に従って進んで行くと、次はタイ・コッタラム(母親の宮殿)と呼ばれる建物に入る。タイ・コッタラムは、パドマナーバプラム宮殿がまだダルパクランガラと呼ばれていた時代(16世紀半ば)に建てられた建物で、宮殿コンプレックス内では最も古い建築物である。ケーララ州の伝統的建築様式とヴァーストゥシャーストラ(インドの伝統的建築学)に則って設計されている。入ってすぐの間はバーグヴァティー女神へのプージャー(礼拝)を行う場所で、木製の柱や天井は繊細に彫刻されている。建物の中心は吹き抜けになっており、雨の日に雨水を浴びることができるようになっている。

タイ・コッタラム
タイコッタラムを抜けると、ちょっとした中庭に出る。ここには小さな柱が立っており、上には38kgの重さの石が乗っている。これは、軍隊への入隊希望者の試験場であった。希望者は力とスタミナを証明するため、この石を100回柱の上に乗せなければならなかった。そのすぐそばには王族が居住する建物群がある。最も目立つのは、宮殿コンプレックス内で最も高い4階建てのウッパリカ・マリカである。上階部分が外側に迫り出している構造は、ヒマーチャル・プラデーシュ州の建築とよく似ている。ウッパリカ・マリカの入り口まで行くには狭い通路を通って行かなければならないが、これもセキュリティー上の工夫である。この狭さのおかげで、大軍が攻めて来ても、一気に押し寄せることが出来ない。ウッパリカ・マリカは王族の居住区であると同時に宝物庫でもあり、宮殿コンプレックス内で最も重要な建物であった。ウッパリカ・マリカの1階は宝物庫、2階と3階は王の寝室、4階は礼拝室となっている。だが、現在は2階までしか入れない。2階には、65種類の薬用樹木を使って作られた豪華なベッドが置かれている。これは16世紀にオランダ東インド会社から贈られたものと考えられている。3階の寝室は断食期間中(7月~8月)に利用されるもので、やはりベッドが置かれているようだ。さらに4階の礼拝室の四方の壁には、18世紀の美しい壁画が描かれているが、保護のために現在では観光客に対して閉ざされている。この壁画の写真は、宮殿コンプレックス内にある博物館に展示されている。

ウッパリカ・マリカ
左下はウッパリカ・マリカ1階寝室に置かれたベッド
ウッパリカ・マリカの1階からは、ヴェップムットゥ・コッタラム(王族女性居住区)の建物につながっている。ここでは王女、姫、侍女たちが生活していた。入ってすぐの長細い部屋の壁には、クリシュナを題材にした水彩画がズラリと並んでいる。また、部屋の両端にはベルギー製の巨大な鏡が飾られている。この他、王女の寝室やトイレなどが併設されている。

ヴェップムットゥ・コッタラム
ヴェップムットゥ・コッタラムを抜けると、今度はヴァダッケ・コッタラムと呼ばれる細長い回廊部に出る。ヴェッダケ・コッタラムは、チャンドラ・ヴィラーサム、テッケテルヴ・マリカ、インドラ・ヴィラーサムの3パートに分かれている。これらは宮殿コンプレックスの中では最も新しい建物である。まず、チャンドラ・ヴィラーサムに入る。特に何の装飾もない殺風景な部屋だが、ここは事務室として使われていた。チャンドラ・ヴィラーサムの隣には、テッケテルヴ・マリカと呼ばれる建物があり、ここには5方向に窓が開いたバルコニーが備え付けられている。窓から外を覗くと民家が並んでおり、宮殿の外周の道に面していることが分かる。王はここからラトヤートラー(山車のパレード)を見物したり、民の不平を聞いたりしたと言う。その隣にあるのはインドラ・ヴィラーサム。この建物は、オランダ人、フランス人、英国人など、外国人賓客のためのゲストハウスとして利用された。外国人の趣味に合わせ、この建物だけは西洋式の建築となっている。

テッケテルヴ・マリカのバルコニー(左)とインドラ・ヴィラーサム(右)
インドラ・ヴィラーサムを出て、貯水湖の周りを回って歩いて行くと、再びタイ・コッタラムに入る。ここでは台所を見ることが出来る。

宮殿を臨む庭園(左上)を歩いて行くと、再びタイ・コッタラムへ
台所や食物貯蔵庫がある
宮殿コンプレックス見学ルートの最後にあるのが、ナヴァラートリ・マンダパム、いわゆるダンスホールである。パドマナーバプラム宮殿の建築物のほとんどは木造だが、このナヴァラートリ・マンダパムと、併設されているサラスワティー女神寺院だけは花崗岩による石造である。ただし、元々木造のものを後に石造で再建したという記録がある。66フィート×27フィートの広間は無数の石柱で囲まれており、床は日光を反射して黒光りしている。ここでは古典舞踊のパフォーマンスが行われた他、ナヴァラートリの期間、9日間連続で音楽の演奏が行われたと言う。ホールの一角には無数の覗き穴の開いた部屋があるが、ここからは王族の女性たちが舞踊などを鑑賞した。

ナヴァラートリ・マンダパム(左)とサラスワティー寺院(右)
また、パドマナーバプラム宮殿には時計塔もある。これは18世紀にマールターンダ・ヴァルマーが作らせたものとされている。この時計塔の裏には、こんな伝承が残っている。マールターンダ・ヴァルマーは、時計の技術を学ばせるため、職人をオランダに送った。時計の技術は極秘とされていたため、職人は盲人の振りをして当時有名だった時計職人に弟子入りし、徐々に信頼を勝ち取った。時計の技術を完璧にマスターしてトラヴァンコール王国に戻った職人は、王のために時計塔を建造した。それがパドマナーバプラム宮殿のプームカムの隣に建っている時計塔である。喜んだ王は職人に広大な土地と金銀財宝を与えたが、同時に、2つ目の時計塔が出来るのを防ぐため、職人の両手を切断してしまった。だが、王国の記録では、ティルヴァナンタプラムのパドマナーバスワーミー寺院のそばにあるプテ・マリガ宮殿博物館の時計塔も、マールターンダ・ヴァルマーの後を継いだティルナル・ラーマ・ヴァルマーの治世に同じ職人によって制作されたとされており、その伝承の信憑性は疑わしい。パドマナーバプラム宮殿の時計塔は今でも動いており、3km先まで届く強力な鐘を鳴らす。

パドマナーバプラム宮殿の時計塔(左)と
プテ・マリガ宮殿博物館の時計塔(右)
宮殿コンプレックス内には博物館もあり、宮殿に所蔵されていた武器や、周辺地域から集められた石像・木像などが陳列されている。この場所には元々馬屋や守衛室があったが、取り壊されて新しくケーララ様式の建物が建てられた。博物館の展示物の中で目を惹いたのは、虜囚の懲罰のために使われた拘束具であった。頭部のフックにより上から吊り下げられるようになっており、これをはめられた虜囚は腕と膝を曲げることが出来なくなる。罪人は一定期間これを身に着けさせられ、自由を奪われる苦しみを味わわされたのであろう。

拘束具
パドマナーバプラム宮殿の各所にはガイドが立っており、解説をしてくれる。英語で一生懸命親切に説明してくれる人もいるが、外国人を見ると、英語がしゃべれないのか面倒臭いだけなのか、見て見ぬ振りをしたり、二言三言のいい加減な解説しかしてくれなかったり、順路を示すだけだったりする人もいた。また、英語による解説が書かれたボードも要所要所に立っていたが、完全ではなかった。よって、もし宮殿に入る前に携行してくれるガイドが見つけたらガイドを頼むべきだし(僕は発見できなかった)、そうでなかったら少なくとも宮殿前の店で売られているガイドブック「Padmanabhapuram
Palace; An Authentic Tourist Guide」を買って、それを参考にしながら見学するべきだろう。パドマナーバプラム宮殿は、200ルピーという法外な入場料を払い、ガイド料を払って巡るだけの価値のある場所だと感じた。
パドマナーバプラム宮殿を見終わった後は、再びバスでティルヴァナンタプラムまで戻った。ネイピア博物館など、ティルヴァナンタプラムのお決まりの観光地を再訪した後、バンガロール行きの飛行機の出発時間まで暇つぶしするため、空港近くのシャンクムガム・ビーチへ行ってみた。本当は世界的に有名なコーヴァラム・ビーチへ行きたかったのだが、そこまで行く時間の余裕はなかった。だが、ティルヴァナンタプラムの市街地から8kmの地点にあるシャンクムガム・ビーチも十分面白く、来てよかったと思えた。

ネイピア博物館
まず面白いのは、海岸のすぐそばに巨大な裸体の女性の像が横たわっていることである。マツヤ・カンニャーカと呼ばれる人魚像とのことだが、下半身が魚になっている訳でもなく、ただのエロチックな裸体像となってしまっている。なぜこんなものがこんなところにあるのか、全く謎であるが、ティルヴァナンタプラムの観光地ガイドにはまことしやかにこの人魚像が見所として取り上げられている。この上に上って遊ぶことが出来たりしたら、それはそれで面白そうなのだが、誰も上っている人がいなかったことから察するに、それは禁止なのだろう。

マツヤ・カンニャーカ
また、ビーチのそばにはインディアン・コーヒー・ハウスやレストランがあり、食事をしながら海を眺められるようになっていた。シャンクムガム・ビーチは、ティルヴァナンタプラムの住民のピクニック・スポットになっているようで、多くの家族連れが遊びに来ていた。とは言ってもモンスーンのこの時期、海は荒れに荒れており、泳いでいる人はいなかった。そもそもインド人は服を着たまま海で遊ぶので、シーズンでも泳ぐ人はいないだろう。そんなインド人の様子を眺めているだけでも楽しいものだ。

ビーチに佇むインド人家族
シャンクムガム・ビーチで最大の収穫だったのは、モンスーンの到来を眼前で目撃することが出来たことである。コッラムではバックウォーター・クルーズを予定していた日に南西モンスーンが直撃したが、面白いことにティルヴァナンタプラムにはまだモンスーンの雲は辿り着いていなかった。よって、ティルヴァナンタプラムでは、夕方から夜にかけて雨が降るものの、まだ日中は晴れていた。シャンクムガム・ビーチに来てみると、北の方に巨大な雨雲があるのがよく見えた。時々雲の中を光の筋が貫いていた。その雲の圧倒的な大きさから、これがモンスーンだと直感できた。

モンスーンの雨雲
その雨雲は、しばらくは遠くでモクモクと動いていたのだが、気付いたらみるみる内にシャンクムガム・ビーチの上空を覆って行った。まるで空に暗黒の絨毯が敷かれていくようであった。今まで西から東へビーチに押し寄せていた波は、苦痛に身をよがらせるように、バラバラの方向にうねり始めた。そしてやがて波の動きは雨雲の動きと平行して北から南へと流れるようになった。

雨雲が青空を異様なスピードで黒く染めて行く
突如、強風が吹き始めた。このときは既にインディアン・コーヒー・ハウスの庇の下でコーヒーを飲んでいたので、その様子を平然として眺めていたが、ターバンをかぶった店員たちは、急いで外に出ている机や椅子を中にしまい始めた。やがて雨が降り始めたが、それほど強い雨ではなかった。本格的に降り始めると移動が困難になるので、オートを拾って空港へ向かった。
こうして、モンスーンに翻弄されたケーララ州(一部タミル・ナードゥ州)の短い旅は、モンスーンの到来を拝んで終了となった。
| ◆ |
5月31日(木) Shootout At Lokhandwala |
◆ |
しばらく南インドにいて、デリーの暑さのことを忘れていたが、やはりデリーに戻って来ると、この暑さは南インドの暑さとは比べ物にならないことを実感する。空気が重さを持って体にぶつかってくるような感じだ。だが、既にデリーに住んで長いので、この暑さが心地よく思えるようになった。インドへの愛と理解は流した汗の量で測られるとしたら、酷暑期のインドを経験せずにインドを語ることは不可能である。今日は、大ヒットしている新作ヒンディー語映画「Shootout
At Lokhandwala」を見に出掛けた。キャストはアミターブ&アビシェーク・バッチャン、サンジャイ・ダット、スニール・シェッティー、ヴィヴェーク・オベロイなどで、今年最大のオールスター映画と言っていい。この映画は、1991年11月16日にボンベイ(現在のムンバイー)のローカンドワーラーで発生した、警察によるマフィア射殺事件の真相に迫る作品で、「真実の噂に基づいて」作られているとされている。
題名:Shootout At Lokhandwala
読み:シュートアウト・アト・ローカンドワーラー
意味:ローカンドワーラーでの決戦
邦題:シュートアウト
監督:アプールヴァ・ラーキヤー
制作:サンジャイ・グプター、ショーバー・カプール、エークター・カプール、サンジャイ・ダット
音楽:ストリングス、ユーフォリア、ビッドゥー・アッパイヤー、シバーニー・カシヤプ、アーナンド・ラージ・アーナンド、ミカ・メヘンディー
作詞:ユーフォリア、ビッドゥー・アッパイヤー、ヴィラージ・ミシュラ
出演:サンジャイ・ダット、スニール・シェッティー、アルバーズ・カーン、ヴィヴェーク・オベロイ、トゥシャール・カプール、ローヒト・ロイ、シャッビール・アフルワーリヤー、アーディティヤ・ラーキヤー、ラヴィ・ゴーサーイー、ディーヤー・ミルザー、ネーハー・ドゥーピヤー、アールティー・チャブリヤー、アムリター・スィン、ラーキー・サーワント、アミターブ・バッチャン(特別出演)、アビシェーク・バッチャン(特別出演)
備考:PVRプリヤーで鑑賞。
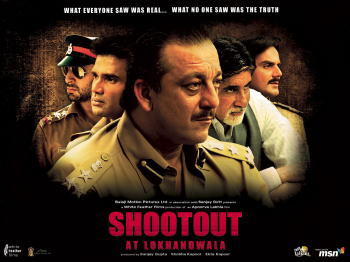
左から、アビシェーク・バッチャン、スニール・シェッティー、サンジャイ・ダット、
アミターブ・バッチャン、アルバーズ・カーン
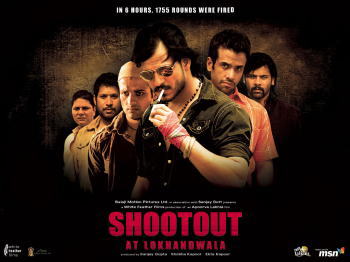
左から、ラヴィ・ゴーサーイー、アーディティヤ・ラーキヤー、ローヒト・ロイ、
ヴィヴェーク・オベロイ、トゥシャール・カプール、シャッビール・アフルワーリヤー
| あらすじ |
1991年11月16日、ボンベイの住宅街ローカンドワーラーで、警察の一団が1755発の実弾を発砲し、アパートに潜む5人のマフィアを殺害する事件が発生した。民間人を危険にさらし、犯人を全員射殺した作戦に対し、内外からは批判が高まり、作戦を指揮したシャムシェール・スィン・カーン警視監補(サンジャイ・ダット)や、その部下のカヴィラージ・パーティール警部補(スニール・シェッティー)、ジャーヴェード・シェーク巡査(アルバーズ・カーン)は裁判にかけられることになった。審査委員に任命された弁護士ディングラー(アミターブ・バッチャン)は、3人の事情聴取を行う。その中で徐々に事件の全貌が明らかになって行く。
事の発端は、パンジャーブ州アムリトサルの黄金寺院に立てこもったスィク教徒テロリストたちを殲滅したブルースター作戦まで遡る。スィク教過激派たちはボンベイまでやって来て、テロ活動を行った。だが、当時ボンベイ警察は制度的にテロリストに対して十分対抗できないでいた。その犠牲となったのがアビシェーク・マトレー警部補(アビシェーク・バッチャン)であった。マトレー警部補と親しかったSSカーンは、カヴィラージやジャーヴェードなど、優秀な警官を集め、対テロリスト部隊(ATS)を設立する。
当時ボンベイのアンダーワールドを牛耳っていたのはマーヤー(ヴィヴェーク・オベロイ)というマフィアであった。マーヤーはドバイに住むボスの命令に従ってボンベイで活動していたが、次第に独立して動き始める。マーヤーの下には、ブワー(トゥシャール・カプール)、ファットゥー(ローヒト・ロイ)、RC(シャッビール・アフルワーリヤー)、ダブリング(アーディティヤ・ラーキヤー)という部下がいた。SSカーンは、建設会社社長の殺人事件からマーヤーの名を知り、彼を追い始める。
SSカーンはマーヤーの一味の家族にアプローチするが、逆にマーヤーはATSの家族を脅迫する。一方、マーヤーは別の建設会社社長の息子を誘拐し、身代金700万ルピーを要求する。だが、このときSSカーンのもとに、マーヤーたちがローカンドワーラーのアパートに潜んでいるとの情報がもたらされる。SSカーンたちは早速アパートを包囲する。興奮したブワーはロケットランチャーを放つが、警察は民間人の住むアパートに向けて銃弾の雨を降らせる。その後アパートに突撃したATSは、5人のマフィアを全員射殺する。その際、人質となっていた社長の息子も殺されてしまう。これが事件の全貌であった。
ディングラーは法廷において、「もし家の外に銃を持った男が立っているなら、それはマーヤーではなく、SSカーンであって欲しい」とSSカーンを擁護する発言をし、彼らは無罪となる。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
日本でも、殺人事件などが発生した場合、しばしば「殺された被害者や遺族の人権が無視され、加害者の人権が守られ過ぎている」との批判が噴出することがある。この映画は正にその問題を扱っている。警察の一団が住宅地でマフィアを皆殺しにすると言う、実際に起こった事件の是非を問うことで、その問題を扱っている。作り手は明らかに「犯罪者は容赦なく罰するべし」という立場に立っている。SSカーン警視監補は、ローカンドワーラーでのエンカウンター(インド英語で「犯人の射殺」を意味する)で、部下たちに「Shoot
to kill(射殺)」を厳命し、逮捕を拒否した。ローカンドワーラー事件における警察の毅然とした態度は当時アンダーワールドにかなりの影響を与えたようで、以降ボンベイでは犯罪率が急落したと言われている。このように「テロリストは即殺すべし」という強烈なメッセージが込められた映画であるが、同時に娯楽映画としても楽しめるように工夫がなされており、それが大衆に受け容れられているように思われる。
主人公の名前は、実在の人物の名前から微妙に改名されたものが使われている。例えばローカンドワーラー作戦を指揮したのはアーフターブ・アハマド・カーンだが、映画ではシャムシェール・スィン・カーンとされている。マフィアのドンはマヒーンドラ・ドーラスという名前だが、映画ではマーヤーになっている。ちなみにアーフターブ・アハマド・カーン自身が、SSカーンに作戦の許可を与えるクリシュナムールティ警視総監役でカメオ出演している。
興味深かったのは、未だに謎とされている部分はどちらとも取れる形で撮影されていたことである。最も重要なポイントは、マーヤーらがローカンドワーラーにいるという情報をSSカーンは誰から入手したか、ということだ。映画では、インフォーマーから情報を得ている映像と、裏切ったマーヤーを殺すためにドバイのボスがSSカーンに居所を教えている映像の2つが使われており、どちらが真実かは特定されていなかった。また、ドバイのボスの名前は全く言及されていなかったが、その容姿から、それがインド最凶のマフィアで現在行方不明のダーウード・イブラーヒームを指していることは明らかである。
今年2月にインドで一般公開された「Black Friday」も、実際に起こった事件をスクリーン上で再現した映画であった。「Black Friday」が題材としたボンベイ連続爆破テロの裏にも、ダーウード・イブラーヒームがいたとされている。どうしてもこの2作品を比べてしまうのだが、映画としての完成度は、「Black
Friday」の方が数段上であった。だが、「Shootout At Lokhandwala」も、警察、マフィア、両方のキャラクターの内面の葛藤や家族との関係まで描写しようとする努力が感じられ、決して一面的な作品で終わっていなかったところが評価できる。
男優陣は豪華キャストと言っていいだろう。アミターブ&アビシェーク・バッチャン親子が特別出演ながら共演していることに加え、サンジャイ・ダット、スニール・シェッティー、アルバーズ・カーン、ヴィヴェーク・オベロイ、トゥシャール・カプールなど、マニアックな顔ぶれである。この中で最も光っていたのはヴィヴェークだ。冷酷な笑みを浮かべる若きマフィアのドンを鬼気迫る演技で演じていた。長らく低迷していたヴィヴェークだが、この映画をきっかけに復活できるかもしれない。逆に雰囲気をぶち壊していたのは毎度お馴染みトゥシャールである。おとぼけ顔の彼に悪役が務まるはずがない。プロデューサーの1人が、トゥシャールの姉でTV業界で絶大な権力を持つエークター・カプールであるため、否応なしにトゥシャールがこの映画にキャスティングされたのであろう。それを思うとさらに情けない。
完全に男が主役の映画だったため、女優陣にほとんど見せ場はなかった。ニュースレポーターを演じたディーヤー・ミルザー、ブワーの恋人タヌーを演じたアールティー・チャブリヤー、SSカーンの妻を演じたネーハー・ドゥーピヤーなど若手の女優が出演していたが、最も活躍できていたのは半分アイテムガールのような存在だったアールティーだろう。だが、本当にこの映画で存在感を示せていた女優は、マーヤーの母親アーイーを演じたアムリター・スィンであった。
音楽監督はアーナンド・ラージ・アーナンドだが、他にも多くのミュージシャンが参加しており、音楽面でもオールスターキャストとなっている。特にマーヤーに関係するミュージカルで、遊びにあるダンスナンバーが多かったが、特に耳に残るものはなかった。アイテムナンバー「Mere
Yaar」は、「Omkara」(2006年)の「Beedi Jalaile」に酷似していたのだが、これは大丈夫なのだろうか?
「Shootout At Lokhandwala」は、インド人の間では意外な大ヒットを飛ばしてしているが、多少大味なところもあり、もしかしたら日本人の趣味には合わない映画かもしれない。



