 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
 これでインディア これでインディア 
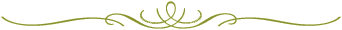
2013年1月
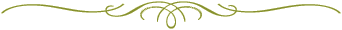
|
|
|
|
インド生活が長くなって来ると、「何年ぐらいインドにいるんですか?」という質問に答えるのがだんだん苦痛になって来る。日本人に対しても、インド人に対しても、である。学生という身分だと尚更だ。インド歴2-3年の頃はまだ胸を張って答えることができたが、5年を越えると次第に口が重くなる。10年の大台に乗ると一瞬だけ開き直れたが、それを越えたら今度は「10年以上です」とぼかして答える癖が付いてしまった。勝手に質問の内容を変えて、インド歴ではなくJNU歴ということにして、鯖を読んで答えることもある。しかし、JNU歴にしてももう10年になってしまう。間違いなく、インドに長く居すぎると、日本人からもインド人からも奇異な目で見られる。
どうやらもうそんな心配もしなくてよくなりそうだ。
2001年7月末から始まったインド留学だが、ケーンドリーヤ・ヒンディー・サンスターン(中央ヒンディー語学院)での2年の語学留学、ジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)での博士課程前期(M.A.)の2年、中期(M.Phil.)の2年、後期(Ph.D.)の5年を経て、今年1月末までに博士論文の審査も完了する見込みとなり、2月中には学位証明書が手に入る目処が付いた。元々ヴィザが2月いっぱいで失効するため、それまでに完全帰国する予定だったが、その通りになりそうだ。2月末にインドを発つことで、合計11年7ヶ月間インドに滞在したことになるだろう。
かなり前から、インドを去るときはどんな気持ちになるだろう、泣いてしまうだろうか、憂鬱になってしまうだろうか、といろいろ勝手に想像を膨らませていたのだが、いざそのときを前にすると、意外に清々した気分であることに気付く。インドは好きだし、デリーはもっと好きなので、この住み慣れた土地を去ることは確かに寂しい。だが、JNUでのコースを一通り終えたことで、JNUの寮に住めなくなることも心にかなりの影響を与えている。緑豊かなJNUキャンパスを去ってデリーのどこかの住宅地に引っ越し、何らかのヴィザを取得してデリーにしつこく住み続けることはあまり考えられない。グルガーオンを含むデリー以外の都市に住むことはもっと考えられない。JNUに住み始めたときから、JNUを去るときがデリーを、そしてインドを去るときだと考えていた。JNUの住環境は、おそらく在インド日本大使でも享受できないほど贅沢なものだった。それを失うならば、もうここに長居する意味はない。

JNUの朝
「これでインディア」は、筆者がインドに住んでいるからこそ成立したウェブサイトであり、帰国後は現在のような形で続行できなくなることは確実である。僕が「これでインディア」を始めたときには、インドからリアルタイムでインドの情報を日本語で発信することは革新的な試みであった。何しろ2001年には自宅でインターネットをすることもままならなかったのだ。だが、この間、少なくともデリーではインターネット・インフラが劇的に改善され、ブログ、mixi、Twitter、Facebookなどの登場により、一般人が容易に世界に向けて情報を発信できるようになった。それに伴い、「これでインディア」の試みも革新性を失い、その価値も激減した。この辺りで潔く引退してもいいのではないかと思うようになった。それにしても、11年以上コンスタントな更新と共に続いた個人運営のウェブサイトというのは割と珍しいのではないかと思う。
デリーに住む日本人の質も変わって来た。駐在員を除けば、かつてインドに長くいる日本人は、本当にインドが好きな人ばかりであった。だが、インドの経済成長が世界中の注目を浴びるようになって以来、必ずしもインドが好きであることがインド滞在の主な動機となっていない人が増えて来た。そのおかげで、僕は古い世代の人間となりつつあると感じるようになった。2000年代半ばくらいまでは、インドに来る日本人は大体「これでインディア」のことを知っていたのだが、2010年前後から必ずしもそういうことはなくなって来た。手前味噌ではあるが、インドのことに興味があって何らかのキーワードをインターネットで検索すれば、大体どこかで「これでインディア」の記事がヒットするものだ。しかし、最近インドに来る人は、インドのことにあまり深い興味がないままインドに来るのかもしれない。新たな種類の人間が増え、コミュニティーが多様化することは歓迎すべきだが、どちらかというとデリーの日本人コミュニティーが日本人社会化して来ており、人間関係が日本とそんなに変わらなくなりつつあるように感じる。そういう意味でも潮時だと感じた。
少し心配なのは、ヒンディー語映画を現地でリアルタイムで見て紹介する情報源がひとつ減ってしまうことである。「これでインディア」の映画評が果たしてどこまでヒンディー語映画の普及に貢献したのか、数値的なデータは当然出て来ないのだが、聞くところによると、少なくともインド在住の日本人には映画鑑賞の際に大いに参考にしてもらっているようである。それが突然なくなると、ますます日本人にとってヒンディー語映画が遠い存在になってしまわないかと勝手に不安になる。盟友のポポッポーさんがポポッポーのお気楽インド映画を続けて行ってくれることを祈るばかりだ。ちなみに、「映画館で見ていない映画は批評の対象にしない」という鉄のポリシーを持っているため、日本に帰国後、DVD、TV、YouTubeなどでヒンディー語映画を見て批評をすることはない。しかし、日本に帰ったら、しばらくはヒンディー語映画が夢に出てきそうだ。
インドに10年以上滞在してやり残したことはないかと聞かれれば、「ある」と答えざるを得ない。時間は無駄にしなかったと胸を張りたいところだが、ここに来て過ぎ去ったこの巨大な時間を「別のことに使っていれば・・・」という妄想も頭をもたげて来る――何かのインド楽器を習っていれば今頃プロ並みになっていたのでは・・・、ヒンディー語以外の言語も勉強しておけばよかった・・・、ムンバイーに住んでいれば映画界にもっと食い込めたかもしれない・・・、などなど。これだけ長く住んだにも関わらず、インド国内にまだまだ訪れたことのない場所があるのも悔しい限りだ(このトピックについては後にまとめようと思う)。しかし、時間の針を戻すことはできないし、今後そのような機会が得られるとも思われない。
一番の救いは、20代という人生でもっとも貴重な時間をインドで無駄なく過ごすことができたという自負心があることだ。30代も半ばとなり、インドを去る今となって、「インドは若い内に行け」という言葉の意味が実感されて来る。インドはいつ行っても意味のある場所ではあるが、感受性の強い20代にこの土地を踏みしめ、そして空気を吸い続けることができたのは、この上ない幸せだった。若いときにはエネルギッシュな環境で過ごすべきだ。インドはそれを存分に提供してくれた。一方、インド滞在中、日本からは暗いニュースばかりが舞い込んで来ていた。そういう時期に日本で暮らさなくて良かった。また、もし30代でインドに来ていたら、インドの見え方はかなり変わっていたことだろうとも思う。何が正しいか、何が良いか、ということはないのだが、20代のときに見えるインドの姿は決して無視できないと信じている。
全てが過ぎ去った後に思えば、インドは僕が望んだものを全て与えてくれたようにも感じる。この地に足を踏み入れたときには1人だったが、今では4人で日本に帰ろうとしている。そして多くの友人たちが、僕の去った後も僕の帰りを待っていてくれるだろう。インドは常に訪れる者を1人にしてくれない国だ。そして去る者も1人にしない、決して手ぶらにしない。「Dilli-6」(2009年)の中の挿入歌「Arziyaan」の一節が脳裏に浮かんで来る。
सर उठाके मैंने कितनी ख़्वाहिशें की थीं
कितने ख़्वाब देखे थे कितनी कोशिशें की थीं
जब तू रू-ब-रू आया नज़रें न मिला पाया
सर झुकाके एक पल में मैंने क्या नहीं पाया
頭を上げてどれだけ願い事をしたことか
どれだけ夢を見たことか、どれだけ努力をしたことか
いざあなたが目の前に現れたとき、目を合わせられなかった
頭を下げたら一瞬の内に願い事が叶わなかったことはなかった
と言う訳で、筆者の帰国により、「これでインディア」が日記の形で更新されて行くことは3月以降なくなると思っていただいて間違いない。だが、ウェブサイト自体はこのまま残ると思うし、まとめ的な更新は時々するかもしれない。その事前報告を新年の挨拶と代えさせていただきたい。謹賀新年!

今年の年賀状に使った家族写真
| ◆ |
1月11日(金) Matru Ki Bijlee Ka Mandola |
◆ |
1月に入ってからデリーは記録的な寒波に襲われ、11年以上デリーに住んだ中でも稀に見る寒さを体験した。その寒さの中で外出や会合が続いたせいか、我が家は大人も子供も次々と風邪に見舞われてダウンして行った。ようやく寒さも病気も峠を越し、映画を見るような余裕もできた。
さて、近年のヒンディー語映画界の新しい潮流の中で、ヴィシャール・バールドワージ監督は間違いなくその中心にいる人物である。シェークスピア作品を翻案した「Maqbool」(2003年)や「Omkara」(2006年)、子供向け映画「Makdee」(Makdee)や「The
Blue Umbrella」(2005年)、ラスキン・ボンド原作の「7 Khoon Maaf」(2011年)、言語障害のある双子を主人公に据えた「Kaminey」(2009年)など、常に変わった映画を撮り続けており、ヒンディー語映画のフロンティアを開拓している。そんなバールドワージ監督の最新作「Matru
Ki Bijlee Ka Mandola」が本日公開となった。今年最初の期待作となる。今回バールドワージ監督は初めてコメディーに挑戦とのことだが、単なるドンチャン騒ぎのコメディー映画ではなく、やはり彼らしいユニークな作品となっていた。
主演はイムラーン・カーン、アヌシュカー・シャルマー、パンカジ・カプールの3人。若手世代を代表するイムラーンとアヌシュカーは今回初共演。他にシャバーナー・アーズミーも出ている。バールドワージ監督は元々音楽監督として映画界に入った人物であり、音楽も自分の手で手掛けている。作詞は盟友のグルザール。題名からして興味をそそられる作品である。
題名:Matru Ki Bijlee Ka Mandola
読み:マトルー・キ・ビジュリー・カ・マンドーラー
意味:マトルーのビジュリーのマンドーラー
邦題:マトルーのビジュリーのマンドーラー
監督:ヴィシャール・バールドワージ
制作:ヴィシャール・バールドワージ、クマール・マンガト・パータク
音楽:ヴィシャール・バールドワージ
歌詞:グルザール
振付:サロージ・カーン、ボスコ・シーザー
衣装:パーヤル・サルージャー
出演:イムラーン・カーン、アヌシュカー・シャルマー、パンカジ・カプール、シャバーナー・アーズミー、アーリヤ・バッバル
備考:DTスター・プロミナード・ヴァサント・クンジで鑑賞。

左からイムラーン・カーン、アヌシュカー・シャルマー、パンカジ・カプール
| あらすじ |
ハリヤーナー州マンドーラー村。地主のハリー・マンドーラー(パンカジ・カプール)は重度のアルコール中毒で、酒を飲むと人格が全く変わってしまう。彼のお気に入りはグラーボーという地酒だった。最近雇った運転手フクム・スィン・マトルー(イムラーン・カーン)と共に、ドライデー(禁酒日)に酒屋にリムジンで突入するなど、酒に渇したときの行動力は異常であった。マンドーラーは禁酒をするが、禁断症状でピンクの牛の幻覚を見るようになり、すぐにまた飲んでしまうのだった。
ところでマンドーラーは村の農地を経済特区(SEZ)にする夢を抱いていた。そのために娘のビジュリー(アヌシュカー・シャルマー)を、地元政治家チャウダリー・デーヴィー(シャバーナー・アーズミー)の息子バーダル(アーリヤ・バッバル)と結婚させようとしていた。ビジュリーはデリーやロンドンで勉強して来た才女で、マトルーとビジュリーは幼馴染みであった。
しかし、村では「マオ」と名乗る謎の人物が、農民たちに、政府に土地を売り渡さないように警告していた。そのおかげで土地買収がスムーズに進んでいなかった。また、チャウダリー・デーヴィーが現地視察に来て見てみると、SEZ建設予定地は、荒れ地と聞いていたのに一面小麦畑となっていた。これでは土地買収により多くの補償金を支払わなくてはならなくなる。だが、チャウダリー・デーヴィーも自分の選挙区にSEZを建設し、政治力を増すと同時に結婚によってその莫大な利益を手中に収めようと考えており、どうしても土地買収は成功させなければならなかった。
そこでバーダルは、過剰に散布すると作物を枯らしてしまう農薬を使って小麦畑を壊滅させようとする。だが、マオに主導された農民たちによってその計画は阻止されてしまう。バーダルは何とかマオの正体を突き止めようと深夜集会に潜入するが失敗する。だが、実はマオはマトルーであった。マトルーは左翼勢力の強いジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)を卒業した青年活動家で、マンドーラーの運転手を装いながら、出身の村の運動を密かに率いていたのだった。
小麦が収穫の時期を迎えた。マンドーラー村の農民たちは市場で作物を売ろうとするが、当局の邪魔が入り、誰も買い手が付かなかった。作物を売って借金を返さなければ、農地は差し押さえられてしまう。そこでマトルーはデリーまで出向き、食料会社シャクティボーグを経営する大学時代の旧友にマンドーラー村の小麦を買い取るように頼む。旧友もそれを快諾する。前金を受け取った農民たちは借金を返済することが可能となる。
農民たちが資金を手に入れたニュースはチャウダリー・デーヴィーやマンドーラーの耳にも届いた。マンドーラーは、今後一切酒は飲まないと誓う。すると途端に豪雨が降り出し、作物が全て水浸しになってしまう。こうして農民たちは土地を売らざるを得なくなってしまう。マトルーの敗北であった。
また、バーダルとビジュリーの結婚式の準備が進められていた。マトルーはデリーに帰ろうとするが、このときまでにビジュリーとの間には恋愛関係が芽生えていた。マトルーはビジュリーの結婚を止めようと画策し、村中の牛をピンク色に塗って結婚式に忍び込ませる。式場でマンドーラーはピンクの牛を見て慌てふためくが、決して酒に触れようとはしなかった。一方、ビジュリーはマトルーと結婚できない悲しみから酒を飲み酔っ払ってしまう。彼女は酩酊状態のままマンダプ(結婚の儀式が行われる壇上)に上がる。聖火の回りを7回回る儀式はなかなか進まなかった。
マンドーラーはまだSEZの契約書にサインをしていなかった。冷静に考えた結果、彼はSEZ建設案を破棄することにし、ピンクの牛に乗って式場に殴り込んでチャウダリー・デーヴィーたちを追い出す。そしてビジュリーをマトルーと結婚させる。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
コメディー映画を銘打っており、確かにブラックコメディーとして秀逸ではあるが、決して単に笑っておしまいの作品ではない。現在インドが直面する「発展」や「開発」の問題を農民の視点に立って描いた作品だ。その点では「Shanghai」(2012年)のテーマとも似通っているのだが、意外なことにコメディータッチで描いたこの「Matru
Ki Bijlee Ka Mandola」の方が「発展」の実態をより明確にしていた。「発展」の名の下に農民たちから農地が奪われて行くが、それは政治家の野心や富豪の金儲けのためであり、決して貧者救済や国家発展のためではない。一方で農民にとって土地は魂であり、農地を失った農民は尊厳をも失う。そして急速にインフレが進むインドにおいて彼らは社会・経済の弱者・貧者に位置づけられ、一生底辺の生活を送ることになる。それを防ぐため、政府に土地を売却しないようにと農民たちに呼び掛ける活動家たちが活躍する。西ベンガル州シングルのターター・ナノ工場建設予定地、ウッタル・プラデーシュ州のヤムナー・エクスプレスウェイ沿線の土地など、この構造の対立は過去にいくつも起こって来た。「Matu
Ki Bijlee Ka Mandola」の舞台はハリヤーナー州であるが、首都デリーに近いこともあり、あちこちで農地が工業団地や住宅地にされている。マーネーサルのスズキ工場で起こった暴動も、この問題と無関係ではない。あまりにも性急な「発展」が社会に大きな歪みをもたらしている。「Matru
Ki Bijlee Ka Mandola」はそれに警鐘を鳴らす真剣な作品であった。
農村は近年のヒンディー語映画のトレンドである。ヴィシャール・バールドワージ監督はそのトレンドセッターの1人だと言っていい。「Maqbool」や「Omkara」などで農村を舞台にし、土臭い作品を作り上げた。だが、今回彼が新たに提示したのは、都市部や海外で教育を受けた若者が生まれ故郷の農村に帰って来て、その村のために献身する様子である。もちろん「Swades」(2004年)で既にそれはあったのだが、より政治的かつ自然な形で提示できていたと思う。マトルーはデリーのJNUで左翼思想の洗礼を受け、自分の村がSEZに呑み込まれないように密かに戦う。「マオ」を名乗って農民を組織し、農地を強制的に接収しようとする政府に立ち向かわせる。一方、地主の娘ビジュリーはデリーとロンドンで学んで来ており、典型的な「村娘」ではない。彼女の立場は複雑だが、曲がったことが大嫌いな性格であり、農民たちを騙し討ちにして土地をせしめようとする動きが出て来たところで彼女は農民たちの側に回る。今までの農村映画ではあまり見られなかったキャラクターであり、ヒンディー語映画の前進を感じさせられた。
バールドワージ監督の映画の言語は非常に写実的なことが多い。この映画でも基本はハリヤーンヴィー語であり、かなり癖がある。特にパンカジ・カプール演じるマンドーラーのしゃべる言葉はほとんど聴き取れない。ハリヤーナー州の人々(農民には「ジャート」と呼ばれるコミュニティーが多い)はかなり粗雑なしゃべり方をすることで知られている。罵詈雑言に分類される言葉を平気で交ぜて話すのだ。だが、その中に不思議なユーモアもあったりして、バールドワージ監督はそれを映画の中で再現することに苦心したようである。その点パンカジ・カプールは本当にうまい。まるで本物のジャートのようだ。イムラーン・カーンも現地に滞在して彼らの言動を学んだようで、いつもの洗練された身のこなし方ではなかった。叔父のアーミル・カーンに似た演技力である。
個人的にもっとも感心したシーンは、マトルーがデリーまで行って作物を売ろうとするところである。彼は大学時代のコネを使って、食品会社の女性経営者に直談判する。詳しく描写されていないのだが、その女性はおそらくマトルーの大学時代の恋人かそれに近い関係の人物であろう。JNUはインドでトップの教育機関であると同時に左翼の牙城であり、マトルーのように革命を志す左翼活動家として地下活動をする卒業生もいれば、政治家になったり実業家になったりして表舞台で活躍する卒業生もいる。だが、どんな人生を歩もうともJNUの仲間は仲間であり、そのコネが後々まで生きて来る。また、たとえ左翼のイデオロギーとは全く逆方向の道を歩むことになっても、心のどこかでJNU時代に育まれた左翼的思想が残っており、機会があればそれに協力したくなってしまう。そんなJNUのセンチメントをうまく捉えていたように思える。また、農民たちに裏切られ敗北したマトルーが、デリーに帰って大学で教えようとするところもJNUの卒業生らしい進路である。
主演イムラーン・カーン、アヌシュカー・シャルマー、パンカジ・カプールの演技は一級であった。特に酔っ払ったときのマンドーラーを演じるパンカジ・カプールは絶品だ。加えてシャバーナー・アーズミーも「Makdee」などを思わせるエキセントリックな演技。バーダルを演じたアーリヤ・バッバルはラージ・バッバルの息子で、プラティーク・バッバルの異母弟になる。
音楽はヴィシャール・バールドワージ、歌詞はグルザール。ハリヤーナー州の田舎の雰囲気がよく出た音楽と歌詞である。いくつかは民謡のようだ。しかも突然アフリカ音楽「Nomvula」がある。これはストーリー中にもアフリカ人のダンサーが出て来て踊っているからであるが、その荒技を平然とやってのけてしまうところがバールドワージ監督の凄いところだ。昨今のアンチ汚職政治家・官僚・警察ムードを反映した歌「Chor
Police」もあれば、農民応援歌のような「Lootnewale」もある。非常に多様なサントラとなっており、出色の出来だ。
「Matru Ki Bijlee Ka Mandola」は、ブラックコメディーに分類される映画であるが、それよりもむしろその内容のシリアスさ・切実さに圧倒される作品だ。「Shanghai」でもっとクローズアップして欲しかった「発展」の裏側がこの映画でよく取り上げられており、考えさせられる。日本企業もハリヤーナー州を初めとしてインドにおいてこの映画のような状況を作り出しているので、日本人も無関係なテーマではない。ただ、言語は非常に写実的なハリヤーンヴィー方言で、聴き取り超困難である。ヒンディー語ができる人でも字幕と共に鑑賞することをおすすめする。
| ◆ |
1月13日(日) 2012年ボリウッド映画界を振り返る |
◆ |
ヒンディー語映画業界でもっとも歴史と権威のある映画賞フィルムフェア賞の2012年ノミネート作品が発表された。フィルムフェア賞のノミネート作品を土台にしてその年のヒンディー語映画の動向を振り返るのが「これでインディア」での長年の慣習であり、最後となるであろう今回もそれを踏襲する。
まず、2012年はヒンディー語映画界にとって当たり年であった。スター出演大予算型映画が軒並み大ヒットした一方で、高品質な低予算映画も多く作られ、そして期待以上の興行成績を上げた。つまり、非常に理想的な年だったと言える。
まず主に大予算型娯楽映画の方から見ていこう。一番の稼ぎ頭は何と言ってもサルマーン・カーンだ。2009年からヒット作を量産して来たサルマーン・カーンだが、2012年に入ってもその勢いが止まらず、彼の出演作2本――「Ek
Tha Tiger」と「Dabangg 2」――はどちらも「100カロール・クラブ」(参照)に入る大ヒットとなった。「Ek Tha Tiger」の国内興行収入は19億ルピーにまで達しており、年末に公開された「Dabangg 2」も1週間で早々に10億ルピーを越した。大衆向けアクションコメディーをメインフィールドに据えてからのサルマーン・カーンは業界でもっとも稼げる俳優となっており、3カーンの中で突出している。また、今年の彼の出演作は、大ヒットしただけでなく、どちらもよくまとまった娯楽作になっており、決して興行先行ではないのも特筆すべきである。
サルマーン・カーンと同じくらい元気なのがアクシャイ・クマールである。サルマーン・カーンと入れ替わりで2009年から不振が続いた彼にとって2012年は起死回生の年となり、出演作5本――「Housefull
2」、「Rowdy Rathore」、「Joker」、「OMG Oh My God!」、「Khiladi 786」――の内「Joker」を除く4本がヒットとなった。特に「Rowdy
Rathore」は14億ルピーの国内興行収入を上げる大ヒットとなっており、完全に息を吹き返した印象である。ただ、今年最大の失敗作のひとつ「Joker」に主演してしまったことで、まだ出演作のチョイスに危うさも残る。
3カーンの2人シャールク・カーンとアーミル・カーンにとって2012年は静かめの年であった。シャールク・カーンは同年、ヤシュ・チョープラー監督の遺作「Jab
Tak Hai Jaan」にのみ出演。現代ヒンディー語娯楽映画のフォーマットを作り上げたヤシュ・チョープラーらしい王道ロマンスで、12億ルピーの興行収入を上げた。一方、アーミル・カーンは優れたサスペンス映画「Talaash」に出演。「Dhobi
Ghat」(2011年)以来およそ2年振りの銀幕登場となった。10億ルピーには達していないようだが、間違いなく2012年の傑作の1本である。
アジャイ・デーヴガンもここのところ調子が良い。2012年は「Bol Bachchan」と「Son of Sardar」をヒットさせた。どちらも国内興行収入10億ルピーを越えている。ただ、年初公開の主演作「Tezz」はフロップに終わっている。アジャイ・デーヴガンもサルマーン・カーンと同様にアクションコメディーを得意とするようになっており、ど派手なアクションを売りとするローヒト・シェッティー監督とのコンビもうまく行っている。
他にもリティク・ローシャン主演「Agneepath」、サイフ・アリー・カーン主演「Cocktail」、ランビール・カプール主演「Barfi!」などが10億ルピーを突破するヒットとなっている。どれもそれぞれ優れた点のある映画で、ヒットも納得できる。他にスター出演の映画と言えば、イムラーン・ハーシュミー主演の2作「Jannat
2」と「Shanghai」がヒットに分類されている。イムラーン・ハーシュミーは「Shanghai」での演技が高く評価されており、今後表現の幅を広げて行くことが期待される。
大まかに言って、2012年はヒットすべき映画がヒットした理想的な年であった。2012年公開作の中で大失敗作――つまり莫大な予算をつぎ込んだにも関わらずヒットしなかった作品――に数えられたのは、アビシェーク・バッチャン主演「Players」とアクシャイ・クマール主演「Joker」の2本のみだったとされている。「Players」のアッバース・マスターン監督はチープなサスペンスで一世を風靡した監督デュオで、個人的には好きな映画監督であるのだが、もう時代の流れに付いて行けなくなっているかもしれない。一方、「Joker」のシリーシュ・クンダル監督は無能なので彼の映画は今後も失敗し続けるだろう。他に、マドゥル・バンダールカル監督カリーナー・カプール主演「Heroine」、シャーヒド・カプールとプリヤンカー・チョープラー主演「Teri
Meri Kahaani」、プラカーシュ・ジャー監督「Chakravyuh」、サイフ・アリー・カーン主演「Agent Vinod」などが意外に不振だった映画として挙げられる。
人気スターが出演し、莫大な予算を投入した映画が軒並み大成功した一方で、低予算映画も元気が良かったのが2012年の最大の特徴だ。イルファーン・カーン主演の伝記映画「Paan
Singh Tomar」、ヴィディヤー・バーラン主演のサスペンス「Kahaani」、精子ドナーを主人公にした「Vicky Donor」など、2012年前半には低予算ながら良作が続き、興行的にも成功した。また、アヌラーグ・カシヤプ監督の野心作「Gangs
of Wasseypur」が2部に分けられて公開され、「インドのゴッドファーザー」として大きな話題となった。マノージ・パージペーイーやナワーズッディーン・スィッディーキーの他に、強烈な女性キャラも魅力だった。
新人・若手俳優の検討も目立った。アルジュン・カプールとパリニーティ・チョープラー主演「Ishaqzaade」はヒットとなり、カラン・ジャウハル監督がスィッダールト・マロートラー、アーリヤー・バット、ヴァルン・ダワンなど新人を起用して作った「Student
of the Year」もセミヒットとなった。前述の「Vicky Donor」もアーユーシュマン・クラーナーという全くの新人を主演に据えながら、テーマと脚本の良さからスーパーヒットとなった。新人とは言えないものの、往年の名女優シュリーデーヴィーのカムバック作品「English
Vinglish」も高い評価を受け、都市部を中心に人気を博した。
総じて、これら非メインストリーム映画が目新しいテーマに果敢に挑戦し、観客もそれを好んで見たことで、ヒンディー語映画はこの1年で金銭的だけでなく内容的にもかなりリッチになったと言える。陸上競技選手から盗賊になった男、行方不明の夫を捜す妊婦、精子ドナー、英語を習う主婦などなど、変わった職業やバックグランドの主人公たちや、マオイスト問題に果敢に切り込んだ「Chakravyuh」、宗教ビジネスの問題点を巧みに取り上げた「OMG
Oh My God!」などが映画界を彩ってくれた。
また、PVRディレクターズ・カットのイニシアチブのおかげで、従来は映画館で全く公開されることのなかったような種類の芸術映画・ドキュメンタリー映画が、少ない上映回数ではあるが、一般公開されるようになったことも2012年の重要な出来事であった。そのおかげで僕は「Superman
of Malegaon」や「Kshay」などと言ったニッチな映画を見ることができた。この方面の動きも是非続けて行ってもらいたいものだ。できることならPVRディレクターズ・カットの料金をもっと安くして欲しい・・・。
ジャンル別に見ると、アクション映画の強さが際立っている。興行収入トップ4――「Ek Tha Tiger」、「Dabangg 2」、「Rowdy
Rathore」、「Agneepath」――はアクション映画で占められている。かつてヒンディー語映画界ではまともなアクション映画がほとんどなくなってしまった時代もあったのだが、「Ghajini」(2008年)辺りからアクション映画への回帰が進み、現在のような状況となっている。このトレンドは今後もしばらく続きそうだ。
2012年、ロマンス映画はいくつかあったが、ボーイ・ミーツ・ガール的な単純なロマンス映画はだいぶ減ってしまったと感じる。代わってロマンス+アルファの映画が増えた。ヤシュ・チョープラー監督の「Jab
Tak Hai Jaan」は王道ロマンスとして存在感を放っているものの、そのスケールの大きさは通常のロマンス映画にカテゴライズすることを躊躇させる。聾唖者を主人公にした「Barfi!」も究極の愛を描いたロマンス映画であるが、決してロマンスだけの映画ではない。伝統的な三角関係を描いた「Cocktail」にしても、その提示の仕方はだいぶ現代的であった。「Student
of the Year」は一応ロマンス映画と言えるだろうが、学園モノとした方がより座りがいい。「Ishaqzaade」もロミオとジュリエット的なロマンス映画であるが、極端にバイオレントな展開だ。大人の恋愛と言えば「English
Vinglish」が筆頭だ。恋の上澄み液のような展開が非常に心地よい。これらの映画を見ると、ヒンディー語映画はロマンスをかなり多様に描くようになったと言える。
ヒンディー語映画界は昔から優れたスリラー映画を作って来ていたが、どうしてもスリラー映画の限界もあった。スリラー映画というのは鑑賞しているときのハラハラ感が一番の売りであって、インド映画が特に世界に向けて提示できるような新しい要素はなかなか見出せない。よって、日本人に特に紹介したいと思わせられるような映画はほとんどなかった。しかし2012年には「Kahaani」と「Talaash」という優れたスリラー映画が登場し、ヒンディー語映画のこのジャンルもようやく国際的なアピールを持ったと評価できるようになった。どちらも胸を張って勧められるインド製スリラー映画の傑作だ。
一方、コメディー映画には特に見るべきものがなかった年であった。もちろん、「Housefull 2」や「Bol Bachchan」のような大ヒットしたコメディー映画はあった訳だが、このジャンルの進化を感じさせるようなものではなかった。むしろ「Vicky
Donor」のような低予算型コメディー映画の方が見るべき価値がある。
2012年は、強力な女性キャラが多く誕生した年でもあった。「Kahaani」のヴィディヤー、「Vicky Donor」のミセス・アローラー(母親)とビージー(祖母)、「Ishaqzaade」のゾーヤー、「Cocktail」のヴェロニカなど、強烈な女性キャラが映画を牽引した。従来の主婦のイメージを踏襲しながらも、「English
Vinglish」のシャシが苦手な英語を克服するために努力する姿は十分魅力的だったし、「Aiyyaa」は少女漫画的な作品でミーナークシーの少女らしい妄想を主軸とした映画だった。しかし、もっとも異質な女性キャラを提示していたのは「Gangs
of Wasseypur」だ。ギャングの抗争を描いた作品は男臭くなるのが常で、女性キャラは添え物に過ぎないことが多い。だが、「Gangs of
Wasseypur」に登場するナグマー、ドゥルガー、モホスィナーなどの女性キャラは皆とても個性的かつ強烈で、今までのヒンディー語映画ではちょっと見られなかった種類の性格である。
さて、フィルムフェア賞ノミネート作品は以下の通りである。まずはノミネート作品をざっとリストアップし、その後、作品賞と監督賞、主演男優賞と助演男優賞、主演女優賞と助演女優賞、音楽関係の賞の順でまとめて見てみることにする。
作品賞
- Barfi!
- English Vinglish
- Gangs of Wasseypur
- Kahaani
- Vicky Donor
監督賞
- アヌラーグ・バス 「Barfi!」
- アヌラーグ・カシヤプ 「Gangs of Wasseypur」
- ガウリー・シンデー 「English Vinglish」
- シュジート・サルカール 「Vicky Donor」
- スジョイ・ゴーシュ 「Kahaani」
主演男優賞
- リティク・ローシャン 「Agneepath」
- イルファーン・カーン 「Paan Singh Tomar」
- マノージ・バージペーイー 「Gangs of Wasseypur」
- ランビール・カプール 「Barfi!」
- サルマーン・カーン 「Dabangg 2」
- シャールク・カーン 「Jab Tak Hai Jaan」
主演女優賞
- ディーピカー・パードゥコーン 「Cocktail」
- カリーナー・カプール 「Heroine」
- パリニーティ・チョープラー 「Ishaqzaade」
- プリヤンカー・チョープラー 「Barfi!」
- シュリーデーヴィー 「English Vinglish」
- ヴィディヤー・バーラン 「Kahaani」
助演男優賞
- アクシャイ・クマール 「OMG Oh My God!」
- アンヌー・カプール 「Vicky Donor」
- イムラーン・ハーシュミー 「Shanghai」
- ナワーズッディーン・スィッディーキー 「Talaash」
- リシ・カプール 「Agneepath」
助演女優賞
- アヌシュカー・シャルマー 「Jab Tak Hai Jaan」
- フマー・クレーシー 「Gangs of Wasseypur」
- イリアナ・デクルーズ 「Barfi!」
- ラーニー・ムカルジー 「Talaash」
- リチャー・チャッダー 「Gangs of Wasseypur」
音楽監督賞
- アミト・トリヴェーディー 「Ishaqzaade」
- プリータム 「Barfi!」
- プリータム 「Cocktail」
- スネーハー・カンワルカル 「Gangs of Wasseypur」
- ヴィシャール・シェーカル 「Student of the Year」
作詞家賞
- アミターブ・バッチャーチャーリヤ Abhi Mujh Mein Kahin 「Agneepath」
- グルザール Challa 「Jab Tak Hai Jaan」
- グルザール Saans 「Jab Tak Hai Jaan」
- ジャーヴェード・アクタル Jee Le Zara 「Talaash」
- スワーナンド・キルキレー Aashiyan 「Barfi!」
男性プレイバックシンガー賞
- アーユーシュマン・クラーナー Pani Da Rang 「Vicky Donor」
- モーヒト・チャウハーン Ala Barfi 「Barfi!」
- ニキル・ポール・ジョージ Main Kya Karoon 「Barfi!」
- ラッビー Challa 「Jab Tak Hai Jaan」
- ソーヌー・ニガム Abhi Mujh Mein Kahin 「Agneepath」
女性プレイバックシンガー賞
- カヴィター・セート Tumhi Ho Bandhu 「Cocktail」
- ニーティ・モーハン Jiya Re 「Jab Tak Hai Jaan」
- シャルマリー・コールガデー Pareshaan 「Ishaqzaade」
- シュレーヤー・ゴーシャール Saans 「Jab Tak Hai Jaan」
- シュレーヤー・ゴーシャール Chikni Chameli 「Agneepath」
作品賞と監督賞は重複することが多いので一緒に話をした方がいい。やはり今回も作品賞のノミネート作品と監督賞にノミネートした監督の作品は全く重なっている。「Barfi!」、「English
Vinglish」、「Gangs of Wasseypur」、「Kahaani」、「Vicky Donor」の5作品である。どれも2012年を代表する高品質の映画である。「Barfi!」は本年度のアカデミー賞外国語映画賞のインドからの公式エントリー作品となっており、作品賞か監督賞を受賞することは確実だ。もし別の映画がどちらかに食い込むならば、「Gangs
of Wasseypur」がもっともふさわしいと感じる。今年もっとも衝撃的な映画であった。
主演男優賞は「Dabangg 2」のサルマーン・カーン以外は誰でも受賞する可能性があるが、やはり強いのは「Jab Tak Hai Jaan」のシャールク・カーンであろうか?対抗馬は「Barfi!」のランビール・カプールになるだろう。「Paan
Singh Tomar」のイルファーン・カーンが受賞してくれると個人的に嬉しいが。助演男優賞は、正当に評価するならば「Talaash」のナワーズッディーン・スィッディーキーが最有力だ。今もっとも乗っている男優であり、彼の出演作は必ず見てみたくなるような魅力を持っている。しかし、スターパワーで「OMG
Oh My God!」のアクシャイ・クマールにさらわれることになるだろうか。「Vicky Donor」のアンヌー・カプールも十分受賞に値する助演振りだった。
主演女優賞は「Kahaani」のヴィディヤー・バーランと「Barfi!」のプリヤンカー・チョープラーの一騎打ちになるだろうが、前者は完全に映画を背負って立つ正真正銘の主演を演じており、有利だ。「English
Vinglish」のシュリーデーヴィーも良かったが、ここは若い女優に道を譲るべきであろう。と言っても「Ishaqzaade」のパリニーティ・チョープラーはまだ若すぎるので、もう少し待つことを余儀なくされるだろう。助演女優賞はさらに明確だ。「Gangs
of Wasseypur」のリチャー・チャッダーが受賞すべきである。彼女が演じた肝っ玉母ちゃん役は、浮気に走る旦那を「私に恥かかせんじゃないよ!」と送り出す異例のキャラであった。
音楽関係で挙がっている映画を列挙してみると、「Agneepath」、「Barfi!」、「Cocktail」、「Gangs of Wasseypur」、「Ishaqzaade」、「Jab
Tak Hai Jaan」、「Student of the Year」、「Talaash」、「Vicky Donor」の9作品である。音楽監督賞で「Jab
Tak Hai Jaan」のARレヘマーンがノミネートを逃しているのが意外だが、後は順当なノミネートだと言える。個人的に好きなのは「Barfi!」、「Cocktail」、「Gangs
of Wasseypur」、「Jab Tak Hai Jaan」の4作品である。女性音楽監督スネーハー・カンワルカルの台頭は2012年のひとつの事件だと表現していいだろう。今一番楽しみな音楽監督であり、彼女の「Gangs
of Wasseypur」は斬新なメロディーで満ち溢れていた。それでも、音楽監督賞は「Barfi!」のプリータムが、作詞家賞は「Jab Tak
Hai Jaan」でWノミネートしているグルザールが「Saans」で受賞しそうだ。プレイバックシンガー賞の方はインド人の趣味を予想するのが難しいのだが、「Barfi!」の「Main
Kya Karoon」を歌ったニキル・ポール・ジョージと「Cocktail」の「Tumhi Ho Bandhu」を歌ったカヴィター・セートが受賞すると僕の趣味にもっとも近くなる。
さて、毎年アルカカット賞なるものを勝手に決めている。ほとんど話題に上らなかったが優れた映画に送られる賞である。2012年は博士論文提出や長期旅行などで細かい映画を満遍なく見ることができなかったのだが、その中でアルカカット賞にふさわしいのは「Delhi
in a Day」であった。超低予算ながら、インド社会の歪んだ構造を浮き彫りにしており、唸らされた。
■1月20日にフィルムフェア賞が発表された。作品賞は「Barfi!」、監督賞は「Kahaani」のスジョイ・ゴーシュ、主演男優賞は「Barfi!」のランビール・カプール、主演女優賞は「Kahaani」のヴィディヤー・バーラン、助演男優賞は「Vicky
Donor」のアンヌー・カプール、助演女優賞は「Jab Tak Hai Jaan」のアヌシュカー・シャルマー、音楽監督賞は「Barfi!」のプリータム、作詞家賞は「Jab
Tak Hai Jaan」の「Challa」でグルザール、男性プレイバックシンガー賞は「Vicky Donor」の「Paani Da Rang」でアーユーシュマン・クラーナー、女性プレイバックシンガー賞は「Ishaqzaade」の「Pareshaan」でシャルマリー・コールガデー。それとは別に批評家賞として「Gangs
of Wasseypur」が作品賞、「Paan Singh Tomar」のイルファーン・カーンが主演男優賞、「Gangs of Wasseypur」のリチャー・チャッダーが主演女優賞を受賞した。また、新人男優賞は「Vicky
Donor」のアーユーシュマン・クラーナー、新人女優賞は「Barfi!」のイリアナ・デクルーズ、新人監督賞は「English Vinglish」のガウリー・シンデー、台詞賞は「Gangs
of Wasseypur」のアヌラーグ・カシヤプなど、脚本賞は「Paan Singh Tomar」のサンジャイ・チャウハーンとティグマーンシュ・ドゥーリヤー、ストーリー賞は「Vicky
Donor」のジューヒー・チャトゥルヴェーディーなどとなっている。概してバランスの取れた配分となっているが、助演男優賞だけは意外であった。2012年にもっとも頭角を現わしたナワーズッディーン・スィッディーキーが何も受賞せず冷遇されており、助演男優賞くらいはあげたかった。
11年以上インドで過ごして来たため、インドはかなり隅々まで旅行したのだが、それでもインドは広く、そして11年間ずっと旅行し続けて来た訳でもなく、行きたくても行けなかった場所はたくさんある。今後、それらを巡る機会が訪れるかどうか分からないので、ここで備忘録も兼ねて、行けなかった場所を挙げて行こうと思う。
インドの北西部に位置する首都デリーに住んでいたこともあり、デリー周辺――つまり北インド――はかなり旅行した積もりだ。また、妻が元々カルナータカ州バンガロール(Bangalore)に住んでいたため、カルナータカ州もかなり制覇している。しかしながら、ざっとインド地図を見渡してみて、極端に弱い地域もこれらの地域の近隣にある。もっとも弱いのがビハール州だ。友人の結婚式に出席するためジャムイーという町を訪れた以外、留学期間中は一度も足を踏み入れていない。留学前にボードガヤー(Bodhgaya)へ行ったことがあるくらいだ。パトナー(Patna)、ナーランダー(Nalanda)、ラージギール(Rajgir)、サーサーラーム(Sasaram)など、訪れてみたかった。ウッタル・プラデーシュ州も、主要な都市は巡ったものの、まだまだ不足している。仏教関係は特に弱く、クシーナガル(Kushinagar)やシュラーヴァスティー(Shravasti)は未踏の地だ。パンジャーブ州も弱く、アムリトサル(Amritsar)しか観光したことがない。南インドではアーンドラ・プラデーシュ州が弱い。まともに観光したことがあるのはハイダラーバード(Hyderabad)くらいで、ワーランガル(Warangal)、ナーガールジュナコンダ(Nagarjunakonda)、ティルマラ・ティルパティ(Tirumala-Tirupati)などの有名観光地には行けなかった。
一般人に比べたらノースイーストは集中的に旅行した方であるが、それでも長らく外国人の入域が制限されていた特殊な地域であり、行き残した場所は多い。アルナーチャル・プラデーシュ州、マニプル州、ミゾラム州、トリプラー州の4州には事実上足を踏み入れたことがない。アルナーチャル・プラデーシュ州を除き、現在ではこれらの地域に外国人も入域しやすくなっているなっているのだが、それを享受する機会には恵まれなかった。しかしながら、観光地としての魅力があるのはやはりアルナーチャル・プラデーシュ州で、同州のタワン(Tawang)やジロ(Ziro)には行ってみたかった。
アンダマン・ニコバル諸島やラクシャドイープ諸島にも行けずじまいであった。アンダマン・ニコバル諸島はインド亜大陸と東南アジアの間に位置し、ラクシャドイープ諸島はモルディヴの北に位置する。実は2004年12月にアンダマン・ニコバル諸島へ行く計画を立てていたのだが、そのときは同時に計画していたナガランド州旅行を優先した。ちょうどその頃、スマトラ沖地震による津波でアンダマン・ニコバル諸島が大きな被害を受けたので、行かなくて本当に良かった。それ以来、アンダマン・ニコバル諸島への旅行を考えると必ず津波が頭をよぎるようになり、ずっと躊躇し続けて今まで来てしまった。
上に挙げた地域の大半は、ロンリー・プラネットなどのガイドブックにも掲載されている比較的メジャーなデスティネーションであり、ここで詳細を説明する必要もないだろう。それとは別に、知られざる潜在的観光地も随分調べた。どこの国でもそうだと思うが、ガイドブックに載っているようなメジャーな観光地以外の場所を旅行しようとすると、日頃の地道な情報収集が非常に重要となる。新聞や雑誌などにマメに目を通して旅行に関係する記事を切り抜いたり、その国の歴史を深く勉強したりしなければ、多くの人が知らない観光地を発掘することはできない。インドは特に観光資源豊富な国で、まだまだ知られざる観光地は山ほどある。そういう場所を「発見」し実際に訪れるのが、インド旅行の本当の醍醐味だ。
一昔前までは、インド国内の旅行者は外国人が大半を占めていた。インド人は避暑地や巡礼地への旅行には熱心だったが、史跡などにはあまり興味を示していなかった。タージマハルですら、敷地内で目にするインド人と言えば、木陰に涼みに来た地元民くらいであった。しかし、急速な経済発展に伴って考え方にも変化が表れ、いつしかインド人も大挙として観光地を訪れるようになった。今ではインドの観光業はインド人観光客によって十分成り立つまでに至ったと言っていいだろう。中には我々と同じ意味で旅行を趣味とするインド人も出始め、彼らはかなりマイナーな場所まで足を伸ばすようになっている。さすがに自分の国のことだけあって、本当にレアなインド観光情報を持っているのはインド人自身だ。外国人旅行者が外国人旅行者の溜まり場で情報を交換し合っても、なかなかそのような情報には巡り会えない。最近では旅好きなインド人旅行者との出会いが一番楽しみだ。インターネット上でも活発に旅行情報が交わされており、参考になる。他に、毎年11月にデリーで開催されるトレードフェアでも、各州観光局のブースでかなりの目新しい観光情報が集まる。
パンジャーブ州は、かなり潜在的な観光資源を隠し持っているのではないかと思う。メジャーなガイドブックに載っていないような場所を精力的に取り上げるアイシャー・グッドアースのガイドブック・シリーズにパンジャーブもあるが、そこにはアムリトサル(Amritsar)、カプールタラー(Kapurthala)、パティヤーラー(Patiala)、チャンディーガル(Chandigarh)の4都市とその周辺の見所しか載っていない。この中ではカプールタラーとパティヤーラーがマイナー観光地と言えるだろう。だが、バティンダー(Bathinda)の周辺地域が抜け落ちており、そこにも何かあるのではないかと思う。パンジャーブ州は一度集中的に旅行してみたかった。ちなみにパティヤーラーにはニームラーナー・ホテル系列の宮殿ホテル、バーラーダリー・パレスがあり、宿泊も楽しめそうだ。
ウッタル・プラデーシュ州ではカーンプル(Kanpur)の南にあるカールピー(Kalpi)に行けなかったのが特に心残りだ。14世紀末、ティームールの侵攻によってデリーが壊滅した後、多くの上流層がカールピーに移住したこともあって、かつては「小デリー」と称せられるべき繁栄を謳歌していたと言われる。カールピーを紹介するウェブサイトKalpriya Nagariによると、今でも多くの遺跡がいい雰囲気のまま残っているようで、旅心をくすぐられる。それと同様にヴァーラーナスィーの北にあるジャウンプル(Jaunpur)もデリー・サルタナト朝の末裔政権が花開いた場所で、ヴァーラーナスィー再訪がてら一度訪れてみたかった。ついでに、ヴァーラーナスィーからそれほど遠くない、ビハール州のサーサーラーム(Sasaram)には、フマーユーンをインドから追い出したアフガーン系の王シェール・シャー・スーリーの墓廟があり、これも見てみたかった。
ウッタラーカンド州では、ガンゴートリー(Gangotri)やヤムノートリー(Yamunotri)など比較的有名な巡礼地へ行ったことがないのだが、それらへは元々あまり行く気がせず、後悔はない。バドリーナートまではバイクで往復した。花の谷(Valley
of Flowers)に花の咲いている時期に行けなかったのは少々残念であるが、花の谷の花のために再訪する気力までは出て来なかった。ウッタラーカンド州で心残りなのはむしろ東側のクマーウーン地域である。クマーウーンではパータール・ブヴァネーシュワル(Patal
Bhuvaneshwar)という洞窟寺院を是非訪れてみたかった。また、インドの大きな秘密が隠されていると言われる、ウッタラーカンド州西部のチャクラーター(Chakrata)も一度内緒で行ってみたかった。外国人の入域は厳しく制限されているのだが、近くまで行って調べた結果、バイクでヘルメットをかぶって突入すればチャクラーターを通り抜けてヒマーチャル・プラデーシュ州まで行けるのではないかとの感触も得た。その危険な試みを実行できずに残念だ。
集めた新聞の切り抜きを改めて見返してみると、他にも行きたい場所が出て来る。ラージャスターン州のデールワーラー(Delwara)にはヒンディー語映画「Eklavya」(2007年)のロケで使われたデーヴィー・ガル城(Devi
Garh Fort)がある; 同州のジャーロール(Jalore)にはトープカーナー・モスク(Topkhana Mosque)という知られざる傑作モスクがある;
ウッタラーカンド州のカウサーニー(Kausani)はマハートマー・ガーンディーも愛した隠れた避暑地; パンジャーブ州のスィルヒンド(Sirhind)にはデリー・サルタナト朝からムガル朝までの遺跡が点在している;
同州のルディヤーナー(Ludhiana)には、ヒンディー語映画「Rang De Basanti」(2006年)のロケで使われたサラーイ・ラシュカリー・カーン(Sarai
Lashkari Khan)という宿泊所跡がある; タミル・ナードゥ州にはティヤーガヌール(Thiyaganur)という仏像が散らばる不思議な村がある;
グジャラート州のバーラースィノール(Balasinor)には「インドのジュラシックパーク」がある、などなど。インドの観光地としての可能性は限りない。
しかしながら、この11年間で、インドの中で何としてでも行きたかった場所には大体行ったようにも感じる。特に昨年ラダックとブルハーンプルに行けたのがよかった。どちらも長らく行きたいと考えていた場所だった。また、インドを旅行し始めてから10年以上が経った今、過去に訪れた多くの場所が、「旅行済み」から「再訪希望」のステータスにどんどん変わりつつある。もちろん未踏の場所は「行ってみたい」のままだ。とすると結局旅というのは切りがない。いくら旅をしても満足することはない。旅をしても無駄なんじゃないかという無力感も沸き起こる。しかしそれだからこそインドは面白い。旅行ひとつを取っても、すぐに底が見える国ではない。今後さらに情報が充実してくれば、また新たな潜在的観光地も発掘されて来るだろう。まだやるべきことを残しながらインドを去るのもまた一興だ。
ヒンディー語映画界にはいろいろな特徴を持った監督がひしめいているが、スディール・ミシュラー監督も一目置かれた存在である。売春婦を主人公に据えた「Chameli」(2003年)、学生運動などをテーマにした「Hazaaron
Khwaishein Aisi」(2005年)、ギャングによる誘拐劇を中心に描いた「Yeh Saali Zindagi」(2011年)など、渋い作品を撮り続けている。先週金曜日公開の最新作「Inkaar」では企業のセクハラをテーマとしており、また新たなフロンティアに挑んでいる。お気に入りの女優チトラーンガダー・スィンに加え、メインストリーム映画で主に活躍するアルジュン・ラームパールをキャスティング。スディール・ミシュラー監督の作品にアルジュンがどうはまるのか、それが一番の見所だ。
題名:Inkaar
読み:インカール
意味:否定
邦題:境界
監督:スディール・ミシュラー
制作:ヴィアコム18モーション・ピクチャーズ
音楽:シャーンタヌ・モーイトラ
歌詞:スワーナンド・キルキレー
出演:アルジュン・ラームパール、チトラーンガダー・スィン、ディープティー・ナーヴァル、サンディープ・サチデーヴ、ヴィピン・シャルマー、シヴァーニー・タンクサレー、モーハン・カプール、リハーナー・スルターン、スジャーター・セヘガル、カンワルジート・スィン、アーシーシュ・カプール、カイザード・コートワール、ガウラヴ・ドイヴェーディー
備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左がアルジュン・ラームパール、右がチトラーンガダー・スィン
| あらすじ |
ムンバイーを拠点とする広告代理店KKドイルのCEOラーフル・ヴァルマー(アルジュン・ラームパール)は、自らが育て上げたマーヤー・ルトラー(チトラーンガダー・スィン)からセクハラの苦情を受けた。女性人権活動家カームダール(ディープティー・ナーヴァル)が、グプター(ヴィピン・シャルマー)、カヴィター(スジャーター・セヘガル)など同僚数人の同席の下、ラーフルとマーヤーの聴取をすることになった。この聴取の中で、ラーフルとマーヤーの関係が明らかになって行く。
7年前、ラーフルは既に売れっ子の広告エージェントであった。毎年恒例のCM賞の授賞式でラーフルはまだ駆け出しの状態だったマーヤーと出会う。ラーフルはマーヤーに才能の原石を見出し、雇って育てる。マーヤーは業界で勝ち抜くテクニックを身に付け、急速に台頭する。同時にラーフルとマーヤーは恋仲となる。2人の仲は同僚の誰もが知っていた。ラーフルとマーヤーはゴールデンコンビとして会社の業績に貢献する。
ところがマーヤーはラーフルがCMのモデルと浮気をしているのではないかと疑うようになる。モデルが彼の自宅に入って行くのを目撃したマーヤーは遂に怒りを爆発させ、自らデリーに転勤してしまう。その後、マーヤーはニューヨークに転勤となり、そこでKKドイルの合弁相手の社長ジョン・ドイルのお気に入りとなる。7年後、マーヤーは再びムンバイーに戻って来る。
ムンバイーに戻るや否や、マーヤーは同社のナショナル・クリエイティブ・ディレクターに出世する。また、マーヤーはタルン(サンディープ・サチデーヴ)というボーイフレンドも連れて来ていた。ラーフルとマーヤーの仲は非常によそよそしいものとなってしまっていた。
ナショナル・クリエイティブ・ディレクターとなったマーヤーは傲慢となり、意見や方針の食い違いで度々ラーフルと衝突するようになる。とある顧客との会議でマーヤーが出しゃばったために商談不成立となり、それがきっかけでラーフルとマーヤーの間で喧嘩が起こる。マーヤーはそのときのラーフルの言動を根拠にセクハラの苦情を提出したのだった。
カームダールの聴取は2日続いたが、結論は出なかった。KK社長(カイザード・コートワール)をはじめとする会社の経営陣は、マーヤーを切る覚悟を決めていた。一方、マーヤーは弁護士に相談した後、ジョン・ドイルの宿泊するホテルを訪れる。その後、オフィスでラーフルとマーヤーは顔を合せる。マーヤーは、ジョン・ドイルと寝たとラーフルに告白する。それを聞いたラーフルは激昂し、マーヤーのことを今でも愛していると叫ぶ。
翌日、オフィスでは最終的な決断について議論が交わされていた。そこへラーフルからSMSが入る。そのSMSの中でラーフルは辞職を願い出る。そのSMSはマーヤーも受け取っていた。それを見たマーヤーも、誰にも告げずに会社を去る。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
かつて恋仲だった男性上司と女性部下が破局後に社内で対立するようになり、最終的に女性部下がセクハラの訴えを起こしたことを巡って、それぞれの主張が吟味される内容であった。ひとつの事実を別々の立場から見せる手法は、黒澤明監督の「羅生門」(1950年)の簡易版と言った感じで、特に目新しいものではない。だが、セクシャル・ハラスメントは非常に主観に左右される犯罪であり、その手法を使って何が真実なのかを追究するのは間違った方法論ではなかった。ただ、もし、男女の違いによって同じ言動が全く異なった受け止め方になっている様子を映像でうまく見せることができたら面白かったのだが、そのようにはなっておらず、お互いの主張の中で言動はかなり変わってしまっており、少なくともどちらかが嘘を付いていることなっていた。
この映画の大きな欠点は、最後を恋愛のもつれでまとめてしまったところだ。せっかくそこまでは緊迫感溢れる展開となっていたのに、最後の最後で「愛してる」「愛してた」の応酬で一気に幕引きをしてしまっていたのが興醒めであった。もっと当事者2人の主張を戦わせて、セクハラの本質を突き詰めれば、いい映画になっていたと思う。端的に言えば、前半はとても良かったが、後半が尻すぼみになってしまった。
ヒンディー語映画では、主人公が会社勤め、または会社経営者、と言った設定はもちろん普通にあるのだが、企業を主な舞台にした映画はまだまだ少ない。ただ、過去にいくつかそれに該当する映画はある。例えば、企業間または企業内のポリティックスなどをテーマにした映画では「Corporate」(2006年)が代表的だ。他に、リライアンスの創業者ディールーバーイー・アンバーニーを非公式に主人公にした「Guru」(2007年)やセールスマンが主人公の「Rocket
Singh: Salesman of the Year」(2009年)などが挙げられる。おそらくこの「Inkaar」を、これらの「企業映画」のリストに加えてもいいだろう。そもそもラーフルとマーヤーの対立が生じたのは、KK社長がラーフルCEOの力をそぐために「分割統治」を画策し、マーヤーに権力を与えたことが原因であり、企業内ポリティックスを十分に体現している。女性が管理職になることへの偏見についても少しだけ触れられていた。
テーマは興味深いが、そのプレゼンテーションと結末に不満が残る映画であった。しかしながら、一番の見所はアルジュン・ラームパールの演技であった。「Deewanapan」(2001年)や「Moksha」(2001年)でのデビュー以来ずっと彼を見続けて来ているが、当初の彼はモデル出身なだけあって、「ハンサムだが大根役者」と表現せざるを得なかった。俳優としてのキャリアもずっと低迷が続いた。しかし、「Om
Shanti Om」(2007年)の悪役で高い評価を受け、その後「Rock On!!」(2008年)、「Ra.One」(2011年)、「Chakravyuh」(2012年)など、着実に演技力を上げて来た。そしてこの「Inkaar」を見て、これだけ演技できる俳優になったかと驚いた。誰が嘘を言っているのか分からない混沌とした状況の中で、彼の台詞回しは、本当のことをしゃべっているか、またはさも本当のことのように嘘や御託を並べているか、のちょうど境界線を行く見事なものであった。このルックスに加えてこの演技力があれば、はっきり言って向かうところ敵なしだ。アルジュン・ラームパールは一応贔屓にしている男優であり、今後も活躍し続けて欲しいと思っている。
一方、チトラーンガダー・スィンは「Hazaaron Khwaishein Aisi」でのデビュー以来、演技力を高く評価されて来た女優である。だが、出演作はあまり多くなく、メインストリームの娯楽映画にもほとんど出演していない。29歳でデビューとなった遅咲きの女優であることも関係していると思うが、スディール・ミシュラー監督は彼女を根気よく起用して来ている。「Inkaar」でもいい演技であったが、意外にアルジュン・ラームパールが素晴らしく、押され気味であった。彼女が演じたマーヤーの人物スケッチがあまり明確ではなかったことも影響しているだろう。
音楽はシャーンタヌ・モーイトラ。「Parineeta」(2005年)、「Lage Raho Munnabhai」(2006年)、「3 Idiots」(2009年)など、彼が音楽監督を務めた作品の中には不朽の名作も多いのだが、「Inkaar」の音楽はいただけなかった。音楽がなくてもよかったぐらいなのに、派手目の楽曲が多く、映画の雰囲気を損なっていた。
「Inkaar」は、企業内セクハラというユニークなテーマの映画だが、恋愛映画の延長線上でまとめられてしまっているところが残念な作品であった。しかしながら、アルジュン・ラームパールの演技力が突然変異的に炸裂しており、それを目の当たりにできたのが良かった。無理に見る必要はない映画だが、アルジュン・ラームパールのファンなら一見に値する。
|
|
|
|
最近ヒンディー語映画界では猫も杓子も続編の様相となっており、2013年も多くの続編映画が公開される。1月25日より公開されている「Race
2」も、2008年に公開された大ヒット・スリラー映画「Race」の続編である。監督は前作と同様にアッバース・マスターン。前作からストーリーのつながりがあり、前作が終わった時点から話が始まる。よって、登場人物の何人かも前作と共通している。
題名:Race 2
読み:レース2
意味:レース2
邦題:レース2
監督:アッバース・マスターン
制作:ラメーシュSタウラーニー、ロニー・スクリューワーラー、スィッダールト・ロイ・カプール
音楽:プリータム、アーティフ・アスラム
歌詞:マユール・プーリー、プラシャーント・インゴーレー、ヨー・ヨー・ハニー・スィン
出演:サイフ・アリー・カーン、ディーピカー・パードゥコーン、ジョン・アブラハム、ジャクリーン・フェルナンデス、アニル・カプール、アミーシャー・パテール、ラージェーシュ・カッタル、アーディティヤ・パンチョーリー、ビパーシャー・バス(特別出演)
備考:DTスター・プロミナード・ヴァサント・クンジで鑑賞。

左からジョン・アブラハム、ディーピカー・パードゥコーン、サイフ・アリー・カーン、
アミーシャー・パテール、ジャクリーン・フェルナンデス、アニル・カプール
| あらすじ |
前作で100万ドルの保険金を手に入れたランヴィール・スィン(サイフ・アリー・カーン)と恋人ソニア(ビパーシャー・バス)はキプロス島でバカンスを楽しんでいた。ところが、ランヴィール・スィンが自動車から降りたときに、暗殺者によって自動車を爆破され、乗っていたソニアは死んでしまう。ランヴィールは暗殺者を追跡して殺す。彼の持っていた携帯電話から、トルコのカジノ王ヴィクラム・ターパル(ラージェーシュ・カッタル)の名前が浮上する。さらに調べた結果、ソニア暗殺の張本人は、ストリートファイターから大富豪にのし上がったアルマーン・マリク(ジョン・アブラハム)であることが分かる。アルマーン・マリクは腹違いの妹エレーナ(ディーピカー・パードゥコーン)と共に財閥を築き上げていた。また、アルマーンにはオミーシャー(ジャクリーン・フェルナンデス)という恋人がいた。ランヴィールはヴィクラムとアルマーンへの復讐を計画し始める。
ランヴィールはまず旧知の探偵ロバート・デコスタ、通称RD(アニル・カプール)の助けを借りて、アルマーンに近付く。RDにはチェリー(アミーシャー・パテール)という新しい秘書がいた。ランヴィールはアルマーンに、ヴィクラムがトルコに持つ5つのカジノを安価で手に入れるプランを伝える。何よりも金が好きなアルマーンはそれに乗る。ランヴィールは、最近何者かにユーロ原盤が盗まれたというニュースを利用してヴィクラムを騙し、彼の所有するカジノをアルマーンにまんまと買収させる。
この一件でアルマーンはランヴィールを信用したと思いきや、裏で彼の身辺調査を進めていた。ランヴィールがソニアの恋人であることが分かると、自分の恋人オミーシャーをソニアの妹タニヤということにして、ランヴィールに接近させる。彼女はアルマーンを暗殺するために彼の恋人の振りをしていると明かす。だが、ランヴィールは以前にタニヤの写真を見たことがあり、彼女がタニヤでないことを知っていた。しかし、表面上は騙されている振りをする。また、エレーナはランヴィールを気に入り、彼の部屋に押しかけて一夜を共にする。
ランヴィールはアルマーンを破滅させるため、危険なプランに誘う。それはトリノの聖骸布を盗み出すという大胆なものだった。アルマーンはランヴィールの意図を知りながらも、それを逆手に取って大儲けすることを画策し、その誘いに乗る。その資金としてアルマーンはゴッドファーザー・アンザ(アーディティヤ・パンチョーリー)から大金を借りることにする。アンザはストリートファイター時代からアルマーンを可愛がっていた。現在アンザの下にはタイフーンというストリートファイターがおり、それに勝ったら金を貸すと約束する。アルマーンはタイフーンとストリートファイトをし、見事勝利する。
一方、イタリアではランヴィールがRDの助けを借りてトリノの聖骸布を盗み出していた。そして聖骸布の偽物をバイヤーに売り渡し、多額の証券を手にする。ところが、その成功を祝う場でアルマーンはランヴィールを毒殺する。そしてアルマーンは、ランヴィールがイタリアの空港に隠していた本物の聖骸布を手にする。
アルマーン、エレーナ、オミーシャーは自家用ジェット機でトルコへ帰途に就いていた。だが、元々アルマーンはエレーナを殺そうとしており、飛行機の中でエレーナに銃口を向ける。しかしそこへ死んだはずのランヴィールが突入して来る。実はランヴィールとエレーナは裏で通じており、毒殺による死も演技であった。アルマーンとランヴィールは機中で決闘するが、その中で飛行機がダメージを受け、墜落寸前となる。アルマーンとオミーシャーは聖骸布と証券を持ってパラシュートで脱出するが、ランヴィールとエレーナも事前に脱出の準備をしており、無事に生き延びる。
アルマーンとオミーシャーはアンザに聖骸布を渡す。ところがこれも偽物であった。しかもアルマーンが持っていた証券も偽物であった。ランヴィールに騙されたアルマーンはアンザに借金を返すことができず、彼の所有物は全て取り上げられてしまった。しかも恋人のオミーシャーもアンザのものになってしまった。
一方、ランヴィールとエレーナはRD、チェリーと落ち合う。RDもアルマーン側かと思われたが、やはりランヴィールの味方であった。2人は各々エレーナとチェリーを連れ、セスナ機に乗り別々の方向へ飛び立って行く。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
登場人物のそれぞれが陰謀を巡らしており、映画の途中でそれが何度も明かされるのだが、誰が最終的に騙されているのか観客は最後まで分からないという展開のスリラー映画であった。しかし、騙し合いがあまりに高度過ぎて予定調和の罠にはまっており、現実味がなかった。現実味がないということはスリラー映画に重要なハラハラドキドキ感がないということであり、この映画の大きな欠点となっていた。「Race」でも「Race
2」でも、死んだはずのランヴィールが突如登場し、大どんでん返しとなるのだが、どうもこの「Race」シリーズでは、もし今後も続いて行くのなら、それがお約束となりそうだ。
アッバース・マスターン監督の映画は基本的にチープさが持ち味で、その馬鹿馬鹿しさを楽しむものである。「Race 2」も例に漏れず馬鹿馬鹿しい展開が続く。なぜヴィクラム・ターパルはランヴィールから偽札を全く確認せずに受け取ったのか、なぜ大富豪のアルマーンが借金するためにストリートファイトをしなければならないのか、なぜ飛行機の中で自動車を運転するのか、なぜその自動車が4つのパラシュートだけで宙に浮かぶのか、などなど、細かいところを突っ込んで行くとキリがない。そういうのを笑って見過ごせる人向けのエンターテイメントだ。
しかし、そんな「Race 2」で一番印象に残ったのは、ディーピカー・パードゥコーンの存在感のなさとアミーシャー・パテールの凋落振りであった。
ディーピカー・パードゥコーンは、もうすぐ日本でも一般公開される「Om Shanti Om」(2007年)でヒンディー語映画デビューして以来、将来を嘱望されて来た女優なのだが、ここに来て低迷が続いており、同年代のライバル女優たちに差を開けられている。ただいい作品に恵まれていないだけかもしれない。しかし、「Race
2」の彼女からは「Om Shanti Om」の頃の覇気が感じられず、単なる飾りに過ぎなかった。このまま没落することはないと思うが、何か一発大きな花火が欲しいところだ。
目に手も当てられないのはアミーシャー・パテールである。「Kaho Naa... Pyaar Hai」(2000年)でデビューし、「Gadar
- Ek Prem Katha」(2001年)で大きく躍進したはずだが、その後はほとんど鳴かず飛ばずで10年以上が過ぎてしまった。なぜかデリー・タイムスなどの新聞への露出は多いのだが、「Race
2」の彼女からは、かつてのあの栄光は全く感じられず、無常感を味わった。今回彼女が演じたのは胸が大きいだけの馬鹿女役である。彼女ほどの長いキャリアのある女優が演じるような役ではない。こんな役しかもらえなかったのか、もしかしたらお金払って出演させてもらったのか。そんな邪推をしたくなってしまうほどであった。
上の2人に比べて健闘していたのがスリランカ人女優ジャクリーン・フェルナンデスである。特にランヴィールとフェンシングで対決するシーンなどはかなり迫力があった。あまりヒンディー語映画ヒロイン向けの顔ではないと前々から思っているのだが、彼女なりの活躍の場を見つけて行けるかもしれない。
女優陣に比べたら男優陣は適材適所に活き活きと演技をしていた。主演のサイフ・アリー・カーンは「死なない男」をハードボイルドに演じ切っていたし、ジョン・アブラハムも見事な悪役振りであった。アニル・カプールについては、前作2008年の時点とはだいぶ立場が変わっている。彼が出演した「スラムドッグ$ミリオネア」(2008年)の世界的な成功のおかげで、国際的な俳優になってしまった。そんな彼が2008年時に出演した映画の続編で前作と同じ色物キャラを演じている姿を見ると、どこか違和感も感じてしまうのだが、さすが演技力はある男優であり、映画の息抜きとなっていた。
音楽は前作と同じプリータム。前作でテーマ曲的に使われていた「Race Saanson Ki」のサビが本作でも繰り返されており、「Allah
Duhai Hai」という曲になっている。豪華なダンスシーンだが、振り付けや衣装が変だ。映画から切り離して完成度が高いダンスシーンはビーチで踊る「Party
On My Mind」であろう。他に特筆すべきはサイフ・アリー・カーンとディーピカー・パードゥコーンのベッドシーンに流れる「Be Intehaan」であろうか。パーキスターンの人気歌手アーティフ・アスラムが歌っている。
映画は、ムンバイー・ロケを除けば、主にトルコで撮影されているようである。トルコはここのところヒンディー語映画の人気ロケ地となっており、「Guru」(2007年)、「Mission
Istaanbul」(2008年)、「Game」(2011年)、「Ek Tha Tiger」(2012年)など、数多くのトルコ・ロケ映画が作られている。トルコ政府がロケ地誘致に積極的であるのがそのひとつの要因のようだ。最近トルコ航空のCMもよく見掛ける。
「Race 2」は、チープな映画作りが魅力のアッバース・マスターン監督らしい娯楽作。騙し騙され誰が最終的に騙されているのか分からないという展開が売りだが、そのどんでん返しの連続に付いて行くのにはかなり思考力を要する。スリラー映画としての完成度は中程度か。今回主な登場人物は生き残っており、さらなる続編が作られる可能性は高い。
|
|
|
|
|
NEXT▼2013年2月
|
|
| *** Copyright (C) Arukakat All Rights Reserved *** |



