 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
 これでインディア これでインディア 
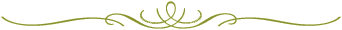
2005年3月
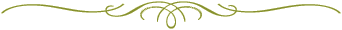
|
|
|
|
しばらく中間テスト期間が続いていたが、今日やっと最後のテストが終了した。ヤマが外れたり運が悪かったりで出来は散々なものだったと思うが、後は野となれ山となれだ。この爽快感と共に今日は新作映画「Sins」を見にPVRアヌパムへ行った。
「Sins」は英語で「罪」という意味。副題は「Crimes of Passion(情愛の犯罪)」。題名だけで何だかやばそうな雰囲気が伝わってくる。この映画はケーララ州の海岸沿いの町を舞台にした英語映画で、現地語のマラヤーラム語が多少入っていた。よって、ヒングリッシュ映画と呼ぶことができない。仮に「印グリッシュ映画」とでもしておくか。監督・脚本はヴィノード・パーンデーイ、キャストは、シャイニー・アーフージャー、スィーマー・レヘマーニー、ニーティーシュ・パーンデーイなど。カトリック教会の神父が若い女性と肉体関係を持つ、という筋の映画で、しかも実際の事件を基にしたらしい。インドのカトリック教会グループがこの映画の上映を禁止するよう裁判所に訴えていたが却下され、A証明(成人向け映画)で先週の金曜日から公開されている。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
シャイニー・アーフージャー(後)と
スィーマー・レヘマーニー(前) |
● |
| Sins |
ケーララ州の海岸沿いの町に住む神父ウィリアムス(シャイニー・アーフージャー)は、看護大学に通うローズマリー(スィーマー・レヘマーニー)と肉体関係を持ってしまう。最初は罪に苛まれて教会で懺悔をするウィリアムスだったが、欲望に打ち克つことができず、ローズマリーと密会を繰り返す。ウィリアムスは人脈を使ってローズマリーの学業と就職や、彼女の弟のドバイ行きを支援する。しかし、ウィリアムスとローズマリーの関係は次第に町の人々に知れ渡り、ローズマリーは悪評に耐えられなくなる。ウィリアムスは特別許可をもらってローズマリーと結婚すると言っていたが、神父の結婚は許されていなかった。ウィリアムスは、ローズマリーをムンバイー在住のグラハム(ニティーシュ・パーンデー)と形式的だけ結婚させ、実際は彼女を愛人にする。
10ヵ月が経った。グラハムはローズマリーと見せ掛けの結婚をしたものの、彼女と本気で結婚したいと思うようになり、彼女が住む町を訪れる。ウィリアムスの暴力に耐え切れなくなっていたローズマリーは、グラハムと本当に結婚することを決意し、彼と初めて一晩共に過ごす。ローズマリーは夜中こっそり逃げ出し、グラハムと共に過ごし始める。そして彼女は妊娠する。
ところが、ローズマリーが逃げ出したことを知ったウィリアムスはますます暴走するようになり、彼女の母親を絞め殺してしまう。母親の葬儀に地元に帰ったローズマリーは、ウィリアムスが母親を殺した証拠を掴む。警察は捜査に乗り出すが、ウィリアムスは刺客を送ってローズマリーを殺害する。警察はウィリアムスを逮捕する。ウィリアムスは裁判所で死刑を宣告される。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
キリスト教グループが一生懸命騒いでいるわりには、非常に稚拙で退屈な映画だった。俳優のセリフや演技が大仰で馬鹿馬鹿しい、1つ1つのシーンのテンポが悪い割には話がまるで歴史の授業のように「〜ヵ月後」「〜年後」という具合に進んで行ってしまう、あまり意味のない性描写シーンが多すぎる、そもそもストーリーに整合性とひねりがない、などなど、いろいろな欠点があった。映画館の座席は当初3分の1くらい埋まっていたが、途中で席を立つ人が何人もいた。今までの僕の経験の中で、これだけインド人から飽きられた映画は、ちょっと思い出せない。よって、詳細な批評に値する映画ではない。
だが、もしこの映画の意義を一言で表すならば・・・一単語で表すならば・・・何と言っても・・・「乳首」であろう・・・。乳首・・・そう、乳首である。今までサルマーン・カーンやサンジャイ・ダットなどのたくましい胸板と猛々しい乳首は思う存分スクリーンで鑑賞して来たが、女優の乳首をインド映画で見たのは、記憶にある限りこの映画が初めてだ。ミーラー・ナーイル監督「カーマ・スートラ 愛の教科書」(1996年)ではかなり露骨なヌードシーンやベッドシーンもあったが、インドでは一般上映されていない。場末の映画館では、俗に言うブルーフィルムが上映されているが、それらのアダルトな映画ですらも女性の全裸やベッドシーンはご法度だったはずだ。よって、最近インド映画は性描写が露骨になって来たものの、ある一定のラインは絶対に越えないと思っていた。その一定のラインのひとつが、「女性の乳首」であった。ビパーシャー・バスもマッリカー・シェーラーワトもネーハー・ドゥーピヤーも、際どいヌードは見せても、乳首は見せたことがない。だが、「Hum
Kaun Hai?」(2004年)でデビューした新人女優スィーマー・レヘマーニーは、なぜかこの映画の中で2、3回、少しだけだが乳首を見せている。インドの映倫がなぜこれらのシーンを見逃したのか、全くもって謎である。確かに映倫が問題にした過激なシーンはこの映画の中にあった。だが、さらに謎を深めるのが、映倫が問題にしたシーンが、スィーマー・レヘマーニーが乳首をさらしているシーンではなく、裸の背中と尻をさらしているシーンであったことである。これらのシーンは監督の主張により結局カットされずに済んだようで、上映されていたプリントではそのまま残っていた。インド映画には絶対にストレートな性描写がないと安心&油断して映画館に来ているので、突然こういうものを見せられると冷や汗が出るほどビックリする。これは果たして、インド映画が乳首を解禁したということなのだろうか、それとも単なるチェック・ミスなのだろうか・・・。ちなみに、それらのシーンが映し出されたとき、インド人観客が一斉に呆然としたのが感じられた。だが、だんだん慣れてきたようで、終盤にあるローズマリーとグラハムのベッドシーンでは笑いが漏れていた(グラハム役の男優がチョビヒゲ+太っちょのおじさんなので、確かにこのベッドシーンは滑稽である)。インド人はホラー映画の怖いシーンでも笑うし、ベッドシーンでも笑うし、何でも笑う国民だ・・・。
エロもあればグロもある。最後でローズマリーがウィリアムスが送り込んだ刺客に刺殺されるシーンがあるが、このシーンは非常に生々しかった。刺客たちはローズマリーを包丁で何度もグサグサと刺し、オートリクシャーに乗り込んで走り去ってしまった。このときの効果音と血しぶきがかなり本物っぽかった。こんなところに気合を入れなくてもいいから、もっとストーリー全体を本物っぽくしてもらいたかった。
登場人物の全員がキリスト教徒というのは、インド映画としては異様に思えるかもしれないが、ケーララ州はインドの中で最もキリスト教人口の多い州で、ありえない設定ではない。ケーララ州の言語はマラヤーラム語で、映画中でも数フレーズだけマラヤーラム語が使われていた。僕が分かったのは「サリ(OK)」だけだ。ケーララ州独特のトロピカルな風景や、海岸に立つ古い十字架の景色などは非常に美しかった。
映画としては全く退屈な作品だが、もしこれがインドの映画界において乳首解禁を告げる映画だとしたら、歴史的な映画として名を残すことになるかもしれない。英語の映画なので、上述の場末の映画館で公開されることはないと思うが(その一点を頼りに監督は「これは芸術映画だ!」と主張しているのだろう)、しかし現地語で撮った方が興行成績は上げられただろう。肌の露出度といい、ストーリーの単純さといい、ほとんどポルノ映画であった。
日本で「おたく」という言葉が一般に普及するようになって久しい。その起源を辿ってみると、「漫画ブリッコ」という雑誌の1983年6月号に掲載された、中森明夫氏の「『おたく』の研究」という記事が発端らしい。中森氏の定義では、「おたく」とは、「コミケなどによく出没する、マンガ好き、アニメ好きの男女で、クラスに必ずいる、運動が全くだめで、休み時間なんかも教室の中に閉じ込もって、日陰でウジウジと将棋なんかに打ち興じてたりする人々」のことを言うようだ。コミケにいる人々がよく「おたくは〜」という二人称代名詞を使用していたのに着目した中森氏が、「おたく」と名付けたらしい。現在では、おたくの意味はもう少し拡大されて、「マニア」と似たような意味になっていると思う。マンガやアニメに限らず、何かしら打ち込んでいるものがある人に対し、「〜おたく」と使われる。僕は「インドおたく」とか「インド映画おたく」と呼ばれて然るべきかもしれない。
ところで、3月3日付けのデリー・タイムズ・オブ・インディア紙に、「Otaku」という言葉が詳細に解説されていた。「Otaku」は既に英語にもなっているが、遂にインドにも上陸したことになる。
デリー・タイムズ紙の解説によると、「Otaku」とは・・・
いつも家に閉じこもっていて、社会生活や恋愛生活を送っておらず、アニメを見たり、TVゲームをしたり、インターネットをしたりして時間を過ごしており、現実世界よりもバーチャルな世界を心地よく思い、社交術が下手で、デートをする能力に欠けた人々のこと
らしい。日本での「おたく」の一般的な用法と非常に近く、正確にそのニュアンスが伝わっている。しかも、最近日本で話題になった「電車男」についても触れられており、この記事を書いたアラン・オブライアン(インド人ではないのか?)という記者が相当日本に詳しいことが伺われる。
だが、インドでの「おたく」の例として挙げられていたのが、コールセンターで働く人々だった。この用例は、少し日本の「おたく」の定義から外れるように思われる。インドでは、米国のちょうど反対側にあるという偶然の地理的利点から、時差を利用したコールセンター代行産業が非常に発達している。つまり、米国で深夜にコールセンターにかけると、そのとき昼間になっているインドでインド人オペレーターが対応する、という仕組みである。国際電話料金はかかってしまうが、インドは人件費が安いため、米国でアメリカ人オペレーターに深夜仕事をさせるよりも割安になるそうだ。また、コールセンターで働くインド人の英語の発音は徹底的に修正され、ネイティブと変わらぬくらいアメリカ英語を話すようにさせられる。だから、電話をした人はその電話がインドにつながっているとは夢にも思わないらしい。
しかし、コールセンターで働いていると、次第に人との生のコミュニケーションが取れなくなってくるらしい。コールセンターでは電話でのコミュニケーションのみなので、声と声だけの意思疎通に慣れてしまう。だから、相手の目を見て話すことが怖くなってくる。また、マニュアル通りの応対をしなくてはならす、それが染み付いてしまうと、友人との会話も自然に行えなくなってしまう。こういう状態のことを、同紙では「Otaku」と呼んでいる。上で挙げた解説は非常に正鵠を射ていたのだが、この用例は少し違うと思う。このままでは、「Otaku=コミュニケーション能力が欠落した人」みたいな意味に取られる可能性が高い。
さて、これからどうインドで受け容れられるかは別として、とにかく「Otaku」という単語が遂にインドにも入ってきたわけだが、僕はどちらかというとインド人ほど「おたく」っぽくない民族はいないと思う。まず、趣味に生きている人が少なすぎる。一部の上流階級のみ、英国貴族風の趣味の世界に没頭しており、一般庶民にはまだまだ生活に関係ないものに金を費やすという考え方はないように思える。職人はいる。先祖代々手工芸品を作り続けてきた究極の「おたく」はいる。カースト制度は、「おたく」醸成装置と捉えることもできるかもしれない。だが、これも正確には「おたく」ではなく、やっぱり職人としか言いようがない。「おたく」は現実逃避のために「おたく」をしているが、職人は第一に生活のためにやっているのだ。インド人といえばITであり、コンピューター大好きなインド人は多いが、彼らにしてもやっぱり生活と仕事のためにコンピューターと関わっている人が多く、あまり「おたく」っぽくない。そもそも、自宅にパソコンやインターネット常時接続環境を持っている人はまだまだ少数派である。アニメ、マンガ、ゲームにしろ、インド人は「子供のためのもの、子供の遊び」と割り切っていることが多く、大人になってまでそれらのものにのめり込む人は稀である。映画にしても、「子供の頃は全ての映画を片っ端から見ていたけど、大人になってからはほとんど見ていない」というインド人が多い。
それに、インドほど人と人とのコミュニケーションが重要な国はない。日本のコンビニのように、無言のまま買い物を済ますことができるシステムはまだほとんどないし、日本のバス停や駅のように、人に尋ねなくても公共交通機関を利用できる親切設計はないし、何より人脈が日本以上にものを言う世界なので、家族の輪、友人の輪、知り合いの輪をどんどん広げていかないことには何も始まらない。よって、インドでは人との意思疎通をする能力がないことは生死に関わる。また、日本人は概して他人にやたらと気を遣う恥ずかしがり屋な民族なので、他人との接触が面倒になって自分だけの世界に閉じこもり、「おたく」になってしまうという潜在的国民性があるが、インド人はデリカシーやプライバシー観念がない人が多く、とにかく「駄目で元々」という感じで積極的に話しかけて来るのが常だ。日本よりも、人と人との距離が近い、と感じる。そのストレートなアプローチは、「おたく」とは程遠い。唯一、デートに関しては少し話が別だ。まだまだ未婚の男女が並んで公共の場を出歩くという文化は一般的ではなく、デートをしたことがないという男女はそれほど珍しくないのではないかと思う。だが、これは文化の違いであって、「おたく」とは関係ない。蛇足だが最後に付け加えるならば、「おたく」はどうやらバーチャルな世界に没頭する傾向にあるらしいが、インドの宗教や哲学はこの現実世界そのものをバーチャルな世界と定義することが多く、インド人の思考は「おたく」の定義の次元を超越しているように思える。
よって、インドは、趣味に没頭し、コミュニケーションが苦手な「おたく」を生みにくい土壌なのではないかと思う。
今日はPVRアヌパムで新作ヒングリッシュ映画「White Noise」を見た。パーキスターンのカラーチーで開催されたカラ映画祭や、イタリアのフローレンス映画祭に出品された、英語の映画である。監督は、TVドラマ界で名を馳せた女性監督ヴィンター・ナンダー。キャストは、ラーフル・ボース、コーエル・プリー、ジャティン・スィヤル、アーリヤン・ヴァイド、モナ・アンベーガーオンカルなど。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
コーエル・プリー(上)と、
ラーフル・ボース(下) |
● |
| White Noise |
カラン(ラーフル・ボース)はムンバイーでTVドラマ制作会社でエディターをしていた。監督のパッラヴィー(モナ・アンベーガーオンカル)は顕示欲の強い女で、脚本家を何度もクビにしてしまっていたので撮影が難航していた。会社のボス、ミッキー(ジャティン・スィヤル)は、新しい女性脚本家ガウリー(コーエル・プリー)を連れて来る。ところが、パッラヴィーとガウリーは犬猿の仲だった。
ガウリーは有能な脚本家だったが、大酒飲みかつ既婚の男に横恋慕する癖のある破滅的な女性だった。ガウリーは、前のボス、パワン(アーリヤン・ヴァイド)とも不倫をしていたが、彼の妻にそれがばれ、パワンを諦めなくてはならなかったばかりか、仕事も失ってしまっていた。カランは職場で出会う前にある雨の晩、酔っ払って街をふらつく彼女と会って、何となく惹かれていた。
ガウリーの参入によりドラマに迫力が出るが、制作スタッフの間では人間関係が複雑になる。ミッキーはガウリーに言い寄るが、ミッキーのことを密かに好きだったパッラヴィーはますますガウリーにきつく当たるようになる。だが、ガウリーがミッキーの誘いを拒絶すると、一転してミッキーはガウリーを冷遇するようになる。カランが激昂的なガウリーと波長を合わせる努力をする内に、2人の仲は次第に近付いていく。
ミッキーとパッラヴィーはさらに追い討ちをかけるように、ガウリーとパワンの不倫をドラマにする計画を出す。それはメディアにも取り上げられ、ガウリーは辱めを受ける。激怒したガウリーはパワンの会社に入り込んで泣き喚くが、どうにもならなかった。とうとうガウリーは仕事を辞める決意をするが、カランは一緒にリシケーシュに行ってから2人で辞職することを提案する。リシケーシュのガンガー河に心を癒されたガウリーは、再起する勇気を取り戻す。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
ムンバイーの都会人の精神的フラストレーションを描いた一風変わったロマンス映画。監督が元々TVドラマ界にいただけあり、インドのTVドラマの裏事情をスタッフ側からの視点で描写していたのもユニークだった。終わり方がインドらしかったのも好感的だった。
「ホワイトノイズ」とは、「単位周波数帯域(1Hz)に含まれる成分の強さが周波数に無関係に一定の雑音」のことを言うらしいが、簡単に言えば、TVの空きチャンネルで流れる「ザーーー」という音のことだ。主人公のカランは、TVから流れてくるそのホワイトノイズを聞くことで、孤独な心を癒していた。職場にて、ガウリーに「何をしているの?」と聞かれ、「ホワイトノイズを感じているんだ。静寂の音をね」と答えるシーンが印象的である。このときと似たやりとりが、映画の終盤、リシケーシュのガンガー(ガンジス)河の河畔で河のせせらぎを聞く2人の間で繰り返される。自然の中での河のせせらぎと、都会のホワイトノイズ。これらを対比したところが映画の優れた部分だった。
女性監督の映画なだけあって、男性キャラクターよりも女性キャラクターの方が際立っていた。特に主人公ガウリーと、そのライバルのパッラヴィー。大人になってまでこんな露骨で陰険な争いをするものなのかとも思うが、かなり生々しい「女の戦い」を演じていた。また、ガウリーのヒステリックで自滅的な振る舞いは、コーエル・プリーの見事な演技力もあって、映画を際立たせていた。それと比べると、男性キャラクターは深みがなかった。
都市部を中心にヒットした「Page3」(2005年)では、ムンバイーのセレブたちの表と裏が描写されていたが、「White Noise」ではインドTVドラマ界の裏舞台が少しだけ暴かれていた。それほどセンセーショナルなものではなかったが、TVドラマ俳優の仰々しい演技や、いつまで経っても嫁と姑の争いという決まりきった筋から抜け出せない業界の後進性などが揶揄されており、これは監督によるTVドラマ業界への三行半とも言えるのではないだろうか。ちなみに、ヴィンター・ナンダー監督は、90年代にヒットしたTVドラマ「Tara」を監督したことで有名である。
ラーフル・ボースは僕が贔屓にしている男優で、彼が出演する映画は全て見ることにしている。何と言っても「Mr.&Mrs. Iyer」(2002年)が最高傑作だが、他にも「Everybody
Says I'm Fine!」(2001年)、「Mumbai Matinee」(2003年)、「Chameli」(2004年)など、優れた映画に出演している。彼はヒングリッシュ映画によく出ており、「ミスター・ヒングリッシュ」と命名している。最近はヒンディー語映画にも出るようになってきた。だが、彼の映画中のキャラクターはだんだんワンパターンになって来ているようにも思える。ボースが監督と脇役出演を務めた「Everybody
Says I'm Fine!」を除けば、彼は内向的で女性的な男性を演じることが多い。「White Noise」でも、ガウリーに必死に自分を合わせようとする内向的な男を演じていた。だが、彼の演技力は申し分ない。
ガウリーを演じたコーエル・プリーは、多少品のない顔と声をしているが、素晴らしい演技力。彼女は「Everybody Says I'm Fine!」にも同じような役で出演していた。ちなみにコーエル・プリーは、インドの人気週刊誌「インディア・トゥデイ」の編集長アルン・プリーの娘だそうだ。
ムンバイーが主に舞台となっていたが、ムンバイーから南に行った海岸沿いにあるアリーバーグや、海上の要塞ジャンジーラー砦、リシケーシュやハリドワールなどでもロケされていた。特にリシケーシュとハリドワールのシーンは映画をまとめる上で非常に重要な役割を果たしていた。だが、カランとガウリーがリシケーシュへ向かう理由が多少唐突過ぎた印象を受けた。
カランは父親と不仲であり、父親が電話をかけてきても決して話そうとしなかった。父親がカランに言う「Winners always go forward(勝者は常に前進する)」という言葉は、そのままカランがガウリーを励ますときに使われる。だが、カランと父親が仲直りするようなシーンはなく、ストーリー上あまり意味のない登場だったように思える。父親のセリフもはっきり言って陳腐な表現である。
言語は9割以上が英語。少しだけヒンディー語が入り、一瞬だけパンジャーブ人の登場によりパンジャービー語も入る。パンジャーブ人の親子がカランに、ドラマの筋を勝手に予想して、しかもああしてくれ、こうしてくれ、と頼むコメディーシーンなのだが、これも映画にはあまり必要ないシーンだったように思えた。ただ、TVドラマの筋を家族や友人であれこれ予想しながら毎週毎週楽しみにする姿は、インドでも日本でも変わらないと感じた。
なぜかドアーズのジム・モリソンがカランとガウリーの会話の中で度々登場した。監督の趣味だろうか。
あと、かなりどうでもいい話だが、映画中でラーフル・ボースが着ていた「東京」ロゴ入りの赤いTシャツは、僕も持っている。色も全く同じである。1年前くらいにベネトンで買った。「オレは日本人だぜ」ということを主張するために購入したが、あまり着なかった・・・。コーエル・プリーもこのTシャツを着るシーンがあった。思わぬところでラーフル・ボースと波長が合って、少しだけ嬉しかった。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
「東京」ロゴ入りTシャツ |
● |
「White Noise」は、ヒングリッシュ映画の隆盛と同時に盛んに作られるようになった、都会人のための都会派映画である。
| ◆ |
3月6日(日) インド人初のF1ドライバー、デビュー |
◆ |
インドのスポーツ界は、長年クリケットが独裁主義とも言える人気を誇っていた。今でも、クリケットにかなうスポーツはインドにはない。だが、2005年に入り、インドのスポーツ界が次第に多極化する様相を見せている。まず、テニス界からサーニヤ・ミルザーという新しいアイドルが生まれ、一気にテニスがインド人の注目を集めることになった。サーニヤに関する記事は、1月22日(土)に既に書いたが、その後も彼女の快進撃と人気は留まるところを知らない。サーニヤは1月に行われた全豪オープンでインド人女性で初めて3回戦まで進出し、続く2月に地元で行われたハイダラーバード・オープンで見事優勝。勢いは止まらず、現在開催中のドバイ・オープンでは全米オープン優勝者のスベトラナ・クズネツォワを破って3回戦まで進出したが、足首の捻挫もあって3回戦で惜しくも敗れてしまった。しかし、全豪オープンのときに163位だった世界ランクは、現在では77位。破竹の進撃という言葉がピッタリだ。しかも、まだまだ上を狙うことができそうな、期待の18歳である。
一方、サーニヤ・ミルザーのブレイクとほぼ時を同じくして、南インドからもう1人の若いスターが誕生した。インド人初のF1ドライバー、ナーラーイン・カールティケーヤンである。1977年1月14日タミル・ナードゥ州チェンナイ生まれのナーラーインは、フランスのエルフ・ウィンフィールド・ドライビングスクールに通い、15歳のときにレースデビューを果たした。ポルトガルGPやフォーミュラ・アジアなどに出場し、1996年にフォーミュラ・アジア・チャンピオンシップでインド人初の優勝を果たす。その後、F3で経験を積んだ後、2001年にはF1のテストドライバーとなり、遂に2005年2月に名門ジョーダンとドライバー契約を結び、念願のインド人初F1ドライバーとなった。そして今週末にオーストラリアのメルボルンで開催されたオーストラリア・グランプリが、ナーラーインのデビュー戦となった。結果は20人中15位。日本の佐藤琢磨(バー)の次だった。デビュー戦で15位という結果が果たしていいのか悪いのか、F1に詳しくない僕には分からないが、彼の活躍により、またひとつ、F1というモータースポーツがインド人の注目を集めることになった重要性は計り知れない。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
ナーラーイン・カールティケーヤン |
● |
ナーラーイン・カールティケーヤンは、ターター社、バーラト・ペトロリヤム社、JKタイヤ社など、インドの大企業とスポンサー契約を結んでいる。インド人の彼がF1ドライバーになれたのも、彼自身の才能というよりも、これらのインド企業の後押しがあったからだと言われているが、逆に言えば、F1ドライバーを輩出するくらいインドの経済力が世界で見逃せなくなってきたということだろう。ナーラーインは、上の写真のような顔をしているが、ちょっと好みの分かれそうな不思議な顔をしている。
ナーラーインのF1デビューをインド人の大半は応援したが、インド政府だけはちょっとご機嫌斜めである。彼らはどうもナーラーインがかぶっているヘルメットが気に入らないようだ。ナーラーインは、愛国心を表明するかのように、インドの三色旗をあしらったヘルメットを着用している。インドの国旗はサフラン色と白色と緑色の三色から成っており、中心に青色の車輪が据えられている。しかし、どういう理由か分からないが、インドではスポーツ選手が国旗の色を身に付けることを法律で禁じており、内務省がナーラーインの三色旗ヘルメット着用を禁止したというニュースが流れたのだ。そういえばインドのクリケット選手は、白色か青色しか着用していない。下の写真が問題のヘルメットである。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
問題の三色旗ヘルメット |
● |
上部には車輪、そして白とオレンジと緑をあしらった、完全にインドの国旗をモデルにしたヘルメットである。かぶらないなら僕にくれ、と言いたいくらい、インド好きの僕にとっては垂涎物のアイテムだ。しかしナーラーインは結局、「政府から直接指示を受けていない」との理由で、そのままそのヘルメットをかぶってレースに出場した。僕の予想では、インドのことだから、これと全く同じデザインのヘルメットが即座にオールドデリーのバイク街あたりで売り出されると思われる。そうだったら即買いである。
さて、ナーラーイン・カールティケーヤンはインド人初のF1ドライバーになったわけだが、果たしてアジア初のF1ドライバーは誰だろうか?調べてみたところ、それはタイ人だった。ビラボンセ・バヌテル・バヌバンド、通称ビラ王子は、タイの王室の生まれで、ミュージカル「王様と私」で有名なモンクット王の孫にあたる。当時はまだタイではなくシャムと呼ばれていた。1914年にバンコクで生まれたビラ王子は、13歳のときに英国に留学し、ケンブリッジ大学に進学すると同時にモーターレースに没頭するようになる。ビラ王子は1950年5月13日に英国シルバーストーンで行われたフォーミュラ・ワン・ワールドチャンピオンシップに出場し、5位に入賞する。その後も世界各地のF1レースに出場し、最高位は4位。1955年にリタイアし、1985年に英国で没した。ちなみに日本人で初めてF1ドライバーになったのは中島悟(1987年〜1991年)で、その後、鈴木亜久里、佐藤琢磨などと続く。
| ● |
|
● |
|
 |
|
|
ビラ王子 |
|
|
 |
|
| ● |
ビラ王子とT15
マシンのデザインが年代を感じさせる |
● |
F1のレースは、このオーストラリアGPを皮切りに、世界中で合計19レース行われる。日本の鈴鹿サーキットでのレースは10月9日である。ナーラーインが来シーズンもF1ドライバーでいられるかは彼の活躍次第だろうが、2005年が終わる頃にはインドでもF1が一般的なトピックとなっているかもしれない。テニスとF1、まだまだインドのスポーツ界は他にも各分野でスター選手を輩出して行きそうだ。と同時に、早くもクリケットの王座を危ぶむ声もちらほらと上がっている。この3月〜4月はインド対パーキスターンのクリケットの試合がインド各地で行われるが、パーキスターンに惨敗を喫するようなことがあると、クリケットはスポーツの独裁的帝王としての地位を急速に失うこともあるかもしれない。かつてホッケーがクリケットに王座を譲り渡したように。ただ、今のところテニスもF1も、庶民のスポーツからかけ離れているので、比較的手軽に遊べるクリケットはまだまだ安泰だろうと思う。僕としては、もっとインドのサッカーが強くなってくれれば、日本との試合もあるし、面白いと思うのだが・・・。
| ◆ |
3月10日(木) Socha Na Tha |
◆ |
今日は、PVRアヌパムで新作ヒンディー語映画「Socha Na Tha」を鑑賞した。「Socha Na Tha」とは、「考えてなかった」「思ってもみなかった」という意味。監督は新人のイムティヤーズ・アリー、プロデューサーはダルメーンドラ、音楽はサンデーシュ・シャンディリヤー。キャストは、アバイ・デーオール(新人)、アーイシャ・タキヤー、アプールヴァー・ジャー、スレーシュ・オーベローイ、ラティ・アグニホートリー、ディットー、サンディヤー・ムリドゥルなど。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
アバイ・デーオール(左)と
アーイシャ・タキヤー(右) |
● |
| Socha Na Tha |
ヴィーレーン・オーベローイ(アバイ・デーオール)は米国留学から帰国して以来、放蕩生活を送っていた。ヴィーレーンには3年間親に内緒で交際中のガールフレンド、カレン(アプールヴァー・ジャー)がおり、彼女と結婚しようと思っていたが、なかなかプロポーズできずにいた。一方で、両親はヴィーレーンのお見合い相手を探し始めていた。ヴィーレーンは適当にお見合いして適当に断ろうと考え、マルホートラー家とのお見合いをすることにした。ヴィーレーンのお見合い相手はアディティー(アーイシャ・タキヤー)という女の子だった。お見合いの席で2人っきりになると、2人はお見合いが馬鹿馬鹿しいイベントであること、またお互い結婚する気がないことを確認し合い、その後は打ち解けてお互いのプライベートなことを話し合う。ヴィーレーンは、なぜかアディティーの前で、今まで誰にも明かしていなかったカレンとの恋愛の悩みを打ち明ける。ヴィーレーンとアディティーの縁談は、2人の計画通り、まとまらなかった。その結果、オーベローイ家とマルホートラー家の仲は悪くなってしまう。
その後、2人は街で偶然再会する。未だにヴィーレーンはカレンにプロポーズできずにいた。ヴィーレーンは、カレンが本当に自分のことを愛しているのか分かりかねて悩んでいた。アディティーは、カレンが彼のことを好きかどうか確かめる提案をする。ヴィーレーンはアディティーをカレンに紹介する。3人は一緒にゴアへ旅行したりするが、次第にヴィーレーンはアディティーの方に惹かれていき、それと同時にカレンが嫉妬を感じ始める。アディティーはカレンの心に気付いていたが、鈍感なヴィーレーンは自分の中で何が起こっているか理解できなかった。
ゴアから帰った後もヴィーレーンはアディティーと出会いを重ねていた。それが家族にばれ、ますます両家の仲は悪くなる。同時に、ヴィーレーンは周囲の雰囲気に流されてカレンにプロポーズをしてしまう。カレンはプロポーズを受け容れるが、ヴィーレーンはなぜか心が晴れなかった。カレンはキリスト教徒、ヴィーレーンはヒンドゥー教徒で、この結婚は困難が予想されたが、ヴィーレーンはカレンの両親とも会って話をし、何とか結婚を認められる。ヴィーレーンの両親も、この結婚を受け容れる。
一方で、アディティーの結婚相手も決まった。相手は幼馴染みのマヘーシュだった。ヴィーレーンは居ても立ってもいられなくなり、わざとカレンの父親を怒らせて結婚を破談させ、アディティーの部屋に忍び込んで駆け落ちすることを提案する。だが、アディティーはそれを拒否した。ヴィーレーンはアディティーの家族に見つかり、家から追い出された上に、自分の両親からも絶縁される。だが、心を入れ替えたヴィーレーンは両親に謝り、父親の会社で真剣に働くようになる。
アディティーの婚約式が行われていた。カレンはアディティーを訪れ、「私からヴィーレーンを奪っておいて、別の人と結婚するのは許せない」と迫り、本当に好きな人と結婚するよう励ます。アディティーは婚約式を抜け出してヴィーレーンの勤める会社に直行する。ヴィーレーンは驚くが、アディティーと駆け落ちすることを決め、2人で遠くへ旅立つ。それを父親は温かく見守っていた。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
若い男女が、障害や困難を乗り越えて恋愛を成就させ、結婚に至るという、典型的なロマンス映画。まとめ方がいい加減だったが、観客の感情操作はうまく行われていた。こういう典型的インド映画を評価する際、最も重視しなければならないのは、ストーリーでもテクニックでも何でもなく、観客の感情をいかにうまく誘導して行ったかどうかにあると思う。その点では「Socha
Na Tha」は合格だった。
この映画では、お見合いで出会った男女が、一旦結婚を拒否しながらも、やっぱり惹かれ合い、最後には結ばれるという、少し捻った筋が一応の見所だと思うが、もっともよく描かれていたのは、主人公ヴィーレーンの迷走する不安定な感情である。ヴィーレーンは、3年間付き合っていたカレンと恋愛結婚するはずが、理想の女性アディティーとひょんなことから出会ったことにより本当の恋を知ってしまい、カレンへの感情は恋愛ではなかったことに気付く。「愛してない人と恋愛結婚してどうするんだ!」ヴィーレーンは自分に問い掛ける。しかしながら、カレンとの結婚は決まってしまい、どんどん後に引けなくなって行ってしまう。ヴィーレーンは、自分の感情がどうなっているのか、具体的にどうしたらいいのか分からずジタバタしている内に話がこんがらがって行き、アディティーやカレンの家族だけでなく、自分の家族にまで迷惑をかけ、終いには見捨てられてしまう。男というのは、自分で自分の感情があまり分かっていないものだ。恋愛結婚にしたって、男にとっては必ずしもその女性を心から愛しているから結婚するというものでもなく、もっと別の理由で結婚するということが多いのではないかと思う。男の感情の機微がよく描かれていたと感じた。
もうひとつこの映画の長所を挙げるならば、ヴィーレーンとアディティーの家族の人物設定がうまかったことだ。ヴィーレーンには両親の他、兄と兄嫁がおり、特に兄嫁が彼のよき理解者となっていた。一方、アディティーの両親は既に死んでいるという設定になっており、彼女は叔父の家族で育ってきた。祖母、叔父、叔母、従兄弟、従兄弟の嫁などがアディティーの家族であった。インドの大家族制をよく表しており、それぞれがどのような役割を果たしているのかもうまく描写されていた。しかし、カレンの家族はそれと比べると貧弱であった。
最後のまとめ方はこの映画の最も弱い部分だ。ヴィーレーンとアディティーは駆け落ちをしてしまうのだが、はっきり言って何の解決にもなっていないし、駆け落ちを両家がやすやすと認めるとは思えない。ストーリーの収拾がつかなくなって、無理矢理ハッピーエンドにしてしまったという感じだった。なぜかヒマーチャル・プラデーシュ州の山奥の村で2人が踊っているシーンが映し出された後にスタッフロールとなる。
ヴィーレーンを演じたアバイ・デーオールは、名前からも分かる通り、映画カースト、デーオール・ファミリーの新しいメンバーである。つまり、往年の名優ダルメーンドラの甥で、サニー・デーオール、ボビー・デーオール、イーシャー・デーオールらの従兄弟にあたる。特にボビー・デーオールと顔がそっくりである。個人的にボビー・デーオールの顔は好きではないので、あれと同じ顔がボリウッドにもう1つ増えたことにはショックを隠し切れない。演技もそれほどうまいとは言えず、ボビーと同じくアクション男優の道を歩むのではないかと思う。
この映画の中で最も輝いていたのは、アーイシャ・タキヤーである。アーイシャは「Taarzan」(2004年)でデビューした新人女優だが、元気はつらつとした魅力があり、これから伸びて行きそうだ。彼女の顔は、今までのインド映画女優で主流だった美人顔ではなく、日本の少女漫画に出てきそうなかわいい系の顔である。インド人の好みがだんだん変わってきていることを示しているのか、それともただ単純にダルメーンドラの好みだろうか。その一方で、カレンを演じたアプールヴァー・ジャーはどちらかというと美人顔に分類される顔であった。
細かいところを気にしなければ、まあまあ楽しめる映画である。だが、3年間付き合っていた彼女を捨てて、お見合い相手と結婚するというストーリーであるため、未婚のカップルで見るには適さない映画かもしれない。お見合い結婚した夫婦向けの映画と言えるだろう。
今日はPVRアヌパムで本日より公開の新作ヒンディー語映画「Karam」を見た。今週の火曜日からパンジャーブ州モーハーリーでインド対パーキスターンのクリケットのテストマッチ(5日間に渡る試合)が行われており、インド人の関心は映画よりもクリケットに向いているため、映画館やマーケットは金曜にも関わらずそれほど混雑していなかった。
題名の「Karam」にはいろいろな意味がある。一般に「業」と訳される「カルマ」の語源であり、「行動」とか「義務」とか「運命」とか、うまく当てはまる訳語は日本語にはなさそうだ。監督は「Kaante」(2002年)や「Musafir」(2004年)などのマフィア映画が得意なサンジャイ・グプター、音楽はヴィシャール&シェーカル。キャストは、ジョン・アブラハム、プリヤンカー・チョープラー、バラト・ダボールカル、ヴィシュワジート・プラダーン、シャイニー・アーフージャーなど。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
プリヤンカー・チョープラー(左)と
ジョン・アブラハム(右) |
● |
| Karam |
ジョン(ジョン・アブラハム)は殺し屋で、マフィアのボス、キャプテン(バラト・ダボールカル)の下で暗殺を請け負っていた。ジョンにはシャーリニー(プリヤンカー・チョープラー)という愛妻がいた。
ある日、ジョンは要人の暗殺の仕事をしたが、そのとき手違いで少女とその両親を殺してしまう。それがトラウマとなり、ジョンは暗殺者の仕事を辞めてシャーリニーと平和に暮らしたいと考えるようになる。ジョンはキャプテンにそのことを話すが、キャプテンは許さず、敵対するマフィア、ユーヌス(ヴィシュワジート・プラダーン)とその支援者4人を暗殺する仕事を課す。しかもキャプテンはシャーリニーを人質に取り、36時間以内に仕事の達成をしなければシャーリニーを殺すと脅した。ジョンはその警告を無視してシャーリニー救出に向かうが、もぬけの殻で、代わりにシャーリニーの左手小指が切り落とされて贈られて来る。ジョンはキャプテンの命令に従うしかなかった。
標的は、企業家、建設王、映画監督、警察幹部などの大物ばかりで、警備も厳重だった。ジョンはまずは映画監督を隙を見て殺害し、続いて企業化と建設王も罠にはめて同時に暗殺する。しかし、敏腕刑事ワーグ(シャイニー・アーフージャー)に追われ、信頼できる仲間も失ったジョンは、一計を案じてユヌスに投降する。ジョンはユヌスらと手を結び、キャプテンを暗殺する代わりにシャーリニー救出を助けてもらうことにした。ユーヌスの仲間である警察幹部の力でシャーリニー救出は成功する。だが、ジョンはそれと同時にユーヌスと警察幹部も殺害する。
逃げ出したジョンとシャーリニーは、キャプテンに追われる。ジョンは1人でキャプテンたちの手下を皆殺しにし、キャプテンも一騎打ちの末、殺害する。だが、そこへ駆けつけたワーグによりジョンは射殺される。シャーリニーはジョンの子供を妊娠しており、やがて出産する。シャーリニーは、ジョンの過失により孤児となった少女も引き取って、2人の子供の世話をしてジョンのことを思い出していた。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
映画のポスターに日本刀が映っていたので、てっきりインド製サムライ映画かと思っていた。ジョン・アブラハムの髪型も野武士みたいで似合っているのではと期待して見に行ったが、特に日本刀が重要なアイテムというわけでもない、普通のアクション映画だった。一応、クライマックスのジョンとキャプテンの一騎打ちでは、キャプテンが変なデザインの刀を振り回し、ジョンが鉄パイプで応戦するという戦いが描かれていたが、見所というほどのものでもなかった。だが、ジョン・アブラハムの「悲劇のアクション・ヒーロー」振りははまっており、精神年齢が低めの人のためのアクション映画として楽しめる作品である。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
インド製サムライ映画かと思った |
● |
最近人気爆発中のジョン・アブラハムは、血と汗と涙にまみれたダーティーヒーロー役がだいぶ板に付いてきた。彼の俳優としての魅力の源は、演技力というよりも激情力である。悩む!怒る!泣く!中途半端な感情の表現がない。とにかく映画の最初から最後まで、感情を発散しまくっている。それが彼の人気の秘密だと思う。そしてあの独特の髪型。おかっぱ頭と言えばいいのか、ツーブロックと言えばいいのか。既に彼の不動のトレードマークとなっているようで、どの映画でも同じ髪型をしている。それに加え、「Karam」ではこれまたおかしな仮想姿も披露して見せた。それが下の写真である。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
仮装したジョン・アブラハム |
● |
何を狙っているのかよく分からない仮装だが、面白いのでよしとしよう。
ヒロインのプリヤンカー・チョープラーも、だいぶ余裕と貫禄が出てきて、女優らしくなってきた。先日発表されたフィルムフェア賞にて、プリヤンカー・チョープラーは「Aitraaz」(2004年)で最優秀悪役賞を受賞しており、「魔性の女」を得意とする女優となっていきそうだが、「Karam」ではひたすら夫に尽くす健気な若妻を演じていて、演技の幅が広がっていることを感じた。プリヤンカー演じるシャーリニーの小指が切り落とされてしまうというプロットはインド映画にしてはグロテスクだったが、その後のシーンでは小指を折り曲げて包帯を巻き、指が切られたように見せかけていることがバレバレだったので、かえって痛々しくなくてよかった。インド映画では、ヒロインはたとえ交通事故に遭っても銃で撃たれても、少し入院しただけで五体満足のきれいな身体に復活するのが普通なのだ。ヒロインの特権と言えよう。
主役の2人以外で目立ったのは、刑事を演じたシャイニー・アーフージャー。先日見たばかりの印グリッシュ映画「Sins」で、猥褻神父役を演じていた男優である。「Sins」では大袈裟な演技をする男優だと感じていたが、「Karam」では脇役なのに主役に迫る迫真の演技をしており、好感が持てた。
この映画の一番の弱みは、主人公のジョンが、誤って少女を殺してしまったことにより、暗殺者を辞めることを決意する、という、あまりありえない筋である。暗殺者はゴルゴ13のように沈着冷静冷酷無比であるべきだ。ジョンのような激情的な人間は暗殺者に向かないし、少女を殺したくらいで自分の仕事に疑問を持つようなら、最初から暗殺者なんてやっていないだろう。そもそもジョンが暗殺者を辞めようとするところからこの話は始まるので、ジョンが辞める理由をもっと説得力のいくものにしてほしかった。
映画の冒頭は、なぜかアニメで始まる。アニメのジョン・アブラハムが見ものである。非常に稚拙なアニメだが・・・。映画とアニメの融合は、「Abhay」(2001年)や「Hum
Tum」(2004年)などで行われていたが、この「Karam」でのアニメの使われ方には全くメリットがなかった。
音楽では、「Tinka Tinka」が最も印象に残る曲だった。しかし、それほどミュージカル・シーンなどに趣向が凝らされておらず、アクション主体の映画であった。
「Karam」は、ジョン・アブラハムのファンは必見の映画。アクション映画としての出来も悪くはない。日本のヒーロー戦隊ドラマを見るような感覚で楽しめる映画である。
| ◆ |
3月12日(土) ミッタル会長、世界第3位の富豪に |
◆ |
インドはよく貧しい国だと言われるが、インドに住んでみると必ずしもそうでないと感じてくる。都市部ではスラム、路上生活者、乞食など、貧困が放り出されているし、農村部へ行けば原始時代みたいな生活を未だに送っている人々を目の当たりにすることができる。だが一方で、インドは日本人の想像を絶するほどの富豪が闊歩している国でもある。インドは貧富の差が極端な国であり、貧しい人はとことん貧しく、貧困から一生かかっても抜け出せない社会システムになっている一方、金持ちはとことん金持ちで、インド国内でマハーラージャーみたいな豪奢な生活をしたり、海外に移住して国際的な活躍をしたりするインド人も少なくない。インドの富豪がいかに富豪か、それを証明するデータが先日発表された。
3月10日、米フォーブス誌が恒例の世界長者番付2005年度版を発表した。1位は11年連続でマイクロソフト社のビル・ゲイツ会長(465億ドル)、2位は5年連続で投資家のウォーレン・バフェット氏(440億ドル)だったが、なんと3位に食い込んだのが、インド生まれ英国在住、ミッタル・スティール社のラクシュミー・ミッタル会長(250億ドル)だった。ミッタル・スティール社は世界最大の鉄鋼会社で、315億ドルの資産価値あると言われ、一社だけで全インドの産出量の2倍の鉄鋼を取り扱っているとされている。ミッタル会長は当然のことながら、インド最大の富豪としても知られているが(英国在住だが国籍はインド)、世界第3位の富豪にまでなるとは、インドの貧富の差の極端さを感じずにはいられない。ラクシュミー・ミッタル会長の伝説で最も有名なのが、愛娘ヴァニーシャーの結婚式である。結婚式は2004年6月にフランスで5日間に渡って行われ、「世界で最も豪華な結婚式」と表現された。婚約式や結婚式の会場は、ヴェルサイユ宮殿やヴォー・ル・ヴィコント城など、フランスを代表する名所旧跡。ゲストは世界中から1000人以上が呼ばれ、アイシュワリヤー・ラーイやシャールク・カーンなどのボリウッド・スターたちも駆けつけた。結婚式の余興に行われた1時間に渡る演劇は、ラクシュミー・ミッタル会長夫妻も出演したが、その裏方はそれだけでボリウッド映画が1本撮れてしまう顔ぶれ――脚本はジャーヴェード・アクタル、音楽はシャンカル・マハーデーヴァン、振り付けはファラハ・カーン――だった。この結婚式にかかった総費用は6千万ドルと言われている。花嫁のヴァニーシャーは父親に、「パパ、あれも買ってちょうだい」とエッフェル塔を指差したとかしなかったとか。この世界最大の結婚式は、ミッタル会長の資産力と、インドにまだ残っている結婚式を派手に行う風習が融合したからこそ実現した出来事だろう。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
ラクシュミー・ミッタル会長 |
● |
ラクシュミー・ミッタル会長を含め、今年のフォーブス誌の世界長者番付全691人中、ランクインしたインド人は12人だった。
| 順位 |
名前 |
会社名 |
推定資産 |
| 3 |
ラクシュミー・ミッタル |
ミッタル・スティール |
250億ドル |
| 38 |
アズィーム・プレームジー |
ウィプロ |
93億ドル |
| 60 |
アンバーニー兄弟 |
リライアンス・グループ |
70億ドル |
| 149 |
クマール・ビルラー |
アディティヤ・ビルラーグループ |
37億ドル |
| 164 |
スニール・ミッタル |
バールティー |
33億ドル |
| 170 |
パッロンジー・ミストリー |
ターター・サンズ |
32億ドル |
| 272 |
シヴ・ナーダル |
HCLグループ(インフォテック) |
23億ドル |
| 355 |
アーディ・ゴードレージ |
ゴードレージ・グループ |
19億ドル |
| 437 |
ナレーシュ・ゴーヤル |
ジェット・エアウェイズ |
15億ドル |
| 437 |
ディリープ・シャングヴィー |
サン製薬 |
15億ドル |
| 488 |
アニル・アッガルワール |
ヴェーダーンタ・リソーシズ |
14億ドル |
| 548 |
オーム・ジンダル |
ジンダル・グループ |
12億ドル |
第60位のムケーシュ&アニル・アンバーニー兄弟は、父親ディールーバーイー・アンバーニーの死後、グループの主導権を巡って兄弟喧嘩をしていることで話題になっている。ディールーバーイー・アンバーニーはガソリンスタンドの見習いから一代でインド随一の大富豪にのし上がった大事業家だったが、その息子たちは愚かなことに、父親の築いた財産を巡って骨肉の争いを繰り広げている。ムケーシュとアニル、それぞれを政界、経済界、映画界などの著名人が自分の利害観念に従って後押ししていることが、感情的な兄弟喧嘩をさらに複雑なものとしている。半年ほど前に兄弟間の確執が明らかになり、その後いろいろ報道されていたが、今でもまだ完全に決着は着いていないと思われる。大企業だと思って調子に乗って内紛を続けていると、急成長した企業だけにすぐに潰れてしまうこともありえないことではない。アンバーニー家の兄弟喧嘩を見ていると、ムガル王朝で毎度のように兄弟間で繰り広げられた王位継承紛争を思い出す。
これに比べ、ランクインした日本人の最高位は、サントリーの佐治信忠社長(58億ドル)の77位。アイフルの福田吉孝社長(56億ドル)が80位でそれに続き、武富士の武井保雄前会長(55億ドル)が84位。これら3人が100位以内に入り、691人中24人が日本人となった。これらの推定資産額でものを語るのも馬鹿馬鹿しいが、簡単に言ってしまえば、日本はインドよりも富豪の数は多いが、富豪の規模は小さい、ということになるだろうか。インドの貧富の差を見てしまうと、中産階級ばかりになってしまった日本が共産主義国に思えてくるものだ。ちなみに韓国人の最上位は、サムスンの李健煕(リー・クンヒー)会長(43億ドル)の122位、中国人の最上位は、CITICパシフィックの栄智健会長(16億ドル)の413位、香港人の最上位は、ハチソン・ワンポアの李嘉誠会長(130億ドル)の22位、台湾人の最上位は、鴻海グループのテリー・ゴウ会長(32億ドル)の170位、シンガポール人の最上位は、豊隆グループの郭令明会長(40億)の138位、タイ人の最上位は、チャロン・グループのチャロン・シリヴァダナバクディ会長(30億ドル)の194位、マレーシア人の最上位は、ロバート・クォク・グループの郭鶴年会長(50億ドル)の94位。ランクインの数は、韓国人が3人、中国人が2人、香港人が15人、台湾人が7人、シンガポール人が4人、タイ人が3人、マレーシア人が6人。それらと比べても、インド人の富豪の数と規模がアジアの中で圧倒的存在感を持っていることを表している。総合的に見れば、インドはアジアの中で日本や香港と肩を並べるほど、大富豪を擁する国となったと言える。
| ◆ |
3月14日(月) エノス・エッカはどこだ? |
◆ |
ここ最近、インドで少なくとも4つの州が政治的に不安定な状態にある。2月に州議会選挙が行われたハリヤーナー州、ビハール州、ジャールカンド州(3州とも開票は2月27日に一斉に行われた)と、奇妙な政権交代が起こったゴア州である。インドの政治の話題は、英語の略称がたくさん出てくるのでややこしいが、なるべく分かりやすくまとめてみた。
ハリヤーナー州の州議会選挙では与党インド国民党(INLD)が惨敗した代わりに、野党国民会議派が全90議席中67議席を確保して圧勝した。ここまでは明白な政権交代で何の混乱もなかったが、国民会議派幹部が、以前国民会議派が政権を担っていたときに州首相を務めていたバジャン・ラールを再度州首相に就任させず、代わりにブーピンダル・スィン・フーダーを新州首相に就任させたことによりトラブルが起きた。フーダーの州首相就任が発表されるや否や、ハリヤーナー州ではバジャン・ラール支持者による暴動が発生したが、現在では事態はほぼ収拾されている。ハリヤーナー州における国民会議派の圧勝は、選挙ごとに与野党が交替するというインドの選挙の慣習もその原因だが、一番の原因は同州が農業州から工業州へと変貌してきたことによると見られている。国民会議派は中産階級の支持を集める傾向にあり、中産階級の拡大が進むハリヤーナー州では自然と国民会議派の支持も拡大していった。また、過去3回州首相を務めたベテラン政治家バジャン・ラールが州首相から外され、ブーピンダル・スィン・フーダーが新しく州首相に選ばれたのは、ハリヤーナー州やその周辺の州で影響力の強いジャート族の支持を集めるためだと見られている。フーダーはジャート族の新しいリーダーとして台頭して来た政治家である。
ゴア州では、1月29日に与党インド人民党(BJP)の議員3人が同時に辞表を提出したことにより、政権運営が危機に陥った。元々ゴア州は国民会議派がずっと政権を担ってきた州だったが、BJPの政治家マノーハル・パニッカルは国民会議派の内紛に乗じ、2000年10月に政権を奪取して州首相に就任し、2002年6月には州議会を故意に解散して、中央政府の国民民主連合(NDA)政権の威光を借り、より安定した政権を確保した。ところが、2004年の下院選挙でNDAが敗北し、中央政府が国民会議派政権に代わってしまったことにより、誤算が生じた。国民会議派が与党となったことにより、ゴア州の州知事はBJPのケーダールナート・サハーニーから、国民会議派の息のかかったSCジャミール(ナガランド出身)になってしまった(州首相は州議会議員から選出され、実権を持つ。州知事は中央から任命され、実権はほとんどないが、有事には重要な役割を果たす)。BJP議員の同時辞任が野党の計略であることは明らかであり、州議会内で政権支持議員は全40議員中18人に減ってしまった。一方、野党は19議員の支持を受けていることを発表した。インドでは中央政府でも州政府でも、政権運営のため、議会で「vote
of confidence」とか「floor test」と呼ばれる、議員による投票を行わなければならない。普通は選挙の後に行われ、組閣の支持を受けた政権は数日以内に、政権が議員の過半数の支持を受けていることを議会で投票により証明しなければならない。だが、この過半数支持の証明は要求があればいつでも行われなければならない。BJP議員の辞任によりゴア州政府には過半数支持の証明を再度行う義務が生じたが、それは困難だった。これを受け、JCジャミール州知事は2月2日にマノーハル・パニッカル政権の解散を命じた。同日、国民会議派のプラタープ・スィン・ラーネーが新しい州首相に任命され、1ヶ月後の3月2日にラーネー政権による過半数支持の証明が行われたが、これまた詐欺臭いものだった。この1ヶ月間、いろいろゴタゴタがあり、3月2日の時点で投票権を持つ議員は33人いた。つまり17人以上の支持を受ければ政権は成立することになる。だが、事前の予測によると、33人の内、政権支持議員は16名、反対議員は17名だった。一見すると、過半数支持の証明は失敗する。ところが、国民会議派が任命したフランシスコ・サルディンハー臨時議長は、過半数支持証明当日に難癖を付けて野党議員1名の投票権を奪い、その結果、政権の支持者と反対者の数は16対16で拮抗してしまった。引き分けとなったことにより、臨時議長が一票を投じることになり、サルディンハー臨時議長は当然のことながらラーネー政権支持の票を投じた。こうして、ラーネー政権が支持された形となった。まさにウルトラCの政治だが、この過程を不適切だと考えた中央政府は、ゴア州を大統領直轄にしてしまった。つまり州議会は機能を停止した。
ビハール州の州議会選挙では、ラールー・プラサード・ヤーダヴ率いる与党国民党(RJD)、ラーム・ヴィラース・パースワーン率いる人民力党(LJP)、そしてBJPと統一人民党(JD(U))のNDAの三つ巴の争いとなった。その結果は、敗北者だけがいて勝者がいないという、荒廃したものとなった。ビハール州議会の総議席数は243議席。その内、RJDは75議席、BJPは37議席、JD(U)は55議席、LJPは29議席、国民会議派は10議席などとなった。即座に国民会議派はRJD支持を打ち出した。BJP+JD(U)のNDAは92議席、国民会議派+RJD+CPIは88議席。これらに、無党派議員や左翼政党の議員が加わるが、それでも両方とも過半数122議席には達することはできない。つまり、簡単に言えば、LJPが味方した連立政党が勝つという結果になり、LJPは「キング・メーカー」と呼ばれるようになった。RJD、LJP、国民会議派は中央政府で統一進歩連合(UPA)と呼ばれる連立政権を組んでおり、もしこれらの政党がビハール州でも連立政権を組めば話は早かったのだが、実はラールー・プラサード・ヤーダヴとラーム・ヴィラース・パースワーンは犬猿の仲で、パースワーンはRJDに協力しないことを明言し、それを押し通した。かといって、彼はJD(U)から分離独立したとという過去があり、NDAとも手を組む積もりはない。よって、どの連立政党も議会内で過半数の支持を受けることができず、結局ビハール州はゴア州に引き続き3月7日に大統領直轄となってしまった。これにて、15年の長きに渡ってビハール州に君臨したラールー・プラサード・ヤーダヴの政権にひとまず終止符が打たれた。もし1人、ビハール州の州議会選挙に勝者がいるとするならば、それはLJPのラーム・ヴィラース・パースワーン党首であろう。カースト別統計を見ると、LJPは新しい政党だが、上層カースト、クルミー(農民)カースト、ダリト(不可触民)、ムスリム、OBC(その他の後進カースト)など、各カーストから満遍なく支持を集めており、これからさらなる成長が見込まれている。依然としてRJDはヤーダヴ族の強い支持を集めており、BJPの票田は上層カーストやクルミー・カーストとなっているが、LJPの出現によりどちらの政党も支持母体が減少している。
さて、ここまでは前置きで、今回最も面白い動きを見せたのが、ジャールカンド州であった。ジャールカンド州議会の総議席数は81議席。その内、BJPは30議席、ジャールカンド解放党(JMM)は17議席、国民会議派は9議席、RJDは7議席、JD(U)は6議席、全インドフォワードブロック(AIFB)は2議席、全ジャールカンド学生連合(AJSU)は2議席、統一ゴア民主党(UGDP)は2議席、ジャールカンド党(JKP)は1議席、ナショナリスト会議派(NCP)は1議席、インド共産党マルクス・レーニン主義解放派(CPI(ML)(L))は1議席、無党派は3議席となった。この内、BJPとJD(U)は連立政党NDAを組んでおり、合計36議席を確保、JMMと国民会議派とRJDも連立政党UPAを組んでおり、合計33議席を確保。つまり、過半数の41議席を確保するには、どちらの連立政党も、非連立政党派の12名の議員を取り込むことが必須となった。ナンバーゲームの始まりである。どちらも動きは早かった。3月1日、NDAもUPAもほぼ同時に、過半数の支持を集めたことを主張して組閣を宣言した。NDAが41名の支持議員のリストをサイヤド・シブテー・ラズィー州知事に提出したのと同じ日に、UPAも41名の支持議員のリストを提出したのだ。どちらも41名の支持議員のリストを提出したので、合計すると議員の数が82人になってしまう。誰かどちらのリストにも載っている議員がいる!それが、ジャールカンド党のエノス・エッカ議員だった。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
エノス・エッカ議員 |
● |
このようなおかしな状況が起こったわけだが、ラズィー州知事は国民会議派の人間だったため、UPAに対して組閣の命令を出した。州知事の命令を受け、3月2日、JMMのシブー・ソーレーンがジャールカンド州の州知事に就任した。ところが、NDAがそれを黙って見過ごすわけがない。BJPのアードヴァーニー党首は、国会議事堂や州知事官邸前でジャールカンド州の5人の非連立政党議員を引き連れてパレードを行った。既にNDAだけで36議員いるので、これに5人の非連立政党議員が加われば41人となる。当初、ソーレーン州首相に与えられた過半数支持の証明の期限は3月21日だったが、アブドゥル・カラーム大統領の指示により、期限は15日に繰り上げられた。しかも、3月9日には最高裁判所が政治に介入し、期限をさらに11日に繰り上げた。このような状況の中で注目を集めたのが、前述のエノス・エッカ議員だった。エッカ議員は地元のキリスト教部族を代表する、36歳の無名の新人議員だったが、NDAとUPAのナンバーゲームに巻き込まれた結果、突如としてインドで最も有名な州議会議員になってしまった。おそらくUPAは、まずは組閣をして、それからゆっくり大臣職をちらつかせてエノス・エッカ議員を説得しようと思っていたのだろう、だが、大統領と最高裁判所の介入により、時間がなくなってしまった。UPAは必死にエノス・エッカ議員にコンタクトを取ろうと試みたが、NDAは他の4人の非連立政党議員と共にエノス・エッカをどこかに隠してしまった。こうして、インドの新聞に「エノス・エッカはどこだ?」との見出しが躍るようになったわけだ。噂では、エノス・エッカ議員はラージャスターン州ジャイプルの、とあるリゾート・ホテルで、国賓級の待遇を受けていたとか。ジャールカンド州の田舎出身議員が、突然のバラ色生活である・・・。結局、NDAによる巧みな妨害工作が功を奏し、3月11日にシブー・ソーレーン州知事は過半数支持の証明を行うことができず、UPA政権は10日で崩壊した。代わってBJPのアルジュン・ムンダーが州首相に就任した。当然のことながら、エノス・エッカら非連立政党議員は、5人とも大臣に就任した。
ところで、3月13日付けのサンデー・エクスプレス紙に、面白い記事が載っていた。エノス・エッカ議員の手記というスタイルのフィクション記事である。原文の雰囲気を忠実に訳してみた。
| エノス・エッカのインクレディブル・インディア! |
ジャールカンドのこと、TVで見ただろ?まるでヒンディー映画みたいさ。カーチェイスしたり、ヘリコプターに乗ったり、かくれんぼしたり、サスペンスあり、ドラマあり・・・全くもって映画だね。アレー・バーバー、何て言うか、オイラはすっごくエキサイトしちまったよ。アルジュン・ムンダーさんは今や州首相さ、そんでもってオイラ、エノス・エッカは大臣さ。ほら、オイラたちは41人、ムンダーさんと苦楽を共にした41人。でもよ、誰がホントのヒーローだと思う?ちょっと当ててみなよ。そう、オイラ、エノス・エッカさ。今や大臣だぜ。ついこの前まではコーレービラー選挙区のちっぽけな州議会議員のことなんか誰も知らなかった。今や全インドがオイラの名前を知ってるんだぜ。最初はみんな言ってたもんさ、「エッカで誰だ?」って。それが今や、「エッカはどこだ?」だからな。みんなはオイラを探すために警察まで出動させたんだぜ。TVはオイラの顔写真を放送してたし、みんなオイラが誰を支持するか知りたがったのさ。
アレー・バーバー、オイラ前から言ってるだろ、オイラはアルジュン・ムンダーさんを支持してるのさ。何度も何度も言っただろう、「オイラはNDAを支持してるんだい」って。でもみんな信じてくれないんだ。みんなオイラに質問し続けるんだ。で、オイラは答え続けるんだ。アレー・バーバー、単純なことさ。ほら、オイラ、あんたに言ってるだろ、ムンダーさんはソーレーンさんよりも頼もしい人なのさ。アレー・バーバー、ムンダーさんはいつでも頼りがいがあるのさ、オイラはムンダーさんを信じてるのさ。なぜってムンダーさんはオイラのためにコーレービラーにヘリコプターを送ってくれたんだぜ。そのヘリコプターに乗ってオイラは州都ラーンチーまで行ったのさ。アレー・バーバー、とってもスリリングだったぜ。プルプルプル・・・風の中に飛び立って、そんでもって降り立ったんだ、まるでヒンディー映画さ、そんでたくさんの人たちがオイラを迎えに来てくれたのさ、まるでヒーローさ、そう、まるでアクシャイ・クマールさ。そんでもってムンダーさんはオイラを大臣にしてくれたんだ。ムンダーさんは言ったことを実現してくれるのさ。
最初からムンダーさんだけがオイラのことを面倒見てくれたのさ、ガンマンがオイラを守ってくれたのさ、24時間。24時間付きっ切りだぜ。まるでヒンディー映画の中にいるみたいだったさ、エノス・エッカ、ヒーローNo.1ってな。ムンダーさんたちはオイラを豪華なバスに乗せてくれて、それで空港まで行ったんだ。そのとき、ステファン・マランディーさん(UPA支持議員)がオイラを探しに来たんだ。「エッカはどこだ?」って。マランディーさんは飛行機の中に入ってきて、椅子の下まで見てオイラを探したんだ。でもオイラはトイレに隠れてたから、マランディーさんはオイラを見つけられなかったのさ。とってもスリリングだったよ。そんでムンディーさんが言ったんだ、オイラたちはクオリス(トヨタ車)とスモー(ターター車)で見知らぬ場所へ行くって。オイラはワクワクしたね、なぜってオイラ、新しい場所に行くことができるからね。オイラ考えてたよ、多分行くのは外国だろう、ネパールだろうか、それともバングラデシュだろうか、とかね。まずは西ベンガル州のドゥルガープルへ行ったんだ。でも西ベンガル州警察が捕まえに来るってんで、今度はチャッティースガル州へ行ったんだ。その後、突然オイラはオリッサ州のブバネーシュワルへ行くことになったんだ。オイラ、旅行を楽しんでたけど、正直ちょっと疲れたよ。
それからオイラは飛行機に乗せられてデリーに来たんだ。アレー・バーバー、オイラは見ての通り田舎者さ、でもデリーじゃみんなオレを歓迎してくれたんだ、まるでオイラ、アミターブ・バッチャンになったみたいだったよ。みんな次から次へとオイラに花輪をかけてくれて、ラッドゥーやらグラーブ・ジャームンやらバルフィーやらいろんなミターイー(お菓子)をオイラの口の中に押し込んで来たのさ。でも悪い気分はしなかったさ、オイラ楽しかったよ。そんでオイラはグジャラート・バヴァンにいることになったんだけど、そこは何しろピュア・ヴェジタリアンだろ。オイラ、チキンを食べたかったんだけどな。でも、オイラ、大統領官邸はすっごく気に入ったよ。大統領官邸はひたすら大きくて、ひたすら大きな門があって、ひたすら大きな護衛がいて、ひたすら大きなライトがあって・・・。オイラ、大統領にナマスカールしたよ、大統領はオイラに微笑んでくれたよ。そんでオイラ、TVに映されることになったんだ。オイラ、TVに映ったよ、まるでアクシャイ・クマールさ。その後、オイラはTVを見たんだ、すると、アレー、オイラの女房がTVで泣いてるじゃないか、オイラが行方不明だって泣いてるよ。オイラとっても悲しくなっちゃったよ。でもムンダーさんはとってもとってもナイスな人さ。ムンダーさんは親切にも、オイラの家族を秘密の家に住まわせてくれたんだ、これでTVの人もオイラの家族と話すことができなくなったってわけさ。
正直言って、大統領官邸の滞在が一番よかったな。トップクラスさ。食べ物もうまいし、時々チキンやマトンも出て来たんだぜ。オイラたちは、ヴァスンダラー・ラージェーさん(ラージャスターン州の州首相)の誕生日会にも行ったんだよ。ケーキとゴール・ガッパーを食べまくったね。オイラたち、いっぱいいっぱい観光したよ、きれいな宮殿や豪華なリゾートを見たよ。まさにファイブ・スターの旅行だったね。ヴァスンダラーさんはマハーラーニーだけど、オイラ、エノス・エッカはマハーラージャーになった気分だったよ。ジャイプルじゃあオイラはショッピングしたんだ。で、ラヴィ・シャーストリー(元クリケット選手・現解説者)さんがクリケットのTVで付けてるようなサングラスを買ったのさ。そんでオイラ、自分のためにかっこいいシャツを買って、家族のためにいろんなプレゼントを買ったんだ。だから言ったろ、ムンダーさんはとっても頼りがいがあるって?
でもひとつ言いたいことがあるんだ。ラージャスターンの大臣さんたちがオイラの世話や護衛をしてくれたのはいいんだけど、でもどうしてヴァスンダラーさんは床屋や便所にまでオイラの護衛をさせたんだろうね?みんなオイラのこと面倒見すぎて、ときどきオイラ、鳥かごの中の鳥のように思えちゃったよ。あ、別に不平言ってるわけじゃないぜ。ただ言ってるだけさ。少なくともトイレの中くらいプライベートでいたいだろ?
とにかく、オイラが大臣になるとこ、TVで見てただろ?オイラ、とってもエキサイトしてるよ。オイラはエノス・エッカ、ヒーローNo.1、大臣、そしてあんたのための州議会議員さ。 |
インディアン・エクスプレス紙(サンデー・エクスプレスは同紙の日曜版)はけっこう硬派な新聞だと思っていたのだが、こんなふざけた記事も載せるようだ。だが、エノス・エッカがどんな「バカンス」を楽しんだのか、よく分かった。本当に彼がこんな田舎丸出しの人間なのかは知らないが・・・。
ひとまずジャールカンド州の紛争はNDAが勝利を収めたわけだが、まだ問題が残っている。それは反脱党法の存在である。実はエノス・エッカ議員が所属するジャールカンド党はUPA支持を表明していた。反脱党法によると、議員は、選挙時に所属していた党の方針に従わない場合、議員資格を剥奪される。よって、NDAには、ジャールカンド党のNEホーロー党首を説得してNDAに引き込むという大仕事が残っている。また、ジャールカンド州の州政府では12人まで大臣を設置することが認められているが、NDAは政権確保のために非連立政党議員や少数政党議員に大臣の地位を与えて味方に引き込んだため、既にその内の6〜7人がNDA以外の議員に占められてしまっている。これも大きな問題である。
それにしても、エノス・エッカを巡るNDAとUPAの争いは、まるで子供の喧嘩のようだ。インドの政治は傍観していると非常に面白い。
| ◆ |
3月17日(木) Chai Pani Etc |
◆ |
今日は新作ヒングリッシュ映画「Chai Pani Etc」をPVRアヌパムで見た。「Chai」とはお馴染み砂糖とミルクがたっぷり入ったインドの紅茶のこと。「Pani」とは水のこと。「Etc」は英語のエトセトラだ。監督はマヌ・レーワル。キャストは、ザファル・カラーチーワーラー、コンコナー・セーンシャルマー、ガウラヴ・カプールなど。コンコナー・セーンシャルマーがダブルロール(1人2役)で出演しているので注意。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
ザファル・カラーチーワーラー(左)と
コンコナー・セーンシャルマー(右) |
● |
| Chai Pani Etc |
サティヤ(ザファル・カラーチーワーラー)は米国で映画を学んで帰国したインド人。政府系のTV局、バーラトTVと契約し、ジャイサルメールのドキュメンタリー映画を撮ることになった。サティヤは昔からの恋人ラーダー(コンコナー・セーンシャルマー)、親友ハリーシュ(ガウラヴ・カプール)らと再会し、またラーダーの大学時代のクラスメイトのシャーンティ(コンコナー・セーンシャルマー)とも出会う。だが、サティヤが帰国した途端、ラーダーは奨学金を取得し、すぐにロンドンへ行くことになってしまった。
サティヤは撮影許可を取るために政府官庁を訪れるが、たらい回しにされた挙句、賄賂を要求される。曲がったことが嫌いだったサティヤは怒るが、何とか上からの人脈を利用して許可を取得した。すぐさまサティヤは撮影隊を引き連れてジャイサルメールへ行く。トラブルの連続だったが、何とか撮影を終えた。ちょうどジャイサルメールでボランティア活動をしていたシャーンティとも再会する。
デリーに戻ったサティヤは、今度は検閲に苦労する。サティヤはジャイサルメールの城塞や街の美しさと共に、ゴミ捨て場でゴミを拾う子供など、投げ出された貧困も正直に映像にした。だが、政府はそれを気に入らず、カットするよう要求した。さらに悪いことには、以前サティヤに賄賂を要求したオフィサー、バクシーが出世しており、検閲を取り仕切っていた。
だが、朗報もあった。サティヤの撮影したドキュメンタリー映画がフランスの国際映画祭に出品されることが決まったのだ。だが、政府はカットをしなければ認可を出さないと言って聞かなかった。仕方なく、サティヤは父親のコネを使って大臣に会い、映画の認可を出すことに協力してもらう。喜び勇むサティヤだったが、その帰りの自動車の中で、内閣が解散されたとのニュースを聞く・・・。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
デリーとジャイサルメールが舞台となり、コンコナー・セーンシャルマーがダブル・ロールに挑戦し、米国から帰国したインド人がインドを舞台にしたドキュメンタリー映画を撮影するという筋だったが、この映画のメインテーマは、インドの官僚に浸透したどうしようもない汚職体質と怠慢体質の描写と検閲制度への批判であった。
撮影許可をもらいに政府官庁を訪れるサティヤだったが、「ボスは今いない」とか「ボスは忙しくて会えない。また来い」と冷たくあしらわれる。ボスは実はいることを突き止めたサティヤが部屋に入ると、ボスのバクシーは居眠りをしていた。バクシーはサティヤに聞く。「チャーイ飲む?それとも水にする?」サティヤは何もいらないと答える。バクシーは撮影許可について話を始める。まずバクシーは「許可が出るには3ヶ月かかる」と切り出す。サティヤが「バーラトTVからは4ヶ月の期限しかもらっていない」と抗議すると、バクシーはよく分からない寄付金の話を始め、5000ルピーの賄賂を要求する。サティヤは怒って部屋を後にする。その他にも、オフィスの部屋に鳩が巣を作っていたり、黙々と編み物をするおばさんオフィサーがいたり、4時になってもランチタイムが終わらなかったりと、インドの官庁によくある風景が忠実に再現されていて、観客は大受けしていた。オフィスだけではない、他にもインドの駄目な点がさらに鋭い視点で描かれていた。例えば、「ここでパーン(噛みタバコ)を吐くのは禁止です」と書いてある注意書きの下にパーンを吐いた跡がたくさん付いてたり、レストランのメニューに載っている料理のほとんどが品切れ中だったり、大雨が降ると雨漏りやら床上浸水が始まったり、インドにしばらく滞在したことがある人なら誰でもニヤリとするような、インドのどうしようもない部分を強調する出来事がいっぱいあった。エキスポなどの展示品が闇で流されている事実も暴かれていた。類似の映画としては、カールギル紛争で死んだ息子の慰謝としてガソリンスタンドを手に入れるまでの汚職との戦いを描いた「Dhoop」(2003年)が思い浮かんだ。
検閲に関しては、サティヤにはあまり同情できなかった。サティヤは政府のTV局からジャイサルメールを舞台にしたドキュメンタリー映画を依頼されたにも関わらず、ジャイサルメールの負の部分まで映し出し、当局から不必要な部分のカットを要求される。もし自費で制作しているならどういう映画を作ってもいいだろうが、政府から依頼されたなら、政府の指示通りの映画を作るのが監督の役目ではなかろうか?検閲に対する批判というテーマはちょっと的外れだった。
最後に、せっかく大臣に検閲なしで認可を出してもらう約束をこぎつけたのに、その日に内閣が解散してしまうというオチは、いかにもインドらしくて笑った。インドはひとつの困難を乗り越えると、新たな困難がすぐに現れるものだ。だが、サティヤの顔に悲壮感はなかった。最初はインドの独特のシステムに溶け込めなかったサティヤも、このときには既にインドのシステムの中に取り込まれていたのだ。ひとつの扉が閉じたら、別の扉が開く、というのもインドで生活する上での常識である!
ジャイサルメールは魔法の都だ。ジャイサルメールという単語を聞いただけで鳥肌が立つくらいの不思議な魅力がある。ジャイサルメールが出てきた映画は、「Meenaxi:Tale
of 3 Cities」(2004年)や「ハリ・オム」(2004年)などが思い浮かぶが、どれも好印象だ。この映画も、ジャイサルメールの美しさが存分に活かされていた。一方、デリーの名所もけっこう映っていた。大統領官邸、ラージ・パト、フマーユーン廟、フィーローズ・シャー・トゥグラク廟(ハウズ・カース)、カーン・マーケットなどが特定できた。デリーのロケではよく大統領官邸からインド門に通じる大通りラージ・パトが出てくるのだが、普通はあまり通らない道路であり、映画に出てくると多少違和感を覚える。ラージ・パトがよく出てくるのは、おそらくデリー政府がラージ・パトしか道路上の撮影許可を出さないからだろう。
コンコナー・セーンシャルマーが1人2役に挑戦していたが、僕にはダブル・ロールをする必要性が全く分からなかった。彼女が演じたラーダーとシャーンティは、特に双子という設定でもなく、ただの大学のクラスメイトだった。おかげで大いに混乱した。それだけでなく、サティヤ、ラーダー、シャーンティの関係自体も実に曖昧だった。サティヤとラーダーは恋人だったのだが、ラーダーはロンドンへ留学してしまう。ラーダーはサティヤに、毎土曜日電話をするよう約束させるが、いざサティヤが土曜に電話をすると、ラーダーはいつも家にいなかった。実はラーダーは英国でちゃっかり新しい彼氏を作っていた。サティヤも負けてはおらず、シャーンティと恋仲になっていた。ある日、ラーダーはサティヤに電話をする。「ごめんなさい、私たちもう別れましょう。」サティヤは答える。「男が出来たのか?いつからだ?」ラーダー「あなたには関係ないわ。」サティヤ「オレも実はシャーンティと付き合ってるからな。」ラーダー「何ですって?いつから?」サティヤ「お前には関係ない。」ラーダー「信じられない!男はみんな同じね!」ガチャ。・・・下手な三流ドラマよりも下手な演出である・・・。苦笑が漏れた。
ヒングリッシュ映画なのでミュージカル・シーンなどはなかったが、いくつか歌の入ったBGMが流れていた。印象的だったのはムハンマド・イクバール作「Sare
Jahan Se Achchha Hindostan Hamara」のモダン・バージョン(とても言うべきか)だった。この音楽と共にサティヤはラージ・パトを自動車で走行していた。
言語は7〜8割が英語。いかにも英語が分からなそうな人との会話はヒンディー語となっており、非常に現実的なダイアログだった。あと、サティヤが着ていたクルターなどの服のほとんどは、デリーを代表する服飾店ファブ・インディア製だった。見た瞬間からファブ・インディア製だと思っていたが、一瞬チラッと襟の裏のタグが見えたので、ファブ・インディア製であることが確実になった。僕もファブ・インディアの服はよく着ている。
いろいろストーリー的、技術的に弱い部分もある映画だが、インド在住の外国人、またはデリーやジャイサルメールの観光をしたことがある人にはオススメの映画である。インドの駄目な部分と美しい部分が対照的に描き出されていてよかった。
| ◆ |
3月18日(金) ドッキリTVでボリウッド大激震 |
◆ |
先日公開された「Page3」という映画で、ボリウッドで女優を目指す女の子が、プロデューサーから配役の代わりに肉体関係を求められる、というシーンがあった。「Main
Madhuri Dixit Banna Chahti Hoon」(2003年)でもそういうシーンがあった。ボリウッドで一花咲かせようとする若い女性は、女性だけなくときに男性も、きれいごとだけでは立身出世をすることができず、権力のある人間に身体を売って人脈を作り、役を手に入れなければならない――それは昔から言われてきたことだし、何もインドに限ったことではなく、日本でもハリウッドでもあることだろう。そのような行為を英語では「キャスティング・カウチ(Casting
couch)」と呼ぶ。カウチとはソファーのことで、つまりはソファーの上で新人俳優と監督・プロデューサーの間で交わされる出演契約のことである。
3月13日、スキャンダラスな報道を得意とする新興TV局、インディアTVが、またもスキャンダルをすっぱ抜いた。標的となったのは、悪役男優として有名なシャクティ・カプール。シャクティ・カプールが若い女性に、肉体関係の見返りに女優として成功させることを約束するシーン、つまりキャスティング・カウチの現場が隠しカメラで撮影され、「India's
Most Wanted」という番組で放映されたのだ。だが、この女性は実はTV局のレポーターで、身分を偽ってシャクティ・カプールに近付き、深夜に彼を隠しカメラの仕掛けられたホテルの部屋に誘って、酒を飲ませた。つまり、シャクティ・カプールは罠にはめられたも同然である。まんまと罠にはまったシャクティ・カプールは、女性にキャスティング・カウチを提案し、その様子がしっかりカメラに映されてしまった。だが、問題は彼だけに収まらず、個人のプライバシーの問題を喚起し、さらにはシャクティ・カプールのある問題発言により、ボリウッド全体をも揺るがす大激震となった。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
シャクティ・カプール |
● |
40分のビデオの中で、シャクティ・カプールは女性に、「もしオレと一緒に寝てくれたら、君を演技とダンスの学校に入学させて、大物監督を紹介してあげよう」と提案したのだが、それと同時に彼は「アイシュワリヤー・ラーイ、プリーティ・ズィンター、ラーニー・ムカルジーも、役を得るためにヤシュ・チョープラー、ヤシュ・ジャウハル、スバーシュ・ガイーと関係を持ったんだ」と口を滑らせてしまった。彼が名を挙げた女優と映画制作者は、いずれもボリウッドを代表する映画人である。
いくら巧妙に罠にはめられたとは言え、シャクティ・カプールがモラルに反することをしたのは否めない。だが、世論はシャクティ・カプールに同情的だ。まず報道の手段が卑怯だ。TV局は、本当のキャスティング・カウチの現場を押えたわけではなく、おとりを使って誘導したに等しい。それに、真夜中に若い女性に密室に呼ばれ、酒を飲まされ、女優として成功するためのアドバイスを色っぽく求められたら、それを拒める男はほとんどいないだろう。また、プライベートな会話が記録されてTVに放送されるというのは、プライバシーの著しい侵害である。インド人の間では、「ボリウッドにキャスティング・カウチがあることは前から公然の秘密で、驚くに値しない」との冷めた意見も多い。
インディアTVのプロデューサー、ソヘーブ・イリヤースィー氏は、ブライバシー侵害との批判にこう答えている。「これは全くフェアなことだ。警察が売買春や贈収賄の現場を押えるためにおとり捜査官を送り込むのと同じだ。ボリウッドでスターになるためにムンバイーに来る若者の多くは、キャスティング・カウチの落とし穴にはまり込んでしまう。多くの場合、キャスティング・カウチは男性に責任があるが、女性が若い男性をいいように利用した例も知っている。人々はこのようなことが起きていることを知る権利がある。キャスティング・カウチの犯罪に対する証拠を集めるために、隠しカメラは最適な手段である。」
当事者のシャクティ・カプールは落胆かつ激怒しており、「これは100%恐喝だ。TV局を訴えるつもりだ。TV局にオレのプライバシーを侵害する権利はない。オレに2000人のガールフレンドがいたとしても、他人の知ったこっちゃない。オレの家族は滅茶苦茶になってしまった。娘は泣いている」と語っている。また、ビデオの中で名前を挙げてしまった女優や監督については、「TV局が勝手に編集したに違いない。私は、スバーシュ・ガイーやヤシュ・ジャウハルは大御所で、アイシュワリヤーやプリーティやラーニーを育て上げたと語っただけだ」と述べており、彼らには既に謝罪のSMSを送ったという。
シャクティ・カプールに名指しされてしまった人々の中で、プリーティ・ズィンターのコメントがあった。「私はボリウッドで仕事をすることができて光栄だが、一匹の汚ない魚が池全体を台無しにしたことが残念で仕方ない。彼は実生活でも悪役だ。彼は映画産業全体から追放されるべき。」かなり手厳しいコメントである。だが、どうやらシャクティ・カプールが出演している映画が上映禁止になるような措置は今のところなさそうだ。
インディアTVがキャスティング・カウチ暴露のターゲットにしたのはシャクティ・カプールだけではなかった。TVドラマ「Kyunki Saas Bhi
Kabhi Bafu Thi」や、スター発掘番組「インディアン・アイドル」に出ているアマン・ヴァルマーも、どうやら同じ目に遭ったらしい。だが、彼は番組が放送される前に警察に駆け込んだとか。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
アマン・ヴァルマー |
● |
僕はこの「India's Most Wanted」という番組を見たことがないのだが、どうやら日本で一時期流行ったドッキリTVのノリのようだ。シャクティ・カプールの場合もアマン・ヴァルマーの場合も、女性との会話が終わるとTV局のスタッフが現場に入って来て、「ドッキリ成功」を宣言するらしい。だが、日本のようにお笑いが目的ではなく、不正や汚職を暴くという目的があるため、ターゲットとされた人はたまったものではない。確かにキャスティング・カウチはボリウッドの影の部分だと思うが、罠にかけるような暴き方はよくないと僕も思う。
ガンジス河。インドにあまり興味のない日本人でも、この河の名前を知っている人は多い。多くの場合、ヴァーラーナスィー(ベナレスまたはバナーラスとも呼ばれる街)とセットになっており、「死体がプカプカ浮かんでいる河」とか「三途の川のモデル」とか「沐浴すると解脱できる河」とか「見ると人生観が変わる河」とか、いろいろなイメージを持たれている。「ガンジス」という表記は、英語の「Ganges」から来ていてあまり好きではないため、僕は頑なに「ガンガー河」と表記することにしているが、「ガンガー河」よりも「ガンジス河」の方がなぜか響きがいいと薄々感じていることは認めなければならないだろう。ちなみに「ガンガー」という言葉はリグヴェーダにも出てくるが、元々は原住民語(ムンダーリー語などのアウストロアジア語族)で「河」という意味らしい。
ガンガー河にイルカがいると聞いたのは、おそらく初めてヴァーラーナスィーを訪れたときか、2回目くらいだったと思う。ガンガー河とイルカのイメージがどうしてもつながらなかったし、実際にイルカが泳いでいるのを見たわけでもないので、半信半疑だったのだが、後からそれは本当の話だと分かった。ガンジス河に生息するイルカは、一般にガンジスカワイルカ(Ganges
River Dolphin)とか、スースー、スース、スーンスなどと呼ばれている。学名は「Platanista Gangetica Gangetica」。口がくちばしのように長くなっているのが特徴で、目は退化している代わりに感覚が鋭いとか。スースーという名前から、その鳴き声が「スースー」と聞こえることが分かる。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
ガンジスカワイルカ |
● |
ところで、インドでは河は女神として神格化され、ガンガー河もガンガー女神として信仰されている。インドの街角には派手な色使いの神様ポスターを目にすることができる。大体の場合、インドの神様は何かしら動物に乗っている。シヴァは牡牛に、ドゥルガーは虎かライオンに、ガネーシュはネズミに、サラスワティーは白鳥か孔雀に、ヴィシュヌはガルールか蛇に、という具合だ。ガンガー女神を描いた絵を見ると、ワニに乗っていることが多い。だが、これは実際はガンジスカワイルカのことのようだ。どうもインドでは、カワイルカとワニが同一視される傾向にある。もちろん、ワニもインドには生息している。蛇足だが、実はヒンディー語では、ライオンと虎もあまり区別されていない。どちらも「シェール」または「バーグ」という言葉で表される。どちらも生息していない日本の言葉で、一応「獅子」と「虎」と区別されているのに、ライオンも虎も生息しているインドの言葉で区別されていないのは不思議である。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
ガンガー女神 |
● |
インドには、マカル(またはマクル、マカラなどとも呼ばれる)という想像上の水棲動物がいる。下の写真のように、よくヒンドゥー教の寺院の排水口になっていたりする。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
マカル
グジャラート州の
バフチャーラー寺院で撮影 |
● |
このマカルも、ワニとイルカの相の子みたいな動物である。マカルは、ギリシアから12星座の占星術が輸入されたときに、山羊座の代わりとなり、それが中国に伝わって摩竭(まかつ)と漢訳された。1月にマカル・サンクラーンティという祭りがある。パンジャーブ地方ではローリー、南インドではポンガルとも呼ばれる。これは占星術上では太陽が山羊座に入ることを言うが、分かりやすく言えば冬至である。この日から日が長くなり始めると同時に、冬の冷え込みも峠を越え、暖かくなり始めると言われている。その他にもマカル・サンクラーンティは収穫祭の意味合いもあり、北インドではサトウキビの収穫が祝われる。ローリーでは初めて収穫されたサトウキビが燃やされる。マカル・サンクラーンティはただ単に「マカル」と言われることが多いため、マカルは想像上の動物ながら、会話で比較的よく出てくることになる。ちなみに、実在の動物のワニもマカルと呼ばれるので、少々ややこしい。
ところで、このガンジスカワイルカは現在絶滅の危機に瀕しているようだ。2月15日の日記でサリスカー野生動物保護区域から虎が一匹もいなくなってしまったという報道を紹介したが、それ以来インドでは絶滅の危機に瀕する野生動物がクローズアップされている。週刊誌アウトルック3月28日号の記事によると、ガンジスカワイルカは現在4000頭ほどしかいないらしい。工業排水による河川の汚染、ダムや堤防の建設や、油脂の採取のための漁により数が減っているそうだ。ガンジスカワイルカの重要な生息地のひとつ、ウッタル・プラデーシュ州のナローラーには原子力発電所もある。ガンジス河の河畔に住む人々にとって、ガンジスカワイルカの「スースー」という鳴き声はけっこう郷愁を誘うものらしいが、それが聞けなくなる日も来るかもしれない。ちなみに僕は、クジャクの鳴き声が好きだ・・・。カタカナで何と表記すればいいのだろうか・・・ホーッ、ホーッだろうか・・・あの鳴き声を聞くだけで、僕は早朝、生まれたばかりの太陽に向かって、草原の中で深呼吸をしたような、すがすがしい気分になる。
スースーの他に、インド特有の動物で絶滅の危機に瀕している動物として、アジアライオン、インドオオカミ、オオヅル、アジアコシジロハゲワシ、キングコブラ、ジンベイザメ、ウシガエル、シシオザル、ブッダオビクジャクアゲハなどが挙げられていた。インドは都会でも道を牛や犬などの動物が行き交っているので、動物に対する愛護心が強い国だと思われがちだが、実際は動物に無関心なだけであることが多く、その無関心が悪い方向へ向けば、このように絶滅の危機に瀕する動物が出てくるのも不思議ではない。だが、動物は儲かるということを教えてやれば、例えばスースーを捕獲する漁師たちも考えを改めるかもしれない。イルカと言えば芸だが、スースーに芸を仕込んで、ヴァーラーナスィーのガートあたりでイルカショーとか開くことはできないのだろうか・・・?
今日は、コンノート・プレイス近くにある日本文化情報センター(JCIC)に用事があったので、デリー中央部のルティエンス・デリーを走行していた。この辺りは道路も広く、街路樹も大きく成長しており、非常に快適な道路である。サフダルジャング廟の前を通過し、プリトヴィーラージ・ロードを通り、LKアードヴァーニー氏の自宅の前を通り抜け、ジャンパトに入って北上し、国立博物館の前を通り、大統領官邸とインド門の間のラージパトを縦断し、フィーローズ・シャー・ロードに入る・・・。非常に快適な走行である。・・・ふと、街路樹が、薄っすらと黄色に紅葉しているのが目に留まった。そういえば最近落葉が多い。風が吹くと、大量の葉っぱが上から降り注いでくる。デリーには常緑樹も多く、街から緑がなくなることはないが、落葉して枝だけになる樹木も少なくない。
その落葉を見ていたら、ふと、クラスメイトが少し前に僕に教えてくれた言葉が思い出された。「インドでは、冬の次に秋が来て、秋の次に春が来るんだ。」
ヒンディー語の入門書の定番、田中敏男氏と町田和彦氏の共著、「エクスプレス ヒンディー語」(白水社)によると、インドの季節は6つに分かれ、それぞれの呼称は、寒期(1〜2月)はシシル、春(3〜4月)はヴァサント、夏(5〜6月)はガルミー、雨期(7〜8月)はバルサート、秋(9〜10月)はシャラド、冬(11〜12月)はサルディーと記されている。また、ヒンディー語の入門書の決定版、スパート・スネル氏とサイモン・ウェイトマン氏の共著「Teach
Yourself Hindi」(Hodder & Stoughton)によると、やはりインドの季節は6つに分かれ、寒期(1〜2月)はシシル、春(3〜4月)はバサント、夏(5〜6月)はグリーシュム、雨期(7月〜8月)はワルシャー、秋(9〜10月)はシャラド、冬(11月〜12月)はヘーマントとなっていた。どこにも、秋が冬と春の間にあるとは書かれていない。気になって別のインド人に聞いてみたが、「秋の後に冬、冬の後に春だ」と言われた。とすると、クラスメイトの言ったことは間違いだったのだろうか?
だが、ヒンディー語には、「秋」を表す別の単語「パトジャル」もある。「パト」とは「葉っぱ」、「ジャル」とは「落ちる」という意味で、つまりは「落葉の季節」という意味だ。古賀勝郎氏著の「日本語−ヒンディー語辞典」(非売品)では、「秋」に対応する日本語の第一候補語は「パトジャル」となっている。確かクラスメイトは、この「パトジャル」という単語を使って、「パトジャルは冬の後、春の前」と言っていた。一般にこの単語は「秋」と訳される。なぜなら四季のある国では、秋に落葉することが多いからだ。英語で「秋」を表す「fall」も、「葉っぱが落ちる」ことからこう名付けられたのだろう。だが、インドではどうも落葉の季節は3月なのではないかと思う。9〜10月はまだ雨期の影響が残っており、木々が葉っぱを落とすには早すぎる。かえって、酷暑期の前に葉っぱを落として軽量化した方が、インドのような暑い国では木にとって効果的なのかもしれない。だから本格的な夏の到来の前のこの時期に木々は葉っぱを落とすのだろう。「パトジャル」は、「秋」と訳すよりも、「落葉の季節」としておいた方がよさそうだ。ブッダと関わりの深い菩提樹も3月に落葉するようだ。
葉っぱで思い出したのだが、独立後のインドを代表する文学者に、サッチダーナンド・ヒーラーナンド・ヴァーツヤーヤン・アギェーイ(1911-1987)という人物がいる。長ったらしい名前なので、ただ単に雅号「アギェーイ(知られることなき者)」と呼ばれることが多い。彼の詩に、「チリヤー・キ・カハーニー(小鳥の話)」という有名な短い詩がある。1959年に発表された詩集に収録されている詩である。
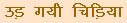
飛び去った 小鳥
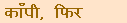
震え、そして

元通り
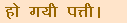
止まった 木の葉。
木の枝に止まった小鳥が飛び立ち、枝が揺れ、葉っぱが震え、しばらく後に静かになって止まった、というだけの詩だが、何となく宇宙的広がりを持っている。アギェーイの時代のヒンディー詩文学では、韻に捕われない自由な散文詩が書かれるようになると同時に、いろいろな実験がなされた。アギェーイのこの詩を見たとき、僕は日本の俳句を思い出した。特に松尾芭蕉の「古池や 蛙飛び込む 水の音」というあの有名な俳句だ。アギェーイは日本の禅宗に影響を受けていたと言われ、俳句からこの詩が生まれた可能性は高い。
だが、アギェーイのこの詩には、日本人とインド人の感覚の違いが表れているように思う。「葉っぱ」を表す単語「パッティー」は単数形なので、揺れた葉っぱは1枚だけであるとすることができる。枝が揺れて、葉っぱが1枚しか揺れないというのは、つまり枝に1枚しか葉っぱが付いていなかったということであり、落葉の季節の詩であると考えるのが普通だ。もし日本人が落葉の季節に同じような詩を作ったら、小鳥の飛翔により震えた残り1枚の葉っぱは、ヒラリと地面に落ちてしまう方が自然ではなかろうか。1枚の葉っぱが落ちる様子に、日本人は底知れない無常観を感じるものだ。しかし、アギェーイの詩では、葉っぱは落ちずにそのまま枝に付いている。僕の解釈では、葉っぱが落ちることができずに取り残されたことにより、孤独と束縛を表しているのだと思う。小鳥は自由に大空を飛び立ったのに、葉っぱは1枚だけ枝にくっ付いて、束縛から逃れることができずにいる、そんな状態が浮かんで来る。さらに考えを進め、葉っぱはアギェーイ自身であり、作者が置かれた孤独で不自由な状態が葉っぱに込められていると考えることも可能だ。この感覚の違いは、冬の前に落葉する日本と、春の前に落葉するインドの、気候の違いから来る侘び寂びの違いなのではないかと感じた。3月には、ホーリーという大きな祭りのある月であり、この時期のインド人はうかれまくっている。落葉は春の訪れを告げる証であり、再生の兆しなのだ。また先日には、風が吹き、多くの葉っぱが宙に舞う様を見て、友人のインド人が、「木々が僕たちにアーシルワード(祝福)をしてくれている」とポジティヴな表現していたのを聞いた。日本人だったらもっと陰鬱な表現をするように思える。例えば、東大では、名物の銀杏並木の葉っぱが散るまでに恋人ができないと、新入生は大学生活4年間ずっと恋人ができない、というジンクスがあると聞いた。日本人は落葉に何かしらネガティヴなイメージを持っているのは確かだ。というわけで至った結論は、落葉に対する感覚には、日本人とインド人に違いがあるかもしれない、ということだ。
ちなみに、ここで話題にしたインドの季節は、あくまでヒンディー語圏の北インド一帯のことだと思ってもらいたい。山間地方、南インド、東北インドなどでは、気候は全く違う。
ホーリー前日の今日、PVRプリヤーで新作ヒンディー語映画「Zeher」を鑑賞した。「Zeher」とは「毒」という意味。プロデューサーはムケーシュ・バット、監督はモーヒト・スリー(新人)、音楽はループ・クマール・ラトード。キャストは、イムラーン・ハーシュミー、シャミター・シェッティー、ウディター・ゴースワーミー、サミール・コーチャルなど。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
シャミター・シェッティー(左)と
イムラーン・ハーシュミー(右) |
● |
| Zeher |
スィッダールト(イムラーン・ハーシュミー)はゴア州警察に勤めていた。妻のソニア(シャミター・シェッティー)とは3ヶ月前に別居状態になっており、スィッダールトの私生活は荒れていた。それでも、スィッダールトはゴアで暗躍していた麻薬の売人を逮捕し、大量のコカインと現金を押収することに成功する。
同じ時期に、スィッダールトと腐れ縁で、ドバイに飛んで一儲けしたチンピラ、シャウン(サミール・コーチャル)がゴアに戻って来る。シャウンはアンナ(ウディター・ゴースワーミー)という若い妻を連れていた。アンナは夫に怯えているように見え、スィッダールトは何となく心配になる。
ある晩、アンナから通報があったため、スィッダールトは彼女の家へ急行する。しかし、家では何も起こっていなかった。アンナは「夫は今ムンバイーに行っていていないの」と言い、服を脱ぎ捨てる。スィッダールトは欲望の赴くまま、アンナをベッドに押し倒してしまった。
それから、スィッダールトとアンナの仲は秘密裡に続いていた。ある日、アンナは、自分が妊娠したことを告げる。夫のシャウンとは数年間関係を持っていなかったため、それはスィッダールトの子供だとのことだった。焦るスィッダールトは、とりあえずアンナと共に病院へ行く。そこで知らされたのは、アンナの妊娠だけではなかった。なんとアンナは癌に冒されており、3ヶ月の余命しかないとのことだった。だが、医者の話では金さえ出せば治療は可能だという。だが、そんな金はスィッダールトの手元にもアンナの手元にもなかった。
死を覚悟したアンナは、自分に生命保険をかけ、その受取人をスィッダールトにしたと告げる。また、ソニアが他の男と一緒に食事をしている場面を見て彼は自暴自棄になる。スィッダールトは、警察署の金庫に保管してあった、押収した現金を持ち出し、アンナに手渡す。だが、その夜、シャウンとアンナの家は火事になり、2人の焼死体が見つかる。すぐに放火であることが分かり、事件の担当はソニアとなる。
全ての証拠は、スィッダールトに不利なものばかりだった。彼はその証拠を何とか隠滅しようと躍起になる。アンナの電話の通話記録には彼の名前が何度も出てきていたが、スィッダールトはその通話記録を改変する。麻薬監視局からは、押収した現金を証拠品として提供するように依頼が来る。スィッダールトは何とかそれを交わしていた。火事があった夜、スィッダールトはアンナの家を訪れていたが、その様子を隣人に見られていた。しかしその人は目が悪かったため、ばれずに済んだ。しかし、アンナに生命保険がかけられていたことが明らかになり、その受取人がスィッダールトであることが遂にソニアに知られてしまう。
一方、スィッダールトは、病院でアンナの妊娠と癌を告げた医者が偽物であることを突き止める。アンナの妊娠と癌も嘘だった。スィッダールトは医者になりすましたその男の行方を追い、奪われた現金を取り戻すことに成功する。また、スィッダールトの元にはアンナから電話がある。アンナは死んでおらず、火事で死んだのは別人だった。アンナは彼に、騙したことを謝ると同時に、シャウンに殺されそうになっているから助けてほしいと言う。スィッダールトはすぐにその場へ向かう。アンナは血を流して手足を縛られていた。スィッダールトとシャウンは銃撃戦と乱闘を繰り広げ、その末にアンナがシャウンを射殺する。だが、アンナの銃口はスィッダールトにも向けられる。実は全てを仕組んだのはシャウンではなく、アンナだったのだ。絶体絶命のピンチだったが、そこへ駆けつけたソニアがアンナを射殺する。スィッダールトとソニアの仲も回復の兆しが見え、一件落着となった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
人妻と禁断の恋をしたら、全てが罠で、濡れ衣を着せられてしまった、というサスペンス映画。この手の映画はヒンディー語映画でもそれほど珍しくなくなって来ている。記憶にある中でも、「Ajnabee」(2001年)や「Jism」(2003年)がそのようなストーリーだった。
「Zeher」で工夫されていたのは、自分が濡れ衣を着せられた事件の捜査をするのが別居中の妻であること、また事件の容疑者として自分の名前が出るのを必死に隠蔽しようとすることの2点だったと思う。それだけが多少評価できるところで、あとはあまり現実的ではない筋書きで気が滅入った。この種の映画では、エロチックなシーンも見ものになっているが、この映画ではそれほどインパクトはなかった。
監督は新人のモーヒト・スリー。なんとイムラーン・ハーシュミーの従兄弟らしく、「Raaz」(2002年)などで助監督を務めていた人物である。特に才能を感じさせるような映像ではなかったが、合格点ではなかろうか。
主人公のイムラーン・ハーシュミーは、何だか分からないが最近よく映画に出演するようになって来た若手男優である。瓜みたいな形の顔をしており、お世辞にもハンサムとは言えないと思うのだが、演技力はある。イムラーンはデビュー前にアミーシャー・パテールに「演技できそうにもないわね」とひどいことを言われたらしく、その悔しさをバネに演技力を磨いて来たとか。イムラーンはデビュー以来、マッリカー・シェーラーワト、ディーヤー・ミルザーら若手女優とキスをしてきており、「イムラーン=キス」というイメージが定着しつつある。この映画でもウディター・ゴースワミーと熱いキスシーンを演じた。
シャミター・シェッティーは、女優シルパー・シェッティーの妹。顔はそっくりである。「Mohabbatein」(2000年)や「Bewafaa」(2005年)に出演していたがあまりパッとしなかった。だが、「Zeher」にてようやく開花しそうだ。芯のある演技をしていてよかった。
ウディター・ゴースワーミーは、インド人というよりも東南アジア系の顔をした女優である。ウッタラーンチャル州デヘラードゥーン生まれらしいので、ネパール人系の血が入っているかもしれない。ウディターは最近の他の女優と同じく、モデルから女優に転身した口だ。「Paap」(2003年)でデビューしたが、共演者のジョン・アブラハムが今や大スターの仲間入りをしたのに比べ、まだくすぶっている。「Zeher」では好演をしていたものの、いわゆる「インド人顔」の女優と比べると顔に力がなく、スクリーンで栄えない。だが、ウディターはこの映画を通してモーヒト・スリー監督と恋仲になったようなので、その人脈で成長するかもしれない。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
ウディター・ゴースワーミー |
● |
舞台は全編ゴア。パナジ名物のパナジ教会が映っていたのが分かったが、それ以外は、あまりゴアの特徴が活かされていなかったように感じた。別に舞台がムンバイーでも可能なストーリーだっただろう。登場人物にもゴアっぽさが出ていなかった。
ここ数週間はホーリーやクリケット印パ戦などの影響で、映画界に力がなく、期待作が公開されていない。「Zeher」も、特に見るべき価値がある映画とは思えなかった。
| ◆ |
3月25日(金) ムシャッラフ大統領の生家 |
◆ |
現在、インドの首相を務めるマンモーハン・スィンは、1932年9月26日、パンジャーブ地方西部のガーという村で生まれた。ガー村はイスラマーバードから南に80kmの地点にあり、現在はパーキスターン領となっている。一方、現在、パーキスターンの大統領を務めるパルヴェーズ・ムシャッラフは、1943年8月11日、デリーで生まれた。つまり、インド首相はパーキスターン出身、パーキスターン大統領はインド出身という奇妙な状態となっている。1947年の印パ分離独立時に、マンモーハン・スィン首相は家族と共にアムリトサルに移住し、ムシャッラフ大統領はカラーチーに移住した。
現在、パーキスターンのクリケット・チームが約50日間の日程でインドを訪れており、インド代表と試合を行っている。ムシャッラフ大統領も、4月17日にデリーで行われるワンデー国際マッチ(ODI)を観戦することが決定した。だが、ムシャッラフ大統領よりも一足早く、大統領の母親ザリーン、息子のビラール、そして兄弟のジャーヴェードがインドを非公式に訪れた。ザリーンが真っ先に向かったのは、オールド・デリーにあるネヘルワーリー・ハヴェーリーだった。
ネヘルワーリー・ハヴェーリーは、ザリーンと夫サイヤド・ムシャラフッディーンが建てた家で、ムシャッラフ大統領自身もここで生まれ、数年間過ごした。現在では、チャーンドニー・チャウクに服飾店を構えるデーヴィンダル・ジャイン氏が所有している。ジャイン氏は1960年にこの家を購入し、40年以上住み続けて来ており、そろそろ引っ越しを考えているようだが、過去に住んでいた人が住んでいただけに、家の買い手がいなくて困っているという。3月17日付けのエクスプレス・ニュースライン(インディアン・エクスプレス紙の折込版)にジャイン氏のインタビューが載っていた。
ジャイン氏曰く、「私の家族は今や大所帯となっており、さらに大きな家に引っ越したいと考えている。だが、誰もこの家を買おうとしない。なぜなら、後で政府がこの家を印パ平和の記念館にしたり、ムシャッラフ大統領に返還したりすることを恐れているからだ。」
ムシャッラフ大統領は、2001年7月14日にインドを訪問した際、このネヘルワーリー・ハヴェーリーを訪れている。そのときは、ムシャッラフ大統領の乳母をしていたカシュミーローも駆けつけ、ネヘルワーリー・ハヴェーリーの庭でTV局にインタビューに答えた。ジャイン氏の家族は、自宅の庭で行われているそのインタビューの様子を、家のTVで見ていたというからおかしい。
実は今日、そのネヘルワーリー・ハヴェーリーを探しにオールド・デリーへ行ってきた。本当の目的はホーリーの写真撮影で、ムスリムの多いオールド・デリーでホーリーはどのように祝われているか調べに行ったのだが、全体的に節度のある祝われ方をしていてあまり楽しくなかったので(ナイー・サラクだけは激しかった)、ネヘルワーリー・ハヴェーリーのことを思い出して探してみたのだ。道端の人に「パルヴェーズ・ムシャッラフ大統領の家はどこ?」と聞いてみたら、けっこうみんな知っていた。場所は、ダリヤー・ガンジの有名な映画館、ゴールチャーのすぐ裏だった。映画館のすぐ南にある路地を入り、すぐに左に曲がってまっすぐ進み、2つ目のT字路を右に曲がり、すぐに左に曲がった突き当たりにある家である。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
ネヘルワーリー・ハヴェーリー |
● |
「ハヴェーリー」とは「邸宅」とか「屋敷」という意味で、割と豪華な家を想像していたのだが、非常に質素な家だった。今でこそ2階建てになっていたが、当時はおそらく平屋建てだったのだろう。ムシャッラフ大統領の父親は外交官だったようだが、生まれは貧しかったのかもしれない。周囲の建物はほとんど3〜4階建てになっていたので、ネヘルワーリー・ハヴェーリーの周りだけぽっかりと穴が開いたような状態になっていた。
家から人が出てきたので、「これがムシャッラフ大統領の生家ですか?」と聞いてみたら、「そうです」と答えた。彼が新聞に出ていたデーヴィンダル・ジャイン氏だったのかは知らないが、案外親切に応対してくれて驚いた。野次馬は帰れ、と追い返されると思ったが・・・。彼だけでなく、オールド・デリーに住む人々は基本的に親切で礼儀正しいと感じた。彼らの話す言葉もきれいだと感じたのは、オールド・デリーがヒンディー語とウルドゥー語の発祥の地のひとつだという先入観があったからだろうか。
ネヘルワーリー・ハヴェーリーがこれからどういう運命を辿るのかは分からないが、少なくともムシャッラフ大統領が政権を握っている間は、少しだけ観光の価値のある場所だろう。ムシャッラフ大統領が政権から消えるときは、おそらく暗殺という結末だと思うが・・・。皮肉だが、インドに亡命、というのもありえるかもしれない。
インドに無数にある祭りの中で、インド人が最も楽しみにしている祭りがホーリーである。ホーリーはヒンドゥー暦のファールグン月の満月の日に行われる、春の訪れを祝う祭りだ。今年のホーリーは3月26日(土)だった。カースト制度による身分制でがんじがらめになっているインドの社会も、ホーリーの日だけは無礼講となり、身分の上下に関わらず色水をかけあったり色粉を塗りあったりして楽しむ。ホーリーが特に盛大に祝われる場所はインドにいくつかあるが、デリーの近くではヴリンダーヴァンのホーリーが有名である。わざわざホーリーの日にヴリンダーヴァンを訪れるデリー在住の人もいるほどだ。ヴリンダーヴァンのホーリーを自分の目で見たわけではないので詳しいことは分からないが、聞くところによるとヴリンダーヴァンではホーリーの日に妻が棒で夫を叩いたりするようだ。これも男尊女卑社会の裏返しなのであろうか。インドには、どんな制度や規則にも必ずはけ口があるので面白い。また、ホーリーはバーング(大麻)が公に解禁される日でもあり、この日のインド人たちは異常なまでのハイテンションとなる。女性旅行者がよくホーリーの日に外出禁止とされるのも、そのような理由による。
インドに留学して1年目のホーリーは、大家さんの家族と相当遊びまくった。最初はベランダの上から通行人に水風船を投げつけたり、水鉄砲で水をかけたりしていたが、面倒になって最後はバケツに色水をためて、それを思いっ切り人にかけたりした。不本意ながら僕の部屋が戦場となり、後片付けが大変になった苦い思い出もある。もちろん、全身色だらけとなってしまった。だが、楽しかった。2年目のホーリーはインドで体験できなかった。ホーリーの休日を利用して日本に帰国していたからだ。3年目のホーリーは、家で静かに過ごした。だが、4年目のホーリーはまたちょっと激しく祝ってみたいと思うようになり、ホーリーの日にジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)を訪れることにした。
その前に、JNUではホーリーの前日に恒例のイベントが催されるから、そのことを書いておこう。ホーリーの前日、JNUの男子寮のひとつ、ジェーラム・ホステルで「チャート」という集会が開かれる。「チャート」とは「無駄口」とか「退屈」という意味で、つまりは観客の前で下らないことを発表し合う集会である。とは言え、それは建前で、みんな自慢のお笑いネタを次から次へと繰り出し、観客の爆笑を誘う。全てヒンディー語なので、ヒンディー語が分からないと笑えないが、ヒンディー語が分かっても外国語の笑いのツボを理解するのは困難であるので、結局外国人には参加が難しいイベントである。だが、普段は普通の学生たちが、お笑い芸人のようなプロフェッショナルな口上で堂々とギャグをかます様子は一見に値する。チャート会は夜通し行われ、この時点で既にJNUの学生たちはハイテンションとなるのだ。
翌日、僕は午前11時過ぎにJNUを訪れた。本当は9時頃が一番ピークなのだが、その時間にバイクで外を走るとかなり危険な状態となるので、ある程度沈静化してからJNUへ向かった。驚いたことに、ホーリーの日でも道端に警察が陣取っており、パトロールを行っていた。警察も大変である。道はがら空きで、無事にJNUへ到着することができた。いや、バイクのカバーを外したりして出発の準備をしているときに、隣の家の子供から赤い水をかけられまくったので、既に無傷ではなかったが・・・。また、帰りには目の前でスクーターが走行中にバランスを失って転倒するのを目撃した。やっぱりホーリーの日は危ない・・・。
JNUの入り口近くにある広場では、多くの人々が集まって騒いでいた。安全そうな場所にバイクを止め、クラスメイトを見つけ、一杯酒を飲んで(寮ではバーングが配られるが、バーングはもう終わっていた)、群集の中に入って行った。知っている人を見つけては、お互いに色粉を顔に塗り合う。だが、やはりピークは過ぎており、ホーリーを祝う人の数は徐々に減って行った。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
JNUのホーリー |
● |
一通り祝った後、ジェーラム・ホステルの友人の部屋に入って、クラスメイトたちと世間話をした。僕のクラスには、ラージャスターン州、ウッタル・プラデーシュ州、ビハール州出身の人がいるが、僕が特に親しくしているのはビハール州の学生たちである。このときも、ビハール州の友人たちと一緒だった。仏教の発祥の地が現在のビハール州であるためか、他の例を見ていても、ビハール州の人々と日本人は比較的友人になりやすい傾向にあるような気がする。ビハール州の人間は「ビハーリー」と言われている。「ビハーリー」という言葉は「ビハールの人」という意味で、元々は何の悪意もない言葉なのだが、ビハール州はインドの中でも最も貧しい州かつ最も田舎の州であるため、軽蔑と差別の意味を込めて「ビハーリー」という言葉が使われることが多い。だが、僕も都会生まれではないので、「日本のビハールから来た」とか言うと、けっこう受けたりする。ちなみに、アタル・ビハーリー・ヴァージペーイー前首相のように、「ビハーリー」という言葉が名前の中に入っている人もいるが、その場合の「ビハーリー」はクリシュナ神の別名である。
さて、ビハーリーたちと会話をしていたわけであるが、その中で1人だけ浮かぬ顔をしている人がいた。日常生活の嫌なことを忘れ楽しむこのホーリーの日に、何か心配事でもあるのだろうか。すると、彼はタイミングを見計らって、2人っきりになったときに自分から僕に話しかけてきた。「ちょっとお前に聞きたいことがある。」何だろうと思って「聞いていいよ」と答えると、つまりは恋愛問題であった。
その恋愛問題について記す前に、ゴーダーヴァリー・ホステルの寮祭について触れなければならないだろう。1週間前の土曜日、僕はJNUの女子寮のひとつ、ゴーダーヴァリー・ホステルの寮祭に呼ばれて行った。この時期、デリーにある大学の各寮ではホステル・ナイトと呼ばれる寮祭が行われる。男子寮の寮祭は比較的オープンだが、女子寮の寮祭は、寮に住む人の招待がなければ入ることができない。去年は女子寮ヤムナー・ホステルの寮祭に招待されて行く幸運を得ることができたが、今年はゴーダーヴァリー・ホステルの寮祭を体験することができた。ムスリムの女の子に呼んでもらえたので、何かレアな感じがしてよかった。ホステル・ナイトと行っても、夕食を食べて、話をして、ディスコで踊るだけであるが。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
ディスコの様子 |
● |
そのとき、ゴーダーヴァリー・ホステルに住む他の女の子とも会うことができたのだが、その内の1人にある女の子がいた。仮に名前を花子ちゃんとしておこう(インド人だが、花と関係ある名前なので)。ついでに、僕を招待してくれた女の子は仮にヒカルちゃんとしておこう(同じく、光に関係ある名前なので)。花子ちゃんとヒカルちゃんは最近仲良しのようで、自然と僕もその輪に加わることになり、花子ちゃんと話す機会もできた。花子ちゃんとは以前にも少し話したことがあったのだが、挨拶程度のもので、その日ほど深く話したことはなかった。昔はもっと垢抜けていない印象があったのだが、いつの間にか田舎っぽさが抜けていたように思えたのは、寮祭のために着飾っていたためだろうか。平常の顔が多少不機嫌そうな感じであるが、笑うとけっこうかわいい子である。ヒカルちゃんが用事があってどこかへ行ってしまったため、2人で話していたときがあったのだが、そのとき花子ちゃんは何か不機嫌そうに黙りこくっていたので、何か気まずいことでも言ってしまったかと思い、どうしたのか聞いてみたら、彼女は「アイスクリーム、もっと食べたいなぁ」と考えていたらしい。寮祭の参加者はそれぞれクーポンがもらえ、夕食、コールドドリンク、コーヒー、アイスクリームの券がある。既に僕たちはアイスクリームの券を使ってアイスクリームを食べてしまっていたのだが、花子ちゃんはどうもアイスクリームが好きなようで、何とかしてもっと食べれないか思案を巡らせていたらしい。すぐ後に、友人から余っていた券がもらえたようで、2つめのアイスクリームを手に入れることができた。花子ちゃんはすごく嬉しそうな顔をしていた。だが、せっかく手に入れたアイスクリームの半分を僕に分けてくれた。僕はアイスクリームに飢えていないので、いらないと言ったのだが、無理に僕に半分くれた。インド人には長所短所いろいろあるが、「共有する」という観念が日本人よりも案外強いところが長所のひとつだと思う。子供の乞食にチョコレートをあげると、それを1人で食べてしまわず、周りにいる兄弟姉妹仲間たちと分け合って食べる。日本では、誕生日は誕生日を迎えた人が「祝われる」イベントだが、インドでは誕生日を迎えた人が喜びを「共有する」イベントである。花子ちゃんがアイスクリームの半分をくれたときも、そんなことを思っていた。寮祭には抜け目なくカメラを持参して行ったので、ヒカルちゃん、花子ちゃん、その他の女の子と共に写真を撮った。ディスコでも一緒に踊った。なかなか楽しいイベントだった。
僕に質問してきた友人は、その花子ちゃんのことが好きだった。寮祭で僕が花子ちゃんと話したことを聞いた彼は、彼女のことに対して情報を入手したい様子であった。だが、彼はやたら自信がなく、「花子ちゃんはオレのこと嫌ってるみたいなんだ」と呟いていた。「嫌いだと言われたのか?」と聞くと、「いや、そんな感じがするだけだ」との答え。誰かのことが好きだと、その人に嫌われてるように感じることはけっこうあるものだ。彼は僕に、「花子はオレのこと何か言ってたか?」と聞いて来た。・・・う〜ん、特に記憶にないが・・・。「そんなに好きだったら、一度気持ちを伝えてみれば」と無責任なアドバイスをしてみると、「お前の国じゃあそういうことが許されるかもしれないが、インドじゃあそういうことはないんだ」とまた消極的な意見。確かにまだインドでは男女の仲は公になっていないところはあるが、JNUは比較的恋愛に対してオープンな気風のある大学である。だが、それでも一歩踏み出すのは勇気がいることだろう。彼はもう22、3歳だと思うが、恋愛レベルでは日本の中学生くらいだ。じれったい部分もあるが、そういう純なところがインド人のいいところでもある。しかも、彼は「花子には婚約者がいるみたいだ」とも言っていた。インドでは依然としてお見合い結婚が多いし、大学生くらいの年頃の女の子に婚約者がいるのは珍しいことではない。とは言え、このまま気持ちを伝えないままでは精神衛生上よくないだろう。「今こそヒンディー文学で培った知識を総動員し、ラブレターを書くべきだ」と冗談っぽく言ってみたが、あまり効果がなかったようだ。
独立インドの代表的詩人、シャムシェール・バハードゥル・スィン(1911-1993)の代表的な詩「トゥーティー・フイー・ビクリー・フイー(壊れて、荒れて)」(1954年)にこんな一節がある。

さあ、君よ、私を恋せよ
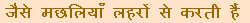
魚が波に恋するように
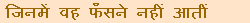
その波に魚は決して沈むことはない
この詩を文字って「さあ、君よ、彼女を恋せよ〜」とまた彼に冗談っぽく言ってみたが、やっぱり反応が鈍かった。これは重症だ・・・。だが、彼にとってはプラス要因の情報もあった。それは、寮祭の日、花子ちゃんは誰も招待しなかったことだ。もしボーイフレンドがいるなら、花子ちゃんは寮祭に彼を招待するのは必然であろう(ちなみにヒカルちゃんには彼氏はいるようだが、急に用事ができて来れなくなったようなので、クーポンを無駄にしないために代わりに僕が呼ばれたようだ)。しかし彼女は誰も呼んでいなかった。僕が「なぜ誰も呼ばないの?」と聞いてみたら、「そういうことは好きじゃない」みたいなことを言っていたように記憶している。だが、本当の理由は分からない。もう面倒だから、僕が花子ちゃんに伝えてあげたい気分になった。
ちょうどそのとき、ホーリーの写真を撮るために危険を冒してデジカメを持って来ていた。そのデジカメの中には、まだゴーダーヴァリー・ホステルで撮影した写真も入っていた。確か花子ちゃんは、「この写真を誰にも見せないで」と言っていた。あのときは恥ずかしいからそう言っていたのだと思ったが、もしかしたら彼と関係のある発言だったのかもしれない。2人の間には既に何かあった可能性もあるが、詳しくは聞かなかった。花子ちゃんには「誰にも見せるな」と言われていたが、こういう流れだったし、僕が寮祭にカメラを持って行ったことは既に知られていたので、仕方なくその写真を見せることにした。彼はじっとデジカメの写真を見入っていた。花子ちゃんが写っている写真は3枚ある。・・・しばらくデジカメの写真を食い入るように見た後、案の定彼は僕に頼んできた。「花子が写っている写真を全部オレにくれ!」
一方では花子ちゃんに「写真を見せるな」と言われており、他方で「この写真をくれ」と言われ、これはヒンディー語で言う「パンス・ガヤー(嫌な状況にはまり込んでしまった)」の状態になってしまった。友情のためには写真を現像して渡してあげるべきだが、写真というプライバシーに関わる事物を他人の手に渡すのはモラルに反する行為だ。しかも、花子ちゃんが写っている写真には僕も写っており、何だかそれを彼に渡すのは変な気がした。一応、「写真だけで満足するなよ、もっと実際的な行動を取るべきだ」と話をそらそうと試みたのだが、彼は聞こうとしなかった。現像した写真は誰にも見せないと約束したので、他の寮祭やホーリーの写真と共に近々現像することにした。
こんなこともあって、心配事を忘れ去るためにあるホーリーなのに、何だか心配事を抱え込んでしまう結果となった。
写真は、本日月曜日にハウズ・カース・マーケットの写真屋で現像した。いつもはグリーン・パークの写真屋でデジカメ写真を現像していたのだが、どうも画質がよくないので、他の場所を試してみようと思っていた。ハウズ・カースの写真屋は、グリーン・パークよりも安い上に(4×6で8ルピー)、きれいな仕上がりで満足。もちろん、日本で現像した方がきれいなのだが、インドの友人に配るための写真は、これからはここを使おうと思った。
写真は2時間で現像でき、早速それを友人のところへ持って行った。彼は非常に喜んでいた。彼はこの3枚の写真を一生宝物にして、それだけで満足して過ごすのだろうか、それともいずれ気持ちを彼女に伝えることができるのだろうか。
|
|
|
|
|
NEXT▼2005年4月
|
|
| *** Copyright (C) Arukakat All Rights Reserved *** |



