| ◆ |
11月1日(火) 風で光るオアシス、ジャイサルメール |
◆ |
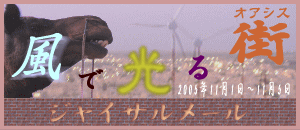
今年のディーワーリー祭は、ラージャスターン州マールワール地方のジャイサルメールで祝うことにした。ジャイサルメールはタル砂漠のど真ん中に位置するオアシスの街で、12世紀に建造された。西アジアと南アジアを結ぶ重要な陸上通商路上にあったため、中継貿易により大いに栄えたが、英国によるボンベイ港の建造など、アラビア海の海上交易路の発展と変革に伴い徐々に落ち目となっていった。そして1947年の印パ分離独立により、ジャイサルメールはインド西端の辺境の街に過ぎなくなり、その繁栄は完全に終止符を打たれた。しかし、そのおかげで古い街並みが比較的よく保存される結果となり、現在では「ゴールデン・シティー」という異名のもと、観光客を引き寄せてやまない魅力ある都市となっている。ジャイサルメールには2002年の3月、ちょうどホーリーの時期に一度訪れたことがある。
今回の旅行はちょっと特殊である。何が特殊だったかと言うと、まず、僕の旅行歴の中で過去最大規模の団体ツアーとなったことだ。バンガロールのIT企業インフォシスに勤める日本人を中心に、僕を含めて合計7人の日本人、1人のインド人と共に旅行することになった。地理別に見ると、デリーから3人、バンガロールから4人、マイソールから1人が、ジャイサルメールに集結することになった。性別では、男性3人、女性5人である。そしてもうひとつ特殊な点は、ジャイサルメールを拠点にビール族という部族を研究している小西公大氏に、旅行の大部分のアレンジをお願いしたことである。小西氏は現在ジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)に留学中だが、ちょうど僕たちがジャイサルメールへ行くときに現地にいることが分かったので、旅行を全面的にバックアップしていただくことになった。
ジャイサルメールへ行く主な目的はキャメル・サファリ。前回ジャイサルメールを訪れたときに日帰りのキャメル・サファリを体験したことがあったが、今回は砂漠で1泊のキャメル・サファリに挑戦することになった。ちなみに、昔、エジプトの白砂漠で1泊2日のサファリをしたことがあるので、砂漠で野宿をするのはこれが初めてではない。ジャイサルメールのキャメル・サファリ業者は相当観光客ずれしており、悪質な業者に運悪く当たってしまうと、サファリ中に身ぐるみを剥がされたり、女性だったらレイプされたり、といろいろなトラブルに巻き込まれるそうだ。しかも、ジャイサルメールのラクダ乗りはほとんどジゴロと変わらない職業とも言われている。これらのトラブルについては、某旅行ガイドブックにも嫌というほど記述されているので、詳しくはそちらの方を読んでもらいたい。そういうこともあり、現地の事情に詳しい小西氏のバックアップがあるのは非常に頼もしい限りであった。小西氏が「絶対に信頼できるキャメル・サファリ業者を紹介する」と太鼓判を押してくれた。
とりあえず信頼できるキャメル・サファリ業者は見つかりそうだったが、僕が個人的に最も心配していたのはサソリであった。今年9月に行ったアルワル・ツーリング中に僕が蜂の大群に数ヶ所刺されたのは、「これでインディア」の愛読者なら記憶に新しいところだと思う。実はツーリングの次の日にも僕は自室で蜂に刺された。2日連続で蜂に刺されるなんて恥ずかし過ぎるのでどこにも書かなかったのだが、もう時効だと思うのでここで暴露しているところだ。だが、聞くところによると蜂の毒は体内にけっこう長く残存しているらしく、何度も刺されると身体が耐えられる許容量を越えて死に達することもあるようなので、気を付けなければならない。と言うわけで、何だか最近刺されることが多いので、キャメル・サファリ中にサソリに刺されることがないか不安であった。もちろん、ジャイサルメール周辺の砂漠にはサソリが出没するという。しかも今はサソリ座の時期。かなり条件が揃い過ぎている。小西氏によると、サソリに刺されると、火で熱した鉄の棒をジュワ〜っと当てられたような激痛が24時間続くという。実際にサソリに刺された経験を持つ大和屋のN氏も同じようなことを言っていた。ただ、幸いなことに大人だったら、サソリに刺されて死ぬことはあまりないようだ。・・・だが、蜂の毒を体内に持つ僕がもしサソリに刺されたら、蜂の毒とサソリの毒が融合して、地元の人々でも手に負えないような強力な猛毒になるのではなかろうか?そういえばドラゴンクエストにサソリバチというモンスターがいた。あれに刺されたときと同じような効果になるのではなかろうか?不安は増すばかりであった。サソリに刺されないようにするための必須アイテムは懐中電灯。サソリは夜行性の動物であるため、夜に砂漠を歩くときはサソリを踏まないように懐中電灯で足元を照らして歩かないと危ないようだ。一応懐中電灯は持っていたのだが、どうも調子が悪かったので、旅行前に藁にもすがる思いで懐中電灯を購入した。また、サソリは物陰を好む。荷物を持ち上げたりしたときに、その下に隠れていたサソリに刺されたりすることもあるようだ。最も気を付けないといけないのは、靴を履くときに一度中を確認すること。靴の中にサソリが潜んでいることもけっこうあるらしい。もし万が一サソリに刺されたら、傷口に砂糖を塗って布でグルグル巻きにし、なるべく動かさないように、また絶対に冷やさないようにする他、腿の付け根をギュウギュウに縛って血液の流れを止めるのが応急処置らしい。こんなことまで聞いて頭に叩き込むほど、僕は本気でサソリを恐れていた。
サソリに対する恐怖心を克服するため、僕は2つの遊びを砂漠で試すことに決めていた。ひとつはスポーツ・カイト。1年前に日本で購入して来たフランス製のスポーツ・カイトがあるのだが、これが今まで満足に上がった試しがない。JNUのグラウンドで1度試したが上がらず、ナガランド州コヒマくんだりまで行って試したがやはり上がらなかった。それでも諦めきれない僕は、ジャイサルメールの砂漠でスポーツ・カイトを飛ばす野望を燃やしていた。どうやら砂漠は風が強いようで、期待が持てる。それに、インド最東端のコヒマまで持って行ったカイトを、インド最西端のジャイサルメールにも持って行くなんて、けっこう粋ではなかろうか?
もうひとつの遊びはスーツ。砂漠でスーツを着て写真を撮るという、ちょっと頭のおかしい人しか思いつかないアイデアを思いついてしまったのが僕であった。直接のきっかけは、日本に帰った友人が捨てて行ったスーツを目にしたことだった。彼はインドの仕立て屋でオーダーメイドをして背広を作らせたのだが、それからだいぶ太ってしまって着れなくなってしまった。彼は僕よりも身長が低く、体格もかなり違うためにもらうことも考えなかったし、他にもらい手もなかったようだ。よって、彼は帰国前にそのスーツを捨てることにした。そのとき既にジャイサルメール行きが決まっていた僕は、どうせ捨てられるそのスーツを砂漠まで持って行って写真を撮ってみてはどうだろうか、と考え出した。考え出したら止まらなくなり、とっさにゴミ箱の中からスーツを拾い出してジャイサルメールまで持って行くことにした。同時に、3、4年前の誕生日に当時の大家さんからもらったダサい色のYシャツと、同じくその友人が置いて行った象さん柄のかわいすぎるネクタイも持って行くことにした。
ディーワーリーはインドの正月である。インド中のインド人が家族や親戚に会うために一斉に移動する時期であり、デリー〜ジャイサルメール往復の列車のチケットの入手には多少困難が伴った。だがそこは年の功、ちょっとグレーな方法で何とか手に入れることができた。ディーワーリー前日の10月31日、午後5時25分オールド・デリー駅発の4059デリー・ジャイサルメール・エクスプレスに乗り込んだ。デリーからジャイサルメールまでの距離は924km。デリーからジャイサルメールへ向かう他の2人のメンバーともオールド・デリー駅で合流することができた。彼らとは実はこのときまで面識がなかったのだが、2人ともフレンドリーな人ですぐに仲良くなれた。この内の1人は、デリー連続爆破テロがあった10月29日の夕方にちょうど、最悪の死傷者が出たサロージニー・ナガルのマーケットにいたという、貴重な体験の持ち主である。爆発があったときにちょうど店の中にいて、爆発に巻き込まれずに済んだらしい。しかも賢いことに爆発があった後にすぐにその場を離れたため、二次爆発にも巻き込まれなかったという(サロージニー・ナガルの爆発では、爆弾の他にガスシリンダーが引火して爆発したため、被害が大きくなった)。彼ら2人のチケットは2等AC寝台、僕は3等AC寝台だったので、列車の中では別々であった。
デリー・ジャイサルメール・エクスプレスに乗り込む前に、ハルディーラーム(大手食品会社)の弁当を買うことができた。ノン・ヴェジで99ルピー。発車時の午後5時半頃に手渡されるため、まだ夕食には早いのだが、腹が減っていたために食べてしまった。その後に車内販売の夕食(ヴェジ;30ルピー)も食べたが、こちらのハルディーラームの弁当の方が圧倒的にうまかった。プラットフォームの入り口で従業員が注文を取っているので、見つけたら頼んでみるといいだろう。
オールド・デリーを出たときは車内はかなり空席が目立った。僕のコンパートメントも、僕しか乗客がいなかった。だが、アルワル駅で1組の夫婦がコンパートメントに乗り込んで来て、多少賑やかになった。その後、ジャイプル駅でかなり多くの乗客が乗り込んできた。
翌日になり、午前7時半頃にジョードプル駅に到着した。ジョードプル駅で今度はほとんどの乗客が降りてしまって、僕のコンパートメントにもおばさん1人と僕しかいなくなってしまった。どうやらこの列車はジャイプル〜ジョードプル間の移動によく利用されているようだ。ジョードプルは既にジャイサルメールと同じ文化圏に当たるマールワール地方であり、ジャイサルメールへのアクセス拠点となる街である。だが、まだまだジャイサルメールは地の果てである。昔、デリーとジャイサルメールを結ぶ直通の列車がなかった頃は、このジョードプルで列車を乗り換えなければならなかった。僕が前回ジャイサルメールを訪れたときも、ジョードプルで列車を乗り換えた。早朝ジョードプルに着き、その夜出る夜行列車でジャイサルメールへ向かった。今では直通列車ができて、だいぶ便利になった。
ジョードプルからジャイサルメールは一直線だが、これがまた長い道のりだった。正午12時頃にポーカラン駅に到着。ポーカランは1974年にインドが初めて核実験を行った場所である。駅から見た限りでは、特に何の変哲もない寒村であった。

ポーカラン駅
「国は前進している」という国威発揚的標語が掲げられていた
ジョードプル〜ジャイサルメール間の列車の中では、外国人観光客に話しかける客引きのインド人がけっこういる。ジャイサルメールへ向かう外国人旅行者を、列車の中で青田買いして、自分のホテルやサファリに引き込もうという作戦である。前回ジャイサルメールに来たときは、うんざりするくらい多くの客引きが話しかけて来たが、今回は1人だけだった。ヘンナ・ホテルというホテルを紹介された。後から聞いた話では、日本人旅行者を特にターゲットにするかなり悪質なホテルのようだ。確かに客引きは日本人が好みそうなやけに慇懃な態度で、日本語を少し話していた。だが、日本人をターゲットにするなら、ホテルの名前はどうにかした方がいいだろう・・・。
午後1時半に到着予定だった列車は、午後2時15分頃にジャイサルメール駅に到着した。プラットフォームで他の2人と再び合流。どうやら列車の中で2人とも体調を崩してしまったようで顔色が優れない。ヘンナ・ホテルの客引きが無料のタクシーを用意してくれるというので、それをうまく利用することにした。もちろん、このホテルに宿泊するつもりは毛頭もない。ヘンナ・ホテルは市街地の外れにあるダラムシャーラー(巡礼者用宿泊施設)のような色気のないホテルで、2、3分見ただけですぐに断って出て来てしまった。そこからジャイサルメールの中心部、ゴーパー・チャウクまで歩いた。ゴーパー・チャウク近くにあるホテル・グランド・ヴューで、ジャイサルメールの主である小西氏や、バンガロール方面からやって来る5人と合流することになっていた。
ここでバンガロール方面のメンバーの道順も説明しておこう。5人は10月31日午後5時45分バンガロール発のスパイス・ジェットOS218に乗り、まずは空路でグジャラート州のアハマダーバードへ向かった。午後7時45分にアハマダーバードに到着し、同日の午後10時発の夜行列車に乗ってジョードプルへ向かった。翌日の午前6時50分にジョードプルに着くと、今度はタクシーをチャーターしてジャイサルメールへ向かった。バンガロールからジャイサルメールなら、本当はデリーまで空路来て、僕が乗ったデリー・ジャイサルメール・エクスプレスに乗ってジャイサルメールへ向かった方が便利なのだが、いろいろな事情があってこういう旅程になってしまっていた。ちなみに現在ジャイサルメールの空港は完全に軍用となっており、飛行機で直接ジャイサルメールへ行くことはできない。
僕たちが乗って来た列車が遅れていたので、もしかしたらバンガロール組の方がジャイサルメールに早く着いてしまうかもしれないと思っていたが、結局僕たちの方が早く着いた。ホテル・グランド・ヴューで小西氏と合流する予定だったが、小西氏は買い物に出かけていて留守だったので、ゴーパー・チャウク近くのミッド・タウン・レストランという眺めのいいレストランで軽食を取って皆を待つことにした。バンガロール組は午後3時半頃にゴーパー・チャウクに到着し、無事に合流することができた。小西氏と、その助手で今回のキャメル・サファリを担当してくれるパブー氏とも合流できた。ジャイサルメールで待ち合わせなんてうまくいくかと思っていたが、何とか無事にメンバーが揃った。
ホテル・グランド・ヴューは、ヘンナ・ホテルよりもさらに変なホテルで、あまり宿泊する気にはなれなかった。だが、ディーワーリー時であるし、グジャラート人観光客が大挙して押し寄せて来ているため、他のホテルでまとまった部屋を取ることは難しかった。小西氏が気を利かせて部屋を予約してくれていたこともあり、今日はとりあえずここに宿泊することになった。1泊300ルピー。
今日は小西氏に、ジャイサルメール砦の中を案内してもらうことになった。ジャイサルメール砦の特異な点は、今でも砦の中に人が住んでいることだ。砦の中はブラーフマン区画とラージプート区画に厳密に分かれており、それ以外のカーストの人は住むことが許されていないという。まずは日の入りが迫っていたのでサンセット・ポイントまで連れて行ってもらった。サンセット・ポイントは城塞の北端部分にあり、大砲が置かれていた。ちょうど夕日が砂漠に沈んでいくところだった。遠くには風力発電のための風車の群れが見えた。この風力発電所の電気がジャイサルメールの電力源になっているようだ。そういえば、こんな辺境の地にある街にしては電力が安定していた。城塞内を散歩していたら、昔ジャイサルメールに来たときに撮影したハヌマーンの壁画が、マイナーチェンジされてそのまま残っているのを発見した。ちょっと感動。日の入りの後、漆黒の砂漠の中に煌々と輝く夜のジャイサルメールを見て、「風で光るオアシス(街)、ジャイサルメール」というフレーズが浮かんで来た。

ジャイサルメールの夕日


左は2002年3月24日撮影、右は2005年11月1日撮影。

ジャイサルメールの街の彼方に見える風車
夕食は、小西氏オススメのレストラン、マンディル・パレスへ行った。マンディル・パレスは、現在のジャイサルメールのマハーラーワル(マハーラージャーよりもランクの低い王の称号)、ブリジラージ・スィンの宮殿である(今では1年の大半をグルガーオンの住宅で暮らしているらしいが)。その一角が同名のホテル兼レストランになっている。このレストランでは、マハーラーワルのご馳走を調理している現役コックが料理を作ってくれるため、マハーラーワルと同じ味覚を味わうことができる。値段もお手頃で、料理もうまい。特にサングリーというラージャスターンの郷土料理がおいしかったのが驚いた。ラージャスターニー料理はあまりおいしくなくて有名で、特にこのゴボウみたいなサングリーという料理は可哀想なことにおいしくないラージャスターニー料理の筆頭に挙げられていたのだが、注文してみたらおいしかった。さすがマハーラーワル直属のコック、腕が違う。しかもこのレストランはあまり観光客に知られておらず、今夜の客も我々のみであった。これは穴場である。さらに、屋上の席からはライトアップされたジャイサルメール砦を一望することができた。さらに素晴らしいことに、ディナー中にディーワーリーもたけなわになって来ており、あちこちで花火が上がっていた。これは最高の夜になった!

マンディル・パレスからライトアップされたジャイサルメール砦を眺める
今日から1泊2日の予定でキャメル・サファリへ行く。ジャイサルメールのキャメル・サファリで最も有名なのはサム砂丘やクーリー村であるが、パブーが連れて行ってくれるのは全く観光客が訪れない場所である。ちなみにパブーは、「地球の歩き方インド2000〜2001年版」のジャイサルメールのページに好意的な紹介が載っているくらい有名な人物である。指定部族(ST)のひとつ、ビール族の出身だ。しばらくキャメル・サファリ業からは離れていたようだが、彼は今、財政的危機から再びキャメル・サファリを始めようとしている。そのファースト・カスタマーが我々であった。
10時頃に出発の予定だったが、ホテル・グランド・ヴューの屋上レストランが朝食を作るのにやたらと時間をかけたため、1時間ほど遅れてしまった。ジャイサルメールのレストランは基本的に注文した品が出て来るのが非常に遅い。混んでいなくても30分、混雑時は1時間くらいを見ておいた方がいいだろう。
まずはパブーの自宅までジープで行った。ジープは、パブーが用意してくれた1台と、バンガロール組の5人がジョードプルから4日間チャーターした1台があった。僕を含む4人は、パブーが用意したジープに乗って一足早くジャイサルメールを発ち、残りの4人はジョードプルの運転手ナーラーヤン・スィンが運転するジープで少し遅れて出発することになった。だが、このナーラーヤンがとんでもない奴で、わがままな上に暴走運転をし、我々の旅行を度々窮地に陥れた。後続の4人の出発が遅れたのも、この運転手が髭剃りをしていたからという、しょうもない理由である。それだけならまだしも、この運転手は勝手に暴走して全く違うクーリー村の方向へ行ってしまった。小西氏がバイクで探しに行ってくれたおかげで何とか連れ戻すことができたが、この後も彼の暴走のおかげでひどい目に遭った。ナーラーヤン、ナーラーヤン!
パブーの家は荒野の真ん中にポツンと立っていた。50mほど先にもう1軒の家が建っているが、その他には回りに何もない。家は2部屋だけの小さなもので、壁は素朴な色彩と模様で彩られていた。電気はない。家族構成はよく分からなかったが、パブー、父親、母親、嫁、子供4人、弟、弟嫁が住んでいたと記憶している。はっきり言って、明日の食べ物もないくらいの貧しい家庭である。それでも家族の人々は満面の笑みと共に我々を迎え入れてくれた。まずは昼食をここで食べた。ハルワー(お菓子の一種)と大豆のカレーだった。

パブーの家
昼食後はラクダに乗って移動する予定であったが、問題が生じていた。予めパブーがラクダ業者から予約しておいたラクダがいつまで経っても来なかったのだ。半分前金を払っていたにも関わらず、である。このディーワーリーの時期は一番の掻き入れ時であり、ラクダを手に入れるのは非常に困難となっているらしい。また、グジャラート人観光客が大挙して押し寄せているため、ラクダがそちらの方に取られてしまっている可能性もあった。それに加え、パブーはずっとキャメル・サファリ業から離れていたこともあり、まだ信用がなかったことも考えられる。それでも、約1ヶ月前に予約をし、前金も受け取っているなら、要望通りのラクダを提供するのは、商売人として最低限のマナーである。これはパブーの過ちではなかったので仕方のないことだった。やっとラクダがやって来たのは夕方で、しかも5頭のはずが3頭しか来なかった。
ラクダが来るまでの間、ナーラーヤンの運転するジープに乗り込んで、近隣の見所を回ることになった。本当はラクダで5〜6時間かけて回る予定になっていた場所である。僕は密かにラクダに長時間乗る必要がなくなって胸をなで下ろしていた。前回キャメル・サファリに乗ったときに、股間一帯を痛めた痛い思い出があるからだ。ちゃんとした装備のあるラクダに乗らないと、特に男にとって、拷問を受けているような状態になる。ちょっとだけ、鞍なしのラクダに乗らせてもらったが、やはり辛かった。
まず行ったのは、ゴーレーラーという廃墟の村。ブラーフマンが集住していたが、数百年前のある日、一夜にして無人の村になったという曰く付きのスポットである。既にどの家屋も屋根は崩落していたが、壁は残っていた。かなり大きな村であったことが伺える。この村にまつわる話は、夜、焚き火を囲んで、ということになった。

ゴーレーラー村
この次に行ったのは、幽霊が出ると専らの噂の墓。ヒンドゥー教徒には墓を作る習慣は基本的にないが、ラージャスターン州には墓というより記念碑的性格のものが各地に残っている。記念碑には人の姿が彫刻されている。ほとんどの記念碑は主に男性のもので、そのそばにサティー(夫の火葬時に未亡人がする焼身自殺)を行った妻が寄り添っている形になっている。ここでどんな幽霊が現れるかはよく聞かなかったが、夜になると霊気がモワモワと漂ってくるらしい。この記念碑のそばには美しいオアシスがあった。その湖畔には不思議なことに貝殻が散乱していた。昔、ラージャスターン州が海だったときの名残だとか。

心霊スポット

オアシス
パブーの家に戻ってみるとラクダが来ていた。ラクダの背中には毛布が何重にも積み重ねられていたため、乗り心地はかなりよかった。前回のキャメル・サファリで乗ったラクダがいけなかったみたいだ。このラクダに乗って、全く観光客が訪れない「プライベート砂丘」まで行った。砂漠で砂丘へ行く、というのは、一般の人には少し辺に思われるかもしれない。ラージャスターン州というと「砂漠の州」というイメージがあるが、日本人がイメージするような「どこまでも果てしなく続く砂の砂漠」は、実はラージャスターン州にはほとんどない。大体はステップ気候のような、ポツポツと木々やサボテンが生えたような荒野である。だから、サファリ中に砂だらけの砂丘を見に行くのは全く変なことではない。サム砂丘が最も有名だが、そこは既に一大観光地となってしまっており、日の入り時ともなると観光客が押し寄せてあまり風情がない。その点、パブーのサファリでは誰も他に人が来ないプライベートの砂丘で夕日を見ることができる。また、ここの砂丘は「ダイビング・ポイント」ともなっている。切り立った砂丘の頂上から勢いをつけて飛ぶのである。下は砂なので、特に変な落ち方をしない限りは怪我はしないはずだ。

ラクダの素乗りに挑戦

プライベート砂丘でのジャンプ大会
小西氏ジャンプ中

砂漠に沈む夕日
夜は焚き火を囲んでのキャンプ・ファイヤー。パブーの兄弟たちがアールー・ゴービー(ジャガイモとカリフラワーのカレー)を作ってくれた。これは絶品だったのだが、追加で作ってくれたカレーにはとんでもない量のトウガラシが入っていて食べれたものではなかった。間違ってトウガラシをたくさん入れてしまった、と言っていたが、多分自分たちで食べるためのものを作ったのだろう。ビール族の一般的な料理はとんでもなく辛いらしい。この他、サトウキビから作った自家製の酒も用意してくれた(もちろん密造酒)。焼酎に似たサッパリした味だった。サボテンの酒というのもあるらしいのだが、今回は用意してもらえなかった。

キャンプ・ファイヤー
ところで、日中に行った廃墟の村、ゴーレーラー村の物語について、パブーが語ってくれた――ジャイサルメール周辺にはかつて、ブラーフマンが住む村が84村あったという。ある日、ジャイサルメールの王がその内のひとつクルダラー村を訪れたとき、1人の美しい娘を見つけ、恋に落ちてしまった。王のカーストはクシャトリヤ(戦士階級)、娘のカーストはブラーフマン(司祭階級)、この恋は許されるものではなかった。王もその恋を諦めようとしたが、家臣に「あなたは王です、何でも思い通りです」とそそのかされ、その娘の父親に対し、「娘を差し出すか、それとも84村のブラーフマン全員どこかへ立ち去るか」と選択を迫った。父親は1日の猶予を願い出た。次の日、ジャイサルメール周辺に住んでいた84村のブラーフマンたちは全員消えていなくなっていた。彼らがどこへ行ったのか、誰も知らない――
ネットで調べてみたところ、パブーが語ってくれた話の詳細や間違いが見つかった(参照)。まず、ジャイサルメール周辺に住んでいたブラーフマンは、パーリーワールというコミュニティー名だった。パーリーワールは元々ジョードプル南部のパーリーを起源とするコミュニティーで、13世紀頃にはジャイサルメール周辺に移住していたようだ。パーリーワールは砂漠で農業を可能にするほどの優れた灌漑能力を持っていた。一説によると彼らはインダス文明の灌漑技術の継承者とか。現在ジャイサルメールで見られる灌漑施設のほとんどは、パーリーワールから受け継いだ技術が用いられているという。パーリーワールは非常に勤勉で裕福な一族で、女性の美しさでも有名だった。パーリーワールが住んでいた84の村が一晩にしてもぬけの殻になってしまったのはどうやら本当の話のようだが、その理由については諸説あるようだ。一番有力なのは、マハーラーワルよりも強大な権力を誇った大臣サーリム・スィンが原因となった、という説である。そのサーリム・スィン説にもいくつかパターンがあるが、パーリーワールの巨万の富をやっかんだサーリム・スィンが、彼らに重税をかけたというのが一番納得のいく説のように思われる。パブーが言っていた、サーリム・スィンが村の娘にちょっかいを出した、という説もまことしやかに人々の間で語られており、こちらの方が話としては面白いが、信憑性は低そうだ。パーリーワールの女性たちがあまりに美女として有名だったため、誘拐や強姦の被害に悩まされていたことが原因との説もあった。とにかく1825年、84の村々の村長たちが協議した結果、ジャイサルメールを一斉に放棄することが決定し、彼らは散り散りになって行った。その際、パーリーワールは財宝を村に隠すと共に、「村の石ひとつでも動かした者は呪われる」という呪いをかけて行ったという。そのため、近隣の村人たちは恐れてパーリーワールの村に足を踏み入れようとしなかった。最近、この伝承を聞いた外国人が金属探知機を持ってクルダラー村で宝探しを行い、見事に黄金の装飾品を発見したそうだ。だが、彼らは警察に逮捕され、財宝は没収されてしまった。現在、クルダラー村は観光地となり、フェンスで囲まれ、入場料を払わないと中に入れなくなっている。また、現在パーリーワールは、ビーカーネールやコールカーターに住んでいる他、米国に多く移住しているという。
パブーの話を聞いたり、みんなで歌を歌ったりゲームをしたり、用意してくれた花火で遊んだりして楽しく過ごしていたところ、突然誰かが叫んだ。「サソリだ!」見てみると、火のそばを本当にサソリがノコノコと歩いているではないか!
――ホントのホントにサソリのお出まし・・・!
白色のサソリだった。すぐに誰かがサソリを潰してくれた・・・が、1匹現れたということは、何匹でも現れる可能性があるということではないか!あれだけ前々から怖がっていたサソリが、現実のものとなって目の前に現れてしまった!しかも紛らわしいことに、この辺りの砂漠には黒いフンコロガシが大量に地面を這っていた。身体で何かがカサカサと動く感触がすると、サソリではないかと震え上がってしまう。大抵はフンコロガシなのだが。
こんな怖い思いもしたが、満天の夜空の下で一夜を明かすことができて、いい思い出になった。ちなみにテントなどはなく、砂漠に布団を敷いてそのまま夜空の下で寝た。砂漠の夜はけっこう冷えると聞いていたが、思っていたほど寒くなかった。防寒具として、寝袋、セーター、ショールを持って行ったのだが、どれも使用しなかった。
砂漠で寝ると、夜になってしばらくすると急激に眠くなり、日が昇る少し前に自動的に目が覚めるような気がする。昨夜は横になって流れ星を待っている内にいつの間にか眠ってしまった。そして今朝は日の出の少し前の、薄らと明るくなる頃合いに目が覚めた。ノロノロと起き上がって東の空を見てみると、ちょうど日が昇ったところだった。早速写真に収めた。

砂漠の日の出
朝食はパブーがパコーラー、ゆで卵、チャーイなどを作ってくれた。朝食を食べた後は、パブーの家に戻り、そこからジャイサルメールへ戻った。
ところで、個人的に今回のメインイベントだった、砂漠でスポーツ・カイトと、砂漠でスーツについて報告をしておかなければならない。まず、スポーツ・カイトだが、昨日と今日、どちらも試してみた。砂漠ではビュンビュン風が吹いている聞いていたので、かなり期待していたのだが、残念ながらそれほど強い風は吹いていなかった。どちらかというと昨日の方が強い風が吹いていた。肝心の飛び状況はというと・・・一応今までで最高レベルの滞空時間を記録することができた。だが、安定して空に浮かぶまでには行かず、すぐにバランスを失って地面に落ちてしまった。スポーツ・カイトは難しい・・・。何人かが挑戦したが、一番うまかったのは今回の団体ツアー参加メンバー唯一のインド人、アミト君であった。やっぱりインド人は天性の凧揚げの才能を持っているのだろうか?

砂漠の空翔るスポーツ・カイト
予定通り、砂漠でスーツも着てみた。昨日の夕暮れ時に着て、スーツのまま夜を明かし、今日の朝まで着ていた。写真を何枚か撮ってみたが・・・どうだろうか?サイズが合ってないのはご愛嬌。スーツを着た男が砂漠の向こうから歩いてくる、という構図の写真を撮り忘れてしまったのが悔やまれる。今回持って来たスーツ一式は、サファリ終了時にパブーにプレゼントした。どうせ友人が捨てて行ったものだし、僕のサイズでもなかったため、最初から彼に贈る予定だった。パブーはかなり嬉しかったようで、早速次の日にそのスーツを着ていた。・・・う〜ん、結婚式とか、そういう特別なときに着るためにあげたのだが、日常着として着ていると、すぐに着潰してしまいそうだ。




右下のおじいさんは、砂漠でペプシや煙草を売って歩いている人
その他、今回のサファリ中に気になったことをまとめて書いておこう。まず、最も悩まされたのがオナモミのような棘のある植物であった。砂漠を歩いていると、必ず靴やズボンの裾にオナモミのような棘がいくつも刺さっていた。これを引き抜こうとして失敗すると、指に棘が刺さったりしてチクチク痛い。毛布とかショールとか、知らない間にいろんな場所にくっ付いているので、注意が必要である。
毒スイカなるものがたくさん育っていたのにも驚いた。荒野のあちこちにツタが這っており、小さなスイカのような実がたくさんなっている。これが、食べると24時間ひどい下痢に襲われた後に死に至るという毒スイカなのだ。サソリだけでなく、こんな紛らわしくて危険な植物が生えているとは・・・砂漠とは大変な場所である。

毒スイカ
念のために書いておくが、砂漠にトイレなどない。オープン・エアーで用を足すしかない。幸い、所々にサボテンが生えているので、その裏ですれば一応安心であろう。慣れればサボテンの数だけトイレがあるように思えてくる。
一応、パブーの連絡先をここに記しておく。パブーはホテル・グランド・ヴュー(旧名スニール・バティヤー・レストハウス)にいることが多いようだ。ジャイサルメールで得体の知れない業者に頼むよりも絶対にパブーに頼んだ方がいいので、ジャイサルメールへ行こうと思っている人は参考にしてもらいたい。値段は、シーズンや日程によってかなり変動するのでここで書くことはできないが、小西氏が口添えしてくれたこと、また我々がパブーのサファリ再開の記念すべきファースト・カスタマーだったこともあり、ディーワーリーのハイ・シーズン時期にしては格安の値段にしてもらえた。直通電話は携帯電話で、小西氏とパブーが共有している。小西氏が出れば日本語で話すことができるだろう。パブーは一応英語が分かる。また、次の日記に記したパブーの人生に関する事柄を読んでもらえば、パブーのことが少しよく分かるだろう。
■Pabu's Fullmoon Safaris
住所: Hotel Grand View, Near Fort Gate, Central Market (Gopa Chawk), Jaisalmer,
Rajasthan - 345001
電話(ホテル): 02992-252533
電話(直通): 09828809863
E-mail: fullmoonsafaris@ホットメール・ドット・コム
ジャイサルメールに戻ってからは、まず宿探しをした。市街地よりも城塞内部のホテルに泊まりたいとの要望が強かったので、中で探してみた。だが、前述の通り非常に混雑している時期だったので、全員が同じホテルに泊まることはできず、分散して泊まることになった。僕が泊まったのはホテル・キラー・バヴァンというけっこう高級な部類に入るホテル。城の一角を無理矢理改造してホテルにしているため、部屋は狭いが、フランス人が経営しているだけあってセンスのある内装となっている。1泊2000ルピー。ちょうど予約客がキャンセルをしたため、偶然空き室があって泊まることができた。そうでなければこの時期にこのレベルのホテルに泊まるのは難しいだろう。城塞の入り口にある広場を見渡す絶好の位置の部屋に泊まることができた。
実は今日で8人のグループの内の、デリーから僕と一緒にやって来た2人が諸事情により列車でデリーへ戻ることになっていた。午後2時半頃にゴーパー・チャウクで2人を見送った。その後は各自自由行動となった。僕は、バンガロールのIT企業勤務で、メヘンディー・アーティストとして一部で有名なケヘカシャーンさんと行動を共にした。
ジャイサルメール市内の観光の目玉は、ハヴェーリー(邸宅)巡りである。中継貿易で財を成した豪商や、マハーラーワルよりも権勢を誇った大臣たちのハヴェーリーがジャイサルメール市内の至るところに残っており、街を歩くだけで楽しいのだが、その中でも特に有名なハヴェーリーは3軒。サーリム・スィンのハヴェーリー、パトワー兄弟のハヴェーリー、そしてナトマルのハヴェーリーである。この順でハヴェーリー巡りをした。
サーリム・スィンのハヴェーリーは1815年頃に建造された。サーリム・スィンはキャメル・サファリの項でもちょっと出てきたが、マハーラーワル・ガジ・スィンの主席大臣で、王よりも強大な権力を誇った。砂漠では水が貴重なため、建築にセメントが使われることはなく、代わりに凸凹を使った接合により家が建てられた。現在、サーリム・スィンのハヴェーリーは修復のため一部にセメントが使われているが、それでも当時の建築の工夫を見ることができる。下部は2つの部分に分かれており、片側は男性の居住区域、もう片側はサーリム・スィンの妻たちの居住区域(ザナーナ)となっている。男性居住区域は今でもハヴェーリー所有者の家族が住んでいる。サーリム・スィンのハヴェーリーで特徴的なのは、最上部が張り出して外壁に華麗な装飾が施されていることだ。遠くから見ると、ジャイサルメールの市街地に浮かぶ船のようなので、別名ジャハーズ・マハル(船の宮殿)とも呼ばれている。この最上部の内部は、鏡が一面に張り巡らされたモーティー・マハル(真珠の宮殿)となっており、ここでサーリム・スィンは踊り子の踊りを鑑賞していたという。サーリム・スィンは、このハヴェーリーからジャイサルメール砦まで橋を渡すことまで計画していたらしいが、あまりの横暴ぶりに反感を買って暗殺されてしまったという。入場料は15ルピー、カメラ料は10ルピー。

サーリム・スィンのハヴェーリー
パトワー兄弟のハヴェーリーは1805年の建造。ジャイサルメールで最も美しいハヴェーリーと言われている。ジャイナ教徒の豪商が、5人の息子のために建てたハヴェーリーで、その壁面の繊細で豪華な彫刻は、ただただ見る者の目を奪う。現在、5軒の内2軒に入ることができる。入場料20ルピーの方は簡単な博物館になっており、神棚、応接間、台所、隠しロッカーなどの様子を見れる他、ターバンのコレクションなどが展示されている。入場料2ルピーの方は、安いだけあってあまり見所がないが、月と太陽が彫刻された小窓がユニークだった。どちらのハヴェーリーも、屋上からジャイサルメール砦を一望することができる。

パトワー兄弟のハヴェーリー
ナトマルのハヴェーリーは1885年の建造。やはり時の大臣の邸宅である。2人の兄弟が建てたハヴェーリーで、外から眺めると左右のデザインが微妙に違う。1階は土産物屋になっていて、2階より上に今でも家族が住んでいる。1階入り口の両隅にある象の像が印象的である。

ナトマルのハヴェーリーの前にある象の像
市街地の主要なハヴェーリーを見て回った後は、城塞内の宮殿を見た。元々マハーラーワルが住んでいた7階建ての宮殿である。入場料はインド人20ルピー、外国人70ルピー、カメラ料は50ルピー。武器の展示室から始まり、歴代のマハーラーワルの肖像画の展示、マハーラーワルが使用していた椅子や輿の展示、切手の展示、ジャイサルメール砦の模型などの他、ラング・マハルと呼ばれる一面に壁画が描かれた間や、中国製のタイルで装飾された間などがあった。だが、一室一室が狭く、あまり住み心地はよさそうではなかった。屋上に出ると、ジャイサルメールの城塞部と市街地を一望の下にできる。また、宮殿の前にはマハーラーワルが庶民に謁見する椅子も置かれている。後にジャイサルメールの市場をぶらついているときに見つけた昔の写真では、マハーラーワルが英国人や大臣と共にこの椅子に座っている姿が写っていた。

マハーラーワルの宮殿
ケヘカシャーンさんが、是非ジャイサルメールのメヘンディー(ヘンナ)を試してみたいというので、小西氏オススメのメヘンディーおばさんの場所へ行ってみた。城塞内の北辺、ブラーフマン居住区に住んでいるサントーシュさんである。店の名前はヒーナー・ビューティー・センター。サントーシュおばさんはメヘンディーと手相占いを生業としており、「ロンリー・プラネットに紹介された」という大きな看板が掲げられているのですぐにこれと分かるだろう。ところがこのサントーシュおばさんが相当な曲者で、外国人だと思って適当なメヘンディーを塗りたくられた。僕はあまりメヘンディーのことに詳しくないので何とも言えなかったが、ケヘカシャーンさんはかなりご立腹の様子だった。ちなみに料金は、長く残るというロング・メヘンディーで片手で200ルピーだった。

サントーシュおばさんのメヘンディー
その後、城塞内を歩いていたら、インド人の女の子に「そのメヘンディー、ちょっと見せて」と話し掛けられた。その子は「何これ?子供の遊びみたい。誰がやったの?」と言うので、「サントーシュっていう人にやってもらった」と答えたら、「あの人は全然駄目」と笑っていた。実はその子もメヘンディー塗りであり、よく見るとその子の家の前に「ボビー・ヘンナ・ペインティング」という看板が掲げられていた。ボビーちゃんが「本物の」メヘンディーを塗ってくれるというので、ケヘカシャーンさんは頼むことにした。ちなみにこちらの料金は片手で350ルピー。高いのではないかと思ったが、サントーシュさんのとどう違うのか見てみようということになった。確かにその仕事のきめ細かさの差は一目瞭然であった。ボビーさんのメヘンディーをアジャンター第1窟の壁画に例えるならば、サントーシュおばさんのメヘンディーはビームベートカーの壁画ぐらいのものだ。ジャイサルメールでメヘンディーを塗るならば、絶対にサントーシュおばさんに捕まってはならない。ボビーちゃんのところへ行くべきだ。だが350ルピーは高すぎるので、もっとディスカウントしてもらうべきだろう。ちなみにボビーちゃんは今月中に結婚するらしい。

ボビーちゃんのメヘンディー

アジャンター第1窟の蓮華手菩薩(左)とビームベートカーの壁画(右)
一応どちらも世界遺産
夕食は、ジャイサルメール城塞の第一門の上というすごいロケーションにある、リトル・イタリーというレストランで食べた。相変わらず料理が出て来るのが遅かったが、いかにも外国人が好みそうなエキゾチックな内装で、料理もあまり期待していなかったがなかなかの味だった。早めに行くと、ジャイサルメール城塞を眺めることができる絶好の窓座席を占拠することができる。

リトル・イタリーの窓座席

ホテル・キラー・バヴァンからの眺め
今日はバンガロール組の5人がジャイサルメールを発つ日である。僕も今日の列車でデリーに戻りたかったのだが、あいにく席が取れず、明日の列車で帰ることになった。つまり、団体旅行の中で僕だけ取り残されてしまうことになる。だが、小西氏やパブーが相手をしてくれたため、孤独な居残りにはならずに済んだ。
朝9時過ぎにバンガロール組を見送った後、ホテルでチェックアウト時間の12時までゆっくりとくつろいでいた。ただでさえ課題が溜まっていたときにジャイサルメール旅行を決行してしまったため、何冊か読まなければならない本を旅行に持って来ていた。このとき読んでいたのは、ギーターンジャリ・パーンデーイ著の「Between
Two Worlds : An Intellectual Biography of Premchand」(Manohar; 1989)である。ヒンディー文学の巨匠プレームチャンドについて書かれた、おそらく世界で最良の本である。残念なことに英語で書かれている。残念、と表現したのは、別に英語を読むのが苦手だというわけではない。ヒンディー文学を代表する文学者についての最良の文献がヒンディー語で書かれていないことは、非常に憂慮すべき事態だ、ということだ。
12時にホテルをチェックアウトし、再びホテル・グランド・ヴューに宿を移した。ここで小西氏、パブーと合流し、一緒に昼食を食べに行った。連れて行ってもらったのはガーンディー・チャウク近くにあるターリー屋チャンダンシュリーで、安くておいしいと地元ではけっこう有名のようだ。しかし、ここにもグジャラート人観光客の大群が押し寄せており、座る場所もないほど。2人掛けの席に3人で座ってターリーを食べた。ラージャスターニー・ターリー、グジャラーティー・ターリー、パンジャービー・ターリーなどなど、各種ターリーが用意されているが、僕たちはスタンダードなターリーを食べた(30ルピー)。ジャガイモのサブジー(カレー)、ダール、ダヒー、ローティー、ご飯、生野菜など、全てお代わり自由で、特にサブジーがうまかった。
その後はホテルに戻って1時間ほど休憩し、今度は僕の要望に従って骨董品店へ連れて行ってもらった。昔、ラージャスターン州南東部のブーンディーという田舎町に行ったときに、ホテルや市場で珍しい骨董品の数々を目にし、ラージャスターン州にはまだまだ面白いものが残っているのではないかと思うようになった。ジャイサルメールは既に完全に観光地化してしまっており、そういうものはもうあまり残っていないかもしれないと思いつつも、地元の人の協力があれば何か新たな発見があるような気がして、パブーに連れて行ってもらった。行った場所は、ジャイサルメール一番の繁華街であるバティヤー・マーケットにあるデザート・ハンディクラフト・エンポリアムという店。はっきり言ってただのお土産屋だが、奥の方に近隣の住宅から買い上げた骨董品の品々が無造作に置かれている。まず目が行ったのが、神様ポスターの生みの親、ラージャー・ラヴィ・ヴァルマーのリトグラフの数々。ラヴィ・ヴァルマー直筆サイン入り(店の親父自称)の「メーナカーとシャクンタラー」の他、スィーター・スワヤンヴァルの絵、7人の聖仙がヤッギャ(儀式)を執り行う絵、シヴァとパールワティーの絵など、けっこう貴重そうなリトグラフがボロボロの額付きで売られていた。また、ホーリーのときに使う金属製の水鉄砲で、噴出口が象の形に象られたものや、豹の顔が象られた短刀など、なかなかかっこいいものがいくつか見つかった。その中で最も食指が動いたのが、店の床にドデンと置かれていた盾。表面は禿げかかっているが、所々に狩猟風景の絵が描かれているのが確認できる。中央に描かれた太陽のマークは、この盾がジョードプルのラトール王家のものであることを示していた。これだ、これしかない!早速値段交渉を始めたところ、言い値は9000ルピー。店主のラクシュミー・ナーラーヤン・カトリーは割と無頓着な値段の付け方をしていたので、適当に交渉をしていたらどんどん値が下がった。妥当なところで手を打って購入した。しかし、こんなもの果たして日本に持って帰れるのだろうか?考古品の持ち出しは厳しく制限されているので、もしかしたら空港で逮捕されたりするかもしれない。とりあえずは自宅に飾っておく予定である。

ラトール王家の盾
他にこの店で、1945年発行の1パイサー貨幣を1枚、盾のオマケでもらった。このコイン、真ん中に丸い穴の空いた、いわゆる穴銭である。日本人は、穴の開いた5円玉や50円玉を、世界でも珍しい貨幣だと思い込んでいる節があるが、実は近代インドにも穴銭は流通していた。昔、コイン・コレクターの友人に「インドにも穴銭があったんだよ」と言ったら「そんなはずはない」と否定されたので、自論の正しさを証明する証拠として購入した。英語で「1
Pice」「India」、英数字で「1945」と記されている他、デーヴナーグリー文字とウルドゥー文字で「1パイサー」と書かれている。裏面は唐草文様のような模様となっている。以下に写真を載せるが、デジカメの調子が悪いのであまり鮮明な写真は撮影できなかった。

1945年発行の1パイサー貨幣
今夜、パブーが自宅でマトン料理を作ってくれるというので、小西氏所有のバイク、ヒーロー・ホンダのCDドーン(100cc)に小西氏、パブー、僕の3人で乗ってパブーの家に再びお邪魔した。家に着くや否やパブーの家族が笑顔で迎えてくれた。パブーの家には、ボーパーと呼ばれる呪術師が来ていた。パブーはいくら頑張っても貧困から抜け出せないので、ボーパーにお祓いをしてもらおうとしているらしい。もう既に一寸先も見えないくらいの真っ暗闇だった。焚き火を囲み、サファリ中も飲んだサトウキビの酒を飲みながら夕食ができるのを待った。電気もなく、周囲に何もないこの家では、夜中にやることと言ったら、食うか、飲むか、寝るか、セックスか、あとはおしゃべりぐらいしかない。こうやって焚き火を囲んで話をしている内に、詩が生まれ、歌が生まれ、口承文学が生まれて行ったのだなぁ、と何となく考えていた。電気もないようなところで寝泊りするのは、サファリなどのツアーを除けばこれが初めてかもしれない。しかし、闇の向こうの地平線では、風力発電の風車がチカチカと光っている。ここで発電された電力は、グジャラート州に送られるそうだ。地元の人々はこんな電気もない貧しい生活を送っているのに、その周囲をこれでもか、というくらいの風車が取り囲んでいる。この状況に理不尽さを感じない者はいないのではなかろうか?ところで、パブーが作ってくれたマトン・カレーはこれまた絶品であった。しかし、またもからい!からすぎる!全く手加減なしのからさである。ヒィヒィフゥフゥ言って食べなければならない。やっぱりこの人たち、自分で食べたいものを作っているとしか思えない。それにしても、インド亜大陸の辺境地域の料理は激辛なことが多いような気がする。ノースイーストの料理しかり、このジャイサルメールの料理しかり。実は北インド平野部の一般的なインド料理は、日本人が思っているほどからくはない。本当にからい料理は辺境地帯にある。貧しい民族ほどからい食べ物を好むという仮説があるが、それは当たっているかもしれない。
ところで、小西氏の話によるとパブーの人生は本当に貧困と苦難の連続のようだ。まず、パブーが属するビール族は指定部族(ST)と呼ばれ、差別の対象になっていることが不幸の始まりである。ビール族は元々アラーヴァリー山脈に住んでいた狩猟採集民だが、時代の変遷と共に平地にも移り住むようになった。ラージャスターン州のビール族は、ラージプートに雇用されて戦争に駆り出されることがけっこうあったようだ。メーワール王国のラーナー・プラタープ・スィンがビール族と協力してムガル王朝の勢力に対抗したことは有名である。ただし、協力と言えば聞こえはいいが、その実は「人間の盾」に近いものだったようだ。戦争になると、ビール族は特攻隊として真っ先に敵陣に突っ込まされ、その後悠々とラージプートの騎兵隊が突撃を行う、というのが一般的だったという。ジャイサルメールのビール族の立場もその程度のものだった。今でもビール族に対する差別は残っている。パブーは昔、貧困から脱出するためにキャメル・サファリ業者を始め、「地球の歩き方」にも紹介されるほどビジネスは好調の波に乗ったようだが、同業者からの妨害と差別に遭い、仕事を辞めざるをえなくなってしまったという。だが、当時のパブーはまだ20歳そこらの若者だった。今ではパブーもだいぶ逞しくなり、人脈も増えたため、仕事を再開しても当時ほど困難はない状況になってきている。そんなことを考えていた矢先にちょうど僕たちがキャメル・サファリのアレンジを頼んだようだ。だから、僕たちも小西氏やパブーがいてくれて助かったのだが、それと同じくらい彼らも僕たちの存在がありがたかったという。ラクダが来なかったりして多少細かいトラブルはあったが、特にキャンプ・ファイヤーのときの気配りや盛り上げ様など、ブランクを感じさせないサファリ手腕だったと思う。
サファリ事業再開が成功するといいのだが、パブーの人生には多くの問題が山積している。その全てを聞いたわけではないが、部分部分を聞いただけでも涙が流れてくる。小西氏とパブーが出会ったのは10年前のようだが、そのときに比べてパブーの財政状況は悪化の一途を辿っているという。借金に借金を重ねる生活で、利子もいつの間にか莫大な額になってしまっている。今回のサファリで儲けた金も、全て借金の返済にあててもうスッカラカンらしい。しかもあるときなどは、凶暴なラージプートの高利貸しに借金の形に娘を誘拐され、レイプされた上に1ヶ月間売春させられたという。その娘の結婚は去年何とか無事に済んだようだが、およそ法治国家とは思えないほどの前時代的残虐非道な話だ。また、昨年には農業を本格的に始めて貧困から脱出しようと奮起し、全財産をはたき、方々から借金をしてトラクターを購入したが、これも差別の一環なのかパブーは騙されてしまったようで、不良品をつかまされて大失敗。ますます財政難に陥ってしまったという。この他、パブーは子供の頃にコブラに噛まれて片目の視力を失っている他、つい最近事故にあって片足の親指をなくしてしまった。だが、そんな不幸はどうでもいいと思えてしまうくらい、彼の人生には不幸と困難が付きまとっている。そしてもっとすごいのは、こんな人生を生きていても人間らしい笑顔を失っていないばかりか、その笑顔は幸せな生活を送っている我々日本人よりも輝いていることだ。僕はパブーがこんなにまで不幸な生活を送っているとは、外見からは全く予想もできなかった。小西氏から話を聞いて初めて知ったくらいだ。
これらの話を聞いて、僕は「ゴーダーン(牛供養)」のホーリーを思い出さざるをえなかった。「ゴーダーン」は先に紹介したプレームチャンドが、死ぬ直前の1936年に発表した最高傑作であり、ヒンディー文学の金字塔である。そしてその主人公ホーリーは、ヒンディー文学を代表する不朽のヒーローと言っても過言ではない。プレームチャンドは、1930年代の北インドの農民の窮状を鋭い分析と共にひとつの作品にまとめ上げた。ホーリーは何とか貧困から脱出しようと努力するのだが、貧しい者をますます貧しくする帝国主義、資本主義、封建主義の三重構造の魔の手にがんじがらめとなって、何事もうまくいかずにますます借金地獄に陥り、農民の命である土地まで売り払い、最後には低賃金労働者となって炎天下の中で重仕事をして死んでしまう。ホーリーは序盤で「一生に一度でいいから立派な牛を持ってみたい」という夢を実現させ、友人から素晴らしい牛を買い取るが、それをやっかんだ親戚により牛は毒殺され、借金だけが残ってしまう。このシーンは、パブーのトラクターと見事に一致した。また、借金の形にパブーの娘が誘拐された出来事は、終盤で娘を老人に売る形で結婚させざるをえなかったホーリーの姿を思い出させる。70年前に書かれた「ゴーダーン」の窮状は、21世紀に入った現在のインドでもどれだけ真実であることか!一体何人のホーリーが、好調な経済発展を遂げつつあるように見えるこのインドの隅々に取り残されていることか!決して「ゴーダーン」は完全なるフィクションでもないし、完全なる歴史でもない。今でも「ゴーダーン」は生きている。「ゴーダーン」だけではない、今でもプレームチャンドの一連の作品群は、インドを理解する上で有用であり、また必須であると思った。ちなみに、筑摩書房の世界文学大系インド集に土井久弥先生が翻訳した「牛供養」が載っているが、不当な理由により半ば勝手に大部分が省略されてしまっており、あまりいい訳にはなっていない。インドが今までにないほど日本人の注目を浴びつつある中、「ゴーダーン」の完訳は急務であろう。
夜は、パブーの家の屋上に小西氏と2人で寝転がって、満天の夜空を眺めながら寝た。小西氏は、パブーを助手にしてビール族の研究を行っているが、それと同時に何とかパブーの貧困脱出作戦を成功させようと色々プランを練っている。僕ももはや傍観者ではいられないので、微力ながらこのウェブサイトを使ってパブーのキャメル・サファリを宣伝することを請け負った(前日の日記にパブーの連絡先が掲載されている)。パブーのサファリが果たして万人にとって楽しいものになるかどうかは分からないし、僕もそれを保証することはできない。だが、少なくとも前回ジャイサルメールを訪れたときに体験したサファリよりも断然素晴らしい思い出になったし、もし次にジャイサルメールに行くことがあれば、また彼にサファリを頼みたいと思っている。あとは、僕が書いた体験記を読んで各自で判断してもらいたい。
| ◆ |
11月5日(土) ジャイサルメール・デリー・エクスプレス |
◆ |
再び砂漠の朝日で目が覚めた。なぜかパブーの家のそばに行商人がキャンプを張っていた。もしかして何かレア物が見つかるかもしれないと思って売り物を見せてもらったが、衣服や生活雑貨など、何の変哲もない商品ばかりしか積んでいなかった。
パブーの家族がしきりに畑を見せたがるので、お言葉に甘えてパブー家所有の畑まで連れて行ってもらった。多分畑くらいしか見せるものがないのだろう。パブーは所要があって出掛けていたため、僕と小西氏の他、パブーの母親と弟、そして行商人の息子(?)が同行した。畑はパブーの家から歩いて10分程の地点にあった。その途中には学校の建物があった。しかしここの先生は評判が悪く、1ヶ月に7日くらいしか学校に来ないという。これでは子供の教育もたかが知れている。畑に行ってみると、そこにはパブーの父親がいた。このとき初めて父親に会った。父親は家にはほとんど帰って来ず、畑で寝泊りして管理しているという。そういえば夜の砂漠では、列車が走るような音がどこからともなくして来る。てっきりどこかに線路が通っているのかと思っていたが、途中ですぐに音が途切れてしまうため、列車とも思えなかった。不思議になって聞いてみると、あれは畑の作物を荒らす鳥や牛などの動物を追い払うためのもので、畑を管理している人が出している音だそうだ。パブーの父親も、あの音を出していたのだろうか。
畑にはスイカとパパイヤがなっていた。特にスイカは大豊作とのこと。今年はインド中で大雨が降ったが、年に雨が降るか降らないか、というここジャイサルメールでも雨が例年に比べてたくさん降ったようで、これだけ雨が降るならスイカでも植えてみよう、ということになったらしい。それが功を奏し、多くのスイカが実った。ただ、その農業の様子はほとんど原始農業に近く、スイカのツタが無造作に地面に伸び、まるでビー玉を地面に散らかしたかのようにスイカの実があちこちに無秩序に転がっている。換金作物として作っているのではなく、完全に自分たちで食べるために作ったものだ。パブーの母親や弟は、あちこちからスイカを取ってきては、素手で数回チョップして真っ二つに割り、僕たちにくれた。熟れているスイカはほんのりと甘いのだが、熟れていないスイカはただの瓜である。彼らの中では、熟れているスイカを見つけるゲームのようになっており、そこら辺から適当にスイカを取って来ては割って遊んでいた。せっかく実ったスイカを、そんな風に無駄にしてしまうとは・・・。また、ここら辺で採れるパパイヤは全然甘くなくておいしくなかった。果物の他、バージラー(キビ)も植えたようなのだが、うまく育たなかったようだ。そういえば昨晩、バージラーのローティーを1枚食べさせてもらったが、とても食べれたものではなかった。ゲーフーン(小麦)のローティーのおいしさを実感した。
畑から戻るとパブーも戻って来ていた。朝食にダールとローティーを出してもらって、それを食べてからまたバイクでジャイサルメールに戻った。ホテルでシャワーを浴びた後、サーリム・スィンのハヴェーリーの隣にあるナトラージ・レストランで昼食を食べた。ここのレストランは多少高めだが、料理が出て来るのも早いし味もおいしかった。
今日は午後3時半発の4060ジャイサルメール・デリー・エクスプレスに乗ってデリーに戻る。小西氏とパブーに駅まで送ってもらい、列車に乗り込んだ。ところが僕のコンパートメントで怪しい人物を発見した。座席の下にスーツケースを置いて、そのまま立ち去ってしまったのだ。乗客ではないのに荷物だけ列車に置く人物・・・これは不審人物だ!もしかして爆弾か何かが中に入っているのではなかろうか・・・。そう思うと急に不安になって来た。だが、同じコンパートメントに入って来た家族がこれまた騒々しかったので、すぐにそんな不安は忘れ、悶々と座席に座っていた。
ジャイサルメールとジョードプルの間では、ポーカラン駅ぐらいでしか軽食や飲み物を補給することができない。だからジャイサルメール駅で最低でも水を買っておかないと後悔するだろう。夕食はジョードプル駅に着く午後10時頃に出て来る。ジョードプルを過ぎるとまた食事が手に入らなくなるため、ジャイサルメール〜デリー間では、ポーカラン駅とジョードプル駅での食糧補給が重要そうだ。ちなみにジョードプル駅を過ぎた辺りで出てきた車内食は、ノンヴェジで60ルピー。味は悪くなかったが、やたらと量が多くて残してしまった。
翌日目が覚めると、いつの間にかジャイプル駅は通り過ぎていた。アルワル駅を過ぎた辺りで大体地理が掴めた。あとはレーワーリー駅に到着すると既にハリヤーナー州。その後はグルガーオン駅に止まった。デリーはもうすぐだ。午前11時頃にデリー・カント駅に到着。同じコンパートメントにいた騒々しい家族もこの駅で降車した。すると、急にジャイサルメール駅で不審人物が残して行ったスーツケースが気になり出した。やっぱりこれは爆弾なのではないか・・・。次の終点オールド・デリー駅に着いた途端に爆発したりして・・・。最近デリーも物騒なので、なるべく危険を避けるに越したことはない。それにオールド・デリー駅で降りてもデリー・カント駅で降りても、それほど距離は変わりない。そこで僕も急いでデリー・カント駅で降りることにした。デリー・カント駅からはオート・リクシャーに乗り自宅へ。ジャイサルメールの骨董品屋で買った盾も無事に自宅に収容した。
インドでは毎年ディーワーリー祭(インドの正月)の時期に期待作が一気に公開される傾向にある。去年のディーワーリーには、「Veer-Zaara」「Mughal-e-Azam」「Aitraaz」「Naach」という全く趣を異にした期待作4本が同時公開され話題を呼んだ。今年のディーワーリーもやはり期待作が3本同時公開となった。「Kyon
Ki...」「Garam Masala」「Shaadi No.1」である。通常、インドでは新作映画の封切日は金曜日なのだが、今年は変則的にディーワーリーの翌日の11月2日(水)がそれらの映画の封切日となった。
ジャイサルメール旅行から帰って来た後、まず見たのは、プリヤダルシャン監督、サルマーン・カーンとカリーナー・カプール主演の「Kyon Ki...」。PVRプリヤーで鑑賞。題名の意味は「なぜって・・・」という意味。プリヤダルシャン監督はケーララ州出身の映画監督で、「コメディーの帝王」と称される有名監督の1人である。最近公開されたプリヤダルシャン監督のボリウッド映画では、「Hungama」(2003年)や「Hulchul」(2004年)が記憶に新しい。今年のディーワーリーは、どういう風の吹き回しか、プリヤダルシャン監督の映画が2本同時公開となった。この「Kyon
Ki...」と「Garam Masala」である。まだ「Garam Masala」は見ていないが、前者は悲劇、後者は喜劇のようで、プリヤダルシャン監督の才能の幅を見せ付ける一人舞台のようになっている。「Kyon
Ki...」の音楽監督はヒメーシュ・レーシャミヤー。キャストは、サルマーン・カーン、カリーナー・カプール、リーミー・セーン、ジャッキー・シュロフ、オーム・プリー、スニール・シェッティーなど。
| Kyon Ki... |
 アーナンド(サルマーン・カーン)は、悪ふざけの行き過ぎにより妻のマーヤー(リーミー・セーン)を溺死させてしまい、精神に異常をきたしてしまった男だった。アーナンドの兄は、彼をクラーナー院長(オーム・プリー)の経営する精神病院に入院させる。クラーナー院長は厳格な人間で、病院の医者、従業員、患者たちから恐れられていた。その病院では、昔アーナンドの父親の家で働いていた使用人の息子で、現在は医者になったスニール(ジャッキー・シュロフ)や、クラーナー院長の娘のタンヴィー(カリーナー・カプール)が働いていた。【写真は、サルマーン・カーン(右上)とカリーナー・カプール(右下)】 アーナンド(サルマーン・カーン)は、悪ふざけの行き過ぎにより妻のマーヤー(リーミー・セーン)を溺死させてしまい、精神に異常をきたしてしまった男だった。アーナンドの兄は、彼をクラーナー院長(オーム・プリー)の経営する精神病院に入院させる。クラーナー院長は厳格な人間で、病院の医者、従業員、患者たちから恐れられていた。その病院では、昔アーナンドの父親の家で働いていた使用人の息子で、現在は医者になったスニール(ジャッキー・シュロフ)や、クラーナー院長の娘のタンヴィー(カリーナー・カプール)が働いていた。【写真は、サルマーン・カーン(右上)とカリーナー・カプール(右下)】
タンヴィーは、36番の番号札を付けていた精神患者のおばさんを手厚く看病していたが、完治したと同時にそのおばさんは彼女のことをすっかり忘れてしまっていた。それに心を痛めていたタンヴィーは、そのおばさんの代わりに36番の番号札を付けて入院して来たアーナンドに当初は冷たく接していた。一方、スニールはかつての雇い主の息子と哀れな状況で再会したことに心を痛めると同時に運命を感じ、彼の治療に全力を尽くすことを心に決めていた。
アーナンドはまるで5歳の子供のように悪戯好きで、病院で問題を起こしてばかりいた。クラーナー院長もアーナンドを要注意人物と認識するようになる。一方、スニールはタンヴィーに、アーナンドのアルバムを渡し、彼の治療に協力するように頼む。タンヴィーはアーナンドの過去を知り、彼に対する態度を変え、愛を持って接するようになる。医者と患者の関係は、次第に恋愛へと発展して行った。タンヴィーの献身により、アーナンドは正気を取り戻す。
ところがクラーナー院長は、娘の結婚相手にカラン(スニール・シェッティー)を選んでいた。ところが、アーナンドとタンヴィーが恋仲にあることを知ったクラーナー院長は、アーナンドを意地でも退院させないことを決め、地下に閉じ込める。アーナンドは脱走してクラーナー院長に飛びつき首を絞める。警備員が急いで駆けつけたことによりクラーナー院長は一命を取り留めるが、アーナンドに手術を施して植物人間にし、復讐を遂げる。植物人間となったアーナンドを見たスニールは、彼のために何もしてやれなかったことを謝り、彼の顔に枕を押し付けて殺す。一方、アーナンドと駆け落ちをしようとしていたタンヴィーは、アーナンドが死んだことにショックを受け、精神異常者となってしまう。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
ボリウッドのスターたちの中では、「Koi... Mil Gaya」(2003年)でのリティク・ローシャンの知能障害児の好演以来、精神に異常をきたしたり、何らかの障害を持つ主人公を演じて映画賞を獲得してやろうという安易な潮流ができているように思われる。その傾向はハリウッドでも顕著で、例えばトム・ハンクスなんかがその罠にはまっているように思われる。「Kyon
Ki...」もその流れで作られたような気がしてならなかった。
もっとも、サルマーン・カーンが今までのヒーロー像を覆す役を演じたのはこれが初めてではない。「Tere Naam」(2003年)では既に半植物人間を演じているし、「Phir
Milenge」(2004年)ではエイズに冒されて死んでいく人の役を演じた。しかし、今回の「Kyon Ki...」の演技は、これまで以上にサルマーン・カーンの「スターから演技派への脱皮」の野望をヒシヒシと感じた。ただ、野望は感じたのだが、それが必ずしも成功していたとは思えない。子供のようにはしゃぐ彼の演技にはまだ自分を捨て切れていない部分がかなり残っていた。やっぱり無駄に筋肉を見せびらかしているし、踊りも相変わらず固い。
その点、ヒロインのカリーナー・カプールの演技は光っていた。サルマーンに比べると活躍の場は少なかったが、シリアスな役をしっかりと演じていて大女優の片鱗を見ることができた。僕は彼女の「今にも泣きそうで鼻の先っぽや頬がほんのりと赤くなっている」表情が大好きである。イケイケギャルのイメージの強いカリーナーではあるが、僕は彼女には悲劇女優の才能の方があると思っている。
しかし、演技の点で最も光っていたのは、オーム・プリーとジャッキー・シュロフであろう。オーム・プリーは既に演技派男優として誰もが認めているのでこれ以上賞賛する必要はないが、ジャッキー・シュロフの脇役演技の秀逸さが光っていた。かつてはジャッキーも主役をはれる男優だったが、いつの間にか脇役男優に甘んじることが多くなってしまっている。「Devdas」(2002年)のチュンニー・バーブーなどは名演であった。だが、実はジャッキーは脇役の方が演技力を発揮できる男優かもしれない。ジャッキーの演じるスニールが、アーナンドに自分のことを必死に思い出させようと努力するシーンなどは、彼の演技力のおかげで映画の見所のひとつにまで磨き上げられていたと思う。
しかしながら、「Kyon Ki...」は万人に受けるような傑作映画とは言いがたかった。一番盛り下がるのは、アーナンドの過去のシーン。マーヤーと出会い、恋に落ち、そして彼女が死んでしまうという一連の流れが、かなり幼稚な手法で描かれていてガッカリした。この過去のシーンは欧州のどこかでロケが行われていたが、どこの国なのかは特定できなかった。教会の神父がインド人だったり、白人の修道女たちが突然ヒンディー語を話し出すのも唐突すぎる。精神病院の中のシーンも、プリヤダルシャン監督お得意のコメディータッチが随所に活かされていたが、見ているこっちがバカになるほど低レベルなお笑いで引いてしまった。僕は映画館に「おかあさんといっしょ」を見に来たんじゃない!この映画の中で最大の爆笑シーンは、アーナンドがマーヤーに告白するシーンではなかろうか?マーヤーの前で自動車のウィンドウをウィーンと上げると、そこに「I
Love You」と書いてあるのだ。これは恥ずかし過ぎる。ただ、終盤に入るとストーリーがまとまって来る。アーナンドが死に、タンヴィーが精神患者になってしまうというアンハッピーエンドで終わるところは意外だった。
「Kyon Ki...」の音楽で名作と呼べるのは、テーマ曲の「Kyon Ki Itna Pyar」のみであろう。マーヤーの死がアーナンドの精神障害の原因となっていることを見抜いたタンヴィーが、マーヤーになりすまして、アーナンドとマーヤーの思い出の歌であるこの「Kyon
Ki Itna Pyar」を歌うシーンは感動的である。そしてその歌詞「なぜなら私はあなたのことをこんなにも愛しているから・・・」は、そのままタンヴィーのアーナンドに対する気持ちの発露となっている。
主人公の名前がアーナンド(享楽)と名付けられたのは、若き日のアミターブ・バッチャンが出演する「Anand」(1970年)に対するオマージュなのではないかと思う。だが、「Anand」のエンディングにあった「感動的アンハッピーエンド」のラス(情感)は、「Kyon
Ki...」にはなかった。
アーナンドが付けられた36番という番号の意味は、ヒンディー語をよく知る人なら分かるだろう。ヒンディー語で「36」と言ったら、「仲が悪い」という意味なのだ。その理由はヒンディー語の数字の形を見れば分かる。まるでお互いが背をそむけたような形になっているのだ。
コメディーの帝王が挑戦した悲劇映画は、残念ながら精彩を欠いていた。インド各地に勢力を持つサルマーン・カーン親衛隊たちが大挙してこの映画を見るために映画館に押し寄せるだろうが、長続きはしないだろう。
今日は、ディーワーリーの翌日の2日から公開された3本の新作ヒンディー語映画の1つ、「Shaadi No.1」をPVRアヌパムで見た。ボリウッド映画には、「Cooli
No.1」(1995年)、「Hero No.1」(1997年)、「Biwi No.1」(1999年)、「Jodi No.1」(2001年)など、「〜No.1」という題名の一連の名作コメディー映画があるが、この映画もそれらの例に漏れず、ヴァーシュ・バグナーニー制作、デーヴィッド・ダワン監督の映画である。
「Shaadi No.1」とは、直訳すれば「結婚No.1」という意味。監督は前述の通り、ボリウッド界の「コメディーの帝王」、デーヴィッド・ダワン。「Kyon
Ki...」のプリヤダルシャン監督も「コメディーの帝王」の称号を持っており、今年のディーワーリーはコメディーの帝王同士の直接対決になったとも言える。音楽監督はアヌ・マリク。キャストは、サンジャイ・ダット、ファルディーン・カーン、ザイド・カーン、シャルマン・ジョーシー、アーイシャー・タキヤー、イーシャー・デーオール、ソーハー・アリー・カーン、リヤー・セーン、ソフィー・チャウドリー、アールティー・チャブリヤー、サティーシュ・シャー、ラージパール・ヤーダヴなど。
| Shaadi No.1 |
 ラージ(ファルディーン・カーン)、ヴィール(ザイド・カーン)、アーリヤン(シャルマン・ジョーシー)は、それぞれバーヴナー(アーイシャー・タキヤー)、ディヤー(イーシャー・デーオール)、ソニア(ソーハー・アリー・カーン)の3姉妹と結婚していたが、妻たちから蔑ろにされていた。気が滅入った3人は自殺を計るが、そのとき、ビジネスがうまく行かずに同じく自殺しようとしていたコーターリー社長(サティーシュ・シャー)を助け、それがきっかけとなって3人はコーターリーの会社で働き出す。【写真は左から、アーイシャー・タキヤー、アールティー・チャブリヤー、ファルディーン・カーン、ソフィー・チャウドリー、イーシャー・デーオール、ザイド・カーン、リヤー・セーン、シャルマン・ジョーシー、ソーハー・アリー・カーン】 ラージ(ファルディーン・カーン)、ヴィール(ザイド・カーン)、アーリヤン(シャルマン・ジョーシー)は、それぞれバーヴナー(アーイシャー・タキヤー)、ディヤー(イーシャー・デーオール)、ソニア(ソーハー・アリー・カーン)の3姉妹と結婚していたが、妻たちから蔑ろにされていた。気が滅入った3人は自殺を計るが、そのとき、ビジネスがうまく行かずに同じく自殺しようとしていたコーターリー社長(サティーシュ・シャー)を助け、それがきっかけとなって3人はコーターリーの会社で働き出す。【写真は左から、アーイシャー・タキヤー、アールティー・チャブリヤー、ファルディーン・カーン、ソフィー・チャウドリー、イーシャー・デーオール、ザイド・カーン、リヤー・セーン、シャルマン・ジョーシー、ソーハー・アリー・カーン】
ところが、コーターリー社長には別の問題があった。それは彼の3人の娘のことだった。コーターリー社長は既に娘たちの結婚相手を決めていたが、フランスに住む娘たちは恋愛結婚しかしないと言い張っているのだった。そこでラージたちは、コーターリーの3人の娘と恋愛してこっぴどく振り、恋愛に失望させる任務を負うことになる。
フランスに渡ったラージはレーカー(アールティー・チャブリヤー)と、ヴィールはディンプル(ソフィー・チャウドリー)と、アーリヤンはマードゥリー(リヤー・セーン)と出会い、首尾よく付き合うようになるが、演技のつもりで恋愛をしていたラージたちは本当に彼女たちを愛するようになってしまう。コーターリーの3人娘たちは、インドに帰ったラージたちを追ってインドに来てしまう。
インドに帰ったラージたちは、家におかしな男が来ているのに気付く。ラクヴィンダル・スィン、通称ラッキー(サンジャイ・ダット)。妻たちの遠い親戚だという。ラージたちはコーターリーの3人娘たちと外で浮気をするが、それをラッキーに見られてしまう。ラッキーは3姉妹にそのことを知らせるが、彼女たちは自分の夫を信じ、ラッキーの言うことを聞かなかった。また、コーターリーはラージたちに騙されたことを知って怒る。
ラッキーの妨害やコーターリーの密告のせいで、やがてラージたちが浮気をしていたことがばれてしまう。ラージたちはコーターリーの3人娘と無理に結婚しようとするが、3人娘にもラージたちが実は既婚者であったことがばれてしまう。一度に妻とガールフレンドを失ってしまった3人は、飛び降り自殺しようとする。それを助けようとした妻たちも落ちそうになってしまうが、ラッキーの活躍により妻たちは無傷で済み、ラージたちも重傷を負ったものの生きながらえる。こうしてラージたち3人の家庭はラッキーの活躍のおかげで何とか元通りになった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
ボリウッドでは2004年の「Masti」あたりから不倫コメディー映画が流行しているようだ。最近では「No Entry」が秀逸だった。「Shaadi
No.1」も不倫がテーマの爆笑コメディー映画である。上記の3つの不倫コメディー映画は、偶然か故意か、3人の男性たちが不倫や浮気の道に足を踏み入れてしまったために繰り広げられるしっちゃかめっちゃかのドタバタ劇という点で共通している。ただ、「Shaadi
No.1」が特殊だったのは、サンジャイ・ダット演じるラッカーが重要な役割を果たしていることだ。だが、最後のクライマックスは稚拙過ぎて興醒めであった。
サンジャイ・ダットは、泣く子も黙るマフィア役を演じさせると世界最強なのだが、実はコメディーの才能もけっこうある。デーヴィッド・ダワン監督の「Ek
Aur Ek Gyarah」(2003年)を見たときはあまりサンジャイ・ダットにコメディーは似合わないのではないかと思っていたが、「Munnabhai
MBBS」(2003年)を見た瞬間にその考えが180度変わった。サンジャイ・ダットは優れたコメディアンでもある。「Musafir」(2004年)でサンジャイ・ダットが演じたビッラーは、マフィアとコメディアンの見事な融合と言っても過言ではなく、彼にしかできない役だろう。「Shaadi
No.1」でもサンジャイ・ダットは遺憾なくコメディーの才能を発揮している。サンジャイ・ダットは、その強面でマッチョな外見に騙されがちだが、実はかなり多才で繊細な俳優だと最近思っている。何しろ彼もボリウッド・サラブレッドの1人だ(父は大俳優スニール・ダット、母は大女優ナルギス)。
サンジャイ・ダット、ファルディーン・カーン、その他の脇役俳優を除けば、この映画に出演している俳優は若手ばかりである。ボリウッドの世代交代を促進させる意味でも、若い才能を発掘する意味でも、この試みは歓迎したい。しかし、いかんせん登場人物が多すぎて、一人一人の俳優の活躍の場は限られていた。特に女優は一気に6人登場。イーシャー・デーオールくらいは何とか認知度がそこそこあるだろうし、リヤー・セーンもまあ少しは名の知られた女優と言っていいだろうが、アーイシャー・タキヤー、ソーハー・アリー・カーン(サイフ・アリー・カーンの妹)などはまだデビューしたてであるし、アールティー・チャブリヤーやソフィー・チャウドリーに至っては、ボリウッド映画をマメに見ている僕でも知らなかったくらいだ。あまりインド映画を見ない人がこの映画を見たら、女優の顔がみんな同じに見えて混乱することは避けられないと思われる。
僕は常々「インド映画の真髄はコメディー映画にあり」と公言しているが、この映画もいかにもインド人が好きそうなコメディー映画であった。コメディー映画と一口に言ってもその面白さの種類はいくつもあるが、この映画で最も優れていたのはセリフ回しであった。セリフのひとつひとつに韻が踏まれていたり、掛け言葉が巧妙に織り込まれていたり、珍妙な例えがポンポン飛び出したりした。特にラッキー兄貴がしつこく繰り返すおかしな「ミサール(諺)」は爆笑ポイントである。この映画でインド人と同じタイミングで笑える人は、ヒンディー語がネイティヴ・レベルに達したと自負していいだろう。ちなみに映画の最後にラッキー兄貴が観客に向かって言うミサールは、「スィーター・ラームやラーダー・クリシュナの話は神様のもの、人間の話になったら『Shaadi
No.1』のことを出しな」というものだった。文末の「bhagwaan ki」と、「Shaadi No.1 ki」で韻が踏まれていた。ヴァ!ヴァ!このマザー(面白さ)はヒンディー語が分からないと味わえないだろう。
この映画は既婚男性の不倫が主なテーマになっていたが、もうひとつ重要なテーマは、「お見合い結婚か、恋愛結婚か」であった。バーヴナー、ディヤー、ソニアの3人と、マードゥリー、ディンプル、レーカーの3人が、それについて議論をするシーンは面白い。既に結婚しているバーヴナーたちはお見合い結婚派で、「恋愛は結婚してからするもの」というインドの伝統的価値観を主張する。一方、マードゥリーたちは断然恋愛結婚派で、「服を買うときは必ず試着をするように、結婚前に恋愛をすることは必須」と主張する。だが、結局この議論の結論は映画中では出されておらず、どちらかというとお見合い結婚の方に軍配が上がった形でエンディングとなっていた。ちなみに、ラージたち3人の不倫相手、マードゥリー、ディンプル、レーカーは、ボリウッドの有名女優、マードゥリー・ディークシト、ディンプル・カパーリヤー、レーカーから来ていることは明らかである。
前述の通り、この映画はセリフを吟味すると面白いが、その中で気になった単語は「ラクシュマン・レーカー」であった。「ラクシュマン」とは、ラーム王子の弟のことで、「レーカー」とは「線」という意味だ。インドに生活している人の間で「ラクシュマン・レーカー」と言ったら、蟻やゴキブリを部屋の中に入って来なくするための薬品が思い浮かぶだろう。一応その語源は、中世バクティ詩人トゥルスィーダースがアワディー方言で著した「ラームチャリトマーナス」(現在インドで広く読まれているラーム王子の物語は、実はサンスクリット語の「ラーマーヤナ」ではなく、この「ラームチャリトマーナス」である)において、森林に隠棲中、ラクシュマンがスィーターに対し「この線を越えて外に出てはいけません」と言って引いた線のことである。スィーターはうっかりその線を越えて外に出てしまったため、ラーヴァンに誘拐されてしまった。この神話から、ラクシュマン・レーカーとは、「既婚の男女が越えてはいけない一線」、つまり「貞節と不倫の間の線」という意味を持っているようだ。
アヌ・マリクの音楽はピンキリであるが、「Shaadi No.1」もそんな感じであった。「Hello Madam, Hello Madam,
I am your Adam」という親父ギャグ的歌詞が面白い「Hello Madam」や、「艶かしい」という意味の単語「Aiyashi」が繰り返される「Aiyashi,
Aiyashi」が優れていたと思う。ダイアログと同様、歌の歌詞もよく聞くといろいろ際どいことを歌っている。
「Dhoom」(2004年)の大ヒット以来、ボリウッド映画ではバイクが流行しているが、この映画ではカリズマの改造車が登場する。どこかのバイク屋でカスタムしてもらえるようで、最近デリーでも改造されたカリズマが走っているのをよく見る。僕はやってもらおうとは思わないが。
「Shaadi No.1」は人を選ぶ映画だと思う。サンジャイ・ダットが好きな人、コメディー映画をセリフで笑えるくらいヒンディー語が分かる人、ちょっと卑猥な映画が好きな人にはオススメだと言えるだろう。登場人物が多すぎる上に知名度の低い若手俳優が大量出演するため、ボリウッド初心者にはちょっとつらい。夫婦やカップル向けの映画ではない。あまりの卑猥さに途中で退席してしまう観客がチラホラいた。気の置けない男友達と見に行きたい映画である。
毎年11月には、日本文化月間(Japan Cultural Month)と称される一連の日本文化紹介イベントが開催される。今年のメインイベントのひとつは、インド初の雅楽公演であった。主催はジャパン・ファウンデーション、公演を行うのは音輪会(おとのわかい)というグループである。本日午後6時半より、シュリーラーム・センターにて公演が行われた。雅楽と言っても、日本人の僕にもあまりピンと来ないので、インド人はあまり興味を持たないのではないかと思ったが、意外や意外、会場はほぼ満席状態で、日本人よりもインド人の観客の方が圧倒的に多かった。日本文化好きっぽい白人の観客も目立った。
2部構成になっており、1部では楽器のみの演奏、2部では舞を伴った演奏となっていた。その合間にリーダーの人の挨拶と、楽器の簡単な説明があった。今回は管楽器と打楽器のみで、弦楽器がなかった。各楽器の説明があったが、特に印象に残ったのは笙(しょう)という楽器であった。17本の竹の筒から成った管楽器で、その音は「天から差し込む光」を模していると言われている。確かに天女の羽衣がなびくような、この世のものとは思えない美しい旋律を奏でる楽器である。雅楽で必ず耳にする音だ。この楽器、演奏中も常に温めておかないと音が出なくなるという面倒な特徴を持っており、演奏者のそばには必ずストーブが置かれるという。
雅楽は7世紀に仏教と共に日本に伝来した音楽で、インドとも関係があるという。インドから伝来したという曲や舞を披露してくれたが、現在のインド音楽やインド舞踊の面影はあまりなかったように感じた。逆に、中国から伝わったという、龍のお面をかぶって踊る舞の方が、インドっぽさを感じた。舞は基本的にかなりのんびりとした動作で、ブータンの踊りを髣髴とさせた。
雅楽とインド音楽の理論的な部分の共通性については全く足を踏み込むことができないが、雅楽について解説したホームページ(参照)で以下のような記述を見つけ、インド音楽ともしかしたら共通しているかもしれないと思った。
管絃の演奏では通常は1つの調子の曲のみを演奏します。1回のコンサートで2つ以上の調子を演奏することはほとんどありません。
演奏会のプログラムでは、まず最初に音取(ねとり)と呼ばれる1分くらいの短いチューニングのための曲が演奏されます。これは各楽器の主奏者と鞨鼓のみで演奏され、チューニングを合わせる目的(特に絃楽器)と、観客に対してこれから演奏する調子の雰囲気を提示するという2つの目的で行われます。
雅楽で言う「調子」とは、インド音楽で言う「ラーガ」に近いものかもしれない。1回のコンサートで2つ以上の調子を演奏することがあまりないのも、インド音楽の伝統的な演奏会と似ている。音取という行為も、インド音楽のアーラープを思い出させる。もっとも、アーラープには打楽器の演奏はないが。
現在、芸術の世界は西洋で確立した理論がさも世界標準であるかのように流布しているが、世界の芸術の歴史を注意深く探っていくと、もしかしたら西洋の芸術理論の方が特殊なのではないかと思うこともある。近代西洋音楽は調性音楽と言われるが、そのような特徴を持った音楽は世界のどこにもないだろう。西洋絵画ではルネサンス期頃から遠近法が確立したが、やはりそのような特徴を持った絵画も世界のどこにもなかっただろう。雅楽にインド音楽との共通性を見出すことはいくらでも可能だが、結局現在の我々を支配している芸術観念が特殊なだけであり、それら「東洋音楽」の共通性と見受けられるものは、人間が人間としての五感や想像力をもって作り出す限り自然に形成されるもので、特に驚くに値しないものなのではないか、と思うことがある。

龍のお面をつけて踊る(The Hinduより)
中身は女性であった
ところで、楽器の演奏者たちは、藍色の和服に黒の烏帽子をかぶって登場した。はっきり言って何だかださかった・・・。もっと派手な衣装はないのだろうか?できることなら雅楽の演奏者には眼鏡をかけてもらいたくない。何となく雰囲気が壊れる。代わりに踊り手はかなり派手な衣装を着て登場したが、かなり重そうだった。もっと軽装で踊った方がいいのではないだろうか?それにしても日本国皇帝はこんな色気のない踊りや音楽を鑑賞して楽しんでいたのか、とインド人っぽい感想を抱いてしまった。ベリーダンスとか、その類のものはなかったのだろうか?皇帝なんだからもっと酒池肉林しとけばよかったのに。
僕は常々インド人は「男性的」なものが好きだと言っているが、今回の催し物はどちらかというと女性的だったと思う。雅楽の演奏も繊細かつスローテンポだったし、舞もパワフルなものはなかった。果たしてインド人観客がどういう感想を持ったのか、正直な感想を聞くことはできなかったが、公演開始時にはほぼ満席だった会場が、公演終了時には半分くらい空席になっていたところを見ると、あまり満足してもらえなかったのではないかと思った。僕もはっきり言って退屈であった。マサーラーが足りないのだ。マサーラーはなくてもいいが、京料理のように薄味な印象を受けた。インド音楽のコンサートは徐々にテンポが早くなって行って、最後に超絶スピードになったりするし、合間にちょっとしたお笑いの要素が入ることも多く、何だか気分が高揚するが、雅楽の演奏は終始同じようなテンポで、ギャグもなく、感情の起伏がなかった。例えるならば、日本の最新式エレベーターに乗っているような感覚か。スムーズ過ぎて楽しくない、というか。インドのエレベーターはいつもガタガタしてるし、操作法がよく分からなかったりするし、常に「途中で停電になったらどうしよう」という不安が付きまとったりするので、何となく面白い。・・・もう僕は日本人の視点で日本の芸術を鑑賞することは不可能かもしれない。
ちなみに、司会兼通訳はジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)日本語科のマンジュシュリー・チャウハーン先生が担当していた。ジャパン・ファウンデーションのイベントなどにはよく引っ張り出される、大和撫子タイプの女教授である。英語もうまいし、日本語も一応できるし、司会にはピッタリの人材であろう。しかしひとつ気になったのは、彼女が「インドは天国」という言葉の通訳をはぐらかせていたことだ。雅楽は仏教と共に日本に伝来したものである。当時の日本人にとってインドは天の軸であり、そこから伝わった雅楽は天国の音楽であった。日本人はインドのことを天国と考えていたのであった。しかし、音輪会のリーダーがそのことを日本語で話したとき、チャウハーン先生は「インドは天国」という言葉を絶対に使わなかった。何度も何度もリーダーは「我々にとってインドは天国だった」とリップ・サービスをするのだが、チャウハーン先生はその部分をうまく別の言葉に置き換えて通訳していた。なぜだろう?遠慮したのだろうか、それとも国民民主連合(NDA)のスローガン「India
Shining」を思い出すから言いたくなかったのだろうか?
今日は、11月2日から公開されたヒンディー語映画「Garam Masala」をPVRプリヤーで見た。今年のディーワーリーには、3本の映画が同時公開された。「Kyon
Ki...」、「Shaadi No.1」、そしてこの「Garam Masala」である。「Kyon Ki...」と「Garam Masala」の監督はプリヤダルシャンで同一。「Kyon
Ki...」は、ちょっとお笑いのスパイスも入った悲劇映画であったが、「Garam Masala」は完全なるコメディー映画であった。そして奇しくもデーヴィッド・ダワン監督の「Shaadi
No.1」と、この「Garam Masala」は、どちらも浮気をテーマにしたコメディー映画ということで競合していた。
「Garam Masala」、つまりガラム・マサーラーとは予め混合されたスパイスのことであり、インド料理に使われる調味料であるが、特に何がどの比率で混合されるかは家庭やレストランによって様々で決まっておらず、厳密には食品名とは言いがたい。また、インド映画のことを「マサーラー・ムーヴィー」と呼ぶことがあるが、これはいろんな要素が詰め込まれたインド映画の特徴を、いろんなスパイスがミックスされたガラム・マサーラーに喩えたものである。映画中、「ガラム・マサーラー」という名の雑誌が出て来るが、それよりも映画全体のスパイシーな雰囲気を題名に込めたと考えた方がいいだろう。監督はプリヤダルシャン、音楽はプリータム。キャストは、アクシャイ・クマール、ジョン・アブラハム、ネーハー・ドゥーピヤー、リーミー・セーン、パレーシュ・ラーワル、ラージパール・ヤーダヴと、3人の新人女優、デイジー、ニートゥー、ナルギスなど。
| Garam Masala |
 舞台はモーリシャス。マック(アクシャイ・クマール)とサム(ジョン・アブラハム)は同じ雑誌会社に勤めるヘッポコ写真家コンビだった。2人はルームメイトでかつ親友であったが、会社の受付のマッギー(ネーハー・ドゥーピヤー)を巡る恋敵でもあった。マックにはアンジャリー(リーミー・セーン)という許婚がいたが、彼はあまり結婚する気がなかった。【写真は、アクシャイ・クマール(左)とジョン・アブラハム(右)】 舞台はモーリシャス。マック(アクシャイ・クマール)とサム(ジョン・アブラハム)は同じ雑誌会社に勤めるヘッポコ写真家コンビだった。2人はルームメイトでかつ親友であったが、会社の受付のマッギー(ネーハー・ドゥーピヤー)を巡る恋敵でもあった。マックにはアンジャリー(リーミー・セーン)という許婚がいたが、彼はあまり結婚する気がなかった。【写真は、アクシャイ・クマール(左)とジョン・アブラハム(右)】
サムは有名写真家から写真をもらってそれを国際写真コンテストに出し見事受賞する。その功績によりサムは昇進した上に会社からボーナスと1ヶ月間の米国旅行をプレゼントされる。また、マッギーは完全にマックを無視するようになる。親友だと思っていたサムの出し抜けに絶望したマックはマッギーよりもいい女を見つけるため、アンジャリーの前から姿をくらますと同時に、年中空いている豪華フラットの管理人に就職し、3人のスチュワーデス、プリーティ(デイジー)、スウィーティー(ニートゥー)、プージャー(ナルギス)と同時に恋愛を始める。マックは気難しい料理人のマンボー(パレーシュ・ラーワル)を雇って、彼にもそれに協力をさせる。マックは3人それぞれと婚約し、自分が管理するフラットに住まわせるようになる。
ところが米国からサムが帰って来てマックの家に住み始めると、次第に事がややこしくなって来る。飛行機のスケジュールが狂うと、彼女たちが鉢合わせにならないよう奔走しなければならなかったし、アンジャリーにも居場所が知れてしまった。また、サムはマックに協力するように見せかけ、3人のスチュワーデスたちを口説いたりしていた。
しかしとうとうアンジャリーと3人のスチュワーデスに真実が知れてしまった。アンジャリーは怒ってインドに帰国するために空港へ向かう。アンジャリーを追いかけてマックとサムは空港まで行き、何とか彼女を引き止めるが、今度はスチュワーデスの大群から追われることになる。マックの運命やいかに・・・。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
一応舞台はモーリシャスなのだが、どこの国の話なのか分からないほど無国籍な舞台設定。脳みそを家に置いて映画館に出掛けても理解できるほど単純だが、よく考えば考えるほど前後の脈絡がチンプンカンプンになってくるストーリー。最初から最後まで女性を遊びの道具としか捉えない男尊女卑的思想で一貫されており、改善の糸口も見えないその偏見性。欠点を挙げるとキリがないが、ギャグと音楽がよかったため、何とかまあまあの満足感と共に映画館を出ることができる映画にまとまっていた。
何年間もヒンディー語映画を見続けており、ヒンディー語の勉強も怠っていないつもりなので、もう最近では通常のヒンディー語映画を見ていてストーリーを見失うことはかなり少なくなった。映画のセリフは、100%とはいかないまでもかなり聴き取ることができるし、インド映画の方程式も身体で理解してきた。しかし、この映画では少なくとも2回、筋を見失ってしまった。ひとつはマックが3人のスチュワーデスと同時に付き合うようになった経緯、もうひとつはマックがマンボーという料理人を雇うようになった経緯についてである。特に前者は映画の中核であり、その動機が説得力ある展開で説明されていなかったのは残念であった。
そしてさらに観客を混乱させるのは、3人のスチュワーデスの見分けが付きにくいことである。3人とも新人女優であるが、「モーニング娘。」のような「ブスというわけでもないが際立って美人でもない」というレベルの似たような顔の女の子が3人交互に出て来るので、誰が誰だか分からなくなる。別に誰が誰だか理解していなくても映画の筋は理解できるほど単純ではあるのだが、どうせならもっと個性のある顔の女優を3人並べてほしかった。

「Garam Masala」でデビューした3人、
デイジー、ニートゥー、ナルギス
誰が誰だか分からない・・・
これら3人の新人女優がけっこう重要な役割を担っていたのとは対照的に、既にデビューしてしばらく経っている若手女優2人の存在感があまりに薄かったのも不思議でしょうがなかった。マッギーを演じたネーハー・ドゥーピヤーは2002年のミス・インディアで、既に主役を演じるほどの女優に成長して来ているのに、今回は非常に限定的で全く重要でない役での出演であった。アンジャリーを演じたリーミー・セーンは、「Dhoom」に出演していた女優であり、やはり既に数本の映画に出演しているが、彼女も全く活かされていなかった。
脇を固めるのはインドを代表するコメディアン、パレーシュ・ラーワルとラージパール・ヤーダヴの2人。特にパレーシュ・ラーワルの活躍が目立った。内容のないことをさも内容があるかのように延々としゃべり続けるマシンガン・トークは絶品。せっかく作った料理をゴミ箱に捨てるシーンが哀愁を誘う。
プリヤダルシャン監督の映画は、最後に必ず、登場人物総登場のドタバタ劇が繰り広げられることで有名である。「Hungama」(2003年)や「Hulchul」(2004年)がその好例だ。しかし、「Garam
Masala」のクライマックスにはプリヤダルシャン監督らしいドタバタが用意されておらず、かなり尻すぼみ的な終わり方となってしまっていた。
この映画の見所のひとつは、アクシャイ・クマールとジョン・アブラハムの絶妙のコンビである。2人が共演するのはこれが初めてだ。アクシャイ・クマールは過去にも「Hera
Pheri」(2000年)や「Mujhse Shaadi Karogi」(2004年)などでコメディー役を演じているが、ジョン・アブラハムがコミックロールを演じたのはこれが初めてである。今までアクションヒーローのイメージが強かったジョンだが、今回はかなり今までのイメージをぶち破るピエロ振りを見せてくれた。2人の息が意外にピッタリと合っていた他、どちらもワイルドなハンサムさを売りにしており、スクリーン上の相性もよかった。ジョンは現在人気沸騰中。彼が映画中、「俺はまだ独身、ガールフレンド募集中」とセリフをしゃべった瞬間、観客席のあちこちから黄色い声が上がったほどだ。ちなみにジョンはビパーシャー・バスと付き合っている。
もうひとつの見所は音楽の踊り。「Dhoom」の大ヒットで一躍名を上げた音楽監督プリータムが作曲しており、聞くだけで身体が動き出すようなアップテンポの名曲がいくつかあった。冒頭のクレジットシーンで流れる「Ada」、パンジャービー・ソング「Chori
Chori」、アドナーン・サミーが歌う「Kiss Me Baby」、「ドゥバドゥバドゥバ・・・」というリフレインが耳に残る「Dil Samandar」などが秀逸。「Garam
Masala」のサントラCDは買って損はない。
ちなみにこの映画は、プリヤダルシャン監督自身が監督したマラヤーラム語映画「Boeing Boeing」(1985年)のリメイクである。しかもその映画は、ハリウッドの「Boeing
Boeing」(1965年)のリメイクとなっている。
これでディーワーリーに同時公開された3本の映画を全て見たことになる。当然のことながら3本の内でどれが最も優れていたか、判断を下したくなる。はっきり言ってどれも期待外れだったのだが、期待外れながら優劣を付けたい。どうやらデリーでの観客動員数からいくと、この「Garam
Masala」が1番のようだ。2週目の今日でもけっこう観客が入っていた。だが、「Garam Masala」も「Shaadi No.1」もうまくまとまったコメディー映画とは言いがたく、テーマも道徳的でなくて「家族の祭典」であるディーワーリー向けではないように思える。よって、僕は悲劇映画ではあるが「Kyon
Ki...」をディーワーリー三部作の中で最も優れた作品だとしたい。
僕が通うジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)の名前は、当然のことながらインド初代首相パンディト・ジャワーハルラール・ネルーから来ている。だが、意外なことに大学構内に今までジャワーハルラール・ネルーの立像はどこにも立っていなかった(胸像ぐらいならどこかの建物の中にあるかもしれない)。そこでネルーの立像を立てようという動きが数年前から起こったようで、その像が遂に完成し、本日除幕式が行われることになった。ビマン・ダースというインド人彫刻家の作品。除幕式を執り行うのは、マンモーハン・スィン首相。人材開発省(インドの文部省)のアルジュン・スィン大臣も臨席した。

ジャワーハルラール・ネルーの像
昨年はアブドゥル・カラーム大統領がJNUに来て講演を行ったのだが、そのとき僕は行きそびれてしまったので、今回は是非スィン首相の講演を聴きに行こうと思った。会場はJNUスタジアム。スタジアムと言ってもただの運動場みたいなもので、屋外である。午前11時〜11時半の間に入場しないとセキュリティーの関係で締め出されると聞いたので、11時前に大学に到着するように家を出た。
僕の自宅からJNUへ通じる道(アフリカ・アヴェニューやアウター・リング・ロード)は、大量の警官により警備されていた。JNU構内に入ると、まずは「マンモーハン・スィン首相、JNUへようこそ」と書かれた横断幕が目に入った。と、その次には「ゴー・バック!マンモーハン・スィン」と書かれた横断幕が掲げられていた。こんなことをするのは・・・一部の「プログレッシブ」な学生に違いない。早くも不穏な空気を感じ取っていた。
なるべく目立たない場所にバイクを停め、携帯電話をバイクの座席の下にしまい、会場へ向かった。インドではこういうイベントではカメラや携帯電話などの電子機器の持ち込みは厳しく制限される。特に最近デリーは物騒だ。10月29日にはデリー連続爆破テロが起こったし、最近は「何者かがハイジャックと自爆テロを計画している」という噂が広まっているため、空港は厳戒態勢となっている。会場にはJNUの学生証や身分証がなければ入れない。学生は比較的簡単に入れてもらえたが、職員などは警察から簡単な職務質問をされていた。
JNUスタジアムの客席は一部のみ屋根があるだけだ。そこが特等席ということになる。けっこう早めに行ったつもりだったのだが、既に特等席は埋まっていた。仕方ないので直射日光が容赦なく降り注ぐ日向席へ腰を下ろした。もう11月だが、日中の日差しはまだまだ強い。帽子を持って来るほど用意もよくなかった。僕が座った場所の目の前には、パナソニック製のフラットTVが置かれていた。マンモーハン・スィン首相はまずアドミニストレーション・ブロックでジャワーハルラール・ネルー像の除幕式を行い、それからJNUスタジアムに来るようだが、除幕式の様子はこのTVで見れるようになっているようだった。しかしTVには終始サハラ砂漠の砂嵐がザァーザァー言ってるだけで、とうとう終わりまで何も映し出されなかった。いかにもインドらしいいい加減さだ・・・。
12時頃に、ラージェンドラ・プラサード学長、バッターチャリヤ大学副総長、カラン・スィン大学総長、アルジュン・スィン大臣などがやって来て、ステージの上の座席に着席した。すると、ターター社のRV車サファリの大規模な車列がモウモウと砂塵を巻き上げてやって来た。スィン首相だ!TVCMみたいにかっこいい登場シーンである!その内の2台がステージの裏に突っ込んでくる。同時に黒服を来たSPたちが走行中の車から飛び降りて警護を始めた。まるでボリウッド映画みたいだ!しばらくすると、壇上にマンモーハン・スィン首相が現れた。やはりあの水色のターバンをかぶっていた。あのターバンの下はつるっぱげらしいぞ!ということは気にせず、我々はスタンディング・オベーションでスィン首相を迎えた。

マンモーハン・スィン首相
JNUに現役の首相が講演に来たのは、JNU創立の1969年以来これが初めてのことらしい。1982年にもインディラー・ガーンディー首相(当時)がJNUで講演を行う予定だったのだが、学生たちの抗議運動により構内に入ることができずに中止となってしまったそうだ。だからけっこう歴史的な瞬間に立ち会えたことになる。また、経済学者としても知られるマンモーハン・スィン首相は、かつてJNUで教鞭を取っていたこともあり、1976年からJNUの名誉教授となっている。
バッターチャリヤ大学副総長、カラン・スィン大学総長、アルジュン・スィン大臣などがまずスピーチを行った後、いよいよスィン首相の講演となった。首相が演説台に立つと・・・恐れていたことが起こってしまった。一部の学生たちが黒旗を上げ、「ワーパス・ジャーオー!(帰れ!)」とプロテストをし始めたのだ。プロテストをしていたのは、インド共産党マルクス・レーニン主義派(CPI−ML)の下部組織、全インド学生連合(AISA)の連中を中心とした過激派の学生たちである。今まで首相の方向を向いていたTVカメラが一斉に客席の方を向いた。それに呼応するかのように、今度はインド共産党マルクス主義派(CPI−M)の下部組織であるインド学生連合(SFI)が、「マンモーハン・スィン万歳!」と連呼し始めた。AISAとSFIは、現在JNUの学生自治会(JNUSU)を連立で牛耳っており、現行の統一進歩連合(UPA)政権の政策に反対の姿勢を取っている点では共通しているが、今回のマンモーハン・スィン首相のJNU訪問に際して抗議するか否かで意見が対立していたようだ。その原因は単純だと思われる。CPI−MはUPA政権に閣外協力をしているが、CPI−MLは現政権とは何の関係も持っていない。それだけならまだしも、国民会議派の下部組織であるインド国民学生連合(NSUI)の学生たちが、妨害をやめないAISAの学生たちに殴りかかったようだ。おかげで警察が乗り出して事態を統制しなければならなくなっていた。会場は「マンモーハン・スィンは帰れ!」「マンモーハン・スィン万歳!」「マルクス主義万歳!」「革命万歳!」「学生全員に奨学金を!」みたいなシュプレヒコール連呼合戦となっていた。ちなみに、インド人民党(BJP)の下部組織である全インド学生連合(ABVP)は特に目立った活動を行わなかった。これらの出来事は全て、幸い僕が座っていた場所の反対側で起こっていたため、僕には何の危害もなかった。

乱闘の様子(The Hinduより)
一方、スィン首相はしばらく事態の沈静化を待っていたが、それが無理だと分かるとプロテストを気にせずにスピーチを始めてしまった。皮肉なことに、首相のスピーチは現在その場で起こっていることと全く正反対のものであった。スィン首相は、「我々は大学において、意見の相違に対してどのようにして取り組むのかを学ぶ。意見を自由に述べると同時に、他人の意見を尊重する重要性を認識する。大学のコミュニティーに属する者は全て、ヴォルテールの有名な格言を受け容れなければならない。ヴォルテールは、『私はあなたの意見には賛同しないが、私は死ぬまで、あなたの意見を述べる権利を否定しない』と述べた。この格言は、リベラルな教育機関で守られなければならない最低限の摂理である。君たち諸君は、大学において学問以上のことを学び、就職以上のことを手に入れなければならない」と述べた。そして最後にスィン首相は、イクバールの「sitaron ke aage jahaan aur bhi hain / abhi ishq ke imtihaan aur bhi hain(星の彼方にもまだ世界がある/まだ愛の試練は始まったばかりだ)」という有名な詩を謳ってスピーチを終えた。・・・が、スィン首相のヒンディー語の下手さには驚いてしまった。パンジャーブ人なのであまり得意でなくても不思議ではないが・・・もしかしてソニア・ガーンディーの方がヒンディー語うまかったりして。ちなみに、講演の司会はヒンディー語だったが、スピーチはほぼ全て英語で行われていた。
AISAは具体的には、国際原子力機関(IAEA)理事会でインドがイランに対して反対票を投じたこと、西ベンガル州での米国との共同軍事演習、石油の値上げなど貧困者の生活を直撃する政策などに抗議活動を行いたかったようだ。しかし、抗議の方法は他にいくらでもあっただろう。首相がこれからスピーチをするというときに野次を飛ばすのは、民主主義的な方法ではないし、ましてや大人の態度ではない。民主主義的な手段で選ばれた一国の首相に対しては、いかにその政策に不満があろうとも、敬意ある態度で臨むのが教養層としての最低限のマナーであろう。今回の出来事は、首相に対する不敬行為であると同時に、JNUの「赤っ恥」を全国にさらしてしまったと言っても過言ではない。当日午後のニュースや翌日の新聞にはしっかりJNUで起こったハプニングが報道されていた。元々JNUは共産主義者の巣窟になっているが、最近の過度の左傾化は目に余るものがある。しかももっとも残念なのが、JNUで最も過激な左翼活動を行っている共産主義活動家の1人、サンディープが僕の元クラスメイトであることだ。イラーハーバード大学時代も爆弾を爆発させたりして相当過激な学生運動を行っていたようで、おそらく将来は有名な左翼政治家になっていくのではないかと思う。彼を見ていると、「Hazaaron
Khwaishein Aisi」という映画を思い出してしまう。彼はラージプートだが、ヤーダヴ(牛飼いカースト)の女の子と禁断のカースト間恋愛をしている一面もある。こっちの方は応援してあげたいのだが・・・。
ところで、2時間ほど炎天下の中座っていたために、熱中症気味になってしまった。以上のような不愉快な出来事も相まって、今日は何もする気になれなかった。

■追記(11月16日):昨日はスィク教の教祖グル・ナーナクの誕生日でデリーは休日だった。その翌日の今日、大学へ行ってみたら、まだ首相訪問時のハプニングの興奮が冷めておらず、学生たちは各々の意見を大声で議論し合っていた。授業中でもそのことが話題に上り、クラスメイトたちは真っ二つに分かれて議論をしていた。一方はCPI−M系のSFIを中心とした学生たち、他方はCPI−ML系のAISAの学生である。聞くところによると、首相訪問前、大学当局と学生自治会(AISAとSFIが与党)の間で、「首相に対して抗議活動や妨害行為を行わない」という協定が結ばれたらしい。しかし、AISAの内部で、首相訪問を政治的アピールのためのチャンスとして捉え、強行に抗議活動を行うことを主張する一派がなかなか妥協せず、おかげでAISAのリーダーであり学生自治会理事長であるモーナー・ダースは、首相訪問中にJNUの外に出るという異例の事態になった。そしてその過激派は宣言通り首相のスピーチ中に抗議活動を行ったというわけである。
やはりJNUの学生の間では、AISAに対して批判が集中しているようだ。まず、大学当局との間の協定を違反したことが槍玉にあげられた。大変な裏切り行為だ。しかも、民主主義の原理である選挙に立候補した結果、自治会を運営しているならば、民主主義の基本原則は自ずと遵守する義務が出て来る。民主主義の世界では、抗議の方法にもマナーがある。誰にでも抗議をする権利があるのと同様、誰にでも意見を言う権利がある。スピーチの前に一瞬抗議の声を上げたり、黒旗や黒シャツを着たりする方法ならまだしも、誰かがスピーチをしている間中、シュプレヒコールを連呼して妨害をするのは民主主義の重大な違反である、というのが批判の概要であった。
一方、AISAの学生も負けてはいなかった。AISAの学生によると、まずSFIは「政権の椅子に座った軟弱な団体」であり、AISAは「常に命を捨てて権力に立ち向かう団体」とのことであった。革命のために命を捧げるAISAの党員の平均寿命は50歳に達していない、と誇らしげに語っていた。そして、大学当局との協定は協定ではなく、「ただの情報である」と主張していた。黙ってスピーチを聞いて、覚書を手渡しているだけでは何の変革もない、我々が抗議の声を上げたことにより政府の不正に世間の注目が集まった、無意味ではなかった、お前たちはどうせ大学を卒業したら、就職したり奨学金を得たりして米国などへ高飛びしてしまうだろうが、俺たちは一生インドのために命を捧げる、というのがAISA側の主張であった。
議論は次第に経済力と学力の方へ傾いて行った。JNUでは、本当に頭のいい学生は勉強そっちのけで政治活動に従事する傾向にある。しかも、頭のいい学生というのはやはりある程度いい家柄の人が多いようだ。そしてそういう学生たちの行き着く先はどうもAISAらしい。僕のクラスの学生を見ていても、それはかなり当てはまる。というわけで、AISAには裕福で頭のいい学生が多く参与しており、インテリを気取っている。一方、SFIの方は、比較的貧しい家の出の人が多いようで、学力の面から言ってもそれほど優秀ではない学生が多いように思える。だから、AISAもSFIも同じ共産党系のグループだが、その立場には微妙な違いがある。今回の首相訪問では奨学金が大きな論点となっていたようで、SFIの学生たちは奨学金欲しさに抗議を控えたという事情もあるようだった。あるSFIの学生はAISAの学生に対し、「1本6ルピーのタバコを吸って、酒をたらふく飲んでるくせに、言うことだけは『革命』かよ!」とか、「首相に抗議をした2、30人がインテリで、黙ってスピーチを聞いてた残りの3000人はただのバカってことかよ!」と怒りを露にしていた。
僕のクラスでは普段、アカデミックな話題のときはあまり議論が沸騰しないのに、一度政治が絡むと喧々諤々の議論が始まる。まるで学園紛争時代の日本を見ているかのようである。あの頃の日本もこんな感じで学生同士が熱く議論を戦わしていたのだろうか?現在の日本の大学ではこんな光景はほとんど見られないだろう。それにしても「インド人が熱くなるもの3つ:政治、映画、クリケット」とはよく言ったものである。というか、ジャングルで覆われた大いなる田舎であるJNUのキャンパスにはそれしか話題がないし、インドのほとんどの地域でも同じような状況なのだろう。
| ◆ |
11月18日(金) Taj Mahal : An Eternal Love Story |
◆ |
インドでは「ハリー・ポッター」シリーズの最新作「ハリー・ポッターと炎のゴブレット」が本日より公開されたが、そんなのには目もくれず、同じく本日より公開の新作ヒンディー語映画「Taj
Mahal : An Eternal Love Story」をPVRアヌパムで見た。「Taj Mahal」は文字通り、アーグラーにある世界的観光名所タージ・マハルにまつわる歴史映画である。
制作・監督はアクバル・カーン。アクバル・カーンは元々俳優だが、1983年に「Haadsa」という映画を制作・監督しており、本作が2作目となる。音楽はナウシャード。「Mother India」(1957年)や「Mughal-e-Azam」(1960年)などで有名な音楽監督である。キャストは、カビール・ベーディー、ズルフィー・サイイド、ソニア・ジャハーン、プージャー・バトラー、アルバーズ・アリー、アルバーズ・カーン、キム・シャルマー、ワクール・シェイクなど。ニガール・カーンが特別出演。
| Taj Mahal : An Eternal Love Story |
 1658年、ムガル朝第5代皇帝シャー・ジャハーン(カビール・ベーディー)の病を機に長男のダーラー・シコー(ワクール・シェイク)と三男アウラングゼーブ(アルバーズ・カーン)の間で王位継承権を巡ってサーモーガルの戦いが勃発、戦いはアウラングゼーブの勝利に終わった。ダーラー・シコーはアウラングゼーブによって処刑され、シャー・ジャハーンは長女のジャハーナーラー(マニーシャー・コイララ)と共にアーグラー城に幽閉されてしまった。【写真は、左からアルバーズ・アリー、キム・シャルマー、プージャー・バトラー、ソニア・ジャハーン、ズルフィー・サイイド】 1658年、ムガル朝第5代皇帝シャー・ジャハーン(カビール・ベーディー)の病を機に長男のダーラー・シコー(ワクール・シェイク)と三男アウラングゼーブ(アルバーズ・カーン)の間で王位継承権を巡ってサーモーガルの戦いが勃発、戦いはアウラングゼーブの勝利に終わった。ダーラー・シコーはアウラングゼーブによって処刑され、シャー・ジャハーンは長女のジャハーナーラー(マニーシャー・コイララ)と共にアーグラー城に幽閉されてしまった。【写真は、左からアルバーズ・アリー、キム・シャルマー、プージャー・バトラー、ソニア・ジャハーン、ズルフィー・サイイド】
幽閉と身なったシャー・ジャハーンはジャハーナーラーに、妻ムムターズ・マハルとのなりそめ話を語り始める――
ジャハーンギール帝(アルバーズ・アリー)の治世、宮廷で皇帝以上に権勢を誇ったのは王妃ヌール・ジャハーン(プージャー・バトラー)であった。ヌール・ジャハーンは、前夫との娘ラードリー(キム・シャルマー)を、ジャハーンギールの長男で後のシャー・ジャハーン、クッラーム王子(ズルフィー・サイイド)と結婚させて完全に実権を掌握しようと画策する。しかし、クッラーム王子は、ヌール・ジャハーンの弟、アースィフ・カーンの娘で後のムムターズ・マハル、アルジュマンド(ソニア・ジャハーン)に惚れていた。ヌール・ジャハーンはそれを阻止するため、アースィフ・カーンを一家共々デカンに左遷する。だが、クッラーム王子はアルジュマンドを追って宮廷を飛び出す。ヌール・ジャハーンはジャハーンギール帝に、クッラーム王子とアースィフ・カーンがクーデターを共謀していると吹き込む。クッラーム王子は捕えられ、宮廷で裁判にかけられる。クッラーム王子は、クーデターを謀っているのはヌール・ジャハーンであると主張し、父親の怒りを買う。ジャハーンギールはクッラーム王子を後継者と目しており、しかもイランの王朝との政略結婚も決めていたので、失望は大きかった。ジャハーンギールはクッラーム王子の禁固を命じ、死刑の可能性も否定しなかった。
しかし、ジャハーンギールは密かにアルジュマンドのもとを訪れる。ジャハーンギールはアルジュマンドに対し、クッラーム王子と密かに逃げるように言う。ところがアルジュマンドはクッラーム王子が皇帝になることを夢見ており、自分のために王子が王座を明け渡すのを潔しとしなかった。アルジュマンドはクッラーム王子に対し、皇帝の言うことを聞いて政略結婚を受け入れ、許しを乞うように説得する。クッラーム王子はそれを受け容れ、イランの王妃カンダーリー(ニガール・カーン)と結婚する。その2年後の1612年、クッラーム王子はアルジュマンドと結婚する。
1627年にジャハーンギールが死去するとクッラーム王子はムガル皇帝の座に就き、シャー・ジャハーンを名乗るようになる。また、アルジュマンドはムムターズ・マハルと呼ばれるようになる。シャー・ジャハーンはムムターズをこよなく愛し、ムムターズは毎年のように皇帝の子供を産んだ。しかし14人目の子供を出産した際の産褥熱により、1631年に死去する。悲しみに沈んだシャー・ジャハーンは、ムムターズの遺言を守り、世界で最も美しい愛の記念碑の建設を開始する。この記念碑は20年以上の歳月の後に完成し、タージ・マハルと呼ばれるようになる。これがシャー・ジャハーンとムムターズ・マハルの永遠の愛の物語であった。
ムムターズ・マハルの死から40年の歳月が経った。ずっと幽閉され続けていたシャー・ジャハーンは、ムムターズの40回忌にタージ・マハルを訪れる許可をアウラングゼーブに求める。アウラングゼーブもそれを許可する。しかし40回忌を前にシャー・ジャハーンは息を引き取る。夢の中でムムターズとの再会を果たしながら・・・。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
世界で最も美しい建築物のひとつに必ず挙げられるタージ・マハルと、その建築の理由となったシャー・ジャハーンとムムターズ・マハルのロマンスを題材にした映画ということで、期待せずにはいられない作品であった。しかし、俳優陣がパッとしないことや、公開が延び延びになっていたことなどから、駄作の臭いもプンプンしていた。だから、正直言って「期待半分、諦め半分」という気持ちで映画館に足を運んだ。映画の評価を一言で表すならば、「映画の完成度は低いが、シャー・ジャハーンとムムターズ・マハルの恋愛はいかに下手な映画でもそれなりに感動できる」といったところか。つまり、映画の力ではなく、シャー・ジャハーンとムムターズ・マハルの史実上の恋愛を映像でなぞることができ、それに感動できる作品である。
この映画の最大の欠点は、「Mughal-e-Azam」とあまりに筋が似すぎていることだ。「Mughal-e-Azam」は、ムガル朝第三代皇帝アクバルと、その息子サリーム王子(後のジャハーンギール)の間の確執や、サリーム王子と侍女アナールカリーの禁断の恋愛が描かれていた。一方、「Taj
Mahal」では、ムガル朝第四代皇帝ジャハーンギールとその息子クッラーム王子(後のシャー・ジャハーン)の確執や、クッラーム王子と家臣の娘アルジュマンドの禁断の恋愛が描かれていた。「Mughal-e-Azam」では、王妃になることを夢見るバハールがサリーム王子とアナールカリーの恋愛を邪魔するが、「Taj
Mahal」では王妃ヌール・ジャハーンの連れ子ラードリーがクッラーム王子とアルジュマンドの恋愛を邪魔する。これだけ読んでも分かるように、はっきり言って時代が一世代後に下り、登場人物が入れ替わっただけで、流れは全く一緒である。それだけでなく、「Mughal-e-Azam」では、「Teri
Mehfil Mein Kismat Azmakar」のミュージカル・シーンで、サリーム王子の前でアナールカリーとバハールが歌合戦を繰り広げるが、「Taj
Mahal」では、「Ishq Ki Daastaan」のミュージカル・シーンで、クッラーム王子の前でアルジュマンドとラードリーが同じく歌合戦を繰り広げる。こんなところまで似ているので、非常に気が滅入ってしまう。

歌合戦のシーン
歴史映画ではセットや衣装などの時代考証も重要な評価対象となる。「Taj Mahal」のセットはかなり豪華できらびやかであったが、重厚さがなく安っぽい印象が拭えなかった。「ケバケバしい」という言葉が一番当てはまるかもしれない。ちなみにロケの大部分はジョードプルのメヘラーンガル砦で行われたようだ。また、衣装もムガル朝時代の細密画でよく見るような服装が再現されていたが、やはり説得力に欠け、どちらかというと「スター・ウォーズ」シリーズに出て来る衣装を彷彿とさせてしまっていた。アミダラ姫とか。クッラーム王子を初めとして、多くの男性登場キャラが長髪だったので、ちょっと少女漫画っぽい印象も受けた。ただ、戦争シーンの迫力はなかなかのものであった。特に冒頭のサーモーガルの戦いのシーンは秀逸。
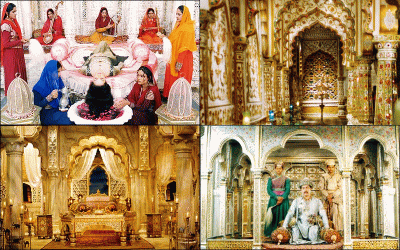
豪華なセットの数々
右下は有名な「孔雀の玉座」
しかしよく見ると安っぽい

衣装も豪華なのだが、何だか奇をてらいすぎな
印象を受けるのは僕だけだろうか?
セットや衣装がケバいのはいいとしても、権謀術数渦巻く宮廷内の人物描写に迫真性がないのが痛い。特にヌール・ジャハーンとラードリーのコンビがやっていることは全く子供じみていて馬鹿馬鹿しいの一言に尽きる。クッラーム王子とアルジュマンドの逢引きを必死になって邪魔するシーンなどは最も盛り下がる場面である。
ナウシャードの音楽も精彩を欠いた。本当に「Mughal-e-Azam」の音楽を作曲した人物だろうか、と思うほどつまらない曲だらけであった。歴史映画なのに中途半端にモダナイズされた音楽だったのが原因なのではないかと思う。ダンスも印象に残るものがなかった。
数ヶ所でCGが使われていたが、映画の質を低下させてしまうほど幼稚なレベルのものだった。いっそのことCGは一切使わなかった方がよかった。あの鹿、あの船、いったい何がしたかったのか訳が分からない。インド映画はまだまだCGの使い方が未熟だ。ハリウッドの足元にも及ばない。
だが、それらの欠点が考慮しても、ムムターズが死んでしまうシーンや、シャー・ジャハーンが生と死の狭間の朦朧とした意識の中、タージ・マハルの前で純白の服を着たムムターズと再会を果たして抱擁するシーンなどはグッと来てしまう。ムムターズの遺言に従い、20年以上の歳月と国が傾くほどの莫大な予算をかけて愛の記念碑を造らせたシャー・ジャハーンの愛情と悲しみの深さは、人々の心を無条件で動かす力がある。ただ、シャー・ジャハーンは幽閉中、ムムターズと瓜二つだった娘のジャハーナーラーと愛人関係にあったと言われている。
俳優陣はあまり有名でない人が多く、パッとしない。一番一般に知られているのはマニーシャー・コイララであろう。久々にスクリーンで見たが、美しさが際立っていてけっこういい感じだった。衣装の関係上、あまりお腹を見せずに済んだことも幸いしたと思われる。演技で最も光っていたのは、「お局様」ヌール・ジャハーンを演じていたプージャー・バトラーである。1993年のミス・インディアであり「Virasat」(1997年)の大ヒットで注目を浴びた女優だが、最近のボリウッドではあまり存在感がなかった。怒ったときの目の開き具合が怖すぎだったが、いい演技をしていた。アルジュマンドまたはムムターズ・マハルを演じたソニア・ジャハーンは、なんと伝説的女優ヌール・ジャハーンの孫娘である。ヌール・ジャハーンは英領時代のインドの映画界を代表する大女優である。歌も歌えて演技もできたのだが、印パ分離独立に伴ってパーキスターンに移民してしまった。彼女の移民により、インドの映画界では歌を歌える女優がいなくなってしまい、代わりにラター・マンゲーシュカルなどのプレイバック・シンガーの台頭へとつながっていったという背景がある。ところでソニア・ジャハーンはフランス生まれのフランス育ちだそうだ。だが、絶世の美女と言われるムムターズを演じるには、美貌の点でちょっと役不足だったように思えた。若き日のシャー・ジャハーンを演じたズルフィー・サイイドは、少女漫画に出て来る男の子みたいな甘いマスクをした若手男優であるが、演技力はしっかりしたものを持っていた。ラードリーを演じたキム・シャルマーは、どうも現代映画と歴史映画を取り違えているように感じた。表情の使い方が「現代のわがままっ子」という感じで気品に欠けていた。どうせなら、もっと有名な俳優でこの映画を撮ってもらいたかった。シャー・ジャハーンはアビシェーク・バッチャンとアミターブ・バッチャンが演じ、ムムターズ・マハルはもちろんアイシュワリヤー・ラーイ。ヌール・ジャハーンはマードゥリー・ディークシトとか。
冒頭では「ヒンディー語映画」として紹介してしまったが、この映画の言語は完全なるウルドゥー語である。「Mughal-e-Azam」は重厚な演劇調のウルドゥー語のセリフであり、時代を感じさせたが、「Taj
Mahal」もそれとあまり変わらない古風で演劇調な純ウルドゥー語だった。インド人観客から「何言ってるか訳が分からん」という声も上がっていたほどである。言語の面でもムガル朝の宮廷の雰囲気を出したい気持ちは分かるが、これほどまでコテコテのウルドゥー語にしてしまう必要があるのか、時々疑問に思う。これでは一般大衆は理解できないだろう。だが、セリフの中にはいくつか美しいものもあった。例えば、ヌール・ジャハーンがアルジュマンドとの禁断の恋愛に関してクッラーム王子に対し「印章の押された命令に背くことは許されない」と叱ると、クッラーム王子はヌール・ジャハーンとラードリーの前で堂々とアルジュマンドにキスをし、「愛の印章が一度押されてしまったら誰にも止めることはできない」と言い返すシーンがあった。そういえばマニーシャー・コイララが案外きれいなウルドゥー語をしゃべっていて驚いた。
映画中では、ムムターズ・マハルの40回忌の前日にシャー・ジャハーンが死去することになっているが、史実ではシャー・ジャハーンが死んだのは1666年であり、ムムターズの死から35年後である。
「Taj Mahal : An Eternal Love Story」は微妙な映画である。タージ・マハルが好きな人や、タージ・マハルにまつわる物語を知りたい人は見る価値があると思う。ウルドゥー語やムガル朝の雰囲気が好きな人にもオススメである。だが、ひとつの作品として見ると非常に弱い映画なのは否めない。ヒットも望めなさそうだ。
| ◆ |
11月19日(土) Ek Khiladi Ek Haseena |
◆ |
今日は、昨日から公開の新作ヒンディー語映画「Ek Khiladi Ek Haseena」をチャーナキャー・シネマで見た。チャーナキャーへ行ったのは久し振りであったが、チベット料理屋街が改築中だったので驚いた。これできれいになったら、名実共にデリーを代表する食のスポットとなるであろう。
「Ek Khiladi Ek Haseena」とは、「1人の詐欺師、1人の美人」という意味。監督はスパルン・ヴァルマー、音楽はプリータム。キャストは、ファルディーン・カーン、コーイナー・ミトラ、ケー・ケー、フィーローズ・カーン、グルシャン・グローヴァー、ローヒト・ロイ、アミーン・ハジーなど。
| Ek Khiladi Ek Haseena |
 アルジュン(ファルディーン・カーン)とローヒト(ローヒト・ロイ)はプロの詐欺師コンビだった。ある日、最後の仕事と決めて銀行に来ていた客を騙し、30万ルピーをせしめる。ところがその金はムンバイーを支配するマフィア、スィカンダル(グルシャン・グローヴァー)のものだった。アルジュンが留守にしている間にローヒトはスィカンダルの部下カイフ(ケー・ケー)に殺される。アルジュンは詐欺仲間のジャック(アミーン・ハジー)やバーティヤー(ムクル・デーヴ)たちとプネーへ逃げるが、スィカンダルの追っ手から逃げることはできなかった。スィカンダルはアルジュンに対し、10日以内に40万ルピーを返すように命令する。もちろん返却できなかったら死あるのみだ。ちなみに10万ルピーは利子とのことだった。また、スィカンダルはカイフをアルジュンの見張りにつける。【写真は左からフィーローズ・カーン、ファルディーン・カーン、コーイナー・ミトラ】 アルジュン(ファルディーン・カーン)とローヒト(ローヒト・ロイ)はプロの詐欺師コンビだった。ある日、最後の仕事と決めて銀行に来ていた客を騙し、30万ルピーをせしめる。ところがその金はムンバイーを支配するマフィア、スィカンダル(グルシャン・グローヴァー)のものだった。アルジュンが留守にしている間にローヒトはスィカンダルの部下カイフ(ケー・ケー)に殺される。アルジュンは詐欺仲間のジャック(アミーン・ハジー)やバーティヤー(ムクル・デーヴ)たちとプネーへ逃げるが、スィカンダルの追っ手から逃げることはできなかった。スィカンダルはアルジュンに対し、10日以内に40万ルピーを返すように命令する。もちろん返却できなかったら死あるのみだ。ちなみに10万ルピーは利子とのことだった。また、スィカンダルはカイフをアルジュンの見張りにつける。【写真は左からフィーローズ・カーン、ファルディーン・カーン、コーイナー・ミトラ】
アルジュンは、ジャック、バーティヤー、カイフと共に、心理学者のナターシャ(コーイナー・ミトラ)を罠にかけ、40万ルピーを手にする。しかし、騙されたことを知ったナターシャはスィカンダルのところへ行き、金を返すように言う。それが無理だと分かると、「アルジュンは25日間で2億5千万ルピーを用意できる男だ」と主張し始める。スィカンダルはその話に興味を持ち、アルジュンたちに対し、スタンダード銀行の総裁で、ムンバイーを表裏で20年間牛耳るドン、ジャハーンギール・カーン(フィーローズ・カーン)をターゲットにすることを命じる。アルジュンはスィカンダルから、その資金として250万ルピーを借りる。
アルジュンはまずスタンダード銀行の副総裁を懐柔し、偽の会社にローンのために2億5千万ルピーを振り込ませることに成功する。バーティヤーがバンコクでその金を現金化し、インドに持ち帰ることになっていた。ところが、アルジュンが中央情報局(CBI)のデーサーイーに追われていることが発覚したことをきっかけに仲間割れが発生する。まずアルジュンはナターシャを仲間から外す。怒ったナターシャはアルジュンの詐欺のことをジャハーンギールに暴露する。また、アルジュンはカイフに2億5千万ルピーを持ち逃げすることをもちかけるが、カイフはそれにのらなかった。カイフはスィカンダルに、空港に2億5千万ルピーが入ったバッグがやって来ることを知らせる。スィカンダルは自ら空港へバッグを取りに出掛ける。空港ではデーサーイーが待ち伏せしており、バーティヤーが持って帰ったバッグを税関ですりかえる。スィカンダルはバーティヤーからそのバッグを奪うが、その中には大量のコカインが入っていた。スィカンダルは警察に囲まれ逮捕となる。一方、アルジュンとカイフが乱闘しているときにナターシャがジャハーンギールの部下と共に現れ、彼女はカイフを射殺する。ナターシャはアルジュンに金はどこにあるか聞くが、アルジュンは「警察の手に渡ってしまった」と言って口を割らなかったため、アルジュンをも射殺する。
ジャハーンギールの部下が去り、ナターシャが去った後、アルジュンの遺体のそばに現れたのはデーサーイーであった。実はデーサーイーもアルジュンの一味であった。デーサーイーはアルジュンに「おい、そろそろ起きろ」と呼びかける。するとアルジュンはひょっこりと起き上がる。実はローヒトが殺されてからの全ての出来事はアルジュンが仕組んだことであった。ナターシャはローヒトの妹で、アルジュンの婚約者だった。アルジュンは、スィカンダルに復讐し、ジャハーンギールから大金をせしめ、それでいてジャハーンギールから追われない綿密な計画を立てたのだった。2億5千万ルピーを手に入れたアルジュンは仲間たちと外国へ高飛びしようとする。ところがその飛行機にはジャハーンギールが仕掛けた爆弾があった・・・。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
アルジュンが何者かに射殺されるシーンから始まり、回想シーンが本編となっており、最後に大どんでん返しが待っている、というハリウッド・テイストの映画だった。スパルン・ヴァルマー監督は「Janasheen」(2003年)や「Karam」(2005年)の脚本家で、今回が監督デビュー。最近新進気鋭の監督によるハリウッド・テイストのボリウッド映画が増えてきたが、これは間違いなく、ボリウッド映画よりもハリウッド映画を見て育って来た世代が次々に監督デビューしているからだと思う。だが問題は、こういう映画は都市部の観客にしか受けないことが多いことだ。田舎の観客はこういう複雑な筋の映画を理解することができないだろう。僕が個人的に問題にしたいのは、ハリウッド・テイストの映画には、インド映画の核とも言える「良心」が入りにくいことだ。「インド映画の良心」とは簡単に言ってしまえば勧善懲悪性である。「勧善懲悪」という言葉は、現代では否定的な視点と共に使われることが多いが、僕はインド映画の勧善懲悪性を悪いものとは思っていない。むしろ、それこそがインド映画の核だと思っている。映画の中でくらい、正義が勝ち、悪い者が罰せられなければ世の中やって行けないだろう。「Ek
Khiladi Ek Haseena」には正義と悪がなく、感情移入もしにくい。だから、ボリウッドの衣をまとったハリウッド映画だと言える。ただ、僕が見たときは、映画館はなぜかやたら盛り上がっていて、コーイナー・ミトラの際どいシーンがスクリーンに映し出されるたびに歓声が上がっていた。こっちの方面で大衆に受ける可能性はある。
この映画で一番の見せ所は何と言っても最後の大どんでん返しにある。ナターシャに殺されたと思われたアルジュンが実は生きていて、ナターシャも元々の仲間で、2億5千万ルピーもちゃっかり手に入れる。だが、その前にも何度かどんでん返しが繰り返されるので、だんだん次の展開が読めてくる。しかも、今までの流れを全てアルジュンが計画したと考えるのはあまりに非現実的だ。手法はハリウッドだが、まだまだボリウッド的強引さは拭えていない。さらに綿密な脚本が必要だ。ただ、宝くじを使っておばさんを騙すシーンは秀逸だった。
全体的に退廃的なオシャレさが漂う映画だった。映画の始まり方などはなかなかかっこ良かった。冒頭のナレーション、「エーク・ター・キラーリー、トーラー・アナーリー、エーク・ティー・ハスィーナー、ウスキ・ディーワーニー、イェ・ハェ・ウンキ・カハーニー(1人のちょっと頭のおかしい詐欺師がいた、その男に惚れた1人の美人がいた、これはその2人の話)」も詩的にいい感じだった。
フィーローズ・カーンとファルディーン・カーンは、「Janasheen」以来の親子共演。2人がエレベーターで会話を交わすシーンは、ファンにはニンマリのシーンである。ファルディーン・カーンはここのところ脇役出演が多かったが、この映画でやっと主役らしい主役に返り咲いたような気がする。落ち着いた演技をしていてよかった。フィーローズ・カーンも持ち前の強面を活かした適役でよかった。ジャハーンギールのセリフ、「カファン・メン・ジェーブ・ナヒーン・ハェ(死に装束にポケットはない=あの世に金を持っていくことはできない)」という言葉が面白かった。カイフを演じたケー・ケーは相変わらず絶妙の演技。間違いなく現在ボリウッドで最も演技のうまい男優だ。
ヒロインはコーイナー・ミトラ。「Musafir」(2004年)のアイテム・ナンバー、「Saaki」でベリー・ダンスを踊っていたアイテム・ガールだったが、いつの間にか女優デビューしていた。アイテム・ガールから女優に出世するパターンは最近ちらほら見かけられる。イーシャー・コーッピカルなど。だが、あくまでコーイナー・ミトラはアイテム・ガール止まりの器であるように思える。取り立てて美人でもないし、演技も下手過ぎた。だが、キスOK、露出OKの女優のようで、それを活かせば将来はないことはないかもしれない。この映画ではファルディーン・カーンと、「Murder」(2004年)のマッリカー・シェーラーワト並みに濃厚な濡れ場を演じていた。
「Ek Khiladi Ek Haseena」は音楽とミュージカル・シーンがいい映画だ。ファルディーン・カーンとコーイナー・ミトラがボクシングで戦うという斬新なミュージカル・シーン「Ishq
Hai Jhootha」と、「マッドマックス」のような雰囲気のミュージカル・シーン(最後のスタッフ・ロールで流れる)「Nasha」が特によかった。「Ek
Khiladi Ek Haseena」のサントラCDは買う価値がある。
結論として、「Ek Khiladi Ek Haseena」は、正統派ボリウッド映画を見たい人向けの映画ではない。ただ、ミュージカル・シーンを楽しむ目的だったらけっこういいだろう。
インドに留学して以来ずっとインド映画を見続け、映画を見たら必ず映画評を書いてこのウェブサイトに載せるようにしているが、こんなことでも長い間続けていればだんだん人々の間で認知されるようになっていくものらしい。今日は、デリー日本人会婦人部ボランティアグループの依頼に応え、インド映画について講演を行った。ボランティアグループは時々デリーの日本人留学生による講演を催しており、今回で5回目となるようだ。実は2004年4月1日にも僕はインド映画の講演を行っており、今回が2回目となる。前回は「インド映画のすすめ」と題して、インドの伝統的芸術理論を通してインド映画を読み解く試みをしてみた。今回は、インド映画の歌と踊りに焦点を当てて講演をすることにした。題して「マハラジャはなぜ踊るのか?」。1998年に日本で公開されてインド映画ブームを巻き起こした伝説のタミル語映画「ムトゥ 踊るマハラジャ」(1995年)の副題にあやかった題名である。
とかくインド映画というと、「突然歌が流れて俳優が踊り出す」というイメージで語られることが多い。別に間違いではないのでそれ自体は問題ないのだが、多くの場合そのイメージには否定的な視点が付きまとい、インド映画を馬鹿にする常套文句にもなっている。あるときなどは、インド映画を最初から最後まで見たことのないような人から、「あんな歌って踊っての映画の批評、どうやってするのか?」と言われたこともある。「ムトゥ」の大ヒットにより、一般の日本人にもインド映画の存在が知れ渡ったのはいいが、副題の影響からか、残念ながらそのイメージはかなり偏見に満ちたものになってしまった。「マハラジャが踊るのは分かったが、ではなぜマハラジャは踊るのか?」つまり、「インド映画にはなぜ突然歌と踊りが入るのか?」インド映画についてほとんどの日本人が抱くであろう疑問はこれであろう。そこで、その疑問について、インド映画を弁護する立場から、時には言い訳っぽい屁理屈もこねくりまわしながら、インド映画の歌と踊りについて講義を行うと決めた。目的はただひとつ、インド映画の歌と踊りは、インド映画の後進性や欠点ではなく、むしろインド映画の最大の長所であり、最大の武器であり、そして堂々と守っていくべきものだ、ということを主張することである。
題材には2001年の大ヒット映画「Lagaan : Once Upon A Time In India」を選んだ。「Lagaan」はインド国内で興行的に大ヒットを記録した他、2002年の米国アカデミー賞外国語映画賞にノミネートされるほど高い評価を得た。映画として楽しめることはもちろん、歌と踊りがストーリーと絶妙にマッチしており、今回の講義向けだと判断した。また、日本でソニー・ピクチャーズ社から日本語字幕付きのDVDが「ラガーン」という邦題で発売されており、日本人向けの講義中に上映する際に非常に便利だという理由もあった。さらに、僕がインド留学して初めて見た映画がこの「Lagaan」で、個人的に非常に思い入れの強い映画であることも密かな要因だ。「Lagaan」と同時公開された「Gadar」も大ヒットを記録し、当時は「『Lagaan』がいいか、『Gadar』がいいか」ということがよく話題になったが、僕は完全に「Lagaan」派である。「インド映画で一番オススメの作品は?」と聞かれても、僕は「Lagaan」と即答する。以下、簡単なあらすじを掲載。だが、「Lagaan」を見ていない人には、今回の話は半分くらいしか分からないだろうし、ネタバレにもなってしまう。インド映画最高傑作と言っても過言ではないので、機会があれば是非見ていただきたい。
時は1893年、英領インド時代。北インドの農村チャンパーネール村では、昨年に引き続いて雨季になっても雨が降らず、今年も年貢を納めることができそうになかった。チャンパーネール村の徴税を担当する英国人将校ラッセル大尉は村人たちに「クリケットの試合に勝ったら今後3年間は年貢を免除してやるが、負けたら3倍の年貢を課す」という意地悪な難題を突きつける。当然、村人たちはクリケットが何なのかも知らなかった。だが、血気盛んな若者ブヴァンはそれを受け入れ、村人たちを組織してクリケットの練習をする。ラッセル大尉の妹エリザベスは密かにブヴァンに恋をしており、ブヴァンを裏から支える。だが、ブヴァンのことを好きだった村の娘ガウリーはエリザベスに嫉妬を燃やす。こうして英国人将校vs村人という前代未聞のクリケットの試合が開催され、接戦の末に見事村人たちは英国人たちを打ち負かし、年貢の免除を勝ち取るのだった。と、勝利の瞬間、空からそれを祝福するかのように雨が降り注ぐ。ラッセル大尉は責任を取らされ、アフリカへ左遷となり、エリザベスもインドを去ることになった。しかし、エリザベスはブヴァンへの恋を忘れず、一生独身を通すのだった。
まずはインド映画の歌と踊りの歴史について簡単に解説した。このトピックに関しては、杉本良男著「インド映画への招待状」(青弓社)を大いに参考にした。一般に、映画は1895年にフランスのリュミエール兄弟が発明したとされている。インドで初めて映画が公開されたのは1896年、ボンベイにて。その後、実験的な映画の公開が散見されるが、インドで映画が興行的に公開されるようになったのは1900年のマドラスにおいてだったとされている。また、映画制作もインドでは映画発明から間もない頃から行われていた。当初はヨーロッパ人が映画制作の中心であったが、すぐにインド人監督も現れて短篇記録映画を制作するようになった。1898年にカルカッタで英国人スティーヴンソン教授が撮影した「The
Flower of Persia」は、同名人気芝居の踊りの部分を映画化したもので、早くも踊りが映画の主題になっていた。1901年にボンベイで長編映画「キリストの生涯」が公開されて大人気を博すと、インド人の間で、インドの宗教や神話を題材にしたインド人の手による純国産映画制作への情熱が沸き起こった。この動きはもちろん、当時の独立運動の高まりとも密接に関連している。そんな中、「インド映画の父」と呼ばれるダーダーサーヒブ・ファルケーが、1913年に初の純国産映画「Raja
Harishchandra」を発表する。これは、インドニ大叙事詩のひとつ「マハーバーラタ」の挿話を題材にした50分ほどの映画だった。ファルケーはその後も神話を題材に映画を撮り続ける。この頃の映画はもちろん無声映画であるが、クリシュナの大蛇退治を題材にした「Kaliya
Mardan」(1919)などは、無声ながらも音楽性や舞踊性に溢れる映画だったと言われている(昔、松岡環先生の講演会で上映されたので、少し見たことがある)。
だが、歌と踊りに満ちたインド映画誕生の直接のきっかけとなったのは、トーキー映画の出現であった。トーキー映画は、倒産の危機を迎えた米国ワーナー・ブラザーズが起死回生を懸けて開発した新技術だった。1926年に同社は部分的にトーキーの「ドン・ファン」を公開し、翌年の1927年には全編トーキーの「ジャズ・シンガー」を公開する。同社の挑戦は大成功し、トーキー映画は瞬く間に世界の映画界を席捲した。インドでは早くも1927年にトーキー映画が公開され、1931年にはインド初の国産トーキー映画「Aram
Ara」が公開された。急速なスピードで映画のトーキー化は進み、1935年には全ての映画がトーキー映画となった。トーキー映画の到来により、インド映画には2つの大きな変化が訪れた。ひとつは言語別映画が登場したこと、もうひとつは歌と踊りが挿入されるようになったことだ。サイレント映画時代には、文字の部分を差し替えたり、弁士が通訳したりすることにより、映画は簡単に言語の壁を越えることができたが、トーキー映画の出現によって映画は言語別に作られるようになって行った。一方、歌と踊りと劇が一体となった伝統的演劇形態が発達していたインドでは、映像と音の同調が可能になったことにより、演劇と似たメディアである映画に歌と踊りが入るのは半ば当然のことであった。
また、インド映画の形態にもうひとつ重要な影響を与えたものがあった。それはパールスィー劇団と呼ばれる大衆演劇であった。パールスィー劇団は19世紀半ばからボンベイを中心に人気を博していた劇団で、シェークスピア劇やインドの神話や伝承などをもとにした演劇を演じていた。その演劇の特徴は観客を呼び込み、喜ばせるためなら何でもやる、何でもありのハイブリッド性で、豪華なセット、派手な衣装、大袈裟なセリフ、歌と踊りとアクションが入ったストーリー展開、観客を驚かせる仕掛けなどが売りだった。つまり、現在のインド映画の源流がパールスィー劇団にあった。映画がトーキー化されたことにより、パールスィー劇団の演劇スタイルが映画でも踏襲されるようになり、その過程で歌と踊りも当然のことながら映画に盛り込まれるようになった。パールスィー劇団の十八番だった「Indrasabha」は1932年に映画化されたが、この映画には59曲もの歌が挿入されていたと言われている。1940年代、第二次世界大戦が始まると、インド映画は歌と踊りを主体にした軽い映画が多くなり、ストーリーは二の次にされるようになる。
トーキーの次にインド映画の歌と踊りに影響を与えたのは、プレイバック・シンガーの登場であった。プレイバック・シンガーが現れる前は、インド映画の俳優たちは自分で歌って踊って演技をしていた。インド映画で初めてプレイバック・シンガーが使われたのは1936年の「Achhut
Kanya」だが、これは女優の喉の調子がたまたま悪かったために姉が代わりに歌ったというもので、偶然の産物だった。本格的にプレイバック・シンガーが台頭したのは、独立前の歌って踊れる大スターたちが映画界から相次いでいなくなったことが直接的な原因だった。例えば、当時を代表する大男優であったクンダン・ラール・セヘガルは「Devdas」(1935年)のヒンディー語版で主演して人気を博し、その後も数々の名作に出演したり名曲を生み出したが、1947年1月に早世した。同じく当時を代表する大女優ヌール・ジャハーンは1942年に13歳で「Khandan」でデビューして以来大スターとなり、数々の名演と名曲を生み出したが、1947年の印パ分離独立によりパーキスターンに移民してしまった。ちなみに、ヌール・ジャハーンは2000年に死去したが、その孫娘が「Taj
Mahal」(2005年)に出演している。このように歌って踊れる大スターを一度に失ったインド映画界は、役者と歌手を分業し、歌にはプレイバック・シンガーを使う手法を取るようになる。ヌール・ジャハーンの移民と共に頭角を現したのが、ラター・マンゲーシュカルであった。ラター・マンゲーシュカルは元々女優としてデビューしたが、1947年にマラーティー語映画「Aap
Ki Seva Mein」でプレイバック・シンガーとしてデビューして以来歌手の道を進み、今日まで14言語3万曲以上の歌を歌い続けている。ラター・マンゲーシュカルの甘ったるいソプラノ声はインド人女性歌手の定番となり、おかげでインド映画音楽の女性プレイバック・シンガーはみんな似たような声の人ばかりになってしまったほどだ。妹のアーシャー・ボースレーもプレイバック・シンガーであり、やはり姉に匹敵するほど膨大な曲を今日まで歌い続けている。プレイバック・シンガーの台頭により、役者は踊りと演技の才能のみを求められるようになり、こうして歌って踊れるスターの時代から踊れるスターへの時代へと変遷して行った。1950年代〜60年代になると、インド映画の定式は「1人のスター、6曲の歌、3つの踊り」と言われるまでになる。もっとも、スターが歌を歌うことが全くないわけでもない。例えばサンジャイ・ダットやアミターブ・バッチャンは時々歌声を披露しているし、カリーナー・カプールも「Dev」(2004年)で歌を歌っていた。だが、それもファン・サービス程度のもので、現在ではインド映画音楽はほぼ100%、プレイバック・シンガーによって歌われていると言っても過言ではない。だから、映像では違う役者が歌を歌っているのに、声は一緒、ということがある。慣れない内は変な感じだが、慣れると別に気にならなくなる。
こうしてトーキー映画の出現以来、歌と踊りが定着して行ったインド映画であるが、次第にそれは束縛とも言えるくらい必要不可欠な存在となり、歌と踊りがなければ映画を作れないようになって来る。インド映画の音楽は、映画公開前にTVやラジオで流されたり、レコード、カセット、CDなどが発売されたりするのが普通である。実はこれが映画にとって最大の宣伝になる。特に今ほどケーブルTVなどが発達していなかった時代では、映画公開前に市場などでガンガン流れ、人々が口ずさむまでに普及する映画音楽が何よりの宣伝であった。そして、音楽がヒットすれば、映画はどんなにつまらなくてもヒットするという公式が出来上がった。ケーブルTVが普及した今では、歌に加えて、公開前に集中的に放映される映画のミュージカル・シーンが最大の広告となっている。だから、音楽監督やコレオグラファーの名前は、映画監督の名前以上に映画の前評判を決定する重要なファクターになる。このような状況なので、映画のスポンサーが歌と踊りのない映画への出資を渋るようになるのはしごく当然のことだ。インドを代表する映画監督であるマニ・ラトナム監督も、日本でも公開された「ディル・セ」(1998年)制作時に、スポンサーの圧力に負けて不本意ながらミュージカル・シーンを入れることになったと言われている。ただ、最近ではラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督の「Sarkar」(2005年)や、サンジャイ・リーラー・バンサーリー監督の「Black」(2005年)のように、メインストリームの娯楽映画でありながら歌と踊りが一切なしで、しかも興行的成功も収める作品も現れており、インド映画の歌と踊りの必要性にも変化の兆しが見え始めている。また、メインストリームの娯楽映画が歌と踊りの挿入など、娯楽性を追求していった一方で、「大地のうた」(1955年)のサティヤジト・ラーイ(サタジット・レイ)監督に代表されるような、歌と踊りのない芸術映画の潮流もインドには深く根付いている。それらのインドの芸術映画にも音楽性は必ずあると思うのだが、娯楽映画の歌と踊りをテーマにした今回の講義ではあまり触れる必要がないと判断し割愛した。また、歌と踊りのスタイルの変遷についても、僕には昔のインド映画の知識が足りないために、言及することが叶わなかった。
このように、トーキー映画の出現から今日に至るまで、歌と踊りはインド映画にとって必要不可欠なものとなって行った。それは伝統への回帰とも言えるし、経済的かつ現実的な理由によるものとも言える。だが、その直接の動機はどうあれ、確実なのはインド映画が歌と踊りを映画のひとつの表現手段として自分のものにし、発展させて行ったことだ。インド映画に歌と踊りが入るのは、ひとつの感情表現手段だと説明されることが多い。それは確かだろう。登場人物の感情が動くときには必ずと言っていいほど音楽が流れ始め、踊りが始まる。だが、それはインド映画をあまり知らない人でも容易に想像ができることだ。僕は、それ以上にインド映画の歌と踊りがストーリー展開上深い意味を持つことがあるということを、「Lagaan」のミュージカル・シーンを使って伝えようと思った。だが、残念ながらその深いレベルの理解まで達するには、言語の理解とインド文化の理解を要する。幸い、日本で発売されている「ラガーン」には日本語字幕が付いているため、言語の問題は一応解決することができた。後はインド文化の解説が必要となった。また、時間が限られているので、「Lagaan」の中でも最も重要だと思われるミュージカル・シーン2つ――「Ghanan
Ghanan」と「Radha Kaise Na Jale」――を特にピックアップすることにした。これら2曲の歌詞は、身毒企画の映画音楽歌詞集に掲載しておいた。
今回の講演で上映した「ラガーン」のチャプターは、ミュージカル「Ghanan Ghanan」が始まるチャプター9「黒い雨雲」から、年貢の免除を巡って英国将校と農民たちのクリケットの試合が開催されることが決まるチャプター12「条件」までと、ジャナマーシュトミー(クリシュナ生誕祭)からミュージカル「Radha
Kaise Na Jale」へと続く、チャプター22「クリシュナとラーダー」とチャプター23「クリシュナ生誕祭」、それにクリケットの試合に勝ったチャプター51「勝ったぞ!」と、最後のチャプター53「閉鎖」である。合計40分ほどだったと思う。
「Ghanan Ghanan」では、雨を心待ちにする農民たちの姿がミュージカルを通してよく描写されている。特にこのミュージカルは、ロングショットを多用したカメラワークと複雑に交差する立体的なグループダンスの調和が見所だ。雨雲がやって来たことに対する農民たちの喜びをダンスで表現すると同時に、雷鳴を轟かせながら雲がぐんぐん広がっていく様子や、雨後に大地にもたらされる自然の変化の様子も歌と踊りで表現している。その後、ラッセル大尉から無理難題を突きつけられるまでの一連の流れは、「年貢の免除を巡ってクリケットをする」という一見馬鹿馬鹿しい筋を、説得力のある脚本と映像で描写していて見事である。

「Ghanan Ghanan」の1シーン
大地に花々が咲き乱れる
そして僕が一番注目したかったのは、クリケットの練習期間中に訪れたジャナマーシュトミー(クリシュナ生誕祭)のときに、祭りの一場面として挿入される「Radha
Kaise Na Jale」のミュージカル・シーンだった。このミュージカルの歌詞と踊りは、クリシュナとラーダーの恋愛をベースにしている一方で、主人公ブヴァン、ヒロインのガウリー、そして白人マダムのエリザベスの三角関係を暗に表現している。クリシュナとラーダーはインドで最もよく目にする男女のカップルのイメージだが、この2人は実は夫婦ではない。クリシュナもラーダーも別の人と結婚している。だが、2人はお互いに愛し合っており、「蓮の葉に浮かぶ夜露」のように、ひとつにも離れ離れにもならない微妙な関係を保っている(つまり不倫ということか)。結婚と恋愛が別であるインドの伝統社会では、インド人は結婚という形で成就できなかった恋愛を、クリシュナとラーダーの姿に投影しているのではないかと僕は考えている。もっとも、「Radha
Kaise Na Jale」の歌の中では、クリシュナとラーダーはそのようなドロドロとした関係ではなく、純粋に恋人として描かれており、ゴーピー(牧女)たちに囲まれてモテモテのクリシュナに嫉妬するラーダーのいじらしい心が歌と踊りで表現されている。この嫉妬心は、エリザベスとベタベタするブヴァンに対するガウリーの嫉妬と見事にシンクロしている。また、このジャナマーシュトミーのシーンでエリザベスはブヴァンから、クリシュナとラーダーの話を聞き、感銘を受ける。

「Radha Kaise Na Jale」の1シーン
クリシュナとラーダーの恋物語に登場人物の三角関係が重ねられている
そして最後のシーン。クリケットに勝利したブヴァンたちは、グラウンドの中央で踊り狂って喜ぶ。ブヴァンは、そこに駆けつけたガウリーと抱き合うが、それを見たエリザベスは、ブヴァンとガウリーが相思相愛であることを悟る。また、このとき突然空から雨が降り出す。もちろん「Ghanan
Ghanan」の音楽と共に。「Ghanan Ghanan」の歌詞をよく読むと、「雨よ、とにかく降ってくれ」というような他力本願的表現が目立つが、クリケットに勝利した末の降雨は、宗教の差、カーストの差を乗り越え、一丸となって英国人将校に立ち向かい、勝利を勝ち取った農民たちへの天からの祝福だと取れる。試合に勝った途端、雨が降り出すのはいかにもインド映画的な予定調和性にも思えるが、冒頭の「Ghanan
Ghanan」との対比から、「天は自ら助ける者を助く」という前向きなメッセージを感じさせるため、僕は高く評価したいと思っている。また、雨の中、びしょ濡れになって喜ぶインド人たちと、雨が降って来た途端、屋内に逃げ込む英国人たちの対比は、インドに生まれインドに生きるインド人たちと、植民地支配にやって来ただけの外国人たちの、インドの自然に対する態度の差をよく表している。インドでは、雨季の雨こそが農業の礎であり、生活の基盤であり、幸せの象徴なのだ。搾取のみをする英国人には、その雨の嬉しさが理解できていない。日本の昔話にもよく、雨を心待ちにする農民たちの姿が描写されており、インド人の雨に対する考え方は決して日本人にも異質なものではないと思うが、しかし現代の日本人に農民の心が残っているとは思えない。だが、1度でもいいからデリーで4月から6月までの酷暑期をずっと耐え忍んで過ごすと、雨季の最初の一滴がどんなに嬉しいか少しは理解できる。「Lagaan」で描かれている雨の中で踊り出すインド人の姿は、決してフィクションではない。冒頭のミュージカル「Ghanan
Ghanan」があるからこそ、音楽と共に農民たちの雨に対する切望感が記憶のどこかにインプットされ、それがこの最後の降雨シーンで劇的に生きてくるのだ。
さて、クリケットでの敗退後、英国政府は屈辱に耐えかねず、チャンパーネール藩王国からの撤退を決定し、ラッセル大尉も中央アフリカへ左遷となる。エリザベスもそれに伴ってチャンパーネールを去ることになるが、その際、アミターブ・バッチャンの声のナレーションは、エリザベスのその後について、こんなことを言う。「エリザベスはブヴァンの像を心に秘めながら英国に帰り、一生独身を通してブヴァンのラーダーになった。」この部分は残念ながらDVDの日本語字幕ではうまく訳されていない。上記のは僕の独自の訳である。インドで、クリシュナとラーダーの話を聞き、結婚とは別の次元にある恋愛の形を知ったエリザベスは、クリシュナへの愛を貫いたラーダーのように、ブヴァンへの愛を貫いたのだった。「Lagaan」は確かにクリケットを主題にした映画であり、また英領インド時代の英国人たちの搾取と農民たちの窮状を描いた映画であり、そして愛国主義的な感情を沸き起こさせる映画であるが、それら表のテーマの合間には、クリシュナとラーダーの恋愛に重ね合わせたブヴァン、ガウリー、エリザベスの恋愛が巧みに紡ぎ込まれている。そして映画の最後の「ブヴァンのラーダーになった」というナレーションは、映画中盤のミュージカル・シーン「Radha
Kaise Na Jale」がなければ決して生きてこない。「Radha Kaise Na Jale」があればこそ、クリシュナとラーダーの神話が観客の心のどこかに残り、この最後のナレーションでインド人観客は一気にエリザベスと一心同体化し、涙するのである。「Radha
Kaise Na Jale」は、決して余興やサービスや時間潰しのために挿入されたミュージカル・シーンではなく、映画の最も重要な部分であり、映画の文学的価値をさらに高める役割を担っている。だが、「ブヴァンのラーダーになった」というセリフで心に感興を催すためには、先にも述べたように、ヒンディー語の理解とインド文化の理解の両方が必要不可欠である。「インド映画は言葉が分からなくても何となく分かる」と言われ、特にミュージカル・シーンは言葉が分からない人が一番楽しめるシーンだとされているが、実はインド映画のミュージカル・シーンの醍醐味を本当に味わうためには、言語と文化、両方の理解を要するのであり、それはインド映画の最も難しい部分なのである。歌は詩であり、詩は文学であり、文学は文化であるから、それは当然のことだ。インドの言語や文化を知らない外国人が、インド映画の歌や踊りについてさも全て分かったかのように批判的に語るのは、インド映画にとっても映画という芸術自体にとっても非常に失礼な行為であると思う。もっとも、インドの教養層もインド映画を馬鹿にする傾向にあるが、それでも彼らは「Lagaan」のような優れたインド映画なら映画館に足を運ぶだけの好奇心は持っている。日本人のインド娯楽映画に対する偏見に満ちた態度は、もしかしたらインド人のアニメ映画に対する態度と似ているかもしれない。もしインド人が、宮崎駿監督や大友克洋監督などの作品を全く知らないのに、「アニメなんて子供の見るものだ」と一笑に付したらどう思うだろうか?インド映画は、馬鹿にされているほど馬鹿にされるような低俗な事物ではなく、真剣に受け止める価値のあるひとつの「世界」だと思う。
「マハラジャはなぜ踊るのか?」その答えを比喩的に表現するならば、マハラジャはマハラジャであるがゆえに自分自身のために踊るのだ。マハラジャが踊り出すのはどんなときだろう?マハラジャは決して庶民や大臣たちのためには踊り出さない。人を踊らせはするが、マハラジャ自身が人のために踊ることはない。マハラジャが踊り出すときは、あくまで自分のためである。別に人を笑わせるために踊るのでもなく、自身を卑下するために踊るのでもない。インド映画が歌って踊りだすのも、観客へのサービスというよりも、あくまでインド映画のためだ。インド映画の歌と踊りは、必ずしも突然意味もなく挿入されるのではない。また、必ずしも登場人物の感情表現を手っ取り早く片付けるために挿入されるわけでもない。優れたインド映画では、歌と踊りは映画の重要な一部を担っており、また歌詞と身体表現とストーリーが絶妙なハーモニーを奏でており、映画に文学的感興を盛り込んだり、伏線を張ったり、メッセージを観客に伝達したり、リフレインによって映画全体に統一感をもたらしたりと、ありとあらゆる効果を醸し出している。確かに、インド映画には突拍子もなく質の低い歌と踊りが挿入される駄作が多いことも認めなければならないだろう。だが、それだけを見てインド映画の歌と踊り全体を否定的に見るのは間違っている。インド映画の歌と踊りはインド映画の最大の特徴であると同時に長所であり、ミュージカル映画の魅力を忘れかけている世界の映画界に向けて堂々と主張し、保持していくべき誇り高き伝家の宝刀だと僕は考えている。
以上、講義で語ったことに加えて、文章を書いている間にさらに浮かんで来た思考を織り交ぜ、また不必要だと思った部分を省略して書き連ねてみた。インド映画の楽しさは本当は理屈ではないので、性に合わない人にいくら言葉で説明しても無駄なような気もするのだが、それでも何とか理論的に説明しようと頑張ってみた。だが、まだインド映画に歌と踊りが入ることに関する説得力のある理由を言い切れていないような気がする。まだまだインド人とインド映画の歌と踊りの関係については、探求と洗練の必要がありそうだ。
今年8月12日に公開されたアーミル・カーン主演の期待作「Mangal Pandey : The Rising」。期待があまりに大きかったためか、作品の評価は思ったほど高くなく、興行的にも大成功とまではいかなかった。だが、2005年のボリウッドを象徴する映画のひとつであることには変わりないだろう。その「Mangal
Pandey」のロケ地のひとつがデリーの近くにある。ハリヤーナー州パタウディーにあるパタウディー・パレスである。「Mangal Pandey」のDVDのメイキング映像によると、同映画のロケはこの宮殿から開始されたようだ。パタウディー・パレスは、「Mangal
Pandey」だけでなく、ボリウッドと非常に密接な関係を持ったスポットである。また、この宮殿はクリケットのある伝説とも関連している。
パタウディーは、ハリヤーナー州南部、デリーから約60kmの地点にある町で、その歴史は13世紀のキルジー朝の時代まで遡る。パターと呼ばれるラージプートの一派が支配していたため、パタウディーと呼ばれるようになったようだ。パタウディーはアウラングゼーブの治世(17世紀〜18世紀初)にレーワーリー地区のパルガナー(行政区画のひとつ)となり、1803年にファイズ・タラブ・カーンの荘園となった。以後、パタウディー王家が始まる。パタウディー・パレスは、1935年に第8代ナワーブ、イフティカール・アリー・カーンによって建設された。デザインを担当したのは、デリーにあるイスラーム系大学ジャーミヤー・ミッリヤー・イスラーミヤーの建物をデザインしたオーストリア人建築家のカール・マルテ・フォン・ハインツである。パタウディー・パレスは、現在ではニームラーナー・ホテル・グループによってヘリテージ・ホテルとして一般に開放されている。
パタウディー王家は、クリケット界とボリウッド界を代表する人材を多数輩出している。第9代ナワーブ、マンスール・アリー・カーンは、「タイガー」の愛称で親しまれたインドのクリケット史を代表するクリケット選手だった。タイガーは1961年にデビューし、翌年には21歳の若さでインドチームのキャプテンに就任した。その頃のインドチームは超弱小で、連敗の泥沼から脱せられないでいた。だが、タイガーは不屈の闘志をもってインドチームを率い、1967年にはインド初の海外遠征勝利を収める。タイガーは実はバッツマン(打者)としては平均的な成績しか収めておらず、クリケットがインド人の国民的スポーツになる前の1975年に引退してしまうが、インドのクリケットの人気と実力の基礎を築き上げた名キャプテンとしてその名は永遠に記憶されることだろう。現在ではインドのスポーツというとクリケットだが、その人気の歴史は案外浅い。インドでホッケーに代わってクリケットが国民的人気を博すのは、インドがワールドカップで優勝した1983年前後からである。ちなみに、タイガーは幼少時の事故により右目の視力を失っている。マンスール・アリー・カーンはまだ存命中であるが、今年中頃、ブラックバックという鹿のような保護動物を密猟した罪で裁判沙汰となったようだ。もしかしてこの事件とパタウディー・パレスのホテル化は何か関係あるかもしれない。

マンスール・アリー・カーン aka タイガー
また、マンスール・アリー・カーンの父親の第8代ナワーブ、イフティカール・アリー・カーンも有名なクリケット選手で、オックスフォード大学留学時代からクリケットで活躍した他、大英帝国チームのレギュラー選手となった3人目のインド人である。1946年にはクリケットのインド代表のキャプテンも務めている。しかもイフティカール・アリー・カーンは、1928年のアムステルダム五輪に、インドのホッケーチームの選手として参加して金メダル獲得に貢献した。スポーツ好きのこのナワーブは1952年、息子の誕生日にポロをしているときに死亡した。まさにスポーツに生き、スポーツに死んだナワーブと言える。

イフティカール・アリー・カーン
第9代ナワーブ、マンスール・アリー・カーンは、ラヴィーンドラナート・タゴールの曾孫娘でボリウッドを代表する大女優シャルミラー・タゴールと1969年に結婚した。シャルミラーは結婚を機にイスラーム教に改宗し、アーイシャー・スルターンと改名したらしい(知らなかった!)。マンスール・アリー・カーンとシャルミラー・タゴールの間には3人の子供が生まれた。長男はサイフ・アリー・カーン、長女はサバー・アリー・カーン、次女はソーハー・アリー・カーンである。サイフは言わずと知れたボリウッドの人気男優の1人で、ソーハーも最近映画デビューをして女優として活躍中である。気になる長女の職業だが、どうやら宝石デザイナーをしているようだ。

ボリウッドの元祖セックス・シンボル
シャルミラー・タゴール

長男サイフ・アリー・カーン、男優

次女ソーハー・アリー・カーン、女優

長女サバー・アリー・カーン、宝石デザイナー
・・・あれっ?
今日はそのパタウディー・パレスまで1泊2日の旅程でバイクで行った。パタウディーはデリーから約60kmということで、今回のツーリングは非常に簡単なものであった。しかし、ニザームッディーンにあるニームラーナー・ホテル・グループのオフィスでもらったパンフレットの地図が間違っていたために苦戦してしまった。地図によるとパタウディー・パレスは、デリーから、ジャイプルへ続く国道8号線を南下して約70kmの地点にあるダールヘーラーから、さらに10km先に行ったビラースプルという町で右折したところにあると書かれていた。デリーから60kmというのに、計算が違うと前々から不審に思っていた。だが、「デリーからこんなに近いんですよ」ということを宣伝するためにわざと少な目の距離を公言しているのかと思い、まずはダールへーラーまで行ってみることにした。ダールヘーラーは9月25日のアルワル・ツーリングのときに経由していたので、よく覚えていた。午後1時頃にデリーを出て、午後2時過ぎにマーネーサルのマクドナルドで休憩し、後はひたすら南下した。すると、ダールヘーラーまであと20kmくらいあるのに、「ビラースプルまであと7km」の表示があり、頭が混乱した。そこで止まって道を聞けばよかったのだが、何となくダールヘーラーまでは行かなくてはならないように思っていたため、そのまま直進してしまった。ダールヘーラーを過ぎ、10kmほど進んだが、ビラースプルらしき町もなければ右折する道も見当たらなかった。そこで途中にあったガソリンスタンドで道を尋ねてみると、やはり行き過ぎてしまったことが分かった。あの地図は間違っていた!デリーから60kmという距離の方が正しかった!ビラースプルは、国道料金ゲートのところにある町で、ダールヘーラーから15kmほどデリー方面へ向かった地点であった。Uターンしてビラースプルまで戻ると、確かに「←パタウディー」と書かれた道標が立っていた。スピードを出していたので見過ごしてしまっていた。だが、この地図の間違いが分かってからはスムーズにパタウディーまで行くことができた。パタウディー・パレスは、国道8号線から沿道に入って7kmほど行った地点にあった。看板が出ていたのですぐに分かった。緑が生い茂る広々とした敷地を進んでいくと、「Mangal
Pandey」に出てきた建物がそのままの姿で現れた。3つのドームを冠した2階建ての、シンプルだがバランスのいい白亜の宮殿であった。迷っていたために2時間半ほどかかってしまったが、デリーから休憩なしで直行すれば、おそらく1時間半ほどで到着するだろう。

パタウディー・パレス

「Mangal Pandey」の1シーン

斜めから見たパタウディー・パレス
下の3枚は全て「Mangal Pandey」から



パタウディー・パレスの正面玄関には虎の剥製が置いてあり、マンスール・アリー・カーンの別名を来客者に彷彿とさせていた。玄関を入ってそのまま進むと、廊下にたくさんの写真が飾られており、マンスール・アリー・カーンやシャルミラー・タゴールの写真などがあった。また、クリケット関連の本や、ウルドゥー語の本なども書棚にしまわれていた。サイフ・アリー・カーンの写真は確認できなかったが、もしかしたら子供の写真がそれだったかもしれない。入って左奥にはビリヤード部屋があり、そこにもクリケット関係の写真がいくつか飾られていた。裏庭ではプールが建造中だった。2階には各所に、いかにもマハーラージャーが寝そべっていそうな寝台兼椅子が置かれており、マハーラージャーごっこができそうだった。パタウディー・パレスには11部屋ほど客室があり、それぞれにいろいろ名前が付けられている。僕はナワーブの名前を冠したマンスール・マハルに宿泊した。天上が高く、非常に広々とした部屋だったが、建物の外見と同じくセンスのいいシンプルな雰囲気にまとめられていた。その他には、イフティカール・マハル、サイフ・マハルなど、歴代のナワーブの名前を冠した部屋があって面白い。

ビリヤード部屋

「Mangal Pandey」の1シーン

マンスール・マハル
また、敷地内にはイフティカール・マスジドというモスクがあった。第8代ナワーブ、イフティカール・アリー・カーンが造ったものだが、こじんまりとしたモスクであった。ナワーブの家族のプライベート用モスクだったのだろう。また、敷地内にクリケット場があるとの情報を得たのだが、未確認である。

イフティカール・マスジド
パタウディー・パレスは今年オープンしたばかりであり、まだ認知度が低いようで、宿泊客が少なくて静かないい雰囲気のホテルだった。敷地内に孔雀がうろついていたり、小鳥たちのさえずりが絶え間なく聞こえたり、遠くから農業用水を吸い上げるポンプの音が聞こえてきたりと、非常にのどかであった。デリーの喧騒を逃れて週末を過ごすのに最適の場所ではなかろうか?何よりデリーからすぐ近くなのがよい。もちろん、ボリウッド映画ファンには、「Mangal
Pandey」のロケ地、かつ、シャルミラー・タゴールやサイフ・アリー・カーン所縁の邸宅として、注目すべき観光地だろう。ホテルになってしまってからはどうなっているか分からないが、噂によると時々サイフ・アリー・カーンなどが来るらしい。それと、日本人にクリケットが好きな人は少ないが、もしいたとしたら、インドのクリケットの生きた伝説が住んでいた宮殿として、やはり観光する価値があるだろう。宿泊費は部屋によって違うが、1番安いシングルルームが2000ルピー、一番高い部屋で7000ルピーである。ただ、ムスリムの王家の宮殿だったためか、それともまだライセンスを取得していないためか、アルコールが出てこない。だからもし酒を飲もうと思ったら、どこかで自分で買って来て、自室で飲まなければならない。また、まだ従業員が接客に慣れていないような印象も受けた。もしかしたら予約をしていないと敷地内に入れてもらえないかもしれない。前述の通り今のところパンフレットの地図が間違っているので、注意が必要であろう(現在修正版のパンフレットを準備中とか)。
| ◆ |
11月28日(月) Deewane Huye Paagal |
◆ |
本日、めでたく全ての課題を提出し終わった。僕の所属しているM.Phil(博士課程前期)にはテストがないので、これで今学期は終了となる。11月はかなり忙しい毎日だった。課題の提出が集中したのに加え、インド映画についてのレクチャーも頼まれ、しかも旅行もしていたので、本当に時間がなかった。ただ、今年の4月頃には課題とテストに追われてストレスが溜まり、帯状疱疹が発生するほどだったが、今回はそういうこともなく、何とか健康にモンスーン学期を終えることができた。とりあえず解放の喜びを胸に新作ヒンディー語映画「Deewane
Huye Paagal」を見にPVRアヌパムへ直行した。
「Deewane Huye Paagal」とは、「狂人が狂人になった」という意味。監督はヴィクラム・バット、音楽はアヌ・マリク。キャストは、アクシャイ・クマール、シャーヒド・カプール、リーミー・セーン、オーム・プリー、スニール・シェッティー、パレーシュ・ラーワル、ヴィジャイ・ラーズ、ジョニー・リーヴァル、ヴィヴェーク・オベロイ(特別出演)、アーフターブ・シヴダーサーニー(特別出演)など。
| Deewane Huye Paagal |
 25年間若返りの薬を研究していたクラーナー博士(オーム・プリー)は遂にその薬を完成させた。クラーナー博士はその薬の成分を金庫の中にしまい、その暗号をオウムの玩具にインプットさせた。ところがクラーナー博士の助手は、博士の双子の兄弟でマフィアのドンのクラーナーと密通していた。ドン・クラーナーは若返りの薬の完成を密かに待っていたのだった。ドン・クラーナーはクラーナー博士の自宅を急襲する。クラーナー博士は金庫は手放すものの、暗号を記憶したオウムの玩具を持って逃げ出した。オウムの玩具はたまたま通りがかった女子大生タニヤ(リーミー・セーン)の手に渡った。タニヤは、ドンの長男バルジートがクラーナー博士を殺すところ目撃してしまい、逃げ出す。そこでドンたちは、タニヤを必死になって捜索し出す。マフィアに追われることになったタニヤは、知能障害児の兄を連れてムンバイーを逃げ出す。【写真は左からスニール・シェッティー、シャーヒド・カプール、リーミー・セーン、アクシャイ・クマール、パレーシュ・ラーワル】 25年間若返りの薬を研究していたクラーナー博士(オーム・プリー)は遂にその薬を完成させた。クラーナー博士はその薬の成分を金庫の中にしまい、その暗号をオウムの玩具にインプットさせた。ところがクラーナー博士の助手は、博士の双子の兄弟でマフィアのドンのクラーナーと密通していた。ドン・クラーナーは若返りの薬の完成を密かに待っていたのだった。ドン・クラーナーはクラーナー博士の自宅を急襲する。クラーナー博士は金庫は手放すものの、暗号を記憶したオウムの玩具を持って逃げ出した。オウムの玩具はたまたま通りがかった女子大生タニヤ(リーミー・セーン)の手に渡った。タニヤは、ドンの長男バルジートがクラーナー博士を殺すところ目撃してしまい、逃げ出す。そこでドンたちは、タニヤを必死になって捜索し出す。マフィアに追われることになったタニヤは、知能障害児の兄を連れてムンバイーを逃げ出す。【写真は左からスニール・シェッティー、シャーヒド・カプール、リーミー・セーン、アクシャイ・クマール、パレーシュ・ラーワル】
一方、大学の食堂で働きながら勉強をしていたカラン(シャーヒド・カプール)は、タニヤに密かに恋していた。しかし同じ大学には、ドンの次男サニーもいて、タニヤに言い寄っていた。カランは誕生日にタニヤを家に呼ぶが、正にその日にタニヤの身に不幸が起こったのだった。カランはタニヤの家を訪ねるが、もうタニヤはどこかへ去った後だった。ただ、カランへの誕生日プレゼントが置かれていた。その袋の中には、オウムの玩具が入っていた。その後、タニヤの消息は誰にも分からなかった。
3年後、未だにタニヤのことを忘れられなかったカランは、喫茶店で働きながらタニヤの情報を集めていた。ある日、遂にタニヤがドゥバイにいることが分かる。カランは、ドゥバイにコネを持つゴロツキのロッキー(アクシャイ・クマール)に、ドゥバイでタニヤを探すよう頼む。ロッキーはドゥバイに飛びタニヤを探す。タニヤはナターシャと名を変えて、駆け出しのシンガーをしていた。ロッキーはナターシャに惚れてしまい、後からやって来たカランに、タニヤは既に結婚したと嘘の情報を伝えてインドへ追い返す。ところがカランは諦めきれず、ドゥバイに残っていた。
一方、ロッキーは何とかナターシャを口説こうと、あの手この手を使って近づく。ところがナターシャの周辺には2人の邪魔者がいた。1人はトミー(パレーシュ・ラーワル)。ナターシャが起こした交通事故により、右手と脳に障害を負ってしまった男だった。ナターシャは、死んだ兄の面影をトミーに見て、彼の面倒を見ながらスィーティーおばさんと一緒に暮らしていた。また、ナターシャの周りにいつもいるもう1人の男、サンジュー(スニール・シェッティー)は、足の不自由な建築家だった。サンジューはナターシャの付き合っていたラージ(アーフターブ・シヴダーサーにー)が実は麻薬密売人だったことを突き止めたりして、ナターシャの周辺の男たちを次々に遠ざけていた。
ドゥバイに残っていたカランは、とうとうタニヤ(=ナターシャ)を見つける。だが、彼女はロッキーと一緒だった。カランはロッキーに騙されたことを知りながらも、そのことには触れずにタニヤと旧交を温める。また、サンジューはロッキーが実は連続殺人犯だという嘘情報を吹き込み、ナターシャからロッキーを遠ざける。それに怒ったロッキーはサンジューを追いかけるが、なんと足の悪いはずのサンジューは松葉杖を放り出して走り出す。ロッキーはそれを追いかけ、それを後からトミーも追いかける。実はトミーも右手や脳に障害などなかった。ロッキーもサンジューもトミーも、ナターシャに惚れてしまった男たちで、あの手この手で彼女に近づこうとしていたのだった。3人はお互いの正体を知ると、今度はライバル同士としてときに一緒に作戦を練り、ときに足を引っ張り合う仲になる。とりあえずカランが標的となり、サンジューは得意の偽情報作戦でカランを彼女から遠ざけることに成功する。
ところがそのとき、ドン・クラーナーたちもタニヤを追ってドゥバイに来ていた。マフィアたちはタニヤの家に押しかけるが、タニヤを愛する次男サニーが暴走し、タニヤを連れて逃げ出す。それを追うドン・クラーナーたち、そしてそれをさらに追うカラン、ロッキー、サンジュー、トミーらだった。タニヤはバルジートに殺されそうになるが、そのときマフィアたちがオウムの玩具を求めていることを知ったカランは、それが今、ロッキーの手元にあることを知らせる。ロッキーはオウムの玩具がしゃべる暗号をタニアだけに聞かせ、オウムを壊してしまう。これでマフィアはナターシャを殺せなくなってしまった。カランやロッキーたちやマフィアたちが入り乱れての乱闘の中で、ナターシャはサンジューとトミーが実は障害者ではなかったことを発見してしまう。
ナターシャは周囲の男たちから騙されていたことを知ってショックを受ける。ロッキー、サンジュー、トミーは必死に言い訳をするが無駄だった。だがカランだけは違った。彼はナターシャのところにラージを連れて行く。ラージはナターシャの元彼氏だったが、サンジューの策略により絶交となってしまったのだった。それを知っていたカランは、ラージこそがタニヤにふさわしいと考えたのだった。しかし、その自己犠牲の心に感動したタニヤは、カランを自分の伴侶に選ぶ。一方、ドン・クラーナーは、若返りの薬を手に入れたものの、飲みすぎてしまって赤ちゃんになってしまった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
インド映画お得意の、大量の登場人物が入り乱れてのドタバタコメディー映画。人間関係が複雑に交錯するが、分かりやすく説明されていたので混乱することはほとんどないだろう。間違いなく今年最高のコメディー映画のひとつに数えられる。また、クライマックスの乱闘シーンは大量のスタントマンを動員したようで、やたら迫力があった。「Silsiley」(2005年)のシャールク・カーンみたいに、スートルダール(ナレーション)役で出演したヴィヴェーク・オベロイもいい味を出していた。ロマンスあり、笑いあり、涙あり、アクションあり、インド映画のスパイスが詰め込まれた良作である。
まずは露出度の高い女性ダンサーがいやらしい動きをするベリーダンス風の踊りで映画は始まる。そして突然、牧歌的な音楽が流れ始め、ヴィヴェーク・オベロイがスートラダールとして軽妙な口調で物語の導入を語り始める。この部分で大方の登場人物の紹介がなされ、観客はスムーズに映画の世界に入り込むことができる。タニヤのムンバイー脱出までの部分は言わば序章で、本編はほぼ全編ドゥバイが舞台となっている。その後の展開は上に書いた通りである。
基本的にコメディー映画だったが、アクションシーンにも力が入っていた。序盤のロッキー役のアクシャイ・クマールが筋肉モリモリの黒人と戦うシーンは、キックの見せ方などインド映画離れしたテクニックを感じた。だが、何と言っても圧巻なのは、終盤にある大乱闘シーンである。モトクロスやバギーに乗ったマフィアの手下たちが、モウモウと砂塵を巻き上げながら迫ってきて乱闘を繰り広げるのだが、それは乱闘と言うよりもアクロバット大会であった。モトクロスで空中一回転をしたり、バギーで前転したり、やり過ぎというくらいにド派手なアクションであった。しかもその後には最近ボリウッドで流行りのバイクチェイスが控えており、ウィリーやジャックナイフや立ち乗りなど、またも曲芸を披露する。ただただ唖然とするばかりだったが、面白かったのでよしとしよう。
シャーヒド・カプールは、序盤では冴えない男を演じていた。最近ボリウッドの男優は、「か弱い男」を演じることにあまり抵抗を感じなくなっているのではないかと感じている。トゥシャール・カプールなどはもはや僕に「のび太君俳優」とあだ名を付けられるくらい、「か弱い男」役が板に付いてしまったが、シャーヒド・カプールのような今をときめく若手人気男優までその路線を行くとは驚きを隠せない。日本では既に「か弱い男」像は市民権を得てしまったように思うのだが、インド映画の世界でももしかしたら「ヒーローは常に強くたくましくあるべき」という伝統的価値観が崩れつつあるのかもしれない。国の経済が発展すると、男は弱くなるものなのだろうか・・・などと深読みをしてしまう。あと、シャーヒド・カプールのダンスは、リティク・ローシャンの次くらいにうまいと思う。
アクシャイ・クマールは素晴らしいコメディアンヌ振り。「Mujhse Shaadi Karogi」(2004年)で既にコミックロールの才能の片鱗を見せていたが、「Garam
Masala」(2005年)を経て、この作品でもはやアクシャイ・クマールのコメディーの才能に疑問を差し込む余地はなくなったと言っていいだろう。元々スタントマン出身で運動神経抜群のアクシャイ・クマールは、芸幅の広い男優として最近急速に株を上昇させているように思える。
リーミー・セーンは、なぜかどうしようもない男たちに惚れられる、男運が強いんだか弱いんだかよく分からないヒロインを真摯に演じていた。個人的にはリーミー・セーンにそれほど大女優のオーラーを感じていないのだが、このままコンスタントに映画に出演していけば、一定の地位は獲得できるかもしれない。この映画のタニヤ=ナターシャの役は、ハリウッド映画「メリーに首ったけ」(1998年)でキャメロン・ディアスが演じたメリーと酷似している。明らかにこの映画は「メリーに首ったけ」を翻案した作品だろう。ヴィヴェーク・オベロイのナレーションの着想も同映画から来ていると思われる。
その他の俳優たちも見事なコメディー振りだった。パレーシュ・ラーワルは言うまでもなく最高のコメディアンだ。この映画を撮影中にドゥバイの空港で麻薬所持の疑いで逮捕されたヴィジャイ・ラーズもいい味を出していたし、久々にジョニー・リーヴァルの四角い顔をスクリーンで見ることができて大満足。スニール・シェッティーも、普段あまり見せないコメディーの顔を見せていた。どちらかというと、いつも安定した演技力を見せるオーム・プリーの存在感が薄かったか。
この映画の中で一番僕が面白かったのは、ドンの次男のサニーであった。「北インド出身の父親から産まれた南インド人」というおかしな設定で、ファミリーの中で1人だけタミル人っぽい外見としゃべり方をパロディーしていた(どうも亡くなった母親が南インド人の浮気相手と作った子供という設定のようだ)。演じていたのはスレーシュ・メーナンという男優である。タミル語映画には北インド人のパロディーが出て来るが、ボリウッド映画にはスィク教徒とタミル人のパロディーがよく出て来るように思える。
音楽は、ベリーダンス風の「Chakle Chakle(Remix)」が一番耳に残った。スートラダールのシーンの「ドゥンドゥンドゥン・・・」というカントリー風の音楽もなかなかおとぼけていてよかった。海外ロケはドゥバイが中心だが、ミュージカル・シーンでロサンゼルスのユニバーサル・スタジオ・ハリウッドなどが出て来る。
「Deewane Huye Paagal」は、特にコメディーとアクションが見所の典型的インド映画である。気分転換に最適の作品と言える。



