|
|
ヒンディー語映画の中心地と言えばムンバイーであり、ムンバイーの旧名ボンベイとハリウッドの掛け合わせから、ヒンディー語映画産業は「ボリウッド」と呼ばれている。マラーティー語話者が大多数を占めるマハーラーシュトラ州の州都ムンバイーにヒンディー語映画の中心地があることは一見奇妙に見える。だが、歴史を紐解いてみるとその理由は自ずと見えて来る。端的に言えば、ムンバイーを含む海に面した地域はいち早く英領植民地となり、西洋の文化の影響を受けて来た一方、ヒンディー語圏は内陸部にあり、海側の地域から始まった英国支配や西洋文化流入は比較的後になってからヒンディー語圏に到達した。当時最新技術だった映画も、ムンバイーなど英国支配が深く浸透した地域から受け容れられて行った。その一方で、当時からインド全土のリングア・フランカとして機能して来たのがヒンディー語またはウルドゥー語であり、インド人による映画制作が始まり、トーキー映画が導入されたときに、全国的な収益を上げられる言語として自然とヒンディー語またはウルドゥー語が選ばれたのだった。ヒンディー語映画の中心地としてのムンバイーの地位は未だに揺るいでいない。多くのヒンディー語映画がムンバイーを舞台にし、ほとんどのヒンディー語映画関係者がムンバイーに住んでいる。
しかしながら、最近デリーを舞台にし、デリーでロケが行われたヒンディー語映画が増えて来ており、一種の流行のようになっている。デリーの空気や光線はムンバイーのそれとは明らかに異なっており、映像からして従来のヒンディー語映画とは一線を画した印象を観客に与えられるのがデリー・ロケの強みだ。「Lakshya」(2004年)でデリーの風景が出て来たときには目新しい印象を受けたものだが、最近ではデリー・ロケは全く珍しいものではなくなり、映画の題名にまで「デリー」が登場することが出て来た。もちろん過去にも「New
Delhi」(1956年)や「Tarzan Comes to Delhi」(1965年)などの映画があった訳だが、最近は「Delhi Hights」(2007年)、「Delhi-6」(2009年)など立て続けに「デリー映画」が続いており、本日公開の「Delhi
Belly」もその1本となっている。題名に「デリー」は含まれないが、全編または大半をデリーで撮影した映画を数えて行ったら切りがないが、「Oye
Lucky Lucky Oye」(2008年)や「Band Baaja Baaraat」(2010年)などがよくデリーの雰囲気をスクリーンに再現したヒット作となっている。
最新映画「Delhi Belly」の題名になっているデリー・ベリーとは直訳すればデリー腹で、つまりは旅行者性下痢のことである。別にデリーでなくても、またはインドでなくてもいいのだが、海外に旅行した際に水が合わなかったり食べ物が変わったりで下痢になることはよくある。それを俗称でデリー腹と言う。デリー腹については以前、最近ニューデリーの名を世界に知らしめたスーパー細菌NDM-1などと併せてNDM-1とデリー腹とナハーリーという記事を書いたことがある。一種の病名であるため、映画の内容がデリーとは全く関係ないこともあり得たのだが、この「Delhi Belly」に関してはそんなことはなく、正真正銘、デリーを舞台にした映画となっている。
「Delhi Belly」の監督はアビナイ・デーオ。今年4月に公開された「Game」でデビューした監督であり、かなり短いインターバルでの次作公開となった。それよりも何よりもこの映画が注目を集める理由となっているのがプロデューサーのアーミル・カーンである。ヒンディー語映画界の3大スター「3カーン」の1人として、ヒット作を見抜く千里眼と、役と一体化する演技力を併せ持つ名優として、また優れた映画監督として、ヒンディー語映画界を牽引する才人であるが、「Lagaan」(2001年)以降はプロデューサーとしても八面六臂の活躍をしており、「Peepli
[Live]」(2010年)や「Dhobi Ghat」(2011年)などユニークな作品を送り出して来ている。主演はアーミル・カーンの甥にあたるイムラーン・カーン。サントラCDの大ヒットもあり、今年下半期の最初の話題作となっている。
ちなみに、「Delhi Belly」はヒングリッシュ・オリジナル版とヒンディー語ダビング版の2種類が公開されている。ヒングリッシュ・オリジナル版は台詞が英語とヒンディー語のミックスである一方、ヒンディー語ダビング版は台詞の全てがヒンディー語となっている。僕はオリジナルのヒングリッシュ版を選んだ。
題名:Delhi Belly
読み:デリー・ベリー
意味:デリー腹(旅行者性下痢)
邦題:デリー・ベリー
監督:アビナイ・デーオ
制作:アーミル・カーン、キラン・ラーオ、ロニー・スクリューワーラー、ジム・フューゲル
音楽:ラーム・サンパト
歌詞:アミターブ・バッターチャーリヤ、ムンナー・ディーマーン、ラーム・サンパト、アクシャト・ヴァルマー、チェータン・シャシタル
出演:イムラーン・カーン、クナール・ロイカプール、ヴィール・ダース、プールヴァー・ジャガンナータン、シェヘナーズ・トレジャリーワーラー、ラーフル・スィン、ラージュー・ケール、ヴィジャイ・ラーズ、パレーシュ・ガナートラー、ラーフル・ペーンドカルカル、アーミル・カーン(特別出演)
備考:PVRプリヤーでヒングリッシュ・オリジナル版を鑑賞。
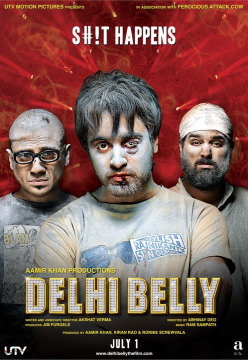
左からクナール・ロイカプール、イムラーン・カーン、ヴィール・ダース
| あらすじ |
ジャーナリストのタシ(イムラーン・カーン)は、イラストレーターのニティン(クナール・ロイカプール)、カメラマンのアループ(ヴィール・ダース)と共にデリーのオンボロアパートに暮らしていた。タシは成り行きからガールフレンドのソーニヤー(シェヘナーズ・トレジャリーワーラー)と1ヶ月以内に結婚することになってしまい、それで本当にいいのか悩んでいた。タシは仕事上で米国から来た女性ジャーナリスト、メーナカー(プールナー・ジャガンナータン)と出会う。メーナカーは離婚した元夫から追いかけられており、タシもそれに巻き込まれて、左目を殴られ、ソーニヤーの父親からもらったばかりの車を傷つけられ、命も危険にさらす。
ところでソーニヤーは航空機の客室乗務員をしていた。ソーニヤーは友人の頼みで、とあるロシア人乗客からマトリョーシカを預かった。それをデリーの手工芸品店に届けて欲しいと言われたが、忙しかったためにその役目をタシに押し付けた。タシはそれをアループに押し付け、アループはそれをニティンに押し付けた。
ところでアループは路上の露店で売られていたチキンを食べて腹を壊してしまっていた。アループはついでにニティンに自分の便を渡し、検査所に届けるように頼んだ。ニティンは誤ってマトリョーシカを検査所に届けてしまい、便を手工芸品店に届けてしまった。
実はそのマトリョーシカの中にはダイヤモンドが30個隠されており、密輸マフィアのボス、ソーマヤージュル(ヴィジャイ・ラーズ)に届けられるべきものであった。ソーマヤージュルはダイヤモンドの代わりに大便が届けられたことに激怒し、部下たちを引き連れてロシア人を襲撃する。ロシア人は今回代理の運び屋を使ったことを白状する。ソーマヤージュルがソーニヤーに電話すると、ソーニヤーはタシが届けたと言う。
タシの住所を聞いたソーマヤージュルは彼の家へ押しかける。そこにはちょうどガールフレンドから振られたばかりのニティンがおり、拷問を受け、天井から吊される。そこへタシが帰って来る。タシも何のことか分からない。そこへアループが帰って来る。アループは検査所からマトリョーシカを受け取って帰って来ていた。ソーマヤージュルがそのマトリョーシカを開けてダイヤモンドを取り出し調べると、本物であることが分かった。満足したソーマヤージュルは3人を殺そうとする。ところがそのとき、天井が崩落し、ソーマヤージュルとその部下たちは下敷きになる。タシ、アループ、ニティンの3人はマトリョーシカを持って逃げ出す。
とりあえずメーナカーの家で一晩を明かした3人は宝石商のところへダイヤモンドを売りに行く。驚いたことに900万ルピーもの値段で売却できた。ところがその直後にソーマヤージュルから電話がある。ソーマヤージュルはソーニヤーを人質に取っており、ダイヤモンドを持って来るよう命令して来た。3人は宝石商のところへ行くと、宝石商はダイヤモンド買い戻しのために2倍の値段を要求して来た。そこで3人はメーナカーの協力を得て、ブルカーをかぶって強盗に押し入り、ダイヤモンドを取り戻す。
ダイヤモンドを持ってソーマヤージュルの待つホテルの一室へ3人は行った。しかし人質交換の方法で折り合わず、あわや銃撃戦が起こる寸前となる。ところがそこへ、宝石商の店から追って来ていた警察が踏み込み、マフィアと警察の間で撃ち合いとなる。トイレに入っていたアループと、咄嗟に身を伏せていたニティンと、そしてソーニヤーを守って倒れ込んでいたタシは助かるが、他の人々はそのまま相打ちとなる。
せっかくソーニヤーを助けたタシであったが、メーナカーとキスしたことを白状してしまい、ソーニヤーとの縁談は破談となる。ダイヤモンドの入ったマトリョーシカは銃撃戦の後にホテルの窓から落ちてしまい、行方不明となるが、それはたまたま階下にいた、3人の大家さんが拾っていた。大家さんは、その中にダイヤモンドがあるとは知らず、マトリョーシカを棚の中にしまった。また、タシは、忘れ物を届けに訪ねて来たメーナカーに強引にキスをする。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
サブタイトルは「S#!T HAPPENS」で、敢えて原文のニュアンスを残して意訳するならば「クソったれのウン命」みたいな感じであろう。しかし本当にクソまみれの映画であるとは全く予想だにしなかった。
まず、主人公3人の内の1人アループが映画の最初から最後まで下痢状態で、事あるごとにトイレに駆け込み、轟音を轟かせて排泄するシーンが何度も出て来る。さらに、密輸されたダイヤモンドの入ったマトリョーシカと、検便のために採取した彼の大便を入れた容器が取り間違えられてしまい、それが3人を大きなトラブルに巻き込む。ヒッチコックが得意とする巻き込まれ型サスペンスの一種であるが、全体的に排泄に関するストレートなダーティーさで溢れた下品な映画であり、家族揃って、スナックを頬張りながら鑑賞するような作品ではない。このクソまみれな要素のみから見るならば、主人公はイムラーン・カーン演じるタシよりもむしろ、デリー腹を抱えたアループであった。アループを演じていたのはコメディアンのヴィール・ダースである。また、大胆にもヒロインのシェヘナーズ・トレジャリーワーラーがトイレで便器に座って用を足してながら電話をしているシーンまであり、ヒロインですら聖域を用意されていない。
このように下品かつ下劣なシーン満載であったが、それでもスピーディーな展開かつブラックコメディーを基本にした味付けで、楽しく鑑賞することが出来た。何らかの荷物を取り違えたことからトラブルに巻き込まれる展開の映画はインドにも数多く、その点で目新しさはなかったが、ストーリーの転機となる要所要所で意外性のある事件が起こっており、全く飽きさせなかった。
映画の認証は18歳未満閲覧禁止の「A」であるだけあり、開き直った大胆なシーンが多かったが、やはり台詞でもっとも冒険しており、放送禁止用語のオンパレードであった。ただ、ヒングリッシュ版は英語の台詞が多すぎたと感じた。気の置けない仲間同士でリラックスした会話をしているときに、デリーのインド人がこのようなこねくり回した英語を使うのはあまりに不自然である。せっかくヒングリッシュ版を銘打ったのだから、もっとナチュラルな言葉遣い――つまりもっとナチュラルな英語とヒンディー語のミックス――の再現を努力すべきだった。それがヒングリッシュ映画の強みなのだから。
デリーを舞台としていながら、敢えてデリーのランドマークをほとんど登場させなかったのにも感心した。下手なデリー映画だと、インド門やらクトゥブ・ミーナールやら、一目でデリーだと分かるランドマークを背景に入れたがるのだが、本当にデリーの地に足を付けた人が撮るデリー映画はかえってそういうことはなく、もっとデリーのローカルな魅力を、デリーの匂いを、デリーの喧噪を、画面に映し出そうとする。「Delhi
Belly」もそういう映画のひとつだった。最近、モダン・デリーの象徴となっているデリー・メトロが出て来たくらいか。見る人が見ればオールド・デリーのシーンはオールド・デリーで撮影されたことが分かる。宝石商にダイヤモンドを売るシーンにしても、オールド・デリーの伝統的な宝石商街であるダリーバー・カラーン近くのチャーウリー・バーザールが映っていた訳で、確かにダイヤモンドを売るためにはそこへ行くのが一番いい。デリーのことに詳しい人ならそういう知識があって密かに納得する訳だが、そういうことについて特に劇中で言及されておらず、デリーという存在は完全に裏方に徹していたと言える。そういうさりげないこだわりが心地よかった。
「Delhi Belly」の上映時間は102分。インド映画の中では非常に短い。また、アーミル・カーン制作、妻キラン・ラーオ監督の「Dhobi
Ghat」(2011年)に続き、「Delhi Belly」はインターミッション(途中休憩)のない映画となっている。その思い切りの良さもよかった。今後ノー・インターミッションの映画が増えて行くかもしれないが、インターミッション中の飲食物売上に収益を依存する映画館側からしたら好ましくないことで、どうなって行くことだろうか。
また、イムラーン・カーン演じるタシはチベット人という設定も重要であろう。年齢からすると難民3世ということになるだろうか。劇中特に彼のエスニシティーがストーリーに絡んで来たり言及されたりする訳ではないが、タシという名前はチベット文化圏で一般的な名前で、実際に監督もそのつもりであるらしい。おそらくチベット人を主人公にしたヒンディー語映画は史上初なのではなかろうか。
イムラーン・カーン、クナール・ロイカプール、ヴィール・ダースと、主演3人はそれぞれ個性的な演技をしており、素晴らしかった。クナール・ロイカプールは、「Action
Replayy」(2010年)や「Guzaarish」(2010年)に出演して最近人気急上昇中のアーディティヤ・ロイカプールの兄である。ヒロインの中ではメーナカーを演じたプールナー・ジャガンナータンが光っていた。ロサンゼルスをベースとするインド系米国人女優で、今回がヒンディー語映画デビュー作となる。劇中ではイムラーン・カーンとホットなキスもしている。もう1人のヒロイン、シェヘナーズ・トレジャリーワーラーは「Ishq
Vishk」(2003年)などに出ていた女優で、最近公開された「Luv Ka The End」(2011年)では脚本も書いている。しかし存在感から言ったらプールナー・ジャガンナータンに完全に呑まれていた。
「Delhi Belly」の長所のひとつは音楽である。作曲はラーム・サンパト。一般的なダンスシーンはほとんどなく、BGMとして流れるだけだったが、ユニークな曲が多く、ヴァラエティーに富んでおり、サントラCDは買いである。特に「Bhaag
D.K. Bose, Aandhi Aayi」はカルト的人気となっている。この曲の歌詞については以前書いたのでそちらを参照してもらいたい。
また、エンドクレジット直前のダンスシーン「I Hate You (Like I Love You)」では驚いたことにアーミル・カーンがアイテムボーイ出演しており、15年前くらいのノリで、ノリノリのダンスを踊っている。これも要注目だ。
「Delhi Belly」はアーミル・カーンが満を持して送り出すブラックコメディー映画。下品な歌があり、下品なシーンも多いが、それを笑って許せるだけの許容力があれば、そして18歳以上ならば、この映画はオススメできる。ヒンディー語版の他にヒングリッシュ版もあり、こちらはほとんど台詞が英語となるので、ヒンディー語が理解できないために普段ヒンディー語映画を見ない人にとっても敷居が低いだろう。上映時間の短さも後押しになる。ほぼ全編デリーで撮影されていることもデリー在住者にとっては嬉しい。今年下半期、まずは「Delhi
Belly」がパンチの効いた笑いを提供してくれた。
| ◆ |
7月6日(水) Bbuddah Hoga Terra Baap |
◆ |
1970年代から80年代にかけて絶大な人気を誇り、ヒンディー語映画産業を「ワン・マン・インダストリー」とまで揶揄させしめたスーパースター、アミターブ・バッチャンは、2010年代も健在で、今でも多くの映画に出演している。しかしながら、先日、息子のアビシェーク・バッチャンと結婚したアイシュワリヤー・ラーイ・バッチャンの妊娠が明らかになり、アミターブは遂にお祖父ちゃんとなる。
そんな絶好のタイミングで公開されたのがアミターブ・バッチャン主演「Bbuddah Hoga Terra Baap」である。題名の意味は「老いぼれはお前の親父だろう」。意訳すれば「オレはまだ老いぼれじゃない」「オレはまだ現役だぜ」「オレを年寄り扱いするな」みたいな感じである。アミターブの主演作は最近でも何本もあるのだが、アミターブを主演としたアクション映画はさすがに見ない。しかし「Bbuddah
Hoga Terra Baap」は現在68歳のアミターブ主演のアクション映画ということで注目を集めている。かつてアングリー・ヤングマンの役柄で一世を風靡したアミターブへのトリビュート的作品であり、アミターブ・バッチャンがヒンディー語映画界で受けている尊敬の度合いがよく分かる。同時代にトップ女優だったヘーマー・マーリニーが「ヒロイン」として出演していることも注目。また、監督は大ヒットしたテルグ語映画「Pokiri」(2006年)などで有名なプリー・ジャガンナートである。
題名:Bbuddah Hoga Terra Baap
読み:ブッダー・ホーガー・テーラー・バープ
意味:老いぼれはお前の親父だろう
邦題:老いぼれと呼ばないで
監督:プリー・ジャガンナート
制作:ABコープ、ヴィアコム18モーション・ピクチャーズ
音楽:ヴィシャール・シェーカル
歌詞:アンヴィター・ダット
出演:アミターブ・バッチャン、ヘーマー・マーリニー、ソーヌー・スード、ソナール・チャウハーン、チャーミー・カウル、プラカーシュ・ラージ、マクランド・デーシュパーンデーイ、スッバー・ラージュー、シャーワール・アリー、ラージーヴ・ヴァルマー、ラージーヴ・メヘター、ヴィシュワジート・プラダーン、アトゥル・パルチューレー、ラヴィーナー・タンダン(特別出演)
備考:DTスター・プロミナード・ヴァサント・クンジで鑑賞。

アミターブ・バッチャン
| あらすじ |
ムンバイーのアンダーワールドのドン、カビール(プラカーシュ・ラージ)は爆弾テロで市内を恐怖のどん底に陥れていた。それに対し、ムンバイー警察のカラン・マロートラー警視監(ソーヌー・スード)はムンバイーからマフィアの一掃を公言する。カビールはカラン警視監の命を狙い、殺し屋を雇う。
一方、カランは大学時代からターニヤー(ソーナール・チャウハーン)という女の子を追いかけていた。ターニヤーはカランを寄せ付けなかったが、親友のアムリター(チャーミー・カウル)はターニヤーが本当はカランのことを好きだと気付いていた。
アムリターはある日、ヴィッジュー(アミターブ・バッチャン)というセクシーな老人と出会い、仲良くなる。ターニヤーとアムリターがチンピラに絡まれているときにもヴィッジューに助けてもらった。ヴィッジューは元々ムンバイーのギャングスターであった。ヴィッジューには妻と子もいたが、警察に逮捕され2年の懲役刑を受けたことで妻子とは縁を切り、単身パリへ渡ってパブを経営していた。その彼が突然ムンバイーに舞い戻って来たのだった。
アムリターはヴィッジューを家に招く。ところがアムリターの母親カーミニー(ラヴィーナー・タンダン)はヴィッジューのことを知っていた。実はカーミニーは若い頃ヴィッジューにゾッコンだったのである。母親の様子を見てアムリターは、自分が実はヴィッジューの子なのではないかと悩むが、ヴィッジューはそれを否定する。それよりも衝撃的だったのは、実はヴィッジューは、カランの母親スィーター(ヘーマー・マーリニー)の夫で、つまりカランは彼の子であるという事実であった。ヴィッジューは、息子の身に危険が迫っていることを知って、息子を守りにムンバイーに戻って来たのだった。
ヴィッジューは影ながらカランとターニヤーを近付ける。カランはターニヤーとの結婚を申し出るが、障害がひとつあった。それはターニヤーの父親プレームナートだった。プレームナートは家庭裁判所の役人で、毎日恋愛結婚の登記に来る若いカップルを見て来て、恋愛結婚の反対者になっていた。それでもカランはプレームナートに結婚を申し出に行くが、カランの両親が恋愛結婚をし、しかも父親がいないということを知ると、憤って彼を追い出す。それを聞いたヴィッジューはまずは脅して2人を結婚させようとするが、プレームナートは暴力に屈する男ではなかった。そこでヴィッジューは愛を使って説得し、プレームナートは考えを改める。
一方、ヴィッジューは息子を守るため、友人になったマフィアの下っ端マック(マクランド・デーシュパーンデーイ)を通じて、カランの命を狙うカビールのマフィアの仲間入りをする。そこで情報を収集し、カランにさりげなく危険を知らせていた。ところがヴィッジューにもマフィアの全ての攻撃からカランを守ることができず、カランは銃撃を受けて危篤状態となってしまう。
怒ったヴィッジューは、喜びに沸くカビールの隠れ家へ行き、巧みにマフィアたちを混乱させて一網打尽にする。最後に残ったカビールをもヴィッジューは撃ち殺す。
まだカランは病室で昏睡状態であった。そこでスィーターに今後のことを聞かれたヴィッジューは、再び危険が迫ったら戻って来ることだけを告げ、ムンバイーを去る。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
典型的ヒーロー物映画であったが、ヒーローが老齢であること、そして自分のことをまだ若者だと考えていることなどによってユニークさを出しているアクション映画だった。主人公のヴィッジューは凄腕の殺し屋であると同時に「ブッダー(老いぼれ)」と言われるとぶち切れるという特異なキャラクターで、しかも若い女の子に目がないナンパ師である。当然のことながら、このヴィッジューを中心にストーリーが展開する。ヴィッジューを演じたアミターブ・バッチャンは果敢にアクションやダンスに挑戦していたが、やはり年齢には勝てないのか、身体が動いていない場面が多かった。だが、それを奇抜なファッションと当意即妙な受け答えでカバーしていた。また、ヴィッジューの年齢に適したシニア・ヒロインとして、ヘーマー・マーリニー演じるスィーターと、ラヴィーナー・タンダン演じるカーミニーが用意されていた。
このシニア層キャスト陣とは別に、ジュニア層のキャストもいた。ソーヌー・スード演じるカラン、ソーナル・チャウハーン演じるターニヤー、チャーミー・カウル演じるアムリターである。通常の映画ならこの年齢層のキャストが中心となるところであったが、「Bbuddah
Hoga Terra Baap」では脇役に過ぎなかった。カランは終盤で重傷を負ってそのままほぼ退場となってしまうし、ターニヤーやアムリターに至っては終盤では全く存在感なしである。
一応脚本上工夫してあったのは、マフィアのドン、カビールが送り込んだスパーリー(契約殺し屋)が、序盤ではヴィッジューであると匂わせておき、インターミッション前後でそれを覆して、実はスパーリーは別人だったとすることである。また、同時にカランは彼の実の息子であることも明かされる。このどんでん返しを除けば、非常に平坦な展開の平凡な映画だったと言わざるを得ない。
唯一高く評価できるのは、ターニヤーの父親プレームナートの改心シーンである。プレームナートは強硬な恋愛結婚反対派で、娘の恋愛結婚にも断固として反対だった。ところが、彼が結婚させたカップルの子供たちから誕生日祝いに花をもらい、しかもその子供たちの名前がプレームナートにあやかったものであることを知って感動する。そして一転、娘の結婚を認めるのである。直接描写されていなかったが、これは裏でヴィッジューが操作していたと予想される。あまりに短絡的な展開ではあるが、「Bbuddah
Hoga Terra Baap」の中でもっともホロリとするシーンだと言える。
ヴィッジューが、負傷した息子と妻スィーターを置いてムンバイーを去って行くシーンで映画は終わるが、いくつか完結していない要素があり、続編につなげられるような終わり方だと感じた。例えばムンバイーで連続爆破テロを起こしていたカビールの裏にはデリーの政治家の影がちらついていたのだが、劇中ではそこまで追求されることはなかった。ヴィッジューとカランの父子関係にしても、カランはヴィッジューが自分の実の父親であるとは知らずに終幕を迎えている。カランとターニヤーの縁談も中途半端に終わってしまった。上映時間は2時間ほどであり、インド映画としては短い作品に入るのだが、あと30分~1時間を加えてその辺りのエピソードを追加しても良かったのではないかと感じた。
アミターブ・バッチャンは完全に若き日の自らのヒーロー振りの再現を楽しんでおり、アミターブ・バッチャンのファンにとっては必見の映画となっている。アミターブは「Nishabd」(2007年)や「Cheeni
Kum」(2007年)でかなりの年の差恋愛をしたり、「Paa」(2009年)で子役を演じたりと、本当にヴァラエティーに富んだ役に挑戦している。この「Bbuddah
Hoga Terra Baap」も彼のユニークなフィルモグラフィーを彩る作品となるだろう。それに加え、彼の出演作の映画音楽をメドレー形式でつなげたダンスナンバー「Go
Meera Go」などは、リアルタイムで彼の活躍を追って来た映画ファンには嬉しいサービスだ。
アミターブ以外に良かったのはソーヌー・スード、チャーミー・カウル、そしてプラカーシュ・ラージである。ソーヌー・スードは基本的にテルグ語映画を本拠地としているが、ヒンディー語映画でもいくつかヒット作に出演しており、顔が売れて来ている。何より長身でガタイが良く、アミターブの息子という役柄は、実の息子アビシェークを除けば、もっともよく似合っていたかもしれない。チャーミー・カウルは、カランの恋人ターニヤーの親友という脇役ポジションであったが、やはりテルグ語映画で主に活躍して来た女優であり、本作が彼女にとってのヒンディー語映画デビューとなる。多少オーバーアクティング気味ではあったものの、表情豊かで、その名の通り本当にチャーミングな女優であった。チャーミーに比べると、ターニヤーを演じたソーナル・チャウハーンは、終始しかめっ面をしていてあまり好印象ではなかった。もちろんヘーマー・マーリニーも貫禄の演技であった。また、悪役カビールを演じたプラカーシュ・ラージも南インドの俳優で、ヒンディー語映画にもちょくちょく出演している。ネットリとした重みのある演技ができる俳優で、今後も「Singham」(2011年)などのヒンディー語映画に出演が決まっており、全インド的な知名度を獲得しそうだ。
特別出演扱いであるが、ラヴィーナー・タンダンがおかしな役で出て来たことが意外だった。ラヴィーナーと言えば90年代から00年代前半まで活躍した女優であり、シリアスな演技で記憶に残っていた。しかし今回彼女が演じたのは、ヴィッジューの昔の愛人またはファンで、ヴィッジューと再会したことで当時の情熱が蘇りおかしな素行をし始めるという、半ばコミックロール、半ば汚れ役みたいなもので、昔のラヴィーナーとどうしても重ならなかった。しばらくスクリーンから遠ざかっていたが、この特別出演が彼女の復帰のきっかけとなるのであろうか?
音楽はヴィシャール・シェーカルだが、短い映画だったこともあり、挿入歌やダンスナンバーが挿入されるシーンは少なかった。前述のダンスシーン「Go
Meera」と、ヴィッジューとスィーターの間で夫婦愛を象徴する「Haal-E-Dil」ぐらいである。また、テーマソングとして「Bbhuddah
Hoga Terra Baap」がある。ユニークなのは、ほぼ全ての曲をアミターブ・バッチャン自身が歌っていることである。アミターブは過去にもいくつかの映画で歌声を披露して来ており、「Kabhi
Khushi Kabhie Gham」(2001年)での「Say Shava Shava」などが有名だ。この点でも「Bbuddah Hoga
Terra Baap」はアミターブ・バッチャンのファンにとって必見の映画である。
「Bbuddah Hoga Terra Baap」は、アングリー・ヤングマンとして知られた70年代からおよそ40年に渡ってヒンディー語映画界に君臨し続けているアミターブ・バッチャンが、老齢ながらも再び全盛期のようなヒーローを演じたユニークなアクション映画である。ストーリー自体に目立って新鮮な部分はなく、エンターテイメントとして見ても強いインパクトのある作品ではないが、アミターブ・バッチャンのファンならば十二分に楽しめることだろう。
かつて「スキン・ショー」という言葉がヒンディー語映画界を騒がせたことがあった。「スキン・ショー」とは文字通り「肌見せ」であり、女優が裸または露出度の高い服を着て登場するシーンや、またはそういうシーンが多かったり前面に押し出されたりした映画のことを言う。その傾向は、ビパーシャー・バスを21世紀最初のセックス・シンボルに押し上げた「Raaz」(2002年)から始まっていたが、スキン・ショーが一応の頂点に到達したのが「Murder」(2004年)であった。その後「連続キス魔(シリアル・キサー)」として有名となるイムラーン・ハーシュミーと、ビパーシャー・バスからセックス・シンボルの座を奪い取ったマッリカー・シェーラーワトが主演で、共にこの映画をきっかけにスターダムを駆け上った。その後、皮肉にもスキン・ショーからは男優すらも逃れられなくなり、女性監督ファラー・カーンは「Om
Shanti Om」(2007年)の中で主演男優シャールク・カーンのスキン・ショーをやってのけた。それは半ば冗談としても、最近では女優を脱がせて観客を動員しようとするような安易な映画はなくなっている代わりに、女優の肌見せはそれほど珍しいものではなくなってしまっている。そのタガが外れたのがちょうど「Murder」前後であった。
そんな2004年の大ヒット作の1本「Murder」の続編「Murder 2」が本日より公開となった。とは言っても前作とのつながりはほとんどない。イムラーン・ハーシュミーが引き続き主演であること、そして映画中で前作の挿入歌が効果的に使われることを除き、「Murder」とは全く別の映画と言っていいだろう。ヒロインはマッリカー・シェーラーワトではなくスリランカ人女優ジャクリン・フェルナンデスとなっているし、前作の舞台はバンコクだったのに対し今回はゴアである。また、監督も前作はアヌラーグ・バスだったが、本作は「Kalyug」(2005年)や「Raaz
- Mystery Continues」(2009年)で有名なモーヒト・スーリーにバトンタッチしている。端的に言えば、「Murder」の続編を名乗る必要性はほとんどなかった作品である。
題名:Murder 2
読み:マーダー2
意味:殺人2
邦題:マーダー2
監督:モーヒト・スーリー
制作:ムケーシュ・バット
音楽:ハルシト・サクセーナー、ミトゥン、サンギート&スィッダールト・ハルディープル、スデャーンシュ・パーンデーイ
歌詞:サイード・カードリー、クマール、ミトゥン
振付:ラージュー・カーン
出演:イムラーン・ハーシュミー、ジャクリン・フェルナンデス、プラシャーント・ナーラーヤナン、スラグナー・パーニグラヒー、スダーンシュ・パーンデーイ、サンディープ・スィカンド、シュエーター・カワートラー(特別出演)、ヤーナー・グプター(特別出演)
備考:PVRプリヤーで鑑賞。
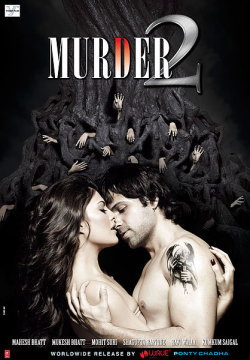
ジャクリン・フェルナンデス(左)とイムラーン・ハーシュミー(右)
| あらすじ |
ゴア在住のアルジュン・バーグワト(イムラーン・ハーシュミー)は警官崩れの悪党で、ドラッグ密輸などをしてあぶく銭を稼いでいた。モデルのプリヤー(ジャクリン・フェルナンデス)はアルジュンに恋していたが、アルジュンは彼女のことを恋愛対象でも性欲のはけ口でもなく、「単なる癖」と呼んでいた。
あるときアルジュンは、コールガールの総元締めサミールから呼び出される。ここ数週間コールガールが次々に姿を消しており、アルジュンはその原因究明を任される。アルジュンは、ライオンを狩るには獲物が必要だと提案し、コールガールを囮にして犯人まで辿り着こうとする。
一方、ゴアの大学で商学を学んでいたレーシュマー(スラグナー・パーニグラヒー)は、貧しい家族を支えるためにコールガールをする決意をしていた。最初の客となったのがディーラジ・パーンデーイ(プラシャーント・ナーラーヤナン)であった。
実はこれまでコールガールを殺して来たのはディーラジであった。ディーラジは普段男性として生きていたが、男性器を切り落としており、女装を趣味としていた。また、女性に深い嫌悪感を抱いており、コールガールを呼んではなぶり殺しにするのを楽しみにしていたのだった。レーシュマーも彼の餌食となり、井戸に放り込まれるが、彼女はまだ生きていた。
レーシュマーが連続殺人犯の元に送られたことを直感したアルジュンは彼女を追う。その内偶然にも彼女の携帯を持つディーラジを発見し追いかける。ディーラジを捕まえて殴りつけたまでは良かったのだが、警察に制止されて署に連行されてしまう。
取り調べを受ける中でディーラジは連続殺人を自白する。だが、ちょうどクリスマス~ニューイヤーのシーズンで、ゴアの観光業の稼ぎ時だった。州政府からの命令でこの事件は公表されなかった。ディーラジは精神鑑定の結果、精神に異常があるとされ、しかもディーラジが師と仰ぐヒジュラー(両性具有コミュニティー)議員ニルマル・パンディトが介入して来たため、ディーラジは釈放されてしまう。
ニルマルはディーラジを、彼の自宅近くに建てられたヒジュラー女神の寺院へ連れて行く。そこにはちょうど、井戸から逃げて来たレーシュマーが隠れていた。ディーラジはニルマルと寺院の僧侶を殺し、レーシュマーを惨殺する。
一方、ディーラジはアルジュンに復讐するため、彼の恋人プリヤーを自宅に呼ぶ。だがその前にアルジュンがディーラジの居所を駆けつけて彼の家にやって来た。アルジュンはディーラジを殴り倒すが、プリヤーが突然やって来たことに驚いている隙に不意打ちをくらい、倒れてしまう。ディーラジは意識朦朧とするアルジュンの前でプリヤーを殺そうとする。だが、プリヤーの悲鳴を聞いて意識を取り戻したアルジュンはディーラジに反撃し、最終的に彼を殺す。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
まず、前作「Murder」がヒットしたのは、当時としてはインド映画レベルを超越した濃厚な性描写がいくつもあったからである。ところが「Murder
2」では、序盤にイムラーン・ハーシュミーとジャクリン・フェルナンデスのベッドシーンがあったものの、基本的にはそれほど際どいシーン満載の映画になっていない。また、前作ではイムラーン・ハーシュミー演じる悪役のことを観客に一旦死んだと思わせておいて実は生きていたというどんでん返しを作り、それをベースにスリラーを展開していた。だが、「Murder
2」では連続殺人犯の正体が序盤で明らかになってしまい、得体の知れないものに対する恐怖もなく、前作のようなサスペンスはなかった。よって、スリラーとしての出来は完全に前作の方が上である。
これらの要因から、「Murder 2」が前作ほどのヒットを記録するとは思えない。しかしながら、悪役ディーラジ・パーンデーイのキャラクターは非常に面白かった。元々女性に対して嫌悪感を抱いていたディーラジは、お見合い結婚後に妻を虐待し始め、両親から家を追い出される。その後ディーラジはヒジュラー・コミュニティーに入り込み、男性器を切除する。ヒジュラーとは建前上両性具有者コミュニティーだが、実際にはヒジュラーとなる者の大部分は性転換している。インドをある程度長く旅行したり住んだりすると、街角や列車などで女装した男性の集団を見掛けるだろう。彼ら(彼女ら)がヒジュラーである。しかしディーラジは性同一性障害ではなく、むしろ女装趣味の正常な男性であった。女性に対する性欲はあったが、既に男性器を切除していたために何もすることができなかった。そこで彼は恐怖に怯える女性を殺すことで代替の性的興奮を味わうようになり、コールガールの連続殺人をするようになるのである。ディーラジのこの深層心理は、彼が拘留中に受けた精神鑑定の中で明らかにされていた。このキャラクターをより発展させて行けば、「インド映画界のハンニバル・レクター博士」のような存在になったかもしれず、彼を中心に再び続編が作られるとすれば是非見てみたいと思うが、少なくとも「Murder
2」の最後では彼は殺されてしまっている。また、ディーラジ・パーンデーイを演じたプラシャーント・ナーラーヤナンも見事であった。
ディーラジ・パーンデーイのキャラが立っていたために、主演のはずのイムラーン・ハーシュミーの影は薄かった。そういえば前作「Murder」では主演のアシュミト・パテールよりも悪役のイムラーン・ハーシュミーの方が目立っており、その点では共通点がある。彼が演じるアルジュンは元警官ながらドラッグ密輸などに関わる悪人という設定である。しかし、彼がディーラジの餌食になった少女レーシュマーに特別な肩入れする理由がよく分からなかったし、恋人のプリヤーに冷たく当たる理由や、その後彼女を受け容れることを示唆するシーンの裏にある心変わりも不明だった。彼の家族は不幸で、幼い頃から孤児として育って来たことは分かるが、ディーラジに比べるとバックグランドの説明が足りなかった。おまけにイムラーンの髪型も変だった。
ジャクリン・フェルナンデスはここ数年内にデビューした女優の中では意外に粘っていると言っていいだろう。「Aladin」(2009年)でデビューしたときには一発屋かと思ったが、その後も「Jaane
Kahan Se Aayi Hai」(2010年)やこの「Murder 2」と出演作を重ねており、今後「Houseful 2」への出演も決まっている。現在ヒンディー語映画界で流行の顔立ちではないと思うのだが、スリランカ人というユニークな立場のおかげか、踏ん張っている。何となくネパール人女優マニーシャー・コイララを思い出す。ヒンディー語の勉強にも精を出しているようで、今後もヒンディー語映画界で活躍して行くつもりなのであろう。「Houseful」(2010年)でアイテムガール出演したり、今回イムラーン・ハーシュミーとの濃厚なキスシーンやベッドシーンにも挑戦したりしていることからも分かるように、聖域なき演技ができる女優で、それが功を奏しているのかもしれない。
前作「Murder」はアヌ・マリクによる音楽も大ヒットしたことで記憶に残っている。「Murder 2」の音楽もヒット中だが、特定の音楽監督の手による作曲ではなく、ハルシト・サクセーナー、ミトゥン、サンギート&スィッダールト・ハルディープルと言った作曲家の合作となっている。イムラーン・ハーシュミーのイメージに合った狂おしい恋愛歌が多く、「Hale
Dil」、「Aye Khuda」、「Phir Mohabbat」などいい曲が揃っている。また、タイトル・クレジットに流れるスローテンポのダンスナンバー「Aa
Zara」ではヤーナー・グプターがアイテムガール出演している。
「Murder 2」は、続編物でありながら前作「Murder」とは全く関係ない作品。基本的にはスリラー映画であるが、狡猾な犯人を追及するようなタイプの犯罪映画ではない。その代わり、悪役のキャラのおかげで、ホラー映画に近い怖さのある映画となっている。前作のようなスキン・ショーは期待しない方がいい。前作「Murder」は大ヒットとなったが、続編は平均的な興行成績で落ち着くのではなかろうか。
| ◆ |
7月13日(水) 制作本数の謎解明とカットの話 |
◆ |
インドで上映・放映・販売される映画は全て、公開される前に、中央政府情報放送省下の中央映画検閲委員会(CBFC)による検閲を受け、認証を受けなければならない。毎年CBFCが発表する年次報告書には、その年に検閲をした映画の統計が掲載されている。CBFCによって認証を受けた作品数のデータがそのまま映画制作本数と見なされて使われているため、インド映画の分析をする際は何かと重要な機関である。昨年から詳しいレポートがCBFCのウェブサイトで公開されるようになったため、便利になった。
2009年のCBFC年次報告書については昨年詳しく分析した(参照)。最近2010年の年次報告書が公開されたため、ここで少しだけ触れておきたい。2010年に認可されたインド製長編特作映画の数は1,274本。前年の1,288本から微減している。言語別の制作本数では、ヒンディー語がトップで215本、続いてタミル語が202本、3位がテルグ語で181本となっている。このトップ3の顔ぶれはずっと変わっていないが、順位に変動はある。前年はヒンディー語がトップで235本、2位がテルグ語で218本、3位がタミル語で190本であった。つまり、ヒンディー語のトップの地位は変わらないが、タミル語とテルグ語の順位が入れ替わっている。
言語別インド製長編特作映画認可本数(2009-10年)
| |
言語 |
2009年 |
2010年 |
| 1 |
ヒンディー語 |
235 |
215 |
| 2 |
タミル語 |
190 |
202 |
| 3 |
テルグ語 |
218 |
181 |
| 4 |
カンナダ語 |
177 |
143 |
| 5 |
マラーティー語 |
99 |
116 |
| 6 |
ベンガリー語 |
84 |
110 |
| 7 |
マラヤーラム語 |
94 |
105 |
| 8 |
ボージプリー語 |
64 |
67 |
| 9 |
グジャラーティー語 |
62 |
62 |
| 10 |
オリヤー語 |
17 |
26 |
| 11 |
パンジャービー語 |
15 |
15 |
| 12 |
英語 |
9 |
8 |
| 13 |
その他 |
24 |
24 |
| |
合計 |
1,288 |
1,274 |
今回の年次報告書で気になったのは以下の記述である。P13では、21世紀の最初の10年の締めくくりということもあり、2001年から2010年までの認可本数がまとめてある。
| 2001年 |
1013本 |
| 2002年 |
943本 |
| 2003年 |
877本 |
| 2004年 |
934本 |
| 2005年 |
1041本 |
| 2006年 |
1091本 |
| 2007年 |
1146本 |
| 2008年 |
1325本 |
| 2009年 |
1288本 |
| 2010年 |
1274本 |
その下に以下のような注意書きがある。
ただし、2001年には他の地域言語から吹き替えられた映画が213本ある。また、以降の年の吹き替え映画の数は、2002年に165本、2003年に114本、2004年に93本、2005年に88本、2006年に49本、2007年に190本、2008年に206本、2009年に202本、2010年に117本だった。もし吹き替え映画の数を考慮すると、インド製長編特作映画の実際の制作本数は2001年には800本、2002年には778本、2003年には763本、2004年には841本、2005年には953本、2006年には1,042本、2007年には956本、2008年には1,119本、2009年には1,086本、2010年には1,157本となる。
1年前の記事で、吹き替え映画の数が認可本数に含まれているのではないかという疑問を呈したが、その推測が正しかったことを示している。つまり、一般にインド映画の「制作本数」とされている数字は、実はCBFCの検閲を通過した認可本数であるだけでなく、言語別に映画が作られ、しかもそれらが交互に吹き替えられるインド映画産業の特殊な実態を反映し、吹き替え映画の本数まで含まれていたことになる。もし、より実態に近い「制作本数」を導き出そうとするならば、吹き替え映画の本数を差し引いて考えなければならない。それでもインドの「映画大国」としての地位が揺らぐことはないが、言語別制作本数には変化が出て来る。幸い、2010年の年次報告書にも吹き替え映画の言語別データが掲載されていた(P35)。
言語別インド製長編特作吹替映画本数(2010年)
| 言語 |
本数 |
| テルグ語 |
68 |
| タミル語 |
18 |
| ヒンディー語 |
17 |
| ベンガリー語 |
4 |
| ボージプリー語 |
2 |
| チャッティースガリー語 |
2 |
| 英語 |
2 |
| オリヤー語 |
2 |
| マラヤーラム語 |
2 |
| 合計 |
117 |
これらの数字をそれぞれ差し引くと、2010年における言語別のより正しい「制作本数」とその順位は以下の通りとなる。
言語別インド製長編特作映画認可本数改訂版(2010年)
| |
言語 |
本数 |
| 1 |
ヒンディー語 |
198 |
| 2 |
タミル語 |
184 |
| 3 |
カンナダ語 |
143 |
| 4 |
マラーティー語 |
116 |
| 5 |
テルグ語 |
113 |
| 6 |
ベンガリー語 |
106 |
| 7 |
マラヤーラム語 |
103 |
| 8 |
ボージプリー語 |
65 |
| 9 |
グジャラーティー語 |
62 |
| 10 |
オリヤー語 |
24 |
| 11 |
パンジャービー語 |
15 |
| 12 |
英語 |
6 |
| 13 |
その他 |
22 |
| |
合計 |
1,157 |
ヒンディー語とタミル語の順位に変動はないが、テルグ語が一気に順位を落とし5位に。その代わり、政治上または必要上の理由で吹き替え映画がないカンナダ語とマラーティー語は順位を繰り上げている。カルナータカ州ではカンナダ語吹き替えが禁止されている一方、マハーラーシュトラ州ではヒンディー語もよく理解され、マラーティー語吹き替え映画の需要があまりないためにこのような結果になっているのだと予想される。それ以下の言語については特に変動なしだ。
長年の疑問が晴れて良かったのだが、今日の本題はそのことについてではない。CBFCウェブサイトの検索窓から検索できる映画の検閲情報についてである。少し試してみたが非常に面白い。映画名と言語名を入力してサーチすることで、その映画の劇場公開版、ビデオ版、予告編などの検閲情報を閲覧することができる。そこには、映画名、映画で主に使用される言語名、映画の年齢認証、認可を受けた地域オフィス名、認可番号、認可日、認可されたリール長、プロデューサー名が記録されている他、「カットリスト詳細」、つまり検閲の結果カットされたシーンや台詞などの詳細が掲載されている。
例えば有名なところで行くと「Billu」(2009年)という映画がある。この映画のタイトルは元々「Billu Barber」だったのだが、「barber(床屋)」という単語が差別用語に当たるとして床屋コミュニティーから批判を受け、現行のタイトルに変更されたのだった。映像からも、劇中の台詞や歌詞からも、「barber」という言葉は削除された。さて、CBFCのウェブサイトで検索してみると、データベース上では映画のタイトルは「Billu
Barber」のままになっており、その詳細を見ると、タイトルが「Billu Barber」から「Billu」に変更されたこと、「床屋」を意味する英語「Barber」やヒンディー語「ハッジャーム」が映画の全ての場面から削除されたことなどが記録されている。
ところで、有名なイタリア映画「ニュー・シネマ・パラダイス」(1989年)のラストで、映画技師アルフレードが上映前に自分で検閲しカットしたキスシーンをつなげたフィルムが流されるシーンがある。それは映画史に残るほど非常に感動的なシーンなのだが、CBFCウェブサイトで何がカットされたのかをつぶさに見て行くと、基本的に罵詈雑言のオンパレードで気が滅入って来る。いくつかの映画の検閲状況を比較してみると、罵詈雑言、卑猥な言語、卑猥なシーン、暴力シーン、グロテスクなシーンなど一般に予想可能なものの他、喫煙関連シーン、飲酒関連シーン、動物虐待シーン、カースト関連や宗教関連の言葉など、インド特有のカットも多いことが分かる。また、インドそのものや政府当局、政党、警察、軍隊などに対する批判の言葉もかなりカットされている。
それと同時に、カットを要求された台詞をどのような台詞で置き換えたかも併記されており、それらを見て行くのも面白い。まるで制作者側と検閲側の知恵比べのようだ。例えば「Kaminey」(2009年)の以下の台詞はカットされた:
भारतवर्ष में ज़िन्दगी बड़ी काल्याण है, और लोग महा कमीने।
訳:インドでは人生はとても安寧で、人々は酷い下衆ばかりだ。
おそらくインドとインド人の尊厳を損なうという理由でのカットであろう。カットされたこの台詞は以下の台詞に置き換えられた:
कलियुग में ज़िन्दगी बड़ी काल्याण है और लोग महा कमीने।
訳:カリユグ(末法の世)では人生はとても安寧で、人々は酷い下衆ばかりだ。
これで下衆はカリユグに住む全世界の人々ということになり、インドの汚名は薄められた。このように台詞の置き換えを見て行くとなかなか面白いのだが、残念ながら多くの台詞は中略されているし、どういう場面での台詞かも明記がないため、これらのカットリストを見ただけでは内容を汲み取れない部分も多い。
かなり昔の映画の検閲情報もこのデータベースに入っている。ただ、古すぎるとカットリストは含まれていない。それと関連して、2004年にカラー化されて再公開された名作「Mughal-e-Azam」(1960年)のカットリストは面白い。通常、検閲によってシーンや台詞がカットされるのだが、「Mughal-e-Azam」カラー版では挿入歌が追加されている。追加されたのは以下の4つの歌曲である。
- 「Mohabbat Ki Jhooti Kahani Pe Roye」
- 「Bekas Pe Karam Kijiye」
- 「Humen Kash Tumse Mohabbat Na Hoti」
- 「Ae Ishq Sab Duniyawale」
これは、カラー版制作者側が、上映時間の短縮を狙って、上記の挿入歌をカットしてカラー版を作ろうとしたところ、CBFCの委員の中に熱烈な「Mughal-e-Azam」ファンがいたのであろう、「これとこれはカットしちゃ駄目だろ」と注文を付けて来て、追加せざるを得なくなったという裏話があったりするのであろうか?そんなことを想像してしまった。
このデータベースから分かる情報で非常に重要なのは、劇場公開版(セルロイド)と、DVDやVCDで発売されるビデオ版にかなりの違いがあるということである。データベースにおいて、各映画には大体セルロイドとビデオが別々のエントリーとなっており、それぞれのカットリストを比較することができる。映画は年齢認証があり、鑑賞者の年齢を制限できるために、検閲内容は比較的緩い。だが、ビデオの方は全年齢層が鑑賞する可能性があることを考慮してか、かなり厳しく検閲が行われている。つまり、劇場公開版に比べてビデオ版はカットされるシーンや台詞が必然的に多くなっているのである。
例えば「Love Sex aur Dhokha」(2010年)という非常に物議を醸した映画があった。この映画の年齢認証はA、つまり18歳未満閲覧禁止である。この映画のセルロイド版カットリストを見てみると、以下の4点の指導を受けている。
- 単語「ダリト & SC/STクオータ(不可触民&指定カースト/指定部族枠)」を削除。
- 単語「ナンギー(裸の)」を削除。認可された単語「ガンディー(エロい)」に置き換え。
- 単語「バウド(仏教徒)」を削除。認可された単語「クマール(少年)」に置き換え。
- ラブシーンを50%カット。
だが、ビデオ版カットリストを見ると、おそらくこれらのカットに加えてということだろうが、以下のカットも指導されている。
- 男性が少年を切り刻むシーンの映像をカット。
- 男性が他の少年たちに「キーンチョー(撮れ)・・・」というシーンの映像と台詞をカット。
- 男性が手で掴んだ少女の頭を切るシーンの映像をカット。
- アーダルシュが性交しているシーンの映像をカット。
- 少年と少女が性交をしているシーンの映像と台詞「ナヒーン・アーカーシュ(だめ、アーカーシュ)・・・」をカット。
- 性交シーンの映像をカット。
- 以下の単語「ベヘンチョード(姉妹を犯す奴)」×5回、「ベヘン・ケ・ラウンレー(姉妹を犯す奴)」×2回、「ジャーント(陰毛)」、「Sex」、「Sucking
Fucking」、「Fucking fucking sex」、「ラーンル(売春婦)」、「アーオー・セックス・カレーン(さあ、セックスしよう)」、「Fucking」、「ナンギー(裸の)」を消音。卑猥語のオンパレードのため自粛。知りたい人は空白部分を範囲選択。
つまり、DVDなどで販売されている映画の内容は、劇場で公開されたものと必ずしも完全に一致しないということが分かる。特に際どいシーンや台詞が多い映画になるとカットが多くなり、オリジナルからかなり離れてしまう。どうやら映画館でインド映画を見るメリットはこの点にもあり、DVDなどで映画を鑑賞しただけではその映画の本来の姿を見られない可能性があることになる(もっとも、劇場公開版にしても検閲のハサミのせいで監督の意図する形ではないことも多いのだが)。やはり、映画館で映画を見なければ、その映画の正当な評価はできないだろう。
以上、CBFCウェブサイトのデータベースを少しいじってみて分かったことをまとめてみた。当然、膨大な量の映画検閲情報が入っており、それらをいちいち確認した訳ではないので、さらに調べることで、もっと面白い事実が浮かび上がって来たり、より適切な事例が見つかったりすることもあるかもしれない。また、検索の性能はあまり良くなくて、データベースに登録されている通りの映画名を入力しなければならないので、目当ての映画になかなか辿り着けないこともある。登録名が、世間一般で知られている映画名の綴りではないことも多々ある。この辺りは改善が必要であろう。しかし、このデータベースの存在のおかげで、CBFCウェブサイトは、インド映画の情報源としてさらに価値を増した。インドの政府機関系ウェブサイトは突然閉鎖されたりするケースがよくあるのだが、願わくは今の路線で維持・発展させて行ってもらいたいものである。
| ◆ |
7月18日(月) Zindagi Na Milegi Dobara |
◆ |
ヒンディー語映画界には数々の映画ファミリーが存在するが、最近非常に存在感を強めつつある家系のひとつがアクタル・ファミリーである。詩人ジャーン・ニサール・アクタル、詩人カイフィー・アーズミー、女優シャウカト・アーズミー、女優シャバーナー・アーズミー、脚本家・作詞家ジャーヴェード・アクタル、脚本家ハニー・イーラーニーなどが連なる家系であり、現在最前線で活躍しているのが、ジャーヴェード・アクタルと前妻ハニー・イーラーニーの間に生まれた双子の兄妹ファルハーン・アクタルとゾーヤー・アクタルである。ファルハーンは「Dil
Chahta Hai」(2001年)や「Don」(2006年)で有名な映画監督で、「Rock On!!」(2008年)では俳優デビューし、映画界において二足の草鞋を履いた活躍をしている。一方、ゾーヤーは2009年に「Luck
By Chance」で映画監督デビューをした。この双子の兄妹が関わる映画では父親ジャーヴェード・アクタルも積極的に協力しており、親子の強い絆が表れている。ただし、2人は継母にあたるシャバーナー・アーズミーとは距離を置いているように見える。
ゾーヤーの監督デビュー作「Luck By Chance」は残念ながら興行的に失敗に終わったのだが、めげずに2作目をリリースして来た。題名は「Zindagi
Na Milegi Dobara(人生は一度だけ)」。「Rock On!!」テーマソングの歌詞中にあったフレーズだ。やはり今回もアクタル父子の強い絆の結晶となっており、ファルハーンがプロデューサーと主演を務め、ジャーヴェード・アクタルが挿入歌の作詞や劇中に登場するウルドゥー語詩を書いている。ほぼ全編スペイン・ロケというのもヒンディー語映画としては珍しいし、リティク・ローシャンやカトリーナ・カイフと言ったAクラスの俳優が出演していることも目を引く。文句なく今年話題の作品の1本だ。ファルハーンの「Dil
Chahta Hai」が2000年代の方向性を決めたように、ゾーヤーの「Zindagi Na Milegi Dobara」が2010年代のトレンドセッターとなるのだろうか?
題名:Zindagi Na Milegi Dobara
読み:ズィンダギー・ナ・ミレーギー・ドーバーラー
意味:人生は二度得られない
邦題:人生は一度だけ
監督:ゾーヤー・アクタル
制作:リテーシュ・スィドワーニー、ファルハーン・アクタル
音楽:シャンカル・エヘサーン・ロイ
歌詞:ジャーヴェード・アクタル
出演:リティク・ローシャン、アバイ・デーオール、ファルハーン・アクタル、カトリーナ・カイフ、カールキー・ケクラン、ナスィールッディーン・シャー(特別出演)
備考:PVRプリヤーで鑑賞、ほぼ満席。
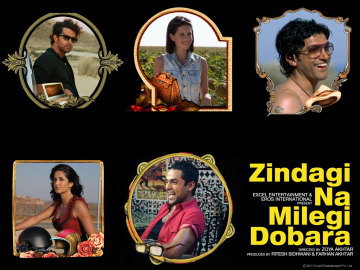
上段左からリティク・ローシャン、カールキー・ケクラン、ファルハーン・アクタル、
下段左から、カトリーナ・カイフ、アバイ・デーオール
| あらすじ |
ムンバイーを拠点に父親の建設会社で働くカビール(アバイ・デーオール)は、ホテル王の娘でインテリア・デザイナーのナターシャ(カールキー・ケクラン)と結婚することになった。結婚式を2ヶ月前に控え、カビールは「バチャラーズ・パーティー」として学生時代の仲良し3人組でスペインを3週間旅することになった。これは「三銃士」と言われていた3人の間での学生時代からの約束だったのだ。
「三銃士」の1人、イムラーン(ファルハーン・アクタル)はプレイボーイかつ大のお調子者で、デリーでコピーライターをして生活していた。それとは別に日記を持ち歩き、密かに詩を書き綴っていた。イムラーンはスペイン行きを聞いたときに偶然に驚く。ちょうど1年前、母親から自分の出生の秘密を聞いたばかりだったからだ。亡き父親は実の父親ではなく、実の父親はスペインで画家をして暮らしているとのことだった。複雑な思いを胸に抱えつつイムラーンはスペイン行きを歓迎する。
一方、「三銃士」のもう1人アルジュン(リティク・ローシャン)は証券トレーダーとしてロンドンで忙しい毎日を送っていた。貧しい育ちだったために金に対する執着が強く、大金を稼いで40歳に引退する人生計画を思い描いていた。彼の異常なまでの上昇志向と金銭欲は、恋人との破局をもたらしたばかりだった。アルジュンにはスペイン旅行に行く時間などなかったが、約束は約束と言うことで、しぶしぶ承知する。だが、ちゃっかり仕事道具は持って来ていた。
また、ナターシャはバチャラーズ・パーティーでカビールが羽目を外しすぎることを警戒していた。それでも彼をスペインに送り出す。ただし、ビデオチャットで毎日交信することになっていた。
バルセロナで久しぶりに再会した3人は、まずはレンタカーに乗って海岸の町コスタ・ブラバを目指す。道中ではイムラーンとアルジュンの不仲が再燃する。実は4年前にイムラーンがアルジュンのフィアンセに手を出したことがあり、それが原因で2人の仲はあまり良くなかった。その場は何とかカビールが収める。
コスタ・ブラバではカビールの提案に従ってスキューバ・ダイビングをすることになった。アルジュンは泳げないために乗り気ではなかったのだが、ダイビング・インストラクターが魅力的な美人だったために彼も挑戦することにする。インストラクターの名前はライラー(カトリーナ・カイフ)。英国人とインド人のハーフで、ロンドンでファッション学校に通っており、休暇にスペインでダイビング・インストラクターのバイトをしていた。スキューバ・ダイビングによって海底の美しい世界を知ったアルジュンはすっかり世界観が変わってしまう。普段の騒音に満ちた生活から、自分の息しか聞こえない沈黙の世界。そしてアルジュンはライラーに恋をしてしまう。
次に3人が向かったのはブニョール。元々ライラーが行こうとしていたところで、そこではちょうど有名なトマト祭り「トマトティーナ」が行われていた。3人もライラーやその友人ヌリアと共にトマト祭りに参加することになる。ところが、はしゃぎ回ってホテルに帰り着いたカビールらを待っていたのがナターシャであった。ちょうど仕事でロンドンに来ており、1泊の予定でスペインまで来ていたのだった。ナターシャはカビールがライラーといちゃついているのを見てショックを受ける。ナターシャは平静を装って皆の輪に加わったが、彼女が加わったことで場の雰囲気が一変してしまう。ナターシャは一応ライラーへの疑いを解き、翌日ロンドンに帰って行ったが、イムラーンとアルジュンは実はカビールとナターシャはあまりいい夫婦にはならないのではないかと考えるようになる。
ライラーと別れ、次に向かったのはスカイ・ダイビング学校。これはアルジュンの希望だった。一番怖がっていたのはイムラーンであった。訓練を受けた後、3人はスカイ・ダイビングをする。そしてその夜バーで酔っ払って喧嘩沙汰を起こしてしまい、警察に逮捕されてしまう。身請け引受人がいなければ拘置所から出られず、裁判所まで行かなければならなくなる。ライラーに助けを求めたが、彼女の電話はスイッチオフだった。万事休すかと思われたとき、突然イムラーンが1人の画家の名を出す。サルマーン・ハビーブ(ナスィールッディーン・シャー)。スペイン旅行中、イムラーンはサルマーンの個展に足を運んだが、実は彼こそがイムラーンの実の父親だった。サルマーンに電話をすると、彼は警察署まで来て身元引受人になってくれる。3人はその後サルマーンの家に招かれる。そこでイムラーンはなぜ母親を捨てたのか、サルマーンに聞く。サルマーンは、画家になる夢を諦められず、妊娠してしまった彼女を置いて去って行ったのだと正直に答える。
実の父親との出会いはイムラーンにとってショックな出来事だったが、同時に気持ちに整理を付けることができた。その気持ちのまま彼はアルジュンに過去のことを謝る。アルジュンもそれを受け容れる。
最後に3人はパンプローナを訪れる。ここでは再び3人はライラーと合流する。イムラーンとアルジュンはやっと勇気を出してカビールに、ナターシャとの結婚は良くないのではないかとはっきり伝える。カビールは最初怒るが、後に本当の経緯を話す。実はカビールとナターシャの結婚はアクシデントの産物だった。カビールは母親の誕生日にプレゼントとして指輪を買ったのだが、母親に渡す前にナターシャに見せた。ナターシャはそれをプロポーズだと勘違いし、とんとん拍子に縁談がまとまってしまったのだった。
パンプローナではイムラーンの提案に従い、有名な牛追い祭り「サン・フェルミン祭」に参加することになる。突進する猛牛に追われる危険な祭りである。3人は、もし生き残ることができたらすることを1人1人決める。イムラーンは秘密日記の詩を公開すること、アルジュンは仕事を放り出してライラーとモロッコへ行くことを決めた。最後にカビールは、ロンドンへ行って結婚キャンセルをナターシャに伝えることを決める。牛に追われ必死に走る3人・・・。それは人生の本当の喜びへのダッシュであった。そこで映画は終幕となる。
後日談として、アルジュンとライラーの結婚式のシーンが登場する。結婚式にはナターシャも参列していたが、カビールの妻としてではなかった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
スターパワーがあり、完成度が高く、面白い映画であるだけでなく、現代インド映画史上多くの意義を持つ非常に重要な映画。そのひとつひとつを読み解いて行こうと思う。1人1人のキャラクターにメッセージが隠されていると言っていい。
ひとつは結婚の成就ではなく婚約の破棄ですがすがしく映画を終わらせている点。カビールとナターシャの関係がそれであり、そもそもスペイン旅行のきっかけとなったのも2人の縁談であった。その破棄がエンディングで、明示されてはいないものの、十分暗示される。インドのロマンス映画の伝統は、当然のことながら男女の出会いから結婚式までを追うものであり、目当ての相手と結婚するために、親などから強要された別の相手との結婚を破棄するというプロットを除けば、恋人との婚約の破棄がエンディングに来ることは今までほとんどなかったのではないかと思う。それもアンハッピー・エンディングではなくハッピー・エンディングとして。それに最も近いのが「ブレイクアップ・パーティー」を広めた「Love
Aaj Kal」(2009年)であるが、この映画にしてもブレイクアップした元恋人とよりを戻すシーンをエンディングにしていた。少なくともインド映画の文脈では非常にラディカルなプロットだったと言える。
女性が監督なのにも関わらず、結婚を前にした男性の心情はかなりよく描かれている。そもそもプロポーズも勘違いから起こった偶発的な出来事であり、実際はカビールは恋人ナターシャとの結婚を急いでいなかった。また、結婚を決めた後にナターシャが徐々に彼の人生を支配するようになって行き、カビールはそれに窮屈さを覚えていた。しかし両家の仲は元々良好で、結婚式の準備はどんどん進んで行ってしまう。そんな中でのスペイン旅行であった。カビールは心のどこかでこの結婚を止められたらと考えていた。だが、頭ではそんなことは無理だと思っていた。そしてもしそれが可能ならば、それは親友イムラーンとアルジュンのみだと期待していた。彼にとっては出口の見えない逃避行であり、ナターシャが無理矢理バチャラーズ・パーティー旅行に割り込んで来たことで、さらにカビールは不安を現実として考えるようになる。イムラーンとアルジュンもカビールの問題に敏感に気付き、親友として彼の最も幸せになれる道、つまり婚約の破棄を後押しする。カビールがやっとナターシャとの婚約破棄を自ら打ち出したのはクライマックスの牛追い祭りであった。敢えてインド映画の黄金律を打ち破り、しかも後味の悪くない映画にまとめたことで、「Zindagi
Na Milegi Dobara」はひとつの金字塔を打ち立てたと言える。
ふたつめは父親に対する価値観の転換である。元々インド映画では父親の存在は絶対で、父権が侵されることは稀である。しかし、「Zindagi Na
Milegi Dobara」では、父親の存在感が全くないばかりか、イムラーンの家族関係によって、父親は比較的ネガティヴな存在として描かれていた。イムラーンはつい最近、自分が父親と考えていた人物が実の父親ではなく、実の父親はスペインに住んでいることを知る。母親が実の父親のことを隠していたことで、イムラーンは母親に対する疑念すら抱くようになっていた。母親は再三デリー在住のイムラーンにムンバイーに来て同居するように促すが、イムラーンはそれを拒否する。今回偶然スペインに行くことになり、当然イムラーンは実の父親との再会を考える。なかなか踏ん切りが付かず、それは逮捕という非常事態の中でやっと実現する。しかし、実の父親サルマーン・ハビーブは、イムラーンが思い描いていたような人物ではなかった。育ての父親の方が、もう亡くなってしまったが、よっぽど父親らしい人物であった。サルマーンははっきりと、母親とのことは「若気の至り」だと言い、夢を追うため、母親になることを願った彼女を置いて逃げて来たと正直に話す。父親の言葉を受け止め、じっくり考えた後、イムラーンは母親にサルマーンと会ったことを伝え、同時に母親に「愛してるよ」と言う。そこには父親の威厳は全く感じられない。ちなみに、このような父権の否定は「Udaan」(2010年)や「Patiala
House」(2011年)にも見られた傾向である。また、自分勝手な行動が他人の心にどれだけ深い傷を残すのか実感したイムラーンは、初めて心からアルジュンに謝る。かつてイムラーンはアルジュンのフィアンセを横取りしたことがあったのだ。アルジュンはそのことをずっと根に持っていたが、イムラーンの気持ちを理解し、快く彼の謝意を受け容れる。
みっつめは仕事を優先する生き方へのアンチテーゼである。これは特に新しいテーマではなく、前述の「Love Aaj Kal」でも見られたものだが、ここ最近のヒンディー語映画では、急速に経済成長し変容しつつあるインドへの反動としての不安と疑問からか、仕事や金儲けを優先して生きる生き方を批判する内容の映画が増えて来た。「Zindagi
Milegi Na Dobara」はその流れに乗った映画だと言える。そして劇中でその要素を体現していたのはアルジュンだ。アルジュンは桁違いの給料が得られることで知られる証券トレーダー。毎日仕事漬けの生活をしているが、40歳までこのハードな生活を続け、その後は引退し、それまでに貯め込んだ貯金で悠々自適の生活をするという人生設計を思い描いていた。仕事に優先するものはなく、恋人ですら例外ではなかった。つまり彼にとって幸せは来るか分からない未来にあり、今日にはなかった。「三銃士」の中でも当初は人間的に最も劣った人間として描写されていた。最もスペイン旅行を渋っていたのもアルジュンだったが、この旅行は多くの意味で彼の人生を変えるものとなった。初めてトライしたスキューバ・ダイビングで、海中の中で自分と向き合う時間を見つけ、今までの自分の忙しい人生に初めて疑問を持つ。そしてスペインで出会った魅力的な女性ライラーから、「40歳まで生きられるって誰が保証したの?」と聞かれ、ハッとする。3人の中でこのスペイン旅行から最も多くのものを得たのがアルジュンであり、彼の人間的成長と人間性の開放がこの映画の主軸になっていた。
また、日本人として興味深いことに、劇中にはリティク・ローシャン演じるアルジュンが日本語を話すシーンがある。おそらくアルジュンのワーカホリックな性格とマッチするようにわざとワーカホリックなイメージのある日本人を出して来たのだろう、スペイン旅行中にも携帯電話回線によるネットを使って日本人クライアント「山本さん」とビデオチャットをして商談をしていた。そのときアルジュンは「もしもし」「こんにちは」「ありがとうございます」など、簡単な日本語を話す。イムラーンがアルジュンを「もしもし」とからかうシーンもあったりして、スペインを舞台にした映画でありながら、奇妙な形で日本が表れるのは日本人としては面白くもあり複雑な気分でもある。
また、「Zindagi Na Milegi Dobara」はロードムービーに位置づけられる。「Dil Chahta Hai」ではムンバイーからゴアへ車で行くシーンがあったが、本作ではスペイン各地をレンタカーで巡る。最初は3人のギクシャクした雰囲気を象徴してか窮屈なバンを借りるが、3人が打ち解け、旅行を本格的に楽しむようになると、オープンカーに乗り換え、一気に解放感と開放感が出て来る。また、カトリーナ・カイフ演じるライラーがロイヤル・エンフィールドのバイクに乗って疾走するシーンもある。キスをするためにバイクに乗ってアルジュンらを追いかけるという情熱的なシーンである。
スペインには行ったことがなく、スペインの地理にも詳しくないため、一体どこからどうやってどこまで移動しているのかチンプンカンプンであったが、Facebook公式ファンページによると、バルセロナ、パンプローナ、ブニョール、アンダルシアなどでロケが行われたようである。簡単に地図を表示してもらえると分かりやすかった。しかしスペインの街並みや自然の風景もインドに負けないくらい美しかった。イスラーム教の文化的影響が風景にもいくつか見られ、その点でインドと共通点もあった。ちなみにロケ地にエジプトも入っているが、それがどのシーンだか不明である。
あらすじを読んでもらえば分かるように、トマト祭り、牛追い祭り、フラメンコなど、スペインの見所がストーリーにうまく組み込まれており、まるでスペインの観光促進映画のようであった。実際、スペイン政府観光局の全面的な後押しを受けている。また、スキューバ・ダイビングやスカイ・ダイビングのシーンもあり、水中や空中でのシーンは本当に美しかった。
普通、個人的には海外で大部分のロケが行われ、劇中でも海外が舞台となっている映画に対しては、「インド性」の欠如から評価が低めとなるのだが、「Zindagi
Na Milegi Dobara」におけるスペインは全く違和感がなく、すんなりと受け容れられた。これも映画の完成度の高さを示しているだろう。
そして何より「Zindagi Na Milegi Dobara」は友情の物語である。これはインド映画の不変のテーマでもある。そこには、時にふざけ合い、時に仲違いし、時に本音をぶつけ合い、時に力を合わせる絶対の親友の姿があった。そういう開けっぴろげの友情はインド人が特に好むもので、意外に悲しい要素が散りばめられたストーリーの中で、全体の雰囲気を暗くさせ過ぎずにうまく娯楽映画としてまとめられたのは、3人の固い友情があったからだと言える。
今回最も演技や存在感において光っていたのはリティク・ローシャンである。近年はソロ・ヒーロー型映画において超人的役柄――「Koi... Mil
Gaya」(2003年)のローヒト、「Krrish」(2006年)のクリシュ、「Dhoom 2」(2006年)のアーリヤン、「Jhodhaa
Akbar」(2008年)のアクバルなど――を演じることが多く、最近の「Guzaarish」(2010年)でも人間離れした雰囲気を醸し出していたが、「Zindagi
Na Milegi Dobara」では久しぶりにマルチスター型映画の中で他の主演者と溶け込み、等身大のリティクを見られたような気がする。彼のダンスも相変わらず突出している。
また、ヒロインのカトリーナ・カイフも素晴らしかった。元々はそのキュートさと美しさが同居した美貌と、元恋人サルマーン・カーンの後ろ盾を武器に台頭して来たが、女優として徐々に成長を見せており、近年ではかなり安定した演技を見せるようになって来ている。今回カトリーナはスキューバ・ダイビングをしたり、バイクに乗ったりと、ヒロイン女優としては型破りな冒険をしており、より箔が付いた印象だ。リティクとのキス・シーンも堂々とこなしている。ポジション的にはかつてのアイシュワリヤー・ラーイを彷彿とさせるし、アイシュワリヤーよりも気取ったところがないので、もしかしたら彼女を越える存在になれるかもしれない。今後のより一層の成長を期待したい。
「三銃士」の他の2人、アバイ・デーオールとファルハーン・アクタルも良かった。アバイの存在は多少イレギュラーに感じたが、元々演技力のある男優であるし、ハンデは感じなかった。ファルハーンは相変わらずダミ声で何を言っているのか分からないこともあるのだが、演技は問題ない。父ジャーヴェード・アクタルが書いた詩を彼が読むシーンが何度もあるのだが、詩の朗読はお世辞にもうまいとは言えない。もっとも、ジャーヴェード自身も朗読がうまいという訳ではないが。詩人が必ずしも詩の朗読に秀でている訳ではない。
「Dev. D」(2009年)で一躍有名となったインド生まれのフランス人カールキー・ケクランはすっかりヒンディー語映画界に定着したが、彼女が劇中で演じる役柄はいつも混乱してしまう。見た目は完全にフランス人なのだが、なぜかインド人役を演じさせられることが多く、今回演じたナターシャもおそらくインド人という設定であった。いくら多様性の国インドであっても少し無理があると思うし、せっかくヒンディー語ができる白人女性がいるのだから、彼女に適した役を宛がってあげればいいと思うのだが、インド人観客はあまり気にしないのであろうか。
音楽はシャンカル・エヘサーン・ロイ。思い起こせばこのトリオがブレイクしたのもファルハーン・アクタル監督の「Dil Chahta Hai」である。当時としては衝撃的な程に斬新な音楽であり、ARレヘマーンと共に21世紀のインド映画音楽を定義して来た。あれから10年になるが、この間すっかりシャンカル・エヘサーン・ロイの名前はヒンディー語映画界のトップ・ミュージシャンとして定着したにも関わらず、その音楽性に古さは感じない。また、彼らの音楽には作家性があり、聞いただけで何となくシャンカル・エヘサーン・ロイだと直感することが多い。「Zindagi
Na Milegi Dobara」のサントラCDも名曲揃いだ。今回はスペインが舞台ということで、スペイン語歌詞とヒンディー語歌詞を融合させたスパニッシュ風「Senorita」やボサノヴァ風「Khaboon
Ke Parinde」がユニークだ。他にも若者をターゲットにした曲が多く、「Dil Dhadakne Do」、「Ik Junoon」、「Sooraj
Ki Baahon Maein」など軽快だ。ただ、最近のヒンディー語映画の流行に則って、BGMとして歌曲が使用されることが多く、ダンスシーンは意外に少ない。
台詞はヒンディー語と英語の自然なミックスである。スペインが舞台ということでスペイン語の台詞も少しだけ登場する。いくつかのシーンではスペイン語の台詞に英語字幕が入る。スペイン語⇔ヒンディー語双方向の言葉の通じなさをネタにしたシーンもいくつかあった。
「Zindagi Na Milegi Dobara」は今年最高の映画のひとつ。「Dil Chahta Hai」などから始まった2000年代の終わりを告げ、その次の10年を予感させる新感覚青春友情映画。スペインと言う今までヒンディー語映画界においてほとんど未開拓の国を舞台にし、リティク・ローシャンやカトリーナ・カイフといったトップクラスのスターたちも出演し、スキューバ・ダイビングやスカイ・ダイビングと言ったエキサイティングなスポーツや、トマト祭りや牛追い祭りと言った異国情緒たっぷりの祭りも登場し、さらに脚本もまとまっていて娯楽映画として完成度が高い。それに加えて婚約の破棄をもって映画をハッピーに終わらせるインド映画ではあまり類を見ないラディカルなプロット。ただただ必見である。
ヒンディー語映画界でサルマーン・カーンを中心に始まった南インド映画リメイクブーム。一時期低迷していたサルマーン・カーンは、「Wanted」(2009年)、「Dabangg」(2010年)、「Ready」(2011年)と、南インド映画リメイクまたは南インド映画テイストの映画を立て続けに大ヒットさせ、一気にトップスターの座に返り咲いた。特にアクション映画が人気のリメイク・ジャンルとなっている。もちろんインドの各映画界は昔から相互に影響を与え合って来ており、南インド映画のリメイクは今に始まったことではない。アクション映画に限っても、また21世紀の映画に限っても、アーミル・カーン主演の「Ghajini」(2008年)をはじめとして南インド映画に原案を持つヒンディー語アクション映画は多い。しかし、このブームを軌道に乗せた功労者はサルマーン・カーン以外にはおらず、このブームから最大限の利益を享受したのもサルマーン・カーン以外にはいない。特に、リメイク映画ではないとは言え、しばらくの間はサルマーン主演の大ヒット作「Dabangg」が同種の映画の比較対象となって行くであろう。
本日より公開のローヒト・シェッティー監督の最新作「Singham」も、当初から「Dabangg」との比較を免れなかった。ローヒト・シェッティーと言えば「Golmaal」シリーズで有名な、ど派手なアクションとコテコテのコメディーを得意とする監督である。そのシェッティー監督がタミル語映画「Singam」(2010年)をリメイクしたのがこの「Singham」になる。主演はアジャイ・デーヴガン。警察官が主人公のアクション映画であること、南インド映画テイストであること、土臭い雰囲気であることなど、確かに両作品には共通点が多い。しかし、サルマーン・カーンが進んで弁護したように、全く別の映画である。
題名:Singham
読み:スィンガム
意味:獅子
邦題:スィンガム
監督:ローヒト・シェッティー
制作:リライアンス・エンターテイメント
音楽:アジャイ・アトゥル
歌詞:スワーナンド・キルキレー
出演:アジャイ・デーヴガン、カージャル・アガルワール、プラカーシュ・ラージ、アショーク・サラフ、サチン・ケーデーカル、ソーナーリー・クルカルニー、サナー・アミーン・シェーク、ヘームー・アディカーリー
備考:PVRプリヤーで鑑賞。
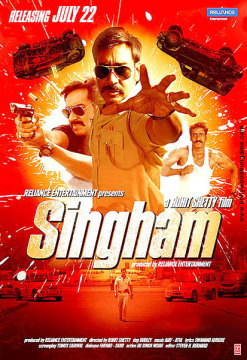
アジャイ・デーヴガン
| あらすじ |
マハーラーシュトラ州とゴア州の州境にあるシヴガル村で生まれ育ったバージーラーオ・スィンガム(アジャイ・デーヴガン)は、地元で警察官をしていた。常に正義を貫き、村の平和のために尽くすスィンガムを村人たちは慕っていた。スィンガムは、パナジから久し振りに村を訪ねて来た幼馴染みのカーヴィヤ(カージャル・アガルワール)と恋に落ちる。
一方、ジャイカーント・シクレー(プラカーシュ・ラージ)は、表向きはホテル経営者や建築業者だが、実態は州内のありとあらゆる違法行為を牛耳るマフィアのドンであった。ジャイカーントは州政府や警察にも影響力を持っていた。ジャイカーントの不正を暴こうとした正義感溢れる警察官ラーケーシュ・カダムは、ジャイカーントによる策略によって汚職の濡れ衣を着せられ、絶望のあまり自殺してしまっていた。その未亡人メーガー(ソーナーリー・クルカルニー)は亡き夫の無実を晴らすために警視総監や州首相にも掛け合ったが、皆ジャイカーントの手に落ちており、何も進展がなかった。
ジャイカーントは数々の訴訟を抱えていたが、誰も彼の有罪を実証できなかった。しかし今回、ジャイカーントは保釈を得た代わりにシヴガル村の警察署に14日間出頭しなければならなかった。当初ジャイカーントは別の人間に出頭させようとするが、スィンガムはそれを許さなかった。怒ったジャイカーントは手下を引き連れてシヴガル村へ乗り込む。だが、スィンガムも全く怯まず、ジャイカーントに屈辱を負わせる。
怒り心頭に発したジャイカーントはスィンガムへの復讐を練る。まずジャイカーントはスィンガムをパナジの警察署へ異動させる。そして自分のテリトリーにスィンガムを置いた後、彼に様々な嫌がらせをするようになる。また、警察から州政府まで皆ジャイカーントを恐れており、汚職も最悪の状態まで進んでいるのを目の当たりにして失望する。とうとうスィンガムは村へ帰ろうとするが、カーヴィヤから止められ、反撃に出ることを決める。スィンガムの勇気を見て、やる気を失っていた部下たちも奮い立つ。また、スィンガムはメーガーからカダムの身に何が起こったかを聞き、彼女のためにもジャイカーントへの復讐の思いを新たにする。
その頃、ジャイカーントは州議会選挙に出馬していた。同時に、スィンガムへの嫌がらせの一環としてカーヴィヤの妹アンジャリを誘拐するが、それが命取りとなり、身代金受取人から辿って行って、遂にジャイカーントの尻尾を掴む。しかしジャイカーントは州議会選挙で勝利し、大臣となることが決まる。早速ジャイカーントはスィンガムを異動させ、街から追い払うことを決める。スィンガムは24時間以内に異動しなければならなくなる。
しばらく絶望に打ちひしがれていたスィンガムだったが、残された時間でジャイカーントに一矢報いようと、まずは警視総監のところへ行って、誰もがジャイカーントを犯罪者だと知っていながら手出ししない警察の弱腰を糾弾する。そして単身ジャイカーントの家へ乗り込むことを告げる。スィンガムの勇気を見て改心した警視総監やその他の警察官はスィンガムに加わり、共にジャイカーントの家へ向かう。
翌日に大臣就任宣誓を控えたジャイカーントは夢見心地でベッドに横になっていた。そこへ警視総監以下多数の警察官がなだれ込む。最初はスィンガムから身を守るための護衛だとジャイカーントは考えるが、皆が彼を殺しに来たことを知り、必死に命乞いを始める。しかし当然のことながらそれは聞き入れられず、ジャイカーントは殺される。警察はそれを、汚職が発覚したことによる恥辱から自殺したことにした。また、カダムの自殺に関しても、ジャイカーントの右腕から証言が得られ、カダムの無実が明らかとなる。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
観る者の正義感を奮い立たせる入魂の作品。ローヒト・シェッティー監督のトレードマークであるど派手なアクションはよりグレードアップした一方、「Golmaal」シリーズよりも社会的メッセージをより色濃くして、娯楽映画の基本路線は守りながらも、正義の勝利を高らかに歌い上げる爽快な勧善懲悪映画となっていた。タミル語原作の影響か、序盤を中心に古風な部分、わざとらしい部分、こじつけがましい部分が散見されたが、一旦映画が軌道に乗るとそれほど気にならなくなる。アクション中心の展開の中に笑いを散りばめることも忘れていない。特に悪役のジャイカーント・シクレーが「恐怖」と「嫌悪」に加えて「喜笑」のラスを担っており、主人公スィンガム以上に魅力的なキャラクターとなっていた。
「Singham」が「Dabangg」と大きく違うのは主人公の性格である。どちらも正義感の強い警察官ではあるが、「Dabangg」の主人公チュルブル・パーンデーイが程よく汚職に染まった融通の利く性格であるのに対し、「Singham」の主人公バージーラーオ・スィンガムは一寸の悪も許さない偏屈なまでの正義漢である。インド神話で喩えるならば、チュルブルはクリシュナ、スィンガムはラームと言ったところか。その方法論も全く正反対である。チュルブルは汚職に染まったシステムをうまく利用して正義を遂行するのに対し、スィンガムはシステムそのものを独力で塗り替え悪を根絶やしにしようとする。当然結末の意味合いも異なって来る。チュルブルはほぼ独力で悪役を倒すが、スィンガムは汚職と怠惰に染まっていた警察システムを一喝によって刷新し、システム全体で悪役を倒した。
しかしながら、ここまで絶対的正義を貫いておきながら、最後に宿敵ジャイカーントを私刑のような形で抹殺してしまったのは脚本の破綻に感じた。いくらジャイカーントが大臣に就任して強大な権力を手にする直前だったとは言え、法の裁きに任せる終わらせ方の方がそれまでの流れから見たらより納得が行った。また、今までジャイカーントと癒着していた警察官たちを罰しなくていいのだろうか?最後の最後にスィンガムの側に付いたことで免罪符であろうか?そういう疑問も感じた。
また、悪役ジャイカーント・シクレーのキャラクターは非常に立っていたが、残酷さが徹底されていなかったように感じる。スィンガムの身内に危害を加えたりすることは一度もなく、意外にスィンガムに対しては大した嫌がらせをしていない。もっとも疑問だったのは、なぜヒロインのカーヴィヤを誘拐しなかったのかということである。このようなプロットの映画ならば、悪役は絶対にヒロインを誘拐してヒーローを挑発するのだが、「Singham」は、故意か偶然か、ヒロインの妹が誘拐されることになった。誘拐されないヒロイン。それは何だか怠け者に聞こえないか?実際、ヒロインの出番は大したことがなく、彼女の存在や言動がストーリー展開に与える影響も限定的である。
「Dabangg」はウッタル・プラデーシュ州の架空の田舎町を舞台にしていたが、「Singham」はゴア州とマハーラーシュトラ州が舞台になっていた。主人公も悪役もマラーターという設定で、台詞の中にもマラーティー語が多用されていた。さらに、マラーター主義がかなり前面に押し出されていたように感じた。「Dabangg」にはそういうローカリズムみたいな側面はなかったため、特異に感じた。これはタミル語原作の影響なのであろうか。
主演のアジャイ・デーヴガンは、サルマーン・カーンに負けないほど堂々と無敵のヒーローを演じていた。肉体作りもバッチリで、街頭を引っこ抜き、悪漢を次から次へとなぎ倒すのにふさわしい外観を獲得していた。昨年から好調が続いており、この「Singham」でさらに安定を増すであろう。
アジャイ・デーヴガン以上にインパクトが強いのは悪役ジャイカーント・シクレーを演じたプラカーシュ・ラージだ。南インド映画界のベテラン俳優であるプラカーシュは、最近ヒンディー語映画にも登場するようになり、「Bbuddha
Hoga Terra Baap」(2011年)でも絶妙な悪役振りを発揮したばかりであった。今のところ芸風が似たり寄ったりなきらいもあるが、もっと幅広い演技のできる俳優であろう。今後ヒンディー語映画でも活躍の場が開けて行くのではないかと思う。
ヒロインのカージャル・アガルワールは、ヒンディー語映画「Kyun...! Ho Gaya Na」(2004年)でデビューしたらしいが記憶にない。その後南インド映画界で活躍して来ており、この「Singham」がヒンディー語映画界カムバック作となる。さすがに場数を積んで来ているだけあって演技はこなれているが、ヒンディー語映画界で活躍する同世代の女優たちと比べるとオーラが足りないかもしれない。「Singham」は単なるきっかけで、最低でも1本はヒット作が続かないと、南インド映画界に逆戻りということもあるだろう。
音楽はアジャイ・アトゥルというコンビ。テーマソング「Singham」は壮大な曲で映画のスケールの大きさを予感させる。だが、音楽は全体的に弱く、「Dabangg」の音楽のようなパンチ力はない。
言語は基本的にヒンディー語であるが、マラーティー語の台詞も多く、実際にはヒンディー語・マラーティー語ミックスと言えるだろう。スィンガムの決め台詞「Jismein
Hai Dum To Fakt Bajirao Singham(度胸があるのはバージーラーオ・スィンガムのみ)」という台詞も、基本的にはヒンディー語であるが、「Fakt(単に)」というマラーティー語の単語が入っている。珍しいところではカルナータカ州マンガロール近辺で話されるドラーヴィダ語族系のトゥル語が出て来る。
「Singham」は、ど派手なアクションで有名なローヒト・シェッティーが監督、アジャイ・デーヴガンが主演の南インド映画リメイクによるアクション映画。現代ヒンディー語映画の文法から逸脱した展開もあるが、全体的には笑いが程よくミックスされた痛快なアクション映画となっている。その痛快さの源泉は何と言っても悪に対する正義の勝利。映画を見終わった直後だけでも「清く正しく生きなければ」「悪に果敢に立ち向かって行かなければ」と奮い立たせてくれるような映画は、インドのような国には特に必要だ。そしてこういうシンプルな筋書きの映画がたまには公開されるのは悪いことではない。見て損はない。
本日をもって、インドに住み始めてからちょうど10年が経ったことになる。昔のパスポートを見てみると、入国スタンプの日付が7月29日になっているので間違いない。
インドの大学や教育機関は通常、7月末から8月初めにかけて入学手続きが始まるので、留学を目的にインドに住み始め、その後も住み続けている外国人は、大体この時期に「インド在住○周年」が来る。
滞在ではなく、旅行でインドに来た日からインドとの関わりをカウントする人もいるが、旅行するのと住むのとは全く違う体験であり、インドに長く住めば住むほど、旅行期間は単なる「助走」期間みたいなものに思えて来る。僕もインドに住み始める前に2回インドを旅行し、そのとき既にかなりの場所を回ったが、自分のインド人生の中でそれは単なる序章に過ぎない扱いだ。インドとの本当の付き合いは、インドに住み始めると同時に始まったと感じる。
ヴィザの種類の違いも精神的にかなりの隔たりを作る。昔からインドの観光ヴィザは、申請すればまず問題なく6ヶ月有効のものがもらえていたため、観光ヴィザでインドに来てそのまま半年間特定の住所に住んだり、違法ではあるが商売をしたりする外国人も多かった。最近は「ジェヌイン(本物)」な観光客を歓迎する一方で、それ以外の「観光ヴィザ所有長期滞在者」をなるべく排除する政策が採られているため、状況は変わりつつあるが、少なくとも数年前までは観光ヴィザだけでかなりインド在住気分を味わうことができた。
しかし、観光ヴィザは観光ヴィザであり、僕は「ジェヌイン」なインド在住者とはあまり認めていない。やはり、学生ヴィザや雇用者ヴィザなど、6ヶ月以上有効のヴィザと共にインドに住むことをインド在住としたい。それは、「インド旅行はヴィザ取得時から始まっている」という長年の格言に似た感情であり、長期滞在用のヴィザを取って始めて「インド滞在が始まる」のである。その感情は、観光ヴィザと共にインドに入国した者が、インドに来てからもいわゆる「FRRO(外国人登録局)の軛」を受けない事実からも増幅される(簡単に説明すれば、長期滞在する外国人は、入国から14日以内に外国人登録しなければならないが、その登録は多大な身体的・精神的労力を要するのである)。そうした意味でも、僕のインド人生は2001年7月29日に始まったと言える。
そしてインド在住10周年は、ほぼ同時に「これでインディア」10周年を意味する。
2001年当時は、インドでインターネットが使えるかどうかも不明な状態であった。その頃はネットカフェ全盛期で、街角にはネットカフェが乱立しており、日本語のフォントやIMEをインストールできたらメールチェックくらいはできるだろうとは思っていたが、自宅である程度快適なスピードとリーズナブルな価格でインターネットが使えるのかどうかは全く手探り状態であった。しかし、もし自宅でインターネットが使えたらいろいろ面白いことができるだろうと思い、インドへ出発する前にノートPCを購入して持って来たのである。それ以前にいくつかウェブサイトを作ったことはあり、ノウハウの蓄積はあった。もしリアルタイムでインドの日常をネット上にアップできたらユニークなコンテンツとなるだろうと出発前から計画していた。
インドに到着し、手っ取り早く住処を決めた後、しばらくはネット環境を整えるために悪戦苦闘の日々が続いたが、「これでインディア」の原型となる日記だけは書き続けていた。当時は電話線によるナローバンドのインターネットが一般的だったが(いわゆるピーーーガーガーガーの奴)、スピードが遅い上に、従量制のややこしい料金体系と複雑なシステム要件で、お世辞にも快適とは言えなかった。しかも電話線を新規に引くのに半端でない時間が掛かった。数ヶ月というレベルではなく、年単位である。賄賂を払えば払うほど早く引いてもらえるというどうしようもない状況であった。
だが、都市部の特定地域を中心に民間資本によるケーブル・インターネットの波が押し寄せていた。そして幸い、僕の住んでいた地域もその恩恵に預かれることが分かった。時間は掛かったが、ケーブルによる常時接続のインターネット環境を自宅に設置することに成功し、「これでインディア」を世界に向けて公開することに相成った訳である。
何度も自慢げに書いていることであるが、おそらくインドにおいて、少なくとも日本人で、自宅に常時接続のインターネット環境を整えることに成功したのは、僕が初めてだったはずである。住居に定めたのは家賃3,000ルピーの小さな汚い一室だったが、多分大使や大企業駐在員の自宅よりも世界とつながっていた。もしかしたら他にも僕より先に常時接続環境を手にした日本人がいたかもしれない。だが、その後たくさんの人から、どうやったらデリーの自宅でインターネットを使えるのかとEメールで質問を受けるようになった。ほとんどの人にとって、自宅で常時接続のインターネットを使うことは、アイデアにすらなかった時代であった。
当時の日記を読むと、2001年10月4日にネット開通とある。8月2日に家を決めてからすぐにインターネット環境整備に動き出していたため、2ヶ月掛かったことになる。実はその日に同時に「これでインディア」を公開したかどうかはよく分からないのだが、それまでネット開通を夢見てコツコツとウェブサイトを構築して来たため、それとはあまり変わらない時期にインターネット上にファイルをアップロードできたと考えられる。また、実はインドに出発する前から「これでインディア」の原型をかなり用意しており、インド到着後から日記を書き始めていたので、インド到着と同時に「これでインディア」が産声を上げたと考えてもいいだろう。
ただ、ここで、先輩となるウェブサイトについて感謝の意を込めて言及しておくのが筋と言うものであろう。僕がインドに留学する前、既に何人かの先達たちが、インド留学やインド生活に関するウェブサイトを立ち上げていた。もちろん、僕よりも前の時代のインドに住んでいた彼らは、現地からかなりの苦労をしてデータをネット上にアップロードしたり、あるいは日本に帰国してからインドでの思い出をウェブサイトにまとめていたりしたと思う。それらのウェブサイトからどれだけ留学や現地の生活に関する貴重な情報が得られたことか。その頃僕が愛読していたウェブサイトのほとんどは今やもう存在しない。サイト名すら覚えていないものが多く、ひとつひとつ名指しで感謝することはできないが、2001年より前にインド関連のウェブサイトを持っていた全ての人々、彼らの努力と貢献があったからこそ、僕もインスピレーションを受けて、このサイトを立ち上げ、続けて来ることができた。本当に感謝している。
当時はインドから生の情報を発信するというだけでユニークなウェブサイトになったものだが、ブログが登場し、SNSが流行し、そしてTwitterが登場したことで、もはや現地情報発信は誰にでもできることになってしまった。10年前にはデジカメの普及度も低かった。僕はカシオのQV-10A(1996年発売)時代からデジカメの潜在性を見抜いて愛用して来ており、インド留学時も当然デジカメを持参していた。デジカメで撮った、インターネットと親和性の高いイメージと共に現地情報を発信するというのもまた斬新な試みであった。しかし今ではそれもごく普通のことだ。また、日本におけるインド関連の報道も、10年前と比べて格段に増えた。当時はインドの最新情報を日本語にして日本に発信するという使命感と共にウェブサイトを運営していたが、そういう必要性もだいぶ減った。こういった状況の変化から、「これでインディア」の内容や方針も、「インド留学日記」を銘打っておきながら、徐々に変化して来たのであるが、何より途中中断もなく続けて来られたのはそれだけで誇っていいことだと思う。
ただ、最初期の頃は個人的な日記の性格が強く、生活の中で出会った人々の個人名もバンバン登場したため、ある時点から公開を控えるようになった。幸い、当時はそんなに読まれていなかったので、本人やそれに近い人から直接苦情が来るようなことはほとんどなかったが、デリーの日本人社会や、日本人と接触のあるインド人たちのコミュニティーの狭さに気付くのに時間は掛からず、自発的に自粛したのだった。最近はブログやTwitterで簡単に情報を発信でき、しかもそれが瞬く間に広まるようになったため、僕が10年前に何気なく犯していた過ちを、ブログやTwitterなどでやはり何気なく犯してしまって、しかも大事になってしまう事態を時々見掛けるが、これは本当に注意すべき問題である。ただ、インド人は一般的に目立ちたがり屋であまり強烈なプライバシー意識を持っていないので、僕がその人と関連することを日記に書きながら、その人の名前を出さなかったり、その人の写真をウェブサイトに載せなかったりすると、逆に怒ったりする人もいたりして、難しいものである。
ちなみに、「これでインディア」はブログが一般に普及する前から存在したウェブサイトである。時々このウェブサイトのことをブログと言ったり、僕のことをブロガーと呼んだりする人がいるのだが、その呼称には不快感を感じる。「これでインディア」は昔も今もウェブサイトであり、ブログのシステムは一切使っていない。一応ブログ版「これでインディア エクスプレス」はあるが、最近全く更新していない。Twitterで事足りてしまう。ホームページを見れば分かるように、僕のTwitterアカウントとこのウェブサイトは一応連動させてある。
それはともかく、僕がインド在住10周年を迎えたと同時に、「これでインディア」もほぼ10年を迎えたことになる。だが、様々な要因から、最初期の日記は公開を控えているため、僕がどういう経緯でインドに住み始めたのか、何を思って生きているのか、そもそも何をしているのか、最近になって読み始めてくれた読者にはいまいち分かりづらいところもあるかもしれない。また、ブログやTwitterの隆盛を横目に、「これでインディア」をそれらとは一線を画したインフォマティブなウェブサイトにしようと努力した結果、最近はかなりマニアックな情報(特にヒンディー語映画関連)しか提供できないサイトになってしまったような気もする。そこで、10年を節目として、「随想」というカテゴリーを作って、もう少し思い出話やその他の雑事を、あまり長くならないように、軽い気持ちで書くようにして行こうと思う。多分これからの1年が僕のインド滞在の最後の1年になるので、それらが僕のインド時代の総集編のようになればと思っている。
| ◆ |
7月31日(日) Gandhi to Hitler |
◆ |
インド建国の父として知られるマハートマー・ガーンディーは、死後60年以上経った今でも学問的研究や文芸作品の題材となっている。ヒンディー語映画界でもガーンディーは「人気のキャラクター」であり、様々な形でスクリーンに登場し、我々に語り掛けて来る。もちろん、皮肉なことに、ガーンディーの人生を題材にした伝記映画「ガンジー」(1982年)は英国人映画監督リチャード・アッテンボローによる作品で、純粋な意味でのインド映画ではないが、21世紀に入ってからも、ガーンディーの哲学を巧みに娯楽映画化した「Lage
Raho Munnabhai」(2006年)や、ガーンディーの家庭人としての一面にスポットライトを当てた「Gandhi, My Father」(2007年)など、ヒンディー語映画界ではガーンディーを何らかの形で題材にした重要な作品がいくつも作られた。
7月29日より公開された新作ヒンディー語映画「Gandhi to Hitler」も、またひとつガーンディーを題材にした映画である。題名が示すように、ガーンディーがナチス・ドイツのアドルフ・ヒトラー総裁に宛てて書いた2通の手紙からストーリーを膨らませて作られた作品である。ガーンディーはヒトラーに対し「親愛なる友」と呼び掛けながら、1939年と1940年の2回、手紙を送っている。その内容はネット上で閲覧することが可能である――1939年7月23日(200番または156頁)と1940年12月24日(520番または453頁)。ガーンディーはヒトラーに対し、世界規模のこの戦争を止めることができるのは君だけだと語り掛けている。ただ、映画の方はどちらかと言うとアドルフ・ヒトラーの最期を中心とした映画であり、ガーンディーの手紙やガーンディー自身はほとんどストーリーに絡んで来ない。また、ヒトラーを含むドイツ人をインド人俳優が演じ、台詞もヒンディー語で進行する。一応国際版と国内版があるようで、国際版の方の題名は「Dear
Friend Hitler」となる。国際版の言語はおそらく英語のはずである。インドで公開されているのは国内版の方だ。
題名:Gandhi to Hitler
読み:ガーンディー・トゥ・ヒトラー
意味:ガーンディーからヒトラーへ
邦題:親愛なる友ヒトラーへ
監督:ラーケーシュ・ランジャン・クマール
制作:アニル・クマール・シャルマー
音楽:アルヴィンド・ライトン、アマン・ベンソン、サンジャイ・チャウドリー
歌詞:パッラヴィー・ミシュラー
振付:スーラジ
衣装:リピカー・スィン、プリーティ・スィン、デーシャー・タッカル
出演:ラグヴィール・ヤーダヴ、ネーハー・ドゥーピヤー、アマン・ヴァルマー、ラッキー・ヴァカーリヤー、ナスィール・アブドゥッラー、アヴジート・ダット、ニキター・アーナンド、ナリーン・スィンなど
備考:DTスター・プロミナード・ヴァサント・クンジで鑑賞。

上から、アヴジート・ダット(左)、ラグヴィール・ヤーダヴ(右)
ネーハー・ドゥーピヤー(左)、ナリーン・スィン(右)
| あらすじ |
1945年ベルリン。ナチス・ドイツはソビエト連邦軍の侵攻を受けており、ベルリンは陥落寸前であった。ナチス・ドイツのアドルフ・ヒトラー首相(ラグヴィール・ヤーダヴ)は、恋人エヴァ・ブラウン(ネーハー・ドゥーピヤー)、建築家・軍需大臣アルベルト・シュペーア(ナスィール・アブドゥッラー)、国民啓蒙・宣伝大臣ヨーゼフ・ゲッペルス(ナリーン・スィン)やその他の閣僚らと共に総統地下壕に待避し、指揮を執っていた。しかし、ドイツ軍は物資の不足からもはや反撃する力を失っており、ベルリンが陥落するのも時間の問題であった。ヒトラーの部下たちも次々に裏切り出す。アルベルトですら辞表を提出して去って行ってしまった。
一方、ドイツ亡命中だったネータージー・スバーシュ・チャンドラ・ボース(ブーペーシュ・クマール・パーンディヤー)によってドイツで創設されたインド人部隊アーザード・ヒンド・ファウジは、ドイツのために戦っていたが、ドイツの敗戦を知って、インドに帰るためにアルプス山脈に沿って逃走を開始する。部隊の隊長を務めるバルビール・スィン(アマン・ヴァルマー)には、故郷に妻アムリター(ラッキー・ヴァカーリヤー)を残して来ていた。バルビールはインドに帰ってアムリターと再会することを夢見て、部下たちと共に苦しい逃走をする。だが、絶望に打ちひしがれた兵士たちの精神は次第にすさんで行き、喧嘩が絶えなくなる。そして、1人また1人と命を落として行く。
アムリターは、両親の世話をしながら、マハートマー・ガーンディー(アヴジート・ダット)とも時々会っていた。ガーンディーは集まった人々に、非暴力の戦いの大切さを説く。
とうとうソ連軍は総統地下壕の500メートル先にまで迫っていた。ヒトラーは、戦意を失ったドイツ国民に失望し、自決を決意する。その前にヒトラーはエヴァと結婚し、遺言を書き残す。ヒトラーはエヴァを逃がそうとするが、エヴァは彼と共に死ぬことを選ぶ。エヴァは毒薬を飲んで自殺し、ヒトラーは拳銃自殺をした。また、腹心ゲッペルスはヒトラーの後を追い、妻子と共に自殺する。
逃走の途中に負傷したバルビール・スィンは中立国スイスとの国境まで辿り着き、何とかスイスに入り込もうとするが、国境警備をしていたフランス軍兵士に見つかり捕まってしまう。そして連行される途中に兵士たちによって殺されてしまう。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
夏休みの自由研究レベルの作品。こんな駄作を国際リリースしてしまったことに驚く。これはインド映画全体の恥であろう。低予算なのは分かる。だが、低予算なりに作り方があったはずだ。ドイツ人キャラクターをインド人俳優が演じるというユニークな試みも単に低予算映画の言い訳に過ぎない。ヒトラーというヨーロッパではセンシティブな題材を選んだことで、欧州やインドのユダヤ教徒コミュニティーの間で物議を醸したようだが、それ以前に鑑賞に値しない出来の映画である。肝心のガーンディーとヒトラーの絡みも、全く意外なことに、映画中では全くない。一体何のために作られたのか分からない映画であった。
ガーンディーとヒトラーの件についてもう少し深く掘り下げてみようと思う。映画の大部分は1945年4月を軸としている。ヒトラーが自殺をしたのが1945年4月30日であり、その前の数日間がこの映画の主軸となる。ところが、ガーンディーがヒトラーに手紙を送ったのは1939年と1940年であり、実際に劇中でもそれが明示される。つまり、ガーンディーがヒトラーに送った手紙を構想の土台としておきながら、映画のストーリーとガーンディーはほとんど絡んで来ないことになる。また、ガーンディーが送った手紙をヒトラーが読んだり反応したりするシーンもない。所々で、ガーンディーが弟子たちに非暴力の教えを説くシーンが挿入されているが、象徴的過ぎてヒトラーとガーンディーの対比にもなっていない。
ドイツで創設されたアーザード・ヒンド・ファウジ(Free India Legion)に部分的に焦点を当てたのは悪くなかった。チャンドラ・ボースの掲げた理念の下に集った若者たちは、インド独立のためにヨーロッパで戦うが、すぐに彼らはインドとは関係ないドイツのための戦いに動員されることになってしまい、自分たちの存在意義や戦いの正当性についてに疑問を感じ始める。ドイツが敗戦したことで彼らは必死の逃走をするが、隊長バルビールは中立国スイスとの国境で捕まってしまい、連行中に殺されてしまう。しかし、良かったのは着眼点のみで、そのシーンもこの映画の質を高めることに貢献していなかった。
無理にインド映画の伝統であるダンスシーンの挿入を試みているのもマイナス要素だった。緊迫感が重要なこの映画の中に、ホーリーのダンスシーンなどは必要なかった。
企画時点で破綻しているために、その後の全ての要素――脚本、台詞、演技、編集、音楽などなど――にも問題が波及しているのだが、俳優たちはこのおかしな設定の映画の中で最大限の貢献をしていたことだけは記しておかねばなるまい。特にヒトラーを演じたラグヴィール・ヤーダヴは、俳優としてのプライドを持って、演技でもって外見のハンデを克服しようと迫真の演技をしていた。エヴァを演じたネーハー・ドゥーピヤー、ゲッペルスを演じたナリーン・スィンなども悪くはなかった。
台詞はほぼ全てヒンディー語である。ガーンディーやその他のインド人キャラクターは当然として、ヒトラーを含むドイツ人キャラクターも普通にヒンディー語をしゃべる。舞台劇などならこういうのもありだと思うが、映画で見ると違和感は拭えない。しかも、エヴァを中心に台詞中に英語を織り込むシーンがあり、それがまた奇妙さを添えていた。どうせなら挨拶程度の数フレーズくらいはドイツ語にしても良かったのではないかと思う。
ドイツ人を演じる俳優が皆インド人で、台詞がヒンディー語であるのに加えて、ロケ地もインドであった。しかもデリー、ノイダ、チャンディーガルなど、主に北インドで撮影されたようである。
「Gandhi to Hitler」は、興味を引かれる題名の映画ではあるが、低予算映画の弱みがモロに出てしまった悲しい出来の映画であり、無理に見る必要はないだろう。
|
|



