 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
 印度文学館 印度文学館 
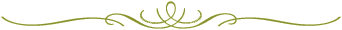
ラーキーの誉れ
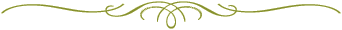
|
|
著者はハリクリシュナ・プレーミー(1908-?)。インド独立運動に積極的に加わったヒンディー文学者。愛とナショナリズムに満ちた戯曲を書いた。
この戯曲は「Raksha Bandhan」(1938年)の一部だと思われる。抜粋されたものしか手元になかったため、調査が必要だ。ヒンドゥーとムスリムの融和を主題とした作品。
【時代背景】
1535年、グジャラート地方を支配していたスルータン、バハードゥル・シャーがメーワール王国に侵攻した。百戦錬磨の王マハーラーナー・サーンガーを亡くした今、メーワール王国は滅亡の危機に瀕していた。一方、ムガル朝第二代皇帝フマーユーンは、ビハール地方でシェール・カーンと対峙していた。 |
|
チッタウルの要塞の内部で、故マハーラーナー・サーンガーの妻、カラムワティーとジャワーハルバーイー、そして他のクシャトリヤ(戦士階級)の女性たちが、皿にラーキーを置いて立っている。女性たちは男性たちの額にティラク(赤い模様)を付け、手首にラーキーを結び、剣を手渡す。
カラムワティー「我がメーワール国において、これほど華やかな夏は過去になかったことでしょう。兄弟たちよ!クシャトリヤの女性たちのラーキーは安くありません。ブラーフマンのように、我々はお金をもらってラーキーを結ぶことはしません。我々のラーキーの見返りは、完全なる犠牲です。命を捧げる覚悟のある者のみ、このラーキーを受け取りなさい。」
クシャトリヤ「メーワールの土地において、そのようなことを改めて述べる必要はありません、王妃よ!我々はいつでも笑って命を差し出して来ました。我々のこの無敵の力の源が他にありましょうか?姉妹たちのラーキーこそが我らに力を与えて来たのです」
アルジュン「王妃よ、あなたの兄弟たちにとって、このラーキーは心の支えです。今日、このラーキーは死を指し示していますが、だからといって我々がどうしてそれを拒絶することができましょう?ただ地図の線を見ただけで、国のために命を捧げることはできません。あなたこそがラーキーによってそれらの線の重要さを教えて下さったのです。国境の線には、このラーキーの中に込められているのと同じだけの無限の愛、悲しみ、祝福が込められているのです」
カラムワティー「勇者たちに勝利を!お前たちからその言葉を聞くことを期待していました。ならばラーキーの誉れに誓って、命ある内はメーワールの旗を土に付かせないと誓いなさい。」
皆「我々は誓います、王妃よ!」
カラムワティー「メーワールの息子たちよ、メーワールの栄誉はお前たちの肩にかかっています。お前たちの栄光は永遠なり!さあ、行きなさい、戦場がお前たちを待っています!」
クシャトリヤたちは一礼して立ち去る。
カラムワティー「姉妹たちよ、お前たちも急いで家で戦勝祈念の断食の準備をしなさい。」
ジャワーハルバーイーを除き、全てのクシャトリヤの女性たちは立ち去る。
カラムワティー「ところで、バーグスィンよ!戦況はどうですか?」
バーグスィン「ラージプート(戦士)たちは勇猛果敢に戦っております。しかるに、我が軍勢は多勢に無勢、しかも敵方には西欧式の大砲が火を噴いております。剣で立ち向かうことは不可能です。我らは死ぬでしょう。笑いながら死んでやります、大勢の敵兵を殺して死んでやります。しかし、残念ながら我らが命を捧げても、メーワールの尊厳を死守することはできないでしょう。」
カラムワティー「非常に困難な状況ですね。私の夫はもういません。夫が生きている内は、メーワールに歯向かう勇気がある者は皆無でした。夫を恐れるあまり、メーワールの外の悪党どもまでが震えていたものです。メーワールの領内に足を踏み入れる勇気が誰にあったでしょう?バーグスィンよ、我々は内部抗争に明け暮れるあまり、自らの手で全てを火の中に投げ込んでしまったように思います。」
バーグスィン「今から後悔しても何の得もありません、王妃よ!さあ、今は我らにどうすべきかご命令下さい。このようなときには、賢明なる支配者にただ従うのみです。」
カラムワティー「私にはひとつの考えがあります。」
バーグスィン「何でしょうか?」
カラムワティー「フマーユーンにラーキーを送りましょう。」
ジャワーハルバーイー「フマーユーンに!イスラーム教徒を兄にするつもりですか?」
カラムワティー「何を驚いているのですか、ジャワーハルバーイー?イスラーム教徒も人間です。彼らにも姉妹がいます。それとも彼らは人間ではないと考えているのですか?彼らは心がないのでしょうか?イスラーム教徒は神をアッラーと呼んでいます、寺院ではなくモスクに行っています、だからといって、我らは彼らを憎む必要があるのでしょうか?」
バーグスィン「しかし、他にも問題があります。果たしてフマーユーンが昔の恨みを忘れることができるでしょうか?スィークリーの戦いの古傷が簡単に癒えるとお思いですか?」
カラムワティー「我らのラーキーは、あらゆる傷を治す冷たい軟膏です。全てのいざかいを燃やして灰としてしまう祝福です。ラーキーを受け取った者が敵意を抱くことができるでしょうか?」
ジャワーハルバーイー「イスラーム教徒はインドの敵です。」
カラムワティー「そんなことを言うものではありません。彼らも今やインドで生まれ、インドで死ぬ運命なのです。我らのように、彼らの故郷もこのインドなのです。彼らをアラブに追い返すことはできません。彼らはこのインドに住まなければなりませんし、我らも彼らを受け容れなければなりません。我々は互いに兄弟と呼び合うべきでしょう。これこそ自然で、正しい道です。それに、このような困難な状況において、メーワールを救う他の方法がありますか?バーグスィンよ、お前の意見を聞かせなさい。」
バーグスィン「私はただ命令に従うだけです、意見を述べる立場にありません。」
カラムワティー「ならば私の決定に異論はありませんね。兄弟愛と人間性を信じ、フマーユーンを試してみることにしましょう。さあ、このラーキーと手紙を持って、今日にも皇帝フマーユーンのもとに使いをよこしなさい。」
ラーキーと手紙を渡す。
ジャワーハルバーイー「分かりました。一体どうなるか見てみましょう。これで、1人のイスラーム教徒の人間性が試されるでしょう、そして、1人のラージプートの女性のラーキーにどこまで力があるかも分かるでしょう。」
ビハールのガンガー(ガンジス河)河畔、フマーユーン軍の駐屯地。テントの中に、フマーユーン、ヒンドゥベーグ将軍、タータール・カーン将軍が座っている。1人の哨戒兵が入って来る。
哨戒兵(一礼して)「皇帝!」
フマーユーン「どうした?」
哨戒兵「メーワールの使節が来ました。」
フマーユーン「メーワールから?よし、ここに通せ。」
哨戒兵は立ち去る。
フマーユーン「メーワールの使節!メーワールは魔法の響きだ。バヤーナーとスィークリーの戦いには、私も父親と共に参加した。我らの軍勢が、ラージプートたちにどれだけ打ちのめされたことか。アッラーはラーナー・サーンガーを鉄で作られたに違いない。奴の鋭い視線は、死の宣告に等しかった。メーワールには今、バハードゥル・シャーが侵攻していると聞くが。」
使節が入って来る。
フマーユーン「よく来た、メーワールの勇者よ!」
使節(一礼して)「故マハーラーナー・サーンガーの王妃カラムワティー様が、この贈り物を皇帝にお贈りになられました。」
フマーユーン(手を差し出して)「これはありがたい!ヒンドゥベーグ!お前も知っているだろう、私がメーワールに一目置いていることを。私だけでない、勇者に対しては誰もが尊敬を払わなければならない。メーワールの土からして頭に乗せてしかるべき尊い品だ。至る所が天国と言えよう。」
タータール・カーン「敵をお褒めになることは皇帝の・・・」
フマーユーン「敵!ハッハッハ!敵!目から敵意の眼鏡を外して見てみよ。我らが敵と思っている者たちは皆、兄弟だ。我らはアッラーの息子たちなのだ、タータールよ!そうだ、それでこの手紙には何が書いてあるかな。」
フマーユーンは手紙を読みながら微笑む。
ヒンドゥベーグ「夢でも見ておいででしょうか、皇帝!カラムワティーからの贈り物は、魔法の箱ではありますまいな?」
フマーユーン「ヒンドゥベーグ、カラムワティーは正に魔法の箱を贈ってよこしたぞ。我が孤独な空に、カラムワティーは愛の月を光らせたのだ。贈られてきたものはラーキーだ。私を自分の兄にしたのだ。(使節に対し)我が妹、カラムワティーに伝えよ、フマーユーンはお前の母親の腹から生まれなかったが、お前の実の兄以上の兄である、と。そして、メーワールの尊厳は我が尊厳だ、と伝えよ。行け。」
使節が立ち去る。
タータール・カーン「カラムワティーは、皇帝の父親の天敵の妻ですぞ・・・」
ヒンドゥベーグ「それに、あの女の夫は、ムガルをヒンドゥスターンから追い出さない限り、チッタウルには足を踏み入れないと誓いました。それをお忘れですか?」
フマーユーン「お前たちはこのラーキーの価値を残念ながら知らないようだ。この小さな2本の糸が、敵意を愛情に変えてしまうのだ。メーワールの勇敢な王妃が私を兄とし、バハードゥル・シャーからメーワールを救うために我が助けを求めたことは、幸せなことだ。」
タータール・カーン「それでは、皇帝はその頼みを承諾なさるおつもりですか?」
フマーユーン「これは頼みなどではない、命令だ。ラーキーを手にした後に、何を考えることができようか?これは火の中に飛び込めという招待状だ。ヒンドゥスターンの歴史において、このラーキーは何千もの自己犠牲を行わせてきたのだ。私はこの世の全ての者に対し、ヒンドゥー教徒の習慣はイスラーム教徒にとっても美しく、清らかであるということを示したい。」
タータール・カーン「皇帝はイスラーム教徒よりもヒンドゥー教徒を大切になさるおつもりですか?」
フマーユーン「ヒンドゥーもムスリムも関係ない!私はよく分かっている!タータール・カーンよ、私が言っていることは、アッラーのご意思に背いていないぞ。」
タータール・カーン「敵の味方をして、イスラーム教徒と戦うのですか?それがアッラーのご意思ですか?」
フマーユーン「お前は忘れたのか。お前たちは皆、アッラーの子孫なのだ。ヒンドゥー教の聖者たちも、お前の預言者たちも、同じ道を指し示しているのだ。2つの宗教の間の友情に、どうして剣を差し込むことができようか?」
タータール・カーン「奴らは我らの預言者を信じていません。」
フマーユーン「ならばお前はヒンドゥーの預言者たちを信じているのか?コーランには、他の預言者たちをも尊敬し、信じるように書かれているではないか。それは真実だ。アッラーのご意思は疑いもないのに、お前はヒンドゥーの宗教も聖者も信じずに彼らと戦っている。今の状況では、ラージプートが正義で、バハードゥル・シャーが悪だ。真のイスラーム教徒のとるべき行動は、正義の道を行くことだ。たとえイスラーム教徒と戦うことになっても何を恐れることがあろうか?さあ、今日中にでもメーワールへ向かわねばならないだろう。」
ヒンドゥベーグ「私はヒンドゥーとイスラームを区別していません。しかし、今、シェール・カーンをこのままにしてメーワールへ向かうことが非常に危険であることは確かです。」
フマーユーン「もう考えている時間はない。妹との関係は、世界の全ての喜び、富、権力、支配よりも尊いものだ。私はこの関係を台無しにすることはできない。たとえ国を失っても、私は世間の者が、『イスラーム教徒は妹を大切にしない』と口にするのを耐えることができない。(玉座から降りて)もし妹を喜ばせることができたなら、私は自分を世界で最も幸運な人間だと思うだろう。カラムワティーよ!妹よ!どうかお前のラーキーが、ラージプートに与えてきた力を私にも与えるように!タータール・カーン、ヒンドゥベーグ、急いで軍勢の準備をせよ!」
フマーユーンはラーキーを手に結びながら立ち去る。
|
|
|
|
|
|
−完−
|
|
| *** Copyright (C) Arukakat All Rights Reserved *** |



