| ◆ |
4月1日(火) 各都市TOIエイプリル・フール記事比較 |
◆ |
毎年密かにタイムス・オブ・インディア(TOI)紙のエイプリル・フール記事を楽しみにしている。だが、残念なことに近年同紙のギャグの切れは落ちて来ている。7年間TOI紙を見守って来たが、最高だったのは2002年4月1日のエイプリル・フール記事だった(参照)。今年も4月1日が来て、真っ先にTOI紙のエイプリル・フール記事を探した。本紙の方にエイプリル・フール記事は見当たらなかったが、サプリメントのデリー・タイムスの方にはひとつだけ偽記事が見つかった。だが、やはりここ数年の低調さから脱却できていない低レベルな記事で、がっかりした。ただ、エイプリル・フール記事はもっともホットな時事ネタをいじったものが多く、インドの最新情報に精通していないと何が偽情報なのか何が面白いのか理解することもできない。よって、その解説をすることで、今インドで何が関心を持たれているかを日本人に知ってもらうことができるように思える。だから毎年エイプリル・フール記事を解説することはもしかしたら少し意味のあることかもしれない。
さて、今年のデリー・タイムスのエイプリル・フール記事の題名は、「ビヨンセ、IPLでダンス出演へ(Beyonce to do a jig for
IPL)」であった。IPLとはインディアン・プレミア・リーグの略で、英国プロサッカーのプレミア・リーグをモデルに今年から新規に立ち上げられるクリケット・リーグのことである。インド人選手だけでなく、世界各国の有名選手が参加する。インドの8都市を拠点とした8チームが編成されるが、その編成過程は変わっている。各チームを買い取ったオーナーが、オークション形式で世界中の有力選手を自チームに引き抜き、チームを編成するのである。初回の今年は以下の8チームになっている。
| チーム名 |
オーナー |
都市 |
| ムンバイー・インディアンス |
ムケーシュ・アンバーニー(リライアンス工業) |
ムンバイー |
| バンガロール・ロイヤル・チャレンジャーズ |
ヴィジャイ・マッリヤー(UBグループ) |
バンガロール |
| デカン・チャージャーズ |
デカン・クロニクル |
ハイダラーバード |
| チェンナイ・スーパー・キングス |
Nシュリーニヴァーサン(インディア・セメント) |
チェンナイ |
| デリー・デアデビルス |
GMRホールディングス |
デリー |
| キングスXIパンジャーブ |
プリーティ・ズィンター(映画スター)、ネース・ワーディヤー(ボンベイ・ダイング)、カラン・ポール(エーピージェー・スレーンドラ・グループ)、モーヒト・ブルマン(ダーバル) |
モーハーリー |
| コールカーター・ナイツ・ライダース |
シャールク・カーン(映画スター)、ジューヒー・チャーウラー(映画スター)、ジャイ・メヘター |
コールカーター |
| ラージャスターン・ロイヤルス |
マノージ・バーダレー、ラチュラン・マードック、スレーシュ・チェッラーラーム(エマージング・メディア・グループ) |
ジャイプル |
試合形式は、昨年初めてワールドカップが行われ大成功を収めたTwenty20。1試合最大5日間続くクリケットの試合だが、Twenty20は数時間で決着が付くもっとも短い試合形式で、スピーディーかつパワフルな展開が売りである。IPLは4月18日から開始される予定で、開幕試合ではヴィジャイ・マッリヤー所有のバンガロール・ロイヤル・チャレンジャーズと、シャールク・カーンら所有のコールカーター・ナイツ・ライダースが激突する。
エイプリル・フール記事の内容は以下の通りである。
IPLが熱を帯びて来ている。ヴィジャイ・マッリヤーとシャールク・カーンは、開幕試合を盛り上げるためいくつかの秘策を用意している。彼らが初めて明かすその内容とは以下のようなものである。
マッリヤーに近い筋の情報によると、「マッリヤーは、ビヨンセ・ノウルズに開幕戦で踊りを踊るように頼み込んだ。ビヨンセが世界ツアーの一環でインドを訪れた際、マッリヤーとビヨンセは親しくなった。ビヨンセは15分間のパフォーマンスをすることで同意した」とのことである。しかし、ビヨンセはクリケットに興味があるのだろうか?「ああ、それはもうひとつのサプライズだ。ビヨンセは熱心なドーニーのファンなんだ」と情報筋は語る。
それだけではない。マッリヤーはロサンゼルスにチャーター便を飛ばし、ハリウッドの友人、例えばデーヴィッド&ヴィクトリア・ベッカム、リチャード・ギア、ジュリア・ロバーツなどを観戦に招待しようとしている。
対するシャールク・カーンも遅れを取っていない。彼は、ボリウッド・スターの一団を開幕戦に揃える手はずを整えた。シャールク・カーンは、「私はテープカットと点火のためにアミターブ・バッチャンを招待した。彼は当初戸惑っていたが、アビシェークが説得に協力してくれた。実はアビシェークとアイシュワリヤーも同席する予定になっている」と語っている。
しかしながら、この話にはツイストもある。カトリーナ・カイフとディーピカー・パードゥコーンは、ビヨンセが招待されたことに立腹のようだ。カトリーナは、「元々ディーピカーと私が踊りを踊ることになっていたけど、今になって私たちは、クリケット・ボールの格好をして手を振るだけでいいと言われた。私はサルマーンに、チームを買うように頼んだわ。少なくとも私が踊りを踊れるように!」と語っている。しかし、サルマーンはリアル・マドリードを購入することの方に関心を持っていると言われている。彼のボディーガードのシェーラーは、「彼は、そうすることでインドのサッカー・シーンを盛り上げることができると考えている」と語っている。では、ディーピカーはどう思っているのだろう?彼女は、「私はクリケットと関われるだけで幸せ」と語っている。しかし、彼女は既にクリケットと関係があるのでは?「私が言いたかったのは、映画とクリケットの結婚のこと。ところで、ランビールも当日駆けつけるわ。私は彼に、私のコスチュームに似合うように、バットの衣装を着るように頼んだわ。私たちはクールなカップルになるでしょう。」彼女は勝ち誇ったように語っていたが、我々は何と答えたらいいのだろう?
少し解説を加えると、アミターブ・バッチャンとアビシェーク・バッチャンは親子で、共にボリウッド・スターである。アビシェークは昨年女優のアイシュワリヤー・ラーイと結婚した。カトリーナ・カイフとディーピカー・パードゥコーンは今一番勢いのある若手女優である。カトリーナの恋人はボリウッド・スターのサルマーン・カーン。一方、ディーピカーはクリケット・スターのマヘーンドラ・スィン・ドーニーやユヴラージ・スィンとの交際が噂されていたが、現在ではボリウッド・スターのランビール・カプールと付き合っているとされている。ビヨンセ・ノウルズは米国の人気歌手で、日本でも有名なので解説の必要はないだろう。以上のことを押さえておかないと、記事の内容をよく理解できないだろう。だが、全体的にパンチ力不足なのは明らかだ。カトリーナ・カイフとディーピカー・パードゥコーンがクリケット・ボールの衣装を着て登場し、ディーピカーの恋人のランビール・カプールがそれに合わせてバットの格好をするという下りが、敢えて言うならば一番の笑いどころか。
最近は便利になったもので、インドの新聞各紙ウェブサイトの多くはEペーパーというサービスを行っている。Eペーパーを利用すれば、本紙と全く同じ内容同じレイアウトの新聞をネット上で閲覧することができる。デリー以外の都市で発行されているTOI紙のエイプリル・フール記事が気になったので、Eペーパーを使って調べてみた。そうしたら、少し面白い事実を発見した。
まず、Eペーパーで閲覧できるのは、ムンバイー、デリー、アハマダーバード、プネー、ハイダラーバード、ラクナウー、コールカーター、バンガロール、マンガロール、チャンディーガル、ナーグプルのTOI紙である。エイプリル・フール記事は伝統的に、本紙に付属して来る折込紙(インドでは「サプリメント」と呼ばれる)に掲載される。TOI紙のサプリメントの名前は、一般的には【都市名】タイムスだが、チャンディーガル版だけは、タイムス・オブ・チャンディーガルになっていた。上記の都市のTOI紙の内、マンガロール版だけはサプリメントがなかった。マンガロール版本紙にざっと目を通したが、エイプリル・フール記事らしきものは見当たらなかった。また、ボンベイ・タイムスとタイムス・オブ・チャンディーガルにもエイプリル・フール記事はなかった。ムンバイーではちょうどラクメ・ファッション・ウィークが開催中で、ボンベイ・タイムスはファッション・ショーを総力特集していた。おそらくその影響でエイプリル・フール記事を載せる余裕がなかったのだろう。一方、ル・コルビジェが設計した計画都市チャンディーガルはインドの中でももっとも規制の厳しい都市であり、もしかしたらエイプリル・フール記事も許容されていないのではと思った。さらによく見てみると、アハマダーバード・タイムス、プネー・タイムス、ハイダラーバード・タイムス、ラクナウー・タイムスは、デリー・タイムスと同様の「Beyonce
to do a jig for IPL」をエイプリル・フール記事としてそのまま採用していた。よって、オリジナルのエイプリル・フール記事を掲載していたのは、カルカッタ・タイムス、バンガロール・タイムス、ナーグプル・タイムスのみであった。
まずはカルカッタ・タイムスのエイプリル・フール記事を見てみよう。カルカッタ・タイムスは2本の偽記事を掲載していた。まずは「ユヴィとディーピカーが結婚!(Yuvi
& Deepika tie the knot!)」という記事。先ほど少し触れたが、クリケット・スターのユヴラージ・スィンと、ボリウッドの新人女優ディーピカー・パードゥコーンは一時期噂になっており、それをネタにした偽記事である。ディーピカーは現在、新人男優のランビール・カプールと付き合っていることを公言しているので、もしユヴラージとディーピカーが本当に結婚をしたら大スキャンダルとなる。記事の内容は以下の通りである。
ランビール、もし立っているなら座りなさい。そして、何かを掴みなさい。君は「Om Shanti Om」の秘密婚シーンを見て心構えをしておくべきだった。そう、ディーピカーがまたやったのだ、しかも今回は現実世界で。ボリウッドの最新ピンナップ・ガールは、元恋人のユヴラージ・スィンと秘密裏に結婚していたのである。
ユヴラージ・スィンの叔母のクシュブー・スィンは、カルカッタ・タイムス(CT)とのインタビューにおいて、2人が昨年12月10日、ユヴラージの26歳の誕生日の2日前に、秘密裏に結婚していたという衝撃の事実を明らかにした。彼女は、「2人はグルドワーラーで秘密裏に結婚をしたわ。ユヴラージの兄弟もその場にいた。そのときディーピカーの映画が公開されていたから、誰にも何も言わなかったの」と語った。
なるほど、2人がユヴラージの誕生日パーティーで見せた仲睦まじさはそれで説明が付く。ディーピカーがパーティーでゲストたちを迎える様子から、2人は婚約したのではとの噂が広まったが、ディーピカーは巧みにその噂をかわした。CTは以前、ディーピカーがユヴラージとの婚約の噂を、今までの聞いた中で「もっともおかしなこと」と言って否定したことを伝えた。
ユヴラージとディーピカーの仲は全てがうまく行っていた。ユヴラージの母親のシャブナム・スィンは、息子に対してボリウッド女優を嫁として家に迎えることは許さないと言いつけていたが、ディーピカーのことはとても気に入っていた。我々は彼女に連絡を取ったが、彼女はコメントを拒否した。「ディーピカーがしたことには何か理由があるはず。それ以上私が言えることはありません。」ユヴラージとディーピカーにSMS(携帯メール)を送ったが、返事はなかった。ユヴラージの父親はおしゃべりで知られているが、彼ですらこの問題には口を頑なに閉ざしている。
ディーピカーは今やランビール・カプールの腕の中に愛を見出したが、一方のユヴラージは「より緑の生い茂った牧草地」へ移動した。それとも2人一緒にと言うべきか?全てのゴシップは、結婚から世間の注目を逸らし、ファンを囲い込むために新婚カップルが企てた戦略なのか?ある映画評論家(匿名希望)は指摘する。「ディーピカーは映画業界では新人であり、もし結婚の事実が漏れたら彼女のキャリアは台無しになってしまう。既婚の女優が未婚の女優と同じマーケットを持ち得ないことは誰もが知っている。」
ディーピカーの相手は、ニハール・パーンディヤー、ドーニー、ユヴラージ、再びニハール、そしてランビールと変わって行き、メディアもそれも追い掛けて来た。しかし、キャリアを始めたばかりの彼女がもう結婚してしまうなんて誰が想像しえただろう!我々以外にはいない!
ディーピカー・パードゥコーンは「Om Shanti Om」(2007年)でボリウッド・デビューを果たし、一躍時の人となった新人女優だ。同映画の中で、彼女は70年代のボリウッドの架空のスーパースター、シャーンティプリヤーを演じた(モデルはヘーマー・マーリニーのようだ)。シャールク・カーン演じる主人公オームは、しがないジュニア・アーティスト(エキストラやスタントをこなす下級の俳優)だったが、シャーンティプリヤーに惚れ込んでしまう。2人はある程度仲良くなるが、ある日オームは、シャーンティプリヤーが既に敏腕プロデューサーと秘密裏に結婚していたことを知ってしまう。この映画のプロットを活かし、ディーピカーが実は元恋人とされるユヴラージ・スィンと結婚していたという偽すっぱ抜き記事を作ったようだ。センスはデリー・タイムスよりもいい。
カルカッタ・タイムスが送るもう1本のエイプリル・フール記事の題名は、「意地悪なマーヒーが私の運命を閉ざした('Insecure Mahi sealed my fate')」。ヴィーレーンドラ・セヘワーグというクリケット選手がいるが、スランプに陥った彼は1年ほどインド代表から外されていた。だが、2008年に入ってから試合に出場するようになり、先日は南アフリカ共和国とのテストマッチに出場してトリプル・センチュリー(300ラン)の偉業を達成し、完全復活を印象付けた。この記事は、トリプル・センチュリー達成直前にヴィーレーンドラが母親に送ったEメール(偽物)に綴った心情をネタにしている。記事の中には、インド代表チームの監督グレッグ・チャペル、ワンデーマッチ(ODI)とTwenty20キャプテンのマヘーンドラ・スィン・ドーニー(愛称マーヒー)、それにテストマッチ・キャプテンのアニル・クンブレーの名前も出て来る。
ヴィーレーンドラ・セヘワーグは、2007年初めの南アフリカ共和国ツアー以来、テストマッチに1年間出場できなかった。先日トリプル・センチュリーを達成した後、彼は「チームから外されたことでだいぶ傷付いた」とコメントし、それがヘッドラインを飾った。CTは、セヘワーグがテストマッチでのカムバック直前に母親に宛てて書いたEメールを独自に入手した。セヘワーグは、「過去のことは過去のこと」を信じているが、CTは、屈辱を味わった後に何が彼のカムバックのきっかけとなったのかを示すため、彼のEメールの一部をここに紹介する。
お母さん
僕がチームから外されて数ヶ月が過ぎました。今では僕は、試合にも出られませんし、保証ももらえません。まるで、バウンダリー(4ランまたは6ランの高得点ショット)を打とうとしているのに、デッドボールだけが来るようです。
アニル・クンブレーがいなかったら、僕は長らく落伍していたでしょう。お母さん、僕はこの重荷を胸から下ろす必要があります。もし他に誰も信じてくれないとしても、お母さんだけは、僕が人生の中で一度も不真面目な態度を取ったことがないことを信じてくれるでしょう。お母さんはこんな新聞記事を送ってくれました。「チャペル監督は、ダーバンのテストマッチの前日、特別召集したにも関わらずセヘワーグが練習に現れなかったことに怒っている。チャペル監督と生物力学者のイアンとアシスタントコーチのフレーザーが練習場を訪れたとき、現地時間の午後6時半(インド時間の午後10時)に来ると言ったにも関わらずセヘワーグが来ていないことに気付いた。報告によると、セヘワーグは後にチャペル監督に対し、練習する気が起こらなかったと語った。」
お母さん、クリケット選手になりたくて、お父さんがやっている種苗と麦のビジネスの道を進まないというリスクを冒した僕が、練習する気が起こらないなんて言うと思いますか?人生に嫌気が差して来た。でも、いつか試合で活躍して、僕を中傷する奴らを見返してやりたいと思います。お母さん、僕に祝福を下さい。
世間の認識と違って、僕はいつもチャペル監督と良好な関係を築いて来ました。数ヶ月前、僕は彼に、コーチとして苦労しているようだと言いました。チャペル監督は僕の考えではココナッツのようです。外はとても硬いけど、中はとても柔らかい。マネージメントの利害関係のせいで、彼はチームのためにベストなことを実行できずにいます。
それに、マーヒーが噂を広めて世間が僕を敵視するようにしています。彼は生意気です。ベテラン選手はよく個人的にマーヒーの高飛車な態度に不平を漏らします。マーヒーは、セレクターが違う主張をしているにも関わらず、試合当日の朝にチームの編成を変えたりします。こういう行為がチームのモラルを破壊します。一番驚いたのは、マーヒーは実はストレス解消のために美容室へ行っているということです。クンブレーによると、マーヒーはチームが負けた日に髪の色を変えるようです。もし試合に勝つと、彼は髪を洗いません。マーヒーはシリーズ中入浴もしないのです。それが、彼が大量のデオドラントを持っている理由です。
彼は美容室に頼りっきりなので、スタイリストを手なずける必要があります。だから、彼はインタビューに答えるとき、いつも彼女の名前を出します。そうするとどうなるか・・・翌日、全ての新聞に彼のコメントが載るんです!
お母さん、僕はジャートです。僕はこういうナンセンスなことに我慢がなりません。マーヒーはあるとき僕に、髪を染めるように言いました。僕は拒否しました。このちょっとした決断が、僕からレギュラーを奪いました。でもマーヒーはずる賢い奴です。彼は僕を引きずり下ろそうとしながらも、本心は誰にも知られないように注意しました。彼は最も困難な状況で僕にボールを投げるように指示して、全世界が僕の投球に注目するように差し向けます。髪を伸ばして赤く染め、彼の言いなりになることを拒否したからこんなことをされるのでしょうか?若い奴らは何も言いません。マーヒーが髪をピンク色に染めるように言っても、彼らはそれに従うでしょう。でも僕はそんなことはできません。意地悪なマーヒーが僕の運命を閉ざしたのです。
最近、クンブレーが僕に、キャプテンとしてのマーヒーはどう思うかと聞いて来ました。僕は大きな疑問を抱いていました。僕たちの意見は、マーヒー・バブルはもうすぐはじけるということで一致しました。お母さん、僕は一人の選手ですし、自分の立ち位置を知っています。チームから外された理由は、僕のフォームとはほとんど関係なく、マーヒーの陰険な性格に関係があります。彼は、僕がキャプテンになることを恐れています。全ては、自分の成功のチャンスを最大限に拡大するため、マーヒーによって企てられたことです。そしてそれは、僕の成功の妨げになっています。僕はメディアにそれを暴露しなければなりません。実は、ある出版社から暴露本の出版のオファーが来ています。お母さんとそれについて相談したいと思っています。
あなたの愛する息子、ヴィールーより
体裁としてはカムバックを果たしたヴィーレーンドラ・セヘワーグが取り上げられているが、主にネタとなっているのは、人気沸騰中のクリケット・スター、マヘーンドラ・スィン・ドーニーである。あたかもドーニーが彼のキャリアを台無しにしたかのように語られている。一方、テストマッチのキャプテンを務めるアニル・クンブレーは、恩人扱いされている。一応説明しておくが、クリケットには現在主に3種類の試合形態がある。5日間続く伝統的なテストマッチ、1日で決着が付くワンデー・インターナショナル(ODI)、昨年から本格的に始まった数時間試合のTwenty20である。インド代表のキャプテンは試合形態によって分担されており、現在テストマッチのキャプテンはアニル・クンブレー、ODIとTwenty20のキャプテンはマヘーンドラ・スィン・ドーニーが務めている。また、ヴィーレーンドラ・セヘワーグが所属するカーストが記事の中で言及されている。彼は、ハリヤーナー州を中心に分布するジャートである。ジャートは主に農業に従事しているが、ラージプートに準ずる戦士階級でもあり、王国を築いたこともある。ジャートは田舎者だが質実剛健なイメージがあり、長髪にしたり髪を染めたりと言ったナンパなことはジャートの威信にかけてしたくない、という設定なのだろう。実際にセヘワーグがそんなことを思っているかどうかは分からない。
バンガロール・タイムスのエイプリル・フール記事は、「サイフとカリーナーが結婚!(Sif-Kareena get hitched!)」。カルカッタ・タイムスの最初の記事と同様に、ボリウッド・スターの結婚ネタである。パタウディー王家の御曹司でボリウッド・スターのサイフ・アリー・カーンと、「映画カースト」カプール家の末裔カリーナー・カプールは昨年末頃から付き合い出し、ボリウッドのホットな話題のひとつとなっている。キャリア的にも2人ともここのところ調子がいい。
皆が「するのか、しないのか?」と考えている中、ボリウッドでもっともホットなカップル、サイフ・アリー・カーンとカリーナー・カプールが、遂に全ての噂をかき消した。2人は3月31日の午前にマハーバレーシュワルの寺院で極秘に結婚式を挙げたようだ。
2人と親しく、結婚式にも出席した情報筋によると、カリーナーは金糸の刺繍の入ったゴージャスな真紅のレヘンガーを着ており、サイフは茶色のアチカンを着ていた。カリーナーの首には数百ものダイヤモンドが散りばめられたネックレスが輝いていたが、噂によるとそれはサイフが南アフリカ共和国の最高級ブティックで彼女のためにオーダーメイドしたもののようだ。
結婚式に出席したのは、カリーナーの姉のカリシュマー、その夫のサンジャイ・カプール、両親のバビターとランディール・カプール、サイフの姉妹のサバー&ソーハー・アリー・カーンなどである。彼らは式の前日に2人が結婚を決めたことを知らされたようだ。カリーナーの親友アムリター・アローラーとそのボーイフレンドのウスマーン・アフザルはちょうど先週ロンドンからやって来ており、2人の結婚式に出席した唯一の友人となった。
しかし、驚くのはまだ早い。情報筋によると、カリーナーは左肩にデーヴナーグリー文字で「サイフ」とタトゥーを入れていた。彼女はノースリーブのブラウスを着ていたため、人々の目に留まったのである。寺院で結婚式を挙げた後、幸福な表情をした新婚カップルはマハーバレーシュワルのモスクに立ち寄り、もう一度手短にニカー(イスラーム式結婚式)を挙げたとされている。バンガロール・タイムスは連絡を取ろうと試みたが、彼らの電話はスイッチオフだった。
マハーバレーシュワルとは、マハーラーシュトラ州の有名な避暑地である。サイフ・アリー・カーンはイスラーム教徒、カリーナー・カプールはヒンドゥー教徒であり、2人はヒンドゥー教寺院とイスラーム教モスクで結婚式を挙げたことになっている。レヘンガーとはインドの伝統的なロングスカートで、アチカンとはインド人男性がよく着ている、学生服を長くしたような服である。カリーナーが「サイフ」とタトゥーを入れたという記述は、サイフがカリーナーと付き合い始めてから左腕に「カリーナー」とタトゥーを入れた事実に基づいたネタである。佳作といったところか。
最後になるが、ナーグプル・タイムスのエイプリル・フール記事は、「本日シャールク・カーンがナーグプルにやって来る!(Shah Rukh Khan
in the city today!)」である。こちらはデリー・タイムスなどと同様にIPLと関連している。ナーグプルは、IPLの拠点となる8都市には入っていないが、ナーグプル在住のビジネスマンが、シャールク・カーン所有のコールカーター・ナイト・ライダースのシェアの一部を購入し、ナーグプルもIPLに関わることになったと大々的にデタラメを載せている。その偽記事によると、4月1日にシャールク・カーンが正式に契約を交わしにナーグプルへやって来ることになっているようだ。つまり、シャールク・カーンのIPLチームは、コールカーターとナーグプルの二都市を拠点とするチームになるということで、ナーグプルでも試合が行われる可能性が出て来る。記事の内容は以下の通りである。
ハレルヤ!遂にナーグプルも煌びやかでグラマーなクリケットの世界と関係を持つことになった。なんとボリウッドの皇帝シャールク・カーンが本日ナーグプルにやって来て、当地在住のビジネスマン、スレーシュ・シャルマーと会い、シャールク・カーン所有のIPLチーム、コールカーター・ナイト・ライダースへの多大な投資取引を結ぶ。ナーグプル・タイムス(NT)は、ナーグプルの著名人にインタビューをし、このエキサイティングな新展開がこの地域の経済・社会にどのような影響を与えるか聞いてみた。
「シャールクにはナーグプルに投資をしてもらいたい」
シャールク・カーンのナーグプル訪問の原因となった張本人、スレーシュ・シャルマーは、今のところキュウリのようにクールである。彼に、クリケットへの投資についてどう思っているのか聞いてみたところ、彼は、「シャールク・カーンのチームは今とても人気があり、最大限の人々に働きかけるには最上の手段だ」と述べた。ずばりシャールク・カーンとの共同事業への投資額を質問すると、彼は、「今のところ詳細を明らかにすることは許されていない」とだけ答えた。我々の情報筋によると、スレーシュ・シャルマーはコールカーター・ナイト・ライダースにおよそ3,7億ルピーを投資したとされる。シャールク・カーンのナーグプル訪問の詳細について聞いてみると、彼は、「彼の旅程を明かすことはできない。セキュリティーの問題から、全てのことをとても慎重に行わなければならない。私は彼に街を案内して、クリケット関係のイベントのための永続的な会場を選んでもらうつもりだ。彼にはナーグプルに投資をしてもらいたいとも思っているし、有名なオレンジを味わってもらいたいとも思っている。」
「ナーグプルにとって大ニュース」
専門家によると、この出来事によって「オレンジ・シティー」ナーグプルは新時代の幕開けを迎えることになるとのことである。酪農開発漁業宗教資産委員会省のアニース・アハマド大臣は、「これはナーグプルにとっていいニュースだ。このような出来事は初めてであり、大きな成果をもたらすだろう。しかし、長期的な成果のためには、関係する企業の真摯さと献身が必要だ。今までの我々の経験では、ビジネスマンが突然発言を翻し、トラブルが始まることが多い。」
「よいホテルとレストランが至急必要」
全体的に興奮の空気で覆われているが、特定のビジネスに関わっている人々の中には、このような巨大な計画の成果を街が享受する前に、解決しておかなければ問題がいくつかあると感じている人もいる。建築家のヴィーレーンドラ・カーレーは、「多くの報道陣、スター、上流観光客がナーグプルにやって来るようになるだろう。しかし、ここにはそのような高級志向の来訪者を迎えるような5つ星ホテルもなければ、国際レベルのレストランもない。それが大きな問題となるだろう」と語っている。
「世界地図にナーグプルが」
建設業のNクマールは、このようなパートナーシップのアイデアに興奮し、「このような巨大な事業にナーグプルが関わることは、我々にとってとても誇り高いことだ。ナーグプルが世界地図に載ることになり、地域は著しい発展を遂げるだろう」と述べた。
「数え切れないほどのセレブが!」
事業家のモニカ・バーグワーガルは、「ナーグプルのような小都市が恩恵を被るときが来た。ナーグプルを拠点にするビジネスマンがIPLのチームに投資をすることで、この街の人材が才能を発揮するチャンスに恵まれるようになる。もちろん、シャールク・カーン以上のセレブリティーはいないが、将来さらに多くのセレブがナーグプルを訪れることになるだろう」と語っている。
「遂に地元の人材に希望の光が」
著名な心臓医ジャスパール・アルネージャーは、コールカーターのチームが近々ナーグプル出身の選手を採用することになり、ナーグプル市民が同チームを応援する絶好の理由が生まれるだろうと語っている。彼は、「ここの人材が選ばれるようになるだろうし、もちろん、スターの存在感も高まる。そうなれば、ナーグプルにとって鼻が高い」と述べた。
「ただの金儲けだ」
だが、この動きに対し楽観的ではない懐疑主義的な人々もいる。ナーグプル初の女性市長クンダー・ヴィジャヤカルは、このようなパートナーシップは、草の根レベルで行われて初めて街と地域の利益になると感じている。「私は、シャールク・カーンが、もし十分な利益が得られないならIPLから撤退すると言ったとの記事を新聞で読んだ。私の考えでは、このようなパートナーシップは市民の利益と、ビジネスチャンスの創出と、地元の才能の育成に結び付かなければならない。そうして初めてそれは目的ある事業となるだろう。」元クリケット選手のプラシャーント・ヴァイディヤは、クリケットはプロモーションのためにいかなるセレブリティーも必要としてないと語っている。「これは、関係者の個人的な利益を推進するだけのただの金儲けだ。私には、これがクリケットや街の将来を変えるとは思えない。一瞬だけナーグプルのグラマー度が上がるだけで終わるだろう。」
「たで食う虫も好きずき」
ビジネスマンのマノージ・ジャヤスワールは、「投資は巨額のものになるだろう。・・・おそらく、街の発展に役立つだろう。ナーグプルはハプニングな場所になるだろう」と述べた。街のビジネスマンの間で、IPLチームのシェア購入が嫉妬と競争の感情を巻き起こしたりしているのだろうか?彼は、「ナーグプルのどの企業もIPLのシェア購入に興味を示していない」と答えた。ならば、スレーシュ・シャルマーはIPLに投資したことで巨大なリスクを冒したのだろうか?これに関して彼は、「私はそんなことは言っていない!」と語っている。
「シャールク・カーンの影響はない」
セントラル・レールウェイのアシュワニー・クマール副社長は、たとえシャールク・カーンであれ誰であれ、彼の部署が影響を受けることはないと感じている。彼は、「あちこちから数千人の訪問者が来たとしても、鉄道のような巨大な組織にとっては何の違いもない」と語る。クリケット・シーズン中に特別列車を運行する予定は?「我々に特別列車を運行する余裕があるとは思えない。」
マハーラーシュトラ州東部の都市ナーグプルはインド亜大陸の中心部にあるため、ナーグプルに住む人々は自分の街を「インドのヘソ」と呼んで誇りに思っている。人口で見れば、ナーグプルはインドで13番目に大きい都市になるが、逆の言い方をすれば、かろうじて10大都市に入れていない、中小規模都市の一員である。また、オレンジで有名な都市で、オレンジ・シティーの異名を持つが、それがどの程度インド人に知られているのかは疑問である。ナーグプル周辺地域はヴィダルバと呼ばれるが、この辺りは借金苦に悩んだ農民の自殺が多い地域として知られ、決していいイメージは持たれていない。歴史的にも度々表舞台に立って来た重要な地域だが、インドの他の大都市に比べていまいち存在感の薄い街だと言わざるをえない。その中途半端なステータスが余計にナーグプル市民の自尊心と愛郷心を促進するようで、上のエイプリル・フール記事からそれがひしひしと感じられた。今年のTOIのエイプリル・フール記事の中では地域密着度がもっとも高く、微笑ましかった。
当然のことながら、いくら不真面目な記事の多いタイムス・オブ・インディア紙と言えど、世界最大の英字新聞のひとつに数えられるだけあって、エイプリル・フール記事をほったらかしにしておくことはできない。TOI各紙のエイプリル・フール記事には、必ずネタ晴らし記事も用意されている。偽記事の最後に「関連記事○ページ」と書かれており、それを見ると、「実はエイプリル・フールの偽記事でした。ハッピー・エイプリル・フール・デー!」みたいに種明かしがされている。だが、ナーグプル・タイムスのネタ晴らし記事だけはいろいろ凝っていて面白かった。
マーク・トウェインは、「4月1日は、我々が1年の他の364日に何であるのかを思い出す日である」と語った。ヒーホー!ヘヘヘ!陳腐な表現で申し訳ない、だが、表の記事を読んで盛り上がってしまった人たちは、まんまと騙されてしまった。どうだっただろう!正直言って、私たちは褒められるべきだ。なぜなら私たちは実に真面目にこの記事を考案したからだ。読者がシャールク・カーンとスレーシュ・シャルマーの契約に反応するように、文章のどこにもクスクス笑いや漏れ笑いが表れないように努力したのだ。この「共同事業」への協力に同意してくれたシャルマー氏も賞賛されるべきだ。なぜシャルマー氏がこの遊びに付き合ったかもしも不思議に思うなら、彼自身のコメントを読んで欲しい。「エイプリル・フールは友人たちとふざけ合って楽しむ日だ。ナーグプル・タイムスがこのアイデアを持って来たとき、とてもユーモラスなコンセプトだったために即座にイエスと言った。多分、この過程で私は敵を作ってしまったかもしれない。だが、彼らは話を鵜呑みにしないと信じている。万一の事態に備えて、今日一日私は携帯電話のスイッチを切っておくことにする。」最初、アニース・アハマド大臣は、シャールク・カーンのナーグプル訪問が、地域や関係組織に利益になることに疑問を呈した。しかし、彼は外交的にそれを支持した。Nクマールは最初、シャールク・カーンは多分インドにいないだろうと言った。だが後に、この取引によってヴィダルバのイメージが変わるだろうと確言した。なるほど、人は生き、学ぶものだ!
唯一ジャスパール・アルネージャーだけが、このエピソード全体の信憑性について疑問を持った人物だったことは特筆しておかなければならない。彼はこの件について意見を述べた後、我々に電話をし、これは悪ふざけなのかを確認して来た。しかし、そのときまでには既に手遅れになっていた・・・。
もし万一、このジョークを見て立腹したり、うんざりしたり、いらいらしたりしたならば、私たちは、あなたを敬慕しており、ジョークは清潔で健康的な悪戯だったと申し上げたい。あなたは真の笑われ者だ。今日は人を騙すチャンスもあれば、そういう習慣もある!
つまり、エイプリル・フール記事の中に出て来てコメントを寄せた人々は実在の人物で、しかもコメントも本当のものだったということだ。スレーシュ・シャルマー以外、シャールク・カーンがナーグプルに来て、ナーグプルがIPLに関与することになることが嘘の情報であることは知らされておらず、ナーグプル・タイムスに対し、それについて大真面目に自分の見解を述べたのである。それが嘘であると気付いたのは1人しかおらず、しかも気付いたのはしばらく後のことだった。よって、本当の4月馬鹿は読者ではなく記事に出て来た人々ということになる。そうやって見ると、ナーグプル・タイムスのエイプリル・フール記事はとても面白い。
デリー・タイムスのエイプリル・フール記事は近年レベルが下がってしまったが、こうやってインド各都市のエイプリル・フール記事を見てみると、けっこう頑張っているところもあり、少し安心した。ネタになっているジャンルを見ると、やはり映画とクリケットである。インドの現代文化を理解するためには、この2つの知識が不可欠だということが、4月1日の新聞からもよく分かる。
最近インド映画のDVDがやたらと安くなった。かつては1枚1,000ルピー以上していたものだが、今では30ルピー前後で手に入るタイトルがたくさん出て来た。はっきり言って音楽CDよりも安い。DVD価格破壊の張本人が、モーゼル・ベア(Moser
Baer)というインド企業である。モーゼル・ベアは世界有数の光記憶媒体製造会社だが、最近ホームビデオ販売事業にも進出し、インド映画各種タイトルのホームビデオ販売権を買い取って廉価なVCD・DVDを販売し始めた。これは当然のことながら海賊版撲滅が目的である。海賊版氾濫の原因のひとつはVCDやDVDなどの光記憶媒体の普及にあり、それを製造する企業として責任を果たしている形になっている。そのモーゼル・ベアが今度は映画制作事業にも進出した。その第一弾が「Shaurya」である。本日より公開された。
題名:Shaurya
読み:シャウリヤ
意味:勇気
邦題:勇気
監督:サマル・カーン
制作:モーゼル・ベア・インディア
音楽:アドナーン・サーミー
作詞:ジャーヴェード・アクタル
出演:ラーフル・ボース、ジャーヴェード・ジャーファリー、ミニーシャー・ラーンバー、ディーパク・ドーブリヤール、ケー・ケー・メーナン、スィーマー・ビシュワース
備考:PVRアヌパムで鑑賞。

左から、ミニーシャー・ラーンバー、ジャーヴェード・ジャーファリー、
ラーフル・ボース、ケー・ケー・メーナン
| あらすじ |
2007年5月8日、カシュミール地方でインド陸軍のジャーヴェード・カーン大尉(ディーパク・ドーブリヤール)が上官のヴィーレーンドラ・ラートールを射殺するという事件が起きる。ジャーヴェードは即座に逮捕され、軍法会議にかけられることになった。
陸軍弁護士のアーカーシュ・カプール少佐(ジャーヴェード・ジャーファリー)は、恋人のナンディニーと婚約したばかりであったが、軍法会議の検察官に任命されてカシュミールへ赴任することになった。続けて、親友の陸軍弁護士スィッダーント・チャウドリー(ラーフル・ボース)もジャーヴェードの弁護士としてカシュミールへ赴任する。
スィッダーントは陸軍での仕事に満足しておらず、バンジージャンプのインストラクターになることを考えていた。今回の仕事も適当に済まそうとしていた。だが、取材に来たジャーナリストのカーヴィヤ・シャーストリー(ミニーシャー・ラーンバー)が、インド陸軍の英雄ルドラ・プラタープ・スィン准将(ケー・ケー・メーナン)が現場に居合わせたという記事を新聞に掲載してしまったことで、世間の注目を集めてしまう。スィッダーントは本腰で裁判に取り組まなければならなくなった。
スィッダーントはジャーヴェードやプラタープ准将に会い、現場も訪れ、次第に事件に疑問を感じ始める。また、カーヴィヤもジャーヴェードの母親(スィーマー・ビシュワース)に会ったりして独自の取材を進めていたが、2人は協力して事件に取り組み始める。殺されたラートールの妻に会ったことで、スィッダーントはジャーヴェードの無罪を確信する。だが、証拠がなかった。唯一、現場に居合わせた兵士が何かを知っていそうだったが、彼は行方をくらましてしまう。また、カーヴィヤは国防関係の情報を収集していた疑いを持たれ、逮捕されてしまう。
だが、行方不明になった兵士はある日スィッダーントを密かに訪れ、事件の真相を明らかにする。ラートールは地元のイスラーム教徒に対し残虐な態度を取っていた。事件の日、彼は無実の村人たちを外に並ばせて、テロの嫌疑をかけて殺害した。しかも少女にまで手をかけようとした。それを見たジャーヴェードは、ラートールを射殺したのだった。
また、スィッダーントは、ラートールと親しかったプラタープ准将が、イスラーム教徒の使用人に一家を惨殺されるという悲劇に直面し、イスラーム教徒全体に激しい憎悪を抱いていることを突き止める。証人席に呼ばれたプラタープ准将はスィッダーントに誘導されてその憎悪を露にし、事件の新たな側面が明らかになる。プラタープ准将は特定のコミュニティーに対する差別的発言によって逮捕される。
軍法会議の判決が出た。ジャーヴェードは無罪となり、復職を許された。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
「勇気」という題名や、軍服を着た登場人物から、戦争物の映画かと思ってしまうが、実際は軍法会議を中心にした裁判物の映画だった。主人公は陸軍弁護士という日本人にはあまり馴染みのない職業。インドには軍隊専属の司法職があるようだ。サマル・カーン監督自身が軍隊経験を持っているようで、軍隊内部の描写は非常にリアルである。
メッセージは明確だった。国家の平和と統合の名の下に特定のコミュニティーをテロリストや危険分子と決め付けて弾圧することに対する批判と、正義のために全てを投げ打って行動する勇気であった。勇気とは人を殺すことではなく、人を守ることにあるとの主張もあった。言い換えれば、国境を守るプラタープ准将の厳しく残忍な勇気と、正義のために上官をも射殺するジャーヴェードの勇気の激突であった。だが、そのメッセージまでの持って行き方は多少強引かつ急ぎすぎで、映画の完成度を損なっていた。
映画の最大の見所はケー・ケー・メーナンの演技だ。扱いとしては特別出演だが、彼が演じるプラタープ准将は映画の核となっていた。管理ライン(LOC)上でスィッダーントと交わす会話、ディナーの席でスィッダーントに語りかける静かだが力強い言葉、そして軍法会議に出頭したときの態度の豹変振り、全てがゾクゾクする迫力を持っていた。
ジャーヴェードを演じたディーパク・ドーブリヤールも迫真の演技をしていた。彼は「Maqbool」(2003年)や「Omkara」(2006年)にも出演していたようだが、目に留まったのは本作である。軍人らしく常に背筋をピンと伸ばし、死刑が求刑されている軍法会議に勇気を持って向かう姿は、彼が只者ではないことを表していた。
コメディアンとしてのイメージの強いジャーヴェード・ジャーファリーもシリアスな役をしっかりと演じていた。今回残念だったのはラーフル・ボースである。ヒングリッシュ映画の申し子ラーフル・ボースは、個人的に注目している俳優の一人なのだが、最近の彼の演技からはミーハー臭が漂う。持ち味を活かせていない気がする。
ヒロインのミニーシャー・ラーンバーは、急に老けてしまった印象である。「Yahaan」(2005年)でデビューしたときは繊細な顔の作りをした女優と感じたが、今ではただのヒステリックなおばさんになってしまった。だが、演技は悪くなかった。
舞台はカシュミールだが、撮影はヒマーチャル・プラデーシュ州で行われたようだ。本場でロケをしていないことで、カシュミール地方特有の美と緊張感が再現できていなかったと感じた。
音楽はアドナーン・サーミーだが、印象に残った挿入歌はなかった。
「Shaurya」は、ケー・ケー・メーナンを初めとした俳優たちの緊迫した演技を楽しむことができるが、全体的な完成度は最高とは言えない。完全に都市中産階級をターゲットにしたシリアスな映画であり、この出来だと興行的には沈没以外ないだろう。
4月1日から8日まで、デリーのインディラー・ガーンディー国立芸術センター(IGNCA)において、「Aqeedat Ke Rang(イスラーム教の色)」と題したインドのイスラーム教芸術に関するイベントが開催されている。イベントは3部構成で、セミナーの部(日中)、展示の部(終日)、パフォーマンスの部(夕方)に分かれている。展示の部は8日まで続くが、パフォーマンスの部は今日が最終日であった。そのトリを飾ったのが、著名な演劇作家ハビーブ・タンヴィールのウルドゥー語演劇「Agra
Bazar」であった。「Agra Bazar」はインドの演劇史の中でもっとも重要かつ有名な演目のひとつである。1954年の初演からデリーで何度も公演されており、ずっと見てみたかったのだが、タイミングが合わなくて鑑賞する機会に恵まれなかった。今回こそは見てみようと思っていたのだが、あいにく午後から季節外れの大雨が降り出し、またも諦めそうになった。だが、午後6時頃には何とか降り止んだので、勇気を振り絞ってインド門近くのIGNCAまで向かうことにした。なぜ勇気を振り絞らないといけないか、日本に住んでいる人には理解不能かもしれないが、大雨が降るとインドの道路はバイクにとってとんでもなく危険な状態となるので、雨の日はあまり出掛けないようにしているのである。
去年の同じ頃、IGNCAでは演劇「City of Djinns」が上演された(参照)。敷地内にあるマーティー・ガルという変わった形をした建物を利用した野外劇で、インドの魅力が詰め込まれた素晴らしい演劇になっていた。今回はマーティー・ガルを利用してはいなかったものの、やはり野外に舞台が用意され、演劇「City
of Djinns」を想起させるようなインドの色に満ち溢れた魅力的なセットが組まれていた。早めに行ったことが幸いし、前方中央のかなりいい席に座ることができた。
午後7時半から開演の予定であったが、インドで時間通りに何かが始まることは稀で、午後8時過ぎにやっと始まった。まずはカシュミールから来た人々による、ナート・カーニーとダルード・カーニーというイスラーム教の宗教賛歌の披露があった。モスクやダルガーで歌われているもののようだ。

ナート・カーニー
午後8時40分頃にやっと「Agra Bazar」が始まった。この演劇は、題名が示すように、アーグラーの市場を舞台にしている。市場を舞台にしているだけでなく、1954年の初演当時、この演劇は密閉された劇場ではなく、本当に市場で上演されたらしい。今回「Agra
Bazar」は野外で上演されたこともあり、初演当時の雰囲気を少し再現できていたかもしれない。さらに、初演で演技をしたのは、ジャーミヤー・ミッリヤー・イスラーミヤー大学の学生を除けば、オークラー村に住む演劇経験のない村人たちであった。劇中には、市場で物を売る村人がたくさん登場するが、おそらくそれらの役を村人たちが演じたのであろう。また、当時デリーの演劇界は西洋の演劇によって独占されており、インドの文化や伝統を基盤としたオリジナルの演劇はほとんど見当たらなかった。あらゆる意味で「Agra
Bazar」は当時の常識を覆す演劇であった。このような破天荒なアイデアは、ハビーブ・タンヴィールの生い立ちを見れば理解ができる。彼は現チャッティースガル州のラーイプル生まれで、幼い頃から農村の素朴だが華やかな文化に影響を受けて育って来た。「Agra
Bazar」にも、祭り、大道芸、踊りなど、カラフルなインド文化の魅力がふんだんに盛り込まれている。

「Agra Bazar」
ヒジュラーたちのダンス
「Agra Bazar」のもうひとつの特徴は、18世紀から19世紀初めのアーグラーに住んだウルドゥー語詩人ナズィール・アクバラーバーディーの詩を題材にしていることである。ナズィール・アクバラーバーディーは1735年にデリーで生まれたとされるが、当時はムガル朝の衰退期であり、デリーは外来勢力の相次ぐ侵略によって混乱の時期を迎えていた。1757年のアマハド・シャー・アブダーリーのデリー侵略を機にナズィールの家族はアーグラーに移住し、そこに住み着く。ナズィールの詩の特徴は、庶民の日々の生活に密着した詩を作ったことである。ヒンドゥー教、イスラーム教、スィク教の祭りから始まり、ローティー、ダール、キュウリなどの食べ物まで、平易な言葉と共に自由な想像力に満ちた活き活きとした詩を書いた。だが、ウルドゥー語文学では高尚なテーマを扱った難解な詩が好まれる傾向があり、彼の作品は生前も死後も文壇の中ではなかなか評価されなかった。彼が再評価されたのは現代に入ってからである。そしてそのひとつのきっかけとなったのが、ハビーブ・タンヴィールの「Agra
Bazar」であった。

「Agra Bazar」
キュウリ売りがナズィール作のキュウリの詩を歌って踊る
「Agra Bazar」内にナズィール・アクバラーバーディー自身は登場しないが、アーグラー市場の人々の会話の中で彼の名前が何度も登場し、彼の詩が詠まれたり、音楽と共に歌われたりする。演劇は、アーグラー市場のキュウリ売り、ラッドゥー(お菓子)売り、スイカ売りの会話で始まる。すっかり景気が悪くなり、誰も物を買ってくれなくなってしまった。そこでキュウリ売りは、誰か詩人に気の利いたキュウリの宣伝文句を作ってもらって売上倍増を計画する。市場には本屋があり、街の文人たちの溜まり場となっていたが、彼らはキュウリ売りなど相手にしない。しかし、凧売りからナズィール・アクバラーバーディーの話を聞く。本屋や文人はナズィールの詩を馬鹿にしていたが、市井の人々の間では大人気であった。キュウリ売りは早速ナズィールを訪ね、キュウリの詩を作ってもらう。それを歌いながら市場でキュウリを売ったら、飛ぶように売れ出した。それを見てラッドゥー売りやスイカ売りもナズィールに詩を作ってもらって大喜び。こんなストーリーである。これに、ホーリー祭、ムジュラー(踊り子による踊り)、猿回しや熊使いなどのミュージカルが加わり、非常にカラフルかつパワフルな演劇になっていた。

「Agra Bazar」
本屋で会話をする人々
ハビーブ・タンヴィールの演劇は初めて見た。ハビーブ・タンヴィールという名前を聞いて、勝手にもっと高尚で難解な教養層向けの演劇を想像していたのだが、インドの一般庶民への愛情が溢れた真にインド的な演劇になっていた。そこで賞賛されていたのは、上流階級の「ピュア」な文化ではなく、一般庶民のエネルギッシュな混交文化であった。また、猿回しの芸などによって、当時の時代背景がそれとなく描写されていて、巧みだと感じた。また、人々の噂の中で、サウダー、ミール、ガーリブなど、ナズィールと同時代のウルドゥー語詩人たちの名前にも触れられており、文学史的な時代背景もよく提示されていた。

「Agra Bazar」
猿回し
会場には御歳84歳のハビーブ・タンヴィールも出席しており、上演終了後は舞台に上がって挨拶をしていた。彼は演技をした人々に対し、「師が飛ぶのではない。弟子たちが師を飛ばすのだ」と最大限の賛辞を送っていた。

ハビーブ・タンヴィール
「Agra Bazar」の上映時間は2時間で、上演が終わったときには午後11時を回っていた。実は劇の途中から雲がゴロゴロと鳴り出し、いつまた雨が降り出してもおかしくない状況だったので多少落ち着かなかったのだが、神様も演劇を楽しんでいたのか、演劇終了まで何とか持ちこたえた。そして演劇が終了した途端にパラパラと雨が降り出した。幸い、大雨にはならず、すぐに止んだが、それはまるで天までもが劇を賞賛しているかのようであった。
ちなみに、4月8日まで開催されている「Aqeedat Ke Rang」の展示の部では、イスラミック・カリグラムが展示されている。偶像崇拝を否定するイスラーム教では絵画を描くことが禁じられているが、その代わりカリグラフィーが発達し、しかもペルシアやインドでは文字によって絵を描くという抜け道文化が花開いた。それはアラビック・カリグラムなどと呼ばれている。現代で言う絵文字みたいなものだ。4月8日まで、IGNCAのマーティー・ガルでは、まとまった数のイスラミック・カリグラムが展示されている。落書きみたいなものから芸術作品と呼べるものまで、圧巻のコレクションである。

アラビック・カリグラム
| ◆ |
4月6日(日) Khuda Kay Liye |
◆ |
インドとパーキスターンというと仇敵同士のイメージがあるが、二国間の文化交流は割と活発である。映画界ひとつを取ってみても、パーキスターン人俳優がボリウッド映画に出演したり、インド人俳優がパーキスターンの映画祭に出席したりしている。1965年の第二次印パ戦争を機にインドではパーキスターン映画の上映が禁止となり、パーキスターンではインド映画の上映が禁止になったが、この点でも雪解けが進んでおり、最近ではボリウッド映画の「Taare
Zameen Par」(2007年)と「Welcome」(2007年)がパーキスターンで上映された。そして遂に、43年振りにパーキスターン映画がインドで公開されることになった。その記念すべき映画は、2007年7月20日にパーキスターンで公開され、同国映画史上最大のヒット作となったウルドゥー語映画「Khuda
Kay Liye」(英語の副題は「In the Name of God」)。予算6,000万ルピー(パーキスターン・ルピー)をかけて制作され、パーキスターンで7,000万ルピー以上の興行成績を上げただけでなく、カイロ国際映画祭で特別審査員賞を受賞するなど、国際的にも高い評価を得ている。インドで43年振りに公開されるパーキスターン映画としては申し分ない。また、インド人俳優ナスィールッディーン・シャーも出演しており、それもインド公開のための好材料となっている。ちなみに、2004年に「Khamosh
Pani」(2003年)という映画がインドで公開された。これは一部では「パーキスターン映画」として扱われているのだが、正確にはドイツとフランスとパーキスターンの合作で、純粋なパーキスターン映画ではないようだ。
題名:Khuda Kay Liye
読み:フダー・ケ・リエ
意味:神のため
邦題:神よ!
監督:ショエーブ・マンスール
制作:ショエーブ・マンスール、ジオ・フィルムス
音楽:ロハイル・ハヤート(BGM)
作詞:ショエーブ・マンスール、ブッレー・シャー、ファイザー・ムジャーヒド
出演:シャーン、ファワード・カーン、イーマーン・アリー、オースティン・セイヤー、ラリー・ニューマンJr.、ラシード・ナーズ、ナイーム・ターヒル、スィーミーン・ラヒール、フマーユーン・カーズミー、アンジェラ・ウィリアムス、アレックス・エドワーズ、ハミード・シェーフ、ルーファス・グラハム、ナジーブッラー・アンジュム、アーユーブ・コーサー、ナスィールッディーン・シャー
備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。
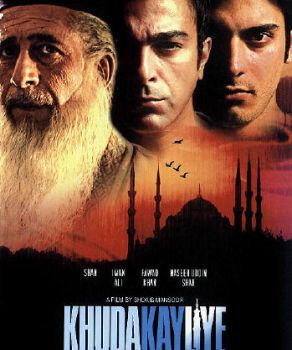
左から、ナスィールッディーン・シャー、シャーン、ファワード・ハーン
| あらすじ |
パーキスターンのラーハウル(ラホール)に住む兄弟マンスール(シャーン)とサルマド(ファワード・ハーン)はデュオを組んで音楽の道を志していた。だが、弟のサルマドは、イスラーム教教義の厳格な遵守をイスラーム教徒の義務と考える神学者マウラーナー・ターヒリー(ラシード・ナーズ)の影響を受け、イスラーム教原理主義者になる。ターヒリーが「イスラーム教では音楽は禁止されている」と説いたため、サルマドは音楽も止めてしまう。また、サルマドは家族にもイスラーム教原理主義を強要するようになる。
そんなとき、ロンドンから叔父(フマーユーン・カーズミー)が娘のメリー(イーマーン・アリー)と共にやって来た。メリーは英国生まれ英国育ちで、ダイヴ(アレックス・エドワーズ)という英国人のボーイフレンドがおり、結婚もしようとしていた。だが、叔父はそれを認めようとせず、娘を騙す形でパーキスターンに連れて来たのだった。実は叔父はメリーの母親の死後、英国人女性と結婚していた。既に彼女とは離婚していたものの、同棲は続いていた。彼の弁では、ムスリム男性はどの宗教の女性とでも結婚できるが、ムスリム女性はムスリム男性としか結婚できないとのことであった。叔父はメリーをマンスールかサルマドと無理矢理結婚させようとしていたのだった。
叔父から相談を受けたサルマドは、メリーとの結婚を、ターヒリーからイスラーム教の尊厳を守るためには正しいことと言われたため、承諾する。ラーハウルではいろいろ面倒だったため、アフガニスタン国境近くの辺境地帯ワズィーリスターンの寒村で結婚式が挙げられることになった。メリーは父親に騙されて旅行の積もりで来たが、無理矢理サルマドと結婚させられ、そこで彼と暮らすことになる。父親は娘をそこに残してロンドンへ帰ってしまう。サルマドはメリーに無理強いはしなかったが、一度メリーが脱走しようとしたため、彼女に子供を産ませれば逃げないとの助言に従い、彼女をレイプする。やがてメリーは身ごもる。
一方、マンスールは米国シカゴの音楽学校に音楽留学していた。そこで米国人女性ジェニー(オースティン・セイヤー)と出会い、恋に落ちる。やがて2人は結婚する。だが、2001年9月11日、同時多発テロ事件がマンスールの運命を変えてしまう。彼はテロリストとして逮捕され、FBIから執拗な拷問を受ける。ジェニーは音楽学校の仲間と共にデモを行うが、何の効果もなかった。また、アフガン戦争が始まり、サルマドはムジャーヒディーンとして戦争に参加して初めて殺人を経験する。
子供を産んだメリーは、密かにダイヴに手紙を送った。それまでにもダイヴはパーキスターンから帰って来ないメリーのことを心配して政府にまで相談していたが、何の手掛かりも援助も得られなかった。だが、その手紙がきっかけとなって具体的な行動が起こされることになった。英国政府がパーキスターン政府に圧力をかけたことにより、メリーはワズィーリスターンから救出され、ラーハウルに戻って来ることができた。だが、メリーはそのままロンドンには帰らなかった。サルマドへの復讐が残っていたのである。彼女はサルマドが自分に結婚を強制したとして裁判を起こしたのである。サルマドもターヒリーの助言に従い、メリーに対して子供の親権を巡る訴えを起こす。2つの裁判はお互いに関連性のある事件として扱われ、同時に審議されることになった。争点は、花嫁の意思に反して強行された結婚は有効か無効かという点と、無効な場合、その結婚によって産まれた子供の親権はどちらに属するかという点であった。ターヒリーは裁判所でイスラーム教とイスラーム法を落ち着き払って説教し、裁判を有利に進めた。また、イスラーム教における音楽と服装の扱いについても議論が交わされた。
裁判が進行する中、メリーはイスラーム教に対しリベラルな考えを持つ神学者マウラーナー・ワリー(ナスィールッディーン・シャー)に会いに行く。ワリーはターヒリーの説く原理主義的教説に反論することになり、裁判所でイスラーム教の寛容性を説く。ワリーは、音楽はイスラーム教では禁じられたものではなく、外見その他も大した問題にはならないこと、女性の意思に反した結婚は「神様は好まない」ことなどを分かりやすく説明する。その影響でターヒリーとイスラーム教原理主義の洗脳から解かれたサルマドは、メリーに対する訴えを取り下げる。
一方、拘置所で拷問の毎日を送ったマンスールは脳に損傷を受けて植物人間になってしまう。ジェニーは精神病院に彼を訪ね、変わり果てたマンスールと再会を果たす。マンスールはジェニーに対しメッセージを残しており、このような目に遭っても米国を嫌いにはならないこと、そしてイスラーム教徒を誤解しないで欲しいことを訴えていた。マンスールはパーキスターンに送還され、家族と共に暮らすことになる。再びマンスールとサルマドの家には音楽が戻って来た。
裁判を終えたメリーは英国へ帰ろうとし、空港まで行くが、思い直し、ワズィーリスターンへ戻る。幽閉の結婚生活を送っていたとき、その村の女の子たちが教育を必要としていることを痛感していたメリーは、そこで女の子のための学校を開いたのだった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
911事件後の国際社会におけるイスラーム教の立場について、そしてイスラーム教の真のメッセージについて、真剣に考え、そして考えさせられる素晴らしい映画だった。イスラーム教徒としてのアイデンティティーに強烈に問い掛ける映画なので、おそらくイスラーム教徒が見ることで最大限の影響力を発揮するのだろうが、日本人が見てもいろいろな発見や映画的感動があり、面白い。現在のパーキスターンの映像娯楽産業は、映画よりもTVドラマの方が盛り上がっているようで、年間の映画の制作本数はインドと比べると圧倒的に少ない。そのパーキスターン映画の中でも「Khuda Kay Liye」は突然変異的な傑作のようだが、この1本を見ただけでも、その底力を感じる。
映画の舞台はロンドン、シカゴ、ラーハウルの三都市、つまり英国、米国、パーキスターンの三ヶ国にまたがっていた。そしてそれぞれの舞台でイスラーム教に関するメッセージがあった。英国の場面では、移民2世のアイデンティティー問題が扱われていた。このテーマは「American
Desi」(2001年)や「Bend It Like Beckham」(2002年)を初めとして、今まで多くのインド映画が取り上げて来たものであり、珍しくはない。唯一特筆すべきだったのは、英国人女性と結婚したパーキスターン人男性が、娘が白人男性と結婚することを頑なに拒否していたことである。その理屈は、「ムスリム男性はムスリム以外の女性と結婚できるが、ムスリム女性はムスリム男性としか結婚できない」という勝手なものであった。
シカゴの場面では、911事件後の在米パーキスターン人コミュニティーの受難の描写に重点が置かれていた。映画の中で911事件当時米国にいたマンスールは、パーキスターン人というだけで周囲の人々からテロリスト扱いされただけでなく、FBIからもテロリストと決め付けられ、アル・カーイダやオサーマ・ビン・ラーディンとの関係を詰問され、白を切っていると考えられて拷問を受ける。しかし、それは単に米国に対する批判ではなかった。マンスールは拷問の末に植物人間になってしまうが、彼が妻のジェニーに送ったメッセージの中には、「それでも米国民の一員として米国を尊重する」という在米パーキスターン人コミュニティーからのメッセージが込められていた。
パーキスターンを舞台にした部分は、映画の核である。もっとも重要なメッセージが込められていると同時に、ロンドンとシカゴのシーンを結んで映画をひとつにまとめる要(かなめ)にもなっている。中心人物はマンスールの弟のサルマド。サルマドは兄と共にミュージシャンを目指していたが、マウラーナー・ターヒリーと出会ったことで、イスラーム教原理主義に傾倒し始める。ターヒリーはラーハウルの名所のひとつであるワズィール・カーン・モスクの主であり、イスラーム教原理主義の旗手であった。ターヒリーは「イスラーム教で音楽は禁じられている」としてサルマドに音楽を放棄するように求める。マンスールは弟に、「酒や博打の方が悪い。イスラーム教徒の音楽家はたくさんいる」と言うが、ターヒリーは「酒や博打の悪影響を受けるのは自分だけだが、音楽は聞いた人々全てに害を及ぼす」と言ってサルマドの心を揺さぶる。サルマドは音楽を止めただけでなく、家の壁から絵を外させ、母親にブルカーをかぶるように要求までし出す。そして、イスラーム教の名の下に、叔父が画策するメリーの強制結婚計画に加担し、ムジャーヒディーンとして戦争で殺人まで犯してしまう。
終盤、メリーとサルマドが起こした裁判のシーンは映画のクライマックスである。裁判の主旨を端的に言えば、イスラーム教の教義と女性の人権の戦い、そしてイスラーム教の中で芸術がどこまで容認されるかという問題であった。サルマド側の証人に立ったターヒリーはイスラーム法を超える法規はないとの前提で、イスラーム教では結婚に女性の意思は関係なく、音楽も絵もイスラーム教では禁じられているとの理論を展開する。一方、メリー側の証人として、リベラルなイスラーム教神学者マウラーナー・ワリーが呼ばれ、ターヒリーの説くイスラーム教原理主義に真っ向から反対する。ワリーは、イスラーム教で音楽はタブーにはなりえないこと、預言者ムハンマドも女性の意思に反した結婚を認めなかったことなどを、分かりやすく説明し、ターヒリーを理論的に論破しただけでなく、サルマドの洗脳も解く。訴えを退けたサルマドが語った言葉は印象的だった。「私は元々、悪いイスラーム教徒ではありませんでした。酒も博打もしていませんでした。しかし、ナマーズ(祈祷文)は読んでいませんでした。それを教えてくれたのはマウラーナー・ターヒリーでした。私はそれを感謝しています。しかし、私は彼のせいで多くの犯罪をせざるをえませんでした。メリーに対してもひどいことをしてしまいました。たとえ彼女が私を許してくれても、私は自分を許すことは一生できないでしょう。」イスラーム教だけでなく、原理主義者たちが宗教の名の下に行っていることの実態をズバリ言い当てた言葉だと思う。
これだけでもメッセージ性のある映画として完成していたと思うが、もうひとつよい余韻を残してくれたのが、メリーの「その後」であった。裁判を終え、義理の母親と共にロンドンに帰国しようとしたメリーは、何か心にしこりがあるのを感じる。メリーが思い出していたのは、無理矢理サルマドと結婚させられたとき、幽閉同然に住まわされていた家庭の少女たちであった。彼女たちはメリーに英語を勉強したいと言っていた。辺境地帯の女性たちは数々の面で抑圧を受けていたが、最大の懸念が教育であった。メリーは空港から取って返し、ワズィーリスターンへ向かって、そこで女の子向けの学校を開く。現実的な展開とは言いがたいが、映画らしい感動を与えてくれるエンディングだったことは評価したい。インドのNRI(在外インド人)物映画では、チャンスやより良い生活を求めて外国へ渡った移民1世や、生まれ育った国の文化にすっかり染まった移民2世が、インド文化の素晴らしさを再認識したり、インドに帰ったりするエンディングが多い。「Khuda
Kay Liye」はパーキスターン映画であるが、メリーの存在が、NRI物映画との共通点を提示してくれている。
インドの観客の視点で見るといくつか面白い部分があったのだが、特筆すべきはシカゴでのマンスールとジェニーの出会いのシーンであった。マンスールは「パーキスターンから来た」と自己紹介するが、ジェニーは「パーキスターンってどこ?国の名前?」と聞く。マンスールが「イラン、アフガニスタン、中国、インドに囲まれているのがパーキスターンだ」と丁寧に説明すると、ジェニーは反応してくれるが、「ああ、インドの隣の国ね。インドのタージ・マハルは憧れだわ!」とインドの話を始めてしまう。このシーンは911事件前という設定だったので、一般の米国人の反応そのものだったのではないかと思う。そこでマンスールは、「タージ・マハルは僕たちが作ったんだ。元々インドを支配していたのは僕たちだったんだ」と説明する。すると混乱したジェニーは「じゃあなぜインドに建てちゃったの?」と質問する。この辺りのやりとりが、インド人観客の反応も含めて、なかなか面白かった。パーキスターン人の苦し紛れの自尊心と歪んだ歴史認識が感じられた。だが、このシーンには一応、パーキスターン人の感情に配慮したのか、オチがある。立ち去ろうとするジェニーはマンスールに1枚のCDをプレゼントする。見てみると、それはパーキスターンの有名なカッワール、ヌスラト・ファテ・アリー・ハーンであった。ジェニーは実はパーキスターンのことを知っており、マンスールのことをからかっていただけだったのである。
脚本も素晴らしかったが、カメラワークでも凝ったところがあり、映像で物を語るという映画の基本も押さえられていたように感じる。
パーキスターン映画界の俳優には詳しくないのだが、「Khuda Kay Liye」に出演していた俳優たちは皆一級の演技をしていた。白人の俳優もたくさん出て来ていたが、雰囲気を損ねている人はいなかった。シャーンは「パーキスターンのシャールク・カーン」と呼ばれる人気男優・監督のようで、貫禄のある演技をしていたが、マンスールの役を演じるにはちょっと老けすぎであった。サルマドを演じたファワード・ハーンは、エンティティー・パラダイムというロックバンドのリードボーカリスト。頻繁に俳優もしているかどうかは不明だが、ハンサムで落ち着いた男優だと感じた。メリーを演じたイーマーン・アリーはパーキスターンのトップ・モデルかつ女優。インドの一般の女優に比べて目鼻立ちが鋭く、典型的な「美人」のカテゴリーに入るルックスだ。俳優の家系に生まれたようで、決して美しいだけでなく、演技もできる女優であった。マウラーナー・ワリー役のナスィールッディーン・シャーは得意のとぼけた演技で、映画の中でもっとも重要なメッセージを伝えるおいしい役を演じていた。他にも、叔父を演じたフマーユーン・カーズミー、マウラーナー・ターヒリーを演じたラシード・ナーズなど、優れた俳優が多数出演していた。
また、監督のショエーブ・マンスールは、著名なTVドラマ脚本家・監督で、今回が映画監督デビュー作だったようだ。
「Khuda Kay Liye」は音楽もいい。心地よいスーフィー・ロック「Bandya」や「Allah Hoo」、タイトルソング「Khuda
Kay Liye」、ピアノの伴奏が美しい「Tiluk Kamod」など、パーキスターンのポップミュージックの魅力を十分体験できる。映画のBGMの音楽監督はロハイル・ハヤートという人物のようだが、サントラCDには挿入歌の音楽監督や作詞家が誰なのかはどこにも記されていない。パーキスターンの映画音楽界ではあまり音楽監督や作詞家に尊敬が払われていないのではないかと感じる。調べてみたところ、ハワル・ジャーヴェードという人物が大部分の曲を作曲し、ほとんどの作詞は監督のショエーブ・マンスールと、ファイザー・ムジャーヒドという人物が行ったようだ。
言語はウルドゥー語と英語。通常の台詞の理解は、ヒンディー語と英語の知識だけで何とか付いて行けるかもしれないが、モスクや裁判所でマウラーナーたちが話す言語はかなり難解なアラビア語・ペルシア語の語彙が用いられていた。コーランやイスラーム法の解釈など、テーマがテーマだったためにそうなってしまったのかもしれない。しかし、ボリウッド映画でもイスラーム教徒の登場人物が難解なウルドゥー語を話すことはあるが、ここまで難しい言語は今まで映画で耳にしたことはなかった。この辺りが「ウルドゥー語映画」の使用語彙のもっとも深い部分だと思われる。また、ワズィーリスターンのシーンでは現地の言葉も少しだけ出て来るし、シカゴのシーンではマンスールの隣人としてスィク教徒が登場し、コテコテのパンジャービー語を話す。
ちなみに、インドで公開された「Khuda Kay Liye」ではいくつかカットされたシーンがあるようだ。確かに途中不自然なつぎはぎ部分がいくつかあった。だからもしかしたら上記のあらすじや評は不完全なものであるかもしれないことを注記しておく。
「Khuda Kay liye」は、43年振りにインドで公開されたパーキスターン映画という記念碑的作品であるが、それを抜きにしても、非常に完成度の高い優れた映画だった。イスラーム教理解の手助けにもなる。必見である。
| ◆ |
4月7日(月) かめ仙人、マトカー・ピール |
◆ |
オールドデリー(シャージャハーナーバード)とヒンドゥー教の聖地マトゥラー、そしてその先のアーグラーを結ぶマトゥラー・ロードは、中世から北インドの重要な大動脈だった。現在の地図ではマトゥラー・ロードは最高裁判所やティラク・ブリッジ駅前の交差点から始まっているが、かつてはオールドデリー南東のデリー門から端を発していた。このマトゥラー・ロードを南下すると、すぐ左手に、プラガティ・マイダーンという大規模な展示会場がある。毎年ここでインド国際貿易祭などの展示イベントが開催される。プラガティ・マイダーンの西端をかすめながらマトゥラー・ロードをさらに南下して行くと、プラーナー・キラー(オールド・フォート)、フマーユーン廟、ニザームッディーン廟など、数々の重要な史跡があるわけだが、プラーナー・キラーが見える前までの左手の風景を注視していると、奇妙なものが目に入ってくる。ガソリンスタンドの隣に、モスクかダルガー(聖者廟)のようなものがあるのだが、その塀の上にいくつかのマトカー(素焼きの水がめ)が並んでいるのである。よく目を凝らすと、敷地内の木々の枝にもマトカーがぶらさがっており、非常に奇怪な光景である。だが、誰かが悪戯や思い付きでやっている訳ではなく、これはマトカー・ピールと呼ばれる、デリーではかなり人気のあるスーフィー(イスラーム教神秘主義)聖者を祀った由緒ある廟なのである。マトカー・ピールを敢えて日本語に訳せば、「甕(かめ)仙人」であろう。マトケー・シャーとも呼ばれるが、同じ意味である。

マトカー・ピールの入り口
マトカー・ピールの本名はハズラト・シェーク・アブーバカル・トゥースィー・ハイダリー・カランダリー。生年は不明だが、デリーの有名なスーフィー聖者、ハズラト・シェーク・ニザームッディーン・アウリヤー・チシュティー(1238-1325年)と同時代の人物で、その人気はニザームッディーンに勝るとも劣らなかった。ニザームッディーンはスーフィーの中でもチシュティー派と呼ばれる宗派に属していたが、マトカー・ピールは別の宗派であるハイダリー派またはカランダリー派に属していた。だが、宗派間の抗争などはなく、マトカー・ピールのカーンカー(修道場)にはニザームッディーンなどの別宗派の聖者もよく訪れていたとされる。マトカー・ピールの没年は1301年である。
聖者がマトカー・ピール(かめ仙人)という愛称で呼ばれるようになった理由については以下のような言い伝えがある。当時ヤムナー河は今よりも西を流れており、現在マトカー・ピール廟のある場所のそばにはヤムナー河が流れていた。マトカー・ピールのカーンカーは、ヤムナー河沿いの小高い丘の上にあった。あるとき、ある男が難病を苦にヤムナー河に入水自殺しようとしたことがあった。それを見た聖者は男を止め、自分のマトカーの水を彼に飲ませた。すると、男が苦しんでいた病気はたちまちの内に治ってしまった。この奇跡譚は瞬く間にデリーの人々に知れ渡り、聖者はマトカー・ピールと呼ばれるようになったと言う。
中世の北インドでは、スーフィー聖者は庶民から絶大な信仰を集めていた。スーフィー聖者は宗教や身分の区別なく困った人々を助け、社会福祉事業を率先して行い、道徳を広めていたためである。スーフィー聖者は政治とは一切関係を持たなかったが、政治の監視は常に行っていた。彼らは決して人里離れた山奥に庵を結ぶ隠者ではなく、都市近郊に住み、積極的に社会に関わることを是として来た人々であった。今で言えばボランティア活動家であろうか。そのため彼らは主要都市にカーンカーを創設することが多かった。デリー・サルタナト朝が樹立して以来、デリーは首都として発展したため、多くのスーフィー聖者が集まって来た。デリーには大小様々なダルガーが今でも残っており、その数は22とも、32とも、64とも、184とも言われている。当時、北インドの政治の頂点にはスルターン(皇帝)がいたが、独裁体制や中央集権体制を敷けたスルターンは稀で、多くのスルターンは諸侯の中の長に過ぎない存在だった。そのため、スルターンはスーフィー聖者の力をもっとも恐れていた。スルターンの宮廷の大臣や直属の兵士の中にもスーフィー聖者の信奉者がたくさんおり、スーフィー聖者がいつか政権転覆を画策するのではないかと怯えるスルターンは多かった。また、ウラマーと呼ばれるイスラーム教神学者たちは、スーフィズムをイスラーム教とは認めておらず、事あるごとにスルターンを焚きつけてスーフィー聖者たちの弾圧を行わせようとした。
マトカー・ピールと同時代のスルターンで強大な権力を誇ったのは、奴隷王朝のギヤースッディーン・バルバン(在位1266-86年)であった。バルバンは元々奴隷だったが、徐々に頭角を現し、第7代皇帝ナスィールッディーン・メヘムード(在位1246-66年)の義理の父にして首相という地位にまでのし上がった人物である。バルバンはスルターンの生前から王朝の実質的な支配者だったが、スルターンの死後は王権を簒奪し、自らスルターンに即位した。首相の時代からスルターンの時代までを合計すると、40年に渡って奴隷王朝の頂点にいたことになる。ちなみに、バルバンの墓廟はメヘラウリー考古公園内にある(EICHER「Delhi
City Map」P142 H3)。何も知らないとただの廃墟だが、バルバン廟にはインドの建築物としてはおそらく初めてアーチの技術が使われており、インド建築史上重要な遺跡になっている。

ギヤースッディーン・バルバン廟
やはりバルバンもマトカー・ピールの人気を恐れていた。デリーの皇帝がスーフィー聖者に対してよく取った手段は、宮廷への召集であった。聖者を宮廷に呼びつけることで、皇帝の権力は聖者にも勝ることを世間に見せ付けようとしたのである。バルバンもあるときマトカー・ピールを宮廷に召集した。だが、マトカー・ピールはそれを拒否した。そこでバルバンは、タミーザンという若い侍女をマトカー・ピールのカーンカーに送った。タミーザンは絶世の美女であった。皇帝は、美女の色香によってマトカー・ピールを誘惑し、堕落させようと画策したのである。ところが、タミーザンの方がマトカー・ピールの人柄や言動に心酔してしまい、熱心な信者になってしまった。彼女はそのままカーンカーに住み、一生聖者の世話をして過ごした。
懲りないバルバンは、今度はマトカー・ピールに「食べ物」を送ってよこした。マトカー・ピールが包みを開けて見ると、そこには砂鉄と土くれが入っていた。聖者は何も言わずにそれを包み直し、神に祈って、再び包みを開けた。すると、砂鉄は炒ったチャナー(ヒヨコマメ)に、土くれはグル(粗糖)に変わっていた。マトカー・ピールはそれらをマトカーに入れて水と混ぜ、その場にいた信者全てに分け与えた。元のチャナーとグルは少量だったが、マトカーから出て来るチャナーとグルと水の混合物は不思議と無尽蔵であった。聖者はまた、その一部を皇帝に送り返した。この奇跡を聞いたバルバンはすっかり聖者の信者となってしまったと言う。また、この出来事があったため、聖者の死後、信者たちは願い事が叶った後のお礼参りとして、マトカーにチャナー、グル、砂糖などを入れてダルガーに寄進し、参拝者に分け与えるようになったようだ。

木にぶら下げられたマトカー
マトカー・ピールのカーンカーとダルガーの敷地はかつて13エーカーに及ぶほど広大なものだったようだが、1971年にその大部分がデリー開発公社(DDA)によって接収されてしまい、そこにプラガティ・マイダーンなどが建造された。おかげでマトカー・ピール廟の敷地は現在では廟の周辺のごく限られた土地となってしまっている。
マトカー・ピールの門をくぐると、左手にはマトカーや参拝用品などを売る売店が2店あり、右手には小さなモスクが見える。そして奥には階段があり、高さ50mほどのちょっとした丘の上まで続いている。マトカー・ピールの墓はこの丘の上にある。階段の隅には数人の乞食が座っており、参拝者に喜捨を求めて来る。階段の途中に靴を預ける場所があるので、そこで靴を脱ぎ、裸足になる。この靴預け所では、スーフィズムとマトカー・ピールについて簡単に解説した「Tasavvuf
aur Hazrat Shekh Abūbakar Tūsī Haidarī Qalandarī (urf Matkā Pīr)」という小冊子が売られている(25ルピー)。著者はムハンマド・ヒファズル・レヘマーン・スィッディーキーという人物で、ヒンディー語版とウルドゥー語版がある。

マトカー・ピールの門をくぐったところ
靴預け所からさらに階段を上って行くと丘の上に出るが、そこはきれいな広場にになっており、その片隅にマトカー・ピールの墓がある。

マトカー・ピールの墓廟
もっとも多くの参拝客がスーフィー聖者廟を訪れるのは木曜日である。今日は月曜日だったためか、それほど多くの参拝客はいなかったが、それでも次から次へと信者がやって来て、マトカー・ピールの墓でお祈りをしていた。願い事が叶った信者がいたのだろう、捧げられたばかりと見られるマトカーもいくつか置かれていた。慣習では、願い事の叶った信者は、250gのグル、250gの炒ったチャナー、250gの砂糖、250gの牛乳、2枚のチャーダル(シーツ)、ひとつのマトカーをお礼参りのときに持参することになっている。

墓廟内部
デリーの他のダルガーと同じく、マトカー・ピールの信者はイスラーム教徒とは限らず、ヒンドゥー教徒やその他の宗教の人もここで祈りを捧げて行く。デリー州首相のシーラー・ディークシトも、マトカー・ピールの熱心な信者らしい。ちなみに、マトカー・ピール廟の階段を上がってすぐ右側にもうひとつ墓があるが、これはハズラト・シェーク・ラヒームッディーン・イラーキーという人物のものである。ラヒームッディーンはマトカー・ピールの後継者であり、参拝者は彼の墓にも花やチャーダルを捧げて行く。

青空とマトカー
おそらくマトカー・ピール廟と関連していると思うが、マトゥラー・ロードを挟んで反対側にはイスラーム教の墓地がある。ほとんどは何の変哲もないシンプルな墓だが、2つだけ特別扱いされているものがある。
まずひとつめは、ミルザー・アブドゥル・カーディル・ベーディル(1642-1720年)の墓。ベーディルはインドで活躍したペルシア語詩人である。ムガル朝時代、インドの公用語と教養語はペルシア語であり、本場ペルシアを凌ぐ質と数のペルシア語文学がインドで生まれた。よって、インドにペルシア語詩人がいることは変なことではない。ベーディルの生まれは現ビハール州のパトナーとも、アフガニスタンの首都カーブル近くのハージャー・ラワーシュとも言われているが、家系は、アフガニスタンとタジキスタンにまたがるバダクシャーン地方のバルラーという部族のようだ。彼の詩体は、ガーリブ、モーミン、イクバールにも多大な影響を与えたとされるが、インドではいつの間にかほとんど忘れられた存在となり、マトカー・ピール廟近くにある墓も長年放置されて来た。そのベーディルの墓が一躍注目を集めることになったのは、2006年8月、タジキスタン共和国のエモマリ・ラフモン大統領の訪印であった。ラフモン大統領はインド政府に対し、ベーディルの墓を詣でたいとの希望を伝えて来たのである。実はベーディルは、インドではほとんど知名度がないが、アフガニスタンやタジキスタンではカルト的な人気を誇っており、大統領自身もベーディルの大ファンだったのである。だが、インドで忘れ去られた詩人の墓は、大統領を案内することができないほど朽ち果ててしまっていた。慌てたインド政府はインド考古局(ASI)にベーディルの墓の緊急リノベーションを命じた。こうして、突然脚光を浴びたベーディルの墓は、今では緑と白を基調とした立派な墓になって墓地の中にひっそりと立っている。また、周辺の墓地はベーディルの名を取って「バーゲ・ベーディル(ベーディルの庭園)」と呼ばれるようになった。だが、脚光を浴びたのは一瞬だけで、インドでベーディルを知る人も、ここを訪れる人もほとんどいないのは、以前と何ら変わりがない。

ベーディルの墓廟
墓の傍らには解説文が刻まれた石版が立っているが、タジク語、ヒンディー語、英語、ペルシア語、ウルドゥー語の5言語で書かれている。この5種の言語で刻まれた石版はインド唯一であろう。

5言語で書かれた解説文
その内容は以下の通りである。各言語で微妙に書いてあることが違うが、ヒンディー語のものを主に参考にした。詩も添えられていたが、これはベーディルの作ではないと思われる。
ベーディルの庭園
この庭園に咲く花の香りを嗅いでくれ
ここに悲嘆の詩人ベーディルが眠る
この石版は、世界的に有名な詩人ミルザー・アブドゥル・カーディル・ベーディルに捧げられたものである。ベーディルの詩は深遠かつ広大だが、それはインドの地において培われたものである。彼の作品は、数世紀に渡ってペルシアやタジキスタンの文学の発展に寄与して来た。
この石版は、インド共和国のAPJアブドゥル・カラーム大統領の招待を受けてインドを訪問したタジキスタン共和国のエモマリ・ラフモン大統領によってここに立てられた。

タジク語(上)とペルシア語(下)の碑文
バーゲ・ベーディルにある墓の中でもうひとつ特別扱いされているのは、ベーディル廟の奥にあるシェーク・ヌールッディーン・マリク・ヤール・パッラーンの墓である。ヌールッディーンは、マトカー・ピールやニザームッディーン・アウリヤーと同時代の聖人であるが、その愛称に関しては面白い言い伝えが残っている。師匠の命令に従ってラールという街からデリーにやって来たヌールッディーンは、マトカー・ピールのカーンカーの目の前にカーンカーを開こうとした。だが、マトカー・ピールはそれを許さなかった。ヌールッディーンが、師匠から命令されていることを説明すると、マトカー・ピールは師匠から委任状を受け取って来るように要求する。するとヌールッディーンは瞬く間に師匠から委任状を受け取って戻って来た。あまりの早さにマトカー・ピールは驚いて、「ヤール、マリク・パッラーン(友よ、お前には羽根があるのか?」と聞いた。そのときからヌールッディーンは「マリク・ヤール・パッラーン(羽根を持つ者)」と呼ばれるようになった。しかし、普通に考えたらヌールッディーンは師匠からの委任状を自分で書いてマトカー・ピールのところへ持って行ったのではないだろうか?ちなみに、マリク・ヤール・パッラーンの墓には天使が住んでいると言われているらしい。だが、それは聖人の愛称から想像が膨らんで生じた民間信仰であろう。墓のそばに立っている石碑によれば、マリク・ヤール・パッラーンの没年は1281年である。

マリク・ヤール・パッラーンの墓
ベーディルの墓廟やマリク・ヤール・パッラーンの墓は、予備知識がないと見ても何も面白くないかもしれないが、マトカー・ピール廟は、あちこちに並べられたりぶら下げられたりしたマトカーが独特の雰囲気を醸し出しており、観光地としても一定の魅力がありそうだ。また、マトカー・ピール廟はデリーの数あるダルガーの中でも比較的管理が行き届いており、物見遊山の外国人にも開放的な雰囲気がした。おまけにここの現世利益の力はかなり強いようなので、プラガティ・マイダーンに来たときなどに立ち寄ってみるといいだろう。もちろん、願い事が叶った暁には、マトカーを持ってお礼参りをするのを忘れないように・・・。
ボリウッドの2007年はコメディー映画豊作の年だったが、今年はまだスーパーヒットと言えるコメディー映画が出ていない。本日より公開の「Krazzy
4」は、狂人4人が主人公ということもあり、期待のコメディー映画の1本であった。しかも、「Koi.. Mil Gaya」(2003年)や「Krrish」(2006年)を送り出したローシャン一族のホーム・プロダクションであり、さらに期待は高まる。
題名:Krazzy 4
読み:クレージー・フォー
意味:狂人4人組
邦題:クレージー4
監督:ジャイディープ・セーン
制作:ラーケーシュ・ローシャン
音楽:ラージェーシュ・ローシャン
作詞:ジャーヴェード・アクタル
出演:アルシャド・ワールスィー、イルファーン・カーン、ラージパール・ヤーダヴ、スレーシュ・メーナン、ジューヒー・チャーウラー、ディーヤー・ミルザー、ラジャト・カプール、ザーキル・フサイン、シャールク・カーン(特別出演)、リティク・ローシャン(特別出演)、ラーキー・サーワント(特別出演)
備考:PVRプリヤーで鑑賞。
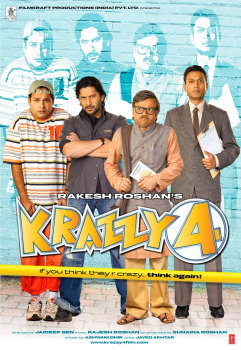
左から、スレーシュ・メーナン、アルシャド・ワールスィー、
ラージパール・ヤーダヴ、イルファーン・カーン
| あらすじ |
精神病院「ウィー・ケア」で治療を受ける4人組がいた。ラージャー(アルシャド・ワールスィー)は怒りを制御できずすぐに暴力を振るう癖があり、自ら精神病院に入院していた。ムカルジー(イルファーン・カーン)は極度の潔癖症だった。ガンガーダル(ラージパール・ヤーダヴ)はまだインドが独立していないと思い込んでおり、独立運動に身を投げ出していた。ダッブー(スレーシュ・メーナン)は挙動不審でしゃべることができなかった。
ある日、4人の治療を行っていたドクター・ソーナーリー(ジューヒー・チャーウラー)は、彼らをクリケットの試合観戦に連れて行くことにする。久し振りに精神病院を出た4人は大いに興奮していた。その途中でソーナーリーは自動車を止め、クリニックに書類を取りに行く。だが、そのままソーナーリーは帰って来なかった。立ち小便をしに車から降りていたダッブーは、偶然ソーナーリーが男たちに連れ去られるのを目撃するが、言葉がしゃべれないので仲間に伝えることができなかった。一方、様子を見に外に出たラージャーは、TVで昔の恋人シカー(ディーヤー・ミルザー)が出ているのを目にする。そのまま彼はシカーに会いに行き、彼女の家も訪れるが、父親の前で暴力を振るってしまい、逃げるように出て行く。実は彼は4年前にもカッとなって父親を殴ってしまい、シカーから狂人扱いされたため、そのまま精神病院へ入院したのだった。
いつまで経ってもソーナーリーは戻って来なかった。そこで4人はソーナーリーの夫のRKサーンニャール(ラジャト・カプール)に会いに行く。RKサーンニャールは今度上院議員に選出される見込みの有力政治家であった。だが、実はソーナーリーを誘拐させた張本人はこのサーンニャールであった。
話はこうであった。ラーナーというマフィアのドンが殺人の容疑で逮捕されてしまい、何とかして彼を釈放しようと、悪徳警官シュリーワースタヴ(ザーキル・フサイン)と共に考えた結果、ラーナーに精神障害があると裁判所で証明することになった。裁判所には4人の精神医が呼ばれることになっており、シュリーワースタヴはその内の3人を買収したが、ソーナーリーだけは買収できなかった。そこで彼はソーナーリーを誘拐し、ラーナーを精神患者だと宣言するように強要したのだった。
だが、サーンニャールが黒幕であることを4人組は知ってしまう。シュリーワースタヴは4人を捕まえて殺そうとするが、運良く彼らは脱走に成功する。彼らはソーナーリーを救出しようとするが、彼女の居場所も分からなければ、1ルピーの手持ちもなかった。ラージャーはTV局に勤めるシカーを頼り、相談する。5人はある作戦を立てる。
5人は、パーティーに出席していたサーンニャールを誘拐し、彼に、「ソーナーリーを見つけた者には5,000万ルピーの報酬を支払う」と発言させ、それを録画する。そしてそれをTVで放送した。誘拐したソーナーリーを見張っていた男たちはそれを知ってシュリーワースタヴを裏切り、ソーナーリーをTV局まで連れて行こうとする。だが、その途中でソーナーリーは逃げ出し、ヴィクトリア病院へ向かう。ヴィクトリア病院ではこのとき、ラーナーの精神鑑定が行われることになっていた。4人組も病院に行くが、実はこの病院ではムカルジーの妻が働いていた。妻の協力によって彼らは精神医になりすまし、ソーナーリーと共にラーナーの「精神鑑定」を始める。それはラーナーの精神を崩壊させるような鑑定であった。
その間にシカーはサーンニャールとシュリーワースタヴの悪行をメディアの前で公にする。こうして、4人の「狂人」の活躍により、サーンニャール、シュリーワースタヴ、ラーナーの3人は逮捕されたのであった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
一言で表現すれば、笑いと涙、コメディーと感動の両方が盛り込まれた映画であった。だが、コメディー色を前面に押し出した表向きとは裏腹に、映画の重要なラス(情感)は「悲哀」であり、「喜笑」のラスを凌駕していた。おそらく爆笑コメディーを期待して映画館に足を運ぶ観客が多いはずであり、彼らにとってもしかしたらこの映画は期待通りとは行かないかもしれない。「正常」な人々が社会でどんな悪事を働き、他人の悪事に目をつむっているか、「異常」と呼ばれる人々がどれだけ純粋な心を持っているか、というある種の社会的なメッセージもあった。ベースがコメディーなのでそのメッセージに説得力はあまりないのだが、着眼点はいいと思った。つまり、この映画を単純にコメディー映画と称するのは間違いだということだ。決してクレージーな映画ではない。だが、必ずしもそれが成功していたわけではなく、むしろお馬鹿なコメディーに集中した方が興行的成功は収められただろう。気の利いたコメディー・シーンがいくつかあったし、もっと真面目にコメディー映画として取り組めば、爆笑コメディー映画としてまとまる潜在力は脚本から十分感じられた。それを敢えてしなかったのは、今やヒットメーカーの一員となったローシャン一族のプライドからであろうか?
「これでインディア」の映画評の中で何度も書いていることだが、インドでは身体障害者や精神障害者に対する差別がまだあからさまに残っており、それが映画からも感じられることがある。「Black」(2005年)は、ヘレン・ケラーの生涯を題材にしたシリアスな映画であったが、その成功を受けて、身体障害者を主人公にしたり、登場させたりして笑いを取るコメディー映画がいくつも制作された。「Pyaare
Mohan」(2006年)や「Tom Dick and Harry」(2006年)がその代表例である。「Krazzy 4」もその一例に挙げられるが、エンディングで精神病患者たちの方を持ち上げる形で社会批判を行っており、そのおかげで「精神障害者たちを馬鹿にしている」という批判は受けにくそうだ。
「Munnabhai」シリーズでムンナーバーイーの相棒サーキットを演じ、一躍時の人となったアルシャド・ワールスィーだが、あれからサーキットからの脱却と俳優としての自立にある程度成功しており、コメディーとシリアスの間を行ったり来たりする高度な演技のできる俳優になって来ている。イルファーン・カーンは逆にシリアスな演技に定評があったが、コミカルな演技もできる俳優として認知されて来ている。「Krazzy
4」では2人の演技とアクションがもっとも光っていた。コメディアン俳優ラージパール・ヤーダヴも、いつも通り滑稽かつダイナミックな笑いに貢献していた。今回、スレーシュ・メーナンという俳優が主役の4人の中に入って来ていた。彼はどちらかというと脇役俳優で、いくつかのボリウッド映画に脇役として出演している。今回狂人4人組の1人に入ったのは多分特別で、これがきっかけでこれから主役を演じ出すことはないだろう。
案外良かったのはディーヤー・ミルザー。出番は少なかったが、感情的なシーンをうまくコントロールして演技できる女優になったと感じた。ジューヒー・チャーウラーは相変わらず大根役者である。彼女は一時期時代を作ったほどの女優なのだが、ヒロイン女優から演技派女優への脱皮に失敗しており、扱いづらい人材になってしまっている。
音楽はラージェーシュ・ローシャン。映画には3つのアイテムナンバーがあり、それぞれ人気俳優が特別出演している。「Dekhta Hai Tu Kya」ではラーキー・サーワントが、「Break
Free」ではシャールク・カーンが、エンディング曲の「Krazzy 4」ではリティク・ローシャンがダンスを踊っており、映画の見所となっている。特にリティクのダンスは素晴らしい。ただし、「Break
Free」と「Krazzy 4」では、ソニー・エリクソンのTVCMに使用されたメロディーが流用されており、それを作曲したラーム・サンパトが訴えを起こしていた。その影響で映画公開が延期されるところだったが、直前にプロデューサーのラーケーシュ・ローシャンがラーム・サンパトに2,000万ルピーを支払い、事なきを得た。聞いてみると、確かにリティク・ローシャン出演のソニー・エリクソンW200iのTVCM「Thump!」のメロディーそのままである。これはいけない。
「Krazzy 4」は、ただのコメディー映画と思いきや、感動の涙を流すこともできる映画である。むしろ、意外なことに涙の方に重点が置かれている。能天気なコメディーを求めて見ると少し失望するかもしれない。また、3曲のアイテムナンバーはなかなか豪華であることを追記しておく。
発見と冒険に満ちたデリーでの生活を綴った有名な紀行小説「City of Djinns: A Year in Delhi」の中で、英国人作家ウィリアム・ダルリンプルはこんなことを書いている。
毎朝7時半ちょうどに、ラッドゥー(大家の使用人)が持って来てくれるベッド・ティーとタイムス・オブ・インディアで目を覚ますことが、インド生活の大いなる楽しみのひとつだった(P.
73)。
タイムス・オブ・インディア(Times of India)はインド最大の英字新聞であるが、それはつまり世界有数の英字新聞であることも意味する。発行部数は240万部以上。全項カラー、サプリメント(折込紙)も豊富であるにも関わらず、その値段はデリー発行の平日版で2.5ルピー(約7.5円)、日曜版で4.5ルピー(約13.5円)と、日本の新聞に比べて格安である。その代わり広告も多い。幅広い読者を想定しているためか、時事問題に鋭く切り込む真面目な記事から白人女性のセクシーなグラビアまで、ありとあらゆる要素がごっちゃになっているのも特徴のひとつである。毎朝僕のところにベッド・ティーは来ないが、タイムス・オブ・インディアは同じく楽しみにしている。
タイムス・オブ・インディアが執拗と表現できるまでに好んで取り上げるジャンルが女性問題である。おそらくタイムス・オブ・インディアが好んでいるというよりも、読者がもっとも興味を示す記事がそれなのだろう。女性問題と言ってもいろいろあるが、代表的なのは、持参金絡みの事件と、レイプ事件である。今日はたまたまこの2つの事件が同時に記事になっていたので、取り上げてみようと思う。どちらも一筋縄では行きそうにない事件である。
まずは持参金絡みの事件。題名は「持参金を要求され、花嫁が結婚式をキャンセル(Asked for dowry, she called off
wedding)」。副題は「花婿の両親曰く、彼女はマーングリクを隠していた(To-be in-laws say she hid Manglik
status)」。その全文を翻訳した。
アニター・バッラー(26歳)は、結婚式の日に許婚のヴァルン・サールナーとの結婚を拒否し、世間の花嫁候補たちに見本を示した。結婚をキャンセルした理由は、彼女の弁によると、ヴァルンの家族が彼女の家族を侮辱し、結婚前に「贈り物」を要求したからである。アニターは大学卒業後、グルガーオンのGenpactという企業で働くコールセンター・オペレーターであり、ヴァルンとは1年半前から同僚であった。
ヴァルンは4ヶ月前にアニターにプロポーズをした。アニターは、「私は10日に結婚する予定で、正式な婚約式は8日に行われた。9日、花婿の家族がティラク・ナガルの自宅でカクテル・パーティーを催し、私の義理の兄のヴィシャール・ワードワーが出席した。そこで彼らは婚約式の準備の不手際に不平を言い、親戚のために金の指輪を要求して来た。また、結婚式のために自動車や5つ星ホテルのホールの予約も強要した。そして、もしそれができなかったら結婚式を中止すると言った。我々の予算は限られており、そのような要求は不合理だ」と述べている。
「私の義理の兄は10日の午前1時頃に帰宅し、何が起こったかを私に語った。私は彼に、サールナー家に電話して結婚式をキャンセルするように言った。」
アニターによると、ヴァルンと彼の家族は10日の午前6時頃にアニターの家を訪れ、彼女と彼女の家族を侮辱した。「遂に午後になって私たちは警察に届出を出した」とアニターは語る。
アニターはヴァルンよりも3歳年上であるが、彼女によればそれは彼も知っていたと言う。アニターによると、彼女の家族では、ホロスコープを合わせる習慣はなかった。だが、ヴァルンの母親のアルカーがそれについてうるさかった。そこでバッラー家はサールナー家にアニターの誕生日と誕生時間を教えた。アニターは、「私はマーングリク(後述)だが、ヴァルンの父親は全く問題ないと言っていた」と回想する。
連絡を取ったところ、ヴァルンは、「私は女性優遇の法律の犠牲者だ。私はアニターの年齢も彼女がマーングリクであることも知らなかった。マーングリクの女性と結婚して命を危険にさらす必要があろうか?私たちは、彼女の義理の兄がカクテル・パーティーで酔っ払ってそれを暴露したときに初めてそれを知った」と語っている。
ヴァルンの母親のアルカーは、「私たちの社会的ステータスは彼らよりも上で、十分なお金も持っている。それなのになぜ彼らに持参金を要求しようか?私の息子は、バッラー家が結婚式のために借りた借金の肩代わりまで申し出た。婚約式の準備はとても悪かったが、私たちが結婚式の中止を決めたのは、酔っ払ったヴァルンが秘密を暴露したときだ。私の息子が彼女と結婚したら、どんな災いが彼に降りかかったことだろう」と語っている。
インドでは結婚を決めるときに、花婿と花嫁のクンダリー(生年月日と時間から算出したホロスコープ)を合わせ、吉兆を占う習慣がある。マーングリクとは、ホロスコープ上、火星の影響の強い状況で生まれた人のことを指し、特に女性に関係する。マーングリクの女性と結婚した男性は、様々な災難に見舞われたり、早死したりすると信じられている。ボリウッドのトップ女優アイシュワリヤー・ラーイもマーングリクで、アビシェーク・バッチャンと結婚する前にマーングリク除去のため、数々の儀式を行ったことは記憶に新しい。また、インドでは一般的に、花婿よりも花嫁の方が年上の結婚は好まれない。
持参金についても少し説明が必要だろう。インドでは持参金のことをダウリー(英語)またはダヘージ(ヒンディー語)などと呼ぶ。一般的に花嫁側の家族が花婿側の家族に支払うことになっている。持参金と言っても受け渡されるのは現金だけでなく、貴金属、装飾品、衣服から、自動車や電化製品まで、花婿側の要求に従って様々な高価な品物を贈答しなければならない。元々は花嫁への財産分与の性格が強かったのだが、現在では花婿側の家族の一攫千金のチャンスのように考えられている傾向にある。昔から持参金は数々の問題を引き起こして来たため、現行の法律では禁止されている。だが、持参金の習慣はインドの社会に根強く残っており、今でも大っぴらに持参金の受け渡しが行われる。花婿側が結婚式の土壇場で持参金の上乗せなどを要求して来ることもあり、結婚式が終わるまで花嫁側の家族は気が気ではない。
さて、上の記事だが、花嫁側と花婿側で証言が完全に食い違っているのが分かる。どちらかが嘘を付いている。花嫁側は、花婿側が結婚式の前日になって無理な持参金の要求をして来たため、結婚式をキャンセルしたと主張している。一方、花婿側は、花嫁が花婿よりも年上でしかもマーングリクであることを隠していたことを理由に、結婚式をキャンセルしたと主張している。キーパーソンとなっているのは、花嫁の「義理の兄」のヴィシャールである。「義理の兄」の詳しい説明はなかったが、普通に考えたら花嫁の姉の夫であろう。花嫁側の主張では、花婿側主催のカクテル・パーティーにおいてヴィシャールが持参金支払いを要求されたことになっており、花婿側の主張では、パーティーで酔っ払ったヴィシャールが、花嫁がマーングリクであることを暴露したことになっている。タイムス・オブ・インディア紙は、花嫁アニター、花婿ヴァルン、花婿の母アルカーにインタビューをしているが、もし真相を明らかにしたいのだったら、ヴィシャールにもインタビューをすべきだったと思う。
インタビューの中でヴァルンは「女性優遇の法律」と興味深いことを発言している。これはおそらく、持参金禁止法(Dowry Prohibition
Act, 1961)のことを指しているのだろう。この法律では、直接的にも間接的にも持参金を要求しただけで罪に問われると規定されている(第4条)。一応、持参金を要求したのが花婿側であっても花嫁側であってもこの法律は平等に適用されるため、この法律自体が女性優遇であるとは言えない。だが、インドの習慣から言ったら、適用の対象になりやすいのは圧倒的に花婿側である。しかも、持参金の間接的な要求だけでも罪になるということは、濫用しようと思えば簡単に濫用できてしまいそうな条文である。もし、花婿側の主張が正しいと仮定した場合、結婚を一方的に破談にされた花嫁側が復讐のために「持参金を要求された」と警察に届出をしたと考えられる。世間の同情も、花嫁側に集まりやすいだろう。タイムス・オブ・インディアの記事も、一応バランスを取る努力はしているものの、冒頭で「持参金を要求して来た花婿側家族に対して結婚破棄を叩き付けた」アニターを英雄扱いしており、完全に花嫁寄りである。
しかし、マーングリクのような迷信を理由に結婚をキャンセルすることに対して何の疑問も投げ掛けられていないのは、さすがインドと言ったところか。これは、持参金問題が嘘だとしたらマーングリクの問題になるし、マーングリク問題が嘘だとしたらやっぱり持参金問題になるという、一筋縄では行かない事件だと言える。
もうひとつの記事は、レイプ絡みのものである。記事は1面と3面に分割されているため、その全てを訳すよりもまとめた方が分かりやすいだろう。一応、1面の題名は「レイプ犠牲者を隣人たちが暴行(Neighbours
beat up rape victim)」である。以下、簡単に事件の概要をまとめてみた。
場所はデリー市内、ヤムナー河の東岸にあるマンダーワリーという町。35歳の女性スィーマー(変名)はラクシュミー・ナガルで使用人派遣の小さな会社を経営しており、3ヶ月前にマンダーワリーにあるラームクマールの家に借家人として引っ越して来た。ここまでは紛れもない事実のようである。
ここからはスィーマーの証言になる。4月3日夜、彼女は大家のラームクマールにレイプされた。ラームクマールの妻スィヤーはそのとき帰省していて留守だった。4月5日、スィーマーは警察にレイプされたことを届け出、ラームクマールは逮捕された。その後もスィーマーはラームクマールの家に住み続けたが、ラームクマールの家族から、訴えを取り下げるように脅しを受けた。10日夕方、スィヤーは隣人と共にスィーマーの家に押し入り、彼女に侮辱の言葉を浴びせかけた。そこでスィーマーは警察署へ行って届出をした。夜10時に自宅に戻って来ると、彼女はスィヤーによって家から閉め出されていた。スィーマーが抗議をすると、スィヤーは再び彼女を侮辱し出した。スィーマーが再度警察署へ行こうとすると、スィヤーはナイフを取り出して脅迫した。スィーマーはそのナイフによって左手の指に傷を負った。すぐに20人ほどの人々がやって来て、彼女に殴る蹴るの暴行を加え始めた。数分後、警察官と地元議員が現場にやって来たが、彼らは暴行を止めようとしなかった。スィーマーは何とか逃げ出して警察署に逃げ込んだ。
これだけを読むと、レイプの犠牲者にさらに集団で暴行を加えるなんて、なんと酷い事件だ、ということになる。だが、ラームクマールの妻スィヤーの証言を読むと、事件の別の側面が見えて来る。前もって特に注記しておきたいのは、強姦罪が親告罪であることだ。強姦された本人が親告しなければ、強姦は強姦にならない(以前書いたインドの姦通罪も参照のこと)。
ここからはスィヤーの証言である。スィヤーが実家から帰って来ると、既にラームクマールはレイプの容疑で逮捕されていた。スィーマーはスィヤーに対し、もし訴えを退けて欲しかったら、20万ルピーと、夫がメーラト(ウッタル・プラデーシュ州の都市)に所有している家をよこすように要求して来た。10日夜、スィヤーは酔っ払って彼女に対して暴言を吐き出した。近所の人々は最初彼女をなだめようとしたが、彼女が聞こうとしなかったため、暴行が始まってしまった。
この事件は女性団体やNGOにも知れ渡り、彼らは11日午後に警察署に届出を出し、スィヤーを含む5人が暴行罪などにより逮捕された。逮捕されたスィヤーだったが、11日夕方、逆に彼女はスィーマーに対し、ラームクマールへの訴えを取り下げるために巨額の金額を要求し、脅迫して来たとして、訴えを起こし返している。
タイムス・オブ・インディアの記事だけではどうも情報が足りないのだが、ヒンディー語のヒンドゥスターン紙にも同じ事件が掲載されており、しかもさらに詳しく書かれていたので、事件の真相により迫ることが出来た。やはりいくつかの記事に分散して書かれていたが、1面の題名は「レイプされた女性に暴行(बलात्कार
पीड़ित महिला की पिटाई)」である。タイムス・オブ・インディアは、どちらかというとスィーマーに肩入れしていたが、ヒンドゥスターンはかなりバランスの取れた記述がしてあった。それらの記事に書かれていた内容をまとめると以下のようになる。ちなみにスィーマーという名前はタイムス・オブ・インディア紙が勝手に付けた変名で、レイプ被害者の本名は明かされていない。ヒンドゥスターン紙でも彼女の名前は出されていないが、便宜的にここでもスィーマーとしておく。
まず、スィーマーの素性についてタイムス・オブ・インディアよりも詳しく書かれていた。スィーマーは元々メーラトに住んでいたが、夫のシャランビール・スィンと喧嘩して飛び出し、デリーに住んでいた。別居生活は14年に及ぶ。2人の間には2人の息子がいたが、長男はメーラトで父親や祖父母と共に暮らし、次男は彼女と共にデリーで暮らしていた。スィーマーは使用人派遣の仕事をして生計を立てていた。その後、彼女は最近になって家庭用品のマーケティングをする新事業を立ち上げた。だが、こちらは現在中断されており、過去1週間彼女は仕事がなかった。彼女は仕事を探していた。そしてスィヤーの言によると、スィーマーは酒飲みで、毎日酔っ払っては騒ぎ、人々を罵ったり、暴力を振るったりすることは日常茶飯事だった。
どうやらスィーマーは、使用人派遣会社や家庭用品マーケティング会社を立ち上げるような起業家精神を持った女性のようだ。だが、事業は必ずしもうまく行っていなかったようで、事件当時は失業状態だった。また、スィヤーによると、スィーマーが、夫がメーラトに所有している家を要求して来たと証言しているが、彼女がメーラトからデリーに出て来たことを考えると、あながち嘘ではないように思えて来る。もしかしたら大家とスィーマーは昔からの知り合いだったかもしれないが、その点については触れられていない。酒飲みなどの点についてだが、これはスィヤーの発言なので完全に信頼することはできないものの、どうもスィーマーは普段からあまり行儀のいい借家人ではなかったようで、近所迷惑になっていたみたいだ。ちなみに、インドで女性の酒飲みというのは稀である。
さて、ヒンドゥスターンの記事で重要なのは10日夜に起こった集団暴行に関する記述である。同記事によると、10日の午後8時15分頃、スィーマーは酔っ払って騒ぎ始めた。スィヤーと近所の人々は彼女を止めようとしたが、彼女は警察署に電話をして警察を呼んだ。駆けつけた警官は人々を落ち着かせ、医療チェックを受けさせるためにスィーマーをラール・バハードゥル・シャーストリー病院へ連れて行った。だが、警察と医者の目を欺いてスィーマーは逃げ出し、午後11時45分頃に大家の家に帰って来た。そしてまた騒ぎ出した。知らせを受けた警官が駆けつけたが、スィーマーは静かにならなかった。そのため、人々は集団で彼女に暴行を加えた。また、医療チェックの結果、彼女が酒を飲んでいたことが証明された。
記事だけで判断する限り、スィーマーの行動には不審な点が多すぎる。なぜ病院から逃げ出したりしなければならなかったのだろうか?このような女性が親告した強姦の訴えを100%信頼していいのだろうか?もし、強姦容疑で逮捕されたラームクマールが無実または罠にはめられたと仮定すると、こういうストーリーが考えられる――事業に失敗して失業し、お金に困っていたスィーマーは、大家の妻が実家に帰省中で留守なのをいいことに、ラームクマールにレイプされたと届出を出した。たまたまラームクマールが自発的に彼女をレイプしたのかもしれないし、スィーマーが彼を誘惑したのかもしれないし、またはレイプされてもいないのに言いがかりを付けたのかもしれない。だが、この場合2番目の美人局的展開が一番事実に近いように思われる。スィーマーは実家から帰って来たスィヤーに対し、訴え取り下げの条件として20万ルピーとメーラトの家を要求する。強姦罪は親告罪なので、被害者が訴えを退ければ罪には問われなくなる。だが、スィヤーはそれを拒否した。近所の人々も、スィーマーの言動には日頃から頭に来ており、スィヤーの味方をした。スィーマーが思っていたほど計画はうまく進まなかった。10日夜、スィーマーは酔っ払って再三に渡って大騒ぎをしたので、遂に人々の怒りが爆発し、彼女に集団暴行を加えるに至った・・・
ラームクマールの強姦容疑については詳細不明だが、1人の人間を集団で暴行して私刑に処すことは立派な犯罪であり、スィヤーや近所の人々は罰せられるべきであろう。また、暴行を静観していた警察も厳罰に処せられるべきだ。だが、事件の一連の流れを見てみると、これも「女性優遇の法律」が少なからず関係しているように見える。女性が「レイプされた」と訴え出れば、その証言だけを根拠に、詳しい捜査もなしに、訴えられた男性は逮捕されてしまう。しかも、「レイプ被害者」には訴えを取り下げるという切り札が与えられており、それをうまく使うことで一攫千金も狙えてしまう。もちろん、本当の被害者は法律を有効利用すべきだが、少し悪知恵が働けば、法律を濫用して他人を貶めたり大金をせしめたりすることが可能である。
たまたま12日付けのタイムス・オブ・インディア紙に掲載されていた2つの何の脈絡もない事件だが、「女性優遇の法律」というキーワードでつながりそうだったので、敢えて取り上げてみた。当然のことながら、どちらの事件も本当の真相は分からない。上で書いたことは、限られた情報からの勝手な推測に過ぎない。
4月11日(金)から13日(日)まで、デリーのチャーナキャプリーにあるネルー・パークでバクティ祭(Bhakti Utsav)が開催されていた。バクティとは神への直接的な帰依を指し、似たような概念であるスーフィズム(イスラーム教神秘主義)との関連も盛んに議論されている。バラモン教やヒンドゥー教の一般的な潮流では、一般人が神に帰依する場合、ブラーフマン(僧侶)を介さなければならないが、バクティ信仰では、バクト(信徒)が神と直接することができると考えられている。歌や音楽はそのひとつの手段であり、バクティ祭ではバクティ信仰やスーフィズムに関連する歌や音楽の披露が行われる。バクティ祭は今年で第6回を迎え、既にデリーの恒例行事となっている。
バクティ祭には、優れたアーティストが呼ばれるのはもちろんのことであるが、毎年ユニークな努力が払われている。それは、なるべく今までデリーでパフォーマンスをしたことがないアーティストを紹介したり、若手の実力派アーティストにチャンスを与えたりすることである。
今までバクティ祭を見に行ったことはなかったが、今年は3日間続けて鑑賞した。ただし、最初から最後まで全員のパフォーマンスを見た訳ではない。午後6時半から開始され、夜まで続くのだが、腹が減ったら帰ることにしていた。最終日以外、大体9時~9時半頃まで鑑賞した。最終日は最初から最後までいた。会場のネルー・パークはアショーカ・ホテルの南にある広大な公園だが、バクティ祭のステージは南側に造営されていた。ステージの裏の大木が白い布とマリーゴールドで飾っており、エキゾチックな雰囲気を醸し出していた。観客席の前半分にはマットが敷かれており、地べたに座り込んでの鑑賞ができた。後ろ半分には椅子席も用意されていたが、バクティ祭を最大限に楽しもうと思ったら、マット席がオススメだ。バクティ祭は、デリー州首相シーラー・ディークシトの後援を受けており、初日には彼女も出席していた。

会場の様子
初日は若手のアーティストが多かった。1番目の演目はストートラ・ガーヤン。ビハール州北部のミティラー地方の伝統的な宗教音楽で、寺院や聖地で歌われて来た。アーティストはヴィピン・クマール・ミシュラとスィッディ・シャンカル。サンスクリット語で神への賛歌を力強く歌っていた。シャンク(法螺貝)やダムルー(デンデン太鼓)などが印象的な使われ方をしていた。

ストートラ・ガーヤン
法螺貝を吹き鳴らす演奏者
2番目も若手アーティストであった。演目はサグン・ニルグン・バジャン。バクティ信仰には2つの大潮流がある。それはサグン・バクティとニルグン・バクティである。サグン・バクティでは、具体的な形のある神に対する信仰が説かれ、ニルグン・バクティでは、偶像を用いずに神に近付く道が重視される。その両方のバジャン(賛歌)が、プネーのプシュカル・レーレーによって歌われた。歌っているときの表情や動作が若い鋭さに満ちていた。

サグン・ニルグン・バジャン
3番目のアイテムは、スーフィー詩人の神秘詩の歌唱。マドー・ラール・フサイン、ブッレー・シャー、カージャー・グラーム・ファリードの神秘詩を、パーキスターンから来たジャーヴェード・バシール&ブラザーズが歌った。特にブッレー・シャーの神秘詩はインドでも人気があり、聞いたことのあるものが多かった。歌い手は2人いたが、どうも息が合っていなかったように見えた。一応左に座っているのがジャーヴェード・バシールで、このバンドのリーダーである。

スーフィー神秘詩
初日はこの後もパドマー・タルワールカル(ムンバイー)によるマラーティー・バジャンと、ボンベイ・ジャヤシュリー(チェンナイ)によるナーマ・サンキールタンがあったが、腹が減ったので帰った。
バクティ祭2日目も最初から鑑賞した。若手のパフォーマンスは1日目のみのようで、2日目からは経験豊かな年配のアーティストが登場した。1番手はケーララ州のソーパナ・サンギート。ケーララ州の寺院で毎日演奏されている寺院音楽である。アーティストはCマーダヴァン・ナンプーティリ。伴奏楽器は太鼓2つのみだったが、透き通った声による独唱で、ケーララ州の寺院をデリーに持って来たかのような荘厳な雰囲気を醸し出していた。

ソーパナ・サンギート
2番目はグジャラーティー・バジャン。グジャラート州サウラーシュトラ地方で歌われている賛歌のようだが、今回のバクティ祭の中で一番印象に残った演目であった。アーティストは、ラージコートから来たヘーマント・ラージャーバーイー・チャウハーンとその仲間たち。皆、グジャラート地方の伝統的衣装を着ての登場。何だかピエロのような滑稽な格好なのだが、衣装で既に他のアーティストたちを圧倒していた。チャウハーン氏は見たところお爺さんなのだが、その歌声は信じられないくらい美しく、まるで天使のようであった。カビールやミーラーバーイーなど、全インド的に有名な中世バクティ詩人の詩から、グジャラート地方の詩人の詩まで、心を込めて歌い上げていた。また、チャウハーン氏の両脇には両手にマンジーラー(小型シンバル)を持った人が座っており、間奏のときにそれらを振り回したりして離れ業を披露していた。

グジャラーティー・バジャン
3番目の演目はマンガンハール。マンガンハールとは「乞食」という意味だが、彼らはラージャスターン州からパーキスターンのスィンド州にかけての砂漠地帯に住んでおり、ラージプートなどの有力者や富豪の庇護の下に歌を歌ったり演奏をしたりしていた人々である。元々ヒンドゥー教徒だったが、イスラーム教徒に改宗した歴史を持っており、ヒンドゥー教的音楽とイスラーム教的音楽の混交が特徴である。インドのマンガンハールの現状は不明だが、パーキスターンでは、音楽に対して規制を科したジヤーウル・ハク政権時代から衰退の一途を辿っているようで、NGOの援助などで何とか持ち応えているようである。今回バクティ祭に呼ばれたのは、パーキスターンのシャフィー・ムハンマド・ファキールとその一団。バンドの構成や歌い方はカッワーリーと似ているのだが、ヒンドゥー教のバクティ詩を歌っており、不思議なメロディーになっていた。

マンガンハール
次の演目はハヴェーリー・サンギート。クリシュナ寺院はしばしば「ハヴェーリー(邸宅)」と呼ばれるが、ハヴェーリー・サンギートはクリシュナ寺院で歌われる賛歌である。通常、神様が人間に何をすべきかを神託を下すものだが、ハヴェーリー・サンギートでは人間が神様に対していろいろ注文を付けるという特徴がある。アーティストはインダウルのゴークル・ウトサヴ・マハーラージ。著名な声楽者でもあり、作詞作曲家でもある。ちょっと怖い外見だが、それを反映するように、古典声楽に近い威厳に満ちた歌い方をしていた。達筆過ぎると何が書いてあるか読めなくなるが、それと同様に喉が達者過ぎても何を歌っているか分からなくなる、そんな感じであった。

ハヴェーリー・サンギート
2日目の最終演目はハンス・ラージ・ハンス(ジャーランダル)によるグルバーニーだったが、やはり腹が減ったので帰った。
1日目と2日目はそれぞれ5演目あったが、最終日3日目は4演目のみ。だが、最終日にふさわしく有名なアーティストが出演するため、もっとも客入りがよかった。1番手はAマヘーシュワル・ラーオ(デリー)によるサンスクリット語とオリヤー語の聖歌。オリッサ州プリーのジャガンナート寺院で歌われているものである。今回のバクティ祭で唯一スィタール(弦楽器)やバーンスリー(フルート)の伴奏が入り、典型的なインド音楽であった。

サンスクリット語とオリヤー語の聖歌
2番手に登場したのは、ボリウッドでも活躍中のシンガー、ハリハランである。基本的にはバジャンであったが、彼のパフォーマンスだけは明らかに他のアーティストたちとは違った。他のアーティストたちは純粋に歌を歌い、演奏をしていたが、ハリハランは観客を乗せることをもっとも重視しており、ショーマンシップ溢れるステージになっていた。さすがエンターテイメントの街ムンバイーからやって来ただけある。また、ギターが入っており、フュージョン音楽になっていた。最初は伴奏者たちと息が合っていない気がしたが、すぐにそれぞれの音を統一させ、見事なパフォーマンスにまとめ上げていた。彼の楽曲はさすがに有名のようで、観客の中には歌詞を丸暗記している人もいた。まだ2番手であったがアンコールも掛かった。

バジャン
ハリハランのボリウッド的なステージから一転して、3番目に来たのはコテコテの古典声楽であった。演目は、ラーグ・サンギートによる「ラームチャリトマーナス(ラームの行状記)」。「ラームチャリトマーナス」は、中世バクティ詩人トゥルスィーダースがラクナウー周辺の方言アワディー語で著した「ラーマーヤナ」の翻訳版であるが、一般的に北インドで「ラーマーヤナ」と言うと、サンスクリット語の原作ではなく、アワディー語の「ラームチャリトマーナス」になる。ちょうど明日14日はラームの誕生日を祝うラーム・ナヴミー祭であり、絶好のタイミングである。一般には「ラームチャリトマーナス」はバジャンのような民俗音楽的手法で歌われるが、今回特殊だったのは、古典声楽の手法で「ラームチャリトマーナス」を歌う試みが行われたことである。アーティストはイラーハーバードのパンディト・ラーマシュレーヤ・ジャー。かなり高齢の頑固そうな声楽者で、パフォーマンスを始める前に、「観客の顔が見えない西洋的ステージは、インド音楽の演奏には適さない」と主催者や観客に訴えていた。やはり達筆ならぬ「達喉」で何を歌っているかいまいち分からなかったのだが、格式高いパフォーマンスであった。

ラーグ・サンギートによる「ラームチャリトマーナス」
バクティ祭最終日最終演目は、スーフィヤーナー・カッワーリー。イスラーム教神秘主義の宗教音楽である。パーキスターンの著名なカッワール、アフタル&サービル・シャリーフ・フサイン兄弟がやって来た。実はこれが一番見たかったのである。昨年から突然カッワーリーに惹かれるようになり、デリーでカッワーリーのコンサートがあると分かったらなるべく見に行くことにしている。だが、どうもインドとパーキスターンのカッワーリーは異なる進化を遂げているようで、どちらかと言うとパーキスターンのカッワーリーの方が評価が高い。そういう訳で、是非パーキスターンの伝統的なカッワーリーを聞いてみたかったのである。幸い、アフタル&サービル兄弟は保守的なカッワールのようであった。伴奏楽器はハルモニウムとタブラーのみで、あとは手拍子とコーラスが入る。だが、アフタル&サービル兄弟の他に、彼らの息子たちも時々リードボーカルに参加しており、かなり賑やかなステージになっていた。佳境を迎えて来ると身振り手振りが激しくなり、アーティストたちの熱狂が視覚聴覚を通じて観衆に伝染していた。パンジャービー語の歌が多かったが、アンコール曲では、カッワーリーの祖と言われるデリー在住詩人アミール・クスローの有名な「Rang」が歌われた。インドのカッワーリーの方がエレキギターやキーボードを使ったギラギラした音とパフォーマンスなのだが、必ずしもそれゆえに豪華さでパーキスターンのカッワーリーに勝っている訳ではないと感じた。伝統的な構成の伴奏によるシンプルなカッワーリーでも、ここまでゴージャスかつ熱狂的なパフォーマンスができることを知った気分であった。

スーフィヤーナー・カッワーリー
バクティ祭を一通り鑑賞したことで、自分の中でバクティ音楽に対するひとつの見解がまとまったような気がする。ヒンドゥー教であれ、イスラーム教であれ、スィク教であれ、神への直接的な帰依を求める歌や音楽にはとても共通点が多く、お互いに影響を与え合って発展して来たことは明らかだ。同時に、インド各地のバクティ音楽を見ると、それぞれの地域の色が出ており、とても面白かった。インドを表現する際によく使われる「多様性の中の統一性」というフレーズが、バクティ音楽にもあてはまる。バクティ祭ではいくつか古典音楽に分類されるパフォーマンスもあったが、どちらかというとそれらは退屈であった。グジャラーティー・バジャンのヘーマント・ラージャーバーイー・チャウハーン、マンガンハールのシャフィー・ムハンマド・ファキール、スーフィヤーナー・カッワーリーのアフタル&シャリーフ・フサインなどの、宗教の融和を説く詩や透き通った信仰心溢れる歌声に、インドの芸術の真の力を感じた。
バクティ祭は入場料無料、招待状なども必要なく、誰でも見に行くことができる。インドの公演は時間通りに始まらないことが多いが、バクティ祭の運営はしっかりしており、午後6時半からピッタリ始まり、演奏を始めると時間のセンスが吹き飛んでしまうアーティストたちにもなるべく時間厳守させていた。大体午後11時ぐらいには終わるようになっている。文化首都デリーを目標として掲げるシーラー・ディークシト州首相の試みは、着実に実を結んでいると言える。
| ◆ |
4月14日(月) インド人の見たチベット問題 |
◆ |
チベット問題の紛糾により、世界中で抗議や妨害に遭遇している北京五輪の聖火リレー。ここデリーでも4月17日に聖火リレーが行われることになっている。チベット亡命政府の拠点があり、多くのチベット難民たちが住むインドは、聖火リレーに伴って世界各地で発生している親チベット反中国運動のクライマックスとなりそうだ。コースはラージパト上、ヴィジャイ・チャウクからインド門にかけての全長2.3kmのものになりそうで、既に道の両脇には堅固なフェンスが設置されている。だが、まだ土壇場での変更の可能性があり、何とも言えない。
果たして、インドの知識人たちはチベット問題、北京五輪、聖火リレーなどについてどう思っているのだろうか?手元にある新聞や雑誌に掲載されていた社説にざっと目を通して整理してみた。基礎知識として重要なのは、インドはダライ・ラマの亡命を受け入れ、チベット亡命政府を庇護していること、インドと中国の間には国境紛争があることである。
■インドは積極的にチベット問題に介入せよ
交渉上手のインド人で成る国であるためか、インドは外交力のある国である。だが、最近中国に対して妙に歯切れが悪くなっており、野党や国民からはそれを心配する声が挙がっている。チベットの人権問題に関し、中国に対して圧力をかけたり、積極的に介入して行くべきだとする意見が多いが、その具体的な方法は、北京五輪ボイコットの行使と、ダライ・ラマとの対話要求である。
3月26日付けのヒンドゥスターン紙には、ジャワーハルラール・ネルー大学のプシュペーシュ・パント教授の「我々はチベットの戦火の傍観者でいいのか(तिब्बत की आग के तमाशबीन क्यों हैं हम)」という論考が掲載されていた。パント教授はまず、国際社会の中で中国がいかに大国であろうとも、中国をインドの宗主国とみなすことはできないし、中国の一喜一憂がインドの外交政策の試金石になってはならないと前置きをしている。そして、インドにとって非常に重要な問題を指摘している。それは水である。
水は命の源である。北インドにはいくつもの大河が流れ、人々の生活を支えている。その内、ブラフマプトラ河、スィンドゥ河、サトラジ河などはチベット高原から流れ出ている。つまり、チベットを支配する中国に首根っこを押さえられた形になっている。中国はこれらの河にダムを作って、中国本土の水不足問題を解決すると同時に、インドへの牽制に使おうとしている。よって、チベットで行われているチベット人弾圧は、インドにとっても無関係ではない。インドと中国は近い将来にも遠い未来にも友好国にはなりえない。安価な労働力であれ、熟練した技術者であれ、巨大市場であれ、常にライバルであり続ける。国際社会にとってインドと中国は選択肢に過ぎない。インド人の方が中国人よりも英語が得意だとか、欧米諸国はインドの民主主義体制を好んでいるとか考えて安心していると、大きな失敗をするだろう。
それらを指摘した後で、パント教授は、インドは北京五輪をボイコットして抗議の意思を示すべきだと主張している。そして、インドはオリンピックに参加しようとしまいと損をする立場にはいない、ならば我々は国益を考えて行動すべきである、チベット問題はオリンピックよりも遥かに重要な問題だ、と述べている。
週刊誌テヘルカー2008年4月12日号では、ラヴィ・ブータリンガムが「チベットで揺れる聖火(A Flickering Torck in Tibet)」という記事で、慎重な書き方ながら、チベット問題に関わることでインドが得られる利益について、さらに突っ込んだ意見を述べている。ブータリンガム氏は、インド工業連盟(CII)印中観光タスクフォースの議長を務めている人物である。彼によると、チベット問題はインドにとっても、チャンスでもあり、危機でもあるとのことである。
ブータリンガム氏の主張によると、長年チベット亡命政府を庇護して来たインドはダライ・ラマの信頼を得ており、ダライ・ラマと中国の交渉の仲介役としてもっとも適した立ち位置にいる。しかも、もし将来チベットが完全な自治を獲得できたら、中国との国境問題の解決が容易になり、二国間関係も良好になる。チベット問題が解決すれば、インドも多大な利益を享受することができるのである。だが、危険なのはチベット問題がインドを感情的な中国バッシングに追い込むことである。北京五輪ボイコットは危険な切り札だ。中国は外国人によって支配された屈辱の歴史を持っており、オリンピックを政治邸手段として利用する者に徹底的に抵抗するだろう。そうなった場合、中国と国境を接するインドは非常に危険な状態にさらされることになる。しかも、もしインドに住むチベット難民がテロリスト化した場合、ダライ・ラマの発言力が低下するだけでなく、インドは国際社会から越境テロ支援国の烙印を押されかねない。インドの国民は自分の見解を自由に表現することができるが、インド政府は非常に慎重に行動することが求められている。
3月31日付けのヒンドゥスターン紙掲載の「国際世論のみが中国を動かせる(विश्व जनमत ही झुका सकता है चीन को)」では、国際問題専門家のプラナイ・シャルマーが、チベットとの対話を開始するように、国際世論によって中国に圧力をかけて行く必要性を強調している。
シャルマー氏はまず、3月下旬に印中間で起きた外交摩擦に触れている。3月21日、チベット人活動家たちがデリーの中国大使館に乱入した事件があった。それを受け、北京政府は在中国インド大使のニルパマー・ラーオを深夜呼び出して注意を与えた。中国は緊急事態だったためと弁明しているが、他国の大使(しかもラーオ大使は女性である)を深夜に呼び出すのは外交儀礼上非常に失礼な行為である。当初インド外務省は反応を示さなかったが、野党からの糾弾を受け、予定されていたカマルナート商工相の中国訪問を中止して抗議を示した。数ヵ月後にはプラナブ・ムカルジー外相の訪中が予定されており、これが実現するか否かが今後の印中関係の試金石になりそうだ。それは、中国がチベット問題をどのように解決するかに依っている。
だが、インド政府がいかに抗議をしようとも、中国が行動を改めるようなことはないだろう。シャルマー氏の主張は、国際社会が中国に圧力をかけなければならないというものだ。中国は2002年から6回に渡ってダライ・ラマの代理人と交渉をしているが、それも国連が圧力をかけたからである。そのとき国連は中国に対し、もしチベットとの交渉を開始しなければ、チベットを独立国として認めると脅した。だが、あれから中国はさらに力を付け、国際的な圧力をかけることが難しくなっている。それでも、世界中の首脳が一丸となれば、再び中国を説得することが可能である。
4月4日付けのタイムス・オブ・インディア紙でも、戦略分析家のブラフマ・チェラニーが「いじめに屈するな(Stop Being Bullied)」で、ニルパマー・ラーオ大使深夜召還事件を取り上げている。だが、彼の怒りは無礼な中国政府よりも、弱腰外交に徹するインド政府に向けられている。
まずチェラニー氏は、深夜呼び出されたラーオ大使はすぐに中国外交部に駆けつけるのではなく、慇懃に、だが断固として、通常業務時間に訪れると返答すべきだったと主張する。しかも、中国は世界最大の民主主義国家に対し、チベット人の抗議権を否定するように要求して来たたけでなく、中国の諜報ネットワークがインド中に張り巡らされていることまで堂々と明らかにした。その上、インドの諜報機関よりも情報収集能力は勝っているとまで発言した。その他にもインドは中国から数々の侮辱を受けているが、インドは黙ったままである。
例えば昨年11月には、スィッキム州、ブータン、チベットの国境地帯で、中国軍がインド陸軍の塹壕を破壊した事件があった。だが、インドはそれに対して抗議しなかったばかりか、事件を覆い隠そうとした。インド政府がそれを認めたのは、事件から4ヶ月後の2008年3月19日であった。実は中国軍は過去2年間に300回以上インドの領土に侵入している。1週間に3回のペースである。だが、それについてもインドは表立って抗議をしようとしない。中国軍はブータンにも侵入している。だが、ブータンの国防の責任はインドが負っているにも関わらず、インドはそれを「中国とブータンの問題」として看過している。最後にチェラニー氏は以下のような警鐘を鳴らしている。
中国は、力を蓄積すればするほど、インドに対して尊大な態度に出て来るだろう。中国の怒りを巧みに処理して来たインドは過去のものとなった。国家間で力関係の不均衡があるからと言って、弱者が強者の顔色を伺う必要はない。外交とは、力の不均衡を相殺し、中和する手段なのである。言行一致の毅然とした行動が後の祭りを未然に防ぐ。インドの現在の日和見的なアプローチは、大きなトラブルを引き起こすだけでなく、国家的損失につながるだろう。
【コメント】チベット問題への積極介入を求めるインド人は、チベットの問題よりもむしろ、インドの外交力の低下を心配しているように見える。チベットはインドの対中外交の重要な切り札であり、いざというときにそれを何らかの形で切ることができなかったら、インドは国家的な損失を被るというのが彼らの共通の認識である。また、穏便な方法でチベットに親インドの独立国や自治区が樹立されれば、それはインドにとって大きな利益になる。インドも本音ではそれを望んでいるだろう。だが、手段を誤るとインドは一転して苦しい立場に立たされることになる。慎重な積極介入という矛盾した姿勢が求められそうだ。
■ブーメランの警戒
チベット問題に深く介入することは、そのままインドにブーメランとして返って来る恐れがあると指摘する人は多い。インドもカシュミール地方やノース・イースト地方で分離独立問題を抱えているため、チベット問題で無闇に中国に圧力をかけると、かえって墓穴を掘ることになりかねない。
4月13日付けのタイムス・オブ・インディア紙では、ギリーシュ・シャハーネーが「チベットに自由を。では、カシュミールは?(Free Tibet. And What About Kashmir?)」という社説を書いている。シャハーネー氏の主張では、チベット独立を支持するインド人は偽善者である。
シャハーネー氏によると、チベット亡命政府がチベット固有の領土として主張する「グレーター・チベット」は、1959年のインド亡命前にダライ・ラマが支配していた領土よりも遥かに大きく、その主張の法的・歴史的な根拠はない。しかも、アルナーチャル・プラデーシュ州もしばしば南チベットと呼ばれる。もし万が一チベットが分離独立したら、アルナーチャル・プラデーシュ州の領有権まで主張し出す恐れがある。チベット独立の正当性も疑わしい。チベットの神権統治者たちは何世紀にも渡ってチベットが中国の一部であると認めて来た。20世紀前半の混乱期にチベットは独立を宣言したが、中国はそれを認めなかった。50年代から60年代にかけてチベットの人々が酷い目に遭ったことは事実だが、大躍進と文化革命はチベットのみならず中国全体に大惨事を引き起こしたことを忘れてはならない。中国共産党は中国全体の人権と自由を尊重するようになって来ており、チベットはそれが進展するのを待つのが得策である。世界の指導者たちが求めているのもそれである。
だが、インド人の多くはチベット問題を誤った視点で見ている。ヤシュワント・スィナー元外相はチベット問題に介入してチベット独立を支援すべきだと主張し、ジョージ・フェルナンデス元国防相もチベット独立を擁護しているが、シャハーネー氏に言わせればこれらは愚かな考えである。インドの軍隊が中国の人民解放軍をラサから追い出すことはまず不可能だし、インドは分離独立運動を抱える国であり、他国の分離独立問題に介入するのは偽善に過ぎない。ジャンムー&カシュミール州問題はその典型例である。しかも、チベットを紛争地域と認める国は一国もないが、インドを含む全ての国はジャンムー&カシュミール州を紛争地域として扱っている。本当ならばチベット問題よりもカシュミール問題の方が他国の介入を招きやすい状態にあるが、インドはカシュミール問題を国内問題として干渉を拒否している。インドは国際社会の中でチベット問題に介入できる権利を持っていない。
3月24日付けのザ・ヒンドゥー紙で、元外務省官僚のMKバドラクマールは、社説「チベット問題とインドのリアクション(Tibet issue and the Indian reaction)」の中で、「インドにとってチベットは外交カードになるか?」と問い掛けた上で、イスラーム諸国会議機構(OIC)の最近の決議案を取り上げている。
OICはイスラーム諸国から成る国際機構で、国連にも常任代表を送っている。インドは世界で3番目に多くのムスリム人口を抱える国であり、OICへの加盟に興味を示しているものの、盟主的立場にいるパーキスターンがカシュミール問題の解決をインド加盟の条件としているため、未だに加盟できていない。それだけでなく、OICは過去何度もカシュミール問題を取り上げて来た。2008年3月にセネガルの首都ダカールで開催されたOIC首脳会議でも、改めて「カシュミール地方インド占領区」におけるカシュミール人の「窮状」に対して遺憾の意が表明され、インドに対してカシュミール人に自決の権利を与えるように要求する決議案が可決された。イスラーム諸国の間では、インドが西アジア外交に関して米国追従の姿勢を強めていると考えられており、それが今回の決議案の遠因となったようである。一方、インド政府はOIC決議案に対して遺憾の意を表明すると同時に、「OICは、インドの固有の領土であるジャンムー&カシュミール州の問題を含む、インドの内政問題に関する事柄について提訴権を有していない。我々はそのようなコメント全てを強く拒否している」と声明を発表している。バドラクマールはインド政府の対応を「少しの刺激に反射的にトゲをとがらすヤマアラシ」と揶揄し、チベット問題への介入がインドにブーメランとして返って来る可能性を指摘している。
【コメント】チベット問題において、インドが微妙な位置に立たされていることは明らかである。その理由のひとつは、多民族国家特有のジレンマだ。インドも中国も多民族国家であり、分離主義者たちに手を焼いている。だが、カシュミール問題やノース・イースト問題を理由に積極的な外交に乗り出さないのは、長い目で見た場合、インドにとって結局不利になるのではないか。チベット問題に介入しないことでカシュミール問題が解決するわけではない。どちらも解決の糸口を見つけられるように行動して行く方が、国際社会に対する示しも付くだろう。
■インドは対中政策を見直すべきだ
インドの対中政策そのものの転換を求める声は強いが、その方向性は真っ二つに別れている。すなわち、中国に対してより強気の態度で臨むべきだという意見と、中国との関係をより強化して行くべきだという意見である。面白いことに、前者はインドが今まで中国を信頼し過ぎたと思っており、後者はインドが中国を未だに敵国とみなしていることに懸念を表明している。
4月14日付けのタイムス・オブ・インディア紙では、パーキスターンの高等弁務官(大使)を務めたこともある外交官Gパルタサラティーが「過去の過ちを繰り返すな(Avoid Past Mistakes)」という論考を寄せている。パルタサラティー氏によると、インドは独立後しばらくの間、ヒマーラヤ山脈をインドの国土の北端を守護する自然のバリアと考えていた。だが、1950年に中国共産党がチベットを支配下に置いたことで、その考えを改める必要に迫られることになった。ジャワーハルラール・ネルー首相やKMパニッカル在中国インド大使は、毛沢東率いる中国共産党や中華人民共和国を、アジア再興の新時代を告げる使者と考えていた。だが、サルダール・パテール副首相やCラージャゴーパーラーチャーリーは中国に大きな懸念を抱いていた。1954年4月、インドは中国と国境貿易協定を結び、チベットを「中国の一部」と認めたが、「中国領チベット」がどこからどこまでを指しているのか、中国に真意を尋ねようとする者はインドにはいなかった。それから数ヵ月後、インド国境警備隊はウッタル・プラデーシュ州(当時)とチベットの国境で人民解放軍が活動しているのを発見する。また、中国の地図にラダック地方の大部分とアッサム地方の一部(現在のアルナーチャル・プラデーシュ州)が中国領と記されているのも発見される。インド側の抗議に対し、中国はそれを「古い地図」と言って改訂を約束するが、中国の意味する「チベット」の本当の範囲は、1962年の中印国境紛争で明らかになった。インドは半世紀に渡ってチベットを中国の固有の領土として認める発言を盲目的に公表して来ている一方、中国はラダック地方の大部分やアルナーチャル・プラデーシュ州をチベットの一部と主張し、マンモーハン・スィン首相のアルナーチャル・プラデーシュ州訪問を非難している。力を付けた中国は、インドに対してだけでなく、日本、ヴェトナム、フィリピンなどのアジア太平洋諸国に対しても強硬な国境政策に出ている。中国の領土的野心は経済力の成長に比例して増大して来ており、中国周辺諸国の大いなる脅威となっている。
また、パルササラティー氏は中国の欺瞞に満ちた外交を非難している。1951年5月23日、中国はチベットと17条協定を結んだ。この協定の中で中国共産党政府はチベットの現行の政体を維持することや、信教の自由、チベット語・チベット文化の振興などを明記している。だが、中国はそれらの条項のひとつも守らず、チベット人を怒らせ、1959年のチベット蜂起を引き起こした。
これらの前置きをした上で、パルタサラティー氏は、中国がアルナーチャル・プラデーシュ州とラダックの大部分をチベットの一部とする主張を放棄しない限り、インドはチベットを中国の固有の領土と盲目的に発言するのを止めるべきだと述べている。また、中国はダライ・ラマがインドから反中国活動を扇動していると主張しているが、インドは中国に対し、1951年の17条協定を遵守し、ダライ・ラマが安全にチベットに帰還できるような態勢を整えるべきだと主張し返すべきだとも述べている。
一方、先ほども出て来たMKバドラクマールは、4月10日付けのザ・ヒンドゥー紙掲載の社説「友好的隣国としての中国(Engaging China as a friendly neighbour)」において、チベット・カードなるものは存在しないと断言し、インドに対して、新しい現実を受け入れ、新しい考え方を採用するように促している。
バドラクマール氏は6つの現実を提示している。1.中国は世界の大国に台頭しつつある。2.中国の台頭はもはや逆行不可能である。3.国際社会は中国の台頭に折り合いを付けつつある。4.中国は世界経済の欠かせない一部となっており、誰も「チベット・カード」や中国の分裂を真面目に語らなくなっている。5.米国は中国に対して封じ込め政策を実施することはできない。6.中国は国際システムの中のステークホルダーになろうとしている。それだけでなく、バドラクマール氏によると、中国の台頭により国際システムそのものが変わろうとしている。中国は既にアジア太平洋地域や東南アジア地域に変革をもたらしており、その影響力が南アジア地域に及ぶのも時間の問題である。このような状況下においてインドにとって必要なのは、中国を友好的隣国として扱うことである。「チベット・カード」のようなフィクションに囚われることなく、国境問題を積極的に解決していく態度が求められている。米国、日本、オーストラリアとの「四ヶ国同盟」に参加したのは破滅的な間違いだった。この構想は元より崩壊する運命にあった。この失敗は、意味のない反中国運動として表れてしまった。だが、インドの外務省や中国のインド大使館は、インド人の思考の中からその「ネオコン」的構想を排除し、中国との友好関係促進に邁進している。
【コメント】元外交官のバドラクマール氏は完全に中国寄りの考えを持っている。おそらくインドの外務省の中にもいわゆるチャイナ・スクールなどいろいろな派閥があり、互いに綱引きをしながら外交方針を決定しているのだろう。突然日本の名前が出て来たが、その書き方から察する限り、インドのチャイナ・スクールは日印関係を軽視する傾向にありそうだ。もし日本とインドがチャイナ・スクールの手に落ちたら、それは中国の思う壺であろう。一方、パルタサラティー氏の見解は、インドの過去の対中政策の失敗から学ぶことを促している。インドは一度中国に痛い目に遭っているので、彼のような考え方の方が一般的だと思われる。
■ダライ・ラマの戦略は失敗、チベットは現実を受け入れよ
ザ・ヒンドゥー紙の中国特派員パッラヴィー・アイヤルは、4月3日付けザ・ヒンドゥー紙掲載の社説「中国はダライ・ラマとその主張についてどう考えているか(How China sees the Dalai Lama and his cause)」で、ダライ・ラマの政策の失敗を指摘している。
アイヤル氏によると、一般の中国人はダライ・ラマ14世がノーベル平和賞を受賞したことも知らないと言う。中国人の学生は学校で、中国共産党政府がダライ・ラマの封建主義的神権体制を打ち破ってチベットの人々を解放したと教えられている。チベット人は中国統治下で経済発展を享受していると思い込んでいる一方、ダライ・ラマを、チベット分離独立を企む邪悪な存在と決め付けている。それだけでなく、多くの中国人は、チベット人が政府から数々の優遇を受けていると考えている。例えば、一人っ子政策はチベット人には適用されていない。よって、一般の中国人はチベット人蜂起の原因を全く理解しておらず、単なる暴動と見ており、欧米のメディアがダライ・ラマ寄りの偏向報道をして中国に言い掛かりを付けていると考え憤っている。彼らの中では、中国人こそが世界の中の犠牲者なのだという感情が沸き起こっている。
このような状況のため、中国共産党政府は、国際社会よりもまず先に国内に向けて面子を保つ必要に迫られている。欧米諸国は中国に対しダライ・ラマ14世との交渉を求めている。確かにダライ・ラマ以外にチベット問題を平和的に沈静化させられる力を持った存在はいないし、ダライ・ラマとの交渉開始を宣言するだけで、国際社会の中で中国は批判を最小限に抑えることができるだろう。そして北京五輪ボイコットの動きにも歯止めががかかるだろう。だが、中国は今まで散々ダライ・ラマを悪人扱いして来たため、そんなことをしたら国民の不満が爆発し、国家崩壊の危機を招いてしまう。中国にとってダライ・ラマとの交渉は決して受け入れることのできない手段なのである。
だが、アイヤル氏によれば、中国共産党政府のチベット政策の行き詰まりには、ダライ・ラマにも責任があると言う。1989年1月28日にパンチェン・ラマ(チベット仏教界で2番目に高位の僧侶)が死去し、2月15日に葬儀が行われたが、このとき中国はダライ・ラマを葬儀に招待している。しかし、ダライ・ラマはそれを拒否し、代わりに欧米諸国との関係強化を図った。同年、ダライ・ラマはノーベル平和賞を受賞しているが、このときから中国の政治家たちはダライ・ラマをチベット問題の交渉人としてみなさなくなり、彼の死を待つ消極的な道を好むようになった。ダライ・ラマの後継者が誰であれ、14世ほど影響力を持つことはないだろうとの判断である。
アイヤル氏の主張では、ダライ・ラマはチベット問題解決のため無闇に欧米の力を借りようとしたため、中国がこの問題で妥協しにくくなってしまったばかりか、かえってチベットに対してますます強硬な政策を取るようになった。世界各地で北京五輪ボイコットや聖火リレー妨害などの運動が起き、ダライ・ラマとの交渉を求める声が挙がっているものの、アイヤル氏は上記のような理由から、それが中国のチベット政策転換のきっかけになることはありえないと考えている。
アイヤル氏と似た主張をしているのが、「Tibet, Tibet: A Personal History of A Lost Land」の著者パトリック・フレンチである。インド人ではないが、関連があるのでここで取り上げておきたい。テヘルカー誌の2008年3月29日号に掲載されていたインタビュー「ダライ・ラマはハリウッドの利用をやめるべきだ(The Dalai Lama should quit his Hollywood approach)」で彼は、ダライ・ラマやチベットに対してシビアな意見を述べている。
まずフレンチ氏は、3月10日にラサで起きた暴動の原因を昨年まで遡って考えている。2007年10月、ダライ・ラマは米国議会から議会金メダルを授与された。このメダルは議会から文民に与えられる最高勲章のようで、ブッシュ大統領が自らダライ・ラマにメダルを手渡した。この様子は世界中で放映され、チベットでもボイス・オブ・アメリカを通じて報道された。これを知ったチベット人の多くが、米国がチベット独立運動支援を決定したと勘違いしたことが、そもそも蜂起の原動力となったとフレンチは指摘している。さらにこのとき、チベットの僧院で受勲を祝った僧侶たちが逮捕されており、3月10日のチベット民族蜂起49周年記念日に彼らの解放を求めたデモが僧侶たちによって行われた。また、ラサ在住のチベット人の間では、チベット経済を握る外来の漢民族や回族に対する不満が蓄積されており、僧侶たちのデモは経済的な動機に基づく抗議運動に拡大して、チベット人以外が経営する店舗への破壊活動につながった。これが大規模な暴動と弾圧に発展したというのが、フレンチ氏の見方である。
その後フレンチ氏は、若く先進的なチベット人の多くは流暢な中国を話し、中国本土へ行って教育を受けており、中国共産党政府のシステムの下で生きていくことを選んでいること、1950年以前のチベットは必ずしも平和な社会ではなく、僧院同士で戦争が多発していたこと、ダライ・ラマはインドに亡命してから非暴力を主張し始めたこと、マハートマー・ガーンディーが「非暴力の抵抗」を行ったのに対し、ダライ・ラマは「非暴力」を主張するだけで「抵抗」らしきものをして来ていないことなどを指摘している。
フレンチ氏の主張で興味深いのは、ダライ・ラマとハリウッドとの関係に対する批判である。80年代末からダライ・ラマはハリウッドとの結び付きを強め、それによって欧米諸国で多大な支持を受けるようになった。フレンチ氏によれば、この戦略は当時一定の意味を持っていた。なぜならその頃ソビエト連邦が崩壊し、次は中国共産党政権が崩壊すると考えられていたからだ。しかし、90年代半ばまでにこの戦略の失敗が明らかになる。中国は崩壊しなかったし、チベットを巡る状況も改善されなかった。そればかりでなく、欧米の力をバックに運動を繰り広げるチベットに対し、中国はより一層態度を硬化させてしまった。フレンチ氏は、ダライ・ラマは90年代初めまでにハリウッドとの連携を解消し、中国政府との静かなバックチャンネル外交に専念すべきだったと振り返っている。欧米諸国で大規模なロビー活動や抗議運動が行われたが成果はゼロで、それによってチベットの状況は悪化こそすれ、改善はされていない。では現在チベット人はどうすればいいのだろうか?フレンチ氏は、現実を受け入れ、中国共産党政府のシステムの中で生きて行くしかないと悲観的である。中国はその体制上、これからも決してチベットの独立を認めないため、チベットの独立が実現するのは、中国で政権交代があったときのみだと述べている。
3月26日付けのザ・ヒンドゥー紙の社説「チベット問題(The question of Tibet)」でも、ダライ・ラマは現実を受け入れるべきだと述べられている。記者は明記されていなかった。
社説の中では、まず3月10日以降にチベットで発生した事件の実態や被害者数について、中国の報道そのものが繰り返されており、それは民主的な蜂起や独立運動などではなく、単なる暴動と略奪に過ぎなかったと述べられている。また、チベットを中国の一部だと認めていない国や、ダライ・ラマのチベット亡命政府を正当な政体と積極的に認めている国はひとつもないことが指摘され、国際社会の中でコンセンサスに乏しいカシュミールの問題とチベット問題は別であることが強調されている。そして、チベットは6年以上に渡って12%の高い成長率を維持していること、中国は2002年以降6回に渡ってダライ・ラマの代表と協議を行っていること、ダライ・ラマの要求するチベットへの「一国二制度」適用や「グレーター・チベット」形成は現実的ではないことなどが論じられ、最後にこう結論付けられている。
1959年以降ダライ・ラマと彼の信者たちを庇護して来たことによって得た影響力をインドが行使するときが来た。チベットの将来について現実的に考え、「ひとつの中国」の枠組みの中で、合理的かつ持続可能な政治的解決法を導き出すため、中国政府と真摯な対話をするように、ダライ・ラマを説得するか、圧力をかけるべきである。
再びザ・ヒンドゥー紙になるが、4月4日付けの同紙に掲載された「チベットから中国のチベットへ:歴史はチベットの味方か?(From Tibet to China's Tibet: Is history an ally for Tibet?)」で、ディビエーシュ・アーナンドが中国寄りの意見を述べている。ディビエーシュ・アーナンドは「Geopolitical
Exotica: Tibet in Western Imagination」の著者で、ウェストミンスター大学の教授である。
アーナンド教授はチベットの歴史を振り返り、チベットの独立運動がどこまで正当化されるかを論じている。確かに1913年から1949年まで、チベットは事実上の独立状態にあった。だが、当時どの国もチベットを独立国として認めていない。インドを植民地化し、チベットの独立を認めやすい立場にいた英国ですらも、チベットの独立を認めなかった。よって、その時期でも中国の支配を否定することはできず、独立運動は歴史的に正当化されない。チベット問題は20世紀前半の地政学の変化がもたらしたものである。チベットにとって不幸だったのは、中国のナショナリズムがチベットよりもかなり早く起こったことと、英国がチベットに対し不干渉主義を取ったことである。チベット人は脱植民地の重要なチャンスを逃してしまった。中国が解体したり、強力な国家の後ろ盾がなければ、もはやチベットの分離独立は不可能であるが、それらの条件が実現する可能性はない。これらのことを述べた上で、アーナンド教授はチベット人や中国政府に対し以下のような提案をしている。
・・・彼らに残された道は、中国の政体の枠組みの中で闘争を繰り広げることのみである。中国は原則的に少数民族に対し大幅な自治権を認めている。「フリー・チベット」のために戦うよりも、「中国のチベット」のために戦った方が、チベット人にとっても、中国人にとっても、解決が容易であろう。もちろん、そのためにまず必要なのは、中国が心を大きく変えることだ。北京政府は、チベット人を中国の中で従属的な地位に追い込むことはできないと気付くべきである。そして、中国の中で彼らの願望が叶えられるようにすべきである。「中国のチベット」は抑圧の場所であってはならない。それは、台頭するドラゴンの包括的ナショナリズムのための真の見本になりうる。
【コメント】南インドを本拠地とするザ・ヒンドゥー紙は、インドの新聞の中でも硬派な部類に入り、記事も信頼が置ける。だが、こうしてチベット問題に関して同紙が掲げる社説を見ると、中国寄りのものばかりである。北京五輪の取材許可か何かを気にしているのか、それとも中国に買収でもされてしまっているのだろうか?この点ではタイムス・オブ・インディアの方がバランスが取れているように見える。ヒンディー語のヒンドゥスターン紙は親チベット的な社説が多かった。欧米諸国でチベット独立に対する支持を集めたことが、かえってチベット本土での独立運動の障害になったという考えは、的を射ているように思われる。仏教は故郷のインドで廃れた一方で、周辺地域に広まり、発展した。チベット問題もどこか似た部分がある。
■チベット問題とはあまり関係ないユニークな意見
4月10日付けのタイムス・オブ・インディアで、サティーシュKシャルマーという人物が「オリンピック会場を固定せよ(Station the Olympics)」というコラムの中でぶっ飛んだ意見を述べている。シャルマー氏はまず、北京五輪のボイコットの可能性に触れ、オリンピックは常に政治利用されて来たことを過去の例を挙げて論じている。その後、彼は国際政治からどのようにオリンピックを解放すべきか、と問い掛けている。シャルマー氏の意見はこうである。
・・・ひとつの解決法は、スイスのような中立国を恒久的なオリンピックの会場とすることだ。しかし、スイスは小国であり、このような重責を負うことを好まないだろう。となると、次なる最善の解決策は、インドがこの役割を担うことである。インドは今まで世界平和を推進して来たことで確固たる記録を作っているし、インドのオリンピックの歴史はさらに輝かしい。インドは、メダル獲得こそほとんどないが、1928年から連続で五輪に参加している。ピエール・ド・クーベルタンの有名な格言「オリンピックは勝つことでなく参加することに意義がある」を地で行く国である。インドは、広大で、様々な気候を内在し、経済も右肩上がりであるため、オリンピックの恒久的会場としてピッタリである。また、この案はインドに経済的利益をもたらすだけでなく、ソフトな大国としての地位確立に貢献する。当然、インドのスポーツ界にも多大な刺激となるだろう。
【コメント】確かに2020年の五輪会場としてインドは最有力候補に挙がっているが、インドが恒久的な五輪ホスト国になるべきだ、というこの案はどこまで本気で提案しているのだろうか?
3月27日付けのタイムス・オブ・インディア掲載の社説「笑い事ではない(No Laughing Matter)」では、ボーリヤー・マジュムダールというスポーツ史家が、聖火リレー以外に中国が取り組まなければならない問題を指摘している。それは、中国の英語問題である。マジュムダール氏は、「中国がいくら金メダルを獲得しようとも、どんなにインフラや交通に投資しようとも、五輪の成功の鍵を握るのは、中国人の英語学習が間に合うか否かにある」と述べている。中国のタクシードライバーのほとんどは英語が苦手で、中国語で書かれた住所を持っていなければ、行きたい場所にスムーズに行けない状態にある。不幸なことに、中国に着いた外国人がまず接触するのが、これらのタクシードライバーなのである。このような状態では、外国人の中国に対する第一印象は悪くならざるをえない。中国政府やタクシー会社は、現在必死でタクシードライバーの英語力向上に努めている。五輪開催期間中は、外国語に堪能なボランティアも動員する予定のようだ。
空港から無事にホテルに辿り着けたとしても、次の難関が待っている。それは食事である。中国のレストランの大半は英語のメニューが用意されていない。北京の中心街のレストランでは最近になってようやく英語のメニューが導入されたが、少し郊外に行くと、まだまだ中国語メニューのみしかないことがほとんどである。おそらく筆者の経験談であろう、レストランでの混乱がこんな風に書かれていた。「塩を頼んだらコショウが出て来て、違うと言ったら出て来たのはマスタード、その次は正体不明のスパイスが運ばれて来た。冷たい水を頼んだら、沸騰したお湯が出て来た!」
英語の他にも大気汚染の問題に触れられていた。だが、マジュムダール氏は最後に、数々の不安要因があるものの、中国は五輪を成功させ、チベット人による抗議のような「刺激物」も一掃するだろう、と結論付けている。
【コメント】日本も十分英語の通じない国だが、東京五輪だって成功させたし、つい数年前にはFIFAワールドカップも開催している。よって、現地人の英語の能力はそれほど心配しなくてもいいのではないかと思う。タクシードライバーのレベルになったら、インドでも英語は通じにくくなる。インド人は、世界中どこでも英語が通じ、教養層は皆英語を話すと思い込んでいるところがあり、時々こういうぶっ飛んだ意見が出て来る。
とりあえずデリーで聖火リレーが行われる4月17日まで、チベット問題、北京五輪問題、聖火リレー問題などに関するインドの世論がどう動くのかを、新聞の社説などを注視して行こうと思っている。
| ◆ |
4月16日(水) U Me Aur Hum |
◆ |
昨年末、人気男優アーミル・カーンが「Taare Zameen Par」で監督デビューを果たした。アーミル・カーンは寡作な代わりに各作品に全身全霊をつぎ込む完璧主義者として知られており、昔から監督志向が強いとされて来た。よって、彼が監督デビューしても、「遂に」という声が上がりこそすれ、驚きの声はほとんど聞かれなかった。だが、アジャイ・デーヴガンの監督デビューは意外性に満ちていた。アジャイ・デーヴガンはアクション・スターとして人気のある渋めの男優で、映画監督タイプの人物ではないというのが大方の見方だっただろう。その彼が初めてメガホンを取り、妻のカージョール・デーヴガンをヒロインに据え、主演監督作「U
Me Aur Hum」を発表した。これで失敗作に終われば「やっぱり慣れないことするから言わんこっちゃない」ということになったのだろうが、さらに意外なことに、「U
Me Aur Hum」は公開と同時に多くの批評家から高い評価を受けている。
題名:U Me Aur Hum
読み:ユー・ミー・アォル・ハム
意味:君と僕、そして僕たち
邦題:君と僕、そして僕たち
監督:アジャイ・デーヴガン
制作:アジャイ・デーヴガン
音楽:ヴィシャール・バールドワージ
作詞:ムンナー・ディーマン
振付:アシュレー・ロボ、ガネーシュ・アーチャーリヤ
衣装:アンナ・スィン、マニーシュ・マロートラー
出演:アジャイ・デーヴガン、カージョール・デーヴガン、ディヴィヤー・ダッター、イーシャー・シェールワーニー、カラン・カンナー、スミート・ラーグヴァン、ムケーシュ・ティワーリー、サチン・ケードカル
備考:PVRプリヤーで鑑賞。

カージョール・デーヴガン(上)とアジャイ・デーヴガン(下)
| あらすじ |
医師仲間のアジャイ(アジャイ・デーヴガン)、ニキル(スミート・ラーグヴァン)、その妻リーナー(ディヴィヤー・ダッター)、ヴィッキー(カラン・カンナー)、その恋人のナターシャ(イーシャー・シェールワーニー)は豪華クルーズに参加してエンジョイしていた。ニキルとリーナーは夫婦喧嘩ばかりの「アンハッピー既婚カップル」だった一方、ヴィッキーとナターシャーは「ハッピー未婚カップル」を謳歌していた。
アジャイは、クルーズのバーでバーテンダーとして働くピヤー(カージョール・デーヴガン)に一目惚れする。アジャイはピヤーの日記を盗み見て彼女の好みや夢を研究し、うまく口説くが、正直にそのことを明かすと一転して嫌われてしまう。だが、ムンバイーに戻って来た後にピヤーはアジャイに電話して再会する。こうして2人は結婚することになった。
ところがある日突然ピヤーにアルツハイマー病の症状が表れ始める。アジャイの先輩の精神医サチン・クラーナー(サチン・ケードカル)は精神病院への入院を勧めるが、アジャイはそれを認めなかった。さらに悪いことに、ピヤーは妊娠していた。妊娠と出産はアルツハイマー病を悪化させる可能性があった。ピヤーは男の子を産み、アマンと名付けられたが、ある日アマンを入浴させていたときにそれを忘れてしまい、アマンは危うく溺死寸前に陥ってしまう。それを機にアジャイはピヤーを、サチンの運営する精神病院へ入院させる。
だが、ピヤーを入院させて一番苦しみを味わったのはアジャイ自身であった。アジャイは考えを変え、サチンに無理を言ってピヤーを退院させる。アジャイは何があっても彼女の世話をし続けることを誓う。
25年後・・・。かつてアジャイとピヤーは、結婚25周年をクルーズ上で祝うと約束していた。アジャイはピヤーをクルーズに連れて行き、かなりの記憶を失ってしまった彼女の前で、今までの2人の話を、とある誰かの話として聞かせるのだった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
映画は25年後のシーン(現在)から始まる。食堂らしき場所で、ある年配の男が、ある年配の女性を口説こうとする。なかなか連れない女に対し、男はアジャイとピヤーという男女の美しくも悲しい恋物語を聞かせる。最初それはいかにもフィクションのように語られるが、実はそれはその年配の男女自身の25年前の恋物語であった。アジャイは、アルツハイマー病に侵された妻のピヤーに対し、2人の出会いから結婚、そして苦難を乗り越えるまでの話を聞かせたのだった。全ての話が終わった後、再び現在のシーンに戻り、それが2人の結婚25周年の日であること、そしてその食堂がクルーズのものであることが明かされる。ピヤーは、アジャイのことを全く忘れてしまう日もあれば、覚えている日もあった。最初彼女はアジャイを他人扱いするが、実はこの日は彼のことを覚えていた。だが、それでも彼女は忘れた振りをして、全ての話を聞いていたのだった。
前半だけ見るとただのロマンス映画かと思うが、後半はアルツハイマー病に悩まされる夫婦の物語となり、かなりヘビーになる。だが、エンディングは再びロマンチックにまとめられていた。全体的に冗長な展開であり、もっとスリムにできたと思う。特に中盤から後半にかけてのヘビーなシーンが長すぎて気が重くなる。しかし、逆に言えば各シーンで丁寧な描写が心掛けられており、アジャイ・デーヴガンにここまで繊細なセンスがあったのかと驚かされる。カメラワークにも工夫が見られ、登場人物の心理状態を映像のみで表現する努力が随所に見られた。
アルツハイマー病という難病を扱った意外にも重い映画だったが、核となっていたのはやはり「愛」であった。もしアルツハイマー病を脳の問題だとしたら、愛は心の問題である。そして、たとえ脳が何と言おうと、全てを忘れようと、心に愛があれば、心が感じることができ、脳を言い聞かすことができると説かれていた。そして、妻がアルツハイマー病のおかげで、毎日女性を口説く楽しみが得られると冗談めかして語られていた。もちろんそれはいかにも映画的な解決法であり、現実世界で本当にアルツハイマー病の患者と接している人から見たら一言言いたくなるだろう。だが、歴史映画に必ずしも完全な史実性が求められないのと同様に、その点でこの映画を批判するのは筋違いだと感じる。この映画はアルツハイマー病の解説ビデオではなく、あくまで「愛」という永遠のテーマの意味に迫った純粋なロマンス映画である。
監督デビューという意味では「U Me Aur Hum」はアジャイ・デーヴガンのために作られたような映画だが、実際に映画を見てみると、妻のカージョール・デーヴガンに捧げられた映画だと感じられた。彼女への愛の表現であると同時に、彼女の演技の才能を最大限に引き出せるように巧みにいろいろな見せ場が設定されていた。アジャイ自身も優れた演技をしており、この2人には賞賛が送られるべきである。映画中のアジャイの友人たちを演じた脇役の中では、男優陣よりも女優のディヴィヤー・ダッターとイーシャー・シェールワーニーの方がよく知られている。だが、男優のカラン・カンナーとスミート・ラーグヴァンもそれぞれいい味を出しており、映画を盛り上げていた。
音楽はヴィシャール・バールドワージ。全体的にシリアスな映画であったが、要所要所にうまくダンスシーンが織り込まれていた。バラード風タイトル曲「U
Me Aur Hum」、ラテン系音楽の「Jee Le」、バーングラー風ダンス曲「Phatte」など、バラエティーにも富んでいる。
「U Me Aur Hum」は、アジャイ&カージョールのデーヴガン夫婦が力を合わせて作り上げた良作である。基本的には高年層向けのロマンス映画であるが、中盤はヘビーな展開が延々と続くので多少気が重くなる。だが、最後には感動できるように何とかまとめてある。素直に新人監督アジャイ・デーヴガンに賞賛を送るべきであろう。
2005年に「Kisna: A Warrior Poet」という映画が公開された。副題の「A Warrior Poet」は日本語に訳せば「戦士詩人」になるだろうか。戦士と詩人というのは一見すると相反する職業のような感じがするのだが、中世インドでは、王に仕える詩人たちは戦争に同行して詩によって兵士たちの士気を高め、勝利の暁には王の戦績を詩にして記録し、必要に応じて武器を取って戦ったと言うし、現代ヒンディー語文学界でも、ヤシュパールやパニーシュヴァルナート・レーヌのように独立運動や反政府運動に積極的に身を投じた文学者たちをその言葉で呼ぶことができるだろう。インド以外では、「三国志」好きな僕には「矛横たえて詩を賦す」と表現される魏の曹操も思い浮かぶし、ヘミングウェイのように実際に戦争に参加し、優れた戦争文学を著した現代作家を挙げることもできるだろう。
デリーにも1人の戦士詩人の墓がある。世界遺産フマーユーン廟の南、ニザームッディーン・アウリヤー廟の東にあるカーネ・カーナーン廟である(EICHER「Delhi
City Map」P98 H6)。フマーユーン廟に似た建築だが、保存状態は比べるべくもない。その癖、入場料を取る遺跡になっており、インド人は5ルピー、外国人は100ルピーを支払わなければならない。

カーネ・カーナーン廟
アブドゥル・ラヒーム・カーネ・カーナーン(1556-1627年)は、ムガル朝の真の立役者と言われる名将バイラム・カーンの息子であり、アクバルの首相を務めた人物である。バイラム・カーンはアクバル即位後の1561年に政敵によって暗殺されてしまうが、アクバルが当時4歳のアブドゥル・ラヒームの世話を引き受けたため、彼は宮廷の恵まれた教育環境の中で育てられた。成長したアブドゥル・ラヒームはムガル軍の司令官としてグジャラート、スィンド、デカンなどを転戦し、ムガル帝国の領土拡大に貢献した。その功績により、1584年には「カーネ・カーナン(カーンの中のカーン)」の称号を受け、5,000のマンサブを与えられた。アクバルの統治機構の中では官位(マンサブ)の序列が数字で表されていたが、5,000マンサブは最高位であった。また、1589年には首相に就任した。アブドゥル・ラヒームは軍事的才能に優れていただけでなく、アラビア語、ペルシア語、トルコ語、サンスクリット語、ポルトガル語など、多くの言語をマスターしており、詩才文才も発揮した。ムガル朝創始者バーバルがトルコ語で著した自叙伝「バーバルナーマ」をペルシア語に翻訳した他、ヒンディー語文学史の中では、バクティ詩人ラヒーム・ダースとして有名である。アクバルの息子サリーム(後のジャハーンギール)の家庭教師も務め、アクバルの死後はジャハーンギールに引き続き首相として仕えた。だが、晩年はクッラム(後のシャージャハーン)の反乱に加担して捕えられてしまう。領地や官位は没収されたが、後に許されて釈放され、「カーネ・カーナン」の称号も返還された。だが、既に実権は失っており、経済的な困窮の末に1627年に病死する。
アブドゥル・ラヒームはトルコ系イスラーム教徒であったが、宗教的に寛大な政策を採ったアクバルに寵愛されて育って来たためか、ヒンドゥー教の文化にも多大な関心と理解を示していた。ラヒームはクリシュナ神へのバクティ(信愛)を謳い上げた詩を書いている。また、戦場では勇猛果敢な戦士だったラヒームが現地語(アワディー語やブラジ語など)で書く詩は、意外なことに実生活に密着した格言的内容のものが多く、普遍の愛情や貧しい人々への同情に満ちたものになっている。中世バクティ詩人カビールの詩とも多くの共通点が見られる。
रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय।
टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गाँठ परि जाय॥
Rahiman dhāgā prem kā, mat toro chatkāy
tūte se phir nā jure, jure gānth pari jāy
ラヒームよ、愛の紐を切ってはいけない
切れたら二度と結ばれない、結ばれたとしても結び目が残る
रहिमन देखि बड़ेन को, लघु न दीजिये डारि।
जहाँ काम आवै सुई, काह करै तलवारि॥
Rahiman dekhi baren ko, laghu na dījiye dāri
jahān kām āwai suī, kāh karai talwāri
ラヒームよ、偉い人と仲良くなっても、貧しい人を忘れないでくれ
針ができる仕事を、剣はすることができない
जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग।
चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग॥
jo Rahīm uttam prakriti, kā kari sakat kusang
chandan vish vyāpat nahīn, lipte rahat bhujang
ラヒームよ、真の聖人は悪者と共にいても何も影響を受けない
白檀に蛇が横たわったとしても、毒で犯されることがあろうか
कहि रहीम संपति सगे, बनत बहुत बहु रीत।
बिपति कसौटी जे कसे, ते ही साँचे मीत॥
kahi Rahīm sampati sage, banat bahut bahu rīt
bipati kasautī je kase, te hī sānche mīt
ラヒームよ、金のあるときは多くの友人ができるだろう
だが困っているときに側にいる人が真の友人だ
アブドゥル・ラヒームは詩人であっただけでなく、他の詩人たちのパトロンとなって文芸を振興した。同時代の著名なバクティ詩人トゥルスィーダースとも親交があったとされている。非常に多才で、広い見識と深い教養を持ち、しかも寛大な人物だったようだ。
カーネ・カーナーン廟の建造時期は明らかではない。普通に考えたらアブドゥル・ラヒームの死後に建てられたことになるが、INTACH「Delhi:
A Thousand Years of Building」の著者ルーシー・ペックは、その建築様式の古さから、元々は1598年に死去した妻のために造られたのではないかと推測している。かつてはフマーユーン廟と同様に、白大理石と赤砂岩で装飾された美しい建物だったようだが、アワド藩王国ナワーブ(太守)アサフッダウラーが実権を握っていた時代(1775-1797年)に白大理石がはがされてしまい、祖父サフダルジャングの墓廟であるサフダルジャング廟の装飾に使用されたとされている。

白大理石をはがされた跡が無残
内装もだいぶ破壊されてしまっており、かつて大理石で覆われていたとされる墓も今ではただの石になってしまっている。だが、よく見ると、天井や壁には繊細な彫刻が残っている部分があり、美しい墓廟であったことが伺われる。

廟内部
左上は墓、右上は天井
左下は廟南部の小室の天井、右下は廟西部の小室の壁
ラヒームの詩には無常観を謳ったものもある。
सर सूखे पच्ची उड़े, औरे सरन समाय।
दीन मीन बिन पच्च के, कहु रहीम काँ जाय॥
sar sūkhe pachchī ure, aure saran samāy
dīn mīn bin pachch ke, kahu Rahīm kān jāy
湖が干上がったら、鳥は別の場所を求めて飛び立ってしまう
ラヒームよ、羽を持たない魚はどこへ行けばよいのだろう
鳥を魂、湖を身体、そして魚を死後に残るもの、例えば墓と解釈すれば、この詩はカーネ・カーナーン廟の現状に当てはまる。インド考古局(ASI)は、カーネ・カーナーン廟を整備して入場料を取る遺跡とし、何とか羽なき魚の延命を図っている。だが現在、カーネ・カーナーン廟周辺にフライオーバーの建設が予定されており、それが実現したら、この辺りの風景も一変してしまう可能性がある。現在カーネ・カーナーン廟は、ボロボロになりながらも、かろうじて青空の中に突き出す威容だけは保っている。だが、近くに廟のドームを見下ろすようなフライオーバーができてしまうと、それすらも失ってしまうことになりかねない。
先日、43年振りにパーキスターン映画「Khuda Kay Liye」がインドで公開された。脚本が綿密に練り込まれていた上に、現代の国際社会におけるイスラーム教の意味について考えさせられ、素晴らしい作品だと感じた。パーキスターン映画に対する関心も自然に高まった。そう思っていたら、早くも第2弾のパーキスターン映画がインドで公開された。2004年にパーキスターンで公開され、74週連続公開されるほど大ヒットした「Salakhain」という映画である。だが、「Khuda
Kay Liye」と違って「Salakhain」は完全な娯楽映画とのことだった。2001年にパーキスターンを旅行したとき、1本だけパーキスターンの娯楽映画を映画館で見たことがあるが、現在パーキスターンでどんな娯楽映画が見られているのかにも興味があったため、公開初日に早速見に行くことにした。
題名:Salakhain
読み:サラーヘーン
意味:鉄格子
邦題:鉄格子
監督:シェヘザード・ラフィーク
制作:ハージャー・ラシード
音楽:Mアルシャド
出演:アハマド・バット、ミーラー、ザーラー・シェーフ、シャフィー・ムハンマド、ファールーク・ザミール、サージド・ハサン、サウド
備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。

ザーラー・シェーフ(左)とアハマド・バット(右)
| あらすじ |
ラーハウル(ラホール)の貧しい家庭に生まれ育ち、両親の期待を背負って勉学に励んでいたファイザーン(アハマド・バット)は、大学の試験会場で受験者が不正をし、監督官もそれに手を貸しているのを目撃して黙っていられなくなった。ファイザーンは告発しようとしたが周囲の受験者たちの暴行に遭い、その上試験を妨害したとされて逮捕までされてしまった。父親はファイザーンの無実を信じながらもショックのあまりに死んでしまい、母親は発狂してしまった。
ファイザーンは牢獄で地元マフィアを束ねるズィーシャーンと出会う。ズィーシャーンは、試験不正の黒幕がザイガム(サウド)という男だということを教える。ザイガムはかつてズィーシャーンの仲間だったが、ザイガムが浮気をしたガールフレンドの顔に塩酸をかけたことで仲違いし、その後ライバル同士となった。ファイザーンは釈放されるとズィーシャーンの面倒を見る政治家の部下となり、ザイガムに対する復讐に乗り出す。ズィーシャーンのマフィアの中には、同じくザイガムに恨みを持つナターシャ(ミーラー)という女性がいた。悪徳試験官を射殺した後、ファイザーンはナターシャの家に身を隠すことになった。ファイザーンとナターシャは次第に心を通わすようになり、一生同じ道を歩むことを誓う。
また、逮捕される前、ファイザーンは近所に住むサヴィター(ザーラー・シェーフ)という女の子と恋仲にあり、結婚を誓い合っていたが、マフィアに入ってしまったために、彼女に自分との結婚は諦めるように言う。そこでサヴィターは仕方なく親の意向に従ってお見合いをし、新任警察官僚の男と結婚する。
ズィーシャーンとザイガムのライバルマフィア同士の抗争が激化し、ファイザーンも警察から追われる身になっていた。この抗争の中でズィーシャーンは慕っていた政治家にも裏切られて殺害されるが、ファイザーンはその後を継ぎ、ナターシャと共謀してザイガムや政治家を殺害する。
ファイザーンとナターシャは警察から逃亡するが、この事件の担当になったのがサヴィターの夫であった。サヴィターはそれを知って現場に直行する。ファイザーンとナターシャが逃げ込んだ家には、ファイザーンの母親がいた。発狂した母親はしばらく精神病院に入院していたが、最近回復し、退院して看護婦の家に住んでいたのだった。ファイザーンと母親は束の間の再会を喜ぶが、既に建物は警察に囲まれていた。ファイザーンとナターシャは逃げ出す。ファイザーンは逃げながらも警察を指揮するサヴィターの夫を捕まえ、殺そうとするが、そこに駆けつけたサヴィターに、それが夫だと知らされる。そしてひるんだ隙に警察に撃たれてしまう。それを見たナターシャはサヴィターの夫を殺そうとするが、ナターシャはファイザーンに撃たれてしまう。こうしてファイザーンとナターシャは2人して死んでしまった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
「Salakhain」が4年前の映画であることを差し引いても、パーキスターンの娯楽映画のレベルはボリウッドとは比べ物にならないくらい低いと言わざるをえない。パーキスターンの娯楽産業は、映画よりもTVドラマの方が質が高いようで、映画だけを見てパーキスターンの娯楽産業全体を評価するのは早計であろう。だが、「Salakhein」はパーキスターンでロングラン・ヒットした映画であり、娯楽映画の中では最高レベルだと考えても差し支えないだろう。その「Salakhain」がこのような古めかしく低品質な映画だということは、やはりパーキスターンの娯楽映画には期待をしてはいけないと結論付けざるをえない。「Khuda
Kay Liye」の完成度の高さが突然変異的なものだということも改めて認識できた。
あらすじを簡単に言ってしまえば、悲劇のアングリー・ヤングマンが社会悪に暴力で立ち向かい、縦横無尽の活躍の後に悲壮な最期を遂げるというものだ。数十年前のボリウッドで流行ったプロットとそう変わりない。途中でどんでん返しのようなものもなく、ストーリーは一直線に進んで行く。その癖、登場人物同士の関係はこれ以上にないほど複雑に、しかも凝縮されて絡み合っており、それによって無理矢理な感動を搾り出している。インド映画はしばしば「マサーラー映画」と呼ばれるが、「Salakhain」を見る限り、パーキスターン映画はマサーラーが利き過ぎである。撮影技術やカメラの性能もアマチュア以下で、台詞を話している人にピントが合っていないというレベルである。音響も最悪。こんな状態でダンス・シーンが見られるものになるはずがない。アクション・シーンも緊迫感に欠けるものが多い。特に銃撃戦シーンでは銃弾の命中率が低すぎて失笑せざるをえない。俳優も、一部を除いて台本棒読み役者かオーバーアクティング役者しかない。
エンディングの解釈はとても難しい。もう一度人間関係をおさらいすると、ファイザーンとサヴィターは幼馴染みで恋仲だったが、ファイザーンがマフィアになったために結婚できなかった。サヴィターは警察官僚と結婚した一方、ファイザーンはナターシャと出会い、愛し合い、共に生きることを誓う。だが、ファイザーンとナターシャは警察に追われ、逃亡する。ファイザーンは警察官僚を殺すチャンスを得るが、ちょうどそこへ駆けつけたサヴィターに制止される。その警察官僚がサヴィターの夫だと知ったファイザーンは油断し、その隙に他の警察官たちに撃たれてしまう。それを見たナターシャは警察官僚を殺そうとするが、倒れたファイザーンが最後の力を振り絞ってナターシャを撃つ。ファイザーンは、サヴィターの夫であり、サヴィターの幸せであった彼を死なせたくなかったと同時に、ナターシャを道連れにした。「なぜ撃ったの?」と問うナターシャに対しファイザーンは、「共に生きることができないなら、せめて共に死のう」と言い、その瞬間に2人は絶命する。ファイザーンは、かつて愛した女性の幸せを守り、現在愛する女性と共に愛を全うしたと解釈すればいいのだろうか?この終わり方は、もう少し洗練すればとても斬新なものになったかもしれない。だが、それまでの展開があまりに粗末だったので、行き当たりばったりな印象が拭えなかった。
主演はアハマド・バットはパーキスターンのトップモデルで、この映画が映画デビュー作だったようだ。モデルだけありスクリーン映えする整った顔立ちをしており、演技も問題は感じなかった。ナターシャを演じたミーラーは、ボリウッド映画「Nazar」(2005年)などにも出演したことのある、パーキスターンの人気女優である。「Salakhain」では、ダンスを踊ったり、ファイザーンを誘惑したり、銃をぶっ放したりと大忙しだったが、基本的な演技力はある女優だと感じた。ただ、公式プロフィールでは1961年生まれのようで、アップのシーンでは年齢を感じることが多かった。もう1人のヒロイン、ザーラー・シェークは、パーキスターンでは人気の女優のようだが、彼女は大根役者としか言いようがなかった。ひとつひとつの仕草はオーバー過ぎるし、大スクリーン向きのオーラが出ている女優ではないと感じた。
ラーハウルが舞台になっていたが、実際に当地でロケが行われたかは不明である。だが、市街地の路地裏を駆け抜けるチェイス・シーンはなかなか迫力があった。カラーコラム山脈で撮られたと思われる雪山を背景に踊るシーンや、無数の小塔が外部に突き出す迫力ある城塞を背景に踊るシーンなど、他にも目を見張るロケーションがあった。
言語は基本的にウルドゥー語である。とは言っても、娯楽映画であるためか、極度に難解な語彙の使用は避けられており、ヒンディー語の語彙の知識で大部分は対応できると感じた。面白かったのはコメディーシーンであった。突然パンジャービー語になるのである。どうやら、映画に限らずパーキスターンのコメディー界はパンジャービー語が主流のようで、それが映画にも影響を与えているように思えた。
2004年にパーキスターンで公開されて大ヒットを飛ばした娯楽映画「Salakhain」は、43年振りにインドで公開されたパーキスターン映画「Khuda
Kay Liye」に続き、インドで公開された。だが、完成度の高さは「Khuda Kay Liye」の足元にも及ばないし、純粋に娯楽映画として見ても、インドの娯楽映画を見た方が数倍マシというレベルである。インドにいながらパーキスターン映画を鑑賞できるようになって来たのは歓迎するが、大ヒット作がこのような状態ならば、残念ながらインドで公開するに値するパーキスターン映画は本当に数えるほどしかなさそうだ。だが、インド市場がパーキスターン映画界に対して開かれたことで、ロリウッド(ラーハウルを拠点とするパーキスターン映画界の別名)にいい影響が出ればと思う。おそらく「Salakhain」自体はインドでは1週間で公開が打ち切られてしまうだろうが、これらの映画交流が印パ新時代の幕開けを告げるものであって欲しい。
4月17日、北京五輪聖火リレーがデリーで行われた。元々予定されていたルートは、ラール・キラーからインド門までの全長9kmのものだったが、世界各地で聖火リレーがトラブルを巻き起こしたことを受け、ヴィジャイ・チャウクからインド門までの、いわゆるラージパトを走るルートに変更された。このルートは毎年1月26日に行われている共和国記念日パレードと同様のものでもあり、周囲は広大な平地となっていて警備が容易だと判断されたのだろう。ちなみにラール・キラーからインド門のルートだと、ダリヤー・ガンジなどの商店街を通り抜けることになる。しかも、新ルートは全長2.3kmで、距離は3分の1以下になった。それだけでなく、ラージパトは数日前から厳戒態勢が敷かれ、当日は21,000人の警官が警備に当たった。一般人は完全にシャットアウトされ、特別に招待を受けた50人の学童のみが観客となった。以前からサッカー選手バイチャン・ブーティヤーと、元警察官僚キラン・ベーディーが聖火リレー参加を辞退していたが、当日になって射撃選手ジャスパール・ラーナーとサロード奏者アヤーン・アリー・バンガシュが辞退したため、合計68人のランナーが走ることになった。単純計算すると、1人あたりの走行距離は35m弱になる。午後4時45分から始まった聖火リレーは、午後5時15分に無事終了した。
一方、チベット人とその支援者たちは、同日にパラレル聖火リレーを行って中国に対する抗議の意を示した。このリレーには合計1,500人が参加したが、その中には、作家アルンダティー・ロイ、政治家ジョージ・フェルナンデス、活動家ナフィーサー・アリーなど、インドの著名人もいた。パラレル聖火リレーはラージガートを午前10時に出発し、ジャンタル・マンタル到着後は抗議集会の形を取った。
このように、一方では厳戒態勢かつ大幅短縮の聖火リレーが無事に行われ、他方では抗議のパラレル聖火リレーが行われた。インドは、中国に配慮しながらも、世界最大の民主主義国家として、チベット人たちの抗議権行使を認め、難局を何とか乗り越えることができた。
あまり知られていないが、聖火リレーに合わせて披露されるはずだったパフォーマンスがあった。インド各地のマーシャル・アーツを一同に集めたステージで、インドならではの伝統的スポーツを提示する目的があった。だが、聖火リレーが以上のような厳戒態勢下で行われることになったため、このステージは中止となってしまった。出演者たちはかなり前からこの晴れ舞台に向けて練習をして来たと思われるが、国際的な混乱の中ではどうしようもなかった。
しかし、デリーのシーラー・ディークシト州首相が出演者に救いの手を差し伸べることを決めた。聖火リレーで上演されるはずだったステージを、デリー市民向けに披露する場を設けたのである。急遽「Khelo
Re(遊ぼうよ)」というイベントが準備され、聖火リレー後の4月18日~20日の3日間、コンノート・プレイスのセントラル・パークで上演されることになった。僕は19日午後7時からの公演を見に行った。
午後6時半頃に現地に着いたのだが、セントラル・パークの野外劇場は既に多くの観客で埋まっていた。後ろの席に座るしかなかったほどだ。シーラー・ディークシト州首相の挨拶の後、「Khelo
Re」が始まった。マーシャル・アーツと言うと聞こえがいいが、実際は武器を使ったダンスや演武のようなものだった。中には大道芸に分類されるものもあった。突然準備されたイベントのためか、パンフレットなどがなく、どれがどの州の何と言う名前のものなのか分からなかったが、パンジャーブ州のスィク教徒たちによる武術披露からケーララ州のカラリパヤットまで、バラエティーに富んだ体技を鑑賞することができた。また、各州の上演が終わった後は、上演者全員登場によるミュージカルもあった。合計1時間ほどの短いステージであった。


インドは聖火リレーに合わせてこんなショーを用意していたということだけでも、知っていただければと思う。
| ◆ |
4月20日(日) 1857: Ek Safarnama |
◆ |
4月18日から25日まで、プラーナ・キラーにおいて、国立演劇学校(NSD)創立50周年記念の演劇「1857: Ek Safarnama(1857年:ある旅行記)」が上演中である。3日目の20日に舞台を見に行った。入場にはパスが必要で(1枚で2名まで入場可)、下調べをして来なかった僕は持っていなかったのだが、運良く1人で来ていたお爺さんと一緒に入れさせてもらうことができた。
オールド・フォートとも呼ばれるプラーナー・キラーは、神話と歴史が混交する魅力的な遺跡である。「マハーバーラタ」に登場する伝説の都市インドラプラスタと比定されている他、ムガル朝第2代皇帝フマーユーンや、スーリー朝創始者シェール・シャーの建造した城塞や建築物が現在まで残っている。プラーナー・キラーが会場となるイベントは、毎年恒例の舞踊祭「Ananya」が有名だが、NSDもかつてはここで「Tughlaq」、「Andha
Yug」、「Sultan Razia」などの演劇を上演したことがあるようである。本物の遺跡を背景に上演される時代劇や古典舞踊ショーは、歴史のない国では味わうことのできない荘厳な雰囲気を醸し出す。
1857年はインド大反乱のあった年であり、インド史の中で「1857」という数字は特別な意味を持つ。よって、教養のある人なら、「1857: Ek
Safarnama」という題名を聞いただけで、インド大反乱をテーマにした演劇であることを理解する。インド大反乱の呼び方は、セポイの反乱、第一次インド独立戦争など、立場によって異なり、その原因についても様々な見方がされているが、全ての人々が意見を一致させているのは、インド大反乱がインドの大きなターニング・ポイントになったという事実である。また、インド大反乱で英国に立ち向かったインド人たち――バハードゥル・シャー・ザファル、ナーナー・サーヒブ、ターンティヤー・トーペー、ラクシュミー・バーイーなど――は、フリーダム・ファイターとしてインド人の間で英雄扱いを受けており、現代インドのナショナリズムを理解する上で重要なキーワードとなっている。
インド大反乱をテーマにした歴史書、小説、演劇、映画などはたくさんあるが、「1857: Ek Safarnama」が特殊なのは、大反乱における民衆の役割に焦点を当てていることである。
演劇はまず、アワド藩王国が英国東インド会社に併合されるところから始まる。アワド地方の農民たちは東インド会社が新しく課した税制に反発する一方、東インド会社が雇用したスィパーヒー(インド人兵士)の中でも反乱の機運が高まっていた。また、マラーター連合の元ペーシュワーで、ビトゥール(カーンプル近くの町)にて年金受給者に成り下がっていたナーナー・サーヒブは、表向きは英国人と友好的な態度を取っていたが、裏では反乱を企てていた。そんな中、1857年5月10日にメーラトの駐屯地でスィパーヒーによる反乱が発生する。ナーナー・サーヒブもカーンプルの東インド会社駐屯地を占領し、反乱に加わった。

アワド藩王国ワージド・アリー・シャーの宮廷シーン
演劇では、インド大反乱の転機を、サティーチャウラー・ガートの虐殺としている。カーンプルを占領したナーナー・サーヒブは、捕えた英国人やその妻子を船に乗せてイラーハーバードに送還することを決めていた。だが、サティーチャウラー・ガートで船に乗った英国人たちは、スィパーヒーたちに虐殺されてしまった。その虐殺の原因については議論がなされているが、「1857:
Ek Safarnama」では、スィパーヒーの反乱で劣勢に立たされていた英国人に義憤を生じさせて形勢逆転するために、英国人自身が計画した策略だったということにしている。一応その証拠もあるようである。
サティーチャウラー・ガートの虐殺の後、劇の舞台は、反乱軍によって英国人から奪還されたデリーへと移る。そこではムガル朝最後の皇帝バハードゥル・シャー・ザファルが登場し、デリー陥落とザファルの逮捕までが描かれる。ザファルの3人の息子は殺され、ザファル自身はラングーン流刑となり、デリーの反乱は完全に鎮圧されて、一応は英国の勝利に終わる。だが、デリーの城門(カシュミーリー門)突破からラール・キラー占領まで7日間かかったこと、そしてデリー奪還までに1万2千人の兵力の半分以上を失ったことなどから、英国人総督がそれを「インドの勝利」と表現し、観客の愛国感情を刺激して劇は終了する。

ムガル朝最後の皇帝バハードゥル・シャー・ザファル
ナーナー・サーヒブ、ターンティヤー・トーペー、バハードゥル・シャー・ザファルなどの歴史的人物が多数登場するが、劇の真の主人公は一般庶民である。その中でも、一介の労働者から独立運動に身を投じたラームサランと、スィパーヒーながら反乱に大きく貢献したシャムスッディーンの活躍が演劇の核となっていた。また、操り人形師が村々を巡って反英の機運を盛り上げる様子、ローティーが村から村へ配られる怪事件(蜂起のメッセージだったと言われる)、娼婦たちで構成された軍隊、反乱に参加するサンタル族など、インド大反乱がインドの全ての階層、カースト、コミュニティを包括する蜂起であったことが浮き彫りにされていた。

村々を巡る不思議なローティーの談義をする労働者たち
インドの演劇らしく、要所要所でミュージカルが挿入され、戦闘シーンでは白熱の剣劇も繰り広げられた。インド大反乱の期間中に起きた事件を全てインド寄りの視点で見ており、結果として一辺倒な愛国主義的演劇になっていたきらいはあったが、インド大反乱の一側面を描き出すことには成功していたと思う。
最後になったが、監督はナーディラー・ザヒール・バッバル、脚本はバッバル監督とヴァルンSガウタムの共作、原作はアマレーシュ・ミシュラの「War
of Civilisations: India 1857」である。言語は一部英語だが、大半はヒンディー語。だが、会場では5ルピーという格安の値段で豪華パンフレットが売られており、演劇の概要を理解することができる。
| ◆ |
4月23日(水) デリーの「Traffic Signal」 |
◆ |
2007年に「Traffic Signal」という映画が公開された。興行的には失敗に終わったのだが、外国人にはなかなか踏み込めない世界が描写されており、個人的に非常に印象に残った作品となった。映画の主人公はムンバイーの乞食や物売りである。乞食と物売りと聞くと日本では別のカテゴリーに思われるかもしれないが、インドで両者の違いはあまりない。何か安い商品と引き換えに施しを求めるのが物売りであり、身体の障害や怪我、飢えた赤ん坊、貧しい風貌などを見せ付けて現金化しようとするのが乞食である。ただ、当然のことながら、乞食には分類されない生粋の物売りも存在し、誤解を招く可能性は大である。よって、ここでは「乞食」という言葉を、乞食と、乞食に限りなく近い物売りの両方を指すものとして使いたいと思う。
インドの乞食にはいくつか種類があるが、この映画で取り上げられたのは、題名通り信号を縄張りとする乞食たちだ。赤信号で停車している自動車に物乞いをしたり、物を売ったりして生計を立てている。「Traffic
Signal」が興味深かったのは、乞食たちがかなり組織化されている様子が提示されていたことである。各信号ごとにマネージャーがおり、マネージャーの上にはコレクターがおり、そのコレクターたちを地元マフィアが統括しており、さらにマフィアは政治家と癒着しているという具合である。ひとつの信号で働く乞食たちの間で団結があったり、稼ぎ頭である身体障害者の平等な分配があったり、フライオーバー建設による騒動があったりと、インドに住んでいる者として、いろいろなことを考えさせられる映画であった。映画評も参考にしてもらいたい。
しかし、「Traffic Signal」はムンバイーの話であった。果たしてデリーでも同じように組織立った「路上インダストリー」があるのだろうかと思っていた。4月21日付けのヒンドゥスターン紙にその答えがあった。記事の題名は「赤信号で児童のブローカー(लाल
बत्ती पर लालों के दलाल)」。乞食全般ではなく、子供の乞食に焦点が当てて書かれていたが、やはりデリーの信号で物乞いをする乞食たちも組織立っているようだ。だが、それを読むと、「Traffic
Signal」で描写されていた乞食の実態とは異なったもののように見える。
デリーの児童乞食の実態は、NGOのBachpan Bachao Andolan(子供時代を救え運動;BBA)が、今年2月にモーティー・バーグのフライオーバー付近で物乞いをする子供たち13人を救出したことで発覚した。BBAのウェブサイトに関連したニュースが掲載されており、ヒンドゥスターン紙の記事の元ネタになっている。
それによると、モーティー・バーグで乞食をしていた子供たちは、ラージャスターン州から連れて来られたらしい。シャーンティという10歳の女の子の話によると、彼女はアジメール近くの村出身で、7歳のときにカーリーという名の女性によってデリーに連れて来られたようだ。「カーリーおばさんは毎日私の村に来てお母さんと話をしていたわ。ある日お母さんが私に、荷物をまとめてニューデリーという大きな町へ行くように言ったの。私の村から7人の子供がここに連れて来られたわ。私は午前8時から午後11時まで乞食をさせられた。みすぼらしい外見になって通行者からより多くのお金をもらえるように、服を引き裂くように言われ、何ヶ月も入浴させてもらえなかったわ。しかも、痩せこけて栄養失調に見えるように、1日1回しか食事をもらえなかった。」子供たちの1日のノルマは300ルピーで、それに満たないと叱責や暴行を受けたり、食事を食べさせてもらえなかったりした。その代わり、故郷の家には毎月1,000~1,500ルピーが支払われていたと言う。つまり、農村の貧しい家庭の子供たちを親の同意の下に借り上げ、デリーの交差点で乞食をさせて中間マージンを搾取するというビジネス・モデルが完成しているのである。
各信号には見張り役が配置されており、子供たちを監視しているようだ。さぼっている子供や、誰かと無駄話をしている子供は夜に暴行を受ける。だから、乞食をしている子供たちは常に怯えており、滅多なことでは他人に身の上や真実を話そうとしない。確かに子供が主力の交差点では、子供が乞食や物乞いをしながら車と車の間を奔走している一方で、汚ない身なりの女性が木陰などに座ってそれを見ているのをよく見かける。てっきり子供たちの母親かと思っていたが、あれが多分監視役なのであろう。ただ、僕が見る限り、本当に不幸そうな子供たちは稀で、仲間同士で和気藹々と乞食をしていることが多い。乞食をしているときは当然憐憫の情を引き起こすような表情や仕草をするのだが、例えば道路脇の水道管が破裂して大きな水溜りができたときなど、子供たちは物乞いの仕事そっちのけで水遊びに興じたりしていて、微笑ましいことがある。インドにはいろいろな問題が山積しているが、インド人にはどんなに不幸でも人間らしさを失わない強さが一般にあり、それが時々我々をホッとさせてくれたり、勇気付けてくれたりする。

デリーの乞食
2001年10月にサーケートのマーケットで撮影。
彼女たちは信号ではなく市場を縄張りにする乞食である。
当時はよく見かけたのだが、最近見かけない。
2人とも嫁いでしまったのだろうか?
また、面白いことにデリーでは信号ごとに「顧客」層に違いがあるようだ。高級住宅地のそばの交差点はやはり裕福な家の車がよく止まるのだろう。当然、金持ちが多く集まる交差点は高い収益が期待できる。そのような信号は「競売」にかけられるようである。競売があるということは、乞食斡旋業者の横のつながりがしっかりしているということであり、彼らをまとめる存在――おそらくマフィア――もいるということである。ちゃっかり「顧客」の嗜好調査やマーケティングも行われており、それに従って信号ごとに商品が違ったりする。デリーの交差点で売られている商品で一般的なものは、ティッシュ、自動車清掃用の布、ペン、花、新聞、雑誌、玩具などである。その他季節商品もあり、独立記念日や共和国記念日が近付くとインドの国旗、クリスマスが近付くとサンタクロースの帽子などが売り出される。また、信号で書籍(主に英語)を売る物売りもいるが、彼らが売る本は大体そのとき話題になっているものばかりであり、ある程度教養のある人物がバックにいることが伺われる。
デリーの乞食については、元デリー在住の少林寺さんのブログ日本企業駐在員インド人化計画でも一度取り上げられており、参考になる。
乞食にお金をあげるかあげないかは全くもって個人の自由である。僕はと言えば、乞食を「歩く賽銭箱」と考えており、何か願い事があるとき、願掛けをしたいとき、徳を積みたいときなど、乞食にお金をあげることにしている。つまり、基本的に自分のために乞食に喜捨をする。乞食のためではない。乞食を憐れんで与えていたらこの国は際限がない。自分のためと思っておけば、神社やお寺の全ての賽銭箱にお金を入れる必要がないように、限られた乞食にお金をあげることで納得が行く。普通のインド人の考え方もそう変わらないのではないかと思う。だが、もしこのように乞食が組織立っているならば、そして人身売買と密接な関係を持っているならば、乞食にお金をあげることはその犯罪に加担することと同然になってしまう。やはり基本的にはあげない方がいいのだろう。
| ◆ |
4月24日(木) Hope and a Little Sugar |
◆ |
先日公開されたパーキスターン映画「Khuda Kay Liye」(2007年)は911事件後のイスラーム教をテーマにした映画だった。同映画に出演していたインド人俳優ナスィールッディーン・シャーは「Yun
Hota To Kya Hota」(2006年)で監督デビューしているが、これも911事件を題材にしていた。米国では、「Fahrenheit
9/11」(2004年)、「World Trade Center」(2006年)、「United 93」(2006年)など、既にいくつも911事件に関連する映画が作られている。後世、21世紀の最初の10年の映画の傾向が分析された場合、必ず911事件がひとつの象徴的テーマとして評価されることになるだろう。2006年初公開ながら、先週の金曜日からインドで封切られた「Hope
and a Little Sugar」も、やはり911事件を題材にした映画である。監督や主演はインド人だが、基本言語は英語になっている。
題名:Hope and a Little Sugar
読み:ホープ・アンド・ア・リトル・シュガー
意味:希望と砂糖少々
邦題:ホープ・アンド・ア・リトル・シュガー
監督:タヌージャー・チャンドラ
制作:スコット・パルド、グレン・ルソー
音楽:ウェイン・シャープ
出演:アヌパム・ケール、マヒマー・チャウドリー、アミト・スィヤール、スハースィニー・ムレー、ヴィクラム・チャトワール、ランジート・チャウドリー、ポール・ベリー、ニコエ・バンクス、シルパー・グハー
備考:PVRアヌパムで鑑賞。
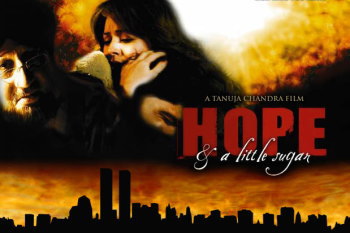
左から、アヌパム・ケール、マヒマー・チャウドリー、アミト・スィヤール
| あらすじ |
ニューヨークでバイク・メッセンジャーとして働きながらカメラマンを目指すインド人ムスリム男性アリー・スィッディーキー(アミト・スィヤール)はある日、菓子屋「Hope
and a Little Sugar」を経営するインド人スィク教徒女性サローニー(マヒマー・チャウドリー)と出会い、一目惚れする。だが、サローニーはオベロイ大佐(アヌパム・ケール)の息子ハリー(ヴィクラム・チャトワール)と結婚していた。それでも3人は仲良くなり、アリーはオベロイ家にも行き来するようになった。
そんな中911事件が発生し、世界貿易センタービルに勤務していたハリーは行方不明になってしまう。オベロイ大佐は貼り紙を作ってあちこち息子を探して回るが、何の手掛かりも得られなかった。次第に彼は荒れて行く。しかも、常にターバンをかぶっていたオベロイ大佐は、米国人からオサーマ・ビン・ラディーンと言われ、攻撃の対象となることが多くなった。さらに、アリーがサローニーと仲良くしているのを目撃し、怒りが爆発する。アリーは大佐に殴られ、オベロイ家に出入り禁止になる。
それでもアリーとサローニーは密かに会っていた。もうアリーはオベロイ家に行けなくなってしまったため、サローニーは初めてアリーの家へ行く。彼の部屋の壁はサローニーの写真で埋め尽くされていた。アリーは彼女に愛の告白をする。
だが、オベロイ大佐の怒りは収まっていなかった。妻(スハースィニー・ムレー)からサローニーの幸せのことも考えてあげるべきだと言われて激怒したオベロイ大佐は、拳銃を持ってアリーの家へ向かった。オベロイ夫人から知らせを受けたアリーは、大事にしていたカメラを質に入れて拳銃を購入し、大佐を待つ。だが、オベロイ大佐は途中でチンピラに捕まってリンチに遭ってしまう。
オベロイ大佐は入院し、一命を取り留める。彼はアリーに謝り、妻と共にインドへ帰ることを決める。ニューヨークに残ったアリーとサローニーは、2人で菓子屋「Hope
and a Little Sugar」を再スタートさせる。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
「Hope and a Little Sugar」は、2006年にニューヨークで開催された南アジア国際映画祭で最優秀長編映画賞を受賞したようだ。だからある程度の質の映画であることを期待して映画館に足を運んだのだが、その期待に応えられるような作品ではなかった。
2001年、ニューヨーク、イスラーム教徒の主人公、スィク教徒のヒロイン、一目惚れ、だがヒロインは既婚、911事件によるヒロインの夫の死、米国人から差別を受けるヒロインの父親、イスラーム教徒への憎悪、夫の死後ヒロインの心の支えとなる主人公、これらのキーワードを与えられれば、あらすじを読まなくても誰でも内容と結末が想像できそうな作品であった。悪い映画ではないのだが、無難にまとまりすぎで、面白みに欠けた。
911事件をインド人の視点から見るため、1992年から93年にかけてのムンバイー暴動と重ね合わせたのは工夫が見られた点であった。主人公のアリーは、幼い頃にムンバイー暴動を経験しており、そのとき弟を死なせてしまう。弟は暴徒に殺されたのであるが、アリーは自分が殺したのだと考え、トラウマとなっていた。そのトラウマは、銃を持ってオベロイ大佐が自分を殺しに来るときに観客に明らかになるが、詳細は映画の中では語られていない。また、オベロイ大佐は1971年の第3次印パ戦争のときの英雄であり、それもイスラーム教徒に対する偏見という意味で、物語の伏線となっていた。
911事件後に、米国において、ターバンをかぶったスィク教徒がテロリストの一味と間違えられて差別を受けたりしたのは有名な話だ。映画で本当に語りたかったのはその出来事だと思われる。911事件で息子を失ったスィク教徒の父親が、人々からテロリストと罵られるのは大変な苦痛である。だが、同じような状況を強力なメッセージと共に描写した「Khuda
Kay Liye」と違い、「Hope and a Little Sugar」ではただの悲劇的な出来事で終わってしまっており、インド人側からの主張みたいなものが全く感じられなかった。結局オベロイ大佐夫妻は米国を去ってインドに帰ってしまい、むしろ何かわだかまりが残る終わり方になっていた。
もしインドの同様の事件と911事件を結び付けて映画らしい効果を求めるならば、ムンバイー暴動や第3次印パ戦争よりも、1984年にデリーで起こったスィク教徒虐殺事件の方が適していたのではないかと思う。
一応カテゴリーとしては恋愛映画になるだろう。映画はアリーとサローニーの出会いから始まり、2人のゴールインで完結しているからだ。だが、911事件で夫を失ったサローニーがアリーに心を開くのが早すぎではないかと思った。そのせいで、恋愛映画として見ても中途半端なものとなっていた。
ヒロインはマヒマー・チャウドリー。彼女を見たのは久し振りである。あまりに久し振りすぎて名前がすぐに浮かんで来なかった。第一印象は「老けたなぁ・・・」というものだった。しかも映画の撮影は2004年に行われたというので、スクリーンに映っているのは4年前の彼女ということになる。今ではもっと老けてしまっているだろう・・・。てっきりお母さん役か何かに転向して出演しているのかと思ったのだが、しぶとくヒロインを演じていた。もしかして英語映画出演は初めてかもしれないが、演技や台詞に問題はなかった。もう少し自分をわきまえた役を演じる勇気を持てば、復活もありうるだろう。
主演のアミト・スィヤールは、舞台などの経験は豊富のようだが、長編映画での演技はこれが初めてのようである。舞台の世界でどれだけ活躍しているかは分からないが、映画向けの俳優ではないと感じた。与えられた役も悪かった。人物描写に失敗しており、個性のないキャラクターになってしまっていた。
他に、ベテラン俳優のアヌパム・ケールが、ヒロインの父オベロイ大佐として重要な役を演じていた。陽気でおどけた表情から、涙を浮かべた激怒の仕草まで、貫禄の演技であった。オベロイ夫人を演じたスハースィニー・ムレーもベテラン女優である。
言語は基本的に英語だが、パンジャービー語やヒンディー語も出て来る。だが、英語以外の言語の場合は英語字幕が付くので、理解には困らないだろう。
「Hope and a Little Sugar」は、インド人の視点から911事件を描いた作品として記録に残る映画の1本になるだろうが、あまりに無難にまとまりすぎており、映画としての楽しさはあまりない。期待はしない方が吉である。
2006年あたりからインド最大の映画コングロマリット、ヤシュラージ・フィルムスと、これまたインド最大のマルチプレックス・チェーン、PVRの仲が悪く、前者の作った映画が後者の映画館で上映されない事態が何度かあった。最近しばらくそのようなことはなかったのだが、ヤシュラージ・フィルムス制作で2008年の話題作の1本「Tashan」がまたもPVRで公開されないことになった。
「Tashan」とはヒンディー語で書くと「टशन」になるが、この言葉は辞書には載っていない。英語でもないようだ。ネット上でも「Tashan」の意味について憶測が飛び交っており、インド人でもよく分からない言葉のようである。一説によると「style」と「fashion」を掛け合わせた言葉のようだが、映画中での使われ方を見ると、いろいろな場面で都合よく使われており、ひとつの意味に限定できなさそうだ。元々パンジャービー語という説もある。日本語に敢えて訳すなら、「かっこつけ」としたい。
題名:Tashan
読み:タシャン
意味:かっこつけ
邦題:タシャン
監督:ヴィジャイ・クリシュナ・アーチャーリヤ
制作:アーディティヤ・チョープラー
音楽:ヴィシャール・シェーカル
出演:サイフ・アリー・カーン、アクシャイ・クマール、カリーナー・カプール、アニル・カプール
備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。

左から、アニル・カプール、カリーナー・カプール、
アクシャイ・クマール、サイフ・アリー・カーン
| あらすじ |
ムンバイーのコールセンターに勤務し、英語教師も務めるジミー・クリフ(サイフ・アリー・カーン)は、ある日プージャー・スィン(カリーナー・カプール)という女性と出会ったことをきっかけに、彼女が勤めるオフィスのボス、バイヤージー(アニル・カプール)に英語を教え出す。ジミーの狙いは最初からプージャーであり、バイヤージーに英語を教えながらプージャーと心を通わすようになる。
バイヤージーの元には定期的に大量の現金が送られて来ていた。ジミーはプージャーが多額の借金を抱え、バイヤージーに結婚を迫られていることを知り、彼女と共にその金を盗んで返済に充てる計画を立てる。あるときそれは実行に移され、2人は2万5千ルピーを盗む。だが、ジミーが荷物を取りにコールセンターに寄ると、そこには警察が来ていた。警察は、コールセンターから3人の富豪の個人情報が漏洩したこと、そしてマフィアのドンがそれを使って脅迫をしていることをコールセンターの職員に話した。そのマフィアのドンこそ、ジミーが英語を教えていたバイヤージーであった。
ジミーはプージャーに連絡を取ろうとするが、彼女は2万5千ルピーと共に姿をくらましていた。ジミーはプージャーに完全に騙されたのであった。
所変わってウッタル・プラデーシュ州カーンプル。町のゴロツキに過ぎなかったバッチャン・パーンデーイ(アクシャイ・クマール)は、バイヤージーに召還される。バッチャンはバイヤージーを尊敬しており、喜び勇んで彼のアジトを訪れる。そこにはジミーが拘束されており、バッチャンは拷問の役を任される。ジミーはプージャーの居所を知らなかったが、バッチャンに叩かれている内に、彼女がハリドワールへ行きたいと言っていたのを思い出す。ジミーとバッチャンは一緒にウッタラーカンド州ハリドワールへ行くことになる。
ジミーの予想通り、プージャーはハリドワールにいた。プージャーは、金の入ったバッグをラージャスターン州に隠したと明かす。そこで3人はラージャスターン州を目指すことになる。
ラージャスターン州ではバイヤージーも待ち構えていた。確かにバッグはあったが、そこには数千万ルピーしか入っていなかった。プージャーは金を分散させてインドのあちこちに隠したのだった。3人はそれを全部集めるように命令される。
ジミーは、金が揃った後はバイヤージーに殺されることを恐れていた。そこでプージャーに、バッチャンを色仕掛けで惑わすように言う。バッチャンは女性とまともに話したこともない硬派な男だった。だが、話している内に実はプージャーは、バッチャンが子供の頃に片思いしていた女の子グリヤーであることが分かる。バッチャンはプージャーにゾッコンになってしまう。ジミーの作戦は見事に成功し、金が全額揃った後、バッチャンは2人を逃がしてくれた。
ジミーはてっきりプージャーがバッチャンの幼馴染みを演じていると考えていたが、彼女は本当に幼馴染みであった。しかも、プージャーの父親はバイヤージーに殺されており、その復讐のためにバイヤージーに近付いたことも明かす。それを聞いたジミーは、バッチャンの身が危ないと悟る。なぜならジミーはこっそり金を横領しており、バッチャンがバイヤージーのところへ持っていたバッグの中身は石ころだったからだ。
バイヤージーのアジトではバッチャンが拷問を受けていた。そこへジミーとプージャーがやって来て、バッチャンを救出する。ジミー、プージャー、バッチャンの3人は、バッチャンの部下たちと壮絶な戦いを繰り広げる。そして最後にプージャーは父親の復讐を果たすことに成功する。ジミーはコールセンターの社長となり、バッチャンとプージャーは結婚して幸せな家庭を築いた。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
前半は、最近のヤシュラージ・フィルムスにありがちな、無理に凝った、人を食ったような展開が続く。大失敗作映画「Jhoom Barabar Jhoom」(2007年)と似た雰囲気で、少し心配になった。だが、アクシャイ・クマールが登場し、インターミッションを挟んで後半になると、お互いにお互いを信用していない3人の男女の珍道中となり、俄然盛り上がって来る。クライマックスはド派手なアクションシーンになっており、何か懐かしいシンプルさがあって良かった。結果として、物語が進めば進むほど、インド人大衆の望むようなシンプルで分かりやすい映画になっていた。
映画中、西インドの大都市ムンバイーと北インドの中小都市カーンプル、都市中産階級の英語と方言混じりのヒンディー語の対比が繰り返されていたのも興味深い。最近のヤシュラージ・フィルムスは基本的に都市中産階級向けの、英語を多用したヒンディー語映画を作って来たのだが、2007年の同プロダクションの映画はほとんどが失敗作に終わってしまった。その反省からか、ヒンディー語を日常的に利用する北インドの中小都市の観客も取り込めるような映画作りへの意気込みが「Tashan」から感じられた。ただし、監督はどちらにも肩入れをしていない。大都市と英語を象徴するジミー(サイフ・アリー・カーン)と、小都市とヒンディー語を象徴するバッチャン(アクシャイ・クマール)のやり取りの中に、両者の立場をバランス良く織り込んで、コミカルにまとめていた。英語を必死に学ぼうとするが、かえっておかしな言葉遣いになってしまったバイヤージー(アニル・カプール)も、両者の葛藤の産物と言えるだろう。バイヤージーの話す言葉は英語とヒンディー語がランダムに入り乱れており、日本で言えばルー語みたいなものになっていておかしい。題名にもなっている意味不明の言葉「Tashan」も、バイヤージーが造り出したものである。
総じて、「Tashan」は、大都市に住み、英語を日常的に使用し、映画に新しさを求める中産階級と、中小都市(特に北インド)に住み、ヒンディー語を母語とし、単純なストーリーを求める大衆の両方をターゲットにした、新しい映画作りへヤシュラージ・フィルムスが踏み出した作品だと評価できるだろう。
この映画でもうひとつ優れていたのは、ロードムービー的にインド各地の風光明媚な土地で撮影が行われていたことである。ラダック、カシュミール、ラージャスターン、ケーララなど、インドの風土や文化の多様性を感じることができるだろう。
ここ1、2年でアクシャイ・クマールの人気はうなぎ上りである。今やインド人の若者の間でもっとも人気のあるスターになってしまった。2007年のアクシャイは全く外れなし。彼にとって2008年の初主演作になる「Tashan」でも彼の魅力が存分に発揮されており、ファンを裏切らない。アクシャイには、田舎の純真な荒くれ者役がもっとも似合っている。
アニル・カプールは最近低迷していた俳優であるが、「Tashan」では久々にマッドな演技を開放し、悪役を思いっ切り楽しんでいた。サイフ・アリー・カーンもいい演技をしていたが、最近の彼が演じる役はいつも同じような「ハンサムだが自己中心的な男」であり、そろそろ飽きられて来る恐れがある。そろそろ「Omkara」(2006年)のようなブレイクがもうひとつ欲しい。
「Tashan」の見所のひとつは間違いなくカリーナー・カプールであろう。いつの間にかすっかり寡作になり影が薄くなっていたカリーナーだが、「Jab
We Met」(2007年)をヒットさせ、しかもそれで数々の主演女優賞を受賞したことで、再びボリウッドのトップ女優候補に返り咲いた。「Tashan」での彼女はいろいろな側面を見せる機会を与えられており、演技力の幅の広さが発揮されていた。特に中盤でのセクシーな悪女の演技と、終盤での暴徒をなぎ倒すアクション女優としての演技がよかった。
音楽はヴィシャール・シェーカル。インド・ロックと表現できそうな「Dil Haara」、誘惑のダンス・ナンバー「Chhaliya」、カッワーリー・ロックとでも言うべき「Dil
Dance Mare」など、ユニークな曲が多い。ヒットチャートでもトップを維持しており、買いである。
「Tashan」は、インドのいろいろな層の人々の趣向に一度に訴えようとした野心的な娯楽映画だと言える。それが興行的に吉と出るか凶と出るかは今の段階では何とも言えない。だが、古いようで新しく、新しいようで古い、不思議な映画に仕上がっていることは確かであり、一見の価値はある。



