|
|
�@�C���h�ɗ��Ă���Ƃ������̂́A����N���N�n���W�Ȃ��Ȃ��Ă���B���{�ɂ���ƁA�N���N�n�ɋߕt���ɂ�āA�N���X�}�X�A��A���A���U�ƁA���͂̕��͋C������ɕς���Ă����̂ŁA����ɗ�����Ă������Ƃ������B���ď����ɂ��Ă��������낤�B�������C���h�ł́A�N���X�}�X�͋ߔN�j����悤�ɂȂ��ė������̂́A�N���N�n�ɓ�����C�x���g�̓f�B�[���[���[���z�[���[�ł���A�P�Q���R�P������P���P���ɂ����Ă̂Q���Ԃ͂����̓��t�ύX�ɉ߂��Ȃ��B����āA�C���h�ɂ���ƑS���N���N�n�ƊW�Ȃ������ɂȂ��čs���B���N�̑�A���ƌ��U�́A�O�W�����[�g�B�J�b�`�n���u�W����A�n�}�_�[�o�[�h��������s�o�X�̒��Ō}���A�����̏o�́A�A�n�}�_�[�o�[�h���烔�@���[�_���[�������o�X�̒��Ŕq�B�����A���N�͐���t�����C���𖡂킨���Ǝv���A�鋫�R�q�}�܂ł킴�킴���낢�됳���O�b�Y�������ė����\�\���ߓ�A�������A���{���i�g�T��j�A���i�X�|�[�c�J�C�g�j�Ȃǂł���B�܂��A���U�ɐ�v�ҕ�n�̓��{�l�̕�ɂ��_��������ċ��{����Ƃ����v������ĂĂ����B
�@�����A��������O�Ƀz�e�����o�āA�����Đ�v�ҕ�n�Ɍ��������B�z�e���E�W���v�t�����v�ҕ�n�܂ł͂P�����قǁB�����Ɖ����Ȃ̂œ��ɐh���͂Ȃ��B���̓r���A�R�q�}�s�X�����n����ꏊ���������̂ŁA�����ł�������q�ނ��Ƃɂ����B�������ɕӂ�͖��邭�Ȃ��Ă���A���̋�ō��ɂ��������肻���ɂȂ��Ă����B���̏�ł��炭�҂��Ă���ƁA�U���P�T�����ɎR�̌��������瑾�z���������B�R�q�}�̂������I���Ȃ背�A�ȓ��̏o�ł���B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�R�q�}�̏����̏o |
�� |
�@���̏o��������A����ɍ�������Ă����ƁA�X�̒��ɐ�Ԃ������B�P�X�S�S�N�̃R�q�}������ɉp�̃C���h�R�ɂ���Ďg�p���ꂽ��ԂŁA�uMedium
Tank M3 Grant I�v�Ɛ�������Ă����B�O�`�͂قڊ��S�Ȍ`�Ŏc���Ă������A�����͂قƂ�ǃS�~�̂ď�̂悤�ɂȂ��Ă���A�S�̓I�ɂ��Ȃ苀���ʂĂĂ����B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
M3 Grant I |
�� |
�@����͐��傪�܂��Ă���A���U�̍������J���Ă���]�݂͔��������̂ŁA������T�����Ƃɂ����B���������������オ�����ꏊ�ɁA�uNo Entry�v�Ə����ꂽ�傪����A���ɏ��Ȃǂ͂���Ă��Ȃ��������߁A���������Ɠ����Ă����ƁA���Ƃ�ʂ蔲���Ă��̂܂ܐ�v�ҕ�n�ɒʂ��Ă����B�ꉞ�Ăю~�߂Ă���l���������A�u���c������̃v�[�W���[�i���{�j���������v�ƌ�������ȒP�ɓ���Ă��ꂽ�B
�@��v�ҕ�n�͓������̎Ζʂɍ���Ă���A�����̕�肪�K�����������ׂ��Ă����B�܂��A����t�߂ɂ͑傫�ȏ\���˂������Ă����B�Ƃ肠�����A���{�l�̕��͂Ȃ����T���Ă݂��B�R�l�Ŏ蕪�����ĂقڑS�Ă̕��ɖڂ�ʂ��Ă݂����A���{�l�炵�����O�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�i�K�����h�̗F�l�̘b�ł́A�R�q�}�̐�v�ҕ�n�ɓ��{�l�̕������Ƃ̂��Ƃ��������A�ǂ����ԈႢ�������悤���B�����Ƃ���ɂ��ƁA�P�X�V�O�N��`�W�O�N��ɂ����ē��{����⍜���W�c������ė��āA�����{�R���m�̈⍜���W���I�ɑ{���������A���̈⍜���������ꂽ�̂̓}�j�v���B�C���p�[���������悤���B�R�q�}�̐�v�ҕ�n�ɂ����{�l�̕悪�������悤�����A������@��N������ăC���p�[���Ɉړ]���ꂽ�炵���B�R�q�}�ɓ��{�l�̈⍜����������Ȃ������̂́A�R�q�}�ɕ������@���Ȃ��������炾�ƌ����B�C���p�[�����Ő펀�������{�l���m�����U�ɎQ�q����Ƃ����̂�����̗��s�̑傫�ȖړI�������̂����A���O�̒����s���ɂ��厸�s�ɏI����Ă��܂����B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
��v�ҕ�n |
�� |
�@����ł��A�����ЂƂЂƂ��Ă����Ɩʔ������ƂɋC���t�����B���ɂ́A��v�҂̏@�����ƂɊe�@���̃V���{�������܂�Ă����B�L���X�g���k�Ȃ�\���ˁA�C�X���[�����k�Ȃ�A���r�A�����A�q���h�D�[���k�Ȃ�uom bhagwate namah�i�_�l�ւ̗�q�j�v�Ƃ����T���X�N���g��̃}���g���Ȃǂł���B�܂��A�p���l���m�̕�肪��ԑ����������̂́A�C���h�l���m�̒��ň�Ԗڗ������̂����X�����̕��m�����������̂��ʔ��������B�C���p�[�����Ő펀�����p�̃C���h�R�̕��m�̑唼�̓��X�����������悤���B�����炭�x���K���n������A��ė���ꂽ�̂��낤�B���X�����̕��ɍ��܂�Ă���A���r�A�����̈Ӗ��́A���Ƃɂ��ƁA�uhuwa
al-Gafuur�i�_�͉��ł��������ɂȂ��邨���j�v�uinnaa lillaahi wa innaa ilaihi raajiuun�i�{���Ɏ������̓A�b���[�̂��́B����̌䋖�Ɏ������͋A��܂��j�v�炵���B�܂��A�q���h�D�[���k�͂قڑS���O���J�[���i�l�p�[���l���m�j�������B�m�[�X�E�C�[�X�g�n��̕����o�g�Ǝv���镺�m�������B
�@�z�e���ɖ߂�����A���{����킴�킴�����Ă����X�|�[�c�E�J�C�g�����o���āA�z�e���̉���֎����čs�����B�{���͂W���P�T���̃C���h�Ɨ��L�O���ɔ�����ƌv�悵�Ă����̂����A�V��s�ǂƗ��K�s���̂��ߒf�O���Ă��܂����B���Ȃ��s���ɑI�ꂽ�̂��A���{�̓`���I���g�����ł��錳�U�ł������B�R�q�}�͕W�����������߁A�����╗���������낤�ƌv�Z���Ă����̂����A�ދ��ȃR�q�}�̊X�f���Ă��A�����ɖ�����ԁB���͗g����Ȃ������E�E�E�B�������������Ă����̂����E�E�E�B
�@���ʃC���h�ł͌��U�͕����Ȃ̂����A�L���X�g���̉e���������i�K�����h�B�ł́A�قƂ�ǂ̓X���܂��Ă����B����ł��ĊX�͓��ɐV�N���j�����͋C�ł��Ȃ��A�莝���������Ȑl�X��������Ă��邾���������B�g���b�N�̉ב�ɏ�����q���������u�n�b�s�n�b�s�j���[�C���[�I�v�ƍ������Ȃ��瓹�H���������Ă����̂������A�B��V�N���ۂ����i�������B����ȏ�R�q�}�ɂ��Ă��d���Ȃ��Ǝv������X�́A�f�B�}�[�v���֖߂邱�ƂɌ��߂��B�����A�R�q�}�̌��U�͌�ʋ@�ւɂ�����ȉe����^���Ă����B�R�q�}�s���p�̃��[�J���E�^�N�V�[�i���F�ƍ��̃c�[�g���E�J���[�j�͑����Ă������̂́A�s�O�p�̒������^�N�V�[�i���F�j���S����������Ȃ������̂��B�z�e�����烍�[�J���E�^�N�V�[�ɏ���ă_�E���^�E���܂ōs���Ă��͕ς��Ȃ������B�ƁA���̂Ƃ��A�f�B�}�[�v�����獡�R�q�}�ɓ�����������̒������^�N�V�[������ė����B���̃h���C�o�[�ƌ�������A�U�O�O���s�[�Ńf�B�}�[�v���܂ōs���Ă���邱�ƂɂȂ����i���K�����͂T�O�O���s�[�j�B�܂��^�N�V�[�ɂ͏�q������Ă����̂ŁA�h���C�o�[�������̏�q�����낵�Ă܂��߂��ė���̂�҂��Ă����B����ƁA��X�̗l�q���f���Ă����P�l�̉������ȃi�K�l���b�������Ă����B�u�E�`�Ɏ��莞��̑�������B���ɗ��Ȃ����H�v�ǂ��������͉���������̂��Ȃ��̂ŁA���߂Ĕނ̎����Ă��鎩���̑��ł����悤���ƍl���A�^�N�V�[�����Ă���ނ̉Ƃ�K��Ă݂��B�Ƃ̓z�e���E�W���v�t���炳��ɐ�֍s�����A�J�e�h�����֍s���r���̍⓹�ɂ������B�Ƃ̗��̖؍ޒu����̉�����A�P���قǂ̗��̏����̖ؑ��ƁA�Q���قǂ��闇�̒j���̖ؑ��A�����Ėؐ��̎M���o�Ă����B�����̖ؑ��͉��܂炵���A�r�[�Y�̎����⎨��������Ă��āA���[�⏗����܂Ő��X�����Č�����Ă����B�m���ɌÂ����������A�c�t�ȍ��Ō|�p�I�ȉ��l������悤�ɂ͎v�����A�����C�����Ȃ������B�ނ������ɂ͂P�T�O�O���s�[�炵���B�j���̑��͑傫�����Ď����ċA�邱�Ƃ͕s�\���낤�B�ؐ��̎M�́A�ނ̐����ɂ��ƁA���������E�҂݂̂��g�p�ł�����ʐ��̎M�炵���B�召�Q�̃T�C�Y���������B���̑��A�ނ̉Ƃ̒��ɂ͓y�Y�����ł͌��邱�Ƃ��ł��Ȃ��悤�ȁA�ς�����`�̖ؐ��Ƌ��ؐ��H��A�����Ȃǂ��u����Ă����B��X�̂P�l���A�r�[�Y�̃l�b�N���X���~�����ƌ����ƁA�u������Ƒ҂��ĂĂ���v�ƍs���Ĕނ͂����ނ�ɑ���o�����B���炭�҂��Ă���ƁA�ނ͎�ɂP�̃l�b�N���X�������đ����ė����B�����N���̎�O���Ď����ė����̂ł͂Ȃ��낤���B���������ʔ����o�܂�����A�ނ���Â��r�[�Y�̃l�b�N���X���w�������B���������ǂꂾ���̉��l������̂��͐��ƂȂ̂ŕ�����Ȃ��B�����A�i�K�����h�Ŗ{���ɂ������̂����Ƃ�����A�y�Y���Ȃǂł͂Ȃ��A���Ƃɍs���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv�����B
�@�R�q�}���P�Q�����ɏo���B�f�B�}�[�v���߂��͋��J�ƂȂ��Ă���A�����̐l�X���J��̐�݂Ńs�N�j�b�N�����Ă���p���ڂɓ������B�i�K�����h�ň�Ԃ̌�y�̓s�N�j�b�N�̂悤���B���������f���[�ʼn�����i�K�̗F�l���A�ǂ����̎R���Ńs�N�j�b�N�����ʐ^��厖�Ɏ����Ă����B�f�B�}�[�v���ɂ͂R���߂��ɓ��������B�������z�e���E�T���}�e�B�ɏh�������B
�@�f�B�}�[�v���̓X���قڑS�ĕ܂��Ă����̂ŁA���ɂ�邱�Ƃ��Ȃ������B�z�e���E�T���}�e�B�̋߂��ɉ��{�Ղ�����Ƃ̂��Ƃ������̂ŁA�����܂ŎU�����Ă݂��B���{�̓J�`���[���[�E���C���Y�ƌĂ�Ă���A���ꂩ���̏��ƁA�j���Ɏ������m���X���c���Ă��鑼�́A�������L�������ƂȂ��Ă����B��͂�s�N�j�b�N�ɗ��Ă���Ƒ���q�������������A���m���X�͂قƂ�ǎq���̗V�ѓ���ƂȂ��Ă����B���m���X�Ƃ͐̍\�����ŁA�m�[�X�E�C�[�X�g�n��̎��鏊�Ɏc���Ă���B���Ƀ��[�K�[�����B�̂��̂��L�����B�����A���̃J�`���[���[�̂��̂͂Ȃ��Ȃ��f���炵���������{���Ă���A���̃��m���X�Ƃ͈ꖡ������|�p���̍������̂ƂȂ��Ă����B�P�O���I������f�B�}�[�v���ɂ́A�J�`���[���[���Ƃ����ꕔ���i�i�K�̕����ł͂Ȃ��j�̉���������A�����̌������͂P�O���I�`�P�S���I�ɍ��ꂽ���̂炵���B�܂��A�R�q�}����f�B�}�[�v���ɗ���ԂɃh���C�o�[���畷�����b�ɂ��ƁA���݂���f�B�}�[�v���w�͎��̓}�j�v���w�Ƃ������O�������Ƃ����B�Ȃ��Ȃ�A�}�j�v�������̃}�n�[���[�W���[���}�j�v���w�ƁA�C���p�[������f�B�}�[�v���ɒʂ��铹�������������炾�B�E�E�E�Ƃ������Ƃ́A�f�B�}�[�v���͌��X�i�K�̗̓y�ł͂Ȃ��A�f�B�}�[�v������R�q�}���o�R���ăC���p�[���ɒʂ��铹���A���X�i�K�Ƃ͑S���W�Ȃ����̂������Ƃ������Ƃ��B�f�B�}�[�v���ƃR�q�}������ׂĂ݂�A�S���Ⴄ�\���̊X�ł��邱�Ƃ������ɕ�����B�}�j�v���Ƀq���h�D�[�̉������ł��Ă���Ƃ��ɁA�i�K�̕��������͈ˑR�Ƃ��đf�����Ŏ�������Ă����B�i�K�����h�ɂ͂قƂ�Ǖ����炵�����̂��Ȃ������̂��B�i�K�����h�B���Ɨ������Ƃ��ɁA������f�B�}�[�v���̓i�K�����h�B�ɑg�ݍ��܂ꂽ�Ƃ����B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
���m���X |
�� |
| �� |
�P���Q���i���j�@�J�[�Y�B�����K�[�������� |
�� |
�@����͌��U�łقƂ�ǂ�邱�Ƃ��Ȃ��������A���������j���Ńi�K�����h�B�̓X�̑������܂��Ă��邱�Ƃ͖��炩�������B�������ĂP���߂����������k�������ʁA�A�b�T���B�̃J�[�Y�B�����K�[������������A��ŖK��邱�ƂɌ��܂����B�J�[�Y�B�����K�[���������͈�p�T�C�ŗL���ȏꏊ�ł���B�l�̓����^���{�[�����������ŃT�t�@������������ŐH���C�����������A���̍ۊe�n�̍����������r���Ă݂�̂��y�������Ǝv���A��p�T�C�̃T�t�@�������邱�ƂɎ^�������B
�@�J�[�Y�B�����K�[���������́A�A�b�T���B�̃i�[�K�[�I���ƃW���[���n�[�g�̊Ԃɂ���A�f�B�}�[�v�������Q�O�O�����قǂ̒n�_�ɂ���B�^�N�V�[���`���[�^�[���āA�����Q�T�O�O���s�[�Ƃ������ƂɂȂ����B
�@��p�T�C�͂����炭�A�b�T���B�ő�̔��蕨�ł���B��p�T�C�̓A�b�T���B�ό��ǂ̃}�[�N�ɂ��Ȃ��Ă��邵�A�A�b�T���E�I�C���̃}�[�N�ɂ��Ȃ��Ă��邵�A�A�b�T���B�𗷍s����ƂƂɂ��������ȏꏊ�ň�p�T�C���ۂ����}�[�N�����邱�Ƃ��ł���B�����A�����^���{�[�����������ł͖ڋʂ̌Ղ�q�ނ��Ƃ��ł��Ȃ��������߁A�����T�t�@���ɂ͋y�э��ɂȂ��Ă����B���������{���ɃT�C�����邱�Ƃ��ł���̂��낤���H�����^���{�[�����������ɂ͂S�O���̌Ղ������Ȃ������B�����A�J�[�Y�B�����K�[���������ɂ͌��݂̂Ƃ���P�T�O�O���ȏ�̃T�C���������Ă���Ƃ����B����Ȃ�T�C�����邱�Ƃ͔�r�I�ȒP��������Ȃ��B�������҂��A�f�B�}�[�v�����o�ăJ�[�Y�B�����K�[���������B�i�K�����h�B�ƃA�b�T���B�̏B���ɂ͌x�@�̌��⏊�����������A���Ɍ��d�Ɍx�������Ă����킯�ł͂Ȃ������B����ł͊ȒP�ɗ��H����i�K�����h�B�ɓ���Ă��܂����낤�B
�@�i�K�����h�B�𗷍s���Ă���Ԃ́A�����������̏B�͂ǂ�������甭�W����̂��A���ɔY�܂���Ă����B�����뉽���Ȃ��̂��B�Y�Ƃ炵�����̂����ɂȂ����A�l�X���ΕׂȂ킯�ł��Ȃ����A�Ǝ��̕������Ղ�����킯�ł��Ȃ��B�S���~���悤�̂Ȃ��B�̂悤�Ɏv�����B�����āA�A�b�T���B�ɓ������r�[�A�L��Ȉ�c�ƒ����A�����ċ���ȐΖ������H��������u�ԁA�܂��܂��i�K�����h�B�̕n�������������邱�ƂɂȂ����B����̉ʂĂɂ́A�i�K�����h�B�̓A�b�T���B����Ɨ�����Ӗ����������̂��A�^��Ɏv���Ă��Ă��܂����B�A�b�T���B�̖����͖��邢���A�i�K�����h�B�̖����͂��܂�ɈÂ��E�E�E�B
�@�f�B�}�[�v������J�[�Y�B�����K�[���������܂ł͖�R���Ԕ��B���������̒����������˂����Ă���悤�Ȍ`�ɂȂ��Ă���A�ʉ߂��邾���Ȃ���ɓ��ꗿ�Ȃǂ�����邱�Ƃ͂Ȃ����A�T�t�@�������邽�߂ɍ�������O��铹�ɓ���ɂ͓��ꗿ�Ȃǂ��K�v�ƂȂ�B�ꉞ���������̒������ӂ�Ƀ��C���Q�[�g�Ǝv����傪����A��p�T�C�̑����u����Ă���B�����A�ǂ̂悤�ɂ��ăT�t�@��������̂��͑S���ē����Ȃ����߁A�O���l�ό��q���P�Ƃł����ɗ��Ă��ȒP�ɃT�t�@�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ����낤�B��X�����̏����Ȃ�������ɁA�h���C�o�[���T�t�@�����������Ƃ��Ȃ��������߁A�S��������Ȃ������B������Ȃ��Ȃ�Ɏ�T���ԂŒ��ׂ����ʁA�܂����ׂ����Ƃ̓W�[�v�̃`���[�^�[�ł��邱�Ƃ����������B�W�[�v�ȊO�̎ԗ��͍����������ŃT�t�@�������邱�Ƃ��ł��Ȃ����߁A���������̓�����ӂ�ɂ��ނ���Ă���W�[�v���`���[�^�[���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���傤�Njx�����������Ƃ�����A�����̃C���h�l�ό��q���K��Ă������߁A�W�[�v�̐����s�����Ă���A�ЂƂ̃W�[�v�ɑ����̃C���h�l���Q���鍬����ԂƂȂ��Ă����B���̒��ʼn��Ƃ��W�[�v�̃h���C�o�[��߂܂��Č����A�T�t�@�������Ă��炦�邱�ƂɂȂ����B���ꗿ�Ȃǂ��̂́A�W�[�v�̃h���C�o�[���������Ă���ł���B
�@�J�[�Y�B�����K�[���������ɂ͂������̒n��i�����W�j������A�P��̃T�t�@���łP�̒n�悵���s�����Ƃ��ł��Ȃ��B�܂��A�n�悲�ƂɃW�[�v�̃`���[�^�[�オ�Ⴄ�B���̗����͂����ƌ��܂��Ă���A�J�[�Y�B�����K�[���������c�[���X�g�E�R���v���b�N�X�̑O�Ɍf������Ă���B�����W�߂Ă݂��Ƃ���A��X���T�t�@�����J�n�����P�Q�������Ɉ�p�T�C���悭������ꏊ�́A�E�G�X�g�E�����W�Ƃ����n��炵���̂ŁA�����֍s���Ă��炤���Ƃɂ����B���O�̒ʂ�A�E�G�X�g�E�����W�͍��������̐������J�o�[����n�悾�����B������Ƀ`�P�b�g�E�J�E���^�[������A�����œ��ꗿ�A�ԗ����A�J�������Ȃǂ��B�����A�x���{�E�ɍ����O���l�������ݒ肳��Ă���A���ʂɓ��ꂵ����^�[�W�E�}�n�������y���ɍ����ό��n�ƂȂ��Ă��܂��B�C���h�l�����͓��ꗿ�Q�O���s�[�A�x����T�O���s�[�A�ԗ����P�T�O���s�[�A�J�������T�O���s�[�A�r�f�I�J�������T�O�O���s�[�Ȃǂł���̂ɑ��A�O���l�����͓��ꗿ�Q�T�O���s�[�A�x����T�O���s�[�A�ԗ����P�T�O���s�[�A�J�������T�O�O���s�[�A�r�f�I�J�������P�O�O�O���s�[�Ȃǂł���B�����^���{�[�����������͂P��̃T�t�@�����S�O�O���s�[�������̂��l����ƁA�J�[�Y�B�����K�[���������͂قƂ�ǃ{�b�^�N���ɋ߂��������ƌ�����B�����A���{�l�Ȃ�u�i�K�����h���痈���v�Ȃǂƌ����C���h�l�����œ���邩������Ȃ��B��X�́A�u���{�l�����f���[�ɏZ��ł���v�ƍݏZ���������Č�������A�C���h�l�����œ���Ă��炦���B
�@�����^���{�[�����������͎ԗ����ƂɎ��R�Ɍ���������邱�Ƃ��ł������A�J�[�Y�B�����K�[���������́A�e���������X�ьx���������K�����s���邱�ƂɂȂ��Ă���A�ނ̐擱�ɕt���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�P���Ԃ��Ƃ̏o���ŁA���̂Ƃ��ɏW�܂����W�[�v�������g��ōs������B����āA�擪�̃W�[�v�ɏ����������Ԃ������ƂɂȂ邪�A��X�͂S�䂠�钆�̂R��ڂ������B�܂��A�ǂ������߂�ꂽ�R�[�X������悤�ɂ��������B
�@�����^���{�[�����������ł͂S�O���������Ȃ��Ղ�ǂ����߂ĂR���Ԍ��������O���O�����������A�J�[�Y�B�����K�[���������ł̓T�t�@�����n�߂Đ������o���Ȃ����Ɉ�p�T�C�������B�͂�����Ă���A���݂̉͊ő����̃T�C������H��ł����B�����A�]�������Y���Ȃ��Ɠ������炢�ɂ����ʂ�Ȃ������Ƃ���ɂ��邾���������B���̌�ǂ�ǂ�i��ł����ƃW�����O���̒��ɓ���̂����A���ɉ��̓��������Ȃ������B��������O���b�Ɖ~��`���Ė߂��Ă��āA�Ō�͓W�]��̂悤�ȏꏊ�ŋx�e���ăT�t�@���I���ƂȂ�B�����ƂP���Ԕ��قǂ������B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
��Ȃ����A���ꂪ��Ԃ悭�B�ꂽ
�A�b�T�������A��p�T�C�̎ʐ^ |
�� |
�@�J�[�Y�B�����K�[���������̖ڋʂ͈�p�T�C�ł���A������K���ό��q�͈�p�T�C�ړ��Ăŗ���킯�����A�����̃T�t�@������@����ɁA�����N�ł��K���T�C�����邱�Ƃ��ł��邾�낤�B���̓_�͂����Ƃ��낾�B�������A�����Ȃ�T�C�����邱�Ƃ��ł��Ă��܂����߁A�����^���{�[�����������̂悤�ɌՂ�ǂ����߂ĉ��x�����x���T�t�@��������y���݂�A����ƌՂɏo����Ƃ��̊���Ƃ������͂Ɍ�����悤�ȋC������B����������قǐݔ��������Ă���킯�ł��Ȃ��̂ɁA�O���l��������������B�z�e����X�g�����Ȃǂ͌����Ă�����̂́A���y�Y���Ȃǂ��قƂ�nj�������Ȃ����A�W�[�v�̎�z���@���S���V�X�e�}�e�B�b�N�ł͂Ȃ��B�����^���{�[���ƃJ�[�Y�B�����K�[�A�Q�̍��������͔��ɑΏƓI�ŁA����Ӗ������[�������B�J�[�Y�B�����K�[�̃��X�g�����Œ��H��H�ׂ���A�R�����Ƀf�B�}�[�v���֔������B
�@�[�H�͌��h�f������ɏ��҂��Ă���Ă����B�z�e���Ɏ����Ԃ��}���ɗ��Ă��ꂽ�B���h�f�̉Ƃ͂Q�K���Ă̋����قǗ��h�ȍ��@�ŁA��ɂ͒r�┨���������B���̍��ł̓G���[�g�x�@�ɔ���ȗ����ƍ��Y���W�����邱�Ƃ���Ă����B�[�H�̓i�K�̓`���ƒ뗿��������Ă�������B�ؓ���E�i�M�̃J���[�A�_�[���A��J���[�A�`���g�j�[�A���G�r�Ȃǂ������B�i�K�����Ƃ����ƃ`���ł������t�������ĂȂ����h�����Ƃ�����ۂ��������A���̗[�H�͉�X�̂��Ƃ�z�����Ă���đS�R�h���Ȃ����t���ɂ��Ă���Ă����B����䥂ł������̔��ɃV���v���ȗ����������A�R�̗����Ƃ��������������B
�@�R�q�}�̐�v�ҕ�n�Ő_���ȐV�N���}����Ƃ�����X�̌v��́A�����s���ƔN���N�n�̒����x�ɂ̂��߂Ɏ��s�ɏI����Ă��܂����B�����̑����̗�Ԃɏ���ăO���[�n�[�e�B�[����f���[�֖߂�Ȃ���Ȃ�Ȃ����߁A�������Ō�̃i�K�����h�؍ݓ��ƂȂ�B�������A�����f�B�}�[�v������O���[�n�[�e�B�[��������Ԃ͌ߌ�S�������̂��߁A�܂����Ԃɗ]�T���������B���U�Əd�Ȃ����y�����I���A�������炢���ȏꏊ���ʏ�ʂ�c�Ƃ��n�܂�\�����������B�f�B�}�[�v���̃}�[�P�b�g������Ƃ���������������A�ǂ����Ă��R�q�}�̔����قƃZ�[���X�E�G���|���A���֍s���Ă݂��������B�܂��A�u�[�^�����s�̓��L�Ŕ������傫�������~�X�E�u�[�^���̎ʐ^�Ɠ����悤�ȁA�~�X�E�i�K�����h�̎ʐ^���B�e����Ƃ����̂������Ȗ�]�������B����āA��X�͑�������R�q�}�܂łƂ�ڕԂ������Ƃ����v��𗧂Ă��B
�@�f�B�}�[�v������R�q�}�܂ł͌����o�X���o�Ă��邪�A��ԕ֗��Ȃ̂̓^�N�V�[�ł���B�f�B�}�[�v���x�O�ɃR�q�}�s���̃^�N�V�[�X�^���h������B��荇���^�N�V�[�i�T�l���j�Ȃ�P�l�P�O�O���s�[�A�݂���Ȃ�T�O�O���s�[�ł���B�O��݂͑���ōs���A����͏�荇���ōs�������A�f�B�}�[�v������R�q�}�܂ł̈ړ����Ԃ͂�͂�Q���Ԃقǂ������B
�@�R�q�}�̃_�E���^�E���Ŏs���^�N�V�[�ɏ�芷���A�܂��͏B�������ق܂ōs�����i�����P�O�O���s�[�j�B�Ƃ��낪�����ق͂܂�����܂��Ă����B�悭����Ɓu���j�x�فv�Ə�����Ă����B���������A�C���h�̑S�Ă̔����ق͌��j�����x�ٓ��ƌ��߂��Ă���̂������B�������Ō�̃`�����X�������̂����E�E�E�B�������A�����ق̑O�ɊW�҂Ǝv����l�����l���ނ���Ă����̂ŁA���ʂɊJ���Ă��炦�Ȃ��������Ă݂��Ƃ���A���傤�ǒ��ɂ����ْ��Ɖ�킹�Ă��ꂽ�B�ْ��Ɏ�����������ƁA���ʂɌ����Ă��炦�邱�ƂɂȂ����B�������J���Ă�����āA�������璆�ɓ������B����̃i�K�����h����Ƃ����A�����ٓ���Ƃ����A�S�ė�������̗��s�ƂȂ��Ă��܂��Ă���E�E�E�B
�@�R�q�}�B�������ق̓i�K�����h�B�̊e�����̏Љ���Ă���B���g��̐l�`�ɂ��ߕ���Z���̃W�I���}�W���A����A���g��A�D���A�����p��Ȃǂ̓W���A�����ĂȂ�������G��̓W�������Ă������B�ْ�������ē����Ă��ꂽ���߁A�������Ă����Ȍ��w�ƂȂ����B�W�����͂Ȃ��Ȃ����R�ƕ��ׂ��Ă���A�C���h�̔����ق̒��ł͂悭�ł������������B�������A���̔����ق̍ő�̌��_�́A�i�K�̕����̒��Œ����ԑ����Ă�������̌����L�����K�������B����Ă������Ƃł���B�ꉞ�[���̓W���͂��������A���ꂾ���������B�i�K�����h�́u�i�K�v�Ƃ́A�q���f�B�[��́u�i���K�[�i���j�v�ƊW���Ă���A�܂�i�K�����h�Ƃ́u�����̍��v�Ƃ����Ӗ��ł���i�ւ��Ӗ�����u�i�[�K�v�Ƃ͊W�Ȃ��悤���j�B�������A�����قɓW������Ă����l�`�͊F�ߕ��𒅂Ă����B������傫�ȉR�U��Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv�����B���Ȃ݂Ɋٓ��͎ʐ^�B�e�֎~�ł���B�ْ�����͔����ق̃p���t���b�g�����炦���B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�B�������ق̓�����̒���
����̂��킢���G������ł��� |
�� |
�@�����ق�������́A�R�q�}�̔ɉ؊X�X�[�p�[�E�}�[�P�b�g�̃Z�[���X�E�G���|���A���֍s�����B�����͕��ʂɉc�Ƃ��Ă����B��͂�i�K�����h�̍H�|�i�͌|�p���������Ȃ��A���͂ɖR�������̂��肾�����B��Ԗڗ����y�Y�͑��B�������ǂ�����Ď����ċA��Ƃ����̂��B���̑��A�G���|���A���ɒu���Ă������i���́A�����Ă���Ǝ��ꂻ���Ȃ��ǂ남�ǂ낵�����A��{�̖łł����M�A�e�����̓����I�ȐD���A�����ɂ����Z���ƌ����������̃l�b�N���X�ȂǂȂǁB�Ȃ����n���̃i�K�l�������ɗ��Ă����̂͂ǂ��������Ƃ��낤���E�E�E�B�F�l�͂��˂Ă��瑄�����Ƃ��Ă����̂����A�G���|���A���Ŗؐ��̃N���X�{�E�����đ����ōw���B�l�i�͂R�P�O���s�[�Ƃ����j�i�̒l�i�B�l�̓p�[���p�̃��C��������������̃A���e�B�[�N���P�[�X�i�T�O�O���s�[�j�ƁA�i�K�����h���Љ���{�i�R�O�O���s�[�j�����B�X�ɂ͖����ߑ��𒅂����̎q�̎ʐ^���ڂ��Ă���Q�O�O�S�N�̃J�����_�[���������Ă������߁A������Ă���̂������Ă݂���A�����ł��ꂽ�B�����ɂ��̃J�����_�[����Ԃ̋M�d�i�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
���ǂ남�ǂ낵���ؑ� |
�� |
�@�X�[�p�[�E�}�[�P�b�g����o�X�X�^���h�ɂ����Ă̏��X�X�ɂ͂������{�����������B�i�K�̌���Ɋւ���{���~�����Ă������̏��X������Ă݂���A����{���ŁA�R�q�}���ӂɏZ�ރA���K�~���̌���uTenyidie�v�̊ȒP�ȃt���[�Y�E�P��W�ƁA�p��A�q���f�B�[��A�i�K�~�[�Y�i�i�K�����h�̊e�����Ԃ̌��p��j�ATenyidie�̂S���������P��W�������Ă������߁A�����w�������i�e�U�O���s�[�j�B�ǂ����������₷�����e�ł͂Ȃ��������A����Ńi�K�����h�̌���ɂ��ď���������悤�ɂȂ肻�����B���Ȃ��Ƃ���L�̖{�̂������ŁA�i�K�~�[�Y�̓A�b�T�~�[��̕����ł��邱�Ƃ����������B�m�[�X�E�C�[�X�g�n��ł́A�q���f�B�[������p��̕����ʂ���Ǝv���Ă����̂����A���Ȃ��Ƃ��i�K�����h�B�ł͉p������q���f�B�[��̕����ʂ��ď��������Ă����B�q���f�B�[�ꂪ������Ȃ��l�͂��Ȃ����A�p�ꂪ������Ȃ��l�͂܂������B���̗��R�̂ЂƂ́A�i�K�̕������m�̌��p��ł���i�K�~�[�Y���A�q���f�B�[��Ƌ߂��W�ɂ���A�b�T�~�[�����ɂ��Ă��邩�炾�낤�Ɛ����ʂ�ꂽ�B
�@���������I������́A�o�X�X�^���h�߂��̐H���Œ��H��H�ׂ��B�|�[�N�E�X�[�v�E�`���E�Ƃ������j���[���ؓ��̓������k�[�h���E�X�[�v�ł��邱�Ƃ��������Ă������߁A����𒍕����A����Ƌ��Ƀ����i�`�x�b�g���L�q�j�������ɐH�ׂĂ݂��B�����͓ؓ��݂̂��������A���I�ƃ^�P�m�R���܂Ԃ��č�����\�[�X�Ƌ��ɏo�Ă��ĂȂ��Ȃ��������������B�P�Q���߂��Ƀ^�N�V�[�X�^���h�Ń^�N�V�[���E���ăf�B�}�[�v���܂Ŗ߂����B
�@�f�B�}�[�v���ɂ͂Q���߂��ɓ��������B�Ō�Ƀf�B�}�[�v���̃}�[�P�b�g���U�Ă݂����A��͂肻��قǂ������͔̂����Ă��Ȃ������B�R�q�}�Ŕ����������Ă����Ė{���ɐ����������B�R�������ɂ̓f�B�}�[�v���w�Ɍ��������B
�@���̓f�B�}�[�v������O���[�n�[�e�B�[�֍s����ԁA�ߌ�S�������Q�O�U�W�W�����E�V���^�[�u�f�B�[�E�G�N�X�v���X�̃`�P�b�g�擾�ł���㒅���������B���h�f�̘b�ł̓`�P�b�g�͊ȒP�Ɏ���Ƃ̂��Ƃ��������A���̓��̓E�F�C�e�B���O�E���X�g�ƂȂ��Ă��܂��Ă����B�������w�̔h�o���̏����⌳�h�f�̗��H��ɂ��A���Ƃ��R�l���̍��Ȃ���ɓ������B�܂����◠���ł���B�ǂ��炩�Ƃ����ƁA�x�@�������K�̓��拖�������Ă��Ȃ���X�ɑ����i�K�����h���o�čs���Ă��炢�����悤�Ȋ�������������A���݂��l�������̂�������Ȃ��B�����ɂ́A�u���͐��K�̓��拖�������ė��Ă��������B����������ł����}���܂��v�ƌ����Ă��܂����B
�@�O���[�n�[�e�B�[����f�B�}�[�v���֍s���W�����E�V���^�[�u�f�B�[�E�G�N�X�v���X�̎ԓ��ł́A�`���[�C�A�R�[�q�[�A�J�c���c�A�`�L���E�t���C�h���C�X�ȂǁA���낢��Ȏԓ��̔��������Ċy���������̂����A�Ȃ����A��̓���Ԃł͎ԓ��̔����قƂ�ǂȂ������B����ł��r���̉w�Ńv�[���[���ĐH�ׂ����߁A���������Ƃ͂ł����B�l�ׂ̗ɂ̓x���K���l�Ŗ����̂̉̎������Ă���Z��������A���������̂����Ă��ꂽ�B
�@��Ԃ͌ߌ�X���߂��ɃO���[�n�[�e�B�[�w�ɓ��������B�w�O�ɂ���A�b�T���B�ό��njo�c�̃c�[���X�g�E���b�W�ɔ��܂肽�������̂����A�����ɂ������������B���ǃI�[�g�E���N�V���[�ɔC���āA�w�̔��Α��ɂ���z�e���E�X�^�[���C���ɔ��܂邱�Ƃɂ����B�m���`�b�̃_�u�����S�W�O���s�[�A�`�b�̃_�u�����U�U�O���s�[�B���ꂵ���������Ă��Ȃ������B�[�H�́A�O��s�����W���X�g�E�t�B�b�V���ŐH�ׂ悤�Ǝv�������A���ɕƎ��Ԃ̂P�O�����߂��Ă��ĐH�ׂ����Ă��炦���A���܂��������A�z�e���O�ɂ���_�[�o�[�i���H���j�Ńt�B�b�V���E�J���[�e���H�ׂ��B
| �� |
�P���S���i�j�@���[�W�_�[�j�[�E�G�N�X�v���X |
�� |
�@�O���[�n�[�e�B�[����f���[�܂ł́A�u�C���h�̐V�����v�Ƃٖ̈��������[�W�_�[�j�[�E�G�N�X�v���X�ŋA�����B���[�W�_�[�j�[�E�G�N�X�v���X�Ƃ́A�C���h�̎�v�e�s�s�����ԓ��}�Q���Ԃ̑��̂ł���A�S�Q��Ȃ��S�G�A�R���ԗ��ŁA��������s�@�̂悤�ɐH���t���ł���B�ԗ��ɂ͓������Q����A�P�͂R�i�Q��ԁA�����P�͂Q�i�Q��ԁB�������Q�i�Q��Ԃ̕��������B���Ȃ݂Ƀ��[�W�_�[�j�[�Ƃ́u��s�v�Ƃ����Ӗ��ł���B����͏��߂ă��[�W�_�[�j�[�E�G�N�X�v���X�̂Q�i�Q��Ԃ𗘗p�����B�f���[�܂ł͂P�X�S�O�����A�R�Q���Ԃ̗��B����Ȃɒ������ԃ��[�W�_�[�j�[�E�G�N�X�v���X�ɏ��̂����߂Ăł���B
�@�O���[�n�[�e�B�[���j���[�f���[�s���̃��[�W�_�[�j�[�E�G�N�X�v���X�͑����U�����B�O���[�n�[�e�B�[�w�ɂ͂T�����ɒ��������A���ɗ�Ԃ̓v���b�g�t�H�[���ɗ��Ă����B�ԗ��͂Q�i�̐Q�䂪�Q���������킳�����S�l�p�R���p�[�g�����g�ƁA�L���������ۂɏc�ɕ��ԂQ�i�̐Q��̂Q�l�p���Ȃō\������Ă���A�l�̐Ȃ͂��̑��ۑ��̍��ȂɂȂ��Ă��܂����B����ł͂��܂�Q�i�Q��Ȃ�������Ӗ����Ȃ��B�R���p�[�g�����g�̓�����Ƒ��ۂ̐Q��ɂ̓J�[�e�����������Ă���A�R�i�Q��ԂƋ�ʂ��}���Ă������A���ɍ�����������킯�ł�������������킯�ł��Ȃ������B�܂��A���݃j���[�f���[�`�����o�C�[�Ԃ��^�s���Ă���ŐV���ԗ��̃��[�W�_�[�j�[�E�G�N�X�v���X���o�����Ă��܂��ƁA���ԗ��̃��[�W�_�[�j�[�E�G�N�X�v���X����͂��͂≽�̍������������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����낤�B
�@��Ԃ͎��Ԓʂ�o�������B���[�W�_�[�j�[�E�G�N�X�v���X�̓`�P�b�g�ɑS�H���̗������܂܂�Ă��邽�߁A�����Ă��邾���ŎO�H�ƃ`���[�C���o�Ă���B�����炭�Q�i�Q��Ԃ̕����R�i�Q��Ԃ����H���̉������悤�Ɋ������B�H���ɂ̓��F�W�ƃm���E���F�W������A���H�̓m���E���F�W�̓I�����c�A�p���A�`���[�C�A���H�Ɨ[�H�̓`�L���E�J���[�A�_�[���A�`���p�[�e�B�[�A���C�X�A�A�`���[���A�T���_�A�_�q�[�A�A�C�X�N���[���ȂǁB�R�Q���ԏ���Ă��ĕ����������A���[�W�_�[�j�[�E�G�N�X�v���X�̐H���̃��j���[�͂قƂ�Ǖς��Ȃ��B���������܂肨�������Ȃ��B������Ō�ɂ͖O���O�����ă��F�W�̃��j���[�𗊂B���������烔�F�W�̃��j���[�̕����������������B�����A���H��[�H�Ƌ��ɏo�Ă���f�Ă��̗e�����̃_�q�[�i���[�O���g�j�͐�i�ł���B�e�킪�_�q�[�̐������z�����݁A�قǂ悢�ł��̃��[�O���g�ɂȂ��Ă���B
�@�O���[�n�[�e�B�[�����U���Ԍ�ɐ��x���K���B�k���̗v�n�j���[�E�W�����p�[�C�[�O���[�w�ɓ����������Ƃ������������A���̌�͂ǂ����ǂ��ʂ��ė����̂͂悭������Ȃ������B��Œn�}�Ŋm�F�����Ƃ���A���x���K���B����r�n�[���B�ɓ���A�B�s�p�g�i�[����K���K�[�͂�����őΊ݂ɂ���n�W�v���w���o�R���Đ��i�B�E�b�^���E�v���f�[�V���B�k����ʂ��āA�B�s���N�i�E�[��ʂ��Ėk���������A�V���[�W���n�[���v�����o�R���āA�K�[�Y�B���[�o�[�h���ʂ���f���[�ɓ������B��������Ԃ̊��ɂ͎��Ԓʂ�ŁA�j���[�f���[�w�ɓ��������̂͗\�蓞�����Ԃ���R�O����̂Q�������������B
�@�f���[�ɖ߂��Ă�����������S���Ǝv�������A�^�C�~���O�����f���[�ł̓I�[�g�E���N�V���[�̃X�g���C�L���s���Ă����B����ł��K�͂̑傫�����̂ł͂Ȃ��������߁A�I�[�g�͗��p�ł����B�ߌ�R���߂��ɂ̓T�t�_���W�����O�E�G���N���C���̎���ɖ߂邱�Ƃ��ł����B�Ƃ肠�����V�����[�𗁂т��������B

�@����̃i�K�����h���s���܂Ƃ߂�ƁA���@�I�Ȉ��S��ꗷ�s�����炵�悤�Ƃ��Ă����ɂ��ւ�炸�A�v�悪�v��̈Ӗ��𐬂��Ă��炸�A�s�������������A���݂͐l���݂̂̊�Ȃ��������s�ƂȂ��Ă��܂����B��Ԓɂ������̂́A�S�l�̒c�̗��s�̂��肪�R�l�ɂȂ��Ă��܂������ƂƁA�����ăi�K�����h�B�ł͓��{�Ɠ����悤�ɔN���N�n�������x�Ɋ��ԂƂȂ��Ă��܂��Ă������Ƃł���B����ł��s�������ꏊ�͑�̍s�����Ƃ��ł��A�����ɖ߂��ė��ꂽ�͉̂^���ǂ������B
�@�m�[�X�E�C�[�X�g�́u�C���h�̒��̈ك��h�v�Ƃł��ĂԂׂ��A�S���Ⴄ�������ɑ�����n��ł���B�A�b�T���B�͂܂��C���h�����̉e�����ɂ��邪�A���̑��̂U�B�\�\�A���i�[�`�����E�v���f�[�V���B�A�i�K�����h�B�A�}�j�v���B�A�~�]�����B�A�g���v���[�B�A���[�K�[�����B�\�\�́A�����ԕ����̋��Z�n�ƂȂ��ė��Ă���A�C���h�̏펯�͂قƂ�ǒʗp���Ȃ��B���݁A�O���l�̓��悪�������ŋ�����Ă���̂́A�A�b�T���B�A���[�K�[�����B�A�g���v���[�B�̂R�B�ł���B����ȊO�̏B�͓��拖�̎擾���K�v�ŁA�ʏ�͂S�l�ȏ�̒c�̂łȂ�����͉���Ȃ��B�}�j�v���B��~�]�����B�͓��拖�̎擾������Ȃ悤�����A�i�K�����h�B�ƃA���i�[�`�����E�v���f�[�V���B�͔�r�I�e�ՂȂ悤���B�܂��A�i�K�����h�B�͋����{�R�Ɖp�̃C���h�R��������ꏊ�ł���A���{�l�ɂƂ��Ă��Ӌ`�[���B�ł���B����āA����i�K�����h�B�𗷍s��ɑI�B
�@�Ƃ��낪�A���ۂɃi�K�����h�𗷍s���Ă݂����ʁA���̏B�ɂ͓��Ɍ���ׂ����l�̂�����̂��قƂ�ǂȂ����Ƃ����������B��X�������̂̓i�K�����h�B�암�̃f�B�}�[�v���ƃR�q�}�����ł���A���ꂾ���Ńi�K�����h�B�ɂ��Č��̂͂������܂������A���������̂Ƃ�����ۂɊό����s�҂����ʂɖK��邱�Ƃ��ł���̂͂��̂Q�s�s�݂̂��ƍl���Ă������낤�B�f�B�}�[�v�����R�q�}�����r���[�ɋߑ㉻���ꂽ�X�ł���A�X���݂�Z���ɓ��ɖ��͂�����킯�ł��Ȃ��B�����Ɠc�ɂ̕��ɍs���Γ`���I�Ɖ�����Ȃǂ����邱�Ƃ��ł���悤�����A���̐l�����Ȃ��ɓc�ɂ̑���K�˂�̂́A�����Q���������H���i�K�����h�B�ł͊댯�ɂ܂�Ȃ��s�ׂł���B�l���c�ɂ̑��֍s���Ă݂��������̂����A���Ǎs�����I���������B�ꉞ�ό��q�����̃c�[���X�g�E���B���b�W�Ȃ���̂��i�K�����h�B�e�n�ɂ���A�`���Ɖ��Ȃǂ����邱�Ƃ��ł���悤�����A���n�܂ŗ����̂�����{�������Ă݂������̂ł���B�����̃c�[���X�g�E���B���b�W�͐���������Ă��Ȃ��Ƃ��������B�C�M���X�l���i�K�����h���Ǘ����ɒu�����̂��A�i�K�����h���̂ɖ��͂≿�l������������ł͂Ȃ��A�A�b�T���n���̒��v�����e�[�V��������邽�߂ł������Ƃ����B
�@���ʂɗ��s���������ł͂��܂�y���߂Ȃ��i�K�����h�B�����A�P�Q����{�ɍs����z�[���r���E�t�F�X�e�B�o���̂Ƃ������͊y���������B�i�K�����h�B�̊e���������������ߑ��𒅂ăR�q�}�߂��̃L�T�}�Ƃ����ꏊ�ɏW�܂�A�e��Â������s���炵���B�܂��A�L���X�g���k�̑����i�K�����h�B�ł́A�N���X�}�X������ɏj����B��X���i�K�����h��K�ꂽ�P�Q�����{�́A�z�[���r���E�t�F�X�e�B�o���ƃN���X�}�X�Ƃ����A�i�K�����h�̂Q��C�x���g���I�������ł���A�i�K�̐l�X���������g���ʂ��������Ԃł������炵���B
�@�i�K�����h�B�͂P�X�U�R�N�ɃA�b�T���B����Ɨ��������A�i�K�̕������Z�ޒn��ł̓C���h�Ɨ��̔N���璆�����{�ƓƗ��������J��L���ė������j������A�x�X�e�������Ȃǂ��������Ă���B���̂��ߎ������ǂ��Ȃ��C���[�W�����������A�l�������i�K�����h�B�͕��a���̂��̂ŁA���Ɋ댯�ȏB�ɂ͌����Ȃ������B�������A�������Ԃ̈ړ������Ȃ��ȂǁA�אS�̒��ӂ�ӂ�Ȃ���������ł���A��͂�C��t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��n��ł��邱�Ƃɕς��͂Ȃ��B
�@�i�K�����h�B�͓��拖���K�v�ȏB�ł͂��邪�A���B�ɏZ�ސl�X�̊�͓��{�l�Ƃ悭���Ă���A���{�l�Ȃ�m�[�`�F�b�N�œ��悪�\�ł���B�l�̗F�l�̊؍��l�Ȃǂ́A�i�K�����h�l�̗F�l�Ƌ��ɖ����œ��悵�Ă����B�����A�z�e���ɏh������ۂ͓��拖�̒����߂��邽�߁A�����̏ꍇ�͕K���m�l�̉Ƃɔ��܂�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��������邾�낤�B�܂��A�����ꂽ�ꍇ�Ȃǂ́A�ǂ�������������̂�������Ȃ��B�����ދ��Ȃ�܂��������A�S�����ꂽ�肵����h���ڂɑ������낤�B��͂���拖���擾���ăi�K�����h�B�𗷍s���ׂ��ł���B�܂��A�K���ł͂S�l�ȏ�̒c�̂������̃J�b�v���̒c�̂ɂ������͉���Ȃ����ƂɂȂ��Ă��邪�A������ł��������Z�ʂ������݂����ł���B�l��������Ȃ��悢�B
�@�l�I�ɑ傫�Ȕ����������̂́A�i�K�����h�B�Ńq���f�B�[�ꂪ�v�����ȏ�ɂ悭�ʂ������Ƃ��B�p������悭�ʂ����B�f���[�ɗ��Ă���i�K�����h�l�͉p�ꂪ���܂��l�������A�ނ�Ƙb���Ƃ��͈ӎ��I�ɉp��ł���ׂ��Ă����̂����A�i�K�����h�B�𗷍s�������ʁA���̓i�K�����h�l�����Ȃ�q���f�B�[��𗝉����邱�Ƃ����������B��͂�q���f�B�[��̉f���s�u�h���}�̉e���������Ǝv�����A�O�q�̒ʂ�A�A�b�T�~�[����x�[�X�ɂ����i�K�~�[�Y�Ƃ������ʌ��b���Ă��邽�߁A�q���f�B�[�������Ȃ藝���ł���̂��낤�B�悭�u�q���f�B�[��̓C���h�S�y�Œʂ��Ȃ��v�Ƃ������������A����̗��s�Ńi�K�����h�B�̓q���f�B�[�ꂪ�ʗp����B�ł��邱�Ƃ�������A�����S�����C�����ɂȂ����B���܂Ŗl�����s�������Ńq���f�B�[�ꂪ�S���A�܂��͂قƂ�ǒʂ��Ȃ������̂́A���[�K�[�����B�̒n���s�s�W�����C�ƁA�^�~���E�i�[�h�D�B�̓c�ɂ��炢�ł���B��{�I�ɓ��O�̐l�̌𗬂̑����ꏊ�ł̓q���f�B�[��̒ʗp�x��������X���ɂ���Ǝv���B���̒��q�ő��̃m�[�X�E�C�[�X�g�e�B�ł��q���f�B�[��̒ʗp�x���m���߂Ă݂����Ȃ����B
�@�i�K�����h�B�̖����ɂ͂��܂��]�����o���Ȃ��������A����Ƃ͑ΏƓI�ɃA�b�T���B�̖L�����ɂ͖ڂ���������̂��������B�Y��ȑ�͂ƍL��Ȉ�c�ƒ����A�Ζ��ƐΖ������H��A��p�T�C�Ƃ�����D�̃}�X�R�b�g�E�L�����E�E�E���ɃA�b�T���̕Ă̎|���͔����ƌ����Ă����B�嗱�̃T���T���̕ĂŁA���ꂪ�������A�b�T���Ŋl�ꂽ���̃J���[�Ƃ悭�����B���K���������������������C���h�Œ��̉����A�A�z�������i1228�`1838�N�j�����������Ƃ��A���̔엀�ȑ�n������Ηe�Ղɗ����ł���B
�@�i�K�����h�̓`���H�|�i�ɂ͑���Ȋ��҂��Ă����̂����A�������ƌĂׂ���̂����܂�Ȃ������n�悾�������āA�H�|�i�ɂ������x�̍������́A�ό��q�̖ڂ�D���悤�Ȃ��̂͂قƂ�ǂȂ������B����ł��A��X�����������Ŗʔ������Ȃ��̂��Љ�悤�Ǝv���B
�@���̂������~���������킯�ł͂Ȃ����A��ԃi�K�����h�炵�����낤�Ǝv���Ėl���������̂́A����̃y���_���g�ł���B�l�Ԃ̊�̌`�������ؐ��܂��͋������̃y���_���g���t���Ă���A��������Ɖ��������̑剤�ɂȂ����C���ɂȂ�B��ŏ����G�ꂽ���A�i�K���̒j���͎�����Ȃ���Έ�l�O�Ƃ͔F�߂�ꂸ�A����������������ׂ��y���_���g���牺���Ď��g�̋������ւ�B���낢��Ȑ��̎t�����y���_���g�����������A�X�Ō������̂̒��ň�Ԏ�̐������������̂́A�l�Ԃ̎�S�{���̎�P�̍��v�T��y���_���g�B�܂�A������牺���Ă����l�́A�S�l�̐l�Ԃ̎�ƁA�P���̋��̎����������ƂɂȂ�B������w�������B�����A���̌�B�������قŁA�����Ǝ�̐��̑����y���_���g���W������Ă����̂ŁA������Ɖ������C���ɂȂ����B����y���_���g�́A��̑O�ɗ��s�����A�[�P�[�h�E�Q�[���u�X�g���[�g�E�t�@�C�^�[�Q�v�̓o��L�����A�_���V���i�C���h��\�j���霂Ƃ������B���̎�̃y���_���g�́A�i�K�����h�Ȃ�ǂ��ł������Ă��邪�A�l�̓R�q�}�̃X�[�p�[�E�}�[�P�b�g�ōw�������B�����l�͂W�O�O���s�[�B���������A���e�B�[�N���ۂ��y���_���g�i�{���ɃA���e�B�[�N���͕s���j�͖@�O�Ȓl�i�Ŕ����Ă���A���ʂ͂P�O�O�O���s�[���z���邽�߁A�����������������Ǝv���B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�T��y���_���g |
�� |
�@�����A��X�̓i�K�����h�����̑��Ə����ċA�낤�ƈӋC����ł����B�i�K�����h�Ŕ����Ă��镐��̐��X�\�\���A���A���A�|�A��A���\�\�́A�܂�ŗL���s�u�Q�[���u�h���S���N�G�X�g�v�̂悤�ł���A�Q�[������ɐ��܂ꂽ��X�ɂ͂��܂�Ȃ��i�X�������B�������w�����āA�U���͂��グ�����Ƃ��낾�������A�u����Ȃ��̔����Ăǂ�����v�Ƃ�����ÂȖ₢�������S�̒��ʼn��x���R�_�}�������߁A�Ƃ��Ƃ��l�͉��̕��������Ȃ������B�������Ȃ���A�l�̗F�l�͉ʊ��ɂ��ؐ��̃N���X�{�E���w�������B�s�u�Q�[���Ō����|�̓G���t�̕���ł���A�F�l�̓G���t�C���ł��������A���̃N���X�{�E�̓I���{�����q�r�������Ă���A��������Ǝ��ꂻ���������B�ꉞ�n���Ȃ̂Ŏ����ċA��Ƃ��ɉ����x�@�Ɍ����邩�Ǝv���Ă������A��Ԃ������̂œ��ɖ��͂Ȃ������B�����炭��s�@�ŋA���Ă����玝���ċA�邱�Ƃ����������������Ȃ��B������̑傫���̕���͂������ɔ����Ȃ��l�������Ǝv�����A���y�Y�p�Ƀ~�j�`���A�T�C�Y�̑��⏂�������Ă����B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�̃N���X�{�E
�K�ѕt��������t���Ă��� |
�� |
�@�i�K�����h�̂����ЂƂ̖����ƌ����A�H���p�̎M�B���{�̑V�̂悤�ɁA�i�K�����h�ł͓`���I�ɑ��ɂȂ����M���g���ĐH��������悤���B���̎M�̓X�^���_�[�h�Ȃ��̂ł͔t�̂悤�Ȍ`�����Ă��邪�A���낢��o���G�[�V����������A�R�̎M�������ɕ���ł���悤�Ȃ��̂�A�M�̓������d���Ă���悤�Ȃ��̂��������B�����̖�ڍ����č���Ă�����̂����������A��͂�P�{�̖����ō���Ă�����̂��D��Ă���Ǝv����B
�@�i�K�����h�̎M�ł͂Ȃ����A�A�b�T���B�Ŗl�̓\�[���t�i�H��̌������j���������w�������B�P�{�̖łł��Ă�����̂ł͂Ȃ��������A�F�������A���e�B�[�N���ۂ��ċC�ɓ��������߂ɍw�������B�f�B�}�[�v������J�[�Y�B�����K�[�֍s���r���A���X�ő��l���ؐ��̒u���Ȃǂ̂��Ă���A�����̓��̂P���ōw�������B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�\�[���t����
�ڂ��Ă���̂�
�O���[�v�t���[�c
�̂悤�Ȋ��k�n�ʕ�
���ɕ~���Ă���̂�
�i�K�����h�����̌��|���J�o�� |
�� |
�@�A�b�T���B�ň�Ԃ��������Ȃ̂́A��p�T�C�̖ؑ��Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���B��L�̒��̏��ő召�l�X�ȃT�C�̑��������Ă����B�T�C�͌��X�����݂����Ȑg�̂����Ă���̂ŁA�����ɂ���Ƃ悭�h����悤�ȋC������B�C���h�ɂ̓��N�_��]�E�̒u���������������Ă��邪�A��ԃz�b�g�Ȃ̂͂��̃A�b�T�������A��p�T�C�̒u�����B���钼�̏��ł́A�P�l�ł͓��ꎝ���グ���Ȃ��傫���̈�p�T�C�̒u�����킸���S�O�O�O���s�[�Ŕ����Ă����B������f���[�܂Ŏ����ċA��͕̂s�\�Ɍ��������ߔ���Ȃ��������A���ꂪ�����f���[�̃f�B�b���[�E�n�[�g�Ȃǂœ����l�i�Ŕ����Ă�����A���w�����낤�B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
��p�T�C�̒u��
����͂Q�O�O���s�[ |
�� |
�@����c�O�������̂́A�~�X�E�i�K�����h�ƌĂԂׂ��������i�K�̏����ɉ���Ƃ��ł��Ȃ��������Ƃ��B�C���h�l�����͓��{�l�Ƃ͕ʎ����̔�����������A�����S�O���Ȃ��ɔ��l���Ǝv����l���������A�i�K�̏��������͓��{�l�Ɗ炪���Ă��邾�������āA�I�l�̖ڂ��������Ȃ��Ă��܂��B���{�l�̃t�B���^�[��ʂ��ăi�K�̏���������ƁA������O�̓��{�l�̂悤�ɂ��������Ȃ��l�������肾�B��������̓��{�̎ʐ^�Ɏʂ��Ă������Ȑl�����������B�܂��A�R�̖����̏h���Ƃ��āA�����Z���̑̌^�������l�����ɑ����B���������Ӗ��ł́A���암�ɂ���f�B�}�[�v���̕����s��I���l�������\���������B
�@�����A�B��̋~���́A�R�q�}�̃Z�[���X�E�G���|���A���ł�������u�����ߑ����܂Ƃ����i�K�̏��̎q�J�����_�[�Q�O�O�S�v�������B�i�K�����h������I�肷�������Ǝv����i�K���l�̎ʐ^�������f�ڂ���Ă���A�����炭���{�l�̖ڂɂ����l���Ǝv����̂ł͂Ȃ����낤���B
| �� |
|
|
|
�� |
|
 |
|
 |
|
|
�~�X�E
|
�i |
�K�����h�H
|
|
|
 |
|
 |
|
| �� |
|
|
|
�� |
�@�����A�����̎ʐ^�̏��̎q���{���Ƀi�K�̏��̎q�Ȃ̂��͐r���^��ł���B�ǂ������烂�f����A��Ă��ăi�K�̈ߑ��𒅂��Ďʐ^���B���������Ƃ����\�����傢�ɂ��肤��B���Ȃ��Ƃ���X���؍݂������Ԓ��A���̃J�����_�[�ɓo�ꂷ��悤�Ȕ����͂P�l������Ȃ������B�������ꂢ���ȁA�Ǝv����l�ł��A�����Ă݂�ƃl�p�[���l�������肵���B�ʂ����ăi�K�ɔ��l�͂���̂��H������̂܂܂ł���B
�@�����͂o�u�q�A�k�p���ŐV��q���f�B�[��f��uVaada�v�������B�uVaada�v�Ƃ́u�v�Ƃ����Ӗ��B�ē̓T�e�B�[�V���E�J�E�V�N�A���y�̓q���[�V���E���[�V���~���[�B�L���X�g�̓A���W�����E���[���p�[���A�A�~�[�V���[�E�p�e�[���A�U�C�h�E�J�[���ȂǁB
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
������A���W�����E���[���p�[���A�A�~�[�V���[�E�p�e�[���A
�U�C�h�E�J�[�� |
�� |
| Vaada |
�@���[�t���i�A���W�����E���[���p�[���j�ƃv�[�W���[�i�A�~�[�V���[�E�p�e�[���j�͍K���ɕ�炷�V���v�w�������B���[�t���͎��̂ɂ�藼�ڂ����������A�Q�l�̐����͈ˑR�Ƃ��čK���������B���[�t���̓J�����i�U�C�h�E�J�[���j���d���̕⍲���Ƃ��Čق����A���̓J�����ƃv�[�W���[�̗͐̂��l�������B�J���������܂�Ƀv�[�W���[�̂��Ƃ����������������邽�߁A�|���Ȃ����v�[�W���[�͔ނƐ�������Ƃ����ߋ����������B
�@������A�v�[�W���[�����݂��Ď���ł���̂�������B�����͎��E�ƌ���ꂽ���A�����O�Ɉ�̂��a�@���瓐�܂ꂽ���Ƃ�����A���E�̋^���������Ȃ�B�e�^�҂Ƃ��ċ��������̂̓J�����������B���X�ɃJ�����ɕs���ȏ؋���������A�J�����͋��n�Ɋׂ�B�����A�J�����͂Ƃ��邫����������A���[�t�����Ӑl�ł͂Ȃ����ƂɊ��t���B�v�[�W���[���E�����̂̓��[�t���ł���ƍl�����J�����́A���[�t���̖ڂ������邱�Ƃ��ꐶ�����ؖ����悤�Ƃ��邪�A���[�t���̕����ꖇ���ŁA�����玟�ւƎ��s�ɏI���B
�@�Ƃ��Ƃ��J�����͑ߕ߂���A�ٔ����ōق���邱�ƂɂȂ�B�ٔ��ł��J�����̓��[�t�����Ӑl�ł͂Ȃ����Ƃ��咣���邪�A���̗��������Ȃ��ԓx�ɂ��܂��܂������̎���i�߂邱�ƂɂȂ�B���ǁA�J�����͏I�g�Y�������n�����B
�@���[�t���͌Y�����ɃJ������K��A�S�Ă�b���B���[�t���̓J�������v�[�W���[���E�����̂ł͂Ȃ����Ƃ�m���Ă����B���[�t���̓V���K�|�[���Ŗڂ̎�p�����Ď��͂����߂��Ă���A�v�[�W���[�����������Ƃ������莩��ɋA���ė������A���̂Ƃ��J�����ƃv�[�W���[�����������Ă���̂�ڌ����Ă��܂����B���[�t���͂��̂Ƃ�����Ӗڂ̐U�����������Ƌ��ɁA�����𗠐����v�[�W���[��ӂ߂��B�v�[�W���[�͍U���I�ȃJ�����̐��i��m���Ă��������߂Ɏd���Ȃ��]���Ă��������ł��邪�A�v�̌�������������Ƃ���Ɏ��E���Ă��܂��B�����A�v�[�W���[�����E�������Ƃ�m�������[�t���́A���̌����ƂȂ����J�����ɕ��Q���邽�߂ɑS�Ă̌v����v�������̂������B |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
�@���́A�f��ق֍s�����͕̂ʂ̉f������邽�߂��������A���ɖ��Ȃ��������߂ɋ}篑���Ɍ��邱�Ƃɂ����f�悾�����B�����A���҂��z����o���Ŗ����B�ו��ɂ��ݍ����ĂȂ����������������̂́A�W�J����]�O�]����A�ϋq��O�������Ȃ�����f�悾�����B
�@��ȓo��l���͂R�l�����B���[�t���A�v�[�W���[�A�����ăJ�����ł���B�v�[�W���[�͕���̖`���Ŏ��E�����Ă��܂��A���̌��z�V�[���ɂ����o�ꂵ�Ȃ��̂ŁA�����I�ɂ̓��[�t���ƃJ�����̂Q�l�𒆐S�ɃX�g�[���[���i��ł����B��ԃX�������O�Ȃ̂́A���[�t�����Ӗڂł͂Ȃ����Ƃ��ؖ����悤�Ƃ���J�����ƁA�Ӗڂł͂Ȃ����Ƃ��B�����Ƃ��郉�[�t���̂��荇���ł���B�C���^�[�o���̒��O�Ɋϋq�ɂ̓��[�t�����Ӗڂł͂Ȃ����Ƃ���������邪�A�J����������Ɋ��t���̂́A���[�t���̕��̃|�P�b�g����{���̃��V�[�g�����Ă���ł���B�J�����͂��낢��v������̂����A��Ƀ��[�t���̕����ꖇ���ŁA�ϋq�̏���U���Ă����B
�@�X�g�[���[��A��Ԃ��ݍ����Ă��Ȃ����������́A�ٔ������烉�[�t���̖ڂ̌�����������ꂽ�Ƃ���ł���B�������s���A���[�t���̖ڂ������邱�Ƃ͂����ɕ�����͂��Ȃ̂ɁA�������ʂ́u�Ӗځv�ł������B�ǂ̂悤�Ƀ��[�t�����������ʂ�ς����̂��A�S�����炩�ɂ���Ă��Ȃ������B�����炭�ҏW�i�K�ŃJ�b�g����Ă��܂����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�@���̉f��̏I�����ɂ��Ă͎^�ۗ��_���邾�낤�B�C���h�f��̓S���̓n�b�s�[�G���h�ł���A���P�����ł���B���������̉f��̏I�����́A�n�b�s�[�G���h�Ƃ��A���n�b�s�[�G���h�Ƃ��������A�܂��P���������Ƃ������������Ƃ������Ȃ��A�s�v�c�ȏI�����������B�ϋq�̓���S���ʂ����ă��[�t���ɍs���̂��A�J�����ɍs���̂��A�ň�ۂ��Ⴄ�̂��낤���A�l�̓��[�t�����̐S��ʼnf������Ă������߁A���Ƃ��J�����������ł����Ă��A���[�t�������S���������߂��I�����͖����ł����B
�@���̉f��̍ő�̌����́A�A���W�����E���[���p�[���ƃU�C�h�E�J�[���ł��낤�B�A���W�����E���[���p�[���́uAankhen�v�i2002�N�j�ł��Ӑl�̖�������Ă������A����̕��������Ƃ������Z�����Ă����B�U�C�h�E�J�[���́uMain
Hoon Na�v�i2004�N�j�̃q�b�g�ł��Ȃ芔���グ�����A���̉f��Ŏ��̒��ōł����Z�͂̂���j�D�ł���Ƃ������Ƃ������t�����Ƃ�����B�A���W�����E���[���p�[���ƃU�C�h�E�J�[���́A�Q�l�Ƃ����g�A�אg�A�n���T���A����ł��ă}�b�`���Ƃ��������悤�ȃL�����N�^�[�����A�Q�l�̓Ǝ��̎������\�\���������̃A���W�����A���{�̃U�C�h�\�\�����܂������o����Ă����B�A���W�����ƃU�C�h�ɁA���ݐl�C�}�㏸���̃W�����E�A�u���n�����������R�l���A���݂̃{���E�b�h�E�̎��j�D�R�l�O���ƌ�����B�A�~�[�V���[�E�p�e�[���͋v���U��ɃX�N���[���Ō����B�o�Ԃ����Ȃ��������A�����Ȃ����Z�������B�ޏ��͍ŋ߁A�ޏ��̎�����s���Ɏg�p�����Ƃ��Ď��̕��e��Ƒ���i���Ă���A�v���C�x�[�g�Ŗ�������Ă���B
�@��ɃI�X�X���̉f��Ƃ����킯�ł͂Ȃ����A���đ��͂Ȃ��f��ł���B
�@��N�P�Q���Q�U���̃X�}�g�����n�k�A�����Ă���ɔ����C���h�m�Ôg�́A��Вn�͂��Ƃ�萢�E���ɑ傫�ȃV���b�N��^�����B���҂̐��͂܂��܂����肳��Ă��Ȃ����A���̂Ƃ��덇�v�P�T���l�ȏ�ƂȂ��Ă���B���̒Ôg�Ɋւ��Ă͊e���ʂ��炢�낢��ȕ��͂�����Ă��邽�߁A�l���킴�킴�������Ƃ��Ȃ��̂����A���̒Ôg�����������ɋ}�ɐ��E�I�ɂ��̖���m���邱�ƂɂȂ����A���_�}�����j�R�o�������̂��Ƃɂ͏����G��Ă������Ǝv�����B
�@�A���_�}�����j�R�o�������́A�C���h�����ނ��듌��A�W�A�ɋ߂��ʒu�ɂ����k�ɘA�Ȃ������X�ŁA�x���K���p�ƃA���_�}���C���u�ĂĂ���B�����ɂ͖k�܂P�O�x���Ȗk�̓A���_�}�������A�ȓ�̓j�R�o�������ƂȂ��Ă���A��ȓ��́A�k����m�[�X�E�A���_�}�����A�~�h���E�A���_�}�����A�T�E�X�E�A���_�}�����A���g���E�A���_�}�����A�J�[���E�j�R�o�����A���g���E�j�R�o�����A�����ăO���[�g�E�j�R�o�����ł���B����ȊO�ɂ��召�l�X�ȓ��ŃA���_�}�����j�R�o�������͍\������Ă���B�A���_�}���Ƃ̓}���[��Ńq���h�D�[���̉��̐_�l�n�k�}�[�����w���A�j�R�o���̓}���[��Łu�����Ɠy�n�v�Ƃ����Ӗ��ł���B�A���_�}�����j�R�o�������̓C���h�̘A�M�����n�̂ЂƂŁA���S�s�s�̓T�E�X�E�A���_�}�����ɂ���|�[�g�E�u���A�B�ŋ߂ł́u�Ō�̔鋫�v�Ƃ��ď��X�Ƀ��]�[�g�ό��n�Ƃ��ėL���ɂȂ�������B�A���_�}�����j�R�o�������̊C�́A�قƂ�ǎ�t�����Ȃ��������Đ��E�L���̔������ƌ�����B�܂��A���݂ł̓C���h�{�y����̈ږ��������Z�ݒ����Ă�����̂́A�A���_�}�����j�R�o�������ɂ͂U���N�O�ɈڏZ���Ă����Ƃ����A���ł�����������Ō��n�I�Ȑ����𑗂��Z���������Z��ł���A���������Ӗ��ł����ɋ����[���n��ł���B�����A�C���h���{���O���l�̗���������������������Ă��邽�߁A���ʂ͊ό��q����Z���ƌ𗬂��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�A���_�}�����j�R�o�������͓���A�W�A�ƒ��������ԏd�v�ȃV�[���[����ɂ��邽�߁A�C���h��R��C�R�̊�n���ݒu����Ă��邱�Ƃ��Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�@���j�I�ɂ��A���_�}�����j�R�o�������͓��قȉ^����H�����B���{�Ƃ��W������Ƃ��낪�����[���B�A���_�}�����j�R�o�������͒��N��Z�������̋��Z�n�ƂȂ��Ă������A���̒n�����߂ăC���h�{�y�̐����̎x�z���������̂͂P�V���I�������B�A���_�}�����j�R�o�������͂P�V���I�Ƀ}���[�^�[�����̎x�z���ɒu���ꂽ��A�P�W�T�V�N�ɉp���ɐ�̂���Đ����Ƃ̗��Y�n�ƂȂ����B����E��풆�̂P�X�S�Q�N�ɂ͓��{����̂��A�X�o�[�V���E�`�����h���{�[�X�Ɏ��R�C���h�����{�̓��ʂ̗̓y�Ƃ��Ē��Ȃ�����A�����I�ɂ͋����{�R�����Ԃ��ĊǗ����s�����B���̂Ƃ��̖��c��ɂ��A�|�[�g�E�u���A�ɂ͐_�Ђ�����A���{�������ׂ�铇��������Ƃ����B�C���h�Ɨ���̓C���h�̂ɑg�ݍ��܂�A�A�M�����n�ƂȂ����B
�@�A���_�}�����j�R�o�������ɂ͍��v�U�������Z��ł���A���̓��̑����͏��ł̊�@�ɕm���Ă��鏭�������ł���B�������������������邪�A�قƂ�ǂ̕����͖����Ɍ��n�I�Ȑ����𑗂��Ă���A�����l�ފw�Ґ����̒n�ƂȂ��Ă���B����w�I�ɂ����ɋ����[���B����̒Ôg�ɂ��A����班�������̈��ۂ��C����ꂽ���A�ĊO�������������Ƃ�����ɐl�X�̊S���W�߂錋�ʂƂȂ����B�P���X���t���̃T���f�[�E�G�N�X�v���X���̐܍��ŁA�T���f�[�E�X�g�[���[���ɁA�����̕�������Ôg����ǂ������c�����̂��A���W������Ă����B
���O���[�g�E�A���_�}�����iGreat Andamanese�j
�@��s�|�[�g�E�u���A������T�E�X�E�A���_�}�������ӂ̓��X�͉p�̃C���h����A�O���[�g�E�A���_�}�������ƌĂ�Ă����B�P�X���I�����̒����ɂ��ƁA�O���[�g�E�A���_�}�������ɂ̓l�O���C�h�l��̍��v�P�O�������Z��ł����BAka-Cari�AAka-Cora�AAka-Bo�AAka-Jeru�AAka-Kede�AAka-Kol�AOku-Juwoi�AAka-Pucikwar�AAka-Bale�AAka-Bea�ł���B�����̕����̍��v�l���͂V�O�O�O�l�قǂł��������A�p���Ƃ̐퓬��A�O���̐l�Ԃ̗����ɂ��u�a�̗��s�ȂǂŐl�����}�����Ă��܂��A�P�X�V�P�N�̎��_�łP�X�l���������c���Ă��Ȃ������B�����̕����̐����c������݂ł̓O���[�g�E�A���_�}�����ƌĂ�ł���A���݂ł͐l���͂T�O�l�قǂƂȂ��Ă���B�ނ�̓~�h���E�A���_�}�����t�߂ɂ���X�g���[�g���ɈڏZ���Đ������Ă���B���ł̓O���[�g�E�A���_�}�����͈ߕ�����ؐg�ɕt���Ȃ����n�I�Ȑ����𑗂��Ă�����̂́A�����̎�҂͐ϋɓI�ɊO�E�ƌ����X���ɂ���A�|�[�g�E�u���A�ȂǂŐX�ьx������x�@�Ȃǂ̐E�Ƃɕt���Ă���҂�����B����A�N�z�҂͎�H�|�i�Ȃǂ��Č��������Ă���B�������ł̓W�F����iJeru�j��b�����A�O���̎҂Ƃ̓q���f�B�[��ʼn�b������B
�@�P�Q���Q�U���̒Ôg�ɂ�鎀�҂̓O���[�g�E�A���_�}�����ɂ͏o�Ȃ������B�ނ炪���������̂́A�����̏U���̎w���͂̂��������Ƃ����B�U���͔N�V���Ă���A��҂͏U���ɂ���قnjh�ӂ��Ă���킯�ł��Ȃ����A����ł��U����N���҂��h�������͍������c���Ă���B�n�k�ƒÔg�����������A�U���͐l�X�ɑ��A�R�R�i�b�c�̖ɓo��悤�w�����o�����Ƃ����B�R�R�i�b�c�̖̏�ŒÔg�����߂�������A���������͋u�̏�Ɉړ����ĂS���ԉ߂����A�C���h���{�̋~����҂����B�������ŋ]���҂͂P�l���o�Ȃ������B���݁A�O���[�g�E�A���_�}�����̓��A�Q�X�l�̓X�g���[�g���ɖ߂�A�c��̓|�[�g�E�u���A�ɑ؍݂��Ă���B�Ôg�ɂ��X�g���[�g���͉����ɐN�H����Ă���A�H�ƂƐ��̋��������S�ɔj��Ă��܂��Ă���Ƃ����B
���I���Q���iOngese�j
�@�I���Q���́A�T�E�X�E�A���_�}�����̓�ɂ��郊�g���E�A���_�}�����ɋ��Z���Ă���l�O���C�h�l��̕����ł���B����l���͂X�W�l�B���Ă̓��g���E�A���_�}�����S�y�ɋ��Z���Ă������A�P�X�V�U�N�ɃC���h���{�̎w���ɂ�苭���I�ɈڏZ�������A���݂ł͓����̃h�D�S���E�N���[�N�ƃT�E�X�E�x�C�ɕ�����ċ��Z���Ă���B��͂�I���Q���������ł��������A���݂ł͗m���𒅗p���Ă���B�����A���ς�炸��̏W�̔��V�q�����𑗂��Ă���B�I���Q���͈ꕔ�ł̓}�����A�̖���������Ƃ��ėL���ł���B�P�X�X�R�N�A�C���h�̔������w�҃f�[���v���T�[�h�E�`���b�g�[�p�f�B���[�C�́A���g���E�A���_�}�����ɏZ�ރI���Q������Ɉ͂܂ꂽ�����𑗂��Ă���ɂ��ւ�炸�}�����A�ɂ�����Ȃ����Ƃ����A���̌������A�I���Q�����Z�ރW�����O���ō̎悳���ɓ��肵���B���̖ɂ͍R�M�����⌌������}�����A�������쏜������\������A���̌㎩�g���}�����A�ɓ`�������Ƃ��ɕ��p�����Ƃ���A�R���Ŋ������Ă��܂����Ƃ����B�����A�`���b�g�[�p�f�B���[�C�́A����ȗ��v�ނ��̖����鑈�����I���Q���̐��Ԍn��j�邱�Ƃ��뜜���A���̃}�����A���\������\���Ă��Ȃ��Ƃ����B
�@�I���Q�����A�\�ߐX�т̉��ɔ��Ă������߁A�Ôg�ɂ��e���͂قƂ�ǎȂ������悤���B������肩�A�P���S���ɂ̓I���Q���̐V���������܂ꂽ�Ƃ����B�����A���ŃI���Q�������ƃ^�o�R�̖����o���Ă��܂����Ƃ̕�����A�ȑO�̐����ɖ߂��̂����O����Ă���B
���W���������iJarawas�j
�@�W���������̓~�h���A���_�}�����ƃT�E�X�E�A���_�}�����̐����ɂ���W�����O���̒��ɏZ�ރl�O���C�h�l��̕����ŁA�A���_�}�����j�R�o�������̒��ōł����n�I�Ȏ�̏W�̔��V�q�����𑗂��Ă��镔���̂ЂƂł���B��͂�`���I�ɗ����ł���A�����L�k�Ȃǂō���������i��g�ɕt����݂̂ł���B����l���͂Q�U�U�l�B���炭�O�E�Ƃ̌𗬂��Ւf���Ă������A�ŋ߂ɂȂ��ăC���h�l�ފw�����ǂ��{�i�I�ɒ����ɏ��o�������Ƃɂ��A����ɃW���������̎��Ԃ����炩�ɂȂ��Ă����B
�@�W���������ɂ��Ôg�ɂ�鎀�҂͏o�Ă��Ȃ��Ƃ����B���X�C�݂ɂ͂��܂�Z��ł��Ȃ��������Ƃ����邪�A�����̏W���Ԃɒ��菄�炳�ꂽ�x��Ԃɂ��Ƃ��낪�傫���B�Ôg�������u�ԁA�x�炳��A����̌x���X�ɏW���Ԃ��삯���������߁A�W���������͔��邱�Ƃ��\�������B�܂��A�����ɓ`���`����V�ϒn�ق���ǂ����@���A�Ôg����̒E�o�ɑ傢�ɖ𗧂����Ƃ����B
���Z���e�B�l�����iSentinelese�j
�@�Z���e�B�l��������Ȃɂ��O�E�Ƃ̌𗬂�����ł��镔���ł���B�|�[�g�E�u���A�̐��ɂ���m�[�X�E�Z���e�B�l�����ɋ��Z���Ă���l�O���C�h�l��̕����ł��邪�A�n����ōł������̗��������₷�邱�Ƃɐ������Ă��镔���ł���A���ɋߕt���Ɨe�͂Ȃ���𗁂т��������邽�߁A�ڐG�͔��ɍ���ł���B����āA�ނ�̐����l���Ȃǂ͖��炩�ɂȂ��Ă��Ȃ��B�����A����ɂ��Ɛl���͂T�O�`�P�O�O�l�قǂ��Ƃ���Ă���B
�@��͂�Ôg�̉e�������O���ꂽ���A�n���s�����ɂ��Ɣނ�͖����̂悤���B�Ôg�̉e���ɂ�蓇�̌`���ς���Ă��܂������Ƃ�����Ă�����̂́A���̂Ȃǂ͊m�F����Ă��炸�A���Ȃ��Ƃ��R�Q�l�̃Z���e�B�l�����̎p�������Ƃ����B�܂��A�w���R�v�^�[�œ��̏����s�����Ƃ���A�W�����O���̒��������ˊ|����ꂽ���Ƃ�����A�u�U���I�ȑԓx�͈ȑO���炠�������A����ˊ|����ꂽ���Ƃɂ��ނ炪�����c�������Ƃ��m�F���ꂽ�v�ƌ���Ă���B
���V�����y�����iShompens�j
�@�V�����y�����̓O���[�g�E�j�R�o�����ɏZ�ރ����S���C�h�l��̕����ŁA����l���͂R�X�W�l�B��E�̏W�E���Ƃ���{�Ƃ������V�q�����𑗂��Ă���B�V�����y�����͑傫���Q�̃O���[�v�ɕ�����Ă���A�O���[�g�E�j�R�o�������ݒn�тɏZ�ރO���[�v��Kalay�A���ݒn�тɏZ�ރO���[�v��Keyet�ƌĂ�Ă���B��{�I�ɃV�����y�������W�����O���̉��[���ɋ��Z���Ă���A�Ôg�̔�Q�͔���Ă��Ȃ��ƍl�����Ă���B
���j�R�o�����iNicobarese�j
�@�j�R�o�����̓j�R�o�������ɂ���P�Q�̓��ɏZ�ރ����S���C�h�l��̕����ŁA�A���_�}�����j�R�o�������ɏZ�ޕ����̒��ōő�̐l����i���Ă���B�n���s�����ɂ��ƁA�j�R�o�����̐l���͂Q���W�U�T�R�l���Ƃ������A���m�Ȑ����ł͂Ȃ��B���̂T�����ƈႢ�A�j�R�o�����͓`�������̑������̂Ăđ傢�ɕ�������e���Ă���A�������͂W�O�����z���A�������Ƃ��Đ��{�@�ւɋ߂Ă���҂������B�X�W�����L���X�g���k�ŁA�Q�����C�X���[�������Ƃ����B
�@�j�R�o�������ł��l���������������ƁA�C�݂ɑ������Z���Ă������ƁA�܂��j�R�o���������Ôg�̉e�����ł���������Ƃ����邪�A�A���_�}�����j�R�o�������̂U�����̒��ōł������̎��҂��o�����ƂɂȂ��Ă��܂����̂��A�`�����̂Ăĕ�������e�����j�R�o�����ł��������Ƃ́A���炩�̊ܒ~���܂��ʂł���悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ��B�����Ƃ��A���X�l�������l�����̂����m�Ȑ������Ȃ����߁A��̂ǂꂾ���̎��҂��o���̂����Ԃ͒͂߂��ɂ���悤���B
�@���n�����𑗂��Ă�����Z���������Ôg�ɂ���đS�ł��Ȃ������Ƃ����́A���ꂾ������Ɣ��ɕs�v�c�Ȃ悤�Ɏv���邪�A���ǁA���ƌ����Ă������̕������W�����O���̉��[���ɋ��Z���Ă������߁A�Ôg�̒��ړI�Ȕ�Q��Ƃꂽ�����̂悤���B����ł��A�����ɒ����ԓ`����Ă����m�b�ƁA���R�Ƌ������邱�Ƃɂ���Ĕ|��ꂽ�����A��Q���ŏ����ɗ}�������Ƃ͔ۂ߂Ȃ��B����̓K�Z�l�^�ɋ߂��Ǝv�����A���镔���͂P���O����Ôg�����邱�Ƃ�m���Ă���A�W�����O���̉��n�̖̏�ɉƂ�����ĒÔg�ɔ������Ƃ����\���������B�������������Ƃ͉��Ȃ̂��A����̒Ôg�ɂ�菭���l���������邱�ƂɂȂ����B

�@�Ôg�֘A�ł����ЂƂʔ����L�����������B�P���P�Q���t���̃^�C���Y�E�I�u�E�C���f�B�A���ɂ��ƁA�o���K���[���̊X�p�����H�������������Ƃ����B���̗��R�́A�����͎��@�A���X�N�A����A�o�X��A�S���w�Ȃǂɂ��ނ���Ă����H�������A�Ôg�̔�Q�ɑ����ċ~���������L�x�ɓ͂��Ă���C���h���ݕ��ɎE�����Ă��邩�炾�B���ɍň��̔�Q�������^�~���E�i�[�h�D�B�i�[�K�p�b�e�B�i����J�h���[���ȂǂɌ�H��������W�����Ă���Ƃ����B
�@�J���i�[�^�J�B��H�~�ψψ���̃`�����h���b�p�E�a�E�}�_���ψ����́A�u���͉�X�͒Ôg�̉e���Ń^�~���E�i�[�h�D�B�Ȃǂ���̌�H�̗��������O���Ă������A�t�Ƀo���K���[�������H�̐��������������Ƃ͊�������Z�������v�Əq�ׂĂ���B��H�͎��͓����ǂ��A�R��t�����Ƃ�O��I�ɌP���������邽�߁A�{�����e�B�A�������x�����ƂȂǒ��ёO���Ƃ����B�\�\���������A�O�W�����[�g�B�Œn�k���������Ƃ����A�~�������ŏ�����Вn�Ɍ�H���E�������Ƃ����b�������Ƃ�����B���ψ����́A�u��H�����͂ǂ�ȏꏊ�ł��A�ǂ�ȏ�Ԃł������c�邱�Ƃ��ł���v�Ƌ���Ă���B
�@�����ƌ�H���ꏏ�ɂ���͎̂��炩������Ȃ����A����ł������Љ�ɂ��܂�g�ݍ��܂�Ă��Ȃ��w�̐l�X���A��ЊQ�����̂Ƃ������ɂ��������ɐ����c���Ă��邱�Ƃ́A�ǂ�������ɉ��ȋC����������B
�@�����͂o�u�q�A�k�p���ŐV��q���O���b�V���f��uAmu�v���ӏ܂����B�uAmu�v�͂o�u�q�A�k�p���łP���P��������J����Ă������ȉf�悾�B�ē̓\�[�i�[���[�E�{�[�X�B�ޏ��͂P�X�U�T�N�R�[���J�[�^�[�o�g�A�����o�C�[�ň炿�A�f���[��w�̖���~�����_�n�E�X�E�J���b�W�ŗ��j�w�w�m���擾��A�j���[���[�N�̃R�����r�A��w�Ő����w�C�m���擾�����B���̈���ŁA�w�������т��ĉ����Ɛ��������Ɏ��g�݁A���T���[���X�̉f��w�Z�𑲋ƌ�A�ēA�r�{�A���������s���č�����̂����́uAmu�v�ł������B�f��ق͖��ȏ�ԂŁA�`�P�b�g����ɓ������̂͊�Ղɋ߂������B���傤�ǖl���`�P�b�g���Ă���Ƃ��ɁA�ׂłP���`�P�b�g���L�����Z�����Ă��邨�������̂ŁA����������Ă��炦���̂������B�Ȃ������ēɂ�邱�̉f�悪����قǒ��ڂ���Ă��邩�ƌ����A�P�X�W�S�N�P�O���̖\�����e�[�}�ɂ��Ă��邩�炾�B
�@�P�X�W�S�N�P�O���A�C���f�B���[�E�K�[���f�B�[�i�����j���X�B�N���k�̃{�f�B�[�K�[�h�ɈÎE�����Ƃ����厖�����N�����B�ꍑ�̎��ÎE���ꂽ�̂�����厖���ɈႢ�Ȃ��̂����A���̈ÎE�̓C���h�S�y�ɖ\���������N�����A����ɐ[���ȑ厖���������N�����Ă��܂����B�C���f�B���[�E�K�[���f�B�[���X�B�N���k�ɈÎE���ꂽ���Ƃ�m�����q���h�D�[���k�͖\�k�Ɖ����A�蓖���莟��ɃX�B�N���k���E�Q���n�߂��̂ł���B���Ɉ�p�����Ɨ���ɑ����̃X�B�N���k������������s�f���[�ł͑����̃X�B�N���k���E�Q���ꂽ�B���̐��͂T�O�O�O�l�Ƃ��P���l�Ƃ������Ă���B�X�B�N���k�̓^�[�o���������A�����E�������킦�Ă��邽�߁A��ڂł���ƕ������Ă��܂��B�����邽�߂ɂ̓^�[�o�������A����E���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�����A�l�O�Ń^�[�o����E�����ƁA����E��邱�Ƃ̓X�B�N���̉����ɔ����Ă����B���݃C���h�ɂ̓^�[�o�����������X�B�N���k�ƁA�^�[�o���������Ȃ��X�B�N���k�̂Q��ނ������邪�A��҂̑����́A���̂Ƃ��Ɏ���̖����~�����߂Ƀ^�[�o����������l�X�ł���B�����A���̉f�悪�ł����ɂ��Ă���̂́A�P�X�W�S�N�̖\�����̂ł͂Ȃ��A�\�������������Ƃ��Ⴂ����ɉB����Ă��邱�Ƃł���B
�@�L���X�g�́A�R���R�i�[�E�Z�[���V�����}�[�A�A���N���E�J���i�[�i�V�l�j�A���V���p�[���E�V�����}�[�A�u�����_�[�E�J���g�i�V�l�j�A�`���C�e�B�[�E�S�[�V���ȂǁB�R���R�i�[�E�Z�[���V�����}�[�͗L���ȏ��D�E�ēA�p���i�[�E�Z�[���̖��ŁA�q���O���b�V���f��ō�����ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��uMr.
and Mrs. Iyer�v�i2002�N�j�ɏo�����Ă������D�ł���B����͊�{�I�ɉp�ꂾ���A�q���f�B�[��A�x���K���[��A�p���W���[�r�[�ꂪ���藐���B�x���K���[��ƃp���W���[�r�[��̃Z���t�ɂ͉p�ꎚ�����t���B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�R���R�i�[�E�Z�[���V�����}�[ |
�� |
| Amu |
�@�č��ݏZ�̃C���h�l�A�J�W���[�i�R���R�i�[�E�Z�[���V�����}�[�j�́A�]�o���g�D�L�[�i�`���C�e�B�[�E�S�[�V���j�̉Ƒ���K�˂ăf���[�ɗ��Ă����B�J�W���[�̓C���h���܂ꂾ�����B�����A�J�W���[�̗��e�͓`���a�Ŏ������Ă���A�J���[�i�u�����_�[�E�J���g�j���{���Ƃ��Ĉ�ĂĂ����B�J�W���[�͎��������܂ꂽ����K��邪�A���܂����v���o���Ȃ������B
�@�J�W���[�̓g�D�L�[�̗F�l�J�r�[���i�A���N���E�J���i�[�j�Əo��B�J�W���[�̓J�r�[���Ƌ��ɁA��w�̂��̃_�[�o�[�i���H���j�̓X��S�[�r���h�i���V���p�[���E�V�����}�[�j�̉Ƃ�K�˂�B�S�[�r���h�̓X�����ɏZ��ł������A�ނ̉Ƒ��̓J�W���[���������}����B�����A�J�W���[�̓X�����̕��i�ɕs�v�c�Ȋ��o���o����B�u���̕��i�E�E�E�������Ƃ�����I�v�S�[�r���h��̘b�ɂ��A���̃X������т͂P�X�W�S�N�̖\���̂Ƃ��ɏĂ�����ꂽ���Ƃ�m��B
�@�J�W���[�̌��ǂ��ăJ���[���f���[�ɂ���ė����B�J�W���[�͎����̏o�g�n�◼�e�̂��Ƃ�q�˂邪�A�J���[�͂͂�����Ƃ������t��Ԃ��Ȃ������B�J�W���[�͑c���̕������玩�����{���ƂȂ����Ƃ��ɍ쐬���ꂽ���ނ������A�J�r�[���Ƌ��Ɏ����̖{���̐e�Ɛ���������{�����ߎn�߂�B���ɂQ�l�́A�J�W���[�̕��e�Ǝv����l����������B���̒j�̖��̓L�V�����E�N�}�[���B���̕ӂ�ł͗L���ȃS���c�L�ŁA�I�[�g�E���N�V���[�̉^�]������Ă����B
�@�J�W���[�̓L�V�����E�N�}�[���Ɏ��������ł���Ƒł������悤�ƂP�l�ނ̂��Ƃ֍s�����A�J���[�͂���������~�߂�B�����ăJ���[�̓J�W���[�̖{���̐e�̂��Ƃɂ��đł�������B
�@�J�W���[�̓X�B�N���k�̉Ƃɐ��܂ꂽ�B���A��A�Z������A���O�̓A�����g�A�j�b�N�l�[���̓A���[�������B�P�X�W�S�N�̖\���̂Ƃ��ɕ��e�͖\�k�ɎE����A�Z�͏Ă�����ł��܂����B��e�͂��̏�ɂ����x�@����Ƃ����ɏ��������߂����������ꂽ�B�s����̂Ȃ��ނ���~���Ă��ꂽ�̂̓O���h���[���[�i�X�B�N�����@�j�������B�O���h���[���[�ŋ~���������s���Ă����J���[�́A�A���[�Əo��A���ǂ��Ȃ�B�����A�₪�ăA���[�̕�e�̓A���[���J���[�ɑ����Ď��E���Ă��܂��B�J���[�̓A���[���������A��e�̈⌾�ɏ]���āA�A���[�ɔߌ����v���o�����Ȃ��悤�C�������Ĉ�Ăė����̂������B |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
�@�uMr. and Mrs. Iyer�v�Ɏ����قǂ̌���B�ǂ��炩�Ƃ����ƃh�L�������^���[�f��ɋ߂��^�b�`�ł���A�uMr. and Mrs.
Iyer�v�قǓo��l���̊���̋@�����I���ɕ`�ʂ��Ă����킯�ł͂Ȃ����A�f�悪�����b�Z�[�W���͂�苭��ł������B�m���ɂ��̉f�悪�咣����悤�ɁA�P�X�W�S�N�̖\���̓C���h�ł͂��܂����҂�Ɍ���Ă��Ȃ��B����^�u�[�ƂȂ��Ă���B�P�X�S�V�N�̈�p�����Ɨ����̑�S����P�X�X�X�N�̃J�[���M�������͌J��Ԃ��f�扻�����ɂ��ւ�炸�A�ł���B�f��قɂ͂Ȃ����f��̃v���f���[�T�[�����Ă���A�f���f��A�ȒP�Ɉ��A���Ă����B�v���f���[�T�[�̘b�ɂ��ƁA�uAmu�v�̓x���������ۉf��Ղɏo�i����邻�����B
�@�����A�ł����̉f�悪�Y�قɕ�������Ă����̂́A���{�ɂ�艹�����J�b�g���ꂽ�����ł���B�J�b�g���ꂽ�Z���t�́A���f��̃E�F�u�T�C�g�ɂ��ƁA�uMinister
hee to the. Unhee ke shaye pe sab hua�i��b��������B��b�̎w�}�ōs��ꂽ�j�v�uSaare shamil
the... police, afsar, sarkar, neta, saare�i�݂�ȃO���������E�E�E�x�@�A�����A���{�A�����ƁA�݂�ȁj�v�Ȃǂł���B���̑��ɂ��������̃Z���t���J�b�g����Ă����B�܂�A�P�X�W�S�N�̖\���͖\�k�ɂ���Ď��R�ɋN�������̂ł͂Ȃ��A���͎҂����̎v�f�ɏ]���ċN�������Ƃ������Ƃ�`����A�����{�I�Z���t���S�ăJ�b�g����Ă����B�������A��҂����ɐ^����m���Ă��炢�����Ƃ����f�搧��҂̈Ӑ}��ł��ӂ��悤�ɁA���̉f��́u�`�v�F�A�܂萬�l�����f��Ƃ���Ă��܂����B���{�͉f�搧��҂����ɑ��A�u�Ȃ��Y�ꋎ��ꂽ�ߋ��̏o�������킴�킴�����Ԃ����Ƃ���̂��v�Ɩ₢�������Ƃ������A��L�̃Z���t���A�P�X�X�Q�N�̃o�[�u���[�E�}�X�W�h�j����A�Q�O�O�Q�N�̃O�W�����[�g�\���Ȃǂɂ��Ȃ��郁�b�Z�[�W���߂Ă��邽�߁A���ɐ_�o���ɂȂ����̂��Ǝv����B�����A���{����A�����ƂȂ����Z���t���A�Q�O�N�o�������ł��^�u�[���^�u�[�̂܂܉B���ʂ����Ƃ��鐭�{�̑̎������ɂ��]�v�I�ɂ��Ă��܂��Ă����B
�@�剉�̃R���R�i�[�E�Z�[���V�����}�[�́A���D�ɂ��Ă͔��̐F�������āA����g�������ϓI�ȃC���h�l�����Ƃ������������A���Z�͂͐\�����Ȃ��B�l�́uMr.
and Mrs. Iyer�v�̐l�Ȗ��̕����������Z�����Ă����Ǝv�����B���V���p�[���E�V�����}�[�́A�uLagaan�v�i2001�N�j�Ȃǂɏo�����Ă����j�D�B���̒j�D�͂Ȃ�������Җ��������A�������o�Ă���Ɨ����Ȃ����ƕs���ɂȂ��Ă���B��͂�uAmu�v�ł����̗�ɘR�ꂸ�A�����ɗ���҃L�����������B�S�[�r���h�͏f������i�X�B�N���k�j�̃_�[�o�[�ŏC�s�����Ă������A�P�X�W�S�N�̖\���̂Ƃ��A�S�[�r���h�͖\�k�ɋ�����āA�B��Ă����f������̋����������Ă��܂����̂������B�J�r�[�����̃A���N���E�J���i�[�͒��̉����炢���B�O���͍אg�ŃW���j�[�Y�n�݂����ł���B�R���R�i�[�E�Z�[���V�����}�[�ƃA���N���E�J���i�[�͂Ȃ����q���f�B�[�ꂪ���肾�����B
�@����̓f���[�B����ăf���[�̕��i����������o�Ă��邪�A�������ɂ����������i�ł͂Ȃ��B���ɃX�����̉��Ȃ��͌������̂܂܂ł���B�������A�t�ɂ��ꂪ���̉f��𖣗͓I�ɂ��Ă����B�����܂Ńf���[�̖{���̎p�𐳒��Ɍ��߂��f��͍��܂łȂ������B�f���[�̏Z�����ǂ�ȂƂ���ɏZ��ł���̂��A�X�N���[����ʂ��Ċώ@���邱�Ƃ��ł���M�d�ȉf��ł���B�f���[��w�̃~�����_�n�E�X�E�J���b�W���o�Ă����B
�@�C���h�f��͂��낢��ȗ��R����n���ɂ���邱�Ƃ��������A�uAmu�v�͂��̌����������̗͂����錆��ł���B�����A�f��̋𗝉�����ɂ́A�P�X�W�S�N�ɋN�������o������������x�m���Ă����K�v�����邾�낤�B�C���h�̐����w��Љ�w�ɊS������l�ɂ͕K���̉f��ƌ����Ă����B
�@�����͂o�u�q�v�����[�ŐV��q���f�B�[��f��uElaan�v�������B�uElaan�v�Ƃ́u�錾�v�Ƃ����Ӗ��B�ē̓��B�N�����E�o�b�g�A���y�̓A�k�E�}���N�B�L���X�g�̓��[�t���E�J���i�[�A�W�����E�A�u���n���A�A���W�����E���[���p�[���A���[���[�E�_�b�^�[�A�A�~�[�V���[�E�p�e�[���A�~�g�D���E�`���N���{���e�B�[�ȂǁB
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�����烉�[���[�E�_�b�^�[�A�W�����E�A�u���n���A
���[�t���E�J���i�[�A�A���W�����E���[���p�[���A
�A�~�[�V���[�E�p�e�[�� |
�� |
| Elaan |
�@���ۓI�e�����X�g�A�o�[�o�[�E�X�B�J���_���i�~�g�D���E�`���N���{���e�B�[�j�́A�Q�����s�[�̌�����f������x���J�[���e�B�[���[���E�V���[���ÎE����B�J�[���e�B�[���[���̗{�q�A�J�����i���[�t���E�J���i�[�j�́A�ǂ��ɂ��邩������Ȃ��o�[�o�[�ɑ����Q�𐾂��A�K���C���h�ɘA�s���邱�Ƃ����ӂ���B
�@�J�����́A�Ⴍ���đސE�������x�@���A���W�����i�A���W�����E���[���p�[���j�𒇊ԂɗU���A�A���W�����̍��ɏ]���āA�o�[�o�[�̎艺�������A�r�}���j���i�W�����E�A�u���n���j��E���������ԂɈ��������B�A�r�}���j���̏��ɂ��A�o�[�o�[�̓C�^���A�̃��F�l�c�B�A�ɂ��邱�Ƃ�������B�܂��A�J�����̓�����T���ē��_�l��_���Ă������|�[�^�[�̃v�����[�i�A�~�[�V���[�E�p�e�[���j����������ނ����s����B
�@���F�l�c�B�A�ɒ������J�����A�A���W�����A�A�r�}���j���́A�o�[�o�[�̈��l�\�j�A�i���[���[�E�_�b�^�[�j�ƐڐG����B�Ƃ��낪�\�j�A�̓A�r�}���j���̗��l�������B�A�r�}���j���̓J������������D���ă\�j�A�Ɠ����悤�Ƃ������A�o�[�o�[�ɕ߂܂��Ă��܂��B�A�r�}���j�������������Ƃ��J������ɓ`�����̂́A���s���Ă����v�����[�������B�A�r�}���j���ƃ\�j�A���E���ꂻ���ɂȂ��Ă����Ƃ���փJ������͋삯���A�~�o����B�T�l�͉��߂ăo�[�o�[�ɕ��Q���邱�Ƃ𐾂��A���������߂�B
�@�J������̓o�[�o�[�̌��ǂ��āA�h�C�c�̃~�����w���֕����B�o�[�o�[����R�̒��̕ʑ��ɂ��邱�Ƃ�͂T�l�́A�������v����ē˓����邪�A�����㩂������B�o�[�o�[�̎艺�Ɉ͂܂�A��̐▽�̃s���`�Ɋׂ邪�A�A���W�����̖����������s���ɂ��A���Ƃ������o�����Ƃɐ�������B�������A���̂Ƃ��ɃA���W�����̓o�[�o�[�ɐ���������A����ł��܂��B
�@�o�[�o�[�̈�������H�œƕ������߂���ʉ߂��Ă��邱�Ƃ�˂��~�߂��J���������́A�t�����X�x�@�̋��͂āA�o�[�o�[���ǂ��l�߂�B�J�����ƃA�r�}���j���͎��X�ƃo�[�o�[�̎艺��Z���������A���Ƀo�[�o�[��߂܂���B�o�[�o�[�̓C���h�Ɉ����n����A�ٔ����Ŏ��Y��鍐�����B |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
�@�n���E�b�h�f����ۂ��e�C�X�g�̃A�N�V�����f��ł��邪�A�����֔��ȐK���ڂ݂̉f�悾�����B�J�����A�A���W�����A�A�r�}���j���A�v�����[�A�\�j�A�ƒ��Ԃ������Ă����ߒ��͖ʔ����̂����A�C���^�[�o���߂����ӂ肩��}�ɃX�s�[�h���ƕ������������Ă��܂��悤�Ɋ������B���������v�����[�ƃ\�j�A���e������Đ키���R��������Ȃ��B�v�����[���J�����ɍ���Ă���Ƃ����ݒ�ɂ��Ȃ��Ă���̂����A���A�Ȃ����ꂽ�̂����`�ʂ���Ă��Ȃ��ē��ˉ߂����B�Ƃ���ŁA�u�}�n�[�o�[���^�v�ł́A�A�r�}���j���̓A���W�����̑��q�B��C�̎���œG�w�̒��ɖ��d�ɂ��˓����Ď���ł��܂��B����f���āA�Ă�����A�r�}���j�������S���邩�Ɨ\�z���Ă������A���̂̓A���W�����������B
�@���P�n�͍��B�C���h�̑��A�C�^���A�A�X�C�X�A�h�C�c�A�I�[�X�g���A�Ȃǃ��[���b�p�̊e�s�s�Ń��P������Ă����B�ē͌��X�G�W�v�g�Ńs���~�b�h�̊Ԃ���蔲����悤�ȃJ�[�`�F�C�X���B�e�����������炵�����A�G�W�v�g���{�̓h�L�������^���[�f�悵���B�e�����o���Ă��炸�A����Ƀ��[���b�p������ƂȂ����Ƃ����B���ՁA��R�̒��̃J�[�`�F�C�X�͕X�_���̒��s���A�g���b�N�̏�ɗ����ďe���Ԃ��������A���W�����E���[���p�[���͈�u�ɂ��Đ�j�ƂȂ�A�o�C�N���^�]�����W�����E�A�u���n���̎�͂�������ŁA�o�C�N�̃N���b�`������Ȃ��Ȃ����Ƃ��B�Ȃ��Ȃ����͂̂���V�[���������B�����A���Ă��ď�Ȃ������̂̓��F�l�c�B�A�ł̃{�[�g�E�`�F�C�X�̃V�[���B���E�I�ɗL���Ȃ��̉^�͂��{�[�g�Œǂ�������������̂����E�E�E�{�[�g�̐����������T�����������Ƃ������Q�O�`�R�O�����o���ĎB�e�����炵�����A����ł��X�s�[�h���Ɍ����Ă������Ƃ͔ۂ߂Ȃ��B����āA�`�F�C�X�Ȃ̂Ƀ`�F�C�X�ɂȂ��ĂȂ��X�s�[�h�łQ���̃{�[�g��������蓮�������̑ދ��ȃV�[���ɂȂ��Ă��܂����B�������B�e���A�X�s�[�h���o���������������ō��g���������Ē┑���̃{�[�g�����z�ǂɂԂ����ĉ��Ă��܂��A���������x���킳�ꂽ�Ƃ������B����̉ʂĂɁu��x�Ɖ^�͂ʼnf��B�e�����Ȃ��ł���v�ƌx�����ꂽ�炵���B�C���h�f��̒p���E�E�E�B����ɁA�A���W�����E���[���p�[�������s���̎Ԃ̏ォ�痎�������ɂȂ����Ƃ��A�o�D�T�l��������W�[�v�����Ə����ŊR���痎�������ɂȂ����Ƃ��A��Ȃ����������b���f��̃E�F�u�T�C�g�ɂ������ڂ��Ă���B���̉f��ēA���C����Ȃ��E�E�E�B
�@���[�t���E�J���i�[�͗L���o�D�������ƃ��B�m�[�h�E�J���i�[�̑��q�ŁA�A�N�V���C�E�J���i�[�̒�B�Z�Ɠ������A����ς�O���̌�ނ��C�ɂȂ�B���ڂ�����܊�Ȃ̂ŁA����̂悤�ȃA�N�V�����f��ɂ͂�����Ɩ������������B�W�����E�A�u���n���͔M���ƌ����Ă����B���傤�ǁuDhoom�v�i2004�N�j�̃E�_�C�E�`���[�v���[�̂悤�ȁA�����o�C���[�E�q���f�B�[������ׂ�S���c�L�̖��������Ă����B�����ɂȂ����u�g��v�Ƃ��������̎h�����Ă��������A�u�g�c��ԁv���v�������ׂĂ��܂����͖̂l�����ł͂Ȃ��Ǝv���B�A���W�����E���[���p�[���́A�uDeewaanapan�v�i2001�N�j��uAsambhav�v�i2004�N�j���v�킹����̔h�̊����U��B�����A�ނ̉��Z�͂������������A�ډ߂��ĂP�P�̃V�[�����u���Z�v�����u�|�[�Y�v�ɂȂ��Ă��܂��Ă���悤�ȋC������B�A�~�[�V���[�E�p�e�[���ƃ��[���[�E�_�b�^�[�́A�����̃q���C���ɊÂ邱�ƂȂ��A�e���Ԃ������ăA�N�V�����ɂ��w�߂Ă����B�����o�[�o�[�E�X�B�J���_�����������~�g�D���E�`���N���{���e�B�[�͊ԈႢ�Ȃ���Ԃ̍D���B�����A�L�����N�^�[�ݒ莩�̂����܂舫���Ƃ��Č������܂���Ă��Ȃ��������߁A���̕��������Ă����Ǝv���B
�@���y�̓A�k�E�}���N�B���[���[�E�_�b�^�[�̓o��V�[���̃~���[�W�J���͏G�킾�������A����ȊO�̑}���͉̂f��̐i�s���ז����Ă����Ƃ����v���Ȃ������B
�@�C�y�Ɍ����A�N�V�����f��ŁA�ɂԂ��ɂ͍œK�����A�B�e���b��\�ߓǂ�ʼnf������ɍs���ƁA������y���ݕ����ł��邩������Ȃ�
�@��N�P�Q�����{�A���[�W���X�^�[���B�𗷍s���ɖl�̈��@�J���Y�}�����҂��ɓ��܂�Ă��܂����B���s����A���ė�����A����͂��̒�o��ی��Ȃǂ̎����葱�����s���A�Ăуi�K�����h�B���s�֏o�������B����ɂ��Ă���Ԃɉ��炩�̐i�W�����邱�Ƃ����҂��Ă������A�c�O�Ȃ��牽�̎�|����������Ȃ������B
�@���̓i�K�����h�B���s���A���͂ǂ̃o�C�N�������v�������点�Ă����B���݈�ԔM���o�C�N�́A�g�l�r�h�i�z���_�E���[�^�[�T�C�N�����X�N�[�^�[�E�C���f�B�A�j�̃��j�R�[���i�P�T�O�����j�ł���B�g�l�r�h�͓��{�̃z���_���P�O�O���o�����ė����グ�������́u�z���_�v�ł���A�z���_���C���h��Ƃ̃q�[���[�Ёi���X���]�Ԃ̉�Ёj�ƍ������ė����グ���q�[���[�E�z���_�����i�ゾ�B�z���_���L�̉H�̃}�[�N�������Ɠ����Ă���B�g�l�r�h�͑n�Ƃ��炵�炭�̓X�N�[�^�[�݂̂��E�̔����ė����̂����A�Q�O�O�S�N�X���ɐ��Ƀo�C�N�������B���̂g�l�r�h�̃o�C�N���e�����j�R�[���ł���B�P�T�O�����N���X�ł̓_���g�c�̃p�t�H�[�}���X�ɉ����A�l�i�����荠�̂T���`�T���R�烋�s�[�B�P�T�O�����N���X�̔���o�C�N�A�o�W���[�W�Ђ̃p���T�[�œ|���f������������A�p���T�[�E�L���[�ƌĂ�ł������x���Ȃ��D�ǂȃo�C�N�ł���B���傤�ǃA�b�T���B�̃J�[�Y�B�����K�[���������ň�p�T�C�i���j�R�[���ƌ����Ίp���������n�����A��p�T�C�����j�R�[���ƌĂ�Ă���j��������������A�S�͂��Ȃ胆�j�R�[���ɌX���Ă����B
�@�������Ȃ���A�ˑR�Ƃ��ăJ���Y�}���L�͌��ł������B�l���̃J���Y�}�����Ƃ��͒艿�W�����s�[�ł���A�����ȃo�C�N���������A���݂͂P�����s�[�l��������Ă���A���Ȃ肨�荠�ȃo�C�N�ƂȂ��Ă����B�P�T�O�����̃Z���E�X�^�[�^�[�t�����j�R�[�����T���R�烋�s�[�A�P�W�O�����̃p���T�[���U�����s�[�A�Q�Q�T�����̃J���Y�}���V�����s�[���ƁA�ǂ����Ă��J���Y�}�̕��������Ɏv���ė���B����ɁA��x�Q�Q�T�����̃o�C�N�ɏ���Ă��܂�����A����ȉ��̔r�C�ʂ̃o�C�N�ɂ͏��Ȃ��Ȃ�Ƃ����̂��傫�ȗ��R�ł������B�����g������Ă����̂ŁA������x�J���Y�}�����Ƃ����C�����������Ȃ����B�Ⴄ�F�̃J���Y�}���Ƃ����I���������������A�F��ւ���Ƃi�m�t�̗F�l�ȂǂɁu�Ȃ��F��ւ����̂��H�v�u�O�̃o�C�N�͂ǂ������̂��H�v�Ƃ����������₳��邱�Ƃ͖ڂɌ����Ă������߁A�ʓ|������邽�߂ɂ��A�����F�̓����o�C�N���܂��������ƂɌ��߂��B�q�[���[�E�z���_�̓��{�l���݈��̕��̂����߂�����A����ɒl���������Ă�����āA�P���P�O���A�Ԃ̃J���Y�}���w�������B
�@���ꂩ��܂��P�T�Ԃ��o���Ă��Ȃ������A�F�l�����ƃc�[�����O�ɏo�����邱�ƂɂȂ����B����̎Q���l���͉ߋ��ő�̂R�l�B�J���Y�}�̑��́A�o�W���[�W�Ђ̃p���T�[�i�P�W�O�����j�A�q�[���[�E�z���_�Ђ̃A���r�V�����i�P�R�R�����j�ł���B�A���r�V�����͂������������Ă��܂��^���ɂ��邽�߁A����̓J���Y�}�̃f�r���[�E�c�[�����O�ƂȂ�Ɠ����ɁA�A���r�V�����̃��X�g�E�c�[�����O�ƂȂ�B�ړI�n�́A�f���[���瓌�ɂW�O�����̒n�_�ɂ���N�`�F�[�T���B���N�̂P���Ƀ��[�W���X�^�[���B�j�[�����[�i�[�ɂ���{�a�z�e���܂Ńc�[�����O���������A���̃j�[�����[�i�[�E�z�e���Ɠ����n��̋{�a�z�e�����N�`�F�[�T���ɂ�����B�}�b�h�E�t�H�[�g�E�N�`�F�[�T���\�\�܂�A�u�D�̏�v�ł���B�j�[�����[�i�[�����ɂ悩�����̂ŁA���̃z�e���ɂ�����Ȃ���҂��Ă����B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
������A�ԃJ���Y�}�Q���i�Q�Q�T�����j�A
���A���r�V�����i�P�R�R�����j�A
��p���T�[�i�P�W�O�����j |
�� |
�@���W�����A�l�̉Ƃ̑O�ŏo�w�����s�����B�Ƃ��낪�A�L�O�ʐ^���B�e���Ă���Ƃ��ɁA��p���p���Ɛ��H���E�E�E�B�u�J�H�v�J�G���I����Ĉȗ��A�f���[�ɉJ���~�������ƂȂLj�x���Ȃ������̂����A�c�[�����O�����鍡���Ɍ����ĉJ���~��o���Ƃ́E�E�E������s�^�I�����A����قljJ�͋����Ȃ�Ȃ��l�q�������̂ŁA�c�[�����O�͌��s���邱�ƂɂȂ����B���ǁA�����P����ʂ��āA�܂莞�X�J�̂悤�ȓV�C���������A�c�[�����O���s�s�\�Ȃقǂ̋����J�͈�x���~��Ȃ������B�܂��̓��[���`�����h�a�@�߂��̃K�\�����X�^���h�ŁA���p�̃K�\�����u�X�s�[�h�X�R�v�^���܂œ��ꂽ�B�������烊���O���[�h��ʂ�A�����Q�S������ʂ��Ĉ�H�����������B
�@�����i�[�͂��z���A�Ί݂ɓ�������ƁA����Ɍ��ݒ��̋���Ȏ��@���������B���ꂪ�ŋߐV������킹�Ă����A�N�V�����_�[�����I�A�N�V�����_�[���͈ȑO�A�O�W�����[�g�B�̏B�s�K�[���f�B�[�i�K���ŖK�ꂽ���Ƃ�����B�A�N�V�����_�[���Ƃ́A�ȒP�Ɍ����q���h�D�[���̏@���e�[�}�p�[�N�݂����Ȃ��̂ŁA�X���[�~�[�E�i�[���[�����Ƃ������l�����c�ɂ����A�q���h�D�[���̐V���@�h���^�c���Ă���B���̃A�N�V�����_�[�����Q�O�����s�[�̗\�Z�������ăf���[�ɂ����ݒ��Ȃ̂����A���̌��݂������ďZ���Ƌ��c�̊ԂŖ��C�������Ă����B�\��ł͍��N�̂R���Ɋ�������Ƃ������E�E�E�B
�@�����Q�S�����́A�K�[�Y�B���[�o�[�h�������߂ē��ɉ��тĂ���B���̓��͓��{�̉����ō��ꂽ�����ŁA�Б��Q�Ԑ��A���������т���̔������ܑ����H�������B����āA�C���h�̓��𑖂��Ă���Ƃ͎v���Ȃ��قǂ̉��K���B�Ƃ��낪�A���̉��K�ȕܑ����H�́A�f���[�����S�O�����̃n�[�v���ŏI�����Ă���A���̌�́A�Б��P�Ԑ��A���������тȂ��̋��|�̓��H�������Ă����B��ԋ��낵���̂́A�Ό��Ԑ��̎ԗ��̋����Ȓǂ��z���B�Б��P�Ԑ������Ȃ��̂ŁA�ǂ��z��������ɂ͑Ό��Ԑ��ɂ͂ݏo���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�o�X��g���b�N�Ȃǂ����̂ɕ������킹�Ă͂ݏo���ė���̂ŁA�o�C�N�Ȃǂ̎�҂͖ق��ē������邵���Ȃ��B����ɓ����댯�ɂ��Ă���̂́A���H�̓r�����m���r���Ɛi�ދ��Ԃ����B���傤�ǃT�g�E�L�r�̎��n�V�[�Y�����}���Ă���A�ԂɃT�g�E�L�r�ڂ������Ԃ������g��œ���i��ł����B���̂������ŏ��X�Ԃ̗��ꂪ�~�܂��Ă��܂��Ă����B���ڂ��ꂽ�T�g�E�L�r�͎ԕ����͂ݏo���ė����ɔ�яo�Ă��邽�߁A���Ɏז��ł������B��x�A���Ԃ��}�ɕ����]���������߁A�l�̃o�C�N�̒[���͂ݏo�����T�g�E�L�r�ɂԂ����Ă��܂����B�T�g�E�L�r�ɏՓˁE�E�E���{�ł͂��肦�Ȃ����̂ł���B�����A���肪�T�g�E�L�r��������������A���ɂ�����ɑ����Ȃǂ͂Ȃ������B
�@�n�[�v�����z���Ă��炭�s���ƁA������Ƃ�����������A�����Ɂu�}�b�h�E�t�H�[�g�E�N�`�F�[�T���v�̑傫�ȊŔ��������B���̊Ŕɏ]���ĉE�ɋȂ���ƁA���͂���Ɉ����Ȃ����B�{���{���ܑ̕����H�͂܂��������ŁA�������A�����A�D���A�Ώ����A�܂�ŃI�t���[�h�E���[�X�����Ă���悤�ȓ��H�������Ƒ������B�V�����قǐi�ނƁA�ĂъŔ����������߁A����ɏ]���Đi��ōs������A�ړI�n�̃}�b�h�E�t�H�[�g�E�N�`�F�[�T���܂œ��������B��f���[����N�`�F�[�T���܂Ŗ�Q���Ԃقǂ������B
�@�N�`�F�[�T���̃}�b�h�E�t�H�[�g�́A�P�W���I�����ɃW���[�g���ɂ���Č������ꂽ�B�W���[�g�Ƃ́A���݂̃n�����[�i�[�B����E�b�^���E�v���f�[�V���B���ӂɏZ�ސl�X�̂��Ƃ��w���B�W���[�g�͂P�W���I�����Ɍ����[�W���X�^�[���B�o���g�v����s�ɉ�����z���A���K���鍑�A�}���[�^�[�����A�C�M���X���C���h��ЂȂǂƓn�荇�����B�N�`�F�[�T�������̃W���[�g�����̈�p��S���Ă����悤���B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�}�b�h�E�t�H�[�g�E�N�`�F�[�T�� |
�� |
�@�}�b�h�E�t�H�[�g�́A���Ɖ��F�ŊO�ǂ����F���ꂽ���n�̏邾�����B���X�C���h�̌��z���̓����K�ƓD�ō�����悤�Ȃ��̂Ȃ̂ŁA�u�D�̏�v�ƌ����Ă����ɒ��������̂ł��Ȃ����Ƃɍs���Ă݂ď��߂ċC���t�����B�l�������������Ƃ��ɂ͂��傤�ǃz�e���Ō��������s���Ă����B�Y�J�Y�J�Ɠ��荞��ōs���āA���Z�v�V�����ŕ����������Ă����悤�ɗ��݁A�������ĉ�������A�j�[�����[�i�[�Ƃ͔�ׂ��Ȃ����炢��x���ȊO���E�����ŃK�b�J�������B����ɂ͂V�̌���������悤�����A�z�e���Ƃ��ĊJ������Ă���͈̂ꕔ�݂̂ŁA�c��̕����͉����̖��Ⴊ���ł��Z��ł���B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
���� |
�� |
�@���X�g�������J���Ă��Ȃ��悤�Ȃ̂ŁA�����͖��p�ƍl���A�����ɗ������邱�Ƃɂ����B�Ăэ����ƓD�ɂ܂݂ꂽ���𑖂��ċA�����B�u�D�̏�v������O�Ɏ��炪�D���炯�ɂȂ��Ă��܂��Ƃ́A���傤���Ȃ����o�ł���B
�@���̂܂܃c�[�����O���I��点�Ă��܂��̂����������Ȃ��̂ŁA�N�`�F�[�T������Q�S��������ɓ��֍s�����Ƃ���ɂ���K���K�[�́i�K���W�X�́j��q�ނ��Ƃɂ����B�K���K�[�͂ƌ����A�����炭�C���h�ň�ԗL���ȉ͂��낤�B���V�P�[�V���A�n���h���[���A���@�[���[�i�X�B�[�Ȃǂ𗬂��K���K�[�͂��L�������A�͂Ȃ��������āA�����̓s�s�ȊO�̏ꏊ�����R�̂��ƂȂ��痬��Ă���B���������A�L���Ȑ��n�ȊO�̃K���K�[�͂��ǂ�ȏ�ԂȂ̂����Ă݂����āA�����Q�S�����ƃK���K�[�͂���������A�u���W�K�[�g�֍s���Ă݂��B
�@�܂��́A�o�C�N�ŃK���K�[�͂�n��Ƃ����̋Ɓi�H�j�𐬂������邽�߁A�͂ɉ˂���������n��A�t�^�[�����Ė߂��ė����B���@�[���[�i�X�B�[�Ɠ������A�K���K�[�͂̐��݂̓K�[�g�i�K�i�j�ɂȂ��Ă��āA���@�⏬���Ȃǂ�����ł����B���݂͂قƂ�NJJ������Ă��炸�A�@�����ď��������������Ă��邾���������B�͂ɂ̓{�[�g�����z������ł����B�u���g���E���@�[���[�i�X�B�[�v�Ƃ����ď̂��ł��K���Ă���Ǝv����B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�u���W�K�[�g |
�� |
�@�܂��̓K�[�g�ɍ~�藧���ĕ����Ă݂��B�������l�̃{�[�g��肽�����b�������ė����B�u�{�[�g�ɏ��Ȃ����H�v�l�i���Ă݂�ƂP�O�O���s�[�ƌ����B���@�[���[�i�X�B�[���������I�l�i�������āA�P�l�Q�T���s�[�A�R�l�łV�T���s�[�ɂ��Ă�������B�{�[�g�ɏ��A�K���K�[�͂����V����B�u���W�K�[�g�̓��@�[���[�i�X�B�[���������Ə㗬�ɂ�����̂́A�͂̐F�̓��@�[���[�i�X�B�[�ƕς��Ȃ����������F�����Ă��āA�ƂĂ�����Ȃ����������悤�Ƃ͎v���Ȃ��B�K�[�g�̈�ԉ����ł͉����オ���Ă����B���@�[���[�i�X�B�[�ɂ�����Α��ꂾ�B���̎��ӂŎ��q���h�D�[���k�́A�����ʼnΑ�����ĉ͂ɗ������̂��낤�B�C���h�ɏ��߂ė����l�����̉Α��������ƁA�}�ɓN�w�҂ɂȂ��Ă��܂����̂����A���Ƀ��@�[���[�i�X�B�[�ʼn��x���������i�Ȃ̂ŁA�l�͂������Ƃ��v��Ȃ������B�E�E�E�ƁA���̂Ƃ��A�����̕�����~�}�Ԃ��Α�������đ����ė����B�Ă̒�A�~�}�Ԃ͉Α���̂����߂��Œ�Ԃ����B�E�E�E����͂��������ǂ��������Ƃ��낤���E�E�E�B�~�}�Ԃʼn^��Ă������҂��}�����������߁A�}篃K���K�[�͂܂ŘA��ė���ꂽ�̂��낤���E�E�E����Ƃ��A�a�@�Ŏ��l���~�}�Ԃɂ��^��ė����̂��낤���E�E�E�B��͂�A�͔Ȃ̉Α���́A��X�Ɏv���̃l�^�����낢��Ɨ^���Ă����B
�@�u���W�K�[�g�͑O�q�̒ʂ�A���@�[���[�i�X�B�[�������������悤�ȏꏊ���������A�ЂƂ������@�[���[�i�X�B�[�ɂȂ����̂��������B����͉͂̒��F�ɂ���Ƃł���B�u���W�K�[�g�̃K���K�[�͂ɂ́A�����������B������A���̏�Ɍ@�����ď����������Ă���B�@�����ď����ł́A�v�[�W���[�i�ՋV�j�p�̕i���Ȃǂ��Ă����B���R�̂��ƂȂ���A���B�ɂ���l�X�͂����ɏZ��ł���킯�ł͂Ȃ��悤���B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�͂̒��F�ɔ��X |
�� |
�@���̃K�[�g�ł����ЂƂʔ��������̂́A�͂̒��ɗ����Ă���l�X�ł������B���̕ӂ�͈̉͂ĊO�̂ŁA�͂̒��ŗ����Ƃ��\�ł���B���`�����炢�܂ł��Z���邭�炢�̐[���ł���B�����A����͂����Ƃ��āA�����ĉ͂�n���Ă���킯�ł��Ȃ����������A�͂̒��Ƀ|�c���Ɨ����Ă���l�X������������������Ă���̂�������Ȃ������B���̗��R�͔��ɖʔ������̂������B�{�[�g���̐����ɂ��ƁA�ނ�͐��ɗ����Ă���R�C���𑫂ŏE���Ă���炵���B�܂�A���Ő����Ȃ���悤�ɂ��Ă����������A������������Ƒ��̎w����p�Ɏg���ďE���グ�A����������Ƃ���̂��B�����A���������Ȃ��͂̒��ɃR�C���������Ă���̂��H���̂Ƃ��A�n�b�Ɛ̂̋L�����h�����B�Q�O�O�R�N�A�m�[�X�E�C�[�X�g�𗷍s�����Ƃ��̂��Ƃ������B�A�b�T���B�̃O���[�n�[�e�B�[���琼�x���K���B�̃X�B���[�O���[�܂Ō������o�X�ɖl�͏���Ă����B�l�̐Ȃ̋߂��ɂ́A�m�[�X�E�C�[�X�g�܂ŏo�҂��ɗ��āA�҂������������đ��ɋA��r���̃r�n�[���l�����l�����Ă����B������������܂�҂����̂��낤�A�ނ�̊�ɂ͊�т��������Ă����B�o�X���u���t�}�v�g���͂ɉ˂��鋴��ʂ肩�������B����ƁA�ނ�o�҂��r�n�[���l�͂����ނ�ɃR�C�������o���āA�o�X�̑�����͂������ē������ꂽ�B�u���t�}�v�g���͂̓C���h���\�����͂ł���A�A�b�T���n���̐��Ȃ�͂ł���B�����ăq���h�D�[���ł͉͂͏��_�Ƃ��ĕ`����邱�Ƃ������B�ނ�́A�u���t�}�v�g���͂̏��_�Ɋ��ӂ̋C���������߂��ΑK�𓊂����ꂽ�̂��B�E�E�E�����炭�A����Ɠ������Ƃ��A���̃K���K�[�͂ł��s���Ă���ɈႢ�Ȃ��B���������A�R�C���T���̐l�X�͋��̉����W���I�ɑ{�����Ă����B����́A�C���h�Ȃ�ł͂̌��i�ƌ�����B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�͂̒��ŃR�C�����E���l |
�� |
�@�{�[�g���V���I������A�u���W�K�[�g�֑�����O���̂Ƃ���H���Œ��H��H�ׂ��B�Ȃ�ׂ������ȃ��X�g�����ŐH�ׂ悤�Ǝv���Ă����̂����A����Ȃ��̂͂Ȃ������B�l���������H��H�ׂ��H���́A�q�Ȃ̖ڂ̑O�Ɉ�ː��|���v������A���̐��ŁA���ݐ��A��p���A�����p���A�H��p���ȂǑS�Ă�d���Ă����B���̐��͂ǂ����痈��̂��E�E�E����ς�K���K�[�̐�����ȁE�E�E�Ƃ������Ƃ͍l���Ȃ��悤�ɂ��āA�v�[���[��H�ׂ��B���͂܂��܂��B�����A���̐����Ԍ�ɁA��X���u�K���K�[�̂��b�݁v���P�����̂͌����܂ł��Ȃ��B�l�͂�����ƕ����ɂ��Ȃ��������ōς��A���ʕ��̎ア�F�l�́A���ɃV�����[��ԁB�Ȍ�A���̏�Ԃ̂��Ƃ��u�K���K�[�E�V�����[�v�ƌĂԂ��Ƃɂ����B
�@���̃c�[�����O�̖ړI�n�̓N�`�F�[�T���ł���A�K���K�[�Q�q�̓I�}�P�ɉ߂��Ȃ������̂����A�N�`�F�[�T�������܂�Ɋ��ҊO�ꂾ�������ƂƁA�u���W�K�[�g���Ȃ��Ȃ��悩�������Ƃ���A�}篃c�[�����O�̑薼�́u�K���K�[�Q�q�c�[�����O�v�ɕύX���ꂽ�B
�@�u���W�K�[�g����ʂ茩�I������́A�����������̂܂܋A�����B�s���Ɠ������댯�ɂ܂�Ȃ����H�𖽂��炪��ʂ蔲���A���{����������H�ɓ����������S�B���̂܂܃X�C�X�C�ƃf���[�ɋߕt�����B�r���A�m�C�_�k���̃K�[�Y�B�[�v���t�߂ŁA�����ɑ�ʂ̒������Ă���̂��B�����ɉ������������B�E�E�E�S�~�̂ďꂾ�B����������̃S�~�̂ď�ł͂Ȃ��B�f���[���̃S�~���W�߂��A���u�����ꏊ�ł���B�����ł����C���h�l�̓|�C�̂Ă����Ƃ��v��Ȃ��̂ŁA���̂悤�ȋ���ȃS�~�W�Ϗꂪ��s�s�̍x�O�ɑS���̕��u��ԂƂȂ��Ă���B�����悤�ȏW�Ϗ�́A�f���[�k�[�ł��������Ƃ�����B�쎟�n�����ŋ}篂��̃S�~�̂ď�֍s���Ă݂邱�Ƃɂ������E�E�E��͂�Ƃ�ł��Ȃ����̒����A�f���[�s���̏o�����S�~�������Ă����B�Ԉ���Ă���E�E�E�����Ԉ���Ă���E�E�E�ɉh�̗��ɁA����قǂ̋���ȉ��������܂�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�A����͔ɉh�Ƃ͌ĂȂ��̂ł͂Ȃ����E�E�E�B�K���K�[�̉Α���Ɉ��������āA��X�͂���Ɏv���̐[���ɕ��荞�܂ꂽ�B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�K�[�Y�B�[�v���̃S�~�W�Ϗ� |
�� |
�@���̃S�~�W�Ϗ�̂����߂��ɂ́A�`�L���A���A���̉��≮�}�[�P�b�g���������B��X���s�����Ƃ��ɂ͊��ɕ܂��Ă������A�����U������J���Ă���炵���B�f���[�ōł��V�N�ȋ�����ɓ���̂́A�`�b�^�����W�����E�p�[�N���h�m�`�}�[�P�b�g���Ǝv���Ă����̂����A�����������炱���̋��̕����V�N��������Ȃ��B������Ƃ��������������B
�@�����i�[�͂�n��A���[�f�B�[�E���[�h�̃K�\�����X�^���h�ōĂуK�\�����^���܂œ���ĔR����m���߂��B����͊��炵�^�]�̂��߁A����قǃX�s�[�h���o���Ȃ������B�S���s�����͂Q�Q�S�D�Q�����A�K�\�����̏���ʂ͂S�D�W�V�k�A����āA�R��͖�S�U����/l�B�́A�N���N�V�F�[�g���Ƀc�[�����O�����Ƃ��ɔR��̓��b�^�[�S�O����������Ƃ������̂ŁA���̂Ƃ������R��ǂ��Ȃ��Ă��邱�Ƃ����������B
| �� |
�P���P�X���i���j�@�i�`�X�ƃ}���W�ƃX���X�e�B�J |
�� |
�@�ŋ߁A�p���̃n���[���q���F�l�̒a�����p�[�e�B�[�ɁA�n�[�P���N���C�c�i���\���j�̓������i�`�X�E�h�C�c�̐����𒅂ĎQ�����A������p����O���T�����X�L�����_���X�ɕ�Ƃ������������c���������B���[���b�p�ł́A���\���̎g�p���֎~���鍑�������Ƃ����B�܂��A���N�S���P�����A���ю����@�̃}���W�i�j�̃��S���ύX����邱�Ƃ����肳�ꂽ�B���R�́A�}���W���n�[�P���N���C�c�Ǝ��Ă��邽�߁A���_���l�c�̂Ȃǂ��甽�����Ă������炾�Ƃ����B���E�I�Ƀ}���W�̃}�[�N�ɑ��������肪�����Ȃ��Ă���悤�Ɏv����B�����A���̓����ɑ��A�ߑR�Ƃ��Ȃ��C����������Ă���͖̂l�����ł͂Ȃ��͂����B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
���ю����@�̐V���S |
�� |
�@�}���W�̓A�W�A�ł͔��ɏd�v�ȃV���{���ł���B����ɂ��ƁA�}���W�^�̃V���{���͐l�ލŌÂ̋L���̂ЂƂŁA�U�O�O�O�N�O�̕lj�ȂǂɊ��Ɍ�����Ƃ����B��ʂɃ}���W�̓C���h�N�����ƌ����Ă��邪�A���@�C�L���O�A�M���V�A�l�A�}���l�A�A�����J�E�C���f�B�A���Ȃǂ��g�p���A���\�|�^�~�A�Ŕ������ꂽ�R�C���ɂ�����Ă�����ɁA���n�L���X�g���̃V���{���ł�����A�A�W�A�����łȂ����ɍ��ۓI�ȃ}�[�N�ł��������Ƃ��f����B�i�`�X�E�h�C�c�̃n�[�P���N���C�c�͙̋t�ł���A���{�̈�ʓI�ȃ}���W�͙̌`�����Ă��邪�A�C���h�ł͗����Ƃ��g�p�����B�t�̓X���X�e�B�J�ƌĂ��B�u�g�ˁv�u�K�^�v�u���N�v�Ȃǂ��ے����邨�߂ł����}�[�N�ł���A�K�l�[�V���_�ƊW���[���ƌ����Ă���B����A�̓X�A���X�e�B�J�ƌĂ�A�u�j��v���ے����A�J�[���[���_�̃V���{�����ƌ����Ă���B
�@�C���h�̊e�@�����ƂɃ}���W�̏d�v�������Ă݂悤�B�q���h�D�[���ɂ����ă}���W���ŏ��ɏ@���I�V���{���Ƃ��Ďg�p�����̂́A�q���h�D�[���̑O�g�o���������̐��T���F�[�_�ɂ����Ăł���B�X���X�e�B�J�́A�K�^�A���z�A�n���_�u���t�}�[�A�G�l���M�[�A�K�l�[�V���_�ȂǑ����̂߂ł������ۂ��ے�����B�܂��A����̕\���A�Ƃ̓�����A��ǂ̌��ւȂǂɂ��̃}�[�N���g�p����邱�Ƃ������B�����ł̓}���W�̓u�b�_�̑��Ղ��ے��������A�㐢�ɂ́u�^���ւ̕��]�v��\���悤�ɂȂ�A�����̋��A��̕��A���̗��Ȃǂɍ��܂ꂽ�B�W���C�i���ł̓X���X�e�B�J�͑�V��e�B�[���^���J���i�c�t�j��\���Ƃ���A�܂��X���X�e�B�J�̂S�{�̘r�́A�l�����܂�ς��S�̏ꏊ�\�\�����ƐA���̐��E�A�n���A�n��A���_���E�\�\���ے�����ƍl�����Ă���B
�@�h�C�c�Ń}���W�`�̋L���������I�ɗ��p�����悤�ɂȂ����̂͂P�X�P�O�N����ŁA�����_���l�̏ے��Ƃ��ă}���W���̗p���ꂽ�B���̌�A�P�X�Q�O�N�Ƀi�`�}�̓}�͂ƂȂ�A�P�X�R�T�N�Ƀi�`�X�E�h�C�c�̍����ƂȂ����B�A�h���t�E�q�g���[�͎����u�䂪�����v�̒��ŁA�n�[�P���N���C�c���u�A�[�����l��̗D�z�Ɣ����_���̏ے��v�Ɛ������Ă���B�i�`�X�E�h�C�c�̃n�[�P���N���C�c�͂S�T�x�X�����t�^����ʓI�ɒm���Ă��邪�A�^��A�S�T�X���Ă��Ȃ��A�t���g�p���Ă���B���̌�A�i�`�X�E�h�C�c�����B�ŋ��|�̑ΏۂƂȂ�ɂ�āA�n�[�P���N���C�c���\�͂Ǝ��̏ے��Ƃ��čl������悤�ɂȂ����B
�@�q�g���[��i�`�X�E�h�C�c���s�������Ƃ̌��߂������ŋc�_�������͂Ȃ����A������i�`�X���v���o���̂���������Ƃ����āA�A�W�A�𒆐S�ɐ��E���Œ����ԋg�˂̈�Ƃ��Ďg�p����Ă����}���W�̃}�[�N�̎g�p���֎~���悤�Ƃ��镗��������̂ɂ͔[�����ł��Ȃ��B����́A���_���l�̉䂪�܂܁A���Đl�̉䂪�܂܂��ƌ����Ă��������낤�B�����}���W���֎~�����Ȃ�A�C�X���[�����E�ɐN�����J��Ԃ����\���R�̃V���{���ł���\���˂����E���ŋ֎~�����ׂ��ł���B�c�O�Ȃ��班�ю����@�̒c�͉̂��Ẳ䂪�܂܂ɋ����Ă��܂����悤�����A���܂ɂ͉�X�A�W�A�l���A�W�A�̎咣�����Ă����Ȃ��ƁA���Ẳ䂪�܂܂Ɏ��~�߂�������Ȃ��Ȃ�B
�@�֑��ɂȂ邪�A�ŋ߃C���h�ł����J���ꂽ�I���o�[�E�X�g�[���ḗu�A���L�T���_�[�v�i���{�ł͂Q���T��������J�̂悤���j�B���̉f�悪��N�A�p�[���X�B�[�i�q���k�j�̊Ԃŕ��c�����������Ƃ��������B�p�[���X�B�[�͌��X�C�����ɏZ��ł������A�C�X���[�����̐Z���ɂ��C���h�܂œ����Ă����l�X���B�p�[���X�B�[�̑����̓}�n�[���[�V���g���B�̃����o�C�[�ɏZ��ł���B�Q�O�O�P�N�̍��������ł́A�C���h�ɂ͂U���X�U�O�P�l�̃p�[���X�B�[���Z��ł���Ƃ���Ă���A�l���I�ɂ̓}�C�m���e�B�[�Ȃ�����A�C���h�̌o�ϊE�ɑ���ȉe���͂������Ă��邱�ƂŒm���Ă���B�A���L�T���_�[�剤�͉��B�ł͉p�Y�I���݂ł��邪�A���̓p�[���X�B�[�̊Ԃł͈����ɓ��������݂��Ƃ����B�Ȃ��Ȃ�A���L�T���_�[�剤�͔q���k�̑�s�E���s�������炾�B���傤�lj��ĂƃC�X���[�����E�ɂ�����I�T�}�E�r���E���f�B���̕]���̈Ⴂ�Ɏ��Ă��邩������Ȃ��B�ŁA�������ɂȂ������Ƃ����ƁA�u�A���L�T���_�[�v�̉f�掩�̂ł͂Ȃ��A���̃��S�ł������B�����A�u�A���L�T���_�[�v�̃��S�ɂ͉H�����ۂ����}�[�N���g�p����Ă����̂����A���ꂪ�p�[���X�B�[�̃V���{���ɍ������Ă���A���ʉ�Łu�A���L�T���_�[�v�������ݕĂ̔q���k�������ᔻ�̐����グ�A���ꂪ�����o�C�[�܂Ŕ�щ����Ƃ����킯���B�����A���u�A���L�T���_�[�v�̉f��̃E�F�u�T�C�g�����Ă݂���A���S���ύX����Ă���A�H�����ۂ����}�[�N���폜����Ă����B�q���k�����̐����ꉞ�I���o�[�E�X�g�[���ē܂œ͂����Ƃ������Ƃ��낤���B
| �� |
|
�� |
|
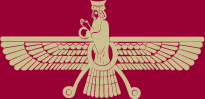 |
|
| �� |
�p�[���X�B�[�̃V���{�� |
�� |
�@�@���I�V���{�������镶�����C�͑��ɂ������Ⴊ���邾�낤�B�L���Ȃ̂́A�ԏ\���̃}�[�N���C�X���[�����ł͐Ԃ��\���˂ł͂Ȃ��A�Ԃ����̃}�[�N�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��B���̗��ɂ͂������A�\���˂ɑ���C�X���[�����k�̔������֗^���Ă���B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�ԐV���}�[�N |
�� |
�@�q���h�D�[���̐��Ȃ�V���{���ł���u�I�[���v���A�I�E���^�����̉e���œ��{�ł̓^�u�[�̂悤�Ȉ�������悤�ɂȂ��Ă��܂����B�挎�A�uHari
Om�v�Ƃ����C���h�f��̏�f��ɏo�Ȃ������A�M��́u�n���E�I�[���v�ł͂Ȃ��u�n���E�I���v�ɂȂ��Ă��܂��Ă����B�����A�C���h�f��ɂ͕K���ƌ����Ă����قǖ`���ɐ_�l�ւ̗�q�V�[�����f����Ă���A�܂��f�撆�ɂ��_�l�ւ̎^���̂��̂��V�[���Ȃǂ��悭����A�u�I�[���v��ے肵����A�C���h�f��̓��{��f���̂��ے肳��Ă��܂����ꂪ����B�u�I�[���v������Ȉ�����������Ȃ�A�u�I�[���v�Ɠ����ꌹ�ƍl������A�L���X�g���́u�A�[�����v�͂Ȃ��������ԂȂ̂��A����ԑ���Ђ�����Ԃ������Ȃ�S���ł���B
�@�V���{���͏ے��Ȃ��������āA�e����A�e�n��A�e�@���̃j�[�Y�ɏ]���Ă��낢��ȈӖ���t���������Ă����B�����A���̕��A��U�����Ӗ����ۂ��t��������Ă��܂��ƁA�������������͔̂��ɓ���B
�@�Q�O�O�S�N���̃{���E�b�h�͑�\�Z������`�f�悪�ڔ������������B���V���E�`���[�v���[�ḗuVeer-Zaara�v�i�\�Z�R�����s�[�j�A�A�V���g�[�V���E�S�[���[���J���ḗuSwades�v�i�\�Z�R�����s�[�j�A�A�j���E�V�����}�[�ḗuAb
Tumhare Hawale Watan Sathiyo�v�i�\�Z�����\�j�Ȃǂł���B�����A�o�u�q�v�����[�Ŋӏ܂����uKisna�v�i�\�Z�Q���T�疜���s�[�j���A��������\�Z�̈�����`�f��ł���A��N���Ɍ��J���\�肳��Ă������̂̓x�X��������A�{��������ƈ�ʌ��J�ƂȂ����B
�@�uKisna�v�Ƃ́A�q���h�D�[���̐_�l�̂P�l�A�N���V���i���a�����`�ŁA��l���̖��O�ɂȂ��Ă���B�ḗuTaal�v�i1999�N�j��uYaadein�v�i2001�N�j�̃X�o�[�V���E�K�C�[�B���y�͂`�q���w�}�[���ƃC�X�}�C���E�_���o�[���Ƃ������R���r�B�L���X�g�́A���B���F�[�N�E�I�[�x���[�C�A�A���g�j�A�E�o�[�i�[�g�i�p���l���D�A�V�l�j�A�C�[�V���[�E�V�������@�[�j�[�i�V�l�j�A�}�C�P���E�}���j�[�i�p���l�j�D�j�A�L���������E�����O���V�F�i�p���l���D�j�A�A�����[�V���E�v���[�A�I�[���E�v���[�A���V���p�[���E�V�����}�[�A���W���g�E�J�v�[���A�X�V���~�^�[�E�Z�[���i���ʏo���j�A���V�^�[�E�o�b�g�i���ʏo���j�ȂǁB
�@�Ȃ��Ȃ��f���炵���f��Ȃ̂ŁA���ꂩ�猩�悤�Ǝv���Ă���l�́A�ȉ��̂��炷����ǂ܂Ȃ����������Ǝv���B���I�������ɓǂ�ŗ�����[�߂Ă��炢�����B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
���B���F�[�N�E�I�[�x���[�C�ƃA���g�j�A�E�o�[�i�[�g |
�� |
| Kisna |
�@���͂P�X�R�T�N�B�q�}�[�����̉��n�A���Ȃ�o�[�M�[���e�B�[�͂ƃA���N�i���_�[�͂���������n�ɂ���f�[�I�v�����[�O�ɁA�L�X�i�[�Ƃ������̔n�g���̑��q�������B���N�L�X�i�͉p���l�s�����s�[�^�[�E�o�P�b�g�i�}�C�P���E�}���j�[�j�̖��A�L���T�����ƒ����ǂ��A�����ꏏ�ɗV��ł����B�L�X�i�[�ɗ��S������Ă����A���̉��y�Ƃ̖����N�V���~�[�́A�L���T�����Ɏ��i��R�₵�Ă����B�������A�L���T�����̓s�[�^�[�ɂ��A����̂��߂ɉp���ɋA����Ă��܂��B
�@�P�Q�N��̂P�X�S�V�N�A�w�Z�𑲋Ƃ����L���T�����i�A���g�j�A�E�o�[�i�[�g�j�͋x�ɂ�������Đ��܂�̋��̃f�[�I�v�����[�O�܂Ŗ߂��ė���B���͐̂Ə������ς���Ă��炸�A�L�X�i�[�i���B���F�[�N�E�I�[�x���[�C�j�ƍĉ����ԁB���N�V���~�[�i�C�[�V���[�E�V�������@�[�j�[�j���A�L���T�������A���ė������Ƃɂ��Ăю��i�S��R�₷�悤�ɂȂ�B�����A���N�V���~�[�̐S���@�������e�́A�L�X�i�[�̗��e�̉��k���܂Ƃ߁A�Q�l�̍����s��ꂽ�B�S�Ă͐̂̂܂܂Ɍ��������A���ǂ͑傫���ς���Ă����B���N�R���ɃC���h���ɏA�C�����}�E���g�o�b�e�����́A�}�n�[�g�}�[�E�K�[���f�B�[��W�����[�n�����[���E�l���[�Ƌ��c���A�W���P�S�`�P�T���ɃC���h�ƃp�[�L�X�^�[�����Ɨ������邱�Ƃ�F�߂��B���̃j���[�X�̓f�[�I�v�����[�O�̑��l���������삳�������A�����ɁA�c�s�ȍs�����s�[�^�[�ɑ���ς���ς��������݂𐰂炷���߂̋N���܂Ƃ��Ȃ����B�L�X�i�[�̏f���ł���A���œ�����J���Ă����o�C���[�E�X�B���i�A�����[�V���E�v���[�j��A�L�X�i�[�̌Z�V�����J���E�X�B���i���V���p�[���E�V�����}�[�j�́A�s�[�^�[�̓@��ɖ�P�������A�s�[�^�[���E�Q�����B�s�[�^�[�̍ȃW�F�j�t�@�[�i�L���������E�����O���V�F�j�ƃL���T�����͕ʁX�ɓ����o�����B�L�X�i�[�����R�L���T�����������A�ꏏ�ɉB���B�L�X�i�[�̕�́A�ނɑ��A�L���T�������f���[�܂ő���͂���悤���߂���Ɠ����ɁA�u�}�n�[�o�[���^�v�����������ɏo���āA�K�v������ΌZ�V�����J���Ƃ��키���Ƃ������Ȃ��悤�������B
�@�L�X�i�[�ƃL���T�����̓f�[�I�v�����[�O��E�o���A�V���v���[�ɏZ�ޗF�l�̉Ƃɐ����ԑ؍݂���B�����Ń��N�}�j�[�i���V�^�[�E�o�b�g�j��Ɏ�������}�����B�L�X�i�[�ƃL���T������ǂ��҂͂R�҂����B��҂̓L�X�i�[�̌Z�V�����J���E�X�B���Əf���o�C���[�E�X�B���B�ނ�͍s�����̉Ƒ��F�E�����f���Ă����B��҂̓��O���[�W���q�i���W���g�E�J�v�[���j�B���O���[�W���q�̓s�[�^�[�ƌ𗬂��������j�ŁA�L���T�����ƌ������悤�Ƃ��Ă����B������҂̓L�X�i�[�̍���҃��N�V���~�[�B�L�X�i�[�ƃL���T�������ꏏ�ɂ��Ȃ��Ȃ������Ƃɉ䖝�Ȃ�Ȃ����N�V���~�[�́A���Ɏ���L�X�i�[��ǂ�������B
�@�L�X�i�[�ƃL���T�����̓n���h���[���w�ɓ�������B�L�X�i�[���f���[�s���̗�Ԃ̐ؕ����ɍs���Ă���ԁA�L���T�����͕�W�F�j�t�@�[�ƍĉ��B�����A�W�F�j�t�@�[�̓��O���[�W���q�ƈꏏ�������B���O���[�W���q�̓L���T������A��čs���Ă��܂��B�����A�L�X�i�[�̓��O���[�W���q��ǂ������A�Q�l�����߂��B�R�l�́A���傤�NJO�V�ɗ��Ă����t�@�C�U�[�o�[�h�̉��܃i�C�i�[�E�x�[�K���i�X�V���~�^�[�E�Z�[���j��A���y�ƃW�����}���E�L�X�e�B�[�i�I�[���E�v���[�j��̏����ɂ�胉�O���[�W���q���瓦��ăf���[���������A�r���ŃV�����J���E�X�B����o�C���[�E�X�B���Ɍ������Ă��܂��B�W�����}����W�F�j�t�@�[�Ƃ͂��ꂽ�L�X�i�[��́A�W�����O���̒��ɓ������ށB����ɐg����߂��Q�l�̂Ƃ���ցA���x�̓��N�V���~�[������ė��āA�u����҂ł��鎄���̂ĂĔ��l�̏��Ɠ�����Ȃ�Ăǂ���������H�v�Ɠ{���I�ɂ��邪�A�L�X�i�[�́u�I���̓L���T�������f���[�܂ő���͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����܂ł͒N�̌������Ƃ������Ȃ��v�Ɠ�����B���N�V���~�[�͓{���ċ����čs���Ă��܂��B
�@�L�X�i�[�ƃL���T�����͍ĂуV�����J����Ɍ������Ă��܂��B�����A�L�X�i�[�̓L���T�������E�Q���悤�Ƃ����o�C���[�E�X�B�����E���A�Z�V�����J���ɂ��a�肩����B�V�����J�����L�X�i�[�̋C�����𗝉����A�Q�l�ɓ����J����B�L�X�i�[�ƃL���T�����̓f���[�ߍx�̊X�K�[�Y�B���[�o�[�h�ɓ������邪�A�����ł̓q���h�D�[�ƃ��X�����̎E���������s���Ă����B���������O���[�W���q�������ɗ��Ă���A�L���T�����͕߂����Ă��܂����A�L�X�i�[�ɂ���ď����o����A���O���[�W���q�͖��c�ȍŊ��𐋂���B�L���T�����͖����f���[�܂ő���͂�����B
�@�L���T�����̓L�X�i�[�ɑ��A�ꏏ�ɉp���֗���悤�ɗ��ނ��A�L�X�i�[�͂�������B�u�N���f���[�܂ő���͂��邱�Ƃ̓I���̒j�Ƃ��ẴJ�����i�s���`���j�������B���ꂪ�����������A�I���̓��N�V���~�[�ƌ������āA�_�����i�@���`���j�𐋍s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�������ăL�X�i�[�̓f�[�I�v�����[�O�ɖ߂��ă��N�V���~�[�ƌ��������̂������B |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
�@��K�͂ȗ��������j�f��ŁA�����Ɨ܂�U���V�[���〈��������������A�S�̓I�ɗD�ꂽ�f��ł������B�������Ȃ���A�X�g�[���[�̂Ȃ��肪�s���Ăȕ������U�����ꂽ���߁A�c�O�Ȃ��犮���x�͂���قǍ����Ȃ��Ɗ������B�ꌾ�Ō����Ă��܂��Ȃ�A�ŋ߂̃X�o�[�V���E�K�C�[�ē̍�i�uTaal�v�̂����Ƃ���ƁA�uYaadein�v�̈����Ƃ�������킹�āA���j�f��I�ȏd���������������悤�ȉf��ł���B
�@�f��͓ˑR�A�P���Q�U���̋��a���L�O���p���[�h����n�܂�B�ǂ���猻��̂悤���B��p�����Ɨ�����ɂ����f�悾�Ǝv���ĉf��قɗ��Ă����ϋq�̓r�b�N������B�P�X�T�O�N�P���Q�U���ɃC���h���@���{�s����A������L�O���邽�߂ɖ��N�P���Q�U���ɂ͎�s�f���[�Ńp���[�h���s����B���̉f�悪���J���ꂽ�̂��{���P���Q�P���A���a���L�O���̂T���O���B���傤�ǂ��̎����ɂ��̉f�悪���J���ꂽ�Ӗ����悭���������B�f��ɘb��߂����B��o�Ƃ��ăC���h��K��Ă����L���T�����́A�E�b�^���[���`�����B�f�[�I�v�����[�O�֍s�������ƌ����o���A���͂̐l�X�����f������B�u�Ȃ�����ȂƂ���ɁH�v�f�[�I�v�����[�O�ɒ������L���T�����́A�����������̐��܂�̋��ł��邱�Ƃ𖾂����A�܂��A�����������^�̃C���h��m���Ă���ƌ����āA�L�X�i�[�̘b���n�߂�B���ꂪ��̂��炷���ŏ������X�g�[���[�ł���B
�@�f�[�I�v�����[�O�B�n�}�Œ��ׂĂ݂�����݂̒��������B���V�P�[�V������K���K�[�i�K���W�X�j�͂�k���āA����Ƀq�}�[�����̉��n�֍s�����Ƃ���ɂ��钬�ŁA��L�̒ʂ�A���傤�ǃo�[�M�[���e�B�[�͂ƃA���N�i���_�[�͂���������n�_�ɂ���B����A�K���K�[�͂��K���K�[�͂ƌĂ�n�߂�n�_�Ɉʒu���钬�ł���B�C���h�ł́A�͂̍����_�͐��Ȃ�n�ƍl�����Ă���A�͂Ɖ͂̍��킳��Ƃ���ɕK����������̎��@��n�����݂���B��ԗL���Ȃ̂́A�K���K�[�͂ƃ����i�[�͂̍����_�ł���C���[�n�[�o�[�h�ł���B�C���[�n�[�o�[�h�͌Ö����e�B�[���g�E���[�W�Ƃ��v�����[�O�ƌ����B�f�[�I�v�����[�O�̑��A�L�X�i�[�ƃL���T�����������ԑ؍݂����V���v���[��n���h���[���Ȃǂ����݂̒��ł���A���Ɍ������̂���f��ł������B���P�n�́A�E�b�^���[���`�����B�̃f�[�I�v�����[�O�A�V���v���[�A���V�P�[�V���A�n���h���[���A���[�j�[�P�[�g�A���N�e�[�V��������A�f���[�Ȃǂł���B�قƂ�ǃE�b�^���[���`�����B�ŎB�e����Ă��邽�߁A�u�R�̃C���h�v�̔������������ɃX�N���[���ɉf���o����Ă��Ă悩�����B
�@�l�ޔ��@�ƂƂ��Ă��L���ȃX�o�[�V���E�K�C�[�ēB�K�C�[�ē͂���܂ŁA�W���b�L�[�E�V�����t�A�}�[�h�D���[�E�f�B�[�N�V�g�A�}�j�[�V���[�E�R�[�C���[���[�A�}�q�}�[�E�`���E�h���[�ȂǁA�����̔o�D�@���ăX�^�[�Ɉ�ďグ���B����̔ނ̑唭���́A�C�[�V���[�E�V�������@�[�j�[�ł���B�C�[�V���[�͗L���ȕ��x�ƃ_�N�V���[�E�Z�[�g�̖��ŁA���ɍ��ۓI�ȕ��x�ƂƂ��Ė��̒m�ꂽ���݂��������A�uKisna�v�ł̑唲�F�ɂ��A���̖��̓C���h�̋��X�ɂ܂Œm��n�����ƌ����Ă悢�B�ޏ��̗x��͕���Ȃ����݂̃{���E�b�h���D�̒��Ń_���g�c�̂m���D�P�ł���B���ɕR�ɂԂ牺�����č��T��g�肷��R���e���|�����[�E�_���X���̗x��͔ޏ��ɂ����ł��Ȃ��|�����낤�B�ޏ��̗x������邽�߂����ł��A���̉f��͌��鉿�l������B��͑������Ȃ����A�u�{���E�b�h���D�͗x��ĂȂ�ځv�Ƃ����펯�����߂Ďv���o�����Ă���邾���̃A�s�[����������҂̐V�l�ł���B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�C�[�V���[�E�V�������@�[�j�[ |
�� |
�@�p���l���D�̃A���g�j�A�E�o�[�i�[�g���f���炵�������B�͂�Ƃ������Z�����Ă��āA�L���T�����̃L�����N�^�[�Ƀs�b�^���������B�����ԃq���f�B�[����������悤�ŁA�O���l�L���X�g�̒��ł͈�ԗ����ȃq���f�B�[�������ׂ��Ă����B���܂ŃC���h�f��ɏo���������l�o�D�̒��ň�Ԃ̉��Z�Ƃ܂ŏ^���Ă��������낤�B�Ȃ����C�[�V���[�ƃA���g�j�A�͔��̘I�o������s���Ă��āA�C���h�f��ɂ��Ă͂��Ȃ肫��ǂ��Z�~�k�[�h�E�V�[�������҂Ƃ��������B
�@��l���L�X�i�[���̃��B���F�[�N�E�I�[�x���[�C����甍�������Z�����Ă��Ă悩�����B�����ɕE�Ƃ������e�͑������������������B���ꂩ��܂��܂��������邾�낤�B
�@�uKisna�v�́A�P���Q�P���ɔ]�쌌�ŋ}�������A�����[�V���E�v���[�̈��̂P�{�ƂȂ��Ă��܂����B�f�撆�̔ނ̖͘e���ɉ߂��Ȃ��������A�ނ��o�ꂵ���Ƃ��ɂ͋q�Ȃ��甏�肪�オ�����B�{���E�b�h�f��E�œƓ��̒n�ʂ�z�����ނւ̃I�}�[�W���̔���ł������B
�@�uKisna�v�̓��ɑO���́A�X�g�[���[�̍��ԂɃ~���[�W�J��������Ƃ��������A�~���[�W�J���̍��ԂɃX�g�[���[������悤�ȁA���y�Ɨx��Ɉ�ꂽ�f�悾�����B���̓_�ŁuTaal�v���v���N���������B�������A�ҏW������Ȃ̂��A�V�[���ƃV�[���̐����������܂�Ȃ��A���̓_�Ŏx���ŗ�f��ƍ��]���ꂽ�uYaadein�v���v���N���������B�X�g�[���[�����R�ɗ���Ă����Ȃ��āA�b���}�ɔ��A���ʂȃV�[������������A�����̂Ȃ��o���������X�ɋN��������ƁA�����C���C��������ꂽ�B�܂��A�L�X�i�[�炪�g���Ă������̃f�U�C�������m�I������悤�Ɏv�����B�{���ɂ��������`�̌����g���Ă����̂Ȃ當��͂Ȃ��̂����A���Ȃ��Ƃ��}�n�[���[�W���[�̋{�a�Ȃǂł悭���镐�픎���قł́A���̉f��ɏo�Ă���悤�Ȍ`��̌����������Ƃ͂Ȃ��B�L�X�i�[�̋����Ȃ܂ł̖��G�̋����ɂ�������Ƌ����߂��Ă��܂����B��p�����Ɨ����ɔ��������q���h�D�[�ƃ��X�����̊Ԃł̐��S�ȎE���������A���ɐ[���`�ʂ���Ă����킯�ł͂Ȃ������B
�@���y�͂`�q���w�}�[���ƃC�X�}�C���E�_���o�[���B�uKisna�v�̉��y�̃e�[�}�\���O�́A�t�[�E�s���ḗu�w�u���E�A���h�E�A�[�X�@�V�n�p�Y�v�i2003�N�j�̂��߂Ƀ��w�}�[�����g����Ȃ����Ȃ̏Ă������ł���B�Q�l�Ƃ��C���h�f��̉��y�E���\���鉹�y�ē����A�uKisna�v�̑}���̂Ɍ���ƌ�������̂͏��Ȃ������Ǝv�����B
�@�ׂ��������̑e�T�������Ă��������̂Ȃ��f��ł͂��邪�A�������������ɖڂ��ނ��āA���i�̔�������C�[�V���[�E�V�������@�[�j�[�̑f���炵���x����y���ނ��Ƃ��ł���Ȃ�A�uKisna�v�ӏ܂͍��N���̃t�B���}�[�i���h�i�C���h�f��ӏ܂ɂ��S�ɕ����N����G�N�X�^�V�[�F�l�̑���j��̌������Ă���邾�낤�B
| �� |
�P���Q�Q���i�y�j�@��e�j�X�E�̐V���A�T�[�j���[�E�~���U�[ |
�� |
�@�C���h�͑卑�ł���Ȃ���A�Ȃ����X�|�[�c���ア���ł���B����͋��N�̉Ăɍs��ꂽ�A�e�l�ܗւł��ؖ����ꂽ�i��_���P���̂݁j�B�܂��A�T�b�J�[�v�t�̗\�I�œ��{��\�ƃC���h��\���������������Ƃɂ��A���{�l�̊Ԃł��u�C���h�͎ア�v�Ƃ����C���[�W���蒅���Ă��܂����B�C���h�̍��Z�Ƃ�������N���P�b�g�ɂ��Ă��A����قNj����킯�ł͂Ȃ��B�S���t�E�ł̓��B�W���C�E�X�B���Ƃ����C���h�n�v���S���t�@�[���劈�Ă��邪�A�ނɂ��Ă��C���h�n�ږ��Ƃ��������ŁA���Ђ̓t�B�W�[�ł���B�C���h�̃z�b�P�[�����G�̋������ւ�����������������A���͐̂̕���ƂȂ��Ă��܂��Ă���B�Ȃ��C���h�l�X�|�[�c�I��͍��ە���Ŏア�̂��B�l�͂��̗��R���A�S�Ă�_�l�Ɖ^���ɔC�������w�͂���߂Ă��܂��C���h�l���L�̓N�w�I�v�l��A�g�̂������Ƃ�ڂ������Ƃƍl����J�[�X�g�ςɋ��߂����Ǝv���Ă��邪�A��͂�X�|�[�c�́A���Y��`���������A������x���⍑�������퐶���ȊO�̂��Ƃɖڂ��������邭�炢�T���ɂȂ�K�v�������ɁA���{���ϋɓI�Ɍ㉟�����Ȃ��ƐU������Ȃ����̂ł���Ƃ����_���傫���B�������A�C���h�o�ς̐����ɏ]���āA����ɃX�|�[�c�̕���Ŋ���C���h�l�I�肪���X�Ɍ���Ă��Ă���̂�������B
�@�C���h�̃e�j�X�E�̃X�[�p�[�X�^�[�ƌ����A�}�w�[�V���E�u�[�p�e�B�ƃ��[���_�[�E�p�G�X�ł���B�Q�l�̓S�[���f���E�R���r�Ƃ��Ēm���A�A�e�l�ܗւł��j�q�_�u���X�ɏo�ꂵ�����A�c�O�Ȃ���S�ʂŏI���A���_���ɂ��ƈ���肪�͂��Ȃ������B�����A���݃I�[�X�g�����A�̃����{�����ŊJ�Ò��̑S���I�[�v���ɂ����āA�V���ȃC���h�l�e�j�X�I��̃X�^�[���a�������B�T�[�j���[�E�~���U�[�ł���B�T�[�j���[�E�~���U�[�̓}�n�[���[�V���g���B�����o�C�[�o�g�A�A�[���h���E�v���f�[�V���B�n�C�_���[�o�[�h�ݏZ�̂P�W�B���O���番����悤�ɁA���X�����ł���B�T�[�j���[�͂Q�O�O�R�N�U���ɍs��ꂽ�W���j�A�E�E�B���u���h���̏��q�_�u���X�ŗD�������C���h�e�j�X�E�̃z�[�v�������B�T�[�j���[�͍���A�u�P���ł���v�Ƃ����C�����őS���I�[�v���ɏo�ꂵ���Ƃ���A���q�V���O���X�Ō����R���܂Ői�o����Ƃ��������𐬂��������B�C���h�l���q�e�j�X�I��ŁA�O�����h�X�����i�S�p�A�S���A�S���A�S�ăI�[�v���j�̃V���O���X�łR���܂Ői�o�����̂̓T�[�j���[�����Ƃ̂��ƁB�������Ȃ��Ȃ����킢�炵��������Ă��邽�߁A��C�ɃC���h�l�̊ԂŐl�C�ɉ��t�����Ƃ����킯���B���X�����̍Փ��A�C�[�h�D�b�E�Y�n�[�i�P���Q�P���j�ɍs��ꂽ�R���̂Ƃ��ɂ́A�����N���P�b�g�̎����ɂ��������������Ȃ��C���h�l�������s�u�̑O�ɌQ�������B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�T�[�j���[�E�~���U�[ |
�� |
�@�R���܂Ői�o�����T�[�j���[��҂��\���Ă����̂́A�����E�`�����s�I���̃Z���[�i�E�E�B���A���Y�i�č��j�B���E�I�ɗL���ȍ��r�e�j�X�v���C���[�ł���B�T�[�j���[�̐��E�����N�͌��݂P�U�R�ʂł������A�Z���[�i�͂V�ʁB�܂�ŏ����ڂ̂Ȃ��킢�������B�����A�T�[�j���[�͌��������B��P�Z�b�g�͂P�|�U�Ŋ��s�ɋ߂��������̂́A��Q�Z�b�g�͂S�|�U�Ƃ��Ȃ苣���������������B������A�Z���[�i�͂P�W�̐V���ɑ��A�u���Ȃ��͏������������B�撣���Ęr���āv�ƌ��サ���Ƃ����B
�@�T�[�j���[�͂P�X�W�U�N�P�P���P�T���A�����o�C�[���܂�B���e�̓X�|�[�c�E�W���[�i���X�g�ŁA���X�X�|�[�c�ɊW�̂���ƌn�������悤���B�U���烍�[���e�j�X�i�Ő��R�[�g�Ńv���C����e�j�X�j���n�߁A�}�w�[�V���E�u�[�p�e�B�̕��b�j�u�[�p�e�B�̎�قǂ�����B���̌�A�n�C�_���[�o�[�h�̓�U�[���E�N���u�ŃR�[�g�e�j�X���n�߁A�X�B�J���_���[�o�[�h�ɂ���V�l�b�g�E�e�j�X�E�A�J�f�~�[��A�č��ɂ���G�[�X�E�e�j�X�E�A�J�f�~�[�ʼnp�ˋ�������B�P�X�X�X�N���獑�ێ����ɏo�ꂷ��悤�ɂȂ�A�Q�O�O�R�N�ɂ̓��V�A�̃A���T�E�N���C�o�m���ƃR���r��g��ŃW���j�A�E�E�B���u���h���ŗD�������B�C���h�l���q�e�j�X�I�肪�O�����h�X�����ŗD�������̂́A�P�X�T�Q�N�̃��^�[�E�_�[�o���ȗ��T�P�N�U��̂��Ƃ������B�����č���A���q�V���O���X�ŏ��̂R���i�o�ƂȂ����킯���B�s�u�Ŕޏ��̃C���^�r���[���������A�ޏ��̉p��͏㗬�K���̂���ł������B�e�j�X�Ȃ�Č��X�ɐl�̓��y�ł���A�����̎q���Ƀe�j�X�̉p�ˋ�����{�����Ƃ��ł���̂́A�C���h�ł͂܂��܂��T���ȉƒ�Ɍ����Ă���B��͂�A�܂��͕x�T�w�̃C���h�l�ƒ낪�q���ɉp�ˋ�����{���Ȃ���A���ە���Ŋ���ł���X�|�[�c�I�肪�C���h���琶�܂��\���͒Ⴂ�Ƃ������Ƃ�������ꂽ�B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�}�w�[�V���E�u�[�p�e�B�i���j��
�T�[�j���[�E�~���U�[�i�E�j
�Ȃ����T�[�j���[�̃V���c�ɂ́A
�����Łu�āv�Ə����Ă��� |
�� |
�@�Ƃ肠�����A�T�[�j���[�����͂��ꂩ����C���h�ő����������B�T�[�j���[�ɂ́A�D���̃n�C�_���[�o�[�f�B�[�E�r�����[�j�[����t�H�ׂĉh�{������Ă�����āA����ɋC��t���Ċ撣���Ă��炢�����B

�@�P���Q�R���t���̃T���f�[�E�^�C���Y�E�I�u�E�C���f�B�A���ɂ́A���������T�[�j���[�̓��W���g�܂�Ă����B�܂��ڗ������̂́A�u�V�����|���m���D�P�A�T�[�j���[�m���D�Q�v�Ƃ����L���B����̑S���I�[�v���ň�Ԑl�C�̓��V�A�̃}���A�E�V�����|�������A����Ɏ����̂��C���h�̃T�[�j���[�E�~���U�[�ł���Ƃ������e�������B���������ɂ��Ă��邩�Ƃ����ƁA�S���I�[�v���̃E�F�u�T�C�g�̃v���t�B�[���̃A�N�Z�X���B���܂œ��E�F�u�T�C�g�͂P�P�O���q�b�g���L�^�������A���̏����Z�N�V�����ŁA�T�[�j���[�E�~���U�[�̃y�[�W�ւ̃A�N�Z�X�����A�V�����|���Ɏ����ő��ʂ������Ƃ����B�܂��S���I�[�v���͏I����Ă��炸�A���̎��_�ł���ȉ���Ȃ����Ƃ��L���ɂ���̂͂ǂ����Ǝv�����A���E�̐l���̑啔�����߂�C���h�l�������ɉ����ЂƂ̂��ƂɊS����������ǂ��������ƂɂȂ�̂���\���Ă���悤�ŁA�����|���C������B
�@�����ɂ́A�T�[�j���[�E�~���U�[���W���b�X�B�[�Ɣ�r����L�����������B�W���b�X�B�[�Ƃ́A�\�j�[�s�u�ŕ��f����Ă���uJassi Jaisi Koi
Nahin�i�W���b�X�B�[�̂悤�ȏ��̎q�͂ǂ��ɂ����Ȃ��j�v�Ƃ����s�u�h���}�̎�l���ŁA�Q�O�O�R�N�Ɏn�܂��Ă���Ƃ������̂́A�C���h�����Ŕ����I�Ȑl�C���ւ��Ă���B�W���b�X�B�[�̉��������Ƃ����ƁA���Ă��Ƃ͂Ȃ��A�ޏ������Y�K���̕��ʂ̏��̎q�ł��邱�Ƃ��B�W���b�X�B�[�́A�_�T���ዾ�������A�����������ŁA�F�C�̂Ȃ��T�����[���E�J�~�[�Y���������Ă���Ƃ����A���܂ŃC���h�f���s�u�h���}�ɂȂ����������I�L�����N�^�[�������B�����A�c�͂������肵�����̎q�ŁA���ɋΕׂ����������B�t�@�b�V������Ђōŏ��͔鏑�Ƃ��ē������̂́A�����O�̍˔\�����Ăǂ�ǂ�o������B�W���b�X�B�[�������郂�[�i�[�E�X�B���́A�S�������̏��D���������̂́A���̂s�u�h���}�̑听���ɂ��A����C���h�Ŕޏ��̊��m��Ȃ��l�͂��Ȃ��قǂɂȂ��Ă���B�W���b�X�B�[�͊��Ɍ���̃C���h�̒��Y�K���̏����̗��z���ƂȂ��Ă���Ɠ����ɁA���N��y�̉��l�Ƃ��Ă̒n�ʂɈ��Z���Ă����f��E��nj�����قǁA�s�u�h���}�Y�Ƃ��}���������邫�������Ƃ��Ȃ����B���̃W���b�X�B�[�ƃT�[�j���[����r����Ă����B��ł̓T�[�j���[�̂��Ƃ��㗬�K�����Ə��������A�ޏ����g�̕قł́u�n�C�_���[�o�[�h�̓T�^�I�Ȓ��Y�K�����X�����̉ƒ�ɐ��܂ꂽ�v�炵���̂ŁA�����������Ƃɂ��Ă������B�ޏ��̕��i�̊i�D�́A��͂�ዾ�������A�V���v���ȕ��𒅂Ă���A������ӂ̏��̎q�ƕς��Ȃ��B�����A��x�e�j�X�R�[�g�ɗ��ĂA�܂�Ŗ��@�ŕϐg�������̂悤�ɁA�`���[�~���O�ȃe�j�X�v���C���[�ƂȂ�B���̗l�q�����āA�L�҂̓T�[�j���[���u�������E�̃W���b�X�B�[�v�Ə^�����Ƃ����킯���B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�W���b�X�B�[ |
�� |
�@�T�[�j���[�̃C���^�r���[�ɂ��ƁA�ǂ������ɉf��E��f���E������I�t�@�[���������悤�����A�ޏ��͒f�����炵���B���̕ӂ͕����킫�܂��Ă���悤�ŁA�D�������Ă�B�u���X�����̏����ł���Ȃ���A���̘I�o�������e�j�X�E�F�A�𒅂邱�Ƃɒ�R�͂Ȃ����v�Ƃ����C���h���ۂ�����ɂ́A�u�������̏@���̓X�|�[�c�����邱�Ƃ��ւ��Ă��Ȃ���B�����C���S�T�x�̒��A�������Y�{���Ńe�j�X������Ƃ����Ȃ�A���͉������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���͍D���D��ő��������Ă���킯�ł͂Ȃ���B�e�j�X�����ɗ��Ă���́v�ƂȂ��Ȃ��܂��Ƃ��ȓ����������Ă���B�ȑO�͐��E�����N�g�b�v�P�O�O���肪�ڕW�������悤�����A�O�����h�X�����R���i�o�������Ƃɂ��A�ڕW�̓g�b�v�T�O����ɏ���C�����ꂽ�������B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�Ȃ����r�����[�h������
�T�[�j���[�E�~���U�[
���i�͍����ዾ�������Ă��� |
�� |
�@�����͂o�u�q�A�k�p���ŐV��q���f�B�[��f��uPage3�v�������B�ē̓}�h�D���E�o���_�[���J���B�uChandni Bar�v�i2001�N�j�ŗL���Ȋēł���B���y�̓T�~�[���E�^���_���B�L���X�g�́A�R���R�i�[�E�Z�[���V�����}�[�A�{�[�}���E�C�[���[�j�[�A�A�g�D���E�N���J���j�[�A�^�[���[�E�V�����}�[�A�r�N�����E�T���[�W���[�A�T���f�B���[�E�����h�D���A�W���C�E�J�����[�i�V�l�j�ȂǁB���Ȃ݂ɁuPage3�v�Ƃ́A���{�̐V���Ō����u�O�ʋL���v�̂��ƂŁA�S�V�b�v�Ȃǒ��S�̖ʂ������B���ɃC���h�ł̓p�[�e�B�[���W�ʂ̂��Ƃ������悤���B�^�C���Y�E�I�u�E�C���f�B�A���̐܍��łł���f���[�E�^�C���X�Ȃǂ�����ƁA��R�ʂ̓Z���u�E�p�[�e�B�[�̋L�����h��Ȏʐ^�Ƌ��ɖ����̂悤�ɍڂ��Ă���B���̑�R�ʂɍڂ邱�Ƃ��A�L���l�̃X�e�[�^�X�E�V���{�����Ƃ���Ă���B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
������R���R�i�[�E�Z�[���V�����}�[
�^�[���[�E�V�����}�[
�T���f�B���[�E�����h�D�� |
�� |
| Page3 |
�@�}�[�h���B�[�i�R���R�i�[�E�Z�[���V�����}�[�j�̓y�[�W�R�̋L�҂ŁA���Ӄ����o�C�[�̃Z���u�̃p�[�e�B�[�ɏo�Ȃ��Ď�ނ��Ă���A�Ќ��E�̒��Ŋ�̒m�ꂽ���݂ƂȂ��Ă����B�����A�}�[�h���B�[�͐^�ʖڂȋL�������������Ǝv���Ă���A�����̔��p�Ƃ̓W�����ǎ��@�̋L���Ȃǂ��ڂ��悤�Ƃ�����A�ҏW���̃f�B�[�p�N�E�X���[�i�{�[�}���E�C�[���[�j�[�j�ɑj�~����Ă��܂��Ă����B
�@�}�[�h���B�[�̓X�`�����[�f�X�̃p�[���i�T���f�B���[�E�����h�D���j�Ƌ��ɓ������Ă������A���R�o��������D�u�]�̏��̎q�K�[���g���[�i�^�[���[�E�V�����}�[�j���ꏏ�ɏZ�ނ悤�ɂȂ�B�}�[�h���B�[�́A�F�l�̐l�C�j�D���[�q�g�i�r�N�����E�T���[�W���[�j�ɗ���ŃK�[���g���[���f��ēɏЉ�Ă��炤�B�����A���̊ē͔ޏ��ɓ��̊W�𔗂������߁A�ޏ��͓����o���ė��Ă��܂��B�܂��A�K�[���g���[�̓��[�q�g�Ɨ����ɂȂ邪�A�D�P�����r�[���[�q�g����̂Ă�ꂽ���߁A���E����������B�K�[���g���[�͈ꖽ�����Ƃ߂����̂́A�f��ƊE�Ɍ��C�������Č̋��̃f���[�ɋA���Ă��܂��B���������āA�p�[������x���ƌ������ĕč������čs���Ă��܂��B�܂��A�}�[�h���B�[�́A���l�Ń��f���̗��̃A�r�W�[�g�i�W���C�E�J�����[�j���Q�C�̗F�l�Ɨ��ŕ��������Ă���Ƃ����ڌ����Ă��܂��A�ނƐ������B�}�[�h���B�[�͌ǓƂɂȂ��Ă��܂����B
�@�y�[�W�R�̎�ނɌ��C���������}�[�h���B�[�́A�X���[�ҏW���ɗ���Ŕƍߕ��Ɉٓ������Ă��炤�B�}�[�h���B�[�̓x�e�����L�҂̃��B�i�[���N�i�A�g�D���E�N���J���j�[�j�Ƌ��ɔƍ߂̎�ނ��s���B����Ƃ����B�i�[���N������ɂ��Ă���Ƃ��ɁA�����^���R�~���}�[�h���B�[�́A������x�@�ɓ`���Đl�g�������s���}�t�B�A�̉Ƒ�{���ɓ��s����B�����A���̃}�t�B�A�̑ߕ߂ɂ��A���N�ւ̐��I�s�҂��s���Ă�����x���������яオ���Ă��܂��B���̑�x���́A�}�[�h���B�[�̋߂�V���Ђ̃X�|���T�[�ł��������B�}�[�h���B�[�̓X�L�����_�����L���ɂ܂Ƃ߂邪�A�ォ��̈��͂ɂ��v�ɂ��ꂽ��ɉ��ق���Ă��܂��B
�@�Ƃɂ������ė܂𗬂��}�[�h���B�[�̂��ƂɃ��B�i�[���N������ė���B���B�i�[���N�̓}�[�h���B�[�ɁA�u�^�����L���ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����������ɂ͕��@������B�V�X�e���̒��ɂ��Ȃ���A�V�X�e����ς��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�ƃA�h�o�C�X����B�}�[�h���B�[�͕ʂ̐V���ЂɃy�[�W�R�̋L�҂Ƃ��ďA�E���A�ĂуZ���u�E�p�[�e�B�[�̐��E����ނ���悤�ɂȂ�B�}�[�h���B�[�͂����ŁA�f���[�ɋA�����͂��̃K�[���g���[�Əo��B�K�[���g���[�ׂ̗ɂ́A���Ĕޏ��ɐg�̊W�𔗂����ē������B�ޏ��̗l�q�������ԍC�����Ă��܂��Ă����B�K�[���g���[�͔ޏ��Ɍ����B�u�������邵���Ȃ������́B�v�p�[�e�B�[�ɂ́A���Ă̗��l�A�r�W�[�g�������B�ނ��o���̂��߂ɃQ�C�ɐg�̂����̂ł���A���̂��߂Ɍ��݂̓Z���u�̒��ԓ�����ʂ����Ă����B���������āA�}�[�h���B�[�́u��͂肱���͎��̂���ׂ��ꏊ����Ȃ��v�ƁA1�l�p�[�e�B�[������ɂ���B |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
�@�����o�C�[�̉₩�ȎЌ��E�̗��ɐ��ޑޔp�I�l�ԊW�Ɍ��Ă����j�[�N�ȍ�i�B�O�������Ă����Ƃ��́A�uLet's Enjoy�v�i2004�N�j�̂悤�ȁA�p�[�e�B�[�̒��ł̊e��l�Ԗ͗l��`������i���Ǝv���Ă������A�㔼�ɂȂ��ċ}�ɘb���V���A�X�ɂȂ�A���ɐ[�݂̂���f��ƂȂ��Ă����B�h���b�O����A�Z�b�N�X����A�Q�C����A���N�ւ̐��s�҂���ƁA�����Ă����e�[�}�͍ۂǂ��������A�C���h�̎���炻�������͂Ȃ��Ǝv�����B
�@�f��̖`���ł́A�č�����C���h�ɂP�T�N�U��ɋA���ė����C���h�l���Y�Ƃ��A�����o�C�[�Ő������邽�߂Ɂu�y�[�W�R�v�����p����V�[�����`�����B�܂��̓p�[�e�B�[����Â��A�e�E�̗L���l�����҂��A���̗l�q���V���̃y�[�W�R�Ɍf�ڂ����A�����͊ԈႢ�Ȃ��Ƃ����B�������烀���o�C�[�Ŗ�Ȗ�ȌJ��Ԃ����Z���u�E�p�[�e�B�[�̗l�q�ƁA�������ނ���}�[�h���B�[������̒��S�ɗ���B�₩�Ȃ�p�[�e�B�[�B�o�Ȃ���Z���u�����̊�Ԃ�͖����ς�炸�A��ӂɂ������|�������Ńp�[�e�B�[������̂��ނ�̒��ł͓�����O�ƂȂ��Ă����B�����͊ϋq���y�������ȃp�[�e�B�[�̗l�q�ɐS���点�邪�A����ɃZ���u�����̊Ԃɖ������鉘�ꂽ�l�ԊW���I�ƂȂ��Ă���B���ɂ��ꂪ�I���ɕ`�ʂ����̂́A��x���̍ȃA���W�����[�����E���A���̑������s���Ă���V�[���ł���B�l�X�̓A���W�����[�̎��𓉂ނ��߂ɂ���ė��邪�A�b�������Ă��邱�Ƃ́A�����ς�炸�S�V�b�v�A�r�W�l�X�A�����Ď��̃p�[�e�B�[�̂��Ƃ���ł���B����������}�[�h���B�[�́A�y�[�W�R�̋L�҂����߂�B
�@�����A����ɃV���b�N�Ȃ̂́A�}�[�h���B�[�����̐V���Ђ��N�r�ɂȂ�A�V�����V���ЂōĂуp�[�e�B�[�̎�ނ��n�߂��V�[���ł���B�}�[�h���B�[�͂����ŁA�����������ς����ă^�o�R�𐁂����K�[���g���[�̎p��ڂɂ���B�}�[�h���B�[���K�[���g���[�ɉ�����Ƃ��A�ޏ��̓p�[�e�B�[�ɓ���߂Ȃ��Ă܂����������C�ȏ��̎q�������B�ēɎ�U�߂ɂ��ꂻ���ɂȂ�����ɁA�D�P�����r�[�A�t�������Ă����l�C�j�D�Ɏ̂Ă��A���E�܂Ő}�����ޏ��́A���̊Ԃɂ��ēɐg���ăZ���u�̒��ԓ�������Ă����B�a�Љ�Ő����邽�߂ɂ́A����a�ނ����Ȃ��Ƃ������Ƃ�ɗ�ɕ`���Ă����B
�@�E�E�E�����A���̃v���b�g�́A�}�h�D���E�o���_�[���J���ē��g�Ɋւ��A������ۂ̎������v���N����������̂ł������B�Q�O�O�S�N�U���A�v���[�e�B�E�W���C���Ƃ����f�揗�D�u�]�̃��f�����A�o���_�[���J���ē����C�v�̍߂ō��i�����̂��B�v���[�e�B�́A�o���_�[���J���ē�������ނ̉f��̃q���C���ɂ���Ɩ������߁A�P�X�X�X�N�`�Q�O�O�S�N�ɓn���ĔނƓ��̊W���������B�������A���ɂȂ��Ă��o���_�[���J���ē��ޏ����q���C���ɂ��Ȃ����߁A�ޏ�������ȏ�̓��̊W��f�����Ƃ���A�����ɉ����|����ă��C�v���ꂽ�Ƃ̂��Ƃ������B�����炭�܂����������낤���A���_�͂Q�ɕ�����Ă���B���Ȃ킿�A���D�ɂȂ肽�����̎q�̎�݂ɕt������Ŏ�U�߂ɂ����o���_�[���J���ē������A�Ƃ����ӌ��ƁA�q���C���ɂȂ肽�������߂ɊēƓ��̊W�܂Ō��сA������������s�ׂɗ��p����v���[�e�B�E�W���C���������A�Ƃ����ӌ��ł���B�ǂ���ɂ���A�ē���A�������g�̃X�L�����_����z�N������v���b�g���f��ɐ��荞�ނƂ́A���̊ē����҂ł͂Ȃ��Ǝv���B
�@���̑��ɂ��uPage3�v�́A�C���h�̎Ќ��E�ƐV���̖��_�����낢��\���o���Ă����B�Ⴆ�A�y�[�W�R�́u�m���x�[���̐l�Ԃ̂��Ƃ������̂ł͂Ȃ��A��s�����Ƀ[��������������l�Ԃ̂��Ƃ��������߂ɂ���v�Ƃ����ҏW���̌��t�́A�ǂ̂悤�ȋL�����y�[�W�R�ɍڂ�̂���@���ɕ\���Ă����B�܂��A�ƍ߂Ɋւ���L���ł́A���Ɛl���ɂ�肢����ł��R���g���[�����ł��Ă��܂��l�����炩�ɂȂ��Ă����B�����A���_�͂��낢��ƒ��ꂽ���A���̉����͉f�撆�ɂ͉���������Ȃ������B�f��͑S�Ă̖�肪�������̂܂܁A�}�[�h���B�[���Z���u�E�p�[�e�B�[��Ќ��E�̐��E����i���ɑ�����Ƃ�\�������ďI�������B
�@�uAmu�v�i2005�N�j�Ɉ��������A�R���R�i�[�E�Z�[���V�����}�[�剉�삾�����B�uMr. and Mrs. Iyer�v�i2002�N�j�̐����ň�C�ɉ��Z�h���D�Ƃ��ĔF�m�x���グ���悤�����A�ޏ��̊O���͂͂����茾���ĕ��ʂ̏��̎q�ł���A���܂��z�����Ȃ��Ɖf��S�̂̃o�����X������Ă��܂��B���́uPage3�v�ł��A�ޏ��̗e�p�͑����}�C�i�X�ɓ����Ă����B�S�[�W���X�ȃZ���u�����̊Ԃ��e�N�e�N�ƕ������p�́A��Ⴂ�Ȉ�ۂ����B
�@�e�����������A�T���f�B���[�E�����h�D���̉��Z�������Ă����B�ޏ��́uSaathiya�v�i2002�N�j�Ń��[�j�[�E���J���W�[������q���C���̎o���������A�uWaisa
Bhi Hota Hai Part II�v�i2003�N�j�ł͕|�����x���̖��������Ă����B�ǂ�������Ɉ�ۓI�ȉ��Z�����Ă������A�uPage3�v�ł�����ɂ��̘e�����Z�ɖ����������Ă����B�q���C���ɂ͂Ȃ�Ȃ�������Ă��邪�A���e���ɂ͂Ȃꂻ���Ȋ�ł���B�{�[�}���E�C�[���[�j�[�́A�A�����[�V���E�v���[�S�����A�R���f�B�[���������V���A�X�Ȗ����|���e���������Ȃ���A�q���f�B�[��f��E�ɂ͂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����h��������j�D�ƂȂ��Ă���B�����ɒ��ڂ��Ă���A�g�D���E�N���J���j�[���D�����Ă����B�f�撆�̃Z���u�E�p�[�e�B�[�ł́A�X�j�[���E�V�F�b�e�B�[���`�����Ɠ��ʏo�����Ă����B
�@����́A�q���f�B�[��U���A�p��S���B�ꉞ���ނł̓q���f�B�[��f��ƂȂ��Ă������A�q���O���b�V���f��ɃJ�e�S���C�Y���Ă��܂��Ă������Ǝv�����B
�@�uPage3�v�́A���h�R���f�B�[�Ƃ��Ă��Љ�h�f��Ƃ��Ă��p�[�e�B�[�f��Ƃ��Ă��y���߂�f��ł���A�C���h�f��̐V���ȓ����J���̂ł͂Ȃ����Ɗ������B�}�h�D���E�o���_�[���J���ḗA�V���o�̃q���f�B�[��f������A���ł����ڂ̉f��ē�1�l���Ƃ������Ƃ��ؖ����ꂽ�ƌ����Ă������낤�B
�@�P���Q�R���t���̃T���f�[�E�j���[�X���C�����i�G�N�X�v���X�E�j���[�X���C���̓��j�܍��Łj�ɁA�f���[�̑�w���̎x�o�z���o�Ă����B�P���s�[���Q�D�T�~�Ƃ��āA���{�~���L�ڂ��Ă������B
| �g�ѓd�b |
�@3,000 -15,000���s�[ |
�@7,500 -37,500�~ |
| �C���^�[�l�b�g |
500 - 1,000���s�[ |
1,250 - 2,500�~ |
| �^�o�R |
700 - 1,000���s�[ |
1,750 - 2,500�~ |
| �ʊw |
50 - 2,000���s�[ |
125 - 5,000�~ |
| �C�^�� |
500 - 2,000���s�[ |
1,250 - 5,000�~ |
| �T���O���X |
150 - 5,000���s�[ |
375 -12,500�~ |
| �W�[���Y |
700 - 1,500���s�[ |
1,750 - 3,750�~ |
| �f�� |
150 - 300���s�[ |
375 - 700�~ |
| ��V�� |
500 - 2,000���s�[ |
1,250 - 5,000�~ |
| ���y�^�{ |
500 - 1,000���s�[ |
1,250 - 2,500�~ |
| �O�H |
500 - 2,000���s�[ |
1,250 - 5,000�~ |
�@���������ǂ������f�[�^�Ȃ̂��S�������Ă��炸�A�قƂ�ǎQ�l�ɂȂ�Ȃ��悤�Ȑ��l�ł��������A���܂肱�������f�[�^�����Ȃ��̂ŁA�����������čl�@���Ă݂悤�Ǝv���B
�@�܂��A�ΏۂƂȂ��Ă���w���́A�f���[��w�̃m�[�X�E�L�����p�X�̊w���w���ł���\���������B�f���[��w�ɂ̓s������L���܂ł��낢��ȃJ���b�W�����邪�A�m�[�X�E�L�����p�X�̃J���b�W�͈�ʓI�ɗD�G�Ȋw���������ʂ��Ă���A�T���Ȋw�������Ȃ��Ȃ��B���ɒ��ӂ��ׂ����Ƃ́A��L�̋��z���A�����̎x�o�̍Œ�z�E�ō��z�ƁA�������Ă��镨�̗����̍Œ�z�E�ō��z����������ɂȂ��Ă���\�����������Ƃ��B��̍��ڂ̓��A�g�ѓd�b�A�C�^���A�T���O���X�A�W�[���Y�́A�����炭�A���P�[�g���ɏ��L���Ă�����̗̂����ł����āA���������̂��̂ɂ��ꂾ���̂������₵�Ă���Ƃ������Ƃł͂Ȃ����낤�B����A�C���^�[�l�b�g�A�^�o�R�A�ʊw�A�f��A��V�сA���y�^�{�A�O�H�̍��ڂ́A�����܂��͓���̌��̕��ϓI�x�o�z���낤�B�ȉ��A�ʂɊe���ڂ����Ă݂悤�B
�@�f���[�̑�w���������Ă���g�ѓd�b�̊z�͂R�O�O�O���s�[����n�܂�B�R�O�O�O���s�[�Ƃ����ƁA���m�N���t���̒��Ìg�ѓd�b���炢���낤�B����͂P���T�烋�s�[�B���̂��炢�̒l�i���ƁA�V�i�̃J���������[�r�[�t���g�ѓd�b��������B�ŋ߁A�f���[�̊w���̌g�ѓd�b�̊ԂŁA�w�����o���̃|���m�E���[�r�[���o���Ƃ����������N���đ���ɂȂ����B���̎���������A�w�������������������@�\�Ȍg�ѓd�b�������Ă��邱�Ƃ�������B
�@�C���^�[�l�b�g�オ�T�O�O�`�P�O�O�O���s�[�Ƃ����̂́A������ƒ��L���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�C���h�ł͂܂��܂�����Ƀp�\�R���������Ă���l�͏��Ȃ��A���̋��z�̓l�b�g�J�t�F�ȂǂŃC���^�[�l�b�g�����邽�߂̑�����Ƃ������Ƃ��B�f���[�̈�ʓI�ȃl�b�g�J�t�F�����́A�P���ԂP�T�`�Q�O���s�[�B�P���v�Z����ƁA�f���[�̑�w���͂P���P�`�Q���Ԃ��炢�l�b�g�𗘗p���Ă��邱�ƂɂȂ�B
�@�^�o�R�オ�V�O�O�`�P�O�O�O���s�[�Ƃ����̂͂������������B�C���h�l�̓^�o�R�������邱�Ƃ͋H�ŁA�甄�肳��Ă�����̂𐔖{���������Ƃ������B�P�{�R���s�[���炢���B������P���v�Z����ƁA�P���P�O�{�O��z���Ă��邱�ƂɂȂ邾�낤�B�ŋ߂̓C���h�l�̎Ⴂ���̎q���i�������Ă���p���悭��������悤�ɂȂ����B��������uPage3�v�Ƃ����f��ɂ��A���̎q���^�o�R���z�����Ƃ����R�̔@���`�ʂ���Ă����B���F�W�^���A���Ȃ̂Ƀw�r�[�X���[�J�[�Ƃ����l�������肵�āA���{�l�ɂ͏����������������ƂȂ��Ă���B
�@�ʊw��̉������T�O���s�[�Ƃ����̂́A������������悤�Ɏv����B�����Ēʂ��鋗���ɏZ��ł��闾���Ȃǂ͒ʊw��[�����낤���A�o�X�p�X�i�o�X�̒�����j�𗘗p��������ƈ����Ȃ�Ǝv���B�ʊw�ɂQ�O�O�O���s�[��������l�́A�I�[�g���N�V���[�𗘗p���Ă���l���낤�B��x���̎q���ɂȂ�ƁA�^�]��t���̎����Ԃő���}�����Ă�����Ă���l�����邻�����B
�@�C�Ɗ��͂T�O�O�`�Q�O�O�O���s�[�B�l�������Ă���ʊw�p�̃����V�����_�[�����b�N�̓O���K�[�I���ōw���������̂����A�P�O�O�O���s�[���炢�������Ǝv���B�C���C���h�Ŕ��������Ƃ͈�x�����Ȃ����A����͊m���Q�O�O�O���s�[�ȉ��������ƋL�����Ă���B�������A�C���h���̌C�͒ʋC���������A�������̂������L���Ȃ邱�Ƃ���A����ȗ��C���h�̌C�͔����Ă��Ȃ��B�C�Ƃ�������A�C���h�l����D���ȃ`���b�p���i�T���_���j�͊܂܂�Ă��Ȃ��̂��낤�B
�@�T���O���X�̉��i�͂P�T�O�`�T�O�O�O���s�[�B�Ȃ��T���O���X�Ƃ������ڂ�����̂��͑傫�ȓ�ł���B�C���h�l��ῂ����艮�̉��Đl�ƈ���Ă���قǃT���O���X�𑽗p���Ȃ��������Ǝv���̂����E�E�E�B�P�T�O���s�[�̃T���O���X�́A������ӂ̓��[�̘I�X�Ŕ����Ă���������낤�B�T�O�O�O���s�[���̃T���O���X�𒅗p���Ă���C���h�l�w�������邱�Ƃ͊ȒP�ɂ͐M�����Ȃ��B
�@�W�[���Y�̉��i�͂V�O�O�`�P�T�O�O���s�[�B�V�O�O���s�[�̃W�[���Y�́A���Ɍ����u���[�J���v�̃W�[���Y�ŁA��̕�����Ȃ���Ж��Ȃǂ�������Ă�����A������Ж����L�ڂ���Ă��Ȃ������肷����̂��낤�B���[�A���[�o�C�X�Ȃǂ́u�J���p�j�[�v�̃W�[���Y�Ȃ�P�O�O�O�`�P�T�O�O���s�[�͂���B�����A�C���h�ł̓W�[���Y�𗚂��Ă��邱�Ǝ��̂��X�e�[�^�X�ł��邱�Ƃ����L���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�C���h�̌�y�̉��l�A�f���͂P�T�O�`�R�O�O���s�[�B�z�����Ă������Ⴂ�悤�Ɏv����B�o�u�q�Ȃǂ̍����V�l�}�R���v���b�N�X�Ȃ�A�P�`�P�b�g�P�T�O���s�[����B�̂Ȃ���̉f��قȂ�A�Q�O�`�S�O���s�[���炢���ł��������Ȃ̒l�i���낤�B�C���h�l�w���́A�킴�킴���������o���Ă܂ŃV�l�R���Ɍ��ɍs���Ȃ��Ƃ��l�����邵�A�P���ɂP�`�Q�{�����f��قʼnf������Ȃ��Ƃ��l���邱�Ƃ��ł���B�E�E�E�Ƃ����l���f����������Ă��邾���Ȃ̂��B�u�b�c�̃����^���͂P���Q�O���s�[���炢�B
�@��V�ё�T�O�O�`�Q�O�O�O���s�[�Ƃ����̂́A���ݑ�ƃf�B�X�R��Ƃ������Ƃ��낤�B�f���[�ł͂܂��܂���V�т��悤�ɂ���V�тł���ꏊ�������Ă���A�o�[�ň��ނ��f�B�X�R�ŗx�邩���炢�����Ȃ��B�o�[�ň��߂r�[���P�{�P�O�O���s�[�ȏ�͂����邵�A�f�B�X�R�ɓ���ɂ̓J�o�[�`���[�W�Ƃ��ĂR�O�O�`�S�O�O���s�[�͎����B�ߓx�����V�т����Ă���A�T�O�O�`�Q�O�O�O���s�[�Ƃ����̂͑Ó��Ȓl�i���낤�B
�@���y�^�{�ɔ�₷���z�͂T�O�O�`�P�O�O�O���s�[�B�w�������͖{��Ȃ���Ύn�܂�Ȃ����A�C���h�ł͕K�������w�����{���K�v�͂Ȃ��B�����̏ꍇ�A�n�����w�������͐}���ق���{���肽��A�R�s�[��������A�F�l����{�������Ă�������肵�ĕ������Ă���A���܂�{���Ƃ������Ƃ͂��Ȃ��B���y�̓J�Z�b�g�Ƃb�c�����邪�A�w���̊Ԃł͂܂��J�Z�b�g���嗬���낤�B�b�c�͂P�O�O���s�[�قǁA�J�Z�b�g�͂T�O���s�[�قǂł���B
�@�O�H��T�O�O�`�Q�O�O�O���s�[�B�O�H�Ƃ����̂��ǂ��܂Ŋ܂ނ̂��s�������A�����̒��H��{�F�l�����Ƃ̉�H��ƍl����Ƃ��̂��炢���B�L�����p�X���̐H���ŐH�ׂ�P�H�P�O�`�Q�O���s�[���x�A�}�N�h�i���h�Ȃǂ̃t�@�X�g�t�[�h�X�łP�H�H�ׂ�P�O�O���s�[�A�`���[�C�͂P�t�Q���s�[�ȂǁB
�@�����̕��ώx�o�z�Ǝv�����L�̂V���ڂ����v����ƁA�Q�X�O�O�`�X�R�O�O���s�[�ƂȂ�A�f���[�̑�w���������g�����������̋��z�̕��ɋ߂��悤�Ɏv����B�������A����ȊO�ɂ��o��͂��邾�낤�B�܂��A�V���L���ɍڂ��Ă����w���ւ̃C���^�r���[�𑍍�����ƁA�ꌎ�̎x�o���Q�O�O�O�`�S�O�O�O���s�[�ɂ��悤�Ɠw�͂���̂���ʓI�ȃf���[�̑�w���̂悤���B�����A�l���ʂ��W�����[�n�����[���E�l���[��w�̊w���́A���Z�܂��̐l���������Ƃ�����A����Ɉꌎ�̎x�o�z�͒Ⴂ�Ɨ\�z�����B
�@�Ƃ���ŁA�����̓��v���Ȃ��V���ɍڂ��Ă������Ƃ����ƁA��w���̊w���������A�Ƃ������Ƃ��咣�����ŁA�f���[�̑�w���͖�������Ȃɑ����̋����g���Ă܂���A�Ɠ`���邽�߂̂��̂������B���̓C���h�̑�w�̊w��͔n���݂����Ɉ����B�Ⴆ�A�f���[��w�̊w��͂P���P�T���s�[�ł���B����ȊO�ɂ����w��A�}���ٔ�A�w���ؔ��s��Ȃǂ̏��o��◾��A���H��Ȃǂ�������̂����A�w��iTuition
Fee�j�Ƃ��Ē�������Ă��闿���͖����P�T���s�[�ɉ߂��Ȃ��B���ɃR�J�E�R�[���P�D�T�r���ł���B�i�m�t�ł��C�m�ے��܂ł̊w��͖����P�W���s�[�ł���B�������A����̓C���h�l�w���݂̂ł���A�O���l���w���̓x���{�E�ɍ����w��킳���B�f���[��w�ł͔N�Ԃ̊w��͂T�T�O�O�`�U�O�O�O���s�[�ŁA����ɉ����ē��w���ɂR�O�O�`�T�O�O�h�����u�O���l�o�^��v�Ƃ��Ďx����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�i�m�t�ł����n�w���͔��N�̊w��͂U�O�O�h���ł���A�C���h�l�Ɣ�ׂĕs���ɍ����l�i�ƂȂ��Ă���B��w�́A�w��l�グ���w���^��������̈������ƂȂ�̂�����A���\�N�Ԋw��Ɏ��t���邱�Ƃ��ł��Ȃ��ł���B���̑���̍������m�ۂ��邽�߁A�O���l���w���̊w������グ��ꂽ�Ƃ����̂�����ł���B�������A����ɃC���h�l�w���̊w��̒l�グ���c��ɏ��悤�ɂȂ��ė��Ă���Ɗ�����B
�@�����A�C���h�͂܂��܂��n�x�̍������������ł���̂ŁA������u��ʓI�ȁv��w���̎x�o�z���w��ƒނ荇��Ȃ��z������ƌ����āA����I�Ɋw���l�グ��̂��l�������B�V���ɍڂ��Ă����w���̎x�o�z�͂ǂ����Ă��f���[�ݏZ�̒��Y�K���̂��̂ł���A�c�ɂ���Ƒ��⑺�l�����̊��҂���g�ɔw�����ăf���[�܂ŗ��Ă���n�R�w�������̍������ӂ݂�ƁA��͂�w��͐����u���Ă����Ȃ��Ƃ����Ȃ���Ȃ����Ƃ��v���Ă���B�Z�킪�����A�n�����ƒ�ł́A�P�l�ɋ�����W��������X��������B�Z��̒��ł����Ƃ����̂����P�l���w�܂ʼn��Ƃ��i�w�����āA�c��̌Z��͑��Ɏc���Ė�ǎd���Ȃǂ����ĉƌv���x����Ƃ����̂��悭������B������A�n�����w���̗��ɂ́A���l�����̋�J�����łȂ��A�����̐l�X�̌��Ɗ��Ɨ܂��B����Ă��邱�Ƃ�����B�l�̃N���X���C�g�̑唼���A��͂�d�C���ܑ����H���Ȃ��悤�ȕn�����������J���Ă���ė�����w�������ł���B�q���f�B�[��C�m�ے����w�Ԋw�������̃X�e�[�^�X�͂i�m�t�ł͑S�R�����Ȃ����A�ނ�����Ƃ��đ��ɋA��A�u�C���h�ō���̑�w�𑲋Ƃ����l�v�Ƃ��Ă��Ă͂₳��邱�Ƃ��낤�B�������ƌ����������ɍ��i���悤���̂Ȃ�i�i�m�t�̊w���͌������u�]�������j�A���������ďj���Ă���邾�낤�B�����A��������ȏ�w������Ȃ��Ă��܂�����A�����̃C���h�̌o�ϔ��W�Ƃ͖����ȕn�������X�̊w������w�Ŋw�тɂ����Ȃ��Ă��܂����Ƃ͕K�肾�B�n�����w���ɂ͏��w�����Ղ��n��悤�ɂ���ȂǁA���낢��z�����w��l�グ�ɂ��Č������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���B
�@�o�C�N�ŃA�[�O���[�܂ōs�������A�^�[�W�E�}�n���ƃo�C�N�̃c�[�V���b�g���B�肽���\�\�C���h�ɏZ�݁A�o�C�N�����悤�ɂȂ��Ă���A���������ꂪ�����Ȗ�]�ƂȂ��Ă����B�f���[����A�[�O���[�܂ł͖�Q�O�O�����B�����S�O�O�����B�o�C�N�œ��A�肷��ɂ͂�����Ɛh�������ł���B����āA�ꔑ����ŃA�[�O���[�܂Ńc�[�����O����v����ȑO���痧�ĂĂ����B��T�̓V�����[�ŐႪ�~�����e���Ńf���[�͊��g�ɏP���Ă������A���T�ɓ����Ď���ɉ������Ȃ��ė��Ă���A�c�[�����O����̂ɂ��傤�ǂ����C��ɂȂ��Ă����B�܂��A�c�[�����O���Ԃ̒��ł͈�ԖZ�����l���A�e�X�g���Ԃ�|�[�g��o�Ȃǂ��n�܂��Ă��炸�A�܂����Ԃɗ]�T���������B����āA�P���̍Ō�̓y�����A�[�O���[�ւ̈ꔑ����̃c�[�����O���Ɍ��肳�ꂽ�B
�@�f���[�̓�A�}�g�D���[����A�[�O���[�ɂ����Ă̈�т͓`���I�Ƀu���W�n���ƌĂ�Ă���B�u���W�n���̓N���V���i�_�b�̕���ł���A���̒n���Řb�����u���W�����́A��������ߑ�ɂ����ăq���f�B�[���w�̒��S����ƂȂ����B���K��������ɂ͓s���f���[��A�[�O���[�Ȃǂɒu���ꂽ���Ƃ���A�����̒��S�n�Ƃ��Ă��h�����y�n���B�u�u���W�v�Ƃ͉ƒ{���q�p�̈͂��n�̂��ƂŁA���̌��t������q�{�̐���Ȓn�悾�������Ƃ��f����B����̃c�[�����O�ł́A�E�b�^���E�v���f�[�V���B�̃A�[�O���[�ƃt�@�e�[�v���E�X�B�[�N���[�A���[�W���X�^�[���B�̃o���g�v���ƃf�B�[�O�̂S���������邱�Ƃɂ����B�o���g�v����f�B�[�O���u���W�n���Ɋ܂߂邩�ǂ����͔��������A�C���I�ɂ̓u���W�n����т�����c�[�����O�ł���B����āA�薼�̓u���W�E�c�[�����O�ƂȂ����B�Q���҂��P���P�U���̃K���K�[�Q�q�c�[�����O�Ɠ��������o�[�łR�l�B�l�͂Q�Q�T�����̐ԃJ���Y�}�ɏ��A�c���2�l�͂P�W�O�����̋�p���T�[�ƁA�P�R�T�����̉��A���r�V�����ł���B���A���r�V�����͑O��̃c�[�����O�����ޗ��s�ƂȂ�͂����������A���ԂƂ��������V���ɕڑł��Ă̎Q���ƂȂ����B����ł���ƒʎZ�S�x�ڂ̃c�[�����O�ƂȂ�A�܂�Ńu�b�_�̎l��o�V�̔@���A�f���[�̎l���Ƀo�C�N�ő���L�������ƂɂȂ�B���܂ł̃c�[�����O�̗������ꖇ�̒n�}�ɂ܂Ƃ߂Ă݂��B�c�[�����O�E�}�b�v�Ƃ��Ă����łȂ��A�f���[����̓��A�藷�s�Ȃǂɂ��Q�l�ɂȂ邾�낤�B���f���[���Ӄc�[�����O�E�}�b�v
�@���X�������ɃT�t�_���W�����O�E�G���N���C���̎�����o���B��ɂ͔�������Ɖ_���������Ă��邪�A���V�ƌ����Ă������낤�B�܂��̓��[���`�����h�a�@�̌����_�߂��ɂ���o�[���g�E�y�g�����A���ň��p�̃K�\�����A�X�s�[�h�X�R�^���܂ŕ⋋�B�������烊���O�E���[�h��ʂ��ē��������A�A�[�V�������Ń}�g�D���[�E���[�h�ɓ����āA���Ƃ͂Ђ�����܂������쉺�����B�}�g�D���[�E���[�h�͕����ʂ�}�g�D���[�ɑ������H�ŁA�����Q�����Ƃ������B�f���[�̏B���ɂ���o�_���v������ɍ��G���Ă��邪�A�n�����[�i�[�B�t�@���[�_�[�o�[�h����A�Б��Q�Ԑ��A���������т���̉��K�ȓ��ŁA���Ƃ̓X�C�X�C�s���B
�@�Ƃ��낪�A�o�_���v���t�߂Ńg���u�������B��p���T�[�̌�ւ��p���N���Ă��܂����̂��B�^�C���ɂ͓B���h�����Ă����B���̓r���œB�\�������邪�A���ւ��Ă���ꏊ�Ō����点�����\���������B�ނ̃p���T�[�͍��܂ʼn��x���B�ɂ�錙���点���Ă���A����Ƃ��ɂ͈�x�ɂR�{���̓B���h����Ă������Ƃ��������B����͒������c�[�����O�Ȃ̂ŁA�p���N���@�ɔނ͎v�����ă`���[�u��V�������̂ɕς����B�`���[�u�����łX�O���s�[�B�ςȂƂ���Ńp���N��������A�p���N�̏C����������������s�X�n�Ńp���N���Ă����Ă悩�����̂ł͂Ȃ��낤���B
�@���ʂ̖ړI�n�̓}�g�D���[�߂��ɂ���}�N�h�i���h�B�����Œ��H��H�ׂ�\��ɂȂ��Ă����B�p���N�Ŏ��Ԃ����X���Ă��܂����̂ŁA�t�@���[�_�[�o�[�h������͈꒼���Ń}�g�D���[��ڎw�����B�f���[����}�g�D���[�܂ł͖�P�T�O�����B�}�N�h�i���h�̓}�g�D���[���炳��ɖ�P�O�����s�����Ƃ���ɂ���B�B�́A�f���[�B���n�����[�i�[�B���E�b�^���E�v���f�[�V���B�ƕϑJ���čs�����B���̓r���A�}�g�D���[�ŃW���C�E�O���E�f�[�����@�ɗ���������B�f���[�`�A�[�O���[�Ԃ𗤘H�ňړ��������Ƃ�����l�Ȃ�A���̓r���ɂ��锒���̋���Ȏ��@���������Ƃ����邾�낤�B���̎p�̓^�[�W�E�}�n���ɂ����Ă���A�U�^�[�W�E�}�n���ƌĂ�邱�Ƃ���������B���̕ӂ�ʂ邽�тɂ����C�ɂȂ��Ă����̂����A����̓o�C�N�ŗ��Ă����̂Ŏ��R�������A���łɗ�������Ă݂邱�Ƃɂ����B�l�͂Ă�����X�B�N���̃O���h���[���[���Ǝv���Ă����̂����A�q���h�D�[���ɋ߂��V���@���̎��@�������B�P�X�V�R�N���猚�����n�܂����炵�����A�����Ɍ��ݒ����������B�ؐH��`�����ɂ��Ă���A���@�̒��ɍ����Ă����l�͉�X�ɍؐH��`�̎��H�𑣂����B�n���ɂ͊��Ɏ����������c�̋L�O�肪����A�ΑK�����u����Ă������A�����ɂ́u���A���A���A����ێ悷��l���ΑK���f��v�Ə�����Ă����B�����������j�̎��@�͒������B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�W���C�E�O���E�f�[�����@ |
�� |
�@�}�N�h�i���h�ɓ��������̂͌ߌ�Q�����������B�c�[�����O�̃��[�g�̓r���Ƀ}�N�h�i���h�̂悤�Ȑ����ȃ��X�g����������Ƃ��肪�����B�����Ƃ����g�C�������邱�Ƃ��ۏ���Ă��邵�A�������Ƃ��ł��邵�A�H�������邱�Ƃ��ł���B�}�N�h�i���h�ł͋v���U��Ƀ}�n�[���[�W���[�E�}�b�N�o�[�K�[�E�R���{�i�X�X���s�[�j��H�ׂ��B�������̂ŁA���̂������������������B�́A�A�[�O���[�̃P�[���h���[���E�q���f�B�[�E�T���X�^�[���Ńq���f�B�[����w��ł������g�A�j�A�l�̃N���X���C�g�̘b�ł́A�A�[�O���[����o�C�N�ɏ���Ă悭���̃}�N�h�i���h�܂ŗ��Ă����������B�����̓A�[�O���[�Ƀ}�N�h�i���h���Ȃ������̂��B���ł��Ȃ���������Ȃ����B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�}�g�D���[�̃}�N�h�i���h |
�� |
�@�}�N�h�i���h�ŕ������炦��������́A��������S�O�����̒n�_�ɂ���A�[�O���[��ڎw�����B���Q�s�s�A�[�O���[�ւ킴�킴���ړI�͂����ЂƂB�^�[�W�E�}�n���̑O�Ńo�C�N�Ǝʐ^���B�邱�Ƃł���B�������A�^�[�W�E�}�n�����ӂ͎ԗ��̐i���͋֎~����Ă���̂ŁA�s�����Ƃ��ł��Ȃ��B�ł̓����i�[�͑Ί݂͂ǂ����B�́A�����i�[�͂ɉ˂�����H��n���ă^�[�W�E�}�n���Ί݂܂ŗ��āA�ʐ^���B������X�P�b�`�����肵�����Ƃ��������B�������̂Ƃ��͓k���������B�������R�`�S�N���O�ɂȂ�B���̂Ƃ��͂����Ƃ������H�Ȃǂ͂Ȃ������͂����B�ʂ����Č��݁A�ԗ����Ί݂܂ōs�����Ƃ��\���낤���H�������[�E�v���l�b�g����o�Ă���uIndia&Bangladesh
Road Atlas�v�i�c�[�����O�̍ہA���ɎQ�l�ɂȂ�n�}���ł���j�����Ă݂��Ƃ���A�^�[�W�E�}�n���̐^��O�́u�^�[�W�E�r���[�|�C���g�v�܂ő��������ڂ��Ă����B���̓���ʂ�s���邩������Ȃ��A��������������X�́A�܂��͍����Q������ʂ��ă����i�[�͂��z���A��������E�ɋȂ����ăA���[�K���E���[�h�ɓ���A�^�[�W�E�}�n���̐^��O�܂ōs�����ƁA���ꂪ�����ł��\�Ȍ���^�[�W�E�}�n���ɋߕt�����Ƃ����̍��Ƃ����B�肵�āu�~�b�V�����E�^�[�W�v�B��D���ȃ^�[�W�E�}�n����������x���邱�Ƃ��ł��邾���ł��A�l�̋��͍������B
�@�A�[�O���[�ɋߕt���ɘA��ē��͍��G���ė����B�A�[�O���[�x�O�ɂ���X�B�J���h���[�i���K������R��c��A�N�o���̕�_�j�̑O��ʂ�A���̂܂܍����Q�������J�[���v�����ʂɌ����đ������B�����i�[�͂ɉ˂��鋴��n��A�������獑��������āA�A���[�K���E���[�h�ɓ���A����Ƃ����镨�̂������߂����H���N���N�V�����A�����Ȃ���ʂ蔲�����B���̕ӂ�ɂ́A�`�[�j�[�E�J�E���E�U�[��C�e�B�}�h�D�b�_�E���[�ȂǁA�A�[�O���[�̃}�C�i�[�Ȉ�Ղ�����������B
�@�A���[�K���E���[�h��쉺���Ă����ƁA�܂��̓A�[�O���[������n����ꏊ�ɏo���B���̏ꏊ�́A���`��f�B�A�ʐ^�قQ�O�O�P�N�̍�i�m���D�P�O�u�T�[���[���v���B�e�����ꏊ�ł���B����ς荡�����h�[�r�[�i����l�j��������ӂɃT�[���[�������Ă����B�Ƃ肠���������ŃA�[�O���[��ƃJ���Y�}�̂Q�V���b�g���B�e�����B
�@�������炳��ɓ쉺���Ă����ƁA�Ƃ��Ƃ��ڂ̑O�Ƀ^�[�W�E�}�n���̈Зe���p���������B�J�[�u���Ȃ������u�ԁA����̒��A�̐X�̌������Ɂu�o���I�v�Ɣ����̃h�[�����������̂����甗�͖��_�ł���B���̂Ƃ��̊����͕M��ɐs�����������قǂł������B���̂܂ܕܑ����H�������Ă���A���ɉ����Ă�������A�����i�[�͂̊ݕӂ܂ŒH�蒅���Ă��܂����B�ݕӂɍs���ɂ͍��n�̍⓹������˂Ȃ炸�A�A��o�C�N�œo��邩�S�z���������A�ݕӂɊ��ɂP��̃o�C�N����܂��Ă����̂ŁA����Ȃ���v���낤�ƁA��C�ɉ���Ă��܂����B�����ă^�[�W�E�}�n���̐��ʂɃo�C�N���߂��B���̎��_�Ōߌ�R���������B�^�[�W�E�}�n���ɂ͍����������̊ό��q���K��Ă���A����Ȕ����̕_�̒����S�}���̂悤�ȑ傫���̐l�X���������̂��������B�����Ƒ����̐l�������Ă�����߂Ă��邱�Ƃ��낤�B
�@�����A�����^�[�W�E�}�n���̑O�Ŏʐ^���B�낤�A���N�̖�]�����A�����悤�\�\�����A�����͖≮�������Ȃ������B�ݕӂɓ��������Ƃ�����A�吨�̎q���������l�����̌����Ăɒǂ������Ă����̂��B����q���͖��ʂ݂̏Ƌ��ɁA����q���́u�����N���������킩��Ȃ��v�Ƃ������\������Ȃ�����A���̎q���ɒx��܂��ƕK���ɑ����ė����B�o�C�N���Ԃ�����ƁA��X�͎q�������Ɉ͂܂�邱�ƂƂȂ����B�q�������͌��X�ɉ���������ł���B�y�������ꂾ�́A���̃o�C�N�͂����炩���́A�l���悹�Ă��ꂾ�́A�ʐ^�����ꂾ�́A���������ꒃ�ȏ�ԂƂȂ��Ă��܂����B�V���ɂ��̖������������^�[�W�E�}�n���A�O���l���ꗿ���V�T�O���s�[�ɒl�グ����Ă��܂������A�Ί݂��疳���Ń^�[�W�E�}�n���߂Ė�������n�R���ȊO���l���s�҂������悤�ŁA�K�R�I�ɂ��̕ӂ��꒣��ɂ��镨�����q�������������Ă��܂����悤���B���N�_�܂ł����B�J�������\����ƁA��ĂɎq���������������Ă��ă|�[�Y�����Ƃ����L�l�E�E�E���̏�Ԃł͎ʐ^���B��Ȃ��E�E�E�B
�@�����������ł̓q���f�B�[�ꂪ���ɗ������B�q�������Ɂu��Ŏʐ^���B���Ă����邩��A������Ƃǂ��ĂĂ��炦�Ȃ����ȁv�ƌ����ƁA�K�L�叫�i�̎q�����������Ă���Ďd���Ă��ꂽ���߁A���Ƃ��^�[�W�E�}�n���ƃJ���Y�}�̂Q�V���b�g���B�e���邱�Ƃɐ��������B���̂Q�l���q���������x�����Ƃ��L�O�ʐ^�B�e���I�����B���̌�͓�����悤�ɂ��đ��苎�����B�E�E�E�����A�ォ��v���A�����Ƃ����ȍ\�}�Ń^�[�W�E�}�n���ƃJ���Y�}�̎ʐ^���B�肽�������B�l���ꏏ�Ɏʂ��Ă����悩�����ƌ�������������B�܂������A�q�������̂��Ȃ����ԑт����v����āA�^�[�W�E�}�n���܂Ńo�C�N�ŗ��悤�Ɛ������B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
|
�^�[�W�E�}�n���ƃJ���Y�} |
|
|
 |
|
| �� |
�C���Ƃ����Ȃ� |
�� |
�@���̖ړI�n�̓t�@�e�[�v���E�X�B�[�N���[�B�t�@�e�[�v���E�X�B�[�N���[�́A�A�[�O���[�ό��R�[�X�ɕK�������Ă���ό��n�ŁA�A�[�O���[�̐���S�O�����̒n�_�ɂ���B�P�T�V�P�N����P�T�W�T�N�̊Ԃ������K�������̎�s�ƂȂ����ꏊ�ŁA�����̈�\���قڊ��S�Ȍ`�Ŏc���Ă��邱�ƂŗL�����B�����A�l�������t�@�e�[�v���E�X�B�[�N���[�֍s����ȖړI�́A��Ղł͂Ȃ������B���̎��ӂɂ́A�F�g�����o�v���邱�Ƃł��L���ł���B���̌F�ƈꏏ�Ɏʐ^���B�肽�������̂��B�������F�g���̑����A�[�O���[�ƃt�@�e�[�v���E�X�B�[�N���[�̊Ԃɂ���Ƃ̏����A�����֍s���Ă݂悤�Ƃ������ƂɂȂ����B
�@�^�[�W�E�}�n���Ί݂���t�@�e�[�v���E�X�B�[�N���[�������̂ɁA�A�[�O���[�s�X�n����Ƃ����A���܂茫���Ȃ����[�g������Ă��܂����B�܂��̓C�e�B�}�h�D�b�_�E���[�߂��ׂ̍�����n���ă����i�[�͂��z���A�������璆���̃o�[�U�[���̕��͋C���c���卬�G�̊X����ʂ��čs�����B�Ƃɂ������Ȃ�ɂ��`���Ƃ܂������i��ł����ƁA�A�[�O���[�̑哮���ƌ������ʂ�A�}�n�[�g�}�[�E�K�[���f�B�[�E���[�h�i�l�f���[�h�j�ɏo���B�l�f���[�h���ɐi�݁A�K���ȂƂ���Ő��܂�āA��������͌����_���Ƃɓ���q�˂�����ŁA�t�@�e�[�v���E�X�B�[�N���[�ւȂ��铹��T�����B�A�[�O���[�͓��ē��̕W�����قƂ�ǂȂ��̂ʼn^�]����̂�����B
�@���Ƃ��t�@�e�[�v���E�X�B�[�N���[�s���̓��������邱�Ƃ��ł����B���̓��͊����ł͂Ȃ��̂ŁA���������т��Ȃ��Б��P�Ԑ��̊댯�ȓ��������B�C���h�l�͖����Ȓǂ��z��������̂ŁA�q�����Ƃ��������ʂ����x���������B���������������ɐi�ރg���b�N���\�����Ă���ƁA�����ǂ������̂ɋ�J���邵�A���Ƃ����ăg���b�N�̗��ɂ����t���Ă���ƁA�g���b�N�̘e���烂�E���E�Ɠf���o����鍕�����v�������藁�т邱�ƂɂȂ�̂ŁA��ς��B
�@���ɂ��̕ӂ�̓��[�ɂ͌F�g���������ҋ@���Ă����B�F�g���́A���s�҂���鎩���Ԃ��ʂ�ƁA�����ނ�ɌF�Ɍ|�������Ē��ӂ������A���s�҂���܂�ƁA����ɑ����̌|�������Ă��������炤�B�F�Ƃ����ƕ|���C���[�W�����邪�A�ނ炪�������炵�Ă���F�͉��܂�������Ă��邻�����B��X�́A�F�g���̑��ɍs���Ă�������̌F�����ƈꏏ�Ɏʐ^���B�낤�Ɩژ_��ł����B���̑��̓t�@�e�[�v���E�X�B�[�N���[����P�O�������炢�̒n�_�ɂ������B�m���ɑ��̉Ƃ̒�ɂ͌F���Ȃ���Ă���B�悵���I�Ǝv���đ��̒��Ƀo�C�N���������ƁA�������������������B�u�F�����ɗ����I�v�ƌ����ƁA�u�F�Ȃ瓹�[�ɂ��邩�炻�����֍s���v�Ɨ₽���Ԏ����A���ė����B�I���ɂ͉������悭������Ȃ�������Ɏ����ē{��o�����q���Ə��������āA���͋C����������̂ŁA�d���Ȃ��ގU���邱�Ƃɂ����B��͂肢���Ȃ�o�C�N�ŏ����ꂽ���炢���Ȃ�������������Ȃ��B���Ǎ���̗��s�ł͌F�ƈꏏ�Ɏʐ^���B�邱�Ƃ��ł��Ȃ������B
�@���̂܂܃t�@�e�[�v���E�X�B�[�N���[�܂Œ��s�����B�ߌ�S�����߂��ɂ̓t�@�e�[�v���E�X�B�[�N���[�̏鉺���ɓ����B�����̓}�[�P�b�g�̓�����̂������ɂ���S�[���@���_���E�c�[���X�g�E�R���v���b�N�X�ɏh�����邱�Ƃɂ����B�g���v�����[���łT�T�O���s�[�B�����̃z�e���̃��X�g�����̓G�b�O�E�J���[���X�y�V�����e�B�[�Ƃ̂��Ƃ������̂ŁA�f���ɂ���𒍕����Ă݂���A���������s�v�c�Ȗ��t���Ŕ������������B�K���Ƀ}�[�P�b�g���U����́A��t���킵�đ��X�ɖ������B
�@���V���N���B���肪�������Ƃɍ����������B���O�Ɍ��Ă���Yahoo!�̓V�C�\��ł͌��j�����J�ƂȂ��Ă���A���̉J�������ɂ��ꍞ�����Ǝv���Ă����̂����A�ǂ����V�C�\��ʂ�ɂȂ��Ă��ꂽ�悤���B
�@1�l�����Q�V���������߁A�l�Ƃ���1�l�͒��̎U���ɏo�������B�U���ƌ����Ă��A���A���r�V�����ɂQ�P�c���Ẵh���C�u�ł���B�t�@�e�[�v���E�X�B�[�N���[�͂R�l�Ƃ��������ɗ������Ƃ����������߁A�킴�킴�Q�U�O���s�[�̊O���l�������Ă܂Ō���C�͂��Ȃ������B�����A�l�ɂ͂ЂƂ����s���Ă݂����ꏊ���������B����́A�t�@�e�[�v���E�X�B�[�N���[�̊O��ɂ���q�����E�~�[�i�[���Ƃ������ł���B�t�@�e�[�v���E�X�B�[�N���[�ɂ͂Q�����Ƃ����������A�q�����E�~�[�i�[���i���̓��j�͉����čs�������Ƃ��Ȃ������B�����A�ŋ߃t�@�e�[�v���E�X�B�[�N���[��K�ꂽ�F�l�̎ʐ^�������Ă�������Ƃ���A���̃q�����E�~�[�i�[���̏ォ��B�����ʐ^������A���ɓo��邱�Ƃ������������߁A����s���Ă݂悤�Ǝv�����B�n�}�Ŋm�F�����Ƃ���A�ǂ������ꗿ������鐳�傩�����K�v�͂Ȃ��A�����瓹�������Ă���悤�������̂ŁA���̓��������Ă݂邱�Ƃɂ����B
�@�t�@�e�[�v���E�X�B�[�N���[�̈�Ղ́A��Ƀ��X�N�n��Ƌ{�a�n��ɕ�����Ă���B���X�N�n��ł���W���[�}�[�E�}�X�W�h�͍��ł��@���{�݂Ƃ��ċ@�\���Ă���A���ꗿ�͖����ł���B�쑤�ɂ��鍂���T�S���̃u�����h�E�_�����[�U�[�i�����j�́A���x���Ă����|�����B�����ɂ̓V�F�[�N�E�T���[���E�`�V���e�B�[�_�Ȃǂ�����B����A�{�a�n��͓��ꗿ���K�v�ŁA���݂̂Ƃ��������͂Q��������B���X�N�����ɋ߂��W���[�h�E�o�[�C�[�{�a�̓�����ƁA�A�[�O���[��i�A�[�O���[������������ŁA�t�@�e�[�v�X�E�X�B�[�N���[�̓�����j���̃f�B�[���[�l�E�A�[���i��ʉy���̊ԁj�̓�����ł���B���̃A�[�O���[��ƃf�B�[���[�l�E�A�[����������̊ԁA�i�E�o�g�E�J�[�i�[�ƌĂ���̋߂��ɁA�k�̋u�����֑����ׂ��Ώ�̓�������A�������Ă����ƕn�������ɏo��B���̒��̓����Ă����Ƌ{�a�����̗����ɂȂ����Ă���A��������q�����E�~�[�i�[���֍s�����Ƃ��ł����B�q�����E�~�[�i�[�������łȂ��A�{�a�����ɂ��ȒP�ɓ���Ă��܂������������B���͋����Ĉ����̂ŁA�I�[�g�E���N�V���[�ōs���̂͂����炭��ς��낤�B�o�C�N�ŗ����b�オ�������Ƃ������̂��B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�q�����E�~�[�i�[�� |
�� |
�@�q�����E�~�[�i�[���́A�C���h�̓����z�̒��ł��ꕗ�ς�����O�������Ă���B���̕\�ʂɏۉ��͂����ˋN�������ɓ˂��o�Ă���̂��B�ŋ߁A�C���h�e�n�Ɏc���Ă��铃�͓������������Ă��ď�܂œo��Ȃ��悤�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ������̂����i�]�����̖h�~�̂��߁j�A���̓��͊J�����ςȂ��ŁA��ɓo�邱�Ƃ��ł����B���̏ォ��t�@�e�[�v���E�X�B�[�N���[�߂�ƁA�Ȃ��Ȃ���i�ł������B�w��ɂ͍L��Ȕ����L����A�C���h�̖L������Y�قɕ�����Ă����B
�@�N���Ɍ�����Ɠ{��ꂻ���Ȃ̂ŁA���̂܂ܑ��X�ɐ�グ�ċA�H�ɒ������B�r���A���𑖂��Ă���Ƃ��ɁA�����ɑ傫�Ȍ������������B�������̌�����ڎw���đ��̘H�n�������B���傤�Ǒ��l�����͒��̖�O�\�ɏo�����鎞�ԂŁA�쌴�ł͎��鏊�Ől�X���ӂ���Ă����B���̌����̓n���F�[���[�i�@��j�������B���[���[�E�W���[���L�[�E�v���T�[�h�{�a�Ƃ����炵�����A�����͕��ꂩ���Ă���A�قƂ�ǔp�Ђ������B�����A���ɂ͐l���Z��ł����B�Z��ł���̂��A�Z�ݒ����Ă���̂��͂悭������Ȃ������B�p�ЂƂ͌��������̂́A���ʂ̕ǂ̒����ⓧ��������͂����������ꂢ�Ɏc���Ă���A���Ẳh���Â����B�Q�O�O�N���炢�O�ɍ��ꂽ�������B�ˑR�K�˂čs�����̂����A���ɏZ��ł����l�͐e�Ɉē����Ă���āA�u�F�l�ɂ����̃n���F�[���[�̂��Ƃ��Љ�Ă���v�Ɨ��܂ꂽ�B����ȕn�������ɂ���ȗ��h�ȃn���F�[���[�������Ă���̂��s�v�c�Ȃ��̂��B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
���[���[�E�W���[���L�[�E�v���T�[�h�{�a |
�� |
�@�z�e���ɋA��A�ב����������A�ߑO�W�������ɂR�l�Ńz�e�����o�������B���̖ړI�n�̓o���g�v���B���[�W���X�^�[���B�ɓ���B�o���g�v���͂P�W�`�Q�O���I�ɂ����ăW���[�g�����̖{���n�ƂȂ����s�s�ł���B�W���[�g���̓��[�W�v�[�g�Ɠ��l�Ɍ��X�O���̖������Ƃ���邪�A���[�W�v�[�g�����Љ�I�n�ʂ͉��Ɍ�����X�����������B�����A�E�҉ʊ����ł̓��[�W�v�[�g�ɏ���Ƃ���炸�A���K��������C�M���X���C���h��Ђɉʊ��ɗ��������������j�������Ă���B�W���[�g�͎�Ƀn�����[�i�[�B�ȂǂɏZ��ł���B���Ȃ݂ɁA�p���W���[�u�B�̃X�B�N���k�̓W���b�g�Ƃ������������A�W���[�g�Ƃ͊W�Ȃ��悤���B�W���[�g�͌��܂��������Ƃň��������A�Ⴆ�P�X�W�S�N�Ƀf���[�ŋN���������X�B�N���k�\���̂Ƃ��ɁA�\������������鍑����c�h�̐����ƁA�T�b�W�����E�N�}�[���c���́A�W���[�g�o�g�ł���B�܂��A���݊O����b�߂鍑����c�h�̃i�g�����E�X�B���̓o���g�v���̃}�n�[���[�W���[�̉ƌn�ł��邪�A�ނ͉����h�̂悤���B
�@�t�@�e�[�v�X�E�X�B�[�N���[����o���g�v���܂ł͖�Q�O�����B�R�O���قǂœ��������B�o���g�v���ł́A���E���R��Y�ɓo�^����Ă���P�[�I���[�f�[�I�����������ł��L���Ȍ��������A�l�������������͎̂s�X�n�̒��S�ɂ��郍�[�n�[�K���i�S�̗v�ǁj�ł������B�}�[�P�b�g���ă��[�n�[�K���܂ōs�����B
�@���[�n�[�K���́A�}�n�[���[�W���[�E�X�[���W�E�}�[���ɂ���ĂP�W���I�Ɍ������ꂽ�v�ǂł���B���̗v�ǂ́A�C���h�ōł����łȗv�ǂƂ��Ēm���Ă���B�P�W�Q�T�N�A�C���h��A���n�����������C�M���X���C���h��Ђ́A�o���g�v���ɂ��U�����d�|�����B�����A�p���l�͈��|�I�ȕ��͂��ւ��Ă����ɂ��ւ�炸�A���[�n�[�K�����ח������邱�Ƃ��ł����A����ȑ��Q���������C���h��Ђ́A�o���g�v���̃}�n�[���[�W���[�ƍu�a�������ԉH�ڂɂȂ����B�o���g�v�������͓��C���h��ЂƉi�v�����F�D���������߂Ă̔ˉ����ƂȂ�A����̓C���h�Ɨ��̂P�X�S�V�N�܂Ŏ���A���̊ԃo���g�v�������͓Ɨ���ۂ��Ƃ��ł����B���������P���������j�����������߁A�Ă����胉�[�W���X�^�[���B��}�n�[���[�V���g���B�ɂ���v�ǂ̂悤�ɁA�f�R��ǂ̎R�̏�̗v�ǂ��Ǝv���Ă������A���͕��n�̏邾�����B���͂͐[���x�ň͂܂�Ă������̂́A���܂Ō��Ă����v�ǂ̒��œ��ʌ��łƂ͎v���Ȃ��\���������B���[�n�[�K���̓��������ɂȂ��Ă���A�l���Z��ł���B�������{�a���z�����c���Ă��邪�A��w�ɂȂ��Ă�����A���@�ɂȂ��Ă�����A�܂��Ă�����A�����قɂȂ��Ă����肵���B�����ق̓��ꗿ�͂R���s�[�B�W�����́A�Α��A����A�����A���̑��}�n�[���[�W���[�̃R���N�V�����ȂǁA���܂茩�鉿�l�͂Ȃ��������A�n���}�[���i����j�͂Ȃ��Ȃ����ꂢ�ɕۑ����Ă���A�ꌩ�̉��l���������B�܂��A�����ق̉��̏������u�̏�ɂ͓S���������Ă���A�\�ʂɂ̓o���g�v�������̃}�n�[���[�W���[�̉ƌn�}�Ȃǂ����܂�Ă����B���̑��A�o���g�v���s�X�ɂ̓K���K�[���@�A�W���[�}�[�E�}�X�W�h�A���N�V���}�����@�Ȃǂ̌��z�����c���Ă���B�P�P�����Ƀo���g�v�������B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
|
���[�n�[�K���̓�����A���[�q���[�� |
|
|
 |
|
|
������ |
|
|
 |
|
|
�L�V���[���[�{�a
���ɂ͓��ꂸ |
|
|
 |
|
|
�S�� |
|
|
 |
|
| �� |
�ƌn�}�����܂�Ă��� |
�� |
�@���Ɍ��������̂́A�o���g�v������k�ɂR�T�����̒n�_�ɂ���f�B�[�O�B�f�B�[�O���o���g�v�������̓s�s�ŁA�Ă̓s�������ꏊ���B�o���g�v������f�B�[�O�֍s�����́A�v���Ă����قLj����Ȃ��������A�r�������ȑ��̒��̓��ɂȂ�ƁA�r�[�ɓ��H�ܑ̕��͔�����s�����Ă���A�����Ȉ��H�ƂȂ��Ă����B�f�B�[�O�ɂ͂P�Q���O�ɓ��������B
�@�f�B�[�O�͍��ۓI�Ȋό��n�A�[�O���[�̋߂��ɂ���Ȃ���A�قƂ�ǖ����̓s�s�ł���B�������A�f�B�[�O�Ɏc���Ă���W�����E�}�n���i���̋{�a�j�́A�K�́A�ۑ���ԁA���z�I���j�[�N���ŁA�����Ɩ���m���Ă��������݂ł���Ɗ������B�P�W���I�Ƀ}�n�[���[�W���[�E�X�[���W�E�}�[���ɂ���Č������ꂽ�W�����E�}�n���́A���[�W�v�[�g���z�ƃ��K�����z�̐ܒ��l���ƂȂ��Ă���B���K�����z���L�̎l���뉀�𒆐S�ɓ�����k�Ƀ��[�W�v�[�g���z���̋{�a���������сA����ɓ����ɂ͋���Ȓ����r������B�}�n�[���[�W���[�̓N���V���i�_�̐M�҂��������߁A�{�a�̌����ɂ̓N���V���i�ɊW���閼�O���t�����Ă���B�P�X�V�O�N��܂Ń}�n�[���[�W���[�����ۂɂ����ɏZ��ł�����������A�ۑ���Ԃ͂��Δ����Ă悢�B�{�a�����ɂ̓}�n�[���[�W���[���g�p���Ă����i�X���W������Ă���B���̒��ł���ۓI�������̂́A���ɂ���S�[�p�[���E�o���@���̑�L�ԁB�ґ�Ȓ��x�i���u����Ă������A�V�䂩��݂艺����ꂽ����Ȑ���|�I�������B���g����������K����R���g���Đ��h�炵�A�L�ԑS�̂ɕ��𑗂��Ă����������B�c�O�Ȃ��猚�������͎ʐ^�B�e�֎~�������B�쐼���ɂ���X�[���W�E�o���@���́A�^�[�W�E�}�n���Ɠ������S�̂����嗝�ō���Ă���B�암�ɂ���L�V�����E�o���@���̉���ɂ͋���Ȓ����r������A���̐��ɂ���Ē뉀�S�̂ɐ����s���n�点�Ă����������B�k���ɂ���i���h�E�o���@���́A�N�V���e�B�[�i�C���h���o�j�̃A�J�[���[�i����j�ɂȂ��Ă����炵���B�����A�l�������K�ꂽ�Ƃ��ɂ͏C�����Œ��ɓ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
|
�W�����E�p���X
�S�[�p�[���E�o���@���ƒ����r |
|
|
 |
|
| �� |
�n���f�[���E�o���@���ƒ뉀 |
�� |
�@���́A�W�����E�}�n���ɂ��钲�x�i�⌚�z���́A���K�������̎x�z���ɂ������f���[��A�[�O���[���痪�D���ė������̂������B�W���[�g�̓��K�������Ɉُ�ȑR�ӎ���R�₵�Ă���A���g�̋{�a�����K�������ȏ�̂��̂ɂ��悤�Ɩ�N�ɂȂ��Ă����Ƃ����B�A�[�O���[�̃^�[�W�E�}�n�����W���[�g�̗��D���Ă��邵�A�f���[�̃��b�h�E�t�H�[�g���W���[�g�̍U�����Ă���B
�@�W�����E�}�n���̓��ꗿ�̓C���h�l�T���s�[�A�O���l�P�O�O���s�[�B�l�̓C���h�̊w���Ƃ������ƂłT���s�[�œ��邱�Ƃ��ł����B
�@�f�B�[�O�͂��傤�ǃ}�g�D���[�̐��S�O�����قǂ̒n�_�ɂ���B�f�B�[�O�ό����I������X�́A�}�g�D���[��ڎw���ē��Ɍ��������B�����A���̓������͍���̃c�[�����O�̒��ōň��������B���Ƒ����Ȃ����͈����Ȃ��ܑ����H���������A���̒��ɓ���ƓD���̂悤�ȓ��H�ɂȂ����肵�āA���ɋ�J�����B�f�B�[�O�ƃ}�g�D���[�̊Ԃɂ̓S�[���@���_�����������B�S�[���@���_���ɂ́A�N���V���i�������グ���R�Ƃ��ėL���ȃS�[���@���_���R������B�R�`�S�N�O�ɃS�[���@���_���ɗ������Ƃ��������̂ʼn������������B���̂܂܃S�[���@���_����ʉ߂��č����Q�����ɏo���B���H�͂܂��}�g�D���[�߂��̃}�N�h�i���h�ł��邱�ƂɂȂ��Ă����̂ŁA��U�A�[�O���[���ʂ������āA�}�N�h�i���h�ŋx�e�����B
�@��̓f���[�Ɍ������Ĉ꒼���ɋA�邾���������B�����łR�l�̊ԂłЂƂ̎��݂��s�����Ƃō��ӂɎ������B��X�̏���Ă���o�C�N�̓��A�A���r�V�����͔r�C�ʂP�R�T�����ŁA���͉����p�̃o�C�N�ł͂Ȃ��B����ăX�s�[�h���o�����Ƃ��ł��Ȃ��B�����W�O�����o���ƃn���h�����u���u���k�������Ƃ����L�l�ł���B����āA��X�͎����V�O������ڈ��ɍ��܂ő��s���Ă����B�������A�l�̃J���Y�}�����ɑ��s�����P�O�O�O�������z���A���낻�늵�炵�^�]�𑲋Ƃ��ăX�s�[�h���o�������Ȃ��Ă������A�p���T�[���{�̂��������ăE�Y�E�Y���Ă����B�����ŁA�A���r�V�����ɂ͂Q�O�������o�Ă�����āA�P�W�O�����̃p���T�[�ƂQ�Q�T�����̃J���Y�}���ォ�獂���Œǂ������Ēǂ������ǂ��������Ă݂邱�Ƃɂ����B�A���r�V�����̓}�g�D���[�̃}�N�h�i���h���ߌ�Q���Q�O�����ɏo���B���̌�A�Q���S�O���ɃJ���Y�}�ƃp���T�[���o���B�A���r�V�����͑�̎����U�O�`�V�O�����ő��s���A�J���Y�}�ƃp���T�[�͎����X�O�`�P�O�O�����ő��s�����B�}�g�D���[�̃}�N�h�i���h����f���[�܂Ŗ�P�T�O�����B���낢��Ȍ덷���܂߂āA�t�@���[�_�[�o�[�h�ӂ�Œǂ����v�Z�ɂȂ��Ă����B
�@�܂��A���͂��̂Ƃ��A�K�\���������s�������Ă����B�p���T�[�͂ǂ��������V�O�����ő��s���邭�炢����ԔR������悤�ŁA�R���ɗ]�T�����������A�A���r�V�����ƃJ���Y�}�͊��ɔ����ȉ��ƂȂ��Ă����B�}�N�h�i���h�̂����ׂɃK�\�����X�^���h�����������߁A�����ŋ�����������̂����A��������X�̓X�s�[�h�X�R�Ƃ��������K�\���������o�C�N�ɓ���Ȃ��Ƃ����������������Ă���A���̃K�\�����͂Ƃ肠�����f���[�ł�����ɓ���Ȃ��̂ŁA�f���[�܂ŋ��������ɒ��s����q���ɏo�邱�Ƃɂ����B�M���M���H�蒅���邩�H�蒅���Ȃ����炢���̋����ł���B
�@�}�g�D���[����f���[�ɒʂ��鍑���Q�����́A�O�q�̒ʂ肫�ꂢ�ȕܑ����H�Ȃ̂ŁA�X�s�[�h���o���ɂ͐\�����̂Ȃ����ł���B���ƌ����āA���{�̍������H�ł͂Ȃ��̂ŁA�r���Ől�⌢�⋍���������肷�邽�߁A���̋߂��Ȃǂł͒��ӂ��đ��s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����ł��A���������Ƃ͂����Ă���������邱�Ƃ͂��܂�Ȃ��̂ŁA�����V�O�����ő����Ă���Ƃ������_�o���g�킸�ɍςB�m���X�g�b�v�ő��s���Ă�����A��̌v�Z�ǂ���A�S���P�T�����A�t�@���[�_�[�o�[�h�ɓ����O�ŃA���r�V�����ɒǂ������Ƃ��ł����B�t�@���[�_�[�o�[�h�ɂ���N���E���E�v���U�ɂ�����Ƃ�����������āA�f���[��ڎw�����B�f���[�̓�����A�o�_���v���ɓ���ӂ�ŁA�A���r�V�����ƃJ���Y�}���������Ń��U�[�u�^���N�ƂȂ����B�J���Y�}�̃��U�[�u�^���N�͂Q���b�g���B���_��̓��U�[�u�^���N�łW�O�������炢����邱�ƂɂȂ��Ă��邪�A�����܂ŃK�\�����^���N���g���������Ƃ͂Ȃ������̂ł��Ȃ�s�����B�o�_���v���͏�ɍ��G���Ă���A�Ȃ��Ȃ��i�܂Ȃ��������A������ăA�|���a�@�̑O��ʂ�A���Ƃ��l���[�v���C�X�̃o�[���g�E�y�g�����A���܂ŒH�蒅�����B�����ŃX�s�[�h�X�R���P�Q�D�P�U���b�g�������B����K�\���������������Ƃ��Ƀ[���ɂ����g���b�v�E���[�^�[�͂T�O�X�D�Q�������w���Ă����B�܂�R��̓��b�^�[�S�P�D�W�V�T�����B�s�X�n�∫�H�𑖍s�������Ƃ��l����A�Ó��Ȑ������낤�B����A�p���T�[�͂ǂ���玞���X�O�����O��ő���ƔR������悤�ŁA�}�g�D���[����f���[�ɖ߂�Ԃɑ�ʂ̃K�\����������A�R��̓��b�^�[�S�R�����قǁB�A���r�V�������X�s�[�h���o��������ƔR������A���b�^�[�S�V�����قǂ������B
|
|



