本日、期末テストが終了した。と同時に、2年間のヒンディー語修士課程が終了したことになる。一応このままM.Phil(博士課程準備期間)に進学する予定であるが、不確定な要因が多いので、すんなり進学できるとは限らない。それはそうとして、参考までに、ヒンディー語修士課程の2年目のカリキュラムを振り返ってみよう。1年目のカリキュラムは、2004年5月2日の日記に書いた。
7月〜12月のモンスーン学期には、「ヒンディー語の随筆とその他の散文学」、「近代ヒンディー語詩」、「現代ヒンディー語詩」、「近代西洋文学理論」の4つの授業があった。「ヒンディー語の随筆とその他の散文学」では、ヒンディー散文学の歴史に加え、以下の文学者の作品を読んだ(ちなみに作品のアルファベット表記は、本に表記がある場合はそれに従い、そうでない場合は適当に書いた。ヒンディー語の書物のアルファベット表記には一定の決まりがないが、映画の題名の表記がかなり近いと思う)。
●随筆:
バールクリシュナ・バット「Chali So Chali」「Naye Tarah Ka Janoon」
プラタープ・ナーラヤン・ミシュラ「Samajhdaar Ki Maut Hai」「Nyaay」
チャンドラダル・グレーリー・シャルマー「Kachhua Dharm」
ラームチャンドラ・シュクラ「Lobh Aur Preeti」
ハザーリー・プラサード・ドイヴェーディー「Kutaj」
●旅行記
バーラテーンドゥ・ハリシュチャンドラ「Sarayu Paar Ki Yatra」
ニルマル・ヴァルマー「Safed Ratein Aur Hawa」
●自伝・伝記
パーンデーイ・ベーチャン・シャルマー・ウグル「Apanee Khabar」
ラーム・ヴィラース・シャルマー「Nirala Ki Sahitya Sadhana vol. I」
●写生文・ルポルタージュ
マハーデーヴィー・ヴァルマー「Bhaktin」など
パニーシュワルナート・レーヌ「Reportage」
この授業は、読む量が多くて非常に大変だった覚えがある。特に、ヒンディー文学界の異端児、スーリヤカーント・トリパーティー・ニラーラーの伝記である「Nirala
Ki Sahitya Sadhana」は、500ページ以上の大作で、読むのに骨が折れた。ニルマル・ヴァルマーの「Safed Ratein Aur
Hawa」は、アイスランドの旅行記で、何となく僕もアイスランドへ行ってみたくなった。
「近代ヒンディー語詩」は、1920年〜1936年くらいまでの詩で、俗に言うチャーヤーワード(陰影主義)の詩を読んだ。具体的には、
●スミトラーナンダン・パント
「Baadal」、「Parivartan」、「Sandhya Ke Baad」
●マハーデーヴィー・ヴァルマー
「Dheere Dheere Utar Kshitij Se」、「Main Neelbhari Dukh Ke Badli!」、「Panth Hone Do Aparichit Praan Rehne Do Akela!」、「Yeh Mandir Ka Deep Ise Neerav Jalne Do!」、「Tu Dhoot Bharaa Hi Aaya」、「Sab Aankhein Ke Aansu Ujle」、「Puchhta Kyon Shesh Kitni Raat?」など
●スーリヤカーント・トリパーティー・ニラーラー
「Saroj Smriti」、「Ram Ki Shakti Pooja」、「Kukurmutta」
●ジャイシャンカル・プラサード
「Kamayani」
ヒンディー語と一口に言っても、いろいろな形態のヒンディー語があり、方言もたくさんある。現在インドの第一公用語になっているヒンディー語は、カリー・ボーリーというデリー周辺部の一方言が発達してできたものである。だが、ヒンディー文学史で詩の言語として長い間君臨して来たのは、マトゥラー周辺のブラジ方言や、アヨーディヤー周辺のアワディ方言であり、カリー・ボーリーで詩が作られるようになったのは20世紀に入ってからだ。しかもそれが詩にふさわしい言語になるのは、このチャーヤーワードの時代からである。特にパントやニラーラーの詩に惹かれた。
「現代ヒンディー語詩」では、主にインド独立後の詩を扱った。
●サッチダーナンド・ヒーラーナンド・ヴァーツヤーヤン・アギェーイ
「Aaj Tum Shabd Na Do」、「Haree Ghaas Par Kshan Bhar」、「Asaadhya Veena」
●シャムシェール・バハードゥル・スィン
「Saagar Tat」、「Ek Peeli Shaam」、「Tootee Hui Bikhree Hui」など
●ナーガールジュン
「Akaal Aur Uske Baad」、「Sindoor Tilkit Bhaal」、「Shaasan Ki Bandook」、「Paine
Daantonwaali」、「Baadal Ko Ghirte Dekha Hai」、「Newlaa」、「Kalpna Ke Putr Hai
Baghwaan」、「Pratibaddh Hoon」など
●ガジャーナン・マーダヴ・ムクティボード
「Andhere Mein」
創造性を象徴的に謳った詩や、個人の内面を見つめる詩、または社会風刺など、多種多様な詩が作られるようになった時代で、韻律などに捉われない自由な形式の詩が主流を占める。マルクス主義の影響も強い。シャムシェールの「Chin
Desh Ka Naam(中国の名前)」という詩は、「中」「華」「人」「民」「共」「和」「国」という七文字の漢字を題材に作られた詩であり、「なんじゃこりゃ」である。ムクティボードの「Andhere
Mein」は読んでで陰鬱になる詩だ。
「近代西洋文学理論」では、プラトン、アリストテレス、ロンギヌスなどの古代ギリシアの哲学者から、ワーズワース、コールリッジなどのロマン主義思想家、TSエリオット、IAリチャード、ロシア形式主義、構造主義、フェミニズムなどの文学理論を学ぶ。はっきり言って、ヒンディー語の文学を学びに来たのに、なぜ西洋の文学理論を学ばなければならないのか不満に思う。だが、割と近代のヒンディー文学者たちは西洋の文学理論にも影響を受けているので、学んでおいて損はないと思った。
1月〜5月の冬学期では、「ヒンディー文学の批評家と批評」、「文学とイデオロギー」、「ヒンディー語の戯曲と演劇」、「特定の文学者の研究」の4つの授業があった。「ヒンディー文学の批評家と批評」では、バーラテーンドゥ・ハリシュチャンドラ、マハーヴィール・プラサード・ドイヴェーディー、ミシュラ・バンドゥ、ラームチャンドラ・シュクラ、ハザーリー・プラサード・ドイヴェーディー、ラーム・ヴィラース・シャルマー、ガジャーナン・マーダヴ・ムクティボード、ナームワル・スィンなどの文学批評について学んだ。実質的にヒンディー文学の批評が現代的な意味での批評の形を成すのはラームチャンドラ・シュクラからである。
「文学とイデオロギー」では、「イデオロギー」という言葉の発達を、アントワーヌ・デストゥット・ド・トラシーやナポレオン・ボナパルトから、カール・マルクス、フリードリッヒ・エンゲルス、アントニオ・グラムシー、ルイ・アルチューセル、カール・マンハイムなどの思想を通し、ポスト・モダニズムまで概観する他、文学とイデオロギーの関係について学んだ。この授業はほとんどマルクス主義洗脳授業でかなりタフだった。
「ヒンディー語の戯曲と演劇」では、ヒンディー語の戯曲の歴史の概観と同時に重要な戯曲作家の作品を読んだ。
●バーラテーンドゥ・ハリシュチャンドラ
「Andher Nagri」
●ジャイシャンカル・プラサード
「Skand Gupta」
●ダルムヴィール・バーラティー
「Andha Yug」
●モーハン・ラーケーシュ
「Aashaadh Ka Ek Din」
●ビーシュマ・サーハニー
「Hanoosh」
ヒンディー語とヒンディー文学は、他の言語や文学と比べて、演劇の影響を強く受けている。先にも述べたカリー・ボーリー方言は、インダル・サバーやパールスィー劇団など、19世紀〜20世紀初頭にかけて活躍した商業的巡回演劇により大きく普及・発達した。戯曲の創作は、ヒンディー散文学の発展を促した。また、これらの演劇は、ボリウッド映画の原型と言えるほど、インド映画にも多大な影響を及ぼしている。「Skand
Gupta」が最も難解で、「Andha Yug」の理解にはマハーバーラタの知識が必須となるが、あとの戯曲は分かった。
「特定の文学者の研究」では、カビール、トゥルスィーダース、プレームチャンド、ニラーラーの4人の文学者の中から1人を選んで、研究を行う。僕はプレームチャンドを選んだ。プレームチャンドの授業は、教授がかなり厳しい人なので、おそらくこれら4つの中で最も難しい。半年の間に読んだ作品は、長編小説では「Sevasadan」、「Premashram」、「Rangbhoomi」、「Nirmala」、「Karmbhoomi」、短編小説では「Balidaan」、「Vidhwans」、「Poos
Ki Raat」、「Sadgati」、「Doodh Ka Daam」、「Thaakur Ka Kunaa」、「Shatranj Ke Khiladi」、「Satyagraha」、「Samar-Yatra」、「Do
Bailon Ke Katha」など、戯曲では「Sangram」である。この他、プレームチャンドの伝記であるシヴラーニー・デーヴィー著「Premchand
Ghar Mein」、アムリト・ラーイ著「Premchand Qalam Ka Sipahi」、マダン・ゴーパール著「Kalam Ka Mazdoor
Premchand」や、評論であるラーム・ヴィラース・シャルマー著「Premchand Aur Unka Yug」、ハンスラージ・レヘバル著「Premchand:Jivan,
Kala Aur Krititva」、ナンドドゥラーレー・ヴァージペーイー著「Premchand: Sahityik Vivechan」、カマルキショール・ゴーエンカー著「Premchand:
Adhyayan Ke Nayee Dishaaen」、ヴィール・バーラト・タルワール著「Kisan, Rashtriya Andolan Aur
Premchand; 1918-1922」などを読まなければならなかった。ここ半年間は、プレームチャンドを中心に生活をしていたようなものだ。
ジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)では特に卒業式などなく、テストが終わればそれでカリキュラム終了となる。かなりあっけらかんとしている。大半の学生がM.Philに進学するので、お別れムードなどはない。また、インド人学生は進学のためにテストがあるので、期末テストが終了しても引き続き勉強を続けなければならないという事情もある。外国人留学生はドル箱なので、別枠で審査があり、インド人学生よりも容易に進学できる。
本日付のインディアン・エクスプレス紙に、興味深いというか、とんでもない記事が掲載されていた。
北京オリンピックまであと3年あるが、ウッタル・プラデーシュ州スポーツ省のRKチャウドリー大臣は既に必勝プランを温めている。チャウドリー大臣は、インドのスポーツをカーストとコミュニティーを基準にしたものにし、才能育成のためのカースト寮を設立することを計画している。
チャウドリー大臣は、「大道芸人カーストのナトは、体操の才能を持っている。マッラー、ケーワト、ヴィンディヤー、ニシャード、カシヤプは、天性のスイマー、天性のダイバーである。アヒール、ゴースィー、ガッディーは天然のレスラーであるし、アーディワースィー、アヘーリヤーは弓技の天才だ」と述べた。
この考えは政治的に正しくないように聞こえるが、大臣によるとこの仮説はアテネ五輪で実証されたという。米国では60年代に市民権運動が活発になり、アフリカ系米国人の雇用が促進された。その結果として、アテネ五輪で米国が獲得した100枚以上のメダルの内、3分の1は黒人選手によるものだった。一方、インドはたった1枚しかメダルを獲得できなかった。
既にウッタル・プラデーシュ州で、カーストを基準としたスポーツ寮「Diversity Sports Hostel」の建設工事が始まっている。スポーツ大臣は、5年以内にこの寮から国際的レベルのスポーツ選手が生まれると太鼓判を押している。
チャウドリー大臣は、「今まで、我々は社会の上層部のみを訓練してきたが、その結果、国際的スポーツ選手はほとんど生まれてこなかった。しかし、カーストとコミュニティーを基準に訓練を開始すれば、毎年何百人ものスポーツ選手を誕生させることができる」と述べた。
しかしながら、スポーツ局は既に困惑している。なぜなら、大規模なカースト人口調査と「先天的な」スポーツの才能の調査を行わなければならないからだ。大臣自身も、最近は図書館に閉じこもって研究している他、インターネットを使ってさらなる情報を集めている。
チャウドリー大臣は、「我々は子供たちを寮に送るよう両親を説得しなければならない。後進カーストやダリトの家族は通常、子供たちを稼ぎ要員と考えており、学校に通学させようとしない」と述べた。
上の記事で語られている「カースト」とは、日本の世界史の教科書で習う、バラモン(ブラーフマン)、クシャトリヤ、ヴァイシャ、シュードラのカーストではなくて、さらに職業別に分かれたジャーティのことだと思ってもらいたい。以後の文章もそのつもりで書く。
インドではカーストは憲法で否定されているものの、カーストなしには動いていかない社会なので、これからも根絶することはないだろう。カーストを基準とした留保制度(学校、官庁、企業などへの優先枠)が法律で決められていることも大いに憲法と矛盾している。カーストは負のイメージで見られることが多いが、必ずしも悪いことばかりではない。カーストの遵守は一種の社会保障制度となっており、社会の分業にも役立っている。その一方で、カースト間の格差を是正するために設けられた留保制度が、逆に高カースト者の入学や雇用を圧迫したり、社会の歯車の障害となっているという現実もある。僕のクラスでも、留保枠で入ってきた学生(つまり後進カースト)と、それ以外の学生(つまりブラーフマン階級など)の学力レベルには歴然とした差が見受けられた。カーストを巡る問題は一言では語りつくせないほど複雑で根深い。だが、そのカーストをうまく利用して、スポーツ振興をしてしまおう、という、突拍子もない能天気なアイデアを打ち出した政治家が現れた。大衆社会党(BSP)の政治家で、ウッタル・プラデーシュ州政府でスポーツ大臣を務めるRKチャウドリーである。
カースト制度により、インドの人々は代々同じ職業を続けてきた。時代の変遷と共に新たなカーストが生まれたり、枝分かれしたり、外部から移住してきた民族が新たなカーストになったりと、話はそれほど単純ではないが、この国は、たとえ異民族でも代々住み続けることにより、いつの間にかカースト制度に組み込んでしまい、何らかの職能を分担させるという包容力を持っている。特殊な能力を要するカーストに、代々培われてきた先天的特殊能力が備わっていると考えることは、インドの社会を観察する者なら誰でも思いつくことだ。英領インド時代の英国人も同じことを考え、スィク教徒たちを「戦闘に優れたカースト」と認知して、軍隊に積極的に登用した。僕もそれについて少し考えたことがある。米国の有名なジャズ・シンガー、ノラ・ジョーンズの父親は、インドの有名なスィタール奏者、ラヴィ・シャンカルである。しかし、ノラ・ジョーンズは生まれてから一度も父親に会っていない。よって、父親の後天的影響はゼロと言っていいだろう。それなのにノラ・ジョーンズは天才的な音楽の才能を持っている。これを「偶然」の一言で片付けることもできるが、もしかしたら代々培われた先天的な音楽家のDNAが、ラヴィ・シャンカルからノラ・ジョーンズへ受け継がれて花開いたのかもしれない。だから、もしかしたらオリンピックなどの国際競技に適合する特殊能力を先天的に受け継ぐカーストがインドにいるかもしれない・・・。
が、それにしても、カーストを基にして国際的スポーツ選手を育成するというのは、あまりにも短絡的な計画ではなかろうか。例えば大道芸人カーストのナトにしても、確かに一般人には真似できないようなアクロバットを披露したりしているが、それが五輪の体操などにそのまま通用するかと言われれば、それはかなり疑問だ。インドにはクシュティーという相撲があり、レスリングはけっこう馴染みのある競技だ。何を隠そう、インド独立後、個人種目でインド人が初めてメダルを獲得した種目はレスリングである。マハーラーシュトラ州サーターラー近くの農村出身の力士、カーシャバ・ジャーダヴが、1952年のヘルシンキ五輪で銅メダルを獲得している。ジャーダヴというカースト名から察するに、彼はアヒール(牛飼いカースト)の一種だと思われる。なぜ牛飼いカーストが力士になるのか、僕はよく分からない。牛乳を飲んでいるから身体が丈夫なのだろうか。だが、やはり田舎で力士をやるのと五輪で競技をするのとでは雲泥の差がある。あと、ノース・イーストかどこかの部族が何かの祭りで弓を射ているシーンをTVで見たことがあるが、的に全然当たっていなかった。獲物を取るための弓術と、五輪のアーチェリーも、はっきり言って完全に別物だろう。
スポーツ選手の裾野を広げることが重要であるのは確かだ。現在のインドのスポーツ界で活躍している選手たちは、ほとんどが都市部の中上流階級の人々である。それでもテニスのサーニヤ・ミルザーや、F1のナーラーヤン・カールッティケーヤなど、国際的なスポーツ選手が誕生しつつある。しかし、10億人の人口と比較して考えると寂しすぎる。単純に計算しても、日本人の10倍のスポーツ選手がいてもおかしくないはずだし、国際レベルで通じる選手も10倍出てくるべきだ。そう考えると、チャウドリー大臣の試みは、貧困層の才能ある子供たちにチャンスを与え、インドスポーツ界の裾野を広げるきっかけになるかもしれない。
だが、一番不安なのは、このチャウドリー大臣が、理論先行型の学者肌な人物に思えることだ。カーストとスポーツ振興を結びつけるというアイデアはなかなかユニークだが、図書館やインターネットで情報収集というのは、何だか机上の空論に終わりそうで怖い。スポーツ振興や才能発掘をしたいのだったら、もっと現場へ出て行って、その計画が実現可能かどうか自分の目で吟味すべきである。米国で黒人選手が活躍している、という例も、論点がずれているように思えてならない。
仮にカーストを基準にスポーツ選手を育成するとして、果たしてどのカーストからどんなスポーツ選手が生まれやすいだろうか?・・・しばらく考えてみたが、あまり思い付かない。サイクルリクシャー・ワーラーに競輪でもやらせてみたらどうか・・・とか、20kgある水のボトルや、かなり重いガスシリンダーを各家庭に届ける仕事をしている人々、または冷蔵庫を1人で運ぶ脅威の身体能力を持つ引越し屋などに重量挙げをやらせてみたら・・・とか、チャウドリー大臣並みの考えしか浮かばない・・・。それにカーストともあまり関係ない。そもそもカーストとは生活に必要な活動を行うためのものであり、スポーツのような非生産的な活動のためにはうまく機能しないのではなかろうか。そう考えると、やはり経済的にも時間的にも余裕のある中上流階級がスポーツを担っていくしかないように思える。
| ◆ |
5月7日(土) Kyaa Kool Hai Hum |
◆ |
今日はPVRプリヤーで新作ヒンディー語映画「Kyaa Kool Hai Hum」を見た。題名は、「何てクールなんだ、オレたち」という意味。その題名から容易に察することができるように、冴えない男たちが一生懸命クールに振舞う姿がおかしいコメディー映画である。監督は「Chura
Liya Hai Tumne」(2003年)のサンギート・シヴァン、音楽はアヌ・マリク。キャストは、トゥシャール・カプール、リテーシュ・デーシュムク、アヌパム・ケール、イーシャー・コーッピカル、ネーハー・ドゥーピヤー、ボビー・ダーリン、ラッザーク・カーン、ラージパール・ヤーダヴなど。
| Kyaa Kool Hai Hum |
 ラーフル(トゥシャール・カプール)とカラン(リテーシュ・デーシュムク)は、それぞれに夢と野望を持ってムンバイーへやって来た若者だった。真面目で誠実なラーフルは、デザイナーになるのが夢だった。また、占い師から「胸にホクロのある女性が福を呼び込む」と伝えられ、そのような女性が現れるのを待ち望んでいた。一方、お調子者のカランは、金持ちで美人の女の子と結婚して逆玉の輿を狙っていた。2人はデザイナーDKの経営するブティックで働いていた。【写真は、左からトゥシャール・カプール、ネーハー・ドゥーピヤー、イーシャー・コーッピカル、リテーシュ・デーシュムク】 ラーフル(トゥシャール・カプール)とカラン(リテーシュ・デーシュムク)は、それぞれに夢と野望を持ってムンバイーへやって来た若者だった。真面目で誠実なラーフルは、デザイナーになるのが夢だった。また、占い師から「胸にホクロのある女性が福を呼び込む」と伝えられ、そのような女性が現れるのを待ち望んでいた。一方、お調子者のカランは、金持ちで美人の女の子と結婚して逆玉の輿を狙っていた。2人はデザイナーDKの経営するブティックで働いていた。【写真は、左からトゥシャール・カプール、ネーハー・ドゥーピヤー、イーシャー・コーッピカル、リテーシュ・デーシュムク】
そのとき、女性を狙った連続殺人犯がムンバイーで暗躍していた。ひょんなきっかけからラーフルがその容疑者となってしまった。ムンバイー警察は、著名な犯罪心理学者、スクリューワーラー博士(アヌパム・ケール)の指示に従い、美人のおとり捜査官をラーフルのもとへ送り込み、現行犯逮捕する作戦、ミッション・フェイルを始動する。おとり捜査官には、レイプ犯などの「女性の敵」への激しいお仕置きで知られるウルミラー・マルトードカル(イーシャー・コーッピカル)が選ばれた。ウルミラーの胸にはホクロがあったため、ラーフルは彼女を歓迎し、一緒に住むように言う。ウルミラーはラーフルと一緒に住み始める。
一方、カランは、DKの恋人キラン(ボビー・ダーリン)と電話で話し、一気に恋に落ちてしまう。キランは大金持ちの娘だったが、両親によって部屋に閉じ込められ、外に出られなかった。また、DKとはケンカをしており、DKは彼女に告げずに米国へ1ヶ月の旅行へ行ってしまっていた。カランはキランの資産目当てで彼女を電話で誘惑し、彼女と結婚しようとする。しかし、キランの両親はカランを追い出す。実はキランはオカマだった。だが、そうとは知らないカランは、電話の声だけでキランに言い寄っていたのだった。不安になった両親は、キランの妹で心理学者のレーカー(ネーハー・ドゥーピヤー)に相談する。レーカーはカランと会うが、実はカランとレーカーは学生時代の知り合いだった。カランはレーカーに「オレと暇つぶししない?」と軽い口調で告白し、レーカーに平手打ちをくらったという過去があった。レーカーは、普通の男の子だったカランが、同性愛者になってしまったのは自分の責任だと考える。レーカーは実はスクリューワーラー博士の教え子で、彼に相談したところ、スクリューワーラー博士はレーカーに、カランを誘惑して女性に興味を再び持つよう仕向けるように助言する。レーカーはカランと何度も会い、愛の告白までするが、キランの財産に目がくらんでおり、しかもキランを男性だとは知らないカランは、キランへの愛を曲げようとしなかった。レーカーは次第にカランに惹かれるようになる。
また、スクリューワーラー博士の妻パールワティーは、夫が若い女性たちと密談しているところを何度も見て嫉妬し、ジムへ通ってシェイプアップを始める。
ウルミラーはラーフルと暮らす内に、ラーフルが女性をレイプして殺害するような人間だとは信じられなくなる。また、いつの間にかラーフルを愛するようになってしまう。だが、警察はラーフルを犯人だと決めつけ、彼の顔を新聞に載せて指名手配する。
一方、DKが旅行から帰って来たことにより、カラン、キラン、DKの三角関係が発生する。キランの両親は、カランもDKもお断りだった。DKは真夜中部下を家に侵入させてキランを誘拐しようとするが、ラーフルがその中に紛れ込み、キランを連れてカランの下へ急ぐ。カランは寺院で結婚式の準備をしていた。いざ結婚式を挙げようとすると、そこへDKやレーカーが辿り着く。カランとラーフルはキランの顔をよく見てみると男であることに気付き仰天する。DKはキランを連れて去っていく。ショックから立ち直れないカランだったが、傍にいたレーカーを見て、彼女にもう一度告白をする。レーカーはそれを微笑んで受け容れる。
ラーフルは自宅へ帰るが、大勢の人が詰め掛けていた。警察がラーフルの家を家宅捜索していたのだ。群衆の1人がラーフルが指名手配犯であることに気付く。ラーフルは何が何だか分からずに逃げ出す。一度は警察に捕まりそうになるが、ウルミラーに助けられる。しかし、そのとき警察署に自首してきた男(ラージパール・ヤーダヴ)がいた。その男は、有名になりたいがために連続殺人をしていた異常者だった。警察とスクリューワーラー博士は急に態度を変え、ラーフルを犯人逮捕のための協力者だったということにしてしまう。こうして、ラーフルとウルミラー、カランとレーカーというカップルが生まれたのだった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
下ネタ連発のお下劣コメディー映画。だが、セリフがよく考えられていた上に、笑いの中にホロリと涙があり、よく出来た映画だった。俳優の特徴や演技も最大限に引き出されていた。しかし、これだけお下劣なネタが連発されるインド映画は初めて見たかもしれない。
主人公のラーフルとカランは、正反対の性格のコンビだったが、ひとつ共通点があった。それは、女性とまともに付き合ったことがないことだ。ラーフルは真面目で恥かしがり屋な性格で、女性の前でいつも上がってしまっていた。一方、カランは、一見プレイボーイ風で、ラーフルに対し事あるごとに自分の派手な女性体験を自慢するが、実はいつもナンパした女性から散々な目に遭っていた。そんな2人が恋人をゲットするまでの騒動を描いた映画だった。
どんなお下劣シーンがあるのかは見てもらえば分かるが、例えばこんなシーンがあった。ラーフルがバリスタ(喫茶店)でコーヒーを飲んでいると、左胸にホクロがある色っぽい女の子を見つけた。ラーフルはその女の子を追いかけようとするが、そのとき女の子は階段でつまづいてバッグを落としてしまう。バッグと中身を拾おうと女の子がかがむと、ミニスカートからパンツが丸見えだった。と、そのときラーフルのパンツの中に偶然火の付いたタバコが入ってしまった。ラーフルは異変に気付いて慌て、股間を揉みしだく。最後にズボンの中に水を注ぎ込んで安堵の表情を浮かべる。その様子を警察の密偵がビデオカメラで撮影していた。ビデオで見ると、まるでラーフルが女の子の色っぽい姿を見て白昼堂々と自慰を始めたかのようだった。そして、ラーフルが連続殺人犯である証拠とされてしまうのだった。
トゥシャール・カプールとリテーシュ・デーシュムクは2人とも2世男優だ。トゥシャールは往年の名優ジーテーンドラの息子で、映画界やTVドラマ界でプロデューサーとして活躍するエークター・カプールの弟。リテーシュはマハーラーシュトラ州のヴィラースラーオ・デーシュムク州首相の息子。彼らはそれらのコネのおかげで映画界デビューを果たしたと言ってよく、はっきり言って三枚目の男優だ。だが、三枚目俳優が三枚目であることを自覚し、それを売りにし始めたら、これほど強いことはない。「Kyaa
Kool Hai Hum」はまさに2人にとってそんな映画だった。トゥシャールは「Gaayab」(2004年)で冴えない男を演じ、僕は彼に「ボリウッド界ののび太君」という称号を与えたが、その称号に恥じない駄目男振りを今回も発揮した。そしてそれが大成功を収めていた。リテーシュも、かっこつけているが実は中身のない男という役を、等身大で演じていた。
2人の男優も素晴らしかったが、それ以上にこの映画で株を上げたのがイーシャー・コーッピカルであろう。イーシャーは、「Company」(2002年)でアイテム・ガールとして出演して以来、「Khallas
Girl」として有名になったが、彼女の方向性を決定的にしたのはレズをテーマにした「Girlfriend」(2004年)であろう。スポーティーで男気のある女を演じさせたらイーシャーほどはまっている女優はいない。「Kyaa
Kool Hai Hum」では、コテコテのマラーティー語を話す暴力女警官を演じていた。イーシャーに比べたら、ネーハー・ドゥーピヤーは印象が薄かった。だが、サーニヤ・ミルザーのような黒ブチ眼鏡(インドでは「司書風眼鏡」と呼ばれる)をかけていてかわいかった。
脇役陣では、アヌパム・ケールの演技が「さすが」のレベルである。「3つのボール」理論なる奇妙奇天烈な理論を唱え、それを基に連続殺人犯の逮捕に協力するのだが、「この事象の裏にはロジックがある」とか何とか言って、ますます事件をこんがらがらせていて面白かった。
音楽はアヌ・マリクだが、「Dil Mera」の一曲だけリシ・リッチとジャイ・ショーンのコンビが手がけている。リシ・リッチーは英国在住のインド人で、今や世界的に有名になったバングラ・ミュージシャンである。ジャイ・ショーンも同じくインド系UKエイジアンで、リシ・リッチに見出されたシンガー。リシ・リッチとジャイ・ショーンは、「Boom」(2003年)の「Nachna
Tere Naal」、「Hum Tum」(2004年)の「Mere Dil Vich Hum Tum」など、コンスタントにボリウッド映画に曲を提供している。だが、「Kyaa
Kool Hai Hum」ではリシ・リッチとジャイ・ショーン、それにJuggy DとヴェロニカというUKエイジアンのミュージシャンもミュージカルに登場し、リテーシュ、トゥシャールらと踊る。
ひとつだけ、セリフの中で気になるものがあった。リテーシュ演じるカランが、ある色っぽい女の子をナンパするシーンがあるのだが、その女の子が「私には悩みがあるの。私には、ムスリムの長さか、グジャラート人の太さが必要なんだけど、なかなかそういう人が見つからないの」と言う。もちろんこれはあのことを指しているのだと思うが、ムスリムは長く、グジャラート人は太い、という認識はインド人一般のものなのだろうか。「ところであなたのお名前は?」と聞かれたカランは、「え、えっと、オレの名前はナスィーッルディーン・シャー(ムスリムの名前)」と答えるところが大爆笑である。
「Kyaa Kool Hai Hum」は、下ネタ連発のお下劣映画だが、笑いと涙のバランスがうまく取られており、ストーリーにも大きな破綻はない。優れたコメディー映画と言うことができる。
4月29日から公開されたヒンディー語映画「Kaal」。公開初日に鑑賞し、その批評をこのウェブサイトに掲載したが、ネタバレを避けるために最後まで批評をしなかった。僕はこの映画のラストを「賛否両論に分かれる」と予想したが、やはりこの映画を見て「つまらない」と思う人も少なくないようだ。だが、僕はこの映画を非常に高く評価した。ここでは、ネタバレを前提として、「Kaal」の批評をしてみようと思う。よって、まだ映画を見る予定のある人は、映画を見てからこれを読んでもらいたい。
「Kaal」のエッセンスを一言で言い表せば、虎の生息するジャングルで多発する殺人事件を描いた映画である。僕は「サファリ・ホラー」と名付けた。最初は人食い虎の仕業に見えるが、次に「誰か」が殺人を行っていることが暗示され(ヴィヴェーク・オーベローイが演じるデーヴが怪しまれる)、最後には、ジャングルを愛しすぎて狂人になってしまった男の亡霊(アジャイ・デーヴガン)が全ての殺人を行っていたことが明らかになる。
「Kaal」を「つまらない」と評価する人は、犯人を亡霊としてしまうことの幼稚さに失望していることが多いと思う。映画に現実味を求める人がこの手の人ではなかろうか。「Kaal」は、までのインド映画にないほどのドキドキ感のある映画である。カメラワークやアングルなどが工夫されており、観客の恐怖心を巧みに煽っている。だが、せっかく緻密にストーリーが展開されていたのに、最後の最後で「実は幽霊の仕業でした」とされることは、今までの臨場感溢れる展開からして我慢がならないのだろう。どうせなら生身の人間がやっていたとしてくれた方がよかった、と考えているのだろう。
だが、もし「Kaal」で殺人を行っていたのが生身の人間だったら、この映画の魅力は半減してしまっただろう。そのような展開は、ホラー映画の常套手段で、あまりに普通過ぎる。また、人食い虎の仕業だったら、それは「ジョーズ」シリーズのようなモンスター・ホラー映画に陥ってしまっていただろう。悪くはないのだが、何のメッセージ性もないただの娯楽映画になってしまっていただろう。
「Kaal」の優れている部分は、ジャングルの気持ちを1人の亡霊に託したことにある。この世界に幽霊がいるかいないかは別として、ひとつのフィクション作品の中に、何かの象徴として「幽霊」の存在を肯定的に利用することは、作品の質を低めないばかりか、高めることになりうる。「Kaal」のカーリー(アジャイ・デーヴガン)は、ただの亡霊ではなく、ジャングルそのものなのだ。ジャングルに住む動物、鳥、虫、樹木、全ての代表なのだ。そして、ジャングルを尊敬せず、ジャングルを破壊する人間たちを次々と殺しているのだ。現に、カーリーは密猟者など、森のルールを守らない人間を優先的に殺害していた。リヤー(イーシャー・デーオール)が殺されるシーンは蛇足に思えたものの、「Kaal」で殺された人のほとんどは、森を何らかの形で傷つけた人である。
カーリーのセリフにも、ジャングルからのメッセージが多く含まれていた。あまり正確には覚えていないが、「動物が人間を襲ったら、悪者にされるのはいつも動物の方だ。しかし本当に悪いのは、ルールを守らない人間の方だ」などというセリフがあった。
また、カーリーの亡霊がそのままジャングルに残ったのもよかった。よく亡霊が出てくる映画では、最後に亡霊は退治されてしまうのだが、この映画では、クリシュ(ジョン・アブラハム)、デーヴ、イシカー(ラーラー・ダッター)の3人が何とかジャングルから脱出することに成功し、カーリーは「ちっ、逃がしたか・・・」とつぶやいて森へ戻っていく。ジャングルにカーリーが残ったということは、つまり、森を傷つけてはいけない、森を守って行かなければならないというタブーが残ったということである。「Kaal」のラストは、こうでなくてはならなかったし、これ以外の終わり方は考えられない。映画に対する感想は各人それぞれあって然るべきなのだが、もしこのエンディングで失望して「Kaal」を駄作と思っている人がいたら、どういう終わり方がベストだったか一度考え直してみるべきだ。
だが、「Kaal」にはいくつか弱点があったことも否めない。まず、過剰な観客サービスがあったことだ。冒頭、ジョン・アブラハムが上半身の肉体をさらけ出しながら全力疾走するシーンは、女性ファンに加え、マッチョな肉体に憧れる男性ファンへのサービスだろう。ラーラー・ダッターとイーシャー・デーオールは、ジャングルを散策するというのにやたら露出度の高い衣服を着ていたが、これも男性ファンへのサービスだろう。冒頭と最後に流れるミュージカル・シーンは、全くストーリーとは関係ない観客サービスである。それらが映画のバランスを悪くしていた。
キャラクターの人物描写に深みがないのも欠点だった。特に女性キャラのイシカーとリヤーには、これといって特徴がなかった。カーリーの圧倒的存在感に比べたら、男性キャラたちにもユニークさがなかった。脇役も、ただ殺されるだけに出ているような捨て駒キャラが多く、ハリウッドのB級ホラー映画の悪い影響が出ているように思えた。
不必要に観客を怖がらせるシーンが多いのも邪魔だった。中盤、イシカーが悪夢を見るのだが、その悪夢のシーンが長すぎてだらけていた。ラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督のホラー映画によくある「なんちゃってホラーシーン」の伝統が「Kaal」でも受け継がれていた。
だが、「Kaal」は、欠点以上に優れた点、ユニークな点が多い映画である。それらのいくつかは前回の「Kaal」評に書いた。本物の虎を使った迫力ある虎遭遇シーンは映画の白眉であるし、効果音や映像効果が効果的に使われていたこともよかった。「Kaal」はこの酷暑期必見の映画の筆頭に挙げられることは間違いない。
デリーで上映されるインド映画のほとんどはヒンディー語映画である。シネコンの普及により、時々インドの他言語の優秀な作品も上映されるようになったが、それでもデリーはヒンディー語映画オンリー地帯だと言って過言ではないだろう。一方、チェンナイやバンガロールなどでは、地元の言語の映画に加え、ヒンディー語映画も割と上映されているため、デリーよりもインド全体の映画界を万遍なく体験できるというメリットがある。別にバンガロールなどに移住したいとは思わないが、バラエティーに富んだ映画を見ることができるという点だけはうらやましい。
ところで、先週の金曜日から珍しくタミル語映画がPVR系列の映画館で上映され始めた。日本で一世を風靡した「ムトゥ踊るマハラジャ」(1995年)で主演を務め、日本で一躍有名となったスーパースター、ラジニーカーントが主演する最新作「Chandramukhi」である。今日はこの映画をPVRプリヤーで見た。英語字幕付きだったので助かった。タミル語は一応勉強したのだが、映画を理解できるほどの能力はない。観客はやはりデリー在住のタミル人ばかりだったと思う。
「Chandramukhi」とは、「月のような顔の女性」という意味。インドでは月は美人の形容詞である。「Devdas」(2002年)にも同名の女性が出てきた。監督はPヴァス、音楽はヴィディヤサーガル。キャストは、ラジニーカーント、プラブ、ジョーティカー、ナヤンターラーなど。
| Chandramukhi |
 サラヴァナン(ラジニーカーント)は米国で心理学を修めた上に読心術を持つ、心優しきヒーローだった。孤児だったサラヴァナンは、センディル(プラブ)の父親に育てられた。【写真は、スーパースター、ラジニーカーント】 サラヴァナン(ラジニーカーント)は米国で心理学を修めた上に読心術を持つ、心優しきヒーローだった。孤児だったサラヴァナンは、センディル(プラブ)の父親に育てられた。【写真は、スーパースター、ラジニーカーント】
センディルはガンガー(ジョーティカー)と恋愛結婚し、新たな家を購入した。だが、それは地元では幽霊屋敷として有名で、誰も寄り付こうとしなかった。幽霊屋敷のある村の地主の家では、姉が最高権力者であった。姉は、弟の娘のプリヤーをセンディルと結婚させることを決めていたが、センディルが別の女と勝手に結婚してしまったことを知り、怒りを露にする。しかし、センディルが幽霊屋敷を買ったことを知り、不気味な笑みを浮かべてそれを了承する。しかも、センディル夫妻、サラヴァナン、そしてプリヤーの家族全員がその屋敷に住むことを提案する。
その幽霊屋敷は100〜150年前、王様の所有物だった。王様は、チャンドラムキーという名の踊り子に恋をし、強引に誘拐して妾としてしまう。だが、チャンドラムキーは舞踊家の男性と恋をしており、その男性は王の隣に住み始め、チャンドラムキーと密会を重ねていた。2人が密通していることを知った王様は、舞踊家とチャンドラムキーを殺害してしまう。チャンドラムキーの魂は無念のまま屋敷に留まったが、その後すぐに王様も死んでしまったため、復讐の機会を失い、永遠に現世を彷徨い続けることになった。チャンドラムキーの魂は、屋敷のある部屋に封印された。それ以後、誰もその部屋に近付こうとしなかった。
全ての人が多かれ少なかれ言い伝えを信じていたが、ガンガーだけは信じていなかった。ガンガーは、庭師の娘ドゥルガー(ナヤンターラー)の助けを借りて、禁断の扉を開けてしまう。それ以後、屋敷では異変が起こるようになり、センディルは2度も命を狙われた。夜な夜なチャンドラムキーの部屋からは音楽と踊りの音が聞こえて来ていた。当初はドゥルガーが疑われたが、心理学を学んだサラヴァナンはいち早く原因を究明していた。幼少時代に精神的ショックを受け、多重人格症気味だったガンガーにチャンドラムキーの霊が乗り移ったのだ。
ガンガーは、自分の夫を、チャンドラムキーを殺した王様だと考え、また家の隣に住んでいた舞踊家の男を、チャンドラムキーの恋人の舞踊家と思いこんでいた。だから王様に復讐するため、センディルを何度も殺そうとしていたのだった。サラヴァナンは、チャンドラムキーが乗り移ったガンガーに対し、自分が王様であると信じ込ませ、彼女のセンディルに対する殺意をそらす。そして、自分がわざと死んだように見せかけてチャンドラムキーの霊を満足させ、霊媒師の力を借りて霊をガンガーの身体から追い出し、彼女の命を救った。こうして幽霊屋敷の問題は解決し、サラヴァナンは密かに恋愛を成就させていたドゥルガーと共に颯爽と去っていくのだった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
久し振りにラジニーカーント主演のタミル語映画を見たが、同じインド映画なのにヒンディー語映画と比べてこうも違うかと改めて痛感させられた。ヒンディー語映画を見る姿勢でタミル語映画を見ることは困難である。タミル語映画には、タミル語映画の文法があり、それを踏まえた上で批評していかなければなるまい。
まず、「Chandramukhi」は、タミル・ナードゥ州で絶対的な人気を誇るラジニーカーントの久々の主演作であることもあり、ラジニーカーントを絶対的なヒーローとした一神教的映画であることを実感させられた。ヒンディー語映画でもスター・システムが採られており、主役のヒーロー、ヒロインを中心にカメラのアングルや画面の構図など、全ての要素が決定されるが、タミル語映画ではそれを遥かに超越した、スーパースター・システムが採られている。ラジニーカーントは、冒頭の登場シーンから最後の退去シーンまで、最初から最後まで圧倒的な強さとかっこよさを誇るスーパーヒーローであり、彼にたてつく者の末路は、悪役として哀れな最期を遂げるか、コメディアンとして観客の嘲笑を買うか、どちらかしかない。これは洗脳映画と言ってもいい。「ムトゥ踊るマハラジャ」を初めて見たときもそうだったが、「なぜこんなおっさんが主人公なのだ?」と思って映画を見ている内に、だんだん「このおっさん、もしかしてかっこいいかも」と思い始め、映画館を出るときにはなぜかラジニーカーントの仕草のひとつひとつが極まりなくクールに思え、みんなで物真似をしていたりする。観客をいかに洗脳するか、という基準で見れば、この映画はそれに成功している。
ラジニーカーントの圧倒的強さにも関係あるが、アクション・シーンがヒンディー語映画よりも長くて気合が込められているのも目立った。ラジニーカーントのひとつひとつの仕草に「シャー!」「シュオー!などという派手な効果音が流れ、彼のパンチやキックにより敵は数メートルも数十メートルも吹っ飛ぶ。なぜか吹っ飛んだ先には必ずガラスがあり、これまた派手な効果音と共に敵はガラスを突き破って血まみれとなる。こうしてラジニーカーントは1人で暴徒の軍団を一網打尽にする。こんな非現実的な無敵の強さを誇るキャラクターは、ヒンディー語映画にはなかなか登場しない。ヒンディー語映画では、お互い血まみれになりながら何とか敵をやっつける、というアクション・シーンか、銃撃戦が多いが、タミル語映画では、1人の圧倒的な強さを持つヒーローが無傷のまま孤軍奮闘して敵をやっつける、というアクション・シーンが好まれるようだ。
ミュージカル・シーンの唐突さもタミル語映画の特徴だ。ヒンディー語映画でも唐突にミュージカルが挿入されることがあるが、タミル語映画は脈絡のないミュージカルが多すぎる。ただ、それだけあってミュージカルの豪華絢爛さと、俳優の踊りのうまさは、タミル語映画の方が一枚も二枚も上手である。いったい観客はミュージカルを見に映画館に来ているのか、ストーリーを楽しみに映画館へ来ているのか、分からないほどだ。
CGが多用されているのも気になった。ヒンディー語映画でも最近はCGが使われることが増えてきたが、それでも「Chandramukhi」のように露骨にCGが使われている映画はちょっと記憶にない。しかも、ハリウッド映画のように、CGで現実感を出そうとしているのではなく、CGをCGっぽく利用しているところが特徴的だった。つまり、一目でCGと分かる映像が、大袈裟に使われているのだ。例えばチャンドラムキーの部屋に巨大なキングコブラがいたが、CGで全て表現されていた。そういうのがかっこいいと思われているのだろうか。
さて、ヒンディー語映画とタミル語映画の比較をしてきたが、「Chandramukhi」自体の批評を始めようと思う。どうしても僕は「ムトゥ踊るマハラジャ」と比較してしまうが、「Chandramukhi」は残念ながら「ムトゥ」を越える作品ではなかった。無駄に登場人物が多いし、ラジニーカーント演じるサラヴァナンの、「心理学者にして読心術を持つ男」というキャラクターも謎すぎるし、サラヴァナンを敵視していた姉の存在もうまく活用されていなかったし、霊媒師に「祈祷が終わるまで家を出てはならない」と言われているのに、みんな余裕で家を出ているし、細かい欠点を挙げていけばキリがない。ラジニーカーントを含む俳優たちの演技も、演技とは言えないレベルである。だが、サラヴァナンとムルゲーシュ(ヴァディヴェル)のやりとりは爆笑ものだし、ラジニーカーントやジョーティカーのダンスは素晴らしかった。ラジニーカーントの映画は、ラジニーカーントの見事なヒーロー振りのみに注目すればいいのであり、あまり細かいことをうだうだ呟くのは野暮というものだろう。チャンドラムキーに乗り移られたガンガーの顔は、必要以上に怖かった・・・。
あと、ラジニーカーントが黄色いカリズマ(僕の乗っているバイク)に乗っているシーンがいくつかあったのが気になった。ただのカリズマではなく、かっこわるく改造がされていた。タミル人のセンスを疑う・・・。
おそらく「Chandramukhi」を見終わった観客が、映画館を出るときに口ずさんでいるフレーズは十中八九「ラカラカラカ・・・」であろう。どういう意味か知らないが、あの「ラカラカラカ・・・」は夢に出てきそうなほど強烈である。「ラカラカラカ・・・」が何か知りたい人は、是非「Chandramukhi」を見ていただきたい。文章では決して説明できない。
そういえば、この映画がタミル・ナードゥ州で公開されたとき(おそらく4月15日)、インドの新聞やTVは、日本人のラジニーカーント・ファン数人が、「Chandramukhi」を見るためにチェンナイを訪れたというニュースを報じていた。TVでも彼らを見た。なんか音楽に合わせて踊りを踊っていた。「えっ?」と思った・・・。ラジニーカーントの映画を見に来るのは別にいいのだが、わざわざそんなことを報道するなんて、けっこう異常事態である。また、「Chandramukhi」では、ラジニーカーントが2回ほど「日本」の名前を口にしていた。前作「Baba」(2000年)では日本人女性が映画出演しているし、タミル映画界やラジニーカーント自身は、かなり親日的になっているように感じる。
「Chandramukhi」は、作品としてはそれほど高評価ではないが、ラジニーカーント・ファンには麻薬のような陶酔を与える洗脳映画であろう。ラジニーカーント映画は、常に我々に「映画の本質とは何か」を教えてくれる。
日本では、他人の名前を見てその人の出身地、宗教、仕事、その他の背景などが分かることはほとんどないと思う。在日韓国人の名前などは何となく特徴があるので、それと分かるときがあるが、日本人の氏名を見て、名前以外のことが分かることは稀である。名前の付け方にしても、日本人ほど何の束縛もなく名付けをしている民族は世界にそうないと思われる。
だが、インドでは幸か不幸か、名前がかなり多くのことを語ってしまう。まず、名前を見ればその人の宗教の大方の見当がついてしまう。「ムハンマド」とか「アリー」とかいう単語が名前の中にあれば完全にムスリムであるし、「スィン」とか「カウル」などが付くとスィク教徒である場合が多く、名字が「ジャイン」となっていればジャイナ教徒であることは確実であるし、欧米人のような名前だったらキリスト教徒である。それ以外は大体ヒンドゥー教徒と考えていいだろう。ここではヒンドゥー教徒の名前を中心に考える。
出身地も慣れてくると分かるようになってくる。「ボース」「チャタルジー」「ムカルジー」など、ベンガル地方特有の名字を持つ人はベンガル地方に起源を持つ家系であることが多いし、「アーンベードカル」「マートーンドカル」「テーンドゥルカル」などのように「〜カル」と付く場合はマハーラーシュトラ州の人であることが多い。「パテール」という名前はグジャラート人に非常に多いし、「モートワーニー」や「アードヴァーニー」など、「〜ワーニー/ヴァーニー」と付く人はスィンド人であることが多い。南インドの地名・人名は、北インドの「タ(ta)」の表記が「tha」と表記されることが多いので、それにより南インド人の名前を特定することが可能である。例えば「ジャヤラリター(Jayalalitha)」や「ラジニーカーント(Rajnikanth)」などである。それ以外にも南インド人の名前の特徴は多い。例えば北インドで一般的な名前は、南インドでは名前の語尾に「アン」が加わることが多い。北インドで通常「ナーラヤン」と表記される名前は、南インドでは「ナーラヤナン」になる。また、南インド人の名前は一般に北インド人よりも長い。ハイダラーバード生まれのクリケット選手、VVSラクシュマンの本名は、ヴァンギプラップ・ヴェーンカター・サーイー・ラクシュマンという。南インドでは日本人と同じく名字が先に来る。
名字からは多くの場合、カーストも分かってしまう。例えば「シャルマー」や「ミシュラー」は北インドのブラーフマンに多い名字であるし、「アガルワール」や「グプター」はバニヤー(商人)カーストに多い名字である。「ヤーダヴ」は牛飼いカーストであるし、「ジャイサワール」は酒屋カーストであるし、「バジャージ」は衣服屋カーストであるし、「ジャウハリー」は宝石屋カーストである。「シュリーワースタヴ」、「サハーイ」、「サクセーナー」などは、カーヤストという書記官カーストに多い名前だ。だが、名字によるカースト名の表示には地域差がある場合もある。例えば「タークル」という名字は、ベンガル地方ではブラーフマンを指すが、ウッタル・プラデーシュ州ではラージプート族を指す。名字だけでなく、名前にもいろいろタブーがあるようで、例えばアショークという名前は全てのカーストに付けられるが、アルジュンという名前はブラーフマンの子供には付けられないらしい。
これだけいろいろなことが分かってしまうため、わざと自分の名前を隠したり、変えたりする人も出てくる。その顕著な例が映画界である。昔は映画に出演することは、本人だけでなくコミュニティー全体の恥とされていたらしく、またいろいろな事情によって、俳優たちは名前を変えて出演することが多かった。例えば名優アショーク・クマール(1911-2001)の本名はアショーク・クマール・ガーングリーという。ガーングリーはベンガル地方のブラーフマンの名字である。ブラーフマン階級が映画俳優のような下賎な職業に就くことは、同階級全体の名誉に関わることであり、彼は自分のカースト名を隠して映画に出演していた。これまた往年の名優ディリープ・クマール(1922-)の本名はユースフ・カーンである。一目瞭然のように、彼はイスラーム教徒だ。インド映画界には歴史的な事情からムスリムが多く関わっているのだが、彼はヒンドゥーっぽい名前を名乗って映画界で活躍した。もっとも、現在では映画業界もそれほど下賎な職業とは見なされなくなってきたため、本名のまま俳優業に就く人が多くなっていると思われる。インドを代表する映画音楽家として有名なARレヘマーン(1966-)は、生まれたときはASディリープ・クマールという名前だったが、ムスリムに改宗したため、現在のアッラー・ラカー・レヘマーンという名前に改名した。これはまた全く別の例である。
僕が所属していた修士課程のクラスは27人いたが、外国人が4人、ブラーフマンが5人、その他は後進カーストと指定部族であった。ブラーフマンとそれ以外の学生の名前を見比べてみても、その差は歴然としている。ブラーフマン階級はファーストネームからカースト名まで堂々とフルネームを名乗っているが、後進カーストの学生は「〜〜・クマール」などのように、カースト名が消去されていることが多い。しかも、ファーストネームの響きの立派さを見比べてみても、やはりブラーフマン階級の方が由緒正しい感じがする。具体的には、ブラーフマン階級の名前の方が、サンスクリト語に忠実な表記だったり、音節が多かったり、意味が高尚だったりする。
プレームチャンドの「Balidan(犠牲)」という短編小説の冒頭に、インド人の名前に関して鋭い分析がなされている。
人間の経済状態の影響を最も受けるのはその人の名前である。ベーラー村のマンガルー・タークルは巡査になってから、マンガルスィンになった。今や彼をマンガルーと呼ぶ勇気のある者はいなかった。牛飼いのカッルー・アヒールは警視と友達になって村長になってから、カーリカーディーンを名乗り始めた。彼のことをカッルーと呼ぶ者がいれば容赦しなかった。それとは逆に、農民のハルクチャンド・クルミーは今ではハルクーになってしまった。今から20年前、彼は広大なサトウキビ畑を所有して砂糖を作っており、商売も繁盛していた。しかし、外国の砂糖が流入したことにより、彼の商売は破綻してしまった。次第に工場は廃墟となり、畑も荒廃し、客足も途絶え、彼自身もボロボロになってしまった。かつて寝台に座ってのんびりとココナッツの汁を飲んでいた彼は、70歳の老人となった今、頭に籠を乗せて畑に肥料を撒きに行っていた。しかし、彼の顔には今でも特有の眼光が、会話には今でも特有の傲慢さが、仕草には今でも特有の自尊心が満ち溢れていた。彼には時間の無情な流れなど関係なかった。縄は燃えてしまったが、芯は残っていた。栄光の日は、1人の人間の人格に永遠に足跡を残すものだ。ハルクーのもとには今やわずかな土地と、2匹の牡牛と、小さな畑しか残っていなかった。
インド人には本名とペット・ネームの2種類があるが、その人の経済状態や地位により、ペット・ネームが封印されて本名のみで呼ばれるようになったり、本名が忘れられてペット・ネームが本名になったりする様子が上の文章でよく表現されている。インド人の名前は、こんなことまで表してしまう。
また、インドでは名前がその人の一生を左右するとも考えられており、ブラーフマンや占星術師などのアドバイスによって命名が行われることが多い。大体の場合、最初の一文字が星の運行などにより決定され、それに基づいて家族は新生児に名前を付ける。つまり、インド人の名前には、過去と現在と未来が詰め込まれているのだ。
インドではよく、「What is your name?」の代わりに、「What is your good name?」と聞かれる。インド特有の英語だと思う。相手の名前を聞いた後に「It's
good name」とか言うことは欧米でもあると思うが、最初から「good nameは?」と聞かれるので、最初このフレーズを聞いたときは、何だか必要以上に敬意を表されているようでくすぐったい気分になったものだ。おそらくヒンディー語の「アープカ・シュブ・ナーム・キャー・ハェ?」をそのまま英語にしたものだろう。日本語に訳すと、「あなたの吉祥なる名前は何ですか?」という、ちょっと大袈裟な表現になってしまう。インドでは名前は単なる名前ではなく、履歴書のようなものであるため、相手に唐突に名前を聞くことは大変失礼なことなのだ。だから、最大限の敬意を込めて、「What
is your good name?」と言うのだろう。
だが、外国人の名前を聞いてもインド人には相手の背景が全く分からない。何も分からないので、インド人は具体的にどんどんプライベートな質問をして来る。国籍や出身地はどこか、職業は何か、年収はいくらか、既婚か独身か、宗教は何か・・・などなど。一通り質問をし終え、満足して去っていくと、また別のインド人がやって来て、全く同じ質問をし出す。これがエンドレスで繰り返されるため、大抵の外国人旅行者はぶち切れてインド人を無視し始める、というパターンが多い。
数十年後にはインド人の人口は世界一になると言われている。その頃にはインド人の名前が世界の至る所で聞かれることになるだろう。だが、現在の日本ではインド人の名前や固有名詞の正しいカタカナ表記すらままならない状態だ。ブラーフマン階級の名字「Vajpayee」が、インド人には通じない「バジパイ」になったり、ヴィシュヌの化身の1人から来た名字「Narasimha」が、まるでマッカーサー元帥が松傘元帥になったかの如く、「ナラシマ」になったり、インドを代表する通信会社「Bharti」が、元の原型を留めない「ブハルティ」になったりと、危機的な無知が氾濫している。インドに住むと徐々に実感するが、インドはインド人の国ではない。多くの民族が立体的に隙間なく詰め込まれた多民族共生社会である。それぞれの職業(ジャーティ)が、別々の民族であると考えた方がインドを理解しやすい。高級ホテルのディスコで踊っている人と、毎日ゴミ集めに来る人の人種は明らかに違う。そして全ての人々に、その人の過去、現在、未来を示す、「名前」というIDが刻み込まれている。この名前の規則が通じる範囲が、「インド人」だと言えるかもしれない。インド人最大人口時代を前に、インド人の名前に対する正しい知識や、その名前に込められたIDの読み取り法を日本人の間で普及させると同時に、カタカナ表記の理論的で客観的な基準を決めることは決して損ではないし、むしろ急務だと思う。
| ◆ |
5月12日(木) Bose : The Forgotten Hero |
◆ |
4月末の小泉首相訪印により、日印関係は大きな転機を迎えそうだが、ちょうどそれとほぼ時を同じくして、日印関係に関係のある1本の映画がインドで公開されようとしている。インド独立運動の英雄、ネータージー・スバーシュ・チャンドラ・ボースの半生を描いた映画「Netaji
Subhas Chandra Bose : The Forgotten Hero」である。チャンドラ・ボースは世界を股にかけてインド独立のために英国に徹底抗戦したベンガル人で、太平洋戦争中の日本にも来ており、日本軍と協力してインパール作戦に参加した。第二次世界大戦終了直後の飛行機事故で死亡したとされているが、インド人の中には彼が生きていると信じている人も少なくないようで、その存在は数多くのフリーダム・ファイターの中でも異彩を放っている。もし彼が独立後にインドに戻っていたら、ジャワーハルラール・ネルーに匹敵するほどのカリスマ的政治家になっていたとも言われている。マハートマー・ガーンディーと袂を分かった経緯もあるため、国民会議派にとってチャンドラ・ボースの扱いは非常に微妙な問題である。よって、東京杉並区の蓮光寺に眠ると言われるボースの遺骨は、未だにインドに返還されていない。ボースの不死伝説については、2月9日(水)の日記で触れた。
僕は去年からこの映画の公開をかなり前から待ち望んでいたのだが、やっと公開日が決定した。5月13日(金)である。だが、その前に試写会でこの映画を見る幸運に恵まれた。映画のサントラをプラネットMで購入すると、5月12日(木)の午後7時からPVRプリヤーで行われる試写会の入場券がもれなくもらえたのだ。実は映画のサントラCDは既に持っていたのだが、試写会のチケットを手に入れるためにもう1枚購入した。CDの値段は150ルピーであり、それで試写会のチケットが2枚もらえるなら安いものである。5月11日(水)にボース所縁の地コールカーターで第一回試写会が行われ、その次の日に、ボースがインド国民軍(INA)と共に目指したデリーで第二回試写会が行われるという粋な計らいだった。それ以前にジャイプルで試写会が行われたという情報もある。

「Netaji Subas Chandra Bose : The Forgotten Hero」の試写会チケット
インドの映画館のチケットは通常、単なる薄っぺらい紙のため、
このようなちゃんとしたチケットは貴重品である。
映画館で容赦なく回収されてしまったが・・・。
保存用に1枚もらっておけばよかった。
監督は、インドを代表する映画監督であるシャーム・ベネガル監督。音楽監督は、これまたインドを代表する映画音楽家であるARレヘマーン。キャストは、サチン・ケードカル、ラージェーシュワリー・サチデーヴ、ラジト・カプール、ディヴィヤ・ダッター、クルブーシャン・カルバンダー、ラージパール・ヤーダヴなど。3時間27分に及ぶ大長編である。試写会会場には、ベネガル監督や出演俳優などが来ていた。また、観客には約50人のINAの生き残りが招待されていた。映画終了後、ベネガル監督と少しだけ話すことができて感激した。
| Netaji Subhas Chandra Bose : The Forgotten Hero |
 英国政府から危険人物とされ、コールカーターの自宅に軟禁されていたボース(サチン・ケードカル)は、1941年1月15日、密かに脱出してペシャーワルへ向かった。ペシャーワルに到着したボースは、パターン族のバガトラーム・タルワール(ラージパール・ヤーダヴ)と共にカーブルへ向かい、インドから移住したウッタムチャンド(クルブーシャン・カルバンダー)の家に匿われる。ボースはロシア、ドイツ、イタリアとコンタクトを取るが、なかなかうまくいかなかった。だが、イタリア大使がイタリア人パスポートを用意してくれたため、モスクワ経由で同年3月28日にベルリンへ到達することができた。【写真は、サチン・ケードカル】 英国政府から危険人物とされ、コールカーターの自宅に軟禁されていたボース(サチン・ケードカル)は、1941年1月15日、密かに脱出してペシャーワルへ向かった。ペシャーワルに到着したボースは、パターン族のバガトラーム・タルワール(ラージパール・ヤーダヴ)と共にカーブルへ向かい、インドから移住したウッタムチャンド(クルブーシャン・カルバンダー)の家に匿われる。ボースはロシア、ドイツ、イタリアとコンタクトを取るが、なかなかうまくいかなかった。だが、イタリア大使がイタリア人パスポートを用意してくれたため、モスクワ経由で同年3月28日にベルリンへ到達することができた。【写真は、サチン・ケードカル】
ボースは、インド人戦争捕虜を編成してソ連、アフガニスタン経由で英領インドに攻め込む計画を立てており、ナチス政府の外相やヒトラー総裁と会談したが、ドイツのソ連侵攻によりその計画は破綻してしまう。一方、同年12月に日本が米国との戦争を開始し、ボースは日本行きを考え始める。また、ボースはこのとき、秘書のエミリーと結婚しており、子供もいた。だが、ボースは愛するエミリーと子供をドイツに残して日本へ行くことを決める。
1943年2月8日、ボースはナチスの潜水艦Uボートに乗ってドイツを後にした。喜望峰を巡ってマダガスカル島沖に到達したボースは、同年4月28日、日本軍の潜水艦、伊26号にボートで乗り移った。こうしてボースは日本へ到着し、東条英機首相との会談も実現する。
1943年7月2日、ボースはシンガポールにてインド国民軍(INA)の司令官に就任し、スローガンを「チャロー・ディッリー(デリーへ進撃せん)」に定める。ボースは女性も戦争で戦うべきだと考え、女性のみで編成されたジャーンスィー部隊を編成し、ラクシュミー(ラージェーシュワリー・サチデーヴ)をジャーンスィー部隊の隊長に任命する。
1944年3月、日本軍はインパール作戦を開始し、ボース率いるINAも同盟軍として作戦に参加する。しかし物資の欠乏と雨季の到来により作戦は失敗に終わり、INAも退却を余儀なくされた。INAはラングーンまで戻り、ビルマに押し寄せる英印軍の攻撃の防衛にあたった。
1945年8月、広島と長崎に相次いで原子爆弾が落とされ、日本はポツダム宣言を受諾して降伏した。ボースはINAを解散し、側近と共にヤンゴンから飛行機で飛び立つ。だが、台北にて飛行機事故により死亡したと報道される。
第二次世界大戦、INAの捕虜たちはデリーに連行され、裁判にかけられるが、それがインド人の愛国主義を呼び覚まし、インド独立の実現に大きく寄与したのだった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
ボースの最後の5年間を忠実に追った伝記映画。ボースに何の思い入れもない人には退屈な3時間半だろうが、ボースの人生とその意義を知る者には至福の3時間半である。よって、チャンドラ・ボースや20世紀前半のインドの歴史に興味のある人は必見の映画だが、インドの歴史に何の興味のない人は見ない方が賢明であろう。
長らくインドでタブーとされてきたチャンドラ・ボースの映画であるし、インド最高の映画監督の1人に数えられるシャーム・ベネガル監督の最新作であることもあり、非常に期待していた。だが、残念ながら映画としての面白味はあまりない。ボースの人生を年代を追って再現しただけであり、登場人物やストーリーに深みがなかった。また、ボースの人生そのもののスケールが大きすぎるため、映画にすると何だか逆にB級スパイ映画みたいになってしまっていた。ドイツから日本まで行くのに潜水艦を使い、しかもマダガスカル島沖で潜水艦から潜水艦へボートで乗り移る、というストーリーをもしフィクション映画で見たら、「そんな馬鹿な」と酷評したくなってしまうだろう。だが、ボースは本当にそんな無謀なことをしたのだ。
3時間半の大長編だったにも関わらず、まだまだ時間が足らなかった印象を受けた。各シーンがかなり急ぎ足で、目まぐるしく展開していった。せっかくARレヘマーンが魂を込めて作曲した挿入歌も、フルで使われていなくて残念だった。日本人が登場するシーンはかなりすっ飛ばされていた。潜水艦でインドネシアに上陸した後、いきなり東条英機との会談になっており、それが終わると一気にシンガポールでのINA司令官就任シーンだった。日本ロケも行われていない。
ちょくちょくコメディアンっぽいキャラが登場したのもマイナス要因だったと思う。インド映画にコメディアンが必ず登場するのは常識だが、この映画には必要なかった。ラージパール・ヤーダヴ演じるバガトラーム・タルワールや、酔っ払ってINAから追放されそうになった兵士など、蛇足的お笑いシーンがあり白けた。インパール作戦などの戦闘シーンも未熟だったように思える。ただ銃をぶっ放して手榴弾を投げてお終い、という感じだった。ジャングルの戦闘を迫力あるシーンに仕上げるのは難しいと感じた。また、あまり残酷なシーンはなかった。
ボースを演じたサチン・ケードカルの顔や演技にも疑問が残った。サチンの顔や体格はボースと非常によく似ているが、目がいけない。サチンの目は、少女漫画のようにキラキラ輝いていて、ボースにしてはかわいすぎるのだ。本物のボースがどのような仕草をする人間だったのか知らないが、サチンの行動や表情は何だか女性的で、僕のイメージする勇猛果敢なボースと違って違和感があった。「私に君たちの血をくれ、そうすれば、私は君達に自由を与えよう!」という有名な演説も、良くも悪くもないレベルだったように感じた。ボースの人物像もあまり鮮明に浮かび上がって来なかった。
しかしながら、この映画を一通り見れば、ボースがどのようにコールカーターからベルリンまで、ドイツから日本まで移動したのかが分かる。まるで歴史の教科書の副教材のような映画である。当時の英印政府にとってボースは、突然ベルリンに現れたり、はたまた日本に現れたりと、さぞや神出鬼没の不気味な存在だったことだろう。また、ボースとマハートマー・ガーンディーとの複雑な師弟関係もさりげなく説明されていた。ボースは、ガーンディーとインド独立という目的を共有しながらも、その手段の違いから袂を分かったのだが、それでも彼はガーンディーを慕っていた。その関係が、冒頭のボースとガーンディーの会話シーンや、途中の所々のシーンでうまく表現されていた。

ボース(左)とガーンディー(右)
ヒトラーや東条英機との会談も映画の見所であろう。どちらも世界史の中であまり好意的な評価を受けていない人物である。映画中、ヒトラーはやたら神経質で落ち着きがなく、ボースとインド独立に対して消極的な見解の持ち主として描写されていた一方で、東条英機は礼儀正しく威風堂々としており、ボースに協力的な人物として描写されていた。東条英機を誰が演じていたのかは情報がない。日本人ではなかったかもしれない。この映画中に出てきた日本語は、「ボースさん」などの「〜さん」と、「ようこそ」ぐらいか。

ボース(左)とヒトラー(一番右)

東条英機(左)とボース(右)
「中村屋のボース」として有名な、ラース・ビハーリー・ボースも一瞬だけだが数回スクリーンに登場した。だが、作業服みたいな変な服を着ており、痩せこけて眼鏡をかけた変なおっさんだった。最近、中島岳志著「中村屋のボース」(白水社)という本が出版されたが、その表紙に載っているボースの写真とはだいぶ違った。
さて、問題なのはこの映画における日本軍の描写のされ方であるが、はっきり言ってあまり好意的ではなかった。特にインパール作戦中の日本軍の身勝手さと非協力的な態度が批判的に描かれていた。まるでインパール作戦が失敗したのは、全て日本軍の責任であるかのようだった(実際、そうだったのかもしれないが)。だが、実際の映像が使われた真珠湾への奇襲シーンは、ボースにとって日本行き決定の要因になった出来事でもあるので、賞賛を含んだニュアンスで語られていた。また、広島と長崎に原爆が落とされたことを聞いたボースは、何日間も部屋に閉じこもって犠牲者に哀悼を捧げていた。
やはりボースは多くの伝説と謎に包まれたカリスマ的指導者であるため、この映画もトラブルに巻き込まれている。ボース自身が設立した政党フォワード・ブロックは、この映画が、まだ結論が出ていない「ボースの結婚」と「ボースの死」を事実として描いていることに批判の声を上げた。ボースはオーストリア人の秘書エミリーとの間に一子をもうけるが、2人が正式に結婚したかどうかは分からないようだ。映画中では、エミリーの願いにより、ドイツ人のインド学教授に無理矢理サンスクリト語のマントラを読ませて結婚式を挙げるシーンがあった。また、それよりももっと大きな問題は、ボースが1945年8月17日に台北で飛行機事故により死亡したかどうかである。映画中では、死亡のシーンは描写されず、エミリーがラジオでボースの死を聞く、という表現に留まっていた。別にボースが死んだことを既成事実化するような意図は見受けられず、悪くない終わり方だったと思うのだが・・・。
この映画の重要性は、インド独立の実現に結びついた数ある要因の中で、今まで軽視または無視されがちだったチャンドラ・ボースの功績を今一度再評価するきっかけを与えることにある。とかくマハートマー・ガーンディーの非暴力・非協力の運動がインド独立を実現したと単純に考えられることが多いのだが、この映画を見ると、ガーンディー1人だけではインド独立は達成できなかったのでは、という気分にさせられる。武力を使い、敢然と英国に立ち向かったボースの存在が、インド独立に寄与しなかったはずはない。また、第二次世界大戦後にデリーで行われたINA捕虜の裁判が、国民のインド独立の気運を最高潮に盛り上げたことは、既に歴史家の認めるところとなっている。それに加え、この映画は我々日本人に、かつて日本とインドが手を取り合って戦ったことがあるという歴史的事実を思い出させてくれる。残念ながらインパール作戦は失敗してしまったのだが、もし成功していたら日本軍とINAの間で内紛が生じて、日印関係の負の要素になっていた可能性もあるから、現在から見ればこれでよかったのかもしれない。今、日本とインドにとって大切なのは、「我々はかつて友人だった」と自覚することである。そうすれば、未来の関係を築く際に役に立つだろう。
最後のスタッフ・ロールと同時に、ボースに関する本物の映像や写真が流される。これらはかなり貴重な資料だと思われる。一番最後は、サングラスをかけた本物のボースのドアップだった。
ロケはラダック、ドイツ、ビルマの3ヶ所で行われたとのこと。アフガニスタンのシーンがラダックで撮影された他、ドイツのシーンはもちろんドイツで、そしてラングーンのシーンがビルマで撮影された。特にラダックのシーンと、カーブルのシーンが映像的に素晴らしかった。ラングーンではボースはムガル朝最後の皇帝、バハードゥル・シャー・ザファルの墓で祈りを捧げていたが、今でも残っているのだろうか。急に行ってみたくなった。ザファルは、1857年のインド大反乱の後、ラングーンに流刑となってそのままそこで没した。デリーを目指して進軍するINAと、ザファルの望郷の気持ちがうまくシンクロしていた。
言語は、半分ヒンディー語、半分英語である。よって、ヒングリッシュ映画に分類できる。試写会で上映されたのは英語字幕付きだったが、一般上映される映画にも字幕が付いているのかは分からない。ただ、多民族国家インドを表現するため、いろんな発音、いろんな方言のヒンディー語が随所で使用されていた。例えばパターン族の話すヒンディー語、スィク教徒の話すヒンディー語、グルカー(ネパール人)の話すヒンディー語、それぞれ異なっていた。
愛国主義映画の決定版、「Netaji Subhas Chandra Bose : The Forgotten Hero」は、インドの近代史に興味のある人は必ず見るべき映画である。映画自体の面白味はあまりないし、チャンドラ・ボースの評価は日本でも微妙なので、日本で公開されることがあるかどうかは何とも言えない。だが、チャンドラ・ボースの映画が作られたということは、日印関係の歴史の中で考慮すべき出来事だと思う。映画を見終わったら、みんなの合言葉は「ジャイ・ヒンド!(インドに勝利を)」だ。
| ◆ |
5月13日(金) Jo Bole So Nihaal |
◆ |
酷暑期真っ只中のデリーは、容赦ない暑さにさらされており、日中は外に出る気がしない。今日は夕方からPVRプリヤーで新作ヒンディー語映画「Jo
Bole So Nihaal」を見た。題名の意味は「この言葉を唱える者は祝福される」という意味で、スィク教徒は「Jo Bole So Nihaal」と言われたら、「Sat
Sri Akaal」と言い返さないといけないらしい。「Sat Sri Akaal」とは、「時間を超越せし不滅の神が真実なり」という意味で、「ナマステー」と同じ感覚でスィク教徒間でよく使われる挨拶である。
監督は、ラーフル・ラワイル、音楽はアーナンド・ラージ・アーナンド。キャストは、サニー・デーオール、カマール・カーン(新人)、シルピー・シャルマー(新人)、ヌープル・メヘター(新人)など。
| Jo Bole So Nihaal |
 パンジャーブ警察のニハール・スィン(サニー・デーオール)は、正体不明の国際的テロリスト、ロミオ(カマール・カーン)と偶然出会うが、取り逃がしてしまう。それだけでなく、ニハールはロミオの仲間だと勘違いされ、警察をクビになる。ニハールの父親は村人の尊敬を集めていたが、ニハールの一件により彼の名声は地に落ちてしまった。その上、ニハールの妹の結婚も破談になってしまった。【写真は、サニー・デーオール】 パンジャーブ警察のニハール・スィン(サニー・デーオール)は、正体不明の国際的テロリスト、ロミオ(カマール・カーン)と偶然出会うが、取り逃がしてしまう。それだけでなく、ニハールはロミオの仲間だと勘違いされ、警察をクビになる。ニハールの父親は村人の尊敬を集めていたが、ニハールの一件により彼の名声は地に落ちてしまった。その上、ニハールの妹の結婚も破談になってしまった。【写真は、サニー・デーオール】
7ヶ月後、ロミオは相棒のリザ(ヌープル・メヘター)と共に、スィカンダルという名を名乗ってニューヨークに住み始めていた。ロミオによる爆弾テロが発生するが、誰もロミオの姿を見た者はいなかった。ニハール・スィンを除いて・・・。FBIはニハールをニューヨークへ呼び、ロミオ逮捕に協力を求める。しかし、ニハールはロミオをパンジャーブの村へ連れ帰ると言って聞かなかった。ニハールの監視役として、スザンヌ(シルピー・シャルマー)が常に彼に同行した。だが、次第にニハールとスザンヌは恋仲になっていく。あまりにニハールが自分勝手な行動を取るため、彼はテロリスト幇助罪で逮捕されてしまうのだが、スザンヌと共に逃げ出す。
ロミオもニハールがニューヨークへ来ていることを知り、彼への復讐の機会を伺っていた。ロミオは豪華客船に乗ってバハマへ向かうことになり、ニハールを船におびき寄せる。ロミオはスィク教徒トミー・スィンに変装する一方で、ニハールは、ニハールと瓜二つの兄ビハールと名乗り、ロミオを探す。トミー・スィンが、「Jo
Bole So Nihaal」と言っても「Sat Sri Akaal」と言い返さなかったのを見て、彼がロミオであると悟ったニハールは、ロミオを取り押さえる。
ニハールはロミオをマイアミに監禁したが、そこへFBIも現れる。だが、実はFBIは大統領暗殺をロミオに依頼するために彼を探していたのだった。ニハールとスザンヌはFBIを一網打尽にし、逃げ出したロミオを追った。ニハールはロミオを再度捕まえ、パンジューブへ連れ帰ることに成功する。こうしてニハールは家族の名誉を回復することに成功する。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
宗教的アクション・コメディー映画という、訳の分からない肩書きを贈呈したくなる映画だが、優れた映画とは言えない。英語をしゃべれない生粋のパンジャーブ人がニューヨークで大暴れするという筋が面白いだけの映画である。
ロミオがあまりに小物のテロリストであることと、FBIがあまりに頼りないことから、この映画のストーリーは最初から最後まで全く説得力がない。挙句の果てに、実はFBIが大統領暗殺を企てていたという、突拍子もない落ちが待ち構えている。
主演のサニー・デーオールは、インド人の庶民に最も人気のある男優の1人である。「Gadar」(2001年)の大ヒットでサニーはその地位を確固たるものにしたが、それ以降あまりヒット作に恵まれていない。彼が最も得意とするのは、スィク教徒の役である。彼がスィク教徒の警官を演じる「Jo
Bole So Nihaal」は、そういう意味でお家芸とも言える映画だ。しかし、残念ながらこの映画もサニーの復活を告げる映画にはならなそうだ。キュートなサルダール・ジー(スィク教徒)を演じたつもりのようだが、サニー・デーオールにコメディーは似合わない。
ヒロインは2人。FBIのスザンヌ役を演じたシルピー・シャルマーと、ロミオの恋人リザを演じたヌープル・メヘターである。どちらも新人のようだ。2人ともあまり特徴のない顔をしており、すぐに消えて行きそうだが、どちらかというとシルピー・シャルマーの方が有望だろう。悪役ロミオを演じたカマール・カーンも新人のようだが、青い目が印象的な男優である。元々はプレイバック・シンガーをしており、この映画でデビューしたという変わった経歴を持っている。
映画中でもっとも印象的かつ面白かったのは、ニハールの母親を演じたお婆ちゃんだ。名前はよく知らないが、時々映画に出てくるので顔は知っている。米国でニハールがスザンヌと親密になるたびに、パンジャーブの田舎で「虫の知らせ」が起きて笑わせてくれた。
どうやらスィク教徒の団体が、宗教的なフレーズである映画の題名にケチを付けたようで、多少揉め事があったようだ。その影響からか、映画の冒頭には「これは宗教的映画ではありません」と注意書きがあった。かなり宗教的だったのだが・・・。
サルダール・ジーが好きな人と、ニューヨークに思い入れがある人には一見の価値がある映画かもしれないが、見てもあまり得しない映画だと思う。

ジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)に入学を希望する外国人は、アブセンティアという制度を利用することができる。アブセンティアとは、入学試験がある5月の第三週にインド以外の国にいる外国人は、自動的に合格になるという制度である。一見するとおかしな制度だが、これは、外国に住むJNU留学希望者が、入学試験を受けるためだけにわざわざインドまで来るような面倒を煩わさないよう配慮されたものである。この制度のおかげで、外国人留学生は書類審査だけで比較的容易に入学、進学することができる。JNUの学費には外国人料金があり、外国人留学生はかなり高額の学費を払わされるため、この制度は外国人にとっても、JNU当局にとっても利益のあるものとなっている。
ただ、今年から制度に多少の変更があったようで、アブセンティアを使わず、試験を受けてJNUに入学した外国人私費留学生の学費がかなり安価になる。例えば、文系学部の外国人留学生の学費は半年600ドルだが、受験して入学した外国人留学生の学費は半年100ドルになるらしい。よって、私費留学希望者の選択肢が事実上増えることになったわけだが、JNUはインド最難関の大学であるため、優秀なインド人学生と競争して合格するのは簡単ではない。ただ、受験しても外国人枠が適用されるのなら、競争相手は外国人留学希望者のみとなる。今年から始まった新制度であり、この辺りが曖昧だったため、僕は安全策を取ってアブセンティアを利用することにした。つまり、5月の第三週(15日〜21日)にインドから他国へ亡命する必要がでてきた。
修士課程に入学するときには、僕はブータンに亡命した。今回はどこに亡命しようか思案を巡らせており、候補地としてはネパール、パーキスターン、モルディヴが上がっていた。もちろん、日本にそのまま帰ってしまうという選択肢もあったが、5月〜6月にかけて面白そうなインド映画が公開されるし、個人的な事情もあり、5月中の日本行きは取り止めた。未だにネパールに一度も行ったことがなく、そろそろ行っておかないと恥をかくと思っているだが、現在ネパールはギャーネーンドラ国王の政権奪取や非常事態宣言発布など、政情が非常に不安定であるため、取り止めた。だんだん暑くなってくるに従って、パーキスターンを旅行する気も失せてきた。そこで、モルディヴ旅行を真剣に考え始めた。モルディヴというとやたら高価なイメージがあったが、ちょっと調べたら首都マーレに割と安いホテルもあるようだった。また、津波の影響でそれほど観光客が殺到していないだろうという期待もあった。赤道に近いモルディヴだったら、いつ行っても暑いだろう、という変な諦めもあった。モルディヴ研究家の友人のアドバイスも得ることができたので、モルディヴ行きがかなり現実味を帯びてきた。
デリーからモルディヴへ行く場合、一度ケーララ州のティルヴァーナンダプラム(トリヴァンドラム)まで何かしらの交通手段で移動し、そこからインディアン・エアラインスの飛行機に乗ってマーレへ飛ぶ方法と、スリランカ航空で一度コロンボまで行って、飛行機を乗り継いでマーレまで行く方法があった。もしデリー〜ティルヴァーナンダプラム間で飛行機を利用すると、インドの国内線はかなり高価であるため、コロンボ経由の経路よりも高くなってしまう。デリーからティルヴァーナンダプラムまで列車で行く気力もなかったので、スリランカ航空を利用してコロンボ経由で行く方法を選んだ。往復で2万1千ルピー(税込)ほどだった。旅の参考資料は、「地球の歩き方モルディブ2005〜2006年版」(ちょうど5月にインドを訪れた日本人の友人に買って来てもらった)と、「Lonely
Planet Maldives」の2003年版である。
ところで、モルディヴの名前は聞いたことはあるが、どこにあるか分からない人のために、モルディヴの場所を解説しておく。モルディヴはインド洋上にある島国で、インドの西南、スリランカの西に位置している、南北に細長い国である。インド人にはモルディヴをインド領と勘違いしている人が多くて驚いたが、インド領となっているのは、モルディヴ諸島の北端にあるラクシャードイープ諸島である。モルディヴはれっきとした独立国だ。ただ、モルディヴとラクシャードイープに住む人々の文化や言語は非常に似ているとされている。
モルディヴ行きをかなり楽しみにしていたのだが、実は4月ぐらいからずっと体調が優れず、一度は回復したものの、5月に入ってからまた下降線をたどるようになってきた。だが、5月の第三週はインドにいてはならないので、何としてもモルディヴへ行かなくてはならない。マーレでずっと寝込むことになってもいいから、とかなり無理をして本日14日、デリーを発った。
デリー発コロンボ行きのスリランカ航空UL192は、午後11時40分発だった。僕は律儀に2時間前にチェックインを済ませ、出発ゲートの真ん前に座ってゲートが開くのを待っていたのだが、驚くべきことにゲートは出発時刻の1時間前、10時40分に開き、飛行機は11時40分ちょうどに動き出して、11時45分には離陸していた。こんな時間に正確なフライトは初めてかもしれない。客席は満席ではなかったが、8割以上は埋まっていた。
デリーからコロンボまで約3時間のフライト。もう深夜なので何もいらないのだが、夕食とも夜食ともつかない食事を出され、しかもつい食べてしまった。あとはずっと寝ていた。飛行機はスリランカ時間の午前3時半にコロンボに到着した。インドからスリランカへの時差は+30分である。飛行機を出ると、すさまじい湿気が身体を包んだ。現在のデリーはかなり乾燥しているので、むんむんとした湿気は久し振りだった。
マーレ行きの飛行機の離陸時間まで半日以上の時間があったため、スリランカ航空にホテルを提供してもらえた。昔、同航空会社でコロンボを経由して日本へ帰ったときも宿泊した、ニゴンボ(コロンボ近郊のリゾート地)のブルー・オーシャニック・ビーチ・ホテルである。このホテルに泊まるのはこれで3回目となる。朝食と昼食も込み。スリランカ航空ならではの嬉しいサービスである。ホテルに着いたら、「グッド・モーニング」と迎えられた。もうそんな時間か・・・。ホテルにチェックインした後はすぐに寝た。
朝8時頃目が覚めた。AC付きの部屋なのだが、それでも湿気がすごい。朝には雨も降ったようだ。早速シャワーを浴びる。バスタブもあったため、お湯をはって久し振りに入浴もできた。
朝食はビュッフェ式。だが、あまりヴァラエティーに富んでいない。果物だけは豊富に用意されていた。バナナ、パパイヤ、パッションフルーツ・・・あとは名前が分からない果物ばかり・・・。一通り全ての果物を食べてみた。
軽く朝食を食べた後は、ビーチを散歩してみた。津波の影響が心配だったが、どうやらここは被害を免れたようだ。特に昔来たときと大きな変化はなかった。ビーチに相変わらず売り子や観光客を目当てにした変な人間がうろついているのも変わらず、何だか安心できた。ビーチには帆船が停泊しており、観光客が寄ってくるのを待っていた。

ニゴンボのビーチと帆船
そのままニゴンボのメインロードも散歩してみた。3年前に来たときと比べてだいぶ整備されているように感じた。「にっこり日本レストラン」という日本料理店もあった。

2002年のニゴンボ

2005年のニゴンボ
右には「にっこり日本レストラン」の看板
空き時間が中途半端だったので、朝少し散歩した他はずっと部屋の中に閉じこもっていた。ランチもビュッフェ式だったが、朝食と比べておいしそうな食べ物が多かった。やはりここまで来たらシーフードを楽しまなければ損というもの。エビ、イカ、魚のカレーを食べまくった。
午後2時半にホテルが用意してくれたバスに乗って空港へ。スリランカの空港ではなぜかセキュリティーがデリーよりも厳しく、荷物検査が3回もある。だが、特に何も言われず通過することができた。コロンボの空港でインターネットができるところを見つけたため、少しメールのチェックをした。15分100ルピー。前回の旅行で余ったスリランカのルピーを少し持ってきていたので役立った。しかし日本語の表示・書き込み共にできず、日本語フォントをダウンロードしてみたがなぜかインストールできなかった。残念・・・。
まだ出発まで時間があったので、空港の椅子に座ってくつろいでいた。すると、3人の女の子が話しかけてきた。デリーからコロンボまでの飛行機で近くに座っていた人たちだ。特にそのときは話をしなかったが、一応お互い顔は覚えていた。デリーに7〜8ヶ月留学して特別教育(障害児の教育)の短期コースを修了し、家に帰る途中のモルディヴ人だった。しかも1人は、これから僕が行こうとしているガン島の出身だった(今はマーレに住んでいるらしいが)。モルディヴ人はほぼ100%ムスリムで、女性はあまり知らない男性と話さないかと思っていたが、けっこう普通に会話をすることができた。モルディヴ人の外見は、典型的北インド人とは違う顔をしているものの、海岸沿いのインド人に近い印象である。スリランカ人とも似ている。他にも飛行機の出発を待っている間、数人のモルディヴ人と会話をすることができた。
コロンボ発マーレ行きのスリランカ航空UL103便は午後5時15分発だった。エコノミー席は横に3+4+3座席あるジャンボ・ジェット機だったが、乗客はほとんどおらず、ガラガラ状態。よって好きに移動して窓際に座ることができた。是非上空からマーレを見てみたかったのだが、残念ながら僕が座っていた場所からはマーレを見ることはできなかった。コロンボからマーレまでのフライト時間は約1時間ほど。スリランカとモルディヴの時差は−1時間。よって、モルディヴ時間の午後5時半頃にマーレの空港に到着した。

どの島か分からないが上空から撮影
モルディヴの首都マーレは東西2.5km、南北1.5kmの楕円形の島である。人口はわずか約7万4千人の小さな首都だが、モルディヴの全人口の4分の1が住んでいる。マーレ島の横に島全体が滑走路と空港になっているフルレ島があり、これがマーレ国際空港と呼ばれている。空港で入国審査を終え、早速両替をした。モルディヴでは米ドルが広く通用しており、現地通貨のルフィヤーを持たなくても旅行できてしまうが、それでは味気ないのでルフィヤーを少しだけ持っておくことにした。1万円両替して1146.42ルフィヤーになった。1ルフィヤー=約8.7円の計算になる。
ホテルなどの予約をしていなかったため、早速空港の観光案内所でマーレの適当なホテルを紹介してもらう。とにかく湿気がすごいので、少なくともAC付きで安い部屋、と条件を提案したら、マーレの人口ビーチ(マーレに自然のビーチはないが、人工的に作られた小さなビーチがある。マーレ島の東にある)の真ん前にあるシティー・ビーチというホテルを紹介された。AC、ホットシャワー、TV付きのシングルルームで、40ドル(朝食込み)だった。部屋は大きくもなく、小さくもなくで、清潔に保たれていた。
夕食はホテルのレストランで食べた。フィッシュカレー、ライス、ミネラルウォーターを注文して70ルフィヤー。日本円にすると600円くらい。このホテルのレストランは中級レストランくらいのグレードだろう。それを考え合わせると、インドに比べてモルディヴの物価は2〜3倍くらいだと思う。
今日の予定は、明日からのガン島への滞在のアレンジをすることと、マーレの観光をすることだった。まずは朝食を食べた後、マーレ島を1周グルリと回ってみることにした。午前9時頃から歩き始めたが、もう日差しはかなり強くなっていた。湿気はコロンボよりはマシで、日陰に入ればそれなりに涼しかったが、それでも歩いていると汗がどんどん出てくる。海沿いの道はほとんど日陰がなくて辛いので、海沿いから少し内陸側に入った道を歩いて行った。ホテルのある人口ビーチから時計回りに回り、アミーニー・マグをずっと西へ向かった。ちなみに「マグ(Magu)」とは「大通り」という意味。ヒンディー語で同じ意味の「マールグ」と関係あると思われる。ちなみに狭い通りは「ゴーリ(Goali)」というが、ヒンディー語にも同じ意味で「ガリー」という単語がある。マーレの道は全て舗装されており、建物がビッシリと肩を並べている。多くの建築物の外壁はきれいにペンキが塗られており、遠くからでも目立つカラフルな色の建物も多い。また、時々サンゴでできた伝統的な家も見かけた。街の雰囲気は、インドではディーウやダマンなんかとよく似ているが、マーレの方が近代的な建築物が多く、より発展した印象を受けた。だが、同じような島都市である香港よりは圧倒的に田舎である。マーレの住民の主な移動手段は、小型バイクかスクーターで、道の至る所に無数のバイクが停められていた。中には大型のアメリカン・バイクに乗っている人もいた。リーファンという中国のメーカーのバイクのようだ。デザインはかなり微妙だが・・・。自動車は、トヨタ、スズキ、イスズ、マツダなどの日本車を多く見かけた。かっこいいのかかっこ悪いのか判断しにくいデザインのスポーツカーも走っていた。こんな狭い島でスポーツカーに乗って、どこでスピード出すんだ、と突っ込みたくなるが、多分形だけであまりスピードは出ないのだろう。

アメーニー・マグ
アミーニー・マグをずっと西進すると、20分ほどで島の西端に着き、そこにはインディラー・ガーンディー記念病院がある。そこから今度は進路を北に変え、歩いていくと、すぐにまた海に出る。海沿いの道は、倉庫や工場などが多く、歩いていてあまり面白くない。だが、島の北端には野菜市場や魚市場などがあった。ちょっと市場を覗いてみたが、インドの市場とは同じような店の配置なのにも関わらず、インドとは比べ物にならないくらい清潔感が溢れていた。インド人には公共の場をきれいにするという考え方があまりないが、モルディヴ人はインド人よりも衛生観念は高そうだ。また、マーレの人はきちんと信号を守るのにも気付いた。歩行者は赤信号を無視することもあるが、自動車やバイクに乗っている人は信号を無視することはほとんどない。だが、中には危険なスピードを出しているバイクもいた。あれだけのスピードを出していたら、事故が起こることは避けられないだろう。ここで一句――狭いマーレ/そんなに急いで/どこへ行く。あと、マーレには野良牛や野良犬はいない。その代わり猫を多く見かけた。

果物市場

信号を守る人々
オーキッド・マグ
北端にはジュムフーリー・マイダーンという公園があった。そこの木陰のベンチに座って一息付いた。ここまでずっと休まずに歩いてきたが、それはマーレの街にゆっくりと座って休める場所があまりなかったからだ。まず、あまり大きな木がないため、木陰がない。そして道が狭いため、道には車道と歩道しかなく、人が座れる場所がない。また、僕が歩いてきた場所は住宅街、オフィス街、倉庫街のような場所だったため、冷房の効いた喫茶店みたいなものも皆無だった。
ジャムフーリー・マイダーンから、今度はマーレ北端から中央部に伸びているメイン・ストリート、チャーンダニー・マグを南下した。この辺りには観光客目当てのお土産屋がビッシリと並んでおり、日本語で書かれた看板もいくつか目にした。「竹中直人の店」なる店もある。どうやら店の主人の顔が竹中直人に似ているかららしい。この通りを歩いていると、あちこちから日本語で「オミヤゲ」「ミルダケ」などの声が掛かる。お土産は旅行の最後に買うのがモットーのため、今日はそれらの客引きの声を無視しておいた。

チャーンダニー・マグ
チャーンダニー・マグをしばらく南下すると、今度はマーレ島を東西に横断する、もう1本のメイン・ストリート、マジーディー・マグに出る。マジーディー・マグを東へ向かう。するとマーレのもうひとつの病院、ADK病院を発見。その辺りからちょっと細かい路地に入り、適度に迷った後、海岸沿いの道に出た。そのまま道に沿って歩いていくと、人口ビーチまで戻って来た。この時点で10時半頃だった。
日中はガン島行きの旅行のアレンジに費やした。と言っても、ホテルでずっと待っていただけだが。昨日空港でホテルを紹介してくれた旅行代理店に、ガン島行きのアレンジも頼んでおいた。正午頃にホテルに連絡があるというので、ACの効いた部屋でのんびり待っていた。まず11時頃に電話があり、ガン島行きの飛行機と、ガン島唯一のホテル、イクウェイター・ヴィレッジの部屋、共に予約が可能である旨が知らされた。故意か誤りか、ちょっと高めの値段を提示されたので、ちゃんと「修正」してもらって、それで予約を取ってもらうことにした。その後、引き続き旅行代理店の人間が金を受け取りに来るのをずっと待っていた。1時頃に来ると言われたが、結局来たのは2時過ぎだった。しかしこんなのはインドで腐るほど経験しているので、何とも思わない。
ガン島は、モルディヴ最南端にあるアッドゥ環礁(シーヌー環礁とも呼ばれる)の島である。マーレから南に500km以上離れた場所にあり、赤道を越えた南半球に位置している。地元の人の話では、マーレから船も出ているようだが、丸2日かかるとのことなので、国内線飛行機で一気に飛ぶことにした。往復245USドル。後から聞いた話では、この往復の航空運賃は、一般のモルディヴ人の2ヶ月分の月給に当たるようだ。スリランカまでの往復航空運賃が205USドルらしいので、それよりも高い。僕にとっても安くなかったが、モルディヴでリゾートに宿泊するならそこしかないと決めていたし、遊覧飛行代込みと考えれば割高ではないだろうと考えて、思い切って購入した。アッドゥ環礁にある唯一のホテル、イクウェイター・ヴィレッジ(日本語に訳すと「赤道村」だ)は、モルディヴに数あるリゾートの中でも一風変わった趣向のリゾートで、しかも日本人もあまり訪れない場所らしい。アッドゥ環礁はモルディヴ諸島の最南端だが、この南にも実は島がある。チャゴス諸島である。チャゴス諸島は英国領となっており、その内のひとつ、ディエゴ・ガルシア島は米軍に貸与されている。ディエゴ・ガルシア島は米軍のインド洋上の最重要拠点だが、いろいろ謎の多い島として知られている。
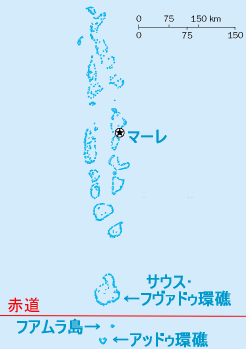
モルディヴ地図
明日からの旅行のアレンジを終えた後は、再びマーレ観光に出た。昨日、コロンボの空港から一緒だったモルディヴ人の女の子がマーレを案内してくれると言ってくれて、電話番号も教えてくれたので、その子に連絡を取って案内してもらうことにした。名前はシヤーという。障害児の教育をしている教師で、デリーに8ヶ月留学していた。ヴァサント・ヴィハールに住んでいたそうだ。昨日デリーから帰国したばかりだというのに、今日からもう働き始めていた。彼女の仕事が終わる2時半以降に落ち合った。シヤーはインドで買ったパンジャービー・ドレスを着て来ていたが、モルディヴ人はあまりパンジャービー・ドレスを着ないらしく、みんなからジロジロ見られていた。おそらく「こいつはインド人か、モルディヴ人か」と思われていたことだろう。

シヤーちゃん
まずは国立博物館へ行った。国立博物館の建物は、かつてモルディヴを統治していたスルターンの宮殿の一部である。と言っても小さな3階建ての建物に過ぎない。入場料は3USドル。内部は冷房が効いていて、涼むにはちょうどいい場所だ。展示物の多くは、スルターンが使用していた調度品など。こういう展示物はインドでも嫌というほど見てきたので、あまり面白味はない。見てみたかったのは、モルディヴがイスラーム化する前の遺物である。古代のモルディヴでは仏教やヒンドゥー教が信仰されていたが、伝説では1153年にモロッコ人バルベリが海の魔人ジンニーをコーランの力により退治したことで、全ての住民がイスラーム教に改宗したとされている。今ではイスラーム教は国教となっており、100%の人がイスラーム教を信仰している。信教の自由はない。だが、モルディヴ各地からは仏教遺跡などが発掘されており、僕としてはそちらの方に興味があった。国立博物館には、それらの仏教遺跡から出土した出土品が少数ながら展示されていた。車輪、卍、魚などの絵が刻まれた板、銅版が保存されていたという箱、仏像、仏頭、動物を象った像などである。特に巨大な仏頭は考古学的にも美術的にも価値が高いと思われる。それ以外には、タミル語に似た古代の文字、コインのコレクション、モルディヴ最初の印刷機などが興味深かった。

車輪、卍、魚などが刻まれた石版

巨大な仏頭

仏像

亀

牛、との説明があった

1969年7月20日に月面着陸に成功したアポロ11号と共に
宇宙へ行ったモルディヴの国旗と、月の石の小片

無線機

モルディヴ最初の印刷機
文字はアラビア文字
マーレの見所といっても、観光に値するのはこの博物館くらいなもので、あとは繁華街をブラブラしてショッピングに付き合ってもらった。まず欲しかったのはモルディヴの言語の独習書みたいなもの。旅行先の言語の本を買い集めるのが趣味で、旅行中少しでも現地の言葉が話せるようになればといつも思っている。繁華街のいくつかの本屋を回って、モルディヴの公用語、ディヴェヒ語について解説してある本を探してもらった。まず、マーレで一番大きい書店ノベルティー・ブックショップで、「Dhivehi-English
Dictionary」という小冊子を手に入れた(35ルフィヤー)。この書店は「モルディヴ大辞典」なる大型の辞書も置いてあったが、それはさすがに買わなかった。まだ他にいい本はないかと思って、見つけた本屋に片っ端から入って聞いてみたが、見つからなかった。だが、意外にこういう本は書店ではなく、観光客向けのお土産屋に置いてあった。本と同時に水着を探していたのだが、水着が置いてある土産物屋でついでにディヴェヒ語の本について聞いてみたら置いてあった。「Maldives
Dhivehi Phrasebook」と、日本語の「ディヴェヒ語会話」を購入した。その後、イクウェイター・ヴィレッジの前にあった土産物屋で、「Practical
Dhivehi」という小冊子も手に入れた。
また、モルディヴで人気の歌手のCDを1枚紹介してもらった。シヤーちゃんお勧めは、「Zero Degree Atoll」というバンド。ロンリー・プラネットにも載っているくらい有名なバンドだ。勧められたCDは「Dhoni」。オールを漕ぐ音が入っていたりして、モルディヴっぽさがありながら、音楽自体はインドの最新ポップスに近く、なかなか良かった(175ルピー)。
だいぶ歩き回って疲れたので、ACの効いたレストランで一休みした。そこで、メニューに「ノン・アルコール・ビール」なるものがあるのを見つけた。モルディヴはイスラーム国であるため、リゾート以外での飲酒は禁止されている。マーレでは一滴も酒を飲むことができない。「ノン・アルコール・ビール」と聞いて真っ先に思い浮かべたのは、「フルーツ・ビール」である。デリーのディッリー・ハートなどに「フルーツ・ビール」という変な飲み物があり、僕はけっこう好きなのだが、おそらくそれのことだろうと思い、この「ノン・アルコール・ビール」を注文してみた。ところが、出てきたのは発泡酒だった。そういえば普通の発想ならアルコール分のないビールと言ったら発泡酒のことだ・・・。

オランダ製発泡酒アムステルダム
その後、シヤーちゃんはまた用事があるようなので、ホテルまで送ってもらって別れた。ガン島から帰ってきたらまた連絡をすることを約束した。
ところで、僕は南アジアの国々を旅行するたびに、ヒンディー語がどの程度通じるかを密かに調べているのだが、モルディヴでもヒンディー語はかなり流通していた。ヒンディー語の読み書きができるモルディヴ人はほとんどいないが、ボリウッド映画を子供の頃から見ているため、聞いて理解できる人は多く、片言ながら話すことができる人も少なくない。ホテルの部屋にはテレビがあったので、暇なときに見ていたのだが、放映されているのはほとんどインドのTV番組である。インドに住んでいるときにインドのTV番組を見ても何も感じなかったが、外国にいてインドのTV番組を見ると、違った角度から見ざるをえなかった。これだけ毎日インドのTV番組が大量に垂れ流しにされていたら、モルディヴ人がインドの文化に洗脳されてしまうのはごくごく自然なことだ。南アジアの中でインドの存在は、まず地理的に巨大だが、それ以上に目に見えない部分でとてつもなく巨大であることを実感させられた。また、TVを見ていたら面白いことに気付いた。イスラーム教では日に5回の礼拝が義務付けられているが、その礼拝の時間になると、番組が中断されて以下のような画面が10秒ほど映し出される。

礼拝の時間を知らせる画面
マーレとガン島を結んでいる航空会社は、アイランド航空サービスという会社である。飛行機の便名はQ23211。午前11時、マーレ国際空港発だった。よって朝9時前にホテルをチェックアウトし、タクシーで空港行きのボートが出ている桟橋まで行って(15ルフィヤー)、9時発のボートに乗って空港のあるフルレ島へ渡った(10ルフィヤー)。
空港の出発口には、当然のことながらモルディヴでの滞在を終えた人々がたくさんいた。飛行機の行き先の関係だろうが、白人観光客ばかりだった。中には肌が痛々しいほど真っ赤になっている人もいた。午前9時半にガン島行き国内線飛行機のチェックインが開始された。真っ先にチェックインした僕は、窓際の席をリクエストした。向こうもよく分かっているようで、窓際の席は外国人観光客に優先的に割り振っているようだ。
マーレ国際空港は国内線も国際線も同じ建物だった。空港内にあるレストランで、滑走路を離着陸する飛行機を眺めながら時間を潰した。出発ゲートは11時頃やっと開いた。飛行機は37人乗りのプロペラ機。乗客は8割がモルディヴ人。残りは外国人で、僕以外は全て白人だった。ガン島にはイクウェイター・ヴィレッジしか宿泊施設がないので、自動的に外国人は全員イクウェイター・ヴィレッジの宿泊客かと思っていたのだが、1人の白人はガン島へ着いた途端、駐車場に停めてあった自家用車に乗って走り去ってしまった。ガン島に住んでいる白人だったのだろうか・・・。

ガン島行きのプロペラ機
それはいいとして、席に着いて飛行機の離陸を今か今かと待っていた。まずは「アッラーフ・アクバル、アッラーフ・アクバル・・・(アッラーは偉大なり)」とお祈りのアナウンスがあった。座席の前のポケットにもアッラーを讃える文句が書かれた紙が入っていた。思わず両手の手の平を上に向けてアッラーに空の旅の無事を祈願した。と、何かディヴェヒ語でアナウンスがあり、ドアが開いて、飛行機を下ろされてしまった。・・・どうやらタイヤがパンクしていたらしい。急に不安になってきたが、まあ出発前にトラブルが判明してセーフだったと考えるべきだろう。アッラーは、げにまっこと偉大なり!

パンクしたタイヤ
また空港の出発ロビーまで戻されて、しばらく待っていた。出発ロビーに置いてあったテレビでは、テレビジョン・モルディヴ(TVM)というモルディヴのTV局の番組が放映されており、モルディヴ映画が放映されていた。インド映画を「ハリウッド映画の劣化コピー」と揶揄する人が多いが、モルディヴ映画は完全に「インド映画の劣化コピー」としか言いようがない。何を言っているのか分からないのでストーリーを追うことはできなかったが、途中でミュージカル・シーンが入るのはインド映画の文法そのものであり、しかもその質はインド映画のどの駄作よりもひどい出来だった。
結局30分ほどで飛行機の修理は完了し、再び飛行機に乗り込んだ。今度はすぐに飛行機は発進し、離陸した。だが、ここでひとつの誤算があった。僕は是非上空からマーレの写真を撮りたかったのだが、僕の座っていた進行方向に向かって左側の窓は、マーレの反対側になってしまった。空港のあるフルレ島はマーレ島の東側にあり、滑走路は南北に伸びている。飛行機は南へ向けて飛び立ったので、右側に座っていないとマーレは見えなかったのだった。その後も上空からモルディヴの島々を眺めることができたが、左側の窓よりも右側の窓の方が多くの島を眺めることができていたように感じた(隣の芝生が青く見えただけかもしれないが)。ガン島行きの飛行機は右側の窓際の席が特等席だと言えるだろう。それでも、モルディヴの美しい環礁と島々を写真に収めることができた。モルディヴの島は、輪っか状の環礁の上に乗っかっていることが多く、上空から見るとその様子がよく分かる。モルディヴには26の環礁があるという。英語で環礁のことを「atoll」と言うが、これはディヴェヒ語で「中央にラグーンを持つ珊瑚礁の島」を意味する「atolu」が語源だそうだ。環礁がなぜできるのかはまだ謎らしいが、洋上の島が海中に沈み、それを中心に珊瑚礁が形成され、やがて珊瑚礁の上に樹木などが茂って島になるというのが定説だとか。ということはこのラグーンの下にかつての島が沈んでいるということか・・・。また、国名「モルディヴ」の語源は、サンスクリト語の「マーラードイープ(花輪の島)」らしい。まさに花輪の島々である。ただ、窓があまりきれいではなかったので、写真はぼやけてしまった。

環礁

細長く連なる島々

これはアッドゥ環礁のフルミードゥ島
飛行機は赤道を越え、モルディヴ最南端のアッドゥ環礁上空へ入らんとしていた。すると、飛行機の乗務員から1枚の紙を渡された。見ると、赤道を越えたという証明書だった。当然のことながら赤道に赤い線などはなく、いつ越えたのか分からなかったが、まあ人生の中でひとつの達成と言えるだろう。昔オーストラリアに行ったときに越えたことはあるが・・・。どっちにしろ、観光客には気の利いたサービスである。
アッドゥ環礁は、モルディヴ最南端にあるハートの形をした環礁で、そのハートのとがった先にあたる位置にある最南端の島がガン島である。一説によると、「ガン」という名称は、ヒンディー語で「村」という意味の「グラーム」と関連しているらしい。ガン空港には1時間ほどで到着した。空港の前にはイクウェイター・ヴィレッジのバンが待っており、それに乗り込んだ。空港からイクウェイター・ヴィレッジは目と鼻の先だった。いったいどんなところかと思っていたが、けっこうきれいに整備された、過ごしやすそうなリゾートだった。スタッフも皆親切だった。

イクウェイター・ヴィレッジの入り口
イクウェイター・ヴィレッジは、元々英国空軍(RAF)の基地だった場所である。モルディヴは1887年に英国の保護領となったが、ガン島に基地が作られたのは第二次世界大戦中だ。スリランカ独立後、1956年にRAFの基地がガン島に移され、フェイドゥ、マラドゥ、ヒタドゥなどの近隣の島を土手道でつないだ。1965年、モルディヴは英国より独立し、1976年、RAFはこの基地を引き払った。その後、兵士たちの宿舎はホテルに改造され、イクウェイター・ヴィレッジとしてオープンした。イクウェイター・ヴィレッジの特徴は、まずモルディヴの数あるリゾートの中でも格安であること。料金はシングル110USドル、ダブル140USドル、トリプル186USドルで、朝昼晩の3食、酒類、各種娯楽(シュノーケリング・ツアー、アイランド・ホッピング、フィッシング・トリップ、卓球、テニス、ビリヤード、自転車)など全て込みである。他の一般のリゾートの1泊の宿泊料金が、下は約200USドルから上は2000USドル以上とかなり高いのに比べると、非常に安い。そして、イクウェイター・ヴィレッジのもうひとつの特徴は、自分でいろいろ島々を探検できることである。モルディヴの一般のリゾートは1島1リゾートという構造であり、リゾートのある島は1周せいぜい数十分の大きさで、地元の住民は住んでいない。もしひとつのリゾートに宿泊したら、アイランド・ホッピングなどのエクスカーションに参加しない限り他の島へ行くことができない。ところが、このイクウェイター・ヴィレッジのあるガン島は、他の4つの島と土手道でつながっており、ホテルで無料レンタルできる自転車で自由に行き来できる。これら5つの島々には地元の人々も住んでいる。地元の人々の生活に簡単に触れることができるのが、僕がこのリゾートに惹かれた最大の理由である。リゾート利用客はドイツ人、イギリス人、イタリア人、ロシア人などが多く、日本人もたまに泊まりに来るとか。かつてこの基地に駐屯した退役軍人もけっこう来るらしい。確かにやたら図体がでかくて強そうなおじいさんを何人かホテルで見かけた。ただ、このリゾートの欠点は、他のリゾートに比べて娯楽性に欠けることである。モルディヴ随一のダイビング・スポットが近くにあり、ダイビングをするには絶好の場所らしいが、その他の最新マリン・スポーツ設備やナイト・エンターテイメントなどはなく、そういうのが目当ての人には退屈極まりないリゾートだ。また、ガン島にはビーチと呼べるような砂浜はほとんど存在しない。宿泊客も、年配の夫婦が多く、若者はほとんどいなかった。このリゾートは、静かに休暇を過ごしたい人か、とにかくダイビング目当ての人か、または僕のように地元住民と触れ合いたい人に向いていると言える。

ロビー
イクウェイター・ヴィレッジに着くと、ウェルカム・ドリンクを出され、チェックインをした。旅行代理店にもらったホテル・バウチャーとマーレ行きの航空券を渡すと、部屋の鍵とホテルの説明が書かれた1枚の紙を渡された。その紙によると、オール・インクルーシブの宿泊代に入っている無料のナイト・フィッシング・トリップは土曜日、アイランド・ホッピング・トリップは木曜日に行われる一方、ガン島の隣の島、ヴィリギリ島(この島は土手道でつながっていない)へのシュノーケリング・トリップは毎日2回行われているようだ。安いリゾートだったので、部屋に大した期待はかけていなかったのだが、テラスハウス式の部屋で、なかなか広くて清潔で満足。AC、ホット・シャワー、冷蔵庫などは完備だが、TVや電話はない。マルチタップがあるので、日本の電化製品のコンセントも使用可能である(ただし電圧は220〜240V)。シャワーの水圧が低いことが不満点だったが、モルディヴでは真水が不足しており、水を節約しなければならないという事情があるので仕方ないだろう。僕の泊まった102号室は海に近い部屋で、夜には打ち寄せる波の音が延々と耳に入ってきた。

102号室玄関

ベッド

バスルーム
イクウェイター・ヴィレッジの食事は3食ともビュッフェ形式である。チョイスはあまりなく、朝食はパン数種類、サラダ、卵、フルーツ、ジュースなど、昼食と夕食はスープ、サラダ、ライスとヌードル、カレー(魚、牛、豚など)数種類、フルーツやデザート、というのが一般的な構成である。夕食は日ごとにテーマが決められており、チャイニーズ・ナイトとか、ウェスト&イースト・フードとかあった。味は決して悪くない。また、スタッフには一言二言日本語が話せる人が多い。

夕食の様子

レセプションの女の子

スタッフのおじさんと共に
昼食を食べた後、早速自転車を借りて冒険へ出かけた。ビーチはないと聞いていたが、どこか泳げそうなビーチがあったら泳ごうと思い、水着を着てそのまま自転車をこいだ。実は隣の島へ行こうと思っていたのだが、道なりに進んで行ったらガン島1周コースに入ってしまったので、まずはウォーミング・アップをすることにした。このガン島1周コースの最大の見所は、空港の滑走路を自転車で横切ることができることだ。ガン島の東から西にかけて滑走路が横断しており、滑走路の隅を横切らないと向こう側に行けないようになっている。一応滑走路に入る前にチェックポストがあるが、聞いてみたら「滑走路に入るなよ」と注意されただけで通してくれた。だが、それ以外はほとんど何もないところだった。延々とココナッツの並木が続いている他は、何の見所もなかった。そのままイクウェイター・ヴィレッジに戻って来てしまった。とりあえずこれだけで汗ビッショリになったので、リゾートのプールに入って身体を涼めた。プールにはバーがあり、ジュースなどを飲むことができる。これらの料金も宿泊料金に含まれている。

滑走路に入る道にあった注意書き
「止まれ
信号を守り、飛行機に道を譲ること」

イクウェイター・ヴィレッジのプール
プールで休憩した後、そのまま濡れた水着を着て再び冒険へ旅立った。今度は土手道を通って隣の島へ渡った。アッドゥ環礁の南西の5島は土手道で一直線のつながっている。順に、ガン島→フェイドゥ島→マラドゥ島→アブーヘラ島→ヒタドゥ島となっている。もちろん目標はヒタドゥ島の先端である。ガン島からヒタドゥ島の村までずっと舗装道路が続いており、走行は楽だったが、あまり日陰がないため、日中のサイクリングはかなり大変だった。しかも自転車の性能があまりよくなくて、足の漕ぐ力が効率的にタイヤに伝わっていないような感じだった。必死で自転車を漕いでいる僕の横を、僕よりも明らかに足の回転数が少ない、おじいさんが運転する自転車が悠々と追い抜いて行ったりした。だが、景色はなかなか面白く、ヤシの並木が延々と続く道や、何やら近代的な施設があったりした。アブーヘラ島までは余裕で辿り着けたのだが、ヒタドゥ島に入ってからはかなり長かった。なぜならヒタドゥ島は非常に細長い島だからだ。舗装道路の最後には村があり、その先はジャングルになっていた。一応獣道が延びていたので、それに沿ってさらに走って行ったら、遂にヒタドゥ島の先端まで辿り着いた。ここには昔、砦か何かがあったらしいが、今では跡形もなく、ただ1本の灯台が立っているのみだった。この先端部はコーテー、またはデーモン・ポイントと呼ばれている。何やら不吉な名前だが、確かに地の果てのような奇妙な雰囲気の場所だった。3時過ぎにイクウェイター・ヴィレッジを出たが、ここに着いたときには5時頃になっていた。ここに来るだけで2時間かかったことになる。帰りが思いやられる・・・。
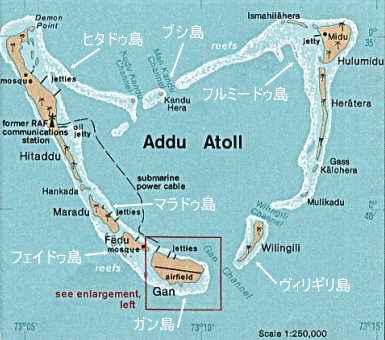
アッドゥ環礁地図

デーモン・ポイント
とは言え、暗くなる前に帰らなければならないので、ほとんど休まずに引き返した。日が傾いて来ており、日陰の面積が増え、風も涼しくなり、気候はだいぶ楽になったが、疲労は容赦なく身体に蓄積しており、力いっぱい自転車を漕ぐことが困難になっていた。また、サドルが硬いので、尻が痛くなっていた。途中休んだり、自転車を押して歩いたりしながらノロノロと進んでいる内に、辺りは真っ暗になってしまった。だが、どうも真っ暗になってからの方がモルディヴの見かけ上の人口は増えるようだ。行きのときは道の途中でほとんど人に会わなかったのだが、帰り、真っ暗な道を走っているときには多くの現地人を道路上で見かけた。みんな海沿いの堤防に座ったりしてくつろいでいた。やはり帰りも2時間ほどかかり、7時頃にイクウェイター・ヴィレッジに戻って来た。夕食を食べた後、バッタリとベッドに倒れこんで爆睡したのは言うまでもない。
ちなみに、せっかく水着を着てサイクリングに出かけたのだが、「南国のビーチ」というイメージに少しでも当てはまるような美しいビーチは、これらの島々には本当に存在しなかった。美しい砂浜と海で世界的に有名なモルディヴとは言え、全ての島にそれらのものが存在するわけではないようだ。これは逆に発見と言えるかもしれない・・・。
イクウェイター・ヴィレッジに来た理由のひとつは、「何もしない」ことだった。今年に入ってからずっと忙しく、「何もしない」ことをしたいとずっと思っていた。また、僕は友達からよく「何かしてないと駄目な人」と言われるので、試しに一度、とにかく何もしないことにしようと思い、何もないこの辺境の島に来たのだった。確かにイクウェイター・ヴィレッジは、「何もしない」ことを目的にする人には絶好の場所である。もし「世界の辺境のリゾート100選」みたいな企画を立てたら、このリゾートは絶対にランクインするだろう。だが、昨日は早速いつもの癖が出て、大冒険をしてしまった。おかげで今日の午前中はずっと部屋で休むことになった。
今日は、モルディヴ人の村に入って行って、人々の生活を垣間見る予定だった。マーレの旅行代理店でホテルと飛行機の予約をしたとき、そこで務める人の1人が、イクウェイター・ヴィレッジがあるアッドゥ環礁の出身だった。実はこの旅行代理店は、インドで培った僕の鑑識眼には、マフィア崩れのいわゆる「怪しいボッタクリ旅行代理店」に映ったのだが、アッドゥ環礁出身の彼の存在が僕に安心感を与えた。彼は僕に、「ガン島へ行ったら、俺の妹に是非会ってくれ」と、自分の妹の名前と住所を僕に教えてくれたのだ。そこまでしてくれるなら、少なくともお金だけかっさらってトンズラするようなところではないだろうと思い、安心して大金を渡すことができた。コミッションは少し取られたが、それでも10USドルくらいのもので、無事にイクウェイター・ヴィレッジに着くこともできた。昨日は苦労してガン島から一番離れたヒタドゥ島まで自転車で行ったのだが、妹が住んでいるのはちょうどガン島の隣のフェイドゥ島であり、すぐに行けることから、今日は本当に妹を訪ねてみようと考えていた。
前述の通り、午前中は疲れが溜まっていたこともあり、部屋でノンビリして過ごした。なぜか部屋は非常に快適で、ベッドに寝転がると永遠に眠っていられそうなほど気持ちが良い。部屋でPCに向かって旅行記をまとめていたら、突然裏口のドアがノックされ、次にガチャッと開いた。驚いて見に行ってみると、掃除係のお姉さんだった。いくら掃除のためとは言え、客室のドアを突然開けるのはちょっといただけない。しかしそのお姉さんは、いかにも「南国の孤島の原住民」みたいな、かなり純朴そうな人だったので怒る気にはなれず、そのまま掃除をしてもらった。ついでに少し会話をしてみた。英語があまりできなさそうだったので、昨日買ったディヴェヒ語の会話集を取り出して、「アハレンゲ・ナマキー・〜(私の名前は〜です)」とか、いくつかフレーズを試してみた。モルディヴの公用語は、マーレで話されているディヴェヒ語だが、やはり環礁や島ごとに方言はあるようで、特にマーレから最も離れた場所にあるアッドゥ環礁はかなり独自の方言を持っている。だが、政府の公用語普及政策のおかげか、ディヴェヒ語は誰でも分かるようだ。そのお姉さんに「あなたはムスリムか?」と聞かれたので、僕は「仏教徒だ」と答えた。するとお姉さんは、「ブッディスト、ノーグッド」と言った。モルディヴ人は、仏教やヒンドゥー教からイスラーム教に改宗した歴史を持っているからか、どうやら仏教に対してはあまりいい印象を持っていないようだ。僕は割といろんな国を旅行しており、それらの国々で「私は仏教徒だ」と公言しているが、「仏教徒はよくない」と言われたのはこれが初めてだった。だからちょっと驚いた。一応場を取り持つために、イスラーム教徒の聖句とも言える「ラー・イラーハ・イッラッラー・ムハンマダン・ラスーッラー(アッラーの他に神はなく、ムハンマドは預言者なり)」と唱えておいた。また、そのお姉さんはフェイドゥ島に住んでいるそうなので、例の妹のことを知っているか聞いてみたら、「すぐ近くに住んでいる」と言っていた。道順も教えてもらった。彼女の名前を口にしただけですぐに反応があったので、この分ならすぐに妹の家を見つけることができそうだと確信した。
軽くプールで泳ぎ、昼食を食べた後、自転車に乗ってフェイドゥ島へ向かった。土手道を進んでいるときに、イクウェイター・ヴィレッジのレストランで働いているアリー氏がちょうど通りかかった。イクウェイター・ヴィレッジの従業員は皆フレンドリーなので、すぐに顔見知りの友人になれる。どうやら昼休みで自宅へ向かうところらしい。彼もフェイドゥ島在住とのこと。そこでその妹のことを聞いてみたら、やはり知っていた。この島の人はみんな顔見知りなのだろう・・・。フェイドゥ島の人口は2000人強らしい。そのまま彼に、妹の家まで案内してもらった。
妹の名前は一応仮名にしてファシーちゃんとしておく。ファシーちゃんの家はおかげですぐに見つかった。突然訪ねて行ったら失礼かと一瞬躊躇したが、やはり村の人は底抜けに親切で、僕のような見知らぬ旅人を何の疑いもなく家に上がらせてくれた。「上がらせてくれた」と表現したのは、この家は日本の家屋のように土間があり、靴を脱いで上に上がる構造になっていたからだ。昨日自転車で島々を巡ったときにチラッと覗いたいくつかの家屋も、そのような構造になっていた。
ファシーちゃんの家は、村の中でもかなり立派な方だった。父親はどこかのリゾートのレストランで働いているらしく、マーレで会った兄も旅行代理店で働いているので、収入はモルディヴ人の中でも少ない方ではないだろう。マーレで会った兄が長男で、その次がファシーちゃん、その下に2人の弟、そして末っ子の妹がいた。ファシーちゃんは歌手らしく、イクウェイター・ヴィレッジで歌ったこともあるとか。次男もまた高級リゾートで働いていたらしいが、今は村に帰っている。三男はまだ高校生で、次女は中学生だった。主にファシーちゃんと次男のマフ君(仮名)が応対してくれたが、お祖母さんも話を聞いていた。ただ、お祖母さんは英語が分からなかった。家には2台のソニー製TV、1台のPC、ビデオデッキなどなどがあり、インドの一般の家庭よりも裕福だと感じた。家に着いた途端、コーラとビスケットを出してもらい、その後モルディヴの伝統的なスナックやコーヒーまで出してもらった。ファシーちゃんは僕とほぼ同じ年で、明るくてかわいい娘だった。マーレでも女の子に案内してもらったし、1人でモルディヴへ来て正解だったと思う。

ファシーちゃんと兄弟

ファシーちゃんの家の一室
最初は、マーレでお兄さんと会ったこと、イクウェイター・ヴィレッジに泊まっていること、インドに住んでいることなどなどから話し始め、彼らといろいろ話をした。モルディヴ人は皆英語がうまいかと思っていたが、彼らの英語はネイティヴ・スピーカーからは程遠いもので、僕と同じくらいの英語力だった。おかげでかえって意思疎通ができた。話している内に、だんだんと物凄いことも分かってきて貴重な体験となった。
まず、マーレで会ったお兄さんは、実はすごい経歴を持った人だった。仲間の誰かが警察に射殺されたことをきっかけに、仲間と共に警察に反抗して撃たれ、しかも逮捕されて牢獄にぶち込まれたらしい。そのときの写真がなぜか彼らのPCに入っていた。ネットから手に入れたらしい。その写真には、腹を撃たれて血まみれになった兄の姿が映っていた。しかもこのとき左手の指を2本失ったらしい。マーレで会ったときには気付かなかったが。それらの写真をなぜ僕に見せるのかと思い、彼らの表情をチラリと見てみたが、ファシーちゃんもマフ君も淡々とした表情をしていて、さらに不思議になった。僕が「お兄さん、今はもう元気だよね?」と聞いたら、ファシーちゃんは物悲しいような、それでいて冗談めいたような笑みを浮かべて、「でも指が3本しかないのよ」とつぶやいた。
次に、オサマ・ビン・ラディーンによるプロパガンダ映像を見せられた。そこに映し出されていたのは、パレスティナやインドネシアなどの宗教対立で殺されたムスリムたちのグロテスクな死体ばかりであり、イスラーム教徒たちを奮起させるようなナレーションがアラビア語で流されていた。若いオサマ・ビン・ラディーンが元気に動いている映像もたくさんあった。恐る恐る、「オサマ・ビン・ラディーンについてどう思ってる?」と聞いてみると、「彼はよくない」と答えたので、ホッと一安心した。だが、やはりなぜこんな凄惨な映像を見せられないといけないのか、不思議に思った。
そして今度はモルディヴの政治の話になった。今まであまり気付かなかったが、モルディヴの政治はかなり悪い状態のようだ。大統領には、行政、司法、立法、軍事、警察など全ての権限が集中しており、しかも20年以上も同じ人が大統領の椅子に座り続けている。大臣は皆、大統領の血縁者ばかりだ。選挙は一応行われるが、大統領に歯向かう立候補者は選挙前に逮捕・投獄されるという有様であり、八百長もいいところ。一応、現行政府に反対する政党はあるのだが、モルディヴ国内では活動できず、スリランカに亡命して政治活動を行っている。大臣たちは特別パスポートを所有しており、外国から自由に麻薬を持ち帰って、国内の若者を薬付けにしている。・・・これらの話を聞いている内に思った・・・モルディヴっていわゆる悪の枢軸みたいな国じゃないか!こうして見てみると、南アジアは独裁国家ばかりだ。ネパールのギャーネーンドラ国王しかり、パーキスターンのムシャッラフ大統領しかり・・・。こういう事情だから、独裁政権の象徴である警察に歯向かったお兄さんは英雄なのだろう。偶然、マーレでモルディヴにずっと関わった経歴を持つ日本人に会ったが、その人が「モルディヴは商売しづらい国だ」と漏らしていたのを思い出した。
だんだん暗い話になってきたので、マフ君と共に外に出て、フェイドゥ島を自転車で一周した。フェイドゥ島の村がいつ出来たのか知らないが、道路が直線的かつ直角に交差しており、非常に整った家並みだと思った。家の多くは珊瑚でできており、必ずと言っていいほど1.5〜2mほどの高さの塀で囲まれ、家には小さな庭があった。人々は、ジョリとかウンドリと呼ばれる独特の形のハンモックに座ってくつろいでいた。また、所々にはバレーボールのコートがあり、夕方に子供や大人がバレーボールをして遊んでいるのを見かけた。ガン島側にはサッカー・グラウンドもあり、やはり夕方に若者たちがサッカーをして遊んでいた。フェイドゥ島の礁湖(ラグーン)側には港があり、マーレや、アッドゥ環礁の北にあるフォアムラ島から来た船が停まっていた。飛行機に乗れない貧しい住民は、これらの船に乗って島を行き来するらしい。ちょっと船の中を拝見させてもらったが、ベッドのようなものはなく、これで数日かけて航海をするのは外国人には非常に困難だと実感した。港の近くには、村人たちの憩いの場のようになっている場所があり、老人たちが石並べみたいなゲームをして遊んでいた。2人で対戦し、1つずつ石を移動させて同じ色の石を3つ揃えるのが基本ルールらしいが、詳細はよく分からなかった。

フェイドゥ村の風景
直線と直角交差を基本とした
非常に整った家並み

ウンドリと呼ばれるハンモック

ローカルの貨物旅客船

船の内部

石並べゲーム
マフ君とファシーちゃんには、またガン島滞在中に立ち寄ることを約束して、イクウェイター・ヴィレッジに戻った。当初の目的通り、地元の人々とノンビリと交流することができて大満足の1日だった。
あまり知られていないが、ダイビングや高級リゾートで有名なモルディヴには、けっこう古代遺跡もある。保存状態がよくないためか、はたまたムスリムの国なのでイスラーム教伝播前の歴史に興味がないためか、遺跡を巡るツアーみたいなものは聞いたことがないが、元々遺跡好きな僕は、どうしてもモルディヴで遺跡を見てみたかった。最初に目を付けたのは、アッドゥ環礁から北に100kmほどの地点にあるサウス・フヴァドゥ環礁のガン島であった。アッドゥ環礁のガン島とは別の島であり、こちらは無人島だ。どうやらこのガン島には、高さ8.5m、23m四方のメキシコ式ピラミッドの遺跡が残っているらしい。紀元前500年頃までモルディヴに住んでいたとされるレディン人の遺跡で、そこで太陽崇拝が行われていたと考えられている。つまり2500年以上前の遺跡ということになる。この記述を見た途端、何が何でも行ってみたくなり、イクウェイター・ヴィレッジのレセプションやスタッフ数人に聞いてみたが、ガン島を見たことがあるという人はいたものの、ガン島に上陸した人はおらず、そこまで行くのも難しいとのことだった。陸上だったら交通手段はどうとでもなるが、相手が海だと無理はできない。残念ながらこの遺跡まで行くのは諦めた。
次に行きたくなったのは、アッドゥ環礁とサウス・フヴァドゥ環礁の間にあるフアムラ島である。ほぼ赤道直下にあるフアムラ島は、他のモルディヴの島と違って、環礁上の島ではなく、ひとつの独立した島となっている。中東、インド、東南アジアを結ぶ要衝にあるため、昔から多くの航海者が訪れており、イブン・バットゥータも1344年に2ヶ月この島に滞在したとか。フアムラ島には、高さ7mの仏教のストゥーパ跡や、古いモスクが残っている他、美しいビーチや、2つの湖などがあるらしい。実は昨日訪れたファシーちゃんのお祖母さんやお母さんはフアムラ島から嫁いで来ており、その関係でフアムラ島の話をたくさん聞かされた。それだけたくさん聞くと、行ってみたくなるのが人情というもの。午前9時にフェイドゥ島から、フアムラ島行きのスピード・ラウンチと呼ばれる高速船が出ており、1時間ほどで着くらしい。だが、同日中にその船がフェイドゥ島に帰って来るかは乗客の数に依るそうだ。また、フアムラ島は観光客向けに開かれた島ではなく、宿泊施設などはない。19日の今日行って、最悪明日の朝の便で帰って来ることも考えていたが、やはり難しそうなのでやめることにした。
そこで、今日はイクウェイター・ヴィレッジが毎週木曜日に主催しているアイランド・ホッピングに参加することにした。このトリップは宿泊代に含まれているので、参加しておかないと損である。だが、他にもけっこう多くの宿泊客がいるにも関わらず、なぜか参加者は僕しかいなかった。午前9時頃、小型のボートでガン島を出港した。
アイランド・ホッピングでは、アッドゥ環礁内の、土手道でつながっていない島、フルミードゥ島と、やはりアッドゥ環礁内の無人島、ブシ島を訪れる。まずはラグーンを縦断して、フルミードゥ島へ向かった。モルディヴの海は聞きしに勝るほどの美しさで、途中イルカが飛び跳ねる姿や、トビウオの大群などを目にした。そういうのを見ると、スキューバ・ダイビングをしたくなる。だが、今回は時間と資金の関係からスキューバ・ダイビングはできない。一応昔、タイのプーケット島でオープン・ダイバーのライセンスは取得したが、あれ以来一度もダイビングをしたことがないから、また一からやり直さないといけないだろう。フルミードゥ島にはガン島から約1時間で到着した。
フルミードゥ島は人口3100人のけっこう大きな島である。伝説ではモルディヴ人が一斉にムスリムに改宗したのは1153年とされているが、フルミードゥ島の住民は、アラブ人が乗船した船が難破して漂着したのをきっかけに、既に872年にムスリムに改宗していたと言われている。それが本当かどうかは分からないが、フルミードゥ島にはけっこう大きなイスラーム教の墓地があった。そこには、この島出身で大統領になった人物の墓もあった。また、フルミードゥ島の村もやはり直線と直角交差を原則とした都市設計がなされており、非常に整然としていた。だが、この島には産業がないため、人口の25%はマーレへ移住してしまっているという。ガイドをしてくれた人の家がこの島にあり、そこで休憩したのだが、その人のお母さんが、鰹節のようなものを作っていて興味深かった。

フルミードゥ島の墓地

元大統領の墓

フルミードゥ島の村の風景

鰹節のようなものを作っている
フルミードゥ島を1時間ほど散策した後で、今度はアッドゥ環礁の北部にある無人島、ブシ島へ向かった。一度環礁の外に出てから、回りこむのようにして上陸した。ビーチがあると聞いて楽しみにしていたのだが、大したビーチではなかった。しかも日陰がほとんどない。こんなところに取り残されたら大変だと思った。だが、このときモルディヴへ来て初めて海で泳ぐことができたので感無量だった。しばらく海の中を見て回って魚はいないか探してみた。思ったほど魚は多くない・・・と思ったら、海蛇を見つけて怖くなったことから、陸へ引き返した。ランチボックスが用意されていたので、数少ない日陰の中に身体を丸めて入り込み、昼食を食べた。浜にはやたらとヤドカリがたくさんいた。1時頃、船は出発し、そのままガン島へ戻った。ガン島に到着したのは2時過ぎだった。

ブシ島

ビーチと船、奥には灯台
海の中を泳ぎまわって疲労困憊していたので、そのまま部屋で横になってしばらく休んだ。今日は空にほとんど雲がなく、特別暑い日だった。モルディヴでは、5月は雨季の初めに当たるのだが、津波の後、異常気象が続いているという。4月にたくさん雨が降り、5月にはほとんど雨が降らないとか。昨日は大きな雲が上空に出来て日光を遮っていたのでけっこう涼しかったのだが、今日の日差しは強烈だった。おかげでかなり日焼けした。
夕方5時頃、いくぶん涼しくなったので、自転車に乗ってホテルの外に出た。軽くガン空港までサイクリングしてみた。すると、イクウェイター・ヴィレッジとガン空港の間に、ガン国際空港と書かれた新しい建物があるのを見つけた。まだ使われていないが、警備員の話ではもうすぐオープンするらしい。ガン島の隣のヴィリギリ島に現在シャングリ・ラ・グループの新しいリゾートが建設中で、それが完成すると、ガン島まで国際線が飛ぶようになるという。現在、外国からガン島まで行くには、まずマーレまで行って、そこから国内線に乗り換えてガン島へ行かなくてはならない。だが、ガン島に国際空港ができることにより、外国からの直通便が発着することになり、今まであまり観光地化されていなかったモルディヴ南部の島々にも多くのリゾートが建つことだろう。そうなると、アッドゥ環礁の島々やイクウェイター・ヴィレッジも現在のようにのどかではなくなるかもしれない。ちょうどいい時期にこの辺境の地に来ることができたと言っていいだろう。
暇だったので、昨日に引き続いてフェイドゥ島のファシーちゃんの家を訪ねた。そこでまたも衝撃的な話を聞いた。なんと、今日の午前9時に出港したフアムラ島行きのスピード・ラウンチが、海上で火事になったらしい。そういえばアイランド・ホッピングをしているときに、遠くの方で船から煙が出ているのを見た。そのスピード・ラウンチに乗ってフアムラ島へ行くことを少し考えていたので、その話を聞いたときには背筋がゾッとした。しかもさらに恐ろしいことには、スピード・ラウンチが火災になったという情報だけが村に伝わっているだけで、乗客がどうなったのかは続報がないらしい。おそらくライフ・ジャケットがあるから大丈夫だろう、と楽観的なことを言っていたが、本当に大丈夫だったのだろうか・・・。だが、後から思い返してみると、アイランド・ホッピングに一緒に行ったスタッフたちは、その火災のことを知っていたように思われる。しきりに携帯電話で誰かと連絡を取っていたからだ(モルディヴでは強力な電波塔のおかげで海上でも携帯電話が通じる)。しかし、僕に余計な不安を与えないために敢えて黙っていたのかもしれない。彼らもプロだから、ゲスト優先の行動をしたのだろう。だが、僕に言ってくれれば、僕1人しかゲストはいなかったので、スピード・ラウンチの乗客を救助に行くこともできたのだが・・・。
今日は午後5時50分発の国内線飛行機に乗ってマーレへ戻る予定だった。それまで半日時間があったので、バイクを借りて島々を駆け巡ることにした。さすがに自転車で再びサイクリングする気力はなかった。朝食を食べた後、ホンダのスクーター、ウェーヴ(110cc)をホテルのレセプションでアレンジしてもらった。レンタルバイクはオール・インクルーシブに入っておらず、1日30USドル支払わなければならなかった。半日料金にはしてもらえなかった。

ウェーブ
ところが、いきなり大きな問題にぶつかった。ムスリムの国では金曜日が休日なのは常識だが、モルディヴではガソリンスタンドも金曜日に閉まってしまうのだ。ガン島とフェイドゥ島にガソリンスタンドがあるのは、サイクリングしたときに見つけて知っていたが、そのどちらも閉業していた。レンタルしたスクーターの燃料計は既に「E」を指している。このままでは途中でガス欠になってしまう。そこで、フェイドゥ島のファシーちゃんの家に寄って助けを求めた。そうしたら、同じ島にある雑貨屋を教えてもらった。その雑貨屋ではガソリンを売っていた。おそらくガソリンスタンドよりも割高だろうが、2ドルで3リットルを買うことができた。日本よりもガソリンの値段は安い。これで何とかあちこち走り回れそうだ。このガス欠問題に1時間ほど費やしてしまった。
自転車でヒタドゥ島まで行ったときは、とにかく道の最後まで辿り着くことを目的に必死に自転車を漕いでいたため、あまり村の様子をゆっくり見たり、脇道にそれて探検してみたりすることができなかった。だが、今回はスクーターなので、島の隅々まで見て回ることができた。フェイドゥ島の村はけっこう把握したので、その隣島のマラドゥ島の探索から開始した。土手道でつながったアッドゥ環礁の島々には、ラグーン側にきれいに舗装された道路が通っており、外洋側に村があって、村の中を通る道は舗装されていない真っ白な道となっている。その村の中を通る道をわざとクネクネ曲がるようにして走行した。マラドゥ島には、マラドゥフェイドゥ村とマラドゥ村の2つがある。だが、どこが村の境なのかよく分からなかった。やはり直線と直角交差を基調とした整然とした町並みである。今日は休日のためか、海で泳いでいる子供たちが多かった。また、ジェットスキーに乗ってラグーンを走り回る白人もいた。モルディヴ人と結婚してこっちに住んでいるロシア人らしい。

海で遊ぶ地元の子供たち
次のアブーヘラ島は無人島である。ココナッツの木が延々と続いており、走行すると一番気持ちいい島だ。途中、ラグーン側のココナッツが群生した場所は、地元の人々のピクニック場所になっているらしく、多くの人々が日陰でくつろいでいた。アブーヘラ島を通り抜けると、アッドゥ環礁の主都があるヒタドゥ島である。ヒタドゥ島は探索のしがいがある島だった。島に入るとすぐに大きなスタジアムがあるのだが、その裏には湖があった。また、島の外洋側には、一応ビーチもあった。波が荒いので、ここで泳ぐのは危険だと思われたが、ダイナミックな波を見ることができた。ヒタドゥ島の村は、土手道でつながった5島の村々の中で最も古いように思われた。なぜなら、この島だけ直線と直角交差の都市プランではなかったからだ。大通りはひたすら真っ直ぐの道だったが、脇道にそれると狭い道が複雑に入り乱れており、家も珊瑚で造られているものが多かった。ヒタドゥ島の村を通り抜けて、再び島の先端にあるデーモン・ポイントまでやって来た。既に昼時になっていたので、そこからイクウェイター・ヴィレッジに引き返した。

ヒタドゥ島のビーチ

ヒタドゥ島の村

ヒタドゥ島の子供たち
せっかく30ドルも払ったので、昼食後もうひとっ走りすることにした。今度は、ガン島の端からヒタドゥ島の端のデーモン・ポイントまで、舗装道路をまっすぐ走って何kmあるか測ってみることにした。ガン空港の建物がある辺りまで行って、そこでスクーターの走行距離メーターの数値と時間をメモし、ヒタドゥ島へ向けて走り始めた。そうしたら、ガン島の端からヒタドゥ島の端まで約18kmあった。時間にして30分ほど。かなり暇なことをしてしまった。これで満足したので、スクーターを返して、出発時間が来るまで部屋で休むことにした。だが、この時点で僕の顔は真っ赤になってしまっていた。プールや海で泳ぐときは気を付けていたのだが、ほとんど日陰のない道路を日中無防備状態でスクーターで走行したことにより、思った以上に日焼けしてしまった。もちろん赤道直下の日差しが強烈だったこともあるだろうが、どうもモルディヴの村が道も壁も真っ白であることにも原因があるように思える。雪山にスキーなどに行ったときに、雪に反射した日光により日焼けする雪焼けという現象があるが、ちょうどあれと同じ状態で、白い道路や壁に反射した日光が容赦なく顔などに突き刺さって日焼けしたような感じだ。インドに戻ったらネパール人と間違われる・・・。
ガン島からマーレへ戻る飛行機は、午後5時50分発のQ23212便である。やはり37人乗りのプロペラ機だ。ガン空港は非常にシンプルな構造で、チェック・インをする部屋と、手荷物検査をする部屋しかない。マーレからガン島へ来るときは、東側の景色を見られる、進行方向に向かって左側の席だったので、今度は西側の風景を見るために、左側の席にしてもらった。だが、既に日没が始まっており、残念ながら景色を楽しむことはできなかった。マーレの夜景もほとんど見えなかった。思うに、マーレの航空写真を撮るには、遊覧飛行機に乗るしかないみたいだ。空港の滑走路からだとマーレは少し遠く、またいいアングルにならない。また、アイランド航空サービスの飛行機は、主翼に大きなプロペラが付いており、客席からだとそのプロペラに景色の半分が隠れてしまう。世にも稀な小島都市の写真を是非上空から撮りたかったのだが・・・。飛行機は7時頃にマーレに到着した。

マラドゥ島を上空から撮影
マーレ国際空港から、マーレ行きのドーニに乗り、マーレへ渡った。前回泊まったシティー・ビーチに部屋を予約しておいたので、ホテルの心配はなかった。予約しておいたおかげで、前回よりも広くてテラスがある、いいシングルルームを提供してもらえた。
今日は観光できる最後の日となる。シヤーちゃんに連絡を取ったら、また案内してくれるとのことだったので、朝ホテルまで来てもらった。シヤーちゃんは僕の真っ赤に焼けた顔を見て驚いていた。マーレは大体見て回ったので、今日はマーレ近郊のヴィリギリ島とフルマーレ島へ行くことにした。
ヴィリギリ島は、マーレのすぐ近く、西の方向にある島で、もともとリゾートだったところだ。マーレの人口過密を解消するために住宅地に変更された。言わば衛星都市のようなものだ。マーレとヴィリギリ島の間には定期便が運航されている。また、ヴィリギリ島にはビーチがあるため、週末にはマーレの住民たちが遊びに来る。ヴィリギリ島へ行くドーニ(船)は、マーレの南西部、インディラー・ガーンディー記念病院付近にあるニューハーバーから出ている。片道3ルフィヤー。マーレからヴィリギリ島までは5分ほどである。
このヴィリギリ島へ行くドーニの中で、偶然シヤーちゃんの友人に出会った。名前はアチという。ヴィリギリ島在住で、自宅へ帰る途中だった。ヴィリギリ島を散歩しつつアチちゃんの家まで行った。ヴィリギリ島はマーレよりもさらに小さな島だが、まだそれほど多くの住民は住んでおらず、人通り、車通り共にほとんどない静かな島だった。ちょうど日本でよくある郊外の新興住宅地のような雰囲気である。アチちゃんの家はヴィリギリ島の一番端にあり、海がすぐそばだった。アチちゃんは結婚しており、夫は大統領の警備員らしい。ベッドルームとキッチンしかないような狭い部屋だったが、TVやパソコンなどを持っていた。それにしてもモルディヴ人は皆パソコンを持っているのかと思う。しかもウィンドウズXPのパソコンばかりだ。

ヴィリギリ島
アチちゃん夫婦はこの家に今年の1月から住み始めたそうだ。つまり、津波の後である。彼らの前にここに住んでいた住民は、津波により大被害を受けたらしい。天井に着くくらい浸水して、家電製品が全てパーになってしまったとか。多分それが原因で前の入居者は引っ越してしまい、その後にアチちゃんたちが住むことになったのだろう。モルディヴ全体では津波により100〜150人の死者が出たものの、マーレ付近では死者は出なかったと言われている。
ヴィリギリ島は映画のロケによく使われるらしく、ヴィリギリ島で撮影されたモルディヴ映画のミュージカル・シーンをいくつか見せられた。モルディヴ映画の音楽は、はっきり言ってボリウッド映画の替え歌のレベルに留まっている。インドで聞き覚えのあるイントロが流れてきたと思うと、突然モルディヴ人歌手によるディヴェヒ語の歌が始まる。ヒンディー語とディヴェヒ語には、似たような言葉が多いため、聞いていると時々意味が分かる単語が出てくるのだが、ヒンディー語の元の歌と同じ位置に同じような単語があるので、もしかしたら替え歌というよりも、ただ翻訳しただけの歌かもしれない。群舞などはほとんどなく、ヒーローとヒロインが2人で踊るだけだ。男優はともかくとして、女優の質も疑問符だらけで、「もっとかわいい女の子がマーレの繁華街を歩いているのに・・・」と首を傾げてしまう。モルディヴ映画を一度見てしまうと、ボリウッド映画がいかに豪華絢爛かつ金と人の力に満ち溢れているか分かるような気がする。また、モルディヴ映画がボリウッド映画の完全なるコピーだと皆に知れ渡っているにも関わらず、それでもパクリだろうが何だろうが自分たちの言語で自分たちの映画を作り続けているモルディヴ映画制作者たちのふてぶてしさとうか、バイタリティーもすごいと思った。
アチちゃんの家でしばらくくつろいだ後、ヴィリギリ島を少し散歩してドーニ乗り場まで戻り、マーレ行きの船に乗った。マーレに着いた後、ニルーちゃんと合流した。ニルーちゃんは、デリーからマーレへ来る間の飛行機や空港の中で出会ったモルディヴ人の1人で、シヤーちゃんと共にデリーへ留学し、同じところで働いている。シヤーちゃん、ニルーちゃんと共に、今度はフルマーレ島へ向かった。

ニルーちゃん
彼女は宗教的理由からスカーフを常に着用していた
去年から着用し始めたらしいが
フルマーレ島は、空港のあるフルレ島の向こう側にある島で、ここもマーレの人口過密を解消するために開発されている新興住宅島である。マーレ北東のドーニ乗り場でドーニに乗った(5ルフィヤー)。マーレからフルマーレ島までは20分くらいかかった。フルマーレ島はつい最近開発が始まった島で、まだほとんど何もない、ただの平地が広がる島だった。大きな団地ができており、既に人が住んでいたが、それ以外の建物はほとんど建設中だった。学校とモスクがあったくらいだ。街路樹なども成長しておらず、日陰がほとんどないので、日中歩くのはかなり大変である。特に見るものもなかったので、すぐにマーレ行きのドーニに乗った。

フルマーレ島の団地
モルディヴに来てから、ほとんどモルディヴ料理を食べていなかったので、「昼食はどこか正統派のモルディヴ料理屋で食べたい」とリクエストしたら、ニルーちゃんがアレンジしてくれた。場所は、チャーンダニー・マグの近くのサルサ・カフェというレストランである。本当はモルディヴ料理は多人数で食べるもので、10人以上いないと作ってもらえないらしいのだが、特別に頼んでくれたおかげで、3人でも出してくれた。ご飯、ローティー、茹でたヤム芋、焼き魚、ココナッツ粉、レモン、生タマネギ、魚の削り粉、魚のタレ、魚のスープなどが大皿に盛られて出てきた。これらをクチャクチャと混ぜて食べるのがモルディヴ料理である。タレはピリッと辛く、カツオの切り身が入ったスープはダシが効いていて味噌汁にミソが入っていないような味だった。これらをご飯の上に適当にかけて混ぜ合わせて食べると、なかなかうまかった。だが、おかしなことに、シヤーちゃんとニルーちゃんは2人ともあまりモルディヴ料理が好きでなく、自宅でもほとんど食べないという。3人で食べて20USドルほどだった。

モルディヴ料理

ガルディアと呼ばれる
カツオの切り身が入ったスープ
昼食後、シヤーちゃんは用事があるというので別れて、ニルーちゃんにチャーンダニー・マグを案内してもらった。いくつかお土産を買おうと思っていたのだ。チャーンダニー・マグにはたくさんの客引きがいて、日本語をしゃべる人も多い。一番端にあったお土産屋から覗いて行ったが、どこも同じようなものを売っている。Tシャツ、ポストカード、ドーニの模型、木彫品、アクセサリー、サメの歯などなど・・・。ところで、チャーンダニー・マグには、マーレに住んで20年以上になる順子さんという日本人が、モルディヴ人の夫と共同経営しているバナナという店がある。ちょうど店にいたので、順子さんと話すことができた。さすがにずっと住んでいるだけあって、もうディヴェヒ語はペラペラだった。ディヴェヒ語を少しずつ習得していたが、ヒンディー語と似ていて割と簡単な言語のように思えたので、「ディヴェヒ語って簡単ですか?」と聞いたら、「それがけっこう難しいのよ」と言っていた。正確な文法がある上に、表情や身振り手振りを使って話さないと、自分の気持ちが正確に相手に伝わらないことがあるという。それが言語学的に何の特徴を表しているかは、それだけでは具体的に分からなかったが、ヒンディー語ととても似た言語なので興味が沸いてきた。バナナでいくつか小さなお土産を購入した。

アイランド・スピリットという店で買った木製のドア止め
今回の買い物の中で一番のお気に入り
一旦ニルーちゃんとは夕食後に再会することを約束して別れ、ホテルに戻った。シヤーちゃんも来る予定だった。夕食をホテルのレストランで食べた後、部屋で休んでいると、ニルーちゃんだけが来た。シヤーちゃんは具合が悪くなったらしい。もしかしてモルディヴ料理が当たったのだろうか?僕は何ともないのだが・・・。仕方がないので、ニルーちゃんに夜のマーレを案内してもらうことにした。
夜のマーレといっても、マーレにはバーやディスコなどはない。人口ビーチの近くにカーニバルという遊園地が新しくできたが、そこも金曜日の夜のみ開いているだけだ。しかし、日中の猛暑の反動か、マーレの人々は夜になると外に出かけ、ブラブラとウィンドウ・ショッピングをしたり、友達と無駄話をしたりして過ごすそうだ。特に週末は夜通し起きていて、友達や家族親類と遊ぶらしい。店も夜遅くまで開いているところが多い。だが、これだけ何もない街に生きていて、退屈過ぎて死なないというのはすごいことだ。
人口ビーチから海岸沿いに反時計回りに歩いて行ったが、別に変わったものはなく、話題になるような出来事もなかった。そのまま島を半周して、島を東西に走るマジーディー・マグからオーキッド・マグに入り、また海岸沿いの道を歩いて人口ビーチまで戻って、そこで飲み物を飲んで夜の散歩は終わった。今夜人々が熱中していたものと言えば、TVで放映されていたサッカーの試合のみだった。大きなTVが設置されたカフェや、TVがディスプレイされた家電屋などに人が集まって、サッカーの試合を見ていた。もう明日は会うことができないので、ニルーちゃんと「またどこかで会おう」と約束して別れた。
今日は午後1時15分発のスリランカ航空、UL502便に乗ってコロンボへ向かい、約3時間空港に滞在して、デリー行きのUL191便に乗る。空港には午前11時頃に着かないといけない。午前中は日記を書いたり、お世話になった人々に電話をかけたりして過ごした。午前10時45分頃ホテルをチェックアウトし、ドーニに乗ってマーレ国際空港へ向かった。
早めにチェックインを済ませ、窓際の席をもらった。上空からマーレの写真を撮影する最後のチャンスである。飛行機が南に向けて離陸することは分かっていたので、進行方向に向かって右側の窓際の席をリクエストした。空港にあるレストランで、余ったルフィヤーを使って軽く食事を取った。
UL502便はほぼ定刻通りに離陸した。僕の座った席からは、狙い通りマーレを一望することができた。しかし、一度飛び立った飛行機は、マーレ島の南側で弧を描いて、北東の方向に進路を向けるため、左側の席からでもマーレを眺めることができたかもしれない。

鮮明ではないが、やっと撮れたマーレの航空写真

こちらはネットで拾ったマーレの写真
こういう角度から写真を撮りたかったのだが・・・
マーレからコロンボまでは1時間15分のフライトである。すぐにコロンボ国際空港に着いてしまった。モルディヴとスリランカの時差は+1時間なので、このときには午後3時半になっていた。今回は出国せずに空港で乗り継ぎ便を待つ。コロンボ空港のレストランで、ちょうどいい場所にコンセントを見つけたので、その席に陣取ってパソコンを広げ、日記を書いて時間を潰した。もちろん、レストランで一応軽食を注文したので、何も言われなかった。
デリー行きのスリランカ航空UL191便は午後7時15分発。6時半頃に出発ゲートへ行ってみたら、たくさんのインド人が座っていた。久し振りにインド人の群れの中に身を置いた・・・。今までモルディヴ人の中にいたときとは明らかに違うプレッシャーをひしひしと感じた。みんな殺気立っているというのか、落ち着かないというのか、ものすごい攻撃的なオーラがインド人から発せられているのに気付いた。みんな我先に飛行機に乗り込もうと必死になっており、なんか黙って座っていたらそのまま存在を無にされてしまいそうだった。席はもう決まっているので、そんなに急いでも何の得もないのだが・・・。いや、荷物の置き場を確保するためなのだろうか?こんな状態なので、僕も我先にと飛行機に乗り込んだ。ちょうど非常口の窓際の席だったため、座席が広くて助かった。
コロンボからデリーまでのフライトは約3時間。スリランカとインドの時差は−30分。インド時間で午後10時10分頃にデリーのインディラー・ガーンディー国際空港に到着した。どこまでも広がる光の絨毯。モルディヴとは全く違う国である。入国手続きを済ませ、税関をほぼフリーパスして、プリペイド・タクシーのカウンターでタクシーを頼んだ。自宅のあるサフダルジャング・エンクレイヴまで550ルピーと言われた。明らかに高い。自宅から空港にメーター付きのタクシーで来たときは約200ルピーだった。最近デリーの空港はきれいに改装されて、外国人旅行者から金を巻き上げるような輩は減ったが、どうもこのプリペイド・タクシーのカウンターは依然として怪しい。しかも空港を出てからタクシーが来るまでだいぶ待たされた。コロンボの空港でインド人の群れに入って以来、精神衛生上よくないことが続き、イライラした。さらに、空港からタクシー乗り場まで案内する人や、運転手がチップを要求してきた。こんなのは一切払わなくていい。プリペイド・タクシーが高額な件については今回は見逃しておいたが、次回までにちょっと探りを入れてみることにする。
インドについて考える際、インドの中からでなく、一度インドの外に出て、別の視点から眺めてみることも重要である。しかしインドからあまりに離れ過ぎると、インドは遠くに霞んで見えなくなってしまう。よって、インドと国境を接している、南アジア諸国からインドを見るというのが、一番効果的なのではないかと思う。よって、僕はインドに住むと同時に、南アジアの国々を順に旅行している。今まで訪れた南アジアの国は、インド、パーキスターン、ブータン、スリランカであり、今回モルディヴを旅行することができた。残ったのはネパールとバングラデシュ。比較的楽に旅行できる国が残ってしまった。特にネパールは、いつか行こうと思いつつも未だに行く機会に恵まれていない。
モルディヴというと、ハネムーンの旅行先として有名な場所だ。世界で最も美しいと言われる海やビーチ、1島1リゾートという贅沢な超高級リゾート、スキューバ・ダイビングやシュノーケリングの楽園・・・などというイメージがあり、南アジアの中でもブータン以上に金のかかる国だと考えていた。確かにモルディヴの物価は南アジアの中ではずば抜けて高い。しかし、調べてみると首都マーレに安いゲストハウスがあったり、格安のリゾートがあったりして、貧乏旅行とはいかないまでも、ある程度予算を抑えた旅行ができそうな雰囲気だった。また、モルディヴの観光ヴィザは空港到着時に発行されるのだが、ホテルの予約があることが条件とのことだった。もしかして高級リゾートの予約をしていないと観光ヴィザを出してもらえないのか、と懸念していたのだが、入国カードに予約あるなしに関わらず適当なホテルの名前を書いておけば全く問題なく観光ヴィザが発行される、との有益な情報も得ることができた。ちょうど5月にインドを旅行しに来た友人に、最新版の「地球の歩き方モルディブ」を買って来てもらったこともあり、準備は万全となった。よって、モルディヴ旅行を決断した。
モルディヴへ出発する1週間前ぐらいから体調を崩していたのだが、モルディヴに着いた途端だいぶ元気になった。旅行中はいつも強靭な体力と気力が沸き起こる。これを僕はトラベル・ハイ状態と呼んでいる。おかげで予定通り旅行をすることができた。ただ、アッドゥ環礁であり得ないほど日焼けしたため、そのせいで旅行の終盤はスローペースになってしまった。マーレを案内してくれたニルーちゃんは、僕の真っ赤に日焼けした顔を見て「まるでチェリーのようだ」と笑っていた。インドへ帰る日に既に皮がむけはじめ、次の日はマイケル・ジャクソンみたいになっていた。
ところで、何の断りもなしに「モルディヴ」という表記を用いてきたが、モルディヴの正式名称はディヴェヒ・ラージェイゲ・ジュムフーリヤー、または単にディヴェヒ・ラージェと言う。ちょうどインドの正式名称が「バーラト」、日本の正式名称が「日本」であるかのようだ。英語名は「Republic of Maldives」または「The Maldives」となっている。日本語のカタカナ表記では、「モルジブ」とか「モルディブ」と表記されることが多いが、僕は「モルディヴ」で統一することにした。
モルディヴでは多くの人々の親切に触れることができ、短かったが充実した旅行になった。今回のモルディヴ旅行の最大の目的は、「現地の人々との交流」というありきたりで幼稚なものであったが、僕の努力ではなく、完全にモルディヴ人の底抜けのホスピタリティーによりそれは実現した。今思えば、僕が会って話をすることができた人々は、偶然が重なって出会うことができた人々ばかりだったが、しかしもし別の日に別の旅程でモルディヴを旅行したとしても、同じような親切に触れることができただろうと思う。それほどモルディヴ人は親切な人ばかりだった。モルディヴのリゾートの中で唯一、地元の村へ自由に行き来することができる、アッドゥー環礁のイクウェイター・ヴィレッジを滞在先に選んだことも大成功だった。
首都マーレとアッドゥー環礁の生活には大きな開きがあった。マーレの生活は非常に忙しく、大して娯楽もないのに活気に満ち溢れているが、アッドゥー環礁の人々は毎日暇そうにのんびりと生活していた。辺境の環礁の島々では金になる産業がない上に、教育施設や病院などが不足しているため、人々は皆こぞってマーレへ移住してしまう。よって、アッドゥ環礁の村々はどこも閑散としていた。首都と辺境環礁の間のこの顕著な格差は重大な問題だ。また、マーレの加速する人口過密も大問題である。マーレは島の隅々まで住宅、オフィス、施設などで埋め尽くされており、どんどん埋め立てて拡張していかない限り、土地が増えることはない。一応ヴィリギリ島やフルマーレ島などの「衛星島」の開発が進んでいるが、果たして成功するであろうか?また、自動車やバイクの数がこれ以上増えることも、狭くて一方通行の道路ばかりのマーレにとって大問題だ。道の真ん中で1台の自動車がしばらく停まっただけで、その後ろには大渋滞ができてしまう。こんな狭い島なのに、スピード狂気味の人が多いのも気になった。僕がマーレを散歩していたときには交通事故などは見かけなかったが、けっこう多いのではないかと感じた。
マーレの街の路地裏はごちゃごちゃしているが、アッドゥ環礁の村はどこも気持ちがいいくらい整然とした町並みであった。大通りは島の端から端まで一直線に村を貫いていることが多く、小さな路地も直線を基調としていた。マーレの旧市街(埋め立てされていないオリジナルな島の部分)や、アッドゥ環礁のヒタドゥ村などは、多少ごちゃごちゃした道になっていたので、これらの都市プランは古いものではないと思われる。また、モルディヴ人の家も非常に清潔であり、どの家にもけっこう高価な電化製品が置かれていたのには驚いた。アッドゥ環礁でお世話になったフェイドゥ村のファシーちゃんの家にはソニー製のTVが2台もあった。だが、ケーブルTVなどはないため、映るのは国営放送のテレヴィジョン・モルディヴ(TVM)のみ。なんだか無駄な買い物のように思えたが・・・。また、モルディヴでは携帯電話が非常に普及しており、ほとんどみんな携帯を持っているかのように見えた。しかもカメラやビデオ付きの高価な携帯電話を持っている人が多い。物価の違いから、インドに比べて高価な携帯電話に手が届きやすいのだろう。
モルディヴの国教はイスラーム教である。パーキスターンの国教もイスラーム教だが、モルディヴはパーキスターンよりも国民にイスラーム教を押し付けており、モルディヴ人は100%ムスリムだと言う。パーキスターンにはわずかながらヒンドゥー教徒やキリスト教徒などもいるが、モルディヴには信教の自由はない。確かにマーレでモスク以外の宗教施設を目にしなかった。モルディヴ人の女性と結婚した外国人の男性は、必ずイスラーム教に改宗しなければならないという法律もあるらしい。また、モルディヴに義務教育はないが、子供たちは必ずイスラーム神学を学ぶようだ。よって、こういう書き方はよくないかもしれないが、イスラーム教を盲信している人が多いように感じた。しかしながら、ブルカーを着用している女性はほとんどおらず、髪の毛をスカーフで覆っている女性も半数ほどであった。ファッションに関してはかなり自由だと感じた。ただ、リゾート以外では酒は一切飲むことができない。海外からの酒の持ち込みも禁止されているため、酒類は空港で預けなければならないことになっている。おそらく豚肉も通常のレストランでは出されないだろう。リゾートでは出されたが。
同じイスラームの国であるパーキスターンと比べて、モルディヴの社会には多くの女性が進出していると感じた。モルディヴの主要産業である漁業は伝統的に男の仕事であるが、空港の職員の半数は女性で占められているように見えたし、自分の店を持っている女性も多そうだった。マーレは女性が夜出歩いてもそれほど危険な街ではないようで、真夜中まで多くの若い女性たちが繁華街をブラついていた。男女の仲がどの程度まで許されるのかについては調査不足だったが、アッドゥ環礁をツーリングしていたとき、ジャングルの中の道を抜けた人里離れた海岸でカップルが何やら愛を語らっていたり、マーレの夜道を若い男女が寄り添って歩いていたりする場面を見たので、インドやパーキスターンほど保守的でもないかもしれない。「地球の歩き方」には、興味深いデータが載っていた。女性の初婚年齢は平均17.5歳、男性は21.3歳。これはインドよりも早いかもしれない。また、女性の平均結婚回数が4回と書かれていたが、これはかなり異常な数値だ。米国人並みの離婚率ではなかろうか?平均的なモルディヴ人女性は一生に4回も結婚するのだろうか?この辺りをもう少し突き詰めてみるべきだったと悔やんでいる。それと、イスラーム法により、男性は4人まで妻を持つことができるが、現在では複数の妻を持つ人は稀らしい。
上記の日記中で、モルディヴの現大統領、マウムーン・アブドゥル・ガユームについての悪い噂を少し書いた。気になったので、その後も引き続き数人のモルディヴ人にガユーム大統領についてどう思うか聞いてみた。彼が独裁的な権力を持っていることは確かかなようだが、しかしモルディヴを観光立国に育て上げたのも彼であり、国民の彼に対する評価は複雑であるように思えた。元々大学教授で国連のモルディヴ大使を務めたガユーム氏は、イブラヒム・ナスィール前大統領が国庫から400万USドルを持ち去ってシンガポールに亡命した後、1978年に大統領に就任した。ガユーム大統領は教育、保健、工業などの発展に努めたが、彼が最も力を入れたのが観光であった。モルディヴに最初のリゾートがオープンしたのは1972年だったが、その経営や税収は順調とは言えなかった。ガユーム大統領は就任直後から「クオリティー・ツーリズム」をスローガンに掲げ、モルディヴの観光業に革命をもたらした。そのスローガンの根幹は、徹底的な規制と規則化であった。リゾートは住民の住まない無人島に建設されなければならないと規定された他、建築物が島の面積の20%を越えてはならない、島の樹木より高い建築物を建設してはならない、などの規制や、島の大きさに基づく部屋数の制限、電力、水道、汚水処理、ゴミ処理などの自給自足の義務化など、多くの規則をリゾートに課した。だが、そのおかげでモルディヴのリゾートと地元民は完全に分離され、モルディヴはゴア、バリ、タイのリゾートで見られるような観光客の無制限の流入によるあらゆる種類の汚染から守られることになり、世界最高水準の「南国の島国リゾート」を実現することができた。1972年にモルディヴを訪れた観光客の数はわずか1097人だったのが、ガユーム大統領就任後、1982年には7万4400人に、1992年には23万5800人に、と順調に増加し、2002年には48万4600人がモルディヴを訪れた。また、ガユーム大統領は観光客1人1泊に付き6USドルの「ベッド税」を課し、それがモルディヴの経済発展に大いに貢献した。現在、観光業による収入は国内総生産(GDP)の32%を占めている。ガユーム大統領就任以来、過去20年間でモルディヴの1人あたりのGDPは300USドルから2800USドルに急増した他、幼児死亡率も12%から1.4%に減少し、平均寿命も42歳から72歳に増え、識字率も99%の高水準に達した。モルディヴの大統領の任期は5年のようだが、ガユーム大統領は現在第6期目である。世界的にもかなりの長期政権だと言えるのではなかろうか。これだけ長い間、政権の座に居座っていれば、独裁的な権力を行使できるようになるのは当然である。一説によるとガユーム大統領の任期中に拷問を受けた人の数は3万8千人以上に及ぶという。モルディヴの人口は約35万人というから、単純計算すると国民の1割以上は大統領により逮捕、投獄、拷問を受けていることになる。サッダーム・フサイン元大統領や金正日総書記もビックリの独裁者だ。しかしながら、上記の記述を見れば分かるように、モルディヴを世界的な観光地に育て上げ、国の経済発展を成し遂げたのは正に彼であり、安易に彼の独裁を責めることはできないだろう。多民族国家が多く、複雑な社会に一様に悩まされている南アジアの国々は、発展の過程においてどうしても独裁者が必要な時期があるように思える。また、一見平和に見えるモルディヴでは、過去に何度もクーデターやクーデター未遂が発生していることも追記しておかなければならない。

マウムーン・アブドゥル・ガユーム大統領
南アジアの国々は、何かしらの形でインドと関係しているし、関係せざるを得ない状況にある。モルディヴもインドと密接な関係を持っている。モルディヴにとってインドは重要な貿易相手であるし、昔からモルディヴはインドの王朝の経済的・軍事的援助を頼りにすることが多かった。1988年にモルディヴで発生したクーデターの際は、ラージーヴ・ガーンディー首相(当時)が軍隊を送って政府を救った。マーレにあるインディラー・ガーンディー記念病院は、名前の通りインドの支援によって建設されたものである。しかしながら、僕がモルディヴを旅行して、目に見える形でまざまざとインドの影響を感じたのは、ボリウッド映画であった。ケーブルTVが入っている家庭のTVには必ずボリウッド映画が映っており、ケーブルTVがない家庭でもレンタルVCDなどでいつでもインド映画を見れる環境にある。マーレの繁華街の街角にはアミターブ・バッチャンの大きな看板があった。世界でも極度にマイナーでマニアックな、モルディヴ映画の世界を少しだけ垣間見ることができたが、それはインド映画の真似というか、真似になってない真似ぐらいのレベルであった。インド映画音楽の替え歌がそのまま使われているのには唖然呆然だった。こんな状況だから、モルディヴの社会におけるインド文化の影響は計り知れない。同時に、ボリウッド映画は決して一般の日本人が考えるようなマニアックな代物ではなく、世界のかなりの国でハリウッド映画に匹敵するほどの影響力を持っている巨大な怪物であるとの認識を強めた。ボリウッド映画はほとんど野放しの垂れ流し状態なので、おそらくデータには表れにくいだろうが、自分の足と目で現地に行って確認すれば、ボリウッド映画の影響力の強さを肌で感じることができるだろう。また、ボリウッド映画の影響で、ヒンディー語を不完全ながらも理解できる人は多かった。多かったというより、ほとんど全てのモルディヴ人がヒンディー語をある程度理解するのではなかろうか。
それでいて、モルディヴ人はインドのことをどこか小馬鹿にしている節がある。インドは全体的にはモルディヴよりも貧しい国であるし、モルディヴ人の衛生観念や倫理観と比べると、インドは汚なくて臭くて滅茶苦茶な国と言わざるをえない。また、モルディヴはイスラームの国であるため、ヒンドゥー至上主義などには反感の眼差しを持っているように見える。デリーに留学していたモルディヴ人の女の子たちに会ったが、彼女たちは一様にインド人の傲慢さ、身勝手さ、マナーの悪さに閉口していた。そういえばスリランカを旅行したときも、スリランカ人はインドに対して「汚なくて貧しい国だ」と偏見を持っていた。モルディヴを1週間だけ旅行した僕ですら、インドに帰ったときにインド人の横柄な態度に一瞬嫌気が差したものだ。インド人は南アジアの国々で相当嫌がられているのだろう。
それほど多くのモルディヴ人に会って話をすることができたわけではないが、どうもモルディヴ人は一様に昔の遺跡に無頓着のように思えた。モルディヴには、探せば数千年前の遺跡から、貴重な仏教・ヒンドゥー教の遺跡まで、いろいろな遺跡がゴロゴロ出てきそうなのに、モルディヴ人は全く関心を払っていない。ムスリムだからイスラーム教以外の偶像崇拝の遺構など関係ない、ということだろうか?スキューバ・ダイビングや豪華リゾートもいいが、遺跡を巡る観光ツアーも十分に観光客を呼び込むネタになりそうなのに、残念なことである。
モルディヴは南アジアの中でもずば抜けて物価が高い国であるため、周辺国家から出稼ぎに来る人も多いようだ。ホテルの従業員や工事の労働者の中には、スリランカ人、バングラデシュ人、インド人(タミル・ナードゥ州やケーララ州の出身が多かった)がいた。もちろん地元のモルディヴ人も働いている。日本人には外見で彼らの国籍を区別することは困難だろう。モルディヴ人だと思って話をしていたら、実はスリランカ人やインド人だった、ということが何度かあった。これはちょっと注意が必要であろう。
今回僕はモルディヴでスキューバ・ダイビングをしなかった。シュノーケリングすらしなかった。「何しにモルディヴへ行ったんだ?」と言われてしまいそうだ。実際、ガン島の土産物屋の店員に、「お前はモルディヴまで来てスキューバ・ダイビングをしないのか?お前は本当のモルディヴを見られないだろう」とまで言われた。「本当の〜」。これはインドでもよく使われるフレーズだ。「君は本当のインドを知らない」「本当のインドはこんなところにはない」など。僕も昔は、「庶民と同じ視線で旅行をし、庶民と同じレベルの生活をしないと、本当のインドは分からない」と思っていた。だが、結局どの視点で見ても、どのレベルの生活をしても、そこから見えるインドはインドそのものであり、「本当のインドではないインド」など存在しない。本当のインドは、その日暮らしの肉体労働者の汗にも映っているし、高級ホテルのレストランで背広を着て食事をしているインド人の金縁眼鏡にも映っている。数週間だけインドを貧乏旅行をした大学生も、インドに関してまともな感想と意見を持って帰ることが多いし、インドに嫌々来て、普通のインド人ができないような生活をしている日本人駐在員も、インドとインド人について日々鋭い観察をしているのを知っている。インドについて語る人々の中で一番厄介なのは、「自分こそ一番インドのことを知っている、自分こそ一番インドのことを愛している、自分こそ本当のインドを見てきた」と思い込んでいる人だ。僕は、インドのことを知れば知るほど分からないことが増えていくのだが、そういう人たちはどうも違うらしい。そういう経験から、「スキューバ・ダイビングをしなければ本当のモルディヴを見たことにならない」との苦言は別に気にしなくていいだろうと思った。僕はその店員に問い返した。「それじゃあ一般のモルディヴ人はスキューバ・ダイビングをしてるのか?」店員は言った。「してるさ、リゾートとかで。」僕はすかさず言い返した。「それは仕事でやってるだけだろう。外国人と同じように、ホビーやレジャーのためにスキューバ・ダイビングをしているモルディヴ人はいるのか?」店員は無言になった。僕は勝利の笑みを浮かべて言った。「地元の人々がやっていないことをやって、本当のモルディヴが分かるというのは疑問だね。」確かにスキューバ・ダイビングをして見ることができる深海の世界もモルディヴの一部だろうが、僕にはそれが、それなしでは「本当のモルディヴ」を見ることが不可能なほど重要な一部には思えなかった。
僕がモルディヴから帰って来た日曜日、デリーの映画館で連続爆弾テロが発生していた。デリーに着いた飛行機の中で、近くの乗客が携帯電話でその話をしていたので、僕はいち早くその情報を得ることができた。爆発が発生したのは、カロール・バーグにあるリバティーと、パテール・ナガルにあるサティヤム・シネプレックスである。家から遠いので頻繁に利用していた映画館ではないが、それでもどちらも数回行ったことがある。これらの映画館は、爆発が起こったとき、サニー・デーオール主演の「Jo
Bole So Nihal」を上映していた。この映画はスィク教徒の団体から上映中止を求められており、パンジャーブ州では既に上映が中止されていた。この爆弾テロを受け、デリーやその近隣の地域の映画館も「Jo
Bole So Nihal」の上映を急遽キャンセルした。デリー中の映画館には警察官が配置され、普段から厳しかった手荷物検査・身体検査も、さらに厳しさを増した。「Jo
Bole So Nihal」は、5月13日(金)の日記でもレビューを書いた通り、あまり面白い映画ではなかったのだが、デリーで連続爆弾テロを引き起こした曰く付きの映画として、インド映画史に永遠に刻まれることになってしまった。おそらくこの映画を映画館で見ることはできないだろうから、早めに見ておいてよかった。
今日はPVRアヌパムで新作ヒンディー語映画「Naina」を見た。いつもより警備は厳重だったが、それを見越して軽装で行ったために特に問題はなかった。監督はシュリーパール・モーラーキヤー(新人)。キャストは、ウルミラー・マートーンドカル、シュエーター・コンヌル、カミーニー・カンナー、アヌージ・ソウニーなど。
| Naina |
 ロンドン在住のインド人、ナイナー(ウルミラー・マートーンドカル)は、幼少の頃の交通事故により全盲になってしまった。その事故で両親も失ったナイナーは、祖母(カミーニー・カンナー)に育てられた。20年後、ナイナーは眼球の移植手術を受け、光を取り戻す。【写真は、ウルミラー・マートーンドカル】 ロンドン在住のインド人、ナイナー(ウルミラー・マートーンドカル)は、幼少の頃の交通事故により全盲になってしまった。その事故で両親も失ったナイナーは、祖母(カミーニー・カンナー)に育てられた。20年後、ナイナーは眼球の移植手術を受け、光を取り戻す。【写真は、ウルミラー・マートーンドカル】
ところが、ナイナーは視力回復後、普通の人には見えないものが見えるようになった。これから死ぬ予定の人と、既に死んだ人を見ることができるのだ。また、鏡には自分以外の別の女性が映っていることも分かった。ナイナーは、精神科医のサミール(アヌージ・ソウニー)に相談するが、彼は彼女の話を信じようとせず、視力回復後によくある幻覚症状だと診断した。ところが、ナイナーは、行方不明になっていた少女が、マンションの屋上の貯水タンクで死んだことを予言し、その通り少女の遺体が見つかる。それを機に、サミールもナイナーの不思議な力を信じるようになる。
サミールはナイナーの眼球の提供者を調べる。提供者は、インドのグジャラート州のカッチ地方、ブジのとある病院で死亡が確認された女性、ケミー(シュエーター・コンヌル)のものであった。鏡に映る女性は、ケミーであった。サミールとナイナーは謎を解明しにインドへ向かう。ナイナーはケミーの魂に導かれるように、スムラーサルという小さな村へ向かう。そこには確かにケミーという女性が住んでいたが、死を予言することができる魔女として村八分に遭い、母親にすら疎まれ、最後には入水自殺をしていたことが分かる。ケミーの母親、ソーマーバーイーは娘の死をきっかけに植物人間同様になっていた。ナイナーはケミーの衣服を身に付け、ソーマーバーイーを外に連れ出して、ケミーの死を再現しようとする。ソーマーバーイーは、湖に身を沈めていくナイナーを見てケミーだと錯覚し、急に動き出して彼女を助ける。母親の娘に対する愛を確認するこの行為により、ケミーは成仏し、ナイナーは二度とケミーの姿を鏡に見ることはなくなった。
ロンドンへ帰って来たナイナーは、地下鉄で大量に人が死ぬ予感を感じる。ナイナーは必死になって人々に呼びかけるが、誰にも取り合ってもらえなかった。結局、地下鉄構内でガソリン漏れによる大爆発が起き、多くの人々が死んでしまう。それと同時に、ナイナーは再び視力を失う。しかし彼女は幸せだった。人の死を予言できる力は、1人の普通の女性には重過ぎる責任であった。そして今や彼女は1人ではなかった。彼女はサミールの愛を得ていたのだった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
4月には「Kaal」というよく出来たホラー映画が公開されたが、それに引き続くようにして、5月にも「Naina」という優良なホラー映画が公開されることになった。ミュージカル・シーンは一切なく、時間も2時間というイレギュラーなインド映画だが、インド・ホラーのひとつの完成形と言える作品であった。
主人公は、幼少の頃に盲目になってしまった若い女性。「Black」も盲目の女性が主人公であった。眼球移植手術をきっかけに主人公のナイナーは、これから死ぬ人と、既に死んだ人を見ることができるようになる。最初はただただ恐怖に怯えるナイナーであったが、やがて自分の使命を自覚し、眼球提供者の住んでいたインドへ行って、ケミーを成仏させる。だが、結局ナイナーもケミーと同様に、自分の持つ超自然的力の責任に耐え切れなかった。ナイナーは地下鉄爆発事故で再び視力を失う。ところが、彼女は幸せだった。映画はナイナーの独白で終わる。「私は再び盲目になったが、私の人生は視力があるとき以上に光に満ち溢れている。」そしてサミールと寄り添って歩き出すのだった。ホラー映画なのに、映画を見終わった後には爽やかなアーナンド(芸術的エクスタシー)を得ることができる、稀な映画であった。「Rakht」(2004年)も、同じくホラー映画なのに後味のよい映画だったことを思い出した。インドのホラー映画が目指すべきひとつの目標は、通常の娯楽映画が持つ「映画館を出るときの爽快感」を、ホラー映画でも観客に与えることだ。そういう意味で、「Naina」は優れたインド製ホラー映画であった。
物語の大半はロンドンを舞台にしているが、出てくる登場人物の多くは不自然なまでにインド人ばかりである。また、急遽ロンドンからグジャラート州のカッチに場面が飛ぶのも、予定調和的ではあった。しかし、カッチの田舎のシーンは、CG依存症に陥っているハリウッド映画にはない「本物」の迫力があり、映画のユニークな見所になっていた。一応、冒頭のシーンで、カッチでケミーが生まれるシーンが伏線として描写されており、カッチに舞台が移ることへの違和感を軽減する努力が払われていた。ところで、僕もカッチを訪れたことがあるし、インドの中でも好きな場所のひとつだから、カッチのシーンが出てきたときは嬉しかった。この映画では、カッチは何やら不気味な場所に描かれていたが、実際のカッチは非常に平和な場所だ。映画中に出てきたスムラーサルという村はどうやら実在するようだ。
主演のウルミラー・マートーンドカルは、「Bhoot」(2003年)以来、ホラー映画に活路を見出したようだ。彼女の昆虫のような目は、恐怖に怯えるシーンで一際輝く。この映画で、ウルミラーはさらに評価を上げたことだろう。だが、この映画の中でウルミラー以外で印象的だったのは、祖母を演じたカミーニー・カンナーぐらいしかおらず、ウルミラーの独断場と言える映画だった。
ホラー・シーンの怖さはなかなかのものであった。特に一番最初にナイナーが死者を見るシーンは、観客にもそれが何が何だか分からず、異様な怖さがあった。その他にも多くの怖いシーンがあった。また、スムラーサル村で発生した爆発事故では、死亡した人々のグロテスクな焼死体が映し出されるので、そういうのが嫌いな人は要注意である。ロンドンの地下鉄の大爆発のシーンは、多少技量不足ではあったが、インド映画にしては頑張った方ではなかろうか。
インドの酷暑期は4月後半から6月前半であり、この時期が最もホラー映画に適した時期となっている。「Naina」は怖いだけでなく、後味のよい映画なので、ホラー映画は絶対に駄目、という人以外にはオススメできる映画だ。
5月22日付けのザ・ヒンドゥー紙に付属している「マガジン」というオマケ紙に、「中産階級は誰か?」と題した、以下のようなコラムが掲載されていた。筆者は、シャシ・タルールという作家である。全文を日本語訳した。
外国人がインド人の「中産階級」について話をするとき、私はいつも、それが何を意味するのか不思議に思う。
経済改革はこの階級を念頭に置いて行われていると言う。だが、それは社会学的かもしれないが、全く論理的ではない。一般常識では、この中産階級は3億人ほどおり、米国全体の市場よりも規模が大きく、上流階級と併せて、米国中産階級が持つ購買力と趣向を兼ね備えているとされている。
今日の経済神話は、このインドの新しい中産階級を、国際的消費財を消費するに値する階層だと見なしている。TV局や雑誌は、大宇のシエロからレイバンのサングラスまで、外国ブランドの製品の広告を垂れ流している。ケロッグはコンフレークと共に大急ぎでインドに駆けつけ、ナイキはインドの元クリケット・キャプテン、ムハンマド・アズハルッディーンを味方に付けて運動靴の宣伝をし、メルセデス・ベンツは自動車生産ラインをインドで稼動させ、ジョニー・ウォーカー・ブラック・ラベルのスコッチは今やインドのブランドになってしまった。かつて、「インドで売られるジョニー・ウォーカー・ブラック・ラベルの数は、スコットランドで蒸留される数よりも多い」というジョークがあったものだが、今ではそのジョークが文字通り本当になってしまった。
しかし、私が聞く限りでは、これらの企業は市場の弱々しい反応に狼狽しているとのことである。なぜなら、インドの中産階級は、誉めそやされているほどのものではないからだ。1986年から1994年の間、ニューデリーにおいて国家応用経済調査評議会(NCAER)が行った調査にて、既にインドの消費者が、3つではなく、5つに分類されることが分かっていた。すなわち、「非常に裕福な階級」は600万人(100万世帯)、「消費階級」は1億5千万人(一般の推定に比して半分)、「発展途上階級」、つまり下位中産階級は2億7500万人、「発展希望階級」、つまり欧米で貧困階級に分類される階層は2億7500万人、そして「貧困階級」は2億1千万人である。当然のことながら、調査が行われてから10年が経過しているので、その数は合計1億人ほど増加しただろうが、5つの階層の相対的なバランスは、全ての階級にそれぞれ進歩があったとしても、劇的には変わらないだろう。
外国の消費財市場調査者にとって最も悪いニュースは、「非常に裕福な階級」に該当する100万世帯のみが、ケロッグ、ナイキ、メルセデス・ベンツ、ジョニー・ウォーカーなどに恒常的な関心を持っているということである。もちろん他の階級も買い物をするが、彼らは多国籍企業の製品よりも、さらにシンプルで安価な消費財を買う傾向にある。もし茶や調理油を売るならば、5つの階層を内包する巨大なインド市場を相手にすることができるだろう。革のサンダルや既製服を売るならば、インドの人口の半分が市場となるだろうし、ゴムひもやプラスチック製のバケツを売るならば、さらに多くの市場人口を獲得できるだろう。しかし、運転手の月給や家賃と同額の運動靴は?最上位の階層以外のことを忘れて商売するしかないだろう。
と言って、インド人の購買力が増えて来なかったわけではない。1980年代以来、紛れもない購買ブームが続いている。タミル・ナードゥ州やケーララ州などの南インドの田舎を旅行したとき、私は村の家々の多くが、藁と泥の掘っ立て小屋ではなく、ちゃんとした建築物であるのを見て驚いた。しかも、家の外にはあらゆる種類の乗り物があった。多くの場合は自転車だが、スクーターやバイク、自動車まであった。驚くべき数のTVアンテナが家の屋根に立っていたし、少数ながらも衛星アンテナを持っている家庭もあった。この経験的な証拠は、NCAERの調査によって裏付けられている。TV所有者の数は増加しつつあり、「貧困階級」以外の階層は腕時計、自転車、携帯ラジオを所有しているとのことである。また、それより数は劣るが、それでも多くの人々が電気製のアイロンと台所用品を買っている。しかし、これらの購買ブームも、キングフィッシャー(インド製ビール)よりもマッカラン(高級ウィスキー)を好むこととは程遠く、ベンツに至っては問題外である。
NCAERは、累積的に、インドの「消費人口」を1億6800万〜5億400万人と結論づけた。しかし、彼らが何を消費し、どれだけ消費をすることができるのかは別問題である。唯一確かに変化しつつあることは、我々の国際的なブランドに対する無関心である。おそらくその無関心は、4千年の歴史のプライドと、50年間の自給自足の保護貿易政策から来たものであるが、徐々にそれは薄れつつある。しかし、その変化のスピードは、国際社会の中では未だに遅いと言わざるをえない。あらゆる場面において、インド人が好んで買うものは、家事用の洗剤から頭髪用オイルまで、タバコからスナックまで、親近感と価格の面で有利なインドのブランドである。
結局、インドに中産階級は存在するものの、彼らが消費する「消費財」は、西洋の労働者階級よりも少ない。経済自由化以降のインドの経済改革は真実であるが、平均的な中産階級のインド人が、ラクメ(インドの化粧品ブランド)をやめてランコムを買い、手製のサルワール・カミーズ(俗に言うパンジャービー・ドレス)を脱いで、ラルフ・ローレンの洋服を着るようになるには、まだまだ時間がかかるだろう。インドで起こっていることは、インド・アクセントのグローバリゼーションだと言える。
このコラムで問題となっているのは、「インドの中産階級というのは、どこからどこまでの人を指して、何人くらいいるのか」ということと、「インド人消費階級の実際の消費傾向はどうなのか」という2点だ。
昨今、インドは世界から熱い注目を集めており、インドに進出する、または進出しようとする外国企業の数も急増してきた。世界の注目の的になっているのは、経済自由化以降、急速に成長してきたインド人中産階級である。人材という観点からも、市場という観点からも、中産階級が現在のインド経済の主役となっていると言っていいだろう。だが、その実態には大きな疑問がある。
昔は、例えばスクーターが中産階級の象徴とされていたように記憶している。1台のスクーターをお父さんが運転し、その後ろにお母さんが座り、お父さんとお母さんの間に1人子供が座り、お父さんの前にも1人子供が立っている、という構図が、インド人の中産階級の典型的なお出かけ風景とされていたような気がする。しかし、今ではスクーターを持っているだけでは中産階級とは言えない。僕なりの理解では、インド人中産階級は、週末にグルガーオンのモールなんかで買い物をしたり、1人150ルピーの入場料を払って高級シネマコンプックスで映画を見たり、「私、ヒンディー語よりも英語の方が得意なの」とうそぶいてみたり、毎年酷暑期にはシムラーやシュリーナガルへ行って避暑をしたり、海外旅行の経験があったり、米国などに留学してそのまま帰って来なかったり、そんな感じのイメージがある。自動車を所有していることは最低条件であろう。日本では「三種の神器」などと言って、持ち物で中産階級を測っていた時代があり、インドでもそれはある程度通用するが、デリーのような大都会では、ライフスタイルが中産階級のシンボルになっていると感じる。だが、誰が中産階級で誰が中産階級でないかと決める決定的な基準は設けにくいだろう。・・・大体マナーが悪いインド人というのも、この中産階級出身というイメージが強いが、これは偏見であろうか。
週末、グルガーオンのモール・ロードへ行くと、本当に混んでいる。そしてインド人の購買力のすごさを思い知らされる。駐車場には車が溢れ、映画館は満員状態、そしてたくさんの買い物袋を提げた家族連れが、さらなる買い物をすべく隣のモールへ向かっていたりする。確かに中産階級が増加し、力を付けたな、と実感させられる。インド全体でどれだけの中産階級がいるのかは分からないが、無視できない数であることは確かだ。そして、優秀な人材の多くが、中産階級の中から生まれていることも容易に推測できる。
しかし、インドの中産階級が、外国企業が期待するような消費層かというと、コラムに書かれている通り、疑問である。インド人は概して必要以上にケチだ。徹底的に節約をする。徹底的に値切る。「定価販売」と書かれていても、とりあえず値切る。安ければ安いほどいい、あわよくば他人から借りればいい、と考えている。しかも、その代わり一度金を払ったら、その金額と同等かそれ以上の見返りは当然だ、と考えている。下層階級は当然だが、中産階級に分類される人でも、この性向に大した変化はない。外国企業は、商品の品質と、多くの国で信頼を得ているブランドの力を盾にインド市場に殴りこんで来るのだが、インド人が最初に見るのは価格である。その次にランニングコスト、そして最後に品質を見る。本物と偽物が玉石混交となっているバーザールで培った鑑識眼は伊達ではない。価格と品質を天秤にかける。「品質に見合った価格」とは、インド人にとっては「安くていいもの」という意味だ。「値段は高いがいい味です」ではない。ブランドなんて関係ない。ジョニー・ウォーカー・ブラック・レベルの瓶には水だって入れることができる。インド人は、このように厳しい消費者なので、インドは外国企業が容易に商売できるような国ではないだろう。インドで韓国企業が成功しているのも、安価な価格設定と徹底的な広告作戦に拠るところが大きいと思われる。やはり三星(サムスン)やLGの製品は安いし、韓国企業は広告の中で、韓国っぽいカラーを極力減らし、まるでインド企業であるかのような巧妙な宣伝の仕方をしている。それらの企業が韓国企業であると知っているインド人は実は多くないかもしれない。品質と「メイド・イン・ジャパン」を売りにしたい日本企業には、もどかしい市場だ。
しかし、一度インド人の信頼を勝ち得ることができるならば、インド人は末永くその商品とブランドを愛用してくれる予感もある。インドの自動車市場にいち早く進出したマールティ・スズキは、自動車企業の戦国時代と化した今でもインド人の根強い支持を受けている。世界一の携帯電話会社であるノキアの携帯は、やはりインドでも最も人気がある。その秘密はどうも、「みんな持っているから」というのが大きいように思える。みんなが持っていることにより、修理やパーツなどにかかる費用が減り、インド人的に一番お買い得の携帯電話になっていると分析している。1996年にインドに進出したマクドナルドは、それより以前に進出して失敗したKFCの教訓から、インドの文化を尊重したオリジナル・メニューを慎重に考案し、インド人から受け容れられた。KFCの店舗が現在バンガロールにしかないのに比べ、マクドナルドの店舗はインド全国に広がっている。
これは私見だが、日本の靴メーカーがインドに進出すると、無条件で人気を博すのではないかと思う。なぜなら、インドには日本の靴に関する有名な歌があるからだ。ラージ・カプール監督主演の「Shree
420」(1955年)に、「Mera Juta Hai Japani(オイラの靴は日本製)」という題名の歌があり、「オイラの靴は日本製/このパンタロンは英国製/頭の上の赤い帽子はロシア製/でも心はインド製」と歌われている。果たして終戦直後の1950年代の日本の靴が、インド映画音楽の歌詞になるほど高品質だったのかは知らないが、少なくともこの歌のおかげで、インド人は日本製の靴に異常な親しみを持っている。伝統的に裸足で生活してきたインド人にとっても、靴は生活に密接した消費財であるし、この歌を知らないインド人はいないと言っていいから、日本の靴メーカーがもしインドで、安くて丈夫な靴を発売すれば、インドで10億人市場を獲得できる可能性がある。
インドの人口は10億人を越えたが、それがそのまま10億人市場には結びつかない。売る物によって、その市場は600万人市場になったり、5億人市場になったりする。特に中産階級と言われる人々がどういう思考で消費活動を行うのか、インドで商売をしようとする企業は研究する必要があるだろう。
| ◆ |
5月27日(金) Bunty Aur Bubli |
◆ |
今日は待望の新作ヒンディー語「Bunty Aur Bubli」をPVRプリヤーで見た。1週間前にデリーで発生した映画館連続爆破テロの影響で、PVRプリヤーは厳戒態勢であり、一切の手荷物を認めないばかりか、ひとつひとつ携帯電話をオフ→オンにさせて、本物の携帯電話か確かめていた。しばらくはこの神経質な状態が続きそうだ。
「Bunty Aur Bubli」とは、「バンティーとバブリー」という意味である。バンティー、バブリー共に主人公の名前だ。プロデューサーはアディティヤ・チョープラー、監督はシャード・アリー・セヘガル、音楽はシャンカル・エヘサーン・ロイ。キャストは、アミターブ・バッチャン、アビシェーク・バッチャン、ラーニー・ムカルジー、そしてサプライズとしてアイシュワリヤー・ラーイが「アイテム・ガール」として一曲だけ登場し踊る。
| Bunty Aur Bubli |
 ウッタル・プラデーシュ州の退屈な小都市、フルサトガンジで生まれ育ったラーケーシュ(アビシェーク・バッチャン)は、都会へ出て一獲千金し、大金持ちの仲間入りを夢見ていた。鉄道に務める父親はラーケーシュを同じく鉄道に就職させようとしていたが、ある日ラーケーシュは家を抜け出し、ラクナウーへ向かう。【写真は、アビシェーク・バッチャン(左)とラーニー・ムカルジー(右)】 ウッタル・プラデーシュ州の退屈な小都市、フルサトガンジで生まれ育ったラーケーシュ(アビシェーク・バッチャン)は、都会へ出て一獲千金し、大金持ちの仲間入りを夢見ていた。鉄道に務める父親はラーケーシュを同じく鉄道に就職させようとしていたが、ある日ラーケーシュは家を抜け出し、ラクナウーへ向かう。【写真は、アビシェーク・バッチャン(左)とラーニー・ムカルジー(右)】
一方、同じくウッタル・プラデーシュ州の小都市、パンキーナガルで生まれ育ったヴィンミー(ラーニー・ムカルジー)は、ミス・インディアになってトップ・モデルになることを夢見ていた。しかし両親はヴィンミーの結婚の話を勝手に進めていた。ヴィンミーは花婿が見合いに来る日の前に家を抜け出し、ラクナウーへ向かう。
ラーケーシュはラクナウーで保険会社にアイデアを売ろうとするが、受け容れられなかった。また、ヴィンミーもミス・インディアの会場で相手にされなかった。ラクナウー駅でうなだれていた2人は、自然と出会い、そして共にカーンプルへ向かう。だが、カーンプルでも、2人は世間の厳しさを知るばかりだった。
そこで、2人はムンバイーへ行くことに決める。しかしそんなお金はどこに?2人は、ラーケーシュを騙した男を協力して騙し、大金をせしめる。この詐欺に味をしめた2人は、バンティーとバブリーを名乗るようになり、行く先々で人々を騙して金を巻き上げ始める。バンティーとバブリーの名前は瞬く間に世間に広がり、ちょっとした英雄になる。
ムンバイーに着いたラーケーシュとヴィンミー。しかしラーケーシュは突然家に帰ると言い出す。ラーケーシュは詐欺師に自分の才能を見出し、1人でこれからバンティーを続けていくことを決めたのだった。ヴィンミーにはミス・インディアになってもらいたかった。しかし、ヴィンミーはラーケーシュに言う。「バブリーがいないバンティーに何ができるの?私がいなくてあなたはやっていけるの?」ラーケーシュは答える。「いや、君がいないとオレは生きていけない」いつの間にか2人はお互いに恋していたのだった。2人はアーグラーまで戻り、タージ・マハルの前で結婚式を挙げる。
結婚したバンティーとバブリーは、ますます詐欺の才能に磨きをかける。ちょうどアーグラーを訪れていた世界有数の大金持ちの白人に、タージ・マハルを売却するという詐欺を行い、大金をせしめる。だが、バンティーとバブリーは、敏腕刑事ダシュラト・スィン(アミターブ・バッチャン)に追跡され始めていた。デリーのレストランでバンティーとダシュラト・スィンは偶然顔を合わせて一緒に酒を飲み、意気投合するということもあった。
だが、バブリーの心に次第に変化が訪れていた。彼女は妊娠しており、子供の将来を心配するようになっていた。バンティーとバブリーはデリーの空港から、空輸中の金を奪い逃走するが、その途中にバブリーは産気づき、市内の病院で出産する。その病院にはダシュラト・スィンが駆けつけるが、ギリギリのタイミングで2人は逃げ出していた。デリーを脱出したバンティーとバブリーであったが、バブリーはもう2度と悪いことはしないし、バンティーにさせないと主張する。バンティーもしぶしぶそれを受け容れる。ところが、そのときちょうどダシュラト・スィンが現れ、捕まってしまう。
長年追い続けていた2人を捕えたダシュラト・スィンだったが、2人が既に改心していること、そして生まれたばかりの子供がいることを見て同情し、2人を逃がす。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
ハリウッド映画「オレたちに明日はない」(1967年)を彷彿とさせる、カップル犯罪者を主人公にした映画だが、僕はどちらかというと日本の人気アニメ「ルパン3世」を思い出した。映画は全体に渡ってカラフルでゴージャスでファッショナブル。詐欺や泥棒に対する罪悪感などはラストを除きほとんどなく、とにかく娯楽のために犯罪を繰り返す能天気なカップルがスクリーンで大暴れする。現実感はほとんどなく、対象年齢はかなり低い。子供たちが喜びそうな映画である。その他、インド各地の観光地がギネスブック級に登場したのが特筆すべきである。
主人公のラーケーシュ、ヴィンミー、共にウッタル・プラデーシュ州の退屈な小都市で生まれ育った。ラーケーシュの故郷はフルサトガンジ。日本語に意訳すると「退屈市場」みたいな意味である。一方、ヴィンミーの故郷はパンキーナガル。これも意訳すると「ダサダサの町」みたいな意味になると思う。これらの町の名前は、大金持ちを目指すラーケーシュと、モデルを目指すヴィンミーの置かれた環境をよく表している。同時に、この時点でこの映画は、子供向けのお伽話みたいなものだと理解しなければならない。細かいことに文句を言うことはできるが、それは野暮というものである。
ラクナウー駅で偶然出会ったラーケーシュとヴィンミーは、「バンティーとバブリー」を名乗って詐欺や泥棒を繰り返すようになる。「バンティー」とは、ラーケーシュが子供の頃、何か悪いことをして叱られたときに、「僕がやったんじゃないよ、バンティーがやったんだよ」と言い訳をしていたことに起因する。その相棒の名前が「バブリー」だった。最初、勝手に「バブリー」と名付けられたヴィンミーは「あなたは正にバンティーって顔してるけど、どうして私がバブリーなのよ?」と怒るが、しばらくして「バンティーとバブリー・・・なかなかいいわね」と微笑む。名前を変えたことに刺激を受け、2人は隠れた才能を発揮するようになる。
バンティーとバブリーの詐欺と泥棒の手口は例えばこんな感じだ。ある高級ホテルに派手な服を着て入る。レセプションは、「スイートルームにお泊りですか?」と聞くが、バンティーは「いや、部屋は必要ないんだよ、このホテルが必要なんだよ、全部」などとはったりをかます。それを聞いたオーナーはすぐにバンティーとバブリーを貴賓扱いし、2人をただで1週間宿泊させる。・・・だが、オーナーが気付いたときには、2人は家具と共に逃げ出した後だった。別の場所では、バブリーがまた大金持ちっぽいゴージャスな服を着てショッピング・モールを訪れる。バブリーは家電製品の店で、洗濯機を全て買い占め、夜中それらを運び出させる。ところが、あらかじめモールに忍び込んでいたバンティーが、洗濯機の中にモール中の高価な商品を詰め込んでいた。バンティーとバブリーは別の町へ行って、それらの商品を格安で売り払って大儲けする。
一方、バンティーとバブリーは、ダシュラト・スィン警視副総監に追われることになる。ダシュラト・スィンは、バンティーとバブリーの行動パターンを研究する内に、彼らが楽しんで犯罪をしていることに気付き、自分も彼らと同じ思考をするように務める。すると、次第にダシュラト・スィンの予想が的中するようになる。だが、最後にはバンティーとバブリーの方が一枚上手で、逃げられてしまうのだった。まるで「ルパン3世」の銭型刑事のようだった。映画のラストで彼はバンティーとバブリーを捕まえるのだが、2人に同情して逃がしてしまう。
これで映画が終われば最高だったのだが、ラストのラストで蛇足なシーンがある。3年後、フルサトガンジで幸せに過ごすラーケーシュとヴィンミーのもとをダシュラト・スィンが訪れる。そして2人と、彼らのかつての仲間を特別捜査官みたいな役職に就けるのだ。訳が分からなかった。
バンティーとバブリーが改心するきっかけとなったのは、2人に子供が生まれたことだが、これもありきたりであったように思う。しかし、「インド映画の良心」という観点では、これは避けて通れないプロットであっただろう。みんなと同じ普通の人生を送るのが嫌で田舎の町を飛び出してきた2人は、自分の子供に、みんなと同じ普通の人生を送らせたいと考えるのであった。一見矛盾しているが、この矛盾こそが人間の成長の証であろう。
アビシェーク・バッチャンがデビューしたときは、演技も踊りもできない、どうしようもない男優だったが、マニ・ラトナム監督の「Yuva」(2004年)で開花してからは、本当にいい男優になった。この映画ではコミカルな演技に挑戦し、表情豊かに演じきっていた。しかも、ミュージカル「Nach
Baliye」では、かなり激しいダンスをいい感じで踊っていた。しかも今回は実の父親、アミターブ・バッチャンとの初共演である。映画中、こんなセリフがあった。ヴィンミーが、酒を飲んで意気投合したラーケーシュとダシュラト・スィンを見て、「あんたたち本当にそっくりね。親戚か何かなんじゃない?」
「Black」(2005年)で重厚な演技を見せたラーニー・ムカルジーは、この映画でポップな役を全身で演じ、演技の幅の広さを見せつけた。特に今回は目と口の使い方が非常にうまかった。ミュージカル「Nach
Baliye」では、ラーニー・ムカルジーにしては思い切った服装で踊りを踊っていた。だが、最近のボリウッドはモデル体型の女優が増えてきて、比較的小柄でぽっちゃりしているラーニーの身体は見劣りがしてしまう。しかし、楽しそうに踊っていたのでよしとしよう。今年2月に発表されたフィルム・フェア賞で主演女優賞と助演女優賞をWゲットしたラーニー・ムカルジーは、シャールク・カーンと共演の「Paheli」の公開も6月に控えている。2003年はプリーティ・ズィンターの大ブレイク年となったが、2005年はラーニー・ムカルジーのためにあるようなものだ。現在、ボリウッドのメインストリーム女優界は、アイシュワリヤー・ラーイを頂点とし、その下にラーニー・ムカルジーとプリーティ・ズィンターの2人が控えるという、ヒエラルキーが完成していると思う。さらに下には、アミーシャー・パテール、カリーナー・カプール、ビパーシャー・バス、プリヤンカー・チョープラーあたりの比較的若手の女優がひしめいている。
アイシュワリヤー・ラーイ
ラーニー・ムカルジー プリーティ・ズィンター
アミーシャー カリーナー ビパーシャー プリヤンカーなど
それにしても突然アイシュワリヤー・ラーイが登場したときには驚いた。彼女が踊るのは、「Kajra Re」という曲のダンスシーン。ラーケーシュとダシュラト・スィン、つまりアビシェーク・バッチャンとアミターブ・バッチャンの親子がレストランで酒を飲んで踊るときに、アイシュワリヤーも登場して踊り出す。化粧が悪かったせいか、ちょっと老けた印象があったが、8分間に及ぶ映画中最長のこのダンスシーンは、インド人が大好きなタイプのダンス(結婚式ダンス、とでも表現しようか)なので盛り上がっていた。音楽監督のシャンカル・エヘサーン・ローイの音楽はどれも素晴らしく、特に冒頭の「Dhadak
Dhadak」や、テーマソングの「Bunty Aur Bubli」などが耳に残る。
ウッタル・プラデーシュ州政府や、インド考古調査局などの全面的協力を得たようで、この映画にはインド各地の街や遺跡が随所に出てくる。まずは街の名前から挙げていくと、アーグラー、ヴァーラーナスィー、ラクナウー、カーンプル、ムンバイー、ムスーリー、リシケーシュ、ハリドワール、デリーなどが出てきた。遺跡や観光地で出てきたものを全て特定するのは、インドをけっこう隈なく旅行している僕でも難しかったが、アーグラーのタージ・マハル、ヴァーラーナスィーのガート、ラクナウーのルーミー・ダルワーザー、ムンバイーのチャトラパティ・シヴァージー駅、ラダックのラマユル・ゴンパ(?)、リシケーシュのシヴァーナンド・ジューラー(?)などが出てきたように記憶している。
ムンバイーのシーンでは、ラーケーシュとヴィンミーの後ろを国際クリシュナ意識協会(ISKCON:俗に言うハレー・クリシュナ教団)に入信した白人たちが通るのが面白かった。
「Bunty Aur Bubli」は典型的な娯楽インド映画だ。若い年代を中心にヒットをすると思われる。大人数で見に行ったり、盛り上がりのいい映画館で見たりするといいだろう。
今日は先週公開されたヒンディー語映画「Nazar」をグルガーオンのPVRメトロポリタンで見た。やはりデリー映画館連続爆破テロの影響で警備が超厳重となっており、手荷物は一切持ち込めない状態となっていた。しかも、以前まではクロークがあったのだが、それすらも閉鎖されていた。客は手荷物を自動車に置いて来るよう指示されていたが、自動車以外の交通機関で来た人はどうすればいいのか?館員は「すみません、自己責任で管理して下さい」と繰り返すばかりで、具体的な代替策は用意していなかった。インドは時々極端から極端へ急転するのでどうしようもない。
「Nazar」とは「目」、「視線」という意味。この映画プロデューサーはマヘーシュ・バット、監督はソーニー・ラーズダーン、音楽はアヌ・マリク。キャストは、アシュミト・パテール、ミーラー、コーヤル・プリー、アリー・カーンなど。
| Nazar |
 ムンバイーに住む人気シンガーのディヴィヤー(ミーラー)は、ある夜、血まみれになって道路に倒れていた女性を見てから、他人には見えないものが見えるようになった。誰かが殺されるシーンが目に浮かんで来るのだ。ディヴィヤーは知り合いの医者タルン(アリー・カーン)に相談するが、「疲れとストレスだろう」と真剣に取り合ってもらえなかった。【写真は、ミーラー(左)とアシュミト・パテール(右)】 ムンバイーに住む人気シンガーのディヴィヤー(ミーラー)は、ある夜、血まみれになって道路に倒れていた女性を見てから、他人には見えないものが見えるようになった。誰かが殺されるシーンが目に浮かんで来るのだ。ディヴィヤーは知り合いの医者タルン(アリー・カーン)に相談するが、「疲れとストレスだろう」と真剣に取り合ってもらえなかった。【写真は、ミーラー(左)とアシュミト・パテール(右)】
そのとき、ムンバイーではバーダンサーを標的とした連続殺人事件が発生していた。捜査を担当することになった女性刑事スジャーター(コーヤル・プリー)は、かつて同様の事件を担当した経験を持つローハン(アシュミト・パテール)をチームに加える。ローハンは連続殺人犯に愛妻チェートナーを殺されたという過去を持ち、すさんだ毎日を送っていた。その連続殺人犯が2ヶ月前に脱獄したこと、そして今回の連続殺人犯の手口が非常に似ていることから、ローハンは捜査への協力を承諾する。
しかし、警察をあざ笑うかのように連続殺人は続いて行った。ちょうどディヴィヤーが入院していた病院でも、バーダンサーが殺害された。そのシーンを神通力で見たディヴィヤーは、スジャーターにそのことを伝えるが無視される。だが、ローハンはディヴィヤーの話に興味を持つ。ディヴィヤーの不思議な力により、捜査が進展したことで、ローハンはますますディヴィヤーを信じるようになる。それと同時に、密かにローハンを愛していたスジャーターは嫉妬を募らせる。また、やはりディヴィヤーを密かに愛していたタルンもローハンに疑いの目を向けるようになる。
ディヴィヤーは、呪術師に相談することによって自身の力を悟ると同時に、「お前の死が迫っているが、その死に直面せよ」との助言を得る。また、ディヴィヤーは、血まみれになって道路に倒れていた女性と会ってから変なことが起こるようなったことに気付く。その女性のことを調べてみると、やはりそのサークシーと呼ばれていた女性も同じような神通力を持っていたことが分かる。ディヴィヤーは、サークシーが自分を殺した人間に復讐するためにこの力を彼女に与えたのだと悟る。
そのとき再び連続殺人事件が起こるが、犯人が逮捕される。それはディヴィヤーの叔父だった。だが、ローハンもディヴィヤーも彼が真犯人だとは思えなかった。自宅に戻ったディヴィヤーは、遂に自身の死のシーンを神通力で見る。異変を感じたローハンは、ディヴィヤーの家に駆けつける。まずディヴィヤーの家を訪れたのはタルンだった。タルンはディヴィヤーに襲い掛かるが、間一髪のところでタルンは射殺される。銃を撃ったのはスジャーターだった。スジャーターはディヴィヤーをマンションの屋上へ連れて行く。だが、ディヴィヤーが見た映像はこうではなかった。・・・と思っていたら、スジャーターがディヴィヤーに襲い掛かる。実はスジャーターが連続殺人事件の犯人だったのだ。スジャーターは、亡き夫の放蕩生活のせいでエイズに感染していた。そこで彼女は、夫にエイズを感染させたバーダンサーの女たちを殺害して復讐していたのだった。だが、ディヴィヤーは駆けつけたローハンにより助けられ、スジャーターはマンションの屋上から落下して死亡する。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
この映画は、5月24日の日記で紹介した「Naina」と同じ日に公開された。だが、奇しくも「Nazar」と「Naina」のプロットは非常によく似ていた。両方とも香港・タイ合作の「見鬼(Jain
Gui/The Eye)」(2001年)という映画を基に作られたらしい。だが、この2作を比べると、圧倒的に「Naina」の方がよく出来た映画である。それを知っていながら「Nazar」をわざわざ見たのは、この映画はいろいろと曰く付きだったからだ。
実は「Nazar」で主演を務めたミーラーは、パーキスターン映画界の人気女優である。よって、「Nazar」は、「初の印パ合作映画」として売り出されている。ただ、印パ独立後、過去にもインド映画にパーキスターン人の俳優が出演したことはあったようだ(どこかでそういう映画のリストを見たのだが、なくしてしまった)。また、2003年ロカルノ国際映画祭で金豹賞を受賞したパーキスターン映画「Khamosh
Pani」に、キラン・ケールなどのインド人俳優が出演していたことも記憶に新しい。マヘーシュ・バット制作の「Paap」(2003年)や「Murder」(2004年)では、パーキスターンの人気ロックバンド、ジュヌーンや歌手アミール・ジャマールが音楽に参加している。インドとパーキスターンの映画界は、親密とは言えないけれども、時に協力し合って映画を制作して来た。
だが、この映画が一躍有名になったのは、「ミーラーがインド映画でインド人男優とキスシーンを演じた」という噂がパーキスターンで広まったからだ。この話は、2月24日の日記で少し触れた。確かにこの映画では、際どい肌の露出シーンや、唇が触れるか触れないかの寸止めキスシーンはあったものの、いわゆる本物のキスシーンはなかった。キスシーンが物議を醸したからカットされたのか、それとも最初からそんなものはなかったのに噂だけが先行してしまったのか、よく分からない。だが、「Nazar」を巡る事件は、「誰も中身を見ていないのに批判だけが存在する」という日本の歴史教科書問題と同じ臭いがする。
ラス理論で「Naina」と「Nazar」を比較すると、前者は「恐怖+勇猛+恋愛」のラスで構成されていた一方、後者は「驚嘆+恐怖+恋愛」のラスで構成されていたと思う。「Naina」は基本はホラー映画で、1人の女性が自身に与えられた使命を勇気を以って克服し、そして愛を手に入れるという筋だった。「Nazar」は、前半はホラー映画的なのだが、全体的にはサスペンス映画で、それに恋愛の絡み合いがあった。
「Nazar」のストーリーには一応ひねりがあったと思う。バーダンサー連続殺人事件の犯人は、当初は過去に連続殺人事件を起こした凶悪犯だと考えられる(後に彼は獄中で死んでいたことが明らかになる)。しかし同時に真犯人はディヴィヤーの叔父のように描写されるが、次第にタルンが怪しいのではないか、という展開になって来る。案の定タルンがディヴィヤーの自宅に押しかけるのだが、実は真犯人は、女性刑事のスジャーターだった、というどんでん返しである。しかし、スジャーターが連続殺人を行う動機があまりにしょぼかった。バーガールを買春していた亡夫にエイズを感染されたから、バーガールに復讐する、というのだ。また、ディヴィヤーを殺そうとする動機は、密かに恋していたローハンを取られたからという、これまた幼稚なもの。この点はもう少しひねってもらいたかった。
ミーラーはパーキスターンで10年間のキャリアがあるだけあり、ちゃんとした演技力を持っていた。その顔立ちはかなり立体的で、全体的に「かわいい系」に徐々に徐々に移行しつつあるボリウッド界の女優陣と比べると、「典型的美人」と言った感じだ。ラヴィーナー・タンダン型の顔か。言い換えれば、パーキスターンでは女優の顔の流行がインドよりも少し遅れているように思えた。唇のそばにホクロがあるのも、何となくマリリン・モンローのような古風な美的感覚を想起させる。

ミーラー
助演女優の扱いになるコーヤル・プリーは、ヒステリックな役を演じさせたら右に出る者はいない女優だ。「White Noise」(2005年)での彼女の演技はなかなかのものだった。あまり美人ではないし、黒板を爪で引っ掻いたようなハスキーな声なのだが、ヒステリックにわめき散らす彼女の演技を見ていると、「素でこんな感じなんだろうな・・・」と心配してしまうほどだ。
女優陣の好演に比べると、男優陣は情けなかった。アミーシャー・パテールの兄、アシュミト・パテールは、ジョン・アブラハムみたいな髪型をしてどういうつもりか知らないが、表情とセリフに力がなかった。アリー・カーンは・・・もっとマシな顔の男優はいなかったのかと苦情を言いたくなった。
この映画を機に、印パ映画界の交流が活発化していくかもしれない。だが、残念ながらそれは、ボリウッドがロリウッド(パーキスターン映画界)を呑み込む形になってしまわざるを得ないだろう。ボリウッドの力はそれほど圧倒的だ。何の規制もなしに両国の映画人が行き来したら、まるでメジャーリーグに有能な選手を次々に奪われる日本の野球界のように、結果的にはロリウッドが枯渇して行ってしまうだろう。ロリウッド映画界がそれを自覚していないとは思えない。だから、印パ映画界の交流はこれからも非常に慎重に行われることになると予想している。「Nazar」でのキスシーンを巡る騒動も、その慎重な姿勢の表れだと言っていいだろう。
| ◆ |
5月29日(日) アーユルヴェーダは安全なのか |
◆ |
インドが誇る伝統医学アーユルヴェーダ。世界的な健康ブームにより、アーユルヴェーダに対する注目が高まっている。とにかく「アーユルヴェーダ」を冠する商品は売れるようだ。僕の手元にも、バンガロールを拠点とするアーユルヴェーダ薬品会社、ヒマーラヤ製薬の商品がいくつかあるし、アーユルヴェーダ化粧品で有名なシャーナーズ・フサインを愛用している人を何人か知っている。インドには5000社以上のアーユルヴェーダ製薬会社があり、アーユルヴェーダ製薬業界市場は230億ルピー規模で、毎年15%成長していると言う。また、世界的には、アーユルヴェーダ薬品の市場規模は142億USドルだと言う。
ところが、5月29日付けのサンデー・エクスプレス紙の折込版サンデー・ストーリーに、気になる記事が掲載されていた。
その記事はまず、最近デリーの病院に入院した中年女性患者のことが載っていた。女性は肝不全で入院したのだが、血液検査により血中のヒ素、鉛、水銀が異常な濃度を示していることが発見された。女性は、便秘を解消するために過去5年間アーユルヴェーダの薬品を服用し続けていたことが分かった。
このようなケースは世界中で報告されていると言う。米国ボストンのとある病院で検査を受けた患者の血液の鉛濃度が、89ポイントの高数値を示していることが発見された。通常の濃度は2ポイント以下である。その患者はインド出身の中年の男性で、やはり関節炎の解消のためにアーユルヴェーダの薬品を6年間服用し続けていた。その薬品からは高レベルの金属が検出された。
ハーバード大学医学部によって行われた、アーユルヴェーダ薬品と、ヒ素、鉛、水銀などの金属中毒の関係に関する調査によると、5分の1のアーユルヴェーダ薬品から、異常な数値の重金属が検出された。短絡的な結論は危険であるが、金属中毒とアーユルヴェーダ薬品の長期服用が関連していることを示すデータは、インドでも海外でも報告されているようだ。
金属中毒は、消化器官、肝臓、神経に悪影響を及ぼす。ヒ素と水銀が肝臓の疾患を引き起こす一方で、鉛は神経、脳、腸を損傷させる。金属は体外に排出されず、体内に蓄積するため、たとえ少量の摂取であっても、継続的な摂取によりその量は莫大なものとなってしまう。
アーユルヴェーダ薬品を巡る問題は、法整備の問題と密接に関係している。1996年、インドの最高裁判所は、現代医学を修めていない医者によるアーユルヴェーダ薬品の処方を禁じる命令を出した。しかし、アーユルヴェーダ薬品は処方箋なしで自由に手に入ってしまうのが現状である。そのため、人々は適切な服用量の知識なしにアーユルヴェーダ薬品を長期に渡って服用してしまう。
アーユルヴェーダ薬品には、その効果についての科学的な実証がないし、それがほとんど要求されないという問題もある。一般的な薬品は、実験によって効能と安全性を立証する必要があるが、アーユルヴェーダ薬品は、アーユルヴェーダの古いテキストなどに療法が記述されていれば、それだけで薬品として認められてしまう。
アーユルヴェーダ薬品の規格化と品質管理も欠乏している。アーユルヴェーダの基本的な考え方は、ある土地で発生した病気は、その土地の自然物により治療される、というものだ。だが、アーユルヴェーダ製薬企業は原材料をあらゆる場所から調達しており、どこからそれが採取されたのか記載されることはない。同じ植物でも、場所が違えば含まれている成分も違うようだ。また、ひとつの植物でも、どの部分が薬品に利用されたか、ということもアーユルヴェーダ薬学では重要であるが、やはり市販されているアーユルヴェーダ薬品には、そのような詳述もない。
さらに、アーユルヴェーダ薬品には、ラベル、パッケージ、説明書、副作用の説明などに対する厳格な規則も存在しない。つまり、アーユルヴェーダ薬品は野放し状態同然である。アンブマニ・ラームダース保健大臣は、アーユルヴェーダ薬品に対する規制を強めていく姿勢を明らかにしている。
昔から現代医学と伝統医学の間には深い溝があり、お互いにお互いを有害だと罵倒し合っているのは周知の事実である。日本などでは現代医学の方が発言力が強いが、インドでは4000年のプライドの賜物か、少なくとも両者を対等の立場に置いて比較する傾向がある。上記の記事で議論されていたのも、アーユルヴェーダ薬品そのものの有害性ではなく、アーユルヴェーダ薬品の不適切な服用による問題であった。アーユルヴェーダ薬品の効能や安全性については、深く立ち入って議論されていなかったし、アーユルヴェーダを頭から否定するような論調でもなかった。とにかく必要なのは法整備である。アーユルヴェーダの薬はとかく「副作用がなくて身体にやさしい」とされがちだが、しかし薬である以上副作用がないはずはない。昔の書物に書いてあるから正しい、と考えるのも馬鹿げた話だ。ちゃんと現代の視点からアーユルヴェーダを研究し直し、現代の法律の基準でアーユルヴェーダの薬品が市販されることは必須である。とりあえず、得体の知れないアーユルヴェーダ薬品の長期服用は控えたほうがよさそうだ。
| ◆ |
5月30日(月) Jo Bole So Nihaal, Sat Sri Akaal |
◆ |
僕がモルディヴ旅行から帰って来た5月22日、デリーの映画館で連続爆破テロが発生した。午後8時15分頃、カロール・バーグのリバティーでまず爆発があった。前から6列目の座席の下に仕掛けられていた爆弾が爆発したらしい。その20分後、今度はそこから約3km離れたパテール・ナガルのサティヤム・シネプレックスのトイレで爆発があった。映画館での爆弾テロということで、第一報を聞いたときには多くの人が死ぬ大惨事になってしまうことを恐れていたのだが、どちらの爆弾もそれほど殺傷力のあるものではなかったようで、死者は1人のみ。負傷者は60人ほどだが、爆発の後に起こったパニックにより怪我をした人が割と多かったのではないかと思う。
デリーでは時々このようなテロがあるので、これだけだったら「普通の」爆弾テロで済んだかもしれない。だが、爆弾テロが発生した2軒の映画館で上映されていた映画が紛争中のものであったために、他の一連のテロとは性格が違うものである可能性が強まった。サティヤム・シネプレックスはシネコンなので、複数の映画が上映されているが、リバティーは通常の映画館であるので、一度に1本の映画しか上映されない。爆発があったときにリバティーで上映されていたのが、サニー・デーオール主演の「Jo
Bole So Nihaal」であった。この映画はサティヤム・シネプレックスでも上映されていた。この映画は、スィク教徒の団体の間で物議を醸していたにも関わらず、強行に上映されたという経緯があり、爆弾テロの目的もそれと関連していると考えられた。映画館連続爆破の知らせが広まるや否や、デリーなどの映画館で同映画の上映が急遽キャンセルされた。ただ、誰も犯行声明を出しておらず、未だに犯人は逮捕されていない(■5月31日、容疑者が逮捕された。バッバル・カールサー・インターナショナルというスィク教テロ団体の犯行だったようだ)。この事件の後、デリーの映画館は気が触れたかのように厳重な警備を始め、普段から映画館に足しげく通っていた僕は、深刻な不便を被っている。
ところで、「Jo Bole So Nihaal」の何がいけなかったのだろうか?スィク教徒は見慣れているが、スィク教にあまり馴染みのないデリー在住日本人には、分かりにくい問題である。きっと、このニュースを聞いて、しばらく映画館へ行くのを控えることにした人も多いだろう。一応、5月13日の日記に映画のレビューを書いたが、それを読んでもスィク教徒が怒る理由を理解するのは困難だろう。
まず、題名の意味が、ヒンディー語が分かってもイマイチ理解しづらい。この題名の意味をすんなり理解できる日本人がいたら、その人はスィク教マニアであろう。「Jo
Bole So Nihaal」という言葉は、「Sat Sri Akaal」という言葉とワンセットになっている。「サト・スリー・アカール」だったら、聞いたことがある人も多いだろう。ヒンディー語やインドの文化を習う際、「インドでは宗教ごとに挨拶が違う」ということを教わる。ヒンドゥー教徒だったら「ナマステー」「ナマスカール」、イスラーム教徒だったら「アッサラーム・アライクム」「アーダーブ・アルズ」であり、スィク教だったら「サト・スリー・アカール」である。「アカール(akaal)」という言葉は、ヒンディー語では「飢饉」という意味で使われることが多いが、スィク教徒の挨拶では、「時間を超越した不滅の神」という意味になるようだ。つまり、「サト・スリー・アカール」とは、「神こそ真実なり」という意味になる。一方、「ジョー・ボーレー・ソー・ニハール」とは、「その言葉を口にした者は祝福される」という意味で、「サト・スリー・アカール」とワンセットで、「『神こそ真実なり』と口にせし者は祝福されん」みたいな意味になる。スィク教徒の間では、1人の人が「ジョー・ボーレー・ソー・ニハール」と言ったら、それを聞いた人はすぐに「サト・スリー・アカール」と答えなければいけないらしい。僕も当初、「Jo
Bole So Nihaal」の意味がよく分からなかったので、スィク教徒の友人に「『Jo Bole So Nihaal』ってどういう意味?」と聞いたら、その人はすかさず「サト・スリー・アカール」と答えていた。そのときはてっきり、「Jo
Bole So Nihaal」という言葉の意味がそのまま「Sat Sri Akaal」なんだと勘違いしてしまったが、後から調べてみた結果、彼は僕の「ジョー・ボーレー・ソー・ニハール」という言葉に反応して、鸚鵡返しのように「サト・スリー・アカール」と答えただけだということが分かった。まるでパブロフの犬状態である。
アウトルック6月6日号のクシュワント・スィン氏による解説では、「Jo Bole So Nihaal, Sat Sri Akaal」というフレーズには宗教的な意味と世俗的な意味の両方があるという。まず、宗教的集会では、1人の人が「ジョー・ボーレー・ソー・ニハール」と言ったら、群集は「サト・スリー・アカール」と連呼しなければならない。しかし、教典などでそれが定められているわけではなく、伝統として行われているだけようだ。また、この習慣はそれほど古いものでもないらしい。
また、「Jo Bole So Nihaal, Sat Sri Akaal」は、戦争時のスィク教徒の掛け声でもある。ヒンドゥー教徒の戦士が「ハル・ハル・マハーデーヴ(シヴァ神への礼賛の言葉)」と叫び、ムスリムの戦死が「アッラーフ・アクバル(アッラーは偉大なり)」と叫ぶのと同様、スィク教徒の戦士たちは、ムガル朝やパターン族との戦争に臨むときに、「ジョー・ボーレー・ソー・ニハール!」「サト・スリー・アカール!」と連呼していたそうだ。ということは、日本の「エイエイオー!」くらいのニュアンスと取れる。さらには、このフレーズはスィク教徒の乾杯の合図にも使われることがあるという。
ところで、スィク教の最高権威は、シローマニ・グルドワーラー管理委員会(SPGC)という団体である。このSPGCこそが映画「Jo Bole So
Nihaal」の上映禁止を訴えた張本人だ。スィク教徒の多いパンジャーブ州とハリヤーナー州では、この映画は1週間で上映中止となったのだが、デリーでは第2週目も引き続き上映され続けていた。SPGCが第一に槍玉に挙げたのが、題名であった。「スィク教の聖なる文句(グルバーニー=グルの言葉)を、宗教的でも歴史的でもない映画の題名にしたことは許されることではない」とし、題名の変更を求めた。次に、映画中、登場人物が靴も脱がず、頭も覆わずにグルドワーラー(スィク教寺院)に入ったシーンがあることを糾弾した。キリスト教の教会を除き、ヒンドゥー教、イスラーム教、スィク教、ジャイナ教、仏教など、インドの宗教施設は基本的に靴を脱いで入らなければならない。これは日本でも同じなので、日本人には理解しやすいだろう(西洋人は理解しがたいようだ)。また、特に女性は寺院などに入るときに頭を布で覆うことを義務付けられることが多いが、こちらは多少日本人にも理解しがたい。その中で、スィク教のグルドワーラーは、男性も布で頭を覆わなければならないことになっている。大概、グルドワーラーの前とかで、バンダナみたいなものを売っているので、それを買って巻いて入ればいい。見ていると、ハンカチをちょこんと頭に乗せただけで入っているインド人もいたりする。だが、映画「Jo
Bole So Nihaal」では、それらの規則が守られていなかったというのだ。僕はそういうシーンは記憶にない。そして最後にSPGCが突きつけたのは、「アムリトダリー・スィク(洗礼済みのスィク教徒)しか映画中スィク教徒を演じてはならない」という厳しい条件である。また、映画中でサニー・デーオール演じる主人公ニハール・スィンの母親が、ニハールとFBIエージェントの女性との性的関係を認める発言をしたり、米国大統領暗殺に共謀したりするシーンにも苦言を呈した。
デリー映画館連続爆破テロがこのSPGCの仕業だとは断定できないし、おそらくそうではないだろう。犯人が誰かは判明していないが、SPGCの主張に影響を受けたスィク教徒だということは十分に考えられる。
最近、スィク教徒たちは、インドだけでなく世界で、スィク教徒に対する弾圧に目を光らせており、しばしば抗議運動を起こしている。先月、デンマークでスィク教の学生が、6インチの短刀を所持していた罪で逮捕された。キルパーンと呼ばれる短刀を常に所持することは、スィク教徒の義務とされているが、911事件後、海外でその義務を全うすることは難しくなっている。だが、SPGCは、そのスィク教徒の学生の解放とキルパーン所持の権利を主張している。また、フランス政府が国内のスィク教徒に対しターバン着用を禁じたことに対しても、SPGCは抗議している。さらには、SPGCは、アムリトサルにある黄金寺院の名称を、英国支配を想起させる「ゴールデン・テンプル」から、正式名称である「ハルマンディル・サーヒブ」または「ダルバール・サーヒブ」に改名することも検討中だとか。ヒンドゥー至上主義ならぬ、スィク教至上主義が台頭してきているかのようだ。
だが、右傾化するSPGCの動きに対し、スィク教徒内部からそれを疑問視する見方も出ている。前述のクシュワント・スィン氏は、スィク教の開祖ナーナクの言葉を引用して、原理主義化しつつあるスィク教を批判している――「Ikna
Sudh, Na Budh, Na Akal Sar, Akhar Ka Bheo Na Lahant / Nanak Se Nar Asal
Khar, Jo Bin Gun Garab Karant」、つまり、「知恵も思考もなく、意味も解せず言葉を言い、良識や誇りもなく行動する者はロバ同然とナーナク言えり」という意味である。また、スィク教は形式的規制が多いために、それに捉われがちになっている宗教だとの批判もある。
現在首相を務めるマンモーハン・スィン氏は、スィク教徒で初めてインドの首相に就任した人物である。既にマンモーハン・スィン政権は1周年を迎えた。しかし、皮肉なことに、スィク教徒の首相が誕生して以来、スィク教徒の活動が何やら不穏になってきているように感じるのは僕だけだろうか。



