| ◆ |
6月1日(金) Rowdy Rathore |
◆ |
ヒンディー語映画界では近年南インドの大ヒット・アクション映画をリメイクすることが流行しており、その内のいくつかは成功している。そのトレンドを生み出すきっかけになった作品の内のひとつがサルマーン・カーン主演の「Wanted」(2009年)であり、その監督がプラブデーヴァであった。
プラブデーヴァと言えば、インド映画界ではその名を知らぬ者がいないほど有名なダンサー、コレオグラファーであり、その軟体動物のような器用な動きから、「インドのマイケル・ジャクソン」の異名を持っている。2005年からは監督業にも進出しており、「Pokkiri」(2007年)やそのリメイク「Wanted」など、いくつかヒット作もある。
さて、本日より公開の「Rowdy Rathore」も、プラブデーヴァ監督のヒンディー語映画であり、南インド映画のリメイクである。オリジナルはテルグ語映画「Vikramarkudu」(2006年、SSラージャモウリ監督)で、その後各言語でリメイクされている――カンナダ語映画「Veera
Madakari」(2009年、スディープ監督)、タミル語映画「Siruthai」(2011年、シヴァ監督)、ベンガリー語映画「Bikram
Singha: The Lion is Back」(2012年、ラージーブ・ビシュワース監督)などである。
南インド映画リメイクが流行して以来、アーミル・カーン、サルマーン・カーン、アジャイ・デーヴガンなど、ヒンディー語映画界のAクラスの男優たちが南インド的なアクション・ヒーローを演じて来たが、今回「Rowdy
Rathore」で主演を演じるのはアクシャイ・クマール。最近低迷中だった彼も、遂にこのバンドワゴンに乗ることになった。ヒロインは「Dabangg」(2010年)でデビューしたソーナークシー・スィナーで、これが2作目となる。
題名:Rowdy Rathore
読み:ラウディー・ラートール
意味:乱暴者のラートール(主人公の名前)
邦題:ラウディー・ラートール
監督:プラブデーヴァ
制作:サンジャイ・リーラー・バンサーリー、ロニー・スクリューワーラー
音楽:サージド・ワージド
歌詞:ファイズ・アンワル、サミール、シラーズ・アハマド、サージド
振付:サロージ・カーン、ヴィシュヌ、ボスコ・シーザー
衣装:ニハーリカー・カーン
出演:アクシャイ・クマール、ソーナークシー・スィナー、ナーサル、ヤシュパール・シャルマー、ダルシャン・ジャリーワーラー、ヴィジャイ(特別出演)、カリーナー・カプール(特別出演)など
備考:PVRプリヤーで鑑賞。
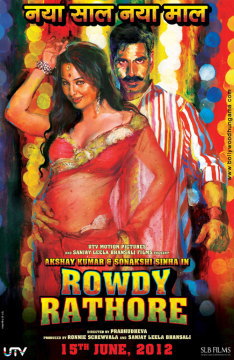
ソーナークシー・スィナー(左)とアクシャイ・クマール(右)
| あらすじ |
ムンバイー在住のシヴァ(アクシャイ・クマール)は天才的な泥棒で、相棒と共に人々から金品を巻き上げる毎日を送っていた。しかしシヴァは、ビハール州から従姉妹の結婚式に参列するためにムンバイーにやって来た女性パーロー(ソーナークシー・スィナー)と出会い、恋に落ちる。シヴァは正直にパーローに自分が泥棒であると打ち明ける。パーローはそんな彼の正直さを評価し、彼の愛を受け容れる代わりに、明日から泥棒を止めるように言い聞かす。シヴァはそれを承諾し、明日から泥棒稼業から足を洗う代わりに、今日一生分の盗みをすることを決める。
シヴァは裕福そうな貴婦人から、金目のものが詰まった箱を盗み出す。ところがその中には1人の少女が入っていた。彼女の名前はチンキーと言った。しかもチンキーはシヴァのことを「パパ」と呼んでいた。子供嫌いだったシヴァであるが、仕方なくチンキーを家に連れて帰る。しかしそれを見たパーローはシヴァの娘だと勘違いし、怒ってビハール州に帰って行ってしまう。残されたシヴァは、チンキーの持ち物の中から、父親が写った写真を見つける。なるほど、チンキーの父親はシヴァにそっくりであった。シヴァはチンキーの父親を捜し始める。
チンキーの父親の名前はヴィクラム・ラートール(アクシャイ・クマール)という名前で、正義感と腕っ節の強い警察官であった。6ヶ月前のこと。ラートールはビハール州デーヴガルの警察署の署長に就任した。デーヴガルはバープジー(ナーサル)というマフィアの支配下に置かれており、警察でさえも立ち向かえなかった。ちょうど地元警察のヴィシャール(ヤシュパール・シャルマー)の妻がバープジーに誘拐され、幽閉されていた。それを聞いたラートールはすぐさまバープジーの邸宅に突撃し、ヴィシャールの妻を助け出すと当時に、彼女を繰り返しレイプし続けたバープジーの息子を逮捕する。バープジーは州大臣とも密通しており、息子はすぐに釈放されてしまうが、ラートールは彼を公衆の面前で辱めようとした息子を逆に高所から落ちさせ、死なせてしまう。
しかしラートールはその後バープジーの刺客から襲撃を受け、頭部に銃弾を受けてしまう。バープジーはラートールが死んだものと考えるが、ラートールは生きていた。ラートールが生きていることは隠しながら、ヴィシャールはラートールをしばらく地元の医者の下で療養させ、その後ムンバイーに運んで治療を受けさせた。彼はムンバイーでラートールにそっくりのシヴァを見つけ、ラートールの娘チンキーを彼の下に住まわせたのだった。
ところが、ヴィクラム・ラートールが生きていることを知ったバープジーは刺客をムンバイーに差し向けていた。シヴァはラートールと間違われ、刺客たちに追われる。ところがそれを助けたのがラートール本人であった。ラートールは1人で暴漢たちを打ちのめすが、頭部に受けた傷がまだ癒えておらず、ピンチに陥る。突然雨が降り出したことで頭部が冷え、一瞬だけ正気を取り戻すが、刺客を全て成敗した後に倒れ込み、そのまま帰らぬ人となった。しかし、息を引き取る前にラートールはシヴァに娘を託した。
シヴァはラートールの意志を引き継ぎ、ラートールになりすましてデーヴガルに乗り込む。デーヴガルではパーローとも再会する。パーローの誤解は解けており、彼女はシヴァとチンキーを受け容れる。
シヴァはまずバープジーの醸造所を焼き討ちし、穀物庫から穀物を奪い出す。そしてバープジーを棒で叩いてこらしめる。しかしながらバープジーの手下で圧倒的パワーを持った刺客がシヴァに勝負を挑む。彼はパーローとチンキーを誘拐し、シヴァを誘い出す。決闘においてシヴァは刺客とバープジーの両方を殺す。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
インドでは各言語で各様の映画が作られており、それらはそれぞれ長所を持っていると思うし、毎年傑作も生み出していることと思う。しかし、特定の言語と地域でヒットした映画を安易にリメイクして他の言語や地域に持って行っても、必ずしも同様のヒットが望めるとは限らない。何かの間違いでヒットしたとしても、その質は必ずしもヒンディー語映画のスタンダードに見合うものではない。近年、南インド映画のヒンディー語リメイクは概ねヒットしているが、その多くは技術的な面でヒンディー語映画界の一般的な商業映画に劣っている。残念ながらこの「Rowdy
Rathore」も、ヒンディー語映画のスタンダードに照らし合わせると、非常に未熟な作品であった。唐突なダンスシーンはまだ許せるとしても、いくつかは非常に退屈で蛇足あった。さらに、主人公のシヴァやラートールをはじめ、キャラクターが立っていないし、特に終盤、ストーリーが飛び飛びになっており、編集のまずさが目立った。昔ながらの文法で映画を作ること自体に問題はない。だが、ヒンディー語映画を過去に引き戻そうとするような試みは止めるべきである。「Rowdy
Rathore」は、全く未来を向いていない作品だった。
それでも、南インド映画のリメイクにありがちな点ではあるが、アクションシーンやダンスシーンの多くの質は良かった。アクションとダンスの合間に、オマケ程度にストーリーが展開するような感じである。不必要だと思ったのは「Dhadhang
Dhang」や「Chamak Challo Chel Chabeli」。逆に素晴らしかったのは「Chinta Ta Ta Chita Chita」と「Aa
Re Pritam Pyaare」である。プラブデーヴァの映画を見ていると、南インド映画界でダンスシーンが高度に発達したのは、プラブデーヴァの存在が非常に大きかったのではないかと思えて来る。プラブデーヴァは「Chinta
Ta Ta Chita Chita」で自ら踊りを踊っているし、多くのダンスシーンでアクシャイ・クマールに南インド的なステップを踏ませている。プラブデーヴァのダンスと振り付けの才能についてはいくら書いても書き切れない。他にコメディーの部分もまあまあ受けていた。総じて、各部品については優れたものがある娯楽作品だったと言える。
数年停滞が続いているアクシャイ・クマールは、この「Rowdy Rathore」でも浮上出来なさそうだ。ただ、彼の演技は悪くなかった。悪いときの彼の演技は非常に大雑把になるのだが、今回はダブルロールをうまく演じ分けていたし、単なるドンチャン騒ぎにもなっていなかった。このまま謙虚な気持ちで真摯に演技をして行けば、また黄金期がやって来るだろう。
ソーナークシー・スィナーについてはまだ才能を測れない。彼女が演じたパーローは全くキャラクタースケッチがうまく行っておらず、映画を見終わった後も一体どんな女性なのかすらよく分からない。だから今回の彼女が混乱した演技をしていたとしても、彼女のせいとは言えない。しかしながら、終盤、誘拐されたときに見せた啖呵の切り方だけは素晴らしく、この線で今後チャンスを掴んで行けるかもしれない。また、最近の女優にしてはムッチリとした体つきで、監督もそれを知ってか知らずか、彼女の豊満な肉体美をよくカメラで捉えていた。まだこういうふくよかな女性を好む人口はインドには多いと思われるので、その筋にも受けて行くかもしれない。
また、悪役バープジーはかなり情けない最期を遂げるが、この役を演じたナーサルはタミル語映画界の名優である。他にヤシュパール・シャルマーやダルシャン・ジャリーワーラーなどが出演していた。
音楽はサージド・ワージド。「Rowdy Rathore」のサントラCD自体はいい曲が揃っているが、前述の通りいくつかの曲においてダンスがうまく伴っていなかった。しかしながらダンスにおいて特筆すべきことは多い。まず、「Chinta
Ta Ta Chita Chita」において、プラブデーヴァに加えてカリーナー・カプールとヴィジャイがカメオ出演していることである。ヴィジャイはタミル語映画のスターで、「Pokkiri」や「Villu」(2009年)などのプラブデーヴァ監督作でも主演を務めている。さらに調子に乗って、アクシャイ・クマール、カリーナー・カプール、プラブデーヴァの3人が一緒に踊るシーンや、アクシャイ・クマール、ヴィジャイ、プラブデーヴァの3人が一緒に踊るシーンなどがあり、非常に豪華なダンスシーンとなっている。また、「Aa
Re Pritam Pyaare」では、マリアム・ザカーリヤー、シャクティ・モーハン、ムマイト・カーンの3人がアイテムガール出演している。マリアム・ザカーリヤーはイラン人とスウェーデン人のハーフで、スウェーデンでボリウッド・ダンスの学校を経営している他、いくつかのインド映画でアイテムガール出演している。シャクティ・モーハンはインド人コンテンポラリー・ダンサー。TV番組「Dance
India Dance」の勝者で、やはり「Tees Maar Khan」(2010年)などでアイテムガール出演している。ムマイト・カーンは米国人とインド人のハーフで、南インド映画界を中心にアイテムガールの長いキャリアを持っている。この3人が揃って踊りを踊る点で、やはり豪華なダンスシーンとなっている。
劇中ではムンバイーとビハール州の架空の町デーヴガルが舞台となっていたが、撮影の多くはカルナータカ州で行われたと見られる。バンガロール、ハンピ、バーダーミなどの景色が見られた。
「Rowdy Rathore」は、アクシャイ・クマール起死回生の一作のはずであったが、南インド映画リメイクの悪い部分が出てしまっており、作品の質はヒンディー語映画標準レベルに至っていない。しかしながら、アクションやダンスには見るべきものがあり、何とか映画を救っていた。地方ではもしかしたら受けるかもしれないが、都市部での成功は見込めそうにない。
| ◆ |
6月4日(月) Flipkart.comを使ってみた |
◆ |
論文を書く上でどうしても欲しい本があった。ケンブリッジ大学出版(CUP)の本で、英国から取り寄せなければならなかった。CUPのデリー支社に問い合わせてみたところ、最低でも3-4週間は掛かるとのことであった。たまたまインドの最大手EコマースサイトFlipkart.com(フリップカート・ドットコム)で調べてみたところ、こちらでは2-3週間となっており、しかもCUPの提示する値段より安かったので、試しに利用してみることにした。

Flipkart.comは2007年にインド工科大学(IIT)デリー校卒業生のサチン・バンサルとビニー・バンサルがバンガロールで設立した会社である。2人は元々アマゾンに勤務しており、その経験を活かして、インドにおいて同様のオンライン書籍販売サイトを立ち上げたのだった。似たようなサイトはインドでも複数登場したが、Flipkart.comは最も成功しており、現在インドのオンライン書籍販売市場の8割を占めているとされる。また、同サイトは本以外にも徐々に取り扱い商品を増やしており、現在では携帯電話、PC、カメラ、MP3など、14カテゴリーに及ぶ商品を扱っている。従業員数は4,500人、2011-12会計年の売上は50億ルピー、1日に3万アイテムを受注していると言う。
Flipkart.comの成功の秘訣は主に3つあるだろう。ひとつは大胆なディスカウント。実店舗で購入するよりも安い値段で商品を提供している。加えて送料も無料である。だが、単なる値引きだけでは、まだオンラインショッピングが浸透し切っていないインドではアピール力に欠ける。Flipkart.comの最大の売りは代金引換の支払い方法を実用化させたことにある。インド人の多くはまだまだウェブサイト上でクレジットカードやデビットカードによる決済をすることに抵抗を持っている。小切手が流通している代わりに、銀行振り込みはまだまだである。そもそも銀行口座やカードを持っていない人も多いし、お金の受け渡しに関して他人を最初から信用するような社会ではない。このような現状のため、代金引換――つまり商品を受け取るときに代金を支払えばいいシステム――の導入はインド人にとってオンラインショッピングの敷居を一気に低くする画期的な出来事であった。もちろん日本でもこの支払い方法はあるが、配達業者が別のため、商品の代金や送料とは別に手数料が掛かることが多い。その点Flipkart.comでは専属の配送員を配備しており、代金引換は無料である。むしろ多くの利用者が代金引換で支払うことを前提としているくらいである。また、現金だけでなく、配送員は携帯式のカードリーダーを持参しており、商品受け取り時にクレジットカードやデビットカードを使っての支払いも可能である。同社はこれを「Cash
or Card on Delivery」と呼んでいる。Flipkart.comの売上の実に6割が、このシステムを利用したものであると言う。この代金引換システムによって利用者のリスクを最大限に減らすと同時に、3つめの売りである「30日交換保証」制度で、購入後のアフターケアにも最大限の配慮をしている。もし商品に欠陥が見つかった場合などは、受け取りから30日以内に申告することで新品と交換が可能である。
他に、最近ではTVなどでも大々的に広告を打ち出しており、それらがなかなかインパクトがある。子供が成人の役を演じ、声だけ成人という設定も面白いが、何より巧妙なのは、インド人がオンラインショッピングに対して抱く疑問をひとつひとつ解消していることである。例えばShopping Ka Naya Address - Three Generationsと題したCMでは、インターネット上の写真だけを見て買い物をすることへの不安をうまく緩和している。CMのあらすじはこうである――3世代が住む家において、祖父がFlipkart.comで携帯電話を購入、それが届いた。孫たちも新しい携帯電話にエキサイト気味である。だが、保守的そうな父親は、写真だけを見て買い物をすることに反対する。すると、妻がぼそっとつぶやく・・・「私だって結婚する前、あなたの写真しか見てないわ。」絶句する父親、笑いをかみ殺す祖父と孫たち――インドの伝統的な社会慣習をうまくオンラインショッピングという新しいシステムにつなげた秀逸なCMである。代金引換システムもさりげなくアピールしている。
さて、僕がFlipkart.comで注文したのは5月22日であった。もちろん支払い方法は代金引換を選んだ。するとすぐにEメールによって注文の明細が送られて来た。そこには、注文から3週間後の6月16日までに配達予定と書かれていた。そしてその日の内に電話が掛かって来て、注文の確認があった。その後、6月1日にEメールがあり、注文の品物を発送した旨が伝えられて来た。そして6月2日に携帯電話にSMSがあり、本日中に配達が行われるとあった。実際にこの日に配達員が来たようなのだが、不運にも寮の警備員と喧嘩し、怒って帰ってしまったようで、また後日来ることになった。そのときちょうど携帯電話を手元に置いていなかったため、僕も電話に出ることが出来なかった。6月4日、またもSMSがあり、同様に本日中の配達が伝えられた。念には念を入れて、警備員にFlipkart.comから配達員が来ることを伝えておいた。果たして配送員は暑い中昼過ぎに再度やって来てくれて、注文していた本を間違いなく届けてくれた。品物を確認し、代金を支払った。もし6月2日に届いていたら、注文から11日で届いたことになる。6月4日だとしても2週間以内であることには変わりなく、少なくともデリーにおいては、非常に優秀な調達・配送システムを保持していることが分かる。Flipkart.comを高く評価するに至った次第である。ちなみに、配送員はちゃんとCMに登場するような制服を着ていた。

Flipkart.comデリバリー成功
梱包もまあまあしっかりしている
ところで、僕の住むジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)は比較的郵便物が届きやすい地域なのだが、首都デリーの中にあっても、住所があってないような住宅地というのも多くあり、そのような地域に住む人々は郵便物の受け取りに多大な苦労を要する。よって、担当の郵便配達員と懇意になっておくことは重要である。いっそのことポスタルアドレス(郵便物受け取り住所)を、自分の住所ではなく、分かりやすい住所に住む知人や友人のものにしてしまっている人も多い。何を隠そう、僕の住所も複数の友人からそのように利用されている。Flipkart.comでは住所の他に、家の近くのランドマークを記載する欄があり、それによってなるべく確実に配達できるように工夫している。分かりにくい住所に住む人の家に確実に注文品が届くならば、Flipkart.comは本物だと言えるだろう。最近では携帯電話があるので、電話で確認しつつ探せば、指定の住所まで辿り着くことにも大きな困難はなくなったであろうが、配達員が英語をしゃべれるとは限らないので、スムーズな受け取りを実現するためには、圧倒的に分かりやすい住所か、多少のヒンディー語力のどちらかが必要になるかもしれない。一般の外国人(ヒンディー語が出来ない人)にとってどれだけ使い勝手がいいかは、もう少し検討を要するだろう。
Flipkart.comが意外に使えることが分かったので、同サイトがどのような本を取り揃えているのか改めて調べてみた。もし古書なども充実していたらありがたいのだが、やはりラインナップは新刊本が中心である。しかしながら、個人的に非常に役に立ちそうなのは、ヒンディー語の本が割と揃っていることだ。英語の本の多くは一般の書店で容易に手に入るが、現地語の本は流通網が全く別で、限られた書店でしか手に入らない。大体の場合オールドデリーまで行かなければならない。ヒンディー語の出版社はデリーに多いので、デリーに住む限り、はっきり言って書店ではなく直に出版社に乗り込んで購入するのが一番早くて確実な方法だ。しかし、Flipkart.comで手に入るのならば、こちらを利用した方が便利そうである。特に酷暑期や雨季のように外出が億劫な時期はとても助かる。
インドの小売の中心は、ローカル・マーケットからモダン・マーケットへ、そしてショッピングモールへと急速に変遷して来た。おそらく次のステップは他国と同様に確実にオンラインショッピングになって行くだろう。そして、その成功の鍵はどうやら、Flipkart.comが実現した手数料無料の代金引換になりそうだ。
現在ヒンディー語映画界においてアヌラーグ・カシヤプ監督に並んで果敢に実験的かつ先進的な映画を作り続けているのがディバーカル・バナルジー監督だ。「Khosla
Ka Ghosla」(2006年)、「Oye Lucky! Lucky Oye!」(2008年)とユニークなヒット作を飛ばし、2010年には突然、野心的な問題作「Love
Sex aur Dhokha」を送り出して世間をアッと驚かせた。これまで彼は低予算型の非スター型映画を作って来たが、これらの作品の成功により、ようやくまとまった予算とスターキャストが揃った映画の制作・監督を許されるようになった。それが本日より公開の「Shanghai」である。典型的なスター俳優ではないものの、名前だけで十分客を呼べるだけの知名度を持ったイムラーン・ハーシュミーを主演に据え、お気に入りのアバイ・デーオール、フランス系インド人女優カールキー・ケクランなども起用した、今までのディバーカル映画の中ではもっとも豪華なキャスティングの作品となっている。
映画の題名を聞いて真っ先に思い浮かべるのが中国の上海であろう。もちろんこの題名は同都市から付けられている。しかしながら、「Shanghai」は上海が舞台の映画ではないし、劇中で上海が重要なキーワードとなっている訳でもない。むしろ、インドの架空の小都市バーラトナガルを舞台にした映画であり、インドの土の臭いに満ちた映画だ。この映画のキーワードは「発展」。上海はその「発展」のメタファーとして使われている。政治家が有権者に対して「あなたたちの町を上海のようにする」と言って発展を約束する場面を想像してもらえれば理解は易しいだろうが、面白いことに劇中にそのような場面はない。
また、あまり表立って宣伝されていないが、「Shanghai」はギリシア人作家ヴァシリス・ヴァシリコスの小説「Z」を原作としている。1963年の王制下に起きた自由主義者グレゴリス・ランブラキス暗殺事件を描いた作品で、1969年にはコスタ・ガブラス監督によって映画化もされている。
劇中の挿入歌「Bharat Mata Ki Jai(インド女神万歳)」の歌詞が、愛国心を毀損する内容であり不適切であるとして物言いも入ったが、公開直前に裁判所から「表現の自由」のお墨付きも出て、どうにかスケジュール通り公開に漕ぎ着けた。今年の期待作の一本である。
題名:Shanghai
読み:シャンハイ
意味:上海
邦題:シャンハイ
監督:ディバーカル・バナルジー
制作:ディバーカル・バナルジー、アジャイ・ビジュリー、サンジーヴKビジュリー、プリヤー・シュリーダラン
原作:ヴァシリス・ヴァシリコス「Z」(1966年)
音楽:ヴィシャール・シェーカル
歌詞:ディバーカル・バナルジー、アンヴィター・ダット、クマール、ニーレーシュ・ミシュラー、ヴィシャール・ダードラーニー
衣装:マノーシー・ナート、ルーシー・シャルマー
出演:イムラーン・ハーシュミー、アバイ・デーオール、プロセーンジト・チャタルジー、カールキー・ケクラン、スプリヤー・パータク・カプール、ティロータマー・ショーメー、ピトーバーシュ・トリパーティー、ファールーク・シェーク
備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左からプロセーンジト・チャタルジー、アバイ・デーオール、
イムラーン・ハーシュミー、カールキー・ケクラン
| あらすじ |
マハーラーシュトラ州では州議会選挙が間近に迫っていた。地方都市バーラト・ナガルでは経済特区インターナショナル・ビジネス・パーク(IBP)の建設計画が進んでおり、州首相(スプリヤー・パータク・カプール)は選挙前にその計画のゴーサインを中央政府から得ようとしていた。しかし、貧困者を住んでいる土地から追い出して「発展」を追求する政府の手段に反対する活動家ドクター・アハマディー(プロセーンジト・チャタルジー)は、住民を説得しIBP計画を止めるためにバーラト・ナガルに降り立った。それを出迎えたのが、地元に住む若き女性活動家シャーリニー・ピアソン・サハーイ(カールキー・ケクラン)であった。米国留学時代にシャーリニーはアハマディーから教えを受けており、2人は師弟関係以上の仲にあった。シャーリニーはメイドからアハマディーの命が危ないとの警告を受けており、終始彼の身を案じていた。
アハマディーは、与党ワーカーたちの妨害に遭いながらもバーラト・ナガルで住民向けに演説会を行う。ところがそれが終わった直後にアハマディーは暴走するトラックに轢かれて瀕死の重傷を負ってしまう。運転手ジャッグー(アナント・ジョージ)は逮捕される。ちょうどその時、バーラト・ナガルでビデオ屋を営むジョーギンダル・パルマール(イムラーン・ハーシュミー)は事故の現場に居合わせる。デリーからアハマディーの妻アルナー(ティロータマー・ショーメー)が飛んで来て、事故の調査を訴える。州首相は子飼いの高級官僚TAクリシュナン(アバイ・デーオール)を調査委員会の委員長に任命する。
州首相の筆頭書記官カウル(ファールーク・シェーク)はクリシュナンに、適当に調査をして報告書をまとめるように言う。酔っ払った運転手による事故だとされており、警察の警備に手抜かりがなかったかを調べればいいと言われていたものの、クリシュナンは警察の報告に矛盾を見つけ、事件の真相に徐々に迫って行く。一方、シャーリニーも独自に、アハマディーの事故は事故ではないと証明しようと動き出す。事故の前にアハマディーの死を予告したメイドが何かを知っているはずだったが、彼女は何も語ろうとしなかった。そこで次に鍵を握っていたのがジョーギンダルであった。彼は、事故の前後に映したビデオを持っていた。また、与党ワーカーに彼の同僚が惨殺される事件があり、他にも何か証拠を掴んでいそうだった。シャーリニーはジョーギンダルとコンタクトを取る。ジョーギンダルは、事故前後のビデオに映っている複数の人物が与党ワーカーであることを突き止める。また、事故を起こしたトラックの荷台に乗っていた男バッグー(ピトーバーシュ・トリパーティー)の特定にも成功する。シャーリニーとジョーギンダルはクリシュナンのところへ行き、証拠が入ったCDを手渡す。
翌日、トラック運転手ジャッグーは釈放されるが、同時にジョーギンダルのタレコミによって、アハマディーの事故に与党ワーカーの関与が疑われることが新聞に掲載される。それに憤った与党ワーカーたちはバーラト・ナガルで暴動を起こし、町には戒厳令が敷かれる。クリシュナンの家やジョーギンダルのオフィスも与党ワーカーたちの襲撃を受ける。シャーリニーとジョーギンダルは一旦バーラト・ナガルから脱出するが、シャーリニーはメイドから電話を受け、彼女を訪ねるために再びバーラト・ナガルへ舞い戻る。実はそのメイドの夫こそがジャッグーであった。ジャッグーは大金を積まれてアハマディー暗殺を実行したことを明かす。また、ジョーギンダルは死んだ同僚がハードディスクに何らかのデータを保存していたことを思い出し、オフィスへ駆けつける。オフィスからPCごと持ち出し、シャーリニーと共にクリシュナンを訪ねる。その中には、州首相がアハマディー暗殺を指示する内容のやり取りが記録されていた。
クリシュナンはその前に州首相と面会しており、犯罪部による再捜査を提案していた。クリシュナンはストックホルムへの赴任や出世も約束されていた。しかしながら州首相の関与が明らかになったため、クリシュナンはカウルと会い、中央政府内務省に報告して州首相を告発することを提案した。カウルも州首相の一味であったが、政治的な判断により、それを渋々受け容れる。
その後・・・。瀕死の状態にあったアハマディーは病院で息を引き取る。クリシュナンはストックホルム行きを断り、州首相の捜査を強行する。シャーリニーはアハマディー暗殺に関する本を書くが禁書処分となり、その本はインドで出版されなかった。ジョーギンダルはポルノ映画を撮影した容疑で指名手配されるが、既に行方をくらましていた。アルナー・アハマディーは政治家になっており、IBP推進派の1人となっていた。IBP計画は実行に移され、ジャッグーは建設予定地に立つ家々を取り壊すブルドーザーを運転していた。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
原作「Z」は未読なのだが、おそらくもっと大きな背景の中で動く政治劇を描いた小説なのだろう。2時間弱の映画である「Shanghai」の中では、とてもでないが全てを描写し切ることが出来ていなかった。とある大長編の物語の一部を切り取ったような作品で、1本の映画の中で物語が完結していなかった。シャーリニーの父親のこと、シャーリニーとアハマディーの関係、ジョーギンダルがジョードプルからバーラト・ナガルに来るまでの話、アルナー・アハマディーの存在、クリシュナンの家族など、主要登場人物がそれぞれより大きなバックグランドを持っていながら、劇中ではそれらが断片的にしか示唆されない。もちろん、叙事詩的な巨大な世界観を匂わせながら、ミクロなストーリーを描くことが必ずしも映画の質を下げることにつながらない。しかしながら、結局劇中で描かれていたのは、ありきたりな政治の陰謀劇であり、特にそれらの背景に興味を引かれるような魅力を醸し出せていなかった。あらすじは一言でまとめることが可能だ。州政府が主導する開発計画に反対する活動家が事故で瀕死の重傷を負い、最終的に死んでしまうが、それは実は事故ではなく、仲間の活動家たちが主張していたように、州首相を筆頭とする与党政治家による陰謀だった、というものである。それに踏み込むのが、インド人と米国人のハーフ女性、何でも屋のビデオグラファー、そしてインド高級官僚(IAS)のトリオである点が幾分目新しいだけであり、基本的なプロットは陳腐かつ退屈であった。よって、「Shanghai」には個人的に多大な期待を寄せていたのだが、正直言って残念ながら期待外れの出来であった。
それでも、ディバーカル・バナルジー監督が今回選んだテーマは非常にタイムリーだった。おそらく西ベンガル州スィングルにおけるターター・ナノ工場建設を巡る反対運動が大きなインスピレーション源となっていたと思われる。また、州首相の人物像からは、ウッタル・プラデーシュ州の元州首相マーヤーワティーやタミル・ナードゥ州の現州首相ジャヤラリターなどが思い起こされる。そして与党のスローガン「ジャイ・プラガティ(発展万歳)」からは、「ジャイ・マハーラーシュトラ(マハーラーシュトラ州万歳)」の連想からマハーラーシュトラ州が脳裏に浮かぶ。以上の州においては発展の名の下に様々な開発計画が進められており、周辺住民や立ち退きを求めらた住民たちとの間に大きな摩擦が生じている。具体的には、西ベンガル州はスィングル問題であるが、ウッタル・プラデーシュ州では例えばヤムナー・エクスプレス・ハイウェイ建設計画、タミル・ナードゥ州ではクーダンクラムの原発建設問題、マハーラーシュトラ州ではジャイタープル原発問題などである。ちなみに劇中ではインターナショナル・ビジネス・パーク(IBP)という経済特区建設を巡って、推進派の与党と反対派の活動家たちによる戦いが繰り広げられていた。
しかし、それらの大規模な建設計画を持ち出さなくても、「Shanghai」が提示した「発展の代償」の問題はもっと身近なものだ。例えばインドでは多くの外国人がゲーテッド・コミュニティーと呼ばれる高級マンション・コンプレックスに住んでいる。それらのコンプレックスには異国情緒溢れる名前が付けられ、その敷地内にいれば確かにまるでインドではないかのような快適な生活が約束される。ゲーテッド・コミュニティーの住民は間違いなく富裕層であり、そこに住むために多額の金を支払っている。しかし「発展の代償」は彼らが支払う高額の家賃・住宅費のことではない。元々その土地に住んでいた人々の人生、生活、尊厳についてである。彼らは住み慣れた土地を追い出され、収入源だった農地を奪われ、その代わり元々彼らが住んでいた土地にやって来た富裕層の下でガードマンや運転手など、社会的地位の低い仕事をして生計を立てるようになる。今までインドのメインストリーム経済から半ば独立した暮らしをしていた人々は、否応なしにその中に取り込まれ、それと同時に自身が社会の底辺に立っていることを思い知らされる。こういう状況を「発展」と名付けていいのか、ディバーカル・バナルジー監督がこの映画で主張したかったことのひとつであろう。
しかしながら、バナルジー監督自身が語っているように、「Shanghai」は決してそのような「発展」に真っ向から反対する作品ではない。冒頭において、アハマディーの声を借りて、「発展」に対する疑問を提示してはいるが、ストーリーはすぐにそのメッセージから離れ、単なるスリラーとなる。そして一連の出来事が終わった後には、何事もなかったかのように、IBPは実行に移されるのである。この種の「発展」はもう止められない。良きにしろ、悪きにしろ、「発展」し続けて行くしかない。僕はバナルジー監督が最終的に達した結論はこれだと感じた。その中で一般庶民が何をしていけるのか、それを問う映画だった。
だが、最後に筆頭書記官カウルがクリシュナンに「波風を立てなければインドは中国になれるのに」みたいな意味の言葉をつぶやいたのも気になった。インドも中国のような著しい発展が出来るのに、という意味である。だが、中国が一党独裁体制と情報統制によって人民を押さえつけて急速に開発を推し進めて来たことは周知の事実である。劇中で与党が採った、反対派を暗殺し、開発計画を推し進める手法は正に中国的な方法論だ。しかも、与党は民主主義の礎である選挙を有利に進めるために、「発展」の名の下に、非民主主義国家である中国の方法を採るのである。選挙をするだけでは民主主義国家としては不十分なのだ。そしてその種の排他的・強圧的な「発展」の先にあるのは中国という独裁国家の姿だ。そう考えると「Shanghai」という題名もかなり生きて来る。しかし、インドにはクリシュナンのような正義感溢れる官僚もおり、州首相の不正や犯罪に対しても声を上げる勇気を持っていた。おかげで「発展」のスピードは遅れるかもしれないが、それは決して否定的なことではない。そこにバナルジー監督がインドに対して抱いている信頼感や誇りも感じた。ただ、最後の最後でシャーリニーの本が発禁処分となったことが簡単に語られており、やはり油断しているとインドでもどんどん表現の自由が削られて行ってしまうという警鐘が鳴らされていたと思う。
総じて、映画自体はとても退屈な出来であったが、行間からバナルジー監督がこの映画で言わんとしていることを読み取る努力をすると、現代のインドにとって非常に意義のある作品になっていたと思う。惜しむらくは、そのメッセージをうまく娯楽映画のフォーマットに載せて語ることが出来なかったことだ。その点では「3
Idiots」(2009年)のラージクマール・ヒーラーニー監督などにはまだ今一歩及んでいない。
主演格3人の演技はどれも素晴らしかった。イムラーン・ハーシュミーは今までのイメージに乗っかりながらも、それを払拭するシリアスな演技を見せていた。彼は常に自然な演技が出来る希有な才能を持った男優である。今までバット・キャンプのB級娯楽映画出演が多かったが、シリアスな役も十二分に演じ切れることが「Shanghai」によって証明されたと言える。イムラーンのキャリアにとって非常に重要なターニングポイントとなるだろう。
アバイ・デーオールはタミル人高級官僚役。タミル語を特訓し、劇中ではタミル語の台詞もいくつかしゃべっている他、彼のしゃべるヒンディー語はタミル訛りになっている。インド映画において官僚は冷たい存在として描かれることが多いのだが、彼は新しい視点からインド人官僚像を定義し直したと言える。
カールキー・ケクランもベストの演技を見せていた。間の取り方が非常にうまい。彼女のヒンディー語は時々聴き取りにくいこともあるのだが、それをネックとは感じさせない好演であった。
他にアハマディーを演じたプロセーンジト・チャタルジーはベンガリー語映画界で活躍する名優であり、ヒンディー語映画に出演するのは珍しい。ほとんど序盤のみの出演であったが、非常に力強い演技で、映画全体を覆う存在感を示していた。カウルを演じたファールーク・シェークも巧みな演技。だが、ピトーバーシュ・トリパーティーを再びスクリーンで見られたことが嬉しい。「Shor
in theCity」(2011年)で一躍注目を浴びた俳優で、今回もバッグーというおいしい役を演じていた。また、アルナーを演じていたティロータマー・ショーメーは、「Monsoon
Wedding」(2001年)でメイド役を演じていた女性である。出番は少なかったが、非常にシャープな演技をする女優だと感じた。
音楽はヴィシャール・シェーカル。ダンスシーンはストーリーに巧みに組み込まれており、問題の「Bharat Mata Ki Jai」も前半の盛り上がりにうまく使われていた。アイテムナンバー「Imported
Kamariya」ですらもアイテムナンバーであることを感じさせない挿入の仕方であった。この2曲は圧倒的なパワーを持っているが、サントラCDに収録されている他の曲は並以下の出来だ。
撮影はマハーラーシュトラ州のラートゥールとバーラーマティーで行われたようだ。インド地方都市の典型的な景色がストーリーをさらに深めていた。
「Shanghai」は、ヒンディー語映画界の牽引役ディバーカル・バナルジー監督の最新作。そのメッセージは「インド」が「バーラト」を無残に呑み込もうとする現状への強い警鐘となっているが、巨大なストーリーの一部を切り取ったような内容であり、プロット自体には特に目新しいところはなく、どちらかというと退屈である。一定の意義は持った映画だが、純粋に娯楽映画として見た場合は弱い。
バードシャー(皇帝)、キング、スーパースター、メガスターなど、スター俳優を形容する仰々しい言葉には事欠かないインド映画各界であるが、そういう名称がいつどのようにして出来上がるのか、一体誰が作っているのか、どういう基準があるのか、実際のところはよく分からないことが多く、自然発生的なものと考えていいだろう。だが、近年少なくともヒンディー語映画界においては、トップスターの「資格」たる具体的な基準が出来つつあるようだ。それが「100カロール・クラブ」である。今日の記事は6月10日付けヒンドゥスターン紙リミックス・ムービー・マジックを大いに参考にしている。
カロール(crore, Cr.)とはインド独自の数単位で「1000万」を表す。英字新聞や英語のニュースにも頻出するため、インド情報を追う際には、「10万」を意味するラーク(lakh,
lac, L.)と併せて、まず押さえておかなければならない単語である。「100カロール」なので10億になる。「100カロール・クラブ」とはつまり、興行収入10億ルピーを突破する大ヒット映画を送り出した、限られた俳優たちのみが入場を許されるカテゴリーである。
100カロール・クラブにはいくつか厳しい条件があるようだ。まずは何より主演映画のコレクションが10億ルピーを突破しなければならない。コレクションと言うのは業界用語で、インド国内の映画館ボックスオフィスにおけるチケットの純粋な売上高のことである。この中にはTV放映権、音楽配給権、フランチャイズ権、海外配給権などの副次的な収入は含まれない。コレクション10億ルピーは大きな壁であり、この壁の突破は単なるヒットでは難しい。次の条件は、マルチスターキャストの映画でないこと。映画の成功如何が主演男優1人の肩に掛かった作品による10億ルピー突破でなければ、100カロール・クラブへの入場は完全には認められない。また、今のところこのクラブは女子禁制となっており、男優のみがこの特権を享受できる。女優はいかなる大ヒット映画に出演しても、その役柄上、脇役や悪役と同様に、その映画の成功に多大な貢献をしたとは見なされない。最後に、繰り返しになるが、興行収入はインド国内のものでなければならない。インド映画には海外市場もあるが、10億ルピーという数字は純粋に国内の興行収入に限られる。
そのような条件に照らし合わせて行くと、現在100カロール・クラブに所属するスターはアーミル・カーン、サルマーン・カーン、シャールク・カーン、アジャイ・デーヴガン、リティク・ローシャンの5人である。それぞれ以下の作品によってクラブ入りを果たした。
■アーミル・カーン
「Ghajini」(2008年) 11.5億ルピー
「3 Idiots」(2009年) 20.2億ルピー
■サルマーン・カーン
「Dabangg」(2010年) 14.3億ルピー
「Ready」(2011年) 12.2億ルピー
「Bodyguard」(2011年) 14.5億ルピー
■シャールク・カーン
「RA.One」(2011年) 11.5億ルピー
「Don 2」(2011年) 11.0億ルピー
■アジャイ・デーヴガン
「Singham」(2011年) 10.0億ルピー
■リティク・ローシャン
「Agneepath」(2012年) 12.2億ルピー
そもそも100カロール・クラブの創始者はアーミル・カーンであった。ヒンディー語映画界において初めて、彼は「Ghajini」によって10億ルピーの壁を越え、金字塔を打ち立てた。さらに翌年、「3
Idiots」によって自身の記録を塗り替えた。「3 Idiots」は今のところヒンディー語映画でもっともヒットした作品である。東アジアを中心とした海外市場でも受けており、国外での収益を含めればその成功の規模はさらに巨大なものとなるだろう。
長年くすぶっていたサルマーン・カーンは近年急激に持ち直し、あれよあれよと言う間にトップスターに返り咲いた。その勢いは100カロール・クラブ的指標にも表れている。「Dabangg」、「Ready」、「Bodyguard」と、10億ルピーを越える大ヒット作品をハットトリックしているのである。この偉業を成し遂げたのは今のところサルマーン・カーンのみだ。
ここ20年くらい「3カーン」の一角として知られて来たばかりか、より正確に言えば「3カーン」の筆頭とみなされて来たシャールク・カーンも、当然のことながら100カロール・クラブの名誉ある会員だ。しかしながら、彼がこのクラブへの入場を許されたのは2011年の後半で、他の2カーン(アーミル・カーンとサルマーン・カーン)に比べたらもっとも遅かった。元々シャールク・カーンの人気は主にNRI(在外インド人)ファン層を基盤としており、国内の興行成績のみを基準とする100カロール・クラブは彼にとって不利だった。彼が「RA.One」に異常なまでのエネルギーを注ぎ込んでいたのも、このクラブ入りを急いでいたからだと考えられる。「RA.One」に続けて主演作「Don
2」も10億ルピーを越えており、この2作品のおかげで何とか面目躍如の形だ。しかしながら、3カーンの中ではもっとも勢いに衰えが見え始めており、最近では暴力沙汰を含むスキャンダルを巻き起こすこともチラホラあって、何かと不安定である。
アジャイ・デーヴガンは、「Golmaal 3」(2010年)で一応10.8億ルピーの興行成績を上げたのだが、この作品はマルチスターキャスト型の映画で、アジャイ・デーヴガンの貢献度がはっきりしなかったため、この作品をもってのクラブ入りは見送られた。しかしながら翌年、ワンマン・アクション映画「Singham」の大ヒットによって今度は文句なしの加入を果たした。彼がここまで躍進するとは、「Hum
Dil De Chuke Sanam」(1999年)の頃には全く想像できなかったことだ。しかし、近年もっとも安定した活躍をしている男優の一人で、100カロール・クラブ入りも不思議ではない。
アジャイに比べたら、リティク・ローシャンのクラブ入りは至極真っ当である。誰もが認める超インド人的なルックスであるし、踊りも世界に出して全く恥ずかしくないばかりか、誇れるレベルだ。固定ファンも多い。「Kaho
Naa... Pyaar Hai」(2000年)での衝撃的デビュー以来、しばらく良作に恵まれなかったのだが、父と叔父とのタッグにより自身の商品価値を着実に上げて来た。「Agneepath」での100カロール・クラブ入りは、その当然の帰結と言えよう。
この5人の他に、アクシャイ・クマールが先月公開されたばかりの「Rowdy Rathore」の大ヒットによってクラブ入りを果たすと見られている。公開後8日間で8億ルピーを稼ぎ出しており、10億ルピーの大台に乗るのも時間の問題である。一応「Housefull
2」(2011年)でも11.2億ルピーを稼いでいるのだが、マルチスターキャスト型映画であるため、保留状態だった。
ちなみに、今のところ女子禁制ではあるものの、100カロール・クラブにもっとも近い位置にいる女優がヴィディヤー・バーランである。「The Dirty
Picture」(2011年)と「Kahaani」(2012年)において、ヒロイン中心の映画に主演し、10億ルピーに届かないまでも、どちらも大ヒットとなっている。最近では女性を主人公にした映画も増えて来ており、しかもヴィディヤーの映画の多くは他の娯楽映画に遜色ないヒットを飛ばしている。彼女が女性初のクラブ入りを果たす日はそんなに遠くないかもしれない。また、主演男優の100カロール・クラブ入りを助けるラッキー・マスコット的存在の女優としては、カリーナー・カプールの右に出る者はいない。「3
Idiots」、「Bodyguard」、「RA.One」と、100カロール・クラブ入りした3作品に出演し、3カーンとの共演も見事にコンプリートしているからだ。しかし、前述の通り、一般的なヒロイン役ではこのエリート・クラブには入れない。
さて、100カロール・クラブの作品をざっと見ると、南インド映画からのリメイクが多いことに気付くだろう。「Ghajini」、「Ready」、「Bodyguard」、「Singham」と少なくとも4本あり、10億ルピー突破必至と見られる「Rowdy
Rathore」を含めると5本になる。間違いなく現在ヒンディー語映画界でトレンドとなっているのは南インド映画のヒット作リメイクである。また、10億ルピー以上の大ヒットとなった作品のほとんどがアクション主体の映画であることも無視出来ない。よって、ここ数年のキーワードは、「南」と「アクション」の2つに絞られると言って過言ではないだろう。
だが、各映画評で度々言及しているように、僕自身は最近のヒンディー語映画界におけるこのトレンドを必ずしも好ましく思っていない。南インド映画のリメイクには、ヒンディー語映画が時代の流れに合わせて独自に培って来た文化や技術の進歩をリセットしてしまうような、後退的なものを感じてならないのである。脚本、撮影、編集などが雑なことが多く、突発的なダンスと、これ見よがしのアクションと、安易なコメディーを詰め込むことで無理矢理まとめたような作品ばかりだ。それでもヒットしてしまうのは、僕の感覚が既に古くなってしまっているからかもしれない。しかしながら、前々からこの変化――僕がつまらないと感じた映画が大ヒットする現象――の理由について、ひとつの仮説を立てている。
それは、地方都市におけるマルチプレックスの普及である。インドの都市分類には複数あり、Tier I, Tier II, Tier IIIや、A-1,
A, B-1, B-2や、X, Y, Zなど、様々な指標があるが、それらは非常に流動的であり、ここではそれにこだわらない。伝統的に4大都市と呼ばれるデリー、ムンバイー、コールカーター、チェンナイや、IT産業で勃興した2都市バンガロールやハイダラーバードでは既に2000年代前半にマルチプレックスが一般化し、それ以外の大都市であるアハマダーバード、プネー、ジャイプル、スーラト、チャンディーガルなどでも2000年代を通して徐々にマルチプレックスが普及して来ていた。一般に「マルチプレックス層」と言った場合、これら大都市のマルチプレックスで映画を見る観客のことを指していた。都会的で洗練されたオシャレ映画、練り込まれた脚本と優れた演技に立脚した映画、それまで映画祭での上映のみを目的として作られて来たような「映画祭サーキット映画」などが、彼らの支持を見込んで作られるようになり、マルチプレックスで上映されて、しかも一定の興行成績を上げた。それが大きなトレンドとなっていたのが2000年代のヒンディー語映画シーンであった。
しかし、2010年前後になると、さらにその下のランクに位置づけられる地方新興都市や中規模都市でもマルチプレックスが登場し、地元民の映画文化に大きな変化がもたらされたと予想される。例えばインド最大手のマルチプレックス・チェーンPVRは現在、NCR(デリー、グルガーオン、ファリーダーバード、ガーズィヤーバード)、ムンバイー、コールカーター、チェンナイ、バンガロール、ハイダラーバードに加え、ラージャスターン州のウダイプル、グジャラート州のアハマダーバードとヴァドーダラーとスーラト、ウッタル・プラデーシュ州のラクナウーとイラーハーバード、マハーラーシュトラ州のアウランガーバードとラートゥールとナーンデード、マディヤ・プラデーシュ州のインダウルとウッジャイン、チャッティースガル州のラーイプル、パンジャーブ州のジャーランダルとルディヤーナー、そしてチャンディーガル準州にチェーンを持っている。地方限定のマルチプレックス・チェーンも各地にある。ここ数年、ちょっと地方都市まで足を伸ばすと、こんな田舎にもマルチプレックスが、と驚くことが多い。マルチプレックスではないにしても、昔ながらの単館がリノベーションされて、マルチプレックスと遜色ない最新設備の整った映画館に生まれ変わることも少なくない。それによって、「マルチプレックス文化」「マルチプレックス映画」という言葉も再定義が必要となって来ているように思われる。
一般に「マルチプレックス映画」と言った場合、4大都市を中心とした大都市在住の中産階級以上の観客が好んで見る映画のことを指し、彼らの支持を受けることで発展して来た新しいインド映画の一連の波を「マルチプレックス文化」と呼んでいた。しかしながら、地方都市にまでマルチプレックスが進出することで、もはやマルチプレックスで映画を見るのは大都市在住の富裕層に限定されなくなっていると考えられる。そして、彼らの趣向は、必ずしも都市在住層とは均一ではなく、昔ながらのマサーラー映画を好む層が一定数根強く存在すると考えられる。また、これまで地方の映画館ではリールの調達などの問題で最新映画上映には高いハードルがあり、古い映画しかやっていないことが多かった。よって、観客の動員にも限界があった。しかし、マルチプレックスの普及や映画館のリノベーションによって、映画のデータを衛星からダウンロードするデジタルシネマが導入され、容易に最新映画を上映することが可能となり、地方の観客層も映画館で最新映画を楽しむようになった。これらの「地方マルチプレックス層」が、「Ghajini」や「Dabangg」をはじめとしたアクション映画の大ヒットを力強く下支えしているのではないかと考えられる。その証拠に、最近のヒット映画の多くが、大都市ではなく、地方都市を舞台としている。これは、このトレンドを敏感に感じ取った映画プロダクションの巧妙なマーケティング戦略であろう。
2011年には少なくとも6本の映画が国内市場において10億ルピー以上のコレクションに成功している。2008年の年末に「Ghajini」が登場するまで、10億ルピーの大台は夢物語でしかなかった。それが今では年に数本もその大台を突破しているのである。これは、映画の質がここ数年で突然上がって来たからだとは考えにくい。チケット代の高騰による興行収入の見かけ上の増加もひとつの要因としてあるだろう。だが、これはそれよりもむしろ、マルチプレックスやその他の最新型映画館のインフラが地方にまで整備されて来たことにより、地方から無尽蔵にチケット代を吸い上げることが可能になって生じた数字なのではないかと予想する。今までボックスオフィスを支配していたのは大都市マルチプレックスであった。大都市のマルチプレックスで受ければ、その映画は「ヒット」とされた。だが、徐々にドル箱は無数にある地方新興都市へと移行していると思われる。すると、観客の趣向の平均値も都市在住者好みのものから地方在住者好みのものへと自然に移行する。彼らが好むのは、外国を舞台にしたハリウッド映画的NRI映画や、脚本を楽しむタイプの映画ではなく、もっとコテコテの分かりやすい映画であろう。とにかく楽しめればOKで、細かいことは気にしない。南インド映画的フォーマットは彼らにとってジャックポットだったのだろう。彼らの人口は甚大で、彼らに受ける映画でなければもはやユニバーサル・ヒット(都市と地方を包括する普遍的ヒット作)は不可能である。また、近年インドで急速に経済成長しているのも地方中小都市であり、映画界におけるこのトレンドはそれとも無関係ではないだろう。よって、2010年前後に、ボックスオフィスにおける地方人口の貢献度が急激に高まったことが、10億ルピー映画連発の原動力となり、昨今のヒット映画のトレンドセッターとなっていると考えられる。
そうなると、今後のトレンドも容易に想像出来る。大都市在住の限られた観客層をターゲットにするよりも、地方の巨大な観客層をターゲットにした方が予算を回収し利益を上げやすい構造が生まれており、ヒンディー語映画界も、次のドラスティックな変化があるまでは、主に地方を向いた映画作りを行い続けるであろう。同時に、コレクション源の裾野が広がり続けることで100カロール・クラブも次第にエリート・クラブではなくなって行き、次なる「200カロール・クラブ」、「300カロール・クラブ」が結成されるのも時間の問題だと予想される。
昨日の「Satyamev Jayate」第6話は身体障害者問題であった。インドの国勢調査において身体障害者の人口が統計されるようになったのは非常に遅く、2001年になってからだったこと、公共の場において身体障害者用のインフラが全く整っていないこと、身体障害者は教育の面で多大な困難に直面することなどが指摘されると同時に、身体障害者の子供を積極的に受け容れる学校や企業の様子などがクローズアップされていた。
一番驚いたのは、番組で紹介されていた、インド人の身体障害者に対する考え方である。多くのインド人は、身体障害者は前世で何らかの罪を犯したためにそのような不自由な身体で生まれて来たのだと信じている。そして、身体障害者に施しをしたり、身体障害者救済機関などに寄付をしたりするのは、身体障害者の福祉のためではなく、徳を積んで自身が天国へ行くためであるという話も出て来た。
総合すると、インド人は一般に障害者を冷遇している、障害者にも健常者と同等のチャンスを与えるべきだ、特に障害者の「教育を受ける権利」を尊重すべきだ、という話になっていたと思う。
しかしながら、今回の「Satyamev Jayate」での論点は、僕のインドでの個人的な体験とは異なっていたので、なかなか納得出来ない部分が多かった。
確かに、インドの街中を少し散歩すれば分かるように、インドの公共スペースにおいて身体障害者用のインフラは全く整っていない。そもそも一般の歩行者にとっても優しくないことがほとんどだ。歩道を歩けば急な段差があるし、突然穴が開いていたり大きな石がころがっていたり沼になっていたり、まるでアクションゲームをしているかのような道である。子供が生まれてベビーカーを押すようになって、インドのインフラ事情の悪さはより鮮明に実感出来るようになった。身体的な障害を持った人にとっては、「移動」というもっとも基本的な行為でさえ、一般人の何倍も困難な冒険になることは想像に難くない。この点には、何人も異論を差し挟むことは出来ない。
ただ、デリーに限って言えば、最近ではスロープの設置など、主に車椅子向けのインフラ整備が徐々に進んでいるように感じられる。僕の住むジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)のキャンパスでも、各所にスロープが設置されつつある。しかし、その仕事振りを見ると、一体誰のために作っているのか分からなくなることが少なくない。例えば下の写真をご覧頂きたい。これは僕の寮の近所の光景である。

スロープの入り口に木が
今まで一段高いところにあるショッピング・コンプレックス(左奥の建物)に至るまでには階段しかなかったのだが、つい最近スロープが作られた。しかし、そのスロープの入り口には1本の木がひょっこり飛び出ており、それが邪魔になって、車椅子の人はこのスロープを使って上に行けないだろう。車椅子利用者ばかりか、一般の人にとっても、この木が邪魔過ぎて、わざわざこのスロープを使おうとは思わない。一体何を考えてこのスロープを作ったのだろうか?インドでは万事がこの調子である。
しかし、僕はインド人が身体障害者に対して冷たい態度を取っているとは思えない。僕の体験はむしろ逆である。インド人は身体障害者にとても優しい。優しいばかりか、普通に接する術を自然に身に付けているように感じることが多い。JNUには身体障害者枠があり、クラスに必ず1人は何らかの障害を抱えた学生がいる。目が見えなかったり、手がなかったり、歩けなかったり、障害は様々であるが、普通に学生生活を送っているし、特にいじめられたりとか、逆にものすごく優遇されたりとか、そういうことはない。ごく自然なのである。僕のクラスにも両手がない学生がいた。身体障害者だからと言って水晶のように心が綺麗な善人だとは限らず、普通のインド人学生と同様に、ちゃっかりしているところはちゃっかりした、本当に普通のインド人であった。あるときクラスで教授が何らかの拍子に「○○の人は手を上げなさい」と指示したことがあった。するとその身体障害者の学生の隣に座っていた学生が、「こいつは手がないんだけどどうするんですか?」と冗談混じりに質問した。日本の感覚が抜けなかった僕は顔面蒼白となったが、両手のない彼はあっけらかんと、「いや、足を上げるからいい」と返し、片足を空高く上げていた。もちろん大爆笑だが、こういうやりとりが自然に行われているのである。
また、就職に際しても身体障害者には優遇制度があり、障害を抱えていた彼は同期でも真っ先に就職先を見つけ、現在ではムンバイーの大学でヒンディー語文学を教えている。一般の学生がなかなか就職先を見つけられないでいる中、身体障害者は悠々と就職出来てしまうのである。
こういう状況を目の当たりにしているため、インドでは障害者が才能を十分に発揮できないと主張する今回の「Satyamev Jayate」の内容はうまく消化出来なかった。ただ、番組の中で焦点が当てられていたのは主に初等教育であった。身体障害者の子供が初等教育において一般の学校に入学しようとすると、なかなか入学許可がもらえないという現状が訴えられていた。その段階ではやはり大きな問題のようだ。インドにおいて身体障害者は、様々な偏見から、まともな教育を受けられないことが多いのは確かであろう。だが、親の努力や回りの協力など、何らかの形で初等教育を受けられれば、その後は身体障害者枠を使ってかなりスムーズに人生を歩むことが出来るのではないかと思われる。番組に登場していた足の不自由な青年サーイーも、やはり初等教育で苦労したようだが、その後は工科大学に入学し、インフォシスに就職し、米国留学までしていた。いわゆるエリート・コースである。おまけにスカイダイビングにも挑戦していた。
インドの街中を歩くと、インフラの劣悪さだけでなく、身体障害者の多さも目に付く。乞食をしている人が身体に何らかの障害を抱えていることは多く、一部では彼らは同情を買いやすいようにわざと身体障害になっているのだという話もあるが、それを抜きにしても、インドの街中では普通に身体障害者が目にする。一方で、番組や、6月11日付けザ・ヒンドゥー紙におけるアーミル・カーンのコラムで、インドでの「公式」の障害者率が全人口の2%しかないことの不思議さに疑問が投げ掛けられていた。米国では12%、英国では18%、ドイツでは9%だと言う。これはもちろん国勢調査の落ち度であろう。インドにおいて何らかの障害を抱える人の数はもっと多いはずである。生来の障害である人も多いだろうし、ポリオや事故など、後天的な不幸によって障害を抱えることになった人も多いだろう。足を引きずっていたり、片手がなかったり、盲人用の杖を突いて歩いたり、もっと遺伝子的な病気を抱えていたり、様々であるが、彼らは間違いなく街の風景の一部である。デリーに住んでいる内に、街中に普通に「普通」じゃない人が存在することに、何だか安心感を覚えるようになった。
翻って日本のことを思い出してみると、街中を歩いていても、そんなに身体障害者に出会わないような気がする。かえってそちらの方が異常に思えて来る。番組で主張されていたように、各国における障害者の人口比率はそんなに違わないはずである。インドの方が人口が多いにしても、比率にしたらそこまで違いがあるはずがない。日本では、「障害者」を「障がい者」と言い換えたり、「盲目」「聾唖」「びっこ」などの言葉を使用禁止にしたり、いろいろ変な部分でねちっこい努力をしているが(僕はそういう言葉狩りには全く反対である)、障害者を社会において目に見えない存在にしているのは、インドよりもむしろ日本なのではないかと感じる。
「Satyamev Jayate」は元から、極端な例を出して問題を簡素化してしまうところがあったのだが、テーマが深刻過ぎたために見過ごされて来たように感じる。だが、今回の件については、障害者枠を含めた、障害者だからこそ享受できる特典や、インフラの不足があるからこその現場での助け合いについて触れられていなかったし、迷信深い人々の先入観に対する先入観を強調するあまりに、社会の実態をうまく反映していない、フェアでない内容になっていたのではないかと感じた。
| ◆ |
6月17日(日) Ferrari Ki Sawaari |
◆ |
かつてスポーツ映画はタブーとされて来たヒンディー語映画界であるが、「Lagaan」(2001年)の大ヒットにより、「スポーツ映画」というジャンルを確立できるぐらいスポーツを題材とした映画が出て来た。その中でも「Iqbal」(2005年)や「Chak
De! India」(2007年)などが成功例で、批評家から高い評価を得た「Paan Singh Tomar」(2012年)も十分スポーツを題材とした映画に含められる。お国柄を反映して、やはりクリケットを題材にした映画が多いが、他にもサッカー、ホッケー、ボクシング、陸上競技、モーターレースなど、守備範囲は意外に広い。
6月15日より公開の新作ヒンディー語映画「Ferrari Ki Sawaari」は、題名とは裏腹にクリケット映画の1本である。「マスター・ブラスター」の異名を持つ、インドを代表するクリケット選手サチン・テーンドゥルカルはカーマニアとしても有名だが、彼が所有するフェラーリこそが、この映画の中心となっている。驚くべきことにサチン所有の本物のフェラーリが映画中で使用される。
また、主人公がパールスィー(拝火教徒)一家である点にも注目である。パールスィーはムンバイーに多く、ヒンディー語映画の中心がムンバイーであるためか、またはヒンディー語映画界にパールスィーの映画人が多いためか、ヒンディー語映画にはパールスィーのキャラクターが度々登場する。「Being
Cyrus」(2006年)、「Parzania」(2007年)、「Little Zizou」(2009年)などがパールスィーを主人公とした代表例で、他にも拝火教徒のキャラクターが断片的に登場する映画は少なくない。デリーに住んでいるとパールスィーと出会う機会は皆無に近いので、文化的差異を多少感じる部分である。
監督はラージェーシュ・マプスカル。「Lage Raho Munna Bhai」(2006年)や「3 Idiots」(2009年)でラージクマール・ヒーラーニー監督のアシスタントを務めて来た人物であり、本作で監督デビューとなる。これらはどれも大ヒットとなった作品であり、ヒーラーニー監督はヒンディー語映画界の売れっ子監督の1人だ。彼のDNAを受け継ぐ映画作りが期待される。また、プロデューサーは同2作と同様にヴィドゥ・ヴィノード・チョープラーである。主演はシャルマン・ジョーシー、ボーマン・イーラーニーなど。現在飛ぶ鳥を落とす勢いの女優ヴィディヤー・バーランがアイテムナンバー出演している点も注目である。
題名:Ferrari Ki Sawaari
読み:フェラーリ・キ・サワーリー
意味:フェラーリー乗車
邦題:フェラーリに乗って
監督:ラージェーシュ・マプスカル
制作:ヴィドゥ・ヴィノード・チョープラー
音楽:プリータム
歌詞:スワーナンド・キルキレー、アミターブ・バッチャーチャーリヤ、グル・タークル、サティヤーンシュ・スィン、デェーヴィヤーンシュ・スィン
振付:スタンリー・デスーザ
衣装:シェヘナーズ・ヴァーンヴァッティー
出演:シャルマーン・ジョーシー、ボーマン・イーラーニー、リトヴィク・サホーレー、パレーシュ・ラーワル、ディーパク・シルケー、スィーマー・パーハワー、サティヤディープ・ミシュラー、アーカーシュ・ダバーデー、ニーレーシュ・ディーヴェーカル、ヴィジャイ・ニカム、ヴィディヤー・バーラン(特別出演)
備考:PVRプリヤーで鑑賞、満席。

左からシャルマーン・ジョーシー、リトヴィク・サホーレー、ボーマン・イーラーニー
| あらすじ |
ムンバイー在住の拝火教徒ルスタム(シャルマン・ジョーシー)は、信号無視すると自ら警察のところへ行って罰金を支払うような、馬鹿正直な人物であった。ルスタムの父親デーブー(ボーマン・イーラーニー)は家で1日中テレビを見ていた。妻は既に亡く、息子のカーヨーゼー(リトヴィク・サホーレー)はクリケットに夢中の少年だった。カーヨーゼーはヴィラーヤト(サティヤディープ・ミシュラー)の教えるクリケット塾でクリケットの練習をしていた。カーヨーゼーは誰もが認める才能を持っていたが、デーブーは大のクリケット嫌いだった。
デーブーがクリケットを嫌いになったのは、過去に不幸な事件があったからであった。実はデーブーは将来を有望された若きクリケット選手であった。ディリープという名の親友と共に切磋琢磨していた。しかし2人の内1人しか代表に選抜されないことになったとき、友人から裏切りを受け、チャンスを奪われてしまった。ディリープはインドを代表するクリケット選手となり、引退した現在はボンベイ・クリケット協会の会長を務めていたが、デーブーは無名のまま終わり、家でテレビ三昧の毎日を送っていたのだった。ルスタムもクリケットの才能があったが、デーブーは決して彼にクリケットをさせなかった。カーヨーゼーがクリケットをすることにも反対であった。
ある日カーヨーゼーの通うクリケット塾に英国からスカウトがやって来て、ロンドンの名門ローズ・クリケット・グラウンドで行われるキャンプの参加者を選抜するためのテストを行うとアナウンスする。インド代表のクリケット選手になることを夢見るカーヨーゼーにとってまたとないチャンスだったが、キャンプ参加費用は15万ルピーと高額で、下位中産階級のルスタムにとってすぐに用意できる金額ではなかった。しかしルスタムは息子に夢を実現して欲しいと願っており、応募することを決める。
ルスタムは何とか15万ルピーを工面しようと奔走し出す。しかしどの銀行もルスタムにローンを出そうとしなかった。そこで従業員積立基金(EPF)へ行こうとする。その手続きのために警察署を訪れたところ、そこで偶然ルスタムはEPFに務めるバッブー(スィーマー・パーハワー)と出会う。バッブーは政治家ターティヤー(ヴィジャイ・ニカム)の会計士も務めていたのだが、彼女は大きなトラブルに巻き込まれていた。ターティヤーの息子パーキヤー(ニーレーシュ・ディーヴェーカル)の結婚式パレードにフェラーリを用意すると言ってしまったのだ。ターティヤーもパーキヤーもそのアイデアを気に入るが、後で調べてみたところ、インドでフェラーリを入手するのは難しかった。ルスタムは、サチン・テーンドゥルカルがフェラーリを持っていると教える。ルスタムの父親がかつてクリケット選手だったことを知ったバッブーは、サチンを説得してフェラーリを借りて来るように頼む。その暁には15万ルピーを報酬として支払うことを約束する。馬鹿正直な公務員だったルスタムは、贈り物を受け取ることには大きな躊躇があったが、息子のためにはそれも曲げなければならなそうだった。
しかし、クリケット嫌いの父親にどうやってそんなことを頼べばいいのか、考えあぐねていたところに電話でバッブーがデーブーとその件について話をしてしまう。デーブーは冗談で「サチンのところへ言ってワシの名前を出せば快く貸してくれるだろう。クリケットの絆は強いんだ」と言うが、ルスタムはそれを信じてしまい、サチンの住むマンションを訪れる。偶然にもマンションのガードマンがおらず、ルスタムはサチンの部屋の前まで誰にも止められず行くことが出来た。思い切って呼び鈴を押すと、ドアが少しだけ開き、手が伸びて来て、自動車の鍵の束を渡された。どうやら運転手と間違われたらしい。ルスタムは急いで返そうとするが、ちょうど電話をして来たバッブーからそのままフェラーリに乗って来るように指示され、ルスタムはそのようにしてしまう。マンションを出るときも全く止められなかった。
ところが、ターティヤーの方では状況が変わっていた。新聞に、息子の結婚式のために多額の浪費をしようとしていると報じられ、豪華な結婚式は止めて、社会福祉事業の一環として集団結婚を執り行い、その中でパーキヤーの結婚も済ますことを考える。パーキヤーはそれに反対する。ターティヤーとパーキヤーで口論が始まるが、バッブーが間に入り両者に妥協させる。結婚式の前日にフェラーリを使ったパレードを行い、結婚式は集団結婚方式にするというものだった。
ルスタムが乗って来たフェラーリは大量の花で飾られ、盛大なパレードが行われる。ルスタムは15万ルピーを受け取り、フェラーリのダッシュボードの中にしまう。そして翌早朝フェラーリをサチンに返しに行く。ところがサチンのマンション周辺は警備が厳重になっており、容易にフェラーリをマンション内に入れることが出来そうになかった。近くに駐車し様子をうかがっていたところ、フェラーリは駐車違反でレッカー移動されることになってしまった。お金はまだダッシュボードの中だった。
一方、サチンの下で働くモーハン(アーカーシュ・ダバーデー)は、フェラーリがないことにショックを受けていた。テーンドゥルカル夫妻はムンバイーにおらず、モーハンが留守番を預かっていたのだが、ルスタムに誤って鍵を渡してしまったのは彼だった。また、ルスタムがマンションを訪れた際に警備をしていた警備員(ディーパク・シルケー)も大きな責任を負っていた。2人はフェラーリ盗難を警察には報告せず、街中を探し始める。
ルスタムは泥棒をしてしまった上に目的も果たせず、深く落ち込む。デーブーもそのことを知ってルスタムを叱る。だが、ルスタムはカーヨーゼーの夢と才能を理解しない父親の態度に憤り、夜中父親をカーヨーゼーとクリケットで対決させる。年老いて、クリケットから長らく遠ざかっていたと言えど、デーブーの投球は確かだった。ところがデーブーの投げる球は片っ端からカーヨーゼーに打ち返されてしまった。一転してデーブーもカーヨーゼーの才能を認め、15万ルピーを工面することを引き受ける。
翌日は選抜テストの日だった。ルスタムはスタジアムまでカーヨーゼーを送って行く。その間、デーブーはボンベイ・クリケット協会へ行く。そう、かつて自分を裏切ったディリープ・ダルマーディカーリー(パレーシュ・ラーワル)に会いに行ったのだった。ディリープは表面上デーブーを歓待するが、15万ルピーを貸して欲しいと頼まれると急に席を外し、そのまま帰って来なかった。
15万ルピーが用意できそうにないことを知ったルスタムは、サチンのフェラーリが保管されている場所へ行く。そこには野次馬が集まっており、警察官が苦労していた。そこでルスタムは手伝う振りをし、まずはフェラーリを覆うカバーを買って来る。そしてフェラーリにかぶせると同時に車中に入り、ダッシュボードにしまった15万ルピーを取り出す。ところがそのときデーブーもそこに来ていた。デーブーはボンベイ・クリケット協会から派遣されて来た振りをし、レッカー車と共にフェラーリを持ち出すことに成功する。
一方、カーヨーゼーは合格し、ロンドン行きが決定した。ちょうどルスタムも15万ルピーを手に入れたところで、カーヨーゼーは大喜びだった。ところがその夕方ボンベイ・クリケット協会で行われた会議で、テスト合格者リストの中にデーブーの孫の名前を見つけたディリープは、カーヨーゼーの祖父は15万ルピーを支払えないと伝えにやって来たと言って、彼を外そうとする。それを見たヴィラーヤトはルスタムに電話をし、すぐに金を持って協会まで来るように言う。ルスタムはカーヨーゼーを連れ、急いで協会へ向かう。途中ルスタムとすれ違ったデーブーは、フェラーリを積んだままレッカー車でルスタムの後を追う。
協会に着いたルスタムとデーブーはディリープに15万ルピーを見せる。ディリープは「既に決定した」と言って断ろうとするが、選考委員会から反対意見が出たため、カーヨーゼーを選抜者として認めざるを得なくなった。ルスタムとカーヨーゼーはフェラーリに乗って家に帰るが、そこではパーキヤーが待っていた。
彼は結婚式前日にフェラーリに乗ってパレードをした訳だが、フェラーリを隙間なく花で飾り過ぎたため、フェラーリに乗っていることが分からなくなってしまっていた。怒ったパーキヤーは結婚式当日もフェラーリに乗ると言い出し、ルスタムの家まで来ていたのだった。パーキヤーはルスタムからフェラーリの鍵を奪い、走り去る。その際、止めようとしたデーブーは怪我を負ってしまう。また、カーヨーゼーにはルスタムがサチンからフェラーリを盗んで来たことを知られてしまう。突然の展開の中、ルスタムはカーヨーゼーを家に残し、怪我をした父親を病院に連れて行く。ところが、父親が泥棒をしたことにショックを受けたカーヨーゼーは姿をくらましてしまう。
カーヨーゼーが行方不明になったことを知ったルスタムは、パーキヤーが連れ去ったと考え、結婚式場へ押し掛ける。そこではパーキヤーがフェラーリで乗り付けたところで、ターティヤーと舌戦を繰り広げていた。ルスタムはパーキヤーに馬乗りになるが、パーキヤーはカーヨーゼーの行方など知らなかった。ただ、彼の手下が海の方へ歩いて行ったのを見たと言ったため、ルスタムはカーヨーゼーが自殺したと早とちりしてしまう。集まったメディアの前でルスタムは大泣きする。
ところがカーヨーゼーはヴィラーヤトの家に来ていた。テレビでルスタムがカーヨーゼーを探していることを知ったヴィラーヤトはカーヨーゼーを連れて結婚式場まで来る。ルスタムはカーヨーゼーが生きていたことに大喜びする。同時に彼はバッブーに15万ルピーを返す。また、その場にはモーハンと警備員も来ており、ルスタムは彼らにフェラーリの鍵を返す。
デーブー、ルスタム、カーヨーゼーが家に帰ると、近所の人々が集まっていた。バッブーの提案により彼らはカーヨーゼーのために15万ルピーの寄付金を集めていた。こうしてカーヨーゼーはロンドンへ行けることになった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
派手さには欠けるものの、「Munna Bhai」シリーズや「3 Idiots」とよく似た雰囲気の心温まる作品だった。インド映画の美しい要素がいっぱい詰まっていたが、中心となっていたのは、正直に正々堂々と生きることの大切さを説くメッセージである。何らかの問題に直面した際、インドの社会ではどうも、神頼みを抜きにすれば、頭を使って切り抜けることが奨励されているところがあり、それはトンチのようなもののときもあるが、方便的な嘘や詐欺に近い方法も意味する。日本では対照的に精神論が強調されるところがあり、この違いは個人的にとても興味深いと思っている。社会の鏡であるインド映画でも、恋愛映画も含めて、主人公が嘘や欺瞞によって問題を解決しようとする姿がよく描かれる。だが、インド映画には「良心」があり、観客を道徳の道へと導く傾向が強い。多くの場合、後悔があり、改心があり、禊があり、そしてエンディングで正しい道への移行や回帰が描かれる。「Ferrari
Ki Sawaari」は正にこのパターンに乗った王道のインド映画である。説教臭いところもあるのだが、このパターンの大きな利点は、後味が非常に良くなるところにある。「Lage
Raho Munna Bhai」も完全にこのパターンの映画であり、ヴィドゥ・ヴィノード・チョープラーがプロデュースする映画の多くは共通してこの方程式を採っている。
もうひとつの軸はクリケットだ。「Lagaan」を見るとクリケットのルールがある程度分かるが、「Ferrari Ki Sawaari」を見るとインド人がいかにクリケットを愛しているかが分かる。クリケットの試合シーンはないのだが、インド人のクリケットへの愛情、そしてクリケット選手への尊敬がひしひしと感じられる映画だった。同時に、「ゲームの裏のゲーム」と揶揄されていた、クリケット管轄団体の汚職にも踏み込んでいたし、金持ちの子供しかクリケット選手になれない構造についても暗示的に触れられており、その点で単なるクリケット映画を越えていた。
しかしながら、この映画でもっとも感動要素が強いのは、祖父、父、息子、3代の男の絆、そして3代を掛けて夢を追い掛ける姿である。献身的に息子の夢を応援する父親はそれだけで微笑ましいし、祖父も最初はクリケットに反対なのだが、最終的には孫の才能を認め、一転して心強い味方となる。彼はかつて自分を裏切った人物に金を無心に行くという屈辱にも耐える。家族の中に1人も女性がいないという異例の家族像ではあるが、インド映画の基本は家族であることを思い出させてくれる作品である。
観客を楽しませるという、娯楽映画として忘れてはいけない点も抜かりなく、作品全体を通してライトなコミックシーンに満ちており、全く退屈しなかった。特にルスタムがフェラーリを持ち出すシーンなどは絶妙である。
主演のシャルマン・ジョーシーは本当にいい役がもらえた。「3 Idiots」で株を上げたシャルマン・ジョーシーだったが、引く手あまたかと思いきやそれほど活躍の場は広がらなかった。ようやく代表作と呼ぶことの出来る主演作が出来た。元々持っていた「いい人」っぽいイメージを膨らませた役作りで、うまく演じ切っていた。
ボーマン・イーラーニーも絶妙な演技だった。特に前半、テレビ三昧のフラストレーション溜まった祖父像は、彼が得意とする「自然なオーバーアクティング」で、本当にうまい演技だった。名前から分かる通りボーマンは拝火教徒で、今回はそのままパールスィー役を演じたことになる。
カーヨーゼーを演じた子役リトヴィク・サホーレーも好演。他に重要な場面でパレーシュ・ラーワルが憎い演技をする。デーブーとディリープの再会シーンは、ボーマンとパレーシュの迫真の演技がぶつかり合う、この映画のクライマックスのひとつである。その他のキャストについてはあまり馴染みのない顔ぶれだったのだが、おそらくマラーティー語映画や演劇をフィールドとする俳優であろう。特にインド版「オバタリアン」と形容しても差し支えないであろうスィーマー・パーハワーの存在感は圧倒的であった。
音楽はプリータム。そのままクリケット応援歌として使えそうな「Mara Re」が劇中で3回使われていた他、ヴィディヤー・バーランをアイテムガールとして迎えたバーラート(結婚式パレード)曲「Mala
Jau De」が強烈である。一応ヒロイン女優なのだが、まるで本物の場末ダンサーのような雰囲気を醸し出しているのが凄い。ここのところ彼女の主演作は当たりに当たっているが、アイテムガール出演のみのこの作品にも幸運を呼び込みそうだ。
「Ferrari Ki Sawaari」は、「Munna Bhai」シリーズや「3 Idiots」が好きな人なら誰でも楽しめる作品だ。クリケットが中心的なテーマであるが、クリケットの試合シーンはないので、クリケットのルールを知っているか否かはあまり映画の理解に影響しない。だが、サチン・テーンドゥルカルを知っているか否かはかなり影響する。よって、完全に万人向けの映画とは言い切れないのだが、今年ベストの1本と断言できる出来。オススメの映画である。
今週は「Ferrari Ki Sawaari」が意外なヒットとなっているのだが、その裏で非常に気になる映画が公開されていた。最高級映画館PVRディレクターズ・カットで1日1回のみ上映の「Kshay」という映画である。白黒映画というのもユニークながら、ロサンゼルス・インド映画祭やニューヨーク南アジア国際映画祭などで受賞しており、出来も良さそうだった。カラン・ガウル監督は元々サウンド・エンジニアを勉強し、作曲などをしていたようなのだが、今回脚本を書き上げ、ほとんど1人で、4年を掛けて映画を作り上げた。90分ほどの映画で、知名度の高い俳優は全く出演していない。監督のインタビューによれば、強迫観念を映像化した作品だと言う。何かとても惹かれるものがあり、平日でもチケット代が850ルピーもする高級映画館に足を運んだ。
題名:Kshay
読み:クシャイ
意味:破滅、腐敗
邦題:腐敗
監督:カラン・ガウル
制作:カラン・ガウル、シャーン・ヴャース
音楽:カラン・ガウル
出演:ラスィカー・ドゥッガル、アーレーク・サンガル、スディール・ペードネーカル、アーディティヤワルダン・グプター、ニティカー・アーナンド、アスィト・レーディジ、アシュヴィン・バールージャー、スィッダールト・バーティヤー
備考:PVRディレクターズ・カットで鑑賞。

「Kshay」
| あらすじ |
下位中産階級の女性チャーヤー(ラスィカー・ドゥッガル)は、夫のアルヴィンド(アーレーク・サンガル)と共にムンバイーの古びたアパートに住んでいた。アルヴィンドはバープー(スディール・ペードネーカル)の下で建築業に携わっていたが、思うような給料はもらえず、2人は貧しい生活を送っていた。チャーヤーは第一子を流産しており、医者によればもう子供は出来ないとのことであった。
ある日チャーヤーは道端で、飛んで来た三角形の石によって右頬に切り傷を負う。そのときチャーヤーは偶然若い彫刻家(アーディティヤワルダン・グプター)の作業場に入り、そこに置かれていた未完成のラクシュミー像に魅了されてしまう。値段は1万5千ルピーだと言う。チャーヤーはとりあえず自分の頬を傷付けた三角形の石を持って帰る。
チャーヤーは、同じアパートに住むシュルティー(ニティカー・アーナンド)から、チャーヤーと似た境遇だったガーヤトリーという女性がラクシュミー女神の礼拝を毎日欠かさずにしていたら子供を授かったという話を聞き、何としてでもラクシュミー像を買おうと考え始める。しかし、1万5千ルピーものお金は手元にはなかった。しかもアルヴィンドは建築業の仕事を辞め、友人と衣料品ビジネスを始めてしまう。しばらくまとまったお金は入って来そうになかった。
アルヴィンドはビジネスの関係で1週間ほど家を空け、チャーヤーが留守番することになる。1人になったチャーヤーはますますラクシュミー像への欲求を募らせ、家具や調理器具を売り払ってしまう。それでも全く足りなかった。そこでシュルティーが付けていた金のラクシュミー・ネックレスを騙し取り、売り払ってしまう。8千ルピーほどにはなかったが、まだ足りなかった。チャーヤーの精神は次第に蝕まれて行き、治りかけていた頬の傷を三角形の石で傷付けて傷口を広げてしまう。
帰宅したアルヴィンドは家に何もないのを見て驚く。チャーヤーが未だにラクシュミー像を諦めていないのを知って憤るが、チャーヤーの精神状態がおかしいことに気付き、何としてでもお金を手に入れようと奔走し始める。アルヴィンドはアースィフ(アスィト・レーディジ)から拳銃を借り、バープーから未払いの給料を脅し取ろうとする。ところがバープーに不意を突かれ、アルヴィンドは殺されてしまう。
夫が死んだことでチャーヤーの手元にはアルヴィンドの定期預金が入って来た。そのおかげで1万5千ルピーが揃い、チャーヤーはやっと念願のラクシュミー像を購入する。家具もなく、夫もいないガランドウの部屋の中でチャーヤーはラクシュミー像の前で微笑んでいた。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
子供がおらず、子供を産めない身体になってしまった主婦の女性が、「子供が欲しい」という欲求を募らせる中で、子供を授かるための手段のはずだった未完成のラクシュミー像をいつの間にか目的にしてしまい、強迫観念の中で精神的な腐敗に陥って行く様子を、現実と夢と妄想の入り交じる白黒の映像で追った実験的な作品であった。主人公チャーヤーの執念を特殊効果を交えた様々な方法で映像化しており、精神をえぐられるような映像体験が続く。最後にはチャーヤーはラクシュミー像を手に入れるのだが、そのときには子供を作るのに必要な夫は既に亡かった。それでもチャーヤーはラクシュミー像を手に入れた喜びに不気味な笑みを浮かべているのだった。
夢や妄想の映像も多いのだが、現実世界に存在する「物」にも、チャーヤーの精神状態が象徴されたり反映されたりしていた。例えばチャーヤーは未完成・不完全なものに異常な執着を示す。未完成のラクシュミー像や黒ずんでしまったラクシュミー像ペンダントなどである。これは、子供を産めないという、女性として不完全な自己の状態の投影だと考えていいだろう。頬の傷もこの不完全さの象徴だと言える。しかしながら、もっともインパクトが強いのは道端で拾った三角形の石である。この石は彼女の頬に大きな傷を付けるのだが、チャーヤーはそれを家に持って帰り、大事に扱う。この石が何を象徴しているのか、それを判断するのは難しい。おそらく見る人によってそれぞれ感じるものがあるだろう。映画の中に出て来る映像や台詞をヒントにするならば、それは完全なものの破片であり、そしてその不安定さが暴力性をもたらしている武器である。チャーヤーが何度も見入るテレビCMの中で、ガラスが割れてその三角形の破片が飛び散るものがある。LGのCMである。また、インド神話によると、ドゥルガー女神は悪魔マヒシャーを退治する際に10の武器を使ったのだが、チャーヤーは三角形の石を11番目の武器だと表現していた。それらを考え合わせると、三角形の石もやはり不完全さの象徴である。チャーヤーは、子供を授かることで「完全体」になることを目指していたのだが、それは無理であることも心の中で自覚しており、無意識の内に自分と同じ「不完全性」に執着するようになったと言える。苦悩するチャーヤーの手の中には必ずこの三角形の石があった。
1人の女性の強迫観念を映像化したこの映画は、はっきり言ってどんなホラー映画よりも怖い。日本のホラー映画が世界に誇る、精神を蝕むような怖さが「Kshay」の中にはあった。おそらくここまで「恐怖」という感情を掘り下げることに成功したインド映画は他にあまりないだろう。そういう意味で非常に重要な映画である。ひとつ批判をするならば、夫アルヴィンドにまでその精神的腐敗が伝染する姿を描写した終盤のシーンは蛇足だと感じた。チャーヤーの心理のみに焦点を当てた方がより引き締まった映画になっただろう。
主演のラスィカー・ドゥッガルはインド映画テレビ学校の卒業生で、今まで「Anwar」(2007年)、「No Smoking」(2007年)、「Tahaan」(2008年)などに出演しているが、それほど名の知られた女優ではない。しかし非常に芯のある演技をしていた。アーレーク・サンガルは舞台俳優としてのキャリアが長いが、「Summer
2007」(2007年)などの映画にも出演している。醸し出す雰囲気がこの映画の雰囲気と完全に一致していなかったように感じたが、悪くない演技であった。
カラン・ガウル監督は元々サウンド・エンジニアだっただけあり、音にも非常に凝った映画だった。この種の低予算映画では音声がおろそかになることが多いと思うのだが、むしろこの映画は視覚情報が白黒のみであることもあってか、音が異常に脳を刺激する。
「Kshay」は白黒、90分、スターキャストなし、限定公開と、突然変異的な作品であるが、「インド映画」というカテゴリーがもはやカテゴリーとして通用しない時代が来ようとしていることを予見させるだけのインパクトを持った映画だ。斬新な試みが随所に見られるが、「もっとも恐ろしいインド映画」と手っ取り早いレッテルを貼っても宣伝しても差し支えないだろう。こういう方向性の映画も今後伸ばして行ってもらいたいものだ。
| ◆ |
6月22日(金) Teri Meri Kahaani |
◆ |
現在ヒンディー語映画界でロマンス映画を作らせたら右の出る者がいない監督はイムティヤーズ・アリーを置いて他にいない。「Jab We Met」(2007年)や「Rockster」(2011年)など、彼はこれまで一貫してロマンス映画しか作っていないが、どの作品も新鮮であり、他の監督のロマンス映画に比べて別格、別次元であり、明らかに突出している。一方、「Hum
Tum」(2004年)や「Fanaa」(2006年)のクナール・コーリー監督も一貫してロマンス映画を作り続けている映画監督である。十分ヒット作を作れる才能を持っているが、いかんせん上にイムティヤーズ・アリー監督がいるため、今のところ「ロマンスの帝王」の称号は与えられずにいる。しかしながら、この2人が切磋琢磨して行けばヒンディー語ロマンス映画はとても面白くなると期待している。
そのクナール・コーリー監督の最新作が本日より公開の「Teri Meri Kahaani」である。主演はシャーヒド・カプールとプリヤンカー・チョープラー。この2人は元々付き合っていたのだが、2011年に破局している。撮影は破局後に開始されており、2人はプライベートを抜きにして、プロフェッショナルに仕事をしたようだ。1910年ラホール、1960年ボンベイ、2012年ロンドンを舞台にし、主演の2人が1人3役を演じるオムニバス形式の恋愛映画で、台湾映画「百年恋歌」(2005年;
英題「Three Times」)との類似も指摘されている。クナール・コーリー監督の巻き返しはあるか?
題名:Teri Meri Kahaani
読み:テーリー・メーリー・カハーニー
意味:君と僕の物語
邦題:君と僕の物語
監督:クナール・コーリー
制作:クナール・コーリー、スニールAルッラー、ヴィッキー・バーハリー
音楽:サージド・ワージド
歌詞:プラスーン・ジョーシー
振付:レーカー・チンニー・プラカーシュ、チンニー・プラカーシュ、アハマド・カーン
衣装:マニーシュ・マロートラー、クナール・ラーワル
出演:シャーヒド・カプール、プリヤンカー・チョープラー、プラーチー・デーサーイー、ネーハー・シャルマー、ヴラジェーシュ・ヒージュリー
備考:PVRプリヤーで鑑賞。

プリヤンカー・チョープラー(左)とシャーヒド・カプール(右)
| あらすじ |
1960年ボンベイ。ボンベイに向かう列車の中で、ミュージシャンを目指すゴーヴィンド(シャーヒド・カプール)は人気女優ルクサール(プリヤンカー・チョープラー)と出会う。ルクサールはゴーヴィンドを気に入り、彼に連絡先を渡す。ボンベイに着いたゴーヴィンドはゲストハウスに宿泊するが、そこに滞在する女性マーヒー(プラーチー・デーサーイー)と出会う。ゴーヴィンドはルクサールと会いながら、マーヒーともデートを重ねる。ところがルクサールとマーヒーは同じ村から一緒にボンベイにやって来た仲だった。ルクサールとマーヒーは同じ男性を好きになってしまったことを知り、ショックを受け、ゴーヴィンドもそれを察知する。
2012年ロンドン。大学で学ぶクリシュ・カプール(シャーヒド・カプール)は誕生日に恋人のミーラー(ネーハー・シャルマー)と破局したばかりで、しかも道端でぶつかった女性ラーダー(プリヤンカー・チョープラー)からスリだと勘違いされ、逮捕されてしまう。ラーダーは間違いに気付き、警察署まで行って彼を解放する。ラーダーは償いとしてクリシュにビールを奢り、それがきっかけで2人は付き合うようになる。ラーダーは別の大学に通っていたが、2人はフェイスブックで密接につながっていた。ミーラーはまだクリシュに未練があり、何とかクリシュと仲直りしようと努力するが、クリシュに新しいガールフレンドが出来たことを知ると、今度はフェイスブックにクリシュの恥ずかしい写真をアップし、復讐を始める。それを知ったクリシュは仕返しにミーラーの恥ずかしい写真をアップする。ラーダーは、クリシュが元恋人と破局した日に自分と付き合い出したことを知った上に、クリシュの元恋人に対する仕打ちに幻滅し、彼の元を去る。
1910年ラホールはサルゴーダー。ジャーヴェード・カードリー(シャーヒド・カプール)は地元で有名な詩人でプレイボーイだった。まだ独立前で、町では英国人官吏が幅を利かせていた。ジャーヴェードは英国婦人とも火遊びをし、それがばれて逃げる途中、偶然アラーダナー(プリヤンカー・チョープラー)と出会う。2人は恋に落ちる。ところで、アラーダナーの父親は独立運動を先導していた。ジャーヴェードは格好付けるため志願し、デモに加わる。ところが英国軍に対峙した途端にジャーヴェードは恐れをなして逃げ出してしまう。アラーダナーは彼の臆病な行動に失望し、扉を閉ざす。自暴自棄となったジャーヴェードは単身英国人官吏を攻撃し、逮捕される。ジャーヴェードは刑務所に入れられるが、彼のことを見直したアラーダナーは頻繁に彼に会いに来るようになる。しかしジャーヴェードは刑務所内でも問題を起こし、3ヶ月間独房に入れられる。やっと釈放されたジャーヴェードがアラーダナーの家を訪れると、アラーダナーは既に結婚した後だった。
ゴーヴィンドはマーヒーに別れを告げ、ボンベイを去る。すると、その列車にルクサールが乗り込んで来る。クリシュはシェークスピア祭のイベントにおいて、観衆の中にミーラーとラーダーがいる中、まずはミーラーに語り掛け、次にラーダーに改めて愛の告白をする。アラーダナーが結婚したことを知ったジャーヴェードは父親の決めた女性と結婚することに決める。しかし結婚の直前に彼は未亡人となったアラーダナーのところに駆け寄り、プロポーズをする。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
軽い。全てが軽い。そして浅い。全てが浅い。オムニバス形式にしてひとつひとつのストーリーに多くの力を注げなかったために、より軽さと浅さが目立ってしまった。残念ながら、クナール・コーリー監督の才能の底が知れてしまった作品と言える。特に3つのストーリーがスリリングに絡み合うこともない。異なる時代、異なる場所において、似たようなキャラクターが似たような人間関係を築くのを繰り返し鑑賞させられるだけの映画であった。似たような構成だがよりB級臭プンプンの「Dangerous
Ishhq」(2012年)の方がよっぽどか面白い作品だった。
1960年ボンベイのストーリーは、まず1960年のボンベイを説得力のある形でスクリーン上に再現する必要があった。確かに当時のボンベイをイメージしたセットが組まれ、おそらくCGなども併用しながら、時代感を出そうと努力していた。また、意図的にコマ数を少なくし、チャップリン映画のようにコミカルな動きになるように工夫してあった。コメディーとしては面白い効果を醸し出していたが、果たしてそれだけでどれだけ笑いを引っ張ることが出来るだろうか?肝心のプロットは全く稚拙で、何の味もない。
2012年ロンドンのストーリーは、PCやスマートフォンを使ったフェイスブックによるコミュニケーションが若者の生活と恋愛模様に浸透している様子が描かれていた。特にスマートフォンによる「いつでもどこでも」のコミュニケーションは新しかった。フェイスブックのみを取り上げ、スマートフォンを導入しなかった「Mujhse
Fraaandship Karoge」(2011年)よりも一歩先に進んでいたと言える。また、元恋人への復讐にもフェイスブックが利用されていた。だが、やはりプロットは浅く、一本調子だった。現代を舞台にしており、ロンドンの大学でロケが行われていたため、セットに関しては問題なかった。
だが、1910年ラホールのストーリーでは再びセットが大きな欠点となっていた。ラホールを再現したセットが組まれ、郊外のシーンではマハーラーシュトラ州ダウラターバードでロケが行われていた。ダウラターバードのシーンは問題ないのだが、セットでの撮影はあらゆる部分がわざとらしく、偽物っぽい雰囲気がプンプンしていた。1910年にラホールで独立運動が盛り上がっていたのかどうかも疑問である。パンジャーブ地方の独立運動の火付け役となったラーラー・ラージパト・ラーイがアクティブになるのは1920年代からであるし、マハートマー・ガーンディーがインドで影響力を持つのも1920年以降だ。時代考証に大いに疑問を感じた。そして言うまでもなくストーリーが薄っぺらかった。
劇中で特に主人公の2人が、異なる時代、異なる場所に輪廻転生して、同じような出会いをし、同じような恋愛を繰り広げているようなことは明示されていなかった。暗示のみに留められていたと言える。しかし、そこで冒険しなかったところがこの映画をもっともつまらなくしていたと感じた。どうせならそれぞれのストーリーに関連性を持たせればインドらしい輪廻転生をテーマにしたロマンス映画になったことだろう。
脚本や演出に難があるために、俳優の演技の評価も不利になる。シャーヒド・カプールは現代的なルックスをしているため、時代が下るごとに浮いた存在になる。それを演技力でカバー出来ていたかと言われれば、必ずしもそうとは言えないだろう。プリヤンカー・チョープラーも各ストーリーでキャラクターを演じ分けていたとは思えない。手を抜いていた訳ではないが、それぞれ2人のベストの演技が見られる映画とは言えないだろう。2人の間のケミストリーも感じなかった。プラーチー・デーサーイーやネーハー・シャルマーなど、サブヒロイン扱いの女優も出ていたが、彼女たちも出番はほとんど与えられていなかった。唯一、1960年の物語で記者を演じたヴラジェーシュ・ヒージュリーがアクセントになっていて良かった。
音楽はサージド・ワージド。テーマ曲的に使われるのが「Mukhtasar」。「様々な出会い、言葉に出来ない物語・・・」という歌詞から始まり、正にこの映画の導入となっている。しかし音使いが古くさい。ここ数年ヒンディー語映画界ではずっとカッワーリーが流行しており、サントラには必ずカッワーリー的楽曲が含まれているが、「Teri
Meri Kahaani」の場合は「Allah Jaane」となる。1910年のストーリーで使用される。「Humse Pyaar Kar Le
Tu」もカッワーリー的であるが、イントロのみで、すぐにパンジャービー・ソングに移行する。「Jabse Mere Dil Ko Uff」は正に1960年代に流行したようなキャバレー・ソングで、1960年のシーンに使われる。一転して「That's
All I Really Wanna Do」は英語歌詞をサビに据えたモダンなラブソングで、予想通り2012年のシーンに使われる。総じて音楽はバラエティーに富んでいて悪くなかったが、それぞれのミュージカルシーンが冗長に感じた。
「Teri Meri Kahaani」はロマンス映画で定評のあるクナール・コーリー監督の最新作であるが、彼の映画の質は作品を重ねるごとに下がって来ているように感じる。少なくともこの映画は彼のキャパシティーを越えていると評さざるを得ない。ここのところ渋めの映画やハードなロマンス映画が続いたため、「Teri
Meri Kahaani」は息抜きになるかと思ったが、残念ながら薄っぺらい映画だった。オムニバス形式の構成もその完成度の低さを助長してしまっている。破局したカップル、シャーヒド・カプールとプリヤンカー・チョープラーのケミストリーも望めない。雨季到来直前のこの時期、納涼にはいいかもしれないが、スキップしても全く構わないだろう。
| ◆ |
6月23日(土) Gangs of Wasseypur (Part 1) |
◆ |
今年、カンヌ国際映画祭と平行して開催される監督週間(Directors' Fortnight)において、インドの娯楽映画として初めて公式上映作品となり話題になった作品がアヌラーグ・カシヤプ監督渾身のギャング映画「Gangs
of Wasseypur」であった。アヌラーグ・カシヤプ監督と言えば、「Black Friday」(2004年)、「Dev. D」(2009年)など、常に斬新な作品を送り出し続けている、ヒンディー語映画界切っての俊英の1人である。ここ数年のヒンディー語映画界は彼を中心にフロンティアを開拓して行っていると言っても過言ではない。彼が最新作に選んだテーマは、現ジャールカンド州ダンバードのギャング抗争。「インドのクエンティン・タランティーノ」と評されて来たラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督の得意とする分野であるが、最近では趣味に走りすぎて低迷するヴァルマー監督に代わって、アヌラーグ・カシヤプ監督の方がタランティーノ監督と比せられるようになってしまった。
「Gangs of Wasseypur」は5時間を越える大長編映画で、カンヌ国際映画祭ではぶっ通しで上映されたらしいが、インドでの商業上映では2部に分割され、パート1とパート2が時間差で公開されることになった。主演はマノージ・パージペーイー、ナワーズッディーン・スィッディーキー、ピーユーシュ・ミシュラーなど。渋い俳優が顔を揃えている。「Paan
Singh Tomar」(2012年)のティグマーンシュ・ドゥーリヤー監督も重要な役で出演している。今年の期待作の1本である。
題名:Gangs of Wasseypur (Part 1)
読み:ギャングス・オブ・ワーセープル
意味:ワーセープルのギャング
邦題:ワーセープルのギャング
監督:アヌラーグ・カシヤプ
制作:アヌラーグ・カシヤプ、スニール・ボーラー
音楽:スネーハー・カンワルカル、ピーユーシュ・ミシュラー
歌詞:ヴァルン・グローヴァー、ピーユーシュ・ミシュラー
衣装:スボード・シュリーワースタヴ
出演:ジャイディープ・アフラーワト、マノージ・パージペーイー、ナワーズッディーン・スィッディーキー、ティグマーンシュ・ドゥーリヤー、リーマー・セーン、リチャー・チャッダー、フーマー・クレーシー、ピーユーシュ・ミシュラー、ズィーシャーン・クレーシー、ヴィピン・シャルマー、シャンカルなど
備考:PVRプリヤーで鑑賞、満席。

マノージ・パージペーイー
| あらすじ |
1941年。炭坑から発展した町ダンバード近くに位置するワーセープル村はイスラーム教徒の村だったが、屠殺業を生業とするクレーシー家が支配しており、クレーシー家とそれ以外のイスラーム教徒に分かれていた。クレーシー家はスルターナー・ダークーという盗賊を輩出していた。スルターナーは英国人に捕まって殺されたとされていたが、実際にはワーセープルに隠れ住んでいた。ワーセープルに住むシャーヒド・カーン(ジャイディープ・アフラーワト)はスルターナー・ダークーになりすまして列車強盗をしていたが、スルターナー・ダークー本人から襲撃を受け、ほとんどの仲間を殺されてしまう。生き残ったシャーヒド・カーンは身重の妻と親友のナースィル(ピーユーシュ・ミシュラー)を連れてダンバードへ流れる。そこで炭坑労働者として生計を立てていたが、妻は出産と同時に死んでしまう。このとき生まれたのがサルダール・カーンであった。
1947年にインドは独立を果たし、英国人所有だったダンバードの炭坑はインドの財閥に譲り渡され、ラーマ―ディール・スィン(ティグマーンシュ・ドゥーリヤー)が請負人として管理することとなった。シャーヒド・カーンはラーマ―ディール・スィンのペヘルワーン(護衛)に抜擢される。だが、ラーマ―ディールはシャーヒドが下克上を狙っていることを知り、彼を暗殺する。危険を察知したナースィルはサルダールを連れて逃げ出す。
大人になったサルダール(マノージ・パージペーイー)はダンバード駅前で客待ちをするジープのドライバーをして生計を立てていた。ラーマ―ディールに父親を殺されたことは忘れておらず、ゆっくりと真綿で首を絞めるように復讐をすることを誓っていた。ラーマ―ディールは請負人から労働組合長を経て政治家になっていたが、サルダールも徐々に力を付けて行き、地元で恐れられるギャングとなって行った。また、サルダールにはナグマー(リチャー・チャッダー)という妻がいたが、それとは別にベンガル人女性ドゥルガー(リーマー・セーン)とも結婚をしていた。サルダールとナグマーの間には4人の息子が、ドゥルガーとの間には1人の息子が生まれていた。
サルダールがシャーヒド・カーンの息子であることに気付いたラーマ―ディールは、サルダールと対抗するためにワーセープルのクレーシー家と手を結ぶ。ワーセープルは現在、スルターナー・ダークーの血を引くスルターンに支配されていた。また、ダンバード市街地の拡大により、ワーセープルはダンバードに取り込まれようとしていた。ラーマ―ディールはスルターンに最新式の拳銃を与え、サルダールを暗殺させようとする。それは失敗に終わるが、このとき長男のダーニシュが怪我を負ってしまう。
サルダールも時代の変遷を感じ取っており、自動拳銃を手に入れようとしていた。彼は次男のファイザル(ナワーズッディーン・スィッディーキー)をヴァーラーナスィーへ送り、銃を密売するヤーダヴから拳銃を購入させる。しかしヤーダヴは警察と密通しており、拳銃を運ぶ途中にファイザルは警察に逮捕され、刑務所に入れられてしまう。刑期を終えて出所したファイザルはヤーダヴに騙されたことを悟り、ヤーダヴから再度購入した銃で彼を殺す。そして警察の目を盗んで購入した拳銃をダンバードまで運ぶ。
一方、ダーニシュはスルターンの妹シャマー・パルヴィーン(アヌリター・ジャー)と恋仲となり、2人は結婚することになった。ラーマ―ディール・スィンからサルダール暗殺の任務を受けていたスルターンは妹の結婚に最初から反対だったが、カーン家とクレーシー家の抗争に嫌気が差していたクレーシー家の人々は結婚を押し切ってしまう。また、この結婚式でファイザルはモホスィナー(フーマー・クレーシー)という女性と知り合うことになる。実はファイザルが少年時代からずっと一目惚れしていた女性だった。
スルターンはサルダール暗殺計画を綿密に立てていた。スルターンはサルダールが単独行動している隙を狙って攻撃を仕掛ける。サルダールは為す術もなく殺されてしまう。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
映画の冒頭の時間軸は2004年で、いきなり当時絶大な人気を誇ったテレビドラマ「Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi(なぜなら姑もかつては嫁だったから)」のオープニングが流れる。しかし、その「ファミリードラマ」の世界はすぐに蜂の巣とされ、観客は血で血を洗うリアリスティック・シネマの世界へ連れ去られる。そして時間軸はインド独立前の1941年に巻き戻され、ダンバードやワーセープルの成り立ちから語られ始める。パート1では1980年代までが描写された。おそらくパート2で2004年までが語られるのだろう。
この映画の面白いところは、旧ビハール州(現ジャールカンド州)と西ベンガル州の狭間に位置する地方都市ダンバードとその近隣の村ワーセープルが、時代の変遷と共に徐々に発展して行く中で、登場人物も年を重ね、職を変え、成長して行くことである。インド独立後、炭坑のコントラクター(請負人)となったラーマ―ディール・スィンは、労働者を組織して政治的な力を蓄え、政治家に転身し、ダンバードを支配する。一方、ワーセープルから追放され、ダンバードで炭鉱労働者として生計を立てていた父親を持つサルダール・カーンは、ダンバード駅前で客待ちをするジープ運転手から身を立て、スクラップ工場や漁業などで儲ける一方、刃物、爆薬、銃器の力を借りて、ダンバードのアンダーワールドを支配するようになる。アンダーワールドとつながる政治家の台頭と、アンダーワールドを支配し政治にも影響力を及ぼすマフィアの台頭が順を追って描かれており、興味深い。また、サルダール・カーンにとってラーマ―ディール・スィンは父親の仇であったが、同様に父親の代からの仇敵であるワーセープルのクレーシー家ともライバル関係にあった。このようにサルダール・カーンは二方面に敵を抱えていた訳だが、ムンバイーのギャング抗争に比べるとどこか牧歌的な側面もあり、この3者が全面戦争をすることはない。お互いにつばぜり合いを繰り返しながら、勢力争いをしている感じである。
また、劇中に登場する小道具からも時代の変遷が分かる。サルダール・カーンの武器はナイフから始まり、爆弾、カッター(国産の低品質拳銃)へと移行し、外国製の自動拳銃に行き着く。それ以外にも、掃除機、冷蔵庫、圧力釜などがさりげなく登場し、観客は自然にストーリーが現代に近付いていることを実感する。70年代にはダンバードの炭坑は国有化され、エマージェンシー(非常事態宣言)があり、80年代にはアミターブ・バッチャンの大フィーバーにもさらりと触れられる。
そのような背景の中で、サルダール・カーン、ラーマ―ディール・スィン、スルターンを中心にストーリーが進行する。思わず目を覆ってしまうような凄惨な暴力シーンがあったり、罵詈雑言を含んだかなり際どい台詞が続いたりするのだが、絶妙な間と粋な台詞が織り成すコミカルなシーンも所々にあったりして、退屈しない。特にこの一見重厚で乾燥したドラマの中において、恋愛シーンが意外に秀逸で、サルダール・カーンがドゥルガーを口説くシーン、ファイザルがモホスィナーの手を握るシーンなど、微笑ましい。まるで「マハーバーラタ」のように無数の登場人物が登場するのだが、その多くが短い登場シーンながら個性を放っており、アヌラーグ・カシヤプ監督の才能が遺憾なく発揮されている。
ただ、まだ前半しか見ていないので、総合的な評価はパート2を見てからにしたい。
パート1はマノージ・パージペーイー演じるサルダール・カーンの物語だと言い切っていいだろう。個性派男優のマノージ・パージペーイーは最近「Raajneeti」(2010年)や「Aarakshan」(2011年)などで悪役を好演して来たが、この「Gangs
of Wasseypur」で晴れて主演を得ており、その演技はそれらすらも色褪せて見えてしまうほどの強烈なものであった。そして台詞回しが絶妙にうまい。かなりアドリブが入っていると思うが、サルダール・カーンというキャラクターを、単なるギャングではなく、人間味溢れる人物として提示することに成功していたのは、大部分が彼のその自由な演技に依っていると言っていい。文句なくキャリア・ベストの演技である。ただ、パート1の最後で(おそらく)死んでしまったので、パート2での登場シーンは限られると予想される。
おそらくパート2ではナワーズッディーン・スィッディーキー演じるファイザルが主人公となるのだろう。パート1では彼の登場は終盤からだったが、十分に印象を残せていた。ナワーズッディーン・スィッディーキーも渋い演技で知られる男優で、最近になって「Peepli
[Live]」(2010年)や「Kahaani」(2012年)などの演技で一気に注目を浴びるようになった。パート2が楽しみである。
重厚な良作を作る映画監督として名を知られたティグマーンシュ・ドゥーリヤーは今回アヌラーグ・カシヤプ監督に説得されたのか、なんと俳優デビュー。サルダール・カーンの宿敵ラーマ―ディール・スィンを落ち着いた演技で見事に演じ切っていた。サルダールの叔父ナースィルを演じたピーユーシュ・ミシュラーは「Tere
Bin Laden」(2010年)での演技が印象的だが、俳優、作曲家、作詞家、脚本家、歌手と多彩な人物で、「Gangs of Wasseypur」でも名曲「Ik
Bagal」の作詞・作曲・歌を担当している。脇役の中ではもっとも光っていた。ちなみに、サルダールのもう1人の相棒デフィニット・カーンを演じたズィーシャーン・カードリーはワーセープル出身で、この映画の原作を書いた張本人である。
女優陣も男優陣に負けず劣らずパワフルだ。サルダール・カーンの妻ナグマーを演じたリチャー・チャッダーは「Oye Lucky! Lucky Oye!」(2008年)でデビュー。そのときはあまり印象に残っていないのだが、「Gangs
of Wasseypur」での演技は決して忘れられない。周囲から恐れられるサルダールを一喝する度胸を持った肝っ玉母ちゃんで、インド人女性の強さを今までにない筆致で描写した、非常にリアルな役、そして演技だった。サルダールの2番目の妻ドゥルガーを演じたリーマー・セーンは一転してなんと艶めかしいことか。ベンガル人で、「Malamaal
Weekly」(2006年)などヒンディー語映画の出演も過去にあるが、基本的には南インド映画女優である。白い肌、豊満な胸、そして背中。それを嘗めるように眺めるサルダール。しかもかなり直球のベッドシーンまである。「Gangs
of Wasseypur」はA認証(18歳未満閲覧禁止)となっているが、暴力シーンを除けば彼女の存在がA認証の原因となっていると言っていい。だが、欲望をむき出しにしたこの映画には欠かせない存在だ。パート1の最後でサルダールを裏切っており、パート2でも重要な役割を果たすことが期待される。他にモホスィナーを演じたフーマー・クレーシーが第3のヒロインとなっていたが、一部のシーン(ファイザルとの会話)を除くとそれほど目立っていなかった。やはりパート2で重要な役割を果たすのだろうか?
音楽は主にスネーハー・カンワルカル。最近MTVの「Sound Trippin」という番組を持っており、インド各所を巡って音集めをし、曲を作っている。「Oye
Lucky! Lucky Oye!」の音楽監督として名を知られる。ヒンディー語映画界では珍しい女性音楽監督でもある。音楽は「Gangs of
Wasseypur」の長所のひとつで、「Jiya Tu」、「O Womaniya」、「Ik Bagal」など、映画の雰囲気をそのまま音楽にしたような土臭い曲が目白押しだ。中でもスネーハー・カンワルカルの才能が発揮されているのは「Hunter」だ。トリニダード・トバゴのチャトニー・ミュージックをベースに、「僕はハンター、彼女は僕のガンを見たがってる」というナンセンスな歌詞を歌った、英語とヒンディー語混じりの無邪気な曲になっている。トリニダード・トバゴには英領時代にサトウキビ・プランテーション労働者として移民したビハール系移民が多く、カリブの音楽とビハールの言語が混じった音楽が発展している。今回、ビハール地方を舞台にした「Gangs
of Wasseypur」において、トリニダード・トバゴから逆輸入されたメロディーとリズムが使われている。サントラCD中もっとも異色の曲である。
一応ヒンディー語映画の範疇に入るが、言語は極度に写実的である。ただし、映画の舞台となっているダンバードの方言ではなく、ボージプリー方言やマガヒー方言に近い言語となっている。ヒンディー語学習者にとってはかなり聴き取り難易度の高い作品だ。しかもスラングやダブルミーニングが多用されており、さらに深い理解力を要する。しかしこの映画の醍醐味の大部分もその台詞にあり、それが楽しめないとこの映画の魅力は半減してしまうだろう。
「Gangs of Wasseypur」は、俊才アヌラーグ・カシヤプ監督の最新作。今週公開されたのは全編5時間の内の前半のみだが、これだけを切り取っても十分に名作だと言える。マノージ・パージペーイーの演技、リーマー・セーンの背中、スネーハー・カンワルカルの音楽など、見所も多い。インド映画における「ゴッドファーザー」的な不朽の名作として、後世まで記憶されることになるほどの名作になるかもしれない。それほど際立った作品である。パート2が待ち遠しい。
■「Gangs of Wasseypur II」はこちら。
ムンバイーが「マキシマム・シティー」の異名を持つようになったのは、スケートゥ・メヘター著のノンフィクション「Maximum City: Bombay
Lost and Found」(2004年)からであっただろうか。ラージャスターン州の古都は昔からイメージカラーを持っているし――ジャイプル=ピンク・シティー、ジョードプル=ブルー・シティー、ジャイサルメール=ゴールデン・シティーなど――、ドミニク・ラピエールの小説「City
of Joy」の題名がそのままカルカッタ(現コールカーター)の愛称になったり、おそらく新聞などのディベロッパーやメディアの宣伝によってグルガーオンがいつの間にか「ミレニアム・シティー」と呼ばれるようになっていたり、都市の愛称の起源は様々だ。デリーにもいくつか愛称があるが、「シティー・オブ・セブン・シティーズ(7つの都市からなる都市)」がもっとも由緒があるだろうか。ゴードン・リズレー・ハーンの「The
Seven Cities of Delhi」(1906年)がその由来だと考えられている。
さて、本日より公開の「Maximum」は、ムンバイーを舞台にした映画ではあるが、スケートゥ・メヘターの著書を原作とした作品ではない。監督は「Sehar」(2005年)などのカビール・カウシク。ナスィールッディーン・シャーとソーヌー・スードが主演の、渋めの警察映画である。
題名:Maximum
読み:マキシマム
意味:最大
邦題:マキシマム
監督:カビール・カウシク
制作:ウダイ・コーターリー
音楽:アムジャード・ナディーム、ヴィクラム・サーワン
歌詞:シャッビール・アハマド、ラキーブ・アーラム
出演:ナスィールッディーン・シャー、ソーヌー・スード、ネーハー・ドゥーピヤー、ヴィジャイ・パータク、スワーナンド・キルキレー、アミト・サード、モーハン・アガシェー、ラージェーンドラ・グプターなど
備考:DTスター・プロミナード・ヴァサント・クンジで鑑賞。
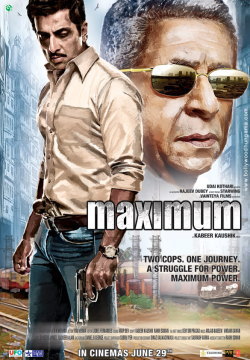
ソーヌー・スード(左)とナスィールッディーン・シャー(右)
| あらすじ |
2003年ムンバイー。ムンバイー警察は、上層部はスボード・スィンとカンナーという2人の警察官僚がライバル関係にあり、現場ではスボードの寵愛を受けるプラタープ・パンディト(ソーヌー・スード)とカンナーと通じるアルン・イマームダール(ナスィールッディーン・シャー)がエンカウンター数(犯罪者を現場で射殺すること)を競い合っていた。プラタープはスプリヤー(ネーハー・ドゥーピヤー)と結婚しており、2人の間にはイーシャーという娘がいた。
ラクナウーからムンバイーにやって来た若きジャーナリスト、アシュヴィン(アミト・サード)は、同じラクナウー出身つながりでプラタープとも親しくなる。また、プラタープはラクナウー出身の政治家ティワーリー(ヴィナイ・パータク)に可愛がられていた。プラタープの父親(ラージェーンドラ・グプター)は大学の英文学教授で、ティワーリーは教え子であった。ティワーリーはムンバイーに住む北インド人政治家として、地元マラーターたちが外部の者に対して持つ排他的な感情を強く感じていたが、党首でマラーターのサーテー州政府内相(モーハン・アガシェー)とは表上親しい関係を保っていた。
プラタープは決して正義漢ではなく、ムンバイー中に様々な人脈を持つ中でアンダーワールドとも通じており、違法行為で私服を肥やしていた。だが、ナンダーという実業家が関わる土地取引に関してマフィアとの癒着を指摘され、裁判に掛けられる。また、ムンバイー警察内でカンナーが実権を握ったことにより、イマームダールの勢力が増大する。プラタープは停職となり、プラタープの右腕だったサードゥも寝返ってイマームダールの腹心となる。プラタープは凋落の一途を辿る。
時は2008年になっていた。プラタープの父親は既に亡くなっていた。だが、長年係争中だった裁判でプラタープは無罪となり、警察に復帰する。また、2008年11月26日にムンバイー同時多発テロが発生し、カンナーが失脚したことで、スボードに実権が移る。プラタープの復権が明らかとなり、イマームダールは焦っていた。そんな中総選挙があり、ティワーリーの所属する党は躍進する。サーテーは中央政府で入閣することになり、ティワーリーが内相に昇格する可能性が強かった。ところが、カンナーやイマームダールと通じ合っていたサーテーは、内相就任の条件として、プラタープの暗殺を提示する。ティワーリーはそれを断ることが出来ず、ナンダー子飼いの殺し屋を使ってプラタープ暗殺を試みる。この襲撃によりスプリヤーが命を落としてしまうが、プラタープは生き残る。憤ったプラタープはナンダーを殺し、ティワーリーの邸宅も襲う。そしてティワーリーを殺す。
プラタープは娘のイーシャーを連れてムンバイーを脱出しようとするが、駅でイマームダールの待ち伏せを受ける。プラタープは腹心バーチー・スィン(スワーナンド・キルキレー)やアシュヴィンにイーシャーを託し、電車に乗せるが、イマームダールとの銃撃戦において相打ちとなってしまう。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
警察を主人公にした映画は星の数ほどあるヒンディー語映画界であるが、警察内の権力抗争を中心に据えたこの作品には一定の目新しさがあった。警察内に2つの派閥があり、それぞれが別のマフィアや実業家と通じている。そしてその派閥の実働部隊となる警官が、実業家の支援を受けて、敵対派閥と通じるマフィアを射殺しまくり、手柄を競い合うのである。つまり、マフィアの抗争や企業間の抗争は現実には警察内の2派閥の抗争でもあることを暗示する内容であった。しかしながら、同様のストーリーの映画には過去にナーナー・パーテーカル主演の名作「Ab
Tak Chhappan」(2004年)があり、最近では「Department」(2012年)があり、全く斬新なストーリーという訳ではない。
「Maximum」のストーリーは主にアシュヴィンの視点から語られる。だが、非常に断片的なストーリーテーリングで、細かい台詞ややり取りを全て丹念に拾い集めて行かなければストーリーに付いて行くのが難しいほどである。それでいて、スクリーンに吸い込まれるようなグリップ力はなく、非常に退屈な展開が続くため、眠気を催してしまう。エンディングも極度に暴力的かつ悲劇的なトーンで救いがない。一言で言えばつまらない映画だった。
唯一光っていたのは、ムンバイーにおける非マラーターの立場に焦点が当てられていたことである。シヴ・セーナーやマハーラーシュトラ再建党(MNS)など、マラーター主義を掲げる政党が根強いムンバイーでは、特にビハール州やウッタル・プラデーシュ州など北インドからの移民に対して、度々排他的な運動が行われる。それは政治の世界でも同様で、ラクナウー出身の政治家ティワーリーは出身地というハンデから州政府の重要なポストにスムーズに就けずにいた。最終的にはティワーリーは夢を叶えるためにプラタープを売ることになる。一方、ジャーナリズムの世界にいたアシュヴィンはマラーティー語を修得し、地元に溶け込もうと努力していた。この部分をもう少し膨らませて行くことが出来たら、より明確なメッセージを持つ映画になっていたことだろう。だが、残念ながら単なる分かりにくい警察内部抗争映画で終わってしまっていた。
ソーヌー・スードは、大ヒット作「Dabangg」(2010年)でサルマーン・カーン演じる悪徳警官チュルブル・パーンデーイに対峙する悪役を演じたのだが、今回はチュルブルと同様にチョビ髭を生やし、自らが悪徳警官となって暴れ回った。警官としての仕事を全うしながらチャッカリ私腹も肥やすという「Maximum」でのプラタープのキャラクターは、確かにチュルブルと共通するものがあるが、性格や言動も映画の味付けも全く異なり、鑑賞中に「Dabangg」を思い出すことはなかった。やはりむしろ「Ab
Tak Chhappan」がかぶっていた。ソーヌー・スードは南インド映画界で主に活躍する男優で、ヒンディー語映画界でもちょくちょく顔を見るが、主演としては作品に恵まれていない。「Maximum」での彼の演技は非常に渋いのだが、正義漢そうに見えて悪いこともしているという「むっつりワル」な役で、ヒンディー語映画界でブレイクしそうなタイプのものではない。
それに対するのはベテラン男優ナスィールッディーン・シャー。彼の老練な演技は、筋骨隆々たるソーヌー・スードの硬派な演技を受け流していて、「柔よく剛を制す」を思い出させた。最後でチープな一騎打ちをしてしまっており、この絶妙なパワーバランスが崩れてしまっていて残念だった。
ヒンディー語映画界の新型コメディアンとして活躍するヴィナイ・パータクは今回政治家役でシリアスな演技を見せていた。元々演技力はあり、とても自然な演技をしていた。最後に主人公プラタープを裏切るのだが、その伏線がなかったために、非常に困難な演技を要求されていたと思う。だが、何とかうまくこなしていたのではないかと思う。
ヒロインのネーハー・ドゥーピヤーにとっては、「Maximum」では大きな活躍の場はなし。しかし、世間から忘れられないためにはこのような作品でも顔を出しておかなければならないだろう。
渋い映画ではあったが、意外にアイテムナンバーが派手で、「Aa Ante Amalapuram」、「Aaja Meri Jaan」など、気合いが入っていた。インド映画なのでダンスシーンをいくつか入れることを要求されるのだろうが、この作品を見る限りでは監督が積極的にアイテムナンバーを挿入したように感じた。
ちなみに、題名となっている「マキシマム」については、劇中に以下のような台詞があり、その種明かしがされていた――「最大の力を手に入れるためには、トップにいるか、それとも黙っているか、どちらかだ」。つまり、第一義的には、「マキシマム」なパワーを巡る、プラタープとイマームダールの抗争を意味すると言っていいだろう。
「Maximum」は、2003年から2008年までのムンバイー警察の内部抗争を描いたシリアスなドラマ。しかしストーリーテーリングに難があり、ストーリーに付いて行くのが難しい。そしてストーリーに何とか付いて行きたいと思わせるほどの魅力もなかった。見なくても構わない映画だ。



