 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
 印度文学館 印度文学館 
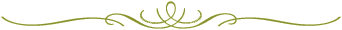

Usha Priyamvada
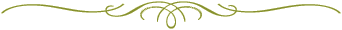
インド人女流作家ウシャー・プリヤンヴァダーの作品。現代人の悲哀を鋭く描いた傑作。定年退職を迎え、長年の単身赴任から家に帰るガジャーダル・バーブーと、彼の家族――妻、息子のアマルとナレーンドラ、娘のバサンティー、そしてアマルの嫁――との間に生まれる軋轢は、父権の危機が叫ばれる日本の家族にも見事に当てはまる。
|
|
|
|
ガジャーダル・バーブーは部屋に集められた荷物に視線を走らせた――2つの箱、バケツ、籠――「この箱は何だ、ガネーシー?」彼は聞いた。
ガネーシーは布団を丸めて縛りながら、誇らしげに、それでいて悲しそうに、そして恥じらいながら言った。「家内の奴がお土産にラッドゥー(インドのお菓子)を、って言って作ったんでさぁ。旦那の好物だから、ってね。あっしらみたいな貧乏人に、他に何ができましょうや?」
家に帰る喜びの中にあって、ガジャーダル・バーブーの心にふと悲しみが生じた。今、慣れ親しんで来た愛情、尊敬、そして日常の仕事との関係が切れようとしているのだ。
「時々はあっしらのこと思い出してください。」ガネーシーは縄を縛りながら言った。
「何か入用があったら手紙をよこしなさい。次のアガハン月(11月〜12月)までには、娘の結婚を挙げさせるんだぞ。」
ガネーシーはターバンの端で涙を拭った。「旦那がいなくなっちまったら、誰があっしらの面倒見てくれるってんですか?旦那がいたら、どんなにか結婚式で心強かったことか。」
ガジャーダル・バーブーは出発の準備を整えて座っていた。鉄道駅の宿舎のこの部屋で、彼は何年の歳月を過ごしたことだろうか。彼の荷物が取り去られたことによって、物寂しく物悲しい雰囲気になっていた。庭に植えていた植木も、全て知り合いにあげてしまい、あちこちで土が無造作に掘り起こされていた。しかし妻や子供たちと一緒に住むことを想像すると、この悲しみも一瞬のさざ波の如く沸き起こって消えてしまうのだった。
ガジャーダル・バーブーは幸せだった。これ以上ない幸せだった。35年の勤務の後、彼は定年になって家に帰るところだった。この間、彼はほとんど単身で過ごしていた。1人で生活しながら、彼はこの瞬間のことを想像して暮らしていた。自分の家族と共に暮らすことができるこの瞬間。この希望を頼りに彼は単身赴任の寂しさを紛らわしていたのだった。世間から見れば彼の人生は成功と言ってよかった。彼は街にマイ・ホームを造り、長男のアマルと長女のカーンティの結婚式を挙げさせた。2人の息子は学校で優秀な成績を収めていた。ガジャーダル・バーブーは仕事のためにいつも田舎の小さな駅に住んでおり、彼の子供たちと妻は勉学に支障がないように街に住んでいた。ガジャーダル・バーブーは非常に愛すべき人柄だった。そして愛に飢えていた。家族と一緒にいるときは、仕事から帰ると子供たちと歓談し、妻を労わることを忘れなかった。それらが失われてしまった後、彼の人生は深い孤独で満たされた。暇なときでも彼は家に住むことができなかった。詩情がなくても、彼には妻の愛情に満ちた思い出が思い起こされてきた。日中、暑くなったときでも、彼女は2時まで火を起こしていた。そして彼が駅から帰ったときには、熱い熱いローティーを作ってくれた。それらを食べ終え、満腹だと言っているにも関わらず、彼女はさらに少し皿によそった。そして愛らしく、食べるように促した。彼が疲れ切って外から帰って来ると、彼の足音だけで彼女は台所のドアまで出てきて、恥ずかしそうに微笑みながら彼を見るのだった。ガジャーダル・バーブーには全ての小さな小さな思い出が思い起こされてきて、そして悲しい気持ちになるのだった。あの愛情と尊敬の中で再び住むときが来るまで、あれからいったいどれだけの月日が経ってしまったのだろう・・・。 +++
帽子を脱いでガジャーダル・バーブーはチャールパーイー(インド式ベッド)の上に置き、靴を脱いだ。すると中から笑い声が聞こえてきた。日曜日だったので、彼の子供たちが集まって朝食をとっていたのだった。ガジャーダル・バーブーのしわがれた顔に思わず笑みがこぼれた。そのまま微笑みながら彼は咳払いせずに中へ入った。見ると、ナレーンドラが腰に手をあてて、昔の映画で見た何かの踊りの真似をしていた。そしてバサンティーは笑い転げて身をよじっていた。アマルの嫁も身体を折り曲げて、顔をヴェールで隠すことも忘れて笑っていた。ガジャーダル・バーブーを見るや否や、ナレーンドラは急いで席に着き、チャーイのコップに口をつけた。嫁も我に返り、急いで頭をヴェールで覆った。ただバサンティーの身体だけが笑いをこらえて揺れていた。
ガジャーダル・バーブーは微笑みながら子供たちを見回して言った。「なあ、ナレーンドラ、何の真似をしてたんだい?」
「何でもありません、お父さん」ナレーンドラは慌てて答えた。
ガジャーダル・バーブーは笑いの輪の中に入りたかったが、彼が訪れたことによって皆、間が抜けたように押し黙ってしまった。それを見て彼は少し悲しい気持ちになった。彼は座りながら言った。「バサンティー、わしにもチャーイをくれないか。お母さんはまだプージャー(お祈り)してるのかい?」
バサンティーは母親の部屋の方を見て、「もうすぐ来ると思うわ」と言って、コップに彼のためにチャーイを注いだ。既にアマルの嫁はこっそりと立ち去ってしまっていた。ナレーンドラもチャーイの最後の一口を飲み干して立ち上がっていた。バサンティーだけが、父親に気を遣って、台所にいる母親を待ちながら座っていた。ガジャーダル・バーブーは一口チャーイを飲んでから言った。「おい、このチャーイ、味が薄いな。」
「じゃあもっと砂糖を入れるわ。」バサンティーは言った。
「まあいい、母さんが来たら飲むことにする。」
しばらくして彼の妻が水壺を持ってやって来た。そして間違ったシュローカ(お経のようなもの)を唱えてトゥルスィー(聖なる木)に水を注いだ。それを見るや否やバサンティーも立ち上がった。妻が来て、ガジャーダル・バーブーを見て言った。「あら、あなた、1人で座ってるの?他の子たちはどこ行ったの?」
ガジャーダル・バーブーは心に何かが突き刺さった気分になった。「それぞれやることがあるんだろう。まだ子供だからな。」
妻は台所に座った。彼女は顔をしかめて汚れたバルタン(鍋)を見て言った。「台所中に汚れたバルタンが散らばってるわ。この家に躾も何もあったもんじゃないわ。」プージャーが終わってすぐ彼女は台所にこもってしまった。そして彼女は使用人を呼んだ。返事がないともう一度大声で呼び、夫の方を見て言った。「嫁が市場に送ったんだわ、きっと。」そして溜息をついて黙ってしまった。
ガジャーダル・バーブーは座ってチャーイと朝食を待っていた。彼は突然ガネーシーのことを思い出した。毎日早朝、乗客が来る前から彼は温かいプーリー(油で揚げたパン)とジャレービー(お菓子の一種)を作っていた。ガジャーダル・バーブーが目を覚まし、準備ができるまでに、ガネーシーは彼のためにジャレービーとチャーイを持って来ていた。チャーイもどんなにかおいしかっただろう、ガラスのコップの上の端まで満たされており、さじ2.5杯の砂糖と濃厚なクリームが入っていた。たとえ乗客がラーニープル(駅の名前)に遅れて来たとしても、ガネーシーはチャーイを届け遅れたことはなかった。彼に何も不平を言うようなことはなかった。
妻の不機嫌な声を聞いて彼は我に返った。彼女は言っていた――こうやって声を張り上げている内に一日が終わってしまう、あれこれ家事をやっつけている内に年を取ってしまった、誰も少しも助けてくれようとしない、などなど・・・。
「嫁は何してるんだ?」ガジャーダル・バーブーは質問した。
「寝そべってますよ。バサンティーは大学へ行ってるからいいとしても。」
ガジャーダル・バーブーは思いついたようにバサンティーを呼んだ。バサンティーは義姉の部屋から出てきた。ガジャーダル・バーバーは言った。「バサンティー、今日からお前が夕食を作ること。朝食はお前の義姉が作ることにする。」
バサンティーは顔をしかめて言った。「お父さん、私、勉強しなきゃ・・・。」
ガジャーダル・バーブーは優しく説得した。「お前は朝勉強しなさい。お前の母さんは年老いてしまって、家事をする元気がないんだよ。お前と、お前の義姉さんが力を合わせて仕事をしなさい。」
バサンティーは黙っていた。彼女が立ち去った後、母親は声を潜めて言った。「勉強なんて言い訳ですよ。勉強してるところなんて見たことないわ。いつもシーラーと遊んでるんだから。あの家には年上の男の子もいるから、毎日あそこで遊ばせるのはいい気がしないわ。止めても言うこと聞きゃしないし。」
軽食をとって、ガジャーダル・バーブーは客室へ行った。家が小さかったため、ガジャーダル・バーブーの部屋は用意されていなかった。ちょうど誰か客人が数日間泊まりに来たときに臨時でこしらえられるように、客室の椅子が壁の方に寄せられ、真ん中にガジャーダル・バーブーのための小さなチャールパーイーが置かれていた。ガジャーダル・バーブーはその部屋に横になって、時々ふと自分が束の間の客になったような気分になっていたのだった。彼は列車が駅にやって来て、しばらく止まった後、再び目的地へ向かって走り去ってしまう様子を思い出していた。
家が小さかったので、客室が彼の部屋となっていた。彼の妻は小部屋を持っていた。しかしその部屋の片側にはアチャール(ピクルス)の壺、ダール(豆)や米の箱やギー(バター)の箱などが積まれており、もう一方には古い毛布や敷物が紐で縛って立てかけてあった。そのそばには家中の冬服が入った鉄の箱が置いてあった。部屋の中央に紐が張ってあり、そこには朝、バサンティーの服が無造作にかけられていた。彼はなるべくその部屋に行かないようにしていた。家の他の部屋はアマルと彼の嫁のものだった。玄関近くにある残りの部屋が客室だった。ガジャーダル・バーブーが来る前、そこにはアマルの嫁の家から送られた3つの竹製椅子のセットが置かれていた。椅子の上には青い座布団と、嫁の手製の刺繍がしてあるクッションが置いてあった。
彼の妻は、何か長い不平不満を言うことがあるといつも、自分の敷物を客室に持って来て敷いていた。その日も彼女は敷物を持ってやって来た。ガジャーダル・バーブーは家計に関する話を始めた。彼は家の状態を気に掛けていたのだった。彼は小さな声で、これから収入が少なくなるから、支出を抑えるように、と言った。
「支出はどれも必要最低限に抑えてます、これ以上何を節約すればいいって言うんですか?お金の勘定ばっかしてる内に年老いてしまったわ、おかげで気に入った衣服や装飾品に使うお金もありゃしない。」
ガジャーダル・バーブーは困惑し、驚いた表情で妻を見た。彼女には何でも話していた。彼の妻がそのとき感じていることを話すことはもっともなことだが、その言葉の中に思いやりの気持ちが全くなかった。それがガジャーダル・バーブーをがっかりさせた。もし彼女が「さあ、これからどうしましょう」とでも言ってくれたら、彼の心配は少なく、満足は大きかっただろう。しかし彼女は家族の全ての問題がガジャーダル・バーブー1人の責任であるかのように不平を漏らしただけだった。
「お前に何が不足してるって言うんだ?家には嫁がいる、息子もいる。お金があるからと言って人は裕福にはなれないんだぞ。」ガジャーダル・バーブーはこう言ったが、言うと同時に、こういう話は妻には理解できないだろうと心の中で感じた。
「ええ、満足してますとも、あの嫁には。今日は台所仕事をしましたけども、何が起こったか見てごらんなさい。」と言って妻は目をつむって寝てしまった。ガジャーダル・バーブーは座りながら妻をしばらく見ていた。これがあの妻だろうか?あの手の柔らかな仕草、その微笑みに彼が全ての人生を懸けた、あの妻だろうか?彼は、あの美しかった人が人生の道のりの中のどこかで失われてしまい、その代わりにまるで見知らぬ女が今ここにいるように感じた。深い眠りに陥った妻の重たい体は非常に醜く、顔は変わり果てていた。ガジャーダル・バーブーはしばらくの間、驚いた表情で妻を見ていたが、やがて横になって天井の方を見つめ始めた。
中で何かが落ちた。彼の妻は飛び上がって座った。「ほら、猫が何かを落としたんでしょう、多分。」そして彼女は中へ走って行った。すぐに戻って来た。彼女の顔は怒りで膨れ上がっていた。「全く、嫁が台所を開けっ放しにしていたから、猫がダールの入った鍋を落としてしまったわ。みんなのための食事だったのに。さあ何を食べさせればいいんでしょうね。」彼女は息をついてから言った。「タルカーリー(野菜カレー)1つと4枚パラーター(パン)を作るのに、一箱ギーを使い果たしてしまったわ。何の痛みも感じないんでしょうね、稼ぎ頭が骨を折って苦労して、ここで食べ物が台無しになっても。私は知ってたわ、家のことは誰がやってもやりこなせるものじゃないって。」
ガジャーダル・バーブーは、妻がさらに何か口にしたら耳が壊れてしまうかと思った。何とか我慢して、寝返りを打って妻に背を向けた。 +++
夕食はバサンティーがわざと一切れも呑み込むこともできないくらいの料理を作った。ガジャーダル・バーブーは黙って食べて席を立ったが、ナレーンドラは皿をどけて立ち上がって言った。「オレはこんなもの食べれない!」
バサンティーは怒って言った。「じゃあ食べなければいいじゃない、誰があんたのために料理するっていうの?」
「お前に料理をするように言ったのは誰だ?」ナレーンドラは叫んだ。
「お父さんよ。」
「父さんは座ってばっかいるくせに何てこと言い出すんだ。」
バサンティーをかばって母親はナレーンドラを諭し、自ら1、2品作って食べさせた。ガジャーダル・バーブーは後で妻に言った。「あんなに大きくなったのに、料理もできないのか、あの娘は?」
「あれ、何でも作れますよ、ただ料理したくないだけです。」妻は答えた。
次の夕方、母親が台所にいるのを見て、服を着替えてバサンティーは外へ出た。すると客室からガジャーダル・バーブーが止めた。「どこへ行くんだ?」
「隣のシーラーの家。」バサンティーは言った。
「そんな必要はない、家で勉強しなさい。」ガジャーダル・バーブーは声を荒げて言った。しばらく不満そうに立っていたが、バサンティーは家の中へ戻った。ガジャーダル・バーブーは毎日夕方散歩をしに出掛けていた。散歩から戻ると妻が言った。「あなた、バサンティーに何言ったの?夕方からすねて寝てるわ。何も食べようとしないのよ。」
ガジャーダル・バーブーは悲しくなった。彼は妻に対して何も答えなかった。彼はバサンティーを早く結婚させようと決意した。その日からバサンティーは父親の目を盗んで過ごし始めた。出掛けるときはいつも裏口から出るようになった。ガジャーダル・バーブーは2、3度妻に尋ねると、彼女は「すねてるんでしょ」と答えた。ガジャーダル・バーブーはさらに腹が立った。女の子というのはなんて性質をしてるんだ、外出を止めただけで父親を無視するのか。さらに追い討ちをかけるように、彼の妻は、アマルが独立して住むことを考えていると知らせた。
「なぜ?」ガジャーダル・バーブーは驚いて質問した。
妻ははっきりと答えなかった。アマルと彼の嫁は多くの不平不満を募らせていた。ガジャーダル・バーブーがいつも客室に寝そべっていたので、誰か客人が来ても座る場所がなかった。彼はアマルに対しても子供のように扱っており、事あるごとに口出しをしていた。嫁が何かをしているときにも、彼はいつもあれにつけこれにつけ注意を与えていた。
「わしが来る前にもこんなことがあったのか?」ガジャーダル・バーブーは聞いた。妻は頭を振って「いいえ」と答えた。以前はアマルが家の主人だった。嫁に口出しする者はいなかった。アマルの友達がよくこの客室に集まっており、みんなでチャーイや軽食を用意して来ていた。バサンティーも好んで輪に加わっていた。
ガジャーダル・バーブーは小声で言った。「アマルに、急ぐ必要はないと言っておけ。」 +++
翌朝、彼が散歩から帰って来ると、客室の彼のチャールパーイーがなくなっているのに気付いた。中に入って質問しようとしたところで、彼の視線が台所に座っている妻に止まった。嫁はどこだ、と言おうとして口を開いたが、思い直して黙った。妻の部屋を覗くと、アチャール、布団や箱の中に彼のチャールパーイーが置いてあった。ガジャーダル・バーブーはコートを脱いでどこかに掛けようと壁を見回した。その後、縄に掛けてあった衣服をどかして、隅にコートをかけた。何も食べずに彼はチャールパーイーの上に横になった。とにもかくにも身体は年老いていた。朝夕遠くまで散歩しに必ず出掛けていたが、歩き疲れてしまっていた。ガジャーダル・バーブーは大きな彼の宿舎を思い出していた。
毎日が同じことの繰り返しの人生だった。朝、乗客が列車から降りてくる。駅はざわめき、知り合いの顔が行きかい、線路の上で列車の車輪が音を立て・・・、全てが彼にとってとろけるような音楽のようだった。急行列車や貨物列車のエンジンの音は、彼の孤独な夜の友だった。セート・ラームジーラールの工場の労働者たちが時々やって来て座っていた。それが彼の友達の輪だった。それが彼の仲間だった。失ってしまったあの生活こそが、掛け替えのない宝物であったことに気が付いた。彼は人生に騙された気分になった。彼は望んだもののひとかけらも手に入らなかった。
横になってこの家の中から聞こえてくるいろんな音を聞いていた。嫁と姑の小競り合い、バケツに滴る水の音、台所のバルタンの擦れ合う音、そして2匹のツバメの会話――そのとき突然彼は決意した。もう家のことについて何も口出ししまい。もし家の主のために家のどこにもチャールパーイーひとつ置く場所すらないのなら、ここに寝ていよう。もしどこか他の場所に置かれたなら、そこへ行こう。もし子供たちの人生の中で父親の必要がないのなら、自分の家でよそ者のごとく寝て過ごそう――その後、ガジャーダル・バーブーは本当に何も言わなくなった。ナレーンドラが小遣いを無心しに来ると、理由も尋ねずに彼にお金をあげた。バサンティーが暗くなった後に隣の家から帰ってこなくても、彼は何も言わなかった。しかし彼がもっとも悲しかったのは、妻ですら彼に心変わりがあったことを指摘しなかったことだ。彼が心の中でどんなにか重荷を背負っていたことか、それを彼女は全く気付かずにいた。むしろ夫が家のことに関して口出ししなくなったため、穏やかに過ごしていた。時々彼女はこんなことを言った。「もうやめてください、横槍を入れるのはやめてください、子供たちも大きくなって、私たちがしていたことをしています。教育を受けさせていますし、結婚もさせます。」
ガジャーダル・バーブーは悲しい表情で妻を見た。彼は、自分は妻と子供にとって単なるお金を稼ぐ者でしかなかったと思った。夫がいるおかげで妻は額にスィンドゥール(既婚の女性が頭に付ける赤い粉)を付けることができ、社会の中でも地位を保つことができる。彼女はその夫の前に1日2回皿を置けば、全ての仕事は完了したと思っている。彼女はギーと砂糖の箱のことで、それだけが彼女の全世界であるかのようにいつまでも愚痴をこぼしている。ガジャーダル・バーブーは彼女の人生の中心ではなかった。彼はもはや娘の結婚についてもやる気をなくしてしまった。何事にも口出ししないと決めた後でも、彼の存在は家族の一員になりえなかった。彼の存在は家の中で、まるで装飾された客室に横たわっていたチャールパーイーのように、気まずく不適切なもののように思われた。彼の全ての幸せは、ひとつの深い悲しみの中に沈んでしまった。
これだけ固く決意したにも関わらず、ガジャーダル・バーブーはある日口出しをしてしまった。妻がいつものように使用人の不平を言っていた。「なんて悪賢いんだろうね、市場で買い物するたびに小金を貯め込んでいるんだよ、食べるだけ食べておいてすぐにどこかへ行ってしまうし。」
ガジャーダル・バーブーも同じように、家の生活様式と支出が全然うまくいっていないと感じていた。大して仕事はないし、家には3人男手がある。誰かが片付けることができるだろう。彼はその日使用人を解雇した。アマルは仕事から帰って来ると、使用人を呼び始めた。アマルの妻が言った。「お父さんが使用人をクビにしちゃったわ。」
「なぜ?」
「節約するためだって。」
この話は全くその通りだったが、嫁はガジャーダル・バーブーに責任があるかのような言い方をした。その日心が重かったのでガジャーダル・バーブーは散歩をしに行かなかった。面倒だったので灯りも灯さなかった。このことを知らずにナレーンドラは母親と話し始めた。「母さん、母さんも父さんに何か言ってよ。1日中座ってばかりだと思ったら召使いをクビにして。もし父さんが、オレが自転車に小麦を乗せて小麦粉を作りにいけばいいと思ってるなら、オレは行かないよ。」
「そうよ、母さん。」バサンティーの声だった。「私は大学へ行って、帰ってきたら家の掃き掃除をしなくちゃいけないでしょう。そんなのいやよ、私は。」
「父さんももう年だよ。」アマルも後に続いた。「黙って寝転がってばっか。それなのに何にでも口出ししたがる。」
妻は皮肉って言った。「しかも何も知らないくせに、お前の嫁を台所に立たせるしね。嫁は15日の食材を5日で使い果たしてしまったよ。」そして嫁が何かを言う前に彼女は台所に行ってしまった。その後、自分の部屋にやって来て灯りをつけると、ガジャーダル・バーブーが横になっているのを見つけて狼狽した。ガジャーダル・バーブーの穏やかな顔から、彼女は彼が何を考えているか推し量ることができなかった。彼は黙って目を閉じて横たわっていた。 +++
ガジャーダル・バーブーは手紙を手にして家の中へやって来た。そして妻を呼んだ。彼女は手を濡らしたまま出てきて、庭で水を切ってそばに立った。ガジャーダル・バーブーは前置きなしに言った。「わしはセート・ラームジーラールの砂糖工場で仕事をすることになったよ。何もせずに座っているよりは、少しでも稼いだ方がいいと思ってな。彼は以前にも私に働くように言って来たんだが、そのときは断ってしまったんだよ。」そして少し口を休めて、まるで消え去る炎が一瞬だけ輝きを放つように、小さな声で言った。「わしは何十年もお前たちと別々に住んだ後、暇をもらって家族と一緒に住もうと思っていたんだが・・・。とにかく、明後日行かなきゃならない。お前も一緒に行くかい?」
「私が?」妻は狼狽して言った。「私が行ったらここはどうなるんですか?これだけいっぱいやることがありますし、年頃の娘もいるし・・・。」
ガジャーダル・バーブーは会話を遮って、残念そうな声で言った。「いいさ、お前はここに住みなさい。わしはただ聞いただけだ。」そして押し黙ってしまった。 +++
ナレーンドラは急いで布団を丸めて結び、リクシャーを呼んだ。ガジャーダル・バーブーの鉄の箱と小さな布団はそこに積み込まれた。朝食のためのラッドゥーとマトリー(お菓子の一種)の入った籠を手に持って、ガジャーダル・バーブーはリクシャーに座り込んだ。一瞬彼は自分の家族に視線を落としたが、すぐに別の方角を向いてしまった。リクシャーは動き出した。
彼が行ってしまった後、皆は家の中に入った。嫁はアマルに聞いた。「映画見に行きましょうよ?」
バサンティーは飛び上がって言った。「兄さん、私も!」
ガジャーダル・バーブーの妻は真っ直ぐ台所に行った。残ったマトリーを金属製の容器に入れ、自分の部屋に持ってきて箱のそばに置いた。そして外へやって来て言った。「これ、ナレーンドラ、お父さんのチャールパーイーを部屋の外に出しなさい。足の踏み場もないわ。」
−完−
|
|
| *** Copyright (C) Arukakat All Rights Reserved *** |



