 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
 印度文学館 印度文学館 
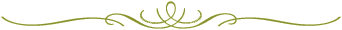

Jainendra Kumar
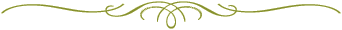
プレームチャンドの後にヒンディー語文学の短編を発展させたのが、ジャイネーンドラ・クマール(1905-1988)。ヴィチャール(思想)を基盤に短編を創作する独自のスタイルを確立した。
|
|
|
|
蓮の花で覆われたこの赤い湖の話、昔々の物語、伝統の語り口で語ろうじゃないか。
昔々、ここから北東の方向にひとつの村があった。村の郊外には廃墟となったシヴァ寺院があったが、村人たちがその寺院へ行くことはなかった。荒れ果てた寺院で、そこには幽霊が出ると専らの噂だった。
そのシヴァ寺院に、どこからやって来たのか、1人のサードゥ(苦行者)が住み着いた。彼はそこに1人で住んでいた。托鉢のために村にやって来ることはあったが、大概の日は寺院にいて、バジャン(賛美歌)を歌ったり礼拝をしたりして過ごしていた。
このような毎日を過ごし、10年の月日が過ぎ去った。もう村にも長いこと行っていなかった。いつしか村の人々がシヴァ寺院へやって来て食べ物を分け与えていくようになっていた。彼は何もしゃべらなかった。感謝の言葉も、祝福の言葉も口に出さなかった。昼には森林や畑へ出掛けた。朝と夕は礼拝に費やしていた。目をつぶることもあれば、戸の外をじっとみつめ、何も言わずに涙を流すこともあった。悲しいのではなかった。彼の心には深い慈愛の情が沸き起こっていたのだ。
彼が以前どこに住んでいたのか、なぜここに来たのか、将来について何を考えているのか、知っている者はいなかった。
このように、さらに5年の月日が過ぎ去った。ある日の朝、信心深い村人たちが彼のところへやって来た。その中の1人が言った。「マハーラージ(目上の人への尊称)、神様はよく見ていらっしゃる、悪行の報いは悪、善行の報いは善ですね。罪を犯した者の身に不幸が降りかかるのを我々は目の当たりにしました。」
その男は具体的な例を挙げて言った。「我々の村の外にハンセン病になった1人の女が住んでます。女は以前売春婦でした。今、女の全身は腐敗してまして、余命幾ばくありません。」
サードゥはその話を無言で聞いていた。人々が去った後も、彼はその話を忘れることができなかった。悪行の報いは悪、善行の報いは善。この言葉が彼の心でグルグルと回転していた。村の郊外で自分の死を待つそのハンセン病の女のことが心から離れなかった。その夜、彼はいつもよりも礼拝に没頭し、いつもより多く泣いた。夜もあまり眠れなかった。彼はそのハンセン病の女を空想し始めた。その女の身体から腐臭が漂ってくる。身体が腐っているのに、誰も彼女の世話をしていない。掘立小屋に横たわった彼女の四方は、ボロ布が散らかっている。小屋の中は汚れきっている。汚物の中、ハンセン病の女は1人で悶々と暮らしている・・・。
空想の中で彼はその女を見ていた。彼の心は沈んでいった。
何とか彼は寝付くことができたが、その女は夢の中にも現れた。すると、どこからか誰かの声が聞こえてきた。「お前はサードゥで、食べ物の心配をする必要がない。お前は苦行者で、人々がお前を崇拝している。しかしお前は私の尊敬は得られない、赤の他人だ。」
彼はまるで誰かに非難されているかのように感じた。さらに声は聞こえてきた。「お前は自分だけがいい報いを得るよう、善行を行っているのだな!お前はただのわがままだ、それ以外の何者でもない。」
朝になって目が覚めても、彼は昨日のことを覚えていた。彼はシヴァ寺院を出て、村の方へ歩き出した。彼は何が何だか分からなかったが、まるで足が自分で勝手に動き出したかのようだった。
ところで、その村には1人の男が住んでいた。その男の名前はマンガルダースと言った。マンガルダースはサードゥや聖者に帰依していた。苦行には偉大な福利があり、聖者たちは神様の大いなる慈悲を受けていると考えていた。聖者たちと交流を保つことにより、あわよくばその福利と慈悲のおこぼれに預かろうとしていた。マンガルダースは賢く、教養があり、器用な男だった。シヴァ寺院に来ては、1人で暮らすそのサードゥの世話をしていた。今にいいことがあるだろう、今にいいことがあるだろう、と考えながら世話をしていた。その日、マンガルダースは夜通し胸騒ぎがして、朝早く目が覚めてしまった。最近はいつもそんな感じだった。市場では価格下落が激しく、商人は大もうけしていた。見る見るうちにある貧乏人は巨万の財産を築き、また見る見るうちにある金持ちは没落した。しかしマンガルダースは勇気がなく、なかなか博打に打って出ることができなかった。その物静かなサードゥにひたすら帰依していたマンガルダースは、朝から彼を拝んで投機をすれば必ずいい結果になるだろうと考えていた。早朝、マンガルダースがシヴァ寺院へ向かうと、なんと道に点々と金貨が落ちているのを見つけた。彼は驚喜し、金貨を拾い集めながらシヴァ寺院まで歩いた。しかしそこにはサードゥはいなかった。マンガルダースは引き返し、道に落ちている金貨に沿って、それらを拾い集めながら歩いて行った。すると、目の前で村の少年が2枚の金貨を拾っていた。マンガルダースは走って行って少年を捕まえた。
「お前、何拾ってるんだ?」
村の少年は答えた。「道に落ちてたから拾っただけだよ。」
マンガルダースはその少年を、「誰かの物をねこばばしていいと思ってるのか?」と叱り付けると同時に、「この金貨の話は誰にもするんじゃないぞ」と口止めした。
このようにマンガルダースは金貨を拾い集めながら、藁で出来た小さな小屋に辿り着いた。しかしその小屋からひどい悪臭がしたため、そこにそのまま立ち止まるのは彼にとって困難だった。彼には、その小屋が金の宝箱に思えてならなかったが、悪臭のため中に入ることはできなかった。彼は、この小屋でハンセン病の売春婦が死に掛けているのを知っていた。
マンガルダースは少し離れた場所に座って、拾い集めた金貨を数えていた。彼は自分の幸運に大喜びしていた。300枚以上の金貨が何の苦労もなく手に入ってしまったのだ。持ち運ぶのが困難なほどの量だった。
すると、売春婦の小屋の中からシヴァ寺院に住むサードゥが出てきた。彼は小屋の四方をきれいに掃除し、離れた場所に穴を掘って、ゴミをその中に捨てた。彼は掃除を終えると、再び小屋の中に入った。しばらくして、サードゥは外に出てきて、自分のシヴァ寺院の方へ歩き出した。
サードゥを追いかけようとしたマンガルダースは驚くべきものを見てしまった。なんと、サードゥが一歩一歩進むごとに、その踏んだ土から金貨が生じるのだ!彼の心は狂喜乱舞したが、彼は口から息すら発しなかった。急いで金貨を拾い集めながらサードゥに気付かれないように後をつけた。途中、彼は誰かが見ていないか不安になった。サードゥがシヴァ寺院まで辿り着くと、彼は自分の家へ戻って、全ての金貨を地面に埋めた。
その後再びサードゥのところへ行って、彼の足元に供え物を捧げて言った。「マハーラージ!どうかこれをお納めください。」
サードゥは愛情こもった目でマンガルダースを見たが、何も言わなかった。
マンガルダースは言った、「マハーラージ、我々は俗世の業に縛られて生きています。私はもうこれ以上この俗世と関わりたくありません。あなたは人里離れて不便な生活を送っています。ですから、私はあなたの世話をしながらここに住みたいと考えています。よろしかったら、私をここに置いて下さい。」
サードゥは何も言わず、まるで何を言っているのか全く理解できないという表情で彼を見つめていた。
実は、マンガルダースは、サードゥの足元から生まれる金貨を誰にも渡したくなかったのだ。
マンガルダースは言った。「マハーラージ、もしあなたの世話をすることができれば、私の人生は実りあるものとなるでしょう。」
サードゥは大笑いし、手を振って言った。「ここは誰の必要もない。」
するとマンガルダースは言った。「そばに藁の小屋を作って、そこに住みます。私は自分の魂を救いたいと思っています。あなたの慈悲があれば、私の魂は浄化されるでしょう。」
サードゥは笑ったが、何も言わなかった。マンガルダースはすぐにそこに掘っ立て小屋を作った。彼は熱心にサードゥの世話をし、四六時中まばたきもせずに彼のそばに立っていた。
サードゥは毎朝必ず、そのハンセン病の売春婦のところへ行き、しばらく滞在してから帰って来ていた。毎日毎日一歩一歩、彼が踏んだ土から金貨が生まれており、マンガルダースはそれらを巧みに拾い集めて行った。そしてひとまとめにしては、家に埋めていた。
ある日のこと、サードゥが歩いていると、後ろから口争いが聞こえた。彼が戻ってみると、そこでマンガルダースと2人の男が口喧嘩をしていた。その道には金貨が落ちていた。
サードゥを見ると、争っていた3人は黙って頭を下げた。
サードゥはそこに立って見ていた。彼は言った、「一体どうしたんじゃ?」
3人の内の誰も答えようとしなかった。サードゥはマンガルダースに、道に落ちている金貨を拾って2人に与えるよう指示した。
マンガルダースはサードゥの言った通り、それらの金貨を拾って2人に与えた。
サードゥが立ち去ると、再び口論の声が聞こえた。さらに激しく言い争っていたように思えたが、サードゥは気にせず売春婦の小屋へ向かった。
サードゥが家に戻ろうとすると、マンガルダースがやって来てサードゥの足元にひれ伏した。「マハーラージ、私はあなたが徒歩で移動していることが苦痛でなりません。私の頭は罪で汚れています。私は自分の肩にあなたを乗せて運びたく思っています。そうすれば、私の身体は浄化されるでしょう。」
サードゥは笑って立っていた。
実は、マンガルダースは金貨を他の誰にも渡したくなかったのだ。彼は無理矢理サードゥを肩に乗せて、他の2人を勝ち誇った表情で見ながら、シヴァ寺院まで運んだ。人々は金貨が欲しかったが、誰しもサードゥが自分の足元から金貨が生じることに気付くことを恐れていた。なぜなら、もしそうなったら、サードゥは金貨を自分のものにしてしまい、金貨は誰の手にも渡らなくなるからだ。このサードゥは愚かにも何も知らない、だからこの男はこんなに質素で慎ましやかで俗世から離れた生活を送れるのだ。
金貨の話は村中に広まってしまった。マンガルダースは焦り始めた。その後、彼はサードゥが外に出るときは必ず肩に乗せて運んでいた。彼はいろんなことを考えていた。数千枚の金貨が彼のものとなったが、彼を肩に乗せて運んでいる内はそれ以上増えなかった。だから彼は苛立っていた。彼は考えた、「サードゥをここからどこか他の場所へ連れて行こう。金貨のことを誰も知らない場所に。しかしどうやって?あの売春婦を見捨ててどこかへ行くとは考えられないし・・・。」
マンガルダースはある日、村人たちの悪口をサードゥに聞かせた。「この村は聖者が住むのに全くふさわしくない場所です、マハーラージ!あなたはどこか他の場所へ行くべきです。あなたの下僕もどこまでも一緒です。」
サードゥはただ笑っていた。彼は何も言わなかった。
マンガルダースは、サードゥが自分の行きたいところへ自分で行くと主張し出すのが怖くて、それ以上強く話すことができなかった。
マンガルダースは思考に思考を重ねた末、あることを思いついた――あの売春婦は、ハンセン病の苦痛を耐え忍んでまでどうして生きているのだろう?シヴァ寺院から売春婦の小屋まで往復すると、人々の視線にさらされることになるし、サードゥをここからあそこまで毎日毎日肩に乗せて運んでいる内に、身体のあちこちが痛くなってしまった。しかも金貨は手に入らない。何の利益もないではないか?
サードゥの必死の看病も虚しく、売春婦の死期は日に日に迫っていた。彼女は実際、死ぬことを望んでいた。彼女は、神様の、またこの世界の人々の許しを望んでいなかった。彼女は自分の罪を自覚しており、この病気はその報いだと考えていた。サードゥが彼女の元を訪れるようになってから、彼女の性格は変わりつつあった。以前の彼女は、誰にでも罵声を浴びせかけ、一日中がなりたててばかりいた。サードゥは、彼女からありとあらゆる罵声を受けながらも、彼女に対して何の悪態もつかなかった。無言で彼女の小屋の掃除をしていた。彼女の汚物を拾って、彼女の汚れた衣服を洗っていた。それを見て、売春婦は最初は全く理解できなかった。数日の内に彼女は、自分の死がすぐに訪れない理由を理解し始めた。自分のためにこの偉大なサードゥが苦労しなければならなかった。彼女は四六時中、神様に対して、自分に死を与えるよう祈っていた。なぜならこのサードゥの真心こもった世話を彼女は耐えることができなかった。彼女は心の中で自分自身を責めていた。
その売春婦が死を望んでいた一方で、マンガルダースは考えた。「あの売春婦が生きている内は、サードゥはこの村から動こうともしないだろう。あの女を殺すしかあるまい。」
こう考えたマンガルダースは、ある夜、こっそり売春婦の小屋までやって来て、眠っている売春婦の首を絞めて彼女をこの世の苦しみから解放してやってしまった。
次の日、マンガルダースの肩に運ばれてサードゥは売春婦の小屋まで来たが、彼女は既に死んでいた。それを見たサードゥはマンガルダースに言った。「衣服をまとめて燃やしなさい。この藁小屋も燃やしなさい、そしてこの女の火葬の準備をしなさい。」
マンガルダースはそんなことしたくなかったが、拒むことはできそうになかった。彼は何とか言い訳を考え出した。「マハーラージ、私はあなたの元に住んでいるため、日銭を稼いでおりません。村へ行って誰かに頼むことにしましょう。」
サードゥはただ笑い、何も言わずに村の方へ歩き出した。
マンガルダースは喜んだ。なぜならこのとき誰も村人はいなかったからだ。サードゥの足元から次々と金貨が生じていた。彼はそれらを全て拾い集めて歩いた。
売春婦の火葬の後、シヴァ寺院に戻って来るや否や、マンガルダースは言った、「マハーラージ、今こそここからどこか他の場所へ移るべきです。この村はあなたにふさわしくありません。」
マンガルダースは考えていた――ここに住んで大金持ちになっても、みんなの嫉妬を買うだけだ。そして噂になるだろう、こんなお金、どこから手に入れたんだって。そうしたらいつかはこのサードゥにも秘密がばれてしまうだろう。そんなことにでもなったら、オレの手元には何も残らなくなる。だからここからどこか他のところへ行って、大邸宅を作らせて、このサードゥを離れにでも住まわせよう。信心深い人々が拝みに来て、賽銭や供え物を置いていくだろう。そうすればたくさん収入が入るだろう。
マンガルダースの家には、妻と母が住んでいた。金貨の話を彼は妻にだけ教え、母親には教えなかった。村人たちは、マンガルダースが他人をサードゥに会わせないようにしているのを見て、彼に敵意を持つようになった。村人たちは、マンガルダースの家に嫌がらせをするようになった。
元々収入が少なかったため、マンガルダースは昔からケチだった。彼は母親をないがしろにしていた。母親はあらゆる仕事をしていたが、食べ物は少ししか与えられなかった。村人たちは、マンガルダースの母親に言った。「お前さんの息子は最近楽して大儲けしてるみたいだよ。もはや大金持ちだってね。」
母親は、村人たちが貧乏人をからかっているだけだと思って言った。「いいかい、あたしたちは貧しいながらも何とか切り盛りして生活してるんだよ。あたしたちのどこにお金なんてあるのさ?貧乏人をからかうもんじゃないよ。」
すると村人たちは言った。「マンガルダースはあんたを騙してるんだよ。あいつは絶対どこかに金を隠してるに違いない。」
その内母親もその話を信じるようになり、嫁と言い争うようになった。結果、家では毎日口論が起きるようになり、平穏な生活はどこかへ消えてしまった。
マンガルダースはもはやこの村を一刻も早く立ち去りたいと考えていた。村人たちは既に敵だった。しかも家ではケンカばかりだった。マンガルダースは、この村を立ち去るようにサードゥを何度も何度も説得した。
サードゥは何も言わなかった。彼は毎日祈りに没頭していた。そして売春婦の魂のために沈黙の行を行っていた。
マンガルダースがしつこくしつこく話しかけて来るので、サードゥは平安に過ごすことができなかった。サードゥは言った。「いったいお前は何を望んでいるのじゃ?」
マンガルダースは言った。「ここの村人はもうあなたを敬っていません。私は、あなたの世話をし始めて以来、村人たちに敵視されるようになってしまいました。だからあなたはこの村を去って、どこか他の場所へ行くべきです。」
「お前はどうして家族をほったらかしにして私を追いかけ回しているのじゃ?」
「マハーラージ、家族は俗世の束縛です。私はあなたの世話をすることにより、幸福を得ることができるのです。」
「お前の家族には誰がいるのじゃ?」
「母親と妻がいます。」
「家族をほったらかしにすべきではない。行って家族の面倒を見なさい。お前がいなかったら、家族の生活はどうなってしまうことか?」
「マハーラージ、何てことおっしゃるんですか?誰が誰の面倒を見るというんです?神様のご慈悲のおかげで我々は皆、生きているのです。神様が我々を守ってくれるというのは、あなたご自身のお教えではなかったのですか?私は、誰かの面倒を見るなんて傲慢なことはできません。私は既に俗世に何の未練もありません。私はあなたの下僕として生きることのみに幸せを感じることができるのです。」
サードゥは笑って言った。「そうかそうか、じゃがな、母親と妻の世話をすることもワシの世話をすることと同じじゃ。分かったら行きなさい。家族と共に暮らしなさい。」
サードゥのこの言葉を聞いて、マンガルダースは目の前が真っ暗になった。彼の心は宮殿が建つほどの野心で溢れていた。ところがその言葉によって彼の夢は音を立てて崩れ出した。マンガルダースはサードゥの足を掴んで言った。「マハーラージ、どうして私に慈悲を投げかけてくれないのですか?」
サードゥは言った。「もし俗世に未練がないのなら、ワシの世話にも未練はないはずじゃ。神様はどこにでもいらっしゃる。お前の家に神様はおらず、この小屋に神様がいると考えているなら、それは大きな間違いじゃ。どうしてもワシの世話をしたいというなら、その理由を教えなさい。」
マンガルダースは言った。「マハーラージ、私は解脱を望んでいます。あなたの世話をすることにより、私の解脱の道が開けるのです。」
「家に住むことによって解脱の道が閉ざされるというのなら、その道を閉ざしているのはお前自身じゃ。道は家でも開かれている。さあ、行きなさい、私のことは構わないでよい。私の世話をこれ以上する必要はない。ワシの肉体は世話を受けるにふさわしくない。この身体は誰かの役に立つために存在しているのじゃ。もしお前の煩悩がワシの身体にあるならば、それはワシの過ちとなる。」
しかしマンガルダースは身を投げ出して手を合わせて言った。「マハーラージ、私を奈落の底へ突き落とさないでください、私は下等な俗物です。私を俗世の悪業の中へ送り返さないで下さい。」
サードゥは笑い出した。「そこまで言うなら、お前の望み通りにしなさい。しかしお前はこれからどんな苦難にも耐えなければならんぞ。」
もしサードゥのそばに住むことで金貨が手に入るなら、マンガルダースは苦難も苦難と思わない男だった。一度でも苦難を乗り越えて多くの財産を築くことができたなら、不幸な星の下に生まれた宿命も全く変わってしまうということを彼は知っていた。この世は金こそが神だ。金こそが全てだ。金があるからこそ妻がいて、兄弟がいて、友人がいて、親戚がいる。もし金がなければ、誰もかまってくれない――こう考えたマンガルダースは言った。「マハーラージ、あなたのそばにいるだけで、私にとって棘すら花に等しくなります。私はこの世で他の何も望んでいません。聖人と共にいるだけで、私は至福なのです。」
マンガルダースの言葉を聞いて、サードゥもこの村から去ることを受け容れた。2人は村から立ち去った。ところが、村から少し歩いたところで、サードゥは体調を崩してしまった。道の途中で、小川が流れている場所があった。サードゥはその小川のそばに座り込んで言った。「マンガルダース、ワシはもう歩けそうもない。帰りたいならお前は帰ってもよい。そうでないなら、ワシのために何とかしてもらわなければならんじゃろう。ワシの身体はもうこれ以上動かん。」
マンガルダースはサードゥの少し後から付いて行って、金貨を拾い集めていた。だから彼は、サードゥを1人残して去ることはできなかった。彼は嬉しそうに言った。「マハーラージ、ここで休んでください。私が全て手配いたします。」
そう言ってマンガルダースは自分の家に戻って、妻に持ち帰った金貨を渡して言った。「あの愚かなサードゥのそばにオレがいる限り、お前はオレの心配をしなくていい。毎日何百ルピーもの金を稼いでいると思ってくれ。今度戻ってきたときは、家がいっぱいになるくらいの金貨を持ち帰るからな。分かったか?そうでなかったら、どこかの町に大邸宅でも造らせて、お前をそこに呼び寄せるさ。そうなったら、2人で王様みたいに悠々と暮らそうじゃないか。」
マンガルダースは息を切らしながらサードゥの元へ戻って来て言った。「マハーラージ、私はあちこちの村々を駈けずり回って来ました。ですが人々には信仰心のかけらもありません。サードゥの偉大さを全く理解していません。どこからも助けを借りることはできませんでした。さあ、ここから6〜7km離れたところにひとつ村があります。そこまで行きましょう。そこなら何でも揃うでしょう。」
サードゥは言った。「ワシはもう歩けない。ワシはこの木の下に住むことにする。お前がもし望むなら、帰っても構わんぞ。」
マンガルダースは心の中で、次の村に辿り着くまでいったいいくつの金貨が手に入るか考えていた。ところがサードゥは木の下に座って眠り込んでしまった。
そこでマンガルダースは村まで行って、サードゥの功徳を説いて回った。マンガルダースの話術は相当なものだった。すぐに村人たちが集まって、小川の岸に小屋を建てた。そして信心深い村人が数人、自ら進んでそこに住み始めた。
サードゥの体調はよくならなかった。彼は何度も何度も吐き、下痢にもなり、食欲もなかった。村人たちは、マンガルダースが語った功徳をそのサードゥに見出すことができなかった。よって村人たちは1人また1人とサードゥから去って行った。
実のところ、マンガルダースは他人をサードゥに近づけたくなかった。なぜならもしサードゥの真の功徳が誰かに知れ渡ってしまったら、マンガルダースは大損することになるからだ。マンガルダースはサードゥの体調がよくなるように看病をし始めた。サードゥが吐いたら、マンガルダースはそれを自分の手で片付けていた。彼はありとあらゆる世話をした。日に日にサードゥは衰弱していき、骸骨のようになってしまった。しかしマンガルダースは希望を捨てず、必死にサードゥの看病をした。
サードゥは弱り切って短気になっていた。小さなことでマンガルダースに厳しい言葉を浴びせかけた。何か失敗があると、ひどく叱り付けた。サードゥは、「ワシの目の前から消えてしまえ!」と言っていた。しかしマンガルダースは全ての罵詈雑言をさらりと受け流していた。何も答えず、ただ再び失敗を繰り返さないようにした。
マンガルダースの必死の看病を見た村人たちは徐々に心を動かされ、いつの間にか彼らはサードゥではなく、マンガルダースを敬うようになった。彼らはマンガルダースを尊敬し、彼にいろいろな供え物を納めるようになった。
自分が尊敬され始めると、マンガルダースは考えた。「これは金儲けの新たな道が開けたな。これ以上サードゥにこだわることもない。」そう考えて、彼はサードゥとは別に自分の小屋を造り、そこに住むようになった。見る見るうちにマンガルダースへの賞賛は四方の村々に伝わり、人々は彼の顔を拝むためにやって来るようになった。
一方、同じ大きさの小屋の中にサードゥは寝ていた。今でもマンガルダースは夜に来ては彼の世話をしていた。なぜならサードゥが起き上がってどこかへ行ってしまうのを恐れていたためだ。しかし最近の彼は、サードゥはもう健康にならないだろうと考えていた。もう手に負えないくらいの病に冒されてしまっただろうと考えていた。
サードゥは次第にほったらかしになり、代わりにマンガルダースの小屋は信心深い村人たちで賑わうようになった。
1人で寝ている内に、サードゥの体調は快方へ向かってきた。
ある日の早朝、数人の参拝者がマンガルダースのところへ来るときに、道に点々と金貨が落ちているのを見つけた。彼らは、これはマンガルダースの奇跡だと考え、彼の前にそれらの金貨を差し出して言った。「マハーラージ、あなたのところへ来る途中にこれらの金貨が落ちていました。あなたのご威光による賜り物に違いありません。これをあなたに捧げます。」
マンガルダースは何も言わなかったが、彼は居ても立ってもいられなくなった。彼は、サードゥがここからどこかへ行ってしまったことを知った。人々が去った後、黙って彼はサードゥを探し始めた。しかし周辺の金貨は拾い尽くされてしまっていて、サードゥを追いかけるのは困難だった。
次の日の朝、彼は村人たちに言った。「昨日、私がマントラ(経文)を唱えていると、手に取った灰が金貨に変わった。ところが、あの病気のサードゥが夜中にこっそり金貨を盗んで逃げ出してしまったようだ。私はあの金貨をお前たちに分け与えようと考えていたのだが・・・。しかしあのサードゥは、お前たちの分け前を盗んで逃げてしまった。奴を捕まえなければなるまい。」
これを聞いた村人たちは、狂ったようにサードゥを探し始めた。後に残った金貨の跡をたどっていけば、サードゥを捕まえることは簡単だった。彼はどこかの木の下で寝ていた。村人たちはサードゥを縛ってマンガルダースの元へ連れて来た。
既にマンガルダースは自分の権威に何の疑いも持っていなかった。2人っきりになってから彼はサードゥに言った。「いいか、サードゥよ、お前は私なしでどこか出歩いたら、どんな不幸が起こるか、すっかり理解しただろう。私はお前に言ったはずだ、お前は私の世話から逃れることはできないって。もしお前が私を無視するなら、私の威光はお前に劣っていないんだぞ。村人たちは私を敬っているが、お前のことは何とも思ってやしないんだ。」
サードゥは言った。「ワシはもう病人ではない。もう元気になった。自分で何でもすることができる。歩き回ることもできる。お前と一緒に住む必要などないじゃろう。それにお前もワシの必要などない。お前は宗教の作法も身に付けた。悟りも開けたように見える。既に人々がお前の世話をするようになっている。お前はもう他人の世話をする必要なんてないじゃろう。」
マンガルダースは自分の座席に座りながら言った。「いや、サードゥよ、私は自分の威信にも名声にも何の興味もない。そんなの皆が無理矢理私に押し付けたものだ。私の心はお前に捧げられているのだ。私は罪の意識に苛まれながらも、お前をここに無理矢理呼び戻した。さあ、もし私と一緒にどこかへ行きたいなら、ここの全ての尊敬を振り切って、今日にでもお前と立ち去る準備はできている。」
サードゥは言った。「私に定住の場などない。どこへ行くにも風任せじゃ。神様の名前のみがワシの全てじゃ。ワシは昔の罪のせいで、ひとときも平安を得られないのじゃ。ワシはお前をこの流浪の人生に引き込むことはできない。お前も知っているじゃろう、食べ物すら時には得られぬこともある。ワシには何の神通力もない。苦しみと悲しみの中でのみ、ワシは安らぐことができる。ワシは何の役にも立たぬ。ほれ、ワシ自身が苦しみであり、ワシ自身が悲しみなのじゃ。お前はどうしてワシのような老いぼれにつまらぬ希望を抱いておるのじゃ、よく考えてみなさい。」
このようにサードゥは、自分の無力さを、延々とマンガルダースに言って聞かせた。
マンガルダースは言った。「サードゥよ!その心配は無用だ。お前もこの世界での金の力を知っているだろう。私はお前に一握りの金を与えよう。金さえあれば、お前は何の困難もないだろう。」
サードゥは驚いて言った。「お前は金を持っているのか?ならどうしてお前はワシと一緒に住んでいるのじゃ?ワシの手元には何もないぞ。」
「私が金を持っているにも関わらず、お前と一緒に住みたい理由は、お前のところに金よりも価値のあるものがあるからだ。」
「もしお前は何か大きなものを信じていて、それを追い求めているなら、どうしてお前は金を抱えているのじゃ?ワシは、お前が金を持って歩き回っていることなど知らなかったぞ。」
「この金貨は村人たちが昨日私に納めたものだ。私は拒むことはできない。この世界の困難の多くは、金がないために起こるのだ。だから私は、何の困難もないのだ。村人たちは皆、私に何かを与えて行く。しかし私はお前を本当に哀れに思う。お前は全く無知な男だ。お前の威光のために私がお前のそばにいたがっていると思ったら大間違いだ。私は宗教的人間だ。私の心は慈悲深いんだ。私はお前を見ると可哀想で仕方ない。お前は無力な男だ。神様は私に、貧乏人と無力な者に慈悲を投げかけるようおっしゃられた。だから私はお前と一緒に住みたいと思っているんだ。お前が病気のときは何かの助けになりたいし、神様のお望み通り、お前のようなか弱い生き物を助けることができて、私は本当に満足している。」
それを聞いて、サードゥはマンガルダースを見直し、感謝すら感じた。
サードゥは言った。「ワシは本当にどうしようもない罪人じゃ。ワシはお前と出会えたことを幸運に思う。ワシは心の中で、お前よりも自分を特別な存在だと思っていた。しかしお前はワシの目を覚ましてくれた。ワシはお前に感謝したい。お前はただ慈悲の情からワシと共にいたことが分かった。これはワシに対するお前の厚意だったのじゃな。今ワシは、お前に、この世界に、そして神様に自分のための慈悲を乞おうと思う。しかしワシの身体は誰かに気遣ってもらうにふさわしくない。ただ行き着くところまで行き着くだけじゃ。いつかは力尽きるべきなのじゃ。神様がその日を決めてくれるじゃろう。だからワシは何の心配もない。ワシはただ流れ流れて放浪するだけじゃ、そしていつか運が巡り合わせたら、お前と再会することもあろう。さあ、ワシを行かせておくれ。」
マンガルダースは言った。「サードゥよ、お前は私の宗教的義務の邪魔しようとしているのか?私は神様から与えられた義務を守っているだけなんだ。私はお前の心配なんかしていない。お前のような罪人は世界にたくさんいる。だが、私はお前に慈悲を投げかけるよう、神様から命令されたんだ。だから私はその命令に背くことはできない。お前の世話をすることが、私の神様に対する奉仕なんだ。私はそれを放り出すことはできない。だから、聞いているか、サードゥよ、もし高潔に生きたいと思うなら、私の許可なく、私の同伴なく、どこかへ行ってはならない。さもなくば、お前も私の力を知っているだろう。ここの村人に少し指図すれば、お前はこの世から消え去ってしまうだろう。」
サードゥはマンガルダースの話を全て理解することができなかったが、ただ彼は神様の言いつけを守りたいだけであり、自分がその邪魔をしてはならないとだけ理解した。そう考えたサードゥはそこに住むようになり、マンガルダースの世話をするようになった。
あるときマンガルダースは、村の若者をこっそり呼んで言った。「いいか、あのサードゥは今や私の弟子になった。彼は非常に熱心な信仰をしている。だから私は彼に祝福を与えた。彼が清い行動をするためどこかへ行くときに、彼の一歩一歩から金貨が生まれるようにしたのだ。信仰の力は偉大なり!この奇跡は苦行の賜物だ!そこでだ、お前にひとつ仕事をしてもらいたい。あのサードゥがどこかへ行くとき、彼の後ろから付いて行って、金貨を拾い集めなさい。サードゥや他人に知られないよう気を付けなさい。つまり、もし彼がこの奇跡に気付いたら、彼は強欲になってしまうだろう。強欲が生じたら、そこで彼の信仰心は消え去ってしまう。だから、弟子の解脱のためにも、あのサードゥは自分の奇跡を自覚しないようにしてやらなければならないのだ。」
その若者の名前はスメールといった。その話を聞いてスメールは感動し、大変喜んだ。スメールはサードゥと共に住み、道に生じた金貨を全て拾い集めた。最初の内、彼は自分のグルジー(師匠=マンガルダース)に全ての金貨を納めていたが、ある日1枚だけ着服した。スメールは考えていた。「お母さんに見せたら、きっと驚くことだろう。そうしたらどんなに愉快だろう。お母さんは『どこから持ってきたの?』って聞くだろう。そうしたら何も答えないでおこう。多分、オレがどこかから盗んできたと考えるだろう。でも黙っていよう。お母さんはまだ、オレが神様に等しいグルジーの弟子になったことを知らないからな。金貨の話も理解できないだろう。」
しかし次第にスメールは、グルジーがケチケチと金貨の計算をしていることに気付いた。マンガルダースはスメールに、「弟子よ、いったいサードゥはどこまで行ったかな、ここから何kmだろう、そうすると何歩歩いたことになるだろう」と聞いて金貨の数を数えていた。その内スメールは、グルジーよりも金貨を重視するようになった。スメールは数枚の金貨を手元に残すようになった。それらを持ち帰って、こっそり水がめの中に隠しておいた。誰にもこのことは話さなかった。
ある日、スメールの妻が水がめの中から荷物を取り出そうとしたとき、金貨が見つかってしまった。これを見て彼女は喜びと共に怒りがこみ上げた。彼女は夕方夫が帰って来るや否やわめき立てた。「あんたはこうやってお金のことを私に黙ってたんだね、『くたくたになるまで働いて、収入はこれっぽっちもない』とか何とか言い訳を並べて、家に金貨を貯め込んでたんだね!」
この話は近所にも伝わってしまった。金貨と聞いて人々は我も我もとスメールの家に集まってきた。スメールが何も言わなかったので、人々は彼が泥棒をしたと理解し、蹴ったり叩いたりし始めた。その内とうとうスメールは口を割った。「オレは泥棒じゃない。グルジーがオレに金貨をくれたんだ。」
これを聞いて、村人たちはマンガルダースの威光をさらに信じるようになった。マンガルダースは質素な生活を送っていた。これほどの財産がありながら、質素な生活をするのは尋常なことではない。真の世捨て人のみがなしうる行為だ。こう考えた村人たちは、聖人マンガルダースをさらに敬うようになった。
一方、あの憐れなサードゥは、森から土を集め、牛の糞を固めて(燃料にする)、食事を作っていた。しかも毎日サードゥとしての日課を怠らなかった。
しかし次第に彼は不思議に思い始めた。どうしてマンガルダースの弟子が自分と一緒に歩いているのだろう?彼は、おそらく自分のやっていることに何か間違いがあって、マンガルダースは慈悲の心から弟子を自分の元へ送っているのだろうと考えた。
しかし、村人たちに秘密がばれてしまって以来、スメールは秘密を守るのが馬鹿馬鹿しくなった。グルジーに対する尊敬も次第にさめて来ていた。だから彼は自分の幼馴染みのチャンダンに秘密を教えてしまった。それ以来、チャンダンもスメールと共にサードゥの後をつけるようになった。今や2人は、拾い集めた金貨の中から、申し訳程度の金貨しかグルジーに渡さず、残りは自分たちのものにしてしまった。
スメールとチャンダンは2人ともそのサードゥを間抜けだと思っていた。しかし毎日毎日こっそりと多くの金貨を拾い集めている内に、2人ともそのサードゥが憐れに思えてきた。ある日、2人は森の中でサードゥを呼び止めて言った。「サードゥさん、さあこれを受け取って。これは全部あんたのものだ。」
サードゥは驚いて立ち止まった。まるで稲妻に打たれたかのようだった。彼は言った。「この金をもらってどうするって言うのじゃ?」
チャンダンは言った。「サードゥさん、オレたちは本当のこと言ってるんだ。これはオレたちのものじゃなくて、あんたのものだよ。」
サードゥは言った。「サードゥをそうやってからかうもんじゃないぞよ。金は心を汚なくするのじゃ。」
チャンダンは言った。「サードゥ、あんたはオレたちを毎日見てただろ?オレたちがいつもあんたの後ろを歩いてたの知ってるだろ?でもなぜだか分かるかい?実は、あんたが足で踏んだ場所から、1枚ずつ金貨が生まれてくるんだ。それが欲しくて、オレたちはあんたの後を追いかけ回してたんだ。たくさんの金貨が集まったよ。でもそれは泥棒みたいなもんだって思えてきてね、あんたのみじめな姿を見て、オレたちは今自分がしたことを恥ずかしく思うよ。さあ、これを持ってってくれ。オレたちは本当のこと言ってるんだ、これはあんたのものだよ。これで自分のみじめな境遇をよくしなよ。あんたはどうしてこんなに大変な苦労をしてるんだい?どうして昼夜を問わずあのグルジーの世話をしてるんだい?」
サードゥは金貨の話を聞き、また目の前の金貨を見て、驚いて立ち尽くしてしまった。彼は何と答えていいか分からなかった。
チャンダンは言った。「サードゥ、あんたはオレたちの話を嘘だと思ってるだろ。でもこれは本当なんだよ。」
しばらくサードゥは黙って立っていた。と、突然地面に突っ伏して、両手で顔を覆って泣き始めた。
スメールとチャンダンはサードゥのこの行動を見て驚いた。何をしたらいいのか、彼らは分からなかった。
サードゥはその後、上を向いて天を仰いで泣きながら祈った。「ああ、神様、あなたは何の罪に対して、私にこのような罰をお与えになったのですか?私の精神と肉体から、いつ金への執着を消し去っていただけるのですか?私は未だに金銭欲から解放されていないのですか?神様、あなたは私に死ねとおっしゃるのですか?そうでないなら、私から金への煩悩を消し去って下さい。」
このように、彼はしばらくの間祈りを捧げていた。そして、チャンダンとスメールと共に引き返した。
チャンダンとスメールが見ると、もはやサードゥの足元から金貨が生じなくなっていた。代わりに、清く正しい心の象徴である、赤い蓮の花が生じるようになった。
マンガルダースの小屋に辿り着くと、スメールはグルジーに1枚も金貨を渡さなかった。スメールは言った。「もうサードゥから金貨が生じなくなりました。」
マンガルダースはそれを聞いて怒り、罵詈雑言を浴びせかけた。チャンダンとスメールは2人とも気を悪くし、グルジーに口答えし始めた。その口論を聞いてサードゥがやって来た。するとマンガルダースは話し方を正して言った。「サードゥよ、この2人の若者が、毎日お前のものを盗んでいたんだ。私は彼らに毎日言ってたんだ、サードゥのものはサードゥのものだって。しかしこいつらはひどいペテン師だ。こいつらはお前のおかげでいったい何枚の金貨を手に入れたかことか。さあ、お前たち、持ってる金貨全てここに出しなさい。そうでなければ泥棒になるぞ!」スメールは何も答えなかったが、チャンダンが言った。「グルジー、自分を偉いと思ってるのなら、汚ない言葉は使わないように。オレはスメールじゃないし、あんたを師匠だとも思ってない。お前はこの憐れで正直なサードゥのおかげで安穏に暮らしてるんだろ。オレは今、全て理解したよ。黙った方が身のためだぜ。さもなくば、村人たちに全部ばらしてやるからな。どうなっても知らないぜ。」
マンガルダースとチャンダンが口論している間、サードゥは立ち尽くしたまま神様に祈っていた――ああ、神様、私にご慈悲を、私をお許しください!
マンガルダースはそのときは恥辱を甘んじて受け容れた。だがその夜、マンガルダースはサードゥに言った。「全ての悪業の原因はお前だ。さあ、どうすればいいか言ってみろ?」
サードゥは本当に全ての間違いは自分にあると信じていた。彼は言った。「お前は今まで私に慈悲を投げかけていた。これからも変わらぬ慈悲を投げかけ、そしてワシに対する罰をお前自身が決めなさい。全ての過ちはワシにあるのじゃ。ワシの過ちのせいで今まで地面から金貨が生まれていたのじゃ。」
マンガルダースは言った。「今まで?どういう意味だ?」
サードゥは言った。「ワシの足元から金貨が生じることが分かったとき、ワシは神様に祈ったのじゃ。そして神様はワシのこの呪いを消し去ってくれたのじゃ。もうワシは金とは何の関係もない。」
マンガルダースは怒って言った。「何?」
サードゥは言った。「お前はもうワシに怒る理由などないはずじゃ。」
マンガルダースは怒りが全身にこみ上げていた。彼は、2年の内に少なくとも近隣で一番の大金持ちになるだろうと計算していた。しかし今、彼の野望は水泡と化そうとしていた。彼は怒って言った。「サードゥ、お前は恥を知れ!オレはどれだけ長い間お前の世話をして来たんだ?今頃になってお前はそうやってオレを騙そうとするのか?いったい何が欲しいんだ?お前はここから立ち去ろうって言うのか?いいか、オレは絶対にお前をどこにも行かさないからな。」
サードゥは言った。「これ以上お前はワシに何を求めるのじゃ?」
マンガルダースは学識のあるブラーフマンでもあった。彼は屁理屈をこねて言った。「もう一度神様に祈って、また一歩一歩金貨が生じてくるようにしてもらえ。お前は馬鹿で何も知らない。もしお前が金から解放を求めているなら、それはお前の利己心だ。なぜそんなにすぐに解脱しようとしてるんだ?いいか、オレがお前に宗教とは何か教えてやる。だからもう一度金貨が生じるようにしろ。金で世界は動いてるんだ。世界は金があるから発展してるんだ。お前は金に何の欲もない、それで十分だ。お前は何の欲も持たなくていい。しかし真の宗教人は他人の邪魔はしないはずだ。だからもしお前が真の宗教人なら、自分の考えを他人に押し付けてはならない。お前は、この世界において金がどのように欲望を生じさせるか知っておく必要がある。欲望の中には意識がある。意識によって神様に祈ることができる。世界にはいろんな事象が溢れている――女性の世話、子供の遊び、家族の愛――この全ては金というアムリタ(不老長寿の薬)から生じているのだ。金はラクシュミー女神の賜り物だ。金があるからこそ商売があり、政府があり、救済があり、浄化があり、ジャーティ(カースト)があり、宗教があるのだ。ラクシュミー女神の金というマントラ(経文)によって全てが成り立ってるんだ。いいか、サードゥ、よく考えて行動しろ。お前は何もする必要ない。お前はただ神様に祈ってるだけでいい。他の面倒なことは全てオレに任せろ。」
マンガルダースはさらに話し続けた。「分かったか?さあ、早く決めろ。もしお前が自分の考えを変えるつもりがないなら、お前はこの先何の救いもないだろう。お前は神様のところへ行きたいんだよな?なら話は早い。オレがお前をあの世まで送り届けて、ヤマ(冥界の王)に頼んでやるよ、こいつを神様のところへ連れてってくれってな。もしオレの言う通りにするなら、お前は信仰、幸福、全てを得ることができるだろう。何の不足もないだろうし、オレの望みを叶えることで、徳を積むこともできる。」
サードゥはマンガルダースの話を聞きながら心の中でつぶやいていた。「ああ、神様、罪人もあなたの一部です。」
マンガルダースは聞いた。「さあ、どうする?」
サードゥは心の中で言った。「罪に耐え、罪をお許しください、神様、罪人にご慈悲を、なぜなら彼は何も知らないのです。」
サードゥが黙っているのを見て、マンガルダースは大声で叫んだ。「どうした、サードゥ、聞こえないのか?」
サードゥは祈りに没頭していた。「神様、この男にも憐れみを、なぜなら欲望に目がくらんでいるだけなのですから。」
サードゥが黙り続けていたのを見て、マンガルダースは激怒した。彼は立ち上がってサードゥを力いっぱい殴った。そしてさらに蹴ったり殴ったりし続けた。
最後にマンガルダースは言った。「これで分かったか、この野郎!」
しかしサードゥは心の中で言っていた。「神様、全てはあなたの一部です。全てはあなたなのです。」
蹴ったり殴ったりされたサードゥは怪我をしたが、重傷ではなかった。サードゥには何の過ちもなかった。実際、賢いマンガルダースは自分の行為に罪悪感を感じていた。マンガルダースは頭のいい男だった。彼は、「金の卵を産む鶏」の話を思い出した。だからサードゥを殺しても自分に何の利益もないことを自分で悟っていた。そのような馬鹿な行為はしないようにしなければ、と自制した。
次の日の朝、村人たちがやって来た。やって来るなり、彼らはマンガルダースに罵声を浴びせかけ、小屋を滅茶苦茶にしてしまった。そのときマンガルダースの座席の下から無数の金貨が出てきた。村人たちは金貨に手を付ける前にマンガルダースをこっぴどく懲らしめた。
一方、サードゥは遠くで空を仰いで祈っていた。「ああ、神様!ああ、神様!諸悪の根源であるこの金が、ワシのどこから生まれて来たのか?ああ、神様、あなたはこんな厳しい罰を私にどうしてお与えになったのですか?」
マンガルダースを罰する役はチャンダンが主に担っていた。チャンダンの話を聞いた人々は、マンガルダースが持っている金貨は全てあのサードゥに与えることを決めた。マンガルダースを散々懲らしめた後、村人たちは金貨の山をサードゥに渡そうとマンガルダースの小屋にやって来ると、そこには1枚の金貨もなかった。代わりに赤い蓮の花が咲き乱れる湖があった!赤い蓮の花は純粋な心の象徴だった。そしてまるで蕾からたった今花開いたばかりのように見えた。
村人たちは大いに驚き、サードゥを心から敬うようになった。
しかしサードゥは言った。「お前たちはあの憐れな男を縛り上げたが、彼の罪もこのように既に消え去ってしまった。だからすぐにあの男を放してやりなさい。」
チャンダンは言った。「あの男は詐欺師です。」
サードゥは言った。「我々を詐欺師に変貌させてしまうものは、もうここにはない。だから誰も詐欺師になりようがないではないか。何か機会が来れば、誰でも過ちを犯すものだ。さあ、あの男を放してやりなさい。」
サードゥの言葉に従い、村人たちは戻ってマンガルダースを解放してやった。
マンガルダースは改心し、サードゥの足元にひれ伏して許しを乞うた。
その後、村人たちは集まってそこに立派なガート(沐浴用の階段)のある湖を作った。無数の蓮の花で赤く赤く染まっているその赤い湖は、今でもそこに残っていると言う。
−完−
|
|
| *** Copyright (C) Arukakat All Rights Reserved *** |



