| ◆ |
8月1日(水) デリーは次なる映画都市か? |
◆ |
7月27日から8月5日まで、デリーのスィーリー・フォート・オーディトリアムにおいてオシアン・シネファン映画祭が開催されている。インド各言語の映画を中心に、日本、韓国、台湾、香港、中国、ネパール、バングラデシュ、タイ、カンボジア、フィリピン、シンガポール、インドネシア、イラン、レバノン、トルコ、アルジェリア、モロッコ、フランス、ドイツ、チェコ、エストニアなどの映画が上映されている。中でも日本映画のプレゼンスは大きい。若松孝二、足立正生、寺山修司、今岡信治、小林政広、塚本晋也、園子温、井土紀州、金田龍、石橋義正、白石晃士、入江悠、山口智、三木孝浩、平沢剛、鎮西尚一、長谷部大輔、藤原敏史、さとうけいいち、森下孝三などの作品(多くがピンク映画かアニメ映画)が上映されている。この映画祭で鑑賞したインド映画については、「これでインディア」でも随時批評をしている。総じて、インド映画の一層の発展を裏付ける、非常に興味深い作品が集まっていると言える。
ところで、映画の上映と平行して、7月31日から8月1日の2日間、「デリー・サミット」と称して、映画は元より、立法、行政、司法、メディア、警察など、多岐の分野に渡る人々を集め、パネル・ディスカッションも行われた。議題は「デリーはインドの次なる映画都市か?(Is
Delhi India's Next Film City?)」であった。
デリーに住みながら10年以上ヒンディー語映画を見続けて来て、個人的にかなり前から強く感じていたのは、デリーこそがヒンディー語映画の中心地になるべきだということであった。
現在、ヒンディー語映画の中心地はムンバイーである。インド映画産業の黎明期からムンバイーはヒンディー語映画界の不動の首都であり、ヒンディー語映画の発展はムンバイーと共にあったと言っても過言ではないだろう。しかし、ムンバイーの言語はヒンディー語ではない。メトロポリタンなのでヒンディー語をはじめとしたインド中の様々な言語が話されており、英語の通用度も高いが、ムンバイーのローカル言語は第一にはマラーティー語である。ムンバイーを舞台にリアリスティックな映画を撮ろうとすると、多くの場合どうしてもマラーティー語に頼らざるを得なくなる。そうするとヒンディー語映画ではなくなってしまう。ムンバイーの映画産業がヒンディー語で映画を作っているのは、国内にヒンディー語を理解する観客が最も多いからであり、最大限の収益を見込めるからである。それ以外の理由はない。もしインドに英語話者が4-5億人いたら、ムンバイーの映画産業は間違いなく英語で映画を作っていたことだろう。
確かにヒンディー語映画はヒンディー語の普及と発展に多大な貢献をして来た。映画には最大公約数的なヒンディー語が使用されることが多いため、外国人ヒンディー語学習者にとっても教材として最適だ。だが、ヒンディー語映画からヒンディー語への愛着を感じ取ることは難しい。いわゆるヒンディー語ベルトに住み、ヒンディー語を母語とする人々とヒンディー語映画の間の精神的隔たりが大きすぎるのである。ヒンディー語をろくにしゃべれない俳優が簡単に主演を張れてしまうことがその何よりの証拠だ。それだけでなく、ヒンディー語ベルト以外出身の、ヒンディー語を母語としない人々がヒンディー語映画を作ることなど日常茶飯事となっている。ヒンディー語映画のクレジットを見ると「台詞(Dialogue)」という役割があるのが目に付くが、これはヒンディー語の台詞を考案するのに脚本家などとは別にヒンディー語のエキスパートをわざわざ雇わなくてはならないというムンバイーの映画産業の実態を如実に示している。
もしデリーがヒンディー語映画の中心地になれば、このような欠点が解消されるのではないかというのが持論であった。デリーこそがウルドゥー語の誕生の地であり、ウルドゥー語こそが現在のヒンディー語の土台となっている言語である。ここではヒンディー語とウルドゥー語の複雑な関係について深く足を踏み入れないが、ヒンディー語が生まれ、足場を固め、そしてリアルタイムで発展しているデリーにおいて、プレプロダクションからポストプロダクションまでヒンディー語映画が作られるようになれば、必ずやヒンディー語映画の質は劇的に向上するだろうという楽観的な展望を勝手に持っていた。
そういうことを考えているのは僕だけかと思ったが、オシアン・シネファン映画祭において「デリーはインドの次なる映画都市か?」と題したパネル・ディスカッションがあることを知り、他に同様のことを考えている人がいることを知って嬉しかった。よって、映画上映以上にこのパネル・ディスカッションを楽しみにしていた。ほとんどのセッションに参加し、参加者の議論に熱心に耳を傾けた。ここではその報告と、それを通して自分なりに考えたことを書こうと思う。
まず、「映画都市(Film City)」の定義が重要となるだろう。映画都市とは何なのか?撮影ロケーションのことか、スタジオのことか、それとも映画文化の中心地のことか?議論の中で何度も「映画都市とは何なのか?」と問い掛けがあったにも関わらず、明確な定義がなされずに議論が進行していた。よってパネラーたちの間で映画都市というコンセプトに対するコンセンサスがなく、思い思いの解釈の下に発言が飛び交っていた。ただ、国家映画振興公社(NFDC)のニーナ・ラス・グプター社長が「いかにデリーを映画フレンドリーな都市にするか」と言う観点から発言しており、この「映画フレンドリー」というキーワードが最も全体の議論に近い解釈となると感じた。単なるロケからポストプロダクション、マーケティング、映画祭まで、映画という分野においてデリーが関わっていける範囲をどのように拡大して行けるのか、ということが議論されたと言えよう。
また、単に「フィルムシティー」ならば既にノイダに存在する。元々は北インドの映画制作拠点を目指して設立されたのだが、現在ここで映画の制作は行われていない。代わってニュースチャンネルのハブとなっている。不思議なことに映画以外の全てはデリーとNCR(首都圏)に集中しつつある。かつてはムンバイーが商業の中心地とされていたのだが、現在ではデリーの方にビジネスと富が集中している。ニュース、出版、IT、金融などなど、「知識産業」と総称されるほとんどの産業は今やデリーがインドの中心である。だが、映画産業だけは頑なにデリーへの移転を避けて来ている。一体なぜデリーと映画はここまで相性が悪いのだろうか?
ただ、「デリーは映画都市になれるのか?」という提議がなされたこと事態、時代の流れを象徴していると言っていいだろう。デリー・ロケの映画は今や特に珍しくなくなっているし、実は最近のヒンディー語映画界ではデリー出身の映画監督が非常に元気がいいのである。現在ヒンディー語映画界の新しくエキサイティングな潮流を先導している映画人のほとんどが、デリー出身またはデリーで学問を修めた人材なのである。アヌラーグ・カシヤプ、イムティヤーズ・アリー、ラーケーシュ・オームプラカーシュ・メヘラー、ディバーカル・バナルジー、ティグマーンシュ・ドゥーリヤー、キラン・ラーオなどなど、世界に出して恥ずかしくない優れた作品を作っている若い映画監督のほとんどはデリー出身だ。ただ、彼らが現在拠点としているのはムンバイーだ。では、なぜ彼らはデリーで映画作りをせずに、ムンバイーへ行かなければならなかったのか?そもそもこの素朴な疑問から今回のパネル・ディスカッションが企画されたと言っていいだろう。
パネラーとして、シェーカル・カプール、イムティヤーズ・アリー、ディバーカル・バナルジー、ムザッファル・アリーなど、新旧の著名な映画監督が来ていた。他にもオシアンの創始者兼会長ネヴィル・トゥリー、映画プロデューサーのボビー・ベーディー、写真家のラグ・ラーイなど、著名人がパネラーとして出席していた。また、聴衆の中には映画監督を志す若者が多かった。単なるパネル・ディスカッションだけではなく、パネラーと聴衆の間でインタラクティブな議論がなされた。
その中で、やはりデリーで映画作りを学ぶ若者の間に、デリーでも映画作りが出来ればという願望が強いことに気付いた。デリーには国立演劇学校(NSD)など、人材育成の機関は存在する。だが、もし映画産業で身を立てようと思った場合、ムンバイーへ行かなければチャンスがないのが現状だ。多くの若者は、北インドの地方からデリーへやって来て、大都市での生活に苦労して馴染みながら演技や映画作りを学ぶ。その後、映画界で仕事を得るため、再びムンバイーに移住しなければならない。北インド出身の映画人の卵にとって、ムンバイーのみに映画産業が集中する現状は非常に不利・不便なのである。しかも、ムンバイーの映画産業は通称「ボリウッド」と呼ばれる娯楽産業の支配力があまりに強く、志高い人材であっても、その産業の文法に自分を何とかアドジャストさせて呑み込まれて行くか、自分の意志を貫きつつ一生あがき続けるかしか道はない。また、元々デリーに住んでいる映画人、例えばムザッファル・アリーなどは、もしデリーに映画産業が育ったらとても面白いことになると、前向きな姿勢を見せていた。デリー出身ながら現在ムンバイー在住の映画人、例えばイムティヤーズ・アリーなどは、正直なところデリーがどうなろうとあまり関心がないような印象を受けた。デリー映画都市化計画の積極的な賛同者は主に、これから映画産業で身を立てようとしている若者と、現在デリーに住んでいる映画人だとまとめられる。
ただ、意外に反対意見も聞かれた。デリーの映画都市化に最も危惧を示していたのは、映画以外の芸術に関わる人々であった。現在のデリーは、州政府による文化振興政策のおかげで、様々な形態の芸術がいい具合に発展して来ている。だが、もしデリーが「第二のボリウッド」化したら、映画産業が全ての芸術を呑み込んでしまい、芸術家は、映画に関わってグラマラスな人生を送るか、映画を避けてスポットライトを浴びない人生を細々と送るか、二者択一になってしまう。もしデリーが「第二のボリウッド」となるならば、デリーの映画都市化には大反対だという意見がちらほら聞かれた。これはもっともな意見であり、もしデリーが映画都市として名乗りを上げるならば、ムンバイーがやっていないことをやらなければならない。写真家のラグ・ラーイはそれに関しもっとも過激な意見を述べていた。彼は、自分は映画関係者ではないと断りながらも、ムンバイーの映画産業を「病気」だと表現し、それに対抗し、本当に良質の映画を作るために、デリーを新たな映画都市に育て上げなければならないと強く提言していた。
このパネル・ディスカッションの中で一番奇妙だったのは、デリー映画都市化計画の提唱者であるはずのネヴィル・トゥリー自身が「私はデリーを映画都市にすることには反対だ」と何度も言っていたことである。彼が反対ならば、誰がこの議論を始めたのか?ただ、彼の話をよく聞くと、彼は映画を越えたさらに大きな視野を持っていることが分かる。彼はデリーを文化ハブとすることを究極の目的として持っており、映画もそれに貢献出来ると考えている。ただし、映画が文化ハブとしてのデリーの障害となるならば、何の躊躇もなく映画を捨てると語っていた。彼が最も関心を寄せているのは建築であり、文化遺産であり、遺跡の保護である。映画によって、デリー各地に残る遺跡の活用が進めば、人々の間に遺跡に対する関心を呼び起こすことが出来る。だが、もし映画撮影スタッフが歴史や遺跡に敬意を払わず、遺跡の破壊をするならば、そのような活動は許さないと明言していた。また、彼は映画制作や映画祭よりもむしろ、作品のアーカイブや映画で使用された小道具の保管などに関心を寄せていた。
パネラーには政策決定者、映画関連部局の役人、警察、弁護士などもおり、彼らに対して政策的な枠組みの提言も行われていた。映画制作者から最も要望が強かったのはシングル・ウィンドウ・システムである。現在では、デリーでロケをする際に多くの部局から認可を得なければならない。例えば遺跡でのロケでは、地元警察、交通警察、インド考古局(ASI)などから許可を得なければならない。しかも、許可を得た後も様々なトラブルが付きまとい、ロケは一筋縄では行かない。もし1ヶ所で全ての許可が得られるならば、デリーでのロケは格段に容易となり、デリー・ロケの映画がさらに増えるだろう。だが、デリー州政府の官僚によると、デリーは中央政府と州政府による二重行政状態にあり、そのようなシステムの確立には大きな障壁があると言う。既に似たようなシステムはあるのだがうまく機能していないという話もあった。
ただ、映画振興のために現在様々な計画が実行中であることも明かされた。例えばジャナクプリーに建造中のディッリー・ハートの用地には、まだ用途が決定していない土地があり、もしかしたらそれを映画スタジオのような形に使えるかもしれないとのことであった。また、現在ムンバイーとチェンナイにおいて映画文化センターのような施設の建造計画が進んでいると言う。映画文化センターでは、映画の上映や映画技術の養成などの他、アーカイブも計画されている。今のところインド映画のアーカイブ施設はプネーにあるが、インド各地の映画文化センターにおいてアーカイブにアクセス出来るようにしたいとのことである。このような施設がデリーにも出来れば、映画都市に一歩近付くだろう。
おそらく最も広く深い視点からデリーの映画都市化について意見を述べていたのはシェーカル・カプールである。インド映画の範疇では「Mr. India」(1987年)や「Bandit
Queen」(1994年)などで有名な監督だが、現在では国際的に活躍しており、「Elizabeth」(1998年)や「Elizabeth: The
Golden Age」(2007年)などでよく名を知られている。インドの映画人の中で最も世界を知っている人物であり、彼の意見は常に国際的な視野と経験に基づいていた。彼は、デリーの映画都市化計画について、まず「ムンバイーはライバルではない」と言い切った。映画によって都市や観光を振興する政策は既に世界中の国や都市が実行しており、もしデリーが映画都市を目指すならば、ライバルやお手本はムンバイーではなく世界中の都市だと指摘した。例えばロンドンは、市内で撮影された映画のロケ費用の25%をペイバックする政策を実施している。シンガポールは、映画ロケ中の滞在費を全額負担し、ロケを全面的に後援している。このような積極的なロケ誘致政策を採らなければ国際マップの中でデリーはいつまで経っても映画都市にはなり得ないと述べていた。
また、シェーカル・カプールは、映画人をはじめとした文化人を呼び寄せ、彼らの間でシナジーを生むには、「アンダーベリー」が必要だと主張した。アンダーベリーというのは日本語の俗語で言えば「アングラ」のことで、政府の干渉なく(時には反体制的な活動のため)、映画監督、俳優、芸術家、詩人などが自由に交流しお互いを刺激し合える場のことである。文化人は魅力的なアンダーベリーのある都市に集まり、新しい文化はアンダーベリーから生まれる。現在それに最も該当するのがベルリンで、そこからエキサイティングな文化が生まれつつある。もしデリーが映画都市を目指すならば、アンダーベリーを作らなければならない。ただ、これは政府が用意するようなものではなく、あくまで当事者たちが作らなければならない。政府の積極的な映画振興政策と、文化人が集うアンダーベリー。この2つが、デリーの映画都市化のために最も重要な要素だと、シェーカル・カプールは述べていた。ただ、同時に、ハリウッド映画の9割はロサンゼルス以外で撮影されていること、ムンバイーは政府の支援なく映画都市となったことなども指摘していた。また、米国ではロサンゼルスの他にニューヨークでも映画制作が盛んであり、デリーもニューヨーク的な立場になれるのではないかと提案していた。つまり、映画産業の文脈において、ムンバイーの衛星都市にもなれるし、映画に独自のアクセントを加える場にもなり得る。シェーカル・カプールの意見ではなかったと思うが、デリーを北インド各都市の映画ロケのゲートウェイとする意見も聞かれた。
はっきり言って2日間の議論を通して何らかの具体的な答えが出たとは言いにくい。だが、少なくともデリーに何らかの形の映画産業を根付かせ、ムンバイーとの共存・並立の中で発展させて行こうとする動きが出て来たことは歓迎したい。いくつかの提案はすぐには実現が難しそうだったが、意外に政府の方でも映画振興のためにいろいろ計画が進められていることが分かった。きっと今日のこの一歩が、10年、20年後のヒンディー語映画の発展において、将来重要なイニシアチブとして記憶されることになるのではないかと思う。
今日はオシアン・シネファン映画祭で良さそうな作品の上映が続いていたため、午後からずっと会場にいて4本の映画を連続で鑑賞した。その内3本はインド映画で、残りの1本はアン・ホイ(許鞍華)監督の香港映画「桃姐」(2011年;
英語題名「A Simple Life」)である。「これでインディア」では基本的にインド映画のみを取り上げるが、「桃姐」について一言だけ。インド映画があまり刺激しない情感を刺激して来る作品で、香港映画の質の高さを見せ付けられた思いであった。方向性は違うものの、このレベルの映画はインドではまだ作れないと感じた。素晴らしい映画であった。
本日まず鑑賞したのはプラシャーント・バールガヴァ監督の「Patang」(英語題名「Kite」)である。グジャラート州アハマダーバードで毎年1月14日に祝われるカイト・フェスティバルを背景として作られた作品であるが、言語は商業的な理由からヒンディー語となっている。監督やプロデューサーは米国在住の在外インド人(NRI)。制作には7-8年を要しており、バールガヴァ監督は毎年数ヶ月アハマダーバードに住んで地元の人々と交流を深め、映画を作り上げたと言う。出演者の多くは実際にアハマダーバードに住んでいる人々である。
題名:Patang
読み:パタング
意味:凧
邦題:凧
監督:プラシャーント・バールガヴァ
制作:JDパンジャービー
音楽:マリオ・グリゴロフ
衣装:スジャーターSヴィルク
出演:スィーマー・ビシュワース、ナワーズッディーン・スィッディーキー、スガンダー・ガルグ、ムクンド・シュクラ、アーカーシュ・マハーエーラー、ハミード・シェークなど
備考:スィーリー・フォート・オーディトリアム2で鑑賞。オシアン映画祭。

アーカーシュ・マハーエーラー(左)とスガンダー・ガルグ(右)
| あらすじ |
デリー在住の実業家ジャエーシュ(ムクンド・シュクラ)は、カイト・フェスティバルの前日1月13日に、娘のプリヤー(スガンダー・ガルグ)と共にアハマダーバードの実家を久し振りに訪れる。実家には母親、兄ウメーシュの妻スダー(スィーマー・ビシュワース)、そして甥のチャックー(ナワーズッディーン・スィッディーキー)が住んでいた。ウメーシュは既に亡く、チャックーは大した仕事もしておらず、経済状態は良くなかった。ジャエーシュは1月14日に自宅に旧友を呼び寄せ、共に凧を飛ばす計画を立てていた。
ジャエーシュが突然実家を訪れたのにはもうひとつの理由があった。彼は実家を売り払い、デリー近郊にアパートを買って、家族皆で住むことを考えていた。だが、母親は絶対に書類にサインしようとしなかった。また、チャックーは以前から父親が死んだのはジャエーシュのせいだと考えており、叔父に反感を抱いていた。ジャエーシュがその計画を披露した途端、チャックーは怒りを露わにする。
プリヤーにとってアハマダーバードは初めてのようなものだった。幼い頃に来て以来だった。プリヤーは8mmビデオを片手にアハマダーバードの街を探検する。その中で彼女は近所に住む青年ボビー(アーカーシュ・マハーエーラー)と出会う。ボビーは近所では随一の凧名人で、普段は父親の店で店番をしていた。
また、ジャエーシュは馴染みの凧屋に特注の凧を届けるように注文する。凧屋はハミード(ハミード・シェーク)という少年に届けさせる。ハミードはチャックーの友人であった。だが、届ける途中にチャックーの喧嘩に巻き込まれてしまい、凧は台無しになってしまう。
カイト・フェスティバルの当日。ジャエーシュはまだ凧が届いていないのに気付き、凧屋に自ら行って凧を買って来る。屋上へ行き、早速旧友たちと凧を飛ばす。また、プリヤーはボビーと共に凧上げをし、その後彼のバイクに乗ってアハマダーバードを巡る。プリヤーはボビーとキスをするが、ボビーと付き合うつもりはなく、そのまま彼を置いて立ち去る。
夜、ジャエーシュは空高く舞う特注の凧の糸にひとつずつ灯籠を灯して行く。その下ではチャックーと子供たちが打ち上げ花火をして遊んでいた。その内花火が凧に直撃し、落下してしまう。その衝撃でジャエーシュは指を切ってしまう。また、屋根の上でその凧をキャッチしようとしたハミードは下に落ちてしまう。チャックーはハミードを病院へ搬送する。幸い命に別状はなく、片腕の骨が折れただけだった。また、スダーはジャエーシュの手当をしながら、過去の話に言及する。ジャエーシュとスダーの間には実は深い心のつながりがあった。
翌日、凧の残骸が散らばるアハマダーバードを後にし、ジャエーシュとプリヤーはデリーに帰って行く。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
久し振りの家族・親類・知人の集まりの中で繰り広げられる様々な人間模様を、年に一度のカイト・フェスティバルに沸くアハマダーバード旧市街を背景にしながら、広く浅く描いた作品で、よく似ているのは「Monsoon
Wedding」(2011年)になる。実家の屋敷を売却して高級アパートに移住する話、ウメーシュの死にまつわる秘密、ジャエーシュの夫婦関係の問題、デーヴァル(夫の弟)とバービー(兄の妻)のただならぬ絆、都会育ちのピヤーと地方都市育ちのボビーとの考え方の差など、様々な問題に少しずつ少しずつ触れられ、決してそれらに深入りすることなくストーリーが進む。観客は断片的な映像や台詞から、この家族に秘められたそれらの問題を推測するしかない。このような問題はどの家族にもあるものだ。だが、問題がありながらも家族は家族としてまとまっている。そんな何でもない風景を自然に切り出すことに成功した映画だと言える。
単なる家族の集まりだったら退屈な映画になっていたかもしれないが、この映画に独特の興奮があるのは、間違いなくカイト・フェスティバルのおかげだ。グジャラート州の最大都市アハマダーバードではマカル・サンクラーンティ(1月14日)の日、インターナショナル・カイト・フェスティバルが開催され、世界中から凧上げの名人が集まって凧のデザインやテクニックを競い合う他、一般の人々も屋根の上に上がって凧を上げ、空は一面凧で埋め尽くされる。カイト・フェスティバルの際に撮影した映像を利用している他、俳優にもカイト・フェスティバル時に演技をさせているため、臨場感いっぱいだ。実際に傍から見ているとそんなに楽しくない凧上げをエキサイティングな映像に仕上げているのも評価出来る。
もちろん、題名にもなっている「凧」は、カイト・フェスティバルだけでなく、様々な事象のメタファーとなっている。第一には実家を離れてデリーに住むジャエーシュの象徴であろう。ジャエーシュがアハマダーバードを出た理由は劇中でははっきりと明かされていないが、両親や兄の家族と何らかのいざこざがあったことが予想される。言わば糸の切れた凧のような状態のまま、ジャエーシュはデリーに住んでいた。だが、今回ジャエーシュは久し振りに実家に戻って来た。それは、糸が切れた凧が、他の人の手を経て、また自分のところへ戻って来るようなものであった。ジャエーシュの特注凧も、一度失われた後にまた戻って来た。
ジャエーシュとアハマダーバードの間の糸は切れていなかったとも考えられる。その一本の糸こそが、兄嫁スダーとの関係であった。ジャエーシュはスダーとその家族が不幸な生活を送っていると思い込んでいるが、スダーは自分たちは幸せだと言い切る。彼女がジャエーシュに語った言葉が印象的だ。「私は凧を切ったり切られたりは好きではないわ。高く高く飛ぶ凧が好き。」「私たちは小さな小さな幸せを大事に掴んで生きているわ。」まるで大空舞う幸せを、か細い糸で掴んでいるかのような台詞だ。凧は幸せの象徴だと言える。
ピヤーが出会ったボビーにとっては、凧は自由の象徴であった。彼はいつかアハマダーバードを出て人生で一花咲かせたいと野望を持っていた。だが、父親のビジネスを助けるために大学を途中で退学しなければならず、店番をする毎日。前途は容易ではない。しかし、彼が飛ばす凧のように、自分もいつか大空へ飛び立ちたいと考えていた。
このように、単にカイト・フェスティバルを背景としているだけでなく、登場人物のそれぞれの思いが凧に込められており、それがとても琴線に触れた。凧や凧上げを効果的に描いたインド映画には「Hum
Dil De Chuke Sanam」(1999年)や「The Japanese Wife」(2010年)などがあるが、凧をここまで中心的なメタファーにした映画は今までなかったと言える。
キャストの中ではスィーマー・ビシュワースとナワーズッディーン・スィッディーキーが有名だ。2人とも演技派・個性派として知られる俳優で、さすがの演技をしていた。スガンダー・ガルグは「Jaane
Tu... Ya Jaane Na」(2008年)などで出演経験のある女優である。スクリーン上では20代に見えたが、もう35歳のようだ。ボビーを演じたアーカーシュ・マハーエーラーは素人で、凧上げの腕を買われて起用された。素人であることを感じさせない演技であった。
「Patang」は、カイト・フェスティバルを背景にしながら、凧をうまく登場人物の感情や状況とリンクさせて、久々に再会した家族や友人の人間模様を描いた作品であった。カイト・フェスティバルの実際の映像を使っているだけあって、臨場感溢れる映像も見所である。NRIがインドに来て作った作品だけあって、外国人好みのインドらしいテーマや映像をうまく料理して一本の作品にまとめあげていたと言える。
引き続き鑑賞したのは、マハーラーシュトラ州ヴィダルバ地方を舞台にした「Baromas」。サダーナンド・デーシュムクの同名マラーティー語小説を原作としているものの、映画の言語は基本的にヒンディー語である。ヴィダルバ地方はかつてマディヤ・プラデーシュ州の一部だったこともあり、一般にヒンディー語が話されているとの監督の弁であった。監督自身はマラーティー語話者で、ヒンディー語はそこまで得意そうではなかった。「Baromas」は「12ヶ月」「1年中」という意味だが、英語の題名はなぜか「Forever」となっている。
題名:Baromas
読み:バーローマース
意味:12ヶ月
邦題:12ヶ月
監督:ディーラジ・メーシュラーム
制作:パッリプラム・サジート、プリヤンカー・スード
原作:サダーナンド・デーシュムク「Baromas」
音楽:ラヴィーンドラ・ジャイン
出演:スィーマー・ビシュワース、スディール・パーンデーイ、デーヴィカー・ダフタルダール、ベンジャミン・ギーラーニー、スブラート・ダッター、ジャティン・ゴースワーミー、ローヒト・パータクなど
備考:スィーリー・フォート・オーディトリアム1で鑑賞。オシアン映画祭。

ジャティン・ゴースワーミー(左)とスブラート・ダッター(右)
| あらすじ |
マハーラーシュトラ州ヴィダルバ地方の農村に住むエークナート(スブラート・ダッター)は都会で教育を受けたが、社会運動に関心を持ち、村に戻って、社会活動家ナルバーウの指導の下、農民たちの組織化や地位向上に尽力していた。一方、エークナートの弟マドゥカル(ジャティン・ゴースワーミー)も高学歴だったが無職で、仲間と共に地面を掘ってお宝探しに明け暮れていた。エークナートにはアルカー(デーヴィカー・ダフタルダール)という妻がいたが、母親シェーワンター(スィーマー・ビシュワース)やマドゥカルとの仲はよくなかった。あるときマドゥカルと喧嘩をし、実家に帰ってしまう。父親スバーンラーオ(ベンジャミン・ギーラーニー)は農民であったが、ここのところ日照り続きで農業はうまく行っていなかった。
サルパンチ(村長)のダグルー・マハーカール(スディール・パーンデーイ)は高利貸しで、困窮した村人たちに金を貸しては、利子や担保を搾取していた。最近もバリという農民が借金に借金を重ねた挙げ句自殺をしてしまった。
あるときマドゥカルは大学時代の友人スレーシュと出会う。スレーシュは就職して裕福な生活を送っていた。スレーシュはマドゥカルに対し、就職するには贈賄は必須だと吹き込み、州議会議員の個人秘書が知り合いだから、今度口利きをしてやると言う。マドゥカルはあと一歩で就職できそうになるが、そのためには20万ルピーの賄賂が必要だった。マドゥカルは両親を説得し、畑を担保にしてダグルーから20万ルピーを借りる。10万ルピーは前金として支払った。
ちょうどそのときエークナートは収穫物を売るために街の市場に出掛けていて2-3日留守にしていた。家に帰って来たエークナートは、マドゥカルが畑を担保にしたことを知って怒る。また、マドゥカルが就職のあてにしていた州議会議員は不正が発覚して姿をくらましてしまった。つまり、10万ルピーは無駄になってしまった。スバーンラーオは畑を失ったことで眠れない夜を過ごす。何とか10万ルピーを作って畑を取り戻さなくてはならなくなったマドゥカルは、夜な夜なハイウェイで強盗をするようになる。スバーンラーオはダグルーに畑を返してくれるように頼みに行くが、ダグルーは承知しない。絶望したスバーンラーオは毒を飲んで自殺しようとする。村の長老の機転によりスバーンラーオは一命を取り留めるが、そのときの治療がトラウマとなり、スバーンラーオはある日忽然と姿をくらましてしまう。
州議会選挙が近付いていた。エークナートは師匠ナルバーウに説得され、立候補することになる。対立候補はサルパンチのダグルーであった。日頃から農民や漁師のために働いて来たエークナートは信望厚く、彼の選挙集会には多くの人々が集まった。ダグルーは落選の危機を感じる。そのときダグルーをマドゥカルが訪ね、20万ルピーを返そうとして来た。ダグルーは選挙後に借金返済の手続きをすると言って彼を返すが、同時にマドゥカルがなぜそんな大金を手にしたのか疑問に感じる。部下に調査させたところ、マドゥカルとその一味が夜な夜な強盗をしていることが分かる。ダグルーは、部下にナルバーウを殺させ、マドゥカルが強盗を繰り返す現場に置き去りにする。マドゥカルは逃亡するが、仲間の多くは警察に捕まってしまい、強盗を白状する。エークナートは、弟が強盗の容疑で逃亡中ということで、一気に不利な選挙戦を戦うことになってしまう。
しかし、ナルバーウの殺人があった夜、偶然エークナートとマドゥカルの友人チャンドラ(ローヒト・パータク)が、現場近くでダグルーの部下を目撃していた。チャンドラはメーラー(祭り)でその男を発見し、逃亡中のマドゥカルと共にとっちめる。マドゥカルとチャンドラは警察に捕まり、連行される。もし部下が全てを白状したら、今度はダグルーの立場が危うくなる。そこでダグルーは策略を巡らせ、部下はマドゥカルがナルバーウを殺す現場を目撃したために命を狙われたことにする。警察もダグルーの話の方を信じ込む。怒ったマドゥカルは警察が所持していた銃剣を奪ってダグルーの腹部を刺す。ダグルーは死んでしまう。立候補者が殺されたことでこの選挙区の選挙は延期となる。
数ヶ月後、再び選挙が行われることになった。エークナートは、ダグルー亡き今、そして師匠を失い、父親が行方不明で、弟が服役する中、もはや選挙を戦う理由はないと、立候補を断念する。しかし母親は、父親がエークナートの社会活動・政治活動を誇りに思っていたと明かし、立候補するように説得する。立候補したエークナートは見事当選を果たす。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
マハーラーシュトラ州ヴィダルバ地方と言うと、農民の自殺が多いことで知られる地域である。世界史の授業でデカン高原は綿花栽培が盛んであると習ったと思うが、正にヴィダルバ地方の農民自殺問題は綿花農業、つまり商品作物農業の問題と直結しており、その視点抜きではなかなか深い理解は得られない。「Baromas」はそのヴィダルバ地方の農村を舞台にした作品であるため、農民自殺問題がテーマの映画であろうと容易に推測される。だが、「Baromas」はむしろより広範な問題を取り扱う作品であった。
劇中にはもちろん自殺する農民が出て来るのだが、借金問題のみと結びつけられており、その奥にある本当の問題まで掘り下げられていなかった。「Baromas」が主に注力していたのは高利貸しによる搾取と農村の若者の就職問題だと言える。サルパンチのダグルーは困窮する農民に高利のローンを与え、借金漬けにして支配していた。また、借金の担保として農地を獲得し、大麻の栽培などをしていた。一方、マドゥカルは大学を出た後も就職できず、農村で無為に過ごしていた。就職には多額の賄賂が必要だと知り、家の農地を担保に借金をするが、うまく就職できず、家に大きな損失をもたらす。その損失を補填するためにマドゥカルは強盗をするようになり、転落の一途を辿って行く。だが、最後にはダグルーを刺し殺し、高利貸しの横暴に一矢を報いる。
これだけだと救いようがないのだが、社会運動家エークナートの存在が希望の光として提案される。エークナートは農民や漁師を組織し、政府の横暴に立ち向かう。州議会選挙においてダグルーの対立候補として立候補し、民主主義的手段によって農民の生活向上を図る。次から次へと悲劇が続く映画なのだが、エークナートが当選するシーンで映画は終了となり、楽観主義的・理想主義的なエンディングとなっていた。
インドの農村の問題をテーマにした映画はいくつもあるが、それらの中で傑出した美点がある作品とまでは評価できなかった。基本的に重厚な作りなのだが、ボリウッド映画の影響であろう、アイテムナンバーが挿入されていたりして、多少グラマラスな雰囲気を出そうともしていたが、蛇足に感じた。農民を巡る問題は、より大きなシステムの欠陥と有機的に結び付いていることを提示したかったと思うのだが、あらゆる問題を広く浅く取り扱い過ぎているような印象を受けた。農村描写に定評のある小説家プレームチャンドの長編小説「Godan(牛供養)」や短編小説「Bade
Ghar Ki Beti(裕福な家庭の娘)」などとも共通点が多い。
それでもいくつかのシーンは特筆に値する。特に、毒を飲んで自殺を図ったスバーンラーオを村の長老が救うシーンはこの映画のハイライトだ。一刻も早く何とかして毒を完全に吐き出させなければならなかった。多少は吐き出したものの、まだ体内に毒が残っていた。そこで長老は子供のウンチを持って来るように言う。そして苦しむスバーンラーオの前でウンチをコップに入れかき混ぜる。同時に長老はマドゥカルに、ターメリックなどを混ぜた水を持って来るように耳打ちする。長老はウンチをかき混ぜたものを飲ませる振りをしてターメリック水を飲ませる。ウンチを飲ませられていると勘違いしたスバーンラーオはとうとう全ての毒を吐き出す。ただ、スバーンラーオは一命を取り留めたものの、ウンチを食べたことがトラウマとなり、ある日忽然と姿を消してしまう。
スィーマー・ビシュワースやベンジャミン・ギーラーニーをはじめとして、皆迫真の演技であった。マドゥカルを演じたジャティン・ゴースワーミーは中でも非常にパワフルであった。
「Baromas」はヴィダルバ地方の農民を舞台とした重厚なドラマ。主人公の家族を中心に、農民を取り巻く様々な問題に少しずつ触れており、よくできた映画だ。それらの問題に深い理解を提供する性格の映画ではないが、十分監督の真摯な努力が感じられる出来となっている。
本日最後に鑑賞したのは「Prague」というヒンディー語映画である。題名の通りチェコ共和国の首都プラハでロケが行われている。プラハは意外にヒンディー語映画とは縁が深い都市で、今まで「Meenaxi:
A Tale of 3 Cities」(2004年)、「Drona」(2008年)、「Rockstar」(2011年)などのロケが行われている。政府が積極的に映画ロケの誘致をしているからであろう。「Prague」はサイコスリラーまたはホラーに分類される映画で、プラハの古い街並みをどのように映画に使うのか、見物である。
題名:Prague
読み:プラーグ
意味:プラハ
邦題:プラハ
監督:アーシーシュRシュクラ
出演:チャンダン・ロイ・サンニャル、クマール・マヤーンク、アルフィー・ラーンバー、ソニア・ビンドラー、エレナ・カザンなど
備考:スィーリー・フォート・オーディトリアム3で鑑賞。オシアン映画祭。
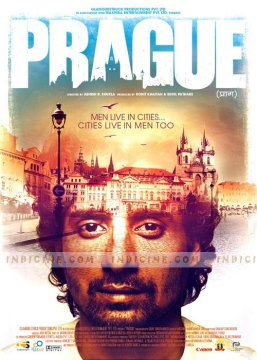
チャンダン・ロイ・サンニャル
| あらすじ |
ムンバイーで建築を学ぶチャンダン(チャンダン・ロイ・サンニャル)は、さらに建築を学ぶためにプラハへ行くことになっていたが、かねてから死んだ友人アルフィー(アルフィー・ラーンバー)の亡霊に悩まされていた。チャンダンは、他の人には見えないアルフィーと話していた。チャンダンは、建築学科の友人グルシャン(クマール・マヤーンク)と共にプラハで学ぶことになっていた。グルシャンはボヘミアンな生活を送る変わった性格の若者で、友人たちから一目置かれていた。
アルフィーは建築学科のアイドルスバーンギー(ソニア・ビンドラー)に振られたことで自殺してしまった。スバーンギーは現在別の男と付き合っていた。チャンダンは密かにスバーンギーに憧れていた。ひょんなことからチャンダンはスバーンギーと仲良くなり、有頂天になる。ところがスバーンギーはグルシャンに取られてしまう。
傷心状態のままチャンダンはプラハの土を踏む。プラハではエレナ(エレナ・カザン)というチェコ人女性と付き合うようになる。ところがチャンダンの下宿先にグルシャンが転がり込んで来る。チャンダンは、またグルシャンにエレナに取られるのではないかという妄想に駆られるようになる。その恐れは現実のものとなった。ある日チャンダンはグルシャンがエレナと情事をしているところを目撃してしまう。
その後、チャンダンはエレナから妊娠したことを告げられる。だが、グルシャンの子供だと考えたチャンダンはエレナを冷たく突き放す。精神的に極限状態となったチャンダンはアルフィーの亡霊に突進する。すると、アルフィーは現れなくなる。解放されたチャンダンは家に帰る。するとそこにはグルシャンがいた。チャンダンはエレナを妊娠させて知らんぷりをしているグルシャンに憤り、彼に殴りかかる。ところがそこにはグルシャンはいなかった。
実はグルシャンも彼の妄想が生んだ亡霊であった。チャンダンはスバーンギーをグルシャンに取られたとき、グルシャンを駅のプラットフォームから突き落とし殺していたのだった。つまり、チャンダンはアルフィーとグルシャンという死んだ友人の亡霊にずっと悩まされて来たのだった。グルシャンとエレナの情事もチャンダンの妄想でしかなかった。もちろんエレナの子供の父親もチャンダンであった。それが分かったとき、エレナは自殺をしていた。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
主人公チャンダンの不安定な精神状態を極限まで映像で表現した作品。現実と妄想、過去と現在が入り交じり、時に同じ映像が繰り返され、恍惚感を醸し出す。俳優の顔を向いたカメラを俳優に固定して動き回らせ、陶酔感を表現する映像技術は既に「Dev.D」(2009年)で効果的に使われているが、この「Prague」でも採用されており、チャンダンの精神をよく表現していた。それだけでなく、チャンダンに付きまとう亡霊を映像化し、彼の精神が次第に蝕まれて行く様子を追っていた。亡霊はチャンダンの精神の投影であるため、チャンダンに危害を加えることはしない。ただチャンダンの言うことに耳を傾け、時々反応するだけである。チャンダンには、アルフィーとグルシャンという2人の亡霊と付き合う内に、彼らの性格が乗り移って来る。しかしチャンダンは現実と妄想の区別が付かないために、自分でない性格のときは自分自身がその行動をしていることに気付かない。この辺りはハリウッド映画「ファイト・クラブ」(1999年)にも似ていた。
舞台は前半がムンバイー、後半がプラハとなる。チャンダンは建築を学びにプラハに留学するのだが、留学先がプラハである必要性は特に感じなかった。異国情緒は出ていたし、精神描写で暗くなりがちな映画の雰囲気に明るさをもたらしていたが、別にインド国内または他の国であっても問題はなかっただろう。
主演のチャンダン・ロイ・サンニャルは「Kaminey」(2009年)のミカイル役で一躍注目を浴びた俳優である。精神を蝕まれて行く様子をよく表現できていたと思う。グルシャンを演じたクマール・マヤーンクもカリスマ性のある俳優であったが、あまり情報がない。
「Prague」は、トラウマを抱えた主人公の次第に蝕まれて行く精神を映像化した作品。映像効果や脚本に自信を感じたが、全く目新しいものではない。それでもよく出来た作品だったと言える。
| ◆ |
8月4日(土) Gangs of Wasseypur II |
◆ |
今回のオシアン・シネファン映画祭の目玉のひとつはアヌラーグ・カシヤプ監督の「Gangs of Wasseypur」であった。5時間以上に及ぶこの映画は、カンヌ映画祭の監督週間ではぶっ続けで上映されたのだが、インドでの一般公開では2部に分割されての上映となっている。パート1は既に6月に公開されており、「これでインディア」でも批評をした(参照)。パート2は8月8日に公開予定である。だが、オシアン・シネファン映画祭ではパート1とパート2を通して上映が行われることになっていた。パート2は今までカンヌ映画祭でしか上映されておらず、これがインド・プレミアとなる。アヌラーグ・カシヤプ監督は、自身のデビュー作「Paanch」がオシアン・シネファン映画祭でのみ上映してもらえた恩もあり、「Gangs
of Wasseypur II」のインド・プレミアをこの映画祭に捧げた。チケットを手に入れるために多少苦労したが、無事にチケットを入手できた。会場にはアヌラーグ・カシヤプ監督、脚本家ズィーシャーン・カードリー、女優リチャー・チャッダー、リーマー・セーン、フーマー・クレーシーなどが来場しており、客席にはラジャト・カプール、ヴィナイ・パータク、ランヴィール・シャウリーなど演技派として知られる俳優たちの姿が見えた。非常にいい雰囲気の中で鑑賞することができた。
題名:Gangs of Wasseypur II
読み:ギャングス・オブ・ワーセープル・ツー
意味:ワーセープルのギャング2
邦題:ワーセープルのギャング2
監督:アヌラーグ・カシヤプ
制作:アヌラーグ・カシヤプ、スニール・ボーラー
音楽:スネーハー・カンワルカル
歌詞:ヴァルン・グローヴァー
出演:ナワーズッディーン・スィッディーキー、リチャー・チャッダー、リーマー・セーン、ピーユーシュ・ミシュラー、ジャミール・カーン、ティグマーンシュ・ドゥーリヤー、フーマー・クレーシー、サティヤ・アーナンド、パンカジ・トリパーティー、ヴィピン・シャルマー、ヴィニート・クマール、ラージクマール・ヤーダヴ、ズィーシャーン・カードリー、アヌリター・ジャー
備考:スィーリー・フォート・オーディトリアム1で鑑賞。オシアン映画祭。

左からズィーシャーン・カードリー、ナワーズッディーン・スィッディーキー、
ピーユーシュ・ミシュラー
| あらすじ |
サルダール・カーンの死後、長男のダーニシュ・カーン(ヴィニート・クマール)は復讐に乗り出した。サルダールを殺した何人かの暗殺者は殺したのだが、ダーニシュはスルターン・クレーシー(パンカジ・トリパーティー)に殺されてしまう。次男のファイザル・カーン(ナワーズッディーン・スィッディーキー)はますます大麻中毒になっていたが、母親から一喝され、祖父と父と兄の仇を討つことを誓う。ファイザルはスルターンの部下ファズルーを惨殺し、以後ワーセープルで恐れられるようになる。ファイザルは製鉄工場を建て、鉄の商売を始める。また、インド鉄道から払い下げの車両を買い取り、分解して売却する商売にも進出し、莫大な利益を手にするようになる。しかしファイザルは力尽くで稼ぐしか能がなく、基本的にビジネスの才能がなかった。それを見てファイザルに取り入ったのがシャムシャード(ラージクマール・ヤーダヴ)であった。シャムシャードはファイザルを騙してマージンを稼ぐようになる。しかしそれもすぐにファイザルにばれてしまう。すると一転してシャムシャードはファイザルに反旗を翻し、ファイザルの不正を警察に密告する。ファイザルは逮捕され、刑務所に入れられる。ちょうどダンバードが新しいジャールカンド州の一部になった頃の話である。
一方、サルダールの三男パーペンディキュラー(アーディティヤ・クマール)はまだ14歳だったが、あまりに好き勝手に振る舞うため、ワーセープルの住民から恐れられていた。四男のタンジェントと共に店を荒らし回っていた。また、サルダールの二番目の妻ドゥルガー(リーマー・セーン)の息子デフィニット(ズィーシャーン・カードリー)も人々から恐れられていた。スルターンはワーセープルの住民たちからパーペンディキュラーの暗殺を頼まれ、実行する。ちょうどパーペンディキュラーが殺された日、ファイザルは逮捕された。このときまでにファイザルはモホスィナー(フーマー・クレーシー)と結婚しており、刑務所の中から携帯電話でモホスィナーと話し、寂しさを紛らわせていた。
デフィニットは拳銃を持って、ファイザルを裏切ったシャムシャードの家に復讐に押し入るが、拳銃が弾詰まりを起こし、逃げ出す。逃亡する中でデフィニットは軍人が乗車する列車の車両に迷い込んでしまい、逮捕されてしまう。デフィニットもファイザルが入所する刑務所に入れられる。出所したデフィニットは早速シャムシャードに会いに行き、彼に手榴弾を投げつける。シャムシャードは片足を失う大怪我を負い、病院に入院する。デフィニットがシャムシャードの家を爆破するところを目撃したスルターンは、ファイザルの家に殴り込む。そこで故ダーニシュと結婚した妹シャマー・パルヴィーン(アヌリター・ジャー)と再会する。スルターンは妹が自分の忠告を聞かずにダーニシュと結婚したことに今でも怒っており、彼女を容赦なく殺す。ギャング同士の抗争が続くワーセープルで女性が殺されたのはこれが初めてのことだった。
時は2004年になっていた。ファイザルが出所することになった。カーン家の宿敵ラーマーディール・スィン(ティグマーンシュ・ドゥーリヤー)にファイザル暗殺を命じられたスルターンは先手を打つために、ファイザルが出所した日の夜に彼の屋敷を襲撃する。この襲撃でファイザルとその家族に被害はなかった。だが、スルターンの手下はナースィル・アハマド(ピーユーシュ・ミシュラー)の息子アスガル(ジャミール・カーン)とファイザルの母親ナグマー(リチャー・チャッダー)を白昼市場の真ん中で殺す。デフィニットと、ファイザルの忠実な部下グッドゥーは、スルターンが隠れ住むバーガルプルまで行ってスルターンを殺す。だが、デフィニットは警察に逮捕され、パトナーの刑務所に送られる。
州議会選挙が近付いていた。この頃ファイザルの下ではイクラークという男が参謀となっていた。イクラークは過去の因縁からサルダールに恨みを持っており、ラーマ-ディールと密通していた。イクラークはファイザルに、ワーセープルから立候補することを勧めたが、ファイザルはラーマーディールの対抗馬としてダンバードから立候補することを決断した。ラーマーディールはパトナー刑務所に服役中のデフィニットを釈放することを決める。ラーマーディールは以前からファイザルとデフィニットの間に亀裂を生じさせようと画策しており、それを利用する機会がやって来たのだった。ラーマーディールは息子のJPスィン(サティヤ・アーナンド)をデフィニットのところへ送る。ところがJPスィンは父親暗殺をデフィニットと共謀する。
釈放されファイザルのところへ戻って来たデフィニットは、イクラークがラーマーディールと密通しており、選挙当日にファイザルを殺そうとしていることを明かす。ファイザルはイクラークの誘いにわざと乗り、デフィニットに彼を殺させる。だが、このときグッドゥーが怪我を負ってしまう。
ファイザルは最後の戦いに出掛ける。その前に妻のモホスィナーから妊娠していることを告げられるが、ファイザルの決意は変わらなかった。デフィニットはラーマーディールに電話をし、ファイザルを殺したと嘘の情報を流す。そのときラーマーディールはシャムシャードを見舞いに病院に来ていた。ファイザル、デフィニット、タンジェント、そして手負いのグッドゥーは大量の銃器を持ち、救急車に乗って病院へ向かう。ラーマーディールは手下に応戦させるが、全員ファイザルらに殺されてしまう。観念したラーマーディールは銃を捨て便器に座り込む。ファイザルは容赦なくラーマーディールに銃弾を浴びせ掛け、3代に渡る復讐を果たす。
ファイザルがラーマーディールを殺すまでに病院は警察に包囲されていた。タンジェントとグッドゥーは警察との銃撃戦の中で命を落とし、ファイザルとデフィニットは逮捕される。途中、チャーイ休憩があった。デフィニットはチャーイを飲みに車を降りる。だが、デフィニットはすぐに戻って来てファイザルを殺す。デフィニットを待っていたのはJPスィンと母親ドゥルガーであった。ドゥルガーはサルダールに捨てられたことに根強い恨みを抱いており、サルダールの一家を根絶やしにすることを人生の目標としていた。その夢をデフィニットが果たしたのだった。
だが、ひとつだけ誤算があった。時は2008年。ワーセープルから流れて来たナースィルとモホスィナーは、ムンバイーのスラムで一緒に暮らしていた。モホスィナーはファイザルの子供を産んでいた。サルダールの血はまだ残っていた。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
「酔い」――「Gangs of Wasseypur」を通して見て感じたのはこの一言だ。この映画には「酔い」がある。観客は誰しもが、地方で繰り広げられる血で血を洗う凄惨な復讐劇に呑み込まれ、あたかも自分が映画の中の登場人物に、もしくは歴史の生き証人になったかのような錯覚に陥る。誰もが映画館を出るときはサルダール・カーンとなり、ファイザル・カーンとなり、デフィニット・カーンとなり、肩で風を切って歩き出す。1941年に始まって2008年に終わるこの物語は、見た者の脳裏にこのおよそ70年の時間の流れを「記憶」として擦り込む。フィクションでありながら、まるで本当の歴史を垣間見た気分にさせられる。強力な文学作品のみが持つそのような魔力を、「Gangs
of Wasseypur」も明らかに持っていた。ストーリーの力、映像の力、台詞の力、音楽の力、映画を構成するありとあらゆる要素が力を持っており、観客を掴んで離さない。この「酔い」を映画に加えることに成功した若きアヌラーグ・カシヤプ監督は、今やインド映画最高の映画監督の一人に数えられてもおかしくはない。「Gangs
of Wasseypur」によってインド映画はまたひとつの転機を迎えたと言える。
インドにおいてギャングがどのように生まれ発展して行ったのか、「Gangs of Wasseypur」ほど深く分かりやすく描いた作品はないだろう。一方で、炭坑の請負人が労働者組合のまとめ役となり、労働者を搾取し政府を欺きながら暴利を貪って政治家に転身し、大臣となって表と裏の世界に絶大な影響力を持つようになる姿が描かれ、他方で一介の流れ者の家系が、炭坑労働者、ジープ運転手、スクラップ工場、漁業の総元締め、製鉄工場、競売支配などを経て、絶大な権力を持つギャングとなって行く。
ギャングが持つ武器も時代の変遷と共に発展して行く。当初武器は刃物のみであった。だが、火薬を使った爆弾が導入され、やがて拳銃が一般的になって行く。カッター(国産拳銃)は信頼性が低く、外国から密輸された拳銃が徐々にギャングの手に渡って行く。最終的には自動小銃AK-47が主流となり、ギャングたちは絶大な火力を手にして全面戦争に突入して行く。
さらに面白いことに、ストーリーの進展と共に登場人物の家に家電製品などが揃って行く。冷蔵庫、掃除機、圧力釜、ポケベル、携帯電話、衛星受信のテレビなど、さりげなく時代を象徴する品物が小道具として登場する。最終的にはインターネットが登場し、ギャングがそれを活用するところが描写される。各時代を象徴する映画もさりげなく登場し、オマージュが捧げられている。
それでいて、最も重要な人間ドラマは決してお座なりになっていなかった。むしろ人間ドラマが中心の映画であった。ここまで各登場人物を力強く描写した映画は他にそうないだろう。パート1のサルダール・カーンとナグマー・カートゥーン、パート2のファイザル・カーンとデフィニット・カーンは非常に強力なキャラクターであるし、全編を通してラーマ―ディールの存在感は圧倒的だし、語り手となっているナースィルの立場――特にナグマーとの関係――も非常に興味深い。そして単なる復讐劇に留まっていない点がいい。サルダール・カーンは、ラーマ―ディールが父親の仇だと知った後、頭髪をそり落とし、仇を取るまで髪は伸ばさないと誓う。しかしながら彼は銃で撃ってラーマ―ディールを手っ取り早く殺す方法は採らない。ラーマ―ディールの権力と名誉をひとつひとつそぎ落とし、彼が自らもんどり打って命を絶つような方法を模索する。サルダールが殺された後は、次男のファイザルが復讐の後を継ぐ。ファイザルも当初はラーマ―ディールをすぐには殺さない。権力闘争と言う一種のゲームの中でラーマ―ディールを苦しめようとする。この絶妙な勢力均衡は、シャムシャードという部外者の乱入によって崩れ、ラーマ―ディールとファイザルは全面戦争に突入する。パート1では牧歌的に見えたこの闘争も、パート2では激化するのだが、どこか敵同士でありながら男と男の間の無言のルールを守って殺し合いを繰り広げるところが、他のインド製ギャング映画と異なるところであった。そしてより現実味を感じた。
サルダールとファイザルの復讐劇を「表」とするならば、ドゥルガーとデフィニットの復讐劇は「裏」であり、結末を見るとこの映画全体の核心でもあった。ドゥルガーはサルダールの二番目の妻で、事実上は妾である。サルダールは非常に性欲の強い男で、しかも繁殖能力に優れていた。妻を次から次へと身ごもらせてしまうのだが、妊娠中は性交を断られるため、売春宿に通ったりして性欲を発散させていた。そんな彼が、妻の妊娠中かつ逃亡生活中に見初めたのがドゥルガーであった。サルダールは妻ナグマーや子供をほったらかしにしてドゥルガーとの情事に没頭する。ところがドゥルガーが妊娠すると、サルダールは途端に彼女から離れてしまう。ドゥルガーはサルダールに深い恨みを抱くようになり、自分の子供を「デフィニット(definite)」と名付けた。これは、サルダールを殺すという「明確な(=デフィニット)ミッション」を持って生まれたことを意味している。サルダールの死後は、サルダールの遺産であるワーセープルの支配権を手にすることがドゥルガーとデフィニットの目的となる。そもそもラーマ―ディールがサルダール亡き後ドゥルガーとデフィニットの生活を助けていたのである。成長したデフィニットは、異母兄となるファイザルに協力しながらチャンスをうかがう。結果的に彼はラーマ―ディールの息子JPスィンと結託し、ラーマ―ディールとファイザルの両者を同時に消し去ることに成功する。復讐の応酬が続くこの映画の中で、最終的に復讐に成功したのはデフィニットであった。デフィニットのキャラクターは、「マハーバーラタ」の影のヒーロー、カルナと比較することも可能であろう。
「Gangs of Wasseypur」は、一見すると暴力映画でありながら、映画の底辺で一貫して投影されているのは因果応報という哲学である。登場人物の誰しもが因果応報から逃れられていない。サルダールがもしドゥルガーという妾を作っていなければ、デフィニットも生まれず、彼の王国が崩れることもなかっただろう。ラーマ―ディールは生き残るためにシャーヒド・カーンやサルダール・カーンなどを殺した。殺さなければ殺されるという状況に身を置かれていたからだ。だが、それもそもそもは労働者を搾取して金を儲けようとした彼自身の身から出た錆びであった。パルヴィーンは兄スルターンを裏切ったためにスルターン自身の手で殺される。パーペンディキュラーはあまりの横暴さに近隣住民から嫌がられ、殺されてしまう。全ての行動が何らかの結果を伴う姿が全編を通して描かれていた。そして最後のムンバイーのシーン、ファイザルの息子が育っていることが示されるシーンで、まだその因果応報の連鎖が終わっていないことが暗示されていた。
前述の通り、あらゆる要素にパワーがあるのだが、何より強力なのは台詞であった。「サルダール・カーンだ、オレの名前は!皆に伝えておけ!」、「ここはワーセープルだ。鳩も片方の羽根で飛び、もう片方の羽根で自分の尊厳を守っている」、「インド人は映画を見続ける限り、アホのままだ」などなど、この映画からは数々の名言が出て来ている。中でも流行語となっているのが「Kehke
Lunga」である。文字通りの意味では「言ってから取る」であるが、意訳するならば「予め忠告してからお前の尊厳を奪ってやる」みたいな意味になる。
技術的な面でも光るものがある。緊迫感溢れるシーンでカシヤプ監督は長回しを多用していた。その中でも、2004年、スルターンがファイザルの屋敷を襲撃するシーンとファイザルがスルターンの襲撃から逃げるシーンは非常に印象的だ。その一方で、クロスカッティングのテクニックを使って緊迫感を出しているシーンもあった。デフィニットとグッドゥーがスルターンを殺すシーンはその代表例である。ラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督は奇をてらったカメラワークが行き過ぎて映画鑑賞の支障となっているが、アヌラーグ・カシヤプ監督は正に適材適所のカメラワークで、各シーンを盛り上げていた。
5時間以上の映画の中で数百人の登場人物が登場する。その誰もがリアルであり、まるでこの役を演じるために生まれて来たようである。パート1とパート2を通し、演技の面で特に高く評価できるのはマノージ・パージペーイー、ティグマーンシュ・ドゥーリヤー、ナワーズッディーン・スィッディーキー、リチャー・チャッダーなどで、それ以外の俳優も素晴らしい演技をしていた。ここまで各キャラに命を吹き込めたのは、俳優たちの演技力と集中力もあるが、それ以上に監督の指導と情熱によるものだと言える。ちなみにデフィニットを演じたズィーシャーン・カードリーはこの映画の脚本家でもあり、実際にワーセープルの出身である。
新進気鋭の女性音楽監督スネーハー・カンワルカルの音楽も素晴らしい。「Gangs of Wasseypur」の音楽の特徴は「ギャップ」だと言っていいだろう。悲しいシーンに明るい音楽が流れたり、緊迫感溢れるシーンに間抜けな歌声が重ねられたりする。実際の人生において、楽しいときに楽しい音楽が、悲しいときに悲しい音楽が聞こえて来るとは限らない。むしろ、自分の感情とは全く逆の雰囲気の音楽が聞こえて来る方が多いのではないだろうか。そしてそれがまた複雑な感情を呼び起こす。例えばダーニシュが殺されたシーンでの脳天気な音楽は、家族の悲しい気持ちをより明確に浮き彫りにしていた。音楽の使い方においてもアヌラーグ・カシヤプ監督は非常にユニークかつ明確なビジョンを持った監督だと言える。
サントラCDはパート1とパート2に分けて販売されている。個人的にはパート1の方に傑作が多いと感じた。サルダールが殺されるシーンで使われる「Jiya
Tu」、ファイザルが拳銃の密輸に成功するシーンで流れる「Hunter」、サルダールがドゥルガーを口説くシーンで流れる「O Womaniya」、シャーヒドがワーセープルを追い出されるシーンで流れる「Ik
Bagal」、サルダールがラーマ―ディールへの復讐を開始するシーンで流れる「Keh Ke Lunga」など、名曲が揃っている。パート2では民謡的な雰囲気の「Taar
Bijli」がとてもいい。テクノ風の「Chhi-Chha Ledar」は、列車で歌を歌って日銭を稼いでいたドゥルガーという12歳の女の子を起用したユニークな作品。「Moora」では英単語をヒンディー語動詞化するという並外れた実験がなされている。
パート1での批評でも書いたが、「Gangs of Wasseypur」の言語はビハール州の言語ではあるが、映画の舞台となっているジャールカンド州ダンバードの言語ではない。旧ビハール州の西部から中央部で話されるボージプリー方言やマガヒー方言に近い言語である。台詞もナレーションもかなり写実的なしゃべり方をするので、聴き取りは非常に困難だ。今回の上映では英語字幕付きだったので理解の手助けとなった。
「Gangs of Wasseypur」は間違いなく2010年代のヒンディー語映画の金字塔として記憶されることになる傑作。インドにおいて、「ラーマーヤナ」、「マハーバーラタ」に続く叙事詩が完成したと表現しても過言ではないだろう。これぞインド映画の最先端・最高峰だ。アヌラーグ・カシヤプ監督に最大限の賛辞を送りたい。
オシアン・シネファン映画祭のクロージング作品はリトゥパルノ・ゴーシュ監督の「Chitrangada」であった。チケットが手に入ったのでこのベンガリー語映画も鑑賞することが出来た。
リトゥパルノ・ゴーシュと言えば、インド映画界で最も審美眼に長けた映画監督で、彼の作る映画には繊細な情感と詫び寂びのある美しさに満ちていて独特である。ベンガリー語映画が主なフィールドであるが、「Raincoat」(2004年)はヒンディー語、「The
Last Lear」(2007年)は英語の映画だ。他にアイシュワリヤー・ラーイ主演の「Chokhar Bali」(2003年)や、ラーイマー・セーンとリヤー・セーン姉妹が出演する「Naukadubi」(2010年;
ヒンディー語版タイトルは「Kashmakash」)なども基本的にベンガリー語映画でありながら全国的に有名である。また、リトゥパルノ・ゴーシュは「トランスジェンダー」に分類される人物で、男性と女性の狭間におり、彼の性別を明言することは難しい。生まれたときの性は男性で、現在では女性ような姿をしているが、性転換手術を受けた訳ではなく、中間性であることを楽しんでいるようである。
「Chitrangada」の題名ともなっているチトラーンガダーとは、「マハーバーラタ」に登場するマニプラ王国の姫である。放浪中のアルジュンと出会い、結婚して、バブルバーハナという息子を生む。ラヴィーンドラナート・タゴールは1892年にこのチトラーンガダー姫を題材に「Chitrangada」と言う戯曲を書いており、リトゥパルノ・ゴーシュ監督のこの映画も、「マハーバーラタ」のチトラーンガダーではなく、タゴールの戯曲を部分的にベースとしている。タゴールのチトラーンガダー姫は、女性として生まれながら、国王から男性として育てられた人物として描かれている。チトラーンガダー姫は勇猛な戦士に育つが、アルジュンに一目惚れし、彼と結婚するために女性への回帰を望む。チトラーンガダーは愛の神カームデーヴの恩恵を受け、美しい女性に変身する。アルジュンは彼女のその美貌を見て恋に落ちる。ところがチトラーンガダーはアルジュンに、あるがままの自分を受け容れてもらいたいという願望を心の奥底で持っていた。そのときマニプラ王国を侵略者が襲う。チトラーンガダー姫は国民を救うために再び戦士の姿となり、侵略者を撃退する。アルジュンは美女としてのチトラーンガダー姫ではなく、戦士としてのチトラーンガダー姫を気に入り、彼女と結婚する。
タゴールのこの戯曲からも分かるように、チトラーンガダー姫は性同一性の問題を抱えており、リトゥパルノ・ゴーシュ監督が映画「Chitrangada」でテーマとしたのも性同一性である。監督自身が男性と女性の狭間にいるため、彼自身の性の葛藤をそのまま映画化した作品とも言える。しかも主演はリトゥパルノ・ゴーシュ自身である。
題名:Chitrangada
読み:チトラーンガダー
意味:「マハーバーラタ」に登場する姫の名前
邦題:チトラーンガダー姫
監督:リトゥパルノ・ゴーシュ
制作:シュリーカント・モホター、マヘーンドラ・ソーニー
音楽:デーボジョーティ・ミシュラー
出演:アンジャン・ダット、ディーパーンカル・デー、ジシュー・セーングプター、アナスヤー・マジュムダール、ラーイマー・セーン、リトゥパルノ・ゴーシュ
備考:スィーリー・フォート・オーディトリアム1で鑑賞。オシアン映画祭。
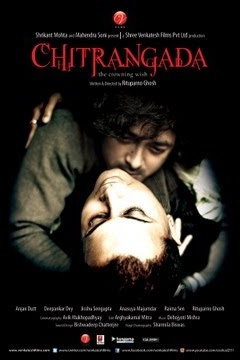
ジシュー・セーングプター(上)とリトゥパルノ・ゴーシュ(下)
| あらすじ |
コールカーターに住む舞踊家ルドラ・チャタルジー(リトゥパルノ・ゴーシュ)は、生物学的には男性として生まれたものの、ジェンダー的には幼い頃から女性であり、恋愛対象も男性であった。ルドラはタゴールの戯曲「Chitrangada」の公演のために準備をしていた。
演劇にはパーカッショニストが必要だった。「Chitrangada」で主演のカストゥーリー(ラーイマー・セーン)は友人のパルトー(ジシュー・セーングプター)を紹介する。ところがパルトーは酷いヘロイン中毒者で、まともに練習もしなかった。ルドラはパルトーを追い出すが、その晩パルトーはルドラの家を訪ねて来る。実はパルトーにも同性愛の趣味があった。パルトーはルドラを誘惑し、2人は恋人同士となる。
瞬く間にルドラはパルトーにのめり込み、将来を考え始める。パルトーが子供好きであることを知ったルドラは、パルトーと結婚し、養子をもらうことを計画する。しかしインドの法律では同性のカップルは養子をもらえない。そこでルドラは性転換手術を受けることを決断する。パルトーは当初から性転換に反対であったし、両親もなかなか息子のその決断を受け容れられなかった。だが、ルドラはドクター・ショームの監督の下、半年に及ぶ手術を受け始める。
まずルドラは乳房移植の手術を受ける。だが、この頃からルドラは睡眠薬に頼るようになり、コンサルタントのシュボ(アンジャン・ダット)に不安を打ち明けるようになる。パルトーも、乳房の付いたルドラの身体を受け容れず、彼の元を去って行ってしまう。さらにパルトーは、しばらく後に、カストゥーリーを妊娠させてしまったことを明かし、そして子供を産んで育てるために金を無心に来る。ルドラはパルトーに金を渡し、追い出す。
女性器形成手術の1日前になった。ルドラの不安は極限まで達していた。シュボとの会話の中で、ルドラは性転換の決断を翻す。ドクター・ショームに電話をし、性転換手術の中止と、移植した乳房の除去をお願いする。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
今回の映画祭でベンガリー語映画の世界にかなり衝撃を受けた。何しろインドを代表する世界的な映画監督サティヤジト・ラーイ(サタジット・レイ)を輩出した映画界であり、リトゥパルノ・ゴーシュ監督の映画も何本か見て来ており、今までベンガリー語映画を評価していなかった訳では決してないのだが、最近のベンガリー語映画の動向については全く無知であった。だが、蓋を開けて見れば、「Gandu」(2010年)や「Cosmic
Sex」(2012年)など、性描写で全く妥協しない映画が作られており、おそらくこの方向性においては全インド映画で最も先進的な実験が行われている。この「Chitrangada」も、過激な性描写こそなかったものの、ジェンダーという複雑な問題を非常に丁寧に、巧みに、そしてインドの文脈において描いており、素晴らしい映画だった。
性は生物学的にも心理学的にも、男性・女性と明確に区別できるものではなく、その間にはグラデーションが存在することはよく知られている。インドでもヒジュラーという、表向きは両性具有者、実際は性同一性障害者のコミュニティーがあり、伝統的にトランスジェンダーの人々の受け皿になって来た。だが、英領時代にインド刑法377条によって同性愛は犯罪とされ、それが独立後も維持されて来た。インドにおいて同性愛が合法化されたのは2009年のことであるが、それもデリーのみ有効のデリー高等裁判所による判決であり、まだまだインドはトランスジェンダーに厳しい国となっている。同性愛者やその他の中間性の人々に対する一般人の偏見も根強い。
「Chitrangada」は、リトゥパルノ・ゴーシュ監督自身の性に対する考え方を映画化した作品だと言える。主人公ルドラの生物学的な性は男性であるが、恋愛や性の対象は男性であり、服装や言動も女性である。だが、彼は性転換をして女性になることまでは望んでいなかった。彼のこの微妙な性の立ち位置が、映画全体を通して説明されたと言っていいだろう。
だが、映画のより大きなテーマは、性同一性を越えて、自己同一性の問題だと言える。ルドラは、恋人のパルトーと結婚し、養子をもらうために、女性に性転換することを決断する。パルトーは子供好きだったが、パルトーと結婚することで当然のことながら彼は子供を生むことができなかった。養子はひとつの選択肢であったが、インドの法律下では同性のカップルは養子をもらえない。そこでルドラは一大決心をしたのだった。
しかしながら、ルドラは男性から女性になることに大きな不安を感じ始める。乳房移植をしてからは、その不安はより大きくなった。彼の性は、あくまで生物学的な男性性の上に築かれた心理学的な女性性であり、性転換手術はその土台を崩すものであった。しかも恋人のパルトーは、部分的に性転換したルドラを捨ててしまう。結局ルドラは女性器形成手術をする前に性転換の決断を翻し、乳房を除去して、元の身体に戻ることを決める。乳房の除去が可能だと知ったとき、ルドラは初めて笑顔を見せる。
何かを得るためには何かを捨てなければならない。だが、自分を捨ててまでそれを得る価値があるのか?我々は常にそれを考えなければならない。ありのままの自分を愛して欲しいという願望は誰にもあるもので、それは化粧や嘘や手術で塗り固められた美や性質では得られないものである。なぜならそのような見せ掛けだけの手段で手に入れた愛は、本当の自分まで届かないものであるからだ。ルドラを通して、自分が自分であり続けることの大切さが主張されていた。
巧みだったのは、タゴールの戯曲「Chitrangada」とクロスオーバーさせてルドラの心情を映像化していたことである。ルドラの感情が揺れ動く有様を、ルドラ自身が演出した演劇のシーンによって表現する。光と影が織り成す演劇の光景は非常に美しく、映画に幻想的なタッチを加えていた。
ルドラが妄想の中で会話をするシュボというコンサルタントの存在も面白かった。ルドラはシュボと会話することで、自分の考えを吐露し、整理し、そして最終的な決断まで至る。シュボと会話をしている中で、ルドラの携帯電話には見知らぬ番号から3つのメッセージが届く。それらも妄想の産物であろうが、ひとつひとつがルドラの決断に影響していた。ひとつめは「飲酒運転が禁止ならば、酒場にはなぜ駐車場があるのか?」、ふたつめは「皆天国へ行きたがっているが、死にたがらないのはなぜ?」、みっつめは「建物(building)が、完成した後も建設中(building)と呼ばれるのはなぜ?」。みっつめの問いにシュボは答える。「なぜなら変化は決して終わらないからだ」。この言葉が、ルドラを性転換手術中止へと導く。
映画監督として名を知られるリトゥパルノ・ゴーシュが俳優としてカメラの前に立つのはこれが初めてではない。「Naukadubi」(2010年)などでも出演している。だが、自身の心理を投影したような映画に自身で主演するのはこれが初めてであろう。男性なのに女性のような装いをしたリトゥパルノ・ゴーシュのことを変人だと考えていたが、彼の性に対する考え方が「Chitrangada」を通してよく分かった。やはり性というのは一筋縄ではいかない問題で、この映画は男性と女性の中間に位置する映画監督がその問題に自ら取り組んだ野心作だと評価できる。リトゥパルノ・ゴーシュの演技も他のプロの俳優に比べて全く遜色ないものであった。
ラーイマー・セーンはヒンディー語とベンガリー語の映画によく出演しており、全国的に名の知られた女優だ。しかし「Chitrangada」の中ではそれほど目立った役ではなかった。より重要だったのは、パルトーを演じたジシュー・セーングプター、シュボを演じたアンジャン・ダット、ルドラの父親を演じたディーパーンカル・デーなどである。ジシュー・セーングプターはベンガリー語映画界の人気スターであり、リトゥパルノ・ゴーシュ監督の過去の作品にも出演している。アンジャン・ダットは本業は歌手で、俳優としてもいくつかの有名な作品に出演している。
「Chitrangada」は、リトゥパルノ・ゴーシュが監督・主演しているばかりか、彼の独白的な作品となっており、性同一性の問題、さらには広く自己同一性の問題にまで踏み込む傑作である。男性と女性の間にある複雑な中間性の実態をよく映像化している。タゴールの戯曲「Chitrangada」とクロスオーバーしたストーリー・演出も見事。リトゥパルノ・ゴーシュ監督の最高傑作と言ってもいいだろう。
当時としては冒険的なエロティック・ホラー映画だった「Raaz」(2002年)の大ヒットを受け、女優の艶めかしい肢体を売りにした「スキン・ショー」映画が大量生産された時代があった。その多くは実のあるストーリーがない駄作で、フロップとして歴史の闇に埋もれて行ったが、いくつかはヒットとなった。その中のひとつが「Jism」(2003年)だった。同映画は、女優の露出度の高さを売りにしていながら、プドゥッチェリー(旧名ポディシェリー)というエキゾチックな舞台とハードボイルドなストーリーのおかげで成功した。当時飛ぶ鳥を落とす勢いだったビパーシャー・バスが主演であるし、ジョン・アブラハムのデビュー作でもあった。
8月3日より公開のヒンディー語映画「Jism 2」は、題名の上では「Jism」の続編となっている。しかし「Jism」との直接のつながりはなく、全く独立した作品だ。この手の「ナンチャッテ続編映画」はヒンディー語映画に多く、「Raaz
- The Mystery Continues」(2009年)、「Murder 2」(2011年)、「Housefull 2」(2012年)、「Jannat
2」などがその一例である。
「Jism 2」には、インド系米国人ポルノ女優として有名なサニー・レオンが主演することで大きな話題となっている。この手の意表を突いたキャスティングによる話題作りはバット・キャンプ(マヘーシュ・バット、ムケーシュ・バット、プージャー・バットなどのチーム)の常套手段だ。監督は「Paap」(2003年)のプージャー・バット。なぜだか知らないが、男優のディノ・モレアがプロデューサーとして名を連ねている。
題名:Jism 2
読み:ジスム2
意味:身体2
邦題:ジスム2
監督:プージャー・バット
制作:ブージャー・バット、ディノ・モレア
音楽:アルコ・プラヴォ・ムカルジー、ミトゥン
歌詞:アルコ・プラヴォ・ムカルジー、マニーシュ・マキージャー、ラシュク、ミトゥン、アヌシャー、アブドゥル・バースィス・サイード
出演:ランディープ・フッダー、アルノーダイ・スィン、アーリフ・ザカーリヤー、サニー・レオン(新人)
備考:PVRディレクターズ・カットで鑑賞。

サニー・レオン(左)とランディープ・フッダー(右)
| あらすじ |
ポルノ女優のイズナ(サニー・レオン)はある日諜報部員アーヤン・タークル(アルノーダイ・スィン)と出会い、1億ルピーの報酬と引き替えに、とある作戦に参加することになり、スリランカへ飛ぶ。そこではアーヤンの上司グル(アーリフ・ザカーリヤー)が作戦の説明をする。現在スリランカには、インド各地でテロを実行するテロリスト、カビール(ランディープ・フッダー)が潜伏しており、イズナの任務はカビールに近付いて情報を盗み出すことであった。なぜイズナが選ばれたかというと、6年前までカビールとイズナは恋仲にあったからである。しかもカビールは今でもイズナのことを愛しているようであった。当時カビールは優秀な警察官であった。だが、ある日忽然と姿を消し、いつの間にかテロリストとしてインドの脅威となっていた。イズナはこの6年間カビールを忘れようと努力して来ており、最初はこの作戦への参加を断るが、最終的には協力を余儀なくされる。
イズナは、カラン・ラージプートと名前を変えたアーヤンと共に、カビールが住む邸宅の向かいに住み始める。カランとイズナは許嫁ということになっていた。イズナは早速カビールと顔を合わせる。確かにカビールであったが、6年前の彼とはだいぶ変わっていた。イズナはカビールに近付こうとするが、カビールの方もグルの居所を察知し、奇襲を掛ける。グルは何とか逃げ出したものの、部下を失ってしまった。カビールに気付かれたことでグルは作戦を中止しようとするが、アーヤンとイズナは続行を求める。
イズナはより積極的にカビールとコンタクトを取るようになる。イズナはカビールを遠くへ呼び出して密会し、その間にアーヤンがカビールの屋敷に忍び込んで情報を探す。だが、カビールは厳重な警備体制を敷いていた上に、アーヤンがカビールのPCから盗み出したのは偽の情報であった。カビールはイズナを疑うが、彼女が銃を突き付けられても頑なに無実を訴えるので、彼女を信頼する。しかし、カビールの忠実な部下サミトは最初からイズナのことを怪しんでいた。
イズナはカビールに、カランを捨てて彼と結婚すると言い出す。カビールもそれを受け容れる。だが、このときまでにアーヤンはイズナを愛してしまっており、イズナがカビールと結婚することには反対だった。だが、グルの命令により、渋々従う。イズナはカビールの家に住み始める。
カビールはイズナを秘密のコテージに誘い、そこに大切に保管されていた彼女との思い出の品を見せる。イズナは、そこにグルたちが探している情報も隠されていることを確信する。一方、アーヤンはサミトの奇襲を受ける。サミトはアーヤンが諜報部員である証拠を掴むが、アーヤンに殺されてしまう。翌朝、サミトがいないことに気付いたカビールは異変を感じ、スリランカを去ることを決断する。イズナはアーヤンに連絡をし、隠れ家のことを伝えようとするが、アーヤンは失恋に沈んでいた。また、カビールは遂にイズナの正体を知ってしまう。
アーヤンの指示により、イズナはカビールを毒殺しようとする。しかし、カビールは過去6年間のことを話し始める。実はカビールはテロの捜査の中で、インドの政治家や高官がテロリストと密通していることを知ってしまう。カビールはそれを知って幻滅し、姿をくらますと同時に、裏切り者を1人1人抹殺し出す。そのためにカビールはインド政府から指名手配されていた。グルも諜報部員ではなく、金で雇われた殺し屋であった。それを聞かされたイズナは信じず、彼を撃って殺す。そして情報を手に入れる。だが、情報を持ち帰ると、グルはイズナを殺そうとして来た。イズナは、カビールが言っていたことの方が正しかったことを知る。だがもう後戻りはできなかった。グルはアーヤンに殺されるが、今度はアーヤンがイズナに、自分と結婚するか死ぬかを迫って来た。イズナは死を選ぶ。だが、彼女はアーヤンも道連れにする。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
いかにもバット・キャンプらしいB級の味付けの映画であったが、ありきたりのストーリーとサニー・レオンの演技のまずさから、いい意味でのB級映画にはほど遠い。正真正銘のB級映画である。
はっきり言ってほとんど何の取り柄もない映画だ。唯一の売りであったサニー・レオンもパッとしない。ポルノ女優と女優は全く別物であることを改めて証明する役割を果たしただけだ。本物のポルノ女優を起用しているものの、「Jism
2」はポルノ映画の範疇に入る映画ではない。多少色っぽいシーンはあるが、大したことはない。劇中でサニー・レオンが演じたイズナはポルノ女優という設定であるが、はっきり言ってかなり純愛の物語であり、ポルノ女優にする必要は全くなかったのではないかとも思った。
国民会議派のベテラン政治家(2011年に死去)アルジュン・スィンの孫アルノーダイ・スィンの演技も冴えなかった。デビュー作「Sikandar」(2009年)や「Yeh
Saali Zindagi」(2011年)ではいい仕事をしていたのだが、「Jism 2」での彼の演技は雑で、未熟なサニー・レオンの救援になっていなかった。ベテラン俳優アーリフ・ザカーリヤーの演技も間が抜けていた。
唯一光っていたのはランディープ・フッダーだ。「Jannat 2」(2012年)で危険な酔っ払い刑事を演じて高い評価を受けたランディープは、この「Jims
2」でさらに精神不安定なテロリスト(実は正義漢)を演じ、さらに磨きを掛けていた。「Monsoon Wedding」(2001年)でのデビュー以来、必ずしも順風満帆なキャリアではなかったが、近年やっと自分の居所を見つけたと見える。危険な香り漂う怒れる男を演じさせたら右に出る者はいない。
音楽監督はアルコ・パルヴォ・ムカルジーとミトゥン。MMクリームによる「Jism」の音楽はヒットしたが、「Jism 2」では音楽にも気合いが入っていなかった。だが、イズナとカビールの再会シーン前に流れる「Maula」は非常に力強い曲だった。歌手はパーキスターンの人気スーフィーロックバンド、ジュヌーンのボーカリスト、アリー・アズマトである。
「Jism 2」は、インド系米国人ポルノ女優サニー・レオンのヒンディー語映画デビュー作という点で話題だが、はっきり言って見所はそれのみで、それすらも見所とは言い難い出来であった。ストーリーもありきたりで容易に予想可能だ。だが、ランディープ・フッダーの演技が良く、それが少しだけ救いになっていた。どちらにしろ、わざわざ見る必要はない中途半端な映画だ。
| ◆ |
8月15日(水) Ek Tha Tiger |
◆ |
2011年には「Ready」と「Bodyguard」という2本の大ヒットを飛ばした人気スター、サルマーン・カーン。2012年の上半期は大人しかったが、独立記念日とイードゥル・フィトルが重なる8月中旬に「Ek
Tha Tiger」を引っさげてスクリーンに戻って来た。ヒンディー語映画界ではイード公開のアクション映画は必ずヒットするというジンクスがあり、ここ数年サルマーン・カーンは「Wanted」(2009年)、「Dabangg」(2010年)、「Bodyguard」(2011年)とイードにアクション映画を故意にぶつけて来ており、それらを着実にヒットさせ続けて来ている。「Ek
Tha Tiger」ももちろんアクション映画である。ヒロインがカトリーナ・カイフである点も話題性たっぷりだ。サルマーン・カーンとカトリーナ・カイフは言わずと知れた元恋人である。2人は2010年に破局している。スクリーン上での共演は、「Ajab
Prem Ki Gazab Kahani」(2009年)や「Tees Maar Khan」(2010年)での特別出演による共演を除けば、「Yuvvraj」(2008年)以来となる。2人は他に、「Maine
Pyaar Kyun Kiya?」(2005年)と「Partner」(2007年)でも共演している。
インドとパーキスターンにはそれぞれRAWとISIと呼ばれる対外諜報機関がある。当然、RAWの仮想敵国はパーキスターンであり、ISIの仮想敵国はインドである。インドの映画においてRAWが題材となることはかつて少なかったのだが、近年急に注目を浴びており、「The
Hero」(2003年)、「Mission Istaanbul」(2008年)や「Agent Vinod」(2012年)など、RAWエージェントが主人公になったり登場したりする映画がちらほら出て来ている。しかしながら、今までRAWが登場する映画はなぜかちっともヒットして来なかった。最近、サイフ・アリー・カーンがRAWエージェントの主人公を演じた「Agent
Vinod」も失敗作に終わったばかりだ。サルマーン・カーンの勢いがどこまで本物か、この「Ek Tha Tiger」はひとつの試金石と言える。
監督はカビール・カーン。「Kabul Express」(2006年)や「New York」(2009年)の監督で、寡作ながら毎回しっかりした映画を作る人物だ。
題名:Ek Tha Tiger
読み:エーク・ター・タイガー
意味:タイガーという男がいた
邦題:タイガー
監督:カビール・カーン
制作:アーディティヤ・チョープラー
音楽:ソハイル・セーン、サージド・ワージド
歌詞:カウサル・ムニール、ニーレーシュ・ミシュラー、アンヴィター・ダット
振付:ヴァイヴァビー・マーチャント、アハマド・カーン
衣装:アルヴィラー・カーン、アシュリー・レベロ、アルン・チャウハーン、アヌーシュカー・ヴェールジー
出演:サルマーン・カーン、カトリーナ・カイフ、ギリーシュ・カルナド、ローシャン・セート、ランヴィール・シャウリー
備考:PVRプリヤーで鑑賞、満席。

カトリーナ・カイフ(左)とサルマーン・カーン(右)
| あらすじ |
凄腕のRAWエージェント、コードネーム:タイガー(サルマーン・カーン)は、イラクでの任務を終えた後、すぐにアイルランドのダブリンへ飛ぶ。今回の任務はこうだった。インドは対ミサイル技術を保有していたが、隣国パーキスターンはまだその技術を確立していなかった。インドにおいて対ミサイル技術の第一人者と言えばアンワル・ジャミール・キドワイー博士(ローシャン・セート)であった。キドワイー博士は現在ダブリンの大学で教えていた。RAWは、キドワイー博士がパーキスターンと接触しているとの情報を入手し、その真偽を確かめるべく、タイガーを派遣したのだった。
タイガーは名前をマニーシュ・チャンドラ、職業を作家と偽って、キドワイー博士に近付く。ダブリンでは、同期のエージェント、ゴーピー(ランヴィール・シャウリー)の後援も受けられた。だが、キドワイー博士は変人で、なかなかタイガーを寄せ付けなかった。タイガーは、キドワイー博士の助手をするインド系英国人女性ゾーヤー(カトリーナ・カイフ)に目を付ける。タイガーはゾーヤーと近付き、信頼を勝ち得る。だが、硬派なタイガーはこのとき初めて女性に恋してしまう。タイガーはゾーヤーに愛の告白もする。
ところが、タイガーはゾーヤーこそがISIのエージェントであることを知ってしまう。ゾーヤーに銃を突き付けたタイガーは、彼女に対する自分の愛は本物だったと明かすが、ゾーヤーは、彼への愛は仕事の一環だったと答える。タイガーは銃を撃つが、彼女に照準は合っていなかった。タイガーはゾーヤーの命を助ける。代わりに、襲って来た別のISIエージェントを殺す。
デリーに戻って来たタイガーは、上司のシェノイ(ギリーシュ・カルナド)にしばしのデスクワークを申し出る。しかし、トルコのイスタンブールで開催予定の外相会議にゾーヤーが来る可能性があることを知り、一転して現場任務に復帰する。イスタンブールでタイガーはゾーヤーと再会する。
実はゾーヤーもタイガーのことを本気で愛していた。タイガーとゾーヤーは、お互いの国や仕事をなげうって逃亡する。シェノイは、タイガーがパーキスターンに誘拐されたと考えるが、後にタイガーはゾーヤーと逃げたことを察知する。RAWとISIは、2人の逃亡先と思われたカザフスターンへ向かうが、そこには2人は現れなかった。2人は完全に行方不明となった。
実はタイガーとゾーヤーはキューバの首都ハバナに来ていた。しばらくは幸せな生活を送るが、地元の悪党と戦っているところを監視カメラにキャッチされ、それがRAWやISIにも知られてしまった。RAWとISIはタイガーとゾーヤーを捕まえるためにハバナへエージェントを派遣する。タイガーとゾーヤーは共に逃げ出すが、ゾーヤーはISIエージェントに捕まってしまう。タイガーはゴーピーがハバナへ来ていることを知り、自ら彼の前に現れて、ゾーヤー救出への協力を求める。ゴーピーとRAWのチームは、パーキスターンへ移送される途中のゾーヤーを奪還する。しかし、タイガーはゴーピーをも出し抜き、ゾーヤーと共に脱出を試みる。RAWとISIはタイガーとゾーヤーを必死で追う。だが、2人はまんまと逃亡してしまう。
その後、タイガー(本名はアヴィナーシュ・スィン・ラータウル)とゾーヤーはRAWとISIのファイルでは行方不明とされた。しかしながら、時々世界各国で2人の目撃情報が寄せられた。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
通常、独立記念日の週に公開される映画は、インド人の愛国心に訴える内容のものが多い。「Mangal Pandey: The Rising」(2005年)や「Chak
De! India」(2007年)などは代表例だ。「Ek Tha Tiger」も、インドの対外諜報機関RAWのエージェントを主人公にし、パーキスターンの対外諜報機関ISIとの諜報戦を描いた作品とのことで、当然のことながらインド万歳的な映画に仕上がっているだろうと事前に予想していた。しかし、驚いたことに、主人公タイガーはインドを裏切り、ISI女性エージェントのゾーヤーと愛の逃避行をしてしまう。愛国心の欠片もない、裏切り者の行動を取ってしまうのである。これには大いに驚かされた。
代わりに「Ek Tha Tiger」で主張されていたのは印パの和平であった。インドとパーキスターンは独立以来、表立って3回戦争をし、1999年には非公式の戦争も戦っている。その後ヴァージペーイー政権時に印パ関係は改善に向かったが、2008年のムンバイー同時多発テロで一気に冷え込んでしまった。現在まで両国はこの事件を引きずっている。
タイガーとゾーヤーの間の禁断の恋愛には、両国の関係が改善し、お互いにRAWとISIが必要なくなるような世の中が早く来るように、とのメッセージが込められていた。今までのアクション映画にありがちだった、パーキスターンを一方的に悪者にして打ちのめし、インド人の愛国心を煽るような種類の映画ではなかった。最近インドでは、多額の汚職や圧政などを巡って、庶民や文化人の間に、政府に対する不満がいつになく蓄積され、時に発露されている。だが、インドという国家に反逆してまでして印パの和平を訴えるようなラディカルな内容の映画は、少なくともメインストリームの娯楽映画では見たことがない。印パの反目は政府レベルの問題であること、庶民レベルでは両国の親善が望まれていることが読み取れ、政府に対する不信が少なからずこの映画から感じられた。そういう意味で、見掛けは大予算型のアクション・ロマンス映画であるが、深く分析すると、非常に世相を反映した映画だと言える。
アクション映画としてもよく出来ていた。冒頭から異国情緒溢れる町並みの中で繰り広げられるスリリングなアクション・シーンがあり、中盤ではロンドンの路面電車を使った派手なパニックシーンが挟まれ、クライマックスではバイクから飛行機に飛び移るという荒技にも挑戦。サルマーン・カーンだけでなく、ヒロインのカトリーナ・カイフも、ISIエージェントという設定に恥じないように、格闘にアクションに奮闘していた。その一方で、RAWエージェントの惨めな日常生活の様子が挿入され、笑いを誘っていた。
ロマンスの部分は多少弱かったと思う。タイガーとゾーヤーは愛のために国や仕事をなげうつ訳だが、そんな極限の行動を取るまで2人の関係が燃え上がったことを暗示するシーンが少なかった。ただ、逃避行中の2人の姿は、さすがに元恋人同士だっただけあり、とても自然で良かった。ゾーヤーは、ハバナの街角で見つけた落書き「狂気のない恋愛は恋愛とは呼ばない」を読み上げるが、正にこれがインドの恋愛の定義であり、「Ek
Tha Tiger」では国家すらも恋愛と言う狂気の前に意味を失ったのである。もちろん、タイガーはゾーヤーに恋した時点では、彼女が敵国の諜報部員であることを知らなかった。だが、恋してしまった後では、国籍や所属などはどうでもいいことであった。敵であることが分かった時点で冷めてしまうような恋愛は恋愛ではないのである。また、タイガーが国家ではなくゾーヤーを選んだのは、上司シェノイの話も関係している。シェノイもかつて恋した女性がいたが、仕事を優先し、その女性を諦めた。彼はそのことを毎日後悔していると語っていた。タイガーは、毎日後悔するような人生を送りたくなかったのである。
サルマーン・カーンの勢いが止まらない。「Ek Tha Tiger」も間違いなく大ヒットすることだろう。彼は役に合わせて演技し分けるタイプの俳優ではないが、カリスマ性はトップクラスだ。そしてそのカリスマ性こそが、インド娯楽映画の重要な要素であることを最近の大ヒット連発で証明し続けている。タイガー役は彼のパーソナリティーとも合っており、適役だった。腕っ節は強いが、どこか抜けたところがあり、ユーモアやチャームがあり、いざとなったら愛のために全てを捧げる。そんなインドの男女の間に根強い理想の男性像を体現するのがサルマーン・カーンである。
カトリーナ・カイフの成長も嬉しい限りだ。僕は「Maine Pyaar Kyun Kiya?」の頃から彼女に注目しており、彼女の出演作ごとに彼女の魅力について書いて来たが、いつの間にかそんなことをしつこく繰り返さなくても、自他共に認めるトップ女優に成長していた。「Ek
Tha Tiger」ではISIエージェントということで、アクションにも力を入れており、走ったり戦ったりする彼女の姿を見ることができる。どこまで彼女自身が演じているのかパッと見分からないが、たとえ大部分がスタントであったとしても、彼女の真摯な努力は見て取れる。エンドクレジット曲「Mashallah」でのベリーダンスも素晴らしい。ただ、ウルドゥー語の発音はもう少し練習が必要であろう。ちなみに、イスタンブールのシーンでの彼女のコスチュームは、絶対にパーキスターンの「美しすぎる外相」ヒナー・ラッバーニー・カルをモデルにしていた。
その他、曲者俳優ランヴィール・シャウリーと、カンナダ語演劇界の重鎮ギリーシュ・カルナドが脇を固めていた。キドワイー博士を演じたローシャン・セートはインド系英国人俳優である。
音楽はソハイル・セーンとサージド・ワージド。世界を舞台にした映画であることを意識して、ロケ地の音楽を採り入れた曲作りに挑戦されていたと感じた。ダブリンでのダンスシーン「Banjaara」はケルト音楽っぽい味付け。ハバナで流れる「Laapata」はサルサっぽい音楽。「Mashallah」はエンドクレジットで流れるために、本編とは関係ないが、トルコが舞台になっていたこともあり、中東の雰囲気である。モロッコ音楽を思い出した。
ロケ地はアイルランドのダブリン、トルコのイスタンブール、キューバのハバナ、そしてインドのデリーなどのようだ。冒頭のイラクのシーンもおそらくトルコで撮られたものであろう。
「Ek Tha Tiger」は、近年当たりに当たっているサルマーン・カーンの最新作で、どこから見ても大ヒットする要素満載のアクション・ロマンス映画である。元恋人カトリーナ・カイフとの久し振りの本格的共演も見所。独立記念日公開作品なのに、国よりも愛を取るプロットなのも意外性があっていい。サイフ・アリー・カーンの「Agent
Vinod」より数倍楽しいスパイ映画である。必見。
| ◆ |
8月24日(金) Shirin Farhad Ki Toh Nikal Padi |
◆ |
インドでは様々な宗教が信仰されているが、その中でもパールスィー(拝火教徒)のコミュニティーは、人口が少ない割には社会的な影響力が強く、特異である。拝火教はイランで生まれイラン文化圏で発展した宗教だが、イスラーム教の誕生とアラブ人によるイランの征服後に衰退し、10世紀頃にはまとまった数の拝火教徒たちが、イスラーム教への改宗や殺戮を逃れるためにイランからインドにやって来た。亡命して来た拝火教徒が最初に定住したのがグジャラート地方であったため、拝火教徒の多くはグジャラーティー語をしゃべる。その後、英国人がボンベイ(後のムンバイー)に入植すると、多くの拝火教徒がそこへ移り住み、新都市建設の主な担い手となった。ヒンディー語映画の中心地はムンバイーであり、歴史的に多数の拝火教徒たちが演劇や映画制作に関わって来たため、ヒンディー語映画においても拝火教徒のプレゼンスは人口に比べたら非常に高い。「イーラーニー」や「○○ワーラー」という名字の人は大体パールスィーであるが、ヒンディー語映画界にはそのような名字を持つ人がやたら多い。そうでなくても、血統を調べてみると、実はパールスィーの血を引いていたと言う人はさらに多い。もっとも、パールスィーの伝統では、拝火教徒の両親から生まれた子供でなければ完全な拝火教徒とは認められない。
このように、映画俳優や監督などに拝火教徒が多いこともあって、拝火教徒を主人公にしたヒンディー語映画も少なくない。例えば「Being Cyrus」(2005年)、「Parzania」(2007年)、「Little
Zizou」(2008年)、「Ferrari Ki Sawari」(2012年)などは拝火教徒の家庭に焦点を当てた映画であるし、その他にも、主人公ではないものの拝火教徒の登場人物が登場する映画はとても多い。
本日より公開の「Shirin Farhad Ki Toh Nikal Padi」も、拝火教徒の家庭を描いた作品である。ロマンス映画はロマンス映画でも、中年の独身カップルのロマンスがテーマと言う変わった風味の映画。プロデューサーは「Devdas」(2002年)などで有名なサンジャイ・リーラー・バンサーリー。圧倒的な美的センスを見せ付けるような芸術的娯楽映画を長らく作り続けて来たのだが、最近になってライトなノリの映画にも手を出している。今年の大ヒット作品「Rowdy
Rathore」(2012年)も彼のプロデュースである。「Shirin Farhad Ki Toh Nikal Padi」の監督は、サンジャイ・リーラー・バンサーリーの妹ベーラー・バンサーリー・セヘガル。主演はボーマン・イーラーニーとファラー・カーンである。ボーマン・イーラーニーはその名の通り拝火教徒であり、今回は適役と言える。だが、ヒロインのファラー・カーンは特殊だ。元々優れたコレオグラファーとして知られた彼女は、「Main
Hoon Na」(2004年)や「Om Shanti Om」(2007年)などの大ヒット作も監督しているし、テレビでの露出も多く、多彩な活躍を見せている。彼女がスクリーンに登場するのはこれが初めてではないのだが、今まではカメオ程度の出演であり、本作が本格女優デビューとなる。実はファラー・カーンの母親が拝火教徒であり、彼女も拝火教徒の血を引いていることになる。
ちなみに「シーリーンとファルハド」とは、イランに伝わる悲恋物語である。シェークスピアの「ロミオとジュリエット」のイラン版だと考えても差し支えない。もっとも、この映画はシーリーンとファルハドの物語をベースにしていない。たまたま出会った2人の中年独身男女の名前が、ちょうど有名な悲恋物語の主人公2人と同じだったという伏線のみである。
題名:Shirin Farhad Ki Toh Nikal Padi
読み:シーリーン・ファルハド・キ・ト・ニカル・パリー
意味:シーリーンとファルハドはうまくやった
邦題:シーリーンとファルハド
監督:ベーラー・バンサーリー・セヘガル
制作:サンジャイ・リーラー・バンサーリー、スニールAルッラー
音楽:ジート・ガーングリー
歌詞:アミターブ・バッターチャーリヤ、ファラーズ・アリー
衣装:サブリーナー・スィン
出演:ボーマン・イーラーニー、ファラー・カーン(新人)、カヴィーン・デーヴ、シャンミー、クルシュ・デーブー、デイジー・イーラーニー
備考:DTスター・プロミナード・ヴァサント・クンジで鑑賞。
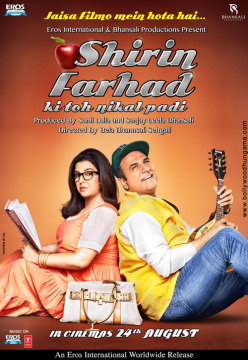
ファラー・カーン(左)とボーマン・イーラーニー(右)
| あらすじ |
ムンバイーに住む45歳独身の拝火教徒ファルハド(ボーマン・イーラーニー)は、同居する母親ナルギス(デイジー・イーラーニー)や祖母からしつこく早く結婚するようにせかされながらも、なかなか理想の女性を見つけられずにいた。大きな障害となっていたのは彼の職業だった。彼は女性用下着店の店員であり、それを聞いたお見合相手は必ず縁談を拒否して来ていた。
あるときファルハドが勤める店にシーリーン(ファラー・カーン)という中年女性が下着を買いにやって来た。ファルハドは一目惚れし、彼女に必死でセールスする。その後も拝火教徒コミュニティーのお見合いパーティーで彼女と再会するが、電話番号ばかりか、彼女の名前を聞くのを忘れてしまう。シーリーンは、運命が巡り合わせたらそのときは電話番号を教えると言い残し去って行く。
ところでファルハドの家は父親の代から違法の貯水タンクを設置していた。それがここに来て問題となり、パールスィー・トラストから違法タンクを撤去するためにオフィサーがやって来た。ナルギスはカンカンになり、ファルハドをオフィスへ送って苦情を届けさせる。ところが、違法タンクの撤去を命じた張本人がシーリーンであった。ファルハドは母親からの厳命を忘れてシーリーンとの会話に没頭し、2人はデートを重ねるようになる。
ファルハドに恋人が出来たことを知ったナルギスと祖母は大喜びする。しかしファルハドは、シーリーンがパールスィー・トラストのオフィサーであることは明かしていなかった。ある日ファルハドはシーリーンを母親と祖母に紹介する。だが、話をしている内にナルギスは彼女がパールスィー・トラストのオフィサーであることを察知し、食べ物を喉に詰まらせてしまう。このことがきっかけでナルギスはシーリーンを忌み嫌うようになる。しかし、祖母はファルハドの味方であった。
シーリーンもある日ファルハドを家に招く。シーリーンには父親がいたが、長年昏睡状態にあった。シーリーンは毎日父親の看病をしており、それが今まで結婚できなかった大きな理由であった。ファルハドは、彼女の父親を看病することを約束し、彼女に結婚を申し込む。シーリーンもそれを受け容れる。シーリーンには姉もいたが、彼女もファルハドを妹の夫として認める。
ところが、ナルギスは何とかしてファルハドとシーリーンの仲を裂こうとしていた。ある日ファルハドとナルギスはシーリーンとの結婚を巡って喧嘩をする。そのときちょうどシーリーンの父親の容体が急変した。シーリーンはファルハドに電話をしたが、母親と喧嘩中だったファルハドはその電話になかなか出ず、やっと出ても冷たい言葉を一方的にぶつけるだけだった。シーリーンの父親は何とか命を取り留めるが、シーリーンはファルハドとの婚約破棄を決意する。2人の仲は急に疎遠になってしまう。
ところがファルハドは諦めなかった。大晦日の日、シーリーンをデートに誘う。最初シーリーンは拒絶しようとしたが、姉の勧めに従ってデートを受け容れる。しかし、シーリーンを迎えに来たファルハドは覗き魔と間違えられてしまい、近所の住民から警察に突き出されてしまう。やっとのことで解放されシーリーンの家に辿り着いたのは元旦の朝だった。だが、2人はなぜか平穏な気持ちだった。昏睡状態の父親の前でファルハドはシーリーンに改めてプロポーズをする。すると、突然父親が目を覚ます。
こうしてファルハドとシーリーンは何重もの幸せの中、結婚をする。ナルギスもとうとうシーリーンを受け容れたのだった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
恋愛の主体が中年の独身男女だという点を除けば、ロマンス映画の王道に則った作品だった。しかしながら、拝火教徒コミュニティーを中心に、コメディーを織り混ぜながら丁寧にストーリーを紡いでおり、非常に安定したラブコメ映画となっていた。突出した部分はないが、安心して楽しめる映画である。
日本でも晩婚化、未婚者人口の増加、少子化そして高齢化社会の問題が取り沙汰されて久しいが、これらの問題において、日本よりも深刻な危機に直面しているとされるのが拝火教徒コミュニティーである。拝火教徒の全人口のおよそ7割はインドに住んでいるとされており、拝火教徒の問題はインドの拝火教徒の問題と捉えても問題ないだろう。2001年の国勢調査によると、インドの現在パールスィー人口は7万人弱であり、独立直後と比べると4割ほど減少していることになる。コミュニティー内での結婚を義務づける風習、女性の高学歴化と社会進出、遺伝子的な問題など、その理由は様々であるが、生涯未婚の人口が比較的多く、結婚しても子供を多く作らないことが、人口減少の直接の原因となっている。インド全体の人口ピラミッドは完全に「富士山型」であるが、インドの拝火教徒コミュニティーだけを抽出すると、日本などの先進諸国でよく見られる「壺型」のグラフとなる。未婚問題だけを切り取っても、おそらく拝火教徒コミュニティーが抱える問題は、日本とそう遠くないはずである。拝火教徒コミュニティーを描くことで、日本人にも共感しやすい内容の作品が出来上がってしまうところは面白い。
ただ、「Shirin Farhad Ki Toh Nikal Padi」のファルハドとシーリーンが中年になるまで結婚をしなかった理由は、特に宗教やコミュニティーの事情とは関係ないということになっていた。ファルハドは女性用下着店の店員だったため、お見合い相手から敬遠されていたのだった。一方、シーリーンには昏睡状態の父親がおり、彼の看病をしなくてはならなかっために婚期を逃してしまっていたのだった。それでも、台詞やストーリーの端々から、拝火教徒コミュニティーの人口減少の問題が取り上げられていた。
全体的にはとてもよくまとまったラブコメ映画だったが、いくつか疑問点もあった。ファルハドがシーリーンに一目惚れするところは、もう少し明確な理由が欲しかった。一旦ファルハドと婚約破棄したシーリーンが、ファルハドのデートの誘いを比較的簡単に受け容れてしまうところも、もう少し説明が必要だと感じた。大人のラブストーリーだからと言って、微妙な感情の機微を省いてしまっているようなところがあり、そこは責められて然るべきであろう。インド映画の伝統に則ってダンスシーンもいくつか挿入されていたが、その内のほとんどは蛇足に感じた。もっとも、ヒロインのファラー・カーンは本業がコレオグラファーであり、彼女を踊らせない訳にはいかなかったという理由もあったことだろう。
ボーマン・イーラーニーは芸幅の広い演技派男優として既にその名を確立させており、彼の演技力については改めて語る必要はない。ただ、脇役や悪役としての出演がほとんどだった中で、今回は正真正銘の主演であり、ボーマン・イーラーニーにとっては、主演作に近い「Well
Done Abba」(2010年)と並んで、思い入れの深い作品になったのではないかと思う。
ファラー・カーンは全く演技をしていなかったと思う。普段の彼女がそのままスクリーンにいた感じだ。それは決して悪いことではない。さすがにコレオグラファーと監督をこなして来た人物だけあって、カメラの前で度胸が据わっているのだろう。今回の女優デビューはおそらくお遊びで、振り付けと監督業に専念すると思うが、女優としてやって行くなら、個性的な脇役が似合うだろう。
その他の俳優の中で特筆すべきは、ナルギスを演じたデイジー・イーラーニーだ。彼女はファラー・カーンの母方の叔母にあたり、拝火教徒として生まれている。ただ、ヒンドゥー教徒と結婚し、後にキリスト教に改宗しているようで、現在の宗教はよく分からない。ジャーヴェード・アクタルの元妻ハニー・イーラーニーの妹で、ハニーとデイジーの「イーラーニー・シスターズ」は50年代から60年代に掛けて子役として大人気だった。体格もそうだが、表情も非常に迫力のある女優である。
音楽はジート・ガーングリー。前述の通り、「Shirin Farhad Ki Toh Nikal Padi」のほとんどのダンスシーンは蛇足に感じた。唯一、「Ramba
Mein Samba」は「Dilwale Dulhania Le Jayenge」(1995年)、「Kuch Kuch Hota Hai」(1998年)、「Kabhi
Khushi Kabhie Gham」(2001年)など過去の大ヒット作品のパロディーになっていて、ちょっとした楽しみはあった。エンディングの、ファルハドとシーリーンの結婚式で流れるタイトルソングもノリノリの曲でいい。
「Shirin Farhad Ki Toh Nikal Padi」は、ヒンディー語映画界で時々作られる拝火教徒映画の一種で、突出した部分はないが、よくまとまった中年ラブコメである。コレオグラファー兼映画監督として知られるファラー・カーンが本格女優デビューしている点にも注目。見て損はないが、見なくても損ではないという立ち位置の映画だ。
| ◆ |
8月26日(日) 「Devdas」について |
◆ |
2012年10月6日-12日まで、東京と大阪でインディアン・フィルム・フェスティバル・ジャパン(IFFJ)が同時開催される予定で、多数のヒンディー語娯楽映画が一挙に公開される。今年公開されたばかりの最新作もあれば、多少古めのものもあるが、どれも21世紀の作品であり、ヒンディー語映画界が今世紀にどのような発展を遂げたのか、概観するのにちょうど適したラインナップとなっている。毎年開催予定とのことで、もしかしたら日本に最新ヒンディー語映画を紹介するプラットフォームとして定着して行くかもしれない。その点で非常に期待している。
縁あって僕も日本語字幕の面でIFFJに協力することになり、数本の映画の字幕を担当した。字幕付け・字幕翻訳に関しては全くの素人で、どの程度自分が訳したものが最終的に使われるのか不明なのだが、少なくとも自分が担当した分については、DVDなどに付いて来る英語字幕からの重訳ではなく、ヒンディー語の台詞・歌詞からのダイレクトな翻訳を心掛けた。
その中で、担当することができて一番嬉しかったのはサンジャイ・リーラー・バンサーリー監督、シャールク・カーン、アイシュワリヤー・ラーイ、マードゥリー・ディークシト主演の「Devdas」(2002年)であった。2002年はヒンディー語映画界の外れ年で、多くの映画がフロップに終わったのだが、その中で「Devdas」だけは大ヒットとなり、映画賞も総なめし、同年を代表する作品となった。バンサーリー監督の類い希な美的センスが光る作品でもあり、「いかにもインド」と言った豪華絢爛な世界や舞踊がスクリーン上を埋め尽くし、見る者を魅了する。おそらくこの「Devdas」は、海外において「インド好き外国人」「ボリウッド好き外国人」を大量に生産する原動力となった代表的作品でもあろう。外国人が何らかのイベントでボリウッド・ダンスを披露する際、「Devdas」から歌曲をピックアップしているのを何度も見たことがある。きっと、今回の映画祭でも同様の効果をもたらすのではなかろうか?
僕は「Devdas」を映画館で2回見た覚えがある。1度目は普通に公開直後に。毎週毎週映画を見てレビューを書いていることもあって、同じ作品を映画館で2回以上見ることはほとんどしないのだが、「Devdas」に限っては2回見た。当時Indo.toに「デリ焼きボリウッ丼」というヒンディー語映画コラムを寄稿することになり、それ用の記事を書くため、記憶を新たにしようと1回目の鑑賞からしばらく経った後に回目を見たのだった。また、「Devdas」にはカッタク・ダンスの巨匠パンディト・ビルジュ・マハーラージが振り付けと歌で参加している。当時は日本人カッタク・ダンサーとして有名な佐藤雅子さんがビルジュ・マハーラージに師事してデリーに住んでおり、「Devdas」撮影の裏話などもいろいろ聞かせてもらっていた。映画の中でカッタク・ダンスを踊っていたバックダンサーの多くはビルジュ・マハーラージの弟子であった。佐藤雅子さんも「Devdas」に出演するチャンスがあったらしいのだが、あと少しのところで却下になってしまったらしい。だが、「Kaahe
Chhed Mohe(どうして私に悪戯するの?)」の中でマードゥリー・ディークシトのバックダンサーを務めたインド人カッタク・ダンサーとも会わせてもらったことがある。そういう訳で「Devdas」に対してどこか心理的に近しいものを感じていた。
「Devdas」とより深い関係を持つことに至ったのは、原作のヒンディー語訳を日本語に訳したことによる。「Devdas」の日本語訳はこのウェブサイトにおいて公開している(参照)。「Devdas」の原作はベンガル人作家シャラトチャンドラ・チャットーパーディヤーイの1917年の作品であり、本当に原典から翻訳しようと思ったらベンガリー語オリジナルを底本とする必要があるのだが、たとえヒンディー語訳からの重訳であっても、シャールク・カーン主演の「Devdas」を見てこの作品世界に興味を持った日本人に原作を紹介するという一定の役割は果たしたことだろう。最近では鳥居千代香先生訳の「デーヴダース―魅惑のインド」(出帆新社)も手に入る。未見なのだが、こちらもおそらくベンガリー語原作からの翻訳ではないと思われる。どうせなら誰かがベンガリー語からの直接の翻訳をすればいいのにと思う。
このような理由で、「Devdas」は個人的に非常に思い入れのある作品で、今回字幕を担当できて本当に嬉しかった。言わば主人公デーヴダース、パーロー、チャンドラムキーは長年の顔見知りであり、久し振りにまた再会できた気分であった。思えばサンジャイ・リーラー・バンサーリー監督の「Devdas」公開から丸々10年が経ってしまっている。今回字幕翻訳に当たってDVDを見直したのだが、さすがに古さは感じずにはいられない。特にジョイント・ファミリー内での大袈裟なファミリー・ドラマは、最近のヒンディー語映画ではほぼ完全に排除されており、南インド映画のリメイクにそれがわずかに残るのみとなっている。舞台ミュージカル的な音楽とダンスの使用も、今ではクラシックに感じる。10年の間にヒンディー語映画はだいぶ様変わりした。だが、そのような古めかしさがあるにも関わらず、そして既に何度も見たことがあるにも関わらず、心を締め付けられるようなシーンが多く、今でもいくつものシーンで涙を流してしまう。思い起こせば、原作を日本語に訳しているときも涙を流しながらキーボードを打っていた。あれからおよそ10年後、台詞を日本語に訳す際にやはり涙を流しながらキーボードを打っている自分がいた。「Devdas」は不思議な作品だ。これは僕だけなのだろうか?それとも他の人も同じように涙を流すのだろうか?デーヴダース、パーロー、チャンドラムキー、とても他人とは思えない。もしかして自分なのではないかとも思ってしまう。そんな強い思い入れが今でもある。
ただ、登場人物に感情移入ができるかというと、実はあまりできない。僕自身は男性なので、まずはデーヴダースに感情移入できるかどうかが重要となるのだが、デーヴダースの性格には全く同意できない。原作でも映画でも、インド人男性の悪い部分を詰め込んだような自分勝手な性格で、場当たり的で暴力的な行動を繰り返し、それが結局自分の首を絞めてしまっている。友達にはしたくない性格の人間だ。パーローの存在も非現実的だ。原作でも映画でも、パーローは一方で勝ち気でプライドの高い女性として提示されている。ところが、映画では幼馴染みのデーヴダースを10年間も一途に想い続ける健気な女性としても描かれている。何か矛盾していないだろうか?小説ではもう少し地に足の着いたキャラであるが、それでもパーローの愛には異常なものを感じる。もっとも現実的なキャラは実はチャンドラムキーだ。特に小説の方ではチャンドラムキーの人生により焦点が当てられている。しかし、それでも娼婦が1人の男に一目惚れし純愛してしまうという俄には信じ難いストーリーを頑張って自分の中で消化しなければならない。
各キャラクターへの感情移入という点では問題があるものの、僕はサンジャイ・リーラー・バンサーリー監督の「Devdas」の方が物語としてはよく出来ていると思う。よく映画は原作を越えられないと言うが、「Devdas」は明らかに映画の方がより洗練されている。映画においてもっとも卓越した改変は、パーローとチャンドラムキーを会わせたことである。原作では2人が出会うことはない。特にパーローとチャンドラムキーが最初に顔を合わせたシーンの台詞のやり取りは素晴らしい。1人の男を巡る、女と女の一騎打ちだったはずだが、パーローはチャンドラムキーが真剣にデーヴダースを愛していることを知り、一転して彼女にデーヴダースを託すのである。パーローはチャンドラムキーの手からデーヴダースを取り返しに娼館まで乗り込んだ。だが、既にブヴァン・チャウドリーと結婚してしまっていたパーローにとって、デーヴダースの幸せのためには、自分以外の誰かが彼の世話をするのが最上の選択肢だった。パーローはその資格をチャンドラムキーに認めたのである。デーヴダースの父親ナーラーヤン・ムカルジーが死の床でパーローに許しを乞うシーンも原作にはないシーンであるが、物語により深みを与えている。さらに、原作の終わり方はとても淡泊で呆気なく、消化不良気味である。何か面倒臭くなって適当に話を終わらせてしまったかのようにも思える。その点、映画ではエンディングは非常にドラマチックだ。最後まで気を抜いてない。
しかしながら、映画のエンディングについては多くの批判も聞く。あまりに悲しすぎる終わり方なのである。デーヴダースは、以前パーローと交わした「死ぬ前に必ず君に会いに行く」という約束を守るために、死ぬ直前にパーローの嫁ぎ先を訪れる。だが、村に着いたときには危篤状態となっており、行き先を告げることもできない。パーローは、デーヴダースの到着直後から直感でそわそわし出すのだが、謎の旅人が危篤状態で家の前で倒れているという知らせを聞いたとき、まさかそれがデーヴダースだとは思わない。その後それがデーヴダースだと分かると、途端に彼の元に走り出すのだが、彼女は家から出ることを禁じられており、夫のブヴァンは屋敷の門を閉じさせてしまう。そのせいでデーヴダースは最期にパーローに触れることもできず死んでしまう。もう少し救いのある終わり方にできなかったのだろうか、とは僕も強く感じる。例えば、触れることは叶わなくても、パーローのヴェールが風で飛んで死ぬ間際のデーヴダースの顔を撫でるとか、たったそれだけでも悲しみの中に一筋の救いがあり、重さが少しでも和らいだはずである。この辺りの捉え方は人それぞれであろうが、個人的には100%悲しいままで終わるような映画は好きではない。1%でも何か救いがあって欲しいものだ。
字幕を付けるに当たって、DVDを何度も見返した。全ての台詞、全てのシーンを理解しなければ、正確な字幕は付けられない。インド映画では、各挿入歌の歌詞に隠された意味をも理解しなければならない。簡単な作業ではない。何度も見返している内に、「Devdas」に対する今までの自分の理解は不完全かつ不十分であったことが分かって来た。それは多くのシーンに当てはまるのだが、もっとも衝撃的な発見だったのは、パーローの処女性を巡る問題である。
パーローは、ヒンディー語映画における「永遠の処女」の代表格としてよく取り上げられる。映画「Devdas」においてパーローが処女を失うシーンは明確には描写されない。結婚後も彼女は夫ブヴァンとはベッドを共にしない。パーローは、ブヴァンの死んだ前妻の穴を埋めるために嫁入りしたのだが、それは子供たちにとっての母親や、屋敷の女主人としての役割を果たすためであり、夫の性的欲求を満たすためでは全くなかった。ブヴァンは今でも前妻スバドラーを愛していた。よって、パーローとブヴァンは夫婦でありながら夫婦関係にはなかった。一方、原作でもその辺りがストレートに描写されている訳ではないが、おそらく夫との夫婦関係はあったのではないかと思われる。しかし、映画を表面的に鑑賞しただけでは、パーローは確かに「永遠の処女」にふさわしい人生となっている。
しかし、「Morey Piya(私の愛しい人)」の歌詞と映像を何度も見直す中で、このときデーヴダースとパーローは性的関係を持ったのではないかと強く感じるようになった。この曲は、パーローの母親スミトラーが、デーヴダースの家で行われた、デーヴダースの兄嫁クムド懐妊を祝うパーティーで踊りを踊るシーンで流れるものである。スミトラーはこの日にパーローとデーヴダースの縁談が成立するものだと期待しており、この踊りのときには期待通りそれが成立したと勘違いしていた。パーローも呼ばれていたのだが来ず、代わりに彼女はデーヴダースと川岸で密会していた。川岸に水汲みに来たパーローの足に刺が刺さってしまい、デーヴダースがそれを抜く。そんなシーンで流れる曲である。「Morey
Piya」は、表面的な歌詞では、インド神話上の恋人クリシュナとラーダーがヤムナー河の河岸で繰り広げる「ラース・リーラー」と呼ばれる愛の踊りを描写しているが、映像上では、スミトラーがパーローとデーヴダースの結婚に勘違いして狂喜する様子と、デーヴダースとパーローの密会を描写している。
重要となって来るのはデーヴダースとパーローの密会と、それに覆い被さる歌詞である。映像の上では、デーヴダースとパーローは夜の川岸で抱き合うだけで、セックスを明示するものはない。ただ、そこに至るまでに数々の暗喩が映像と歌詞を通して行われており、それを吟味する必要がある。まずデーヴダースはパーローの装飾品を次々に外して行く。パーヤル(足飾り)、ナーラー(腰紐)、首飾り、そしてヴェール。デーヴダースも自分のショールを脱ぎ捨てるシーンがある。特にパーローの足の裏に刺さった刺を抜くシーン、そして流れ出た血をデーヴダースが嘗めるシーンは、暗喩でありながら、かなり真相に近いものを表現している。このシーンでパーローが取る数々の妖艶なポーズは、「カーマスートラ」、カジュラーホーの寺院彫刻、密教デーハタットヴァなどで描写される体位と酷似している。
デーヴダースがパーローの足の裏の刺を抜こうとするシーンの歌詞はこうである。表面上は刺を無闇に抜かれるのを拒否しているのだが、実際には情事中のやり取りに聞こえる。
न बहियाँ धरो आती है मुझे शरम
na bahiyaan dharo aati hai mujhe sharam
腕を掴まないで・・・恥ずかしいわ・・・
हाँ छोड़ दो तुमको है मेरी कसम
haan chhod do tumko hai meri kasam
離して・・・お願いだから・・・
न ज़िद न करो जाने दो मुझे बालम
na na zid na karo jaane do mujhe baalam
無理をしないで・・・許して・・・愛しい人・・・
देखो दूँगी मैं गालियाँ बावरे चलो हटो सताओ न मोरे पिया
dekho dungi main gaaliyan baavre chalo hato sataao na more piya
でないと大変よ どいて お願い 離して 無理をしないで 愛しい人・・・
そして刺を抜いた後、スミトラーの踊りに切り替わるが、歌詞はクリシュナとラーダーの踊りを描写しながら、引き続きデーヴダースとパーローの情事を暗示する。テンポもどんどん早くなり、その行為を象徴する。このシーンの歌詞はこうである。太鼓、歌、興奮、渇望、波など、セックスを暗示する要素が次々と現れる。
जमुना के तीर बाजे मृदंग
jamuna ke teer baaje mridang
ヤムナー河の河畔で 太鼓が鳴り響く
करे कृष्ण रास राधा के संग
kare Krishna raas Radha ke sang
クリシュナよ ラーダーと共に愛の踊りを踊れ
अधरों पे गीत मन में उमंग
adhron pe geet man mein umang
歌を口ずさみ 興奮の波に乗りながら
करे कृष्ण रास राधा के संग
kare Krishna raas Radha ke sang
クリシュナよ ラーダーと共に愛の踊りを踊れ
साँसों में प्यास तन में तरंग
saason mein pyaas tan mein tarang
息を切らしながら 体を波打たせながら
करे कृष्ण रास राधा के संग
kare Krishna raas Radha ke sang
クリシュナよ ラーダーと共に愛の踊りを踊れ
इसे देख देख दुनिया है ढंग
ise dekh dekh duniya hai dhang
クリシュナとラーダーの踊りを見て 世界は震撼する
करे कृष्ण रास राधा के संग
kare Krishna raas Radha ke sang
クリシュナよ ラーダーと共に愛の踊りを踊れ
これらを全て勘案すると、「Morey Piya」の時点でデーヴダースとパーローは性的関係になったと見て間違いない。そうだとすると、「Morey
Piya」はヒンディー語映画のこの10年間の中でもっともエロティックなシーンに数えていいのではないかと感じる。ここまでエロティックに、かつここまで巧みにオブラートに包んで、お互いに求め合う男女の情事を描写したヒンディー語映画は近年他に思い付かない。このとき2人はてっきり自分たちが結婚するものだと考えており、この行動はモラルからそれほど逸脱していない訳だが、デーヴダースがこの後に取った行動は非常に身勝手であった。家族が結婚に反対したことで、易々とパーローとの結婚を諦めてしまったのである。パーローが夜中にデーヴダースの部屋を訪れ、自分の「権利」を主張したことも、「Morey
Piya」での出来事を理解した後では、より納得できる。その後デーヴダースも幾分改心し、両親に対してパーローとの結婚を直談判する訳だが、聞き入れられない。とうとうデーヴダースは怒って家を出るが、このときパーローを連れて行くことはしなかった。後にデーヴダースはパーローに手紙を書き、自分たちの間に愛はなかったと公式に絶縁を宣告する。デーヴダースは精神的に非常に弱い人間であり、家族の意向に反してまでパーローとの結婚を決行できなかったのである。デーヴダースに全てを捧げたパーローは、デーヴダースとその家族に騙されたと強く感じたことであろう。
ただ、デーヴダースは後に自分がしてしまったことの重大さに気付き、反省する。そのきっかけとなったのが、チャンドラムキーの踊りであり、「Kaahe
Chhed Mohe」のダンスシーンである。ここでも再びクリシュナとラーダーの情事が歌詞の中で描写される訳だが、今回はラーダーの視点からそれが語られる。クリシュナの悪戯によって、ヴェールが落ちる様子、ミルクの入った壺が壊される様子、チューリー(手首を飾る輪)を壊す様子、全てが女性の尊厳を奪うメタファーである。ただ、女性の方も満更ではない様子だ。また、この歌は娼婦チャンドラムキーの半生を象徴していると拡大解釈することも可能であろう。夫以外の男性からそのような目に遭った女性は、インドの社会では尊厳ある人生は送れず、娼婦に身を落とすしか生きる術がなくなる。原作ではもう少しその辺りの経緯が説明されるが、映画ではそれがこの歌に凝縮されている。クリシュナがラーダーの貞操を奪う様子を描写した歌詞を聴き、それを理解したデーヴダースは、自分がパーローにしたことの重大さに気付き、急いでパーローのところへ向かったのだった。だが、そのときにはパーローの結婚式が行われていた。
小説であろうと映画であろうと、「Devdas」という物語の中でもっとも奇っ怪な出来事は、デーヴダースが真珠のネックレス(原作では釣り竿)でパーローの額をぶち、傷を付けるシーンであろう。フェミニスト的観点、いや人道的観点、いやどんな観点から見ても、それは完全なる暴力である。何をもってしても正当化できる行為ではない。普通だったら、結婚直前の女性の顔に一生消えない傷をわざと付けるなんて、デーヴダースは何て酷い奴だ、ということになる訳だが、パーローはそれを許すばかりか、デーヴダースの愛の印として一生それを額に飾って生きて行くことを決める。一般の観客にはいまいち理解しにくい部分である。一応その伏線は張られている。映画の中で何度もパーローの美しさと月が比べられるが、パーローはかねてから、月にはアザがあるため、完全無欠の自分の方が美しいと自惚れた発言をしていた。デーヴダースはパーローの額にも傷を付け、その自惚れを直し、月と同じ地位に落としたのだった。日本語にも「傷物」という言葉があるが、パーローの額の傷は、デーヴダースに体を捧げ、純粋ではなくなったパーローの状態を暗示しているとも言える。そして、だからこそパーローはその傷を甘んじて受け容れたと考えられる。また、真珠のネックレスでぶったときにパーローの額から流れ出た血をデーヴダースはパーローの頭頂部に塗る。これはスィンドゥールという既婚女性の印を暗示するものであり、形式的にはデーヴダースはこのときパーローを妻としたのだった。このときのパーローの心情は「Hamesha
Tumko Chaha(いつもあなたを求めていた)」の中でとうとうと語られている。
こうして考えると、デーヴダースとパーローは、肉体的にも精神的にも形式的にも夫婦として結ばれた存在であった。しかし、それでも2人は夫婦とはなれなかった。時代と社会が2人を引き離してしまったのである。この理解から、「Devdas」の評価は始まると言っていい。今回「Devdas」の字幕を担当したことで、映像、台詞、歌詞などをひとつひとつ吟味する機会を与えられ、「Devdas」の世界をここまで理解することができ、幸いだった。そして、やはりヒンディー語映画においては、歌詞の理解は映画全体の理解の上で、非常に重要だと再認識した。
こういう解釈まで字幕に吹き込むことができれば一番いいのだが、残念なことに字幕には制限が多く、そこまでの理解を提供するものにはならない。多くの場合、字幕では映画は理解し得ない。やはりオリジナルの言語を理解し、その国の文化を理解した上でその映画を見なければ、なかなかその作品世界の奥深くまで足を踏み込めないだろう。だから、字幕にのみ頼った鑑賞によってその映画を一方的に批評するのは不適切だ。インド映画では、歌詞、つまり詩の理解も重要な要素となるため、それはさらに困難となる。詩の理解はどの言語でも最大の難関である。インドの各映画を本当に理解して評せられる人は、日本にはあまりいないのではないかと感じる。どうしても「歌って踊って」「勧善懲悪」「何でもあり」など、自分の知性の及ぶ範囲の分かりやすいキャッチフレーズで切り取って理解しようとしてしまう。だが、ヒンディー語映画は既に10年前の時点で、そういう安易な尺度では太刀打ちできないレベルにあった。今回の映画祭で、どれだけの人がヒンディー語映画を正当に評価してくれるだろうか?
本日、長らく懸案だった研究ヴィザ(リサーチ・ヴィザ)の延長に成功した。これであと6ヶ月インドに滞在できることになった。
研究ヴィザの延長は今まで3回行っており、だいぶ要領が分かったので、ここでまとめておこうと思う。
まず、研究ヴィザとは、インドで研究活動を行う外国人が取得しなければならないヴィザのことである。特に、インドの大学で博士号を取得しようとした場合、必ず研究ヴィザを取得しなければならない。
似たようなヴィザに学生ヴィザ(スチューデント・ヴィザ)があるが、こちらはインドの教育機関において、論文を書くのではなく、単に勉強をしたり芸術関係の訓練を受けたりする外国人が取得する。学士コース(Bachelor)、修士コース(Master)、そして修士と博士の間にあるM.Phil.コースは学生ヴィザで入学可能である。例外的に、博士課程の1年目のみ学生ヴィザでの入学・進学を許されたケースもある。なぜなら博士課程の1年目は研究テーマを決める期間であり、論文を書く期間ではないからである。だが、博士課程の初めから研究ヴィザを取得するのが好ましい。
研究ヴィザの取得については、自分の体験を元に、以前まとめたことがある(参照)。だが、当時とはだいぶ状況が変わっており、参考にはならないかもしれない。ただ、研究ヴィザの取得は以前に比べて容易になったので、そんなに身構える必要はない。
本日の主な話題は研究ヴィザの延長である。
僕が研究ヴィザを取得したときは最大5年有効のヴィザが一気にもらえていた(僕の場合はパスポートの期限が先に切れるために5年もらえなかった)。しかし、最近では長くても3年有効のヴィザしかもらえないようだ。インドでは博士号を取得するには通常4-5年は掛かるので、多くの場合、途中でヴィザの延長が必要となって来る。
研究ヴィザの延長に必要な書類は以下の通りである:
- 大学からのレター(オリジナル)
- 住所証明(コピーまたはオリジナル)
- 財源証明(コピーでOK)
- 入学許可証(コピーでOK)
- パスポートとヴィザのコピー
- パスポートサイズの写真(1枚)
大学からのレターには、当人が大学の在学生(Bona-fide student)であること、ヴィザ延長の目的、いつまでヴィザを延長したいのか具体的な日にちなどを盛り込んでもらう必要がある(1回の延長に付き最大1年まで)。もちろん権限者のサインとスタンプも必要である。大学のレターヘッドがあるとベスト。このレターがもっとも重要で、これがないとヴィザの延長は不可能と言っていい。
住所証明は住んでいる場所によって異なる。もし大学の寮に住んでいるなら話は早く、寮から住所証明を出してもらえるはずである。もし何度でも住所証明を出してもらえるなら、オリジナルを提出してしまっても構わないだろう。貸家に住んでいる場合は、大家さんとの賃貸契約書(Rent
Agreement)が住所証明となる。そのコピーを提出する。もしホテル住まいならば、チェックイン時に外国人だけが記入させられるCフォーム(C-form)という書類のコピーが住所証明となる。
財源証明は、もし奨学金をもらっているならば、毎月いくら支給されて、奨学金の期限がいつまでなのかが明記された書類が必要となる。ICCR奨学生なら、ジョイニング・レポートを提出するともらえる書類がそれとなる。銀行口座開設時にも使ったはずである。この書類はコースが終わるまで大事に保存しておかなければならない。もし奨学金の期限が来ていたら、ヴィザ延長の前に奨学金の延長をしなければならない。私費留学生は銀行の残高証明がそれとなる。
入学許可証は、いわゆるアドミッション・レター(Admission Letter)というやつで、研究ヴィザを取得する際にも活躍したはずである。もしこのオリジナルをインド大使館に提出してしまっていて、コピーを手元に持っていないとなると、入国後2週間以内に行うことを義務づけられているレジストレーションのときに困ったことになる。オリジナルを提出しなければならない書類は、提出前に必ずコピーを取って手元に置いておくべきである。これはインド生活の「いろは」の「い」だ。おそらくヴィザ延長時にこのレターは必須ではないと思うが、僕は毎回提出しており、すんなり延長ができている。
パスポートとヴィザのコピーやパスポートサイズの写真は基本であり、このような手続きのときには必ず持っていなければならない。余分に持参するとさらに安心である。このとき注意しなければならないのは、ヴィザ延長申請時にヴィザの有効期限が切れていないことである。もし切れている場合、まずは内務省(Ministry
of Home Affairs)へ行ってオーバーステイの許可をもらわなければならなくなるので厄介だ。内務省はデリーにしかないので、インドのどこに住んでいても、この手続きをするためにデリーに来なければならない。
デリー在住者はヴィザ延長申請のためにFRRO(外国人登録局)へ行く。FRROではオンライン予約が必須となった。まずはFRROのウェブサイトからオンライン予約フォームへと進み、必要事項を埋めて予約する。どうもシステム上、申請日翌日は予約できず、2日後からとなるため、注意が必要である。最近FRROは予約日を厳しくチェックしており、予約日前にFRROを訪れた人を容赦なく弾いている。予約の時間は気にする必要はないが、予約日には最大限の注意を払うべきである。オンライン予約するとPDFファイルが生成されるので、それをプリントアウトして予約した日にFRROまで持って行く。念のために2部プリントアウトしておくといい。
FRROで何らかの手続きをする際、僕の攻略法は、まず朝7時頃にFRROを訪れることである。トタン屋根の待合場の奥に机があり、その机の上には大抵1枚の紙が置かれている。そこに番号と名前を書き込む。多分朝7時の時点だと、1桁の番号が得られるはずである。FRROが開くのは9時半なので、僕は一度家に帰って朝食を食べくつろぐ。9時過ぎにFRROを再び訪れるようにすれば、ちょうどそのとき点呼が始まっていることだろう。紙に書かれた番号順に入場が許される。実は昼休み(2時)後の方が空いていて手続きがスムーズという話もある。FRROが混雑する大部分の理由は大量のアフガーニスターン人がいるからであるが、ラマダーン(断食月)時に彼らは一斉に帰省するので、この期間FRROはとても平和である。それも覚えておくといいだろう。
FRROオフィスに入ってすぐ右にレセプションがあり、まずはここで書類のチェックをしてもらわなくてはならない。何か書類の不足・不備がある場合はここで玉砕となる。このレセプションをパスすると、今度は書類自体の検証が行われる。これには数十分掛かるので、本でも読んでいるのが吉である。検証が終わると名前を呼ばれるので、書類を受け取る。
書類には、入場時の番号とはまた別の番号が記入されている。電光掲示板で自分の番号が示されたら、部屋の奥に並ぶカウンターへ行く。だが、書類の検証が行われている間に自分の番が来ていることがほとんどなので、実際には書類を受け取ったらそのままカウンターへ向かうことになるだろう。アフガーニスターン人専用のカウンターもあるので注意。空いたカウンターへ行ってオフィサーに書類を渡す。何も問題がなければヴィザの延長をしてもらえるだろう。カウンターに記帳が置いてあるので、そこに自分の名前と国籍を記入し、サインする。そのとき通し番号をオフィサーに聞かれるので、それを教える。その番号がそのままヴィザ番号となる。
はっきり言って研究ヴィザの延長はFRROでの手続きの中では比較的簡単な部類だと言える。必要書類さえ揃っていれば、難なく延長してもらえるだろう。
しかしながら、僕の場合は多少違ったゲームをしなければならなかった。なぜなら研究ヴィザは一般には最大5年とされているからだ。僕は2007年7月に研究ヴィザを取得したため、2012年7月に5年が終わっていた。だが、特記事項として、論文提出後、その他所要手続き(formalities)を完了するために6ヶ月の延長が認められている。この「所要手続き」が意味するのは口頭審査(Viva
Voce)だと考えていいだろう。論文提出後、審査官から口頭で審査を受けて初めて博士号を取得できる。インドの大学では、口頭審査は論文提出からかなり後に行われることが多く、このような措置が必要となる。僕の所属する学科でも、どう頑張っても6ヶ月は掛かる。よって、5年が終わったにも関わらず、6ヶ月の延長を申請したのだった(その前に論文提出のために8月31日まで延長してもらった)。この辺りの事情は、大学からのレターにキチンと盛り込む必要がある。
研究ヴィザのガイドラインに以上のことは明記されており、5年が終わった後の6ヶ月の延長で苦労することはなかった。レセプションで少し疑問を呈されたが、担当者(In-Charge)が事情をよく分かっており、一言「6ヶ月延長してやれ」と言ってくれたので、丸々6ヶ月の延長がもらえた。2012年7月から数えると、実際には7ヶ月延長してもらっており、ボーナスと言える。
ICCR奨学金についても追記しておく必要があるだろう。研究ヴィザの期間が5年+6ヶ月となっているのと同様、ICCR奨学金の期間も5年+6ヶ月となっている。5年以内に論文を提出し、大学から「当人は論文を提出した、口頭審査のために半年の奨学金延長を求む」という旨のレターをもらえば、それで奨学金を延長できる。ICCR奨学生の場合、まずはICCRから奨学金の延長を勝ち取る必要がある。それが済めば、研究ヴィザの延長は赤子の手をひねるようなものだろう。ちなみに僕はICCRからこのレターをもらうために1週間を無為に過ごした。ヴィザの延長よりも奨学金の延長の方が厄介だと認識すべきである。
| ◆ |
8月28日(火) Delhi in a Day |
◆ |
最近PVRディレクターズ・カットが非常にいい。PVRディレクターズ・カットはインド最高級の映画館であり、入場料は日と時間にも依るが1,000ルピー前後と、日本とそんなに変わらない。だが、サービスや設備は値段に見合ったレベルで、静かにまったりと映画を鑑賞したい人にはうってつけの場所だ。さらに重要なのは、一般の映画館では公開されない、限れた観客向けの映画も果敢に上映していることである。僕の住むJNUのすぐ隣に立地していることも、僕にとっては好都合だ。PVRのこの試みは、きっとデリーの映画文化の発展に大きく貢献することだろう。願わくは、チケット代を抑えて欲しいものだ。
今日PVRディレクターズ・カットで見たのは「Delhi in a Day」という映画である。監督はプラシャーント・ナーイル。インド生まれ、ヨーロッパ、アフリカ、北米育ち、現在パリ在住というインターナショナルな人物で、本作が彼の長編映画デビュー作となる。キャストには、リレット・ドゥベー、クルブーシャン・カルバンダー、ヴィクター・バナルジーなど、演技派として知られる俳優たちが名を連ねている。言語は基本的にヒンディー語で、英語も頻出する。英語以外の台詞には英語字幕が付いていた。
題名:Delhi in a Day
読み:デリー・イン・ア・デイ
意味:デリーでの1日
邦題:デリーでの1日
監督:プラシャーント・ナーイル
制作:プラシャーント・ナーイル
音楽:マティアス・ドゥプレシ
衣装:マヒマー・シュクラー、ナローラー・ジャミール
出演:リー・ウィリアムス、リレット・ドゥベー、クルブーシャン・カルバンダー、ヴィクター・バナルジー、アンジャリー・パーティール(新人)、ヴィディヤ・ブーシャン、アルン・マリク、ディネーシュ・ヤーダヴなど
備考:PVRディレクターズ・カットで鑑賞。
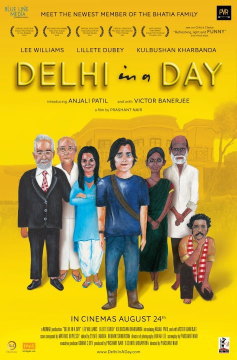
Delhi in a Day
| あらすじ |
デリーの富裕層であるムクンド・バーティヤー(クルブーシャン・カルバンダー)とカルパナー(リレット・ドゥベー)の家に、ムクンドのロンドン留学時代の親友の息子ジャスパー(リー・ウィリアムス)がやって来ることになる。カルパナーは準備に大忙しだった。ムクンドとカルパナーには2人の子供がいた。長男はジャイ、長女はマドゥであった。また、バーティヤー家にはカルパナーの祖父(ヴィクター・バナルジー)が同居していた。さらに、彼らの家では5人の使用人が働いていた。ラグ(ヴィディヤ・ブーシャン)は20年間バーティヤー家に仕える最年長。その養女のローヒニー(アンジャリー・パーティール)も共に働いていた。ローヒニーはラグの実の娘ではなかったが、彼女の両親が共に死んだことで、彼女を引き取ったのだった。ローヒニーの夢はムンバイーへ行って女優になることだった。ウダイ・スィン(ディネーシュ・ヤーダヴ)は料理人。ターター家で15年間働いていたことが誇りであった。チョートゥー(アルン・マリク)は雑用。他にタミル人運転手のヴェーンカトとナトラージがいた。
早朝ジャスパーは空港に着き、そこからタクシーに乗ってバーティヤー家までやって来る。とりあえず午前中はバーティヤー家の自動車を借りてデリーを散策した。昼食を取りにバーティヤー家まで戻るが、そのときジャスパーは部屋に置いておいたポンドの現金がなくなっていることに気付く。その額はルピーにすると3-40万ルピーになった。それを聞いたムクンドとカルパナーは血相を変える。カルパナーは使用人を1人1人呼んで問い質す。ジャスパーが外出している間、彼の部屋に入ったのはラグのみだった。という訳で自動的にラグが犯人に仕立て上げられてしまいそうだった。ムクンドは翌日警察を呼ぶことを決める。
ローヒニーは、ラグが逮捕されてしまうかもしれないことに焦り、何とか盗まれた分だけのお金をどこからか調達しようとする。彼女は単身マフィアから金を借りに行くが、借りることはできなかった。
その日の晩にはジャスパーを歓迎するためのパーティーがバーティヤー家で開かれ、たくさんの友人がやって来た。そのパーティーも終わり、カルパナーが一息付いていると、彼女は窓の外で娘のマドゥが、恋人のビリーと交わしている会話を聞いてしまう。ビリーはならず者で、前々からカルパナーは娘とビリーの関係に反対していた。その会話で、ビリーがマドゥに金を盗ませたことが発覚する。翌朝、カルパナーはマドゥを問い質す。マドゥは自分が盗んだことを白状する。
その頃、早起きしたジャスパーは、ローヒニーが泣いているのを見る。ローヒニーは英語が話せなかったため、2人の間でコミュニケーションは取れなかったのだが、ジャスパーは彼女の置かれた状況を察知した。朝食のとき、ジャスパーはバーティヤー家の人々にお金が見つかったと明かし、一件落着となる。おかげでラグも警察に逮捕されなくて済んだ。しかし、実際にはお金は見つかっていなかった。ジャスパーはローヒニーを助けるために嘘を付いたのだった。
この日、ジャスパーはヴァーラーナスィーへ向かう予定だった。バーティヤー家に見送られながらジャスパーは家を出る。ジャスパーが向かう先は、鉄道駅ではなく、空港であった。ジャスパーはお金がなくなってしまったため、インド旅行を続行することができなくなり、そのまま英国に帰ることを決めたのだった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
インドが「インディア」と「バーラト」の2つに分かれ、昨今これらの距離がますます広がっているとの指摘がされるようになって久しい。「インディア」とは、急速な経済成長、都市在住富裕層とその高い購買力、IT、ショッピングモール、多国籍企業や国際ブランドの進出などなどが象徴する「インドの光の部分」であり、対する「バーラト」は、農村、スラム、貧困、悪習などが象徴する「インドの影の部分」である。「Delhi
in a Day」では、とあるデリー在住富裕層の家という限られたロケーションを舞台にしながらも、この2つが非常にコンパクトに対比されていた。バーティヤー家の家族とその使用人の関係は、もちろん雇用者と使用人という関係であるのだが、インドではこの2者の間の溝は想像以上に深く、同じインド人でありながら、全く別の世界に住み、全く異なった運命を持っているかのごとくである。
さらに、英国人若者が外国人旅行者の視点を持ちながらその世界に飛び込んで来ることで、「外国人の目から見たインド」も加わる。多くの外国人にとって、インドとはスピリチュアルでミステリアスな国のイメージが今でも根強い。主人公のジャスパーも全くそのようなイメージを持ちながらインドに飛び込んで来た。僕が「Delhi
in a Day」で面白いと感じたのは、この外部からのインドに対する視点が、我々外国人にとって非常に共感できるものであったからである。
バーティヤー家の家族やその友人たちも描写されていたのだが、この映画の中でもっとも優れていたのは、使用人たちの心情描写である。例えば料理人のウダイ・スィン。ジャスパーの歓迎パーティーで腕を振るうのだが、カルパナーはデリーの有名レストラン、モーティー・マハルからカバーブを注文する。カバーブならウダイ・スィンも作れた。しかしカルパナーは、ジャスパーが「モーティー・マハルのカバーブ」を食べたいと言ったためにそうしたのだった。この出来事がウダイ・スィンを酷く傷付けてしまう。きっとジャスパーはガイドブックを見てモーティー・マハルの名前を出したのだろう。彼に全く悪気はなかった。だが、ウダイ・スィンの心の傷は深く、最終的には「もうこの家で働くのを辞める」とつぶやくに至る。このような使用人の微妙な心情描写は、今までのインド映画であまり見たことがない。
使用人の弱い立場をもっともストレートに表現したのはローヒニーであった。ローヒニーはジャスパーに対して、その理不尽さをヒンディー語でとうとうと語る。家でお金が盗まれると、何の証拠もないのに、使用人が疑われ、警察に突き出されてスケープゴートにされるのである。今回スケープゴートにされたラグは、20年間バーティヤー家に仕えて来た、忠実な使用人であった。だが、このような事件が起こると、それまでの実績は全く考慮されず、犯人にされてしまう。使用人には何の人権もない。そんな現状が訴えられていた。
使用人同士の人間関係もよく描写されていた。家の中のことを取り仕切る使用人は皆ヒンディー語圏から来た人々だったが、運転手はタミル・ナードゥ州出身で、明らかにこの2つのグループの間で溝があった。タミル人運転手は満足にヒンディー語も話せないので尚更である。また、バーティヤー家の人々が眠っている間、使用人たちが集まって、彼らの悪口や物真似をするシーンもあった。その癖カルパナーに一喝されると皆そそくさと仕事に戻る。何だかんだ言って使用人たちは絶対に主人には逆らえないのである。この辺りはかなり現実に即した描写だったと感じる。一方で、ムクンドとカルパナーは、おそらく恋仲になってしまった使用人と娘が両親によって殺されたと言われる有名なタルワール事件をテレビで見て、「世も末だ」と嘆き合う。インディアはバーラトを恐れ、バーラトはインディアを恐れる。お互いがお互いを異質なものと捉え、陰口をたたき合いながら、お互いを利用できるだけ利用しようとする。そんなインド社会の危機的な状況に対する警鐘が、この一見穏やかな雰囲気の映画において鳴らされていたと感じた。
外国人の視点からは、ジャスパーの行動もとても理解できる。ホームステイ先のインド人家庭で自分のお金がなくなり、使用人たちが疑われることになった。一生懸命働いて稼いだお金で、それがないとインド旅行もできない。インドは憧れの土地で、今回はその夢の実現だった。しかし、そのせいで使用人たちの人生が脅かされていることを感じ取る。ジャスパーは、その損失の責任を自分で取ることを決める。バーティヤー家の人々に、お金が見つかったと嘘を言い、ヴァーラーナスィーに向かう振りをして英国に戻ってしまうのである。もしかしたらこの辺りの行動は一般のインド人には理解されないかもしれない。だが、日本人なら理解できると思う。それだけでなく、ジャスパーがローヒニーに対して好意を抱いていたことも暗示される。ジャスパーはスケッチが趣味で、密かに描いたローヒニーのスケッチを別れ際に彼女にそっとプレゼントする。しかし、彼の行動は、ローヒニーへの好意のみに起因するものではなく、先進国の人間としての倫理観から来るものだと信じたい。お金はまた稼げる。インドにもまた来られる。だが、下層に位置するインド人の人生は吹けば飛ぶような脆弱なもので、一度失われたら二度と取り戻せないのである。
ちなみに、ジャスパーが受けた「洗礼」も外国人にとってはお馴染みだ。彼は空港からバーティヤー家までタクシーで来る。カルパナーは空港まで迎えをよこすと言っていたのだが、ジャスパーは「ディスカバー・インディア」にこだわっており、それを断って自力でバーティヤー家まで行こうとするのである。この情熱もよく理解できる。彼はタクシーを捕まえ、やっとのことでバーティヤー家まで到着する。今までフレンドリーに接していたタクシー運転手は急に真顔となって、2,000ルピーを要求する。ジャスパーは、タクシー運転手が吹っ掛けて来ることを事前にガイドブックか何かを通して知っており、「それ来た」とばかりに「1,000ルピー以上は払わない」と値切る。結局運賃は彼の主張通り1,000ルピーとなる。ジャスパーは「悪徳ドライバーから首尾良く値切ってやった」と自慢気にカルパナーに語るのだが、実際には正規の運賃は数百ルピー程度だった。半額まで値切ったつもりが、まだまだ法外な値段だったのである。デリーではよくある出来事である!
ネタバレになるが、ジャスパーのお金はカルパナーの娘マドゥが盗んでいた。カルパナーは偶然それを知り、彼女を問い詰める。マドゥもそれを白状する。しかし、カルパナーはマドゥを守るために、そのことを秘密にする。そしてラグに罪をなすりつけることを決める。家の名誉を守るためである。この辺りの考え方も非常に現実に即しており、インド人富裕層の欠点だと言える。
1時間半ほどの短い映画だったが、インドの社会で今後ますます問題になりそうなこの「インディア」と「バーラト」の剥離問題を、非常にミクロな事件を通して突いており、優れた映画だと感じた。特にインドにおいて使用人を使う立場にいる人が見ると参考になるのではないかと思う。
低予算映画ではあったが、演技の面で妥協はなかった。リレット・ドゥベー、クルブーシャン・カルバンダー、ヴィクター・バナルジーなど、インドを代表する演技派俳優たちが非常にリラックスした演技を見せていたし、使用人グループを演じた俳優たちも素晴らしかった。特にラグを演じたヴィディヤ・ブーシャンは、本物の使用人のような風貌と演技で、絶賛に値する。ローヒニーを演じたアンジャリー・パーティールも良かった。
音楽を担当したマティアス・ドゥプレシはフランス人ミュージシャンで、「Peepli [Live]」(2010年)でもBGMを担当したことがあり、本作は彼のインド映画参加2作目となる。一般的なインド映画のフォーマットからは外れており、ダンスシーンなどなかったが、音楽は非常に効果的に使われていた。
題名の通り、デリーが舞台となっており、デリー在住者にはお馴染みの風景がいくつも登場する。ジャーマー・マスジドがもっとも有名なランドマークであろう。だが、それらのランドマークをこれ見よがしに映し出すことはしておらず、デリーの何の変哲もない街角を切り取っており、好感が持てた。
ちなみに、一瞬だが、「JAF」という日本航空(JAL)の旧ロゴ(鶴丸ではない方)にそっくりなロゴを持った飛行機が出て来る。ジャスパーが乗って来たもので、ロンドン-デリー便だと思われる。「Japan
Air Flight」か何かの略だろうか?
「Delhi in a Day」は、非常に限られた上映となっているが、今年のベストに入れてもおかしくはない傑作である。富裕層の家庭で働く使用人に焦点を当てた点でもっとも賞賛されるべきであるが、外国人の視点から見たデリーもよくスクリーン上に再現されており、外国人観客にとっても興味深い。必見の映画である。
| ◆ |
8月30日(木) ギャングス・オブ・デリー |
◆ |
アヌラーグ・カシヤプ監督の「Gangs of Wasseypur」(2012年)では、ジャールカンド州ワーセープルを拠点とするギャングの抗争が題材となった。ヒンディー語映画には、ダーウード・イブラーヒームのDカンパニーをはじめとして、ムンバイーのギャングが登場することが多い。しかし、今のところデリーのギャングを大々的に取り上げた映画はあまりない。「Jannat
2」(2012年)くらいか。現在制作中の「Zilla Ghaziabad」がそれに近い映画になるかもしれないが、ガーズィヤーバードはウッタル・プラデーシュ州なので、厳密にはデリーではない。
8月28日付けヒンドゥスターン紙によると、デリーでは主に5種類のギャングが暗躍していると言う。なかなか興味深い洞察であったため、ここに紹介したい。
まずはバングラデシュ・ギャング。バングラデシュから西ベンガル州へ違法に入国したバングラデシュ人のグループがデリーで犯罪に手を染めているという。彼らはティームールプル、ジャーミヤーナガル、マダンプル・カーダル、JJコロニー、バダルプル、サンガム・ヴィハール、オークラー、プシュプ・ヴィハール、キドワイー・ナガル、スィーラムプル、ウスマーンプル、スィーマープリー、コーンドリー、バワーナー、ジャハーンギールプリー、ナレーラーなどに住んでいる。彼らが主に生業とするのは空き巣である。日中、バングラデシュ・ギャングの連中はカバーリー(廃品回収屋)に身を扮して高級住宅地を徘徊する。その際、施錠がしてあり、新聞紙などが溜まっていて長期的に留守の家を探す。そして夜中に空き巣に入って金品を盗み出す。もし事前の調査と違って家に人がいた場合、殺人も厭わない。警察の各派出所(ターナー)にはバングラデシュ・ギャング対策専門の部門が必ず設置されているほど、このギャングの活動は活発のようである。バングラデシュ・ギャングには主に4つのグループがある――クルシード・ギャング、ヌール・イスラーム・ギャング、サラーム・ギャング、サイード・ギャングである。
次に紹介するのはタクタク・ギャング。「タクタク(ठक्ठक)」とはヒンディー語でノック音のことで、日本語にするならコンコン・ギャングと言ったところか。ターゲットは主に自動車で、運転手がよそ見をしている間に、ボンネットや車内に置いてある金品を盗むのが彼らの常套手段である。赤信号のときに片側からドアをノックし、運転手の気を逸らして、別の側からもう1人が盗みを働くというのが基本のようだ。他に、わざと数枚の10ルピー紙幣を地面に落として運転手に「自動車の下にお金が入り込んでしまった」と言って注意を引いたり、「パンクしてる」と伝えて運転手の気を逸らしたり、様々な手段を用意している。人気のないところに駐車してある自動車のガラスを割って金品を盗むこともあるようだ。興味深いことに、タクタク・ギャングの95%はタミル・ナードゥ州出身だと言う。プシュプ・ヴィハール、マダンギール、アンベードカルナガル、ニザームッディーン、サンライト・コロニー、トリロークプリー、カリヤーンプリーなどに住んでいる。成人だけでなく、子供も仕事に参加する。デリーにはタクタグ・ギャングが12グループ活動中とのことである。
バイカーズ・ギャングは有名だ。バイクで疾走しながら歩行中の女性のハンドバッグや金のアクセサリーなどをひったくる連中である。他に凶器で脅して強盗をしたりもする。バイカーズ・ギャングの最大の武器は機動力で、ひったくりや強盗をした途端に現場から全速力で逃亡する。デリーには100以上のバイカーズ・ギャングのグループが暗躍しており、新聞にもよく彼らの仕業と思われる事件が載る。女性もこの犯罪に荷担することがあるらしく、男女2人乗りのバイクもこのバイカーズ・ギャングである可能性がある。デリーで生活をする上で、もっとも被害に遭う可能性の高いのがこのバイカーズ・ギャングであろう。
デリーの外からやって来て犯罪を行うのがメーワーティー・ギャングである。ハリヤーナー州のデリー隣接地域はメーワート地方と呼ばれており、メーワーティー・ギャングはその地方の村に住んでいる。メーワーティー・ギャングの主な生業は家畜の盗難である。夜中に軽トラックに乗ってやって来て、デリーの農村部などで家畜を盗んで持って行ってしまう。彼らの軽トラックには大量の石が積載されており、もし警察や近隣住民などが止めようとすると、投石して攻撃して来る。メーワーティー・ギャングは時にトラックやダンプカーの強盗も行う。メーワーティー・ギャングを取り締まるのは非常に困難である。なぜなら警察は彼らの住む村に容易に入れないからである。もし力尽くで犯人を逮捕しようとすると、村人たち全員が命がけで抵抗して来るため、手が出せない状態だと言う。
最後に紹介するのはオート・ギャングである。オートリクシャーに乗り込んで来た乗客から金品などを強奪するギャングだ。彼らは通常、数人でオートリクシャーに乗ってターゲットを探す。見た目が裕福そうで、荷物が多く、道に不案内そうな人を探し、声を掛ける。非常に安い運賃を提示し、乗客をオートに座らせる。運賃をシェアするという名目で、最初からオートには乗客の振りをした仲間が座っていることが多い。そして、巧みに乗客の気を逸らして荷物の中から貴重品を抜き取ったり、睡眠薬などを使って乗客を眠らし、一切合切を盗んで人気のない場所に放り出したりして、目的を遂げる。デリーには12グループほどのオート・ギャングが活動していると言う。
デリーでは、「コロニー」と呼ばれる高級住宅地は深夜になると必ず出入り口が閉ざされ、警備員が夜警をし、まるで要塞のような姿となる。これもこれらのギャングから住民を守るためである。区画の構造上、その守備範囲に入らない地域も出て来てしまうのだが、外国人はなるべくその防衛ラインの内側に住むのが安全だ。なぜデリーにいくつも残る中世の城塞が全て高い城壁を持っていたのか、それは現代とそんなに理由は変わらない。遠い外国からの侵略者よりも、近くに住むならず者の方が、都市在住者にとってはよっぽど怖かったのである。
ヒンディー語映画界のスーパースター、シャールク・カーンは、コレオグラファーから映画監督に転身したファラー・カーンと共に「Main Hoon
Na」(2004年)と「Om Shanti Om」(2007年)の2本を世に送り出し、どちらも大ヒットとなった。シャールク・カーンとファラー・カーンのゴールデン・コンビは、今後も数々のヒット作を送り出してくれるだろうと期待されていたのだが、「Om
Shanti Om」公開後にこの2人の不仲が報道されるようになり、とうとうファラー・カーンは監督第3作目の主演をアクシャイ・クマールに据え、「Tees
Maar Khan」(2010年)を作った。だが、この映画は大コケしてしまった。
どうやらシャールク・カーンとファラー・カーンの不仲の原因となったのは、ファラー・カーンの8歳年下の夫シリーシュ・クンダルの存在であった。シリーシュ・クンダルはフロップ作「Jaan-e-Mann」(2006年)の映画監督として知られている。シャールク・カーンが、シリーシュ・クンダルの映画に出演することを拒んだために、ファラー・カーンとの戦いが勃発してしまったとされている。後に仲直りしたと報道されているのだが、どうもまだシコリが残っている感じだ。
このシリーシュ・クンダル、映画監督としては、どうもあまり才能がない人物のようである。シャールク・カーンが出演を断ったのも、どうやらそれが一番の理由のようで、プロとしては真っ当な判断だと言える。ファラー・カーンの方が圧倒的に才能もあるし業績もある。だが、彼女は妻として、健気に夫の肩を持っている。それが最近、彼女の才能やネットワークを束縛しているように思えてならない。シリーシュ・クンダルの新作「Joker」が今日から公開されたが、公開前からその出来には疑問の声が上がっていた。主演は「Tees
Maar Khan」と同様にアクシャイ・クマール、ヒロインはソーナークシー・スィナー。2人とも最近当たっている俳優である。シリーシュ・クンダルは汚名返上なるだろうか?
題名:Joker
読み:ジョーカー
意味:ジョーカー
邦題:ジョーカー
監督:シリーシュ・クンダル
制作:ロニー・スクリューワーラー、ファラー・カーン
音楽:GVプラカーシュ・クマール、ガウラヴ・ダーガーオンカル
歌詞:シリーシュ・クンダル
出演:アクシャイ・クマール、ソーナークシー・スィナー、シュレーヤス・タルパデー、ミニシャー・ラーンバー、アスラーニー、サンジャイ・ミシュラー、ダルシャン・ジャリーワーラー、アレックス・オニール、チトラーンガダー・スィン(特別出演)、ファラー・カーン(特別出演)
備考:PVRプリヤーで鑑賞。

ソーナークシー・スィナー(中央左)とアクシャイ・クマール(中央右)
| あらすじ |
パグラープルは、ウッタル・プラデーシュ州とマディヤ・プラデーシュ州とラージャスターン州の狭間に位置する村だった。まだインドが英国の植民地だった1946年、英国人高官が視察に訪れたのだが、この村にあった精神病院から精神病患者が大脱走し、大混乱となっていたため、視察が完了しなかった。そのためにパグラープルは地図に載ることはなく、どの州にも組み込まれなかった。
所と時代が変わって現代の米国。アガスティヤ(アクシャイ・クマール)は宇宙人との交信を試みる科学者であった。だが、2年間何の手掛かりも得られず、資金提供をした企業から叱責を受けた。何とか1ヶ月だけ猶予をもらえたが、その短期間で成果が出せるか疑問であった。同時に、彼の父親が危篤だという連絡が彼の弟からあった。アガスティヤと同棲する恋人のディーヴァー(ソーナークシー・スィナー)は、彼と共にインドに行くことになる。
アガスティヤはパグラープルの出身だった。アガスティヤはディーヴァーに村のこと、父のこと、弟のことなど全く話したことがなかった。だが、ディーヴァーは村について納得する。パグラープルの村人たちは皆どこかおかしいのである。アガスティヤの弟バッバン(シュレーヤス・タルパデー)は得体の知れない言葉をしゃべるし、教師(アスラーニー)は未だに第二次世界大戦が終わっていないと勘違いしているし、ラージャージー(サンジャイ・ミシュラー)は自分のことを王様だと思って生きている。アガスティヤの父親(ダルシャン・ジャリーワーラー)はパグラープルの村長であったが、病気というのは嘘で、単にアガスティヤを村に呼び戻すための言い訳に過ぎなかった。
アガスティヤは、スポンサー企業から与えられた1ヶ月という貴重な時間を、父親や弟の嘘のために無駄にしてしまったために激怒し、夜中にディーヴァーを連れて村を出ようとする。だが、結局彼らを許し、村人たちの悩みを聞くことにする。
パグラープルが直面していた大きな問題は近くに出来たダムであった。このダムのためにパグラープルの近くを流れる川が干上がってしまい、農業が出来ずにいた。アガスティヤはウッタル・プラデーシュ州、マディヤ・プラデーシュ州、ラージャスターン州の州首相に順に直談判するが、誰もパグラープルは自州にはないと言って責任逃れをする。そこでアガスティヤは別の手段を考えなくてはならなくなる。
ふと彼はテレビで、ミステリーサークルのニュースを目にする。ひらめいたアガスティヤはパグラープルにもミステリーサークルを偽造し、それを無線で流す。たちまちの内にパグラープルに世界中からメディアが集まって来た。その中にはレポーターのニミシャー(ミニシャー・ラーンバー)もいた。そのおかげでパグラープルは一気に潤う。ところが、米国でアガスティヤのライバルだったサイモン(アレックス・オニール)も来てしまう。サイモンは、ミステリーサークルが偽物だと言いふらす。パグラープルに集まったメディアは一気に帰途に就く。
今度はアガスティヤは村人に宇宙人の変装をさせて登場させる。またもメディアがパグラープルに殺到する。地球への侵略者かもしれないということで、今度は軍隊までやって来る。サイモンは必死でその正体を暴こうとするが、アガスティヤは彼を拉致して閉じ込める。米国人が宇宙人に拉致されたことで、FBIまで出動して来て大事になる。
世界中の注目を浴びたことで、パグラープルには3州の州首相が同時にやって来て、是非パグラープルを自分の州に組み込もうとする。アガスティヤは、村のために一番貢献した州政府の州に入ると宣言する。おかげで今まで電気もなかったパグラープルに電気と水道が来る。
そろそろ潮時と見たアガスティヤは、サイモンを解放し、宇宙人の帰還を演出する。しかしサイモンの妨害によって宇宙人が村人であることがばれてしまう。アガスティヤは首謀者として逮捕される。バッバンは、アガスティヤが米国から持参した交信器を使って宇宙人に助けを求める。すると、本物の宇宙人が空飛ぶ円盤に乗ってやって来る。なんとバッバンがしゃべる意味不明の言葉を宇宙人もしゃべっていた。意思疎通が成り立ち、バッバンと宇宙人は親友となる。宇宙人が宇宙へ帰って行くが、お土産を置いて行く。そのお土産とは石油であった。昔からパグラープルには石油が産出すると言われていた。だが、誰も見つけられずにいた。今、パグラープルからは石油が噴出した。それに目の色を変えた3州の州首相は我先にとパグラープルを自州に組み込もうとするが、アガスティヤはそれらを全てはねのけ、どの州にも入らないと宣言する。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
もし国際ゲテモノ映画祭なるものがあったら、今年のインド代表はこの作品で決まりだろう。シリーシュ・クンダルというのは本当にどうしようもない映画監督であることが今はっきりした。「Joker」は本当にどうしようもない映画である。素人が作ったとしか思えない。狂人だらけの村を舞台にした映画だが、こっちまで狂人になりそうだった。
舞台となったパグラープルとは「狂人の町」という意味で、1946年に精神病院から脱走した精神病患者たちが作った村である。題名の「Joker」とは、インドの地図から排除され、どの州にも属さないパグラープルの状態を示している。トランプの中でジョーカーはどの色にも属していないからである。しかし、ミステリーサークルが出現し、宇宙人が発見されたことで、パグラープルは正にトランプゲームを制するジョーカーのような立場となる。題名の付け方は面白いと思う。
だが、ストーリーは滅茶苦茶だ。そもそもパグラープルの村人たちが主人公アガスティヤを米国から呼び戻したのは、近くに出来たダムの問題を解決するためだった。しかし、ダムの問題はすぐに忘れ去られてしまい、エンディングまでそのことに触れられることはない。アガスティヤは宇宙人との交信を試みる科学者であるが、この設定は「Koi...
Mil Gaya」(2003年)と全く同じで、今頃なぜ二番煎じをしているのか疑問である。しかも最後には宇宙人が本当に現れるが、CG丸出しの陳腐なスタイルの宇宙人で失笑。パグラープルのセットも非常にチャチで、美的センスが全く感じられなかった。また、辺鄙な村に突如メディアが集まる様子は、「Peepli
[Live]」(2010年)の真似としか考えられない。「Koi... Mil Gaya」と「Peepli [Live]」の劣化コピーのような映画であった。
僕がこの映画で一番不快に感じたことは、村の「発展」の幼稚な定義づけである。ミステリーサークルが出現し、宇宙人が目撃されたことで、3州がパグラープルの領有権を主張し、競って村のインフラ投資を行う。電気がなかった村に電気が通るのはいい。水道がなかった村に水道が通るのもいい。だが、マクドナルドやコカコーラの看板を村中に設置して「発展」と名付けるのはいかがなものだろうか?多国籍企業の進出をもって「発展」としてしまっていいのだろうか?自給自足の生活を送って来た村を、一夜の内に都会のようにネオン輝く場所とすることで、「発展」させたことになるのだろうか?インドには確かにまだ電気の通っていない村がたくさんある。だが、このような状態を「発展」と名付けて映像化して見せ付けるのは、非常にグロテスクな行為だ。
しかし、おそらくファラー・カーンが振り付けを担当したのだろう、ダンスシーンは非常に豪華であった。特にチトラーンガダー・スィンがアイテムガール出演する「Kaafirana」は前半のハイライトだ。この映画を完全なる失敗作に陥ることから唯一救っていたのは、間違いなくダンスシーンである。
アクシャイ・クマールは最近「Houseful 2」(2012年)や「Rowdy Rathore」(2012年)など順調にヒット作を飛ばしており、かつての勢いを取り戻しつつある。だが、この「Joker」で再びダウンだ。彼自体の演技は悪くなかったが、このような失敗作に出演したことは、後々まで彼のキャリアの傷となるだろう。
一方、ソーナークシー・スィナーは光っていた。劇中、そこまで重要な役割を果たす訳でもないのだが、肉厚感ある彼女の存在感は映画に花を添えていた。細身の女優が多い中で、彼女だけは異様にポッチャリしており、健康的な女性を好むインド人ファンの支持を受けている。「Dabangg」(2010年)、「Rowdy
Rathore」とヒット作に恵まれており、スターとしてのオーラも出て来た。彼女にとっては、この映画への出演はマイナスにならないはずである。サブヒロインのミニシャー・ラーンバーが細身であるため、より彼女の肉厚感が目立った。ミニシャーはさらに目立たない役だった。
他にシュレーヤス・タルパデー、ダルシャン・ジャリーワーラー、サンジャイ・ミシュラー、アスラーニーなどがパグラープルの狂った村人として出演している。彼らのぶっ飛んだ演技のおかげで、ハチャメチャなストーリーの中でも笑いはしっかりとあった。チトラーンガダー・スィンのダンスも良かった。
音楽は主にGVプラカーシュ・クマール。彼はARレヘマーンの甥にあたる。ARレヘマーンはヒンドゥー教徒からイスラーム教徒に改宗したが、彼はヒンドゥー教徒のままのようである。レヘマーンほどの才能はないと思うが、ヒット曲を作れるだけの才能はあるだろう。ただ、「Joker」の中で一番ヒットしている「Kafirana」はガウラヴ・ダーガーオンカルの作曲である。
「Joker」は、前に向かって進もうとしていたヒンディー語映画を後ろから足カックンして転ばせるような、奇襲的駄作である。子供向け映画と割り切るならそれでもいいが、子供でもそんなに楽しめないのではないかと思う。シリーシュ・クンダルは監督業から足を洗うべきである。そしてファラー・カーンにもっと自由に映画を作らせるべきである。ゲテモノがどれだけゲテモノなのか確認したいという奇特な人以外は「Joker」は見ない方がいいだろう。



