 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
 これでインディア これでインディア 
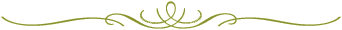
2003年1月
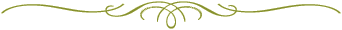
|
|
|
|
昨年は2001年最後の夕日と2002年初日の出を見ることにかなり気合を入れていたが、今年はマーンダウののんびりとした土地柄のせいか、あまり気合が入らなかった。2003年の初日の出はホテルの近くに建っている廃墟から眺めた。マディヤ・プラデーシュ州のどこまでも続く地平線から昇る太陽、というのをイメージしていたのだが、目の前にあった木が邪魔して地平線が見えなかった。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
2003年初日の出 |
● |
今日はレーワー・クンド・グループのループマティー・マンダプから観光を開始した。ここも入場料100ルピーが必要である。ループマティー・マンダプは元々兵士たちの駐屯所だが、マーンダウのスルターン、バージバハードゥル・シャーの愛妃ループマティーの名前が付けられている。バージバハードゥル・シャーとループマティーの恋愛はインド人なら誰もが知っていると言うほど有名らしく、以下のようなストーリーが語り継がれている。
| ループマティー |
| マーンダウの16世紀のスルターン、バージバハードゥル・シャーは音楽愛好家として知られ、自身も音楽をよくした。あるときバージバハードゥルがマーンダウの南28Km、ナルマダー河河畔のダラムプリー周辺で狩りをしていると、美しい歌声を聞いた。その声の主はループマティーという美しい女性で、ラージプートの地主ターンスィンの娘だった。その声と美貌に惚れこんだバージバハードゥルは、彼女を宮廷へ招待し、シャーヒー・マハルに住まわせた。ところがループマティーは信仰心の厚い女性で、毎朝ナルマダー河にお祈りをするのを習慣としていた。シャーヒー・マハルからナルマダー河は見えないため、ループマティーは毎朝輿に乗ってマーンダウ城の最南端にある駐屯所からナルマダー河にお祈りをしていた。 |
ループマティー・マンダプから日の出を眺めたら、けっこう素晴らしかったかもしれない。今日はやたらとインド人観光客が多くて、僕は「写真を撮らせてくれ」攻撃にさらされた。僕が観光に来たのに、僕自身が観光対象になってしまった・・・。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
ループマティー・マンダプ |
● |
ループマティー・マンダプの近くにはバージバハードゥル・マハルがある。ここはもともとナースィル・シャーが1508年に建造した宮殿だったが、バージバハードゥル・シャーによって音楽ホールとなった。ここでバージバハードゥル・シャーとループマティーの華麗なる共演が繰り広げられたという・・・。
バージバハードゥル・マハルより少し北に、エコー・ポイントと呼ばれる場所がある。マーンダウ村とループマティー・マンダプを結ぶ道の途中に長方形の石が無造作に置かれているだけだが、その上に乗って東に向かって叫ぶと声がコダマして返って来る。不思議なことに、その石の周辺でしかコダマは起こらない。さすがにインド人はこの手のものが大好きで、このエコー・ポイントに来ると、物好きなインド人たちの叫び声が頻繁に聞こえてくる。僕は「エ〜イド〜リア〜ン!」と叫んでおいた。びっくりするほど跳ね返ってくる。
レーワー・クンド遺跡群で最後に見たのはニールカント寺院。ここはモスクがシヴァ寺院になっており興味深い。もともとシヴァ寺院があったのを、ムスリムの支配者が破壊してモスクにし、その後再びヒンドゥー教徒がヒンドゥー寺院に改変したものらしい。壁にはウルドゥー語が刻まれているのだが、シヴァリンガを参拝するヒンドゥー教徒で賑わっている。今日は1月1日ということで、これが期せずして初詣でになってしまった。
昨日はトラヴェラーズ・ロッジに宿泊したが、今日は再びループマティー・ホテルに宿を変えた。マーンダウで快適に過ごそうと思うなら、このホテルがもっともよい、というかこのホテルしかない。ジェネレーターがあるホテルはここだけだし、食事もおいしいし、気持ちのいいテラスや庭があって、山間のヴァカンスを満喫できる。
マーンダウは空気もきれいで気候もよく、またのどかな農村と素朴な村人たちが心地よく、時間さえ許せばしばらく腰を落ち着けて滞在したくなるような場所だった。しかし他にも行きたいところがあるので、今日マーンダウを去ることにした。
マーンダウ最後の時を満喫しようと、昼頃までループマティー・ホテルの庭でブランチをとりながらゆっくりしていた。すると1人のインド人のおばさんが近付いてきて、なぜかリンゴをくれた。食後にリンゴを食べていると、また同じおばさんが近付いてきた。僕が「リンゴおいしかったです。」と言うと、おばさんは僕に「あなたはトライブ(部族民)か?」と聞いてきた。今まで「ネパーリーか?」と聞かれたことはあれ、トライブだと聞かれたことはない。少々びっくりしつつも「日本人です。」と答え、「あなたはどこの人ですか?」と聞き返したら、「私はトライブだ。この辺に住んでいる。」と答えた。マディヤ・プラデーシュ州には、ドラヴィダ人やアーリヤ人がインドにやって来る前から住んでいたと思われる、多くの先住民、部族民が住んでいる。マーンダウの村に住んでいる人々も実はほとんどがトライブらしい。そのおばさんは部族民の中でもリッチな階級みたいで、わざわざマーンダウの高級ホテルに家族と共にやって来て宿泊していた。
行きと同じく、帰りもダールでバスを乗り換えてインダウルまで戻った。道が非常に悪く、まるで船に乗って荒波の中を進んでいるかのような揺れ具合だった。マーンダウからダールまで約2時間、ダールからインダウルまで約3時間かかった。
マーンダウ〜ダール〜インダウルのバスに乗っていて気付いたことだが、やはりこの辺りに住んでいる人々は、普通のインド人と少し人種や文化が違う。顔付きがまるでマサイ族みたいだったり、東南アジア人みたいだったりする。女性の服装も、サーリーを着てはいるものの、なんか違う。この周辺はトライブ密集地域のようだ。やはりマディヤ・プラデーシュ州は面白い。
午後5時頃、やっとのことでインダウルに到着した。インダウルの市街地に入ると一気に空気が悪くなったのを感じた。これに比べたら、デリーの空気はまだマシな方だ。デリー政府が推進しているCNG化計画は、もしかしたら功を奏しているのかもしれない。
インダウルの近くには密かにヒンドゥー教の聖地が密集している。4大聖地のひとつウッジャインや、12ジョーティルリンガの中のふたつ、マヘーシュワルとオームカーレーシュワルである。全部行ってみたい、というのが本音だが、今日はその中でも特に興味を引いたオームカーレーシュワルへ行ってみた。
オームカーレーシュワルはナルマダー河とケーヴェーリー河の合流点にある川中島である。インダウルの南、約77Kmの地点に位置している。この島のユニークな点は、島の形がヒンドゥー教の聖印「オーム」の形をしていることである。普通、ヒンドゥー教の巡礼者たちは、この島のオームカール寺院に安置されているシヴァ・リンガを参拝しに来るのだが、僕は本当に「オーム」の形をしているのか確かめに行ってみた。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
オームカーレーシュワル島は
ヒンドゥー教の聖印
「オーム」の形をしている |
● |
インダウルからオームカーレーシュワルへは直通バスが出ており、約2時間半ほどかかった。オームカーレーシュワルのバス停から島までは、ずっと参拝道が続いており、道の両側にはお土産屋がズラリと並んでいる。ヒンドゥー教聖地によく見られる風景である。そのまま参拝道に沿って進んでいくと、次第にオームカーレーシュワル島の姿が眼前に現れ始める。そのまま参道沿いに進めば橋に出るし、途中にある階段を降りていけば河畔に出る。その橋を渡って島へ渡ることもできるし、河まで降りて舟で渡ることもできる。舟の運賃は1人5ルピーと言われた。特に舟に思い入れはないので、僕は橋を歩いて渡った。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
オームカーレーシュワル島 |
● |
橋を渡って島に着くと、さらに参拝道が続いている。参拝道の終点にオームカール寺院がある。異教徒でも簡単に入ることができたので、僕もノコノコと入らせてもらった。外見は新しい寺院だが、中は薄暗くて歴史がありそうだった。寺院内は「オーム・ナマー・シヴァー・・・」というマントラが継続的に流れ、なんだかボーッとして来る。狭い入り口から腰をかがめてリンガのある小部屋へ入る。そこには底の浅いお椀をひっくり返したような形の、黒いリンガが置いてあった。これが12リンガのひとつか・・・。正直言ってあまり迫力がない。巡礼者たちは熱心にそのリンガに花や葉っぱや水を捧げていた。僕はただ手を合わせて花を掛けておいただけだった。
オームカーレーシュワル島はこんもりとした山になっており、オームカール寺院はその中腹部にある。そこからさらに上に登っていくと、山頂にはスィッドナート寺院がある。1000年以上前の寺院で、半壊しているものの、基壇部は残存しており、美しい彫刻を持つ柱が列を成して並んでいる。寺院内部にはシヴァリンガが安置されていた。また、寺院の外周部分一面に生き生きとした象の彫刻が彫られており、息を呑む。今にも動き出しそうな躍動感に満ち溢れた彫刻で、こんなのはインドで初めて見た。また、寺院の壁に刻まれている半裸の女たちの顔のいくつかは、典型的なインド人顔ではなく、むしろトライブっぽい感じがしたのも印象的だった。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
スィッドナート寺院の象の彫刻 |
● |
スィッドナート寺院の辺りはちょうど山の頂上になっているのだが、それでも島全体を見渡せるほどの高さはない。だから本当にオームカーレーシュワル島がオーム型をしているのか、見極めることができなかった。しかし、島の半分くらいを歩いて観察してみた結果、オームっぽい形はしているかもしれない、と思うようにはなった。
オームカーレーシュワルは日本人には全然有名な観光地ではないが、ロンリー・プラネットに掲載されているため、白人旅行者が少し訪れる。町の雰囲気はヴァーラーナスィーに似ており、ヴァーラーナスィーに飽きたらしき長期滞在型白人バックパッカーたちをチラホラと見かけた。こんな地の果てまでやって来るとは、お互いご苦労様である・・・。まだ旅行者向け施設はほとんど完備されておらず宿や食事にすら困るくらい(巡礼宿や巡礼者向け食堂しかない)だが、おそらくここも10年後には立派な観光地になっているのではなかろうか。
オームカーレーシュワルはシヴァ色の強い場所だが、ここの一般的な挨拶は「ハリ・オーム」である(ハリ=ヴィシュヌ神)。最初道端の子供から「ハリ・オーム」と言われたとき、「ハリョー」と聞こえて、「ハロー」が訛って「ハリョー」になったのだろうと勝手に思考を巡らせていた。「ハリ・オーム」だと理解した後は、人に会うたびに「ハリ・オーム」と挨拶してみた。
4時頃にオームカーレーシュワルのバス停でインダウル行きのバスに乗った。オームカーレーシュワルはツーリスト・スポットの邪悪な雰囲気から離れてのんびり滞在するのにちょうどいいところに思えた。おそらく滞在費もかなり安く済むだろう。
デリーからインダウルに向かう列車の中で、インダウル在住のインド人の女の子から、インダウルのグルメ・スポットを教えてもらっていた。彼女が言うには、インダウルのマハーラージャーの宮殿、ラージワーラー近くのサラーファーというところがおいしいらしい。しかし午後9:30から始まるそうだ。なんだか高級なレストランを勝手にイメージしていた。実は昨日も夕方にサラーファーなるレストランを探しにラージワーラー近くのマーケットを散策した。しかし、サラーファーという地区は発見したが、サラーファーというレストランは発見できなかった。いろんな人に尋ねてみたが、誰も知らなかった。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
ラージワーラー |
● |
今日もレストラン・サラーファーを探しにサラーファー地区を訪れた。サラーファーは宝石・貴金属市場となっており、昨日は7時頃に訪れたために道は宝石屋できらびやかに覆われており、目が眩しいくらいだった。しかし今日は9時過ぎに訪れたため、ほとんどの宝石屋は閉まっていた。代わりに閉じたシャッターの前に多くの屋台が並んでおり、一帯は屋台市場と化していた。そして多くのインド人たちが立ち食いを楽しんでいた。今日もいろんな人にサラーファー・レストランを尋ねてみたが、やはり誰も知らなかった。虚しい気分になってサラーファーを去ったが、後でよく考えてみたらあの女の子は夜9:30以降に始まるあの屋台市場のことを教えてくれたのだと気付いた。早とちりした僕は、勝手にレストラン・サラーファーなる幻の高級レストランを思い浮かべて探し回っていたようだ・・・。あのサラーファーの屋台、おいしそうだったな・・・。
今日はインダウルの観光をした。まずは博物館へ。一般的なインドの博物館、という感じで、まず屋外にヒンドゥー教の神様の彫刻が無造作に並べられており、全く保存に関して配慮がなされていない。屋内はだだっ広くて、順路がよく分からず、展示物の説明が不親切である。この博物館には、ウッジャインより北の、マンサウル地区から発見された彫刻が多かった。マンサウルという場所はガイドブックでも白紙地帯になっているが、展示品を見た限りでは多くの遺跡が残っている地域に思えた。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
ヴィーナーを弾くシヴァの彫刻
けっこう珍しいのでは? |
● |
博物館の後はカーンチ寺院へ行った。カーンチ寺院はジャイナ教寺院であり、マーケットの一角にある小さな寺院なのだが、中に入ってビックリ、天井から床から四方の壁まで、全て鏡。まるで遊園地によくあるミラーハウスのような寺院である。顔が映る普通の鏡もあるが、大部分は着色された鏡か、ジャイナ教の教義に関する鏡の絵で覆われていた。ジャイナ教徒には金持ちが多いため、時々莫大な金を掛けたと思われるジャイナ教寺院が存在する。このカーンチ寺院もその内のひとつである。
カーンチ寺院は昨日行ったサラーファーやラージワーラーの近くで、この辺り一帯はインダウル旧市街、巨大なマーケットとなっている。ラージワーラー中心にマーケットは形成されており、区画ごとに売られているものが全く違う。衣服のマーケットには布地、サーリーや衣服しか売られていないのだが、ふと角を曲がると今度は文房具品マーケットとなり、文房具やグリーティング・カードを売る店オンリーとなる。非常にきれいに整理されたマーケットに思えた。また、ここのマーケットで気付いたのだが、地方で本屋と言ったらヒンディー語の本しか売っていない。デリーでは本屋と言ったら英語の本しか売っておらず、ヒンディー語の本を買うためにはオールド・デリーにある特別な本屋に行くしかないのだが、地方都市では英語の本を買う方が困難のようだ。
3時20分にインダウルのバス停でボーパール行きのバスに乗り込んだ。今回の旅行で、ボーパールが最終滞在地となる。ボーパールからデリーに戻る予定だ。ボーパール訪問はこれで通算3度目となる。
案外バスは順調に進み、8時頃にボーパールへ到着。ウッタル・プラデーシュ州のバス移動には閉口したが、マディヤ・プラデーシュ州のバスは非常に便利である。ハミーディヤー・ロードのホテルに泊まることにした。
帰りのチケットを予約していなかったので、ボーパール駅の予約オフィスへチケットを予約しに行った。昨年の同じ時期にアーンドラ・プラデーシュ州の州都ハイダラーバードからデリー行きのチケットを取ろうとしたとき、予約がいっぱいで普通の方法では取れなかった。インド人の冬休みと重なっている――というか、僕もインドの学校に通っている輩なのだが――ので、帰省ラッシュに巻き込まれてしまうのだ。密かに心配しながら予約オフィスへ入った。
ボーパールの鉄道予約オフィスは、日本の銀行みたいにまず番号券を取って、自分の番号が呼ばれるまで待つシステムになっている。ニューデリー駅の予約オフィスは、予約窓口の前にできている長蛇の列に並ばなければならないので、デリーよりも進んでいるといえる。番号はカウンター番号と共に電光掲示板に表示される。その番号券を守ろうとしないインド人もいなくて、非常にスムーズに予約窓口まで辿り着くことができた。列車のチケットも何の問題もなく取ることができた。しかし、予約オフィスの中には各列車の1ヶ月間の空席状況がズラリと表示されるモニターもあり、それを見た限りでは1月10日前後まで各列車の空席は非常に少なかった。
ボーパール駅のプラットフォームにも電光掲示板が設置され、各プラットフォームにどの列車が何時に来るか表示されていた。面白かったのは、列車番号、列車名、発車時刻の他に、「Late」の欄があったことだ。つまり、どれだけ遅れているかを表示する欄があった。見てみると、「Late」の欄が「0:00」になっている列車はなかった。「遅れるのが当然です」と暗に言われているみたいで苦笑した。
無事に席が取れて安心してしまったので、今日は特に何もせずに休んだ。
2002年の11月にボーパールを訪れた際、真っ先にビームベートカーへ向かったが、今回ももう一度ビームベートカーを見てみたくて足を運んだ。前回と同じくオートリクシャーをチャーターしてボーパールから約50Km離れたビームベートカーを訪れた。オート・ワーラーも行ったことがなく、僕が道を教えながら行った。300ルピーで事前に交渉したが、結局「こんなに遠いとは思ってなかった」とごねられて350ルピーになった。
ビームベートカーは相変わらず入場料なし。法外な外国人料金がはこびるインドの観光地において、ここの存在はオアシスのようだ。前回訪れたときとあまり変わっていなかったが、以前よりも管理が少しだけ厳しくなっているように感じた。それにしてもこんなところを何度も訪れる外国人は僕だけだろう。
今回も立入禁止区域を歩き回って、公開されていない壁画を見て廻った。どうも一般公開されている壁画は、一目で何が描かれているか理解できるものが中心のようだ。それ以外の壁画の中には、非常に巨大ながら何を描いているのかよく分からないものなどが多い。また、どうも誰かが悪戯して描いたと思われるものもあった。
ビームベートカーはボーパールから2時間弱かかり、宿泊施設やレストランなども皆無で、トイレすらないので、まだ観光地としては未開発状態である。しかし次第に紹介され始めたようで、観光客も増え続けており、その内観光客向け施設も整うだろう。また、まだ一般公開されている地区はほんの一部なので、さらに広域に渡って一般公開をすれば、十分多くの観光客を呼び込めるだけの魅力を持ったスポットである。これほど多くの壁画が残っている場所は、インドはおろか世界でも稀なので、是非もっと多くの人に見てもらいたいと思っている。
ボーパールにはあまり見所がないが、前回の訪問で考古学博物館に行くことができなかったので、行くことにした。またもやオート・リクシャーが場所を知らなくて、科学博物館という違う博物館に連れて行かれ、しかもそこの博物館の人が考古学博物館を知らなかったので、多少トラブルに巻き込まれたが、なんとか辿り着くことができた。
入場料は設定されていたはずだが、なぜか入場料を徴収されずフリーで入ることができた。ちょうど「Ram Katha」という特別展示が行われており、ラーマーヤナのストーリーがインド各地に残る16〜18世紀の細密画によって再現されていた。ラーマ王子の誕生からヴィシュヴァーミトラ仙との修行の旅、スィーターとの結婚、スィーターの誘拐、ラーマとハヌマーンの出会い、ラーヴァナ討伐、アグニパリクシャー、アヨーディヤー帰還、スィーターの追放、ラヴァとクシャの武勇など、お馴染みのシーンが数々の細密画で描かれていて、非常に参考になった。しかし、これらの細密画は本物ではなく、写真だった。もし本物が展示されていたらどんなに素晴らしかったことか。
考古学博物館のメインの展示は、あまり数が多くないが、どれも逸品揃いだった。全て6世紀〜10世紀のヒンドゥー教の神像で、特にカールッティケーヤ像とルドラ・シヴァ像が素晴らしかった。カールッティケーヤ像は若いブラーフマンの姿をしており、左手に鶏を握っていた。全く他のヒンドゥーの神像と様式が違い、まるでルネッサンス期の彫刻のような躍動感があった。マンサウルから出土したらしい。ルドラ・シヴァ像は、この博物館でもっとも目を引く巨大な像で、恐ろしい姿ながら愛嬌があり、これも他のヒンドゥーの神像と一線を画していた。ここの博物館は小さいながらもユニークな展示物があって、必見の場所かもしれない。
| ● |
|
● |
|
 |
|
|
ルドラ・シヴァ |
|
|
 |
|
|
カールッティケーヤ |
|
|
 |
|
| ● |
シヴァ |
● |
博物館を見た後はボーパール旧市街を歩いた。この辺りには古い建物がいくつか残っているものの、どれも保存状態がよくなくて、ほとんど崩壊してしまっている。普通、インドの都市は新市街よりも旧市街の方が面白いことが多いのだが、ボーパールは新市街であるTTナガルの方が、人類学博物館や考古学博物館、バーラト・バヴァンやヴァン・ヴィハールなど、面白い見所が多いような気がする。
しかし泊まっているところは旧市街なので、ボーパールのホテル街であるハミーディヤー・ロード近辺にはかなり詳しくなった。この辺りでおいしいレストランと言ったら、ハミーディヤー・ロードの東端、ランジート・レストランだろう。インド料理、中華料理からコンティネンタル料理まで何でも揃っており、値段もお手頃でおすすめである。ここのチキン・スィザラーはうまい。また、ヴェジタリアン料理だったら同じくハミーディヤー・ロード沿いのマノーハル・レストランがおいしい。ここはミターイー(甘いお菓子一般)やナムキーン(塩味の菓子一般)、フルーツ・ジュースも売っており、いつも地元の人で賑わっている。
また、ランジート・レストランの前には映画館がある。ここの映画館は日替わりでポルノ映画を上映している。その映画館の横にはインディアン・コーヒー・ハウスがあり、ここの食事もおいしいが、映画館の影響からか、ここで食べていると売春婦らしき女(あくまで予想だが)が食事をしているのを見ることができる。なかなかボーパールが好きになりつつある。
夜9時25分、デリーのニザームッディーン駅行きのボーパール・エクスプレスに乗った。そんなに寒くはなかったが、極寒のデリーに備えて寝袋に入って寝た。
寒さで目が覚めた。TVや新聞で度々北インド一帯を寒波が襲っているというニュースを目にしたが、本当にデリーに向かう列車内部は寒くなっていた。こんなに寒かったのか、というくらい寒い。列車は時間通り8時頃ニザームッディーン駅に到着し、外に出てみた。やはり寒い。デリーを出たときよりも確実に寒くなっている。冬休みが終わるときに一番寒くなったのでは、冬休みの意味がないではないか。もっと遅く帰って来ればよかった、と思いつつ家へ急いだ。
家に帰ると僕を待っていたのは停電。この寒さの中で停電では、もうやる気もない。ただひたすら毛布にくるまって、春が来るのを待つしかない・・・。手足の指先が凍えて、何もする気が起こらない。デリーでは12月31日に雨が降ったらしく、それ以降急激に寒くなったそうだ。クリスマス・イヴの雨といい、大晦日の雨といい、正月の寒波といい、最近のデリーの気候はなんかいじけてるみたいだ。
| ◆ |
1月10日(金) Bolliwood Holliwood |
◆ |
旅行に行っている間にまた面白そうな映画がいくつか公開された。その中で今注目のヒングリッシュ映画に分類される「Bolliwood Holliwood」を見に、ラージパト・ナガルに新しく完成した高級映画館3C’sへ行った。
3C’sのチケットはフロント・シートが100ルピー、リア・シートが150ルピー。座席数は325席で、中規模映画館といった感じだ。座席の色はPVRの青色に対抗してか赤で統一されている。映画館の天井が星空のようになっており、とりあえず高級感はある。音響設備は申し分なく、低音がズンズンと響いてきて気持ちいい。このインドの高級映画館の高音質大音響に慣れてしまうと、日本の映画館の音が物足りなくなるくらいだ。今回客層は若者が多かった。
「Bolliwood Holliwood」はインド人監督、インド人俳優主体、アメリカ・ロケの英語映画である。監督はディーパー・メヘター、主演はラーフル・カンナー(アクシャイ・カンナーの弟)、リサ・レイ、ジェシカ・ペレ、モーシュミー・チャタルジー、ディーナー・パータクなど。ちなみにアクシャイ・カンナーがアクシャイ・カンナー役で特別出演する。
| ● |
|
● |
|
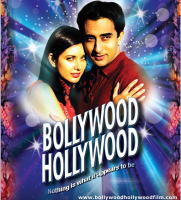 |
|
| ● |
リサ・レイ(左)と
ラーフル・カンナー(右) |
● |
| Bolliwood Holliwood |
ラーフル(ラーフル・カンナー)はアメリカ在住のインド人で大富豪。彼は白人のガールフレンドで人気アイドルのキンバレー(ジェシカ・ペレ)と結婚しようとしたが家族に反対される。何の因縁か、キンバレーは撮影中の事故で急死してしまう。悲しむラーフルを尻目に、母親(モーシュミー・チャタルジー)はラーフルの花嫁探しを開始する。どうしてもラーフルの姉の結婚式までに、ラーフルの婚約者を決めておきたかったのだ。しかし母親はラーフルの花嫁に絶対的な条件を勝手に決めていた。相手はインド人でなくてはならない、という条件である。
そんな中、ラーフルはクラブで1人の女の子と出会う。彼女の名前はスー(リサ・レイ)。最初ラーフルは彼女をスペイン人と勘違いするが、実際は彼女はインド人だった。ラーフルは彼女を一時しのぎの婚約者に仕立て上げ、なんとか急場を凌ごうとする。ラーフルは彼女に大金を渡してうまく口裏を合わせてもらう。
ラーフルはスーを家族に紹介する。とにかくインド人の婚約者が決まってラーフルの家族は大喜びする。スーは家族に溶け込み、次第にラーフルも彼女に惹かれていく。そして遂にラーフルはスーに愛の告白をする。
ところがスーは売春婦だった。それが発覚するとラーフルは彼女との結婚を取りやめる。家族にもそれを説明する。しかしラーフルは彼女を忘れることができなかった。ラーフルはスーの家へ行きプロポーズをする。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
デリーでは割とヒットしているみたいだが、イマイチの映画に思えた。ストーリーに起伏がなくて、盛り上がりに欠ける。基本的にラヴコメだったのだが、ギャグが稚拙でまるで日本のTVのコント劇のようなシーンもあった。僕は予め「Bolliwood Holliwood」のCDを買っており、けっこういい曲が多いと思っていたのだが、それらの音楽の使われ方が納得できなかった。もっと映画の中で使って欲しいと思うようないい曲が、お情け程度に挿入されるだけだった。音楽監督サンディープ・チャウターもこれでは納得いってないだろう。最後のクレジット・シーンで流れる「Chin
Chin Choo」だけが光っていたが、なにしろ最後なので、そのシーンを見ずに席を立ってしまうインド人観客も多く、なんか非常に中途半端に思えた。監督はもっとインド映画のあのド派手なストーリーの起伏とミュージカル・シーンを勉強すべきだ。
途中でアクシャイ・カンナーが突然登場するが、彼の登場にしてもストーリー上何の脈絡もない。確かに主演のラーフル・カンナーとアクシャイ・カンナーは兄弟だが、だからと言って何の前振りもなしに登場されたのでは頭が混乱する。普通特別出演する俳優というのは、ある程度名声が確立した人であることが普通だ。しかしアクシャイ・カンナーはそんな特別出演できるまで人気のある俳優ではないと思う。ただ弟が出演しているからというだけで特別出演できたのだろう。だが、そんなしょうもない理由でやすやすと特別出演してしまったのでは、逆に格が下がってしまう。さらに不幸なことに、この映画でアクシャイは気味の悪い踊りを踊っており、この映画で彼の格は2ランクぐらい下がったと思う。おいおい・・・。
「Bolliwood Holliwood」という題名なので、もっとハリウッド的要素もあるのかと思ったが、はっきり言ってボリウッドがハリウッドに出会うようなシーンは全くなかった。ただ冒頭のシーンで主人公のラーフルが白人の人気アイドルと恋仲なだけである。かと言ってボリウッド的要素がふんだんに盛り込まれているわけでもない。やっぱり中途半端な映画である。
アクシャイ・カンナーの弟、ラーフル・カンナーは、はっきり言って兄よりもハンサムだと思う。アクシャイはかなり前髪の生え際が際どくなっていた。ラーフルは前髪もまだ大丈夫そうである。ただ顔がなんかお面みたいで気持ち悪い。この兄弟の顔は極端過ぎてあまりファンがつかないと思うのだが・・・。一方、主演女優リサ・レイはカナダ生まれのインド人で、ムンバイーでスーパー・モデルとして活躍しているらしい。しかしモデルにしてはあまり突出した美人というわけでもなかった。演技ももっと磨きが必要。
ヒングリッシュ映画というのは外れがないと思っていたのだが、その神話もこの映画のせいで崩れ去ってしまった。英語で映画を作っても、作り方が悪ければ映画は面白くなるはずもない。その現実を見せ付けられてしまった。
寒い、寒すぎる・・・!最近のデリーは本当に寒い。何もしないと全く熱が身体に蓄積されない。ずっと手足の指先が凍りついたままだ。このままでは凍傷になってしまう。こうも寒くては何もする気にならない。手がかじかんでキーボードをタイプすることもままならない。ヒーターを買うか・・・。しかしあと1、2週間我慢すれば、すぐに暖かくなるだろう。どうするか・・・。
1月大寒波により凍りついた頭を何とか回転させながらずっと考えたが、とうとう耐え切れなくなってヒーター購入を決意した。デリーの冬は基本的に我慢さえすればやり過ごすことができるので、暖房、つまり部屋を温めるという考え方がそもそもあまりない。焚き火に当たって暖をとる、というのは一般的だが、暖房付きのエアコンはほとんどないし、ストーブの普及率も低い。そんな中、庶民の暖房器具はヒーターと呼ばれる器具である。
ヒーターには2種類ある。いわゆる電気ストーブと、部屋を温める用のファン付きヒーターである。どちらにしろものすごい電気を消耗するという話だ。要するにドライヤーをずっと付けっぱなしにしておくようなものだから。しかし幸い、僕の部屋の家賃は電気代込みだから電気代を気にする必要はないし、僕の部屋は小さいので、温めようと思ったらすぐに温まると思われる。ヒーターを買って損はない。
インドで何かを買おうと思ったら、いろいろ情報収集が必要である。今回のヒーターの場合、どこのメーカーの、どういうタイプのものがよくて、どこのマーケットで買うのが一番安いか、という情報を集めなくてはならない。しかしそれはもう予め調査済みだった。先日Yamato−yaへ行ったとき、そこで使われていたヒーターがけっこう調子良さそうだったので、そのヒーターの情報をそれとなく聞き出しておいたのだ。Orpatというメーカーのヒーターで、サダル・バーザールで買ったらしい。全く同じのを買うのは何だか猿真似っぽいが、失敗はしたくないので、同じのを買うことに決める。
サダル・バーザールで買ったということなので、サダル・バーザールへ行くことにする。オート・ワーラーへ「サダル・バーザールへ行きたいんだ」と言うと、「どこのマーケットだ?」と聞き返された。サダル・バーザールはあらゆるものが安価で手に入るデリー最大の庶民マーケットだ。どうもサダル・バーザールの何々マーケットと言わないといけないらしい。ここはストレートに言うべきだ。「ヒーター買えるマーケットへ行きたい」と言うと、「サダル・バーザールじゃあヒーターは買えない。ラージパト・ナガルかカロール・バーグへ行くべきだ。オレはサダル・バーザールに住んでるんだ。オレの言うことは絶対に正しい。」と大口を叩き出した。それでは、ということでカロール・バーグへ向かうことにした。
カロール・バーグのグッファー・マーケットを久しぶりに訪れる。ここは携帯電話を買おうと決意したときに何度も足を運んだ場所だ。ついでに携帯電話の視察をしてみる。僕が携帯を買った去年の10月頃に比べて、心なしか品揃えが減っているような気がする。デザインもあまりいいのがない。僕の買ったパナソニックの携帯は人気があるみたいで、値段が値上がりしていた。あのとき買っておいてよかった。
さて、ヒーターを探し始めるが、グッファー・マーケットで売られているのは、なぜかNovaというメーカーのものだけだった。パッケージを見てみると、Novaというメーカーは日本の会社で、本社は大阪にあるそうだ。こんな会社聞いたことない。英会話の学校じゃああるまいし。店員に問いただしてみると、実際は台湾かどこかの会社らしい。嘘を書くなって・・・。一気にNovaという会社の信用度が落ちた。
カロール・バーグの他の市場も探してみたが、Orpet社の製品は見つからなかった。どうもヒーターを初めとする電気製品には、カンパニーとローカルの2種類があり、カンパニーはインドの会社にしろ中国の会社にしろ日本の会社にしろ、一応どこかの会社で生産されているもの。ローカルは近所の誰かが組み立てたような簡単な構造のもの。ヒーターならカンパニーは1000ルピー以上するのに対し、ローカルは500ルピー前後である。
Orpet社のヒーターはカロール・バーグでは見つからなかった。そこでやはりサダル・バーザールへ行ってみた。カロール・バーグも混雑していたが、サダル・バーザールはもう混雑というより混沌としていた。自動車、オート・リクシャー、サイクル・リクシャー、人間、牛、そして荷物を運ぶ人々の群れが、ごちゃごちゃになって好き勝手な方向に進んでおり、排気ガスと砂埃で悪臭がたちこめていた。サダル・バーザールで情報収集してみた結果、サダル・バーザール内のナーラーヤン・マーケットというところに、ヒーター専門街があるらしい。早速そこへ向かう。
ナーラーヤン・マーケットは、サダル・バーザールの横丁のような細い路地にあった。確かにヒーターを売る店が固まっている。その中でOrpet社のヒーターを訪ね歩いてみたが、どうもOrpet社の評判はよくない。「あんな会社の製品、うちにはおいてない」という感じなのだ。また、Orpet社はどうも中国の会社らしい。数軒の店を見て廻った後、やっとOrpet社のヒーターが置いてある店を発見。置いてあるというよりも、残っていた、と書いた方が正しいだろう。そこの店員もやはり「このヒーターは品質がよくない」とあまりオススメしなかった。じゃあ何がいいのか、と聞いてみると、「Maharaja Whiteline」という。どこの会社か聞いてみると、インド製。しかし見た目はあまりよさそうじゃない。Orpet社のヒーターを試しに動かしてみたが、問題なさそうだ。「Made in China」か、「Made in India」か、究極の選択を迫られることになった。中国かインドかと言われれば僕はインドの方が好きだが、中国製品とインド製品だったら、まだ中国の方が上だろうか・・・。しかし店員が自らオススメしていない製品を買うリスクはかなり大きいだろう・・・。いろいろ考えた挙句、やはりYamato−yaで活躍していた姿が印象深かったので、Orpet社のヒーターを買うことにした。1100ルピー。
帰って早速使ってみた。このヒーターは1000ワットと2000ワット、出力を2段階に調節できる。まずは1000ワットのパワーで動かしてみる。・・・あまり暖かくならない。こうなったらフルパワー2000ワットだ!・・・なかなか暖かくなってきた。数時間動かしっぱなしにしておいたら、室温が30度近くまで上がった。これは優れ物だ。これでなんとか冬を越せそうである。中国製を信じてよかった。
| ◆ |
1月12日(日) 松岡環さん講演会パート2 |
◆ |
インド映画研究家として有名な松岡環さんの、インド映画に関する講演会が、デリー日本人会婦人部主催でジャパン・ファウンデーションにて行われた。松岡さんは2年前にも同様の講演会をデリーで行っており、その影響からか駐在員のマダムたちの間でも密かにインド映画ブームが起きたらしく(本当かどうか知らないが)、第2回が催されたといういきさつである。ちなみに僕は第1回の講演会にも出席した。
前回と同じく、インド映画の歴史を簡単に説明してくれた。前回よりグレード・アップしていたのは、インド映画年表と同時にインド映画と日本映画の交流の歴史も盛り込まれていたことだ。以下ざっと講演の要約。
初めて作られたインド映画は1913年の「Raja Harishchandra」。「マハーバーラタ」の神話を題材に撮られた映画である。その後1931年に初のトーキー映画「Alam Ara」が作られ、以後インド映画の2大特徴である「ミュージカル映画」と「言語別製作」が開始された。映画がトーキー化され、歌と踊りが挿入されるようになり、俳優が自分で歌を歌う時代が続いたのだが、1947年のインド・パーキスターン分離独立を機にプレイバック・シンガーが定着した。以後、俳優は演技に専念、歌は吹き替え歌手が歌う現在のインド映画の様式が確立する。1952年には初のカラー映画「Aan」が作られる。また同年にムンバイーで第1回インド国際映画祭が開催され、日本映画「雪割草」が上映される。この映画がインドで初めて上映された日本映画ということになるらしい。一方、1954年には日本で先程の「Aan」と、タミル語映画「Chandralekha」が日本で上映された。これらが日本で初めて公開されたインド映画ということになる。1966年にはサタジット・レイ監督の「大地のうた」(1955年作品)が日本で公開され、その後も彼の作品のみが続々と公開されることになる。これが以後「インド映画=サタジット・レイ」という偏見が日本に根付く原因となる。1960年代にインドでは映画製作に関する機関が整備され、1970年代にインド映画は黄金期を迎える。1975年に公開された伝説的大ヒット映画「Sholay」がその象徴である。1980年代のインド映画界はテレビ・ビデオの普及により苦戦する。しかし80年代後半には「Tezaab」(1988年)、「Maine
Pyar Kiya」(1989年)などのヒットにより持ち直す。90年代に入ると俳優の世代交代が進み、現在日本でも名の知れ渡っているシャールク・カーン、サルマーン・カーン、アーミル・カーン、カリシュマー・カプール、ジューヒー・チャーウラーなどが活躍した。一方、日本では1998年にタミル語映画「ムトゥ 踊るマハラジャ」が大ヒットし、一時的なインド映画ブームとなるが、業界裏でいろいろ不幸な事件が起こった結果、加熱のスピードと同じくらいのスピードでブームは一気に鎮火され、現在にいたる。21世紀に入り、2002年の「Lagaan」アカデミー賞ノミネートがインド映画のさらなる躍進のきっかけとなると思われたが、残念ながら去年のインド映画界はあまり芳しくなかった。日本では「Monsoon Wedding」が公開され、まあまあの健闘をしたようだ。
また最新情報として、3月に「Lagaan」と「Mission Kashmir」がソニー・ピクチャー・エンターテイメントからDVDとビデオで発売されるらしい。本当は「Lagaan」はDVD発売よりも前に映画館で公開してもらいたかったのだが、まあ仕方ない。「Mission Kashmir」は昨今のカシュミール情勢に便乗する形で発売が決定されたような気がしてならない。また、1月には「Monsoon
Wedding」のDVDも発売予定のようで、にわかにインド映画がDVDで発売され始めている。これは個人的に嬉しい。正直言って日本でも映画館でもっとインド映画を上映してもらいたいのだが、結局日本人の趣向とインド映画はあまり相容れないみたいなので、採算を取るのは難しいのだろう。だからせめて細々とDVDでコンスタントにいいインド映画を発売してもらいたい。確かに1500円や1800円も出して見に行くほど価値のあるインド映画は少ない。年に1本か2本くらいだろう。しかしそれはハリウッド映画でも同じことだ。不公平なのはハリウッド映画の駄作が平気で日本で大々的に一般公開されるのに、「Lagaan」のようなインド映画の最高傑作に入る作品が上映までなかなか漕ぎ付けないことだ。
僕が夢見ているのは、インド映画専門の映画館が東京にできること。大体インドの近代的街造りを見ていると、新しい街を郊外に造営する場合、まずその敷地の中心に巨大な映画館がドンと建つことが多い。その後次第に映画館を取り巻く形で商店、寺院、住宅地などが立ち並び始め、街としての体裁が整ってくる。インド人にとって映画館は街の中心にあるべきものなのだ。だからもし東京にもインド映画専門の映画館が完成したら、必ずその周辺はインド人街になると思う。インド料理レストランが立ち並び、輸入雑貨屋が軒を連ね、インド人の溜まり場のチャーイ屋ができ、牛が闊歩し始め、乞食が路上で生活し始め・・・と書くと何だか悪夢みたいだが、現代社会において外国にインド人街ができるということは、要するにシリコン・バレーができるとほぼ等しいと思う。そうなるとそのインド人街は日本におけるインド文化の中心地となるだけでなく、ソフトウェア産業の中心地になる可能性もある。考えるだけなら楽しそうだなぁ・・・。
| ◆ |
1月15日(水) Kaleidoscope 2003 第1夜 |
◆ |
ICCR主催の文化交流イヴェント「Kaleidoscope 2003」が今日から1週間に渡ってカマニ・オーディトリアムで行われる。第1夜の今日は、スリナムの「チャトニー」というグループが演奏をするとのことだった。スリナムと言えば南米にある小国で、インド系移民が多くすんでいるところだ。招待券をもらったので行ってみた。
カマニ・オーディトリアムで行われるイヴェントは、大方の場合満員御礼の場合が多い。しかし今回のこのイヴェントは満席にはなっていなかった。
「チャトニー」はスリナムから来た4人組みの楽団で、リーダー格の人物とその父がハルモニウムを演奏、同時にヴォーカルもこなし、1人は両面太鼓ダウラク、もう1人はギターを演奏していた。どちらかというと結婚式などで演奏をする楽団っぽい雰囲気で、カッワーリーをベースにした演奏をしていた。
面白かったのは、アフリカ音楽との融合。スリナムにはインド系移民と同じくらいアフリカ系移民も多い。よって音楽も自然と融合し、インド音楽の中にアフリカ音楽のリズムやラップ調のメロディーが入ったような演奏もしていた。
イギリス植民地時代、多くのインド人が契約労働者として世界各国のイギリス植民地へ連れて行かれた。契約労働者はサトウキビ・プランテーションで過酷な労働を強いられた。しかし元々低カーストで貧しい人々が契約労働者になったケースが多かったことから、契約労働が終わった後もインドに帰らず、その地で暮らすことを決意した人が多かった。やがてイギリスから独立し、インド系移民が人口の多くを占める国が世界の各地に誕生した。スリナムもそんな国のひとつである。
彼らインド系移民たちは、母国インドを離れてもインドの文化を忘れないよう、特に音楽を積極的に継承して行った。「ラーマーヤナ」などを題材とした宗教歌が好んで歌われ、また本国から離れて暮らす悲しみを歌う歌や、労働歌などがたくさん作られた。今回スリナムの音楽グループが演奏したのも、その種のものだった。
言語はブラジュ・バーシャーと呼ばれるヒンディー語の方言系である。しかも100年以上前のヒンディー語だ。インド本国では失われてしまったような言語の特徴が、今でもそれら海外のインド系移民国家で残っていることがある。今回、楽団たちは歌を歌うだけでなく、途中で落語のような笑い話を話し出したりして、それらの歌や話がもろに訛ったヒンディー語だったのだが、半分は理解できて半分は理解できないくらいだった。会場に来ていたインド人がどういうバック・グラウンドを持った人なのかは知る由もないが、彼らは歌や話をちゃんと理解できたみたいだ。やたらと盛り上がっていた。ちょうど客席の真ん中に座っていたので、周りが大爆笑したり大感動したりしているとき、僕は理解できなくてポツンと取り残されるようなことがしばしばあった。なんか悲しかった・・・。
| ◆ |
1月16日(木) Kaleidoscope 2003 第2夜 |
◆ |
今日もカマニ・オーディトリアムで行われた文化交流イヴェント「Kaleidoscope 2003」を見に行った。今日はフィジーとインドのパンジャーブ州のグループが公演を行う。フィジーは個人的に思い入れのある国だし、パンジャーブ州のバングラ・グループは是非見てみたかった。
フィジーから来たグループは女の子ばかりのダンス・グループで、全員インド系移民だった。服装はフィジーの伝統的なデザインをあしらっており、インド舞踊とハワイアン・ダンスをミックスしたような踊りを、ポリネシアンな音楽に合わせて踊っていた。しかし、本場インドでインド舞踊をいくつか見て来た僕の目には、彼女らのダンスはどうも素人っぽく映ってしまった。というか、誰が見ても明らかに素人っぽかった。リゾート・ホテルのレストランで踊っていそうな感じのダンサーたち、と描写すれば当たらずとも遠からずだろう。モーニング娘。の方がもっとましなダンスをするのではなかろうか・・・。
フィジーのグループが期待外れだったのに対し、パンジャーブ州から来たバングラ・グループは期待に違わぬハチャメチャぶりだった。バングラとはパンジャーブ州の伝統音楽で、一昔前には、バングラ音楽にテクノ音楽をミックスしたバングラ・ビートが日本でも一部で流行したことがあった。インド人はバングラ音楽が大好きであるように思える。デリーにはパンジャーブ人が多いため、そう思えるのかもしれない。しかし結婚式のダンス・ステージや、ディスコ、テレビなどで、一番インド人が盛り上がるのは、バングラ音楽が流れたときである。あの独特のノリの音楽がかかっただけで、インド人は大喜びだ。両手の人差し指を上に向けて、腰を少し低く構えて肩と腰と足を動かすだけで、一応形になる手軽さがいい。そして満面の笑みは必須である。このときばかりは髭の濃いインド人がうらやましくなる。なぜなら髭はバングラ・ダンサーの重要なファクターだからだ。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
バングラ・ダンス |
● |
今回公演したバングラ・グループは、テレビでよく出てくるようなカラフルなターバンと衣装、それに特徴的なヒゲと満面の笑みを浮かべた男たちが構成員で、まるでチンドン屋のようなおかしな楽器を各自駆使しつつ、独特の音楽空間を作り上げていた。そしてただ演奏するだけでなく、踊りも披露してくれた。あの独特のステップは、もしかしたら日本の阿波踊りに通じるものがあるかもしれない。そして徹底的なエンターテイメント精神。肩車、といか肩の上に人間が立って、まるでサーカスのようなダンスをしたり、変な雄叫びをあげて観客を沸かせたりと、全く退屈しない。もしかしてバングラ・ダンスは、男が踊るダンスの中で、純粋に楽しめる数少ない踊りのひとつかもしれない。
バングラ・グループの公演が終わった後、フィジーのグループも出てきてグランド・フィナーレとなった。ところがそこで突然バングラ・グループが再び勝手に演奏を開始して、舞台はバングラ・ダンスのディスコと化した。バングラ・ダンサーたちはフィジーの女の子たちにもバングラ・ダンスを強制し、カオス的な状態のまま踊り狂っていた。スケベな奴らだ・・・。でも十分楽しませてもらった。おかげで次回インドの結婚式に出席したときに踊るバングラ・ダンスのレパートリーが増えた。
2002年はボリウッド興行収入最悪の年として歴史に名を刻むだろうが、去年の年末から急にインド映画界が再び急上昇を始めたような気がする。昨年の12月20日に同時公開された「Saathiya」と「Kaante」はヒットを続けており、特に「Saathiya」はロング・ランしそうな雰囲気。そして今日、再びロング・ラン濃厚な2作品が公開され始めた。アイシュワリヤー・ラーイ&アルジュン・ラームパール主演の「Dil Ka Rishta」と、ビパーシャー・バス主演の「Jism」である。今日は「Jism」を見にラージパト・ナガルの3C’Sへ行った。
主演女優のビパーシャー・バスといえば現在のインド映画界のセックス・シンボル的存在である。「Jism」とは「体」という意味。映画のポスターも、ビパーシャー・バスの艶かしい容姿を前面に押し出しており、期待を煽る。彼女の他に、ジョン・アブラハムとグルシャン・グローヴァーが出演していた。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
Jism |
● |
| Jism |
舞台はタミル・ナードゥ州ポンディチェリー。女好きで飲んだ暮れの不良弁護士カビール(ジョン・アブラハム)は、ある日美しい人妻ソニヤー(ビパーシャー・バス)と出会う。ソニヤーは敏腕実業家ローヒト・カンナー(グルシャン・グローヴァー)の妻だったが、夫は週末に時々やって来るだけで、残りの日は1人で寂しく暮らしていた。カビールはソニヤーを口説き、二人は肉体関係を持つようになる。
愛に狂ったカビールとソニヤーは、その内ローヒトを殺害する計画を立て始める。カビールはローヒトを殺し、死体を爆弾で爆破、事故にみせかける。カビールはちゃんとアリバイも作っておき、計画は完璧のはずだった。ところがローヒトの家に弁護士から電話がかかってくるのだった。なんとローヒトが書いた遺産分配の遺書に、カビールの名前が記載されていたのだ。ソニヤーが勝手に書き換えたものだった。カビールは事件の渦中に巻き込まれ、やがてローヒトは事故で死んだのではなく、殺されたのだということが警察にも分かってくる。
アリバイも手抜きがあったため通用せず、次第に追い詰められてきたカビールは、ソニヤーと共にどこかへ逃げ出すことを考える。しかし待ち合わせ場所に現れたのはソニヤーが放った刺客だった。カビールは間一髪で刺客の攻撃をかわし、ソニヤーの家へ殴りこむ。全てはローヒトの遺産欲しさに巧妙に計画された、ソニヤーの罠だったのだ。
しかしカビールはソニヤーを心底愛していた。憎悪と共にソニヤーの家に乗り込んだカビールだったが、ソニヤーの姿を見るとその憎悪は消え、ただ愛情だけが心を支配した。カビールは警察に自首することを決め、その場を立ち去ろうとする。すると突然、振り向いたカビールをソニヤーは銃で撃った。カビールは重傷を負いながらもソニヤーの銃を奪って彼女を殺し、そのまま海岸に出て倒れ込む。そして親友に看取られながら、最後の日の出を見ながら静かに息を引き取った。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
元フランスの植民地である、タミル・ナードゥ州のポンディチェリーが舞台になっており、全体としてフランス映画に似た洒落た雰囲気の漂う映画だった。ポンディチェリーでは今でもフランス語が話されており、映画中でも「ヴォンジュール」と挨拶しているシーンを見ることができた。しかしヒンディー語映画であるため、言語はヒンディー語。
ストーリーはどこかで見たことあるようなものだった。僕にはカビールとソニヤーがローヒト殺害計画を立てている時点から、ソニヤーがカビールを罠にはめようとしていることが予想できた。しかし物語を深くしているのは、ソニヤーが本当にカビールを愛していたのかどうかを曖昧のままにして終わったことである。カビールを銃で撃つ前、彼女はカビールへの愛を、愛ではなく「体の欲求」と言い切っていたが、カビールを撃った後、「あなたを本当に愛していたの」と涙目で語った。多分普通のインド人からしたら「いったいどっちなんだ、白黒はっきりさせろ」というところだろうが、こういう曖昧な終わり方は僕は個人的に好きである。
セクシー女優ビパーシャー・バスは今回もセックス・シンボルとして存分に魅せつけてくれた。セリフのしゃべり方がなんとなく舞台演劇っぽいのだが、知的でセクシーな女性を演じればそれも不自然ではない。聞くところによると彼女はベンガル人なので、ヒンディー語があまり得意ではないようだ。彼女の演技力云々を問うよりも、むしろ彼女は演技をしない演技をした方がいい。あまりアクションを大袈裟にせず、セリフもあまりしゃべらず、目だけでグッと語りかけるような佇まいをさせたときに、彼女の魅力がもっとも発揮される。クライマックスで、怒り狂って家に乗り込んでくるカビールを待つときの彼女の表情は美しい。
主演男優のジョン・アブラハムは今回がデビュー作。アルジュン・ラームパールやビパーシャー・バスと同じくモデル出身の俳優である。だんだんモデル出身俳優の派閥がボリウッドでできつつあるような気がする。モデル出身だけあってジョン・アブラヒムはワイルドかつ洗練されたかっこよさがあり、新時代のボリウッド俳優という感じがした。演技もなかなかだった。ちなみに彼の名前はインド人っぽくないが、それは彼がパールスィー(ゾロアスター教徒のペルシア系インド人)の家に生まれたかららしい。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
ジョン・アブラハム |
● |
| ◆ |
1月21日(火) Dil Ka Rishta |
◆ |
現在のボリウッドはまだアイシュワリヤー・ラーイの天下であるように見える。カリーナー・カプール、ビパーシャー・バス、ディーヤー・ミルザーなど、魅力的な新人女優が次々に登場したものの、アイシュワリヤーの絶対的な美しさと人気に適う力量を持った女優はまだ今のところいないように思える。もっとも、アイシュワリヤーの2002年は、「Devdas」で存在感を示すことができたものの、それ以外目立った活躍をすることができなかった。2003年の彼女は「Dil
Ka Rishta」でスタートを切った。先週から封切られ、評判はまあまあ。今日チャーナキャー・シネマに見に行った。
「Dil Ka Rishta(心の絆)」のキャストは、ラーキー、アイシュワリヤー・ラーイ、アルジュン・ラームパール、プリヤーンシュ、イーシャー・コーッピカル、パレーシュ・ラーワル。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
アイシュワリヤー・ラーイ(左)と
アルジュン・ラームパール(右) |
● |
| Dil Ka Rishta |
ジャイ(アルジュン・ラームパール)は大富豪の御曹司。南アフリカのケープ・タウンに住んでいたが、亡き母親の誕生日にムンバイーへ駆けつけた。そこで父親(パレーシュ・ラーワル)、親友のアニーター(イーシャー・コーッピカル)と再会した。ジャイはたまたま立ち寄った聾学校で美しい女性ティアー(アイシュワリヤー・ラーイ)と出会い、恋に落ちる。ジャイはティアーに愛の告白をするが、彼女には既にラージ(プリヤーンシュ)というボーイフレンドがいた。
それでも諦めの付かないジャイはティアーにアプローチを続ける。だが、ティアーはしつこいジャイを嫌う。ジャイの思いは適わず、ラージとティアーは遂に結婚式を挙げる。やがて二人の間には息子が生まれる。
一方、ティアーを忘れられないジャイはアルコールで気を紛らわすようになっていた。酔っ払いながらアニーターを乗せて車を運転していたとき、ジャイは交通事故を起こしてしまう。偶然にも事故の相手はラージとティアーの乗った車だった。この事故によりラージとアニーターは死に、ティアーは記憶喪失になってしまう。しかもティアーの脳の損傷は深刻で、過去の出来事を思い出すと、ショックで気が狂うか死んでしまう可能性もあった。何とかティアーに過去の思い出を思い出させないようにするしかなかった。
ティアーの肉親は母親(ラーキー)と息子だけだった。母親は事故を起こしたジャイを憎むが、ジャイは何とか償いをしたいと申し出る。ジャイはティアーの精神状態を安静に保つために彼女と母親をケープ・タウンへ連れて行く。ティアーには本当のことを隠し、ジャイが交通事故で妻のアニーターを失ったことにする。そしてティアーとラージの息子は、ジャイとアニーターの息子ということにする。そしてティアーと母親はジャイの家に住むことになった。こうしてジャイとティアーは新たな関係を築き始めることになった。
ティアーは記憶を失ってしまったことを悔しがるが、新しい人生を歩み始める決心をしていた。そしてジャイと過ごす内に彼を好きになる。しかしティアーの母親はジャイを憎んでおり、ティアーとジャイが接近することを禁じていた。またジャイはティアーのことを愛していたが、ティアーの記憶がもし戻ったら彼女は自分を憎むことが分かっていたので、彼女に心を開くことができなかった。唯一ジャイの父親だけが、ジャイとティアーの仲を結びつける努力を続けた。父親の説得により、ティアーの母親もティアーがジャイと再婚することに同意する。
しかしジャイ自身がティアーとの結婚を拒否した。絶望したティアーは何もかも信じられなくなり、家を飛び出して自殺を計る。それを止めたジャイは、ティアーに本当のことを全て打ち明ける。ティアーは事実を知って驚くが、それでも記憶は戻らなかった。ジャイは改めてティアーに愛を打ち明ける。こうしてジャイとティアーは結ばれたのだった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
記憶喪失というありふれたテーマの映画ではあるが、3時間飽きずに見通すことができた。それはおそらくアイシュワリヤー・ラーイの魅力に依るところが大きいだろう。この映画はアイシュワリヤーのためにあるようなものである。彼女の美しさは今更言うまでもないが、演技にダンスに大活躍していた。
一方、依然としてあまりパッとしないのがアルジュン・ラームパールである。顔は日本人受けしそうな、細身でスッキリとした二枚目顔なのだが、声が低すぎる上にセリフ棒読みの癖が抜けていない。それに彼のダンス・シーンはほとんど登場しない。多分アルジュン・ラームパールはあまり踊りが得意ではないのだろう。彼は精力的に踊るアイシュワリヤーの横でただ突っ立ってるだけだった。アルジュン・ラームパールのファンになって1年以上経つが、さすがに彼の大根役者ぶりをこれだけ見せ付けられると、かなり不安になってしまう。早くヒット作を出さないと、彼の役者生命もそう長くは続かないだろう。
普通、映画中で記憶喪失になった人は、最後には記憶が戻るのが常だと思うのだが、この映画では最後まで記憶が戻らなかった。そしてそのおかげでティアーとジャイは結ばれることになった。だが、結婚後にもし記憶が戻ったらどうなるのだろうか?また、交通事故で記憶喪失になるという筋書はまだ許せるのだが、記憶が戻ることによってティアーの脳が損なわれる、だからティアーに過去を思い出させてはならない、という設定はどうも強引すぎるような気がする。全体としてはきれいなラヴ・ストーリーに収まっていたが、細かいところではやはりインド映画的強引さが見え隠れしていて興醒めだ。
音楽はナディーム・シュラヴァン。この映画のサントラはあまり魅力を感じなかった。それゆえか、ダンス・シーンからも気合を感じなかった。せっかく後半部分は南アフリカが舞台となっているので、もっとアフリカっぽい要素を盛り込んだダンス・シーンがあってもよかったのではないだろうか。
そういえばアイシュワリヤーって、左の二の腕に大きなホクロがある。今日初めて気が付いた。
今日はリパブリック・デイ(共和国記念日)。1950年1月26日にインド憲法が施行されたことを祝う日であり、国民の祝日となっている。デリーのインド門でパレードが行われるので、デリー市民にとっては特に特別な日である。
インド人のリパブリック・デイに対する思い入れは特別なものがある。もちろん愛国心から来るものが多いが、もうひとつは最近のテロリズムに対する異常なまでの警戒心である。1ヶ月以上前からインド門の大通り両脇に、パレード見物用のベンチが作られ、またインド門周辺は厳重に警備され、一般人は近付くことができなくなっていた。そんな早くから準備する必要があるのかと思ったが、これもテロを警戒してのことであろう。また、1週間前から毎日パレードの予行練習が昼頃行われ、インド門周辺部は交通麻痺状態になっていた。木曜日には総リハーサルが行われていた。そういえば小学生の頃、運動会のリハーサルは必ず木曜日にしていたような気がする。木曜日にリハーサルして、金・土で修正して、日曜日に本番、という感じだったような・・・。3日前にリハーサルというのは万国共通の観念なのだろうか?
これは関係あるか知らないが、前々日からネットがつながりにくくなっていた。ネットはつながるのだが、スピードがやたらと遅く、しかもホットメールにアクセスできない状態になっていた。僕は勝手に「リパブリック・デイに伴う通信規制だろう」と結論付けていたが、友達の家に行ったら余裕でネットができたので、もしかしたらネット会社の怠慢だったかもしれない。(■後から知ったのだが、このとき世界的なネット障害が起こっていたらしい)
というわけで、今日はインド門でパレードが行われた。一般人がパレードを生で見るのは難しい。まずパスがないと現場に近づけない。パスをどうやって手に入れるのか、僕は興味がなかったので分からない。しかし近所の親父が持っていたりするので、コネがあれば簡単に手に入るのかもしれない。パスがあったとしても、現場へ行くときに厳重な身体検査が行われる。カメラや携帯電話などの電子機器はもちろん持ち込み禁止で、それ以外にボールペンや新聞紙なども持ち込むことができないらしい。また、必ず身分証明書を持って行かなくてはならない。これだけ面倒な手続きを踏まなければ見ることは適わないため、僕は去年と同じくテレビ中継でパレードを見た。
去年はちょうど印パが緊張状態にあったときにリパブリック・デイ・パレードが行われた。よって全ての軍隊はパーキスターン国境に配備されており、パレードに軍隊は参加しなかった。よって非常に質素なパレードになってしまっていた。しかし今年は去年よりも平和な状態にあるため、軍隊のパレード出動も可能だったみたいだ。インド自慢の兵器が公開された。あまり兵器には詳しくないが、調べたところ今回公開された兵器は、ロシア製戦車T−90とT−72、インド国産戦車Arjun、これまたロシア製ヘリコプターMI−17IV、レーダー車インドラ−II、超音速ミサイルのブラフモース、核搭載可能ミサイルのアグニ−I、プリトヴィーなどなどだった。インドの兵器は神様や神話から名前が取られていて、密かに楽しい。
毎年外国から賓客が呼ばれるが、今年はイランの大統領ムハンマド・カータミーが来ていた。米国のイラク攻撃が秒読み段階に入った今、イランの大統領がインドを訪れたというのは深い意味があるような気がする。もちろんアタル・ビハーリー・ヴァージペーイー首相とアブドゥル・カラーム大統領も出席。その他、副大統領バイローン・スィン・シェーカーワト、副首相ラール・クリシュン・アードヴァーニー、防衛大臣ジョージ・フェルナンデスや、コングレス総裁ソニアー・ガーンディーなどなどが出席していた。
パレードのアナウンスを聞いていて思ったのは、鮮明なるテロリズムに対する対抗意識である。兵器の紹介には必ず「この兵器は隠れているテロリストを探すのに役立つ」とか「これでテロリストを一網打尽にする」などの説明が付け加えられていた。国民の感情を愛国心に向けるには、共通の敵を設定するのが一番手っ取り早い。しかしその敵をパーキスターンなどの外国に直接向けてしまうと、外交上何かとトラブルが多い。だから国内の病巣であるテロリストを敵に設定するというのは、最も簡単で安全な解決策である。インドはテロをうまく国民感情の統一に使おうとしていると感じた。
軍隊や警察のパレードの後は、インド各州がそれぞれ個性を活かして作ったパレード・カーが登場。これがなかなかよく出来ていて、インド人でもこんなの作れるのか、と妙な感心をしてしまった。特にデリーのパレード・カーは昨年の暮れに運行開始したばかりのデリー・メトロを題材にしていて印象に残った。
JNUで毎年恒例のフード・フェスティバル。JNUの外国人留学生が自国の自慢料理を披露するイベントである。去年も行ったのだが、何かを食べた途端に下痢になったという忌まわしき思い出が脳裏に残存していた。しかしいろんな人が来て楽しそうなので行ってみた。
僕は午後7時頃にJNUに到着した。特にこれといった開始時刻はあまり設定されていないようで、開いているブースもあれば、まだ準備中のブースもあった。参加国は韓国、チベット、ヴェトナム、バングラデシュ、中央アジア各国、中国、タイ、シリア、ネパール、アフガニスタンなどなどである。我が日本もブースを出していたが、なぜかもぬけの殻・・・。JNUの日本人学生がどこかで準備しているらしいが、いつまで経っても始まらなかった。おかげで日本ブースは食事スペースになってしまい、多くの人がそこで食事を食べ、ゴミを捨てて行った。という訳で、ゴミ大国日本となってしまっていた。
僕が食べたのはチベットのモモとチャン、中国の餃子、韓国料理各種、アフガニスタンのビリヤーニなどなどであった。レストランが後援しているようなところはなかなかいける料理を出していたが、素人の学生が作っているところはあまりおいしくなかった。冷めてしまっている料理も多かった。まあこんなもんだろう。今年は急性の下痢にならなかっただけマシである。
さて、そろそろ宴もたけなわかな、というときになって、やっと日本勢が会場に到着。大急ぎで準備に取り掛かっていた。日本ブースが今回用意したのは抹茶ケーキ、焼き鳥、散らし寿司である。待望の日本ブース開店ということで、一気に人が集まってきた。2、3人で切り盛りしていたので、僕も手伝うことにした。
さて、抹茶ケーキ、焼き鳥、そして散らし寿司という品目。値段はそれぞれ10ルピー、20ルピー、30ルピーである。この中で何が一番売れたか。経過を見守っていたところ、飛ぶように売れたのは意外や意外、抹茶ケーキであった。フード・フェスティバル終盤になっていたため、みんなお腹いっぱいになっており、デザートの需要が多かったと考えることもできるが、ただ単純に抹茶ケーキがおいしかったということもあるだろう。結局抹茶ケーキは完売してしまった。焼き鳥はコンスタントに売れたが、大量に売れ残ってしまったのは散らし寿司。まずインド人や他国の人にとって、米と酢の組み合わせがあまり好まれなかったようだ。また、味付けが塩辛くなってしまっていたことも不評の原因であろう。焼き鳥と散らし寿司は大量に作り過ぎたことがたたって、かなり売れ残ってしまった・・・。
| ◆ |
1月27日(月) Kucch To Hai |
◆ |
ボリウッド最悪の年と呼ばれた2002年、最大の興行収入を得た映画が、ビパーシャー・バス主演の「Raaz」であった。「Raaz」はインド映画には珍しいホラー映画であり、二匹目のドジョウを狙っているのか、これから続けていくつかホラー・ヒンディー語映画がリリースされる予定である。その先陣を切ったのが「Kucch To Hai(何かがいる)」。先週の金曜日から封切られており、今日PVRアヌパム4へ見に行った。
「Kucch To Hai」のキャストは「Jeena Sirf Merre Liye」でセリフ棒読みの演技をしたトゥシャール・カプール、ボビー&サニーのデーオール兄弟の妹にして、名優ダルメーンドラの娘イーシャー・デーオール、そして新人女優のナターシャーである。また、トゥシャール・カプールの父ジテーンドラやリシ・カプールなどのベテラン俳優や、ジョニー・リーヴァルやラザック・カーンなどのコメディアン俳優も登場。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
イーシャー・デーオール(左)
トゥシャール・カプール(中)
ナターシャー(右) |
● |
| Kucch To Hai |
シムラーに住むカラン(トゥシャール・カプール)は、どこにでもいる純粋な大学生だった。カランの幼馴染みでお隣さんのターシュー(ナターシャー)はカランに恋心を抱いていたが、カランは学校のアイドル、タニヤー(イーシャー・デーオール)に恋していた。しかしタニヤーはこれまた学校のヒーローであるヤーシュと付き合っているともっぱらの噂。ヤーシュはカランのことを面白く思っていなかった。ヤーシュは一計を案じてカランに近付く。ヤーシュはタニヤーとはただの友達であり、実はターシューに恋していることをカランに伝えた。そしてカランがターシューとヤーシュの仲を取り持つ代わりに、ヤーシュがカランとタニヤーの仲を取り持つことになった。この悪巧みはカランに恥をかかせるためのものであったが、これが裏目に出てカランとタニヤーは急接近し、ターシューは失恋する結果となってしまう。また、カランとヤーシュはいざかいの末仲直りし、親友となる。
大学にはバクシー教授という、少し頭のおかしな教授がいた。バクシー教授は平気で生徒を殴り倒すので、学校中で恐れられていた。大学の期末試験の日にカランたちの監督官となったのがこのバクシー教授だった。この試験中、カランがヤーシュに答案を見せようとしたところをバクシー教授に見つかり、カランをかばったタニヤーの答案が無効となってしまう。つまりタニヤーは留年確実となってしまう。
しかし試験は別の場所で採点がされるはずである。まだバクシー教授の家に保管されているはずだ。その答案用紙の束の中に、タニヤーの答案をこっそり入れておけば、タニヤーの留年は免れる。そう考えたカランたち7人組はバクシー教授の家に忍び込む。ところがそこで発見したのは、棚の中に置いてあった拳銃と、ミイラ化した彼の妻の死体だった。やはりバクシー教授はやばい人物だった。バクシー教授に見つかった7人は、命からがら自動車に乗って逃げる。そして逃走途中でバクシー教授を轢き殺してしまう。
7人はバクシー教授の死を隠すことに決めた。バクシー教授の遺体は崖の下に落ちて発見されず、誰にも交通事故のことはばれなかった。大学を卒業した7人は皆シムラーを離れてそれぞれの道に進んだ。
そして3年後、7人の内の2人が結婚することになった。結婚式はシムラーで行われるため、他の5人も雪深いシムラーへ戻って来た。その3年の間、カランとターシューは婚約していた。3年振りにカランと再会したタニヤーは、彼らの婚約を聞いてショックを受ける。しかしカランの心の中にはまだタニヤーへの恋心が残っていた。それがターシューを傷つける。
しかしシムラーに帰った7人は、バクシー教授の影に怯えることになる。バクシー教授はまだ生きているというのだ。何度も何度も黒いコートを羽織った男の影が7人の命を狙い始める。結婚式が終わった夜、とうとう恐怖は現実のものとなる。1人、また1人と殺されていく。いったいその殺人鬼は本当にバクシー教授なのだろうか・・・? |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
予告編を見たときから、一発で分かっていた。この映画がハリウッド映画「ラストサマー」のリメイクであることを・・・。それでもインド人が作るホラー映画というのはまだ物珍しいので、見てみた次第だが・・・残念ながら雑な作りの映画だった。
「Raaz」のときも思ったが、ホラー映画にインド映画特有のミュージカル・シーンは全く似合わない・・・!怖い気分になっているときに、どうして心地よい歌が流れ出すのだ・・・!?ホラー映画を作ろうという気概は悪くないので、あとはホラー映画はホラー映画として、インド映画の公式から離れて作るというスタンスに目覚めてもらいたい。
ストーリーもところどころでクエスチョン・マークが付く場面が多かった。特に一人目の男(パトという名前だったと思う)が殺されるシーン。なぜにちょうどパトが倒れこんだところの地面に積もった雪の中から殺人鬼が現れるのだ?あのシーンはギャグ・シーンなのか?あれは超常現象の域に達していた。ただ、ジョニー・リーヴァルとラザック・カーンは面白かった。ホラー映画にコメディーは基本的に似合わないのだが、彼らのお笑いシーンはホラー映画の中にあってホラーを超越したお笑いで楽しかった。もしこの映画で秀逸な点を探すとしたら、ホラー映画とコメディー映画を見事に融合させた彼らの見事な演技力だろう。
結局謎の殺人鬼の正体は2人おり、バクシー教授本人と、愛にとち狂ったターシューだったのだが、これもかなり強引である。バクシー教授が生きていて復讐し出すのはまだいいにしても、どうして大人しそうな女の子のターシューが急に殺人鬼に早変わりできるだろうか?しかもバクシー教授が黒いコートを着て虎視眈々とうろついている中を、ターシューも同じ格好をしてうろついていたと思うと全く馬鹿馬鹿しい限りである。
役者の演技も絶望的だった。トゥシャール・カプールは相変わらず心のこもっていないしゃべり方。顔も決してハンサムではないだろう。いったい彼はインド人的に見てどうなのか、疑問である。彼に似合うのは、あまりパッとしない平均以下な駄目男の役だ。のび太君みたいな。
イーシャー・デーオールはどうも好きになれない。額の傷痕は、肉体派の兄サニー&ボビーとの壮絶なる戦いの跡だろうか?顔はまるで売春婦のように、気品がなくてケバケバしい。バスタオル一枚を身体に巻いてサウナに入るお色気シーンがあったが、あれも彼女の品格を落としてしまっていた。早く消えてほしい女優の1人である。
音楽はアヌ・マリク。「Kuch To Hai」のCDはヒット・チャートでまずまずの健闘をしているのだが、あまり買う気が起こらない。「Ding Dong」だけはいい曲だと思ったが、それ以外は退屈な曲ばかりだった。
それにしてもなぜこの映画のプロデューサーはホラー映画を冬にリリースする気になったのだろうか?シムラーの雪景色が出てきたりして、余計寒くなってしまった。
今絶好調の新人男優、ヴィヴェーク・オーベーロイ。彼は今まで「Company」、「Road」で、不良な若者を演じて好評を博していたが、現在まだ公開中の「Saathiya」で初めてロマンチック・ヒーローを演じてこれがまた大受け。彼の潜在能力はまだ尽きていない。今日はヴィヴェークの新作映画「Dum」を見に、PVRアヌパム4へ行った。
題名「Dum」は、「気合、度胸、根性」みたいな意味合いで映画中使われていたと思う。ヴィヴェーク・オーベーロイのヒロインを務めるのは、これまた若手の中で最も勢いのある女優ディーヤー・ミルザーである。他にアトゥル・クルカルニー、スシャーント、ヤシュパール・シャルマー、ムケーシュ・リシなど。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
ディーヤー・ミルザー(左)と
ヴィヴェーク・オーベーロイ(右) |
● |
| Dum |
ウダイ(ヴィヴェーク・オーベーロイ)とモーハン(スシャーント)は警察官になるのを夢見て日々切磋琢磨し鍛錬する若者だった。彼らは警察官試験を受け、見事1次試験を突破する。そのときの試験官ラージ(ムケーシュ・リシ)は以後彼らのよき相談相手となった。
ウダイは妹の見合い相手の妹カヴェーリーと恋に落ちる。ウダイとカヴェーリーは兄弟の結婚式の準備を進めながらデートを重ねていた。そのとき、後にウダイの天敵となる悪徳警察官シャンカル(アトゥル・クルカルニー)と遭遇する。酔っ払ってカヴェーリーに嫌がらせをしたシャンカルに、ウダイは殴りかかり、シャンカルは顔に大怪我を負う。その傷痕は消え去ることなく、それによってシャンカルのウダイに対する憎悪は増幅されるのだった。
ウダイの妹の結婚式の日、シャンカルはウダイを探し出して拉致し、拷問を加える。ボロボロになったウダイは線路の上に放置されるが、間一髪で助かる。しかしシャンカルによって負わされた怪我により、ウダイは警察官試験の2次試験を受けることが難しくなる。だがウダイは気合でその怪我を克服し、警察官に内定する。ところが警察官になるのに必要な推薦状を作成する役を請け負ったのがシャンカルだった。シャンカルはウダイが生きていることを知り、再び魔の手をウダイとウダイの友人、家族に伸ばす。このときの襲撃により、ウダイの親友モーハンは命を落としてしまう。
ウダイとシャンカルの復讐合戦は繰り返されるが、最後にウダイとシャンカルは一対一、素手と素手の殴り合いを繰り広げ、ウダイはシャンカルを抹殺する。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
ほとんどヴィヴェーク・オーベーロイのワンマン・ショー的映画だった。同じく人気沸騰中の女優ディーヤー・ミルザーがせっかく共演しているのに、彼女は添え物でしかなかった。ヴィヴェーク・オーベーロイのモダンな男らしさ満載の3時間。これを見てヴィヴェークのファンにならない人はいないだろう。僕は彼に「現代のアミターブ・バッチャン」または「サニー・デーオール2世」という称号を与えたい。怒れるインドの若者の叫びを代弁する熱いヒーローの誕生だ。
ヴィヴェーク洗脳光線は、まず最初のミュージカル・シーン「Dum」から始まる。黒い革ジャンを来た男たちが炎と闇の中で繰り広げる踊りで、非常にかっこいい。ヴィヴェークが飛び蹴りを喰らわしたサンドバッグが大爆発するシーンが秀逸。ヴィヴェーク・オーベーロイはバイクとも相性が抜群で、砂漠の中を仲間たち(?)と隊列を組んで疾走するシーンは、「Kuch To Hai」でトゥシャール・カプールが踊る「Ding Dong」の同じようなシーンとどうしても見比べてしまい、改めてヴィヴェークのかっこよさが強調される(←僕の映画評もだんだんマニアックになって来たな・・・)。
冒頭のミュージカル・シーン「Dum」ですっかりヴィヴェークにしびれ切ってしまうが、決定的な洗脳シーンはすぐ後にやって来る。ヴィヴェーク演じるウダイと、ディーヤー・ミルザー演じるカヴェーリーが見つめ合うシーンがあるのだが、そのときにヴィヴェークのつぶらな瞳のアップが長時間映し出されるのだ。しかもヒロインのディーヤー・ミルザーの瞳のアップ・シーンを差し置いて・・・。
あらすじははっきり言って暴力インド映画の典型であるが、ヴィヴェークの男らしい魅力と、アトゥル・クルカルニーが憎たらしくもコミカルな悪役を演じたことから、楽しめる映画に仕上がっていた。それに音楽が非常にいい。音楽監督は現在もっとも伸び盛りの若手サンディープ・チャウター。ポスト・ラフマーンとでも呼ぶべきヨーロピアンな音楽を作る人だ。「Dum」のCDはオススメである。
「Dum」のCDの中にはいい曲がたくさんあった。その中でもっともインド人受けしそうなのが、「Babuji Zara Dheere Chalo(ちょいとゆっくり行きましょうな、あなた)」。後半のあまり関係ないシーンでいきなり挿入されたが、この映画でもっとも盛り上がる部分だろう。色っぽい女優が酔っ払いの男どもに囲まれながら踊る映画「Company」の「Khallas」タイプのシーンだった。映画が終わった後、「バ〜ブ〜ジ〜・ザラ・ディ〜レ〜・チャロ〜」と合唱する若者が続出していた。それにしても最近映画の途中であまりストーリーとは関係なくゲスト・ダンサーの色気ムンムン・ハイテンションなミュージカル・シーンが突然挿入される映画が増えてきたような・・・それとも昔からか。「Shakti」の「Ishq
Kaminaa」がいい例だ。
映画の最後でヴィヴェークは観客に問いかける。「お前の心にDUMはあるか?」と。この映画の影響をモロに受けた若者たちが、悪徳警官をぶん殴る事件とか起こりそうである。
東京都に対する神奈川県や千葉県のように、デリー周辺にも首都圏を構成する他州の都市が存在する。ハリヤーナー州のグルガーオン、ファリーダーバードや、ウッタル・プラデーシュ州のノイダ、ガージヤーバードなどである。今日はその中でもヤムナー河の東岸にある、碁盤目状の整然とした計画都市ノイダを訪ねた。もちろんデリーからは日本が造った美しいトール・ロード(有料橋)を渡ってヤムナー河を越えた。友達のバイクの裏に乗せてもらった。ちなみにトール・ロードのバイク料金は1台8ルピー。ところが告知によると2月1日からバイク料金は1人8ルピーになるそうだ。つまり2人乗りしていたら16ルピー、3人乗りしていたら24ルピー払わなくてはいけなくなる。バイクに人数分課金する国なんてインドだけでは・・・?
ノイダの住所は計画都市の宿命から、セクター何番という番号で示されている。ノイダの繁華街といえばセクター18である。セクター18にはマクドナルド、ピザ・ハット、ドミノ・ピザ、バリスタ、サブウェイ、ウィンピー、ホット・ブレッド、ナトゥ・スウィート・コーナー、カフェ・コーヒーデイ、プラネットMなど、繁華街を象徴するチェーン店が密集していた。特にサブウェイがあったのには驚いた。デリーにはまだPVRアヌパム4のマーケットにしかないと思っていたのだが、ヤムナー河を越えたこんな辺境の土地にもサブウェイが進出していたのだった。
ノイダ・セクター18には現在2つのデパートが建っている。ひとつはサブ・モール、もうひとつはエボニーである。サブ・モールはまだ半分くらいしか店舗が入っておらず、非常に閑散とした雰囲気だった。一方、エボニーはごちゃごちゃしていた。
ノイダでもっともオシャレなバーはCaisar(シーザー)というところだそうだ。エジプトをテーマにしたバーで、大音量の音楽がガンガン垂れ流される系のバーではなかったが、料理が貧弱だった。
ノイダのどこかに近代的な映画館があるという情報も得たのだが、今回は発見できず。そこら辺にいた人に「この辺りに映画館はない?」と聞いてみたら、「映画を見たかったらデリーへ行け」と言われてしまった。ノイダに住んでいる人の感覚はこんなもんなんだろう。
総論として、わざわざ買い物しにデリーからノイダへ来る必要は皆無であることが分かった。ヤムナー河の冷たい風を身体に浴びつつ、巨大な光の繭の中への帰途に着いた。
|
|
|
|
|
NEXT▼2003年2月
|
|
| *** Copyright (C) Arukakat All Rights Reserved *** |



