 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
 これでインディア これでインディア 
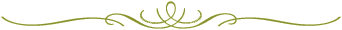
2003年11月
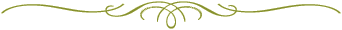
|
|
|
|
もう何度目のことになるのか知らないが、最近一応インドとパーキスターンが、お互いに牽制し合いながらも歩み寄りを見せている。もちろんこのまま印パ関係がすんなりと改善されるという保障は全くないし、この二国が仲直りしてしまうとあらゆる分野で何だか拍子抜けしてしまうような気もするので、今まで通り「仲良くケンカしな」ぐらいの方が退屈しなくていいというのがいろんな人の本音ではなかろうか。インドに住む者として気をつけなければならないのは、こういう一応平和へ向かいつつあるときに、それを望まない人々が大規模なテロを起こす可能性が高いことだ。
しかし最近の印パ関係のニュ−スを見て、ひとつ気になることがある。それは国境間の交通のことである。デリーに定住しているとは言え、一応心は旅人のままなので、何かあったらすぐにでもデリーを飛び出て旅行に出掛ける準備はできている。だから旅情報には敏感なのだが、最近のインドとパーキスターンの対話において、いくつか国境がオープンされそうな話が持ち上がっている。ジャンムー&カシュミール州においてシュリーナガル(印)とムザッファラーバード(パ)間のバス運行、デリー(印)とラーホール(パ)間の鉄道運行、ラージャスターン州マナーバー(印)とスィンド州コークラーパル(パ)間の鉄道運行、ムンバイー(印)とカラーチー(パ)間のフェリー運航などであり、さらに国境を開く計画も持ち上がっている。
もちろんたとえこれらの国境が開いたとしても、外国人旅行者に開かれるのはまだ先のことだが、上記の地名を頭の中で線で結んでみると、いろいろ新たな旅行ルートが浮かび上がってくる。デリー〜マナーリー〜レー〜シュリーナガル〜ムザッファラーバード〜ギルギット、フンザ〜イスラーマーバード〜ラーホール〜デリーなんていう西ヒマーラヤ一周旅行が可能だし、ラージャスターン州からスィンド州に抜けて、カラーチーからムンバイーへ向かうなんてことも可能だろう。
新しい国境通過点というのも気になる。空路はともかくとして、陸路はどこの国境が開くのだろうか?インドのグジャラート州とパーキスターンのスィンド州が結ばれても面白いだろう。両州にまたがってインダス文明の主な遺跡が広がっているので、インダス文明ツアーというのも簡単にできるようになるだろう。
2001年に僕はパーキスターンを旅行したのだが、そのときはカラーチーから入ってイスラーマーバードへ抜けるコースをとり、パーキスターンだけを旅行して廻った。旅行の途中で何人か旅行者に出会ったが、僕がパーキスターンだけを旅行していることを知って彼らに驚かれた覚えがある。そのとき感じたのだが、一般的なバックパッカーにとって、パーキスターンはインド、イラン、中国へ行くための通り道に過ぎないということだ(まるで現代までシルクロードの伝統が残っているみたいだ)。みんなパーキスターンには全く期待しておらず、さっさと通過して次の国へ行こうとしていた人がほとんどだった。だが、案外パーキスターンが過ごしやすいのを知って、少し滞在期間を増やしている人も多かった。インドがバックパッカー天国なのは揺るぎない事実だが、パーキスターンはそういう意味で旅行の目的地としての認知度があまり高くない。もし両国間の複数の国境が開いて、現在よりもインド〜パーキスターン間の越境が簡単になれば、インドに対するネパールのような感じで、パーキスターンの観光業にもプラスになるのではないだろうか。
ちなみに現在のところ、インドの日本大使館はパーキスターンのヴィザ取得のために必要な大使館レターを発行していない。インドからパーキスターンへ抜けるためにはあらかじめ第三国でパーキスターンのヴィザ取得が必要である。
昨夜は徹夜でレポートを終わらせたが、これによって宿題地獄も一山越えた。今日は気分転換したかったので、映画を見に出掛けた。今週は「マトリックス・レボリューションズ」が世界同時公開されるので、インドの映画館もスケジュールが変則的である。今日はPVRプリヤーで、今週限りで入れ替わってしまいそうな「Sssshhhh...」を見た。
「Sssshhhh...」とは要するに「静かに」「黙れ」という意味の、口の前に人差し指を当てるジェスチャーの「シー」である。このジェスチャーはインドでも同じだ。世界共通なのだろうか?映画のチケットを購入するときに「シーのチケットください」と言わなければならないから少し面白い。主演はタヌージャーの娘にしてカージョールの妹、タニーシャー(新人)と、ディノ・モレア。他にカラン・ナート、ガウラヴ・カプール、スヴァルナー・ジャーなど。ジャンルは最近インドでもすっかり定着したホラー映画である。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
Sssshhhh... |
● |
| Sssshhhh... |
のどかな山の都シムラーで殺人事件が起き、男女が惨殺された。メヘク(タニーシャー)はその被害者の妹だった。6ヶ月経った今でも姉の死が忘れられず、事件を引きずっていた。あるとき、彼女のもとに電話がかかって来て、「お前も殺す」と言われた。メヘクは恐怖の毎日を過ごす。
メヘクは地元の大学生だった。お調子者のロッキー(ディノ・モレア)、新入生のスーラジ(カラン・ナート)、ラジャト(ガウラヴ・カプール)、ゲヘナー(スヴァルナー・ジャー)などが彼女の仲間だった。メヘクは母親と共に住んでいた。父親は家族を捨てて他の女と一緒になってしまっていた。
電話があった後、メヘクは仮面をかぶった黒装束の「ジョーカー」に何度も命を狙われるが、なんとか助かっていた。ジョーカーは遂に警察に射殺されたが、メヘクは気持ちが晴れない。そこで仲間たちは、一緒にタイへ行って気分転換しようということになった。
実はこの仲間内でも人間関係が複雑になっていた。ロッキーとメヘクは幼馴染みだったが、友達以上恋人未満な仲だった。しかしロッキーはメヘクに恋していた。一方、新入生のスーラジもメヘクに恋しており、メヘクもスーラジに好意を抱いていた。その2人を見て、ロッキーは嫉妬していた。また、ゲヘナーはロッキーのことが好きだった。ロッキーの親友は、事あるごとにロッキーの嫉妬心を煽っていた。
タイに着いた彼らは、無人島へ行くことにした。しかしその島で次々と仲間がジョーカーに殺されていった。ジョーカーはやっぱり内部にいたのだ。最後まで残ったのはロッキー、スーラジ、メヘクだった。ロッキーとスーラジ、どちらがジョーカーなのか。メヘクは困惑するが、スーラジを信用することにした。しかし実はスーラジがジョーカーだった。
スーラジはメヘクの父親と蒸発した女の息子だった。メヘクの父親のせいでスーラジの家族は不幸のどん底に突き落とされ、彼の家族に復讐をしようとしていたのだった。また、なんとラジャトはスーラジの弟であることも判明する。ラジャトは死んだはずだったが、それは見せかけだけだった。つまり、スーラジとラジャトが立ち代りジョーカーになってメヘクをおびやかしていたのだった。しかし最後はロッキーが二人を殺し、メヘクと共に無人島を去った。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
無茶苦茶なストーリーのホラー映画だったが、インド映画特有のあらゆる要素が含まれた映画だったので、案外楽しめた。
前半の舞台はヒマーチャル・プラデーシュ州の州都シムラー。行ったことがあるならすぐにシムラーだと分かる。ザ・モール、スキャンダル・ポイント、教会などシムラーの名所が登場する。
主人公のメヘクは姉を殺された上に、自分の命も何者かに狙われる。「ジョーカー」と呼ばれるその殺人鬼は、「ラスト・サマー」や「スクリーム」などに登場する殺人鬼とイメージがだぶる。ハリウッドのホラー映画の手法がよく研究されており、なんでもない映像がやたら怖く感じた。ただ、殺人シーンなどはワンパターンで幼稚である。ジェイソンみたいにユーモアのある殺し方をすればよかったのだが、ジョーカーはただナイフで切りつけるだけである。しかもジョーカーはおっちょこちょいで比較的弱いのが笑える。
後半の舞台はタイだった。カオサン通りでロケが行われたようで、無人島はおそらくプーケット島近辺で撮影されたと思われる。すがすがしい山の町から始まって、インターミッション後にバンコクの都会へ移り、その後は南の島へ。これらの、舞台の思い切った切り替えがあったおかげで、それほど退屈しない映画だった。
一番残念なのは脚本に破綻があることだ。結局スーラジが犯人で、しかもラジャトまで共謀者だったという筋書きは、思い起こしてみただけでもいくつか矛盾する点がある。最大の矛盾はバンコクへ舞台が移ったところだ。航空券の関係でスーラジとメヘクが先にバンコクへ行くことになったのだが、もしスーラジがメヘクに殺意を抱いているのなら、このとき簡単に彼女を殺害できたはずだ。「気分転換にタイへ行くぞ!」「お〜!」で大学生の若者数人が簡単にタイへ行けてしまうというのもちょっと話がおかしいと思う。いったい誰が旅費を出すのだ。
これまで再三「ホラー映画にミュージカル・シーンは必要ない」と主張してきたが、この映画は案外うまくホラー映画にミュージカル・シーンを挿入していて感心した。しかしタイに着いた直後のダンス・シーンは強引すぎる。なぜかタイのホテルで「パンジャービー・ナイト」のイベントが行われており、それがそのままパンジャービー・ダンスチックなミュージカルとなる。なぜタイでパンジャービーなのだ・・・!だが、このとき流れる「Ishq Da Maara Hai」はこの映画の挿入歌中最高の出来だ。ちなみに音楽監督はアヌ・マリク。
この映画ではディノ・モレアが輝いて見えた。今まで彼が出演した「Raaz」とか「Gunaah」では、影のあるキャラクターを演じていたので、彼自身もそういうおとなしめのキャラなのだと思っていた。しかし「Sssshhhh...」のディノは、ワイルドでアクティヴな若者を演じており、それがけっこうはまっていてかっこよかった。ディノ・モレアのこれからの成長に期待である。
主演女優のタニーシャーは、あのカージョールの妹らしい。眉毛がつながってなかったので気付かなかったが、言われてみれば似ていないこともない。だがむしろタッブーに似ている。顔立ちは悪くないのだが、鼻が大きすぎて個人的にはいまいちだ。
| ◆ |
11月6日(木) シャンカル・マハーデーヴァン |
◆ |
2001年のインド映画音楽界の一大事件と言えば、「Dil Chahta Hai」サントラのリリースだったと言っていいだろう。シャンカル・エヘサーン・ロイというトリオ作曲グループが音楽監督を務める同CDは、インド離れした斬新なセンスで溢れ、映画のヒットと共にロング・ラン・ヒットした。2001年度のフィルム・フェア音楽賞はA.R.レヘマーンの「Lagaan」に持って行かれたものの、今聞いても全く色あせないそのメロディーは、「Dil Chahta Hai」の完成度を改めて証明している。
シャンカル・エヘサーン・ロイとは、ボリウッド音楽界に一石を投じるために(?)結成された、シャンカル・マハーデーヴァン、エヘサーン・ヌーラーニー、ロイ・メンドーサの3人の作曲チームである。名前から察する限り、それぞれヒンドゥー、ムスリム、クリスチャンである。中でもシャンカル・マハーデーヴァンがリーダー格だ。歌も歌えば作曲もするマルチなミュージシャンである。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
シャンカル・マハーデーヴァン |
● |
最近のインド音楽界では、映画業界でミュージシャンとして活躍していた人が、映画音楽から離れてCDを製作する動きが活発になっている。日本でも名の知れたA.R.レヘマーンも、「Vande Mataram」など、いくつか素晴らしいCDをリリースしている。サンディープ・チャウターの「Mitti」というCDもお気に入りのひとつだ。プレイバック・シンガーも独立して「シンガー」としてCDを出し始めており、いくつかはヒット・チャートの上位に食い込んでいる(ただ、大ヒットしたプレイバック・シンガーのCDはまだ少ないかも)。もはやプレイバック・シンガーをシンガーと呼んでいいのではなかろうか?その一方で、なぜかプレイバック・シンガーが、脇役とかチョイ役ではなく、主役として主役として出演する逆現象も起こっており、ラッキー・アリーやケーケーをスクリーン上で見た。また、間もなく公開されるであろう「Love
In Nepal」では、ソーヌー・ニガムというプレイバック・シンガーが主演をはる。
シャンカル・マハーデーヴァンもソロ・アルバムをリリースしている。1998年に発売された「Breathless」は大ヒットを記録したそうだ。僕はこのCDを持っていないのだが、Indo.toの矢萩多聞さんに聞かせてもらった覚えがある。特にタイトルになっている「Breathless」という曲は、息継ぎなしでずっと歌いっぱなしという特異な歌である。
最近テレビを見ていたら、シャンカル・マハーデーヴァンの「Oh Sahibaa」という曲のプロモーション・ビデオが流れており、いい曲だと思っていた。スーフィー音楽っぽい循環的で陶酔性のある、アップテンポの曲で、インドの田舎の美しい風景が共に映し出されていた。このプロモーション・ビデオは「Saathiya」の監督シャード・アリーが撮影したそうだ。日本で発売されているDVD「ボンベイ」の最後に収められているA.R.レヘマーンの「Vande Mataram」は、僕の大好きな音楽ビデオのひとつだが、映像と音楽併せて、それに匹敵するくらい素晴らしいと思っていた。この曲が欲しいな、と思っていたら、偶然CD屋で発見したので即買いした。
アルバムのタイトルは「9 Nine」だった。今年の8月に発売されているので、随分長い間気付かずにいたことになる。CDには9つの曲が入っている。9という数字は言うまでもなくインドでは特別な意味を持っており、ナヴァラサ(9つの情感)、ナヴァラトナ(9つの宝石)、ナヴァグラハ(9つの星)など、9に関係するものはいくつかある。このCDに収められている9曲はそれぞれ9つの感情のテーマを持っており、その9つの感情とは「歓喜」「悲哀」「恋愛」「嫉妬」「希望」「恐怖」「平安」「熱情」「感情」である。最後の「Jazbaat(感情)」だけは何だかテーマから外れているように思えるが、「Jazbaat Ki Sau Rang Hai(心は色とりどり)」という題名なので、他の8つの感情をまとめる意味を持っているのだろう。僕が気に入っていた「Oh
Sahibaa」は「歓喜」の曲で、CDの第一曲目に収められていた。テレビやラジオで聞いて「この曲いいな」と思ってCDを買ってみると、「あれ、こんなんだったかな」と失望することも多かったりするものだが、「Oh Sahibaa」は今聞いても変わりなくいい曲だ。
シャンカル・マハーデーヴァンはムンバイーのタミル人家庭に生まれた。幼い頃から多くの著名的音楽家たちから手ほどきを受け、類稀な才能を発揮したようだ。最初はプレイバック・シンガーとして名を売ったが、毎年定期的にライブ活動を行ったり、エヘサーンやロイらと共にインド映画音楽を作曲したりと、各方面で活躍している。シャンカル・マハーデーヴァンと、シャンカル・エヘサーン・ロイ、両方にこれからも期待している。
| ◆ |
11月7日(金) 東京コンテンポラリー・ダンス |
◆ |
11月2日からカマニ・オーディトリアムで第二回アジア舞台芸術祭が開かれていた。今年の参加国はインド、中国、韓国、日本だった(ヴェトナムはドタキャン)。忙しくて全然見に行けなかったが、最終日の今日は日本の公演日なので、見に行くことにした。
他国は伝統芸術を披露したが、唯一日本だけはコンテンポラリー・ダンスを題材に選んだ。正式な題目は「3つのステージで見る東京コンテンポラリー・ダンスの歴史」。1970年代の「舞踏の時代」を象徴するダンサーとして室伏鴻、1980年代の「ポスト・モダンダンスの時代」を象徴するダンサーとして黒沢美香、1990年代の「テクノロジーと身体の時代」を象徴するダンサーとして川口隆夫がパフォーマンスを行った。
皮肉な話だが、デリーに住むようになってかえって日本の文化が身近になったが、こういうコンテンポラリー・ダンスなんか日本に住んでいたら絶対に一生見ることがなかっただろうと思う。確か1年前にも何かのイベントで日本のコンテンポラリー・ダンスを見る機会があったので、これで2回目になる。
まずは川口隆夫が「夜色」というダンスを踊った。最初はギターのチューニング中のような音に合わせて踊っているだけで訳が分からなかったのだが、途中からフラッシュやバック・スクリーンなどを使って面白い効果が出ていた。次に黒沢美香が「クロソフスキー/アクタイオーンの水浴を覗くディアーナ」というダンスを踊った。最初は無音の中を、薄気味悪い格好をして踊っていて訳が分からなかったのだが、途中から音楽が鳴り始めて踊りらしくなってきた。最後に室伏鴻が「Edge-India」というダンスを踊った。最初はいきなり飛び降り自殺したり、奇妙な声を上げたりして訳が分からなかったのだが、途中から全裸になってクネクネとした踊りをし始めて何となく玄人っぽかった。とにかく、訳が分からないダンスばかりだった。これがコンテンポラリー・ダンスである。
コンテンポラリー・ダンスを見ると、なんだか「ミスト」というゲームを思い出す。詳しく説明するのは避けるが、つまり突然無人島に突き落とされたような気分になる。全く訳が分からないのだ。しかも無性に不安になってくる。この不安は何だろうと自分で分析してみると、まずは「日本人はこんな踊りを見て楽しんでいるのか」とインド人に思われるのが恥ずかしい、という気持ち。そして「もしかしてこれを見てつまらないと思っているのは僕だけなのかな」と焦る気持ち。さらに不安は深くなり、「これをつまらないと言ってしまったらそのままだから、楽しいということにしておこうか、でも、何が楽しいのかと聞かれたら答えれないから、つまらないと断言してしまった方が楽かな。いや、つまらないところが楽しい、と言うのはどうだろうか」と思考がグルグル廻る。とにかく、コンテンポラリー・ダンスは何とか観客に楽しんでもらおうという姿勢ではないので、もし楽しもうと思ったら、自分から理性的に楽しまなくてはならない。それがつらいところだ。
また、コンテンポラリー・ダンスは極度に好みが分かれると思われるので、他人を誘うのも躊躇してしまうところがある。他人を誘って「つまらなかった」と言われたら責任を感じてしまうし、「楽しかった」と言われても「本当に楽しかったのかな」とこちらが逆に疑ってしまったりもしてしまうので、あまり人を誘うことはしなかった。
結局、僕はあまりコンテンポラリー・ダンスが好きではないのだろう。芸術映画や前衛芸術などもあまり好きではない。「これがオレの芸術だ、分かる奴だけついて来い!」と、他人を突き放したような形の芸術は、僕はあまり芸術と認めていない。他人の心を総合的に刺激し、操作してくれる芸術がいい。見ていて疲れたり、不快な気持ちになるだけのものは、わざわざ見たいとは思わない。そう思いつつ少し暗い気持ちになっていた。
ダンスの後は、慶応大学教授の石井達郎氏が、日本のコンテンポラリー・ダンスについて解説してくれた。いくつか代表的なコンテンポラリー・ダンスのステージのビデオも少しだけ見せてくれたのだが、そこに映っていたダンスは素直にすごいと思えた。エンターテイメントという雰囲気がした。このビデオがなかったら、僕はコンテンポラリー・ダンスをもう二度と見ないと決めてしまったかもしれないが、おかげでもっと本格的なコンテンポラリー・ダンスを見てみたいと思うようになった。こういう感情が生じただけでも、今日のダンスは僕にとって収穫だった。
| ◆ |
11月8日(土) クルクシェートラ・ツーリング |
◆ |
スィク教の創始者グル・ナーナクの誕生日である今日、デリーにまたひとつ新たな伝説が生まれた。デリー・ツーリング・クラブ結成である。デリー・ツーリング・クラブは、デリー在住の(長距離走行に支障のない)バイクのオーナーが入会可能という、非常にオープンなクラブである。今日は記念すべき第一回ツーリング。目的地はデリーの北、ハリヤーナー州に位置する、マハーバーラタ戦争の古戦場、クルクシェートラだ。日本人にはあまり知られていないが、ヒンドゥー教の聖地のひとつとして、インド人なら知らぬ者はいないだろう。クルクシェートラは去年の3月に一度訪れたことがあるため、大体の道順、観光名所などは分かっている。距離的にも日帰りにちょうどいいと判断した。参加者は2人。アルカカットは赤のカリズマ(225cc)、友人のK氏は銀のパルサー(180cc)である。
朝8時半頃にアルカカット邸を出発し、ムールチャンド病院近くのバーラト・ペトローリアム(ガソリン・スタンド)でガソリンを補給。もちろん新発売のハイオクガソリン、スピード93だ。オクタン価93の、インド最高峰のガソリンである(1リットル35ルピー)。・・・しかし調べてみたら、どうもこの水準は日本に比べたらかなり低いみたいだ。日本工業規格(JIS)では、「ハイオクガソリン」をオクタン価96以上と定めており(ちなみにレギュラーは89以上)、一般的に日本のハイオクガソリンはオクタン価100、レギュラーでも90〜91らしい。しかしインドではレギュラーはオクタン価87しかない。スピード93も日本の基準で見たらレギュラーに毛が生えた程度のガソリンのようだ。・・・オクタン価がいったい何なのか詳しくはよく知らないが、とにかく高ければ高いほどいいようだ。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
出発時に一枚記念写真 |
● |
オベロイ・ホテル、プラーナー・キラー、プラガティ・マイダーンなどを通過してリング・ロードへ。そのままずっと北上。今日は祝日のため、道路が空いていて快適だ。ITO、ラージ・ガート、ラール・キラー、ISBTなどを通過し、マジュヌ・カ・ティッラーやチベッタン・キャンプを越えると、アウター・リング・ロードに入る。すると急に辺りの風景が地方都市のようになって来る。極めつけはアウター・リング・ロードとグランド・トランク・ロード(国道1号線)の交差点である。この国道1号線をずっと北上すればいいのだが、ここが大ゴミ捨て場になっており、周囲数キロに渡って悪臭が漂っている。こんなところには絶対に住みたくない・・・。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
奥に見える台地みたいなのが
全てゴミの山である |
● |
国道1号線に入ってしばらくすると、道は非常に快適になる。乗用車が横に5台くらい並べるくらいの道幅が片側車線にあり、立派な中央分離帯もあり、案外道はきれいに舗装されていて穴ぼこだらけでもない。道の両側には並木があって日陰を作ってくれている。周囲の風景は広大な畑である。インドでツーリングをするというと、自分でも危ないイメージがつきまとっていたのだが、実は日本よりも快適な道だった。もちろん、自動車専用道路ではないので、道を人が横切ったり、牛の大群が歩いていたり、自転車がフラフラと走っていたり、牛車が荷物を運んでいたりするのだが、かえってそういう障害物が刺激になって、眠気を催さない。時速80kmで走行し続けた。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
牛たちも通る国道1号線 |
● |
デリー州からハリヤーナー州に入り、しばらく北上し続ける。10時頃、途中ソーニーパト辺りの茶屋でチャーイを飲んで休憩。南デリーのガソリン・スタンドから約60kmほどだった。ヘルメットを長時間かぶっていると、頭が痛くなってくるので、1時間おきぐらいに休憩をしないとつらい。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
ソーニーパトの茶屋にて |
● |
さらに国道1号線を北上、11時過ぎにパーニーパトに到着。南デリーからちょうど100kmほどの地点。パーニーパトは、クルクシェートラのように神話上の古戦場としてではなく、歴史上の古戦場としてその名を刻んでいる。ここではムガル朝の興亡に関わる重要な戦争が3回起こった。第一回パーニーパトの戦いは1526年4月に起こり、北西インドから南下したバーブルが、デリーを支配していたローディー朝のイブラーヒームの軍を破り、ムガル朝創立のきっかけとなった。第二回は1556年11月に起こり、ムガル朝第三代皇帝アクバルの軍が、デリーを占領していたヘームーの軍を撃破して、ムガル朝の北インド支配拡大のきっかけとなった。第三回は1761年1月に起こり、アフマド・シャー・ドゥッラーニー率いるアフガン軍が、ムガル皇帝擁するマラーター軍を破って、ムガル朝衰退のきっかけとなった。現在パーニーパートは雑多な町になっている。デリーを北上して最初に出会う、町らしい町である。
パーニーパトにニルラーズを見つけたので、そこで2度目の休憩をした。ここにはニルラーズ・ホテルもある。デリー〜チャンディーガル間で休憩するのにいい場所である。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
パーニーパトのニルラーズと
ニルラーズ・ホテル |
● |
11時半にパーニーパトにニルラーズを出発し、さらに北上。ハリヤーナー州北部の中心都市カルナールも越え、さらにさらに北上し、12時半過ぎにやっとピプリーに到着した。ピプリーはクルクシェートラの入り口にあたる町である。南デリーからざっと170kmだった。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
クルクシェートラの入り口 |
● |
南デリー〜ピプリー間では印象的な出来事が2つあった。1つは、リング・ロードから国道1号線まで、何台もクラシック・カーが走っているのを目にしたことだ。どうもクラシック・カー・マニアたちのツーリングが同時に行われていたようだ。僕は自動車に詳しくないので、どれが何なのかよく分からないが、相当価値のある車なのは人目で分かった。どれも非常にかっこよかった。もう1つは、途中1000cc以上はある、ホンダやヤマハの日本製大型バイクに乗ったスィク教徒4人組と遭遇したことだ。彼らも国道1号線を北上しており、すさまじいスピード(時速150km以上?)で僕たちを追い抜いて行った。あれに比べたら、カリズマもパルサーもオモチャみたいなものだ・・・。どうやらこのルートは、カーマニアやバイクマニアのインド人たちも普通にツーリングに利用しているようだ。
ピプリーのドライブ・インで昼食を食べた後、クルクシェートラ観光を開始した。まずはクルクシェートラ・パノラマ科学センターへ。この博物館の1階は科学博物館になっており、インドの古典科学と、現代科学がごっちゃになって展示されており、見方によっては面白い。2階はマハーバーラタ戦争のジオラマになっている。案外よく出来ていて、もし「マハーバーラタ」の知識があるなら、けっこう楽しめる。
次に同じ敷地内にあるシュリー・クリシュナ博物館へ行った。こちらはクリシュナ関係の美術品が展示されている。けっこういいものを揃えており、ゆっくり見るとこちらも面白い。
ところが、なぜか今日はどちらの博物館も大混雑だった。今日はスィク教の祭日だが、クリシュナや「マハーバーラタ」とは関係ないはず。なぜここまで多くの人が押しかけて来ているのかは全く分からなかった。というわけでゆっくりと鑑賞することができなかった。僕は以前にも既に見ているので特に残念でもないのだが。
その後、クリシュナがアルジュンに「バグヴァド・ギーター」を説いた場所に建つと言われる寺院ジョーティサル、アルジュンが瀕死のビーシュマのために地面に矢を放って水を湧き出させた場所と言われるビーシュマ・クンド、ブラフマー神が作ったと言われる巨大な湖、ブラフマー・サローヴァルなどを簡単に見て廻った。やはりどこも混雑していて、少し当てが外れた。以前来たときは静かでのんびりとした町だったのだが・・・。
暗くなる前に何とかデリーに着きたかったので、3時頃にはクルクシェートラを発った。かなり急ぎ足になってしまった。来た道をそのまま戻り、一度パーニーパトのニルラーズで休憩、もう一度ソーニーパトの茶屋で休憩しつつ南下した。ソーニーパトを過ぎるともう辺りは暗くなってしまった。6時半頃には何とかデリーに戻った。マジュヌ・カ・ティッラー(チベッタン・キャンプ)でモモを食べた。
クルクシェートラ〜デリー間では、印象的な出来事がひとつあった。途中から、青いカリズマが僕に勝負を挑んできたことだ。おそらくカリズマを買ったばかりなのだろう、嬉しくて嬉しくて仕方なかったのだろう、やたらと僕に対して挑発的な走行をして来ていた。追い抜かしては待ち、僕が追い抜くとまた追い抜いてきたり、わざと並んで走行したり、裏からパッシングしてきたりと。まあ、傍目から見たら、赤いカリズマと青いカリズマの華麗なる競演と表現することもできるかもしれない。ちなみに、青いカリズマを道路で見たのは初めてだ。7色あるカリズマの中で、赤カリズマ、黄カリズマが圧倒的に多く、銀カリズマ、黒カリズマも見たことがあった。だが、青カリズマはショールームでしかお目にかかったことがなかった。けっこうな珍種に出くわしたものである。
その後、リング・ロードを南下して、フマーユーン廟近くのガソリン・スタンドでガソリンを補給。その結果、カリズマの燃費が計算できた。出発時にガソリンを補給したガソリン・スタンドから、デリー到着後そのガソリン・スタンドに着いた時点の総走行距離は369.6km。費やしたガソリンは8.58リットル。つまり、1リットルで約43km走ったことになる。もちろん、都市部を走っているときはそれを下回るだろうが、郊外でほとんどノンストップで走行すれば、リッター40km以上走ってくれることが証明された。なかなかいい数字だ。
デリー・ツーリング・クラブの第一回ツーリングは、何の問題もなく無事に終了した。走行中、インドでツーリングする際にいくつか気を付けなければならない点が分かった。まず、トラックの後ろは危険だということ。何が危険かというと、後輪に弾き飛ばされた石が飛んで来るのだ。しかも隕石くらいはある巨大な石も平気で飛んでくる。ヘルメットをかぶっていないと、その石が脳天を直撃して即死ということにもなりかねない。あな恐ろしや・・・。次に、夜走行することはかなり危険だということ。一番危険なのは、変な虫がヘルメットのバイザーにベチョベチョぶつかって潰れていくことだ。その内前が見えないくらいになる。もちろん、バイザーを上げたら顔に直で虫がぶつかって来ることになる。ほとんど道案内がないので、道に迷いそうになったら積極的に人に質問することも大切だ(デリー〜クルクシェートラ間はほとんど一本道だが)。
日本で何回かツーリングをしたことはあったが、はっきり言ってインドの方がツーリングしやすい国だと思った。少なくともデリー周辺部の道は舗装が進んでおり、「穴の中に道路がある」という状態ではない。現在進行中の「黄金の四角形」計画(デリー、コールカーター、ムンバイー、チェンナイ間を結ぶ高速道路建設計画)が完成したら、さぞや面白いことになるだろう。ほとんど一直線の道だし、警察や罰金を気にする必要もないので(罰金は一律100ルピー)、飛ばそうと思ったらバイクの限界まで飛ばすことも可能だ。歴史のある国なので、インドのことを研究すればするほど、ツーリングの目的地にしたい場所がたくさん出てくるのもいい。有名な観光地ならガイドブックなどを読めば出ているが、それ以外でも面白い場所はインド全土に散在している。デリー周辺にも目的地候補は多い。ただ、デリー周辺には海がないので、海岸線走行ができないのが残念だ。「Dil Chahta Hai」みたいに、ムンバイーからゴアにアラビア海に沿って走ったりできたら、どんなに気持ちいいだろう。また、インドで販売されているバイクは、まだまだ性能が低いので、長距離走行するのに不安があるのが一番の懸念だ。225ccのカリズマでギリギリくらいだった。180ccのパルサーは少しつらそうだった。やはり余裕のあるツーリングのためには400ccは欲しい。もし大排気量のバイクが欲しかったら、現時点ではあのスィク教徒4兄弟のように、海外から輸入するしか方法はない。しかし、何より日本のツーリングと違うと思ったのは、バイクで牛の群れを追い越したり、羊の群れの中を通ったりできたことだ。バイクで聖地巡礼というのも我ながらなかなかシャレてると思った。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
田舎の風景とカリズマ |
● |
日本では「文化の秋」と言うが、デリーの「文化の季節」は11月から2月あたりの「冬」にあたる時期である。この時期になると、毎晩毎晩どこかで何かしらの文化イベントが開かれている。今日は毎年恒例のICCR外国人留学生の文化祭が開催された。
ICCRとはインド文化関係評議会(Indian Council for Cultural Relations)のことで、外国人留学生に奨学金を提供している団体である。デリーにはICCRの奨学金を得て留学している外国人がかなりいて、今日の文化祭は、彼ら奨学生たちの文化の祭典というわけだ。
こういうイベントに日本が参加することは稀だったのだが、今年は強力なリーダーシップが発揮され、日本も参加することとあいなった。しかもICCRから奨学金をもらっていないにも関わらず、僕も参加することになっていた。安請け合いをしてしまう性格なのだ。協議の結果、結局日本チームは「盆踊りを踊る」という何の変哲もない結論に至った。
9月の末からICCRのイベントに向けて準備が始まった。まずはメンバー集めから始めなければならなかったが、ほとんどの人はつれない返事。みんな「忙しい」と言ってむげに断ってくる。特に博士課程の人々は全く相手にしてくれないという悲しい状況。ICCRから奨学金をもらっているくせに、全く恩義を感じていないようだ。彼らは、奨学金をもらうということは、それなりの義務が生じるということを理解していない。ここで軽く批判しておく。
何とか人数が集まり、最終的に男3人、女4人で踊ることになった(この内の1人はなぜかタイ人である。日本語を習っていて、是非参加したいと言ってきた)。日本人学校から「東京音頭」のテープを借り、日本文化情報センター(JCIC)から浴衣を借りて、何とか体裁も揃ってきた。10月から本格的に踊りの練習を行い、だんだん形になってきた。この過程はまさに青春ドラマのようで、涙あり、笑いあり、メンバー間の軋轢あり、感動的和解ありで、ここで書くのは恥ずかしいくらいなので、書かないでおく。本番前になって、日本人学校の学生が太鼓叩きとして参加してくれて、さらに完成度は増した。
いよいよ当日になった。場所はプラガティ・マイダーンの野外劇場ハムサドワーニー・シアター。午後6時半から開場だった。
今年の参加国は、演目順に、ベラルーシ、ポーランド、スーダン、ウズベキスタン、日本、バングラデシュ、ブータン、ルーマニア、ギアナ、キルギスタン、ネパール、シリア、カザフスタン、ウガンダ、ウクライナ、ガーナ、タジキスタン、スリランカ、ラテン・アメリカの19カ国である。・・・つまり、押しも押されぬ先進国は日本のみ、残りの18カ国は日本ではあまり馴染みのない後進国ばかりである。もちろん、インドには先進諸国から来ている留学生もいる。だが、彼らはこういうイベントに積極的に参加しようとしない傾向にある。いや、正確に言えば、先進国になればなるほど、固有の文化を失う傾向にあり、文化イベントでやることがないのだ。一方、発展途上国の留学生は皆一芸を持っているから、こういうイベントでも出し物に困らない。というわけで、日本は必然的に先進国代表ということになってしまったのだった。
インドにいて視野が広がる点は、日本にいるとあまり馴染みのない上記の国々の人々と交流できることだ。そして日本人の頭の中にこびりついている間違った「世界」観をぶち壊すことができることだ。日本で「世界」という言葉を使う場合、知らず知らずの内に「世界=欧米諸国」という勝手な定義が出来てしまっているような気がする。欧米諸国で受け入れられれば、「世界で愛用されている○○」とか、「世界中で大ヒット」などというキャッチコピーが平気で使用されてしまう。入ってくる情報も欧米関係のものばかりだ。日本にいると気付かないが、少し海外に出れば、日本のニュースには過剰なまでにアメリカのニュースが多いことが分かる。こういう情報環境にいるため、日本人は欧米以外は暗黒世界のように思えてしまう。インドに留学するなんて人生を捨てたか、などと思われる要因もそれにある。しかし欧米諸国というのは、客観的に世界の地図と歴史の中で見たら、マイナーな部類に入るし、新参の田舎者に過ぎない。歴史を公平な目で見れば、世界の中心は何千年もアジアとアフリカであり続けたことが分かるし、今でもそれは基本的に変わっていないと思う。そしてアジアとアフリカの中心的な国こそインドだ。上記のような国々の留学生を一同の下に会させることができる国はインドしかないのではないだろうか?
というわけで、日本は踊った。日本の看板を背負い、そして先進諸国の看板を背負って。他の国々の人々がきらびやかなステージ衣装を身にまとっている中、女の子はまだしも、日本人の男3人はあまりさえない安物っぽい浴衣を着て踊った。日本は世界第二の経済大国のはず・・・周りは日本から多額の援助を受けている国の留学生ばかり・・・それなのに文化イベントでは日本はなぜか前座か引き立て役扱いに近いこの屈辱・・・見よ、他の人々の顔を。まるで「今夜の主役はオレだ」というような誇らしげな顔をしている。国の歴史がぶらさがったようなカッコいい衣装を身に着けている。しかし日本人の顔にそれほどの覇気はない。日本人の服装にもそれほどの壮麗さはない。仕方ない、我々はいつの間にか、経済発展と引き換えに、民族の記憶と誇りを捨ててしまったのだ。それでも日本は踊った。僕なりのささやかな抵抗と共に・・・僕の頭にはピカチュウのお面が光っていた。ピカチュウ・・・これこそ現代の日本が世界に誇ることのできる大衆文化・・・世界の友よ、このピカチュウのお面を見てしばし思い出してもらいたい。ピカチュウは日本で生まれたのだ。日本のピカチュウが世界の子供たちの心を捉えているのだ。できればホンダのアシモに踊ってもらいたかった・・・という叶わぬ夢を胸の奥に押し込み、僕たちは精一杯踊った。会場からは温かい拍手が。ありがとう、世界の友よ。日本は踊った、踊ったよ。先進諸国が軒並み、後進国との交わりを避ける中、日本だけはこのステージに立ったよ。自動車や電化製品でしか日本を知らない人々よ、日本のことを少しは分かってもらえただろうか?
テストやレポートで追われる中、なぜか盆踊りの練習をしている自分にふと疑問が沸いたことが何度もあったが、インドで、外国人留学生の前で、盆踊りを披露できたことは非常に素晴らしい経験だった。参加した留学生たちと仲良くなれたことも大きな収穫である。なんとブータン人からサッカー交流試合を申し込まれたりした。
| ◆ |
11月11日(火) Ek Din 24 Ghante |
◆ |
今日はPVRアヌパムで「Ek Din 24 Ghante(1日24時間)」という映画を見た。主演はナンディター・ダースとラーフル・ボース。監督は「Mumbai Matinee」や「Jogger's Park」のアナント・バーラーニー。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
ナンディター・ダース(左)と
ラーフル・ボース(右) |
● |
| Ek Din 24 Ghante |
舞台はムンバイー。サミーラー(ナンディター・ダース)は幼少の頃から予知能力があった。夢で見たことが現実に起こるのだった。サミーラーにはヴィーレーン(ラーフル・ボース)というボーイフレンドがいた。サミーラーの父は実業家だったが、風来坊な生活をしているヴィーレンを忌み嫌っていた。父にはソニアという愛人がいた。
ある日、サミーラーは不吉な夢を見た。案の定その夢は現実になった。ヴィーレーンが賭博場で大負けし、マフィアのボスに捕まってしまったのだった。ヴィーレーンはサミーラーに、24時間以内に200万ルピーを用意して港に持ってくるように頼む。さもなくば、ヴィーレーンの命の保証はないという。ヴィーレーンを愛していたサミーラーは、何とか金を用意することに決める。
サミーラーは父親にその金の工面を頼むが、もちろん受け入れられない。そこでサミーラーは銃を取り出して父親を脅し、200万ルピーを強奪する。父親は金を取り返すために刺客を送り込む。
サミーラーは一路港へ向かうが、ちょうどその日はバンド(ゼネスト)の日で、交通機関が麻痺し、街には暴徒が溢れていた。サミーラーは暴徒から逃れ、警察の追跡をかわし、父親が放った刺客を逆に利用したりして、なんとか時間内に港に辿り着く。
港にはヴィーレーンとマフィアがいた。サミーラーが金を渡そうとするが、父、刺客と警察が同時に踏み込んできて、相互の銃撃戦となる。結果、マフィアのボスが生き残り、200万ルピーを奪って逃げる。しかしサミーラーのおかげでヴィーレーンは助かった。
ところがその夜もサミーラーは夢を見る。その夢に従ってある家に入ると、そこにはヴィーレーンとソニアがいて、会話をしていた。なんと父親の愛人だったはずのソニアは、ヴィーレーンとできていたのだった。今回の事件は全てヴィーレーンとソニアが大金を手に入れるために仕組んだことだった。それを知ったサミーラーはヴィーレーンを撃ち殺し、去っていく。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
非常に評価の分かれる映画。というより、ほとんどの人が駄作と認める映画。でも、もしかしたら傑作と評する人もいるかもしれない。
今年は後半になってアナント・バーラーニー監督の映画が立て続けに3本上映された。「Mumbai Matinee」「Jogger's Park」そしてこの「Ek Din 24 Ghante」である。前者2つの映画は非常に面白かったので、この映画にも自然と期待していた。しかも僕の好きな男優ラーフル・ボースも出演しているので、期待しない方が不自然だった。そういう意味では、期待外れだったと言わざるを得ないだろう。
物語の中心は、恋人を助けるために200万ルピーの金を背負ってひたすら走るサミーラー(ナンディター・ダース)である。バンドのために人っ子一人いないムンバイの街を一人ひたすら走る姿は印象的だ。昔日本で公開されたドイツ映画「ラン・ローラ・ラン」を思い起こさせるが、あの映画のようにテクノ音楽が使われているわけでもなく、スピード感、緊張感があるわけでもなく、黒沢明監督の「羅生門」的展開でもなく、全く単調だ。主人公に予知能力があるというのは少しひねったところだろう。夢のシーンの特殊効果はうまかった。だが、その予知能力がいろいろな場面でサミーラーを救う設定になってはいるものの、別にその能力がなくても映画は成り立ったと言ってもいいだろう。そう考えると、全く蛇足の設定ということになる。結局事件の真相は、ヴィーレーンの狂言誘拐ということで終わるが、もうこの筋は多くの映画で使い古されており、何の新鮮味もない。
最悪の映画と評したいところだったが、ふと感じたことがあった。この監督はもしかして日本映画っぽい手法で映画を撮ろうとしているのではないか、ということだ。インド映画には珍しく、やたらと長回しが多用されていて、それが映画を非常に冗漫にしているのだが、途中から何となく、北野武監督映画っぽい雰囲気を出そうとしているような気がしてきた。もしそうだとしたら、アナント・バーラーニーはドイツ映画や日本映画など、世界各国の映画をよく研究していることになる。残念ながらそれが実っているとは言いがたいが、インド映画にとって彼の存在は決してマイナスではないだろう。
ラーフル・ボースには少し失望した。彼の出演している映画は今まで全て満足のいくレベルだったのだが、今回は映画全体と、彼自身の演技、共に納得がいかなかった。
昨日に引き続き、今日も映画を見にPVRアヌパムを赴いた。昨日気付いたことだが、最近PVRの警備が2割増しくらいに厳しくなった。周囲を警官が見張っているし、内部でも従業員が積極的に客に「May I Help You?」と話しかけ、それとなくチェックをしている。少し前に起こったスイス大使館員レイプ事件の影響だろうか?
今日見た映画は「Dhoop(光)」。主演はレーヴァティー、オーム・プリー、サンジャイ・スーリー、グル・パナグ(新人)である。
| ● |
|
● |
|
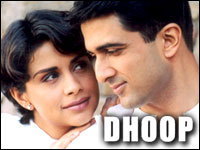 |
|
| ● |
グル・パナグ(左)と
サンジャイ・スーリー(右) |
● |
| Dhoop |
デリーのジャナクプリーに住む、大学教授のスレーシュ・クマール(オーム・プリー)と、図書館勤務のサヴィター(レーヴァティー)の間にはローヒト(サンジャイ・スーリー)という息子がいた。ローヒトは両親の反対を押し切って軍人となった。ローヒトにはピーユー(グル・パナグ)というフィアンセがいた。しかし1999年5月、カールギル紛争が起こり、ローヒトは殉死してしまう。ローヒトの死は、カプール一家やピーユーの人生を一変させてしまう。
スレーシュは息子の死に絶望したが、それよりも悲しかったのは、妻が自分を責めることだった。元はと言えば、スレーシュがローヒトの軍隊入りを認めたのだった。それだけでなく、スレーシュはローヒトに、「背中に銃弾を受けるな、捕虜になるな、負けたら家に戻って来るな」と檄を飛ばしていた。それにより、サヴィターはスレーシュを責めていた。マスコミの心無い報道にも心を痛めた。
そんなある日、内務省から手紙が届いた。国家のために殉死した息子の代わりに、ガソリンスタンドを提供するという内容だった。サヴィターは息子の死をガソリンスタンドごときで償おうとする政府の態度に激怒するが、ピーユーとスレーシュは、それをローヒトからの贈り物、さらにはローヒトそのものだと考えることにし、ガソリンスタンドをもらうことに決めた。また、ピーユーはガソリンスタンドが手に入るまでは、誰とも結婚しないと言い張った。
しかしガソリンスタンドをもらうには、政府のいろいろな役所に行って書類を集めなければならなかった。しかも各部署の役人はスレーシュにそれぞれ50万ルピー以上の賄賂を要求した。真面目な性格だったスレーシュは、賄賂を渡すことを拒否し、役人の横暴を上司に訴えることにした。しかしその上司も賄賂を要求するという有様で、インドの腐ったお役所仕事が露になるだけだった。やっとガソリンスタンドの土地は手に入ったが、自宅から48kmも離れたジャングルの中だった。しかも電気や水を引くのにさらに賄賂を要求された。役所と争う内にスレーシュはマスコミでも取り上げられるようになるが、同時にマフィアから嫌がらせも受けるようになる。それでも彼は諦めなかった。
スレーシュはガソリンスタンドを「カールギル・ハイツ」と名付け、戦死した兵士たちの名前を壁に刻むと決めていた。その健気な努力が実を結び、スレーシュは首相に直談判する機会を与えられる。スレーシュとサヴィターは首相官邸へ行き、役人の腐敗を訴える。それにより、今までスレーシュに賄賂を要求した役人たち全員が停職となった。カールギル・ハイツも完成し、スレーシュたちは見事にローヒトの死を乗り越えたのだった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
ずばり今年最高の映画のひとつと言ってもいいだろう。素晴らしい映画だった。監督は新人のアシュヴィニー・チャウドリー。また楽しみな人材がインド映画に登場したものだ。この映画を楽しむには、ヒンディー語の読解力が多少必要だが、見て損はしない映画だと保証できる。
実話に基づいたストーリーのようで、重要な転機となるカールギル紛争もれっきとした歴史的出来事だ。1999年5月、パーキスターンの正規軍と武装勢力が、カシュミールの停戦ラインを越えてインドに侵入し、それに対してインド軍が反撃したため、「宣戦布告なしの」戦争が始まった。ちょうど1年前の1998年5月には印パが相次いで核実験を行っており、カールギル戦争では実際に核弾頭がミサイルに装着されるまで至ったと言われている。しかし国際的に孤立したパーキスターンのナワーズ・シャリーフ首相が7月に軍を撤退させて和平を申し出たため、この戦争は終結した。この戦争での敗北が、パルヴェーズ・ムシャラフ現パーキスターン大統領のクーデターの発端ともなった。
カールギル紛争では印パ合計1000人以上の死者が出たと言われる。たった4年前の出来事なので、インド人の脳裏にも未だに印象深く残っていることだろう。もしかしたら、映画館にいた観客の中には、家族や知り合いをこの紛争で失った人もいたかもしれない。ローヒトの殉死が告げられるシーンでは、僕の両隣に座っていたおじさんが涙を拭っていた。
映画の前半は、ローヒトを失った悲しみが冗漫になるくらい長々と描写される。見ていて痛くなるほど悲しいムードで溢れている。このままこのペースで続けられると心臓に穴が開いてしまうのではないかと思っていた矢先、政府からガソリンスタンド贈与が決まり、ストーリーは急展開していく。確かに戦争で大事な息子を失って悲しんでいる家族に、「息子の代償にガソリンスタンドをあげます」と言っても、まさに「火に油を注ぐ」結果にしかならないだろう。しかしスレーシュらはそれをポジティヴに考え、ガソリンスタンドを受け取ることにする。だが、そこからがこの映画の主題だった。つまり、政府の役人の腐敗糾弾である。
インドは賄賂社会である。この映画で描かれていることは決してフィクションではない。学生だったらよっぽどのことがない限り賄賂を渡す必要はない。ただ、賄賂を渡しておくといろいろ手続きがスムーズに進むというのは、友人の経験から判断して真実である。だが、もしインドで何かビジネスをしようと思ったら、賄賂は決して避けて通れない。賄賂を渡すかどうかではなく、賄賂の額をいくらにするかどうかの交渉に臨まないといけない。役人に逆らっても損するだけなのも、映画中で徹底的に描写されている。しかし、逆に言えば何でも金で解決してしまう国なので、便利と言えば便利である。
スレーシュは大学で国際経済を教える教授だった。しかし賄賂には縁のない人物だった。スレーシュは「国に息子を差し出したのに、これ以上何を差し出すというのだ?」役人は言う。「国には差し出しただろうが、オレには何を差し出したんだい?」そして「あんたは国際経済を教えているくせに、ビジネスのことを全く分かってない」と付け加える。スレーシュはその後、警察、電気局、軍などのオフィスを転々とするが、行く先々で高額の賄賂を要求され、怒り心頭に達する。僕も役人たちのふてぶてしい態度にかなりムカムカしてきた。これはインドの嫌な面であることは確かだ。こうして、国の英雄の父スレーシュの、ポスト・カールギル戦争が始まるのだった。スレーシュ、サヴィター、ピーユーは執拗な嫌がらせを受けるが、最後は首相が救いの手を差し伸べ、悪は根絶やしにされた。なんだか胸がスカッとした。首相が出てくるところは映画の手法としては非現実的だが、実話に基づいた話ということなので、それも本当のことなのだろう。
俳優の演技も素晴らしかった。レーヴァティーは元々タミル映画の女優で、「Mitr, My Friend」(2001年)という傑作も監督している。心配性なお母さん役をやらせたら右に出る者はいないぐらいで、この映画でも母親としての怒り、悲しみを最大限に表現していた。オーム・プリーもベテラン俳優だ。顔は悪役っぽいが、確かな演技をする。ローヒトの死を知って泣きすがるピーユーに対する表情――自分も悲しいが、悲しむ息子のフィアンセを何とか励まそうとする表情――が非常にうまかった。新人のグル・パナグは面白い顔をしており、なかなか魅力的だった。大女優になるにはオーラが足りないが、そこそこの女優にはなれると思う。サンジャイ・スーリーは特別出演という扱いだったので、あまり出番はなかった。
舞台がデリーということもあり、お馴染みのデリーの風景が随所に見られたのが、デリーの一住民として楽しかった。映画中に出てきたデリーのロケ地で特定できた場所は・・・インド門、大統領官邸、ローディー・ガーデン、サフダルジャング・フライオーヴァー、プラーナー・キラー、プラガティ・マイダーン、メディカル・フライオーヴァーなどなどである。メディカルのフライオーヴァーが完成していたので、かなり最近撮影されたと思われる。
カールギル紛争を題材としながら、インドの役人の腐敗が描かれていた。それに加え、父としてどう生きるか、夫としてどう生きるか、母としてどう生きるか、妻としてどう生きるか、という人生の手本が示されていたようにも感じた。まるで「ラームチャリト・マーナス」のような、いろいろな示唆に富んだ映画だと思った。
よく「愛は国境を越える」などと言われるが、日本とインドの間に広がる広大な空間を愛は越えることができるのだろうか?
巷では、日本人女性×インド人男性のカップルはけっこう多い。それにはいろいろな要因が考えられる。インド人男性は押しが強いから、とか、インド人男性は日本人にはないかっこよさがあるから、とか、インド人男性が日本に行きたいから、とか、日本でもてなかった日本人女性がインドで突然もててそのまま・・・とか。だが、結局は日本人女性の文化的制約の少なさが最大の要因だろうと思う。ここで「文化」とは一応「何をすべきか、何をすべきでないかの共通基準」とでも定義しておこう。現代の日本人女性は性をタブー視する習慣もかなり薄れたし、宗教的制約もないに等しいし、一人で自由に行動し、生きる権利も獲得している。インド人と付き合ったり結婚したりするのも、人生の自由というわけだ。
一方、日本人男性×インド人女性というカップルは、逆に比べたらかなり少ない。ゼロに等しいと言ってもいいだろう。日本人男性がもてないわけではない。はっきり言って日本人はインドでは非常に好感を持って受け容れられているので、日本という国籍をちらつかせるだけで女の子が寄って来ると言っても過言ではないだろう(もちろん、とんでもないのが)。しかし、恋仲になったり結婚したりするケースは、そこまで多くないし、困難が伴うことは容易に想像できる。やはりこの要因も、インド人女性側の文化的制約の厳しさが関係している。
しかし、デリーに長く住んでいると、インド人女性と付き合ったり、結婚したりした日本人男性にも出会う。そういう人にインタビューをすることにより、何となくインド人の恋愛観が見えてくる(自分で試さないのがずるいところだが)。依然として謎の部分が多いのだが、1年前、2年前に比べたら何となく分かってきたような気がする。
インド人女性の恋愛観を語る際、一番重要なのは「結婚と恋愛は別」という鉄則だ。恋愛結婚が増えて来たとはいえ、インド映画で繰り返し苦難を乗り越えた恋愛結婚が描かれているとはいえ、未だに主流はお見合い結婚である。だから、恋人がいたとしても、親が結婚相手を決めたら、恋人と関係を切って親に従うというケースが非常に多い。だから自然と恋愛も一時的なものになる。また、恋愛に対する罪悪感も多いようだ。
婚前交渉の可否については、不明な点も多いのだが、総合的に判断すると、「困難」という結論に達せざるをえない。ある日本人男性は、インド人女性と2年間付き合ったが、「キスもしてない」とのこと。またあるアメリカ人男性によると、インド人女性と1年間付き合ったそうだが、「何もできなかった」とのこと。しかし、別の情報筋によると、あるエチオピア人男性は、パンジャーブ出身のインド人女子学生と会ったその日にベッドインしたという。全く訳が分からない。しかし、インド人女性と結婚したある日本人男性によると、インド人女性は結婚につながる恋愛を「生きるか死ぬか」のラインで考えているようで、生半可な気持ちでインド人女性と付き合うことはできないと言っていた。つまり、インド人女性は恋愛と結婚を別にして考えており、結婚のない恋愛は肉体関係を伴わない純粋な「友達」としての仲で、結婚につながる恋愛は、命を懸けるほど真剣な人生の一大事と捉えていると言っていいだろう。日本の恋愛の感覚でインド人女性と付き合うと、プラトニックな恋愛のまま時間が過ぎてしまうか、結婚しないと自殺されるか、どちらかになってしまう恐れがある。
「結婚と恋愛は別」というインドの鉄則は、結婚後の不倫を増加させる要因にもなる。実はインドは非常に不倫の多い国である。恋愛は恋愛で恋人との関係をそのまま続けて、結婚は結婚で夫と結婚生活を送るという女性がけっこう多いようだ。結婚後に新たな恋人を作ることも怠らないだろう。あれだけ結婚前の女性が制約される文化でありながら、結婚後はノータッチというのも理解に苦しむ。女性が家にこもりっきりであることが多いのがひとつの要因になっているのかもしれない。インド神話の永遠の恋人、クリシュナとラーダーも実は不倫関係であるが、それも何か関係しているのではないかと思っている。また、これは男性のみだろうが、なぜか結婚後の不倫について日本ほど社会の目は厳しくない(女性については不公平なほど厳しいかもしれない)。JNUの大学教授にも、奥さんがいるのに愛人と同棲していたりする人もいるようだが、特に何のお咎めもなかったりするし、それがその人の権威を失墜させることも全くない。ヴァージペーイー首相は独身ということになっているが、彼にも愛人はおり、公然の秘密となっている。だが、それが政治的スキャンダルにならないのが、日本人には不思議なところだ。クリントン元大統領もビックリだろう。
上で「インド人女性」と何の定義もなく使ってきたが、これはつまりアーリヤ系インド人のことである。同じインド人でも、ノース・イーストの女性になると、恋愛観は一変する。あちらは女性上位社会の傾向が強く、妻問婚の風習があったりするため、基本的にフリー・セックスの風潮が根強い。だから、とりあえず肉体関係をもって、それから付き合うかどうか決める、という態度の女性が多いようだ(まさに妻問婚)。これはノース・イーストの女性と付き合っている日本人男性の証言から推測された。
一般的な認識として、大都市ほど恋愛がオープンで性が乱れていると言われるが、デリーに関してはそう一概にも言えないかもしれないと最近感じている。確かに田舎に比べたらデリーには派手な格好をしている女の子が多い。しかし一方で、インドでは上流階級になるほど戒律が厳しくなるという傾向もある。よく、高級ホテルのディスコで「上流階級の子女が踊っている」みたいなことが言われるが、ああいうところにいるのはどうも成金中産階級のお坊ちゃま、お嬢様で、本当の上流階級の子女はかなり厳しく育てられているように見える。ノース・イースト系の若者もディスコに多い。つまりデリーで夜遊びしているのは、外国人か、ノース・イーストの若者か、小金持ちのインド人か、である。もし上流階級の大富豪インド人が派手に道楽しようと決意したなら、インドにはいないだろう。アメリカかヨーロッパにいってブイブイ言わす方が早い。デリーは大都市だが、案外保守的な家庭、女性が多いと言ってよい。
デリー大学(DU)とジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)の女子学生の比較も面白い。DUは学部生が多いので、18歳ぐらいの女の子からいることになる。だから全体的に非常にキャピキャピした雰囲気で、派手な格好をしている人も多い。しかしDUの学生はデリー出身であることが多く、つまり自宅生が多いので、案外放課後は厳しく監視されていて、思うように恋人とデートしたりすることができない状況に置かれている。一方、JNUは基本的に大学院大学なので、21、2歳が下限ということになる(ただ、外国語学部には学士コースもあるため、若い女の子もいる)。教養も高く、全体的にアカデミックな雰囲気で満ちている。地方から上京して来ている人が多く、ほとんど全員寮住まいである。つまり、親元から離れている人がほとんどだ。だから、恋愛も思うのまま、ということになる。インド人の女の子が平気で男子学生の部屋で一夜を過ごしたりするので、けっこうビックリする(ただ添い寝しているだけとの説もある)。結論として、DUの女子学生は見た目は派手だが、実は恋愛には制約があり、JNUの女子学生は見た目は地味だが、一度恋愛の道にはまり込むと行き着くところまで行ってしまう暴走特急的志向がある。
特に結論はないのだが、敢えて結論を述べるとしたら、インド人女性と付き合いたかったら、ノース・イーストの女性が一番楽だ、ということだ。しかしあちらの人はどちらかというと東南アジア人に近く、インド人と恋愛をしている気分ではないだろう。JNUは、DUに比べればインド人と恋愛するのにいい場所かもしれない。しかし、インド人はしたたかな人が多いので、「日本人」であることを目当てに寄ってたかってくる連中が非常に多い。その中から本当に自分のことを純粋な恋愛対象として見てくれる人を探すのはけっこう難しいかもしれない。また、考え方の差、食文化の差、経済の差などのギャップを埋めることが必要になるが、その際、文化的制約の少ない日本人の方が我慢を強いられることが多くなるのにも注意しなければならない。
突然何の前触れもなく、PVRアヌパムで「Anaahat」というマラーティー語映画が上映され始めた。PVRでは時々インドの他言語の映画も上映される。今までの経験から言うと、ヒンディー語映画圏と他のインド映画圏との間に横たわる高い壁を乗り越えて入ってくる映画は、十中八九面白い。しかもポスターを見てみると時代劇のようだ。今年度のインド国際映画祭でも上映されている。今日は暇を見つけてその映画を見に行った。
「Anaahat」とは「無傷」「無垢」という意味。英語のサブタイトルは「Eternity」。主演はアナント・ナーグ、ディープティー・ナーヴァル、ソーナーリー・ベーンドレー。ベテラン俳優2人と、ヒンディー語映画でおなじみの女優が出演していて、キャストだけでも期待がもてる。監督はアモール・パーレーカル。言語はマラーティー語なので、英語字幕が付いてた。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
アナント・ナーグ(上)と
ソーナーリー・ベーンドレー(下) |
● |
| Anaahat |
紀元前10世紀、マッラ朝の王都シュラヴァスティー。マッラ王(アナント・ナーグ)と王女シーラヴァティー(ソーナーリー・ベーンドレー)はお互い愛し合い、幸せに暮らしていた。しかし彼らにはひとつだけ問題があった。後継者である。マッラ王はインポテンツのため、子供を作ることができなかった。元老院は王家の跡継ぎを授かるため、ニヨーグの儀式を執り行うことを決めた。
ニヨーグとは、不能者の王を持つ王女が行う儀式で、王女が人民の中から一人男を選び、一晩だけその男と交わり、子供を作る行為だった。ニヨーグは3回に渡って行われることになっていた。マッラ王は愛する妻が他の男と一夜を共にすること、自分が不能であること、妻を苦しい立場に追い込んでいることなどに心を痛め、平静を失う。シーラヴァティーも侍女長のマハートリッカー(ディープティー・ナーヴァル)に怒りと悲しみを打ち明けて反発するが、元老院の決定は絶対であった。
ニヨーグの儀式の日が来た。マッラ王はシーラヴァティーに花輪を渡す。これは、王女が花輪をかけた男と一晩共にする権限を与えることを意味する。シーラヴァティーはニヨーグを行う。
次の日、宮廷にはぼんやりと虚空を見つめて立つシーラヴァティーがいた。マハートリッカーが話しかけると、シーラヴァティーは昨夜起こったことを話す。「男がこれほどのものを私に与えてくれるとは。私の身体がこれほどの快楽をもたらしてくれるとは。私は初めて女であることを知りました。」王女は性の快楽に目覚めてしまったのだった。マハートリッカーは「女性が性の快楽を口に出すものではありません」と戒めるが、王女は昨夜の感動を話し続けた。そして1週間後に再びニヨーグの儀式を行うよう、命令を出す。それを知ったマッラ王は激怒する。二人の仲は険悪になるが、シーラヴァティーはマッラ王に「あなたはあなたができること以上の幸せを私に与えてくれた」と言って、二人は仲直りする。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
ただのインド神話風時代劇だと思っていたので、こういう展開にはなると思っていなかった。意表を突かれてなかなか面白い映画だった。しかし最後はあまりに急ぎすぎで、なぜ二人が仲直りしたのかよく理解できなかった。性の快楽に目覚めた王女が、夜な夜なニヨーグを繰り返すという展開だったら、もっと面白かったのだが。
紀元前10世紀のインドが舞台なので、登場人物も風景も全て古代インドをイメージしたものになっている。ロケ地はカルナータカ州にある遺跡の町ハンピ。ハンピで撮影された時代劇映画といえば、「Agnivarsha」(2002年)が思い浮かぶが、あの映画よりも「Anaahat」の方が雰囲気がよく出ていた。
ニヨーグという儀式はヴェーダ時代に本当に行われていたようだ。やはり王朝にとって跡継ぎというのは大きな問題だったようで、それに対処するためにいろいろな方法が古代から考案されてきたのだろう。そういえば古代インドにはアシュヴァメーダ(馬祀祭)という儀式もあった。王が馬を1年間放して、その馬が通った土地が王の領土になるという、王権を誇示する儀式だ。1年後、その馬が帰って来ると、馬は生贄にされて殺され、その後なぜか王女がその馬の死骸と一晩床を共にするらしい。今から考えるとよく分からない儀式だが、これも跡継ぎと何か関係あるのだろうか・・・。
俳優陣はベテラン揃いだったので文句のつけようがない。ソーナーリー・ベーンドレーは久しぶりにスクリーンで見たような気がする。ニヨーグを無理矢理させられて戸惑う「ニヨーグ前の清純なシーラヴァティー」と、男を知り、女の快楽を知った「ニヨーグ後の覚醒したシーラヴァティー」の表情が全然違って、それだけで彼女が優れた役者であることが知れた。ちなみにソーナーリーの(インド映画にしてはかなり際どい)入浴シーンが見られる。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
ソーナーリーの入浴シーン |
● |
原作はスレーンドラ・ヴァルマーのヒンディー語舞台劇「Surya Ki Antim Kiran Se Surya Ki Pehli Kiran Tak(日没から日の出まで)」。王女が見知らぬ男と日没から日の出まで共に過ごさなければならないニヨーグの掟をそのまま題名にしたようだ。映画の題名「Anaahat(無垢)」は、物語の最後のシーラヴァティーの独白の中に出てくる単語である。
| ◆ |
11月18日(火) Waisa Bhi Hota Hai Part II |
◆ |
変な映画が上映され始めた。「Waisa Bhi Hota Hai Part II(そういうふうにもなっている:パート2)」。題名を正確に表記するなら、「Aisa Waisa Bhi Hota Hai Part II Ye Part 2 Kyu Hai?(こういうそういうふうにもなっている:パート2:このパート2ってのはなぜ?)」。この映画のパート1は今まで上映されておらず、いきなりパート2で始まっている。題名だけでもこの映画の変さが分かるだろう。映画のポスターはハードボイルドなアメコミ・タッチで、一人の男が「オレはお前の兄を殺した」とセリフをしゃべっており、もう一人の男が「オレのガールフレンドは警察だ」と言っている。そのそばで警察の制服を着た女性が立っている。全くどういう映画なのか読めない。チャーナキャーに深夜の回を見に行った。
キャストはアルシャド・ワルスィー、サンディヤー・ムリドゥル、プラシャーント・ナーラーヤン、プラティマー・カズィマー、アーナンド・ジョーグ。監督はシャーシャンカー・ゴーシュ。テレビで活躍している俳優・スタッフが多い。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
Waisa Bhi Hota Hai Part II |
● |
| Waisa Bhi Hota Hai Part II |
ムンバイーの広告代理店に勤務するプニート(アルシャド・ワルスィー)は警察官のガールフレンド、アグニ(サンディヤー・ムリドゥル)と暮らしていた。実はプニートの兄パルヴィーンはマフィアだったのだが、プニートはそれを隠していた。兄とは長年音信不通になっていたが、ある日パルヴィーンが殺されたことが分かり、プニートは初めてアグニに兄のことを打ち明ける。アグニは今まで兄の存在を黙っていたことに怒り、彼を家から追い出す。
酔っ払って外のベンチで眠っていると、そばで一人の男が数人の男に銃撃され始めた。プニートは訳が分からないまま血まみれの男を助け、病院に運ぶ。その男の名はヴィシュヌ(プラシャーント・ナーラーヤン)。凄腕の殺し屋だった。ヴィシュヌはプニートに恩を感じ、彼を自宅に住まわせた。プニートとヴィシュヌは全く違う仕事をしていたが、妙に気が合って、やがて固い友情で結ばれる。ヴィシュヌはマフィアの大ボス、ガンパト(アーナンド・ジョーグ)にプニートを引き合わせる。
ガンパトにはガングー・ターイー(プラティマー・カズィマー)という敵対しているマフィアがいた。ガングーこそがヴィシュヌに刺客を送り込んだ張本人だった。ガングーはヴィシュヌと共にいるプニートが、パルヴィーンの弟であることを突き止める。実はパルヴィーンを殺したのはヴィシュヌだった。ガンパトの組織内部で内輪もめを引き起こすため、ガングーはガンパトにその情報を垂れ込む。ガンパトはヴィシュヌに、プニートを殺すよう指示するが、ヴィシュヌは拒否する。ガンパトの別の部下がプニートを銃撃するが、ヴィシュヌは彼を助けた。しかしプニートはガングーの部下にさらわれてしまう。
ガングーはプニートをなぜか気に入り、ガンパトの刺客から彼を守るため、自分のアジトに軟禁する。一度プニートは仕事を理由に外出を許可されるが、そのときアグニがガングーの逮捕状を持って乗り込んできて、ガングーを連れて行った。ガングーはすぐに釈放されるが、今度はガングーがアグニを誘拐し、アジトに引き連れてくる。そこへプニートが帰って来て、アグニを助けて脱出を図るが、プニートは逃げ遅れてしまう。仕方なくプニートは庭に停まっていた自動車のトランクの中に身を隠す。
脱出に成功したアグニは、次の日警官を引き連れてガングーのアジトを襲撃する。しかしアグニの一瞬の隙をついてガングーは彼女を人質にとって、自動車で逃走する。その自動車のトランクにはプニートが隠れていた。
一方、ヴィシュヌはガンパトと決別を決意し、彼の金を持って逃走していた。そこへちょうどガングーの乗った自動車がやって来たため、彼は運転手を撃ち殺すが、ヴィシュヌはガングーに撃たれてしまう。その隙にアグニはガングーを撃ち殺し、トランクの中にいたプニートを助け出す。ヴィシュヌはプニートの目の前で息を引き取る。プニートとアグニは、ヴィシュヌが持っていた大金を手に入れ、夢だったナイニータール生活が一気に現実のものとなった。
ところで、ガンパトは、映画女優とベッドを共にするために単身ホテルを訪れていたが、そこでマヒマー・チャウドリーと偶然会って、絡んでいた。そこへスィク教徒の旅行者たちがやって来て彼女を救出した。こうしてガンパトはスィク教徒たちに無理矢理連れられてパンジャーブまで自動車で行くことになってしまった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
マフィア抗争の映画だったにも関わらず、ドロドロしておらず、コメディー・タッチでさえあった。「A Not-Normal Urban Film」という宣伝文句通りの新感覚の映画で、けっこう楽しかった。ストーリーは複雑だったが、最後はうまくまとまっていた。
まずは「Waisa Bhi Hota Hai Part I」が始まる。断片的な映像ばかりでよく分からない。しかしこれらの映像全てが物語の伏線となっている。「〜Part I」は10分もしない内に終了する。次に「Waisa Bhi Hota Hai Part II」が始まる。ストーリーは上の通りだから詳しくは書かない。最後に「Waisa
Bhi Hota Hai Part III」が流れるが、これはオマケみたいなものだ。プニートとアグニが大金を手にし、ガンパトがスィク教徒に連れられてパンジャーブへ行くシーンが映されるだけでエンド・クレジットになる。
プニートとアグニの友情は映画の核で、マフィア映画での常套手段だ。ギャングのボスと部下の友情が描かれた「Company」(2002年)、ギャングのボスと、その旧友(実は警官)との友情が描かれた「Footpath」(2003年)などが思い浮かぶ。ひょんなことから殺し屋の命を助けたことから、プニートとヴィシュヌの友情が始まる。プニートは、ヴィシュヌたちマフィアと会って話す内に、マフィアといってもみんないい奴ばかりであることに気付く。プニートが、パルヴィーンの弟であることを知った後でも、ヴィシュヌはプニートへの友情を曲げなかった。まずはプニートに銃を渡し、「オレがお前の兄を殺した。オレを撃て」と言う。しかしプニートは拒否する。「兄はマフィアをしていたから、殺されるのも運命だった。もし兄が軍隊にいて、パーキスターンとの戦争で殺されたら、オレはパーキスターン人全員を銃で殺すのか?」こうしてヴィシュヌはプニートが、彼を殺すためにわざと組織に潜入したのではないことを確信する。プニートの考え方は非常にインド的で、僕は感心した。まさに「バグヴァド・ギーター」でクリシュナがアルジュンに説いていること通りだ。命を危険にさらす職業に就いているなら、死ぬのも仕事の内である。日本人にはこの感覚が希薄だ。自衛隊に入っているなら、死ぬのも仕事の内であるはず。自衛隊イラク派遣問題において、その是非はともかくとして、自衛隊の隊員に犠牲が出るとか出ないとか云々の議論は焦点が間違っていると思う。
ガングー・ターイーはこの映画の中でもっともキャラクターが際立っていた。ヴィシュヌ暗殺に失敗した部下たちに言う。「日本のマフィアのこと知ってるか?」いきなり日本が出てきたので何かと思ったら、ヤクザが指を切ることを言っているらしい。こうして暗殺に失敗した責任を取らされ、一人の部下が指が切られる。「日本のマフィアみたいにきれいに布に包んで、切り取った指を私のとこに持って来な!」ガングーの館にその指を見てガングーは叫ぶ。「どの指を切ったんだい!これじゃあ銃を撃てないだろ!」こうして可哀想に指を切り取られた部下の名前は以後「ウングリー(指)」となった。ガングーがプニートを「私に息子がいたら、あんたみたいだったろうよ。私のこと、お母さんって呼びな」と言ってかわいがるところも面白い。
マヒマー・チャウドリーが本人役で特別出演していたのには驚いた。確か「Baghban」でも特別出演していたような・・・。彼女は最近落ち目なので、こんな形でしかスクリーンに登場できないのか、と思ってしまう。
インド映画にしては脚本が非常にしっかりできていた映画だった。というより、キャラクターを設定したら、自然とその登場人物たちが動き出してストーリーを作ってしまったような映画と表現したらいいだろうか。観客の受けもよかったので、少々ヒットしてもおかしくはない。
1998年に日本で公開された「ムトゥ 踊るマハラジャ」は、日本で空前のインド映画ブームを巻き起こした。しかしブームは所詮ブームでしかなく、その後急速にインド映画人気は廃れ、また配給に関する不幸なトラブルも原因となり、インド映画は「マニアの映画」という元の鞘に納まってしまった。インド映画をキワモノと捉える見方はもはや日本で支配的と言っても過言ではないだろう。もしかしたら日本のインド学者の中にすら、そう考えている人がいるかもしれない。
実は僕が初めて見たインド映画も「ムトゥ」だった。元々インドに興味があったが、あの映画を見てから強烈に「インドに行きたい」という衝動に駆られ、インド旅行を実現した後には、勢いでヒンディー語を学び始め、やがてはインド留学ということになってしまった。あまり認めたくはないのだが、「ムトゥ」は僕の人生を変えた映画ということになるだろう。
ヒンディー語を学習し、研究対象にもしようと思ったときに、ヒンディー語に対して2つの期待があった。1つは、ヒンディー語は世界第3位の話者人口を誇っており、ほとんど誰もしゃべっていないような小言語を習得するのに比べたら実用性があること、もう1つは、ヒンディー語映画をより楽しむことができるようになることだ。メジャーなのにマイナーというその微妙な立場も、天邪鬼な僕の性格を刺激した。
あれから数年の歳月が過ぎ、ヒンディー語映画を字幕なしでも80%くらいは理解できるようになった。日常会話も支障がないし、最近は田舎からやって来たインド人と話す機会にも恵まれて、ヒンディー語の方言にもけっこう耳が慣れてきた。インド文学からもかなり得るもの感じるものがあり、インドへの愛は深まるばかりだ。また、インド国内の非ヒンディー語圏や、南アジア諸国の人々にもヒンディー語を理解する人が多いのを知り、ヒンディー語理解者人口は統計値以上に相当数いるのでは、という漠然とした期待も出てきた。他人にヒンディー語を学ぶことを勧める自信はないが、個人的にはヒンディー語を習得できて非常によかったと心底思っている。
当初、ヒンディー語映画を楽しむことは、ヒンディー語習得の副産物でしかなかった。当時は依然としてインド映画というと「歌って踊って」というイメージが強く、暇つぶしの娯楽くらいにはなるだろう、ぐらいに考えていた。しかし、最近ヒンディー語映画をもっと真剣な眼差しで見るようになって来た。
まず、インド映画の国際性が明らかになったことが、非常に僕に感銘を与えた。デリーには各国からの留学生が来ているため、彼らと話す機会がけっこうあるのだが、ほとんど全ての国の人とインド映画やインド映画の俳優の話題で盛り上がれることに驚いた。彼らの国ではヒンディー語映画がかなり人気のようだ。僕自身も実際に旅行した国々で、インド映画が上映されていたり、テレビやビデオで視聴可能だったりするのを体験していた。思い出せる限りのヒンディー語映画流通国を挙げてみると、フィジー、中国、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、バングラデシュ、ブータン、スリランカ、ネパール、パーキスターン、アフガニスタン、イラン、ドゥバイ、モーリシャス、モルディヴ、ロシア、ウクライナ、タジキスタン、カザフスタン、エチオピア、エジプト、トリニダード・トバゴ、赤道ギアナ、スリナム、アメリカ、イギリスなどなどである。ヒンディー語の国際性はともかくとして、ヒンディー語映画の国際性は相当なものであると言わざるをえない。ハリウッド映画はアメリカ文化を洗脳させようと世界中に意図的、積極的にばら撒かれているが、インド映画の場合は、民衆のもっと自然な要望に後押されて広まっているように思われる。僕はこの流れを「ハリウッド映画は上から世界を覆い、ボリウッド映画は下から世界を満たす」と表現したい。かえって日本がその「世界の潮流」から取り残されているだけだ。これは「クリケットはマイナーなスポーツ」と思っている日本人が多いことにも似ている。野球の方がマイナーなんですが・・・。日本におけるアメリカ文化の洗脳はいつ解けるのだろうか、最近心配である。
インド映画の国際性と同様に、最近重要だと思うようになってきたのは、ヒンディー語映画で話されるヒンディー語の標準語性、公用語性である。インドは多言語国家の宿命を背負い、言語が大きな問題となっている。日本国憲法の中に言語に関する規定がどこにもないことからも、日本人がいかに言語問題から自由でいられたかが推し量られる。インドでは日本のように言語に無関心でのほほんとはしていられなかった。ヒンディー語とウルドゥー語の争いが、インドとパーキスターンの分離独立の原因となったと言っても過言ではないし、公用語の問題が北インドと南インドの対立を煽ったと言っても過言ではない。その中で、「ヒンディー語とはなんぞや?」という根本的な問いが成される。この問いは「いったいインドの公用語としての『ヒンディー語』とやらを話している人が、インドにいるのか?」という深い疑念を含む。確かに現在「ヒンディー語」と呼ばれている言語の内部には、多くの方言を含む。10年ごとに行われる国勢調査では、ヒンディー語は約50の方言に分割されている。これらの方言の間では、意思疎通が困難なくらいの違いがある。これらをひっくるめて「ヒンディー語」と称するのは果たして正しいのだろうか?また、ヒンディー語とウルドゥー語はひとつの言語なのか、別の言語なのか、も未だに議論され、多くの誤解を招いている。さらに、学校などで教えられている「標準ヒンディー語」はサンスクリト語の難解な語彙で溢れ、民衆の言語とはかけ離れた、まるで「砂利石を詰め込んだ枕」のような言語になってしまっている。この状況はウルドゥー語でも同じで、こちらにも難解なアラビア語、ペルシア語の語彙が詰め込まれ、まるで「厚化粧をしたスッピン美人」のような言語になってしまっている。どちらも国語、公用語と呼ぶにはあまりに愛着の沸かない言語だ。ヒンディー語とは実は実態が不明の言語なのだ。
だが、一方で、インド各地を旅行すれば、インド全土でほとんど通じる「公用語」にあたる言語がインドには存在することが分かる。それは決して英語ではない。外国人観光客がたくさん来るようなところだけを旅行していれば、インドのどこでも英語が通じるように思ってしまうが、実態はそうではない。英語の単語が積極的に取り込まれていることは確かだが、ベースはあくまでもインドの土着の言語である。その「公用語」に敢えて名前を与えようとすれば、やはり「ヒンディー語」ということになる。または、それを意図的に「ヒンドゥスターニー語」と呼ぶ人もいる。とにかく、ヒンディー語がある種の公用語性を既に持っていることは、明らかである。
この「公用語」は、何百年もの間、インド亜大陸全土を往来して来た商人、吟遊詩人、巡礼者、大道芸人、サードゥたちの小さな小さな積み重ねの上に自然と完成した共通理解言語である。この言語に名前を付けようとした人物は歴史上に何人か存在するが、彼らは現代的センスで名付けをしたわけではなく、ただ単にサンスクリト語やペルシア語などの教養語の対極に位置する、民衆の「国の言葉」と言いたかっただけだ。「国の言葉」と言った場合、それはインド全土で遍く話されていた言語全体を漠然と指すものである。元々インド人にとって日常語の名称というのはあまり重要ではなかったと言える。それに必要以上の価値付けをしたのは、イギリス人だ。イギリス人がインドの言語の分類を始めたときから、インドで言語問題が発生したと言っても過言ではないだろう。人間というのは、名称が違えば実態も違うと思ってしまう習性を持っている。
とにかく、現代のインドは、意図的にか無意識にか、外部からの支配者によって多言語国家にされてしまった。こうなってしまった以上、インドを多言語国家として捉えていくより他はないだろう。しかし、そのバラバラになったインドの言語をひとつにまとめる可能性を持ったメディアがある。ヒンディー語映画だ。ヒンディー語映画で使用されている言語は、ムンバイヤー・ヒンディー(ムンバイーのヒンディー語)とも言われるが、非常に公用語性の強いヒンディー語となっている。つまり、インドのどの地域の人でも理解できるような語彙が使用されており、日常語化した英語語彙の使用も積極的に成されている。例えヒンディー語を話せなくても、理解はできる、という人はインドに多い。これはヒンディー語映画の影響だろう。「ヒンディー語とはなんぞや?」という問いには「ヒンディー語映画で話されているヒンディー語こそ、ヒンディー語のあるべき姿である」と答えるのがもっとも妥当だと思われる。かつてマハートマー・ガーンディーが提唱した独立インドの国語「ヒンドゥスターニー語」に最も近い形が、ヒンディー語映画の中で見られる。インド映画には、民衆の怒りや憂いがそのまま投影されることも非常に重要である。
ヒンディー語映画はただの大衆娯楽ではなく、ヒンディー語とインドの未来を背負った重要なメディアであることが分かってもらえただろうか?決してマニアのための映画ではないのだ。ヒンディー語映画のファンは、言わば、ヒンディー語とインドの未来を見据え、大衆の不満を察知し、統一インドのために戦う憂国の志士と言っていいだろう。いや、ただのファンか。
今日の日記を書いているときに、何となくヒマーチャル・プラデーシュ州のダラムシャーラーで泊まった宿のことが思い出されてきた。ダラムシャーラーは言わずと知れたチベット難民の町であり、ダライ・ラマのお膝元である。その宿のレストランではテクノやトランス化したチベット音楽が毎日流されていた。別に悪くはなかった。だが、僕は部屋ではヒンディー語映画の音楽を自分のPCで聞いていた。あるとき宿の主人のチベット人が僕の部屋にやって来て言った。「君はインド映画の音楽が好きなのか?」僕は「そうだ」と答えた。すると彼は目を輝かせて言った。「僕もインド映画が好きなんだよ。いくつかカセット交換しないか?」残念ながら僕は音楽を全てMP3に変換してPCに入れているので、それはできなかった。僕が「チベット人だからチベット音楽の方が好きなんじゃないの?レストランでも流れてたし」と質問すると、「あれは観光客のために流してるだけさ。僕はインド映画音楽の方が好きだな」と答えた。彼はインドで生まれたチベット難民だった。チベット難民の心にもヒンディー語映画が浸透していることが、なぜか無性に嬉しかったのを覚えている。なぜ僕が嬉しくなるのか分からないが・・・。
今日はチャーナキャーに新作映画「Out Of Control」を見に行った。題名は英語だが、基本的にヒンディー語映画。
プロデューサーは「Cooli No.1」や「Mujhe Kucch Kehna Hai」のヴァシュ・バグナーニー。監督はラーマージト・ジュネージャーとアプールヴァー・アシュラーニー。キャストはリテーシュ・デーシュムク、ブレンダ・ロドリック、アムリーシュ・プリー、リシター・バット、サティーシュ・カウシク、サティーシュ・シャーなど。主役のリテーシュ・デーシュムクは、マハーラーシュトラ州のヴィラースラーオ・デーシュムク前知事の息子で、「Tujhe Meri Kasam」(2002年)でデビューした。映画のヒロイン、ブレンダ・ロドリックはプレイボーイ詩などのグラビア・アイドルのようだ。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
左からブレンダ・ロドリック、
リテーシュ・デーシュムク、
リシター・バット |
● |
| Out Of Control |
パンジャーブからニューヨークへ一攫千金を夢見てやって来た若者ジャスヴィンダル(リテーシュ・デーシュムク)は、新聞配達、タクシー・ドライバー、ガソリン・スタンドの店員などの仕事をしながら地道に生活をしていた。親友のマンゴー(サティーシュ・カウシク)に連れられてたまたま入ったナイトクラブで、ジャスヴィンダルはサリー(ブレンダ・ロドリック)という白人女性と知り合いになる。サリーはヒンディー語映画ファンで、ヒンディー語をしゃべることができた。ジャスヴィンダルとサリーは一気に仲良くなり、恋人関係になる。
ところが、ジャスヴィンダルのヴィザが切れてしまい、移民手続きも認められず、インドへ帰らないといけなくなった。それをサリーに打ち明けると、サリーは「私と結婚しましょう」と言う。こうしてジャスヴィンダルとサリーは結婚し、彼はアメリカに移民することができた。
ある日突然、ジャスヴィンダルの元にパンジャーブから電話があり、父親が重病だと告げられる。ジャスヴィンダルは急遽パンジャーブへ帰ることになる。
だが、父親ジャッター・スィン・ベーディー(アムリーシュ・プリー)の病気は、ジャスヴィンダルを呼び戻すための仮病だった。田舎に戻ったジャスヴィンダルは妹と共に強制的に結婚させられてしまう。ジャスヴィンダルは妹の結婚式が関係していたこともあり、サリーのことを父親に言い出せなかった。結婚式後、彼は新妻のリーチャー(リシター・バット)を残して一人ニューヨークへ戻る。
ジャスヴィンダルは、サリーにもそのことを言い出せず、悶々とした日々を過ごす。そこへ突然、ジャッター・スィンとリーチャーがニューヨークへやって来た。ジャスヴィンダルは、サリーとリーチャーを引き合わせないようにして何とかやり過ごしていたが限界があった。遂にサリーとリーチャーの共通の知り合いでオカマのフラワー(サティーシュ・シャー)によって事実が明らかになってしまう。サリーは激怒し、ジャスヴィンダルを訴える。リーチャーも失望してインドへ帰る。
ジャスヴィンダルは二重結婚と、永住権獲得のための詐欺結婚の2つの罪で起訴された。しかし、サリーは、彼のことが心配で戻ってきたリーチャーを見て訴えを取り下げる。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
見るだけで全身が気だるくなるような駄作。「Out of question」だ。グラビア・アイドルのブレンダ・ロドリックの刺激的な肢体がなかったら、全く何の取り得もない映画で終わっていただろう。
前半は特に退屈。アメリカン・ドリームを夢見てパンジャーブの片田舎から単身ニューヨークへやって来たインド人の若者ジャスヴィンダル(アメリカではジミーと名乗っている)。新聞配達、タクシー・ドライバー、ガソリン・スタンドの店員などをやっている様は非常に現実的だった。しかし、そんなうだつの上がらない出稼ぎインド人が、どうやって白人の女性と恋仲になり、挙句の果てに結婚できてしまうのだ?しかもその女性がヒンディー語映画ファンで、ヒンディー語がしゃべれて、おまけにプレイボーイ誌を飾るような美しくセクシーな女性なんてことは、天地がひっくり返っても絶対にありえない。・・・絶対に、と言うのは言いすぎだとしても、この映画のような事態が発生する確率は天文学的に少ない確率だろう。インド人の荒唐無稽な誇大妄想映画と言わざるを得ない。単純思考のインド人がこの映画を見たら、間違った夢や希望を植えつけられてしまう恐れがある。
インターミッションを挟み、後半になると少しは面白くなる。パンジャーブでリーチャーと結婚してしまったジャスヴィンダル。ニューヨークへ戻ったものの、以前のように落ち着いて仕事ができない。そこへ父親とリーチャーが突然訪問して来る。リーチャーにはサリーを隠し、サリーにはリーチャーを隠して、なんとかばれないようにあたふたする様は、あまりに陳腐なコメディーだが、それでもいくつか笑えるシーンがある。
最後は裁判になるのだが、あまりに呆気ない解決のされ方で呆気にとられる。アメリカの裁判でこんな簡単に決着が付くとは思えない。最初から最後まで浮世離れした内容の映画だった。
映画中、ひとつだけ気になるセリフがあった。ナイトクラブで際どい格好をして歌を歌うサリー。それをかぶりつき席で見ていた下品なアメリカ人の酔っ払いが、サリーに絡み出した。それを見たジャスヴィンダルは、「少なくとも自分の国の女には尊敬を払え!」と言ってそのアメリカ人に殴りかかる。このセリフ、この発想、あまり日本にはないような気がする。日本人男性は日本人女性に対して、他国の女性に比べて多くの尊敬と気遣いをしているかと言われれば、全くそんなことはないし、そういう発想すらないだろう。インド人にとってまず重要なのは同族の女性で、それ以外の女性にはとりあえず何をしてもいいということだろうか。何となく騎馬民族っぽい考えに思えた。そういえば、インドでは女性の露出度などに対する規制がインド人と外国人では違う。この映画でも多くの白人が際どい格好をして踊っていたが、同じことをインド人女性がやったら検閲で引っかかるのは必至だろう(パンチラ・シーンもあったような・・・)。また、テレビでもハリウッド映画などの白人同士のキス・シーンはほとんど垂れ流し状態だが、インド人同士のキス・シーンにはまだまだ規制が強い。アダルト・ビデオでも、白人モノは割と規制が甘く、簡単に手に入るが、インド人モノは厳しく規制されており、あまり流通していない。これも自国の女性の尊厳を保護し、彼女たちに尊敬を払っているということだろうか。
この映画はブレンダ・ロドリックを楽しむ以外の目的で鑑賞する価値が全くない。けっこう拡大公開されており、インドではエロい映画が思わぬヒットを飛ばすことがあるため、この映画もロングランする可能性がないでもないが、僕にとってはこの映画は時間と金の無駄に過ぎなかった。
インドではディーワーリーのある11月前後から結婚式シーズンに突入する。ヒンドゥー暦では結婚式を挙げていい月と、挙げてはいけない月が決まっており、また吉日も星の運行によって決められているので、結婚式は自ずと短期間に集中するようになる。ある星占い師によると、今年は10月6日まで結婚に適した日が全くなかったと言う。今年の結婚最適期間は10月17日〜12月9日までで、特に11月27日が今年最高の結婚日和らしい。と言うわけで、11月27日にはデリーだけで1万2千組の結婚式が行われる予定というから、いったいどうなることやら・・・。しかもその日はイスラーム教最大の祭りイードと重なる可能性がある。
結婚式がこの季節にこぞって行われるのは、農業と無関係ではないだろう。冬は農閑期に当たるため、祭りや結婚式が集中的に行われる。また、この時期は天然のクーラーになるため(というか寒いため)、屋外でいろいろ催し物をするのにちょうどいい。
今週の木曜日にも、去年まで通っていたケーンドリーヤ・ヒンディー・サンスターンの恩師の娘の結婚式があり、顔を出した。南デリーのさらに南には、ファームハウスと呼ばれるイベント会場のような広場がひしめき合っている地域があり、結婚式シーズンには無数にあるファームハウスで夜な夜な盛大な結婚式が行われる。その結婚式もヴァサント・クンジのあるファームハウスで行われていた。夜8時頃、バイクで迷い迷い会場まで乗り込んだ。ヴァサント・クンジでもあちこちで結婚式が行われており、会場に向かう自動車で大渋滞となっていた。しかもまるでお互いに派手さを競い合っているかのごとく、あっちで花火が上がったり、こっちで大音響のパンジャービー音楽が鳴り響いたりと、騒然となっていた。
インドの結婚式というと、誰でも最初はワクワクするものだ。僕も最初に参加した結婚式ではけっこう気合が入っており、ダンス・フロアで踊ったり、新郎新婦と写真を撮ったりと、結婚式が終わる深夜まで楽しんだ。2回目の結婚式はラージャスターンの田舎の結婚式だったこともあり、これはこれでまた楽しめた。しかし3回目、4回目となってくると、だんだん退屈になり、終いには行くのも面倒になる。また、盛大な結婚パレードは、深刻な渋滞を引き起こすため、インドの結婚式にはイライラさせられることがほとんどになる。インド人側からすると、外国人が結婚式に来てくれるということは非常に名誉なことのため、インドに住んでいるとあまり親しくない人からも結婚式に誘われたりするが、僕はもう既に結婚式には基本的に参加しないことにしてしまっている。友達が多い人は、結婚式シーズンは非常に大変である。しかし今回はお世話になった教師の娘の結婚式だったし、今年はまだ一度も結婚式に参加していないので、忙しい中ではあったが参加することにしたのだった。だが、かなり寒かったので、2時間ちょっといて、花嫁が会場に到着する前に帰ってしまった。
今まで僕はヒンドゥー教、スィク教、ジャイナ教の結婚式を経験した。ムスリムの結婚式は残念ながらまだ見たことがない。その中で一番楽しいのは断然スィク教の結婚式である。なぜならまず肉と酒が出る可能性が高いからだ。ヒンドゥー教、ジャイナ教の結婚式は十中八九ヴェジタリアン料理オンリーなので、食を楽しもうと思うと、日本人にとっては期待外れになることが多い。また、スィク教徒といえばパンジャービー・ダンス。最近のデリーの結婚式には必ずと言っていいほどダンス・フロアが設置され、DJが流行りのダンス・ミュージックを流している。インド映画のヒット曲、欧米の英語曲などが流れるが、やっぱりデリーで一番盛り上がるのはパンジャービー音楽。パンジャービー音楽を聞いて踊りださないパンジャーブ人はいないと言っていいだろう。彼らと一緒にバーングラー・ダンスを踊ると非常に楽しい。両手の人差し指を上に立てて肩を動かすと、簡単にそれらしくなるところがいい。これは少し偏見になるが、スィク教徒の人にはハチャメチャで暴走気味の人が比較的多いような気がするため、彼らの暴走ぶりを見るのも面白い。
結婚式には必ずと言っていいほどヒジュラー(簡単に言えばインドのニューハーフ)が訪れるので、彼女らと一緒に写真を撮ったり、インタビューしたりするのもまた一興である。
23日付のサンデー・タイムズ・オブ・インディア紙に、インドの「一般的な」結婚式の費用が載っていた。メヘンディー(ヘンナ)屋、チューリー(腕輪)屋、ビンディー(額の点)屋を呼ぶのに1晩10万ルピー、ラージャスターニー式楽団を呼ぶのに1晩2万ルピー、DJを呼ぶのに1晩1万〜2万5千ルピー、パーン屋を呼ぶのに1晩7万ルピー、シェフを呼ぶのに1晩5万ルピー、花嫁衣裳に30万ルピー、化粧品に5千ルピー、花に5万ルピー、照明に30万ルピー、ビデオと写真に2万5千ルピー、果物に5万ルピー、宝石に40万ルピー、ウェディング・プランナーに5万ルピー、ウェディング・カードと贈答品に10万ルピー、ボリウッド・スターを呼ぶのに50万ルピーなどなど・・・。結局、インドの結婚式にかかる費用は、70万〜1億ルピー(210万〜3億円に相当)だそうだ。もちろんこれは結婚式そのものの費用であり、結婚費用はさらにそれを上回る。ちなみに、インドに平均はないので、平均結婚費用を算出することは無意味であることも付け加えておく。
一方、社会の均質性が強い日本なら、平均を出すことは比較的参考になる。調べてみたところ、日本の結婚式の平均費用は、地域によって開きがあるが、278万円らしい(通産省特定サービス産業実態調査報告書より)。そうすると、物価の差などを考えると、インドの方が遥かに盛大な結婚式を行っていることは明らかだ。インドというと貧しい国というイメージがあるが、一度インドの結婚式を見たら、その固定観念にグサッと疑問符が突き刺さることは必至である。どんな貧しい人でも、例えスラム街の住人や乞食でも、一生のうち1回や2回は結婚式をドカンと打ち上げるだけの潜在的財力を持っていると言われる。ミドルクラス以上ともなれば、日本の一般的な結婚式を遥かに凌駕するレベルの結婚式を行うことが常で、裕福な家庭なら、3日〜1週間に渡って結婚式が行われる。これだけ結婚式を盛大に行うのは、やはりまだインドには結婚を神聖視する思考が根強く残っているからだろう。日本では今、地味婚が流行してるとか・・・。結婚式に莫大な費用を使うくらいだったら、新婚旅行や新婚生活のために金を使う、という考えだろうか。それとも結婚が人生の中で重要性を失いつつあることを意味しているのだろうか。
それにしてもこれだけ結婚式があちこちで行われているのを目の当たりにすると、インドの人口はさらにネズミ算式に増え続けていくという実感が沸く。「ゴキブリを1匹見たら、その家には100匹いると思え」という格言が日本にはあるが、「インドで結婚式を1回見たら、その地域の人口は100人ずつ増えていると思え」という新しい格言が生まれそうだ。
今日は僕の誕生日だった。インドにいると誕生日が少し重圧になる。年をひとつ取るという重圧はどの国にいても同じだが、それ以外の圧力が周囲からかかるのを感じる。日本では誕生日の人は周りからチヤホヤされて幸せな1日を過ごすことが多いのだが、インドでは「幸福は分け与えるべき」という鉄則があるため、誕生日の人が友人にミターイー(インドの甘いお菓子)を食べさせたり、パーティーに呼んだりするのが半ば義務化しているのだ。もうすぐ誕生日だということがばれると、「ミターイーを食べさせてくれるかい?」と聞かれたりする。結局インドにおいて誕生日というのは、誕生日になった本人がいろいろ大変で、その周りにいる人はただ「誕生日おめでとう」と言って祝福するだけで恩恵にあずかれるという、ちょっとお得な日である。
もうインドで迎える誕生日も3回目になったので、このインド独特の誕生日の祝い方にはだいぶ慣れた。今日はちょうど今学期最後の授業の日だったので、朝、グリーン・パークの割と有名なミターイー屋エヴァーグリーンでバルフィーというミターイーを買って学校に持って行った。インド人というのは本当に男も女もミターイー好きで、ミターイーの箱を開けた途端みんなパクパク食べてしまった。「どうしてもっと先に誕生日だって教えてくれなかったんだ?」と聞かれたが、どうせ教えたって「誕生日には何してくれるんだ?」とこちらが聞かれるだけなので、突然の誕生日宣言ということにしたのだった。おかげでみんなに「誕生日おめでとう」と祝福してもらえた。ただ、ちょうどラマダーン(断食月)中だったので、イスラーム教徒の人にはミターイーを食べてもらえなかった。
実は僕はインドのミターイーが好きではない。ネットリとした甘さをしており、1つ食べるだけでも精一杯だ。インド料理は基本的に何でも食べるが、アチャール(ピクルス)とミターイーだけはいつまで経っても好きになれない。好きではないから、無数にあるミターイーの名前を覚えることができていない。こういうのはやっぱり女の子が得意で、ミターイーにはまるとインドに来て数週間でほぼ全てのミターイーを制覇してしまう人もいる。しかしあまりにはまり過ぎるとインド人のようにプクプク太ってしまうので注意が必要だ。
ミターイーはインドの人間関係の潤滑油である。何か祝い事があったり、何か頼み事があったり、とにかく人間関係に何らかの非日常的接触点が生じたときにミターイーを持ち出すと、予想以上に事がうまく運ぶ。
僕のある友人が、インドの観光ヴィザ延長のためにネパールの首都カトマンズのインド大使館へ行ったことがあった。インドの観光ヴィザを延長するのはけっこう運頼みで、詳細はよく分からないのだが、タイミングによって何ヶ月延長してもらえるかが変わったりするらしい。その人は少しでも事を有利に進めようと、機転を利かしてインドからミターイーを持って行ったそうだ。そしてカトマンズのインド大使館でミターイーを渡したら、大受けして、職員たちがすごい勢いでパクパク食べてしまったらしい。そして手続きも非常にスムーズに進み、無事6ヶ月ヴィザを延長してもらえたそうだ。
誕生日のような祝い事があったときも、ミターイーは人と人をつなぐ架け橋になる。知り合い同士で祝いあうのも大事だが、ミターイーが配られているのを見つけると、見ず知らずのインド人でも「なんだなんだ、何か嬉しいことでもあったのか」と寄ってくる。ミターイーを渡すことで知らない人にも祝福してもらえるきっかけができ、また新しい人間関係も生まれる。これがインド独特の人間関係醸成システムなのだろう。誕生日に誕生日の人が他人にプレゼントを渡すという習慣は最初慣れないのだが、これはこれで合理的なように思える。
まさに「ミターイーを制する者はインドを制す」、インドで何か問題に直面したり、人間関係を改善したかったりしたら、ミターイーの魔力に頼ってみるのもひとつの手だろう。インド人に聞けば、近所のおいしいミターイー屋もすぐに教えてもらえる。
インドの首都デリーで1年に1回開催される現代版定期市といえば、インド国際貿易フェア(India International Trade Fair:IITF)である。インド各地、世界各国から7000以上の展示業者が集結し、400万人以上の来場客が訪れる南アジア最大の展示イベントだ。今年もプラガティ・マイダーンで11月14日から2週間開催されている。
デリー市民は毎年恒例の貿易フェアを非常に楽しみにしているが、一方で貿易フェアはプラガティ・マイダーン周辺の道路に慢性的かつ深刻な渋滞を引き起こすため、毎年いろんな対策が考案されている。今年は駐車場を思いっきり遠隔地に設置し、会場と駐車場間に無料のシャトル・バスを運行したようだが、やっぱり渋滞は避けられなかったようだ。ただ、去年に比べたらだいぶマシになったという声もある。休日には10万人の来場客と、1万5000台の自動車が貿易フェアに押しかけるので、渋滞しない方がおかしいと言えるだろう。
貿易フェアが始まってもう10日以上経つが、まだ僕は訪れていなかった。毎年行っても特に大した買い物もしない(去年は散々歩き回った挙句、何も買い物をせず、ただココナッツ・ジュースを飲んだだけだった)ので、行かなくても何の後悔もしなかっただろうが、今日はちょうどイスラーム教の祭日イード・ウル・フィタルで休みだったし、11月27日までで終わってしまうため、どうせなら今日行こうと思い立って、朝10時の開場に合わせてプラガティ・マイダーンを訪れた。駐車場の問題があったので、バイクではなくオートで行くことにした。
平日の午前中は買い付け業者向け時間帯ということで、入場料300ルピーと高額な代わりに、中は非常に空いているはずだった。しかし今日は祝日だったため、そういう特別措置はなく、休日と同じ扱いだった。休日料金で大人一人35ルピーを払い、中に入った。まだ朝だったため、開いてない店も多かったが、来場客も少なく、サクサクと見て回れた。
貿易フェアではいろんな分野の商品・展示品を見たり買ったりすることができるが、その中でも一番面白いのはサラス(「新鮮」という意味)と呼ばれる一画を中心に展示されているインド各州の多様な手工芸品である。ここを歩いていると、インド文化の底力を実感する。各州が主催するパビリオンも面白い。それぞれ独自の色合いが出ていて、ある州は民俗工芸品を中心に展示をし、またある州は近代的産業発展の様子を展示したり、観光情報を発信したりしている。ここでは各地の料理も食べることができる。今回の貿易フェアで特に目を引いたのは、テクノロジー部門パビリオンに、中国企業ブースが大々的に展開されていたことだ。最近インドと中国は急速に歩み寄りを始めており、その外交関係の変化の影響が貿易フェアにもすぐに表れていることを感じた。ただ、日本製品を知っていると、中国企業が誇らしげに展示している電化製品なども、まだまだ洗練されていないと感じてしまう。その他、パーキスターンからの業者もかなり来ていて驚いた。去年はこんなに来ていただろうか。
貿易フェアをグルッと回っていくつか感じたことがあった。普通、日本人だったら、貿易フェアのようなイベントがあった場合、なるべく普段手に入らないものを買おうとするだろう。僕なんかは完全にこのタイプで、ありふれたものには目もくれず、珍しいものを求めて彷徨うことしかしない。だが、インド人来場客を見ていると、普段簡単に手に入るような商品が売られているブースにたくさん群がっている印象を受けた。貿易フェアでは、珍しい品物が手に入るのと同時に、いろいろなものが安く手に入るというメリットもある。もしかしたらインド人はバーゲン・セールのような感覚で貿易フェアに来ているのかもしれない。
また、パーキスターン・ブースを見て思ったのだが、そこでは印パの対立関係を全く感じさせないほど、インド人来場客とパーキスターン人商人たちの間で活発な売買が行われていた。お互い話している言語はほとんど同じだし、センスも似ているので、当然のことかもしれない。だが、もし北朝鮮人が日本の貿易フェアで同じようにブースを出したら、日本人は彼らを自然に迎えるだろうか、と考えた。日本人はまず外国人を国籍で判断する傾向があるが、インド人は少なくともバーザールでは国籍その他一切関係なく、商品と金を媒介とした、商人と客という立場でしかものを考えていないように思えた。言葉の違いすら彼らはあまり気にしていない。とにかく値段さえ通じれば商売は成り立つという勢いである。これがインド人が何千年も培ってきたバーザール文化の賜物なのだろう。インドには古来より大陸各地から多種多様な商人たちが往来していた。一方、日本はアジアの離れ小島に位置し、こういう国際的バーザールを経験して来なかったので、大陸の人々とは異質なところがあるかもしれない。
個人的にヒットだったのは、チャッティースガル州の展示ブースだった。職人たちが実演して手工芸品を製作していたり、珍しくてアーティスティックな置物などが売られたりしていた。僕はこのブースで今回唯一の買い物をした。まずは金属製の小物入れ。四辺に像の顔が彫られている。僕はこういう装飾品と実用品を兼ね備えたものが好きだ。本当かどうかの250ルピー。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
小物入れ |
● |
もうひとつはミュージック・スティックと呼ばれる棒。これを振ると口笛みたいなヒョロヒョロ〜ッという音が出る。これはなかなか楽しい。ブンブン振り回すと、競馬のスタート時の音楽のようなメロディーになる。この棒を剣のようにして振り回しても面白い。ドラゴンクエスト風に「魔法の木の棒」とか「歌う木の棒」とでも名付けたくなる。棒の表面には魚の絵などが彫られている。80ルピーだった。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
ミュージック・ステッキ |
● |
これらの工芸品を見て、チャッティースガル州にも行かねば・・・と思ったのは言うまでもない。あまりチャッティースガル州の観光名所や遺跡などは有名ではないが、いくつか古い寺院などがあるようだ。
この他、ラージャスターン州パビリオンで展示されていた、2m以上ある巨大な木製の扇風機はすごいと思った。日本の家屋じゃ置き場所に困るだろうが・・・。他にもラージャスターン州はいいものを揃えていた印象がある。
1時を過ぎると人がかなり増えてきたし、これだけでかなり疲労困憊してしまったため、もう帰ることにした。貿易フェアをゆっくり全部回るためには丸1日2日必要だろう。
今年のボリウッドは、去年の駄作連発どん底状態と比べたらヒット作にも恵まれ、何とか上昇の兆しが見えてホッとしている。もう今年もあと残すところ1ヶ月となり、そろそろ今年のボリウッド界を総括してもいい頃だ。今年は何と言っても8月に公開された「Koi... Mil Gaya」が大ヒットを飛ばし、これ以上のヒット作は年内には望めないだろう・・・と思っていたら、やって来ました、今年最後の期待作「Kal
Ho Naa Ho(明日があろうとなかろうと)」。キャスト、スタッフ、ポスター、予告編などから判断する限り、期待が持てそうだった。これを見ずして2003年のボリウッドは語れない。そして全世界のインド映画ファン待望の「Kal Ho Naa Ho」が遂に本日から公開され始めた。
マニアと思われると嫌だが(もう既に思われているだろうが)、僕はこの期待作を公開初日の初回に見る光栄にあずかった・・・というより、昨日わざわざグルガーオン(自宅からバイクで30分ほど)まで行って座席を予約したのだが。PVRグルガーオンの朝10:45からの回を見たので、おそらく全インドでもっとも早くこの映画を見た一人になっただろう(他の映画館は早くても11時〜11時半が初回だ)。別に誰よりも早くこの話題作を見てやろうと躍起になっていたわけではなく、ただこの週末三連休(12月1日は選挙のため休日)を前にして、単にこの回のチケットしか手に入らなかったからだ。明日から期末テストで、今日は個人的に休日だったことも幸いした。まさに題名通り「明日があろうとなかろうと」、テスト勉強を犠牲にして映画を見たのであった。そしてその選択は、テストの出来を抜きにして、映画の出来から判断するならば、正しすぎる選択だった。結論から言えば、「Koi... Mil Gaya」が霞んで見えるほどの名作中の名作だった。
プロデューサーはヤシュ・ジャウハル、監督はニキル・アードヴァーニー(新人)、脚本はカラン・ジャウハル、音楽はシャンカル・エヘサーン・ロイ、振付はファラー・カーン。キャストはジャヤー・バッチャン、シャールク・カーン、プリーティ・ズィンター、サイフ・アリー・カーンなど。その他、サンジャイ・カプールとソーナーリー・ベーンドレーが特別出演する。ヤシュ・ジャウハルとカラン・ジャウハル親子は、「Kuch Kuch Hota Hai」や「Kabhi Khushi Kabhie Gham」など、超ヒット作を次々に送り出すヒット・メーカーである。その他のキャスト、スタッフも精鋭揃いだ。
下に全てのあらすじや解説を書くが、これはヒンディー語が分からない人のためで、ヒンディー語が分かる人は是非前知識なしで見るべきだと思う。途中あっと驚くどんでん返しも用意されている(このどんでん返しもヒンディー語が分からないとひっくり返らないとは思うが)。
| ● |
|
● |
|
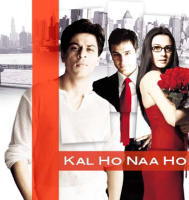 |
|
| ● |
左からシャールク・カーン、
サイフ・アリー・カーン、
プリーティ・ズィンター |
● |
| Kal Ho Naa Ho |
舞台はニューヨーク。大学生のナイナー(プリーティ・ズィンター)は、家庭の問題によっていつしか笑うことを忘れていた。彼女の父親は自殺し、クリスチャンの母親ジェニファー(ジャヤー・バッチャン)と、パンジャーブ人の祖母の間には言い争いが絶えなかった。弟は足が不自由で、母親が養女にした妹のジヤーは祖母に忌み嫌われていた。父親が遺したレストランは母親が何とかしていたが、経営がうまくいかず、負債を抱えていた。彼女の唯一の心の拠り所は、クラスメイトのグジャラート人ローヒト(サイフ・アリー・カーン)だった。ローヒトは金持ちでハンサムでプレイボーイだったが、おっちょこちょいで根が優しい男だった。ローヒトはナイナーに恋心を抱いていたが、二人の仲は親友に過ぎなかった。
そんなある日、向かいの家にアマン(シャールク・カーン)というやたらと陽気なインド人がやって来た。アマンは誰にでも分け隔てなく笑顔を振りまき、いつの間にか全ての問題を解決するという不思議なオーラを持っていた。ナイナーは最初強引なアマンを避けていたものの、一緒に母親のレストランを支えている内に彼を恋するようになる。彼女の顔にもいつの間にか微笑みが溢れるようになっていた。一方、ローヒトと親しくなったアマンは、彼のナイナーに対する心を理解し、二人の仲を取り持とうとする。ところが、ローヒトがナイナーに告白しようと思った日、ナイナーはローヒトに、アマンへの恋心を打ち明ける。ローヒトは何も言うことができず、逆にナイナーの恋を応援してしまうという駄目男振りであった。しかもアマンに電話をし、ナイナーが彼のことを好きであることを伝える。
ナイナーは気持ちを打ち明けるためにアマンの家を訪れる。ところが、アマンは1枚の写真を見せる。そこにはアマンと花嫁衣裳をした女性が写っていた。「これはプリヤー。僕の妻だ。」アマンはナイナーに何気なく伝える。アマンは夫婦喧嘩して家を出た妻を追ってニューヨークまで来たと言う。それを知ったナイナーはショックを受け、アマンの家を後にする。しかし、アマンも涙を流す。アマンの母親が「お前はナイナーのことが好きなんだろ」と言うと、アマンは叫ぶ。「人生で初めて愛することができる女性に会ったよ。でも僕の命はあと少ししかないんだ!」アマンは心臓病を患っており、あと少しの命だった。実はナイナーに伝えたことは嘘で、プリヤーは彼の妻ではなく、医者だった。アマンは、自分がナイナーと結婚しても彼女を不幸にするだけであることから、ローヒトとナイナーを何とか結婚させようとする。
ローヒトはナイナーの本心を聞いてショックを受けていたが、アマンが彼に「6日で女をものにする方法」を伝授する。アマンの言われた通りにローヒトが行動する内に、ナイナーはローヒトの気持ちを知り、それを受け容れることができるようになる。遂にローヒトはナイナーにプロポーズし、彼女はそれを承諾する。二人の婚約式が行われ、結婚式も間近に迫っていた。また、アマンはナイナーの母親と祖母の争いも解決する。なんと養女のジヤーは、自殺した父親の愛人の子供だった。ジェニファーは夫の愛人の子供を、夫の不倫に対する憎悪を乗り越えて養女にして育てていたのだった。祖母もそれに感動し、ジェニファーとジヤーを愛するようになる。
しかし、アマンの死期は刻一刻と近づいていた。ローヒトとナイナーが買い物をしているときに、二人は偶然プリヤー(ソーナーリー・ベーンドレー)に出会う。プリヤーは本当の夫アバイ(サンジャイ・カプール)と一緒だった。アバイは二人に、アマンの病気のことを話してしまう。アマンの病気、アマンの死期、アマンの愛、アマンの友情を知った二人はとまどう。アマンは本当はナイナーのことを愛していた。しかし病気のことを隠し、愛する女性の将来の幸せのことを思って、ローヒトとナイナーをくっつけたのだった。何という嘘つき、そして何という自己犠牲の思いやりだろうか。しかし二人はアマンの気持ちと命を無駄にしないためにも、結婚することに決める。
ローヒトとナイナーの結婚式の日、アマンは倒れる。病院に運ばれたアマンは、ローヒトに「次に生まれて来るときは、ナイナーはオレに譲れよ」と言って息を引き取る。アマンは短い間に、ナイナーに、笑うこと、愛すること、生きること、全てを教えてくれたのだった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
素晴らしいの一言に尽きる。全体としては悲しいストーリーだが、その中にも笑いと感動と遊び心が溢れ、それらが心地よい調和を保っている。3時間の映画だったが、一生映画を見たような気分になる。映画館を出るときに誰かが「泣きすぎて頭がおかしくなっちゃうわ!」と叫んでいたが、まさにその通り、涙なしでは見られない、インド映画至高の傑作だった。「Kabhi Khushi Kabhie Gham」の涙は何となく強制的に泣かされている感じだったが、「Kal
Ho Naa Ho」の涙はもっと完成度が高い感じがした。また、これほどニューヨークが美しく描かれている映画も他にないかもしれないとまで思うほど、映像がきれいだった。
まずは不幸な日常を送るナイナーの姿が描かれる。ナイナーは眼鏡をかけ、お堅い外見、そしていつも何かとカッカ怒っている女子大生だった。彼女の家はパンジャービーで、スィク教だったが、母親はクリスチャンで、イエス・キリストとグル・ナーナクの肖像がまるで睨み合うかのように壁にかかっているような家庭だった。母親が養女にしたジヤーも争いの元だった。それら全てがアマンの登場により一変する。アマンはミュージカル「Pretty Woman」と共に派手に登場する。この歌はロイ・オービンソンの有名な同名曲のパンジャービー&ヒンディー・リミックス・バージョンだ。ぶっ飛ぶこと間違いなし。アマンの影響により、ナイナーは眼鏡をかけるのをやめ、いつしか笑うようになり、そして恋を知った。自分が不幸なときは、他人の幸せを見るとイライラする。しかし自分が幸せなときは、他人の幸せを見ても自分までもっと幸せになるものだ。そんな心境の変化が、ミュージカル「Kuch
To Hua Hai」で描かれる。
アマンはナイナーだけでなく、全ての人々の心をつないだ。アマンはジェニファーのレストランの一大改革を打ち出す。彼女のレストラン「Cafe New York」は、サンドイッチなどを出すニューヨークでは何の変哲もないレストランだったが、最近向かいに出来た中国人経営の中華料理店に客を奪われていた。そこでアマンは、ジェニファーのレストランをインド料理レストラン「Cafe
New Delhi」にする改革を打ち出した。近所総出で店内を改造(このとき流れる音楽が大ヒット映画「Lagaan」の「Chale Chalo」だからおかしい)、それが大ヒットして、たくさんの客を呼び込むことになる。
アマンに気持ちを打ち明けることを決意したナイナー。ところが、アマンに妻がいることを知り、彼女は失恋の味も知ることになる。それはナイナーのクラスメイト、ローヒトも同じだった。ローヒトはナイナーのことが好きだったが、ナイナーはアマンが好きであることを知り、失恋を味わっていた。彼にはナイナーの心の痛みがよく理解できるし、一度誰かを好きになった彼女が、簡単に他の人を好きになれない気持ちもよく理解できたから、余計つらいのだった。
だが、アマンは実は独身だった。アマンは心臓病で死期が迫っており、ナイナーと結婚しても彼女を不幸にするだけであることを知っていた。だから彼は、既婚だと嘘をついたのだった。この場面は観客もエッと驚くところだ。プリヤーは伏線としてチラホラと登場していたのだが、てっきりアマンの妻だと観客も思い込んでしまうような描写のされ方だったからだ。しかし実際は彼女はアマンの親友であり、医者に過ぎなかった。そしてこのとき初めて観客は、映画の題名「明日があろうとなかろうと」に込められた真の意味を悟る。
アマンはナイナーの幸せを考え、ローヒトとナイナーを何とかくっつけようとあれこれ奔走する。ローヒトは失恋して落ち込んでおり、アマンに対する感情も複雑だった。ローヒトはアマンに「お前だってナイナーのことが好きなんだろ」と言う。「ああ、好きさ。もし独身だったらオレが彼女にプロポーズしたさ。でもオレには妻がいるからそれはできない。だからお前に6日で女をものにする方法を教えてやるのさ!」アマンは嘘とも本当ともつかないことを口にして彼を説得し、作戦を開始する。そして本当に6日でナイナーはローヒトに気持ちを動かされる。ただ、ローヒトがナイナーにプロポーズするシーンは、この映画中唯一しらける場面である・・・。とにかく、ナイナーはローヒトと結婚することを承諾する。
僕はよく知らないのだが、どうもパンジャーブ人とグジャラート人の間には何か歴史的軋轢があるように思えた。ナイナーの家はパンジャーブ、ローヒトの家はグジャラート。それがナイナーの祖母には少し気に食わなかったようだが、とにかく婚約式はグジャラート文化とパンジャーブ文化のミックスで盛大に行われる。つまり、ガルバー(スティック・ダンス)とバーングラー(パンジャービー・ダンス)である。このときに流れる「Maahi
Ve」は映画中もっとも盛り上がる場面で、なんとラーニー・ムカルジーやカージョールが一瞬だけ出演する。そういえばウダイ・チョープラーやラージパール・ヤーダヴも他のシーンで一瞬だけ出ていた。だが、アマンは踊っている最中に発作が起こって倒れる。そのときは彼の病気のことはばれなかったが、ローヒトとナイナーは偶然出会ったプリヤーと彼の夫から、アマンの病気のことが知れてしまう。
ナイナーのことを愛しながら、自分の死期が近いことを悟り、ローヒトとナイナーの仲を取り持つアマン、アマンのことを愛しているナイナーを愛し、アマンの助けを借りて彼女との結婚が実現したものの、アマンが実は独身で、彼女のことを愛していることを知るローヒト、そして愛する人がもうすぐ死ぬ運命であることを知るナイナー、この3人の激動の心境が、この映画のもっとも核となる部分である。この中でも特にローヒトの感情に僕は心を動かされる。自分の愛する女性が、他の男を愛していることを知り、さらにその男が、自分の恋を実現させてくれた。しかしその男はすぐに死ぬ運命にあり、しかも本当はその女性のことを愛していた。それを知ったときには、ローヒトは男としてアマンには全くかなわないことを悟ったと思う。死を前にした人間が、ここまで陽気で寛大になれるかどうか、自分の愛する女性を、他の男に託せるかどうか、いろいろ考えてしまうだろう。
結局、ローヒトとナイナーは結婚し、アマンは息を引き取る。おまけとして、20年後のローヒト、ナイナー、そしてジヤーが出てくるが、このシーンでのサイフ・アリー・カーンは爆笑ものだった。20年後のプリーティ・ズィンター、あまり老けた感じではなかった。
あまりこういうことは好きではないのだが、少し他の映画との比較をしてみる。まず思いつくのはカラン・ジャウハル監督のデビュー作「Kuch Kuch
Hota Hai」(1998年)である。「Kal Ho Naa Ho」でも「Kcuh Kuch Hota Hai」でも、大筋は死を中心に置いた三角関係の恋愛がテーマになっていた。また、死に行く者の予想外の陽気さが、他の人々に明るさを与えるという設定は、若き日のアミターブ・バッチャンが出演している「Anand」(1970年)を想起させる。そしてニューヨークを舞台とした、インド離れしたオシャレな雰囲気は、「Dil
Chahta Hai」(2001年)っぽくもある(なんとインドのシーンがひとつもない)。しかし、それら全ての映画をひっくるめたとしても、まだ何か余りある素晴らしい映画である。また、ちなみにこの映画中にはいくつか他の映画のパロディー・シーンもある。「Lagaan」(2001年)のパロディーは前述したが、他に「Devdas」(2002年)や「Jism」(2002年)などのパロディーがあった。他にもあるかもしれない。一瞬だけ特別出演する俳優がいたりするのも楽しい。
アマン、ローヒト、ナイナーの三角関係が映画の軸だったが、他にもいろんな要素が詰め込まれていた。スィク教とキリスト教の争いと和解から宗教問題、パンジャーブ人とグジャラート人の争いと和解から地域間意識などなど。インド料理レストランで中華料理レストランに対抗したシーンには笑った。暗にインド人の中国人に対する対抗意識を表明したのだろう。穴馬的存在だったのはジャヤー・バッチャン演じるジェニファー。夫の不倫に耐え、夫の自殺に耐え、夫の愛人の子供を家族に真実を内緒にして育て、それが原因で起こる姑のいじめにも耐え・・・けっこう重い役だったと思う。
シャールク・カーンはやっぱり素晴らしかった。彼でなければこの映画の主役は務まらなかっただろう。「Devdas」っぽい、病に蝕まれて死にそうになりながらの演技や、一気に悲しみをぶちまけてまくしたてるシーン、そして心に悲しみを秘めながら微笑むその笑顔など、他のシャールク映画でも見られる彼の特徴がこの映画でも発揮されていた。
プリーティ・ズィンターもはまり役だった。ナイナーの役には、ブスと美人の境界にいる女優が必要だった。それにプリーティは適役だ。プリーティ・ズィンターは僕も大好きな女優なのだが、角度によってはすごいブスに見える。しかし彼女の笑顔はまるで太陽のようだ。不幸なときの暗い表情と、幸せなときの明るい表情のギャップが、彼女の女優としてのキャパシティーを広げていた。彼女が酒に酔っ払って踊る「It's The Time To Disco」を見て、そのノーセクシーさやダサさが逆に彼女の役得だと思った。アイシュワリヤー・ラーイのような、完璧な美女ではこの役は務まらない。プリーティ・ズィンターは「Koi...
Mil Gaya」の大ヒットに続き、この映画でも大ヒットを飛ばすだろう。今年は彼女の当たり年だったと言える。主演女優賞の受賞圏内にもいると思う。
サイフ・アリー・カーンの役は他の男優でもできたかもしれない。アルジュン・ラームパールとか、リティク・ローシャンとか・・・。脇役たちは皆個性的で、映画をさらに魅力的にしていた。
この映画では、パンジャーブ人とグジャラート人が登場するため、通常の言語はきれいなヒンディー語なのだが、ときどきパンジャービー語とグジャラーティー語が混じる。しかし何の字幕も出ないので、それらの言語が分からない人は、聴き取る努力をするか、聞き流すしかない。だが、はっきり言ってヒンディー語が分かっていれば、それらの言語も何となく分かるし、他のインド人も何となく理解しているようだった。11月19日の日記でヒンディー語映画の言語の標準語性を議論したが、この映画によってさらに押し進んだ考えを持つようになった。いや、この映画だけでなく、他のヒンディー語映画でも、ベンガリー語などが出てきたりするが、字幕が出ることはないし、観客もそれでしっかり理解して反応している。それらから判断すると、北インドの言語をヒンディー語、パンジャービー語、ベンガリー語、グジャラーティー語など、別の言語として分類するのはもしかしたら間違いなのかもしれない。北インドの言語は、言わば「インド語」とでも呼ぶべき共通性を持っており、ヒンディー語もパンジャービー語もベンガリー語もグジャラーティー語も、インド語の方言と分類すべきものなのかもしれない。ヒンディー語内部にもいくつもの方言があるが、それらの方言を方言とする基準と、上記の言語を別の言語として分ける基準がよく分からない。文字が違うという議論もあるが、文字は言語の基盤には成りえない。文字のない言語もこの世界にはいくつもあるのだから。まあ結局、政治と、それによる帰属意識の方向性の相違が、文化と言語の境界線を作り出しているのだろうが。とにかく、ボリウッド映画には、この「インド語」が使われていると言っていいのではなかろうか。そしてマラーティー語映画やベンガリー語映画などの北インドの他言語映画は、インド語方言映画としてもいいのではなかろうか。ボリウッド映画には、インド語の方言がときどき出てきても、基本は同じだから字幕は出ないし、大抵のインド人なら字幕なしでの意味を汲み取ることができる。これは日本のテレビで関西弁が出てきても、字幕がないのと同じ感覚だと思う。地方の方言が出てくるとさすがに標準語字幕がつくことが多いが、大抵の方言なら、字幕なしでも日本人なら理解できるだろう。しかし、映画中アメリカ人が何の脈絡もなくヒンディー語をしゃべり出すのだけは勘弁してもらいたかった。先日見た「Out of Control」ほどひどくはなかったが。
一点だけ気になったのは、冒頭の映画題名が出てくるシーン。シャールク映画などにはアルファベットとデーヴナーグリー文字とウルドゥー文字の三種類の文字で題名が表記されることが多かったのだが、この映画ではアルファベットとデーヴナーグリー文字しか表記されなかった。特に気にする必要のない部分なのかもしれないが、この映画題名の表記文字については前から少し気になっていた点であるので、簡単に書いておいた。
「Kal Ho Naa Ho」がどれだけヒットを飛ばすかはまだ予想がつかないが、興行成績、批評家の反応共々「Koi... Mil Gaya」を越える可能性は十分ある。あるアナリストによると、「Koi... Mil
Gaya」の3倍はいくだろう、とのこと(何を根拠にそんなこと言ってるんだか・・・)。「Koi... Mil Gaya」は「E.T.」のパクリ疑惑や、日本人作曲家きたろうの「夜明け」という曲の盗作の疑いがあるため日本での公開は難しいが、この映画なら何の問題もないと思われる。「Kal
Ho Naa Ho(明日があろうとなかろうと)」は、今年の流行語大賞も狙えそうだ(そんなのインドにはないが・・・)。
|
|
|
|
|
NEXT▼2003年12月
|
|
| *** Copyright (C) Arukakat All Rights Reserved *** |



