 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
 これでインディア これでインディア 
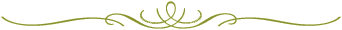
2003年2月
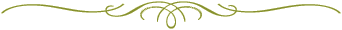
|
|
|
|
2003年1月16日に打ち上げられたスペース・シャトルSTS−107(コロンビア)が、昨日1日、着陸直前にテキサス州上空で空中分解した。乗組員7人全員死亡し、この事件は今後の宇宙開発に重大な支障を及ぼす他、アメリカの対イラク戦争にも少なからず影響を与える見通しである。
このニュースはYahoo!Japanや読売新聞などのニュース・サイトで知ったのだが、日本での報道のされ方に「アレッ」と思わざるをえないところがあった。日本のニュースでは、コロンビアにイラン・ラモーンという「イスラエル人初のスペース・シャトル搭乗者」が乗っていたことが度々触れられているが、「インド人初のスペース・シャトル搭乗者カルパナー・チャウラー」のことがほとんど触れられていなかったことだ。
コロンビアの乗組員7人の名前と出身地を列挙すると、リック・ハズバンド(アメリカ)、ウィリアム・マッコール(アメリカ)、マイケル・アンダーソン(アメリカ)、カルパナー・チャウラー(インド)、デイビッド・ブラウン(アメリカ)、ローレル・クラーク(アメリカ)、イラン・ラモーン(イスラエル)。7人中5人はアメリカ人で、外国人はカルパナー・チャウラーとイラン・ラモーンだけである。しかも2人とも母国で初のスペース・シャトル搭乗者である。イラン・ラモーンはイスラエル初のスペース・シャトル搭乗者であるだけでなく、初の宇宙飛行士らしいが、カルパナー・チャウラーはインド人宇宙飛行士としては2人目であるものの、インド初の女性宇宙飛行士だ。平等に扱われてもおかしくないはずだ。
ここまでイスラエル出身のイラン・ラモーンがもてはやされるのは、ただ単純にイスラエルという国籍が持つ意味が重かったのと、彼が1981年にイラクを空爆したパイロットで、しかも当時彼は最年少パイロットだったことが大きいのだろう。実際、この事故でイスラエル人宇宙飛行士が死亡し、それがイラク空爆に参加したメンバーだったことがイラクに伝わるとあちこちから歓喜の声が上がった、というニュースもセットで出ていた。どうも事件を劇的にしたがるマスコミの演出・脚色が入ったために、イスラエル人のイラン・ラモーンが無闇に日本で脚光を浴びることになってしまったように思える。
しかし、根底に流れる問題はそうではない。今回の日本のマスコミの報道の仕方(といってもネットでしか見ていないが)を見て、一番残念に思ったのは、未だに日本のマスコミにはインド軽視の考えが浸透していることが感じられてしまったことだ。なぜ日本のマスコミは、カシュミール問題、インドとパーキスターンの核問題以外は、あまりインドに関心を示さないのだろうか?もっとインドのいろんな側面を報道してもらいたいのに。今回の事故に関連して、インドにいるカルパナー・チャウラーの家族が悲しむ映像とかを流してもらえれば、「インドでも人が死んだら悲しむんだな」とか「死体をガンジス河に流すっていうけど、今回のような場合はどうするのかな」とか、いろいろ視聴者に興味を想起させることができただろうに。この日本のマスコミのインド軽視、僕の気のせいだったらいいのだが・・・。
もっとも、カルパナー・チャウラーの国籍で混乱があるのかもしれない。彼女の出身はインド、ハリヤーナー州のカルナール(デリーのすぐ近くである)だが、アメリカの市民権を得ていたようなので、インド人なのか、アメリカ人なのか、日本のマスコミにはよく分かっていなかったのかもしれない。だが、出身地は完全にインドだし、家族もインドに住んでいるし、インドでの報道のされ方もカルパナー・チャウラー中心なので、やはりインド人としてのアイデンティティーの方がアメリカ人としてよりも強いだろう。
とりあえず一般のインド人にも、同胞がスペース・シャトル事故で死亡したことはあまり関心がなかったようだ。マーケットはごく普通に活気を呈していたし、カルパナー・チャウラーを哀悼するようなイベントは僕の見た限りでは何も行われていなかった。インド人は、生と死に対しては「全部神様任せ」的なものの考え方をしているので、見ず知らずの人の死なら、例え同じインド人でもあまり動じないのかもしれない。
やはり海外生活を送る際、文化の違いには必ずぶち当たるもので、慣れてしまえばどうでもよくなるのだが、慣れないといちいち腹が立つことも多い。インドのレストランにも、独特の習慣が存在する。
例えばムガル料理・中華料理・南インド料理全てを出すレストランがあるとする。そこに4人で食べに行ったとする。1人はバター・チキン・ボーンレス・ハーフとナーンを注文し、1人はチョウメンを注文し、1人はマサーラー・ドーサーを注文し、1人はポーク・スティームド・モモを注文したとする。そうすると何が起こるかというと、ウェイターはそれらの料理を全て一度に持ってくるのだ。どうも料理は全員分一度に持ってこなくてはならないという規則がインドには存在するようだ。これらの料理ははっきり言って調理する時間がそれぞれ異なる。コックがその時間差をうまく計算して料理すれば問題ないのだが、インドでそこまで気の回るコックはほとんどいない。よって、一番早く完成してしまった料理はそのまま放置され、客のもとに届く頃には冷めてしまっていることが少なくない。だから、予めウェイターに、「出来たものから順番に持って来い」と告げておくことは意外と重要なことなのかもしれない。
この「人数分一気出し」の法則はまだ許せるとしても、「空いた食器は即撤収」の習慣にはとまどう日本人が多いようだ。前に述べたように、インド料理は基本的に全ての料理が一気に出てくる仕組みになっている。フランス料理のように次々と料理が出てくるわけではない。だから客が食事を食べ終えて、テーブルの上に空いた皿が乗っていても別に邪魔にはならない。しかしインド人のウェイターは、客が皿に乗っている料理を食べ終えた瞬間、その皿を持って行ってしまうのだ。
はっきり言って僕は「インドではそれがサービスだと思っているんだろう」と思って気にしなかったのだが、割と外国人で気にする人は多いようで、僕もだんだん気になり始めた。皿をすぐに持って行かれると、「早く出て行け」と暗黙に催促されているみたいで気分が悪いらしい。確かにそう言われてみればそうである。僕もバリスタなどの喫茶店で人と待ち合わせをし、相手が来るのをコーヒーを飲んで待っていたとき、そのコーヒーが空になるや否や、店員がやって来て持って行ってしまったことがあった。そのとき僕は嫌な気分になったものだ。喫茶店というのはもちろんコーヒーや紅茶を飲む場所だが、それ以上に人と団欒したり待ち合わせしたりする場所だということがまだインド人には分かっていないらしい。喫茶店でコーヒーを前に座っていれば絵になるが、テーブルからコーヒー・カップを持っていかれたら、ただの座っている人になってしまうではないか。これではかっこ悪い。空でもいいからコーヒー・カップを残しておいてもらいたかった。
この「空いた食器は即撤収」文化は、インドの食文化と密接に関係しているような気がする。まず、インドではもともと外食という文化はなかった。食事は家で家族とするものであり、外で食べる食事は不浄であると考えられていたからだ。一方で、インドには聖地巡礼の習慣があり、巡礼者のための宿(ダラムシャーラー)や食堂(ダーバー)は用意されていた。だが、あくまで巡礼者、旅行者のためのものであり、地元の人が食べに来るようなことは想定されていなかっただろう。そのダーバーが、西洋の影響から都市部を中心に、次第に地元の人を主なターゲットとした食堂に変わって行ったはずだ。しかしそこで食事をするのは大概出稼ぎにやって来た独身男性が中心だったはずで、彼らはまさに食事をするために来るのであり、食事が終わったらさっさと席を立って帰ってしまうのが常であったと考えられる。よって、食事が終わったらすぐに食器を片付ける文化も生まれて来たのではないだろうか?その文化は西洋的レストランにも受け継がれ、客が食事を終えたら即食器を撤収するように、ウェイターは躾けられているのだろう。
もうひとつ考えられるのは、カースト制度との関連である。レストランのウェイターをよく観察すると、食事を運んでくる人と、食器を片付ける人は別であることがほとんどである。ちょっと小ぎれいなレストランへ行くとよく分かる。注文を取り、食事を運び、勘定を持ってくるのは、割ときれいな制服を来た人で、食器を片付けたり、テーブルを拭いたり、床を掃除したりするのは汚ない身なりをした人である。また、厨房をチラッと覗いてみると、奥の方でずっと汚れた食器を洗い続けている人が存在する。つまり、全て分業制になっているのである。そしておそらくそれらの仕事の間には、厳密に身分の上下が存在する。だから食器を片付ける係りの人は、食器を片付ける仕事しかないため、また仕事を常にしていないとマネージャーから目を付けられるため、目ざとく空いた食器を探し当てる習慣が付いてしまっているのだ。また、食器洗いの人に仕事を常に与えるために、積極的に汚れた食器が集められているとも考えられる。
もっともデリーの一部の高級ホテルのレストランでは、だんだん西洋風のサービスが受けられるようになって来たようだ。僕はほとんどその手のレストランで食事をしたことがないので分からないが・・・。
| ◆ |
2月4日(火) Kaahe Chhed Mohe |
◆ |
昨年一世を風靡した映画「Devdas」のCDに、「Kaahe Chhed Mohe」という曲が収録されている。「Devdas」の音楽はイスマイル・ダルバールが作曲したのだが、この「Kaahe Chhed Mohe」だけは作詞・作曲をカタック・ダンスの大御所パンディト・ブリジュ・マハーラージがこなし、自身も歌を歌っている。彼の他には大女優マードゥリー・ディークシトと、カヴィター・スブラマニアムが歌っている。ビルジュー・マハーラージのコンサートには何度も行ったことがあるので、彼のことはよく知っていた。
僕はこの曲を初めて聞いたときにしびれてしまった。何だか分からないけどすごい歌だ、と。変調が激しいし、途中で「タケタタケタタケタ」と変な声が入るし、マハーラージが普段の声と変わらない声で余裕綽々で歌っているし、とにかくすごい歌だ、と。しかし意味が分からない。何を言っているのだ。ヒンディー語なのには変わりないが、非常に訛ったヒンディー語なのだ。これはブラジュ・バーシャーと呼ばれるアーグラーやマトゥラーを中心に話されている方言だ。だが方言と言っても馬鹿にしてはならない。ブラジュ・バーシャーは、現在の標準ヒンディー語が整備されるまでヒンディー語文学の担い手だった由緒ある方言である。ブラジュ・バーシャーはクリシュナ信仰の中心地の言葉だったため、クリシュナ関連の文学がブラジュ・バーシャーによってたくさん作られた。
その「Kaahe Chhed Mohe」を何とか解読したいと思っていた。やはり普通のインド人にも何を言っているのかよく分からないようだ。しかしよく分からないながらもいい歌である、という共通認識はあるようだ。インターネットで探し回った結果、Bollywood Lyricsというサイトでやっと「Kaahe Chhed Mohe」の歌詞と英語訳を発見することができた。発見したのは随分前だが、今日になってやっと思い立ってこの曲の歌詞と日本語訳を載せることができた。身毒企画の映画音楽歌詞集に格納してある。
参考にしたのは前述のBollywood Lyricsだが、それでもまだ完全ではなく、間違いも多かった。何度も聴き取りながら何とか自分で納得できる歌詞、日本語訳にしておいた。多分まだ足りない点があるだろう。また学校の先生にでも質問してみようと思う。
歌の内容だが、実はけっこう色っぽい歌だった。題名の意味は「どうして私に悪戯するの」。クリシュナとゴーピーを題材とした歌で、クリシュナに悪戯されたゴーピーが、クリシュナの母親ヤショーダーに訴えるという内容のものである。クリシュナは大声を上げてゴーピーを驚かせ、ゴーピーの持っていたミルクの入った壺を壊し、彼女の顔を覆っていたヴェールを外させ、顔中にキスし、手首のバングルを破壊し、とやりたい放題である。それを訴えるゴーピーの言葉がかわいい。ブラジュ・バーシャーというのは標準ヒンディー語の固い発音と違って、滑らかにかわいく聞こえる言語で、僕はかなり好きである。
さすがにTAB譜は無理だった。しかしこの歌を歌えれば「インド人もビックリ」の特技となるだろう。
| ◆ |
2月5日(水) Vasantotsava 2003 第1夜 |
◆ |
昨日ビルジュー・マハーラージのことを書いたばかりだったが、今日はそのビルジュー・マハーラージを生で見る機会に恵まれた。マハーラージが経営する学校カラーシュラム主催の毎年恒例イヴェント「Vasantotsava(春祭り) 2003」が今日から4日間、カマニ・オーディトリアムで行われる。初日の今日と、最終日の8日にブリジュ・マハーラージが登場するということで、今日は外せなかった。
デリーにおいて、この種の公演は全て無料で見れることが多い。しかしその代わり、招待状がないと入れないことがある。特に有名なアーティストが来るときなどはかなり厳しくなる。実はその招待状を手に入れるのが非常に難しい。ほとんどコネの世界だからだ。今回、僕は招待状を手に入れることができなかった。しかしめげずに会場へ行ってみた。やはり今回の公演は厳しくチェックされるみたいだった。しかし僕はうまく知り合いの中国人と合流し、その人たちに混じって入場することができた。しかも会場と同時に入ったため、特等席をゲットすることができた。さすがマハーラージの知名度は抜群で、カマニ・オーディトリアムは間もなく満席となった。
今日の演目は4つ。1番目の題目は「Naman(挨拶)」。カラーシュラムの生徒と、ラームモーハン・マハーラージが踊った。コンテンポラリー・ダンスの趣向が強い踊りだった。
2番目は「Antaheen Yatra(終わりなき旅)」。デーヴ・クマール・ポールというインド人パントマイマーが主体の踊りだった。最初見たときは、上半身裸、下半身白タイツのおじさんが登場したので焦ってしまったが、彼のクネクネ器用に動く身体を見ていると、だんだん惹き付けられて来た。縄に上ってサーカスのようなことをしたりもして、なかなか楽しめた。
3番目は「Universal Rhythms」。プラタープ・パーワルという老齢のカタック・ダンサーが、タブラー、パカーワジュ、ムリダンガムに加えて西洋のドラム・キットと共演するという一風変わった趣向の踊りだった。タブラーとパカーワジュはカタックと切っても切れない関係にあるが、南インドの打楽器であるムリダンガムと合わせたり、ましてやドラム・キットと合わせるのは珍しい。やはり前者3つはインドの楽器なので、インド舞踊にピッタリ来る。しかしドラム・キットは・・・ドラムでリズムを取ると、踊りはカタックでも、どうしてもディスコで踊っているような雰囲気になってしまうのがおかしかった。受け狙いだったのだろうか?しかしドラム・キットをこしらえただけで「Universal Rhythms」と名乗るのはおこがましいような気がした。せめてアフリカの太鼓や、できたら日本の和太鼓も呼んでもらいたかった。
トリはもちろんパンディト・ビルジュー・マハーラージだが、その前にインド声楽の大御所、ラージャン・ミシュラとサージャン・ミシュラの兄弟が歌を歌った。この歌が長いのなんのって・・・。インド人の音楽家というのは我の強いのが多いが、やはり今回のコンサートでもその我の強さをまざまざと見せ付けられた。ビルジュー・マハーラージが大トリだというのに、自分たちが主人公だと勘違いしてたのか、延々と1時間も歌を歌い続けた。しかも兄弟の間でマイクの取り合いというか、歌の歌い合い、つまりはどちらか目立つか大会を行っており、非常に興醒めだった。タブラーの人が早く終わらそうとしてペースを上げるのだが、それでも余裕綽々で歌い続けるミシュラ兄弟・・・。かなり腹が立ってしまった。ビルジュー・マハーラージを見ずに席を立ってしまった観客も多かった。彼らの歌が終わったときに起こった拍手は、「やっと終わってくれた!」という意味であることを彼らに教えてあげたかった。
ミシュラ兄弟の歌が予想以上に長引いたため、ビルジュー・マハーラージが登場したのは夜10時頃だった。マハーラージも直接ではないが、「お前たち長過ぎなんだよ」と文句を言っていた。
ビルジュー・マハーラージはもう高齢のためか、最近滅多に長く踊らない。今回も座り踊り少しと、立ち踊りを少ししただけで終わってしまった。さすがにパントマイムはうまかったが、ミシュラ兄弟との掛け合いがあまりうまく行っていなかった。彼らはカタックと合わせたことがあまりなかったのだろう。
8日にはマハーラージはオリッスィー・ダンスの大御所ケールーチャラン・モハーパトラと共演するので、もしかしたらマハーラージの踊りをたくさん見ることができるかもしれない。
今日はヴァサント・パンチュミー、インドの暦で春の始まりの日だ。また夜は寒いが、確かに日中はもう春の陽気である。春の到来を祝うため、今日は黄色い服を着る慣わしがあるようだ。そういえば昨日もパンディト・ビルジュー・マハーラージは黄色いクルター・パージャーマーを着ていた。
今日は春の始まりの日であると同時に、ベンガル地方を中心にサラスヴァティーを祀る日とされている。サラスヴァティーは学問の女神。伝統的なブラーフマンの家庭では、子供たちの教育は今日から開始されるそうだ。一番気候のいい時期に学業が始まるというのは、世界各国どこも同じかもしれない。日本では4月から学業暦が始まるし、アメリカでは9月からだ。ただ、現代のインドの大学は雨季の始まる7月から始まることになっている。なぜだろう・・・。
春の到来と共に、結婚式の季節の到来も同時に訪れたようで、突然街中は結婚式だらけとなった。ひとつ角を曲がるごとに結婚パレードと出くわすぐらいの勢い。景気よく打ち上げ花火が上がってる結婚式場もあったりして、インドはもう春真っ盛りである。そしてこの春が悲しいくらい短いのだ・・・。
| ◆ |
2月7日(金) Vasantotsava 2003 第3夜 |
◆ |
カラーシュラム主催のダンス・イヴェント「Vasantotsava 2003」を一昨日に引き続き見に行った。今日は著名なアーティストが出演しないためか、観客数も警備の厳重さも一昨日に比べたら低かった。
今日は5つの題目があった。1つめは「Asadh Ka Din(雨季の日)」。サンジャイ・バッターチャーリヤという聞くところによると有名な画家がステージの上で白いキャンバスに向かって雨季をテーマに絵を描いている横で、ダンサーたちがダンスを踊るという、斬新な構成だった。どうも今回の「Vasantotsava」は、2つのアートの融合が全体を貫くテーマになっているらしく、絵と踊りの融合が試みられたとのことだった。日本人カタック・ダンサーの佐藤さんも参加しており、インド人に負けず劣らず切れのあるダンスを披露していた。
2つめは「Paraspar Angik Bhava(相互的身体感情)」。サッティリヤというアッサム地方のダンスと、カタック・ダンスの共演で、それぞれ男女1組がペアになって踊っていた。カタックの方は何度も見る機会に恵まれていたし、今まで最高レベルのカタックも見ているので、カタックだな、と思った程度だが、サッティリヤというのは初めて見た。どうもバラタ・ナーティヤムに似ていると思った。
3つめは「Pravaha(流れ)」。今度はカタックの女性ダンサーとバラタ・ナーティヤムの女性ダンサーの共演だった。カタックとバラタ・ナーティヤムは同じインド舞踊でありながら全く雰囲気が違う。カタックはスーフィー・ダンスのような旋回に特徴があり、イスラーム教の影響をモロに受けているような印象を受けるのだが、バラタ・ナーティヤムの動きは、インドの寺院の彫刻の1シーン1シーンのようなカクカクした動きである。マニアックな例えをすると、「サムライ・スピリッツ」という格闘ゲームに出てくるタムタムのような動きである。腰や太ももの筋肉がすごい要りそうだ。カタックとバラタ・ナーティヤムのそれぞれの特徴を比較することができて、なかなか楽しかった。
4つめは「Krishna Rang(クリシュナの色)」。8人の女性カタック・ダンサーが登場し、「Devdas」でマードゥリー・ディークシトとアイシュワリヤー・ラーイが踊ったような踊りを踊っていた。しかし8人のレベルに差があるのか、なんかアンバランスな印象を受けた。
本日のトリは「Chitra Vichitra(特別な絵画)」。これも絵と踊りの融合を試した演目で、プラシャーントという画家が次々に絵を描く傍ら、4人のカタック・ダンサーが踊っていた。だが、絵を描くといっても、ただキャンバスにペンキで色をベッタリと塗っていくだけだったし、踊りもこれといってトリを務めるほどのものではないと感じた。というか、絵に集中していると踊りが見れないし、踊りに集中していると絵が見れないという板ばさみ状態で、目が忙しかった。どうも踊りと絵を融合させるには、もう少し工夫が必要かもしれない。例えばダンサーは真っ白な服を着て、その服に画家がペンキで色を塗っていったりするといいかもしれない。
昨日から一気に4本の新作ヒンディー語映画が封切られた。インド映画ファンとしては、どれから見に行こうか嬉しい悲鳴である。今日はまず「Satta」を見に行った。
「Satta」とは「パワー」という意味。副題は「The Game of Power」。政治家の権力闘争を描いた映画で、キャストはベテラン揃い。ラヴィーナー・タンダン、サミール・ダルマーディカーリー、ヴァッラブ・ヴィヤース、ゴーヴィンド・ナームデーヴ、アトゥル・クルカルニーなど。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
左からゴーヴィンド・ナームデーヴ、
アトゥル・クルカルニー、ラヴィーナー・タンダン、
ヴァッラブ・ヴィヤース、サミール・ダルマーディカーリー |
● |
| Satta |
政治に全く関係のない生活をしていたごく普通のOLアヌラーダー(ラヴィーナー・タンダン)は、有力政治家の息子ヴィヴェーク・チャウハーン(サミール・ダルマーディカーリー)と結婚したことにより、人生が全く変わってしまった。ヴィヴェークは政治のことにしか興味のない短気な男で、家庭を顧みようとしなかった。また、彼の父親で、政界から引退したものの未だ絶大な影響力を誇るマヘーンドラ・チャウハーン(ヴァッラブ・ヴィヤース)は、アヌラーダーの人権をほとんど無視した高慢な態度をとっていた。
州議会議員の選挙が間近に迫る中、アヌラーダーに転機が訪れる。彼女の夫ヴィヴェークは酔っ払って酒場で殺傷事件を起こし、留置所に入れられてしまう。マヘーンドラの選挙区からはヴィヴェークが後継者として出馬する予定だったが、それが不可能になる。そこでその妻アヌラーダーが担ぎ出されることになった。アヌラーダーはしぶしぶ承諾し、突然政治の世界に飛び込むことになる。また、アヌラーダーの相談役として、ヤシュワント・ヴァルデー(アトゥル・クルカルニー)がつくことになる。
最初アヌラーダーは選挙運動という慣れない仕事に戸惑うが、次第に自分の主張をしっかり話せるようになる。有権者の支持も集まり、彼女は見事当選する。しかしアヌラーダーはチャウハーン一家の傀儡となるつもりはなかった。アヌラーダーは独自の路線へ走り出し、遂にチャウハーンのライバル、リヤーカト・アリー・ベイグ(ゴーヴィンド・ナームデーヴ)やヤシュワントと組んで、新しい党を作る。出所したヴィヴェークは怒り、アヌラーダーと離婚し、何とか彼らの邪魔をしようとするが、何者かに殺害される。
この頃アヌラーダーはヤシュワントと恋仲になっており、ベッドを共にしたこともあった。しかし、最も危険な男はヤシュワントだった。彼も結局権力の虜となった男だった。州首相の座を巡ってヤシュワントとベイグはまだ醜い争いを繰り広げていた。そしてヴィヴェークを殺させたのはヤシュワントであることがアヌラーダーに知れてしまう。遂にアヌラーダーも政治家を信用することは全くできないことを悟り、一計を案じる。アヌラーダーはベイグに接近してそそのかし、ヤシュワントを殺させ、そしてその事件の真相を切り札に使ってベイグを政界から追放する。こうしてアヌラーダーは、普段から尊敬していた穏健派の老政治家アンナーを州首相に擁立する。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
政治をテーマにした映画だったので、細かい部分の言葉を理解するのに難易度は高かった。しかし政治の世界でやってることはどこでも一緒なので、分かり易い映画とも言えるかもしれない。登場人物が多かったのだが、皆個性的で、混同することは全くなかった。
普通の女性が政治家に突然転進するということで、日本の政界でも聞いたことがあるようなストーリーである。果たして現実世界でそういう女性が有権者の支持を得られるのかは分からないが、これは映画。アヌラーダーは一気に人気者となった。その後、彼女は政界の汚ない権力闘争を否応なしに見せ付けられ、最初は嫌悪感を抱き、その嫌悪感はずっと続くのだが、最後に彼女は使命感に目覚め、政界の毒蛇たちを一掃する。その方法は「毒をもって毒を制す」やり方であった。
ラヴィーナー・タンダンは、普通の女性の姿と、毅然とした政治家の姿をうまく演じ分けていた。特にうまいと思ったのは、義父のマヘーンドラから「ヴィヴェークの代わりに立候補してくれないか」と頼まれたときの表情。しかしラヴィーナーももう老けてしまっているので、あまり未婚の役が似合わなくなって来た。
脇役陣は曲者俳優ばかり。個人的に好きなのはヤシュワントを演じたアトゥル・クルカルニーである。彼は「一見善人そうだけど、その人当たりのいい笑顔の裏に悪魔が潜んでいる」という役がすごいうまい。今回も最初は善人っぽい役だったのだが、後半で実は悪人であったことが分かる。「Dum」の悪徳警官役もまだ印象に残っている。
総合的に見てなかなかよく出来た映画だと思った。僕は最近ヒングリッシュ映画に目を奪われていたが、ヒンディー語でも既存のインド映画の枠をはみ出た、良質の映画が作られ始めている。2003年は言語にこだわらず、ヒングリッシュ映画よりももっと大きな視点でインド映画を見ていかないといけなくなるかもしれない。
| ◆ |
2月8日(土) Vasantotsava 2003 第4夜 |
◆ |
カラーシュラム主催の毎年恒例イヴェント「Vasantotsava」、今日は最後の日である。大トリを務めるはカラーシュラムの主催者パンディト・ビルジュー・マハーラージと、オリッスィー・ダンスの大御所中の大御所ケールーチャラン・モハーパトラ。これを見なければデリーに住んでいる意味がないと言っても過言ではない。Vasantotsava自体は6時半から始まったが、僕は用事があったため、9時頃会場に到着した。僕が着いたときにちょうどビルジュー・マハーラージがステージに出てくるところだった。間に合った!
今夜のマハーラージは踊る踊る。まさに「ビルジュー 踊るマハーラージ」。僕が今まで見てきたマハーラージの中では、もっとも長時間激しく踊ってくれた。若いカタック・ダンサーと比べて、踊りにダイナミックさがないように感じたが、身体のしなやかさ、表現力は他の追随を許さない。しかも観客の反応を大事にする人で、所々で受けを狙いつつ踊っているのもさすが。インド最高峰のダンスを見ることができ、会場は感動に包まれていた。
マハーラージのソロ・ダンスの後、オリッスィー・ダンスの大御所ケールーチャラン・モハーパトラと、カタック・ダンスの大御所ビルジュー・マハーラージの共演を見ることができた。マハーラージの誕生日は1937年2月4日、今年で66歳、ケールーチャランの誕生日は1926年1月8日、今年で77歳。2人ともはっきり言って老人である。しかしまだまだ現役のダンサーとして踊ることができるくらい身体が動く。これだけでも驚きである。
| ● |
|
● |
|
● |
|
 |
|
 |
|
| ● |
ケールーチャラン・モハーパトラ |
|
ビルジュー・マハーラージ |
● |
見たところ、おそらくマハーラージがクリシュナ役、ケールーチャランがクリシュナの母親ヤショーダー役だった。クリシュナが宙吊りの壺からギーを盗もうとしているシーンなどがダンスで表現されていた。僕はオリッスィー・ダンスを見るのは初めてだったのだが、ケールーチャランの方も老齢のためかあまり激しい動きをしなかったため、あまりオリッスィー・ダンスの特徴を掴むことができなかった。だが、ケールーチャランの踊りはまるで体重がないかのような、軽やかなステップだった。喜寿を迎えてもあれだけ軽快に踊ることができるとは・・・。
ダンスの中で2人は花びらをお互いに掛け合ったり、抱き付き合ったりと、何だか老人2人の不思議な空間が醸し出されていた。そういえばマハーラージは両刀使いとの噂を聞く。抱きつくシーンはやたらと真に迫っていたな・・・ウゲ。
ダンスが終わった後はスタンディング・オヴェーション。拍手は鳴り止むことがなかった。今回の公演を見て思ったのは、やはり芸術は老齢に達して初めて大成されるものであることだ。少なくともインド人はそう考えている。若さ溢れるダンスもいいのだが、そういうダイナミックさはしばしば「無駄な動き」になってしまうことがある。そういう無駄な動きがそぎ落とされた2人の老ダンサーの踊りは、まるで天に昇るかのような神々しい踊りだった。
だから、日印の文化交流機関も、もし日本からインドへアーティストを招待しようと思ったら、若者ではなく老人を招いた方がインド人受けがよいのではないだろうか?若者のパフォーマンスを見ても、目の肥えたインド人は「若いのが頑張ってる」くらいに感じるだけで、日本の文化を知ってもらうレベルまで到達しないと思う。最近の日本では「10代の天才歌手」みたいな早熟のアーティストがもてはやされる傾向にあるが、芸術というのは年月と共にじっくり熟成されていくものであることをもう一度自覚した方がいいと思う。
今日から南アフリカでクリケットのワールド・カップが始まった。開会式は昨日だったが、時差の関係でインドでは昨夜の真夜中の12時に開始されたので、事実上インドでは今日から始まったと言っていいだろう。朝からブラス・バンドが街中を行進していたのだが、あれはワールド・カップ開始を祝ってのパレードだったかもしれない。クリケット狂のインド人にとって、これからの1ヶ月半は寝ても覚めてもクリケットという生活だろう。
どこから入れ知恵したのか知らないが、日本のサッカー・ワールド・カップ期間中のように、デリーのレストランでは「クリケット・ワールド・カップ観戦キャンペーン」みたいなことをどこもやっている。ワールド・カップ特別メニューなんかをこしらえたりしていて、そういう気合の入り方を見ていると、なんだか去年のサッカー・ワールド・カップの興奮が蘇ってくるようだ。しかし日本に住んでいたら、クリケットのワールド・カップが行われていることなんて誰も知らないだろう・・・。
クリケット・ワールド・カップに対抗するつもりなのか、たまたま重なってしまったのか、ワールド・カップ期間中には多くの映画が公開される。今週から封切られた映画も4本ある。今日はPVRアヌパム4に新作映画「Khushi」を見に行った。
「Kushi(喜び)」は、ヒット作にあまり恵まれないながらも未だ飛ぶ鳥を落とす勢いのカリーナー・カプールと、デビューから4、5年経つにも関わらず人気いまいちで伸び悩むファルディーン・カーンの映画である。他にアムリシュ・プリー、ジョニー・リーヴァルなどが出演していた。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
カリーナー・カプール(上)と
ファルディーン・カーン(下) |
● |
| Khushi |
カラン(ファルディーン・カーン)はコールカーター育ちのひょうきんな若者、クシー(カリーナー・カプール)はガルワール育ちの純粋な女の子だった。2人は運命に導かれてムンバイーの同じ大学に入学し、クラスメイトとなる。2人は出会ったときからお互いに惹かれあうものを感じるが、なかなか友達の関係から踏み出せずにいた。
そんな中、カランの友達のビッキーが、クシーの友達のプリヤーに恋をしていることが分かる。カランとクシーは2人をくっつけるために協力し、2人は見事恋人となる。しかし依然としてカランとクシーは友達のままだった。
カランはクシーが自分のことを好きなのを知っていた。クシーもカランが自分のことを好きなのを知っていた。しかし2人はプライドと恥からいつも口喧嘩で終わってしまう。その内イライラがつのり、2人は絶交状態となってしまう。
一方、プリヤーの父親はマフィアのような男だったので、ビッキーたちの恋愛もうまく行かなかった。とうとうプリヤーの父親は彼女の結婚を勝手に決めてしまう。カランとクシーは絶交状態ながらも、彼らの仲を取り持つのは自分たちの責任だと考え、協力して彼らを駆け落ち結婚させる。
大学も終わり、カランはコールカーターに、クシーはガルワールに帰ることになる。しかし最後の最後で2人は自分の気持ちを伝えることを同時に決意し、カランはクシーの乗るガルワール行きの列車へ、クシーはカランの乗るコールカーター行きの列車へ行く。だが2人は行き違いになってしまう。そこで2人は置き手紙を残して去って行った。その手紙には、今まで言おうとしても言えなかった愛の告白がつづられていた。その手紙を見た2人は涙する。
ガルワールに戻ったクシーを待っていたのは、彼女の結婚式の準備だった。クシーは戸惑うか、結婚相手を見て驚く。それはカランだった。カランはクシーの手紙を見て列車から降り、飛行機でガルワールまで直行していたのだった。カランとクシーは抱き合って喜ぶ。2人の間には17人もの子供ができたそうな。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
正統派インド映画。男女の出会いからストーリーが始まり、2人の結婚でストーリーが終わる。こういう映画を何度も見ていると飽きてしまうが、最近こういう普通のインド映画があまりなかったため、かえって新鮮な印象を受けた。分かりやすいラヴ・コメディーで、言葉が分からなくても理解できるだろう。音楽、ミュージカル・シーンも上質。カリーナー・カプールも自分の得意な役柄をのびのびと演じており、久々にインド映画的気持ちよさと共に映画館を出ることができた。
やはりカリーナー・カプールはいい。よく分からないけどいい。最初カリーナーを見たときはあまりピンと来なかったのだが、だんだん彼女の価値が分かってきた。こういう女優は、インド映画にいつの時代にも必要な人材である。コミカルな演技ができて、下手に演技派を目指さず、踊りも無難にこなし、お色気シーンも難なくこなせる。それに姉のカリシュマー・カプールにはなかったカリスマ性がある。カリーナーが出ていれば、どんなクソ映画でも見たくなる、そういう気分にさせてくれる不思議な女優である。
ファルディーン・カーンもカリーナー・カプールに合わせてコミカルな演技をしていた。彼は悪くはないのだが、どうもインド映画の男優に必要な素質の何かが欠けているように思えてならない。彼について語る際、必ず文の最後に「・・・のか?」と付けたくなる。ファルディーンはかっこいい・・・のか?ファルディーンの演技はうまい・・・のか?ファルディーンの踊りはうまい・・・のか?という具合に。
悪役を演じることの多いアムリシュ・プリーだが、今回はコミカルな父親役に徹した。ガルワールの田舎からムンバイーに出て来たときの顛末などは爆笑もの。やはりうまい俳優だ。ジョニー・リヴァールの登場機会も多く、大いに笑わせてもらった。
はっきり言って、ほとんど主人公のカランとクシーの行き違う恋愛だけで3時間ももたせることができたことが一番すごいと思った。やろうと思えば10分20分で2人の出会いから結婚まで描けたと思うのだが、それを3時間映画に引き伸ばしてしまうところがインド映画のすごさだろう。ジョニー・リーヴァルのギャグ・シーンが多かったのは、それが原因なのかもしれない。また、無意味に長いシーンも多かった。途中で、サーリーを着たクシーがベンチに座って勉強をしており、その横でカランがクシーの腰をじっと眺めるシーンがあるのだが、その腰のシーンがやたら長い。カリーナー・カプールの露な腰(サーリーを着ていると腰から腹にかけて露になるのはご存知の通り)がシネスコ・サイズでず〜っと映し出されるのだ。しかもその腰はじっとりと汗ばんでいる・・・。クシーはカランが自分の腰を見ていることに気付いて怒り、その事件は後々まで尾を引くのだが、あのカリーナーの腰は2003年のインド映画迷シーンのひとつに数えられるだろう。
音楽監督はアヌ・マリク。彼の音楽は当たり外れが激しいと思うのだが、「Khushi」の音楽はミュージカルと合わせて当たりだと思う。まずカリーナーの登場シーンで「Khushi Aayee Re Aayee Re」が流れるのだが、その歌のサビ直前の「チュッチュッチュッチュッチュ・・・(キスの音)」が秀逸。もちろんその音に合わせてカリーナーがキスの仕草を観客に向けてして来る。また、このときのカリーナーは半袖半ズボンの上に水の中で踊っているので色っぽい。特に太ももの付け根の日焼けしていない部分がいやらしい。全てが計算されて作られているかのようだ。
ファルディーン・カーンの登場シーンに流れるのは「Good Morning India」。ハウラー橋、ヴィクトリア記念堂、地下鉄など、コールカーターの観光名所をバックに踊っていたのが新鮮だった。近い内にデリー・メトロも映画に登場することがあるだろう。
後半の一番最初に流れる「Hai Re Hai Re」は、おそらく「Khushi」の中でもっとも出来のいい歌であると同時にミュージカル・シーンもギャク満載。ファルディーンとカリーナーがヒッピーやら警官やらカウボーイやらヒップホップ・ダンサーやら、いろんな仮装をして登場するので、観客には大受けだった。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
ヒップホップ・ダンサー・・・? |
● |
インド映画をインド映画として見ることのできる人なら、「Khushi」は必ず楽しめる映画だ。ヴァレンタイン・デイにピッタリの映画なので、もしかして少しはヒットするかもしれない。
| ◆ |
2月12日(水) クリケット・ワールド・カップ白熱中 |
◆ |
2月8日から南アフリカ共和国で始まったクリケットのワールド・カップ。インド人の大半はクリケット狂であることから、インドでも連日試合の様子が放映されている。
果たして日本でクリケット・ワールド・カップはどういう報道のされ方をしているのか、少しネットで調べてみたが、それはもう可哀想なくらい全く相手にされていないようだ。スカイ・パーフェクトTVでも試合が見れない状態らしい。世界で最も競技人口の多いスポーツはサッカーだが、2番目はクリケットである。野球よりも断然メジャーなスポーツなのだ。それほど人気のあるスポーツのワールド・カップが行われているというのに、日本では試合を見ることもできないとは・・・。大半の日本人はクリケットなんかに興味ないと思うのでいいのだが、日本に住んでいるクリケット大好き外国人たちが可哀想だ。
インドに住んでいるとどうしてもインド・チームのサポーターになってしまうが、インド近隣諸国の様子も気になる。まず月曜日にはスリランカがニュージランドに勝ち、火曜日にはパーキスターンがオーストラリアに大敗し、バングラデシュがカナダに負けた。特にパーキスターンの敗北はインド人には小気味良かったようで、うちのジャイナ教の大家さんはパーキスターンの敗北が決まった瞬間、「鶏を殺さなきゃいかんな」とつぶやいた。インドで鶏を殺して食べるのは、何かめでたいことがあったときのみである。不殺生主義のジャイナ教徒が何という残虐なことを言うのか、と驚いた。
今日はインド対オランダの試合があった。オランダはクリケットの世界では新参者のようで、インド人たちも「訳の分からない国が対戦相手になった」となめ切っていた。試合はまずインド・チームのバッティング(防御)で、サチン・テーンドゥルカルが52ランと健闘し、合計204ランを上げた。この数字は決して油断のならないポイントなのだが、やはりオランダはあまり強くなくて、136ランしか取れなかった。よって結局インドが余裕で勝利を収めたことになる。
今日はちょうどイスラームの祭日イード・ウル・ズハー(犠牲祭)で、国民の祝日となっていた。イスラームの街では大量のヤギが殺されてアッラーへ捧げられていた。だが、インド戦が行われているときは街は静かで、インドのバッティングが終わると再び賑やかになり、またインドのボウリング(攻撃)が中盤ぐらいに差し掛かると静かになり、インドの勝利が確定すると賑やかになった。しかし、白熱した試合でもなかったため、それほど熱狂的な盛り上がりではなかった。
インドに住む日本人をクリケットで分類すると、きれいに2つに分かれる。つまり、インドに来てクリケットが好きになる人(実際にプレイするかしないかは別として)と、「クリケットなんてつまらん」と言い張って歯牙にもかけない人だ。僕は最初ルールがあまりよく分からなかったのだが、2001年に公開された映画「Lagaan」を見て何となく骨格を掴むことができ、TVで試合を何となく観戦している内に何となく分かってきた。ルールが分かるとクリケットはけっこう楽しい。今ではけっこうクリケットのファンである。
なぜクリケットが楽しいかというと、まずインドではクリケット選手というのは映画スターと同等またはそれ以上のカリスマであるからだ。日本で言えば巨人の選手みたいなものだ。TVCMなどにもよく出演するし、クリケット選手のグッズも売られている。クリケットについて知っていると、インド生活が1割2割楽しくなること請け合いである。インド人と話を合わすこともできるようになるのも嬉しい。
クリケット自体も魅力的なスポーツだ。その歴史は優に2、300年あり、「Lagaan」の舞台設定は決して絵空事ではない。イギリスの国技で、紳士のスポーツ。野球と違い、投球側が攻撃で、打球側が防御である。1チームは11人。打者は後ろに立てられた3本の棒(ウィケット)を命懸けで守らなければならない。ウィケットはフィールドに20m間隔で2つ立てられており、打者は投球者の投げるボールを打ち返し、ボールが返って来る間にウィケットとウィケットの間を走って点を稼ぐ。しかし野球のように1人で走るわけではない。別のウィケット側にはもう1人打者が待機しており、彼も同時に向かい側のウィケット目掛けて走らなければならない。打者がウィケットを離れているときに野手がウィケットを破壊したら1アウト。実際に打つ打者(ストライカー)と、向かい側に待機している打者(ノンストライカー)の息が合わないと、すぐにアウトになってしまう。また、打者が打ったボールを、攻撃側の野手がノーバウンドでキャッチすればそれもアウトになるが、野手はグローブを使ってはいけないため、クリケットの固いボールを素手でキャッチしなければならない。かなり痛そうだ。もちろん投球者のボールが直接ウィケットを破壊してもアウトだ。打者がウィケットの間を走って、向かい側のウィケットまで辿り着いたら1点、打ったボールが転がってフィールド外へ出たら4点、ノーバウンドでフィールド外へ出たら6点である。10アウトで1イニングが終わる。大体これだけ知っていればクリケットの試合を楽しむことができるだろう。また、投球者は6球(1オーバー)ごとに交替しなければならず、国際マッチでは50オーバーが1イニングとなっている。つまり、投球者が300球ボールを投げた時点でも1イニングが終わる。
「Lagaan」が日本で一般公開してまずまずのヒットを収めれば、もしかして何かの雑誌が「クリケットとは何ぞや?」みたいな記事を掲載し、一瞬だけでもクリケット・ブームが起こるかと期待していたが、「Lagaan」はどうも一般公開されないようだ。やはりオスカーを取り逃したことが大きな痛手となった。あのとき「Lagaan」がオスカーを取っていれば、歴史は変わっていたかもしれない。
3月1日は伝説のインド対パーキスターン戦。とりあえずここ最近で最も危険な日である。
意外に思われるかもしれないが、インドでもヴァレンタイン・デイはちゃんと祝われる。デリー各地にチェーン展開するグリーティング・カード屋のアルチーズが先導する形で積極的に街をヴァレンタイン・デイ化しており、各地のマーケットではヴァレンタイン・デイにかこつけた冬物処分セールが行われていた。ちなみにインドではヴァレンタイン・デイはVデイと略されている。
ヴァレンタイン・デイは世界各国2月14日ということで変わりないが、内容は大分違うようだ。日本では女の子が男の子にチョコレートをあげる日だと記憶しているが、インドではどうも男の方が女の子に何かプレゼントをあげないといけないようだ。チョコレートやバラの花などが一般的なプレゼントのようである。ヴァレンタイン・カードは相互に渡すものらしい。ヴァレンタイン・デイにアルチーズへ行くと、2〜3000ルピー相当のプレゼントを一気に買って行くインド人の男の姿を目撃することができる。
実は3、4日前にはチョコレート・デイというものがあった。この日は同性の友達にチョコレートを渡す日らしい。その日、大家さんの息子のスラブが急に僕を外に連れ出して、駄菓子屋でチョコレートを物色し始めたので、僕はてっきりヴァレンタイン・デイに誰かにあげるために買っているのだと思い、「誰にあげるつもりなんだ?」とからかってみたら、「兄さんにあげるんだ」と真顔で言われて焦った。冗談だろうと思ったが、本当に彼の買った20ルピーのチョコレートは僕に手渡されてしまった。インドにはチョコレート・デイなるものがあると説明されてやっと半分理解できたが、なぜそんな日をわざわざ作ったのか、ますます不思議にもなった。さらにその3、4日前にはフラワー・デイというものもあり、この日は友達に花をプレゼントする日だったらしい。そういえばラクシャー・バンダンの近くにフレンドシップ・デイという非常に似通ったお祭りが行われたりする。ただでさえインドは祭りの多い国なのに、どんどん勝手に祭りの数を増やしているような気がする。
最近のデリーのヴァレンタイン・デイともなると、もうかなりカップル文化が発達してきたと言わざるを得ない。デリーいちのショッピング・モール、アンサル・プラザでは当然のごとくヴァレンタイン・デイ・セールとイヴェントが行われており、多くのカップルが集っていた。僕は直接見なかったのだが、僕が立ち去った後、アンサル・プラザでヒンドゥー・ナショナリストたちのアンチ・ヴァレンタイン・デイ運動が展開されたらしい。ヴァレンタイン・カードを燃やしたりして、それはもう大変な騒ぎだったようだ。彼女のいない男もヤケクソになって一緒に燃やしたりしたとかしなかったとか。
PVRアヌパム4マーケットもすさまじい数のカップルが集合していた。PVRアヌパム4の屋根の上ではなぜかインド人の生バンドが洋楽を演奏をしており、全く訳が分からない状態。ここにはバーが7つほどあるのだが、全て満席状態だった。とにかくどこのモダン・マーケットも相当な混雑ぶりだったことだろう。インドも変わったものである。
現在南アフリカ共和国で行われているクリケット・ワールド・カップ。2月15日に行われたオーストラリア戦でインド・チームは歴史的大敗を喫してしまい、インド国民の怒髪天を突いた状態だ。いくらオーストラリア・チームが強いからって、あの負け方はひどかった。インド125/10に対し、オーストラリア128/1である。つまり、インド・チームが125点取るのに10人費やしたのに対し、オーストラリアは3人で128点取ってしまったということだ。予選リーグを勝ち残るためには、とにかく勝ち続けるしかない状態なので、インド・チームにはめげずに頑張ってもらいたいものである。
現在インドではクリケット関連商品が多く売り出されている。もっとも意表を突いたのがペプシ社のブルー・ペプシ。インド・チームと同色の青色をしたペプシである。青色の飲料なので、毒薬のような外見なのだが、案外普通に飲める。味は普通のペプシより炭酸が低く甘いような気がする。このブルー・ペプシと、オールド・モンク(ラム酒)を混ぜると緑色になり、ちょっぴりオシャレなカクテルという感じになるので、最近好きである。
どこの国も考えることは同じで、ワールド・カップの応援歌CDもいくつか発売されていた。過去の名曲の中から応援歌っぽい雰囲気の曲を寄せ集めただけのものから、オリジナル曲も入っているものまで様々だが、その中でも目に付いたのは、「Adnan Sami's Aa Yeah O!」というCDだ。最近TVCMでもよく流れている曲「Aa Yeah
O!」が中心に構成されたCDである。「Aa Yeah O!」はみんなで合唱したくなるような曲で、応援歌にピッタリだ。CMの中ではインド・チームの選手や、自慢のヒゲをインドの国旗色に染めたアミターブ・バッチャンが登場し、非常に豪華である。アドナーン・サーミー自身もクリケットの審判の格好をして歌い踊っている。この曲の他は、「Lagaan」の「Chale Chalo」や、「Phir Bhi Dil Hai Hindustani」の「I'm the Best」などのインド映画の曲や、最近インドで大流行の「The
Ketchup Song」、リッキー・マーティンの「The Cup of Life」などの洋楽が入っている。ワールド・カップ抜きにしても割とお買い得かもしれない。
だが、ひとつ非常にひっかかることがある。アドナーン・サーミーはパーキスターン人ではなかったか?パーキスターン人がインド・チームの応援歌を歌っていいものなのだろうか?これはまるで韓国人歌手が日本のサッカー・チームの応援歌を歌うような売国奴的行為なのではなかろうか?
非常に気になったので調べてみたら、アドナーンはイギリス生まれのパーキスターン人だった。父親はパーキスターン人、母親はインド人、現在アメリカのヒューストンに在住とのことなので、あまり国籍とは関係のない生活をしている人なのかもしれない。誕生日は1973年8月15日。今年で30歳。誕生日がインド独立記念日と同じというのは、やはりインドに関わりが強い運命にあるのかもしれない。
| ◆ |
2月19日(水) Escape From Taliban |
◆ |
2月に公開される映画の中で、僕が最も注目していた映画がこの「Escape From Taliban」だった。マニーシャー・コーイラーラー主演で、一昨年、昨年と話題をさらったアフガニスタンのイスラーム原理主義政権タリバーンがメイン・テーマになっている映画である。タイトルを聞いただけでも興味をそそられるではないか。あらすじをチラッと耳にしたところ、アフガニスタンへ嫁いだインド人女性がタリバーンからインドに逃げて来るという、実話を元にした映画とのこと。実際の見聞どころか実話が元なのできっと生々しくて新鮮なアフガニスタンの描写があるに違いない。そしてきっとヒットするに違いない。非常にワクワクしながら公開を待ち焦がれていた。やっとのことで先週の金曜日から封切られたのだが、蓋を開けてみてビックリ。デリーでは3館しか上映されていないという意外な縮小公開ぶり。俄かにクソ映画の臭いがプンプンし始めた。PVRなどのシネマ・コンプレックスで公開される映画はある程度の質が期待できるのだが、公開初週にも関わらず上映映画館数が少ない映画は、十中八九クソ映画であるというのが今までの経験から得た法則である。しかし悲しいかな、期待の映画のなりの果てを見届けたくて、今日、パハール・ガンジ近くのシーラー・シネマへ足を運んだ。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
マニーシャー・コーイラーラー |
● |
| Escape From Taliban |
アフガニスタン人のジャーンバズ(ナワーブ・カーン)と駆け落ち結婚したインド人(ヒンドゥー教徒)のスシュミター(マニーシャー・コーイラーラー)は、家族を捨て、故国を捨ててアフガニスタンへやって来た。しかし彼女が見たアフガニスタンはまるで地獄だった。タリバーンの圧政のもと怯えながら暮らす人々、毎日のように繰り返される殺人、女性はまるで子供を産むためだけに生まれてきたような扱いをされ、夫の家ではヒンドゥー教徒ということで厄介者扱いだった。しかも一番耐え切れなかったことは、スシュミターは実はジャーンバズの2人目の妻だったことだ。とうとう耐え切れなくなり、スシュミターはインドへ何度も脱走を試みる。しかしジャーンバズ一家の執拗な追跡により全て失敗に終わる。一度はパーキスターンまで逃れることができたのだが、インド大使館もアフガニスタン大使館も彼女に救いの手を差し伸べようとはしなかった。
それでも諦めないスシュミターは真夜中に家を抜け出す。途中タリバーン兵たちに見つかるが、それでも逃げる。危機一髪のところで彼女を助けたのは、ジャーンバズ一家の長ドラヌイおじさんだった。彼はスシュミターをパーキスターン国境まで連れて行き、インドへの航空券とパスポートを渡して彼女を逃がしてやる。こうしてスシュミターはインドへ帰ることができたのだった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
分かっていた・・・分かっていたんだ、クソ映画だということは・・・しかし見てしまった・・・貴重な金と時間を割いて・・・。いったいどうしたらこんな完成度の低い映画を作ることができるのだろうか?題材は非常にいいと思うし、キャストも悪くなかった。それなのにこんなクソ映画が出来上がってしまったか・・・。こんな映画を作って見せられるぐらいだったら、僕がその映画の予算・キャスト・題材を使ってもっといい映画を作りたくなったくらいだ。
まずロケ地のほとんどはラダックで、アフガニスタン突撃現地ロケではなかった。それはそれでいいとしよう。僕もラダックには行ったので、あの希薄な酸素の中でよく走ったり踊ったりしたもんだと感心した。が、なぜアフガニスタンの風景の代わりにラダックを選んでおいて、わざわざラダックの名所であるラマユル・ゴンパを映すのか?そんなことしたらアフガニスタンにいる気分じゃなくなってしまうではないか?ラダックをアフガニスタンの風景に見せかける努力をもっとすべきではないのか?道の途中にアラビア文字を書いた紙を張っても何の意味もない。そのせいで、この映画における時代考証、現地の風習、マニーシャーらの身に付けていた現地風の衣装などを全く信用できなくなった。
途中で砂丘砂漠のシーンも何度か挿入された。見てすぐに特定できた。ラージャスターン州のジャイサルメール近くにあるタル砂漠だ。よくインド映画に出てくるところなので、別にそこを使ったことに文句を言うつもりはない。しかしその砂漠は悲しいほどに足跡だらけなのには文句を言わせてもらう。映画を撮るときぐらい、1日ぐらい前から砂漠に人を入れるのを規制させて、キレイな砂漠で撮影して欲しかった。
タリバーンの一方的な描写の仕方にも幻滅した。まるで「インディー・ジョーンズ」に出てくるナチスのような、「パール・ハーバー」に出てくる旧日本軍のような、絵に描いたような悪役像をそのまま押し付けられた形だった。タリバーン兵たちは本当にこんな残虐なことを日常的にしていたのだろうか?本当だったら申し訳ないのだが、僕は違うと思う。タリバーン兵の全員が全員手当たり次第に銃をぷっ放して殺戮の限りを尽くしていたわけではないだろう。僕はもっと違った描写の仕方を期待していたのだが・・・。オサマ・ビン・ラディーンやオマル師が友情出演していたら、この映画の評価もガラリと変わったと思うが無理か。
何と言ってもこの映画の一番いけないところは、時間軸がはっきりしないこと。回想シーンがどこからどこまでかよく分からない。しかも昼と夜もあまりはっきりしない。突然夜から昼になったりするし、山の上を走っていたと思ったら次のシーンでは急に砂漠を走っていたりして、何が何だかよく分からない。編集が甘すぎる。いったい監督は何を考えているのか。ちなみに監督の名前はウッジャル・チャタルジー。
音楽監督はバーブル・ボースという人。僕はあまり聞いたことがない。映画がクソ映画なら、音楽もクソ音楽。全く取るに足らない音楽ばかりだった。踊りも大したことなかったし、振り付けもいい加減だったし、ミュージカル・シーンのカメラ・ワークもその低品質さに適したものだった。
クソ映画は文句の付け所ばかりで疲れるから困る。最後にマニーシャー・コーイラーラーに文句を言っておこう。マニーシャーよ、どうしてよ〜く監督の才能を見極めてから、よ〜く脚本を読んでから映画を選ばないのだ?最近の君の出る映画は、君の女優のイメージを損なう映画ばかりだよ・・・。しかしどうしてマニーシャーがこの映画に出たかったかは容易に推測できる。彼女は抑圧された女性の立場を訴えるのが好きなのだ。おそらくマニーシャーは2001年に公開された「Lajja」と同じ目的でこの映画に出演したのだろう。「Lajja」はまだ悪くなかったが、この映画に出演しちゃったのは絶対に将来汚点になるだろうよ。
| ◆ |
2月21日(金) アーグラー・サンスターン視察旅行 |
◆ |
僕が現在通っているヒンディー語の語学学校ケーンドリーヤ・ヒンディー・サンスターンの本部は実はアーグラーにある。デリーのサンスターンは支部に過ぎない。その他サンスターンの分校はインド各地に点在しており、ヒンディー語普及のために尽力している。周知の通り、数百の言語が話されているインドは、公用語の設定が非常に難しかった。いろいろ紆余曲折はあったものの、最終的にヒンディー語が第一公用語としての地位を確立し、非ヒンディー語圏の人々にヒンディー語を普及させる機関が必要となった。ケーンドリーヤ・ヒンディー・サンスターンはその目的を達成するために設立された政府系の学校である。当初はヒンディー語を母語としないインド人へのヒンディー語教育が主だったが、やがて海外に住むインド系移民たちを中心に外国人にも門戸が開かれ、現在アーグラー本校とデリー校は外国人が入学することができる。よって、アーグラー・サンスターンでも多くの外国人がヒンディー語を勉強している。
僕は日頃から、デリー・サンスターンの学生とアーグラー・サンスターンの学生の交流会のようなものがあればいいのに、と思っていた。デリーとアーグラーはそれほど遠くないにも関わらず、今までそういう機会がほとんどなかった。去年の11月にリシケーシュ・ツアーへ参加したとき、一応アーグラー・サンスターンの学生たちと出会うことができた。しかし、あのツアーはデリー、アーグラー、ヴァーラーナスィーなどに住む外国人留学生を対象としたものであり、サンスターンの学生同士の交流会ではなかった。
と思っていたら、急に一昨日デリー・サンスターンにサンスターンのディレクター(一番偉い人)が来て、「明後日デリー・サンスターンの学生たちは、アーグラーへ来るように」との通達を出した。こうして急転直下、デリー・サンスターンとアーグラー・サンスターンの交流の場が設けられることとなったのだった。
しかし話が急だったため、また集合時間が朝の6時だったため、デリー・サンスターンから参加できる人はそれほど多くなかった。50人ほどいる学生の中からアーグラー行きに参加する人は9人のみだった。国別に見ると、日本人3人、韓国人2人、ウクライナ人2人、イラン人2人だった。もちろん僕は参加することになった。先生1人が同伴し、トヨタのクオリスで早朝アーグラーへ向かった。
朝6時過ぎにデリーを出発し、ずっとマトゥラー・ロードを通って南下。途中朝食休憩、パンクのためのタイヤ交換などを経て、10時過ぎにはアーグラーへ到着することができた。デリーでケーンドリーヤ・ヒンディー・サンスターンはあまり有名ではないのだが、アーグラーでは誰もが知っていると言っていいほど有名で、ちゃんと道路に看板も出ていた。案外アーグラー郊外に位置しており、スィカンドラーから自動車で5分ほどのところにあった。
デリー・サンスターンは、去年の7月に移転して新しい建物になったとは言え、お世辞にも大きいとは言えない。しかしアーグラー・サンスターンはキャンパスと呼ぶべき広大な敷地を有していた。運動場があり、学生寮があり、校舎も広く、無駄に思えるほど部屋がたくさんあり、コンピューター・ルームまで存在した(使えないらしいが)。なんたる格差・・・。しかしアーグラー郊外にあるため、やることがなさそうだ。というか、たとえアーグラーの市街地にあったとしても、やることはないだろう。これだけの格差を目の当たりにしながらも、やはりデリーに住んでデリー・サンスターンで学ぶ方が僕が好きである。アーグラー・サンスターンと同レベルの設備と敷地がデリー校にあればそれが一番いいのだが、それをやってしまうと誰もアーグラーに来なくなってしまうので、あえてデリー校は小さく、という方針が取られているようだ。現在アーグラー・サンスターンでは56名の外国人が学んでいる他、インド各州から来た非ヒンディー語母語のインド人たちもたくさんいた。
| ● |
|
● |
|
 |
|
|
アーグラー・サンスターン |
|
|
 |
|
|
コンピューター室 |
|
|
 |
|
| ● |
視聴覚室(?)。
テレビやコンポなどがある。
ここで映画を見たりするらしい。 |
● |
今回アーグラー・サンスターンに外務省から何やらお偉いさんが来たようで、その歓迎会が行われた。それにデリー・サンスターンの生徒たちもついでに呼ばれた形だった。何か出し物をしなくてはいけないとのことなので、僕もヒンディー・フィルミー・ソングをギターで弾き語るつもりだった。しかも何かスピーチをする予定だった。ところがそのお客さんたちのスピーチがやたらと長すぎて、時間がなくなってしまった。だからパフォーマンスをしたのは数グループだけで、僕のギターの出番もスピーチの出番も省略されてしまった。緊張して損した・・・。
昼食はアーグラー・サンスターンの女子寮の食堂で食べさせてもらった。いわゆるターリーで、サブジー、ダール、ローティー、チャーワルなどなどが出され、自分で取っていくシステムだ。インドの一般的な寮の食事形態である。あちらの生徒の話では今日はやたらと豪華な食事が出されたらしい。アールー・ゴービー、ダール、パニール、ライターなどなどが出された。だが、正直な感想、「こんなもん食ってられるか〜!」と机をひっくり返したくなるような、お世辞にもおいしいとは思えない料理だった。アーグラー・サンスターンの人は毎日これ以下の食事をしているのか・・・。そう思うと人知れず同情の涙が溢れ出てくるのだった。
リシケーシュで仲良くなった人たちとも再会することができてよかったのだが、何しろ日帰りなのですぐにアーグラー・サンスターンを出なければならなかった。3時半にはアーグラー・サンスターンを出発した。
少し時間があったので、アーグラー観光をすることになった。ちょうどタージ・マホーツァヴァというバザーが行われていたので、タージ・マハルへ行くことにした。名前からタージ・マハルの中でフェスティバルが行われているのかと思っていたが、行ってみたらタージ・マハルの駐車場横の広場で行われており、タージ・マハルの方は金曜日で閉まっていた。だから外から眺めただけだった。しかし今年もタージ・マハルを拝むことができて嬉しかった(去年は多分来なかった)。
思うに、タージ・マハルは日本の富士山に似ている。色も似ているし、雄大さや繊細さも共通点がある。僕は富士山を見ると勇気付けられるのと同様に、タージ・マハルを見るととても心が引き締まる。これで何度目のタージ・マハルだろうか。もう数えるのが面倒なくらいタージ・マハルを見ているが、見れば見るほどもっと来たくなる建物である。
アーグラーのタージ・マハルは世界的に有名だが、インド人にとってアーグラーにはもうひとつ有名なものがある。それはペーターというミターイーである。カボチャでできた半透明の甘いお菓子で、ミターイー嫌いの僕も割と好きな味である。パーンチュミーという名前だったか、有名なペーターの店があるのだが、現在では同名の店がアーグラー中に乱立してしまっているそうだ。アーグラーに詳しい先生がその有名な店よりさらにおいしいというペーター屋に連れて行ってくれたので、大家さんへのお土産に買って行った。
アーグラーを発ったのは6時頃だった。だがこのアーグラーからデリーの道が本当に災難続きだった。デリーからアーグラーに来るときにも1回パンクしてしまったのだが、なんとアーグラー〜デリー間は3度もタイヤがパンクしてしまった。スペア・タイヤに交換しても、それがまたパンクしてしまうという最悪の状況。運転手がパンクしたタイヤを持って車をヒッチハイクしてパンク修理屋へ行き、またヒッチハイクして戻って来るということをしている内に時間はどんどん過ぎ去ってしまった。今日は夜9時半からフィルムフェア・アワードがあったので、それまでにデリーに帰りたかったのだが、結局自宅に帰りついたのは深夜1時。もうヘトヘトだった・・・。
昨年のちょうど同じ時期に、アヨーディヤーのバーブリー・マスジド跡にラーム・ジャナムブーミ寺院を建てるか建てないかという騒動が起こっていた。結局ヴァージペーイー首相の巧妙な舵取りにより決議は最高裁に委ねられ、寺院建設は延期ということになった。あれから1年経ち、アヨーディヤー問題が再燃している。23日にはアヨーディヤー問題を話し合う集会がデリーでもたれ、今日はVHPのメンバーやサードゥたちのパレードが国会周辺で行われた。とうとうVHPはヴァージペーイー率いる現政権に反旗を翻し、寺院建設を認めない政治家たちを相手に「現代の新たなマハーバーラタ戦争」を宣戦布告した。
果たしてバーブリー・マスジド跡にラーム・ジャナムブーミ寺院は建つのかどうか。現時点でそれは分からない。しかし建つべきなのかどうか。これは僕のような第三者でも議論することができる。特に僕は去年アヨーディヤーを訪れ、バーブリー・マスジド跡もこの目で確認して来たから、少しは語る資格があるだろう。
まず観光業という観点から見ると、ラーム・ジャナムブーミ寺院の建設は新たな名所の創出ということで、少しは面白くなるかもしれない。現在インドを訪れる外国人旅行者数は回復しているのかどうか知らないが、見所は多ければ多いほど観光業にとってプラスになることは間違いない。特にアヨーディヤーはウッタル・プラデーシュ州の中心部にあり、ラクナウー、ゴーラクプル、イラーハーバードなど観光名所のある都市から近い。他のUP州の観光都市と合わせて観光ルートを作りやすくなると思う。
しかしこの観点は本当に第三者から見た全くお気楽なもので、このラーム・ジャナムブーミ寺院の建設は百害あって上に挙げた一利ぐらいしかない。そもそもインド全土の歴史あるモスクや廟のほとんどはヒンドゥー寺院を破壊して造られたものである。もしラーム・ジャナムブーミ寺院再建が認められるなら、1992年12月6日にアヨーディヤーのバーブリー・マスジドを破壊したように、インド全土のイスラーム建築を破壊することも許されてしまう。デリーの観光名所であり世界遺産でもあるクトゥブ・ミーナールもヒンドゥー寺院を破壊して造られたものである。これも破壊するのか。インドの至宝タージ・マハルもヒンドゥー寺院を破壊して造られたものである可能性が高い。これも破壊するのか。破壊しだしたらキリがない。
それにバーブリー・マスジドの建っていた場所が、ラーム王子の生まれた場所だとどうして分かるのか?そもそもラームは神話上の登場人物である。歴史的人物とはいいがたい。VHPを中心としたヒンドゥー・ナショナリストたちがバーブリー・マスジドを破壊したのは歴史的真実である。ムガル朝の創始者バーブルがヒンドゥー寺院を破壊してマスジドを建設したことも、おそらくは歴史的真実だろう。しかし100%確実ではない。ところがその場所でラームが生まれたことは歴史的な事柄ではない。神話と歴史をごっちゃにしてはならない。もしラームは神様の化身であると認めるならば、それは神話や信仰に分類されるものであり、ラームが生まれた場所というのは特定できないはずだ。もしラームが歴史的人物だと認めるならば、どこかでラームのモデルとなる人物が生まれたことは確かであるが、何千年も前のことで考古学的に特定することは困難だろうし、英雄扱いならまだしも神様扱いする必要はないはずだ。ヴァールミーキの「ラーマーヤナ」にはラームは人間として描かれ、トゥルスィー・ダースの「ラームチャリト・マーナス」にはラームは神様として描かれている。どうもこれら「ラーマーヤナ」と「ラームチャリト・マーナス」をごっちゃにしてラームを語ることが誤解と矛盾を生んでいるように思える。このようなこんがらがった状態で寺院を建てることは、かえって罰当たりではないだろうか?
一番いい解決法は、バーブリー・マスジド跡以外から真のアヨーディヤー城を発見することである。でっち上げでもこの際許すから、アヨーディヤー郊外の何もない原っぱにアヨーディヤー城跡を発見してしまえばいいのだ。マトゥラーにあるクリシュナの生誕地だってでっち上げである。クリシュナはラームよりも歴史的人物であった可能性が若干高いが、当時のマトゥラーは別の場所にあった。だから現在のマトゥラー市街にクリシュナの生まれた場所があるわけがない。この要領で、バーブリー・マスジド跡以外の場所を発掘し、真アヨーディヤーをでっち上げ、そこにラーム・ジャナムブーミ寺院を建設すればスムーズに事が運ぶだろう。しょうもない解決法だが・・・。
結局人間が平和に暮らすには、歴史の知識は余計なものなのかもしれない。人間の歴史は残酷な戦争の歴史である。そして歴史は支配者が容易に書き換えることが可能だ。その歴史を紐解いて心に去来するものは悲しみと憎しみ、そして欺瞞だけではないか。僕もインドに住みながら時々思う。歴史さえなければ、韓国人や中国人とも何のわだかまりもなく付き合うことができた、と。歴史があるゆえに、僕たち日本人はいつまでたってもアジアの中で快適な居所を見つけることができない。そういえばインド人はかつて歴史を捨て去った民族だった。近代に至るまで、インドに歴史書は存在しなかった。インド人は歴史を記述してこなかった。それは非常に高度な哲学に基づく平和維持システムだったのかもしれない。過去に何が起こったのか知らなければ、現在あるがままで満足することができるだろう。領土復帰にやっきになることもなく、歴史を改ざんする必要もないだろう。
とにかく、神話と歴史をごっちゃにすること、そして闘争と悲劇の歴史をまた闘争と悲劇を生むために使うこと、これをやめなければ僕はラーム・ジャナムブーミ寺院建設を支持することができない。
今日から3日間、プラーナー・キラーでICCR主催の文化交流イヴェントが開かれる。プログラムを見てみると、25日の今日はブータン王国、26日はマレーシア、27日はベラルーシとのこと。この3つの中でもっとも面白そうなのは断然ブータンである。特に用事もなかったので、夕方プラーナー・キラーまでブータンの伝統芸能を見に行った。
やはり会場にはブータン人らしき人々がつどっていた。ブータン人の顔は非常に日本人に近い。日本の田舎の人みたいな顔付きである。服装も和服の親戚のようなものを着ている。ブータン人に囲まれるとなんだかワクワクしてくるのはなぜだろうか?会場にはブータン大使も出席していた。
今回パフォーマンスしたのは、ブータンのRoyal Academy of Performing Artsの人々。王立アカデミーということで、よっぽど由緒正しい学校なのだろう。ほとんどが20代くらいの若者で、皆ブータンの派手な民族衣装を身に付けていた。まずはTendrel Luzheyというウエルカム・ダンスから始まり、DrigingやDramitse Ngachamという仮面舞踊など、9演目を披露してくれた。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
9番目の演目Tashi Laybey
全員勢ぞろいして儀式終了の歌を歌う |
● |
フォーク・ダンスなので、大体輪になって踊る系の踊りが多い。動きは緩慢で、片足を高く上げてフワッと回転する動作が特徴的だった。また時々両足を上げて高くジャンプしていた。音楽は大体生演奏で、鉄琴、弦楽器、横笛、細長い金属製の縦笛などが使用されていた。
正直言って退屈な踊りだった。動きがスロー過ぎるし、表現力に長けているわけでもない。ステージ上で魅せるダンスではなく、祭りのときにみんなで輪になって踊る部類のダンスである。衣装がきれいだったのと、仮面劇の仮面がよくできていたことぐらいが特筆すべき点だろう。ありきたりな感想になるが、輪になって踊る踊りは日本の盆踊りと非常によく似ていた。また、仮面舞踊はスリランカのキャンディアン・ダンスを髣髴させた。
| ◆ |
2月25日(火) Anita and Me |
◆ |
ブータン・ダンスが終わった後、PVRアヌパム4へ新作映画「Anita and Me」を見に行った。この映画はイギリス生まれのインド人女流作家ミーラー・シャールの同名小説を基に作られた映画で、言語は英語。ヒングリッシュ映画のひとつと数えることができるだろう。監督はメティン・フサイン。この人がどういう人なのかは調べたがちょっと分からなかった。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
Anita and Me |
● |
物語はミーラー・シャール自身の少女時代をベースにしており、1970年代のイギリスの片田舎の町タリントンが舞台。しかし登場人物たちの話す英語がやたらと訛りまくっていて、恥ずかしながらあまり聴き取れなかった。大体のあらすじを書くと、主人公のミーナーはインド系移民の家庭に生まれた女の子で、インドの伝統的価値観と高等教育を押し付けようとする両親に反発していた。そしてミーナーは作家になる夢を抱いていた。そんなときミーナーの隣にアニターというませた白人の女の子の一家が引っ越して来る。アニターはきれいなブロンドの髪を持ったかわいい女の子で、ミーナーの憧れの的になる。ミーナーはアニターと奇妙な友情を結び、彼女の行動を逐一観察する。次第にアニターは不良少女への道を歩み始める一方で、ミーナーは名門学校の試験に合格し、彼女の書いた小説も雑誌に掲載されることになる。ミーナー一家は住みなれたタリントンを去ることになり、以後2人の人生は別々のものとなってしまう。
もし日本語字幕付きで見たらけっこういい映画だったかもしれないが、言葉をあまり理解できなかったため、楽しさ半減だった。さすがのインド人も完全に理解している人は少なかったように思える。会場から漏れる笑い声がいつものヒングリッシュ映画やハリウッド映画よりも少なめだった。だがユーモア溢れる登場人物と牧歌的なイギリスの田舎町の風景はよかった。僕は男だからあまり偉そうなことは書けないが、思春期を迎えた女の子の心情が非常にリアルに描かれていたと思う。
主演のインド人少女チャンディープ・ウッパールは全くの素人俳優らしい。あんまりかわいくないのだが、演技はしっかりしていた。原作作家のミーラー・シャールも端役で出演していた。「Bend It Like Beckham(邦題:ベッカムに恋して)」に似た作品なので、その映画の成否によっては日本でも上映されることがあるかもしれない。
| ◆ |
2月26日(水) Freaky Chakra |
◆ |
昨日見た映画の英語がほとんど理解できなくて少なからずショックを受けたので、自信を取り戻すために別のヒングリッシュ映画を見に行った。「Freaky Chakra」、先々週の金曜日から公開されている映画で、評判も上々である。俳優は皆インド人なので、インド訛りの聴き取りやすい英語をしゃべってくれるだろう。昨日と同じくPVRアヌパム4で見た。
「Freaky Chakra」に出ている俳優で知っているのはディープティー・ナヴァル。「Leela」や「Shakti」に出ていた女優である。後はあまり知らない人ばかりだった。この映画のポイントとなるのは、作者(本当の作者ではなく、役としての作者)映画中に登場することである。そしてその作者が映画の進行を見守り、手を加えていく。それが斬新な点だった。舞台は割と珍しくカルナータカ州の州都バンガロール。
| Freaky Chakra |
トーマス夫人(ディープティー・ナヴァル)は夫の死を境に医者をやめ、ひっそりと死体装飾の仕事をしているミドル・クラスの未亡人だった。口うるさい性格だったので、同じマンションに住む人々は皆トーマス夫人のことをうざったく思っていた。彼女の生活は毎日ルーチン・ワークで、何の生き甲斐もないようだった。たったひとつ、彼女のところには毎晩見知らぬ男からのいやらしい電話がかかって来ていた。トーマス夫人はその電話を毎日密かに楽しみにしていたのだった。
ところがある日、ひょんなことからトーマス夫人の家に若い男(スニール・ラーオ)が居候するようになる。その若者はいつしかトーマス夫人の心の支えとなり、彼女の生活や性格も次第に明るくなっていった。しかしこの展開は作者(ランヴィール・ショーレイ)の思惑外だった。
作者はトーマス夫人と若者の仲を強引に裂く。若者が去って行った後のトーマス夫人はまた以前の退屈で八つ当たりに満ちた生活に逆戻りしてしまう。しかし若者は作者を追いかけて復讐し、トーマス夫人と仲を取り戻す。最後は作者が映画の登場人物に追いかけられて終わる。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
冒頭では「蛇口をひねっても水が出ない!」とか「オート・リクシャーに乗車拒否された」とか、インドで生活していると必ず体験する日常の小さなアクシデントが鋭く描かれていて面白かった。トーマス夫人と同じマンションに住む人々も個性的。トーマス夫人に淡い恋心を抱いて夜な夜な悪戯電話をする中年のおっさんや、悪戯ばっかりするスィク教徒の兄弟、トーマス夫人が怒り出すと耳に耳栓をして雷が去るのをぼーっと待つのが日課のガードマン、廊下で毎日のようにいちゃつくカップルなどなど。インド人は普段から個性的なので、こういう個性的なキャラクターを設定するのは案外容易かもしれない。
しかし最近のインド映画の密かなトレンドとして、20代くらいの若い男が、40代以上の女性と恋に落ちるというあらすじがやたら目立つようになってきた。この傾向は「Dil Chahta Hai」(2001年)に始まり、「Leela」(2002年)に受け継がれ、この「Freaky
Chakra」まで続いている。潜在的にインド人の若者には、年上の女性に対する恋心があるのかもしれない。
映画中、中年独身女性の寂しい生活が痛々しいほど生々しく描かれていた。これは映画だから実際はどうなのか知らないが、生きていく上で男が女を必要とする以上に、女は男を必要とするのだなぁと何となく思ったりした。これはインドの伝統的な考え方にも合致する。
個人的にあまり必要なかったのだが、ディープティー・ナヴァルのシャワー・シーンが2回も出てきたりして、冗漫な部分もあった。だが全体的にユーモアのセンス溢れるオシャレな映画だった。ヒングリッシュ映画を見るといつも思うのだが、今回もインド人もここまで良質な映画を作るようになったかと驚いた。最後のチープなまとめ方にはおそらく賛否両論あるだろうが、僕はまあいいんじゃないかと思った。
細かいポイントになるが、映画中に「スーパーマリオブラザーズ」のゲーム画面がチラッと登場したので懐かしかった。バンガロールの街並みや、ディスコ、喫茶店チェーンのクウィッキーズも少し登場。インド映画撮影の中心地と言ったらムンバイーだが、バンガロールぐらいの規模の都市の方が低予算映画には向いているかもしれない。
幸い、この映画の英語は大体理解することができた。会話は英語が主体で、ヒンディー語が1割〜2割ぐらいを占めているという典型的なヒングリッシュ映画の言語構成。だがこの言語状況はもちろんフィクションである。バンガロールの人は英語が上手そうだが、母語はやはりカンナダ語で、日常的にあんまりヒンディー語を使用しないと思う。ムンバイーを舞台にした一般的なヒンディー語映画でも、日常会話でヒンディー語が使われるのは実は実情とそぐわない。あそこはマラーティー語が話されている地域だ。しかし敢えてヒンディー語が映画の中で積極的に使われているのは、ヒンディー語を名目上だけでなく、真の意味においてインド全土の第一公用語にしようとする政治的な意図と結びついているような気がする。インド人全員が日常的にヒンディー語で会話をするという理想的世界は、今のところ映画の中だけに存在する。
先日「Devdas」のDVDを購入した。海賊版なら映画公開後すぐに手に入ったが、正規版は今月から新発売されたようだ。ボーナスDVDとポストカード(4枚)付き特典バージョンで、DVD2枚組999ルピーだった。ボーナスDVDの方にはメイキング・シーン、シャールク・カーンやアイシュワリヤー・ラーイ、マードゥリー・ディークシトらのインタビュー、カンヌ映画祭の様子、各種予告編や、彼ら主要登場人物3人の過去の出演作の名場面集が入っていた。まあインド映画ファンには嬉しい特典、と言っておこうか。インタビューはありきたりのコメントがあるだけであまり楽しくなかったが、個人的にメイキングでビルジュー・マハーラージがマードゥリーに踊りを教えているシーンを見れたのはよかった。マハーラージのインタビューもあった。さすが正規版だけあって、本編の映像や音声にぬかりはない。英語字幕も付いているが、訳し方が甘いように感じた。しかもやたらと難しい英単語を使うのはやめてもらいたい。不満点がなかったわけではないが、とにかくインド映画ファンなら必携のアイテムと言えるだろう。
DVDと同時にVCDももちろん発売され、その他「Devdas Dialogues」、「Devdas Songs With Selected Dialogues」という企画オーディオCDも発売された。映画中のセリフがピックアップされて録音されているCDで、これは今までなかった新しいコンセプトのCDである。ヒンディー語の勉強にいいかもしれない。このタイミングで「Devdas」関連の商品が一気に発売されたのは、フィルムフェア賞(インドでもっとも権威のある映画賞)やアカデミー賞と関わりがあるだろう。そういえば今年のフィルムフェア賞は「Devdas」が主要部門を独占して終わった。残念ながらアカデミー賞外国映画部門にはノミネートされなかったが・・・。
それにしても最近のボリウッド映画のDVD化の早さには驚かされる。「Humraaz」、「Road」、「Kaante」などなど、2002年後半に公開された映画のいくつかがもう正規版DVDで発売されている。しかも安い。「Kaante」のDVDなんて200ルピーという脅威の安さである。200ルピーという値段はVCDと同レベルだ。そうでなくても一般的なインド映画の正規版DVDは500ルピー前後で、俗に言う「お求め安い価格」に落ち着いてきた。これは2年前には全く考えられなかった現象である。「Lagaan」のDVDを買うのにパーリカー・バーザールの闇市場で1500ルピー払わなければならなかった時代はもう過去のものとなったようだ。
VCDの方はDVDよりもさらに積極的だ。今、プラネットMやミュージック・ワールドなどの大手音楽ショップへ行けば、1、2ヶ月前に公開された最新映画の正規版VCDが簡単に手に入るようになっている。VCDは画質・音声の低品質さや、映画の途中でCDを入れ替えないといけない煩わしさなどから僕はあまり好きではないのだが、インド映画鑑賞のためには未だに最も適した媒体と言えるだろう。
これだけ早く安くDVD化されるようになったのは、インドにおけるDVDプレーヤーの普及と関係しているだろう。しかし一方で、海賊版VCD、DVD、TV放送に対する対抗措置でもあるだろう。映画公開より前にその映画の海賊版VCD、DVDが市場で手に入ってしまうことも多いし、ケーブルTVで最新映画が違法に放映されることなど日常茶飯事だ。そういう映画業界の寄生虫たちに利益を吸い取られるよりは、自分たちで正規のVCD、DVDなどを発売し、二次利益を海賊業者に持っていかれないようにしようとする意図が見受けられる。前述の通り、最近VCD化は非常に早くなったが、まだDVD化権を持つ会社の足並みが揃っていないようで、全てのボリウッド映画が迅速にDVD化されている訳ではない。だが将来的にはVCDに代わってDVDがインド映画の主要な媒体になると思われる。200ルピーでDVDを買うことができるなら、VCDはもう必要ないだろう。
インド映画の特徴を考慮してみると、これほどDVDというメディアに適したソフトはない。インド映画の上映時間は大体2時間半〜3時間くらいだ。この長さが日本でのインド映画の公開の妨げになっていることは否めないが、DVD化に際してこの長さは1枚のDVDにちょうど収まりきる長さである。それにインド映画はストーリーの途中でミュージカルが挿入されることが大きな特徴のひとつであるが、これもDVDの長所と合致する。よくインド映画のDVDのメニューには、チャプター選択の項と同時に歌選択のチャプターも存在する。また気の効いたDVDなら、ミュージカル・シーンだけを再生する機能が付いていることもある。これらはビデオやVCDではできなかったことだ。だがDVDならできてしまう。DVDの特徴を最大限に引き出すのがインド映画なのだ。まさにインド映画はDVDになるために生まれてきたと言っても過言ではないだろう。これからもっと最新映画の迅速なDVD化と、コストダウンを推し進めてもらいたい。
|
|
|
|
|
NEXT▼2003年3月
|
|
| *** Copyright (C) Arukakat All Rights Reserved *** |



