 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
 これでインディア これでインディア 
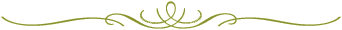
2003年3月
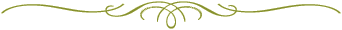
|
|
|
|
| ◆ |
3月1日(土) 開戦!インドVSパーキスターン |
◆ |
マハーシヴァラートリーの今日、遂に待ちに待った戦争が開始された。と言ってもイラク対アメリカではない。南アフリカ共和国にて開催中のクリケット・ワールドカップで、往年のライバル、インド対パーキスターンの戦いの火蓋が切って落とされたのだ。
この両国の因縁はかなり深い。インドとパーキスターンの確執は核戦争の脅威もあり、誰もが知るところだが、クリケットの国際試合でもその確執は変わりがない。印パ分離独立後から今までインド対パーキスタン戦は合計84試合行われた。結果はパーキスターン52勝に対しインド28勝。パーキスターンの方が勝ち星の数が圧倒的に多い。ところが最も由緒あるワールドカップの試合になるとパーキスターンは全く駄目で、インドはパーキスターンに3戦3勝している。今回はワールドカップにおける4度目の対決ということになる。
印パ戦を告げる今日の朝刊には、「これはクリケットではない、戦争だ」という見出しが踊る。これは日本の大学間試合における早慶戦、日本の野球における巨人対阪神戦はもちろん、サッカー国際マッチにおける日本対韓国戦にも勝る命を懸けた激突である。何しろインドとパーキスターンは今まで3度も実際に戦争を行っているのだ。しかも両国は同じ血を分けた兄弟国家同士。この悲劇が余計に戦いを面白くする。印パ戦に臨む選手たちにとって、この戦争は勝ったら英雄、負けたら死の世界だ。ワールドカップで優勝することよりも、印パ戦で負けないことの方が意味があるとまで言われているくらいだ。
今日は朝っぱらから外を楽団がパレードしていた。もちろん結婚式などではない。印パ戦でのインド・チームの健闘を祈ったパレードである。どことなくインド人たちは皆そわそわしている。道を歩く人の姿もいつもより少ない。バーザールを見てみたところ、スナック菓子の売れ行きがいつもよりもいいようだ。家で試合を見ながら食べるために、多くの人が買い求めているのだろう。おそらく酒類の売れ行きもいいはずだ。
僕はインドに住んでいるので、断然インド・チームのサポーターである。パーキスターンにも少しは思い入れがあるが、やはり街角の看板や広告でインド・チームのクリケット選手の顔を見る機会が多いので、インド・チームの方に思い入れが強い。そういえばインド・チームのボウラー、ハルバジャン・スィンには実際に会ったことがある。もうインド人と一緒に頑張れインド状態だ。
今回のワールドカップにおけるこれまでのインド・チームの戦績を見てみよう。クリケット・ワールドカップの参加国数は14国。予選リーグは7チームずつグループAとグループBに分かれており、総当たり戦をする。各グループから上位3チームずつスーパ・シックス・シリーズへ進むことができる。スーパー・シックスに選ばれた6国は別リーグから勝ち上った3国と試合を行い、この中から上位4国が準決勝戦を行い、勝ち残った2国が決勝戦を行う。インドはこれまで予選リーグのグループAでオランダ、オーストラリア、ジンバブエ、ナミビア、イギリスと対戦し、4勝1敗。オーストラリアに大敗を喫してしまったものの、それ以後連勝を続け、かつての宗主国イギリスにも快勝してしまった。ほぼスーパ・シックス進出間違いないのだが、まだ油断できない。インド・チームとしてはパーキスターンに勝ってスーパー・シックス入りを確実にしたいところだ。一方パーキスターンはオーストラリアとイギリスに敗れて2勝2敗。もしインドに負けたらスーパー・シックス入りが限りなく遠のく。パーキスターンにとって、もともとインド戦は負けることができない上に、さらに崖っぷちに立たされた状態で戦いに臨むことになったと言える。
インドでは印パ戦は昼の1時半頃から始まった。まずはパーキスターンのバッティング(クリケットはボールを投げる方が攻撃側だから、つまりインドの先攻)から始まった。さすがにパーキスターンは気合が入っていて、順調な滑り出し。クリケットの試合で選手に贈られる主な称号に、センチュリーとハット・トリックがある。センチュリーは100ラン以上を走ったバッツマンに、ハット・トリックは連続で3ウィケットを取ったボウラーに与えられる(ちなみにサッカーでもハット・トリックという称号は使われるが、これはクリケットが由来)。パーキスターンにそのセンチュリーを叩き出す男が現れた。ワン・デイ国際マッチにおいて世界記録の194ランを持つサイード・アンワルである。サイードは101ランでセンチュリーを取る大奮闘。彼のいかにもムスリムチックな厚ぼったいヒゲにも驚かされた。それ以後もパーキスターン・チームの猛攻は止まらず、結局50オーバーが終了し、273ラン/7ウィケット。かなりの高得点である。もうスタジアムのパーキスターン人は勝ったも同然の大騒ぎ。パーキスターンの旗が悠々と振られ続けていた。インドは果たしてこの数字を越えることができるのか、インド人に緊張が走る。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
センチュリーを叩き出した
サイード・アンワル |
● |
5時半頃からインド・チームのバッティングが始まった。道から人影は消え、光に群がる虫のように、人々はテレビの前に群がる。最初のバッツマンはインドの英雄サチン・テーンドゥルカルと、ヴィーレーンダル・セヘワーグ。サチンはインドはもとより世界でも最高のバッツマンとして知られ、インド人の子供たちは皆サチンになるのを夢見て日々クリケットに勤しんでいる。インドの松井秀喜と呼んだら失礼か、と思うぐらいに偉大な人物である。もうすぐ彼は30歳になろうとしており、スポーツ選手としてのピークは過ぎたと言えるのだが、今回のワールドカップでサチンはどのバッツマンよりも多くのランを稼いでおり、「インドにサチン未だ健在」という印象を世界のクリケット・ファンに知らしめている。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
インドの英雄
サチン・テーンドゥルカル |
● |
やはりサチンのバッティングを見ていると豪快で巧みと言わざるをえない。サチンを迎え撃つボウラーはパーキスターンが世界に誇る速球投手、ショエーブ・アクタル、ワシーム・アクラム、ワキール・ユーヌスら。しかし彼らの渾身の投球をものともせず、サチンはしょっぱなから4S(転がってホームラン)や6S(ノーバウンドでホームラン)を連発し、急ピッチでランを量産していった。軽く50ランを越え、このままセンチュリーかと思ったところで不幸にもサチンの持病である足の筋肉痛が起こってしまった。しかしサチンは我慢した。足を引きずりながらもウィケット間を走り抜け、人々の感動を呼んだ。セヘワーグがウィケットとなり、次に出て来たインド・チームのキャプテン、サウラヴ・ガーングリーが初球でウィケットになってしまうというハプニングもあったが、それでもサチンの勢いは止まらなかった。あと2ランでセンチュリーまで届くというときになってサチンの打ったボールがキャッチされてしまい、惜しくも彼はアウトになってしまった。しかし既にこのときインド・チームは残りのオーバーで勝利に十分届くだけのランを稼いでいた。ムハンマド・カイフがウィケットになった後、ラーフル・ドラヴィルと期待の若手ユヴラージ・スィンのコンビが手堅くランを積み重ねて行き、とうとうインド・チームは276ラン/4ウィケット(45.4オーバー)で勝利をものにした。やはり英雄はサチン・テーンドゥルカルだ。最近彼はCMに出まくっているので、クリケットを知らない在印外国人にも有名である。大体においてスポーツ選手が好んでタレント業に足を踏み入れ始めると、急に落ち目になることが多いが、彼は違った。やっぱりサチンはすごい。また、若手のユヴラージ・スィンがハーフ・センチュリー(50ラン)を記録し、同じく若手のムハンマド・カイフも健闘して、インド・チームは若い選手も順調に育ってきていることを印象付けた。
インド・チームの勝利が確定した瞬間、デリーの街はもうそれは大変な騒ぎだった。ホーリーがもうすぐやって来るというのに、ディーワーリーがまた始まったかのようなお祭り騒ぎだった。打ち上げ花火がド〜ンと上がり、大量の爆竹が爆音を発し、道では大声を上げて喜ぶ若者を満載した車が駆け回った。この勝利はパーキスターンに対する勝利だけでなく、スーパー・シックスへ進出を決めた勝利でもあった。インド人の喜びは頂点に達し、テレビはインド各地の喜びの様子を映し出した。デリー、コールカーター、ムンバイー、バンガロール、ラクナウーなどなど・・・。どこでもインド人たちは踊り狂って喜んでいた。サッカー・ワールド・カップで決勝トーナメント進出を決めたときの日本みたいだ。ただ、ジャンムー&カシュミール州の州都シュリーナガルの報道だけは気になった。インド・チームの勝利が濃厚になると、イスラーム原理主義者の仕業がどうか知らないがシュリーナガル全市でケーブル・ラインがカットされたらしい。マハーシヴァラートリーのプージャーをしながら、ラジオから流れてくるクリケットの試合の様子に耳を傾けるブラーフマンの図、というのも面白かった。
今回のクリケット・ワールドカップでも、僕の一生でも、クリケットの試合を最初から最後までほぼ全部見通したのはこのインド対パーキスターン戦が初めてだった。改めてクリケットは観戦しててとても楽しいスポーツだと実感した。どんなスポーツでもルールが分かれば楽しいものだ。日本人にはクリケットに理解のない人が多いというかほとんどだが、ルールも知らずに「つまらん」と言い捨てることほど愚かなことはない。日本でもクリケットを普及させたくなったなぁ・・・。また、見ていてクリケットはどのスポーツよりも選手が大人であるような気がした。審判の権力は絶対のようで、僕はクリケットの試合で今まで、野球やサッカーの試合のように、審判に詰め寄って抗議する選手たちの図、というのを見たことがない(実際はあるかもしれないが)。スポーツマン・シップをもっとも感じるスポーツである。クリケットの試合がもっとも盛り上がるのはラストの攻防だ。今回の印パ戦はほぼ中盤で試合が決定してしまったのだが、どちらが勝ってもおかしくないような状況だと、本当にドキドキする。幸い僕の贔屓チームであるインドはスーパー・シックス入りを確実にし、まだ続けて応援することができるので、これからも楽しみだ。
| ◆ |
3月3日(月) Mango Souffle |
◆ |
個人的にインド映画界の2002年はヒングリッシュ映画躍進の年だったと評価しているが、2003年になってもヒングリッシュ映画の勢いは止まりそうにない。今日は先週から封切られたヒングリッシュ映画「Mango Souffle」を見に行った。デリーではPVRアヌパム4のみ上映されており、しかも午後11時からの回のみという風変わりな公開の仕方である。上映される映画館が少ない映画は普通駄作であることが多いのだが、この映画に限っては少し違うものを感じたので見に行くことにした。なにしろ同性愛が主題の映画である。きっとお忍びで映画を見に来るゲイやレズのカップルに配慮しての公開なのだろう。僕もお忍びで夜11時にPVRアヌパム4へ行った。
主な出演俳優はアトゥル・クルカルニー、リンキー・カンナー、アンクル・ヴィカール、フェアドゥーン・ドードー・ブジワーラー(なんじゃその名前は)、ヒーバー・シャー、デンズィル・スミス、サンジト・ベーディー、マハムード・ファルークイー。「Mango Souffle」は舞台劇用の脚本をもとに映画化された映画のようで、俳優たちも舞台俳優っぽい濃い顔の人が多い。この中でアトゥル・クルカルニーは一般のインド映画にもよく出演しており、僕の好きなベテラン俳優でもある。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
Mango Souffleの個性的俳優たち |
● |
| Mango Souffle |
舞台は緑豊かな庭園都市バンガロール。ある日有名なデザイナーで自他共に認めるゲイのカムレーシュ(アンクル・ヴィカール)は友人たちをマンゴーの木生い茂る自宅へ招いた。そこへやって来たのはカムレーシュの元恋人(もちろん男の)シャラド(フェアドゥーン・ドードー・スミス)、カムレーシュの親友(こちらは女)ディーパリー(ヒーバー・シャー)、イギリス帰りのインド嫌いな偏屈な男ランジト(デンズィル・スミス)、そして有名な映画スターのバニー(サンジト・ベーディー)である。突然呼ばれたことに驚く友人たちを前に、カムレーシュは妹のキラン(リンキー・カンナー)が結婚すること、そしてバンガロールを去ってカナダへ行くことを告げる。ところがカムレーシュがカナダへ行くのにはある秘密があった。カムレーシュとのよりを取り戻したいシャラドはその秘密を握る一枚の写真を発見する。その写真では2人の男が裸で抱き合っていた。1人はカムレーシュ、1人は謎の男・・・。実はその男はカムレーシュの妹キランのフィアンセ、プラカーシュ(アトゥル・クルカルニー)だった。カムレーシュはシャラドと別れた後、プラカーシュと付き合っていた。しかしカムレーシュはプラカーシュにふられた上に、彼はキランと結婚することを決めてしまったのだった。カムレーシュはプラカーシュへの愛よりも、妹の幸せを尊重することにした。キランはプラカーシュがゲイであり、兄の恋人だったことを知らなかった。だが、それに耐え切れなくなったカムレーシュはバンガロールを去って海外へ行くことを決めたのだった。カムレーシュはその秘密を友人たちに話し、誰にも言わないように約束させる。
ところがその場にキランとプラカーシュが偶然来てしまったから話がややこしくなった。キランは兄の様子がおかしいことに気付き、どうしたのか問い詰める。しかしカムレーシュは口を開かない。シャラドは機転を利かせて、カムレーシュと自分の仲がうまくいってないから彼は困っているのだ、と言う。なぜうまくいかないか、とのさらなる問いに、シャラドはゲイをやめてストレートになることにした、と答える。ところがその態度を見てカムレーシュはシャラドに「I Love You」と告白する。それを見ていたプラカーシュが嫉妬し出してカムレーシュと2人きりになって口論をする。実はプラカーシュはまだカムレーシュのことが好きだったのだ。それを聞いてカムレーシュも激怒する。彼らが口論している間に例の写真がキランの目に届き、遂に彼女はプラカーシュがゲイであることを知る。プラカーシュは必死に弁明するがキランは許さなかった。最後にプラカーシュはカムレーシュとキランの2人に「I
Love You」と告げて去って行く。カムレーシュはシャラドと仲直りし、キランも結婚から解放されてほっとする。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
先にも述べたように舞台劇を映画化したので、舞台劇っぽい映画だった。場面があまり動かず、シャレたセリフの交換でストーリーが進んでいくような展開。演技もちと大袈裟過ぎ。せっかく映画にしたんだから、もっと映画っぽい撮影の仕方をした方がよかったのでは、と感じた。俳優たちの顔は、大学の劇団のメンバーという感じ。華やかさよりも、見ていて目が疲れるほど個性が際立った顔をしている人が多い。と言うか、あんまりインド人に見えなかった。
3人のゲイの三角関係が主題になっていたが、映画中繰り返し用いられたセリフ「他人の目を気にするな」というのがもっとも作者が観客に伝えたいメッセージだろう。カムレーシュとシャラドは自分がゲイであることをカミング・アウトしていたが、プラカーシュは自分がゲイであることに戸惑っており、社会には隠していた。そのため彼の最後はあまりにも惨めである。いわば同性愛啓発映画というところだろう。
やはりアトゥル・クルカルニーは面従腹背のような、表情と心情を別々にした演技が非常にうまい。今回はキランへのストレートな愛と、カムレーシュへの同性愛の間の葛藤をうまく表現していた。途中、プラカーシュ(アトゥル・クルカルニー)とカムレーシュ(アンクル・ヴィカール)が素っ裸でプールで泳ぐシーンがあったのだが、あれは同性愛者たちへのサービス・カットだったのだろうか・・・。
同性愛をテーマにした映画だったからか知らないが、隣の席に座っていた男の指がやたらと僕の腕を触ってきて気になった。気のせいだったらいいのだが、気のせいだと思って我慢するのが痴漢に遭ったときに一番してはいけないことだと、これまでの経験から感じているので、すぐに席を移動させてもらった。
言語は英語が9.5割。召使いのマクサード(マハムード・ファルークイー)と会話するときだけヒンディー語が使われていた。しかしそのヒンディー語はなんとなくカタコトだった。みんな英語はうまかったのだが・・・。
先週見た「Freaky Chakra」もバンガロールが舞台で、「低予算映画にバンガロールは向いているかも」と書いたが、まさにその低予算映画がコレだった。バンガロール発のヒングリッシュ映画が2作続いたか・・・。今度はデリー発のヒングリッシュ映画を期待したい。
| ◆ |
3月3日(月) オート・リクシャー最新事情 |
◆ |
最近デリーのオート・リクシャーにはちょっとした変化あり、変わらないところもあり、というまあ取りとめのない状況である。ちょっとした変化というのは、全てのオートに電子メーターが付き、旧型のアナログ・メーターが一掃されたということである。変わらないところというのは、メーターが新しくなったにも関わらず、依然として乗る前に値段交渉をしなければならないことがほとんどであることだ。昨年の暮れから今年の始めにかけて長期に渡るストライキを繰り広げ、政府に対して運賃値上げ交渉を行ってきたオート・ワーラーたちだが、もう最近は新しいシステムにも慣れたようで、普通に運行をしている。
2月から始まった新しい制度によると、オートの運賃は1kmごとに3.5ルピーで、いわゆる初乗り料金が4.5ルピーである。よって10km乗ったら、3.5×10+4.5=39.5ルピー、よって40ルピーの運賃ということになる。僕は今までこの新制度に準じた電子メーターを1度だけ見たことがあるが、ほとんどのメーターは初乗り2.5ルピー、1kmごとに2.5ルピーという旧運賃に基づいている。電子メーターは運賃と共に距離も表示するので、その距離を運賃に換算しなければならない。
旧運賃の1km2.5ルピーなら計算しやすかったのだが、1km3.5ルピーというのはかなりやっかいな数字である。暗算するのに少し苦労する。あまり教育を受けていないオート・ワーラーたちにとってはなおさらだろう。だがこの新運賃はオート・ワーラーたちがストライキによって政府から勝ち取った勝利の証である。まあせいぜい頑張って計算してくださいな。
以前はあまりオート・リクシャーの取り締まりが厳しくなかったのだが、今年に入ってからかなり警察のチェックが厳しくなった。メーターで走っていないオート・ワーラーは罰金を払わされるらしい。だから値段交渉をしてオートに乗ると、オート・ワーラーはこっそり僕に念を押してくる。「もし警察が来たら、メーターで行ってるって言うんだぞ」と。そんなことあるのか、と思っていたが、実際に一度僕もそのポリス・チェックに立ち会ったことがあった。オートに乗って信号待ちをしていると、どこからともなく警察がやって来てオート・リクシャーのナンバーをメモし、ちゃんとメーターで行っているか確認する。
そのポリス・チェックをかいくぐるためにオート・ワーラーはオート・ワーラーでいろいろな対策を練っている。例えばメーターで行かなくてもメーターをオンにして走っていれば、それはそれでポリス対策になる。しかしそれでは客に正しい運賃がばれてしまう。だから客が乗る前から電子メーターを回しておいたり、客が乗ってしばらくしてからメーターをオンにしたりして、客に運賃が分からないようにする奴が多い。電子メーターは以前のアナログ・メーターよりも改造しにくいようだが、やはりインド人に不可能はないようで、既に改造電子メーター(つまり実際よりも早く回るメーター)も裏市場に出回っているようだ。だからそれを使って金を稼ぐオート・ワーラーもいる。結局は政府とオート・ワーラーのいたちごっこが続いているだけである。
ところで外国人旅行者はオート・ワーラーのことをリクシャー・ワーラーと呼ぶことが多いが、僕は意識的に彼らのことをオート・ワーラーと書くようにしている。なぜならリクシャー・ワーラーという言葉はリクシャー(人力車)、サイクル・リクシャー、オート・リクシャーの3つの運転手を指す広い言葉であり、狭い意味では人力車のリクシャー・ワーラーのみを表す言葉であるからだ。しかもデリーの人はあまりリクシャー・ワーラーという言葉を使わない。オート・ワーラーか、さもなければスクータル・ワーラーと呼んでいる。外国人が慣用的にリクシャー・ワーラーと呼んでいるだけだと思う。
話はまた変わるが、インドを旅行しに来た外国人や、インドに住んでいてもヒンディー語が分からない外国人は、オート・リクシャーとのトラブルは日常茶飯事のようだ。しかしインドに住んで、ヒンディー語がある程度分かれば、オート・ワーラーとの温かい交流というのも生まれてくるものである。デリーのオート・ワーラーの中にはどうしようもない悪質な奴もいるが、そういう奴らは大体旅行者の集まる場所にたむろしており、観光客とはあまり無縁な南デリーに住む僕は悪質オート・ワーラーに会う機会がほとんどない。大体一般的なオート・ワーラーは真面目に仕事をしており、運賃をふっかけるのも最大で1.5倍程度だ。その内顔見知りのオート・ワーラーが近所にできてきたりして、地域の一部に溶け込んだような気分になるものだ。
僕個人のオート・ワーラーとの温かい交流というと、PVRアヌパム4でいつも客待ちをしているあるオート・ワーラーが思い浮かぶ。僕はよくそこへ映画を見に出掛けるので、次第に映画館出口周辺にたむろっているオート・ワーラーの間で少し名の知れた存在になりつつある。特に夜の回に映画を見て外へ出ると、必ず僕に声を掛けてくるオート・ワーラーがいる。彼は既に何度も僕をガウタム・ナガルへ連れて行ってくれており、何も言わなくても家の前まで行ってくれるというVIP待遇である。普通のオート・ワーラーなら「ヘイ、リクシャー必要か?どこへ行くんだ?」と声を掛けてくるところを、彼は「ガウタム・ナガルだろ?」と聞いてくる。ただ、最初に乗ったときに50ルピーで行ってしまったので、それ以後ずっと50ルピーを払い続けている。夜間料金でPVRアヌパム4からガウタム・ナガルなら40ルピーで行けることが今までの経験から分かっているのだが、いかにも親しげに声を掛けて来てくれるのでついつい利用してしまう。
実は今日もPVRアヌパム4で「Mango Souffle」を見た後、いつもの彼が僕を出迎えてくれた。彼は僕が映画のチケットを買うところを見たらしく、そのときから僕を外で待っていたらしい。なんか泣けてくる話というか、羽柴秀吉と織田信長というか、これはオート・ワーラーの口からのでまかせに見事はまっているだけなのだろうか?もちろん今夜もそのオート・ワーラーのリクシャーに乗り、家に帰った。彼の情報によると、明日PVRアヌパム4にアミターブ・バッチャンがくるそうだ。「また明日もPVRへ行くかい?だったら帰りはまたオレがガウタム・ナガルまで連れて行ってあげますぜ」と言われた。遂にオート・ワーラーから有益な情報を得られるまで親密度がアップしたようだ。現在アミターブ・バッチャンに会うためにPVRに行こうか考え中である。
| ◆ |
3月6日(木) The Days of St. Petersburg |
◆ |
デリーでロシアのバレエをやっているというので見に行った。場所はマンディー・ハウス近くのサプルー・ハウスというところ。今回初めて足を踏み入れた劇場である。日本の小学校の体育館ぐらいの規模の劇場があり、上流階級のインド人やデリー在住の外国人を中心に、けっこう多くの人が見に来ていた。入場料はいつも通り無料。
プログラムの題名は「The Days of St. Petersburg」。ペテルスブルグから来た劇団の公演なのだろうか・・・パンフレットなどがなかったためよく分からなかった。実際はバレエだけでなく、ロシアのフォーク・ダンスも一緒に見せてくれた。
ロシアン・バレエの実物を見た経験というと、あまり記憶がないので、これが初めてだったかもしれない。ダンサーは男女各1人で、男も女もかなり際どい衣装を身につけて踊っていた。特に女のバレリーナの方はバレエ特有の爪先立ち回転をしており、「ああ、バレエだな」と大満足。想像していたのと見事に合致すると安心する。インドにいると、想像していたものと実物が全く違う、ということが多いので、だんだん自分の勝手に抱いたイメージや膨らませた期待に信用を置けなくなっているのかもしれない。
しかしバレエよりも個人的に楽しかったのはロシアのフォーク・ダンスの方だ。男3人と女7、8人がきらびやかな民族衣装に身を包み、舞台に上がって楽器を演奏したり踊ったりした。ロシアの民族音楽は案外日本によく紹介されているみたいで、耳に馴染みがあり、目新しさはなかった。しかし三角形の巨大な弦楽器バラライカを初めて見ることが出来た。他にウクレレほどの大きさの小さなバラライカや、アコーディオン、笛やその他細々した打楽器を使って演奏していた。
ロシアのフォーク・ダンスも他の地域と同じく、輪になって踊るタイプの踊りがメインのようだ。基本的に男女でペアを組んで踊り、はないちもんめのような2列向かい合っての踊りもあった。気になったのはロシアのフォーク・ダンスがだんだんパンジャービー・ダンスに思えてきたこと。両手を軽く上げて踊るタイプの踊りもあり、ステップも似ていた。彼らの着ていた衣装もそういえばカシュミール地方の女性の民族衣装や、先月見た映画「Escape
from Taliban」でマニーシャー・コーイラーラーが身に付けていたアフガニスタンの民族衣装に似ているような気がした。似ていても不思議ではないだろう、それらの国や地域は隣り合わせに等しいのだから・・・。
長身で美しいロシア人女性たちが、本当に楽しそうに踊っていたので、とても楽しめたパフォーマンスだった。バレエとフォーク・ダンスは全く対極にあるダンスの形態なのに、それを同時に見せれてしまうところがロシアの文化の深さだと思った。ロシアもすごい国だと思う。
インドとロシアは昔から文化交流が盛んだったことから、ロシア語をしゃべれるインド人は高齢者を中心に実はけっこう多い。また、ヒンディー語を理解するロシア人というのも実は少なくないようだ。インド映画はロシアでも人気があるという話を聞いたことがある。そういえばケーンドリーヤ・ヒンディー・サンスターンの教師たちの中にも、モスクワにあるヒンディー語の語学学校で教鞭をとった経験のある人が何人かいる。その学校は海外にあるヒンディー語学校の中ではトップ・クラスの質の教育をしているようだ。また、JNUの言語文化研究科で最初に設立されたのもロシア語学科であるし、インドに関するロシア語の文献の数も多いため、インドの研究をするのに、ロシア語の知識が必要になることもある。このようにロシアとインドというのは実はけっこう切っても切れない関係にある。というわけで、会場の観客の中にはロシア語をしゃべるインド人がけっこういて、「ハラショー(いいぞ)」とか「スパシーボ(ありがとう)」などのロシア語が飛び交っていた。僕もロシア人と間違われ、インド人の老人からいきなりロシア語でしゃべりかけられた。ロシアには日本人の顔とそっくりなモンゴロイドも多く住んでいる。
こんなわけで、なかなか変わった夜を体験することができた。
ある雑誌からヒンディー語の風刺小話を翻訳してみた。作者はアルン・クマールという人。
| 大臣の微笑 |
ナンダンワン(歓喜の森)に住む動物たちは困りに困っていた。「無料食料提供」省の事務員たちが賄賂を払わないと仕事をしないのだ。動物たちは同省の下級役人に苦情を申し立てた。ところがその下級役人こそが賄賂を取る張本人だった。彼は自分の署名の持つ権力を濫用していた。だから困窮した動物たちの苦情が詰まった嘆願書はどこかへ紛失してしまった。
苦情が何の効力も持たなかったのを見た動物たちは、同省の上級役人に苦情を申し立てた。その上級役人も負けず劣らず賄賂の鬼だった。彼は自分のもとに来た書類を1枚1枚数え、夕方には下級役人を呼んで手に入った賄賂を自分の机の中にしまっておくのだった。動物たちの苦情は再び闇に葬られたのは言うまでもない。
絶望した動物たちはその省の大臣ボールーラーム・スィヤールのオフィスへやって来て嘆願した。上級役人の苦情を聞いて、大臣はニヤリと笑って言った。
「あの役人は非常に立派な男だ、彼の苦情は今日まで一度たりともなかった。しかしお前たちがそんなに言うなら、彼を別の場所へ異動させよう。そして正直者として有名なある役人を代わりに送ろう。」
上級役人が正直者になれば、あのにっくき役人ども全員が自然と真面目になるだろう。賄賂を取ることにさえ恐怖を覚え、苦情を出されないように仕事をするだろう。動物たちはこう考えながら大喜びして帰った。
正直者の役人が役所を改善してから数ヶ月が経った。動物たちは再び大臣のオフィスを訪問した。今度は動物たちは昔の汚職役人を元に戻してくれるよう頼みに来ていた。動物たちは口を揃えて言った。
「私たちはあんな正直者の役人なんて要りません。私たちの仕事がちっとも進みません。法律に則ってしか動けない奴で、私たちの書類を受け取ろうとしないのです。下っ端の事務員たちも今では書類の粗探しをして私たちをたらい回しにします。彼らは正直者役人の下で賄賂が受け取れないと分かると、代わりに書類を作る権力を振りかざし始めたのです。ああ、どうかお願いします。昔の役人を返して下さい。彼は賄賂を取っていましたが、私たちの仕事はちゃんと進んでいました。新しい役人は仕事もしないし賄賂も取らないんです。」
大臣は微笑んでいた。 |
インドに住む上で、賄賂というのは重要な問題である。日本にももちろん賄賂はあるが、あまり日常生活で必要はない。ただテレビで政治家が収賄事件で逮捕されたりする様子を眺めているだけである。賄賂に対する嫌悪感も多い。賄賂を贈る奴はなんて悪い奴なんだ、インドに来る前の僕はそう考えていた。しかしインドに住み始めると、その考えを180度転換せざるをえなくなった。賄賂は手続きをスムーズにするための潤滑油のようなものである。
電話線架設の工事の早さと、賄賂の額の多さの比例関係について、以前はよくインド在住日本人の中で盛んに噂されていた。最近は簡単に電話線を引けるようになったようだが、以前は賄賂を贈らなければ電話線を引くのに1年待たされるとのことだった。実際に申請から1年後に電話局のオフィサーが家を訪ねて来た、という人を知っている。
また、金さえ払えば、不幸な事態を避けることができることがある。僕がインドに住み始めたときにこんなことがあった。近所のインド人の家でくつろいでいたら、急に宴会の準備が始まった。僕は帰ろうとしたが、「まあこのままいてくれ」と言われたのでそのまま留まった。するとやがて2人の男が入ってきた。彼らはある大学の教務課の事務員だった。聞くところによるとその家の子供が大学試験に落ちてしまったらしく、教務課の事務員を宴会に招き、賄賂を贈って無理矢理合格にしてもらおうとしていたようだ。インド人家族と事務員、双方に全く悪びれた素振りはなく、どちらもこれが当然のような顔をして宴会を楽しんでいたことに僕は驚いてしまった。そして彼ら事務員は日本人(つまり僕)と知り合えたことに機嫌をよくして帰って行った。
僕が今、「賄賂社会というのは完全な悪か?」と問われたら、「そうでもないんじゃない」と答えると思う。特にインドでインド人相手にビジネスをする際、賄賂を贈らないと非常に難しいだろうし、賄賂があるおかげで不可能が可能になることだってある。
賄賂が横行しているからといって、その個人や民族を短絡的に非難することはできないと思う。インドの社会を見てみれば、彼らが賄賂を取りたくなる気持ちも分かってくる。インド人には自分で独立して金を儲けようとする気持ちが希薄な部分が多く、与えられた仕事をこなしておけばそれでいいや、という投げやりなところがある。おそらくカースト制度とも関係しているだろう。インドには政府の仕事に就くことが一番いいことだと思っている人が多く、これがインド人と中国人との大きな違いと言われている。インドにおいて大体庶民を相手に賄賂を搾取しようとしてくるのは、下っ端の役人が多い。彼らは一生退屈なデスク・ワークをし続けなければならないのであり、昇給の望みも薄い。だから自分に与えられた権力の中で、いかに金を持っている人々から金を搾取するか、ということに腐心する。考えてみると、賄賂は一番親切な搾取の手段である。賄賂を払うことによって、賄賂を受け取った方はもちろん、賄賂を払った方にも仕事が早く進んだり、少々の不備に目をつむってもらえたりと、利益があるのだから。
上に挙げた風刺話も賄賂に関係している。結局インド人も、賄賂社会に諦めているというより、賄賂社会をうまく利用しているということだろう。インドから賄賂がなくなった方が、困る人が多いのかもしれない。こういう話は実際によくあることで、有能で正直な役人がトップに立つと、部下や市民の要求ですぐに左遷されることが多いようだ。
今の日本を見てみると、僕にはどうも「正直者の役人」がやって来た社会のように感じる。日本の政治家や役人がクリーンだということではなく、法律通り、時間通りに物事が進む世の中であることだ。おそらく昔の日本はもっとルーズだったと思うのだが、いつの間にかこういう社会になってしまった。僕がインドに住んで快適に感じるのは、ナンダンワンの動物たちのように、正直者の役人の社会が窮屈に感じたからなのかもしれない。僕が生まれたときには既に日本は正直者の役人の国になっていた。だからその役人の前の社会を知らない。だが、日本を発展させてきた世代の人たちはおそらく知っているだろう。彼らはいったいどう思っているのだろうか?今の役人で満足なのだろうか?それとも昔の役人を呼び戻したいのだろうか?そんなことをふと上の話を読んで思った。
デリー・ウォーカーというコンテンツを立ち上げて以来、デリーの情報を集中的に集めている。今日は僕の友人で、パハール・ガンジに6ヶ月以上住み続けたパハール・ガンジの主に、パハール・ガンジの情報を頂戴しに、パハール・ガンジへ赴いた。今日の日記は「パハール・ガンジ」という単語が頻出しそうだ。
パハール・ガンジはデリーの安宿街としてバックパッカーの間で有名で、交通の便もいいため、多くの旅行者が滞在している。ちょうど日本の大学の春休みシーズンで、パハール・ガンジは久しぶりに日本人旅行者で溢れ返っていた。インドを訪れる日本人旅行者の数は回復傾向にあるかもしれない。
まず紹介してもらったのはナヴラング・ホテル前のチャーイ屋。片手が不自由な男が作っており、なかなか絵になるとのことだったが、僕たちが行ったときには別の人が作っていた。チャーイは1杯3ルピー。飲んでみたが砂糖が少なくてあまりおいしくなかった。ナヴラング・ホテルは僕もインド留学当初滞在していた安宿で、あの頃は多くの日本人バックパッカーたちが集結していたのだが、現在は完全に韓国人旅行者の宿と化しているようだ。現在日本人バックパッカーはブライト・ゲストハウスへ移動している。
ゴールデン・カフェ辺りから続くサブジー・マンディー(野菜市場)も案内してもらった。地元の人にとってのパハール・ガンジは、この野菜市場のために重要なポイントのようだ。狭い道の両側に野菜がずらりと並べられ、野菜売りたちの個性的な掛け声が飛び交っていた。
ゴールデン・カフェ近くにあるサトウキビ・ジュース屋も地元の人には有名のようだ。1杯5ルピー。今までの僕のサトウキビ・ジュースの概念を覆すほど甘いサトウキビ・ジュースだった。サトウキビはウッタル・プラデーシュ州から直輸入しているそうだ。
パハール・ガンジの主イチオシのレストランは、エヴェレスト・ベーカリー・カフェ。ネパール人が経営しているだけあって、ネパール料理がうまい。僕はいつも通りチキン・スティームド・モモを注文したが、味はなかなか。かなりマニアックな場所にあるため、パハール・ガンジ・マニアでないと行けないだろう。ここのオーナーは以前サムズ・カフェを経営していたらしい。エヴェレスト・ベーカリー・カフェの壁には絵が描かれているのだが、それはある日本人の女の子が描いた。ちょうどパハール・ガンジにいたので、その人も紹介してもらった。
日本人旅行者には有名な、ゴールデン・カフェでも食事をした。ここも現在では韓国人の溜まり場と化しており、壁にはハングル文字が躍っている。辛ラーメンやキムチ・チャーハンなどの韓国料理を食べることができ、味もなかなからしい。
このゴールデン・カフェで千年に一度の偶然に出くわした。僕の小中高を通しての友人に偶然会ってしまった。高校を卒業してからずっと会っていなかったのだが、まさかインドのデリーのパハール・ガンジのゴールデン・カフェで再会を果たすことになろうとは誰が想像しえただろうか?人生とは時々魔法を見せてくれるものだ。お互い夢見心地だった。
ずっとインドに住んで、同じインド在住者と話をしていると、どうしても話すことがマニアックになっていく。しかし時々こうやってパハール・ガンジに来て旅行者と話すと、初心を思い出してよい。特に初インドの大学生旅行者などは非常に初々しく、驚くほどインドのことについての知識がない。ただインドに対するロマンを胸にインドに来ている、という感じだ。僕にもこういう時代があったかなぁ・・・と感慨に耽ると同時に、僕のこのホームページって一般人にはかなり専門的すぎて理解不能なんじゃないかと思ったりもする。ディープで日常的なインドを紹介すると同時に、インド用語についての丁寧な説明も忘れないようにしないといけないだろう。
パハール・ガンジの主(彼はパハール・ガンジを愛するあまり、背中にパハール・ガンジというタトゥーを入れた)が紹介してくれたところでデリー・ウォーカーに使えそうなポイントはそんなに多く、その代わりにこういう形で日記の中に登場させたのだが、旧知の友人に会えたこともあり、実りのあるパハール・ガンジ訪問となった。
日本に急用ができて、ホーリーの休暇を利用する形で一時帰国することになった。インド三大祭のひとつであるホーリーをインドで祝えないことや、クリケットのワールド・カップを見ることができないことが残念無念だが、致し方ない。本日午後7時半初のJL472便で東京へ向かった。
今回僕はJALで往復することにした。僕は今までインドに来るとき、エア・インディアとスリランカン・エアラインズを利用したことがあったが、JALは初めてだった。学生割引が効いてデリー〜東京間往復が税込33500ルピー前後である。JALであることを考えれば割安だ。
そういえばJALにまつわるヒンディー語のウンチク話を聞いたことがある。ヒンディー語で「ジャル」というと2つの意味が考えられる。ひとつは「燃える」という意味の動詞「ジャルナー」の命令形である。つまり「燃えろ!」という意味になるので、航空会社の名前としては非常に縁起が悪い。一方で、「ジャル」とは「水」、特に聖なる河ガンガーの水のことを指す意味もあり、こちらは非常に霊験あらたかな意味になる。「燃えろ!」と「聖水」の狭間にJALという名前は位置していることになるから、おそらく燃えてもすぐに鎮火されるだろう。
さすがにJALは日本人乗客のために特化したサービスを提供しており、他の航空会社とは一線を画している部分がいくつも見受けられた。まずは出発時間と到着時間の便利さ。午後7時半という出発時間は荷造りをし、空港に向かってチェック・インをするのに非常に便利な時間であり、また翌朝の早朝6時半頃東京に到着するというのも、ビジネスマンにとってはありがたいフライト・スケジュールだろう。
チェック・インのときから片言の日本語がしゃべれるインド人が応対してくれるのも、英語の苦手な日本人旅行者にとってはありがたいサービスだろう。フライト・アテンダントは全員日本人。機内では日本語が公用語として使用され、飛行機に乗り込んだ瞬間から日本に帰ったような気分にさせてくれる。機内食ももちろん日本食が用意されており、なかなかよい。機内販売の免税品も、いかにも日本人が好みそうなものばかりだ。エア・インディアの機内販売とは大違いで、けっこう利用してる人が多かった。
ところがどうもJALは日本人以外の乗客には乗り心地が悪いのでは、と思われる部分が気になった。まず、フライト・アテンダントの英語レベルがあんまり高くないような気がした。外国人の乗客との間でコミュニケーションに支障をきたしている客室乗務員がいた。彼女たちは研修生だったのだろうか?特にインド方面のフライトに同乗するなら、あのインド訛りの英語にも対応できるスチュワーデスが必要だろう。また、機内食にヴェジタリアン・メニューがないのにも驚かされた。インドに乗り入れる航空会社で、機内食にヴェジとノン・ヴェジを設定しないという傲慢を張っているのはJALだけではなかろうか?ヴェジタリアンのインド人は、チェック・インの際に予め伝えて、特別にヴェジタリアン・メニューを用意してもらわなければならないようだ。かわいそうに。
何より怒り心頭に達したのは、機内映画にインド映画が全くエントリーされていなかったことだ。インド映画ほど飛行機内でいい暇潰しになるものはないのに、なぜ無視するのだろう。しかもデリーから日本へ行く便では、時間の関係からか機内映画上映の時間がなかった。オーディオの方にはアジアン・ポップスの中にインドの歌が1、2曲入っていた。
僕はてっきりエコノミー席でも各座席に個人用モニターが付いているものだとばかり思っていたが、この便にそんなものはなかった。JALの癖に後進的な設備である。エア・インディアでこの設備なら許すが、JALは許せない。あと夕食のときにフランス産の安っぽい赤ワインを飲んだが、インド産ワインを遥かに下回るまずさだった。あんなものを舌の肥えた日本人によく提供するなぁと思った。
やはり一応高級キャリアとして認知されているだけあって、その他の格安航空会社よりも評価の目は厳しくなるのは当然である。他の航空会社ならギャグとして済ませられるところも、JALなら不満点となってしまう。いくつか不満点があったが、それでもデリーから東京まで直行で8時間足らずで行けるのは便利だし楽である。また、時間通りに運行する可能性が高いことも安心できる。マイレージを溜めることができるのもいい。エア・インディアを毎回使っていたら永久にマイルなんて溜まらないからなぁ・・・。
| ◆ |
3月19日(水) インド国際映画祭2003 |
◆ |
去年から日印国交樹立50周年記念イベントが日本・インド双方で行われて来た。もう2003年になったので、50周年記念イベントは打ち止めになったかと思いきや、まだまだ2002年度ということで、しぶとく行事が行われ続けていた。その締めとも言える行事が今日から東京で開催される。その名もインド国際映画祭。僕はひょんなことから東京にいたので、幸運にも参加することができた。会場は溜池山王駅近くにある国際交流基金。第一日目は、2001年に公開されて大ヒットを記録し、アカデミー賞外国映画部門にもノミネートされた名作中の名作、「Lagaan」。邦題は残念ながら「ラガーン クリケット風雲録」という誰をターゲットにしてるんだか何のウケを狙ってるんだか分からないトンチンカンな題名。聞くところによると、香港で公開されたときの題名をそのまま引用して来たらしい。近年稀に見るインド映画の傑作を、題名ひとつで駄作臭プンプンの作品に変身させてしまうその見事な手腕にインド人もビックリだ。「ラガーン」はもう何度も見たのだが、せっかくだから日本で日本人と一緒にもう一度見てみようと思い、足を運んだ。
開演1時間前くらいに会場に到着してしまったのだが、既に十数人の人々が来ており、開場を待っていた。「ラガーン」の字幕を担当した松岡環さんもいた。会場には今回上映される映画のポスターが飾られており、また歴代のインド国際映画祭のパンフレットや、「ラガーン」や「アルターフ(原題Mission Kashmir)」のDVDが売られていた。
いったいどんな人が見に来るのか、それが僕の一番の関心事だった。インド映画好きな人がたくさん来るのは一向に構わないのだが、やはり普通に映画が好きな人に僕はこの映画を見てもらいたかった。いざ蓋を開けて、ざっと見渡してみると、ほとんど日本人である。インド映画マニアか普通の一般人かは一見して分かるはずがないが、特に怪しさを醸し出しているような人物はあまりいなかった。なんとなく一安心。インド人らしき人影もチラホラ見かけたが、大半は日本人だったと言ってよい。
特に何の挨拶もなく突然「ラガーン」が始まった。それから約4時間、途中5分のインターヴァルを挟み、延々と上映され続けた。ちゃんとした映画館ではなく、ただの多目的ホールに椅子が並べられただけだったので、あまりインド映画を見るのに適した環境とは言えなかったかもしれない。しかし観客はグッと惹き付けられており、みんなじっと静かに鑑賞していた。僕は「ラガーン」を現地の映画館で、しかも熱気に包まれた超満員の映画館で見たので、インド人が笑うポイントは大体分かっている。僕がよく覚えているのは、審判が「アウト」と言って人差し指を上に向けると、ブバンら村人たちが空を見て「何だ何だ」と言い合うシーンがやたらと受けていたことだ。だが、それを笑うにはクリケットのルールの知識が要るため、日本人には全く受けていなかった。仕方ないか・・・。
だんだん映画が進み、クリケットのシーンになると、会場の雰囲気も次第に緊迫して来た。会場からはわずかだったがおそらくインド人を中心に、選手たちの一挙手一挙動に声が上がるようになり、またも一安心。映画が終わると、律儀にスタッフ・ロールまで流してくれた。インドの映画館でスタッフ・ロールを最後まで見ることはできない。映画が終わると同時にプチッと切られてしまうからだ。だからインド映画のエンド・ロールは実は貴重な映像なような気がする。少なくとも僕にはそう思えた。エンド・ロールが終わると会場から拍手が沸き起こり、解散となった。
改めて「ラガーン」を最初から最後まで松岡環さん入魂の日本語字幕と共にじっくり鑑賞し、やはり「ラガーン」は歴史に名を残すべき素晴らしい映画だと実感するに至った。インドを知れば知るほど、その深みを理解することができるだろう。村人チーム11人の中にはヒンドゥー教徒、イスラーム教徒、スィク教徒が、インドの宗教人口比に対応して組み込まれているし、不可触民の問題にもわざとらしい形ながら触れられているし、クリシュナとラーダーの恋物語が物語全体の伏線になっているし、クリケットのルールが分からない人のためにも一応さりげなくルールの説明がしてあるし、まとめの難しいスポーツ映画を、最後まで緊張感を保ったまま上手にまとめているし、まさに絶賛の嵐である。
映画上映後は、在京インド大使や国際交流基金関係者、その他の人々が集まって簡単な立食パーティーが開かれた。図々しくも僕もそれに参加させてもらった。インド人が出席するパーティーにビーフを出すという主催者側の勇気と無知に驚愕したが、「ラガーン」に出ていた主人公の母親役の女優スハーシニー・ムレーが急遽出席してくれており、なかなか楽しかった。在京インド大使の日本語が上手だったのにも驚いた。
今日は人類史に刻まれる忌まわしき日となってしまった。アメリカとイラクの戦争が始まってしまったのだ。18日にアメリカ合衆国大統領ジョージ・ブッシュが、イラク大統領サダム・フセインに、48時間以内に亡命するように通告し、その期限が切れると同時にイラクへの攻撃を開始した。
戦争が始まったとき、ちょうど僕は成田を飛び立ちデリーに向かっているところだった。成田空港のセキュリティーは普段の5割増しくらいに厳しく、手荷物検査が厳重に行われていた。そのため入国審査の前には長蛇の列ができていた。やはり戦争開始時に飛行機に乗るのを避ける人がいたためか、機内は空席が目立った。パニックを避けるためか、飛行機内のニュースで開戦は知らされなかった。僕はデリーに着いてから戦争が始まったことを知った。インドはとりあえず戦争開始に遺憾を表明する立場をとっている。マハートマー・ガーンディーを生んだ国として当然の態度だろう。しかしアメリカを支持しなければならない日本の苦しい立場も分かる。重要なのは立場を明確にすることだ。
ちょうどデリーでは昨日ホーリーが行われたところだった。さすがにもう水掛けは行われていなかったが、色の付いた服を着た人がチラホラ見受けられたり、地面が色で染まっていたりした。そういえば、空港の機内預け荷物受取所のところに色水の跡があった。空港内でもホーリーが祝われたのだろうか・・・?
今回は10日間だけ日本に帰っていた。あまり休まる暇のない日本滞在だったが、こういう忙しい方が僕は好きだ。デリーに着いてみると、この10日の間にガラッと気候が変わったことに驚かされた。僕がデリーを発ったときはまだ肌寒くて、セーターを着ても寒いくらいだった。あれから10日後、出発時と全く同じ格好でインディラー・ガーンディー国際空港に降り立ったのだが、今度は一転して暑く感じた。ホーリーが終わると酷暑期が始まると言われているが、全く本当にその通りだ。僕は寒いより暑い方が好きなので、自然と顔から笑みがこぼれた。これから汗ビッショリの季節が始まる。水シャワーが気持ちよさそうだ〜。
イラクとアメリカが戦争を始めたというのに、インド人の関心は別の方向へ向いている。それはクリケットのワールド・カップである。僕が日本にいる間にインド・チームはスーパー・シックス・シリーズでケニア、スリランカ、ニュージーランドを下し、堂々の準決勝進出を果たした。僕がデリーに着いたときにちょうどインドVSケニアの準決勝戦が始まっており、インド人は皆テレビに見入っていた。試合はインドでは真夜中まで続き、遂にインドがケニアに勝利した。半ば信じられないが、インドは決勝進出を果たしてしまった。決勝戦で戦うのは強敵オーストラリア。もうインドはイラク戦争どころではない。
これから世の中がどう動いていくのか分からないが、この時期にインドにいることができるのは幸せなことだと思う。日本にいるより安全そうだし、クリケットのおかげで、戦争だからといって雰囲気が暗くなってないのでよい(日本のTVは暗かった・・・)。
それにしても無性に気になるのはサダム大統領のことをフセイン大統領と呼び慣わす日本のマスコミである。湾岸戦争の頃から問題となっており、いろんなところで専門家が「フセイン大統領と呼ぶのはおかしい」と主張しながらも、もう慣例化してしまって直されずに来ている。イスラーム世界では名字がない代わりに父親の名前を名乗るので、サダム・フセインの「サダム」が実の名で「フセイン」は父親の名である。現地の映像で見てもサダム大統領と言っている。フセイン大統領という呼称は聞いたことがない。仕方ないと言えば仕方ないのかもしれないが、間違った固有名詞が日本で慣例化してしまうのは、インドにおいても他人事ではないため、個人的に非常に憂慮している。
| ◆ |
3月22日(土) Chura Liyaa Hai Tumne |
◆ |
久々に期待できそうなヒンディー語映画が封切られた。その名も「Chura Liya Hai Tumne(君が盗んだ)」。音楽がとてもかっこよくて、気に入っていた上に、ジャケットになぜか中国語が書かれていた。もしかして中国を舞台にしたインド映画だろうか?訳の分からない期待が膨らんでいた。
主演は新人ザイード・カーンと、僕はあまり好きではないイーシャー・デーオール。個性的すぎる悪役俳優として定評のあるグルシャン・グローヴァーも出演していた。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
Chura Liyaa Hai Tumne |
● |
| Chura Liyaa Hai Tumne |
ヴィジャイ(ザイード・カーン)とティナー(イーシャー・デーオール)はビーチで出会ってお互いに恋するようになった。だが突然ティナーはトニーおじさんに会うためにバンコクへ発ってしまった。ヴィジャイはティナーを追いかけてバンコクへ行く。
バンコクでティナーは、トニーおじさんが事故で死亡したことを知らされる。そして彼の遺品を受け取る。そんなティナーを待ち受けていたのは、オーム(グルシャン・グローヴァー)、シーナー、チンガールという3人組の悪党だった。彼らは執拗にティナーに「1億ルピーはどこだ?」と言い寄る。困惑するティナーを助けたのは、インド大使館のディーパク・チョープラーだった。彼はティナーに事件の真相を伝える。
実はトニーおじさんは、3年前に起こった現金輸送車襲撃事件の犯人だった。トニーおじさんはオーム、シーナー、チンガールらと共に現金輸送車を襲撃し、どさくさにまぎれて奪った1億ルピーを持って雲隠れしてしまっていたのだった。トニーおじさんが死んだ今、1億ルピーがどこにあるかを知っていそうなのはティナーだけだった。ディーパク・チョープラーもティナーに「1億ルピーはどこだ?」と聞く。そんなの全く知らなかったティナーは困ってしまう。
ヴィジャイと合流したティナーは、彼に全てを打ち明ける。しかしオームはティナーに暴露する、ヴィジャイもオームらの仲間で、1億ルピーを狙っていると。実は3年前の事件を起こした犯人グループの中にもう1人いた。名前はマヘーシュ・ヨーギー。しかし彼は仲間に裏切られて殺害されていた。だが実際は生きながらえたということもあり得る。実はヴィジャイはマヘーシュではないのか?ティナーはヴィジャイを尾行する。
ヴィジャイがホテルのレセプションから「ヨーギー」と呼ばれているのを影から聞いたティナーは、ヴィジャイに問い詰める。しかしヴィジャイは「オレはマヘーシュ・ヨーギーの弟、プラカーシュ・ヨーギーだ」と言う。兄の敵を討つためにオームらの仲間になり、1億ルピーを取り返そうとしているのだ、と語った。ティナーはその言葉を信じる。
1億ルピーはいったいどこにあるのか?ティナーも在り処を知らないことを知ったオームたちは、一緒に知恵を絞って考えることになった。本当は別の誰かが隠し持っているのではないか?ヴィジャイは疑問を提起して仲間割れを誘った。疑心暗鬼渦巻くオームら悪党たちは、お互いにお互いの荷物をチェックすることになった。その過程でチンガールとシーナーが何者かに殺害される。
実はトニーおじさんは1億ルピーを200万ドルの価値のある1枚のコインに換えていたのだった。そのコインはティナーが持っていた。しかし同時にマヘーシュ・ヨーギーには弟などいなかったことが、ディーパクからの連絡により判明する。もはやヴィジャイを信用することができなくなったティナーは、ディーパクにそのコインを渡すことにする。ところが、ディーパクがインド大使館員というのは真っ赤な嘘で、彼こそがマヘーシュ・ヨーギーだったのだ。チンガールらを殺害したのも彼だった。ティナーは一度マヘーシュにコインを渡してしまうが、土壇場でヴィジャイがマヘーシュをやっつける。最後に明かされたのは、ヴィジャイの正体はインド大使館のオフィサーだったというオチだった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
久々に骨のあるお馬鹿インド映画を見てしまった気分だ。僕はこの映画をサスペンス・コメディーと分類したい。サスペンス映画にしてはあまりにストーリーがお粗末で破綻だらけだ。コメディー映画にしても、ウケを狙ったギャグのようなものは見当たらない。だが、サスペンスにしてコメディーだと思えば、けっこうそのハチャメチャぶりを楽しむことができる映画である。
トニーおじさんがどこかに隠した1億ルピーを巡ってのサスペンス(というよりドタバタ劇)だが、まず悪役が面白すぎる。グルシャン・グローヴァー演じるボスのオームは、ヒゲの形が馬鹿っぽ過ぎて全然恐怖感が出ていない。すぐに人に油をかけて火をつけたがるチンガールも、遂に映画中で実際に人に火をつけたことはなく、ただのチンピラで終わってしまっていた。やたらセクシーな格好をしているシーナーにしても、そのセクシーさを武器に何かをする訳でもなく、大した活躍もせずに死んでしまった。この3人組のキャラクターは何かに似ている・・・そう、タイムポカン・シリーズの悪役3人組だ!悪役なのにコメディーチックなのだ。しかしウケを狙っているわけではない。かと言って悪役として失格というところまで落ちぶれてもいない。悪役とコメディアンの間の微妙な境界線に位置するキャラクターだった。おかげで命を狙われているはずのティナーにも全然緊張感がなかった。というか、ティナー演じるイーシャー・デーオールの演技力のなさなのかもしれないが。
新人ザイード・カーン演じるヴィジャイも面白いキャラだった。正体不明の謎の男なのだが、やたらと陽気で無邪気だ。ティナーに恋する男ヴィジャイ⇒オームたちの仲間マヘーシュ・ヨーギー(?)⇒マヘーシュ・ヨーギーの弟プラカーシュ・ヨーギー⇒いったい何者?⇒実はインド大使館員、と彼の名前は次々に変わっていき、正体がばれるごとに「今度はいったい何て言い訳するのか」と笑いが漏れたほどだ。この謎ぶりと性格の明るさは、日本の少女漫画に出てくる、主人公が恋する男の子のキャラクターに似ている・・・かもしれない。
ザイード・カーンは俳優サンジャイ・カーンの息子である。サンジャイ・カーンがどれほど有名な俳優だったかは知らないが、彼の娘スザンヌ・カーンはリティク・ローシャンと結婚したことで有名である。だからザイード・カーンとリティク・ローシャンは義理の兄弟ということになる。ザイード・カーンの顔はいかにも今時の若者という感じの甘いマスクで、もし日本で有名になったら「インドのキムタク」と紹介されそうなぐらいだ。90年代のボリウッドは、シャールク・カーン、サルマーン・カーン、アーミル・カーンなどカーン姓を持つ男優たちが大活躍したが、このザイード・カーンも新たなカーンとして注目されている。だが、この映画がリティク・ローシャンのデビュー作「Kaho Na... Pyar Hai」ほどヒットすることはないだろう。
舞台はタイの首都バンコクだった。ほぼ全体に渡ってバンコクで撮影されており、なかなか目新しい雰囲気だった。バンコクのスカイトレインが登場したり、デリーより遥かに発展したバンコクのショッピング・モールが惜しげもなくロケに使用されたりと、見ていて楽しかった。僕はもう3年以上バンコクへ行っていないので、どこがどこだかあまり分からなかったが、多分バンコクに足繁く通っている人なら、ロケ地を特定できたはずだ。なんとパッポン通りのゴーゴー・バーまで出て来た。かなり際どい衣装を着て踊る女の子たちが「背景として」登場していた。この映画は全年齢対象のはずだったが、ゴーゴー・バーなんて映しちゃってよかったのだろうか・・・?
映画中、数人のタイ人が脇役として登場してセリフをしゃべったが、彼らは一応タイ語を話していた。「サワディー」や「コプクン」ぐらいは聞き取れた。最後のエンド・ロールにもタイ人の名前が見えたので、バンコク・ロケでタイ人がスタッフとして参加していたはずだ。「マイペンライ」の国で「コーイー・バート・ナヒーン」の人々が映画を撮ると、どういうことが起きるのだろうか?なんとなく撮影現場を見てみたくなった。
というわけで、映画を見る前に抱いていた「中国語がジャケットやポスターに使われているから中国関連インド映画」という期待は見事にすかされたことになった。つまりインド人にとって漢字もタイ文字も同じに見えるということか・・・。インド系文字の仲間であるタイ文字くらい認識してあげてもいいのに・・・。確かにバンコクにはチャイナ・タウンもあるが、映画中には全く出てこなかったからその言い訳は通用しないだろう。でもバンコク・ロケという路線は決して悪くなかったと思う。他のインド映画にはない独特のアジア的空気が漂っていた。
ストーリーはどう考えても辻褄が合わない箇所がいくつかあったが、お馬鹿インド映画ということでいちいち荒さがしするのはやめておく。大味で変な映画だったが、なぜか見終わった後の感情は悪くなかった。キワモノ映画好きの人や、バンコク好きの人にオススメの映画、と言っておこう。
| ◆ |
3月23日(日) クリケット・ワールドカップ決勝戦 |
◆ |
世界中のマスコミがイラクを中心とした中東情勢に注目する中、我々インドに住む民たちは、南アフリカの首都ヨハネスブルグに全身全霊を傾けていた。今日、クリケット・ワールドカップの決勝戦が行われる。我らがインド・チームは幾多の激戦を乗り越え、決勝戦まで勝ち上がってきた。対するはディフェンディング・チャンピオンかつ現在も世界最強を誇るオーストラリア・チーム。インドとオーストラリアは予選リーグでも一戦交えており、結果はインド・チームの惨敗。過去の戦績を見てみても、オーストラリアはインドに圧勝している。この戦いはインドにとって決勝戦であると同時に、雪辱戦でもある。オーストラリア・チームは今回のワールドカップで無敵を誇っており、一度も負けていない。勝つのは困難かもしれないが、是非勝ってもらいたいものだ。
試合はインドの時間で昼頃から始まった。まずはオーストラリア・チームのバッティングから。ザヒール・カーン、ジャワーガル・スリーナート、アーシーシュ・ネーヘラー、ハルバジャン・スィンらインド・チームのボウラーたちが気合を込めて投球し続けたが、どうしてもアウトが取れない。一方、オーストラリア・チームのバッツマンはアグレッシヴかつ慎重なバッティングでどんどんランを稼いで行った。今日はハルバジャン・スィンの調子がよく、なんとか彼が2ウィケットを奪取したものの、それ以後インド・チームの攻撃は全く通用しなかった。オーストラリア・チームのキャプテン、リッキー・ポーティングが大活躍し、一人で140ランも取ってしまった。とうとう50オーバーが終了し、オーストラリアは359ランという大量得点を稼いだ。この数字はワンデイ・マッチ得点歴代トップ10にランクインするほどの驚異的な得点である。インド・チームの勝ち目はもうほとんど残っていない。しかしインド・チームはこの巨大な壁にぶつかっていかねばならない。この困難な大逆転劇のキーとなるのはマスター・ブラスター、サチン・テーンドゥルカルと、キャプテン、サウラヴ・ガーングリーの活躍である。
インド・チームのオープナー(先頭打者2人)はいつも通りサチン・テーンドゥルカルとヴィーレーンドラ・セヘワーグ。ところが最初のオーバーでサチンがアウトになってしまうというハプニングが起こった。この時点で既にインド・サポーターの希望の灯火の5割は消え去ったと言ってよかった。サチンの後にはサウラヴ・ガーングリーが登場し、セヘワーグと共に慎重にバッティングを重ねていったのだが、ガーングリーもやがてすぐにアウトになってしまった。インド・チームの強打者2人が早々にフィールドから消え去ってしまったことにより、ほぼ勝負はついたと言ってよかった。
意外な活躍を見せてくれたのがオープナーのセヘワーグだった。ガーングリーの次に出て来たムハンマド・カイフが1ランも稼げないままアウトになってしまうと、その次にラーフル・ドラヴィルが出て来た。このセヘワーグとドラヴィルのコンビが安定したバッティングを見せ、セヘワーグは合計82ランを稼いだ。だが彼も運に見放された形でラン・アウトになってしまった。
次々にバッツマンがウィケットを取られる中、インド・チームに思わぬ助っ人がやって来た。それは雨雲である。急にヨハネスブルグの空を雨雲が覆い始め、やがてポツポツと雨が降り始めた。これは恵みの雨か?何となく「Lagaan」のラスト・シーンを想起させる雨である。雨が降るとフィールドが濡れ、ボールが滑りやすくなり、バッティングに有利になる。それだけでなく、もしこのまま雨が止まなければ試合が延期になるか、あるいは中止になる可能性もある。予選リーグで雨が降り続いた場合、その試合はドローとなっていた。決勝戦で雨が降った場合はどうなるのか分からなかったが、なにやらインド・チームに流れが傾いてきたようにも思えた。
雨が強くなり、とうとう試合は一時中断してしまった。雨が止むまで待つことになった。ヨハネスブルグの雨はスコール型のようで、ザァーッと降ってすぐに止むようだ。試合が中断している間、TVはコマーシャルやハイライト・シーンを流して対応していた。数十分ですぐに雨は止み、空にはキレイな虹がかかった。果たしてこの虹はどちらのチームのためにかかっているのか?フィールドが整備され、再び試合が開始された。
ところが雨の後、ますます試合はオーストラリアの一方的な試合になっていった。ラーフル・ドラヴィル、ユヴラージ・スィン、ディネーシュ・モーンギヤーと後続打者が徐々にアウトになって行き、後はボウラーだけが残ってしまった。ボウラーはあまりバッティングが得意でないようで、ハルバジャン・スィン、ザヒール・カーン、ジャワーガル・スリーナートらはあっけなくアウトになってしまった。結局インド・チームは10ウィケットで合計234ランしか取ることができず、オーストラリア・チームにまたも苦い敗北を喫してしまった。こうして2003年のクリケット・ワールドカップは、オーストラリア・チームの優勝で幕を閉じた。しかし悲しむことはない。優勝こそ逃したものの、インドは準優勝なのだ。よく頑張ったと賛辞を送りたい。
ところで、今回のクリケット・ワールドカップを観戦していろいろ気になる点があった。まず、どうも国ごとにレベルの差がありすぎるような気がした。クリケットが盛んな国はほぼ旧大英帝国植民地だった国と重なるが、強い国はとことん強く、弱い国はどう転んでも弱小国という感じだった。今回優勝したオーストラリアはやはり攻守共にバランスが取れており、弱点が見当たらない。その他、僕が見たチームの中では、インド、スリランカ、パーキスターンなどが強いと思った。一方で、オランダ、ナミビア、カナダ、バングラデシュのように、予選リーグでほとんど勝ち星を挙げれなかった弱小チームも存在する。これら強いチームと弱いチームの試合を見ていて、素人目にもはっきり分かる歴然とした実力の差をまざまざと感じた。もしクリケットを発展させていきたいのだったら、大至急クリケット後進国の育成に力を入れないといけないと思った。このままだと差が広がり過ぎて、ワールドカップが面白くなくなる恐れがある。
クリケットの試合において、微妙な判定のときにビデオ映像や音波測定器などのハイテク機器の情報が判断材料に使われることも気になった。例えば日本の野球の試合だったら、VTRで見て明らかに誤審であっても、審判の判断が採用される。しかしクリケットの場合、微妙な判定のときにはVTRが流され、それに従って最終的に判断が下される。音波測定器は、バットがボールに触れたか触れなかったかを判断するために使用される。野球よりも古い歴史を持っていながら、案外新しいものを積極的に取り入れているスポーツだと思った。
また、TVでクリケットの試合を見ていて、本当にイライラするのはコマーシャルの多さ。オーバーごとにTVCMが入り、試合中継中も上の方に文字広告が入る上に、試合フィールドにはデカデカとスポンサーのLGとペプシのロゴマークが横たわっている。ウィケットを取ったり、誰かが6sを打ってもCMが入る。インドのTVCMはけっこう楽しいので、基本的にCMを見るのは好きだが、同じCMを何度も見せられると飽き飽きしてしまう。
インド人がクリケット大好きなのは有名だが、インド人のクリケットTV観戦方法はなんとなく日本人の野球・サッカー観戦時に比べて温度差があるような気がした。まず、試合ごとにインド人の熱の入れ方が全然違う。やはりパーキスターン戦がもっとも重要視されているらしく、一般庶民から政治家まで、相当熱狂的な応援体勢だった。決勝戦も盛り上がっていたが、パーキスターン戦の盛り上がりを見てしまうと、なんとなく物足りないように思えてしまった。また、インド人は勝っていると乗り気で応援するが、敗色が濃厚になると「もうだめだ」ということで急に熱が冷めてしまうところもある。あと、やはりクリケットの試合は果てしなく長いので、最初から最後まで1シーンも欠かさず見るような人は、いくらインド人でも少ないようだ。途中で適当に息抜きしながら見ている。
何かの外国語を習う際、必ず最初に触れられるのが、「言語を学ぶことは文化を学ぶことであり、文化を学ぶことは言語を学ぶことである」という一文である。外国人が日本の文化を理解したかったら多少の日本語の知識は必須であるし、日本語を学ぶことによって自然と日本人の文化や思考を知ることができる。インドの場合もほぼ同じで、インドの文化を知ろうと思ったらヒンディー語の知識は多少なりとも必要である。ただ日本の場合と違うのは、ヒンディー語の他にも必要となる言語の数が圧倒的に多いことである。国土が広いだけに、また周辺地域との文化交流が昔から盛んだっただけに、興味の対象が広がるごとに古今東西各種の言語の知識が必要となってくる。現代インド言語ならヒンディー語、ベンガリー語、タミル語、マラーティー語、パンジャービー語などなど、ヒンディー語の中でも方言がいくつかあり、ブラジュ方言、アワディー方言、ラージャスターニー方言、パハーリー方言、ビハーリー方言などなど、古典語ならサンスクリト語、パーリ語、プラークリト語など、周辺諸国の言語まで触手を広げるとペルシア語、アラビア語、ロシア語、ポルトガル語、フランス語などなど。英語はそれらの無数にある言語を超越する言語に思われがちだが、所詮それらの言語の一部にしか過ぎない。ヒンディー語だけの知識で全インドを語ることが難しいのだから、英語の知識のみでインドを語ることがどれだけ愚かなことか、それは自明の理だ。
とはいいつつも、なかなか一度に多くの言語を学ぶのは難しいものだ。現在僕は専らヒンディー語を勉強している。それでも、ヒンディー語を通してインドの文化や習慣をふと垣間見ることが時々ある。今日は1人称の代名詞「マェン」と「ハム」の話。文法の話だが、なるべく簡単に分かりやすく書こうと思う。
ヒンディー語の標準的な文法を学ぶと、1人称単数の代名詞は「マェン」、1人称複数の代名詞は「ハム」と教えられる。つまり、「私は」が「マェン」であり、「私たちは」が「ハム」である。英語の「 I 」と「We」に対応するので、これを理解するのにそんなに困難はない。
ところが実際にインドに来て、人々の話すヒンディー語を聞いていると、耳のいい人はすぐに「あれっ」と気が付く。「マェン」の代わりに「ハム」と使っている人がけっこういるのだ。例えば標準ヒンディー語で「マェン カーナー カーウンガー(私は食べ物を食べます)」と言うところを「ハム カーナー カーエンゲー(私たちは食べ物を食べます)」と言う人が多い。また、映画のタイトルも「マェン」より「ハム」が使われることが圧倒的に多く、去年日本で公開されたヒンディー語映画「ミモラ」の原題も「ハム ディル デー チュケー サナム」だった。直訳すると「私たちは心を与えた、恋人よ」になるが、真の意味は「私は心を与えた、恋人よ」である。最初は「ハム」を使うインド人は教養がなくて間違って話しているのか、と思ってしまうが、映画のタイトルにまで「ハム」が使われているのを見るにつけ、ある程度一般に認められた用法であることが分かってくる。
「マェン」の代わりに「ハム」を使うのは、一種の敬語だと説明されたことがある。「マェン」を使うより「ハム」を使って話した方が、柔らかな印象になるそうだ。ヒンディー語では同じような敬語のシステムが2人称・3人称の代名詞にもあり、単数の対象に対してわざと複数形を用いると、相手を持ち上げた表現になる。この敬語システムはヨーロッパの言語にもよく見られる。また、常に「ハム」を使って話すと、文法が楽になるという利点もある(専門的な話になりすぎるので説明は省略)。
これとは逆に、「マェン」の代わりに「ハム」を使うと尊大な表現になるという人もいる。日本の古語文法で言う自敬表現になり、目の前の人よりも自分の方が立場が上であることを示すことになるそうだ。
「マェン」の代わりに「ハム」を使うのは一種の方言だと説明されたこともある。確かにビハール州、ジャールカンド州、ウッタル・プラデーシュ州、マディヤ・プラデーシュ州、ラージャスターン州、ハリヤーナー州、ウッタラーンチャル州、ヒマーチャル・プラデーシュ州など、北インドの大部分で話されているヒンディー語の方言は「マェン」がなく、1人称単数でも「ハム」を使う。また、ベンガリー語やマラーティー語でもヒンディー語の「マェン」に当たる単語がなく、やはり1人称単数でも「ハム」に当たる代名詞を使う。
1人称単数形の「ハム」がこれだけ広まったのは、伝説的映画スター、アミターブ・バッチャンが「ハム」を連発したからだ、という面白い説も聞いたことがある。アミターブ・バッチャンはウッタル・プラデーシュ州のイラーハーバード出身であり、1人称単数形に「ハム」を使う方言が話されている地域に含まれる。アミターブ・バッチャンを崇拝するインド人は信じられないほど多いので、彼の話し方を真似するインド人が続出する図は容易に想像できる。アミターブ・バッチャン登場以前と以後の映画のセリフを比べてみれば、この説が実証されるかもしれないが、今のところ面倒なのでやっていない。
しかし僕が聞いた中で、もっとも説得力あるのが以下の説である。もともとインド人に「マェン」という概念がなかったという説だ。つまり、「個人」という概念がないため、「私は」という言葉を使う必要がなかったし、そういう考えもなかったというのだ。基本的にインド人は農耕民族かつ大家族主義なので、団体行動が生活の主体となる。いつでも集団の中で相対的に生きているので、絶対的に「オレが〜する」ということがなかった。何かをしようと思ったときは「ハム」、つまり「みんなで〜しようぜ」ということになり、個人行動する機会がないのだ。卑小な言葉で片付けてしまえば、「連れション主義」ということになるだろう。日本のような個人主義の発達した国でも連れションは存在するかもしれない。しかし日本での連れションが「僕はションベンしに行くけど、君は?」という個人の意見を尊重する感じなのに対し、インドの連れションは「さあ、ションベンしに行こうぜ!」という強制的で包括的な雰囲気なのだろう。個人と個人の間に境界がなく、あたかもみんな同じ存在の一部であるかのように行動する。インド人のこの「ハム」の感覚を理解できるのとできないのとでは、インド生活で受けるストレスの量が全く違うと思われる。彼らにとって個人の持ち物などもともと意味をなさないのであり、「みんなのものはオレのもの、オレのものはみんなのもの」の世界なのである。
しかしやがて産業革命の余波がイギリス人らによってインドに到達するに従い、また都市部で全く赤の他人が隣り合わせに住むようになるにつれ、インドにも「個人」という概念が生まれた。「マェン」という代名詞が使われ始めたのは、昔から都市として発展していたデリーから、比較的豊かだったパンジャーブ地方にかけての地域のようだ。近代的な生活が導入されるにつれて公と私が区別され、個人の意見を表明する機会や、個人行動する機会が増え、それに伴い、「私は」と言う必要が生まれた。これが「マェン」の誕生の由来である。20世紀に入り、標準ヒンディー語文法が形成される段階で、英語文法などとの対比から1人称単数を表す代名詞を設定する必要が生じ、デリーで使われていた「マェン」がその地位に居座ったのだろう。しかし「マェン」はインド人の本質とはあまり相容れない単語であり、それ故「マェン」を使うより「ハム」を使った方が丁寧な表現に聞こえるのかもしれない。それは今でもインド人の心の中で、近代的な個人主義が完全に一般化していない証拠とも言える。そう思うとなんとなく安心する。
去年の11月に、デリー、アーグラー、ヴァーラーナスィーなどの教育機関に留学している外国人学生を対象としたセミナーがリシケーシュであった。これは毎年行われている行事で、セミナーと聞いただけで行く気をなくす人も多いのだが、実態は修学旅行のような和気藹々とした旅行、もっと言えば合コンのようなものなので、インドで勉強している留学生は妻子を質に入れてでも行くべきである。去年のセミナーでは、デリーからはデリー大学、ジャワーハルラール・ネルー大学、ケーンドリーヤ・ヒンディー・サンスターン、ジャーミアー・ミッリアー大学、ガンダルヴァ・マハーヴィディヤーラヤなどから外国人留学生が参加していた。このセミナーに参加するだけで一気に知り合いが増え、その後のデリー生活が一段と楽しくなること請け合いである。・・・ただ僕の場合、敵も多少増えたが・・・。
そのリシケーシュ・セミナーで、僕は高名な教授とも知り合いになった。インドの人間国宝または勲一等に当たるパドマシュリーを受賞した、シャーム・スィン・シャシ博士だ。セミナー中、僕はパドマシュリー博士と呼び習わしていた。社会学が一応彼の専門分野らしいが、詩や文学など各分野にマルチな才能を発揮している人で、人柄も大変温厚かつ頼りがいのある人だ。彼の著書は300冊を超えるらしいが、その中でも全110巻の規模を誇る「インド大百科(Encyclopaedia
Indica/1996年編纂開始/全巻セットで165000ルピー)」を編纂したことは驚嘆に値する。1936年生まれなので、今年で67歳。若者に対して非常に温かい眼差しを投げかけてくれる人で、「私を目指して努力しなさい」というのが口癖である(でも全然嫌味のない言い方)。
そのパドマシュリー博士の著書に「アグニサーガル(火の海)」という小説がある。けっこう有名な本らしく、インドの国営放送ドゥールダルシャンでドラマ化されたほどらしい。やはりパドマシュリーはやることなすこと常人とは違う。今日はその「アグニサーガル」を題材にした舞踊劇がトリヴェーニー・シアターにて行われるということだったので、学校の友人などと共に見に行った。
会場にはシャーム・スィン・シャシ博士本人の他、インドを代表する文学者が一堂に会していた(と思われる)。6時から開始の予定だったが、本日の主賓である情報放送省大臣ラヴィ・シャンカル・プラサードがなかなか来なかったため、皆ずっと待っていた。しびれを切らして、もう始めてしまおうか、とのそのそ動き出した矢先にやっと大臣が来場した。6時半過ぎにやっと始まったが、大臣は遅れて来た割にすぐ途中で帰ってしまった。かなり忙しいようだ。
まずはサラスヴァティー女神へのプージャーから始まった。シャシ博士や大臣が壇上に上がり、舞台の隅に鎮座するサラスヴァティーの像に花輪をかけた。本来のプージャーならディーヤー(灯火)を灯すところだが、パドマシュリー博士の「場内は火気厳禁だからやめとこう」の一言で点火が見送られた。さすがパドマシュリー、インド人らしからぬ、宗教を妄信しない融通の利きようだ。
プージャーが終わり、一通り賓客同士で花輪の掛け合いが終わった後、3人の子供たちが何かの歌を歌った。そしてTVドラマ「アグニサーガル」のダイジェスト版が放映された。リシケーシュでシャシ博士と会って以来、「アグニサーガル」を読んでみようと思っていたが、今日まで読むことがことができなかった。だからどんな内容なのかよく知らずに今日は臨むことになってしまった。ダイジェスト版を見た限りではなんか楽しくなさそう・・・というかこれは映像が古臭くてしかもダイジェスト版だったためかもしれない。意味も全然掴めなかった。
TVドラマ版「アグニサーガル」上映の後は、いよいよ舞踊劇「アグニサーガル」。具体的に言えば、今回の舞踊はカタック・ダンスだった。姉妹カタック・ダンサーとして有名なナリニー&カマリニーが主演を務め、振り付けは彼女たちのグルであるグル・ジテーンドラ・マハーラージ。最近のインド舞踊のトレンドとして、ただ踊るだけでなく、演劇性のある舞踊をやったり、コンテンポラリー・ダンスの要素を取り入れたりするのが流行っているが、今回の「アグニサーガル」もそんな感じだった。衣装が非常に美しく、手の動きと顔の表情、そして全身を使った感情表現が素晴らしかった。まるで手話の演劇を見ているかのようだった。相変わらず「アグニサーガル」のストーリーはよく分からないままだった。
舞踊劇の後、なぜか「オマケ」ということでナリニー&カマリニーのデュオ・ダンスが始まった。タブラーとヴァイオリンの生演奏の加え、グル・ジテーンドラ・マハーラージがボール(口三味線)を担当した。
ピンクの衣装を着たナリニーと、緑の衣装を着たカマリニー、さすがに2人は姉妹だけあって息があっていた・・・と書きたいところだが、どうも2人の間にレベルの差があって、アンバランスな印象を受けた。どちらが姉か分からないが、とりあえずナリニーの方が背が高く老け顔をしているし、ナリニー&カマリニーというようにナリニーの方が名前が先に来ているので、おそらく彼女が姉だろう。ところがどう見てもカマリニーの方が圧倒的に踊りが上手いのだ。ダンスというのは案外知ろうと目にも上手い下手が分かってしまうもので、特に並んで踊っている2人を見ると、その差はすぐに分かってしまう。ダンスの切れ、回転の速さと正確さ、顔の表情、手の動きの艶かしさ、どれを取ってもナリニーよりカマリニーの方が上だった。う〜む、貴乃花、若乃花のようにならなければよいが・・・。
ナリニー&カマリニーの踊りは確か「オマケ」だったはずだが、これが長いの何のって、もう果てしなく続くんじゃないかと思うくらい続いた。サティヤ・サーイーバーバーのような髪型をしたグル・ジテーンドラ・マハーラージは、顔をブンブン左右に振って舞踊と音楽の指揮に没頭しているし、姉妹は永久機関で動いているかのように疲れも知らずに踊り続ける。インド伝統芸能のコンサートを鑑賞していると、このような事態はよく起こる。インドのアーティストたちは舞台に上がるとやたらとでしゃばりたがり、しかも自分の割り当て時間を大幅に延長する積もりで最初からやっているとしか思えないほど確信犯的な時間の使い方をする。見るともう時計は9時を廻ってしまった。しかしここでもパドマシュリーが動いた。しびれを切らして「そろそろ帰りたい」「早く終わらないか」と思い始めた観客の気持ちを察知してか、彼は走り書きを書いたメモをグルに渡させた。おそらく「早く終われ」と書いてあったのだろう。それを見たグルは「これが最後だ」と言ったが、まだ終わりそうな気配がない。そこでもう一度パドマシュリーが動く。2枚目のメモを受け取ったグルは、追い込まれるような形で音楽と舞踊を切り上げた。やっと終わった・・・!
最後にグル・ジテーンドラ・マハーラージ、ナリニー&カマリニー、その他のダンサー、演奏者、シャシ博士などなどが舞台に上がり、大団円となった。しかしここでパドマシュリー氏はひとつのミスを犯した。誰も指摘しなかったが、舞台の下では冒頭で歌を歌った3人の子供たちが、舞台に上がってもう一度拍手を受けたそうに待っていたのだった。まだ10歳にも満たなそうな女の子たちである。9時を過ぎたのでもう眠たくなっているだろう。それを我慢して今までずっと最後まで残っていたのだ。彼女たちのこの忍耐に報いるためにも、もう一度彼女たちにスポット・ライトを当ててあげてもよかったのではないか。しかし思った以上に時間が押してしまって焦ったのだろうか、パドマシュリー博士はあっさりと大団円を解散させてしまい、子供たちが舞台に上がる機会は永遠に失われた。
結局「アグニサーガル」がどんな内容なのか全く分からなかったが、おかげでその本を読んでみようという野望が生まれた。面白い内容だったら、パドマシュリー先生の許可をもらって、また「デーヴダース」のように翻訳でもしてみようかと思っている。
| ◆ |
3月29日(土) 大阪外語大学ヒンディー語劇 |
◆ |
大阪外語大学ヒンディー語学科というと、インドのヒンディー語学会でけっこう名の知れた存在である。なぜなら毎年溝上富夫教授率いるヒンディー語劇劇団がインドで公演を行っており、高い評価を得ているからだ。溝上教授は去年ヒンディー語研究で功績のあった外国人に贈られるジョージ・グリアルソン賞を日本人で初めてインド政府から受賞した。今日はその大阪外語大学ヒンディー語劇劇団がデリーで演劇を行った。今回は、今年で第5回目を迎えた国立演劇学校(National School of Drama)主催の演劇祭、バーラト・ラング・マホーツァヴァに「招待」されるという大変名誉ある公演だった。場所は国立演劇学校内にあるアビマンチュ劇場。
今までの経験から、どうせフリーパスで入れるだろうと思って高をくくっていたが、今回は夜8時半からという悪条件にも関わらず、やたらと盛況だった。席は指定席制で、チケットを持っていない人は席に座ることができない状態。僕は天からの授かり物で最前列のチケットを手に入れていたので、余裕で鑑賞することができた。
まずは「Bure Fanse Mohabbat Mein(恋の虜)」というヒンディー語オリジナルの劇が行われた。登場人物は3人だけ。全く性格と趣味の異なる姉妹が、同じ男を好きになってしまうというドタバタ劇。姉のリターは物静かな男が好きで、妹のラッジーはおしゃべりな男が好きだった。マノーハルは姉妹を二股しており、リターの前では温厚でシャイな男のふりをし、ラッジーの前では口のよく動く男のふりをしていた。しかし姉妹が揃っているところにマノーハルが来てしまい、姉妹はショックを受けて倒れてしまう。そのままマノーハルはまたどこかへ去って行ってしまう、というあらすじだ。
3人しか登場人物がいないということは、必然的にセリフの負担が一人一人に重くのしかかっているということだ。なのに3人とも流暢にヒンディー語のセリフをしゃべっていてすごいと思った。演技もそれぞれ個性が際立っていてよかった。姉妹が同じ部屋にいるときにマノーハルが呼び鈴を鳴らし、その鳴らし方でリターが「この優しい押し方は私の彼だわ」、ラッジーが「この荒々しい押し方は私の彼だわ」、そして2人で、「きっと私たちの彼が2人同時に来たのよ」と言い合っているところは絶妙だったが、その後の展開が急速に尻すぼみで終わってしまったのが残念だった。僕が脚本家だったら最後の直前までマノーハルに一人二役を続けさせて姉妹をだまし続ける筋にするのだが(インド映画にはよくあるプロットである)。インド人受けはかなり上々だった。というか、今回は日本語字幕などなかったので、日本人の観客には少々酷だったかもしれない。だからインド人にしか受けていなかった、という状況だった。どうも単語の使い方や台詞回しが相当おかしいみたいで、それによって受けている感じだった。
次の演目は「Saras Prem(鶴の恋)」。「夕鶴」のヒンディー語版である。インドの童話集「パンチャタントラ」と「鶴の恩返し」の類似性・関連性を溝上教授が指摘するところから始まり、一気に舞台は懐かしい日本の学芸会のような雰囲気に。皆、いかにも日本という衣装を身に付けて登場。大阪外語大の生徒の他、デリー日本人学校の子供たちもエキストラ出演していて微笑ましかった。最初の演目もよかったが、やはり日本人がインドに来てヒンディー語の劇をする際、たとえ言葉がヒンディー語でも、日本が舞台になっている劇をやる方がしっくり来るようだ。インド人に日本人の情緒がどんなものか見てもらうことができるからだ。「Saras Prem」は「Bure Fanse Mohabbat Mein」のコメディチックな雰囲気とは一転して、悲しみと嫌悪のラス(情感)が強い劇で、特にお通(鶴)役の人は渾身の悲哀に満ちた演技をしていた。素晴らしかった。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
Saras Prem |
● |
彼ら劇団はこれからボーパール、プネー、ムンバイー、ナースィクなどを巡回公演するそうだ。西インドの文教都市プネーや、マハークンブメーラーの開催地である四大聖地のひとつナースィクはまだ僕が行ったことのない街なのでうらやましい。はっきり言って、この大阪外語大のヒンディー語劇は、2002年度に行われた日印国交樹立50周年記念のどの行事よりも日印の文化交流促進のために役立っているような気がする。この調子で頑張ってもらいたい。
| ◆ |
3月30日(日) Ek Aur Ek Gyarah |
◆ |
今日は新作ヒンディー語映画「Ek Aur Ek Gyarah」を見にラージパト・ナガルの3C’Sへ行った。「Ek Aur Ek Gyarah」とは「1+1=11」という意味で、日本語の諺「三人寄らば文殊の知恵」みたいな意味だ。キャストはサンジャイ・ダット、ゴーヴィンダー、アムリター・アローラー、ナンディニー・スィン、ジャッキー・シュロフ、グルシャン・グローヴァーなど。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
Ek Aur Ek Gyarah |
● |
| Ek Aur Ek Gyarah |
ターラー(ゴーヴィンダー)とスィターラー(サンジャイ・ダット)はお互い孤児だったが、一緒に育てられた仲だった。2人の生業は泥棒で、金持ちの家に忍び込んでは高価な品から家具まで全部盗んでしまうということを繰り返していた。そんなある日、警察に捕まりそうになった2人は、通りがかりの人を人質にする。ところがそれは指名手配中テロリストのコブラ(アーシーシュ)だった。ターラーとスィターラーはコブラと共に捕まってしまう。しかし護送中にコブラの部下が救出に来て、2人はコブラと一緒に逃げ出す。コブラはターラーとスィターラーを殺そうとするが、2人は銃を奪ってコブラの足を撃ち、逃げ出す。コブラは警察に再び捕まってしまう。
警察とテロリストに追われることになったターラーとスィターラーは、軍隊の将軍ラーム・スィン(ジャッキー・シュロフ)の家にうまく居候させてもらうことに成功する。そこでターラーはラーム・スィンの妹ピンキー(ナンディニー・スィン)と恋仲になり、スィターラーはピンキーの友達プリーティ(アムリター・アローラー)と恋仲になる。ラーム・スィンも4人の仲を認め、結婚の話を持ち出す。
ところがコブラがまんまと脱走してしまう。コブラはターラー、スィターラーの育ての母親を人質にとり、刑務所に囚われている兄弟分のパンサー(グルシャン・グローヴァー)の救出をさせる。パンサーは逃げ出し、その責任を問われてラーム・スィンは停職処分になる。ラーム・スィンはターラー、スィターラーに怒りを爆発させるが、2人はラーム・スィンに「必ず自分たちでコブラとパンサーを捕まえる」と誓ってテロリストのアジトへ乗り込む。
ターラーとスィターラーは一度はピンチに陥るが、テロリストの戦車を乗っ取って適当にいじっている内にテロリストを壊滅させ、コブラとパンサーも御用となる。こうしてターラーはピンキーと、スィターラーはプリーティと結ばれることになる。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
最近フロップを連発しているゴーヴィンダーだったが、久々にまあまあ面白そうな映画に出演したな、と思っていた。タイトル・シーンではシャンカル・エヘサーン・ロイ作曲のノリノリな音楽に合わせてフラッシュ・アニメーションのようなアニメが流れてなかなかシャレた雰囲気。ゴーヴィンダーはパンジャービー訛りのヒンディー語を早口でしゃべったり、コメディアンとしての才能を遺憾なく発揮したり、得意のダンスを惜しげもなく披露したりしてけっこう活躍していた。
ところが、ゴーヴィンダーの相方役サンジャイ・ダットはいったい何なのだ?あの悪役顔にこの映画のようなコメディーは全く似合わない。気持ち悪すぎる。しかもあの顔で若いヒロインと恋に陥るのには無理がありすぎる。もう彼にロマンチックな役はさせないでもらいたい。配役を考えたのは誰なんだ?ゴーヴィンダーとサンジャイ、どっちももういい年したおっさんだが、ゴーヴィンダーはまだコメディとダンスがいけてるから許せる。だがサンジャイ・ダットだけは許せない。
ヒロイン2人はあまり知らない人だ。はっきり言って二人ともブレイクしなさそうな個性のない顔。添え役のようなヒロインだったので、特に書くことももない。
というわけで、この映画の見所はもうゴーヴィンダーしか残されていない。彼のダンスはいつ見ても素晴らしい。リティク・ローシャンのようなダンスもいいが、インド人が本当に好きなのは、ゴーヴィンダー・タイプのダンスだろう。ギャグも面白かった。駄作に近い映画ながら、けっこう気楽に笑うことのできるコメディー映画である。観客もよく大笑いしていた。だが、結局映画館で見る価値のある映画とは思えない。
|
|
|
|
|
NEXT▼2003年4月
|
|
| *** Copyright (C) Arukakat All Rights Reserved *** |



