 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
 これでインディア これでインディア 
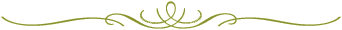
2003年10月
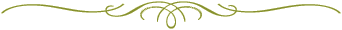
|
|
|
|
| ◆ |
10月2日(木) Jogger's Park |
◆ |
今日はインド独立の父、マハートマー・ガーンディーの誕生日のため国民の休日である。次の日曜日にダシャヘラーがあるため、JNUには今日から日曜日まで4連休をとって田舎に帰る学生も多い。デリー大学はこの時期約2週間の長期休暇となるが、JNUにはそのような休みはない。この連休のためか、今週に入り、急にデリーの人口が減ったような気がする。
今日はPVRアヌパム4でヒングリッシュ映画「Jogger's Park」を見た。「Bolliwood Calling」でデビューし、つい先日見た「Mumbai Matinee」にも出演していた新星パリーザード・ゾーラービヤーンと、ベンガルのベテラン俳優ヴィクター・バナルジーが主演。監督は「Taal」などで有名なスバーシュ・ガーイ。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
パリーザード・ゾーラービヤーン(左)と
ヴィクター・バナルジー(右) |
● |
| Jogger's Park |
ムンバイーに住むジャスティス・チャタルジー(ヴィクター・バナルジー)は公正な審判で有名な判事で、40年の勤務を終えて引退したばかりだった。仕事が生き甲斐だったチャタルジーは、引退後の暇つぶしに家族の勧めで、ジョッガーズ・パークと呼ばれる公園で毎朝ジョギングをするようになった。
ジョッガーズ・パークは近隣の老若男女が集まる社交の場でもあった。チャタルジーはジョギングを続けるうちに、ジェニー(パリーザード・ゾーラービヤーン)という若い女の子と出会う。ジェニーは明るくて知的でモダンな性格で、チャタルジーとすぐに仲良くなり、彼のことをJCと呼ぶようになった。
実はジェニーにはひとつの問題があった。ジェニーの母親はかなり昔に死に、父親も数年前に死んだのだが、その遺産を巡って叔父と裁判沙汰になっていた。JCはジェニーを助けるために友達の弁護士を紹介し、そのおかげでジェニーは裁判に勝つことができた。
ジョッガーズ・パークで出会いを重ねるごとにJCとジェニーの仲は深まっていった。JCはジェニーへの恋に狂い、ファッションや言動まで変わってきた。JCの家族は退職によってプネーに引っ越す予定だったが、JCはあと1年ムンバイーに延長して住むと言い張る。あるときジェニーはJCの心を見透かして言った。「私、あなたに恋しちゃったわ。あなたも私のこと好きでしょ?別に何も特別なことじゃないわ」こうしてJCは、妻がありながらジェニーと恋人関係になってしまった。
しかしある日JCの元へ一人のジャーナリストが訪ねてくる。彼は以前JCに助けてもらった経験があった。彼はJCの娘にある写真を渡す。その写真はJCとジェニーの逢引きの写真だった。明日の新聞に一大スキャンダルとして掲載される予定だったのを、彼が止めさせたのだった。我に返ったJCはジェニーとの恋愛を諦め、即プネーに移ることにしたのだった。
4年後、ムンバイーの空港でJCはジェニーと偶然再会する。ジェニーは有名な音楽家ランジートと結婚し、一子をもうけていた。ジェニーを見送る彼の胸には、ジェニーからもらったネックレスが輝いてた。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
人生で一度も道から外れたことがなかった初老の男と、今の人生を精一杯楽しんで生きる若い女性との、不倫めいた恋愛がテーマの映画だったが、ジョッガーズ・パークの明るい雰囲気と、シャレた音楽、そして微妙な匙加減のコメディー・テイストのおかげで非常にさわやかな映画だった。とてもいい映画だ。見逃さなくてよかったと思った。
主人公のジャスティス・チャタルジーは職業柄、生真面目であまり感情を表に表さない男。判事をやっていたため、誰からも何の贈り物ももらおうとしないほどだった。一方、もう一人の主人公ジェニーは、定職につかない、日本で言うフリーターだが、その日その日を楽しんで生きている明るい女性。ジェニーは当初、係争中だった裁判でチャタルジーの助けを借りるために彼に近づいたのだが、次第に彼の性格に惚れてしまう。チャタルジーも最初は強引な性格のジェニーにうろたえていたものの、次第に毎日ジョッガーズ・パークで彼女の姿を探すようになる。
チャタルジーはジェニーに会う前は、恋愛は悪だと考えていた。法律こそ絶対の真実であると考えていた。しかしジェニーとの出会いによって、愛という絶対の真実に目覚める。誰かを愛してしまえば、年齢も世間体も法律も全て何でもなくなってしまうことに気が付く。しかし最後に彼が戻っていったのは、ジェニーではなく、家族の元だった。彼は自分の熱情ではなく、家族の尊厳を守ることに決めたのだった。この終わり方はインド映画っぽくてよかった。
一応ヒングリッシュ映画にカテゴライズしたが、この映画の言語は都市部のインド人のごく自然なしゃべり方だった。つまり、ヒンディー語と英語がちょうどいい混合率でミックスされていた。
「Jogger's Park」は新しい流れのインド映画のひとつに数えられるが、音楽も新しかった。というか、「新しい音楽」と宣伝されていた。インド初のフュージョン音楽らしい。それはともかく、何曲かいい曲があった。アドナーン・サーミーが歌う「Ishq Hota Nahin Sabhi Ke Liye(愛はただ一人のため)」は映画中何度も流れ、アドナーン・サーミーの甘い歌声は映画館を出た後もしばらく頭の中をリフレインしている。いい曲だ。ジャグジート・スィンが歌う「Badi
Nazuk Hai Yeh Manzil(今、このときの至福)」もとてもいい。インド映画にありがちのミュージカル・シーンは1つ2つほどしかなく、これらの音楽は映画中でBGM以上、ミュージカル未満の絶妙なポジションで流れていた。
低予算ながら、インド映画のいいところがギュッと詰め込まれた気持ちのいい映画だった。少し中だるみしたところはあったと思うが、ジェニーとの恋愛を諦めた後、奥さんの作ったキール(ミルク粥)をチャタルジーが「なんておいしいんだ!」と泣き叫んで食べる終わり方がよかったので、気にならなかった。
インドに来ると、手のない人、足のない人をよく見る。大方は乞食であり、信号で停まったときなどに喜捨を求めて来たり、寺院の前で物乞いをしていたりする。その悲惨な姿を見て一気にインド嫌いになってしまう人もいれば、インド旅行を終える頃にはボランティア精神に目覚めてしまう人もいれば、その開けっ広げのインドの姿勢に、逆に日本の「臭いものには蓋」への疑問をつのらせる人もいる。
乞食に関してよくこんなことが書かれている。不具の乞食はお金をもらいやすいため、乞食に子供が生まれると、わざとその子の手や足を切断するという話だ。インドの絶望的な惨状を強調するためによく使われるエピソードである。果たしてそんなことが本当に行われているかは分からない。が、人工的に不具にさせられたと思われる、明らかに不自然な身体障害の子供を稀に見かけるので、その話は全くのデタラメでもないと思っている。
目立つのは身体障害者の乞食だが、普通に仕事をして生活をしている人でも、案外何らかの障害を持っている人はけっこういる。
身体障害者とはまた別かもしれないが、奇形児もインドでは割と普通に生活している。インドで一番有名な奇形児といったら、リティク・ローシャンかもしれない。リティク・ローシャンはインド映画界のトップ・スターだが、彼の右手の親指は2本ある。つまり右手の指が6本ある。初期の映画やポスターでは右手がうまく隠されていたが、最近はスクリーンで彼の2本目の親指を簡単に見ることができるようになった。当初はリティクの映画を見ると、右手が気になって気になって仕方がなかったのを覚えている。リティクと同じような奇形児はけっこういるようで、今まで2回、6本指の人に会ったことがある。
JNUに入って少し驚いたのは、学生の中に身体障害者がけっこういることである。インドの大学では、身体障害者、部族出身者、低カースト出身者などに優遇措置がとられていることは知っていたが、実際に大学で身体障害者があちこちでうろついているのを見るとなんだか変な気分になる。地面をクモのように這いつくばっている人、杖を使ってヨロヨロ歩いている人、腕がない人などが、普通に溶け込んで授業を受けている。
実は同じクラスにも身体障害者がいる。彼には両腕がない。生まれつき腕がないようで、名前から察するとブラーフマン階級の人である。足の指にペンを器用に挟んで、足で文字を書いて勉強している。最初彼に会ったとき、握手しようとしたら腕がなかったのでギョッとした。しかし彼と接しているうちに、だんだん彼の性格に惹かれてきた。まず頭がとても切れる。しかも歌がとてもうまくて、多くの映画音楽などをプロ並みに歌うことができる。また、詩人でもあり、自作の詩を歌ったりもする。何より、自分のハンディキャップをものともせず、毅然とした態度で生きている姿勢が僕は好きだ。左の足首に腕時計を巻いているのが個人的に彼のチャーム・ポイントだと思っている。
さすがにインド人は普段から身体障害者を見慣れているだけあって、クラスメイトの彼に対する接し方はいたって自然体である。日本人にありがちな、「なるべく自然体で接しようとしている不自然な自然体」ではなく、本当に自然に接しているところがすごい。彼に対して冗談も普通に言う。ヒンディー語科とウルドゥー語科の合同授業が週に2回あるのだが、その授業で教授が「ヒンディー語科の者は手を挙げろ」と言ったときに、両腕のない彼の隣に座っていた人が「先生、こいつは手がないけどどうしますか?」と冗談を言って爆笑を誘っていた。日本で身体障害者に対してこんな発言をしたら問題になってもおかしくないが、教授も他の人も普通に笑い、本人も別段気にせず、「手の代わりに足を挙げるからいいや」とか言って足を高く挙げ、さらに爆笑を誘っていた。
インドの身体障害者を取り巻く環境が、日本やアメリカなどの先進国に比べて優れているとは死んでも思えない。だが、精神的な面で、なんとなく身体障害者も身体障害者と接する人も、自然体なのがいいと思った。
ちょうど2ヶ月前にグルガーオンを訪れて、そのショッピング・モールの発展ぶりに驚いたものだが、今日再び行ってみたら、モールにさらに店舗が入っており、さらに発展していた。この辺りにはさらにモールが立ち並びそうなので、もう少し経てば、デリー圏最大のショッピング・ストリートになるだろう。今日はPVRメトロポリタンで新作ヒンディー語映画「Khel」を見た。
「Khel」とはゲーム、スポーツ、遊びという意味。この映画では「犯罪の駆け引き」みたいな意味になるだろう。キャストはサニー・デーオール、スニール・シェッティー、セリーナ・ジェートリー、アジャイ・ジャデージャー、グルシャン・グローヴァー、スハースィニー・ムレーなど。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
Khel |
● |
| Khel |
大物実業家のデーヴ・マーリヤー(スニール・シェッティー)は、偶然出会った若手インテリア・デザイナー、サーンジュ・バトラー(セリーナ・ジェートリー)に一目惚れし、彼女に自宅のインテリアのデザインを注文する。デーヴには兄弟同然に育ってきた幼馴染み、ローハン・ポーッダル(アジャイ・ジャデージャー)がいた。目的のためなら手段を選ばないデーヴの荒い性格とは対照的に、ローハンは誰からも好かれる優しい性格だった。ローハンもたまたまサーンジュと出会い、サーンジュはローハンに惹かれる。
ローハンとサーンジュの仲がいいことを知ったデーヴは、嫉妬しながらも二人の結婚を仲介する。ところがあるとき、ローハンは暴徒に襲われていた売春婦を救おうとして誤ってその売春婦を撃ち殺してしまう。すぐに駆けつけた警察にローハンは逮捕される。
デーヴは弁護士を呼び出す。弁護士はてっきり彼がローハンを助けるために呼び出したものと思ったが、彼が指示した内容は、「デーヴを一生牢屋から出れないようにしろ」だった。弁護士たちの巧みな策略により、法廷でローハンは付き合いのあった売春婦を私情によって撃ち殺したとされ、無期懲役を言い渡される。ローハンに裏切られて泣き崩れるサーンジュを、デーヴが優しく抱きしめる。やがてデーヴとサーンジュの結婚が決まる。
偶然ローハンと顔見知りだった警察副本部長ラージヴィール・スィンディヤー(サニー・デーオール)は、ローハンのニュースを新聞で知り、彼が殺人をするのはおかしいと予想する。ラージヴィールは事件を調べる内に、大富豪デーヴ・マーリヤーの行動の不可解さに気付き、サーンジュが事件の隠された中心であることを確信する。ラージヴィールはローハンの事件の再審判をさせるが、その裁判の日にデーヴとサーンジュの結婚式が行われていた。結婚の儀式を急がせるデーヴだったが、あと少しのところでラージヴィールとローハンが現れる。ローハンは無罪となって釈放されていた。デーヴは最後のあがきをしてラージヴィールに襲い掛かるが、乱闘の末ラージヴィールに打ち負かされ、逮捕される。こうしてローハンとサーンジュはめでたく結婚となった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
前半は退屈な恋愛劇で眠たくなるが、中盤ローハンが逮捕される辺りから割と楽しくなり、インターミッションの後サニー・デーオールの登場によって、典型的暴力刑事映画となる。総合評価は、「見なくてよし」である。
「Khel」という題名なのだから、さぞかし登場人物同士の駆け引きのやりあいで、次々とどんでん返しが起こるかと思っていたが、ストーリーは非常にシンプルかつストレートだった。前述の通り、前半は非常に退屈。インターミッションに入ると「And
The Game Begins...」と出るので、これから急速に楽しくなるのかと思ったら、普通のインド映画の筋と大して変化はなくガッカリ。サニー・デーオールとスニール・シェッティーの対決が一応この映画の目玉だったようだが、二人の駆け引きがあったのは後半のわずかな時間だけで、直接の肉弾戦はお約束のクライマックスのみでしかもすぐに決着がつく。
サニー・デーオールの登場シーンはなかなかかっこよかった。悪漢たちを一人で次々となぎ倒すのだが、サニーのパンチが敵に当たると、敵の身体が一瞬レントゲン写真のようになって骨格が表れ、それがゴキッと折れたりする。
主演女優、セリーナ・ジェートリーは2001年度のミス・インディア・ユニバースらしい。しかしやたら老けて見えたので全然魅力的ではなかった。スニール・シェッティーは普段とあまり変わらない役柄で別段何も取り上げるところがない。サニー・デーオールが出てくると全部同じ映画になってしまうのも泣けてくる。もっと工夫してくれ・・・。アジャイ・ジャデージャーが演じたローハンのキャラクターは、唯一この映画で光っていたところで、そのおかげで観客は彼に感情移入ができたと思う。しかし後半になるとローハンも輪郭のぼやけたキャラに成り下がってしまうのが残念である。
今日はバイクを初回点検に出した。インドのバイク会社は案外アフター・ケアがしっかりしていて、定期点検も2万kmまでは無料でしてくれる。というか、日本製のバイクと違って、定期的に点検しないとやっぱりインドのバイクは何かしら問題が出てくる。現在僕のカリズマは約600km走ったが、いつからか後輪から摩擦音がするようになっていた。だが点検してもらったらちゃんと直してもらえた。ついでにコーティングをしてもらったら、細かい傷が消えてピカピカになった。
夕方から停電になって、ずっと復旧しなかったので、サーケートに映画を見に行った。見た映画は新作ヒンディー語映画「Baghban」。パッと見たときは「神様」という意味の「Bhagvaan」のことだと思ったら、よく見たらつづりが少し違って、「庭師」という意味だった。
キャストはアミターブ・バッチャン、ヘーマー・マーリニー、サルマーン・カーン(ゲスト出演)、マヒマー・チャウドリー(ゲスト出演)、パレーシュ・ラーワルなど、往年の名優や90年代を彩ったスターたちが多い一方、アマン・ヴァルマー、サミール・ソーニー、サーヒル・チャッダー、ナスィール・カーン、リーミー・セーンなど若手の俳優たちも多く出演していた。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
Baghban |
● |
| Baghban |
ラージ・マルホートラー(アミターブ・バッチャン)は40年間勤めた銀行を定年退職した。彼は愛する妻プージャー(ヘーマー・マーリニー)と共に、息子たちと住むことを夢見ていた。ラージにはアジャイ、サンジャイ、ローヒト、キランという4人の息子がいたが、それぞれ結婚して独立して生活しており、両親と一緒に住むことを嫌がっていた。そこで息子たちと嫁たちは相談して策略を練る。まずはラージが長男アジャイの家に、プージャーが次男サンジャイの家に滞在し、6ヵ月後にはラージが三男ローヒトの家に、プージャーが四男キランの家に滞在するようにした。ラージとプージャーは離れ離れに過ごすことなど考えられないほど愛し合っていたので、その提案を聞いて、息子たちと一緒に住むことを諦めると謀ったのだが、意外なことに両親はそれを受け入れる。
ラージはデリーに住むアジャイの家族と一緒に暮らすことになった。孫はラージになつくが、長男夫婦はラージに冷たい態度をとる。ラージは妻がいない寂しさを、近くのカフェで紛らわすようになり、そこの店主の勧めで今までの人生の経験を文章にすることを決める。彼は昼夜タイプライターを叩く毎日を送った。
一方、ムンバイーの次男夫婦と住むことになったプージャーも、家族から冷たい待遇を受けていた。しかし孫娘のパーヤル(リーミー・セーン)だけはプージャーの愛に心を動かされ、彼女に心を開くようになる。
6ヶ月が過ぎ、ラージとプージャーの移動の日となった。ラージとプージャーは途中の駅で待ち合わせて6ヵ月ぶりの再開を果たす。そしてもう再び離れ離れにならないことを決める。そのとき偶然出会ったのが、アーローク(サルマーン・カーン)だった。アーロークは元々靴磨きの子供だったのっだが、ラージの援助によって学校へ通えるようになり、やがてアメリカに留学して、フォードに就職していた。アーロークはラージのことを神様のように尊敬しており、彼はラージとプージャーを自宅へ呼ぶ。そこには妻アルピター(マヒマー・チャウドリー)もいた。アーロークは実の息子たちと違って、ラージを大歓迎する。
そんな中、ラージが書いた自伝が出版されることが決まった。「Baghban」という題名のその本は国際的な大ベスト・セラーとなり、ラージの元には巨額の版権が舞い込んでくる。
一方、途中でラージとプージャーが消えてしまったので、4人の息子たちはうろたえて探し回っていた。そしてラージの本がベスト・セラーとなったことを知った彼らは、両親を住まわせなかったことを後悔する。
ある日、出版社主催の、ラージの講演会が開かれた。4人の息子たちの元にも招待状が届いた。ところが「ラージの息子」として壇上に上がったのはアーロークだった。ラージは「時代が変わったからといって、親への尊敬を忘れることは許されない」と演説する。息子たちはラージに許しを請うが、ラージは勘当を言い渡し去っていく。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
定年退職後の夫婦が主人公のシルバー・ロマンスかつ、現代の家族の在り方の問題点を一喝したお説教映画であった。典型的なインド映画の方程式に則って作られていたので、初めてインド映画を見る人にもオススメの映画である(この前インドに初めて来て、初めてのインド映画に「Boom」を選んでしまった人に会ったが、あの映画を見てしまったらインド映画を誤解するだろう・・・)。しかし終わり方は意外な展開だった。完全なハッピー・エンドではなかったが、勧善懲悪という意味では悪は善によって打ち負かされた終わり方だった。
序盤はアミターブ・バッチャン演じるラージと、ヘーマー・マーリニー演じるプージャーの、年甲斐もないラブラブぶりが描かれてむずがゆくなる。ラージが外から帰ってくると、玄関のベルを鳴らす前にプージャーはドアを開ける。「ベルも鳴ってないのに、どうしてオレが帰ってくるのが分かるんだ?」と不思議がるラージに対しプージャーは言う。「あなたの足音が聞こえると、私の胸のベルが鳴るのよ」うう、むずがゆい・・・。しかしヘーマー・マーリニーは年をとっても非常に若々しい美しさを保っているなぁと思った。「この年になってヒロインを演じることができるなんて思ってもみなかったわ」とインタビューで彼女が言っていたのを記憶している。
ラージは全く老後のための貯蓄をしていなかった。お金は全て息子たちのために使ってしまっていた。しかし彼に心配はなかった。老後は息子たちが自分たちの世話をしてくれるだろうと期待していた。ところが実際はそうではなかった。4人の息子たちは両親と住むなんてまっぴらごめんだったのだ。やがて成り行きから、ラージは長男と共に、プージャーは次男と共に、別々に暮らさざるをえなくなってしまう。
プージャーは毎朝ラージのために紅茶を淹れていた。しかし離れ離れになってしまったため、それができなくなる。プージャーは一人で唇を噛みしめる。「ああ、ごめんなさい、初めてあなたに紅茶を淹れてあげることができなかったわ・・・」ここまで来るとこの老後ロマンスもほとんどギャグの領域に入ってくる。
息子夫婦と暮らすラージとプージャーは、それぞれ冷遇を受ける。西洋的個人主義に浸った息子たちにとって、年老いた親と一緒に住むことは苦痛以外の何物でもなかった。日本人にとっても分かりやすい展開である。家族主義のインドでも、人間の感情というのはあまり変わりないのだろう。
ラージの書いた自伝が突然大ベスト・セラーになるというのは、いかにもインド映画的強引な展開だ。だがインド映画に慣れてしまうと別段不思議にも思えなくなる。本の題名も映画の題名も「Baghban」。これは「庭師」「庭の世話をする者」という意味である。庭の木はやがて大きくなると日陰を作り、手入れをしてくれた人に休息を与えてくれる。親と子供の関係を、庭師と庭木の関係に喩えた題名のようだ。
最後のラージの演説は、映画のもっとも核となる部分だろう。現代の親子の絆の危機について、アミターブ・バッチャンが警鐘を鳴らす。チャップリンの「独裁者」を彷彿とさせた。だが、僕は映画の最後にこういう説教がある映画はあまり好きではない。映画なのだから、何か訴えたいことがあったとしても、言葉で表現するのではなく、映像と脚本で表現すべきだと思う。
僕は最後の最後で、ラージが4人の息子たちを許してハッピー・エンドと予想していたのだが、意外にも勘当という結果になった。この終わり方により、この映画の隠れたテーマは、親子の愛よりも夫婦の愛が勝り、世代間の愛よりも同世代間の愛が重要、ということに固定されたように感じた。
サルマーン・カーンがゲスト出演していたのも面白かった。彼の今回の役柄はひたすら「いい人」である。僕は先日公開されたサルマーン・カーン主演の「Tere
Naam」を見なかったので、彼をスクリーンで見たのは久しぶりだった。しかし路上生活者を酔ってひき殺して逃走したサルマーン・カーンに対する反感はインド人の間でけっこう根強く、彼の人気はどん底である。今回の彼の役柄は、なんとなく罪滅ぼし的要素を感じた。同じくゲスト出演のマヒマー・チャウドリーは、全く印象に残らなかった。出なくてもよかったのではなかろうか。
主役のアミターブ・バッチャンの演技は素晴らしかった。文句のつけようがない。若者たちと踊るダンス・シーンが多く、まるで若いエネルギーを吸い取っていてさらにパワーアップしたかのようだった。「Kabhi Khushi Kabhie Gham」の「Say Shava Shava」で見せた白人のお姉ちゃんたちとのダンス以来のはしゃぎぶりであった。
「どうしてインドが好きになったんですか?」
「インドの何が好きなんですか?」
時々こういう質問をされる。それに対する答えは、僕がインドに深く関わるに従って変遷して来たように感じる。最初の頃は、「インドは神秘的で不思議な国だから」と答えていたように記憶している。「日本は仏教を通してインドから大きな影響を受けているから」とか、「そこにインドがあったから」とか、その他にもいろいろ理由を必死に考えて答えていたが、結局「ビートルズが好きで、その影響でインドも好きになった」という答えに落ち着いてきた。インド好きな人の中にビートルズ好きな人がけっこう多いことに気が付いたからで、僕自身ビートルズが好きなのは確かなので、その答えはまんざら嘘でもない。しかしその理由を口に出すとき、もう一人の自分が冷静な目で、「それは本当の理由ではない」とつぶやいているのをいつも感じていた。「なぜ好きか」と質問されて、すらすらと理由を答えられることは、「好き」という感情とは相容れない。理屈抜きで好きになることが「好き」なのだと思っている。しかし一度理屈抜きで何かを好きになったところで、今度は好きでい続けるか、そうでないか、決断を迫られるときが来る。好きになったものの嫌な面を見てしまったときが、その決断のときだ。そのときに初めて理性が働く機会が訪れる。「もう駄目だ」とすぐに嫌い、または無関心になってしまうか、それとも、「ある程度嫌なことがあっても、このまま好きでい続けるよう努力しよう」と考えるか、である。インドに旅行に来る人の大半は、何となくインドの不思議な魅力に惹きつけられた人である。しかし現実のインドを見て、嫌悪感を全く感じない人はこの世に皆無だろうと思う。例えデリーの空港から南デリーの5つ星ホテルへ直行し、そのままジャイプル、アーグラーをササッと観光して日本に帰ったとしても、その間、絶対にインドの負の面を目にしてしまう。そこで目をそむける人は、おそらくこれからの人生も、自分の常識と相容れないものに対して理性を働かせることなく嫌いになってしまう可能性の高い人だと思う(「好きだから好き、嫌いだから嫌い」というタイプの人だ)。そこで理性を働かせ、現実を直視し、じっくりと考えることができる人、または現実をありのまま受け入れることができる人は、インドから多くのものを得ることができるだろうし、きっとインドを好きになるだろうと思う。よく「インドは好きになる人と嫌いになる人がはっきり分かれる国だ」と言われるが、僕はあまりその言葉を信じていない。なぜならその中間に当たる人を何人も見てきたからだ。しかし、好き嫌いに理性を働かせられるか、働かせられないか、これは2つに1つのような気がする。そうだとしたら、僕はおそらく理性を働かせられる人間である。僕はかなり理性的にインドを好きになっている。嫌なことはいくらでもあるが、理性を働かせ、自分なりの理屈付けをして、全てを受け入れ、全てを許す覚悟で臨んでいる。あらゆるハプニングを予め予測し、何か起こっても「やっぱりな」と思える心の余裕を持って事に臨んでいる。だから、「なぜインドが好きか」と質問されたら、「インドを好きになるように努力しているから」と答えるのが一番いいのかもしれない。「インドの何が好きか」はこの場合意味をなさないことになる。なぜなら好き嫌いの判定に理性が働いている限り、対象は何でもいいのだから。
「なぜインドなのですか?」
こういう質問も時々ある。僕がインドに住んでいると言うと、何の脈絡もなくこういう質問をされることがある。「なぜインドなのか」・・・シンプルかつ本質的な質問である。あまりに直線的過ぎて、こう来られると時々うろたえを隠せない。というより、こういう質問が成り立ってしまうことに、「インド」という単語の持つ特殊な力があると思う。「なぜアメリカなのですか?」「なぜフランスなのですか?」「なぜイタリアなのですか?」国名をすげ替えて見るとなぜかしっくり来ない。名の通った先進国だと駄目なのか。「なぜエチオピアなのですか?」「なぜタジキスタンなのですか?」「なぜボリビアなのですか?」日本人にとってあまりイメージの沸かない国を当てはめてみてもやっぱりピタッとしない。この質問に関しては、質問する側にある程度その国の知識があることが前提になっているからだろう。「なぜインドなのですか?」やはりインドが一番落ち着きがいい。「なぜにインド!?」ここまでシンプルになるともはやインドにしか務まらない文章になってしまう。「インド」という言葉には不思議な力がある。おそらく、日本人はインドに関してある程度情報があるのだが、その情報が変なものばかりなので、いつの間にか「インド」という単語に「インド」以上の意味が付け加えられているのだと思う。
ところでなぜインドなのだろう?インドじゃなければ駄目なのか。多分駄目だろう。インドじゃなければ、僕は住んで勉強しようとは思わなかっただろう。僕は言語を主要テーマにインドに留学している。言語は文化である。文化は人である。外国語を学ぼうと思ったとき、その言語と関連している国や地域の人や文化に尊敬がなければ、僕は真剣にその言語を学ぶことができない。インドに留学したのも、インドに住み続けられるのも、インドを尊敬しているからだ。他の国を考えた場合、インドほど尊敬できる国は今のところない。だからインド以外の外国語を学ぶ気があまりしない。インドじゃなきゃ駄目なのだ。というより、インドじゃ駄目なのか?上の質問は、「インドは駄目」という前提に基づいて発せられるものであることが多いような気がする。それならば、今度「なぜインドなのですか?」と質問されたら、「インドじゃ駄目なのか?」と聞き返せばいいかもしれない。
「インドと日本、どちらが好きですか?」
これは非常に難しい質問である。「インド」と答えたら「じゃあインドに永住しろ」と言われそうだし、「日本」と答えたら「じゃあインドに住むな、早く日本に帰れ」と言われそうだ。しかし正直に答えるとしたら、「日本人としてインドに住むことが好きだ」という答えが一番妥当だと思う。
話を分かりやすくするために、人生を人生ゲームとする。人生ゲームには国籍別の「版」と、国別の「マップ」が存在する。普通、「版」と「マップ」は一致している。つまり、日本人として生まれ、日本を出ずに日本に住み続けるならば、その人は「日本人版・日本マップ」の盤上で生活していることになる。この場合、地道にゲームを戦っていかなければならない。しかし一度海外へ飛び出ると、つまりグローバル・バージョンの人生ゲームへバージョン・アップすると、いろいろなバラエティーが出てくる。そしてまずこれを読んでいる人に宣言しなければならない。あなたは現代に日本人として生まれただけで、グローバル人生ゲームに半分勝ったも同然だと。海外に出ると、日本国籍の有用性を感じる機会がたくさんある。特に発展途上国へ行けば、日本人としてのステータスはもちろんのこと、経済的優位性は揺るぎないものとなる。インドでも、日本人という立場は非常に有用である。日本人は最近100年間の目覚しい進歩と活躍により、かなり尊敬されている。大東亜戦争中でも、日本はインドとは直接あまり関係なかったので、中国や韓国のような露骨な反日感情はない。かえって、日露戦争での日本の勝利が、インドの独立運動に勇気を与えたくらいだ。もちろん日本製品のクオリティーは日本の評価を限りなく高めている。というわけで、日本人というだけで、インド人との親密度は初対面でもプラスになっていることがほとんどである。それだけでなく、インドでは基本的に外国人は超カースト扱いなので、カーストのしがらみに縛られることが少なくなる。僕はインドに留学しているので、言わば「グローバル人生ゲーム・日本人版・インドマップ」という難易度の低い盤上で生活していることになる。
しかしあまりにインドにどっぷり漬かり、インドに永住、基盤もインド、ということになってしまうと、その人は「インド人版・インドマップ」の人生ゲームへ移行してしまう。いや、転落と言うべきか、バージョン・ダウンと言うべきか。こうなると難易度は一気に急上昇する。あくまで日本人としてインドマップを楽しまないと、インドはあまりに厳しい国である。こういう考え方はあまり好まれないかもしれない。しかし、この点をちゃんと抑えておかないと、人生を間違えてしまう可能性があると思う。人生は不平等である。不平等だから、もし優位な立場を何かの運命で幸運にも得て生まれることができたら、その立場を使って何ができるかを考えるべきだ。日本人として生まれ、インドに関わったなら、日本人としての立場を使って、どうインドのために生かしていけるか、そしてそれをどう日本に還元することができるか、考えるべきだ。インド、特にデリーに住んでいると、日本人としての特権を感じることがある一方で、日本人であることの責任を感じる。僕に100ポイントの能力があるとしたら、デリーではその100ポイント全てをフルに使用することができるし、それを期待されているように感じる。ときには100ポイント以上のことをしなければならないこともある。日本にいたら、特別な存在でない僕は、その内の50ポイントも活用できないだろう。昔、某商事のある駐在員が語ってくれたことがある。「日本に住んでいたら僕は1億分の1の存在に過ぎないけど、インドなら1000万分の1、もしかしたら100万の1の存在くらいになれるかもしれない。」僕も全く同感である。これが日本人としてインドに住む楽しみである。
| ◆ |
10月10日(金) ヒンディー語とウルドゥー語の不幸 |
◆ |
現在、ヒンディー語はインドの第一公用語に、ウルドゥー語はパーキスターンの国語になっている。しかしヒンディー語とウルドゥー語は元々同根の姉妹語であり、現在では完全に別の言語でもなければ、完全に同一の言語でもないという、複雑な関係にある。ヒンディー語とウルドゥー語の歴史は、インド亜大陸の歴史と密接に関わっている。そしてそれは主観的な見方をすれば、不幸な歴史と言わざるをえない。
インドの言語の歴史をひもとく際、よくサンスクリト語→パーリ語→プラークリト語→アプブランシュ語→ヒンディー語という流れで簡単に説明されることが多い。つまり、アーリヤ系民族がインドに侵入し、支配権を確立した際に話されていた言語がサンスクリト語で、それが訛ってパーリ語となり、またそれが訛ってプラークリト語になり、さらに訛ってアプブランシュ語、そしてヒンディー語となった、という説明である。だが、実際はこんな簡単なものではない。
標準語と方言の関係について考える際、どうしても「まず標準語ありき」で、標準語が訛ったものが方言だと思い込んでしまうことが多い。しかし実際はそうではなく、「まず方言ありき」で、政治的、経済的、軍事的、社会的に優位に立った地方の方言が、標準語として整備され、他の地方に流布されていくという形が普通である。インドの場合も、まずは各地域にいろんな方言が存在し、その中からサンスクリト語が主に文学や宗教の標準語、共通語に値する形に洗練されて作られ、時代の変遷と共にそれが理解しがたい言語になったときに、そのときの方言からパーリ語が生まれ、同じようにさらに時代が下った後に各地の方言から各種プラークリト語が生まれた。その後、アプブランシュ語がインドの文学・宗教用言語として整備され、使用され始めたのが8世紀頃で、その後14世紀くらいまで使用され続けた。いつの時代も文学に使用された言語は、当時の日常の言葉とは開きがあり、その開きがあまりに大きくなり過ぎると、その都度日常語に近い形に修正されることを心に留めておかなければならない。
アプブランシュ語と平行して、次第に近代インド諸語とよく似た言語が文学で使用され始める。アプブランシュ語が文学の共通語であったのに対し、それらの言語はその土地で日常的に話されている生きた言語であった。13世紀〜14世紀にデリーで活躍した詩人アミール・クスローはその言語をヒンドヴィーと呼び、14世紀〜15世紀にビハール州北部のミティラー地方で活躍した詩人ヴィディヤーパティはその言語をデーシー・バーシャーまたはアワハットと呼んだ。アプブランシュ語が消滅していくと同時に北インド文学の共通語はアーグラー周辺の言語であるブラジ語となった。ラクナウー周辺で話されていたアワディー語、ラージャスターン州のラージャスターニー語、パンジャーブ州のパンジャービー語も北インド文学の担い手となった。
一方、北インドの歴史を見てみると、1206年にアイバクがデリーで奴隷王朝を興して以来、北インドはトルコ人、モンゴル人、アフガニスタン人、中央アジア人など、外部からの侵入者によって支配されるようになった(デリー・サルタナット朝)。デリーはサルタナット朝成立以前にも交易の中心地であり、隣国から多くの貿易商がやって来ていたが、サルタナット朝成立により、交易はさらに活発になった。貿易商たちは商売の利便のためにデリーの言語を身に付け、またデリーの言語も外国の商人たちの言語を吸収した。こうして成立したのがデリー周辺地域の方言と言われるカリー・ボーリーである。アミール・クスローがヒンドヴィーと呼んだ言語も、当時のカリー・ボーリーだった。1526年にデリー・サルタナット朝最後の王朝ローディー朝を破ってムガル帝国を建設したバーブルは、当時のカリー・ボーリーを指してヒンドゥスターニー語と呼んだ。
ムガル朝時代のインドの公用語はペルシア語だった。主な支配層はムスリムだったが、ペルシア語ができればヒンドゥー教徒でも官吏になれた。つまり、いい職に就くためにペルシア語が必須となった。宮廷では文学も専らペルシア語で行われた。その一方で、デリーではカリー・ボーリーにペルシア語の語彙、またはペルシア語を介して伝わったアラビア語の語彙が大量に流入した。ムガル朝時代に、デリーの市場で話されていた、アラビア・ペルシア語彙に満ちたカリー・ボーリーこそが、初めてヒンディー語と呼ばれるようになった言語だった(レークター語とも呼ばれた)。しかし北インドではヒンディー語は文学の担い手ではなかった。市井の言葉だった。宮廷文学はペルシア語、その他の文学はブラジ語をはじめとする地方の言語で作られていた。
一転して今度は南インドの動向に目を移さなければならない。南インドというとドラヴィダ語族という印象が強いが、デカン高原の広がるカルナータカ州やアーンドラ・プラデーシュ州辺りまではデリーとの交流があったので、貿易の関係でカリー・ボーリーがある程度流布していたと言われている。そんな中、デリー・サルタナット朝第3番目の王朝、トゥグルク朝の時代になって大事件が起きた。インド全土に領土を拡大していたトゥグルク朝の王ムハンマド・ビン・トゥグルクは1327年突如首都をデリーから、現マハーラーシュトラ州アウランガーバード近くのダウラターバード(デーヴァギリ)へ遷都した。このときにデリーの住民は強制的にダウラターバードへ移住させられた。ほとんどの人々はデリーからダウラターバードまでの道のりを歩いて移動したのだから、いったいどれだけの時間がかかり、どれだけの死者が出たかは計り知れない。やっとの思いでデリーの住民たちはダウラターバードに辿り着いたのだが、ムハンマドは再び突如首都をデリーへ遷すと宣言した。散々な目に遭っていた住民たちの大半は、デリーに帰らずにダウラターバードに残ったという。この事件がきっかけとなって、デカン高原にデリーのカリー・ボーリーを中心に、その周辺地域で話されていたブラジ語、バーンガルー語、パンジャービー語、アワディー語などが移植された。
トゥグルク朝は意味不明の首都移転など、政治的軍事的失策によって弱体化し、1398年にはティムールによってデリーを陥された。それに従ってデカン高原ではバフマニー朝(1347−1527年)が起こり、バフマニー朝が衰退した後はアフマドナガル王国(1490−1636年、マハーラーシュトラ州)、ビージャプル王国(1489−1686年、カンナダ州)、ゴールコンダ王国(1518−1687年、アーンドラ・プラデーシュ州)などが次々に興った。これらの王朝では公用語がデリーの方言であるカリー・ボーリーになった。しかしこのカリー・ボーリーは、テルグ語やカンナダ語などドラヴィダ系言語の音韻や語彙の影響を受けており、独自の形態を持っていた。この言語はダキニー語と呼ばれた。ダキニー語は南インドで宮廷文学の担い手となり、特にゴールコンダ王国ではダキニー語が文学の言語として完成された。ダキニー語は現代のヒンディー語、ウルドゥー語とほとんど同じ構造をしており、カリー・ボーリー文学の最も初期の形と言われる。ペルシア文字で表記されたものの、語彙はどちらかというとペルシア語よりもサンスクリト語からの借用語が多かった。
17世紀中期にはアフマドナガル王国は滅び、南インドではビージャプル王国とゴールコンダ王国の二国が覇権を争っていた。ところが17世紀末になると、ムガル朝第6代皇帝アウラングゼーブの遠征を受け、両王国は次々に滅ぼされた。このときデカン高原に支配権を確立するため、アウラングゼーブは軍隊と共にしばらくの間デカン高原に滞在した。アウラングゼーブの軍隊たちはデリーのカリー・ボーリーを話していた。南インドの人々はカリー・ボーリーから変化したダキニー語を話していた。南インドの人々はアウラングゼーブの軍隊たちと意思疎通ができたものの、自分たちと少し違う言語を話していることに気付き、軍隊たちの言語を「ザバーネ・ウルドゥー・エ・ムアッラー(高貴な軍営の言語)」と呼んだ。このとき初めて「ウルドゥー」という言葉がカリー・ボーリーに適用された。しかし、未だにカリー・ボーリーの名称はヒンドゥスターニーまたはヒンディーが一般的であった。
再び北インドに戻る。17世紀まで、相変わらずムガル朝の宮廷ではペルシア語のみが文学言語として使用されていた。そんな中、1700年に、ワリーという詩人がムガル朝の宮廷に現れる。ワリーはデカン高原のアウランガーバード出身と言われ、ダキニー語で詩作をしていた。ワリーの美しい詩に感動したムガル朝の宮廷詩人たちは、ワリーに習って、デリーの市場で話されていたカリー・ボーリーで詩作を始める。文字はもちろんペルシア文字が使用され、アラビア・ペルシア語彙が多用された。詩も元々アラブ地方発祥の詩形だったガザルが、ウルドゥー語で作られるようになる。これがウルドゥー文学の幕開けであり、それと同時にダキニー語とペルシア語は急速にインドの文学から姿を消すことになる。また、18世紀を境に、今までヒンドゥスターニー語とかヒンディー語と呼ばれていた言語が、ウルドゥー語と呼ばれるようになった。
ここまで見ると、ウルドゥー語の誕生は、デリーの方言で北インドで貿易用の言語として広く流布していたカリー・ボーリーと、アラビア語・ペルシア語の語彙や韻文学との華麗なる融合だった。ヒンディー語がさらに美しくなった形態がウルドゥー語であった。現にウルドゥー語は世界で最も美しい言語のひとつと言われている。そして当時は決してウルドゥー語はムスリムだけのものではなかった。ヒンドゥー教徒もウルドゥー語で詩作をしていた。ところが、ムガル朝が衰退し、イギリスがインドで支配を確立し始めるにつれて、状況が徐々に変わっていった。
19世紀はヒンディー語とウルドゥー語が袂を分かつきっかけとなった世紀だった。1800年、イギリス東インド会社の官吏養成のためにカルカッタにフォート・ウィリアム大学が設立された。フォート・ウィリアム大学ではインドに関する数々の研究と教育がなされたが、その中で、デーヴナーグリー文字で書かれたカリー・ボーリーをヒンディー語、ペルシア文字で書かれたカリー・ボーリーをウルドゥー語とする分類が生まれた。1837年、イギリス東インド会社は公用語をその地域の言語に設定するよう宣言する。それまでムガル朝の権威は凋落していたとはいえ、依然として北インドの公用語はペルシア語であり、政府機関の仕事は全てペルシア語、ペルシア文字で行われていた。1837年を境にその地方の言語が公用語となることになったのだが、多種多様の言語が共存していた北インドでは、どれがその地方の言語なのか見極めるのが困難だった。現在のウッタル・プラデーシュ州やビハール州では、ブラジ語、アワディー語、ボージュプリー語、マイティリー語など多くの言語が話されていたのだが、結局ヒンドゥスターニー語が公用語とされた。だが、公用語がペルシア語だったときの名残で、文字はペルシア文字(ウルドゥー文字)、語彙もペルシア語からの借用語が多かった。
1857年のインド大反乱を機に、イギリスはインドの支配を東インド会社による間接統治から、直接統治に切り替え、同時にムガル朝は滅亡した。18世紀後半から、ヒンドゥー教徒の知識層を中心に、公用語の文字にデーヴナーグリー文字の使用も認めるよう訴える運動が活発化した。ところがここで抑えておかなければならないことがある。デーヴナーグリー文字は元々サンスクリト語を表記するために使用されており、サンスクリト語の教育はブラーフマン階級に独占されていた。ブラーフマン階級はヒンドゥー教徒の庶民たちの教育を妨害していたのだ。だから一般庶民は文字を読めない人が多かった。商人階級の中には、カイティー文字という、デーヴナーグリー文字が崩れたような文字を使っている人もいた。そしてカイティー文字を公用語の文字にするよう訴える運動もあった。だが、ブラーフマン階級はウルドゥー文字にも増してカイティー文字を忌み嫌っていた。だから、公用語の文字にデーヴナーグリー文字の使用を訴えた人というのは、一部の知識層だったことが十分予想される。このときにはその訴えは却下された。
イギリス統治下となったとはいえ、当時の支配者層には、ムスリムが多かった。教養のあるインド人の大半はムスリムだった。当初ヒンドゥー教徒が政府に訴えたのは、ウルドゥー文字とデーヴナーグリー文字(ヒンディー文字とも呼ばれるようになった)の並存だったが、自分たちの訴えが聞き入れられないと、次第に考えは過激になっていった。ペルシア文字をウルドゥー語と結びつけ、ウルドゥー語をイスラーム教徒と結びつけると同時に、デーヴナーグリー文字をヒンディー語と結びつけ、ヒンディー語をヒンドゥー教徒と結びつけた。元々ヒンディー語とウルドゥー語はひとつの言語の違う名称に過ぎなかったにも関わらず、ヒンドゥー教徒過激派はヒンディー語とウルドゥー語を区別し、ヒンディー文字が受け入れられないことをヒンディー語が受け入れられないことに拡大解釈し、その原因はウルドゥー文字で書かれるウルドゥー語を使うムスリムの支配者層にあると主張した。こうしてウルドゥー語、ひいてはムスリムに対する反感を煽るようになった。同時に彼らは18世紀に華麗なる融合を果たして誕生したウルドゥー語から、アラビア語やペルシア語の語彙を排除し、代わりに難解なサンスクリト語の語彙を放り込んで「正しいヒンディー語」を作ることに腐心し始めた。それまでブラジ語がウルドゥー語以外の北インド文学の主流だったものの、デーヴナーグリー文字で「正しいヒンディー語」の文学を書くことが推奨され、ラージャー・シヴァプラサードやバーラテーンドゥ・ハリシュチャンドラなどがその先駆けとなった。また、それに対抗する形でムスリムの知識人たちも、ウルドゥー語を「我らムスリムの言語」と考えるようになり、ウルドゥー語に難しいアラビア語・ペルシア語の語彙を意識的に使用するようになった。こうしてヒンディー語もウルドゥー語も庶民の日常語から剥離し、難解で宗教色の強い文学言語へと迷走を始めてしまった。ちなみに1900年にデーヴナーグリー文字は公用語での使用を認可されたのだが、そのときにはもう既に問題は文字だけでは収まらなくなっていた。19世紀後半のこの運動をヒンディー語運動と言う。
マハートマー・ガーンディーは、独立後のインドの公用語を見据えて、ヒンディー語とウルドゥー語の問題の解決に積極的に関わった。ガーンディーは、難解なサンスクリト語彙のないヒンディー語と、難解なアラビア・ペルシア語彙のないウルドゥー語、つまりヒンディー語とウルドゥー語の基礎的で共通的な部分かつ、誰でも理解できるような簡単な言語をヒンドゥスターニー語と呼び、ヒンドゥスターニー語こそが独立インドの公用語となるべきだと主張した。文字はデーヴナーグリー文字、ウルドゥー文字両方で表記されるとし、インド人は両方の文字を習うべきだとした。しかしガーンディーの意見を受け入れる者は少なかった。ヒンドゥー教徒はヒンディー語、イスラーム教徒はウルドゥー語に執着した。結局英領インドは、ヒンディー語とウルドゥー語の問題がヒンドゥーとムスリムの問題までこじれて、インドとパーキスターン分離独立ということになってしまった。何度も繰り返すが、元々ヒンディー語もウルドゥー語も同じ言語であった。そしてヒンディー語にもウルドゥー語にも、何の宗教色もなかった。それが文字の問題からヒンドゥー教とイスラーム教の対立にまで発展し、やがて国家を分断するほどの大きな亀裂になってしまったのだ。インドとパーキスターンは、言語が分離したと言っても過言ではないだろう。
1947年の分離独立後も、ヒンディー語とウルドゥー語の不幸は続いた。独立前のインドを実質支配していたムスリムの知識層や支配層は皆パーキスターンに逃れてしまったため、独立インドに残ったムスリムたちにはほとんど力が残されていなかった。ウルドゥー語は無視される形となり、インドの公用語はデーヴナーグリー文字で表記されるヒンディー語となった。しかし移行措置としてしばらくの間英語が公用語として使用されることになった。1965年からヒンディー語がインドの第一公用語となったものの、英語の地位は依然として揺るぎなく、いい職に就くには英語の能力が必須のままだった。しかも独立インドで公用語として規定されたヒンディー語は、誰も理解できないようなサンスクリト語語彙で詰まった役立たずの言語となってしまっていた。ますます人心はヒンディー語から離れ、どうせなら英語を習得した方がマシだ、という風潮になってしまった。ヒンディー語はその誕生以来ずっとインドにおいて正当な地位を得られていないのかもしれない。そしてそれはヒンディー語を宗教やナショナリズムと結びつけたインド人自身に責任がある。ウルドゥー語に対する偏見と誤解がある限り、ヒンディー語の誕生から発展にいたる過程もちぐはぐになり、いったいいつヒンディー語が生まれ、どのように変遷してきたのかを正しく語ることができない。ウルドゥー語をヒンディー語とは別の言語だと考え、ウルドゥー語をムスリムの言語だと決め付け、ウルドゥー文字で書かれた文章は全てウルドゥー語だと思っている限り、ヒンディー語の過去はあまりに曖昧かつ貧弱で、ヒンディー語の未来はあまりに暗い。唯一明るいのは、ヒンディー語映画の中のセリフや歌で使われているヒンディー語である。今のところ映画のヒンディー語こそが、ヒンディー語とウルドゥー語のもっとも心地よい調和点である。英語の語彙も自然な形で取り込んでおり、言語本来のダイナミズムも失っていない。これがガーンディーの目指したヒンドゥスターニー語なのだろう。
一方、パーキスターンにおいてウルドゥー語は国語になったものの、これがベンガリー語を母語とする東パーキスターン(現バングラデシュ)の住民を刺激して反感を強める原因になった。また、パーキスターンにおいてウルドゥー語を母語とする者は全人口の10%以下で、実質的にはパンジャービー語が主流派であること、インドと同じく英語のステータスは依然として残り続け、英語の能力が要職に就くための必須条件に変わりないことなど、相対的にウルドゥー語の地位は低いままである。インドよりも国土が狭いこともあり、パーキスターン政府のウルドゥー語普及運動は、インドのヒンディー語普及政策に比べたら成功していると思われるが、国際的な認知度ではウルドゥー語はヒンディー語よりも圧倒的に低いし、正当な評価をされていないような気がする。
結局、ヒンディー語とウルドゥー語は血を分けた兄弟であり、分身でありながら、お互いそれぞれ文字を独り占めし、お互いそれぞれ宗教という独裁者に魂を売っていがみ合ったために、どちらも得することなく痛み分けという結果になってしまったということだろう。特に事の発端はどちらかというとヒンドゥー側にあったと感じられる。しかし当時の支配者層だったムスリム側も大人気がなかったと言わざるをえない。とにかく子供の喧嘩のような争いが、やがて核戦争の引き金とも言われるほど大きな問題になってしまったことは、南アジアだけでなく、人類の歴史の不幸だろう。しかし逆の見方をすれば、この不幸な経歴こそがヒンディー語とウルドゥー語のもっとも面白い部分であると言える。
ヒンディー語の親族名称はけっこう難しい。インド人と会話をしていると頻繁に親族名称が出てくる。お兄さんお姉さん、お父さんお母さん、お祖父さんお祖母さんくらいまでは簡単だが、そこから枝分かれする親族の名称はかなり複雑である。しかも、ヒンディー語の親族名称はときどき実態にそぐわないことが多いので、さらに複雑だ。英語の単語も普通に使われる。
基本的にヒンディー語の親族名称は男系の方が細分化されている。例えば父方の兄弟、つまり日本語の「おじ」にあたる人の呼称は2種類あり、父の兄を「ターウー」、父の弟を「チャーチャー」と言う。しかし母方のおじは、年上年下に関係なく、「マーマー」である。これはつまり、同居するか同居しないかに関わっている。インドでは花嫁が花婿の家に来ることが普通であり、また大家族主義なので兄弟が結婚後も同居することが多い。よって、父方のおじさんたちとはひとつ屋根の下に住むことになるので、名称も細分化されている。一方、母方のおじさんたちとは頻繁に会うこともないので、名称も一本化されている。
女性にとっては結婚後、別の家族の一員となるわけであり、それに伴って「義理の〜」という親族名称も出てくる。日本語に嫁と姑にあたる言葉もちゃんとヒンディー語にある。義理の母親を「サース」、義理の娘を「バフー」と言う。やはり「サース・バフーの争い」というのも存在し、インド映画でもよくその様子が描かれる。
「兄弟」という意味の「バーイー」は非常に広い意味で使われる。年上でも年下でも一応兄弟なら「バーイー」で、特に年齢の差を強調したいときは「大きいバーイー」「小さいバーイー」のようになる。また、父母の兄弟の息子、つまり日本語の従兄弟に当たる人々も「バーイー」と呼ばれる。だからインド人には「バーイー」がやたらたくさんいる。僕の大家さんの息子は一人っ子なのだが、それでも時々「バーイー」がやって来る。最初は驚いて「いつの間に兄弟ができたんだ?」と聞いたが、従兄弟だと分かって納得した記憶がある。「バーイー」は特に呼びかけのときに「バイヤー」になることが多い。また、年上の兄を特に「ダーダー」とか「ダー」とか呼ぶこともある。
「バーイー」「バイヤー」「ダー」などは血のつながりのない男同士でも普通に使用される。日本語でも見知らぬ人に対して「ちょっとお兄さん」みたいな呼びかけがあるが、それとそう変わりない。特に親しい間柄では、自分たちの関係を紹介する際、「友達」という意味の「ドースト」という単語を使うことを嫌う。「バーイー」と言うのが普通だ。日本語の「親友」にあたる言葉はおそらく「バーイー」だろう。
「バーイー」に関連して、「バービー」というのは面白い使われ方をする。「バービー」の元々の意味は「兄の嫁」である。しかしスラングでは、親友の彼女に対して使われる。一方、女性が自分の親友の彼氏に対して「ジージャー(姉の夫)」と呼んだりするかは・・・今まであまり聞いたことがないが、あるかもしれない。
親族名称がそのまま悪口になってしまったものもある。有名なのは「サーラー」である。「サーラー」の元々の意味は「嫁の兄弟」である。しかし日常会話では、「この野郎」みたいな意味で、「サーラー」とか「サーレー(意味は同じ)」が使われる。どうも、嫁の兄弟というのは何かにつけて文句をつけてくることから、悪口になってしまったようだ。ちなみに「サーラー」の「ラ」は日本人の苦手な「L」なので、この言葉をうっかり口に出してしまうことは少ないだろう。
何かのインド映画でこんなシーンがあった。店で店主が小間使いの少年を「サーラー、サーラー」と呼んでこき使っていた。それを見た客が、「何もそんな罵声を浴びせて働かさなくても」と注意すると、店主は「こいつはオレの(本当の)サーラーだよ」と答えた。悪口とは言ってもれっきとした親族名称なので、実生活でこういうことが起こっても不思議ではないだろう。
日本語の親族名称で半ば悪口になっている言葉に「親父」があるが、ヒンディー語の「父」に当たる言葉に悪い意味は全くない。そればかりか大体の場合において尊敬が込められている。「父親」という意味の単語はたくさんあるが、その中でも「バープー」には特別な意味が込められている。インド独立の父、マハートマー・ガーンディーのことを「バープー」と呼ぶのだ。このことからも、「父」という言葉に最高級の尊敬が込められていることが分かる。同じく、インド初代大統領、ジャワーハルラール・ネヘルーは、「父の弟」という意味の「チャーチャー」と呼ばれている。父の弟というのは、インドの子供たちにとっては何かと遊んでくれたり世話を焼いてくれたりする頼もしい存在らしい。そこからネヘルーの呼称が「チャーチャー」になったと言われる。ただ単にガーンディーの弟分だったからかもしれない。
ヒンディー語の親族名称の応用的使用法(血縁以外の人に使う親族名称)について、日本語と大きく違う点がある。日本では呼称が絶対的だ。つまり、日本では大体10代後半くらいから20代くらいまで他人から「お兄さん」「お姉さん」と呼ばれ、30代になると次第に「おじさん」「おばさん」と呼ばれるようになり、定年頃には「おじいさん」「おばあさん」となる。しかし、インドでは相対的である。
おそらく20代の女性がインドに来ると、少しムッとすることがあるだろう。5歳〜10歳前後の子供から、「アンティー(おばさん:英語のaunty)」と呼ばれるのだ。男でも同じだ。僕は近所の子供から決して「バイヤー(お兄さん)」とは呼ばれない。「アンクル(おじさん:英語のuncle)」と呼ばれる。いくら「バイヤーと呼べ」と言っても大して効果はないだろう。なぜなら彼らにとって僕は、お兄さんというよりは、彼らのおじさん(お父さんの弟)と同じ年齢なのだ。一方、僕の立場からすると、既に彼らを「ベーター(息子)」と呼ぶべき年齢になっている。しかし僕にはまだ、見ず知らずの子供に対して「息子よ」と呼びかけるような心の準備はできていない。実の息子もいないのだし、いたとしても日本じゃ息子に対して「息子よ」とは呼びかけないだろう。とにかく、インドでは相対的に呼称が決まる。
ちなみに、実生活でもそうだが、特にインド映画でよく目にする光景に、父親や母親が自分の娘や若い女性に対して、「ベーター」「ベーテー(これも息子という意味)」と呼びかけていることがある。「娘」という意味の単語は「ベーティー」であり、娘や女性に「息子よ」と呼びかけていることになるので、ヒンディー語を習い始めた人は「アレッ」と首を傾げるのではなかろうか?しかしこれは間違いではない。日本でもそうだが、インドでは娘よりも息子の方が重要視される習慣が根強く残っている。女の子しか産まなかった女性はけっこうひどい目に遭ったりすることもあったりする。娘や若い女性に対して使われる「ベーター」「ベーテー」は、この男尊女卑の思想から生まれたもので、要するに、娘に対して「お前は女だけど、息子と等しい存在としてみなしているよ」ということを表している。だから、娘に対して「娘よ」と呼びかけるより、「息子よ」と呼びかけた方が愛情が深いことになる。これと同じく、特にデリー周辺での特別なヒンディー語の用法として、相手の女性に対してわざと男性複数形を適用して会話をすることも少なくない。つまり「あなたは女性だけど、男性と同じだけの尊敬を払っております」ということだ。
どこかで、インド映画を理解するのに親族名称の知識が役に立つという意見を見たことがある。ヒンディー語が分からなくても、親族名称だけ覚えれば登場人物たちの人間関係が分かって、筋を追えることがあるという話だった。だが、以上のことを考え合わせると、まず親族名称を覚えることが大変で、かつ実態とかけはなれた使われ方も頻繁にされるので、結局親族名称の知識の有用性は絶対ではないと思う。親族名称を覚えるくらいだったら、普通にヒンディー語本体のマスターに時間を割いた方が、ヒンディー語映画字幕なし理解への近道だろう。
| ◆ |
10月15日(水) Main Madhuri Dixit Banna Chahti Hoon |
◆ |
先週末からインド国際映画祭がデリーで開催されているが、大学で時間的破産を確信するほどレポートの宿題が出ているので全然見に行けない。去年の映画祭のときは10本以上の映画を見たものだった。去年の一般公開の部はデリー中の映画館で上映されており、日頃足を運ばない映画館を何とか探し出して見るという楽しみがあったのだが、今年はPVRアヌパムだけで上映されている。デリーいちの高級映画館なので、設備はいいのだが、なんだかあっけない。去年一番の収穫は北朝鮮のぶっ飛んだ映画を見れたことだったが、今年は残念ながら北朝鮮映画はなかった。
というわけで、既に行きつけの映画館となったPVRアヌパムは、現在のところ映画祭で使用されているので、一般映画は夜だけ上映されている。今週は是非見てみたいヒンディー語映画が2本上映された。今日はやっとひとつレポートを終わらせて、その内の1本、「Main Madhuri Dixit Banna Chahti Hoon」を見た。
題名が長ったらしくてヒンディー語が分からない人にとってはチンプンカンプンだろうが(以下映画の題名はMMDBCHと略す)、基本的な文章で、その意味するところは「私はマードゥリー・ディークシトになりたいの」である。マードゥリー・ディークシトといったら、インド人でその名を知らぬ者はいない。インド映画界随一の踊りの名手の女優である。「Devdas」のきらびやかな古典舞踊は記憶に新しい。しかしこの映画自体には直接出演していない。主演はアンタラー・マーリーとラージパール・ヤーダヴ。プロデューサーは最近乗りに乗ってるラーム・ゴーパール・ヴァルマーである。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
Main Madhuri Dixit Banna Chahti Hoon |
● |
| Main Madhuri Dixit Banna Chahti Hoon |
チュトキー(アンタラー・マーリー)は人並み外れたダンスの才能を持つ、村の女の子。村で祭りがあると、チュトキーは自慢のダンスを披露していた。彼女は村では「マードゥリー・ディークシト」と呼ばれていた。彼女自身もムンバイーへ行ってマードゥリーになるのを夢見ていた。しかし村でそんな夢物語が相手にされるはずがない。チュトキーは母親から無理矢理結婚させられそうになっていた。
ラージ(ラージパール・ヤーダヴ)は間抜けだが純朴な、チュトキーの幼馴染みだった。ラージはチュトキーに恋心を抱いていた。ある日ラージはムンバイーへ行ってマードゥリーのようなヒロインになるという夢をチュトキーから聞かされる。そのためにラージは彼女にひとつの案を提案する。「まず僕と結婚するんだ。そしたら自由にムンバイーへ行って夢を実現することができるよ。」その突拍子もないアイデアを、藁をもすがる思いのチュトキーは受け入れ、こうしてラージとチュトキーは結婚式を挙げる。
結婚後、ラージは「ムンバイーでビジネスを始める」と両親を誤魔化して、チュトキーと共にムンバイーへ行く。しかし田舎から出てきた二人にとって、ムンバイーはあまりに大都会だった。次から次へと押し寄せる人ごみ、ぼったくろうとするタクシー、高い家賃に狭くて汚ない部屋、映画スター志望のただのキザ男、何より何のつてもない二人が突然映画の業界に飛び込めるはずがなかった。チュトキーはくじけそうになるが、ラージの励ましによって夢を諦めなかった。チュトキーは美容院へ行って田舎女から都会の女へと変身を遂げる。
二人に次第に運が巡ってきた。チュトキーはモデル事務所の紹介で、ビデオ・クリップのダンサーをすることになった。そこでチュトキーのダンスが炸裂し、絶賛を浴びる。これがきっかけとなって念願の映画の仕事が舞い込む。なんとシャールク・カーン、アミターブ・バッチャン、リティク・ローシャンなどの大物俳優との共演で、ヒロインはチュトキーただ一人だという。喜び勇んで撮影所に出掛けたチュトキーだったが、実は偽物俳優たち勢揃いの低予算映画だった。しかしチュトキーは精一杯仕事をこなす。
チュトキー主演の映画「ローシュニー」がいよいよ公開されることになった。ラージとチュトキーは初日に映画を見に行くが、映画館はガランガランだった。わずかにいた観客たちもその映画を大声で酷評していた。すっかり自信を失ったチュトキーたちは、村へ帰ることにした。夢を諦めると同時にチュトキーはラージの愛情を初めて実感するのだった。
村に帰るとチュトキーが映画に出演したことがばれていた。なんとかラージが謝って許してもらったのだが、そこへモデル事務所の社長がやって来る。そして「ローシュニー」は都市部ではヒットしなかったが、村では大ヒットしていることを告げる。そして次から次へと仕事も舞い込んでいた。ラージとチュトキーは再びムンバイーへ向かった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
文句なしの合格点。「こんなインド映画を待っていた!」という感じの、一風変わった、でも存分にインド映画らしいシンデレラ・ストーリーだ。見終わった後の爽快感も抜群。
何と言ってもまず最初に賞賛しなければならないのはアンタラー・マーリーだろう。アンタラーは2002年に「Company」でデビューし、続く「Road」でヒロインをつとめ、2003年には「Darna Mana Hai」にもチラッと出演していた。「Road」のときのアンタラーが一番印象的で、顔はそんなに美形ではないが、セクシーで迫力のある女優だと思っていた。MMDBCHでのアンタラーは、「Road」の頃に比べると痩せてしまっていたので、最初見たときは判別できなかった。
マードゥリー・ディークシトみたいにダンスの上手な女の子の話なので、主演女優はダンスがうまくなければつとまらない。しかしその点アンタラーはまさに適任。アンタラーがこんなに踊りがうまいとは思っていなかった。リズミカルかつ表情豊かな踊りは、相当才能があるか、相当練習したか、どちらかだろう。これだけ踊れれば、リティク・ローシャンと並んで踊っても遜色ない。是非、この二人のダンスを見てみたいものだ。変な話になるが、どうしても目が行ってしまったのが、アンタラーの腹。なんだか特徴的な腹をしている。腹筋のようにも見えて、ぷよぷよした贅肉のようにも見える。ヘソ出しルックの服装で踊っているときのアンタラーの腹は必見だ。アンタラーの腹、これぞこの映画の目玉だと断言してもいい。見てみればわかる。
ラージパール・ヤーダヴもいい演技をしていた。ラージパールはチビでチョコマカしたコメディアンとして、インド映画によく登場して爆笑を誘っているのだが、MMDBCHのような、どちらかというと演技力を要求される映画にも出演したのには驚いた。
この映画で最も印象的なシーンは、最後、夢を諦めて二人がムンバイーに帰る直前のシーンである。そこに至るまでの伏線がいくつかある。(偽装の)結婚後、ラージと一緒にすぐにムンバイー行きの列車に飛び乗ったチュトキーは、高価なものだからと言って、マンガルスートラをラージに渡す。マンガルスートラとは主にマハーラーシュトラ州辺りの既婚の女性が首にかけている首飾りで、夫が生きている限り外してはならないとされている。しかしチュトキーにとってラージとの結婚は夢実現のための手段だったので、マンガルスートラを簡単に外してラージに渡してしまったのだった。その後、ムンバイーに到着した二人はいろいろな苦難に遭う。田舎っぽい外見をしていたら、いつまで経っても駄目だと気付いたチュトキーは美容室へ行って、モダンな髪型にしてもらう。そのときチュトキーが後ろで束ねていた三つ編みは途中でバッサリと切られてしまう。ラージは床に落ちたチュトキーの三つ編みの切れ端をこっそり持ち帰る。最後になって、夢を諦めたチュトキーは部屋の片付けをしていると、ラージの棚にマンガルスートラと三つ編みの切れ端を見つける。それを見てチュトキーはラージの愛に気付き、マンガルスートラを首にかけるのだった。それを見てラージも涙する。僕も涙した。
チュトキー主演の映画「ローシュニー」は、ムンバイーではヒットしなかったが村ではヒットした。これは実際にもあることで、都会でヒットした映画が村では全然受けず、逆に都会でフロップに終わった映画が村で大成功を収めるということは不思議なことではない。インドではそれほど都会と村での趣向の格差があるということだ。例えばヒングリッシュ映画なんか絶対に都会でしか受けないだろうし、逆にマッチョな男優が悪役を次々と殴り倒すようなアクション映画は、都会よりも村で人気を博すことが多い。
チュトキーがバーザールにいると、村の映画館(映画小屋?)の主人が宣伝カーに乗ってやって来て「今日の○時に『Devdas』の上映があるぞ!」と宣伝してまわる。デリーではこんな光景は見られないが、田舎の方へ行けばまだまだ映画宣伝カーが村や町をグルグル廻っているのを見ることができる。映画中、実際の「Devdas」の映像が一部だけだが使われる。こういうのってちゃんと許可をもらってやっているのだろうか、とふと思った。ちょうどマードゥリーが「Maar
Daala」を踊っているシーンで映画がプチッと切れる。映画館の主人曰く「まだこの次のリールが届いておりません!」こういうのも昔の日本では時々あったと聞くし、インドでもあるのだろう。もちろん観客は「金返せ!」と怒り出すのだが、そこでチュトキーが見よう見まねでマードゥリーの踊りを歌って踊り出すと、観客もみんな盛り上がって一緒に踊り出す。しかも「Maal
Daala」と「Kaahe Chhed Mohe」のアレンジ・バージョンに合わせて。このシーンもよかった。
インドの映画撮影の様子を少し見れるのも楽しいかもしれない。それを見て、ついつい9月にTVCM撮影のためにムンバイーへ行ったときのことが思い出された。インドの撮影現場は混沌とはしているが、案外テキパキしている。そしてその中で一番目立つのがダンス・マスターと呼ばれる振付師たちだ。彼らの踊りは本当にうまい。バック・ダンサーやヒーロー、ヒロインよりも遥かにうまい。実際に見た撮影現場でも、この映画の中での撮影現場でも、同じような印象を受けた。
分かりやすい筋の映画だし、気持ちよく見終わることができるので、おそらく今年オススメのヒンディー語映画の内の1本となるだろう。そして何と言ってもアンタラー・マーリーの腹。・・・と踊り。何だか急にアンタラーのファンになってしまった。
突然だが今日引越しをした。
今まで僕はガウタム・ナガルに住んでいた。ガウタム・ナガルは南デリーではけっこう便利な場所にある。北はサウス・エクステンション、南はハウズ・カース、東はアンサル・プラザ、西はユースフ・サラーイ、南西にはグリーン・パーク、南東にはスィーリー・フォート。モダン・マーケットから庶民的マーケットまで、ヴァラエティーに富んだマーケットへ徒歩でアクセスできる。その上交通の要所で、ユースフ・サラーイへ行けばデリーの南北へ行くバスに乗ることができ、サウス・エクステンションへ行けばデリーの東西へ行くバスに乗ることができる。地域のグレードも、高級ではないがスラムでもないという、ちょうど中くらいのレベルである。ノース・イースト系の人が多く住んでいるので、日本人が住んでいてもあまり目立たないのもよい。昔ケーンドリーヤ・ヒンディー・サンスターンがアルビンド・アーシュラム近くにあったときは、アクセスの簡便さと土地の利便性から、多くの日本人学生がガウタム・ナガルに住んでいたと言う。
この日記を読んでいると自然と分かると思うのだが、僕は大家さんとも良好な関係を保っていた。インドで住む際に大家さんとの相性は非常に重要である。その点で僕は非常に幸福だった。
しかしいろいろ個人的な要因により、サフダルジャング・エンクレイヴへ引越しすることになった。
サフダルジャング・エンクレイヴはガウタム・ナガルの西側にある。南デリーを代表する高級住宅街のひとつで、外国人も多く住む地域である。日本人会室や日本食材店Yamato−yaなどがあり、その内日本人街へと発展していく可能性もある。ヴァサント・ヴィハールなどに比べると少しごちゃごちゃしていることは否めないが、だだっ広いよりはかえって過ごしやすいということもある。個人的にJNUに近いのもいい。
インドで引越しをするのは初めてだった。元々狭い部屋に住んでいたので、荷物はあまりない。予めダンボール箱に本やCDなどの小さな荷物を詰めておき、引越し当日の今日、本格的に荷造りをした。4時頃終わったので、それから「テンポ」を呼びに行った。ちなみにインドで「トラック」というと本当に巨大なトラックになってしまう。引越しなどに使う中型のトラックは「テンポ」と呼ばれている。
テンポは常にどこか街角に停まっている。彼らを見つけて交渉すればよい。まずはテンポ、ドライバー、クーリー(運び人)2人を雇って500ルピーの値段を提示された。以前他人の引越しを見ていたときは確か300ルピーだった。高いと思ったが、値段は引越し先の距離、荷物の量、引越し元と引越し先の階数、時間帯などで変動する。まずは荷物の量を見てもらうことにして、ドライバーとクーリーを家に呼んだ。
すると彼らは「もっとクーリーが必要だ!」と言い張る。こんな狭い部屋に住んでて大した荷物はないのに、なぜもっと必要なのだ!大家さんも500ルピーは高すぎると言って、一度追い返した。しかし彼らは家の外でしばらく物欲しげな顔をして見ていた。もう一度交渉に行く。彼らの言い分では、朝と夕方は本当はテンポが住宅地に入り込んではいけない時間帯で、特別な許可がないと引越しができないと言う。そして彼らはその許可を持っていると、自慢げにその許可証を見せた。もし許可証なしで住宅地に入って警察に見つかると2000ルピーの罰金を取られるらしい。だから許可証のない業者に頼むと、引越しは制限時間帯の終わる9時過ぎになるそうだ。これが彼らが高い引越し料金を取ろうとする理由だった。なんとなく納得してしまい、とにかくクーリーは2人でいいから、ドライバーも一緒になって荷物を運ぶように頼む。後からチップだとかチャーイ代だとか言われるのが嫌なので、最終的にチップ込みで550ルピーということに固定させた。
あれだけ「もっと人数が必要だ」と言っていたわりに、彼らは信じられないスピードで荷物を運び出し始めた。冷蔵庫、勉強机、ベッドなど、普通考えたら一人で運ぶのは不可能そうなものを、一人で運んでいく。僕はただ見て監督しているだけでよかった。というより手助けしようとすると嫌がられた。インドでは他人の仕事を手伝うのは、他人の仕事を奪うことにつながり、悪なのだ。結局30分もしない内に荷物はテンポに詰め込まれた。
その後すぐにテンポで引越し先のサフダルジャング・エンクレイヴに直行し、再び荷物を運び出し始めた。今回もさらに手際よくどんどん荷物を部屋に運び入れる。やっぱり30分もしない内に全ての荷物が引越し先の部屋に収まってしまった。つまり、1時間以内に引越しが完了したことになる。なんだか瞬間移動したような気分だ。
新居は旧居に比べて圧倒的に清潔で広いので、快適である。突然始まった新しい生活に、なんとなく自分自身が信じられない気分のまま一夜を明かした。
現在のところまだインターネットのケーブルが移転していないので、このサイトの更新も途切れ途切れになると思われる。ちょうどディーワーリーがもうすぐ来るので、もしかしたらケーブル移転はものすごく遅れるかもしれない。
1週間前ぐらいからJNUで急に選挙活動が活発化しだした。授業中突然人がぞろぞろと教室の中に入ってきて、あ〜だこ〜だ話したいことを話して帰っていく。最初は何かと思ったが、これも全てJNU学生自治会の役員選挙のためなのだ。
聞くところによると、学生自治会選挙はJNUの2大イベントの1つらしい。ちなみにもうひとつはホーリーである(JNUのホーリーは相当凄まじいらしい)。選挙が大学の大イベントになるなんて、最近の日本の大学ではあまり考えられないから新鮮だ。うちのクラスからもいつの間にか2人立候補していた。ヒンディー語学科にいる人は、官僚や政治家志望の人がけっこういるので、こういうことにも積極的だ。
僕はあまり詳しくないのだが、JNUには主に7つの学生団体が存在するようだ。その中でもっとも目立つのが共産主義、マルクス主義系の団体である。僕のクラスから立候補した2人も共産主義系の団体に所属している。
授業中突然教室に入ってくる人々の言っていることをよく聞いてみると、実はあまり大したことを言ってない。まず彼らが英語でスピーチを始めると、「ここはヒンディー語学科だ。ヒンディー語で話せ」と不満が上がる。インド国会下院の選挙が近いこともあり、彼らのスピーチは連邦政府与党のBJPや、西ベンガル州の共産党などの政党批判と絡めて行われることが多いのだが、これもまた教室から「JNUの選挙でなんで国の問題を持ち出すんだ」と批判が相次ぐため、仕方なくJNUの問題のスピーチとなる。大体選挙のスピーチというのは、現在の不便な点をあげつらって人々の不満を煽るものだが、基本的にJNUは設備が整っているので、不満点はしょうもないものばかりだ。図書館に教科書を揃えよう、とか、センターに映画を見るためのプロジェクターを、とか、インターネットのできるPCをもっと増やそう、とか、急に話題は卑近なものになる。そういう方が分かりやすいのだが。しかし、ちゃんと候補者が各教室を廻って自分の意見を述べるという伝統は、迷惑だが正しい。どうもインドの大学で唯一まともに選挙が行われるのがJNUらしい。
僕は日本の大学ではこういう選挙に全く関わらなかったし、投票もしなかったのだが、どうもJNUではそういうわけにはいかないようだ。投票しなかった人はリストアップされて公表され、後日みんなから後ろ指を差されるらしい。半ば強制的に投票しないといけないことになっている。しかもクラスメイトが立候補しているので、義理で彼らに投票してやらなければならない。こんなだから投票率はかなり高そうだ。
10月20日の今日が投票日だった。朝9時から投票開始とのことだったので、9時きっかりに行ったのだが、まだ始まっていなかった。校舎の前には各政治団体の机が並んでいた。立候補した僕のクラスメイトもそこにいた。僕は勝手に共産主義団体のバッジを胸に付けられた。
1時間遅れで投票が始まると、選挙会場の入り口は昔のデリーの空港の出口みたいになった。入り口前の両脇にズラリと人が並び、口々に「誰々に投票してくださ〜い!」と言って来る。そして勝手にポケットに立候補者の名前が書かれた紙をねじ込まれる。しかし入る前にそれらの紙は全て没収されてしまう。
投票はけっこう難しかった。名前が書かれた紙を渡され、そこにスタンプを押すのだが、名前しか書かれていないので、どの人がどの団体所属か全く分からない。つまり予め自分が投票したい人の名前を覚えておかなければならない。だから立候補者はみんなうるさいぐらいに自分の名前を連呼していたのだろう。僕はクラスメイト以外は適当に印象的な名前の人に投票した。
投票日当日と次の日が休みになるのも、選挙がかなりのビッグ・イベントであることを表している。JNUはディーワーリーでもホーリーでも基本的に1日しか休みにならないという、極度に休日の少ない大学なのだが、選挙だけは2日も休みになる。おかげで溜まりに溜まった課題をこなす時間ができた。
結局、僕のクラスから立候補した2人は落選してしまった。落ち込んでいると思ったら別にそんなこともなく、「当選したって落選したって何の変わりもない」といたってのほほんとしていた。どうも選挙に勝ってどうのこうのしたかったというわけでなく、ただ選挙に参加して楽しみたかっただけのようだ・・・。
9月14日の日記で、ある日系企業のTVCMの撮影のためにムンバイーへ行ったことを書いた。そのCMが最近になって遂に放映され始めた。第一発見者は昔住んでいたところの大家さんの奥さんだった(10月14日)。奥さんは足が悪くて1日中家にいてTVを見たりしているので、発見も早かった。そのCMを見たら一発で僕だと分かったそうだ。
その後、僕も遂に自分が出ているCMを見てしまった。音楽を聞いた瞬間に、ムンバイーの撮影所に何度も何度も流れていた音楽だったので、すぐにこれだと分かった。ひとつひとつのシーンが「あのとき撮ってたな」というもので、初めて見たのに初めて見た気がしなかった。そして最後のシーンで僕の登場。僕は恥ずかしくてまともに見ていられなかったが、CMの出来は可もなく不可もなくといったところで、ひとまず安心した。僕の出演シーンも2秒ほどなので、そんなに印象は強くないだろう。とりあえず、今まで道を歩いていて、「お前はひょっとして」と話しかけられたことはない。
僕の家にはテレビがないのであまり見る機会がないのだが、友人の話によると、午後4時と午後11時頃にインドのニュース番組アージ・タクで僕のCMが放送されるようだ。また、最近クリケットの国際試合が行われており、そこでも僕のTVCMが頻繁に流れているらしい。しかし基本的にレアなCMのようだ。
クラスメイトにはCMのことを予め伝えていたので、撮影後から「いつCMが流れるんだ」と待望されていた。遂に放送され始めたので、いろんな人が僕をTVで見たようだ。割と親しくしているインド人の友人なんか、僕のCMを見てすぐわざわざSTD(電話屋)から電話をしてくれた。かなり興奮していて、何を言っているんだか最初は分からなかったのだが、後日会ったときにそのときのことを詳しく話してくれた。彼はJNUのホステルに住んでおり、ちょうど食堂で食事をしていたときに、そのCMが流れたそうだ。彼は食堂で「これはオレの友達だ!」と狂喜して叫んだらしい。他のインド人は「日本人なんてみんな同じ顔をしている」と最初は取り合わなかったようなのだが、彼は一生懸命みんなに僕のことを説明して、その後すぐに電話をくれたらしい。そこまで喜んでくれなくても・・・。
CMが流れるのをけっこう恐れていたのだが、蓋を開けてみればそれほど集中的に放送されているわけでもなく、僕の登場時間も短いので、案外目立たないようだ。出演料ももらえたし、ムンバイーにも行けたしで、損はしなかったと言えるだろう。続けてCM出演や映画出演の依頼が舞い込むわけでもなかったのは少し寂しいかも・・・。
今日はPVRアヌパムでヒンディー語映画「Samay」を見た。
「Samay」とはヒンディー語で「時間」という意味。副題は「When Time Strikes(時間の襲撃)」。主演はスシュミター・セーン。スシャーント・スィン、ラージェーシュ・ケーラー、ディネーシュ・ランバー、トゥシャール・ダールヴィーなど、マイナーな俳優が脇を固める中、特別出演としてジャッキー・シュロフが最後に登場する。
| ● |
|
● |
|
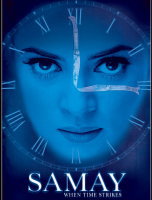 |
|
| ● |
Samay |
● |
| Samay |
インド有数の富豪が殺害された。敏腕女性刑事として有名なACP(警察副本部長)のマールヴィカー・チャウハーン(スシュミター・セーン)が捜査に当たるが、とりあえず犯行の完璧さから犯人は相当頭の切れる人物だということが分かっただけだった。
今度はトップ・アクトレスの殺人事件が起こった。一見別々の事件に見えたが、マールヴィカーは2つの事件の犯人が同一であると考える。さらに捜査を進める中、ある有名な殺人鬼が容疑者として浮上し、彼の居所を突き止めるが、そこには彼の遺体が横たわっていた。
3つの事件を照らし合わせて考えていたマールヴィカーは重要な事実に気が付く。富豪の死亡時刻は12時、女優の死亡時刻は3時、殺人鬼の死亡時刻は6時だった。しかも遺体の両手は死亡時刻と同じ時計の針の方向を向いていた。犯人は「時間」を弄んで連続殺人を行っているのだった。しかもターゲットは名の知れた人物ばかりだった。そして次の犯行時刻は9時と予想された。
マールヴィカーは殺された3人の共通した特徴に気が付く。3人とも眼鏡をかけており、しかもそれらは同じ眼鏡屋から購入したものだった。彼らは眼鏡を買ったその日に殺されていることも判明した。マールヴィカーはその眼鏡屋の顧客データを調べ、そこから一人の人物が浮かび上がる。
次のターゲットはある有名な音楽家であることが予想された。ちょうど彼はコンサートを行っていた。犯行予想時刻の9時前にコンサート会場に到着したマールヴィカーらは、会場を警備するが、9時になっても彼は殺されなかった。
引き続き音楽家の警備を続けるマールヴィカーの元へ、一人の男(ジャッキー・シュロフ)が現れる。彼こそが連続殺人犯だった。マールヴィカーは9時に犯行が行われなかったことから、このゲームはお前の負けだ、と言うが、男は不敵な笑みを浮かべて言う。「ゲームには勝った」と。彼は9時ちょうどに、マールヴィカーの一人娘を殺害していたのだった。それを知って逆上したマールヴィカーは彼を銃で射殺する。彼の死亡時刻はちょうど12時だった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
硬派なサスペンス映画。連続殺人事件を巡る、愉快犯と女性刑事の知力を尽くしたバトルが、ハリウッド・タッチの描写で描かれていた。セリフで物語が展開していく部分が多いので、ヒンディー語がかなり分からないと理解は難しいだろう。
スシュミター・セーンは冷静で知的な女刑事マールヴィカー役を緻密な演技でこなしていた。元々男っぽい容姿をしているので、下手に恋愛映画のヒロインを演じるよりは、こういう硬派な役ははまっている。大きな目でじっとカメラを見据えて物を考える様子や、氷のように冷たい表情はかっこいい。殺人事件の調査の合間に、一人娘との心温まる交流がわざとらしく挿入されていた。このシーンでのマールヴィカーだけは普通の母親に戻る。マールヴィカーのキャラクターに幅をもたせるためだろうが、正直なところこれらのシーンは邪魔に思えた。もちろん、娘は最後のシーンのための伏線なのだが。
時計と時間を題材にした連続殺人事件の筋は斬新で面白かった。それらを追っていくマールヴィカーたちの捜査過程も楽しめる。特にマールヴィカーの、相手の心を見透かしたような話し方がいい。しかし眼鏡から最終的に犯人が割り出されるというのは少し強引な気がした。大富豪や殺人鬼が、街角の何の変哲もない眼鏡屋で眼鏡を買うだろうか・・・?結局、12時、3時、6時、9時と時間に合わせた殺人ゲームは、犯人自身の時間ピッタリの死により、完遂してしまった。つまり警察側の敗北で映画は終わった。ハッピーエンドではないが、インド映画にしては、どんでん返しかつまとまった終わり方だったと思う。
なぜかマールヴィカーと連続殺人犯の共通の趣味がパックマンで、物語の中でも時々、暗闇の中で黙々とパックマンを遊ぶ不気味な犯人の姿が映し出される。しかしパックマンってナムコのゲームじゃないのか・・・?勝手に映画の中で使ってしまっていいいのだろうか・・・という野暮ったいことはインド映画では言いっこなしなのだ。映画の冒頭ではヒッチコックの映画(題名は忘れた)の最後のシーンが使われていたのも、インド映画ならではか。ヒッチコックへのオマージュと受け取っておけばいいだろう。
ジャッキー・シュロフは渋い登場の仕方をする。一応犯人の声だけは事前に何度か聞くことができ、どこかで聞いたことのある声だと思っていたのだが、まさか犯人がジャッキー・シュロフだとは思ってもみなかった。彼の登場で観客からも「アレ!」と声が挙がった。
音楽はサンディープ・チャウター。途中に一度だけミュージカル・シーンがあるが、無理矢理挿入された印象を強く受けた。こういうシリアスなテーマの映画に、無理にミュージカルを入れなくてもいいと思うのだが、インド映画の製作者たちは「歌と踊りを入れないと映画は売れない」と思っているので、どうしても1、2曲は入ってしまう。その他、同じくサンディープ作曲の、「Bolliwood Holliwood」の曲「Rang Rang」が愛嬌程度に使用され、その音楽に合わせてスシュミター・セーンが娘役の女の子と、見ていてこっちが恥ずかしくなるような、かなり自然体の踊りをしていた。
昨日はディーワーリーだった。ディーワーリーも3度目となるとかなり迷惑な祭りに思えてくる。最初のディーワーリーでは近所の子供たちとカンシャク玉を投げ合って楽しく遊んだものだった。ロケット花火が僕の家のすぐ上に飛び込んで火事になったのも、今ではいい思い出である。2度目のディーワーリーは先生の家で迎えた。もう食べられないと言っているのにどんどんプーリーを皿に盛られて困ったものだった。3度目のディーワーリーは、外に置いたバイクが花火で燃やされないかと心配しながら、また引っ越したばっかなのにディーワーリーのバクシーシを要求してくるチャウキーダール(門番:新居にはちゃんと門番がいる!)に頭を悩まされながら、膨大な量の課題に絶望的な気持ちになりながら迎えた。
今日はPVRアヌパムで新作映画「Pinjar(鳥かご)」を見た。女流作家アムリター・プリータムの同名小説が原作で、インド・パーキスターン分離独立時が舞台の、2001年大ヒット作「Gadar」を想起させるストーリーである。インド映画業界にしては大冒険の、パーキスターン・ロケを敢行したことで話題だ。キャストはウルミラー・マートーンドカル、マノージ・バージペーイー、サンジャイ・スーリー、サンダリー・スィンハー、プリヤーンシュ・チャタルジー、イーシャー・コーピカル、リレット・ドゥベーイ、クルブーシャン・カルバンダー、ファリーダ・ジャラール、アローク・ナート、シーマー・ビシュワースなどなど。主役はちょっと癖のある俳優2人、準主役は最近売り出し中の若手俳優数人、脇役はベテラン俳優ばかりという布陣である。監督はチャンドラプラカーシュ・ドゥイヴェーディーという人で、元々TVドラマなどの監督をしている人のようだ。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
Pinjar |
● |
| Pinjar |
1946年、パンジャーブ。アムリトサルに住むヒンドゥー教徒のプーロー(ウルミラー・マートーンドカル)は結婚相手を探すため、家族と共にアムリトサルから父親モーハンラール(クルブーシャン・カルバンダー)の田舎へ来ていた。縁組はとんとん拍子で進み、プーローは地元の名士シャームラールの長男ラームチャンド(サンジャイ・スーリー)と結婚することに決まった。同時にプーローの兄トリローク(プリヤーンシュ・チャタルジー)と、ラームチャンドの妹ラージョー(サンダリー・スィンハー)の結婚も決まった。
ところがある日プーローは、モーハンラールの家に恨みを抱いていたムスリムの家の息子ラシード(マノージ・バージペーイー)に誘拐される。トリロークは警察に届け出て彼女を捜索することを主張するが、父親は承知しない。娘が誘拐されたとあっては家名を汚すことになるからだ。両家はプーローの誘拐を隠し、プーローの妹ラッジョー(イーシャー・コーピカル)をラームチャンドと結婚させることに決めた。こうしてラームチャンドとラッジョー、トリロークとラージョーの結婚式が行われた。
一方、プーローはラシードの家に監禁されていた。プーローを誘拐したのは父親の命令であったが、彼はそれ以前に彼女に一目惚れをしていた。プーローは毎日泣き暮らしていた。ある夜こっそり逃げ出して家に戻るが、両親は彼女を受け入れなかった。もはやプーローは死んだことになっており、今さら帰って来てももはや家に住む場所はなかった。プーローは泣く泣くラシードの元へ帰り、彼と結婚することになった。彼女はハミーダーというムスリム名を名付けられ、腕に刺青を入れられた。
プーローとラシードは彼の田舎へ引っ越した。ラシードはプーローを誘拐したものの、彼女をひどく扱うことはしなかった。半年ほどは泣き暮らしていたが、次第に自分の運命を受け入れるようになっていた。この間、彼女は自分の夫となるはずだったラームチャンドに一度出会っている。
1947年8月15日、インドとパーキスターンはイギリスから分離独立を果たした。この分離独立によってヒンドゥー教徒・スィク教徒とイスラーム教徒の間に深刻な暴動が発生し、特にパンジャーブ州ではインドに向かうヒンドゥー・スィク教徒と、パーキスターンに向かうイスラーム教徒の間で血で血を洗う殺戮が繰り広げられた。
プーローとラームチャンドの家はパーキスターンの領土になった。ラームチャンドの家族はインドへ向かうことになったが、途中でムスリムの暴徒たちに襲われ、ラームチャンドの両親や妻は殺害され、妹のラージョーが誘拐されてしまう。途中、プーローと偶然出会ったラームチャンドは、彼女にラージョーを探すよう頼む。
プーローはラームチャンドの旧家で使用人として働かされていたラージョーを発見し、ラシードの助けを借りて彼女を救い出す。その頃パーキスターンとインドの国境の町ワーガーでは、行方不明になった身内を探すために両国からたくさんの人が来ていた。ラシード、プーロー、ラージョーはワーガーへ行き、ラームチャンド、トリロークと再開する。
トリロークはプーローに、インドへ来るよう説得する。しかしプーローは承知しなかった。既に彼女の心はラシードと共にあった。彼女はラシードと共にパーキスターンに住むことに決めたのだった。彼女の決意を尊重したラームチャンド、トリローク、ラージョーはインドへ帰っていた。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
興行収入の観点から見たら、2001年の「Gadar」は成功した作品だったと言えるだろう。しかしストーリーには不満点が残った。特にラスト・シーンは普通のインドのアクション映画とあまり変わらなくて、力づくでごりおしされていた感が強かった。しかも全ての問題が解決されておらず、結果的に「Gadar」の脚本は破綻していたと言っていいだろう。その「Gadar」と同じく、印パ分離独立の時代をテーマにしたこの映画、もちろん「Gadar」の二番煎じとの声が挙がるのは避けられないが、僕は「Gadar」よりも数段上の作品だと自信を持って言える。たとえ興行的に失敗したとしても、「Pinjar」は2003年度必見の映画のひとつに数えられるだろう。
時は1946年。独立イギリスからの分離独立が現実のものとなって見えてきて、どのような形で独立するかの議論が盛んに交わされていた時期だった。そんな混迷の時代に、アムリトサルに住むプーローは、まるで空を飛び回る小鳥のように自由気ままな生活を送っていた。その様子は冒頭のパンジャービー語ソング「Maar Udari」で「飛べ飛べ小鳥よ」と歌われている。
結婚が決まり、幸福の絶頂にいたプーローを一転して不幸が襲う。彼女はラシードによって誘拐され、幽閉されてしまう。その後彼と結婚したプーローは、家族とも離れ離れになって、ムスリムとして生活することを余儀なくされる。これが題名「Pinjar(鳥かご)」の比喩するところであることは言うまでもない。だが、彼女が幽閉されたシーンの直後に、鳥かごに入った鳥の映像が映し出されるのはあまりにステレオタイプに思えた。
日本人には、娘プーローを誘拐されたモーハンラールのとった態度が理解できないだろう。僕もあまり納得できなかった。普通娘が誘拐されたら捜索するだろう。しかし彼は「娘が誘拐されたとあっては家名が穢れる」として、娘は死んだものとして扱い、その事件を世間に公表しなかった。そういうものなのだろうか。
1947年の印パ分離独立時に起こった大混乱、大殺戮は、現在に至るまでインド人に語り継がれており、度々話題にのぼる。この映画でもその描写はすさまじく、ヒンドゥーもムスリムも大勢の人々が暴徒に襲われて命を落とした上に、女性たちは誘拐され、レイプされ、奴隷とされた。プーローは暴動から逃れてきたヒンドゥーの女の子を助け、さらに誘拐された兄の嫁ラージョーを何とか探し出してインドに帰す。この映画の隠れた主題は、「女性問題」だった。
ラスト・シーンで、プーローはインドに帰らず、パーキスターンに住み続けることを決心する。この展開は、おそらくインド映画をたくさん見ている人にとっては心地よく、あまり見ていない人には「なぜ?」と納得がいかないものかもしれない。誘拐されて無理矢理結婚させられた女性がいたとし、自分の家族の元に帰るチャンスがやって来たとしたら、普通は帰ろうとするだろう。北朝鮮に拉致された日本人の例を見ても明らかだ。しかしプーローは夫と共にパーキスターンに残った。これはインド映画の不文律「結婚は絶対である」に則っていると考えられる。インド映画の中で、一度結婚してしまった男女は、どんなにお互い憎みあっていても、別の好きな人がいても、別れないようにできている。その内お互いに惹かれあってめでたくハッピーエンドとなることがほとんどだ。たとえ離婚しても、ラスト・シーンではまた再婚したりする(「Haan... Maine Bhi Pyar Kiya Hai」が記憶に新しい)。僕はいかにもインドの道徳に沿った、悲しいが心地よい終わり方に思えた。
ウルミラー・マートーンドカルは「Bhoot」に引き続き、ヒステリックな演技が随所に見られた。このままこの路線で行くのだろうか?ウルミラーはどちらかというと二流のイメージが強いので、そろそろ独自の路線を確立した方がいいかもしれない。マノージ・バージペーイーは「Road」で演じたような気味の悪い悪役の再演かと思いきや、繊細な感情を持った不器用な男役を迫真の演技で演じ、やはり只者ではないと感じさせられた。どちらかというと、プーローよりもラシードの方が重要な役柄だったかもしれない。もう少しラシードの心情描写があれば、もっといい作品になったと思う。
プーローの父モーハンラールを演じたクルブーシャン・カルバンダーは、「Lagaan」でマハーラージャー役をやっていた俳優だ。あのイメージが強かったので、彼がスクリーンに登場したときは「ジャイ・マハーラージ!」と言いそうになった。
端役だったが、シーマー・ビシュワースがパグリー(狂女)役で出演していた。この女優はいつも変な役を演じるので、個人的に注目している。パグリーは男児を生んで野垂れ死ぬが、その子供をプーローは育てようとする。パグリーはヒンドゥー、プーローはムスリム(にさせられた)だったから、村の長老の反対にあって子供を取り上げられる。
音楽は大ヒットCD「Gadar」を作曲したウッタム・スィン。アップテンポの音楽から、ゆるやかな祈りの音楽まで、幅広い音楽が「Pinjar」のCDに入っている。なんとウッタム・スィンは映画にも特別出演している。
2001年の「Lagaan」「Gadar」の2大ヒットからインド映画も時代劇に手を出すようになってきた。この映画もその流れから作られた時代劇と言えるだろう。時代劇というと、精密な時代考証と美術・衣装スタッフなどの腕が問われる。しかしなんだか肝心なセットが安っぽくて、重厚な雰囲気が出ていなかったのが残念だ。おそらく本物の当時の自動車やバスなども登場したが(コレクターなどから借りたのだろう)、それだけ本物っぽくて、周りの雰囲気にあまり溶け込んでいなかったように思えた。パーキスターンのワーガーでロケを行ったそうなのだが、ワーガーのシーンも、別にワーガーで撮影しなくても撮れるような中途半端な環境だった(逆に言えば、国境の町ワーガーの限られた場所でしかロケが認められなかったのかもしれない)。物語の重要なシーンではあったのだが、言われなければそこが本当にワーガーだとは気付かず、その価値が分からない。ラーホールのアーラームギーリー・ゲートでも映してくれればパーキスターンでロケをしたと一発で分かるのだが。ここは、「パーキスターンでロケを行ったという事実がとりあえず重要だ」としておこう。パーキスターンではインド映画の上映が禁止されているようなのだが、この映画くらいは上映されてもいいかもしれない。両国の映画業界もこれをきっかけに是非歩み寄ってもらいたい。
この映画から推し量られたのだが、独立前のインドの町の看板などは、全部ウルドゥー語で書かれていたようだ。デーヴナーグリー文字が初めて表れるのは、ラストシーンのワーガーだったように記憶している。独立前のインドはヒンディー語よりもウルドゥー語の方が主流だったのだろう。
ちょっと久しぶりに昔住んでいた家を訪ねてみた。一応10月いっぱいまでの契約なので、鍵は返したものの、月が替わるまでは僕は自由に部屋へ入る権利がある。実はまだいくつか前の部屋に荷物が置いてあったので、それを完全に運び出す用事もあった。それより何より、前の大家さんとは2年間の付き合いだったので、時々こうやって訪れてはご機嫌伺いするつもりだ。
日本式に言って2階にある大家さんの家へ行ってみると、大家さんがいた。息子のスラブと、使用人のシャームーもいた。しかし奥さんがいなかった。どこかへ出掛けているのだろうと思い、鍵をもらって5階にある旧アルカカット邸へ行った。もうほとんど持ち去ってしまったが、細々としたものがまだいくつか残っていた。それをバッグに詰めて再び大家さんの家へ行ってみた。スラブにはいつか僕の新居へ連れて行くと約束していたので、今日当たりにその約束を実行しようかと思っていたが、スラブはどこかへ行ってしまっていた。大家さんが部屋の真ん中で一人で酒を飲んでいた。かなり飲んだくれているようだった。僕に夕食を食べていけと言うので、「じゃあ少しだけ」ということで夕食を準備してもらった。
「おばさんはどこ?」と聞くと、「実家に帰った」と言う。「ディーワーリーを祝うために帰ったの?」と聞くと、「いや、ケンカして出て行った」と言う。なんだか家の雰囲気がおかしかったが、やっぱりそういうことだったか・・・。気まずいときに来てしまったものだ。しかし、夫婦ゲンカして、奥さんに実家に帰られて、一人酒を飲んだくっている夫の図というのがあまりにいかにも、という感じだったので、少し可笑しい気持ちもした。
ガウタム・ナガルの前の家に住んでいるときは、あまり大家さんのプライベートなことについて踏み込んで書かないようにしていたが、もう出てしまったので、ちょっと気楽に書けるようになった。大家さんは超デブで悪役顔だが、基本的にいい人である。いくら親しくなっても金にだけはうるさいのはインド人ならではだが、他の部分で特に嫌な思いをしたことはなかった。だが、数点の不満もあった。それらは全て大家さんの家族に関わることだった。以前、田舎に住んでいる大家さんのお母さんが病気の治療のためにその家に住んでいたとき、大家さんの、お母さんに対する扱いがあまりに酷かったのを覚えている。一般的に言っても、未亡人のお婆さんというのは、インドではかなり酷い扱いを受ける。まるで「早く死んでくれ」と言わんばかりである。未亡人は不吉な存在とされて家族とは別の部屋に住まわされたり、祭りの参加できなかったりするし、「年寄りだから」と言って差別的な処遇をされたりする。それを見て可哀想な気分にならざるを得なかった。
それ以上に、大家さんの酒癖の悪さにはかなり辟易していた。酔っ払っているときに大家さんと話をし出すと、意味の分からないことを延々としゃべり続けられてグッタリするし、悪酔いしたときには家族を殴ったりするのだ。僕は殴られたことはないが、酔っ払った大家さんが僕の上に倒れ掛かってきて、押しつぶされそうになったことがある(繰り返すが、大家さんは超デブである)。
ある日、大家さんがシラフのときに、「なぜ酒を飲むのか」と批判したことがあった。そのときはちょうど大家さんが僕にジャイナ教の崇高な教えをとくとくと説いていたときだった。不殺生だとか非暴力だとか、偉そうなことを言っていたので、ちょっと意地悪するために大家さんの欠点を指摘してやろうと思ったのだった。酒を飲むこと事態は別に完全に悪いことでもないが、飲み過ぎることはいけない、と主張してみた。同じ場にいた奥さんも「この子は全く正しいことを言う」と同意した。これで大家さんは窮地に陥ったかと思うと、大家さんは急に真剣な顔になり、「ちょっと別室に来い」ということになってしまった。
それからどのくらい話が続いただろうか。大家さんが話したことは、酒を飲んで酔っ払うことにこれだけ深い言い訳を結びつけることができるのか、と呆れ感心してしまうものだった。大家さんが酒を飲み始めたのはかなり若い頃だったそうだ。大家さんの家は貧しく、大家さんも子供の頃から働いてお金を稼いでいた。帰ってくるのは毎日真夜中だったが、お母さんは大家さんのために夕食を作ってくれなかったそうだ。曰く「眠気が覚めるから」。仕方なく大家さんは外食して腹を満たしていたが、概してそういう場所では一日の仕事を終えた肉体労働者たちが安物の酒を飲んだくっているものだ。そこで大家さんは自然と酒を覚えたそうだ。これが大家さんが酒を飲み始めたきっかけの話だった。次に大家さんは、酒を飲んだくれる理由を語った。実は大家さんの奥さんは足が悪く、歩くのに問題がある。結婚前から足は悪かったようだが、大家さんは結婚するまでそのことを知らされていなかったらしい(もちろんお見合い結婚である)。身体障害者と結婚させられた大家さんは「騙された」と表現したが、しかし人生においてそのことに対して不平を述べたことはなかったと言う。ただ、どうも奥さんの身体の悪さは、詳しくは知らないが、夜の営みが不可能なほどらしい。一応息子が一人いるが、一人しかいないのはそういう理由があったのかもしれない。大家さんは言った。「オレは健康だ。性欲だってある。オレはセックスがしたい。でも妻はできない。売春婦を買うことだってしたくない。じゃあどうすればいい?酒を飲むしかない。酒を飲めば、酔っ払って泥酔して、気付けば次の日になってる。これが酒を飲んで酔っ払う理由だ」とのことだった。こんな話を他人にするのも初めてだと言っていた。
突然だが、インド人の酒飲みで有名な人に、ウルドゥー詩の巨匠ミルザー・ガーリブ(1797-1869)がいる。彼は飲酒が禁止されているムスリムなのだが、借金をしてまで酒を飲んでいたほどの酒好きだった。イスラーム教徒にとって聖なる場所であるはずのモスクに来てまで酒を飲んでいたガーリブを見かねて、「モスクで酒を飲むとは何事か」とある人が注意したところ、彼は「アッラーはどこにいても我々を見ているのだから、どこで飲んでも一緒じゃないか」と笑って答えたという。酒飲みには酒飲みの哲学があり、何を言ってものれんに腕押しだ。ガーリブのようにユーモアを交えてその哲学を語ってくれたらこちらも気分が楽になるが、大家さんの飲酒の理由はあまりに悲劇的だったので、何も言い返すことができず、僕は黙ってうなずいているしかなかった。真夜中になってやっと解放してもらえた覚えがある。
しかし酔っ払う正当な理由があるとしても、酔っ払って家族に暴力を振るうのはまた別問題だ。どうも今回の別居騒動も、それがエスカレートして遂に最終局面まで来てしまったという状況のようだ。インドではまだまだ離婚率は低いので、それ以上事が進展することはないと思うが、ちょっと残念だ。だが、僕が去ったと同時にこういうことが起こったということは、「もしかして僕って平和の男神?」とか思っちゃったりして、自分の能天気さに呆れたりもするものだ。
JNUのことをあまりよく分からずにJNUで学び始めたが、他のインドの様々な事象と同じく、何の前説明もなしに、いきなり本番みたいな感じでカリキュラムが進んでいくので大変である。入学手続きからしてJNUの地理に精通していなければこなせないし、授業が始まっても、何のマニュアルもないのに、全ての教育プログラムを理解していることを前提に進められていく。
思い出してみれば日本でもそんなことがあった。僕は小学校くらいの頃から漠然とバイクに憧れがあったので、大学時代に二輪車の免許を取るため教習所へ行き始めた。僕はそれまで、ただ憧れていただけで全くバイクに乗ったことがなかった。教習初日、4、5人の新入生と共にバイクに乗って横一列に並ばされた。そしていきなり「発進」と言われた。他の人々は轟音と共に走り去ってしまったが、全くの初心者だった僕はそのままポツンと残っていた。それを見た教官が「君はバイクに乗ったことがないのか?」と驚いた。「乗ったことがないからここに来ているんですけど・・・」と理不尽な気持ちになったことは言うまでもない。ていうか、なんでみんな知ってるのだろうか?もしかしてみんな暴走族?それも今では昔の話、まさかインドのカオスの中でバイクを運転することになろうとは、あのとき誰が想像しただろうか。
JNUに毎日通ってカリキュラムをこなしていく内に次第に分かったことだが、JNUでの学業の大きなポイントはどうやらクラステスト、タームペーパー、セミナーペーパー、期末試験の4つのようだ。クラステストは中間テストのようなもので、モンスーン・セメスター(8月〜12月)では9月頃に行われる。タームペーパーは小論文であり、大体10枚前後のレポートを書かなければならない。10月締切である。セミナーペーパーは、発表・議論用のもので、5枚〜10枚が相場のようだ。11月上旬締切である。11月下旬には期末テストがあり、これらの総合的評価により成績が決まるようだ。出席をとる教授もいれば、全く出席をとらない人もいるのは日本と同じである。
JNU最大の難関、少なくともヒンディー語科の最大の難関はタームペーパーとセミナーペーパーだ。5つの必須科目があるので、10月〜11月上旬にかけて、5×2の合計10個のレポートを提出しなければならない。ヒンディー語科はもちろんヒンディー語で書かなければならず、そのうちの2つはウルドゥー語の授業のものなので、習ったばかりのウルドゥー語で書かなければならない。これらが最近の僕を超多忙にさせており、「殺人的スケジュール」とか「時間的破産」とか嘆きつつなんとか間に合わせているところだ。と言ってもインド人はやっぱり時間を守らないので、提出日にレポートを必死に仕上げて持って行っても、平然として「明日出します」とか教授に言っている奴もいたりするから拍子抜けする。
タームペーパーやセミナーペーパーの表紙の書き方についても、何の説明もない。先輩から聞いて、その通りに書くしかない。タームペーパーは「awadhi patr」、セミナーペーパーは「sangoShThi patr」とヒンディー語で書くようで、カリキュラム番号、カリキュラム名、トピック、提出先、自分の名前、センター名などを書く。とにかくシステムが分からない上に、それを視覚的に説明したマニュアルなどがないので困る。全て口承と見よう見まねで伝達されていく。まるで口承文学と師弟制度の伝統が未だに残っているかのようだ。
今日は突然セミナーがあった。その教授がもうすぐどこかへ長期出張するということなので、事前に提出したタームペーパーを元にセミナーが行われた。セミナーで何が行われるかと思ったが、一人一人前に立たされて、タームペーパーについていろいろ言われるだけだった。その多くは叱責である。特に文法やスペリングなどのミスに厳しい人なので、句読点の間違いまで見つけて指摘してくる。インド人でも全然正しいヒンディー語が書けていない人がおり、みんなの目の前で「お前のヒンディー語は間違いだらけだ。ヒンディー語修士の学位を取る資格はない。」と厳しく言い放たれる。手を抜いてタームペーパーを提出してしまった人にとってはまさに屈辱の時間であった。内容の間違いについても厳しく指摘された。
僕はというと、最近なんとなく興味があるヒンディー語とウルドゥー語にまつわるテーマの小論文だったので、けっこう一生懸命書いた。インドの論文の書き方は、とにかくできるだけ多くの大物学者たちの文献を読み漁って、それらからずらずらと重要な文章を引用して批評を加えて、それに自分の意見を混ぜるという形が一般的なような気がするが、そんなに多くの本を読む時間も気力もなかったので、必要最低限の本だけ読んで、後は自分のオリジナルな意見を、この日記に書いているような感じで書き連ねていった。でもかなり真面目に考察した。てっきり「お前は文献をちゃんと読んだのか」と怒られるかと思っていたが、意外や意外、「独自の意見を独自の手法で述べていて面白かったぞ、日本の友よ」と教授は褒めてくれた。クラスの中で褒められたのは4、5人しかいなかったので、けっこう嬉しかった。しかしやっぱり最後に「お前は文献をちゃんと読んだのか」と聞かれたが、別に叱られなかったからホッとした。
今日の活躍により、また僕の株がひとつ上がってしまったようだ。セミナー後にはクラスメイトから「おめでとう」と握手された。教授から褒められることはよっぽどめでたいことのようだ。しかも僕の書いたレポートのコピーを欲しがる人までいた。こういう賞賛ならまだいいが、このくらいまでくると、だんだんクラスメイトから嫉妬の対象になって来るから怖い。JNUのインド人学生の狡猾さは前に少し耳に挟んだことがある。わざとライバルに間違った試験日を教えたりするらしい。日記には書かなかったのだが、実は半月ほど前、JNU構内に停めておいた僕の愛機カリズマの後輪がパンクしていた。調べてみると小さな釘が刺さっていた。状況から判断しておそらく故意にやられた。僕のバイクはかっこいいので、それを妬んでの犯行と思われる。インド人でも陰険なことをする奴がいるもんだ。ちなみにパンク修理はデリーでは一律20ルピーだから痛くも痒くもない。
もっとも、少なくとももうクラスに親身になって助けてくれる人はいなくなるかもしれない。既にウルドゥー語のクラスでは、僕は「かなり出来る奴」ということになってしまっているので、インド人のクラスメイトから質問されたりするようになった。どうも彼らはヒンディー語文学についての知識は相当叩き込まれているが、言語学的分析力や外国語習得能力はあまりないように思える。しかし来週のカビール(インド中世の詩人)のセミナーでは僕の株は急落するだろう。インド屈指のカビール研究家に対してカビールについての小論文を書いて出すのは、カビールをほとんど読んでいない上に、読んでも簡単に理解できない僕にとっては酷すぎる・・・。撃沈間近である。
|
|
|
|
|
NEXT▼2003年11月
|
|
| *** Copyright (C) Arukakat All Rights Reserved *** |



