|
|
| ◆ |
5月7日(金) Badmaash Company |
◆ |
しばらく大作の公開が控えられていたヒンディー語映画界だが、先週から堰を切ったように期待作:話題作の公開が続いている。今週の目玉はヤシュラージ・フィルムスの「Badmaash
Company」。監督は、元々テレビドラマ俳優として有名だったパルミート・セーティー。脚本も彼の手によるものだが、報道によると6日で一気に書き上げたものであるらしい。ここ数年堅実に良作にて好演をし続けているシャーヒド・カプールが主演の他、アヌシュカー・シャルマーがヒロインを務めていることで注目を集めている。デビュー作「Rab
Ne Bana Di Jodi」(2008年)でいきなりシャールク・カーンと共演を果たし、映画もヒットしたが、その後出演作が途切れていた。「Badmaash
Company」が彼女にとって第2作となる。他に目を引くのが東洋人風外見のメイヤン・チャン。インド生まれの中国人で、インディアン・アイドルという米国発タレント発掘番組インド版の第3期でファイナリスト10人の内の1人となった歌手である。本作が彼にとっての俳優デビューとなる。
題名:Badmaash Company
読み:バドマーシュ・カンパニー
意味:悪党会社
邦題:バドマーシュ・カンパニー
監督:パルミート・セーティー(新人)
制作:アーディティヤ・チョープラー
音楽:プリータム
歌詞:アンヴィター・ダット
振付:アハマド・カーン
衣装:アミーラー・パンヴァーニー、マムター・アーナンド
出演:シャーヒド・カプール、アヌシュカー・シャルマー、ヴィール・ダース、メイヤン・チャン、アヌパム・ケール、キラン・ジューネージャー、パワン・マロートラー、ジャミール・カーンなど
備考:PVRプリヤーで鑑賞。
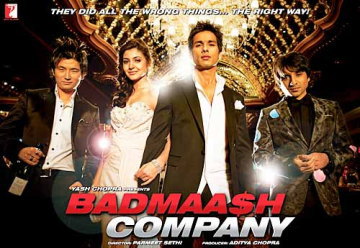
左から、メイヤン・チャン、アヌシュカー・シャルマー、
シャーヒド・カプール、ヴィール・ダース
| あらすじ |
1994年ボンベイ。大学を首席で卒業したカラン・カプール(シャーヒド・カプール)は、24年間真面目に会社勤めをしていた父親(アヌパム・ケール)のような人生を毛嫌いしており、手っ取り早く大金持ちになることを夢見ていた。大学の親友チャーンドゥー(ヴィール・ダース)とジン(メイヤン・チャン)と共に、ボンベイとバンコクの間で密輸品を運ぶキャリアーをして金を稼ぐ。このとき、同じくキャリアーとして密輸に参加していたモデル志望の女性ブルブル・スィン(アヌシュカー・シャルマー)と出会う。4人は意気投合し、フレンズ&カンパニーという会社を興して、リーボックのスニーカーをバンコクからグレーな方法で輸入する事業を始める。当時のインドでは輸入靴に120%の関税が掛かっていた。それを巧妙な手段により無関税で輸入する方法を編み出し、ボロ儲けしていた。また、カランはブルブルと恋仲になっていた。
ところが、マンモーハン・スィン財務大臣(当時)による経済開放政策が実施され、輸入品への関税が一気に引き下げられた。靴の関税も20%になってしまった。これでは商売あがったりである。4人は会社をたたんで米国へ移動する。米国ではカランの叔父ジャズが服飾品企業を経営しており、彼を頼っての移住であった。
カランはまず、革手袋をインドから輸入する事業に手を付ける。ただし普通の方法ではなく、米国人事業家チャーリーを手玉に取って大金をせしめる。次に住宅ローンを使って購入した家を次々に売買することでさらなる大金を得る。しかし、金に酔ったカランは次第に傲慢になって行く。まずはジンが抜け、次にブルブルが去り、最後にチャーンドゥーも米国人の恋人リンダとの安穏な生活を選んだ。
一人残されたカランはひとまずボンベイに戻る。そこで、25年勤務の表彰を受ける父親の姿を見て、真面目に働くことの大切さを実感する。そのまま米国にとんぼ返りしたカランは、住宅ローン詐欺の疑いで警察に逮捕される。何とか刑事裁判は免れたが、民事裁判によって半年の禁固刑となる。出所したカランは、叔父ジャズの会社で下働きをして地道に生活をする。
ジャズの計らいでカランはブルブルと再会する。ブルブルはカランの子を身ごもっていた。カランが改心して真面目な人間になったのを見たブルブルは、初めて妊娠を打ち明け、結婚を申し込む。2人は結婚することになる。
ところが同じ頃ジャズの会社が大きな危機に直面していた。マドラスから大量輸入したYシャツが、洗濯すると色落ちが激しく、返品されて来てしまったのである。この噂はたちまち市場に伝わり、会社の株価がガタ落ちした。カランは、かつての仲間たちを再び招集し、色落ちするYシャツを、「洗濯するごとに色が変わる新技術のYシャツ」として売り出す。しかもマイケル・ジャクソンのバックダンサーを務めていたチャーンドゥーの妻リンダの協力を得て、そのYシャツをマイケル・ジャクソンに着てもらう。たちまちの内にそのYシャツは大人気となり、株価も回復した。底値のときに大量の株を購入していたために、株価回復後に売却することで大きなボーナスも得る。
このことがきっかけで、カラン、ブルブル、チャーンドゥー、ジンはジャズの会社で働くことになり、カランは父親とも仲直りすることができた。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
「大儲けをするには大きなアイデアが必要だ」という格言をもとに、アイデアひとつでインド、バンコク、米国を渡り歩いて派手に金儲けをする主人公の物語であった。時代設定は90年代であったが、古いインドと新しいインドの衝突と葛藤が根幹テーマとしてあり、それは近年のヒンディー語映画の潮流にモロに乗っている。古いインドの象徴は、アヌパム・ケール演じる父親である。ひとつの企業に25年間毎日真面目に勤務し、それを誇りに感じていた。だが、毎日同じ生活を送る父親の退屈そうな人生を見て、新しいインドの象徴である、シャーヒド・カプール演じるカランは、もっと手っ取り早い方法で成功を掴み取ろうとする。だが、カランは金の魔力に酔い、仲間を失い、恋人も失い、逮捕投獄され、全てを失う。その彼の心に響いたのは、25年の皆勤賞を受賞した父親の言葉「この25年間、稼いだお金の内、1銭も不正をして稼いだものではない」であった。父親は以前にもカランに「頭脳を正しく利用しなさい。そうすれば全てうまく行くだろう。しかし間違った利用をすれば、自らの首を絞めることになるだろう」と忠告していた。それらの言葉を思い出したカランは改心し、出所後は底辺の仕事を真面目にこなすようになる。この辺の展開は、正しく生きる大切さをべースにストーリーを構築する「インド映画の良心の法則」に則っている。しかし、辛気くさく映画が終了するのを避けるため、最後にカランのアイデアに活躍の場が与えられる。叔父の会社の危機をチャンスに変え、同時に離れて行ってしまった仲間の心も引き戻す。喧嘩別れした父親との仲直りもエンディングで描写され、ハッピーエンドで幕を閉じる。「悪党会社」という意味の題名の映画ではあるが、良心に訴える典型的なヒンディー語映画であった。
カランは劇中で主に4つのアイデアを実行する。その内、最初のアイデアは時代を反映していてなかなか興味深かった。かつてインドは高関税によって自国産業を守る社会主義的経済体制を採っていた。おかげで自給自足経済が浸透し、「ロケットから爪楊枝まで」自国生産をしていると言われていたが、国際競争から切り離され国に守られた各産業の発展は停滞することになった。高価ながら高品質な輸入品は国民全体の憧れの的であり、全ての人が手にできるものではなかった。ナイキやリーボックなど、国際ブランドのスニーカーも十分に憧れの対象であった。輸入靴には120%の関税が掛けられており、とてもじゃないか庶民の手が出るようなアイテムではなかった。今でも田舎にナイキやリーボックの大きなショールームが突然立っており、こんな田舎でも意外にスニーカーの需要があることに驚くが、それはこの頃に庶民がスニーカーに対して抱いていた羨望感が原因のようである。もっとも、今でも国際ブランドのスニーカーの価格は十分高く、ステータスシンボルとしての実体的な価値は失われていない。
そのような状況の中で、カランは、「靴は片方だけでは価値ゼロだ」という言葉からアイデアを思い付き、バンコクからリーボックのスニーカーを片方ずつ輸入し始める。バンコクのリーボックで購入した靴の片方のみを集めてインドのとある港へ、もう片方を別の港へ送り、インドの税関で片方しか届いていないことを理由に受け取り拒否するのである。税関で受取人が現れなかった荷物は、1ヶ月後に競売にかけられる。しかし、そこで片方だけの靴を買おうとする者は他におらず、最低価格で落札ができる。別々の港で片方だけの靴を落札し、それらをボンベイへ運んでひとつにする。すると、正式な手続きを踏んで輸入したスニーカーなのにも関わらず、無関税状態の低価格で売り出すことが可能となるのである。
この違法スレスレの商売は軌道に乗り、短期間で大金を稼ぎ出すが、すぐに大きな障害に直面する。当時財務大臣を務めていたマンモーハン・スィンが1991年に経済政策を大転換し、経済自由化に踏み切ったのだが、その余波が靴の輸入業にも拡大したのである。映画の時代設定は1994年で、既に経済自由化が実行された後であるが、おそらくストーリー上関連している靴への関税が大幅に引き下げられたのはそのタイミングだったのだろう。ちなみに、関税は120%から20%に引き下げられた。これでは商売にならないと考えたカランは潔くこのビジネスから足を洗い、新天地の米国へ旅立ったのである。
このひとつめのアイデアは時代を反映していてなかなか面白かったのだが、それ以後のアイデアと商売は現実感が希薄であった。次に取り掛かったのは革手袋の輸入。靴と同様に両方ないと価値がないという特殊性を使ったアイデアだったが、ここまで来ると詐欺である。まずはカランとブルブルが米国大手の手袋輸入企業の社長チャーリーから最安値で受注を取り付け、信頼を築く。チャーリーから大量注文を受けたことで行動開始。受注量の2倍を輸入し、片手のみの手袋をペアにしてチャーリーに納入し、金だけ受け取ってトンズラする。次にジンが中国人の振りをしてチャーリーを訪ね、片方のみの手袋を半額で買い取る。最後にチャーンドゥーが出て行って、両方の手袋を合わせてチャーリーに売りつける。カランは、しっかり品物をチェックしなかったチャーリーが悪いと弁明するが、詐欺であることには変わりない。その次にカランが思い付いたのは不動産を使った詐欺。まずはブルブルがローンを使って家を購入する。そしてすぐにその家を2倍の価格で売り出す。その家をジンがローンを使って購入し、その金の半分を使ってローンを返却した後、またすぐに2倍の価格で売り出す。このように仲間内で値段を倍々につり上げて行き、ローンの返済額を除いた差額を懐に入れて行くのである。最後にローンが返済し切れなくなって家は差し押さえになるが、その家の価値は元々売り出されていただけの価格程度しかなく、痛くもかゆくもないという訳である。しかし、現実にこのような詐欺がうまく行くとは思えない。
最後のアイデアは逆転の発想があってまあまあ面白かった。インド製の衣服で品質の悪いものは色落ちが激しいのだが、その色落ちの激しさを新技術として定義し直し、洗濯するごとに色が変化するYシャツとして売り出すのである。それだけでなく、当時存命中だったマイケル・ジャクソンを勝手に広告塔にしてしまうしたたかさも発揮した。米国人がこんな子供だましのアイデアに騙されるほど単純だとは思えないが、これは誰かを騙して金儲けをするような性格のものではなく、欠点を長所に変えて売り出す広告戦略であり、その点で、頭脳を正しく使うことを奨励するストーリーに適合していた。
以上のアイデアが象徴するように、ストーリーの出だしは好調なのだが、米国に渡ってからは単調な展開となる。ここまでカランのキャラクタースケッチや4人の主人公の人間関係の描写も十分ではなく、そのせいでカランの豹変や、仲間が1人また1人とカランのもとから去って行くシーンが唐突に感じられる。再び仲間と結集して返品された大量のYシャツを売り出す終盤の山場は何とかまとめられたという感じだ。後味が悪くならなかっただけでも合格点だと言える。総合的には佳作ぐらいの評価になるだろう。
主演のシャーヒド・カプールは堅実な演技で安定感があった。ヒロインのアヌシュカー・シャルマーは、デビュー作「Rab Ne Bana Di Jodi」とは打って変わって今回かなり大胆な衣装を身に付け、しかも勝ち気なチョイ悪女を演じており、大きなイメージチェンジとなっている。女優のトップまで登り詰めるほどのオーラは感じないが、女優としての成長は十分見られるため、このまま業界に定着して行けるかもしれない。チャーンドゥーを演じたヴィール・ダースは「Love
Aaj Kal」(2009年)などへの出演経歴があるようだが記憶にない。根が優しげな顔をしているため、今回のような小悪党の役は荷が重かったように感じた。ジンに暴力を振るわれたリンダを気遣うシーンがもっとも彼自身の人間性をよく表していたと感じた。
ジンを演じた中国人俳優のメイヤン・チャンは、もし台詞を自分の声でしゃべっていたとしたら、十分にヒンディー語がうまく、ヒンディー語映画俳優として実用レベルであった。ジャールカンド州生まれのようなので、ヒンディー語がネイティブレベルであってもおかしくはない。彼が演じるジンは劇中で何度も「中国人」と揶揄されていたが、設定はスィッキム人である。インド東北部に主に住む、東洋系の顔をした人々は、通常のインド人から「チーニー(中国人)」と呼ばれ、まるで外国人であるかのように差別を受けることが多いが、ジンは自分がインド人であることを誇りに思っており、「インド」の名を冠したバーも開いていた。ボリウッドには、ダニー・デンゾンパやケリー・ドルジと言った、いわゆる東洋人系の顔をした俳優が少しだけ存在するものの、インド映画にメイヤン・チャンのような典型的な中国人顔をした俳優がおおっぴらに出て来ることは非常に珍しい。今回、彼が主人公4人の中に選ばれ、スィッキム人の立場からアイデンティティーに関する発言をいくつかしたことで、インドの中の「非インド系インド人」の存在が自ずからクローズアップされることになり、珍しい効果を生んでいた。昨今のインド映画で同様の問題に触れたのは、「Chak
De! India」(2010年)くらいであろう。メイヤン・チャンが今後インド映画界の中で独自の地位を築いて行けば、面白いことが起こりそうだ。しかし、普通に考えたら、風貌が明らかに他の俳優と違うので、インド映画の枠組みの中では使い所の難しい俳優であろう。
他に、アヌパム・ケールが地味ながらも重要な役で出演しており、この映画の本質的メッセージを観客に伝えていた。「マイケル・ジャクソン」が2回出演し、2回目では伝説的なムーン・ウォークも披露していたが、当然本人ではなく、どこかからそっくりさんを連れて来たのであろう。
音楽はプリータム。彼らしいキャッチーな曲が多かったが、家に持って帰りたいようなレベルの良曲はなく、全て使い捨てのように感じた。音楽の弱さもこの映画の弱点のひとつに数えられるだろう。
時代背景についてはほとんど上で触れたが、もうひとつこの映画で時代を感じさせるものは固定電話であった。90年代という設定で、携帯電話は「サイエンス・フィクションの世界」であったため、人物間の連絡は家庭用電話や公衆電話などの固定電話で行われる。カランが、女子寮に住んでいたブルブルに電話をする際も、彼女の個人用電話番号はなく、寮の電話に掛けるしかなかった。カランはお父さんを装ってブルブルを呼び出し、ブルブルも「お父さん」と呼びかけながら応答するのである。こういうシーンに懐かしさも感じるのだが、同時に、既に90年代が時代劇のような扱いになっていることに、時の流れの早さをひしひしと感じさせられた。
ちなみに、劇中ではムンバイーがボンベイと呼ばれていたが、ボンベイがムンバイーに変更されたのは1995年のことである。ボンベイという地名を毛嫌いする極右政党シヴ・セーナーへの当てつけのように、「1994年ムンバイー、おっと、この頃はまだボンベイだった」とナレーションが入っていた。
「Badmaash Company」は、90年代を舞台に、4人の若者がアイデアひとつで手っ取り早く金儲けをする物語である。だが、結局は真面目に働くことの価値が主張されており、「インド映画の良心」を地で行く娯楽映画となっていた。ストーリーや展開に弱さもあるが、つまらない映画ではない。インド生まれの中国人俳優がかなり重要な役で出演していることも珍しく、注目して然るべきであろう。
| ◆ |
5月9日(日) It's A Wonderful Afterlife |
◆ |
海外を拠点とするインド人女性映画監督は現在主に3人いる。ニューヨーク在住のミーラー・ナーイル、カナダ在住のディーパー・メヘター、ロンドン在住のグリンダル・チャッダーである。あまり好き嫌いで映画監督を評価していないが、今まで見て来た彼女たちの作品を基準に自分の中での高評価順に並べると、上記の順になる。グリンダル・チャッダー監督は、代表作「Bend
It Like Beckham」(2002年)が「ベッカムに恋して」の邦題と共に日本で公開されたこともあり、日本でも一定の知名度がある監督ではあるが、彼女の作る映画にはインド映画らしさがあまり感じられず、何か不気味な波動を受け取ることが多いのである。彼女は、英国のインド人コミュニティーを題材にした映画を作り続けているのだが、そのことをインド映画らしさの欠如としている訳ではない。インド映画らしさというのは端的に言えば社会の枠組みを守ろうとする保守的な価値観である。NRI(在外インド人)を主題にした映画では、インド文化の束縛からの解放か、インド文化の美点の再確認とそれへの回帰か、どちらかが主題となることが多いのだが、チャッダー監督の映画は極端に前者に偏っている。チャッダー監督の映画では、インド人女性と白人男性の国際結婚を積極的に推奨するようなメッセージが受け止められ、他の一般のインド映画にはないラディカルさがある。もし英国で彼女の映画を見たら違った感想を持つかもしれないが、インドの地において彼女の映画を見ると、インドの文化を蹂躙されているような、何とも言えない不快感を感じるのである。それは単にインドかぶれの外国人の偏愛に満ちた視点なのかもしれないが、おそらくそれがチャッダー監督の映画を個人的にもっとも低評価する原因になっているのではないかと思う。
今週からグリンダル・チャッダー監督の最新作「It's A Wonderful Afterlife」が公開された。英国では既に4月21日に公開されているが、評価は良くないようだ。インドでは、英語版とヒンディー語版が公開されている。英語版の題名は「It's
A Wonderful Afterlife」だが、ヒンディー語版は「Hai Marjawaan(ああ、死んでしまう)」になっている。英語版とヒンディー語版の同時公開は、チャッダー監督の前作「Bride
& Prejudice / Balle Balle! Amritsar to L.A.」(2004年)でも試行された試みだが、当時はヒンディー語版の制作を予め予定していなかったようで、不都合もあったようだ。今回は最初からヒンディー語版の制作も計画に組み込んで制作したため、どちらを見ても満足行く仕上がりになっているとのことである。どちらを見ようか迷ったが、「国際版」とも言える「It's
A Wonderful Afterlife」でこの映画を評価することに決めた。
題名:It's A Wonderful Afterlife
読み:イッツ・ア・ワンダフル・アフタライフ
意味:死後は素晴らしい
邦題:死後もワンダフル
監督:グリンダル・チャッダー
制作:シャラン・カプール
出演:シャバーナー・アーズミー、ゾーイ・ワナメイカー、ジミー・ミストリー、サリー・ホーキンス、センディル・ラーマムールティ、ゴールディー・ノーティー、マーク・アッディー、サンジーヴ・バースカル
備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。

左から、センディル・ラーマムールティ、ゴールディー・ノーティー、
シャバーナー・アーズミー
| あらすじ |
ロンドンのアジア人街サウスオールで、インド料理やインド料理用調理器具でインド系の人々が次々と殺される奇妙な連続殺人事件が起こっていた。ロンドン警察サウスオール署に配属されたインド系警察官DSムールティ(センディル・ラーマムールティ)は「カレー連続殺人事件」の捜査を開始する。既に4人の被害者が出ていた。その中で偶然、旧知のセーティー夫人(シャバーナー・アーズミー)と出会う。
セーティー夫人は、夫を亡くし、2人の子供を抱えていた。弟の方はどうでもよかったが、心配の種だったのは姉のルーピー(ゴールディー・ノーティー)の結婚だった。セーティー夫人は何度も見合いをさせたが、ルーピーが太りすぎだったために誰も彼女と結婚しようとしなかった。セーティー夫人はとうとう頭に来て、ルーピーを拒絶した男やその家族を次々と殺して行ったのだった。そう、実はセーティー夫人がカレー・キラーだったのである。
ある日、セーティー夫人のもとに4人の幽霊が現れる。彼らは彼女に殺された人々であった。だが、セーティー夫人は「ルーピーを拒絶したあんたたちが悪い」と物怖じしなかった。幽霊たちはいつまでも幽霊でいられないため、早く成仏して輪廻転生したかった。だが、殺された人の魂は、殺した人が死ぬまでは成仏できないようであった。幽霊たちはセーティー夫人に自殺を促す。一旦は自殺を決めたセーティー夫人だったが、考え直し、娘を結婚させるまでは死ねないと言い出す。そこで幽霊たちはルーピーの婿探しに協力することになる。
警察の捜査が進む中で、殺された4人のインド人がルーピーとお見合いをした人、またはお見合いをした人の家族であることが分かり、ルーピーが容疑者として浮上する。そうこうしている内に手違いでセーティー家の隣に住むゴールドマン夫人(ゾーイ・ワナメイカー)が、セーティー夫人が自殺しようとして作った毒入り団子を食べて死んでしまった。ますますルーピーに疑惑がかかる。ムールティは、ルーピーの嫌疑を晴らすために彼女に近付き、やがて付き合うようになる。ムールティは、ルーピーの言動に怪しさを感じず、彼女は犯人ではないと考える。また、ゴールドマン夫人も幽霊となってルーピーの婿探しに協力することになる。
ところで、ルーピーにはリンダ(サリー・ホーキンス)という親友がいた。リンダはインドに旅行してインドかぶれになってしまっており、ギーターリーと改名までしてしまった。しかも、前世からの縁があるというデーヴ(ジミー・ミストリー)というインド人男性と電撃結婚を決める。ところが、リンダとデーヴの婚約式において、デーヴは突如ルーピーに「実は君のことが好きになってしまった」と告白する。また、ルーピーはムールティが自分をスパイしていたことを知ってしまう。これらの混乱の中で、常々霊感があったリンダは、大麻のパコーラー(天ぷら)を食べてその力を増幅させ、デーヴの裏切りによって驚異的な超能力を発揮し、会場をカレーまみれにしてしまう。
後日、ムールティは改めてルーピーの家と訪れ、彼女にプロポーズする。だが、ルーピーはまだ怒っており、それを拒絶する。ムールティの上司スミス(マーク・アッディー)はその様子を物陰からうかがっていたのだが、セーティー夫人に見つかってしまう。スミスは足を滑らせてセーティー夫人が構えていたハサミに突き刺さってしまい、絶命する。セーティー夫人はルーピーに、ムールティは彼女をスパイしていたのではなく、彼女の嫌疑を晴らそうとしていたのだと説得する。ルーピーはムールティを追いかけ、プロポーズを受け容れる。
ルーピーとムールティの結婚式の日、セーティー夫人は倒れる。実はセーティー夫人は癌に冒されており、もはや死期が迫っていた。セーティー夫人は、家族と幽霊に見守られながら息を引き取る。そして魂となった彼女は、幽霊たちと共に天に召される。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
今まで見て来たチャッダー監督の作品の中で、初めて高く評価できる映画であった。「結婚」というインド映画の王道をテーマにしているが、普通の映画と違うのは、年頃の娘を抱えた母親が主人公であることと、娘が美人ではないことである。インド映画では散々結婚をテーマにした映画が作られ続けているが、ほとんどの場合、花嫁となるべきヒロインは絶世の美女である。少なくとも美貌の欠如が理由でお見合いや結婚が破談になるようなことはありえないと言っていい。だが、全ての女性が絶世の美女という訳ではないし、はっきり言ってしまえば、美人ではない人の方が多いのである。母親としては、そういう娘も何とか嫁に出さなければならず、頭を悩ます訳である。そのような現実を見据えた上でストーリーが構築されており、インド人コミュニティーの正直な現状が描写されていて、他の「結婚」映画とは一線を画していた。
しかし、現実的なのはここまでで、ここからはファンタジーとなる。何しろ幽霊が出て来るのである。しかし、ホラー映画的な世にも恐ろしい幽霊ではなく、あくまで人間味のある幽霊だ。そもそもインド人の幽霊である。生のインド人と接していても、こんな考え方をするのか、と感心してしまうことが多い。死んだインド人なら、もっと突拍子もない行動や考え方をしてもおかしくはない。ホラー映画では、誰かに殺された幽霊が、自分を殺した人に「恨めしや」と復讐をするのが常識となっているが、この映画を見ると、こんな幽霊もいるかもしれないな、いや、むしろこっちの方が普通かもしれない、と思わせられてしまう。「It's
A Wonderful Afterlife」の幽霊は、恐ろしくプラクティカルな考え方を持っている。死んでしまったのだから、今から誰かを道連れにしたりしても仕方ないと考えている。そしていかにもインド人的に輪廻転生の信仰を持っており、早く幽霊姿を捨てて転生したいと考えている。ところが、成仏するには殺人者の死を待たなければならない。もし殺人犯が逮捕されてしまったら、死刑が廃止されている英国では死が延期されてしまう。だからそれだけは避けなければならない。しかも、来世でよりよい人生を送りたかったら、果報を積まなければならない。ここで自分を殺したセーティー夫人の娘の花婿探しに協力すれば、いいポイント稼ぎになる。そんな訳で、幽霊たちはセーティー夫人の協力者となるのである。
しかし、幽霊たちが具体的にセーティー夫人を助けるシーンは非常に限られている。彼らは口々に言いたいことを言ってばかりで、あまりセーティー夫人の助けにはなっていない。幽霊のおかげで助かったシーンと言えば、セーティー夫人が警察の尋問を受ける場面だ。セーティー夫人も取り調べを受けるのだが、幽霊たちがいろいろアドバイスをくれたおかげで、パーフェクトに答弁することができ、アリバイを証明することに成功する。幽霊が、自分を殺した殺人犯が警察に逮捕されるのを避けるために、必死に協力するというのがこの映画の最大のコメディーになっていると言っていいだろう。もし世の中(外?)が本当にこんな構造になっているとしたら、犯罪の中でももっとも重い罪である「殺人」を巡って奔走する警察や司法は滑稽な存在でしかなくなる。それでも、幽霊がルーピーの「婚活」において大して重要な役割を果たしていないことで、結局幽霊が出て来なくてもこの映画は成り立ったのではないかという疑念も生じる。また、幽霊をコミカルに登場させてしまったことで、個人的な理由で次々に人を殺したセーティー夫人が全く罰を受けていないことになり、道義的に心にしこりが残る展開でもある。基本はコメディー映画ではあるが、心地よく笑うことができない映画になっていた。腹からカレーが噴出したり、婚約式会場がカレーだらけになったりと、食べ物を粗末にするようなグロテスクなシーンもあった。
主演はシャバーナー・アーズミーである。彼女のイメージは常に凛とした強い女性という感じなのだが、今回は体重を増やし、思いっきり老けメイクで、どこにでもいそうな心配性のお母さんという大胆なイメージチェンジをしていた。それでもやっぱりうまい女優であり、好演であった。他には英国で活躍している俳優ばかりで、ほとんど面識がないのだが、ルーピー役のゴールディー・ノーティー、ムールティ役のセンディル・ラーマムールティなどの演技に欠点は見られなかった。
上映時間は100分ほどで、インド映画レベルからしたらかなり短い映画なのだが、音楽も多数使われていた。英国で活躍するインド系ミュージシャンの楽曲が多く、パンジャービーMC、ステレオ・ネイションのターズ、バリー・サグーなどが参加している。
英語版「It's A Wonderful Afterlife」はほとんどの台詞が英語であった。ヒンディー語やパンジャービー語なども少しだけ聞こえて来たが、ほとんど誤差のレベルである。英語のみで全体を理解できるだろう。チャッダー監督のインタビューでは、インド人の間の台詞はヒンディー語版「Hai
Marjawaan」の方が生き生きとしたものになっているとのことである。
「It's A Wonderful Afterlife」は、「結婚」がテーマのNRI映画ではあるが、その一言解説から想像される映画とは全く違う出来となっている。この映画では、コメディータッチのストーリーの中で「死」があまり重いものと受け止められておらず、インド人独特の死生観の片鱗がうかがわれ、面白い。だが、やはり真面目に考えたら、死を茶化しすぎな部分もあり、そこで評価が分かれるかもしれない。食べ物関連のグロテスクなシーンもあり、注意が必要だ。それでも、チャッダー監督の今までの作品の中では一番共感できる映画であった。
| ◆ |
5月16日(日) チャッティースガリー映画 |
◆ |
今年4月にインド中を震撼させる事件が起こった。チャッティースガル州ダンテーワーラー県においてマオイストの殲滅作戦に従事していたCRPF(中央予備警察部隊)が、マオイストの奇襲に遭い、部隊の9割以上に当たる76人が死亡した。マオイストはインド共産党毛沢東主義派とか、ナクサライトとか呼ばれる極左組織で、西ベンガル州、ジャールカンド州、チャッティースガル州などの密林地帯を支配し、インドの国内安全保障の最大の脅威となっている。Pチダンバラム内相は、マオイストを一網打尽にするためにオペレーション・グリーンハントを主導しているが、このダンテーワーラー事件での被害は敗戦を意味するほど大きく、同内相は辞表提出を余儀なくされた。もっとも辞表は受理されなかった。
チャッティースガル州には一度旅行したことがある。旅行する前は憧れの地のひとつであり、実際に旅行してみたらけっこう気に入った場所であるので、チャッティースガル州関連のニュースには特に目を奪われてしまう。ダンテーワーラー事件のおかげでチャッティースガル州はマオイストの脅威にさらされた危険な地域という認識が余計に広まってしまったように思うが、州都ラーイプル周辺はごく普通のインドの雰囲気であるだけでなく、マハーラーシュトラ州東部の中心都市ナーグプルから、西ベンガル州州都コールカーター、オリシャー(旧名オリッサ)州州都ブバネーシュワル、アーンドラ・プラデーシュ州東岸地区中心都市ヴィシャーカパトナムの3都市を結ぶ幹線上に位置しており、実はかなり開けた場所である。しかし、この幹線を外れるとかなりの田舎であることは否めない。
チャッティースガル州のマオイストの牙城となっているのが、州南部を覆うバスタル県とダンテーワーラー県である。実はチャッティースガル観光で一番の見所もこのエリアであり、自然と部族と手工芸品の宝庫になっている。僕もチャッティースガル州旅行の際はこちらにも足を伸ばした。ラーイプルからこの地域に向かうと、途中で急な坂を上ることになり、標高が500mほど上がる。意外に涼しくて驚いた覚えがある。バスタル県の県都ジャグダルプルや、ラーイプルからの幹線は何ともないが、それらを外れて森林を探検しようとすると非常に困難である。バスは1日1便、2便のレベルだし、タクシードライバーはマオイストを恐れて森の中へ行こうとしない。それでも、バスを乗り継いでダンテーワーラー県の県都ダンテーワーラーまでは行った。マオイストに出くわすことはなかったが、インドにしては人口過疎気味で、寂しげな雰囲気の地域であったのを思い出す。道も所々とても悪かった。
ジャグダルプルからは、マオイスト影響下の森林地帯を通り抜けてアーンドラ・プラデーシュ州の州都ハイダラーバードまで抜ける道がある。マディヤ・プラデーシュ州方面からチャッティースガル州に入った僕は、この道を通ってハイダラーバードまで出ようとしたが、ちょうど移動前日にハイダラーバード行きのバスがマオイストに捕まって燃やされ、たまたま乗っていた警官が殺害されるという事件があり、バスの運行が停止してしまった。仕方がないのでオリッサ州へ抜ける道を取って旅を続けたが、抜けた先のオリッサ州西部も、特徴的な外見をした部族のひしめくエリアで、面白かった覚えがある。
チャッティースガル州は一応ヒンディー語圏になっており、ヒンディー語が通じるが、この地域の人々が話す言語には特にチャッティースガリー方言という名前が付いている。ラーイプルで見た看板に、「チャッティースガリヤー、サブレー・バリヤー(チャッティースガル人は一番素晴らしい)」という方言丸出しのキャッチフレーズが載っていて思わず笑みがこぼれたのを覚えている。オリヤー語に近い言葉遣いになっていると言える。
全く知らなかったのだが、本日付のタイムズ・オブ・インディア紙によると、チャッティースガル州でもローカル映画が制作されており、結構な人気を博す作品もあるようである。ヒンディー語、ベンガリー語、マラーティー語、テルグ語、タミル語、マラヤーラム語などをメジャーな言語の映画とするならば、インドにはそれらの他にもマイナー言語の映画がコンスタントに作られており、うまく様々な要素が噛み合うと、大ヒットを記録する。マイナー言語映画には、ヒンディー語の方言とされる言語による映画の数が多く、その中でも最大勢力を誇るボージプリー方言の映画については、「これでインディア」でも以前に取り上げたことがある(参照)。今回はチャッティースガリー映画について取り上げることにする。
記事によると、史上初のチャッティースガリー映画は1965年に公開された「Kahi Debe Sandesh(メッセージを伝えよ)」であるらしい。カースト間恋愛をテーマにした意欲作で、インディラー・ガーンディー首相(当時)も鑑賞したと伝えられている。チャッティースガリー方言の第2作は1971年公開の「Ghar
Dwar(家々)」。どちらも台詞はチャッティースガリー方言であるが、どちらも興行的には失敗に終わり、以後、チャッティースガリー映画に手を出そうとする者はしばらく現れなかった。
チャッティースガリー映画が再び盛り返したのは21世紀に入ってからである。バスタル生まれのサティーシュ・ジャインは、ボリウッドで人気男優ゴーヴィンダーと組み、「Dulara」(1994年)、「Pardesi
Babu」(1998年)、「Rajaji」(1999年)、「Hadh Kar Di Apne」(2000年)などのストーリーを書いてきたが、ゴーヴィンダーとコンビ解消してからは地元に戻り、チャッティースガリー映画の可能性を模索することになった。しかし、誰も興味を示す者がいなかったために、プロデューサー、監督、資金集め、配給など、全て自分でやらなくてはならなかった。プレイバックシンガーが見つからなかったため、弟のティークーが歌を歌うことになった。こうして2000年10月27日に公開されたのが、「Mor
Chhaihan Bhuinya(私の影と地)」であった。
ところで、チャッティースガル州は新しく出来た州で、以前はマディヤ・プラデーシュ州の一部であった。サティーシュ・ジャインがチャッティースガリー映画を作っていたのも、まだチャッティースガル州が出来る前であった。ところが「Mor
Chhaihan Bhuinya」が公開されて3日後、アタル・ビハーリー・ヴァージペーイー首相(当時)が突然チャッティースガル州の新設を宣言した。このニュースに歓喜したチャッティースガルの人々は、愛郷精神に突き動かされ、久々に公開されたチャッティースガリー映画に殺到した。こうして、予算わずか200万ルピーで制作されたこの映画は、2,500万ルピーを稼ぎ出す大ヒットとなった。ラーイプルのバーブーラール劇場では27週連続で公開されたと言う。この大成功によりチャッティースガル州の映画産業は一気に盛り上がり、2001年以来、少なくとも60本のチャッティースガリー映画が制作された。だが、金目当ての素人プロデューサーが多かったために、興行的に成功する作品は少なかったようだ。ヒット作としては、前述の「Mor
Chhaihan Bhuinya」の他に、「Maya De De Maya Le Le(愛をくれ、愛をあげよう)」(2003年)や「Jhan
Bhoolo Ma Baapla(両親を忘れるな)」(2004年)などの名前が挙がっている。トップスターはアヌジ・シャルマーという名の男優で、演技と歌の両方をこなし、ギャラは1作50万ルピーほどのようである。しかし、チャッティースガリー映画にはボリウッド映画の安易なリメイクも多く、剽窃の疑いで訴訟に巻き込まれることもある。2009年には「Maya(愛)」というチャッティースガリー映画初のデジタル映画が公開され大ヒットを飛ばしたが、これはボリウッド映画「Swarg
Se Sundar」(1986年)の完全なリメイクであり、裁判沙汰になった。しかし、安価に映画が制作できるデジタル映画は、ローカル映画産業にとってありがたい新技術で、今後デジタル映画フォーマットのローカル映画が多数作られて行く様子だと言う。ボリウッドにもデジタル映画の波は到達しており、今年初めにボリウッド初のデジタル映画「Love
Sex and Dhokha」が公開された。ボリウッドにおいては、デジタル映画は完全にマルチプレックス向けの実験的映画を後押ししている。
チャッティースガリー映画の隆盛をざっと観察すると、その様子はボージプリー映画のそれと非常によく似ている。ボージプリー映画も60年代~70年代にかけて一時的に盛り上がりを見せるが、本当に脚光を浴びることになったのは21世紀に入ってからである。これは、マルチプレックス文化の普及とグローバル化の影響で、ヒンディー語映画が都市中産階級や海外在住インド人の嗜好に合う映画を好んで作るようになり、地方の観客がメインストリームから取り残されたことに起因すると見ていいだろう。インド映画はよく「マサーラー映画」と形容されるが、最近のヒンディー語映画で「マサーラー映画」を標榜できる作品は非常に少なくなってしまった。インド味のハリウッド映画みたいな映画が多く、ある程度教養がないと面白さが理解出来ないような作品も少なくない。英語の台詞が多用されることも最近かなり増えた。完全に大都市在住のインド人をターゲットにしており、それ以外はほとんど眼中に入っていない。一方、地方の観客が見たいのは、笑いあり、涙あり、アクションあり、スリルありの、昔ながらの分かりやすい娯楽映画であり、その需要を、各地域の観客層が日常的に使用している方言や見慣れたロケーションと共に吸い上げることに成功したのが各ローカル映画だと言える。
ボージプリー映画やチャッティースガリー映画の他にも、ヒンディー語圏で様々なローカル映画産業が育っている。ウッタル・プラデーシュ州のメーラトではカリー・ボーリー方言による映画が作られており、「Dhakad
Chhora」(2004年)が大ヒットとなっている。だが、ハンディカムで撮影されている上に主な販路はVCDで、アマチュアレベルのようだ。ウッタラーカンド州でも、ガルワール地方やクマーオーン地方で映画が作られているが、やはりカリー・ボーリー映画と似たような状況で、映画館よりもVCDでの販売が主な資金回収源となっているようである。ヒンディー語ではないが、最近ホットなのがラダッキー映画である。制作者はタクシードライバー、僧侶、主婦など、全くの素人だが、ここ8年でおよそ30本のラダッキー映画が制作されており、最大ヒット作は「Delwa」(2005年)となっている。
かつてトーキー映画の普及により、インドでは映画の言語別生産と映画産業の分散が進んだ。2000年代のマルチプレックス革命はトーキー映画以来、映画という媒体に大きな影響を及ぼした事件だと考えていたが、2010年代にはマルチプレックスに加えてデジタル映画が新たなキーワードとして浮上しつつあるように感じる。マルチプレックスの普及により、ヒンディー語映画界では国際的なアピール力のある多様なジャンルの映画が作られるようになったが、同時に単純な娯楽を求める地方の観客層が切り捨てられることになり、ローカル映画産業の勃興と、都市と地方の格差も生んだ。デジタル映画の普及はインドではハリウッドに比べて10年遅れているが、安価に映画制作ができるため、今後さらにヒンディー語映画の多様化を推し進め、ローカル映画産業の低予算映画を助けて行くことになるだろう。デジタル方式の映画制作法により、一方で「Love
Sex aud Dhokha」のような前衛的な映画がマルチプレックス層向けに作られて行くだろうし、他方で「Maya」のようなローカル映画が地方の観客層向けに作られて行くだろう。デジタル映画の切り札は3Dデジタル映画である。インドでもジェームズ・キャメロン監督の「アバター」(2009年)が大ヒットし、俄に3Dデジタル映画ブームが到来している。ちょうど現在、インド初の3Dデジタルアニメーション映画「Bal
Hanuman 2」が公開中で、今後も続々とインド製3D映画が登場する予定だ。しかし、3Dデジタル映画の需要増によって、インドのアウトソーシング産業が恩恵を被ることはあるだろうが、インド映画産業への影響はまだ限定的なように思われる。むしろデジタル技術自体の普及がインド映画産業を変えて行くだろう。

今回のツーリングは、元々「マナーリー・レー・ツーリング」のつもりで企画・実行したのだが、諸事情により途中で旅程変更せざるをえなくなり、結果的に「ラーハウル・ツーリング」と題することになった。それを念頭に置いて読んでいただきたい。
僕のインド滞在時間もおそらくあと1年ほどである。もし今のままの状態で1年が過ぎ去ったとして、何かインドでやり残してしまったと考えることはないかと想像した場合、ひとつの大冒険が真っ先に思い浮かぶことになるだろう。それはマナーリーからレーまでのツーリングである。マナーリーはヒマーチャル・プラデーシュ州にある山間の避暑地で、レーはジャンムー&カシュミール州ラダック地方の主都、「インドのチベット」の中心地である。マナーリーからレーまでバイクで走破するのは、インドのバイク野郎たちの共通の夢である。と同時に、地球上でもっとも困難なツーリングルートでもある。標高4,000m級、5,000m級の峠をいくつも越え、全475kmの内の365kmをガソリン無補給で走破しなければならない。道中、悪天候、高山病、バイクの故障、ガス欠など、様々な困難に直面することは必至で、全ての挑戦者が走破できる訳ではない。
2007年6月に、やはり難関とされるキンナウル・スピティ周回ツーリングを成功させて以来、いよいよ次はマナーリー・レー・ツーリングに挑戦するときが来たと考えていた。しかし、タイミングの問題や、バイクの老朽化の問題などがあり、なかなか実行に移せなかった。バイクは購入から既に5年が経っており、あちこちにガタが来ていた。しかし、最近思い切ってエンジンをオーバーホールしたところ、満足な走りが出来るようになり、次々と寿命を迎えつつあった消耗品類も一通り交換が済んで、遠出しても問題ない状態になったように感じた。また、妻が現在出産のために一時帰国中で、マナーリー・レー・ツーリングに適した時期に単独自由行動を行えるチャンスが得られた。そもそも子供が生まれたらもうこんな馬鹿な冒険は出来なくなってしまう。いろいろな状況を考え合わせると、今年がこのツーリングに挑戦するおそらく最後のチャンスであることは明らかであった。やって後悔する方がやらなくて後悔するよりもマシである。4月頃から徐々にマナーリー・レー・ツーリングの計画を立て始めた。
ところで、マナーリー~レーのルートは1年中通行できる訳ではない。1年の大半は雪で閉ざされており、夏の一時期のみ通行が可能となる。前述の通り、マナーリー~レー間にはいくつもの峠が立ちはだかっているのだが、ルート開通と関係しているのはロータン峠(Rohthang
La; 標高3,978m)とバララチャ峠(Baralacha La; 標高4,891m)である。この2つが開けば、大体の場合マナーリーからレーまで行くことが出来る。キンナウル・スピティ周回ツーリングのときにお世話になった、夏季マナーリー在住、山荘「風来坊」経営の日本人、森田さんに峠の開通状況を確認したところ、5月中旬の段階でロータン峠は開通していたが、バララチャ峠はまだとのことであった。5月16日頃を出発予定日としていたのだが、少しだけ先延ばしにすることにした。
森田さんにはデリーからマナーリーまでのルートについてもいろいろ指南をいただいた。デリーからマナーリーへ行くには、アンバーラー~ビラースプル~マンディー~クッルーを経由してマナーリーにアプローチするのが一般的なルートであり、もっとも早く快適だが、シムラー経由で行く別の道もいくつか存在する。その内、もっとも遠回りではあるが、もっとも冒険に富んだルートとなっているのが、ジャローリー峠(Jalori
Jot; 標高3,223m)を越えるルートである。しかも、今の季節がジャローリー峠のもっとも美しい時期で、ツーリング先としては最適だと言う。バララチャ峠の開通を待つ間、このルートを通って峠越えの練習をしようと考えた。もしかしたらバララチャ峠の開通が遅れて、手ぶらで帰ることになるかもしれないので、このツーリングの中で少なくとも何か新しいことに挑戦しておきたいという気持ちもあった。
早朝に出ればデリーからジャローリー峠に直行することも可能であろうが、高山病を避けるための高地順応も兼ねて、ジャローリー峠の手前のどこか標高が高めの場所に1泊することを考えた。いくつか候補はあったが、ロンリープラネットにも情報が載っているナールカンダー(Narkanda;
標高2,708m)を宿泊地に定めた。ナールカンダーは冬の間スキーリゾートになる場所らしいが、もうそのシーズンではない。
マナーリー~レーの道に関する情報収集や、マナーリーまでのルート決めをすると同時に、この地球上でもっとも困難なツーリングルートの成功率を少しでも上げるため、バイクの装備向上にも着手した。キンナウル・スピティ周回ツーリングのときは現地調達がモットーの行き当たりばったりの旅行で、今思い返せばよくあんな無防備なツーリングが出来たものだと呆れるが、今回はさすがに念入りに準備をした。まずは輸送量を増やす必要があった。今回、摂氏45度の平野部から、氷点下の高山まで、様々な気候帯に直面しなければならないため、各気候に対応した衣服を持っていなければならない。バイクの後部に装着するサイドバッグがあれば理想的であったが、インドでそんな気の利いたものが手に入るとは思っていなかった。しかし、ネットで調べてみたところ、バンガロールのCramsterという会社がいろいろツーリング用品を製造しており、サイドバッグもあることが判明した。そしてデリーにもCramster社製品の取扱店があった。サティヤ・ニケータンのAdventure 18というアドベンチャー用品店である。そこでカリズマにフィットするモデルを2,100ルピーで購入した。また、実は日本からもバイクの後部に積載できるツーリング用の防水ザックを買って来ていた。知る人ぞ知る、上野バイク街の象徴、光輪モータース(既に倒産)の商品である。今まで出番がなかったが、今回サイドバッグと併せて利用することにした。このザックの中には主に衣服類を入れた。構造的に錠を掛けられないので、盗まれても一番ダメージの少ないものを入れることにしたのである。また、普段デリーの町乗り時に利用している防水性のショルダーバッグ(Pacific Outdoor社製)も持って行くことにした。長距離移動時はショルダーバッグが重いと肩が疲れるので、ほとんど中に重い物は入れないが、レーなどで町乗りをするときのためにあった方が便利だと考えた。防水ザック以外にはダイヤル式南京錠をかけ、盗難防止にも努めた。
なまじっか輸送量が増えたために色気が出てしまって、今回はノートPC(A4型で結構重い)も持参することにした。ツーリング時は荷物を減らすためにノートPCを持参しないことが多いのだが、今回は長期ツーリングで、帰宅してから旅行記をまとめるのが面倒になる可能性もあったので、旅先で旅行記を書きながらツーリングをするスタイルを試すことにした。
最近バイクの調子は悪くないので、ツーリング中にエンジンが停止してしまうような深刻なトラブルはほとんどないだろうと予想された。一番怖いのは何と言ってもパンクである。もしマナーリー~レーの道でパンクしたら、ほとんど集落がないような地域なので、かなりピンチになる。そんなことを考えていたら、ツーリング出発予定日の数日前に前輪のタイヤがパンクしてしまい、顔面蒼白となった。早速ネットで検索。マナーリー~レーをバイクで走破する人々は、タイヤをどうしているのだろうか?チューブレスタイヤに交換するというオプションもあったが(インドの二輪車は未だにほとんどがチューブタイヤで、僕の乗る初期型カリズマも例外ではない)、もっとも推奨されていたのが、タフアップチューブに交換する方法である。タフアップチューブというのは、ホンダが開発した二輪車用の高性能チューブである。釘などが刺さってもチューブ内を巡る液体が即座に凝固して空気漏れを最小限に抑える優れ物だ。チューブレスタイヤと違って、修理方法も今までのチューブと同様で、僻地のメカニックでも十分に対応できる。実は後輪のタイヤには既にタフアップチューブを装着していた。以来、パンクになったことはなかった・・・と思ってよく確認してみたら、後輪のタイヤに1本の釘が刺さっていた!いつ刺さったのか分からないが、大した空気漏れはなく、今まで全く気付かずに乗っていた。タフアップチューブの威力を思い知った。これは是非とも前輪にもタフアップチューブを装着しなければならないと考え、まずはヒーロー・ホンダのサービスセンターに問い合わせてみたが、前輪用のタフアップチューブはないとのこと。それでも諦めきれなかったので、今度はホンダのショールームへ行って聞いてみたら、タフアップチューブを出してくれた(390ルピー)。多少サイズが大きめだが、前輪にも装着可能とのこと。早速前輪に装着し、足回りの不安を取り除いた。ただし、もちろんいかにタフアップチューブと言えど、パンクするときはパンクするので、おまじないみたいなものに過ぎないのだが・・・。
インドでは3ヶ月に1度、ガソリンスタンドなどに併設されているキオスクで排気ガスをチェックし、PUC(Pollution Under Cntrol)という証明書を発行してもらわなければならない。しばらく排気ガスチェックをしてなかったので、万全を期すために思い立ってチェックを受けてみたら、なぜか排気ガスの汚染度が許容範囲を越えていた。こんなことは初めてである。それでもPUCは出してもらえたが、通常より5ルピー上乗せされた。排気ガスが多いということはガソリンが無駄になっている可能性があり、念には念を入れて出発前日にメンテナンスに出した。これによって排気ガスの汚染度が減ったかどうかはわざわざ測らなかったが、バイクを万全の状態にすることが出来たのは良かった。排気ガスのことを言われなかったら、メンテナンスをせずにツーリングに出発していたこともあり得た。ちなみに、メンテナンスではセンタースタンドの老朽化が指摘されたため、それを交換した。
お金の準備も怠らなかった。十分な金額のお金を準備するのはもちろんのことであるが、それよりも密かに重要なのが、小額の紙幣を揃えることである。特に100ルピー札が鍵となる。田舎では500ルピー札や1000ルピー札は受け取ってもらえない。もっとも信頼性の高い高額紙幣が100ルピー札となる。100ルピー札100枚の札束を銀行で提供してもらって、お金の心配を絶った。
旅の参考資料としては、ロンリープラネット英語最新版やEICHER「Road Atlas India」の他、高木辛哉著「旅行人ウルトラガイド:ラダック」(旅行人、2001年初版)、Koko
Singh著「Driving Holidays in the Himalayas: Ladakh」(Rupa, 2006年初版)、「Indian
Himalaya Maps」(Leomann Maps)などを利用した。町や峠の標高については資料によってまちまちなのだが、基本的に「Indian
Himalaya Maps」のデータに準拠し、ロンリープラネットを補助的に参考にした。
他に、信心深い方ではないのだが、ツーリングの無事を祈るため、事前にハズラト・ニザームッディーン廟に参詣した。デリーに宗教施設は星の数ほどあるが、僕が効力を信じてるのは聖者ニザームッディーン・アウリヤーのダルガー(聖廟)である。現代風の言い方をすれば、デリー随一のパワースポットだ。きっとうまく行くだろう。
以上、前置きが長くなったが、つまりはかなり念入りに準備や下調べをしてツーリングに出発した訳である。最近はネットでもインド人が盛んに情報交換をしており、検索すればそのやりとりがヒットするため、とても参考になった。こういう前置きは、もしかしたら普通の人にとっては呆気なく読み飛ばされてしまうような代物かもしれなし、それならそれでいいのだが、同様にマナーリー・レー・ツーリングを計画している人にはとても参考になるだろうと考え、詳細に記録したものである。
元々5月16日をツーリング出発予定日と考えていた。その日はアクシャイ・トリティーヤという吉日であり、旅立ちに縁起が良いかと思ったのである。結婚式にも最適の日とされており、デリーだけでもこの日2万カップルが結婚式を挙げた。その吉日がなぜ吉日かと言うと、その日の行動は永遠に持続され、消滅しないとされているからである。結婚式に最適な日とされるのも、この日に結ばれた夫婦の絆は未来永劫維持されると考えられているからだ。しかし、逆にこの日に行った悪事もずっと残ってしまうことになる。だから1年の内でもっとも身を慎まなければならない日でもある。よって、ただの吉日とは言えない。アクシャイ・トリティーヤを旅立ちの日という観点から考えた場合、旅立ちという行動が永遠に続くことになってしまい、それはつまり帰らぬ旅ということになってしまわないかとふと怖くなった。もちろんそれだけが理由ではなく、峠の開通状況のことなどもあり、出発を2日延ばすことにした。
現在北インド平野部は日中摂氏40度以上の酷暑となっている。涼しい早朝になるべく平野部を駆け抜けて、日が高くなる頃には標高の高いところに辿り着いているのが理想的だ。本日の目的地ナールカンダーへ向かう上で、ヒマーラヤ山脈の玄関口となるのはカールカー(Kalka)である。デリーから距離にしておよそ260km。午前10時前にカールカーに到着するための出発時間を計算すると、午前5時にはデリーを出る必要がある。しかも僕の住んでいるのは南デリーであり、今回は北に向かうルートであるため、巨大なデリー市街地を通り抜ける時間も加味しなければならない。そうすると午前4時出発が最適という結論になった。結局、旅行前の興奮で早く目が覚めてしまい、準備も早く済んでしまったため、午前3時半に出発することになった。
アウターリング・ロードからマトゥラー・ロードを抜けてリング・ロードに出て、NH1(国道1号線)を目指した。この時間のデリーの幹線は大型トラックの支配下にある。大型トラックは夜間のみデリー市街地の通行を許可されているため、夜には大量のトラックがデリーに雪崩れ込む。まるで巨人の国に迷い込んだ小人の如くリング・ロードを走り抜け、30分ほどでNH1に出た。こちらの方面に足を伸ばすのは久し振りであったが、NH1とリング・ロードの交差点にフライオーバーが新設されており、便利になっていた。しかし、フライオーバーを抜けた先のNH1自体の工事がまだ進行中で、フライオーバー通過以降しばらく渋滞があった。それでもすぐに拡張工事済みの広い道路に出たため、後は快適な走行をすることが出来た。他にもデリー~アンバーラー間にはいくつか新しくフライオーバーが完成しており、途中の市街地を抜ける必要がなくなったため、格段にスムーズになった。午前5時半にパーニーパト、午前6時にカルナール、午前6時半にクルクシェートラの玄関口ピプリーを通過し、午前7時頃にアンバーラーに到着した。
アンバーラーからNH1を下りてシムラー方面へ向かうNH21、そしてNH22に乗らなければならない。この道は過去に2回バイクで通っているが、アンバーラーからチャンディーガルやシムラーへ抜けるフライオーバーや道路の工事がずっと行われており、その影響で、外部の者には分かりにくい道になっていた。しかしこのフライオーバーや道路も既に完成しており、道標に従って走行していれば迷うことなく目的地へ向かえるようになっていた。大きな進歩である。ただ、アンバーラーを越えるとまだ工事中の箇所が多く、道の状態は悪くなった。カールカーの麓にあるピンジャウル(Pinjore)に到着したのは午前8時頃。ここで一度給油すると同時に、道中の砂塵や排気ガスで顔が真っ黒になっていたので水で洗顔した。カールカーには午前10時到着を目標にしていたが、早めに出たことと、途中の道がスムーズになっていたことで、午前8時半には到着した。ピンジャウルから既にヒマーラヤ山脈が始まっており、上り坂となる。カールカーからは本格的な山道となっており、グングン標高を上げた。ありがたいことに今日は曇りがちの天気で、これまで暑いと感じたことはなかった。午前8時45分頃に道の途中にあったダーバー(安食堂)で朝食休憩を取り、午前9時に出発してシムラーを目指した。途中もう1回小休止を挟みながら、シムラーには午前11時頃に到着した。
ヒマーチャル・プラデーシュ州の州都シムラーは北インド随一の人気避暑地でもある。現在平地からの避暑客による大混雑が予想されたため、市街地を通らず、バイパスを通ってシムラーの向こう側に出ることにした。途中、本当にこの道でいいのかと不安になるような道であったが、最終的にはシムラーの向こう側に出ることに成功した。後はクフリー、ファグー、ティヨーグなどを通過してナールカンダーまで一直線だ。この道はNH22、そのままキンナウルを抜けてチベットまで通じているため、ヒンドゥスターン・チベット・ハイウェイとも呼ばれている。
デリーからカールカーまでの道も曇りがちだったが、カールカー以降も霞がかった天気で、残念ながら景観は良くなかった。もしかしてと思っていたが、途中から雨が降り始めてしまった。この道はキンナウル地方へ続く道で、キンナウル・スピティ周回ツーリングの時も通ったのだが、そのときも雨に見舞われた。雨の多いエリアなのだろうか?当時はレインコートすら持っていなかったのでかなり困り、しばらく民家の軒先で雨宿りしていたが、今回はレインコートを持参していたので、レインコートを着てしばらく走った。雨量も最初はそれほど恐れるに足るものではなかった。地域ごとに雨の強さが違ったのだが、先に進むごとに明らかに雨は強くなって行った。もう限界だ、と思ったときにダーバーを見つけたので、そこに転がり込んだ。ちょうど昼時でもあったため、そこで素朴なダール・チャーワル(豆カレーとご飯)を食べ、チャーイを飲んで身体を温めた。そのダーバーで30分以上雨宿りしていたのだが、途中で雹が降り出したりして深刻な天気になってしまった。しかし、聞いてみるとナールカンダーまであと少しだったので、雨が大体止んだ頃合いを見計らって出発し、ナールカンダーに急いだ。
ナールカンダーでは、ヒマーチャル・プラデーシュ州観光振興局経営のホテル・ハトゥ(Hotel Hatu)に宿泊した。シングルで1,800ルピー弱と安くはなかったが、山小屋風の雰囲気のいいホテルであることは事前の情報から知っていたし、再び土砂降りになっていたので、ここに泊まることにした。チェックイン後はとりあえず眠った。ナールカンダーはスキーリゾートと言われているが、冬期にどこにスキー場が現れるのかイマイチ分からなかった。標高は2,708mで、既に相当寒い。セーターは必須だ。まだ高山病の症状は出ていない。

ホテル・ハトゥ
暇を持て余したインド人宿泊客が駐車場でクリケットをしていた
ホテル・ハトゥのレストランではアップル・ワインという酒が売られていた。要は果実酒であろう。この地方の特産品のようである。通過した町の市場でも時々「アップル・ワイン」の看板を見た。ここでは1瓶225ルピー。レストランでもグラスでは提供されておらず、飲みたかったら1瓶丸ごと買わなくてはならなかった。荷物になるので試さなかったが、何となく気になる商品である。夕食にはチキン・ダールーというこの地方特産のチキンカレーを食べた。
本日の走行距離444.9km。ちなみにニュースによると今日のデリーの最高気温は史上最高の47.6度。今日出発して正解だったようだ。
昨日の午後は雨に悩まされたが、夕方には雨も上がり、遠くの景色もある程度見えるようになった。ところが深夜になるとものすごい嵐が断続的に吹き荒れ、目が覚めてしまった。谷を展望できる窓から外を見ると、雷が真横で光っていた。山の天気の変わりやすさ、恐ろしさを実感した。ホテルの駐車場に野ざらしで立っていたバイクのことが不安で仕方なかったが、翌朝見たらそのままの姿で立っていてホッとした。むしろ激しい雨のおかげで、洗車されたようにピカピカになっていた。朝には昨晩の雷雨が嘘だったかのように快晴の空が広がっていた。
既に午前6時には出発準備が整っていたのだが、レセプションに人がいなかったため待たされることになり、結局午前6時半の出発となった。今日はジャローリー峠(Jalori
Jot; 標高3,120m)を越えてマナーリーを目指す。
ナールカンダーの市街地を抜け、NH22を東に向かうとすぐにサトラジ谷の谷底まで続く下り坂が始まり、標高が下がり出す。しかし昨晩の雨の影響で空気がヒンヤリとしており、既に厚手のジャケットとセーターを着込まないとバイクを運転できないような気温であった。この辺りは鬱蒼としたデーオダル(ヒマラヤスギ)の森林となっており、遠くに雪を抱いた山が見え、谷底には怒濤のサトラジ河が流れており、自然の景観がとても美しいエリアである。ついつい要所要所でバイクを停めて写真を撮りたくなる。

サトラジ谷の光景
サトラジ河の河畔に位置するサインジ(標高1,372m)からNH22を下りると、1車線のみの狭い道となる。ここまではずっと2車線の広い舗装道であった。交通量が多くないので走行はスムーズだが、油断するとカーブで急に対向車が現れてヒヤリとする。ルフリー(Luhri;
標高792m)という町で橋を渡ってサトラジ河の対岸へ渡った。しばらくはサトラジ河の右岸を下流方向へ下る道になっていたが、途中から登坂道路となり、サトラジ河の支流を遡るルートとなった。緑豊かで河のせせらぎが心地よい、非常に美しい谷であった。途中、いくつもの集落を通過したが、アーニー(Anni;
標高1,240m)という町がもっとも大きかった。グングン標高を上げて行き、カナーグ(Khanag; 標高2,692m)という集落を過ぎると、いよいよジャローリー峠へ向かう7kmの困難な坂道が始まる。勾配がありえないほど急で、しかも冬期の凍結のせいか道路の状態が非常に悪いため、かなりの難所となっている。しかし、距離はそれほど長くはないので、根気よく運転していればすぐに峠に出る。ジャローリー峠に出たのは午前9時頃であった。

サトラジ河に架かる橋、ルフリーにて
ジャローリー峠は、今まで越えた経験のあるクンザム峠(Kunzam La; 標高4,551m)やロータン峠(Rohthang La; 標高3,978m)とは全く違った雰囲気の峠であった。狭い尾根のスペースに数件の茶屋が並び、一際高い丘に寺院が建っていた。既に雪は跡形もなく、山は緑で覆われていた。そして遠くにヒマーラヤ山脈の高峰がきれいに並んで見えた。ヒマーラヤ山脈の絶景のひとつであろう。

ジャローリー峠

ジャローリー峠からの眺め

記念撮影
ジャローリー峠の茶屋で朝食を食べ、45分ほど休憩し、マナーリー方面へ向かう道を下り始めた。やはりこちら側も急斜面の上に悪路であり、ファーストギアのエンジンブレーキを使って慎重に下りた。途中、1車線しかない山道の舗装工事をしていて通行止めになっており、工事が完了するまで待たされるところだったが、バイクならギリギリ通り抜けられるスペースがあったため、崖っぷちではあったが勇気を出して突っ切った。このとき、通行止めを喰らって先に進めず困っていたインド人のおばさんがヒッチハイクを求めて来たため、彼女を乗せて次のバンジャール(Banjar;
標高1,524m)まで行くことになった。ムンバイー生まれながら山に魅了されてずっとマナーリーやバンジャールで生活していると言う。名前はシンデレラ。ニックネームかと思ったが本名らしい。どうもポルトガル系のインド人みたいである。バンジャールは峠の反対側にあるアーニーよりも大きな町で、しかもちょうどメーラー(祭り)が行われており、人でごった返していた。ちょっと寄って行きたい気もしたが、バイクに積んだ荷物が心配だったので素通りすることにした。シンデレラさんをバンジャールで下ろし、先を急いだ。
バンジャール以降は、ビャース河の支流ティールタン河の河畔を行く道となる。ラールジー(Larji; 標高975m)という町でティールタン河はサインジ河と合流し、その水はアウト(Aut)のダムに蓄えられる。そろそろ給油すべき頃合いになっており、ラールジーにあると聞いていたガソリンスタンドに立ち寄ったのだが、ディーゼルはあったもののペトロールはなかった。インドの山間部や僻地では、ガソリンスタンドの数が少ない上に、ガソリンスタンドのガス欠がよくあるので、慎重に給油して行かなければならない。もっとも、まだ燃料に余裕があったため、大きな問題にはならなかった。

ラールジーの合流点
左がサインジ河、右がティールタン河
アウトには全長2,806mのインド最長トンネルがある。これを通るのは2回目だが、このトンネルは本当にすごい。走っても走っても先が見えず、地面を除く三方の岩盤は剥き出しで、地獄の底へまっしぐらに走っているような錯覚に陥る。アウトのトンネルはクッルー谷の玄関で、デリー方面からクッルー・マナーリーに向かおうとすると、大体必ず通ることになる。ただのトンネルではあるが、デリー~マナーリー間の大きな見所のひとつだ。
NH21上にあるこのアウトのトンネルを抜けてしばらく進む。もうこの辺りは幹線なので道路は2車線以上ある快適な舗装道となり、走行は断然スムーズである。ガソリンスタンドも豊富にあり、この道路を走っている限りガス欠の心配はしなくてもいい。途中にあったガソリンスタンドで500ルピー分給油し、クッルー・マナーリーを目指した。
クッルー(Kullu; 標高1,217m)に差し掛かったのは正午12時頃であった。クッルーの市街地を通らなくても先まで行けるバイパスが新設され、手前のブンタル(Bhuntar)から伸びているのだが、このときはそれを知らず、市街地に迷い込んでしまった。市場の狭い道路をバスを初めとした自動車が通るために常にクッルーの市街地は混雑している。そうでなくてもビャース河の西岸を通る道は交通量が多いため、道路のスムーズさほどには走っていて楽しくない。そこでクッルーを抜けた後に東岸に渡って、マイナーな道路の方を通ることにした。この道を通ってもマナーリーに行くことが出来る。こちらも道はそんなに悪くなく、何より交通量が少ないので、断然快適に走ることができた。途中、ナッガル(Naggar;
標高1,840m)という観光地で昼食休憩をした。ちょうど1時頃であった。歴史ある寺院や宮殿が残り、ロシア人芸術家ニコライ・レーリッヒ所縁の地でもあるナッガルには、キンナウル・スピティ周回ツーリングのときに訪れたことがあり、勝手は分かっていた。ここにあるヒマーチャル・プラデーシュ州観光振興局経営のホテル、ナッガル・キャッスルは、それ自体がクッルー王国のマハーラージャーの宮殿で観光地になっているが、併設のレストランも評判高く、ちょうど昼食時であったこともあり、ここでランチを食べた。ヒマーチャリー・プラーオという郷土料理をカリー・パコーラーと共に食べた。
午後1時半頃にナッガルを出て、そのままビャース河東岸の道を進み、午後2時頃にはマナーリーに着いた。今回宿泊するのは、キンナウル・スピティ周回ツーリングの時もお世話になった、日本人夫妻経営の山荘風来坊で、事前に予約も入れていた。風来坊はマナーリーの隣の温泉村ヴァシシュト(Vashisht)にある。ヴァシシュトのメインロード沿いにはないので場所は分かりにくいが、インド在住日本人のリピーターが多い快適な宿である。オーナーの森田さんは山をこよなく愛する登山家でもあるため、ヒマーラヤ山脈のトレッキングに出掛ける登山家が集まる宿にもなっている。ちょうど、グジャラート州ヴァローダラー(旧名バローダー)駐在の日本人が1人、避暑のために宿泊中であった。ここではYさんとしておく。
本日の走行距離215.0km、本日までの総走行距離659.9km。
ここ数日、マナーリーの天候は荒れ模様で、ロータン峠へ行くのも難しい状態だったようだが、昨日は大きな天候の崩れもなく、今日はロータン峠越えに挑戦しても問題ない様子であった。風来坊に宿泊中だった日本人Yさんも数日前にヴァシシュトに到着して以来、このタイミングを待っていたようで、ロータン峠へタクシーで行く準備をしていた。
クッルー谷とラーハウル谷の分水嶺、標高3,978mのロータン峠は、マナーリー観光の大きな目玉である。冬期は雪で閉ざされ、夏の一時期のみ開く。映画やテレビなどでしか雪を見たことのない平野部のインド人が初めて実物の雪に触れる場所であり、開通と同時に多くの観光客がこの峠を訪れる。インドでもっともアトラクション化された峠であり、純粋に自然や光景を楽しむためには必ずしも適していない場所とも言える。雪で覆われた高山がいかに寒いのかを全く知らない人々を相手にした商売――うっかりTシャツ短パン草履履きで来てしまった人でも凍えないような防寒具一式レンタルなど――が繁盛しているのは面白い。あまりに多くの人々がロータン峠へ通じる山道に殺到するため、賢い人々は大体午前5時頃にマナーリーを出発する。僕も午前5時出発を予定していたし、Yさんも同様であった。ただし、僕は峠を越えてラーハウル谷の主都ケーロンを目指すが、Yさんはロータン峠を観光してまたヴァシシュトへ引き返す。
午前5時ちょっと過ぎにヴァシシュトを出発し、ロータン峠へ向かった。やはり早朝出発しているタクシーが何台もいた。出発した直後、道を我が物顔で闊歩する山羊の大群が引き起こす渋滞に捕まってしまったが、バイクだったのでスルリと抜けることができた。この辺りの道路はきれいな舗装道で、走行に全く問題はない。デーオダル(ヒマラヤスギ)の森林の中を抜ける心地よいドライブであるが、標高が上がるにつれて気温も下がって行く。森林限界を越える辺りから所々ダートになっている箇所が目立ち始め、雪解け水によって道路が河となっている部分もいくつか越えることになった。しかし、このような悪路は今まで何度も越えて来たので怖くない。観光客を乗せたジープやトラックに混じりながら果敢に走行し続けた。
午前6時半前にマーリー(Marhi; 標高3,320m)に着いた。ここには数件の茶屋が並んでおり、休憩地点となっている。森田さんに勧められていたヒマラヤン・ダーバー(Himalayan
Dhaba)を探し、バイクを停めた。ちょうどこのときYさんの乗ったタクシーも到着した。しかしあまり腹が減っていなかったので、ここではチャーイを飲んだだけであった。チャーイを飲みながらふと外を見ると、細かい雪が降っているのに気付いた。・・・雪か!今までインドはおろか日本でも、バイクで雪が降る中を走行したことはなかった。もしかして上の方では吹雪が吹いているのでは・・・。そんな恐怖が脳裏を横切った。しかし、幸い雪は粉雪に分類されるような軽いもので、吹雪のような状態にはならず、寒い以外は走行の大きな支障とはならなかった。むしろ困ったのはマーリー以降の道路の状態である。現在道路の拡張工事が行われており、その影響で道が泥だらけになっている部分がいくつもあるのである。まさに泥沼状態。泥にタイヤを取られて転倒しないよう、慎重に走行した。交通量がまだ少なかったし、対向車もほとんどなかったので、泥道でも比較的固まっていそうな部分、通りやすそうな部分を選んで走行することができた。しかしもしこれが渋滞状態となって、車輪を走らすラインを選べなくなったら、かなり難儀しそうである。対向車がはね飛ばす泥も容赦なく降りかかって来ることだろう。3年前にロータン峠を越えたときにはこんなに酷くはなかったと記憶している。一応帰りのルートのひとつのオプションとして、来た道をそのまま引き返すことを考えていたのだが、マーリーからロータン峠へ続く道の泥沼状態を見て、考え直すことになった。

マーリーの茶屋集落
写真では分からないが雪が降っている

クッルー谷
下に見える集落がマーリー
雪が降ったり泥沼状態だったりして苦労したのだが、午前7時半にはロータン峠に辿り着くことが出来た。一面雪と氷の世界であった。まだ観光客も少なく、神秘的な峠の雰囲気をかなり残していた。観光地化されているのは主に峠のクッルー谷側で、峠を越えてラーハウル谷側へ出れば、より手つかずの雪原を見ることが出来る。ここでもYさんと合流し、記念撮影などをして、僕は午前7時45分には峠を下り始めた。Yさんとは今度こそ本当の別れとなるだろう。

ロータン峠
まだ早朝だから空いているが、もうしばらくすると大渋滞大混雑となる

同じくロータン峠
こちらはクッルー谷側

道の両側には雪の塊
除雪車も埋もれてしまっている

ロータン峠のラーハウル谷側
こちらの方が手つかずの雪原が残っている

記念撮影
ラーハウル谷側の道路の状態も大して変わらなかったが、こちらの方が圧倒的に交通量が少ないので楽だった。峠のこちら側ではもう雪は降っていなかったし、途中で写真を撮りながら下る余裕もあった。クッルー谷側を走行中はほとんど写真どころではなかった・・・。しばらくクネクネと蛇行する山道を下って行くと、まずは分岐点に出る。地名はグランプー(Gramphu;
標高3,200m)となっているが、特に何もなかった。ラーハウル谷はチャンドラ河に沿って東西に延びており、この分岐点をチャンドラ河上流方面である東に向かえば以前ツーリングしたスピティへ向かうことになる。3年前、この道を通ってスピティから来たのだった。グランプーをチャンドラ河下流方面である西に向かえばそのままラーハウル谷が続き、本日の目的地ケーロンまで出る。

ラーハウル谷

ロング・アンド・ワインディング・ロード

この谷の奥にはスピティ
一路ケーロンを目指していると、午前9時にコークサル(Khoksar)という集落に出た。ここにはチェックポストがあり、外国人はパスポートとヴィザのチェックを受ける。ついでにここのダーバーで朝食としてマトン・モモ(チベット風蒸し餃子)を食べ、30分ほど休憩した。コークサルにはレストハウスもある。もし帰りにもロータン峠を越えるなら、コークサルで一泊し、翌早朝に峠を目指せば、もっとも安全に峠を下りることが出来るだろう。

コークサルのチェックポスト周辺
コークサルまではチャンドラ河の南岸を走行していたが、コークサルに橋が架かっており、今度は北岸を走行することになる。この道は途中まで非常に美しい舗装道となっており、スムーズに走ることが出来た。しかし、スィスー(Sissu;
標高3,130m)という集落を越えると、今正に道路の舗装工事が行われているところで、所々大きな水たまりを越えたり、泥道を進んだりしなくてはならなかった。

こういう「道」を通らなければならない
途中にあるゴーンドラー(Gondla; 標高3,160m)には、磨崖仏や中世の城などがあり、寄って行こうと思っていたのだが、いつの間にか通り過ぎてしまい、しかもその通り過ぎた道が酷い悪路だったので、引き返す気が起こらず、そのままスキップしてしまった。もし帰りにロータン峠ルートを通るならば、今度こそはゴーンドラーに立ち寄ろうと考え、先を急いだ。

ゴーンドラー周辺の風景
ゴーンドラーから9kmほど進むと、ターンディーという集落に出る。ここは、チャンドラ河とバーガー河の合流地点となっており、以後この河はチャンドラバーガー河と呼ばれ、やがてチャナーブ河(Chenab)となる。河の合流点ということは道の合流点ともなっており、ここからチャンドラ河上流、バーガー河上流、そしてチャンドラバーガー河下流へ向かう道が出ている。今日の目的地ケーロンはバーガー河上流方面にある。しかしそれよりもターンディーが重要なのは、ラーハウル谷唯一のガソリンスタンドがある場所であることだ。ここからどこを目指そうとしても、必ずターンディーのガソリンスタンドで満タンに給油して行く必要がある。特にラダックへ抜けようとする際、この先365kmガソリンスタンドがない。世界でもっとも重要なガソリンスタンドだと言える。もしここでペトロールが枯渇中だったらレー行きを諦めて引き返す他なかったが、幸い手に入ったので、満タンにした。

ターンディーのガソリンスタンド

「次のガソリンスタンドは365km先」
ターンディーにてバーガー河に架かる橋を渡り、8km上流へ遡ると、午前11時15分にケーロン(Keylong; 標高3,348m)に到着。チベット風のカラフルな門が迎えてくれる。そこから道は二手に分かれるが、左の道はバイパスとなっており、右の道はケーロン市街地へ続いている。ケーロンでは、メインバザールの端にあるホテル・タシデレ(Hotel
Tashi Deleg)に宿泊。階によって値段が違うが、部屋のレベルは基本的に変わらず、眺望が違うだけなので、もっとも低くもっとも安い650ルピーの部屋に泊まった。バスルームにギザがあるのでいつでもお湯を浴びられる。

ケーロンの町並みと山々
ホテル・タシデレより撮影
到着してからとりあえずシャワーを浴び、洗濯したが、それ以外はテラスで雄大な雪山の光景を見ながら日光浴し、高地順応に努めた。午後1時半に昼食としてトゥクパ(チベット風ラーメン)や春巻きを食べた後、午後2時頃にケーロンの町をゆっくり散歩した。さすがラーハウルの中心だけあって、市場には一通りのものが揃っている。防寒具もここで十分揃う。メインバザールの中心部は三叉路になっており、そこには「中村屋のボース」として有名なラース・ビハーリー・ボースの胸像が立っている。ベンガルに生まれ、日本に亡命したボースの胸像がなぜこんな僻地に?実はボースは逃亡中にケーロンに滞在していたことがあり、地元に所縁のあるフリーダムファイターの1人として胸像が立てられたのである。詳しくは中島岳志著「中村屋のボース」(白水社)を読んでいただきたい。

ラース・ビハーリー・ボースの胸像
ところで、今まで標高3,000mを越えると必ずと言っていいほど高山病になっていたのだが、今回はまだ高山病と言える症状が出ていない。徐々に高度を上げて行ったのが幸いしたのかもしれないが、ヴァシシュトを出る際に森田さんからバファリンを分けてもらったことも功を奏したと思われる。高度を上げる前にバファリンを半錠ほど飲んでおくと高山病予防になるらしく、勧め通り、まず半錠を服用していた。他には、水をたくさん飲むことと、身体を冷やさないことなどが高山病予防のために大切だ。
本日の走行距離114.4km、本日までの総走行距離774.3km。
宿泊中のホテル・タシデレのオーナーは周辺エリアのエキスパートであり、いろいろ情報を提供してもらえた。やはり最大の関心事はラダックへ抜けられるか、ということだった。オーナーによると、現在バララチャ峠までは行けるようだが、その先の道がまだ閉ざされているようだ。ケーロンの先にもいくつか宿泊できる場所があり、そちらへ移動して開通を待つという方法もあったが、やはりケーロンはラーハウル谷の中心だけあっていろいろ便利なので、とりあえずケーロンにもう1泊して様子を見ることにした。高地順応にもなるし、休息にもなる。今日はバイクに乗らない日と決め、のんびりすることにした。
午前中は旅行記の執筆や写真の整理などをして過ごした。午後からは、バーガー河を挟んでケーロンとは反対側に立地するカルダン・ゴンパ(Khardong
Gompa)までトレッキングすることにした。ゴンパとはチベット仏教寺院兼僧院であり、チベット文化圏の観光ではゴンパ巡りがメインとなる。ラーハウル谷はヒンドゥー教の方が優勢ではあるが、既にチベット文化圏の一部でもあり、キンナウル谷と同様にヒンドゥー教とチベット仏教の混交が見られる。900年の歴史を持つカルダン・ゴンパはラーハウル谷で最大のドゥクパ派ゴンパとなっており、男性の僧侶と女性の尼僧が住んでいる点でもユニークである。カルダン・ゴンパまではジープ道も通っており、バイクで行けばすぐであるが、どうせ暇なこともあって、とぼとぼ歩いて向かうことにした。
正午12時頃に宿を出発。市場をターンディー方面へ向かう。まずは途中にあったラーハウル&スピティ部族博物館に寄ってみた。建物は立派だが、ほとんど写真展示ばかりで大した展示物はなかった。
さらにターンディー方面へ少しだけ歩くと、病院へ下りる階段がある。その階段を下って道なりに進み、病院の脇に延びている階段をひたすら下って行く。一応一部を除き石段のようになってはいるものの、かなり急な坂道である。

ケーロンからバーガー河へ下りる道
急な坂道をひたすら下ると、バーガー河に架かる橋を渡ることになる。橋を渡ると今度は上り坂であり、それをひたすら上って行くことになる。しかし今日は雲一つない快晴で景色は素晴らしく、一休みしたり写真を撮ったりしながら、のんびりと坂を上って行った。

対岸から眺めたケーロンの町
坂を上った先はジープ道に出る。このジープ道を右に行くとカルダン村になり、この村を通ってゴンパまで行くことも出来るのだが、左に進んでそのままジープ道を辿って行った方が遠回りではあるものの勾配が急でなく比較的楽である。僕もゴンパまではこちらの道を通った。ただ、道端にあまり樹が生えておらず、日陰に乏しいのが難点である。

カルダン・ゴンパ遠景
午後2時半にはカルダン・ゴンパに到着した。寺院の他、僧侶の住居と見られる建物がいくつか建っていたが、誰かいる気配がなく、見た目新しい寺院も閉まっていた。だが、ゴンパの前面にせり出したテラスの眺望は素晴らしく、谷を一望の下にすることが出来た。しばらくゴンパで待っていたら1人の尼僧がどこからともなくやって来て寺院の扉を開けてくれた。中は写真撮影禁止だったが、大きな仏像が3体祭られていた他、壁には新旧入り交じった壁画が描かれていた。また、隣のお堂には巨大なマニ車が納められていた。

カルダン・ゴンパ近景

巨大マニ車
カルダン・ゴンパからカルダン村へ下りていく急な階段があり、帰りはこちらの道を通った。村で1杯チャーイでも、と考えていたが、茶屋もないような本物の村であった。この村からジープ道に沿って歩いて行くと、行きの時に通った分岐点に出るため、そこからは同じ道を通ってケーロンまで帰った。はっきり言って帰りの方が辛かった。特にバーガー河の橋からケーロン市街地まで上る道は人間工学を考慮していないような坂道であり、数歩進んでは休憩、というペースでやっと登り切った。ケーロンに帰り着いたのは午後4時半頃であった。
本日は走行なし。本日までの総走行距離774.3km。
| ◆ |
5月22日(土) トリロークナート、ウダイプル |
◆ |
宿のオーナーの話では、ラダックに通じる道がオープンするのにあと1週間かかるかもしれないとのことであった。少なくとも25日前にオープンする可能性はないと言われ、旅程を考え直す必要に迫られた。元々予想していた事態とは言え、想定内では最悪のケースである。やはり5月はまだマナーリー・レー・ツーリングには早すぎたか。いつまでも待っていられる訳ではないため、開通がこれ以上遅れると、ラダック行きは諦めなければならない。
もし今の状態でどうしてもケーロンからラダックへ行かなければならない場合、主に2つの代理ルートが考えられる。ひとつはロータン峠を越えてマナーリーまで引き返し、そこからマンディー、ダラムシャーラーなどを経由してパターンコートまで出て、そこからジャンムー、シュリーナガル、カールギルを通ってレーを目指すコースである。シュリーナガル~レー間のルートも冬期は閉ざされているが、既にオープンしているようである。このコースはかなりの遠回りであり、事実上ツーリングのやり直しになる。だが、ケーロンで1週間待つよりは確実にレーに辿り着く。もうひとつは、チャンドラバーガー河~チャナーブ河に沿って進み、パッタン谷からパンギー谷に抜けて、キッラル(Killar)というヒマーチャル・プラデーシュ州の州境の町からジャンムー&カシュミール州に入って、ジャンムーとシュリーナガルをつなぐNH1Aに出るルートである。この道はあまり知られておらず、地図にも載っていないことが多いが、ラーハウル谷とジャンムー、シュリーナガルをつなぐ道は確かに存在する。この道を通ってシュリーナガルまで出てしまえば、後は上で説明したルートを通ってレーまで行ける。距離的にはもっとも近い。しかしこのルートの難点は、途中でカシュミール分離派テロリストのキャンプがあるとされ、毎日何かしら事件が起こっていると言う超危険地域を通り抜けなければならないことだ。キシュトワール(Kishtwar)からドーダー(Doda)までの道が特に危ないと言われている。他に、キッラルからサチュ峠(Sach
Pass; 標高4,390m)を越えてチャンバー(Chamba; 標高996m)に出る、細いジープ道が通っているとの情報もあった。チャンバーまで抜けられれば、やはりシュリーナガルまで出ることが出来る。だが、サチュ峠が開通するのは例年6月中旬のようでバララチャ峠よりも遅く、バララチャ峠開通を待っている上ではあまり意味がない。
改めて今回のツーリングの目的を考えてみると、レーに辿り着くことよりも、マナーリー~レー間の道をバイクで走破することに重点が置かれている。もちろん、シュリーナガル経由でレーまで行き、その頃にはバララチャ峠も開いているだろうという前提の下、帰路でレーからマナーリーを目指すことも出来るが、どちらかというとロマンに欠ける旅程となる。やはりマナーリーからレーを目指すという方向性が重要なのである。それを考えると、ケーロンで待つ方法を選択するしかなかった。
とりあえず神に祈る以外はひたすら待つしかないので、待っている間なるべく有意義に過ごすことを考えなければならない。今日は、チャンドラバーガー河下流方向、パッタン谷の2つの観光地をバイクで巡ることにした。トリロークナート(Triloknath;
標高2,760m)とウダイプル(Udaipur; 標高2,743m)である。ウダイプルからさらに先に行けば上述した州境の町キッラルに出るのだが、キッラル経由のルートは取らないことに決めたため、その途中にある観光地をケーロンから日帰りで巡ることにしたのだった。
午前8時半に宿を出発して、ターンディー方面へ向かった。ターンディーの合流点では、チャンドラ河とバーガー河に鉄橋が架かっている。てっきりターンディーでチャンドラ河を渡ってチャンドラバーガー河の下流を目指すのかと思って走っていたが、それは間違いで、その道はとある村で行き止まりとなっていた。ウダイプル方面へ向かうためには、ケーロン方面から行くと、バーガー河に架かる橋を渡る前に上に伸びている道を進まなければならなかった。多少の混乱はあったものの、基本的に山道の構造は単純であるため、すぐに軌道を修正でき、ウダイプルへ向かうパッタン谷の道を走った。下流に向かうということは標高を下げるということであり、日が高くなって来たこともあって、徐々にではあるが、気温は上がって行った。ラーハウル谷よりもより緑豊かで、それでいて険しい山々からは氷河がダイナミックに降下しており、非常に美しく、かつ迫力のある谷であった。

パッタン谷の風景
右奥に見える白い筋は氷河
途中のティロートという村までは、所々で小川越えなどをしなければならなかったものの、基本的にスムーズに走行できる舗装道が続いていた。しかし、ティロートを過ぎるとダート道の方が支配的になり、砂利道、デコボコ道、小川道、泥道など、かなり酷い状態になっている部分を越えて行かなければならなかった。交通量も、まだ少ないと呼べるレベルではあるが、割と往来があって、道が1車線しかない部分では道を譲るために止まらなければならなかった。しかし、ロータン峠を越えて来た者には大した難関ではないだろう。

チャンドラバーガー河の湾曲部に広がる村
奥には氷河が見える
やがてトリロークナート寺院へ通じる分岐路が左に伸びている地点に辿り着いた。派手な看板が出ているので見落とすことはないだろう。まずはトリロークナートの方へ向かった。橋を渡り、しばらく道なりに進んで行くと、寺院に到着した。

トリロークナート
中央の白い尖塔が寺院
トリロークナート寺院の由来は興味深い。元々シヴァ神を祀ったヒンドゥー教寺院だったのだが、後にチベット仏教寺院に改変された。聖室に安置されているのは仏陀の化身のひとつアヴァローキテーシュワラを象った大理石の像であり、寺院はチベット仏教僧によって管理されているが、この寺院にはヒンドゥー教徒も訪れ、像をシヴァ神と考えて礼拝を行っている。建築は一般のゴンパとは全く違った造りであり、尖塔があったり、境内にはナンディー像があったりして、完全にヒンドゥー教寺院スタイルなのだが、チベット風の旗がたなびいていたり、聖室周辺にマニ車が巡らされていたり、前室にチベット仏教の礼拝道具が置かれていたりして、ゴンパっぽい特徴も備えている。ヒンドゥー教とチベット仏教の興味深い混交をこの寺院に見出すことが出来るのである。ちなみに、寺院内部の写真撮影は禁止されている。

お婆さんと子供
午前11時頃にトリロークナートを出発し、分岐点まで戻って、今度はウダイプルへ向かう道を進んだ。やはり道の状態は相変わらずで、悪路に悪戦苦闘しながら走行した。朝はほとんど快晴だったのだが、トリロークナートを過ぎた辺りから雲が目立つようになって来た。
ウダイプルには午前11時45分頃に到着。街道沿いの宿場町と言った雰囲気で、市街地にはダーバーが並んでいた。ウダイプルの見所は12世紀建造のマルクラー女神寺院である。カーリー女神を祀った寺院で、外見は一般的なヒマーチャル様式であるが、圧巻は内部の木彫である。インドでは木造建築の古い寺院はヒマーチャル・プラデーシュ州とケーララ州ぐらいにしか残っていないが、かつてはさらに広く木造寺院が造られていたとされる。現存する石造寺院と同様に木造寺院にも細かな彫刻が施されていたようで、ヒマーチャル・プラデーシュ州ではいくつかの優れた木彫を誇る木造寺院を見ることができる。ウダイプルのマルクラー女神寺院はそのひとつだ。シヴァ神の神妃であるカーリー女神を祀っている割には、ヴィシュヌ神関連の彫刻が多いように見受けられた。「マハーバーラタ」や「ラーマーヤナ」のシーンを再現した彫刻もあった。

マルクラー女神寺院

前室天井の彫刻
内部撮影禁止だが、禁止される前に撮影
ちょうど昼時になっていたので、ウダイプルの適当なダーバーで安っぽい食事を食べた。ウダイプルを出発したのは12時半頃であった。そのまま来た道を引き返し、ターンディーのガソリンスタンドでガソリンを補給した後、午後2時半にはケーロンに帰り着いた。
今日のアクションはこれで終了なので、後はケーロンの町をブラブラ散歩したり、ホテルでのんびりしたりしていた。夕方7時頃、どこからともなくブォ~という低い笛の音が聞こえて来た。時報か何かかと思って気にしないでいたが、その音はどんどん近付いて来ていた。外に出て見てみると、ケーロンのバーザールを行列が通っていた。旗を持った人が列の先頭を務め、一反木綿のような長い白布を抱えた一団が続き、その次に神輿のようなものが運ばれている。何かのお祭りかと思って、その行列の後を付けた。そうしたらバーザールを抜けて市街地の外に出てしまった。一体どこへ行くのかと行列の中の人に聞いてみたら、これはお祭りではなく葬式の列であった。これから遺体を燃やしに行くらしい。平野部ではあまり見られないような葬列であった。

葬列
本日の走行距離129.2km、本日までの総走行距離903.5km。
朝から雨。もはやラダック行きは絶望的である。一応、マナーリー・レー・ロードの開通予定日は事前に5月25日と決まっていたようで、その日までケーロンで待つことにするが、その日まで待ってもまだ開通の目処が立たないようであったらマナーリーへ引き返すことを考え始めた。
雨は昼前には一旦止んだ。今日は宿のオーナーが、ケーロンの背後に建つシャシュル・ゴンパまでジープで連れて行って案内してくれると言うので、その好意に甘えることにした。シャシュル・ゴンパまではジープ道が通っており、自動車でも行くことが出来るが、道幅はギリギリ1車線しかなく、かなり危険な崖道になっている。道の状態も悪く、バイクでは苦労しそうであった。
シャシュル・ゴンパまで上っている途中、ゴンパから下りてくる軽自動車とすれ違った。その自動車にはなんとリンポチェが乗っていた。14世ダライ・ラマの師の生まれ変わりに最近認定された少年で、普段はカルナータカ州に住んでいるが、現在は里帰り中であるらしい。生まれは、一昨日訪れたカルドン村である。祝福を与えてもらえた。偶然中の偶然だが、ラッキーであった。

リンポチェ
ケーロンを出たのは正午12時頃だったが、ジープでも案外山道を上るのには時間がかかり、5~6kmジープ道を上った地点にあるシャシュル・ゴンパに到着したのは12時半頃であった。

シャシュル・ゴンパ
シャシュル・ゴンパは、17世紀にブータン国王の特使デーヴァ・ギャツォによって建造された。宗派はドゥクパ。外観は新しいが、その新しい外郭の中に古い寺院がスッポリ収まっている。寺院は3層になっており、3階にもっとも古そうな像、壁画、タンカ、写本、マニ車があった。チベット仏教の尊格については全く疎いので、どの階に誰が祀られているのか判別できないのが悔しい。

3階のラカン

古い彫像が並ぶ
ちょうど地元のおばさん、お婆さんたちが参拝に来ており、そのままゴンパの居間で勝手に団らんし始めた。我々も混ぜてもらって、バター茶などをご馳走になった。この地域の一定以上の大きさの屋敷では、必ず暖炉を囲んだ居間があるようで、チャーイなどを飲みながら団らんできるようになっている。一様に紫色の衣装を身に纏った年配の女性たちは、ヒンディー語とは完全に異なった言語を話しており(おそらくチベット系の言語なのだろう)、何をしゃべっているのか全く分からなかった。

ゴンパ内の団らんの間
シャシュル・ゴンパを見終わった後は、そのまま徒歩でケーロンまで戻った。ジープ道とは別に山道をほぼ垂直に上り下りするような道が、ケーロンのオールド・バススタンド付近から出ている。だが、この道を上って行くのは大変そうだった。
宿まで帰り着いたのは午後2時半頃であった。ホテルのレストランで昼食を食べていたら、いつの間にか外ではまた雨が降り始めていた。雨が止むのを待って、「中村屋のボース」ラース・ビハーリー・ボースがケーロンで滞在した家を探してみることにした。1912年12月に、デリーのチャーンドニー・チャウクにおいて、パレード中のハーディング総督に対する爆弾テロを決行したラース・ビハーリー・ボースは、逃亡中にケーロンまで辿り着き、地元の名士バーブー・トゥクトゥクの家に滞在したと言う。その家は、滞在中のホテル・タシデレのすぐ下にあった。立派な造りの屋敷であったが、住人に聞いてみると、既にボースが滞在した屋敷は取り壊されており、現在あるのはその後に再建された新しい屋敷とのことである(と言っても築6、70年にはなるようだ)。ボース関連の遺物や古い写真でも残っていないかと聞いてみたが、杖などいくつかの品物があったものの、紛失してしまったらしい。ちなみに、「旧バーブー・トゥクトゥクの屋敷」では、チャーイやビスケットを出してもらって、歓待してもらえた。
本日は走行なし。本日までの総走行距離903.5km。
朝から快晴であった。もうケーロンでやることがなくなってしまったので、今日は懸念のバララチャ峠まで様子を見に行ってみることにした。この峠が雪で閉ざされているためにレーまでの道がなかなか開かないのである。開通予定日は25日とのことだが、実際のところいつ頃オープンすることになりそうなのか、はっきり言ってケーロンでは誰も正確な情報を持っていない状態なので、直接除雪現場まで行って聞いてみるのがもっとも確実だと考えた。また、もしレーまでのツーリングを諦めることになったとしても、行けるところまで行ったという事実があるだけでも満足できるし、観光にもなる。バララチャ峠にはスーラジ・タールという、インドでも有数の高山湖があり、バーガー河の源流となっている。非常に美しい場所だと言う。少なくともスーラジ・タールまでは行けるようなので、除雪状況を聞きに行くついでに、スーラジ・タールまでピクニックと洒落込むのも悪くないと考えた。
午前9時半にホテルを出発し、バーガー河に沿って伸びる道を上流に進んだ。途中、スティングリ(Stingri)、ジスパ(Jispa; 標高3,142m)などの集落を通り過ぎたが、もはやケーロンよりも大きな町は存在しない。この辺りの道路はトラックが余裕ですれ違えるくらいの広さの、美しい舗装道であり、走行が楽しかった。現在舗装工事が急ピッチで行われており、あと1、2ヶ月後ならこの辺りのルートは本当に爽快に走行することができるだろうと予想された。

ジスパ周辺の道路
やがてダルチャ(Darcha; 標高3,400m)という集落がある、開けた場所に出たが、そこがこの谷の最後の集落のようだった。紺碧のバーガー河が山間の広大な空間を縦横無尽に流れていた。河に架かる橋沿いにダーバーが並んでいたが、まだ峠が開いていないために開店閉業中のようであった。

ダルチャ周辺の風景

記念撮影
通りすがりの人に撮ってもらった
ダルチャを過ぎると急な上り坂になるが、また谷に沿った平行の道路になる。ここも舗装工事が行われている最中だったが、まだ悪路の部分が多く、かなり大きな河も渡らなければならなかった。しばらく谷の奥へ続く道を進んでいると、左手に緑色の小さな湖が現れた。特に表示はなかったが、これがディーパク・タールであるらしかった。スーラジ・タールはさらに先になる。

ディーパク・タール
ディーパク・タールを過ぎるとパツェオ(Patseo)という場所に出る。ここには政府系のレストハウスがあったが、営業している気配はなかった。開けた場所にトランジット・キャンプなるものもあったが、これももぬけの殻であった。

トランジット・キャンプ周辺
峠を目指して走るごとに次第に雪が深くなって行った。道路は基本的に良質の舗装道なのだが、左右の山からせり出して来る雪の塊が道路を今にも覆わんとしていた。と言うより、道路を覆ってしまった氷塊を除雪車が除雪し、自動車1台が通れるぐらいの道が開かれていたのだが、奥に進むごとに人間の力は無力となって行き、代わりに自然の力が圧倒しつつあるような感じであった。

雪の間を進む

もはや正真正銘の雪山である
途中、ジン・ジン・バル(Zing Zing Bar; 標高4,150m)という場所に、除雪作業を行う作業員たちのキャンプがあり、それを過ぎると、とうとう道路にまだ雪が積もったままになった状態が続くようになった。トラックやジープが通った轍が両脇に残っているので、そこをうまく通れば何とかなることもあるのだが、ちょっと雪の高さが高くなると大体はスリップしてしまう。スリップならまだましで、下手すると車輪が雪の中にはまり込んで身動きが取れなくなってしまう。途中2度雪の中に車輪がはまり込んでしまい、万事休すかと観念したが、もがいていたら何とか抜け出せた。しかし、今回のツーリングで初めて本当の恐怖を感じた。ジョー・ダル・ガヤー・サムジョー・マル・ガヤー(恐れた者は死んだと思え)。このとき僕の旅は終わったと言える。

危険な雪道
雪道をもがきながら進み、とうとう除雪作業最前線まで到着した。雪は相当深く、スーラジ・タールにすら行けない状態であった。ちょうど昼食中だった作業員にいつ頃峠が開くのか聞いてみたら、あと5日はかかるとのことであった。もちろん、この雪の状態を見る限り、天候に恵まれれば最低でも5日ということであり、どう考えても1週間以上はかかりそうであった。数日内のレー到着は絶望的と言うより不可能である。もし時間とお金が無尽蔵にあるならば、このまま開通を待つこともできる。だが、たとえ開通したとしても、開通したばかりの時期にレーまでの道を無理に走ると、通常時ルート上にあるはずの茶屋や宿泊用テントがまだ準備されていない可能性があり、そうなると途中休憩なしでレーまで到着しなければならなくなる恐れがある。ただでさえ困難なルートなのに、さらにもっとも困難な時期に走行することになるのである。これは賢い選択ではない。つまり、このままレーを目指そうとしたら、かなりの時間待たなければならなくなるのである。行けるところまで行って、踏ん切りが付いた。一生に一度という覚悟と意気込みで挑戦したマナーリー・レー・ツーリングであったが、バララチャ峠の開通の遅れにより、レー行きは諦めることにした。時には前進よりも後退の方に勇気がいることがある。バララチャ峠の状態を自分の目で見て、勇気ある後退を決めた。と言うより、自然を前にしたら、人間のちっぽけな勇気など何でもない。ちなみに、除雪作業最前線に辿り着いたのは正午12時頃で、ケーロンから2時間半かかったことになる。

このすぐ先がバララチャ峠だと思うが、もはや進めず
カリズマにラダックの空を見せられなかった
ところで、マナーリー・レー・ツーリングに挑戦するのには時期が早すぎたのではないかと思われるかもしれない。だが、峠の開通は完全に天候と積雪量に依存しており、年によって大きく前後するのである。5月末の今、バララチャ峠はオープンしていてもおかしくないのだが、今年は例年に比べて雪が多く、しかも雪崩があったようで、開通が大幅に遅れている状態みたいだ。実際、既にケーロンなどには他にも多くの人々が、インド人外国人、四輪二輪問わず、ラダック行きを目指して集まって来ており、この旅の途中にも何人かそういう人々と出会った。やはり峠の開通の遅れは皆を一様に失望させており、時間に余裕のない旅行者は引き返すことを決めている様子であった。

バーガー河

奥に見える山はセブンシスターズ

ケーロンの町
レー行きを諦めたこと、ケーロンに長期滞在することになったことで、今回のツーリングはマナーリー・レー・ツーリングと言うよりもラーハウル・ツーリングになってしまった。マナーリー~レー間の中継地点として見られることの多いケーロンであるが、長く滞在してみるとそれなりに魅力のある場所であり、この町を拠点に、あまり観光地化されていないラーハウル谷を堪能できたのは稀な体験だったと言えるかもしれない。ケーロンは避暑地としての潜在性も高い。標高は他のメジャーな避暑地に比べて1,000m以上高く、アクセスも困難だが、それ故に酷暑期の狂った混雑とは無縁であり、のんびりと避暑が出来る場所になっている。もちろん、もっと僻地へ行けば、ヒマーラヤ山脈には避暑に適した隠れた秘境がいくつも存在するだろうが、ケーロンには一応まとまった市場があり、文明から完全に隔絶している訳ではないところに安心感があり、そういうちょっとした利便性を求める避暑客には最適かもしれない。ただし、一応町にネットカフェはあるが、滞在中インターネットが通じたことはなかった・・・。
本日の走行距離138.8km、本日までの総走行距離1042.3km。
| ◆ |
5月25日(火) ゴーンドラー、ロータン峠、ヴァシシュト |
◆ |
レー行きを諦めたことで、今日は来た道を引き返し、ロータン峠を越えてヴァシシュトへ向かう。
旅行中は常に何かをしていないと落ち着かないタイプである僕は、一ヶ所に長期滞在することはあまりない。よって、期せずして5日間も滞在することになったケーロンは、いろいろ想い出の町になりそうだ。宿泊したホテル・タシデレのオーナー、タシ・カルパ氏は、なかなかバララチャ峠が開かないことに苛立っていた僕に、ラーハウル谷の魅力を熱心に説いてくれた。暇を持て余していた僕をシャシュル・ゴンパまでジープで連れて行ってくれたし、「中村屋のボース」ことラース・ビハーリー・ボースに関する有力な情報も提供してくれた。また、ケーロンにはいくつかレストランやダーバーがあるが、結局このホテルの食事が一番おいしかった。それもそのはず、タシ・カルパ氏が時々自ら厨房に入って料理を指導していた。通常のインド人ホテル・オーナーを超越した働きぶりであった。もしまたケーロンに来ることがあれば、そのときも是非このホテル・タシデレに宿泊したい。マナーリー・レー・ツーリングに再挑戦する上で、頼もしい前線基地が出来た気分である。

奥に見える多層の建物がホテル・タシデレ
午前6時には出発できる態勢が整っていたのだが、タシ・カルパ氏に別れのチャーイを驕ってもらったりしている内に出発は午前7時になってしまった。今日をケーロンから引き返す日に選んだのはたまたまだが、実はロータン峠をラーハウル谷側から越えるのにはかなり都合の良い日であった。なぜなら火曜日は、一般車両のマナーリー側からのロータン峠入りが全面禁止される日になっているからである。路線バスや、ラーハウル側からの一般車両通行は特に禁止されていない。通常、マナーリーから大量の避暑客が雪遊びをしにロータン峠に詰めかけるため、峠へ続く道は早朝を過ぎると大混雑となるのだが、このルールのおかげで火曜日だけは混雑とは無縁となっている。ロータン峠の道の状態を見て、帰りはかなり苦労するだろうと恐れていたが、この火曜日ルールをうまく使えば、ロータン峠越えは圧倒的に容易となる。逆に、火曜日にマナーリー側からロータン峠を越えようとした場合、通行が遮断される前、つまり早朝7時前ぐらいに、ロータン峠の麓の集落コーティー(Kothi)を越えなければならないようだ。本当は思いっきり早朝にケーロンを出て、少しでも渋滞が軽い内にロータン峠を越えようと考えていたのだが、これを知ったおかげで、余裕を持ってケーロンを出ることが出来たのだった。
ガソリンは十分にあったので、ターンディーのガソリンスタンドでは給油せず、そのままチャンドラ河を遡った。途中、ゴーンドラー(Gondla; 標高3,160m)という町に立ち寄った。ここにはいくつか見所がある。行きのときに立ち寄ろうと思っていたのだが、うっかり通り過ぎてしまったため、帰りには忘れずに立ち寄った。ただ、やはり気を付けていても村へ下りる道が分かりにくかった。東から来ても西から来ても、ゴーンドラー村に入ってすぐのところに下へ続く村道があるので、それを下りて行かなければならない。ゴーンドラーの最大の見所は、17~18世紀に建造されたとされるタークル(地主)の居城である。角塔型の建築で、中にはダライ・ラマから贈られたとされる「知恵の剣」が収められているらしい。ただ、地元の人に聞いてみたところ、現在では「政府の所有物」になっており、中には入れないようだ。

ゴーンドラーのタークルの居城
タークルの居城から少し西へ行ったところに、公立のシニア・セカンダリー・スクールがある。その門の脇に大きな岩があるのだが、その一面に磨崖仏が大小3つ並んでいる。これもゴーンドラーの見所のひとつである。7~10世紀のものとされているようだ。同様の磨崖仏は、ケーロンの街角にも転がっていた。この周辺ではこの種の磨崖仏があちこちにあるのではないかと思う。他にゴーンドラーには石窟ゴンパがあるようだが、そちらは探さなかった。

ゴーンドラーの磨崖仏
ゴーンドラーを見終わった後は、ラーハウル谷の美しい光景を楽しみながらドライビングした。スィスー(Sisu; 標高3,130m)を過ぎると道は格段に良くなり、走行が楽しくなる。朝日に輝く雪山を目指してバイクを走らせるのはたまらなく爽快だ。

今日でラーハウル谷も見納め
午前9時頃にコークサル(Khoksar)のチェックポストに到着。外国人はここでパスポートとヴィザのチェックを受ける。ついでに、行きでも立ち寄ったチャイニーズ・ダーバーでマトン・モモを食べて朝食とした。朝っぱらからモモが食べられるのはありがたい。午前9時20分頃にコークサルを出て、ロータン峠越えに入った。ロータン峠のラーハウル谷側の雪は既に日光を浴びて溶解が始まっており、道の大部分は河となっていた。ここまで悪路だとやはり上るのには相当な苦労を要する。交通量が少ないのが救いだが、それでも依然としてロータン峠はインドの中でももっとも困難な峠だと言わざるをえない。特にバイクでこの峠の悪路を苦労して走っていると、どんどん気力を奪われて行って、もう二度とこの道を走りたくないと考えるようになってしまう。それに対抗する唯一の武器は忘却であろう。この苦労を完全に忘却したとき、僕はまたここに戻って来るのではないかと思う。

土砂除去工事のため一時的に道路閉鎖
道は濁流となって来る者を阻む
しかし、一旦峠を越え、クッルー谷側に出たら、とてつもない開放感を味わうことになった。火曜日ルールのおかげで、本当に車がいないのである!キンナウル・スピティ周回ツーリングの際、ロータン峠越えをしてここで大渋滞に巻き込まれて辟易したが、それがまるで嘘だったかのような空き振りである。たまに路線バスや軍関係の車両などが通るが、観光客を乗せた乗用車の交通は一切なし。道は相変わらず悪いが、行きのときと比べて経験値が上がったので、特に大きな困難は感じなかった。マーリーを過ぎると美しい舗装道が現れ、世界でも有数と思われる変化に富んだグニャグニャの山道をフリーラン状態。インドをバイクで旅行していて、これほど爽快だったことはない。

前を見ても誰もいない

下を見ても誰もいない
正午12時頃にはヴァシシュトに到着。今回も山荘風来坊に泊めていただいた。一応昼食にチキンラーメンを出してもらったのだが、足りなかったのでヴァシシュトの市場へ出掛けた。ヴァシシュトにはおいしい日本食を出すレストランがあると聞き、そこへ行ってみた。ヴァシシュトの温泉からさらに奥へ行ったところにあるセブン・スペース(Seven
Space)というレストランである。古い民家を改造して開放しており、それだけで雰囲気はベリーグッド。メニューも、オムライス、うどん、丼物から日本食ターリーまで一通り揃っており、新鮮な牛乳を使って作ったプリンも出している。当然、日本人が作り方を教えたのだが、現在のところ日本人は常駐していないようである。試しに親子丼を注文してみたが、米がインド米であることを除けば、普通においしい親子丼であった。日本人の溜まり場になっているとのことであったが、僕が行ったのは3時頃だったためか、客は他に誰もいなかった。

セブン・スペース

客席
ヴァシシュトに来たのはこれで3回目になるが、いつもツーリングの中継地点として利用しているため、あまり隅々まで歩き回っていない。ヴァシシュトが目的で来ている訳ではなく、あくまで休憩が第一のため、あまりヴァシシュトを深く掘り下げようという気持ちが今までなかった。しかし、セブン・スペースで食事をした後、ちょっと思い立って散歩してみたら、セブン・スペースの建物に負けないような立派な古い民家が周辺には林立しており、圧倒された。村のちょっとした貯水池や井戸などに見られる石の造形も相当古そうだったし、少し奥に入ると、村の女性たちがアンティークな機織り機で機織りをしながらおしゃべりをしており、まるで数百年タイムスリップしたかのようであった。ヴァシシュトはインドの中でも特に、日本人を含む外国人の長期滞在者が多い場所だが、それだけの魅力があるところなんだろうと共感できた。ただ、観光地化と近代化のスピードも早く、村のあちこちで無個性な近代的家屋の建築が進んでいた。市場もパハール・ガンジ化が進行して久しく、外国人旅行者には便利だが、デリーで普通に暮らす者の目には異質な空間、異質な人間関係が広がっている。ヴァシシュトまで足を伸ばして来ているマナーリー滞在中のインド人避暑客も多く、特に温泉周辺は常に大混雑だ。長く滞在するなら、ケーロンの方がまだ落ち着ける。

ベランダで機織りする村の女性
風来坊では大体、民宿風に、夕食時に森田さん夫妻と宿泊客が一緒にテーブルを囲むことになる。サービスのビールの杯を傾けながら、ヒマーラヤに関する森田さんの体験談や自慢話に耳を傾けるというのが一種の通過儀礼となっている。今日は偶然、近所にお住まいのチューリップの安部俊幸さんが風来坊に訪ねて来ており、安倍さんを交えての夕食となった。世代がかなり違うし、チューリップと聞いてもすぐに代表曲が浮かんで来る訳ではなくて本当に申し訳なかったのだが(「心の旅」とか「サボテンの花」とかぐらいか)、ビートルズ好きということで接点があり、意外にも話が盛り上がった。ビートルズの偉大さを改めて思い知った。
本日の走行距離118.2km、本日までの総走行距離1160.5km。
今日はヴァシシュトから山を下り、平地を目指す。前回キンナウル・スピティ周回ツーリングのときは、一種の挑戦として、ヴァシシュトからデリーまで1日で走破してしまったのだが、今回はなるべく楽にマナーリー~デリーを往復することをテーマに、どこか途中で1泊することにした。いくつか候補はあった。森田さんに勧められたのは、シヴァーリク山脈の麓にあるナーラーガル(Nalagarh)の宮殿ホテルであった。しかし、調べてみたところ、最低でも1泊3,000ルピー以上するようで、予算オーバーだったので、ナーラーガルは諦めることにした。代わりにハリヤーナー州のピンジャウル(Pinjore)がちょうどいい位置にあったので、ピンジャウルで1泊してデリーを目指す計画を立てた。
ヴァシシュトを出発したのは午前8時過ぎ。メインロードであるマナーリー~クッルー側のビャース河西岸の道路ではなく、裏道であるヴァシシュト~ナッガル側のビャース河東岸の道を通って南下した。この道はそのままクッルーのバイパスに連結し、空港があるブンタル(Bhuntar)まで出る。ブンタルで橋を渡って西岸に移った。ブンタルの交差点を東へ進めば、ヒッピーの楽園とされるパールヴァティー谷になる。
ブンタルから広い舗装道をずっと進むと、やがてアウトのトンネルに出る。このトンネルを抜けて右へ向かい、ビャース河すれすれの切り立った崖の道を進む。もうこの辺りになると標高もかなり下がり、暑さを感じるようになった。パーンドー(Pandoh)を過ぎた辺りでセーターを脱いだ。ヒマーチャル・プラデーシュ州のヘソとなっているマンディー(Mandi)を過ぎ、スンダルナガル(Sundernagar)、ビラースプル(Bilaspur)、スワールガート(Swarghat)を越え、ようやく平地に着いたのは午後2時頃であった。ここまでほとんど休憩なしに走行した。
もしナーラーガルやピンジャウル方面へ向かう場合、山道の終点にある、ヒマーチャル・プラデーシュ州とパンジャーブ州の州境の検問を過ぎたら、すぐに左へ曲がらなければならない。ヒマーチャル・プラデーシュ州側から来ると特に表示がなく分かりにくいが、左手に大きな工場が見えるので、それに向かって進むことを念頭に置いておけばいいだろう。一応まっすぐ進んでも、チャンディーガル経由でデリーに行くことが出来るが、遠回りになるし、市街地を通り抜けなければならなくなる。実はキンナウル・スピティ周回ツーリングのときもこのナーラーガルの道を通ろうとしていたのだが、左へ折れる道に気付かずに直進してしまった。今回もうっかり見過ごすところであったが、「山道を下りたらすぐ左」と気を付けていたので、何とか軌道修正することが出来た。
この道は必ずしもいい状態ではなかった。1車線しかない部分がほとんどであるし、舗装もちゃんとしていないし、トラックやバスなどの交通量も多い。どうやらこの道を通るとヒマーチャル・プラデーシュ州から直接ハリヤーナー州に入ることが出来て、州を越える度に通行税を払わなければならない車両は税金を浮かすことが出来るらしい(二輪車は無税)。だから道も敢えて整備されないし、交通量も多いのである。
さすがに何も食べずに山を下りて来て空腹だったので、午後2時15分頃にナーラーガルの手前にあるホテル・リバー・ビュー(Hotel River
View)というレストランで昼食を食べた。もう平地なので酷暑期の酷暑は標高に守られずにそのまま襲いかかって来る。空腹ながら食欲があまり出ず、注文したターリーを全て食べきれなかった。午後2時45分頃に出発。途中、橋が崩落した部分が2ヶ所あり、干上がった川底を進まなければならなかった。本当にわざとやっているとしか思えないくらい道が悪い。一旦パンジャーブ州に入っていたのだが、ナーラーガル辺りは再びヒマーチャル・プラデーシュ州になる。遠くに見えるナーラーガルの宮殿ホテルを横目で見ながら、ナーラーガルの市街地を通り抜け、ピンジャウルを目指した。ハリヤーナー州のピンジャウルに到着したのは午後4時頃であった。
ピンジャウルは、「マハーバーラタ」の主人公パーンダヴァ5王子が滞在したとされる歴史ある町である。元々パンチプラと呼ばれていたのが、パンジプル、ピンジャウルと訛ったようだ。だが、現在ピンジャウルが有名なのは、当地にあるムガル庭園のおかげである。17世紀に建造されたムガル庭園は、現在ではパティヤーラー王国のマハーラージャー・ヤーダヴィンドラ・スィンにちなんで、ヤーダヴィンドラ・ガーデンと名付けられ、観光地として開放されている。そのムガル庭園のすぐ隣に、ハリヤーナー州観光局経営のブジャリガー・モーテル(Budgerigar
Motel)がある。ここに宿泊することにした。一番安い部屋で1,600ルピーと安くはなかったが、ACなど完備で、部屋は申し分なかった。マナーリー~デリー間の中継宿泊地としては理想的である。
ホテルにチェックインしてシャワーを浴びた後、早速ヤーダヴィンドラ・ガーデンを見に行った。入場料は20ルピー。ムガル帝国の歴代皇帝はガーデニング愛好者で、インド各地に庭園を残している。ジャンムー&カシュミール州のシュリーナガルにある庭園などは非常に有名である。フマーユーン廟やタージ・マハルも、墓廟を中心とした庭園となっている。ピンジャウルにある庭園は、アウラングゼーブの親戚フィダーイー・カーンによって設計されたとされている。

ヤーダヴィンドラ・ガーデン

奥に見えるのはシーシュ・マハル
ヤーダヴィンドラ・ガーデンの近くには、9~11世紀のものとされるビーマー女神寺院もある。そこも見てみようとしたのだが、入場は午前10時~午後5時までで、そのとき既に5時を回っており、入れさせてもらえなかった。
本日の走行距離291.0km、本日までの総走行距離1451.5km。
早朝、荷造りする間にチャーイを注文したのだが来ず。荷造りも終わってしまったので、そのままチャーイは放っておいてチェックアウトした。午前7時半にピンジャウルを出発し、デリーを目指した。
ピンジャウル~デリー間の移動で特筆すべきことは多くない。ピンジャウルからパンチクラー(Panchkula)に続く道は現在道路工事中で分かりにくくなっているが、完成すればデリーからシムラーまで一直線の道路が出来るだろう。アンバーラーを過ぎれば天下のNH1(国道1号線)、中央分離帯のある片側2車線以上の広い道になっているので、走行に支障はない。午前9時半前にはピプリー(Pipli)を通過した。ピプリーを過ぎた辺りにあるダーバーで朝食休憩をし、午前10時に再びNH1を南下。午前10時半にはカルナール(Karnal)、午前11時にはパーニーパト(Panipat)を通過し、ぐんぐんデリーに近付いて行った。
さすがに酷暑期の日中を走行しているので暑さは尋常ではなかったが、今日は幸いにも空に霞がかかっており、風も突風と言えるほど強く、比較的暑さが抑えられていたのではないかと思う。デリーの州境を越えた後、リング・ロードを時計回りに回って南デリーに向かったが、ワーズィラーバード周辺で工事のために大きな渋滞があった他はスムーズに走行できた。今日はちょうどチベット暦におけるブッダ生誕祭サガ・ダワ(Saga
Dawa)であり、チベット人が多く住んでいるマジュヌー・カ・ティッラーやISBT辺りで数ヶ所、道行く人へシャルバトの無料配給が行われていた。この暑さの中、冷たいシャルバトほどありがたいものはない。ブッダに感謝しながら数杯シャルバトをいただいた。
午後1時過ぎにカールカージーの自宅に到着。10日間に渡った今回の長期ツーリングは無事に幕を閉じた。
本日の走行距離275.7km、今回のツーリングの総走行距離1727.2km。

5月下旬の時期にデリーからマナーリー経由でレー行きを目指したのだが、今回はバララチャ峠の雪に阻まれ、失敗に終わってしまった。マナーリー~レー間にはいくつもの峠が行く手を阻んでいるのだが、道の開閉に密接に関わっているのが、ヒマーチャル・プラデーシュ州にあるロータン峠(Rohtang
La; 標高3,978m)とバララチャ峠(Baralacha La; 標高4,891m)である。ラダック地方にはもっと標高の高い峠があるのだが、そちらは降雪量が少ないため、大きな問題とはならない。問題なのは豪雪のロータン峠とバララチャ峠であり、これら2つの峠の除雪作業が済めば、マナーリー・レー・ロードがオープンしたことになる。デリーを出る前に、「ロータン峠は開いたが、バララチャ峠はまだ開いていない」との情報を受け取っていたのだが、数日待っていればバララチャ峠も開通するだろうという予測の下、見切り発進した。マナーリー・レー・ロードの中継地点となるケーロン(Keylong;
標高3,348m)で数日間待ったものの、結局バララチャ峠は開かなかった。遂には自らの目でバララチャ峠の状態を見るためにバイクを走らせたのだが、そこで見たのは、峠道を塞ぐ圧倒的な量の雪で、それはレー行きを諦めさせるに十分な自然の驚異かつ脅威であった。
もちろん、バララチャ峠開通までひたすら待ち続けるという選択肢はあった。あわよくば今年のマナーリー経由陸路レー入り一番乗りを狙っていたのだが、マナーリー・レー・ロードを途中まで走ってみた結果、「必殺仕分け人」蓮舫参議院議員ではないが、このルートに限っては1番を目指しても意味がないと感じた。1番乗りを果たすには開通直後にバララチャ峠を越えることになるが、そうした場合、シーズン中はルート上に点在するテント集落(宿泊、食事、休憩などができる)などがまだ準備されていない可能性が高く、自分でテントを持参しない限り、1日でレーまで走破することを余儀なくされる。バララチャ峠を越えたら標高はしばらく4,200mより下がらず、酷暑期でも夜は氷点下の世界で、高山病になる確率が限りなく高いし、途中でバイクが故障する可能性もある。そういうときに、開通直後では助けてくれる人はまずいないと考えた方がいい。シーズン中なら、僻地とは言え往来はあるので、何かトラブルが起こっても何とかなることが期待される。また、まだ路面上に雪が残っている状態のところをバイクで走るのはかなり危険である。たとえ除雪作業がある程度完了し、何とか通行できるようになったとしても、その道をすぐにバイクで走るのはかなり大変だ。往来によって路面上の雪が踏み固められ、のけられるのを待った方が賢い。
マナーリー・レー・ツーリングを志す以上、悪路を恐れてはならない。だが、結局ツーリングの楽しみというのは爽快な走行をしているときにもっとも感じることが出来るものであり、道路がきれいに舗装されていればそれに越したことはない。現在マナーリー・レー・ロードは急ピッチで舗装作業が行われているが、それでも開通時に全ての道が舗装された状態になることはあり得ない。舗装作業はマナーリー・レー・ロードが開いている以上ずっと行われるので、開通してから時間が経てば経つほど、舗装道の距離も増える計算になる。それも、開通直後に無理してこのルートをバイクで走行する意味があまりない理由のひとつになる。結局、ある程度時間が経ってからの方が快適なライディングが出来るのである。
そういう訳で今回はレー行きを諦めた。また機会があれば挑戦してみたいが、果たしてその時が来るかどうかは分からない。しかし、途中まで走った結果、いくつか装備品の不足を感じた。ひとつはブーツである。出発前にブーツを購入しようかと考えていたのだが、インドにあまりいいブーツがないこともあり、今回結局ブーツは買わず、普通の靴を履いてツーリングに出掛けた。普通のツーリングならそれでも全く問題ないのだが、標高5,000m前後の峠道を越えるツーリングでは、やはりブーツはあった方がいい。インドの山道では道路が雪解け水などで河になっている部分が必ずあり、そこをバイクで越える際、普通の靴だとどうしても水が靴の中に入って来てしまう。標高の高い場所では、靴の中に侵入して来た水はそのまま凍り付く。足が凍り付くと体温は急速に奪われ、危険な状態となる。どう考えてもブーツは必需品だ。また、日焼け止めも必要だと感じた。今回全く日焼け対策をしていなかったのだが、着実に日焼けをしており、気付いたら顔が真っ黒になってしまっていた。ロータン峠やバララチャ峠での雪焼けも入っているかもしれない。防寒具は持てるだけ持って行った方がいい。ヤクや羊の毛を編んだ手袋、靴下、帽子、ショールなどの伝統手工芸品やその他現代的な防寒具がマナーリー、ヴァシシュト、ケーロンなどで入手可能なので、それらを現地調達して使ってもいいだろう。僕はヴァシシュトでヤクのショールや靴下を購入し、ケーロンで冬用グローブを購入した。標高の高いところはとにかく寒い。デリーにいると想像できないが、本当に寒い。しかしここ数年日本で売られているユニクロのヒートテックなどの保温下着はかなり役立った。標高の高いところではヒートテックの長袖シャツとロングタイツを常に着用していたが、おかげでかなり寒さに耐えることが出来た。
レー行きを諦めたことで、今回のツーリングの特色は、ジャローリー峠越えとラーハウル観光の2点となった。ジャローリー峠も冬期は凍結するようだが、5月に通る分には全く雪の心配はない。それでもかなり勾配が急な悪路を上り下りすることになるため、難易度は決して低くない。峠からの景色も美しく、デリーからジャローリー峠のみを目指してツーリングしても十分な達成感が得られるだろう。ラーハウルは、ヒマーチャル・プラデーシュ州の中でもっとも観光されていない谷だと言えるだろう。マナーリーからレーを目指すと必ず通ることになるが、多くの旅行者にとってはやはり単なる通り道に過ぎず、その魅力に迫らずにラダックへ去ってしまうことがほとんどだと思われる。しかし、谷の美しさはそんな通りすがりの旅行者の目にも決して見過ごされることはない。僕が2002年にマナーリーからレーまでの道を1日で走破する乗り合い弾丸ジープに乗ったときも、ラーハウル谷の美しさは強烈に印象に残った。その後のラダックの景色もまた強烈で、そのおかげでラーハウル谷の美しさの印象が薄れてしまいがちなのが難点なのだが、あの頃の僕はちゃんとラーハウル谷を称賛することを忘れていなかった。2002年7月13日の日記にはこんなことが書いてある。
・・・マンディーからマナーリーまでの道も十分すごかったが、このマナーリーからレーの道はもっとすごい。ヒマーチャル・プラデーシュ州の真髄というか、もう何とも形容しがたい圧倒的な光景だ。四方を何千メートルもの高さの山で囲まれ、激流が谷間を流れ、しかしそれでもそこに村があり、畑があり、人間が住んでいる。道は山の中腹部を通っているので、そこから下を眺めれば、まるで飛行機の中から地上を覗き見ているような感覚だ。まさに「風の谷のナウシカ」に出て来たあの村のようだった。外の景色を眺めていて全く退屈しなかった。ヒマーチャル・プラデーシュ州にはまってしまいそうだ。
あれから8年後にラーハウル谷をここまでしゃぶりつくすことになろうとは、全く予想していなかった。だが、漠然と、この谷をゆっくり観光してみたら楽しいだろうということは考えていた覚えがあり、それが8年の歳月を経て実現したとも考えられる。レーに行けなかったことは残念だが、代わりにラーハウル谷を巡ることが出来たのは幸いであった。
今回はあらゆる神様にバララチャ峠の開通を祈った。出発前にはニザームッディーン廟で祈ったし、ラーハウル谷に着いてからはトリロークナート寺院、マルクラー女神寺院、カルダン・ゴンパ、シャシュル・ゴンパで祈った。しかし結局バララチャ峠は開かなかった。日頃の善行が足りなかったか、お布施が足りなかったか。とは言うものの、バララチャ峠以外は不思議とうまく行った旅行であり、それは神様のご加護があったのかもしれない。バララチャ峠を越えられなかったのも、今はその時機ではないという神の意志が働いたのだと考えれば何とか納得が行く。
それはともかく、涼しい地域を巡って来た後のデリーの暑さはすさまじ過ぎて脳が働かない。慣れるのに2、3日かかりそうだ。
10日間に渡る山間部のツーリングから帰って来て、デリーの暑さにまいっていたため、冷房の効いた場所へ逃げようと映画「Kites」を見に行った。5月21日公開の新作ヒンディー語映画であり、今年の期待作の1本である。監督は「Murder」(2004年)、「Gangster」(2006年)、「Life...
In A Metro」(2007年)で有名なアヌラーグ・バス。しかし、ラーケーシュ・ローシャン、ラージェーシュ・ローシャン、リティク・ローシャンのローシャン一族がそれぞれプロデューサー、音楽監督、主演を務めており、事実上「Koi...
Mil Gaya」(2003年)や「Krrish」(2006年)に連なるローシャン映画である。最初から国際市場を狙った作品で、ヒンディー語版「Kites」の他、英語版「Kites:
The Remix」の公開も予定されている。
題名:Kites
読み:カイツ
意味:凧
邦題:カイツ
監督:アヌラーグ・バス
制作:ラーケーシュ・ローシャン
音楽:ラージェーシュ・ローシャン
歌詞:ナスィール・ファラーズ、アースィフ・アリー・ベーグ
出演:リティク・ローシャン、バーバラ・モリ、カビール・ベーディー、カンガナー・ラーナーウト、ニック・ブラウンなど
備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。
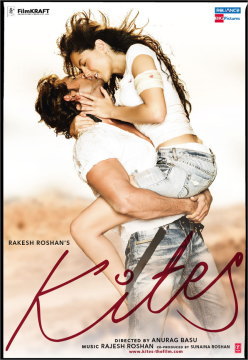
リティク・ローシャン(下)とバーバラ・モリ(上)
| あらすじ |
ラスベガスで一攫千金を夢見てあらゆる仕事に手を染めていたインド人J(リティク・ローシャン)はある日、大手カジノ「プラザ」のオーナー、ボブ(カビール・ベーディー)の娘、ジーナー(カンガナー・ラーナーウト)と出会う。ジーナーは、Jのダンス教室の生徒であった。最初はジーナーのことを気違い女と考えていたが、彼女が億万長者の娘であることを知ると、これぞ一攫千金のチャンスと、ジーナーに近付く。2人はダンスコンペティションにペアで出演して優勝し、ボブにも仲を認めてもらう。Jの人生は一気に加速した。
ジーナーにはトニー(ニック・ブラウン)という兄がいた。Jはトニーの婚約式に招待される。そこで目にしたトニーの婚約者ナターシャ(バーバラ・モリ)とは以前面識があった。Jはグリーンカード目当ての移民のために偽装結婚のバイトもしていたが、ナターシャはそのときJと結婚した1人で、メキシコからの不法移民であった。
結婚式前夜、Jはナターシャを呼び出す。結婚する前に離婚しなければ、というのが口実であった。だが、お互い何となく惹かれ合っていた2人は、そのままナターシャの家で抱き合ってしまう。そこへトニーが乱入して来る。Jは思わずトニーに銃を突き付け、ナターシャはトニーを殴って気絶させてしまう。Jとナターシャは逃げ出す。
ボブとトニーは警察を動員し、Jとナターシャを捜索し出す。2人は何度も警察に捕まりそうになりながら、Jの親友ロビンの助けも借りて、トニーから大金をせしめてメキシコへ逃げ出す。そこで2人は結婚式を挙げる。ところがトニーはメキシコまで追って来ており、ロビンが殺されてしまう。Jも銃弾を受けるがナターシャは何とか逃げ、彼を列車の中に隠す。
Jはメキシコ人に発見され、治療を受ける。Jはメキシコの荒野を歩きながらナターシャを探す。やがてナターシャと別れた駅に辿り着き、そこで落とした携帯電話を見つける。携帯電話にはナターシャからのメッセージが入っていた――私はもう行く。私のことは忘れて。なぜだか分からないJは、トニーから逃げながらラスベガスまで戻り、トニーの運転手ジャマールと連絡を取る。ジャマールは、ナターシャは崖から落ちて死んだことを伝える。Jはナターシャが死んだ場所まで行き、崖から飛び降りる。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
アヌラーグ・バス監督らしい、狂おし系のロマンス映画であった。本当はこういう映画はイムラーン・ハーシュミーがもっとも得意とするのだが、リティク・ローシャンも十分に狂おしさを出せていた。
あらすじは時系列に沿って書いたが、映画では「現在」と「過去」のシーンが交互に入り、徐々に主人公のJやヒロインのナターシャの身に起こった「過去」が明らかにされて行く。だが、いきなり全てが明かされず、三段仕掛けとなっていた。まずはナターシャの家でJがトニーに発砲されるところまでが明かされ、それが「現在」における、瀕死状態で発見されるシーンにつながっていると思わされる。だが、次に「過去」のシーンに移行すると、実際にはそのときJはトニーの銃を避けており、逆にトニーがナターシャに殴打されて気絶してしまっていたことが明かされる。そしてその後の逃亡劇がさらに描写され、メキシコにおけるJとナターシャの結婚と、メキシコまで追って来たトニーから逃げるシーンが描写される。そして最後まで明かされなかったのは、ナターシャの行方である。「私はもう行く。私のことは忘れて」というメッセージだけが残され、彼女がどこへ行ったか分からなかったJは、彼女を追い求めてラスベガスまで戻って来る。そこで知らされたのはナターシャの死であった。Jはナターシャが死んだ断崖絶壁まで行って、自らも身を投げる。インド映画には珍しい悲恋映画であった。
映画は、グローバルな観客を念頭に置いたグローバルな作りになっており、もはやインド映画の枠組みを完全に超越している。主な登場人物はインド人だが、ヒロインはメキシコ人、舞台は米国とメキシコ(実際のロケは米国のみ)で、インドらしさは極度に排除されている。グローバル映画として脱皮しようとする昨今のインド映画の最たる例であり、「My
Name Is Khan」(2010年)と並んで、今年のインド映画の傾向を論じる際に避けられない作品となるだろう。だが、何度も主張するように、グローバル化を目指せば目指すほど、インド映画はハリウッド映画と真っ向から戦わなければならなくなる。やや落ち目だとは言え、世界中に市場を持ち、潤沢な資金源と高度な技術力に裏打ちされたハリウッドとタイマンを張るのは容易なことではない。その際、インド映画らしさを捨ててハリウッドと戦うのは賢明な選択ではないだろう。インド映画らしさを維持しながらグローバルな観客にアピールして行く方向性を模索し、ハリウッド映画と棲み分けをしながら共存することが、インド映画の将来にとってより有益だと感じる。ハリウッドっぽい映画は既にハリウッドが作っているのだから、ボリウッドがそれに追従する必要はないのである。
もし万一「Kites」がグローバルな観客に受けたとしても、それはインド国内でのヒットを必ずしも意味しない。「Kites」はハリウッド的映画作りを目指すあまり、インド国内のインド人の趣向を無視しており、彼らにとって単調で退屈な映画になってしまっている。全体的に低調で乾燥しすぎなのである。もう少しハイテンポで笑いを織り交ぜた展開にしないと、インド人を楽しませることは出来ないだろう。Jとナターシャの結婚式がメキシコ式で行われていたが、これもインド人観客からしたら滑稽にしか映らないだろう。インド文化をここまで排除するのは、インド市場を考えた場合、得策とは言えない。グローバル化を目指すボリウッドのドーナツ化現象が最近進行しているように思えてならない。
これでストーリーの本筋がしっかりしていればまだ弱点を補えたのだが、それほど作り込まれたストーリーでもなかった。もっとも弱いのは、バーバラ・モリ演じるナターシャのキャラクターである。なぜトニーほどの億万長者御曹司が違法移民のナターシャに惚れたのか、主人公Jまでもがナターシャに熱を上げるのか、ほとんど説明されていない。絶世の美女という訳でもないし、何か彼女にしかないものがある訳でもない。むしろJとナターシャは言葉が通じず、コミュニケーションギャップに悩まされている。「恋愛に言葉は必要ない」という格言を信じたとしても、このストーリーには説得力がないし、目新しさもない。
ちなみにバーバラ・モリには日本人の血が入っている。父方の祖父が日本人である。他にはウルグアイ人やメキシコ人の血が入っており、混血となっている。「モリ」という名字も日本人の名字「森」から来ているのではないかと思われる。ただ、国籍はウルグアイのようである。
悪役トニーを演じたニック・ブラウンのキャラクターも深みがなかったし、カビール・ベーディー演じるボブも出番が少なくて活かされていなかった。カンガナー・ラーナーウト演じるジーニーもほとんど序盤のみの出演で、最後で思い出したように突然現れてJに重傷を負わせる。キャスティングがうまく噛み合っていなかった映画であった。
それでも主演のリティク・ローシャンは自身の長所を全て注ぎ込む演技で、国際的アピール力を発揮していた。特に「Fire」ではリティク・ローシャンの超絶ダンスを見ることが出来る。右手の親指が2本あることが世界市場でどう受け止められるか不明であるが、この映画をきっかけに何か国際的プロジェクトに呼ばれることもあるかもしれない。
ちなみに、題名「Kites」には、天空に舞う2つの凧は、いつか一方の凧の糸を切り落としてしまう、つまり、Jとナターシャの危険な恋愛が象徴されていた。
「Kites」の大きな弱点のひとつは音楽である。ラージェーシュ・ローシャンは既に時代遅れの音楽監督であり、彼の作る音楽は「Kites」の雰囲気に全くフィットしていなかった。唯一の聴き所は、リティク・ローシャン自身が歌う「Kites
In The Sky」である。彼が歌声を披露したのはこれが初めてのはずだ。もっとも、英語版「Kites: The Remix」では「Fire」以外のミュージカルシーンはカットされているようだ。
言語は英語ミックスのヒンディー語。メキシコ人のナターシャは英語が得意ではないという設定で、スペイン語を話すが、大部分のスペイン語台詞には英語字幕が付く。
「Kites」は、「My Name Is Khan」と同様に、国際市場、グローバルな観客をターゲットに作られた野心的ボリウッド映画である。しかし、インド映画らしさがなく、インド国内の観客が置き去りにされていると同時に、ストーリーの陳腐さから、国際的にも受け容れられることはあまりないように感じる。インド映画らしさを求める昔からのインド映画ファンには退屈に感じるだろうし、一般の映画愛好家にもアピール出来るものは少ない。決してつまらない映画ではないし、いかにも映画らしい工夫がしてあったりするのだが、「帯に短したすきに長し」な作品だと評せざるをえない。
|
|



