2月末からクリケット・ワールドカップが開催されている影響で、ヒンディー語映画界は自粛モードに入っており、ここ1ヶ月間まともな新作は公開されなかった。だが、そのワールドカップも4月2日の決勝戦でもって終了するため、今週から映画公開が始まった。本日公開のヒンディー語映画は主に2本。「Game」と「F.A.L.T.U.」である。どちらも新人監督の作品になるが、前者はスリラー、後者はコメディーで作りは全く逆だ。
「Game」の監督はアビナイ・デーオ。「Dil Chahta Hai」(2001年)、「Don」(2006年)、「Rock On!!」(2008年)などでコンビを組んでいるリテーシュ・スィドワーニーとファルハーン・アクタルがプロデュースしている。主演はアビシェーク・バッチャン他。マルチヒロイン型映画だが、最近「Manu
Weds Tanu」(2011年)が当たって絶好調のカンガナー・ラーナーウトがメインヒロインと言える。
題名:Game
読み:ゲーム
意味:ゲーム
邦題:ゲーム
監督:アビナイ・デーオ(新人)
制作:リテーシュ・スィドワーニー、ファルハーン・アクタル
音楽:シャンカル・エヘサーン・ロイ
歌詞:ジャーヴェード・アクタル
振付:ヴァイバヴィー・マーチャント、シヤーマク・ダーヴァル
衣装:ジャイマル・オベドラ
出演:アビシェーク・バッチャン、カンガナー・ラーナーウト、アヌパム・ケール、ボーマン・イーラーニー、シャハーナー・ゴースワーミー、ガウハル・カーン、ジミー・シェールギル、サラ・ジェーン・ディアス(新人)
備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左からカンガナー・ラーナーウト、アビシェーク・バッチャン、サラ・ジェーン・ディアス
| あらすじ |
世界各地に住み全く接点のない4人――トルコのイスタンブール在住カジノ・オーナー、ニール・メーナン(アビシェーク・バッチャン)、タイのバンコク在住政治家で新政党を立ち上げ次期首相を狙うOPラムゼイ(ボーマン・イーラーニー)、インドのムンバイー在住ボリウッド・スーパースター、ヴィクラム・カプール(ジミー・シェールギル)、英国のロンドン在住犯罪ジャーナリスト、ティシャー・カンナー(シャハーナー・ゴースワーミー)――のもとに、世界的大富豪カビール・マロートラー(アヌパム・ケール)から手紙が届き、彼らはギリシアのサモスに招待される。4人はそれぞれ問題を抱えており、それを解決するためにサモスへ行くことを決意する。
サモスの孤島に位置するカビールの豪邸にやって来た4人をカビールの秘書サマラー・シュロフ(ガウハル・カーン)が迎える。カビールは4人を前に、1人の女性の話を始める。
その女性の名前はマーヤー(サラ・ジェーン・ディアス)。マーヤーは幼くして人身売買の餌食となり、バンコクの孤児院に送られた。その孤児院は当時ラムゼイが経営していたが、その実態は売春宿であった。マーヤーは幼少時からその過酷な環境の中で育つ。だが、遂にマーヤーは逃亡に成功し、流れ流れてイスタンブールのカジノでダンサーをして生計を立てるようになる。そのカジノのオーナーがニールであった。だが、ニールの裏の顔は麻薬のブローカーであった。マーヤーもその片棒を担ぐようになる。その後マーヤーはムンバイーに戻るが、夜道を歩いているときに交通事故に遭う。彼女を牽いたのがヴィクラムであった。ヴィクラムは事故を隠蔽しようとし、マーヤーを埋めようとする。だがこのときマーヤーはまだ生きていた。ヴィクラムもそれに気付いていたが、そのまま生き埋めにしてしまった。
カビールが明かしたところによると、マーヤーは彼の娘であった。マーヤーはカビールの元恋人の子であったが、彼の子供を身ごもっていたことは3年前に初めて分かった。そのときから、マーヤーの人生を狂わした人間に復讐しようと計画を練っていたのだった。また、マーヤーは双子であった。マーヤーの姉妹、つまりカビールのもう1人の娘こそがティシャーであることもカビールは明かす。だが、ティシャーはカビールを父親として受け容れようとはしなかった。また、ラムゼイ、ヴィクラム、ニールも罠にはめられたことを怒るが、絶海の孤島にあるカビールの邸宅から逃げることは不可能であった。明日、ロンドンに拠点を置く国際監視機関からエージェントがやって来ることになっていた。4人はそれぞれ不安な夜を過ごす。
ところが翌朝、一発の銃声が響く。カビールの書斎からのようであった。扉は中から固く閉ざされていた。真っ先に駆けつけたのはニールとサマラーであった。ニールは扉を破ろうとするが、サマラーは扉の横のガラスを割って内側から鍵を開けた。中へ入ってみるとカビールは机に突っ伏して死んでいた。拳銃自殺のようであった。国際監視機関からはシヤー・アグニホートリー(カンガナー・ラーナーウト)らオフィサーがやって来て、事件の捜査を始める。シヤーはカビールの死は自殺ではなく他殺の可能性もあることを疑っていたが、確たる証拠はなかった。ニール、ラムゼイ、ヴィクラム、ティシャー、サマラーらの取り調べを行ったが、それでも手掛かりは得られなかった。仕方なくニール、ラムゼイ、ヴィクラム、ティシャーを帰すことになった。だが、シヤーは4人それぞれに監視を付けた。特にニールの監視を重視した。
しばらくシヤーはロンドンの本部オフィスから遠隔操作でイスタンブールのニールの監視をしていた。ところがニールは監視をかいくぐって姿をくらます。その頃バンコクではラムゼイが選挙に出馬をしようとしていた。そのときラムゼイの邸宅に侵入し、監視カメラを設置する男がいた。それはなんとニールであった。ニールはラムゼイに電話をし、ラムゼイの過去の秘密が記された「ファイル」を持っていると脅す。ラムゼイは焦って腹心を呼びつけ、自分が過去に行っていた売春斡旋業の隠蔽作業のことなどを問いただす。ところがその場面はニールが設置した監視カメラを通して世界中で放映されてしまっていた。それを知ったラムゼイは心臓発作を起こして憤死する。
シヤーはこの事件を見てニールの仕業だと直感し、今度はヴィクラムに接触するはずだと考え、ムンバイーへ直行する。ちょうどヴィクラムはメイクアップ・ドレッサーの殺人事件の渦中にいた。シヤーの読み通りニールはムンバイーに来ており、ヴィクラムを待ち伏せして瀕死の状態にし、マーヤーを殺したことを警察に自白させていた。警察に自白した後、ヴィクラムはリストカットして自殺する。
ニールはマーヤーのためにこれらのことをしていた。実はマーヤーはニールの恋人であった。しかし、命を狙われる危険な仕事をしていたニールは、マーヤーを安全な場所に移すためにムンバイーに送ったのだった。だが、マーヤーはそこで交通事故に遭って死んでしまった。今回の事件で彼女の出生から死までの出来事を全て知ってしまったニールは、カビールに代ってラムゼイとヴィクラムに復讐したのだった。また、実はニールは国際監視機関の覆面エージェントだった。そのことをシヤーはずっと知らずにニールを追いかけていたが、ニール自身から明かされ、その後は共にカビールの死について捜査を開始する。
そのとき、ティシャーが自殺未遂をしたというニュースが入って来る。シヤーが駆けつけ事情を聞くと、ティシャーは自殺などしていないと言う。誰かがティシャーの命を狙っていた。シヤーはティシャーの育ての親に、世間にはティシャーが死んだと公表するように助言する。
ニールとシヤーは、カビールの財産を狙った犯行だと考え、カビールの弟イクバールを疑う。しかしイクバールは癌に冒されており、インドの病院で寝たきり状態であった。イクバールが黒幕ではあり得なかった。また、イクバールの娘がいたが、彼女も既に死去していると伝えられた。しかしニールはイクバールの娘がまだ生きているという証拠を掴み、それがサマラーであると考える。サモスに飛んだニールとシヤーはサマラーと対面し、カビール殺害の手口を言い当てる。シヤーはサマラーを逮捕しようとするが、どこからか銃弾が飛んできてシヤーは負傷する。それを撃ったのはカビールとうり二つの人物であった。彼こそがカビールの双子の弟イクバール・マロートラー(アヌパム・ケール)であった。しかしニールは隙を見て逆にイクバールを撃ち殺す。こうして、イクバールが死に、サマラーが逮捕されたことで、事件は一件落着となる。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
基本的なストーリーラインは、外界から遮断された場所に互いに初対面の複数の人間が集められ、そこで殺人事件が起きて、探偵や警察がそれを解決するという、サスペンス物の定番、密室殺人事件であった。また、もっとも疑わしい容疑者だった人物が実は捜査機関のエージェントだったという設定も目新しいものではない。密室殺人事件物の映画は低予算映画にありがちだが、一旦密室から犯人候補たちが解放され、インド、タイ、トルコ、英国でストーリーが進む点は新しさがあり、「Game」は予算をかけた作品になっていた。キャストの顔ぶれもある程度豪華である。しかしながら、脚本や編集は決して成熟したものではなく、スパイアクション映画と密室サスペンス映画を中途半端に融合させたような作りで、真犯人も容易に想像できるものであり、映画としての楽しみには欠けた。また、キャストの個性を生かし切れておらず、出演した俳優にとってもあまりプラスにならない映画であった。
アビシェーク・バッチャンのキャラクターは、おそらく「Dhoom」シリーズと同じ路線を狙ったものであろう。だが、まずはカジノのオーナーとして、次に麻薬のブローカーとして、最後に国際監視機関のエージェントとして、設定がコロコロ変わる。それだけならまだしも、やたら戦闘に慣れていること以外、特にエージェントであることを匂わすような伏線が張られていないため、真の正体判明の際にも説得力がない。アビシェークとしても演じにくいキャラクターだったと思うし、うまく演じられてもいなかった。
最大のダウンポイントはカンガナー・ラーナーウトであろう。最近ヴァラエティーに富んだ役を演じるようになり、今年は「Tanu Weds Manu」(2011年)のヒットで好スタートを切ったのだが、「Game」で大きなスピードプレーカーにぶち当たってしまった印象である。元々精神に異常をきたいしているような役は上手かったのだが、今回のような知的で冷徹な女性の役はあまり似合っていないと感じた。特に台詞回しの点で難点を感じた。彼女のハスキーで多少舌足らずな声は、感情を表に表わさないエージェントには適していない。潜在的な演技力は十分にあるのだが、娯楽映画における演技は別物として考えないと今後さらにつまづくことになるだろう。
「Game」は、2007年のミス・インディア、サラ・ジェーン・ディアスのデビュー作である。サラは、ストーリーのキーポイントとなるマーヤー役を演じていた。ほとんど回想シーンのみの出演で、出番は少なく、彼女の将来性について評価できる段階ではない。だが、ストーリー中ではマーヤーとティシャーは双子ということになっていた。ティシャーを演じたのはシャハーナー・ゴースワーミーで、当然顔は全く違う。一応「二卵性双生児だから顔が違ってもおかしくない」という言い訳が台詞中にあったが、どうせだったら片方がダブルロールで対応すべきであった。
ボーマン・イーラーニーやアヌパム・ケールらベテラン俳優陣の演技は全く問題ない。ジミー・シェールギルは最近脇役ばかりになってしまったが、適切な演技をしていた。
音楽はシャンカル・エヘサーン・ロイ。キャバレー風「Mehki Mehki」がもっとも金がかかった群舞で見物だったことを除けば、特筆すべき曲はなかった。タイトル曲の「It's
Game」も退屈な曲だった。
言語は基本的にヒンディー語で、補助的に英語が使われていたが、タイのシーンではタイ語が、トルコのシーンではトルコ語が字幕などなしで使われていた。
「Game」は、ワールドカップに伴う映画空白期間明け映画の第1弾だが、残念ながらクリケット熱を映画に転換できるほどの実力のある映画ではない。「F.A.L.T.U.」の方に期待したい。
映画の裏方の中で、コレオグラファー(振付師)がここまで重視される映画界はインド以外にはなかなかないのではなかろうか。その理由はもちろん、インド映画において依然としてダンスが映画の重要な要素になっているからだ。もちろん監督の腕がもっとも映画の出来を左右するが、ダンスが優れた映画はそれだけで集客力を持ち、映画公開後も人々の記憶に残ることが多い。良質のインド映画は、ストーリーと歌と踊りがうまく調和しているが、それもコレオグラファーの才能に依るところが大きいだろう。
コレオグラファーの出番は当然ダンスシーンということになるが、本番前に、数日から数週間に渡り、主演俳優を含めダンスシーンの出演者たちに振り付けを指導するために、出演者との人間関係は自ずと濃くなる。また、ダンスの指導は演技の指導と同等以上の監督力を要することは想像に難くない。よって、もしかしたらインド映画界で活躍するコレオグラファーは、もっとも監督に近い職業かもしれない。実際、コレオグラファーが監督に転身した例はいくつもある。ヒンディー語映画界でコレオグラファーから監督に転身した人物としてもっとも有名なのは「Om
Shanti Om」(2007年)のファラー・カーンである。同作品中では多数のトップスターたちがカメオ出演しており、監督の人脈の広さを感じさせられた。当然、ダンスシーンも非常に優れたものであった。また、最近ヒンディー語映画界ではダンスシーンがない娯楽映画が徐々に増えて来ているため、コレオグラファーが必要に迫られてメガホンを取るということもあるのかもしれない。
先週の金曜日から公開されたコメディー映画「F.A.L.T.U.」もコレオグラファーとして有名なレモ・ディスーザの初監督作品である。プロデューサーはヴァーシュ・バグナーニー。彼は「Kal
Kissne Dekha」(2009年)で自分の息子ジャッキー・バグナーニーをデビューさせたが、この映画はヒット作にはならなかった。ヴァーシュ・バグナーニーは今回も懲りずにジャッキーを主演に据えて映画を制作。若手俳優中心キャストだが、リテーシュ・デーシュムク、アルシャド・ワールスィー、ボーマン・イーラーニーなど、中堅~ベテラン俳優の助演もある。
題名:F.A.L.T.U.
読み:ファールトゥー
意味:役立たず
邦題:F.A.L.T.U.
監督:レモ・ディスーザ(新人)
制作:ヴァーシュ・バグナーニー
音楽:サチン・ジガル
歌詞:サミール
振付:レモ・ディスーザ
出演:ジャッキー・バグナーニー、プージャー・グプター(新人)、チャンダン・ロイ・サンヤル、アンガド・ベーディー(新人)、アルシャド・ワールスィー、リテーシュ・デーシュムク、ボーマン・イーラーニー、ミトゥン・チャクラボルティー、アクバル・カーン、ダルシャン・ジャリーワーラー
備考:PVRプリヤーで鑑賞。
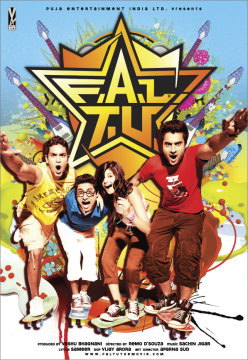
左からアンガド・ベーディー、チャンダン・ロイ・サンヤル、
プージャー・グプター、ジャッキー・バグナーニー
| あらすじ |
リテーシュ(ジャッキー・バグナーニー)、プージャー(プージャー・グプター)、ナンジ(アンガド・ベーディー)とヴィシュヌ(チャンダン・ロイ・サンヤル)は高校の仲良し4人組であった。ヴィシュヌは最終試験で95%のマークを狙う優等生だったが、残りの3人は落ちこぼれだった。リテーシュ、プージャー、ナンジは40%前後の成績を取ってギリギリ卒業し喜ぶ一方、ヴィシュヌは94%の結果に泣いていた。
ヴィシュヌは名門セント・ピーターズ大学に進学する。だが、リテーシュ、プージャー、ナンジの3人はどこにも入学できる大学がなかった。ヴィシュヌの父親ワルダン氏(アクバル・カーン)は高等教育を司るUGCの委員長であり、3人は両親を巻き込んでワルダン氏に何とかしてもらうように頼みに行く。だが、ワルダン氏はヴィシュヌの友人たちを好いておらず、鼻から相手にしなかった。このままではリテーシュは父親(ダルシャン・ジャリーワーラー)の廃品回収屋を継ぐことになり、プージャーは結婚させられ、ナンジは古典音楽家の父親にこっぴどく叩かれることになってしまう。絶体絶命のピンチであった。
そこでリテーシュは自分で偽物の大学を作り出すことにする。大学の名前はファキールチャンド・アンド・ラキールチャンド・トラスト・ユニバーシティーに決め、入学許可証を偽造する。そして新聞に生徒募集の広告を出し、ウェブサイトまで作った。そしてリテーシュ、プージャー、ナンジはその偽造入学許可証を両親に見せる。両親は自分の子供が何とか大学に入学することが出来て大喜びするが、初日に大学まで子供を送って行こうとする。そこでリテーシュらは大学自体をこしらえなくてはならなくなった。リテーシュは何でも屋のグーグル(アルシャド・ワールスィー)に相談する。
グーグルはムンバイーから285kmのパンチガニーにある廃校になった大学を見つけ、それをリテーシュらに提供する。リテーシュらはその大学を1日できれいにし、大学らしく外見を整える。また、グーグルは学生役としてジュニア・アーティスト(エキストラ専門俳優)たちを呼び、大学の雰囲気を作り出す準備をした。また、校長としてバージーラーオ(リテーシュ・デーシュムク)という落ちこぼれ教師を引き抜いて来る。バージーラーオは校長になるのが夢で、勤務していた学校を止めて偽造大学に来てしまう。
大学初日。大勢の学生役ジュニア・アーティストたちが集まり、リテーシュらも両親と共に大学を訪れた。リテーシュの父親は大学の名前の頭文字を取って「FALTU(ファールトゥー;役立たず)」と呼んだ。それがそのままこの大学の愛称となった。両親たちはキャンパスの雰囲気や校長の人柄に満足して帰って行く。とりあえず山場を越えたことで胸をなで下ろしたリテーシュらは、グーグルに礼を言って、ジュニア・アーティストたちを帰してもらう。
ところがキャンパスにはジュニア・アーティストたちが帰った後も大勢の若者たちが残っていた。どうやら新聞に掲載した偽の広告や偽のウェブサイトを見てやって来てしまった「入学者」たちであった。リテーシュらは彼らに、この大学が偽物であることを説明するが、彼らも落ちこぼれでどこにも行き場がなく仕方なくこの大学にやって来た身の上で、もはや帰る場所がなかった。彼らは意地でもこのファールトゥーに居座ると言い出す。そこでグーグルは、本当にファールトゥーを大学にしてしまうことにする。「ファールトゥー生」たちは大喜びし、以来連日パーティーが続く。名門セント・ピーターズ大学に通っていたヴィシュヌも、こっちの方が楽しそうだとファールトゥーに入り浸り、すっかり弾けてしまった。
しかしリテーシュは、このままではファールトゥーはその名の通り落ちこぼれの寄せ集め大学で終わってしまうと考える。そこでファールトゥー生たちに勉強をするように呼びかけるが、元々落ちこぼれの彼らは全く勉強する気になれなかった。終いにはせっかくグーグルが送った教科書を全て焼いてしまう。グーグルとバージーラーオは彼らを見捨てて立ち去ろうとするが、リテーシュは最後のチャンスを求める。そこでバージーラーオは生徒たちに、自分が本当にやりたいことを聞き、ファールトゥーではそれを追求するように提案する。ファールトゥー生たちは、俳優、DJ、トレイナー、シェフ、デザイナーなど、思い思いの趣味や夢を口にし、それに打ち込み始める。先生を呼ぶことは不可能であったが、その道の有名人にビデオでレクチャーをしてもらう。また、リテーシュは大学に通えない他の若者たちのためにもそのビデオをウェブサイトで公開する。
ところがワルダン氏に、息子がセント・ピーターズ大学に通っていないことから、ファールトゥーの存在がばれてしまう。ワルダン氏は即刻ファールトゥーを閉鎖させようとするが、グーグルは裁判所から執行保留命令を手に入れ、7日間の猶予をもらう。その間にファールトゥーを救うために何とかしなければならなかった。そこで、セント・ピーターズ大学で近日中に開催予定の大学対抗文化祭でファールトゥーの実力を見せることにする。文化祭にはUGCのワルダン委員長に加え、人材開発省大臣(ミトゥン・チャクラボルティー)も出席していた。リテーシュらは飛び入り参加し、彼らの前で大学名を伏せて、数字主義の教育を批判する内容の素晴らしいパフォーマンスを見せる。観客はスタンディング・オベーションを送るが、演技者がファールトゥーの学生であることを知るとワルダン氏の態度は一変し、彼らを追い出そうとする。しかし人材開発大臣はそれを止め、ファールトゥーの存在意義を認め、ファールトゥーに大学の地位を正式に与える。
数年後・・・。リテーシュはファールトゥーの経営者になり、ファールトゥーは2000人の学生を擁する大学に成長していた。校長はもちろんバージーラーオであった。また、プージャーはDJに、ヴィシュヌは人気俳優に、ナンジはセレブ・トレーナーになっていた。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
馬鹿馬鹿しいストーリーだった。どの大学にも入学できなかった落ちこぼれ学生たちが自分たちで大学を偽造するなんてことが現実に可能であろうか?しかも中盤からその大学は、各生徒が自分の趣味を追求する大学になるが、もし本当にその道を究めたいならそれぞれの専門学校があるはずで、わざわざ大学に行く必要もない。しかも、それぞれの道を究めた達人たちのレクチャーをビデオ撮影し、それを上映することで授業にするという幼稚な発想の上に成り立っている。全く現実味のないご都合主義の馬鹿映画であった。
しかし、そのメッセージははっきりしている。クライマックスにおけるリテーシュの言葉がそれだ。「35%~70%の成績だった学生はどこへ行けばいいのか。もしどこにも行き所がないなら再試験をさせてくれればいいのに。」簡単に解説すると、インドでは12年生の最後に受ける試験のパーセンテージによって入学できる大学のランクが決まる。日本のように浪人(つまり再試験)というシステムは基本的にないので、つまりは1回きりのその試験の出来如何によってその後の人生が決定する。いわゆる名門校に入学するためには最終試験で95%以上の点数を取らないと難しいようで、どんなに底辺の大学でも45%はないと足きりに引っかかる。リテーシュが言いたかったのは、かいつまんで言えば、この試験で失敗した学生にも再チャンスを、ということであろう。ただ、映画中のリテーシュのキャラから想像するに、もし再チャンスがあったとしても、彼はろくに勉強せずにまた酷い点数を取ることであろう。そういう意味では、せっかく最後に主人公の口を借りて主張したメッセージも破綻している。インドの教育制度の問題点を指摘した、似たようなメッセージの映画では「3
Iditos」(2009年)が思い当たるが、とてもじゃないが完成度では「3 Idiots」の足下にも及ばない。
このようにメチャクチャな映画ではあったが、若い俳優たちのバイタリティーが溢れていた上に、観客の感情操作やコメディーの部分がよく出来ており、見ていてとても楽しい映画だった。こういう無名の若手俳優を起用した映画ではダンスシーンが弱いことが多いのだが、さすがコレオグラファー出身レモ・ディスーザ監督、ダンスシーンも並以上の出来であった。もちろん、アルシャド・ワールスィー、リテーシュ・デーシュムク、ボーマン・イーラーニー、ダルシャン・ジャリーワーラー、そしてミトゥン・チャクラボルティーなどの中堅~ベテラン俳優を要所要所で起用したのも当たっていた。
主演のジャッキー・バグナーニーは「Kal Kissne Dekha」でデビューした男優。相変わらずウダイ・チョープラーに似ているが、前作よりは演技力に成長が見られる。ヒロインのプージャー・グプターは2007年のミス・インディア・ユニバースで本作がデビュー作。バランスの取れた美女という訳ではないが、落ちこぼれ3人組の一角を担い、フレッシュな演技をしていた。ヴィシュヌを演じたチャンダン・ロイ・サンヤルは実は「Kaminey」(2009年)でもっともぶっ飛んだミカイル役を演じ注目を集めた。今回はガリ勉君から道化師への華麗なる転身を演じ、おまけにラギング(新入生いじめ)のシーンまでこなして笑いを取った。老け顔なので大学生には見えないが、そのハッスルは高く買いたい。ナンジを演じたアンガド・ベーディーにとっても「F.A.L.T.U.」はデビュー作である。
上述の新人・若手4人に比べたら、アルシャド・ワールスィーとリテーシュ・デーシュムクは主役級の俳優であるが、今回はサポート役に徹した。2人ともコメディーは得意であるし、リラックスした演技をしていて良かった。ボーマン・イーラーニー、ダルシャン・ジャリーワーラー、ミトゥン・チャクラボルティーなども適材適所であった。
音楽はサチン・ジガルというコンビ。「Teree Sang」(2009年)などを作曲しているが、まだ目立った活躍はない。「F.A.L.T.U.」の音楽は、個性はあまり強くないが、派手なダンスナンバーが多く、サントラCDを買ってもいいと思ったが、店頭では見つけられなかった。もしかしたらダウンロード販売のみかもしれない。冒頭で流れる「Bhoot
Aaya」の歌詞が秀逸。その一部は「小さかったときはトゥインクル・トゥインクルしていた、大きくなった今、トゥインクル・トゥインクルしている」というもの、つまり子供の頃は「きらきら星」を歌っていたが、大きくなったらトゥインクル(女の子)のお尻を追いかけているということである。他にもハード・カウルの「Char
Baj Gaye, Party Abhi Baki Hai」やミカ・スィンの「Fully Faltu」など、ご機嫌なダンスナンバーが多い。サチン・ジガルは将来性のある音楽監督コンビだと言える。
「F.A.L.T.U.」は、主役に有名な俳優がおらず、ストーリーも全く幼稚であるものの、主演俳優の無邪気さ故か、ダンスの秀逸さ故か、グリップ力があり、とても楽しいコメディー映画になっている。同時公開された「Game」は救いようがなかったが、「F.A.L.T.U.」の方は条件付きでお勧めできる映画である。その条件とは・・・脳みそを映画館に持って行かなければ!
ボリウッド・コメディーの1ジャンルとして、複数の既婚男性がそれぞれの妻の目を欺いて浮気を同時進行するストーリーがある。「Masti」(2004年)、「No
Entry」(2005年)、「Shaadi No.1」(2005年)などがその代表例である。「No Entry」で一躍売れっ子監督となったアニース・バーズミーは、その後もコンスタントに「Welcome」(2007年)、「Singh
Is Kinng」(2008年)などのヒットコメディー映画を送り出して来たが、本日公開の新作ヒンディー語映画「Thank You」において、「No
Entry」タイプの浮気コメディーに回帰した。だが、映画タイトルは「Welcome」や前作「No Problem」(2010年)と同じセンスで、英語の挨拶にしてある。主演はアクシャイ・クマール。アニース・バーズミー監督とアクシャイ・クマールは過去に「Welcome」と「Singh
Is Kinng」を成功させている。マルチヒロイン型映画だが、主演扱いはソーナム・カプール。ただ、アクシャイ・クマールとソーナム・カプールは映画中ではカップルではない。この2人以外は単独でスターパワーや集客力がある俳優とは言い難いが、面白い顔合わせではある。特別出演のマッリカー・シェーラーワトとヴィディヤー・バーランを合わせるとさらに顔ぶれは面白くなる。
題名:Thank You
読み:サンキュー
意味:ありがとう
邦題:サンキュー
監督:アニース・バーズミー
制作:ロニー・スクリューワーラー、トゥインクル・カンナー
音楽:プリータム
歌詞:クマール、アーシーシュ・パンデイト、アミターブ・バッターチャーリヤ
出演:アクシャイ・クマール、ボビー・デーオール、スニール・シェッティー、イルファーン・カーン、ソーナム・カプール、セリナ・ジェートリー、リーミー・セーン、チャーハト・カンナー、ムケーシュ・ティワーリー、マッリカー・シェーラーワト(特別出演)、ヴィディヤー・バーラン(特別出演)
備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左からリーミー・セーン、イルファーン・カーン、
ボビー・デーオール(下)、アクシャイ・クマール、ソーナム・カプール(下)、
スニール・シェッティー、セリナ・ジェートリー
| あらすじ |
カナダ在住のインド人ラージ(ボビー・デーオール)とヨーギー(スニール・シェッティー)はヴィクラム(イルファーン・カーン)の経営するヨット販売会社で働いていた。3人とも既婚であったが、3人とも派手な女遊びをしていた。ところがヨーギーは、妻マーヤー(セリナ・ジェートリー)が雇った探偵によって浮気がばれてしまった。離婚は免れたものの、ヨーギーはマーヤーにこき使われる毎日を送っていた。
ところで、ラージの妻サンジャナー(ソーナム・カプール)、ヴィクラムの妻シヴァーニー(リーミー・セーン)とマーヤーも友人同士であった。サンジャナーはとあるきっかけからラージの浮気を疑うようになる。そこでサンジャナーはマーヤーの助言を受けて、ヨーギーの浮気を確認した探偵キシャン(アクシャイ・クマール)に相談しに行く。キシャンは携帯電話の通話先リストからすぐに浮気を実証するが、純朴なサンジャナーは信じようとしなかった。そこでキシャンはサンジャナーにラージの浮気現場を現行犯逮捕させることに決める。
ニューイヤー・パーティーの日。ラージ、ヴィクラム、ヨーギーは、妻と共に出席していた。キシャンはそこにラージの浮気相手を大集合させる。だが、ヴィクラムの咄嗟の判断によってラージはサンジャナーの疑惑を晴らすことに成功する。しかし3人の男たちは、妻たちが誰かの助けを得ていると考え、キシャンのところへやって来て、その黒幕を捜し出すように依頼する。キシャンはそれを承諾する振りをして、さらに3人を追い込むことにする。
キシャンは、今度は3人を仲違いさせる計画を立てる。その計画は成功し、ラージとヴィクラムはヨーギーを敵視するようになる。おかげでヨーギーは、密かに進めていた浮気がマーヤーにばれてしまう。マーヤーはヨーギーを置いて出て行ってしまう。次にキシャンの計略によってラージの浮気が発覚するのだが、ラージはそれをヨーギーの仕業だと考える。しかし、ヴィクラムとラージは、カナダの秘密警察である振りをしてその危機を乗り越える。騙されやすいサンジャナーはラージのことを秘密警察だと信じ込むようになる。つまり、ラージは浮気のライセンスを得たも同然であった。
そこでキシャンは、マフィアのドン、キング(ムケーシュ・ティワーリー)になりすまし、ラージとヴィクラムを脅して、浮気相手と共に彼らを呼びつける。目隠しをされた2人は、キングになりすましたキシャンの前で、秘密警察の振りをしたのは浮気をごまかすためだったことなどを話す。その場には当然サンジャナーとシヴァーニーも来ていた。おかげで今度こそラージとヴィクラムの浮気はばれてしまう。
サンジャナーはナイアガラの滝に身を投げて死のうとするが、それをキシャンが止める。キシャンはラージを更正させることを約束する。サンジャナーは実家に帰り、キシャンも同伴した。ラージは何とかサンジャナーに会おうとするが、キシャンがそれを止める。ラージはヴィクラムに助言を求め実行するが、キシャンの方が一枚上手で、なかなかうまく行かなかった。ところでシヴァーニーは夫の浮気が分かった後もヴィクラムの家にいた。ヴィクラムは妻の仕付け方がいいからだと自負するが、シヴァーニーは復讐の機会を狙っていた。シヴァーニーは夫を騙して全財産移譲の書類にサインさせる。それを知ったヴィクラムは思考停止に陥ってしまう。だが、どうやら彼女の「兄」がシヴァーニーのこの行動を指示しているとヴィクラムは考えた。
キシャンはさらなる行動に出て、黒装束に身をまとい、サンジャナーとデートをする。そしてその様子をわざとヨーギーに発見される。ヨーギーはそのことをラージとヴィクラムに報告する。困った3人は再びキシャンの元を訪れ、ラージの浮気相手やシヴァーニーの「兄」を探すように依頼する。そこでキシャンはカルワー・チャウトの日にわざと3人を誘導し、ラージの浮気相手かつシヴァーニーの「兄」がキングであると錯覚させる。キシャンは、キングの妻が夫の浮気相談に来たことを明かし、キングの妻と共に彼を追い詰めることを提案する。3人はキングの妻に会いに行き、一緒にキングのアジトへ乗り込む。ところがキングの浮気相手は全くの別人であった。キングの妻が怒って発砲する中、3人はこっそり逃げ出す。
この期に及んでようやく3人は、全ての黒幕がキシャンであることに気付く。特にラージは憤慨するが、サンジャナーがキシャンをかばったことで、彼女に離婚を突きつける。
その後、落ち込む3人のところへキシャンがやって来て、サンジャナーが再婚することを知らせ、結婚式の招待状を渡す。キシャンがサンジャナーと結婚すると考え、怒った3人は大暴れするが、警察に逮捕されてしまう。留置所に入れられていた3人を助けたのがキングであった。3人が引き起こした騒動のおかげでキングは重傷を負ったものの妻と仲直りしていた。感謝の意を込めてキングは3人を釈放させたのだった。だが、ラージは怒りが収まらず、キングから銃を手に入れると、サンジャナーの結婚式会場へ向かった。そして会場にいたキシャンに発砲する。しかし、これは全てキングを巻き込んだキシャンの策略で、銃は空砲だった。実はその結婚式はラージとサンジャナーの再婚式であった。キシャンは命を賭けてラージとサンジャナーを仲直りさせたのだった。
キシャンがここまで彼らの手助けをするのには訳があった。キシャンにはかつて妻(ヴィディヤー・バーラン)がいたが、浮気がばれ、彼女は自殺してしまう。そのときから彼は、自分の妻のような女性を救うことを使命と考え、探偵をして来たのだった。再婚式ではヨーギーとマーヤー、ヴィクラムとシヴァーニーも仲直りした。一件落着を見届けたキシャンは人知れず去って行く。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
浮気物コメディーとしてはまずまずの出来。過去の同系統の作品の寄せ集めという印象が強く、新しい展開は見られなかった。まとめ方も月並みであるし、脚本も破綻気味。しかし、アニース・バーズミー監督のコメディーセンスは健在で、要所要所での笑いは保証されている。また、浮気物映画であるにも関わらず、最後には「妻を愛しましょう」というメッセージになっており、インド映画の良心を感じた。
登場人物の中でもっとも弱かったのはヨーギーとマーヤーのカップルである。ヨーギーは一旦ラージとヴィクラムの敵となり、キシャンとも通じるが、いつの間にかラージとヴィクラムの側に回っていて、混乱させられた。マーヤーは途中から全く出なくなり、終盤になってようやく再登場する。このカップルを中心に脚本の弱さが露呈するが、さらなる弱点は俳優の演技と存在そのものにあった。
ヒロイン3人はそれぞれ問題を抱えている。メインヒロインのソーナム・カプールは、今に始まったことではないが、台詞のしゃべり方に難があり、ストーリーに溶け込めていない。同世代のライバルであるディーピカー・パードゥコーンやカトリーナ・カイフがヒンディー語を苦手とするのに比べると、言語の面ではソーナムに分があるはずだが、台詞をしゃべるとどうも弱い。台詞をしゃべらなければ美しいのだが、そう考えると、デビュー作「Saawariya」(2007年)における起用法は間違っていなかったと言わざるをえない。
マーヤーを演じたセリナ・ジェートリーは、整形のし過ぎで不気味な容貌となって来ている。2001年のミス・インディア・ユニバースの栄冠に輝きボリウッドのチケットを勝ち取ったセリナは、今までこれと言って代表作がなく、売れなかったミスコン出身女優の典型として記憶されることになりそうだ。シヴァーニーを演じたリーミー・セーンは、「Dhoom」(2004年)などのヒット作がある分、セリナよりもマシなキャリアであるが、しばらく見ない間に太ってしまった。彼女もヒロイン女優としての寿命は終わったと言える。つまり、「Thank
You」は女優のキャスティングで大きな失敗している。
一方、男優陣の方は皆的確な演技であった。最近外しまくっていたアクシャイ・クマールであるが、「Patiala House」(2011年)に続き好演で、徐々に安定を見せつつある。イルファーン・カーンはさすがにうまいし、ボビー・デーオールも良かった。もっとも光っていたのはスニール・シェッティーで、コミックロールではベストの演技のひとつであった。アクション映画のイメージが強いが、「Hera
Pheri」(2000年)をはじめ、名作コメディー映画にもコンスタントに出演し、芸幅の広さを見せている。
マッリカー・シェーラーワトは「Razia」におけるアイテムガール出演。サプライズだったのはヴィディヤー・バーラン。キシャンの亡き妻役で最後に少しだけ顔を出す。他に、サンジャナーの妹を演じたチャーハト・カンナーも限定的な出演ながらなかなか良かった。テレビ出身の女優だが、今後映画でもっと大きな役がもらえるかもしれない。
音楽はプリータム。コメディー映画らしく派手でアップテンポの曲が多い。「Pyar Do Pyar Lo」、「Razia」、「My Heart
Is Beating」など。だが、バラードの「Pyar Mein」が一番印象に残る。
ほとんど言及がないが、舞台はカナダ。バンクーバーとトロントでロケが行われたようである。他にタイのバンコクでもロケがあったようだが、どの場面かは特定できなかった。
「Thank You」は、コメディー映画で定評のあるアニース・バーズミー監督の新作コメディー映画。過去のヒット作「Singh Is Kinng」などよりは質が落ちるが、男優陣の頑張りのおかげで楽しい映画にまとまっている。先週公開のコメディー映画「F.A.L.T.U.」よりもスターパワーがあり派手なので、コメディー映画で迷ったら「Thank
You」の方がいいだろう。
| ◆ |
4月10日(日) 汚職撲滅運動とロークパール法案 |
◆ |
先週(4月4日~9日)のインドは、社会活動家アンナー・ハザーレーがニューデリーのジャンタル・マンタルで行った「アーマラン・アンシャン(決死の断食)」の話題で持ち切りであった。71歳のアンナー・ハザーレーは、マハーラーシュトラ州を中心に、農民の生活レベル向上や、政治家・官僚の汚職撲滅のために活動を行って来た人物であるが、全国的には3月までほとんど無名の人物であった。アンナー・ハザーレーは今年に入り、汚職を監視するロークパール制度の導入を中央政府に求める活動を開始し、マンモーハン・スィン首相などとも会談を持ったが、望みなしと判断し、4月5日からジャンタル・マンタルにおいて、自身の命を賭けた断食による抗議活動を開始した。

アンナー・ハザーレー
デリーの観光地のひとつ、中世の天文台ジャンタル・マンタルの裏は、公認の抗議場となっている。デリーではジャンタル・マンタルと言えば、遺跡よりもむしろこの抗議場のことを指す。ジャンタル・マンタルでは毎日何かしら抗議活動が行われており、現在インドでどんな問題が起こっているのか概観できるユニークな場所となっている。ジャンタル・マンタルでは普段から多くの団体や個人が抗議運動をしており、ひとつひとつの抗議運動が世間の注目を集めることは稀なのだが、アンナー・ハザーレーの汚職撲滅運動はどういう訳か、メディアに加えて、SMSなどの携帯電話メッセージや、フェイスブックやツイッターなどのソーシャル・ネットワーク・サービス(SNS)によって瞬く間に大衆に広まった。例えばフェイスブックにおけるアンナー・ハザーレーのファン数を見てみると、彼が断食を始めた当初は3,000人ほどであったのが、4日間の内に110,000人にまでふくれあがった。その結果、当初少人数で開始されたアンナー・ハザーレーのアーマラン・アンシャンであったが、日を追うごとにジャンタル・マンタルには多くの人々が押し寄せ、アンナー・ハザーレーの抗議の輪に加わるようになった。断食などの苦行により願望を叶えるという行為はインド神話によく登場するが、それを現代的な抗議活動に昇華させたのはマハートマー・ガーンディーであった。それ故、いつしかアンナー・ハザーレーは「現代のマハートマー・ガーンディー」と呼ばれるようになった。
アンナー・ハザーレーが設置を要求するロークパールとは、簡単に言えばオンブズマンのことである。「ローク」とはヒンディー語で「世界」「社会」「民衆」など広い意味を持つ言葉で、「世間」という日本語がもっともピッタリ合う。「パール」とは「守護者」という意味である。スカンジナビア諸国などで導入されているオンブズマン制度をインドにも導入し、汚職を撲滅しようというのが今回のアンナーの運動の主旨だ。トランスペアレンシー・インターナショナルが毎年発表している腐敗認識指数(2010年)によると、インドは178ヶ国中87位(順位が高いほど汚職が少ない)。この指数上ではインドの汚職具合は世界のちょうど中間であるが、近年はインディアン・プレミア・リーグ(IPL)汚職事件、英連邦競技大会(CWG)汚職事件、2Gスペクトル汚職事件、カルナータカ州土地汚職事件、アーダルシュ・アパートメント汚職事件など、政治家や官僚などによる多額の金が絡んだ汚職事件が相次いでおり、インドの民衆は汚職に対して嫌気が差している。一応インドには中央捜査局(CBI)汚職対策部門や会計監査官(CAG)など、汚職撲滅に取り組む役職が用意されているが、完全に独立していなかったり、その役職自体が汚職にまみれていたりして、正常に機能していない。その結果、権力者はたとえ汚職が明らかになったとしてもまともな刑罰を受けない構造となっている。これらの汚職を監視し、汚職に手を染めた者を徹底的に処罰する責務を負った役職を置くべきだというのがアンナーの要求である。
ただ、ロークパール制度導入はアンナーの発案ではなく、1960年代から何度も法案が国会に提出されて来た。だが、その度に何らかの事情によって暗礁に乗り上げ、可決されずに流れてしまうような状況が繰り返されて来た。また、政府案のロークパールは単なる勧告機関で権限が弱く、汚職撲滅に十分な力を持っていない。そのため、アンナーら社会活動家たちと、NGOインド・アゲインスト・コラプション(IAC)は、対案として、ロークパールに強力な権限を与えることを盛り込んだジャン・ロークパール法案をまとめ、政府にその検討を求めているのである。
当初はアンナー・ハザーレーの抗議活動を過小評価していた政府であったが、徐々にジャンタル・マンタルがエジプトのテヘリール広場と同様の様相を示して来るに従い、彼の要望に真剣に耳を傾けるようになった。デリー内外の多くの若者たちもジャンタル・マンタルに駆けつけ、断食という古風な方法で抗議するアンナーと同時並行して、キャンドルを使った流行の方法で抗議に加わった。ボリウッド映画界の重鎮やその他のセレブリティーたちも、ツイッターでつぶやいたり、現場に駆けつけたりして、次々とアンナーへの支持を表明した。インド人民党(BJP)をはじめとした野党政治家たちも得点稼ぎのチャンスと見て駆け込もうとしたが、賢明にもアンナーはこの抗議運動に政治色を加えることを避けた。断食4日目の4月8日、政府は遂にアンナー・ハザーレーの要求を丸呑みする形で受け容れた。それを受け、アンナー・ハザーレーは断食5日目、4月9日の午前11時頃に、その場にたまたまいた5歳の少女からニンブー・パーニー(ライム水)を受け取ってそれを飲み、断食を終了した。各紙は一連の出来事を「民衆の勝利」「民主主義の勝利」と表現した。アンナー・ハザーレーが勝利宣言をして断食を終了したとき、ジャンタル・マンタル周辺では大変なお祭り騒ぎになったとのことである。
ただ、勘違いしてはいけないのは、今回政府はアンナーらが提案するジャン・ロークパール法案を受け容れた訳ではないことだ。ロークパール制度を検討するための委員会設置に関し、アンナーらが要求する枠組みの要求をほぼ全面的に受け容れただけである。委員会にはプラナブ・ムカルジー財相など大臣級政治家に加えて、アンナーなど、ロークパール制度を推進する社会活動家も加わることになった。今後会議が開かれ法案が調整される。そして今年のモンスーン・セッションに可決が目指されることになっている。
ただ、あまりに急速なアンナー・ハザーレーに対する支持の拡大は、端から見ると危険な熱狂のようにも感じられてならない。現にアンナーらが提案するジャン・ロークパール法案の中身を見てみると、かなりラディカルな内容であると言わざるをえない。アンナーが掲げる「汚職撲滅」には賛成だとしても、果たしてこの法案を理解し支持している人がどれだけいるだろうか?
例えば、政府案のロークパール法案におけるロークパールは、政治家の汚職のみを管轄とする一方、ジャン・ロークパール法案におけるロークパールは、首相をはじめとした政治家、官僚、裁判官の汚職を取り扱うため、立法、行政、司法の全てを監視する権限を持っている。さらに汚職によって民間企業が利益を得た場合は、その企業にも多額の罰金を科すことが出来る。政府案では、国防や外交に関する案件はロークパールの管轄から除外されるが、ジャン・ロークパール法案ではそのような「聖域」は認められていない。ロークパール法案のロークパールは単なる勧告機関で、警察権も持っていないし、国民から直接訴えを受ける権限もない。だが、ジャン・ロークパール法案のロークパールは、独自に汚職捜査をすることも出来るし、国民の誰からでも訴えを受けて行動を起こすことも出来るし、どの機関からの認可も必要とせずに独立して汚職者を起訴することも出来るし、効果的な機能のために独自に規則を定めることすら出来る。ロークパール法案によると、汚職が明らかになった人物に対しては1年~3年の禁固刑が罰則として定められているが、ジャン・ロークパール法案では、最低5年、最高終身刑という重い罰則を提案している。もし汚職者がジョイント・セキュレタリー以上の高官または大臣である場合、禁固刑は最低10年となる。さらに、汚職によって国庫に金銭的損失が生じた場合、汚職者の財産からその分が補填されるという罰則付きである。また、ジャン・ロークパール法案では、犯罪歴のある者がロークパールになることを禁じるなど、ロークパール自身の汚職を防ぐ最大限の努力が払われている。ただし、ロークパールは選挙による選出ではなく、任命である。つまり民主主義的な手続きを経なくてもロークパールになれるということである。
確かにジャン・ロークパール法案が規定するような強大な権力を付与しなければ、ロークパールはインドから汚職を一掃できないだろう。だが、汚職を防止する法的枠組みが既にいくつか存在していた中でも抜け道が生じ、汚職が発生し、汚職者がなかなか処罰されない現状を見るにつけ、ロークパールがどこまで汚職対策になるか、疑問である。選挙を経て国民の信任を受けていない人物がこのような強大な権力を持つことにも疑問の声が多い。そして、もしロークパール自身が汚職に手を染め、権力を乱用するならば、彼は首相にも匹敵する力を持ち、国策を左右する影響力を持つことになる。ロークパール制度を導入することは簡単だが、一度制度が出来たら、今度は誰をロークパールに任命するのか、慎重に検討しなければならないし、国民も常にそれをチェックしなければならない。
個人的な見解では、インド人は本当に汚職を完全に撲滅させたいと考えているのか、という点で疑問を感じる。インドでは、汚職と共生する「チャルター・ハェ(こういうものさ)」文化が根付いてしまっており、庶民は権力者の汚職に抑圧され搾取されながらも、それを上手に利用してサバイバルしている部分もある。インドに滞在する外国人も、そういう「融通」を享受して生活している部分は少なからずある。アンナーの運動は庶民から絶大な支持を受けたが、もしそれが失敗するとしたら、汚職まみれの政治家たちによるプレッシャーよりも、やはりそういう「融通」を心地よく感じる庶民側からの反発が原因となる可能性が高いのではないかと思う。
断食を完了したとき、アンナーは「これからが本当の戦いの始まりだ」と宣言した。ジャン・ロークパール法案はアンナーの改革の一部に過ぎず、今後選挙改革などにも取り組んで行くと言う。果たしてアンナーの一連の運動が、現代インドの重要なターニング・ポイントとなるのか、それとも単なる通過点となって歴史に埋もれて行くのか、まだ結論は出ないが、今後注目である。
コメディー映画こそがインド映画の真髄である。映画が娯楽の王様である限り、映画は気の置けない友人や家族と共に鑑賞するためのものであり、その際にもっとも好まれるジャンルは自ずと気楽に楽しめるコメディーとなる。この不文律を意識しているのか、普段シリアスな映画を作っている監督が突然コメディー映画を作ることがある。今年に入り、リアリズム娯楽映画の旗手マドゥル・バンダールカル監督が「Dil
Toh Baccha Hai Ji」(2011年)というコメディー映画を作り、周囲を驚かせたのが記憶に新しい。そうかと思っていたら、今度は「Rang
De Basanti」(2006年)や「Delhi-6」(2009年)などの傑作で知られるラーケーシュ・オームプラカーシュ・メヘラー監督がコメディー映画をプロデュースした。監督はムリグディープ・ラーンバー。今まで「Don」(2006年)や「Yuvvraaj」(2008年)などで助監督として下積みして来た人物で、本作が監督デビュー作となる。ベテラン俳優オーム・プリー、中堅俳優シュレーヤス・タルパデー、個性派俳優ディーパク・ドーブリヤールの3人が主演。予告編を見る限り、十分に期待が持てた。さて、蓋を開けてみたらどうだっただろうか?
題名:3 Thay Bhai
読み:ティーン・テー・バーイー
意味:3人の兄弟がいた
邦題:ビッグ・ブラザーズ
監督:ムリグディープ・ラーンバー
制作:ラーケーシュ・オームプラカーシュ・メヘラー
音楽:スクヴィンダル・スィン、ランジート・バーロート
歌詞:グルザール
出演:オーム・プリー、シュレーヤス・タルパデー、ディーパク・ドーブリヤール、ヨーグラージ・スィン、ラーギニー・カンナー
備考:PVRプリヤーで鑑賞。
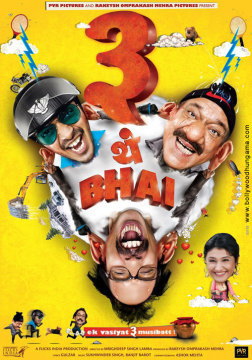
左上はシュレーヤス・タルパデー、右上はオーム・プリー、
下はディーパク・ドーブリヤール、右下はラーギニー・カンナー
| あらすじ |
チクシー・ギル(オーム・プリー)、ハッピー・ギル(ディーパク・ドーブリヤール)、ファンシー・ギル(シュレーヤス・タルパデー)はパンジャービー3兄弟であった。チクシーはバティンダーで商店を経営していたが商売は上がったりで、食欲旺盛でプクプク太ってしまった娘たちの嫁の行き先に悩んでいた。ハッピーはすぐに歯を引っこ抜く歯科医として悪名を持ち、借金に悩んでいた。ファンシーはパンジャービー語映画で俳優をしていたが、英語の台詞をむやみに入れたがるために毛嫌いされていた。夢はハリウッドであった。3人の仲は決して良くなく、顔を合わせると喧嘩ばかりしていた。
あるとき、父親カプティー・ギル(ヨーグラージ・スィン)の訃報が届く。葬式に赴いた3人は早速喧嘩を始めるが、弁護士のチャッダーから父親の遺言を聞いて目の色を変える。父親はヒマーチャル・プラデーシュ州に土地とコテージを所有していたが、その価値は現在数千万ルピーになる見込みであった。だが、3人がその不動産を相続するためにはひとつの条件があった。それは、3年間、1年に1度、父親の命日に、3人がそのコテージに集まり、父親の遺灰の番をすることであった。3人は仕方なくその条件を守ることにする。
2年間は何事もなく過ぎ去った。だが、最後の3年目、次々と問題が発生した。まずはチクシーがコテージに到着し、その後ハッピーも来たが、ファンシーの到着が遅れた。もしその日が終わるまでに3人が揃わなかったら条件を見たさなくなってしまう。何とかファンシーは到着するが、途中で愛犬を亡くしており、意気消沈していた。3人は早速喧嘩を始め、酒の力もあって、最終的に3人とも床に寝転んで眠ってしまう。
翌朝、3人はコテージの煙突に誰かがいるのを発見する。3人はその男を捕まえて素性を問いただすが、男は隙を見て逃げ出してしまう。探し回る内に3人は近くで外国人女性たちが行っていたドラッグ・パーティーに迷い込む。だが、そこへ警察が踏み込み、3人は麻薬密売人と勘違いされて逮捕されてしまう。
警察署に連行された3人は熱血警官に取り調べを受けるが、まんまと逃亡に成功する。そのまま山を下りてもよかったのだが、父親の遺灰がコテージに置きっぱなしであることを思い出し、3人はコテージに戻る。そこには既に警察が来ており、ショベルカーでコテージを取り壊そうとしていた。3人はコテージに忍び込んで遺灰を取り戻そうとする。ところがそこへ熱血警官と弁護士のチャッダーが駆けつける。チャッダーが明かしたところによると、父親が遺した別の遺言では、3年後にこのコテージは別の人物に売却されることになっており、取り壊しを行っていたのがその人物であった。3人はすっかり元気をなくしてしまった。何も手に入らなかった3人であったが、この一件により彼らの絆は何となく深まったのだった。
1ヶ月後。3人のもとに女性弁護士マンプリート・カウル(ラーギニー・カンナー)と、煙突に隠れていた男がやって来る。この男は実は探偵で、3人が遺言の条件を実行しているか監視する役目を負っていた。また、マンプリートはハッピーの初恋の相手であった。マンプリートの話によると、父親の遺言に従い、コテージを売却して出来た金1億7千万ルピーあまりが3人に相続されるとのことであった。これを聞いて3人は大喜びする。父親は、3人の仲を修正するため、生前にこのような大芝居を考えついたのだった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
「ビッグ・ブラザー」というオランダ発祥の国際的人気リアリティー番組がある。外界から隔離され、マイクやカメラが至るところに仕掛けられた家で、多額の賞金目当ての数人の参加者が、毎回互いを脱落させ合って生き残りを目指す方式のゲームで、そこで繰り広げる人間模様が赤裸々に放映される。インドでは「ビッグ・ボス」というタイトルで放映され、物議を醸しながらも人気を博した。「3
Thay Bhai」は、この「ビッグ・ブラザー/ビッグ・ボス」から着想を得たストーリーであるようで、映画中でもこの番組の言及があった。3人の兄弟が、父親が遺した遺産を巡って、大雪によって外界から遮断された屋敷で共に一夜を過ごすというのが導入部である。
もしこの部分の脚本や台詞を緻密に作って行ったら、低予算ながらもパンチ力のあるスリラー風コメディー映画となったことだろう。だが、映画はこれだけでは終わらず、3人はコテージの外にも出て、ドラッグ・パーティーに乱入したり、警察に逮捕されたり脱走したりと、騒動を巻き起こす。この後半部分の出来が最悪、全くの蛇足で、映画の完成度を著しく低めていた。さらに、この後半に時間を割いたために、前半の「リアル版ビッグ・ブラザー」の部分も中途半端になってしまっていた。よって、全くの失敗作で終わってしまっていた。インドの映画界では一目置かれるラーケーシュ・オームプラカーシュ・メヘラーの名前を冠しながらこの体たらくとは、ため息しか出ない。ムリグディープ・ラーンバー監督の才能とメヘラー監督の鑑識眼を疑う。
それでも、主演3人はそれぞれ個性派俳優であり、誠実な演技であった。実年齢差を考慮しなければ合格点であろう。面白かったのは父カプティー・ギルを演じたヨーグラージ・スィンである。元クリケット選手、現在パンジャービー語映画の人気悪役俳優で、なんと現役クリケット選手ユヴラージ・スィンの父親。プリトヴィーラージ・カプールを思わせる豪快な演技であった。紅一点ラーギニー・カンナーはテレビ女優出身であり、おそらく本作が映画デビュー作となるが、映画向きではない。
音楽はスクヴィンダル・スィンとランジート・バーロート。ダレール・メヘンディーの歌う「Pigeon Kabootar (Teen Thay Bhai)」がタイトルソング扱いである。この曲の歌詞は一見に値する。「Listen
Suno Bhai...」から始まるが、他にも「Choose Chuno」、「Pigeon Kabootar」、「Parrot Tota」など、英語とヒンディー語で同じ意味の言葉を並べており、全くナンセンスな響きを楽しんでいる。エキセントリック少年ボウイの「少年ボウイ」「犬ドッグ」「鳥バード」と似た言葉遊びである。ただ、これが映画にプラスに働いたかと言うと決してそうでもない。
「3 Thay Bhai」は、ラーケーシュ・オームプラカーシュ・メヘラー監督プロデュースのコメディー映画ということで期待されていたが、全くその期待に応えられない駄作である。ほとんど褒められる場所がない。避けるが吉の映画である。
| ◆ |
4月22日(金) Dum Maaro Dum |
◆ |
アラビア海に面したゴア州はインドを代表する観光地だ。ポルトガル領時代の遺構やフランシスコ・ザビエルのミイラも見物だが、何と言ってもゴアが世界に名を轟かせているのはそのビーチである。沿岸線にいくつものビーチが点在し、それぞれが独自のアイデンティティーを持っている。かつてはヒッピーの天国と呼ばれ、外国人長期滞在者の溜まり場となっていたゴアも、最近では地元インド人観光客が押し寄せるようになり、すっかり様変わりしたが、中心部から外れたビーチでは今でもヒッピー全盛時代のゴアの面影を探すことが出来る。また、ゴアはフルムーン・パーティーやレイヴ・パーティーと言ったパーティー文化でも有名である一方、ドラッグ汚染でも悪名を轟かせている。ドラッグ絡みと思われる外国人の変死事件や殺人事件も明るみに出るようになっている。ゴア州警察は健全な観光地として汚名返上するためにパーティーやドラッグの規制強化に努めており、かつての自由さはなくなって来ているとの話も聞く。また、既に本物のヒッピーたちは、ごった返したゴアを離れ、カルナータカ州やケーララ州のさらなる秘境ビーチに移動しているという話もある。
本日より公開の新作ヒンディー語映画「Dum Maaro Dum」は、ゴアのアンダーワールドを舞台にしたスリラー映画である。ゴアはボリウッド映画の本拠地ムンバイーから近い風光明媚の地であることから、昔からヒンディー語映画の舞台として好まれて来た土地であるが、近年のインド人の間でのゴア人気のきっかけとなったのは確実に「Dil
Chahta Hai」(2001年)である。その後もゴアはいくつもの映画の舞台となって来ており、最近では「Guzaarish」(2010年)や「Golmaal
3」(2010年)などが記憶に新しい。だが、ゴアのアンダーワールドと限定すると、「Musafir」(2004年)辺りが近い。また、ドラッグをテーマにしたインド映画と言うと、「Charas」(2004年)や「Dev.
D」(2009年)などが思い浮かぶ。
「Dum Maaro Dum」の監督は「Bluffmaster!」(2005年)のローハン・スィッピー。主演は「Game」(2011年)に続きアビシェーク・バッチャン。ビパーシャー・バスがヒロイン扱いと言えるが、意外に汚れ役で、この作品中にヒロインらしいヒロインはいない。ヴィディヤー・バーランとディーピカー・パードゥコーンの特別出演は豪華。他に、プラティーク・バッバルの出演や、テルグ語映画で活躍中のラーナー・ダッグバーティがヒンディー語映画デビューを果たす点にも注目。ちなみに題名となっている「Dum
Maaro」とは「ハッパを吸え」という意味である。
題名:Dum Maaro Dum
読み:ダム・マーロー・ダム
意味:ハッパを吸えハッパを
邦題:パラダイス
監督:ローハン・スィッピー
制作:ラメーシュ・スィッピー
音楽:プリータム
歌詞:ジャイディープ・サーニー
振付:ボスコ・シーザー
衣装:ファールグニー・タークル
出演:アビシェーク・バッチャン、ビパーシャー・バス、ラーナー・ダッグバーティ(新人)、プラティーク・バッバル、アーディティヤ・パンチョーリー、ゴーヴィンド・ナームデーオ、アナイター・ナーイル、ヴィディヤー・バーラン(特別出演)、ディーピカー・パードゥコーン(特別出演)
備考:PVRプリヤーで鑑賞。

上からビパーシャー・バス、アビシェーク・バッチャン、
ラーナー・ダッグバーティ、プラティーク・バッバル
| あらすじ |
ゴアで生まれ育った青年ロリー(プラティーク・バッバル)は、米国の大学留学を夢見ており、合格通知も受け取るが、奨学金には通らなかった。留学には15,000ドルの資金が必要であり、中流家庭のロリーは留学を断念せざるを得なかった。一方、幼馴染みのタニー(アナイター・ナーイル)は、裕福な家庭に生まれ留学資金にも困っていなかったにも関わらず、大学にも奨学金にも合格し、米国に留学することになった。
1人残され落ち込むロリーに近寄って来たのが、ゴアのアンダーワールドにコネを持つリッキーであった。リッキーはロリーに15,000ドルを支払うことを約束するが、その交換条件としてドラッグの運び屋になることを提案する。最初は断ったロリーであったが、最終的にはリッキーの誘いに乗ってしまう。米国へ飛び立つために家族に見送られて空港へ向かったロリーであったが、そこでヴィシュヌ・カーマト警視監(アビシェーク・バッチャン)に捕まってしまう。ヴィシュヌはロリーの鞄の中からドラッグを発見し、ロリーを署にしょっ引く。
ヴィシュヌは5年前には非常にアクティブに活動していた警察官であった。次々に事件を解決する代わりに、汚職にもどっぷり浸かっていた。だが、ドラッグ中毒者が運転する自動車が引き起こした交通事故で妻(ヴィディヤー・バーラン)と子供を失い、それ以来孤独の世界に浸っていた。ところが、ゴア州の内務大臣が、ゴアのドラッグ汚染があまりに酷くなってしまったことを見て、ヴィシュヌを召還し、彼にドラッグマフィア一掃を命じる。それ以来、ヴィシュヌはメルシーとラーネーという2人の相棒と共にゴア中を駆け巡ってドラッグ密売マフィアたちの包囲網を敷いて来た。ゴアのアンダーワールドの総元締めはローザ・ビスクッタ、通称ビスケット(アーディティヤ・パンチョーリー)という男であった。表向きは実業家兼慈善活動家であったが、裏ではゴア中のドラッグ密売を取り仕切っていた。ビスケットを追う内にリッキーが捜査線上に浮かんだが、リッキーを追い詰めた時には既に殺されていた。リッキーにロザンナというブラジル人のガールフレンドがいること、彼女が出国しようとしていることを突き詰めたヴィシュヌは空港へ向かった。ブラジルの外交官の横槍が入ったためにロザンナを逮捕することは出来なかったが、ヴィシュヌはたまたまロリーに目を付け、彼を取り調べたのだった。
ロリーを署に連行するときに、1人の男がヴィシュヌの前に現れ、彼の無実を訴えた。ヴィシュヌはその男も署に連行した。その男の名はDJジョキ(ラーナー・ダッグバーティ)。職業はギタリスト。かつて彼にはゾエ(ビパーシャー・バス)というガールフレンドがいた。ゾエはスチュワーデスになることを夢見ており、客室乗務員養成学校を卒業したが、なかなか就職できずにいた。そんなときにビスケットやリッキーと出会い、スチュワーデスの夢を叶えるためにドラッグの運び屋となることを承諾した。だが、何度か運び屋をする内に行為がばれて逮捕されてしまい、14年の懲役刑を受けた。だが、ビスケットの愛人となることで14日で出所し、それ以降ビスケットの秘書兼愛人として暗黒の人生を過ごしていた。それを見ていたジョキは、ロリーが第二のゾエとなりつつあることを心配し、忠告して来た。だが、ロリーは聞く耳を持たず、このようなことになってしまったのだった。ジョキはロリーに、洗いざらい全て話すことを助言するが、ロリーは脅されており、なかなか口を割ろうとしなかった。そのままロリーは少年院に入れられてしまう。
だが、ビスケットやゴアの麻薬ディーラーたちの方も、ヴィシュヌが取り締まりと摘発を強化したために商売に支障が出て来ていた。そこで安全策を採り、手持ちのドラッグを全て集め、ゴアのアンダーグランドの真のボスであるマイケル・バルボーサに預けることにする。その価値は30億ルピー以上に上った。その情報を掴んだヴィシュヌは、ジョキの力も借りてマイケル・バルボーサについて調べ始めるが、全く得体の知れない人物で、誰もその正体を知らなかった。マイケル・バルボーサを追う内にメルシーが殉職してしまう。また、ジョキは密かにゾエと接触し、2人の間には再び関係が芽生える。
国際的麻薬ディーラーたちはゴアでの麻薬売買から手を引こうとしていたが、ビスケットは場所をカルナータカ州のゴーカルナに移し、大レイヴ・パーティーを開催して、そこで今まで通り麻薬売買を行うことを宣言する。その情報をキャッチしたゾエはジョキに密告するが、それがビスケットにばれてしまい、彼女が殺される。だが、ジョキは責任を持ってその情報をヴィシュヌに渡す。また、ヴィシュヌはロリーに一部始終を紙に書かせ、その中からマイケル・バルボーサのヒントを探す。ヴィシュヌはゴーカルナのレイヴ・パーティーを急襲して密売人やドラッグ使用者を一網打尽にする。同時に彼はマイケル・バルボーサの正体も突き止める。だが、そのとき部下のラーネーに撃たれてしまう。実はラーネーはビスケットと密通していたのだった。ヴィシュヌは殉職する。
ヴィシュヌ死後もジョキは独自に捜査を続けた。ジョキは、ヴィシュヌが遺したダイイング・メッセージに気付き、ヴィシュヌはラーネーに殺されたことを知る。また、ジョキはゾエの墓参りに行ったときにたまたまマイケル・バルボーサの秘密にも気付く。マイケル・バルボーサとは麻薬密売の黒幕ではなく、麻薬の隠し場所のことであった。マイケル・バルボーサという故人の墓に麻薬が隠されていた。ジョキはそれを全て奪い、ラーネーをおびき寄せてヴィシュヌの仇を取る。また、ビスケットも後に非業の死を遂げる。一方、ロリーは罪が晴れ、少年院から出て、帰郷していたタニーと再会する。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
まずは映像表現と音楽が格好いい映画だった。ゴアのドラッグ・カルチャーやパーティー・カルチャーをサイケデリックな映像と印象的なリフの繰り返しで存分に表現していた。まるでゴアを訪れる外国人全てがドラッグ中毒者であるかのような、誇張した描写には多少疑問を覚えたが、ほぼ全編ゴアで撮影されて、ナイトマーケットやビーチも登場し、ゴアの俗語も満載で、総じてゴアの雰囲気がよく出た映画になっていた。
物語は前半と後半で大きく分かれる。インターヴァル前の前半は、ロリー、ヴィシュヌ、ジョキと言う3人の主人公が今回の事件に関わることになるまでを各々の視点から順に追っている。この3人の接点となるのが空港で、ロリーはヴィシュヌに捕まり、ジョキもそこに飛び込むことになった。インターヴァル後は、ヴィシュヌと共に観客もマイケル・バルボーサの謎を追う。終盤でなんと主役だと思っていたヴィシュヌが死んでしまうという大番狂わせがある他、マイケル・バルボーサの正体もほとんど予測不可能なもので、意外性のある脚本になっていた。スリラーとしては一級の作品である。
ただ、ヴィシュヌのキャラクターは「Dhoom」シリーズでアビシェーク・バッチャンが演じたジャイと酷似している。頭脳明晰かつ大胆不敵な警察官と言ったキャラである。アビシェークは「Game」(2011年)でも同様の役柄を演じており、次第にイメージが固定して行ってしまっている。彼の演技は悪くはなかったが、このまま同じような役を演じ続けることは避けた方がいいだろう。
アビシェークの他に主役級だったのがプラティーク・バッバルとラーナー・ダッグバーティ。それぞれロリーとジョキを演じた。「Dhobi Ghat」(2011年)での演技が記憶に新しいプラティークはオーバーアクティングなところがあったが、テルグ語映画からヒンディー語映画に飛び込んだラーナーは堂々とした演技で、アビシェークと十分に渡り合っていた。
この映画に本当の意味でのヒロインは存在しない。ジョキの元恋人ゾエを演じたビパーシャー・バスがもっともヒロインの位置に近いが、悪役ビスケットの情婦となってしまっており、終盤には殺されてしまう。ロリーの幼馴染みタニーを演じたアナイター・ナーイルや、ヴィシュヌの亡き妻を演じたヴィディヤー・バーランは出番がほとんどない。密通者ラーネーを演じたゴーヴィンド・ナームデーオや、ビスケットを演じたアーディティヤ・パンチョーリーは好演だった。
「Dum Maaro Dum」は音楽が印象的。作曲はプリータム。その素晴らしさの大部分は「Mit Jaaye Gham [Dum Maaro
Dum]」で繰り返される不安定なリフに依っている。この曲は「Hare Rama Hare Krishna」(1971年)中の挿入歌「Dum Maro
Dum」のリミックスで、このリフはその中でも出て来るのだが、ミディヴァル・パンディトの手によって、映画の顔とも言うべきメロディーに生まれ変わっている。この曲は終盤のゴーカルナ・レイヴ・パーティーで使用され、ディーピカー・パードゥコーンがアイテムガール出演して挑発的なダンスを踊る。また、「Thayn
Thayn」ではアビシェーク・バッチャンが歌声を披露している。
言語は基本的にヒンディー語であるが、ゴア州の言語であるコーンカニー語のエッセンスが混じっているようで、何を言っているかはっきり理解出来ない部分がいくつかあった。聞くところによるとゴアのスラングが随所で使われているらしい。他に珍しいところではロシア語の台詞もあった。ゴアはロシア人の人気バカンス先となっており、映画中でも外国人の中で特にロシア人のプレゼンスが高かった。
ところで、「Dum Maar Dum」の中で、「ゴアでは酒は安いが、女はもっと安い」という台詞があり、公開前にゴアにおいて物議を醸していた。直前になってこの台詞は「酒は安いが、人間関係はもっと安い」と置き換えられた。
劇中にカルナータカ州ゴーカルナという地名が出て来るが、ここは最近ゴアに代って浮上して来たビーチのひとつである。カルナータカ州沿岸部にはゴーカルナの他にも無名の極上ビーチが点在しており、穴場となっている。
「Dum Maaro Dum」は、ドラッグが蔓延するゴアを舞台にしたスリラー映画であり、格好いい映像と音楽、そしてサプライズのある脚本のおかげで、楽しめる娯楽映画となっている。特別出演まで含めればキャストも豪華。見て損はない。
| ◆ |
4月24日(日) 米外交公電中のボリウッド |
◆ |
ジュリアン・アサンジ氏が2007年に発表した機密情報公開サイト「ウィキリークス」は、2010年にアフガン紛争やイラク戦争に関連する大量の漏洩機密文書を公開したことで世界的な注目を集めるようになった。機密情報内部告発の波は日本にも打ち寄せ、「ウィキリークス」とは直接関係ないものの、海上保安官が尖閣諸島中国漁船衝突映像を動画投稿サイトYouTubeに流出させた事件があったことは記憶に新しい。
インドでは3月15日から、クオリティー・ペーパーとして名高いザ・ヒンドゥー紙が、ウィキリークスと提携し、インド関連の米外交公電を毎日掲載している。主にニューデリーの米国大使館やインド各地の米国総領事館が本国に送った公電が中心である。特定の政党を狙い撃ちしている訳ではないが、ダメージが大きいのは長く中央の政権に就き自然とネタも多くなっている国民会議派である。ザ・ヒンドゥー紙との提携直後、早速ウィキリークスが巻き起こした騒動は、2008年の内閣信任投票における「票買収(Cash
for Votes)事件」。当時はまだ国民会議派率いる統一進歩連合(UPA)政権第1期の頃で、左翼政党の閣外協力が政権運営に不可欠であった。だが、インドと米国の間で締結された民生用核開発協定の是非を巡って左翼政党が閣外協力を撤回し、与党は下院において「過半数の証明」、つまり内閣信任投票をしなければならなくなった。このとき、「インド史上もっとも弱いリーダー」と揶揄されて来たマンモーハン・スィン首相は今までにないリーダーシップを発揮し、内閣信任を勝ち取った。だが、この投票で不正があったことを示す情報がウィキリークスによって暴露されたのであった。
その後もザ・ヒンドゥー紙にはウィキリークス提携記事が掲載されており、興味深い紙面となっている。その中で個人的に興味を引かれたのは、インドの映画産業に関する公電である。米国はボリウッドをはじめとしたインド映画産業にも注目しており、ムンバイーの総領事館を中心にその動向と分析を本国に送っている。4月22日には映画関連の公電2つが公開された。これらの文書はムンバイー米総領事館が2010年2月11日に作成したもので、それらの詳細やリンク先は以下の通りである。
- Reference ID: 10MUMBAI51
Subject: THE BOLLYWOOD-HOLLYWOOD PARTNERSHIP: GREAT POTENTIAL BUT SLOW
TO FIND TRACTION
題名訳:ボリウッド・ハリウッド・パートナーシップ:巨大な潜在性と安定軌道への苦戦
- Reference ID: 10MUMBAI52
Subject: CAN THE INDIAN FILM INDUSTRY GO GLOBAL?
題名訳:インド映画産業のグローバル化は可能か?
これらの中で、インドの映画産業は制作本数や観客動員数の面で世界最大であること(制作本数は米国の2倍、チケットセールスは2.5倍だが、チケットの安価さなどからインドの市場規模は米国の6分の1ほど)、ハリウッド映画のいくつかはインドでもヒットしているが、ローカル映画に比べたらそのプレゼンスは著しく低いこと、ムンバイー拠点のヒンディー語映画界は「ボリウッド」と呼ばれ、全インド的な知名度と影響力を持っていること、それにも関わらずヒンディー語映画界よりも南インド映画の方が利益率がよく発展していること(ヒンディー語映画のヒット率は10本に1本なのに対し、南インド映画では10本に4本がヒット)、2000年まではインドの映画産業は銀行から融資が受けられず、アンダーワールドから資金調達をせざるを得なかったこと、ヒンディー語映画界はスター中心システムからプロダクション・ブランド中心システムに移行しつつあること、国内映画産業の伸びしろはまだまだ膨大であること、米国のプロダクションが近年インドとの連携を模索しているがなかなかうまく行っていないことなどが紹介・分析されている。今まで「これでインディア」の中でも書いて来たようなことであり、「これでインディア」を参考にして書かれている訳ではないにしても、米国の大使館・総領事館の中に相当なインド映画通がいることがうかがわれる。
ハリウッドがいかにインドの映画産業に食い込もうとしているか、その試行錯誤の部分は読んでいて非常に参考になる。話をヒンディー語映画界(ボリウッド)に限定し、まずは公電の情報をもとに、自分なりの解説を加えながら、これまでのハリウッド・ボリウッド・パートナーシップを概観してみる。公電によると、米国のソニー・ピクチャーズ・エンターテイメントは、インドのプリーティーシュ・ナンディー・コミュニケーションズと3本の映画を共同制作する協定を結び、さらに同社はインドのエロス・インターナショナルと3本の映画を世界配給する契約を結んだ。ソニーとプリーティーシュ・ナンディーの共同制作映画は2011年4月現在まだ公開されていないはずである。ちなみにソニーは過去に「Saawariya」(2007年)を制作して大失敗している。また、公電によると、米国のワーナー・ブラザーズは、インドのピープル・ツリー・フィルムスと3本の映画の制作と配給の契約を結んだ。ワーナーは過去に「Chandni
Chowk to China」(2008年)をピープル・ツリー・フィルムズと共同制作して大失敗しているが、それに懲りずに上記の契約を結び、その内の1本「Jaane
Kahan Se Aayi Hai」(2010年)が公開された。だが、ヒットにはならなかった。それより以前にワーナーは「Saas Bahu Aur
Sensex」(2008年)という低予算映画も制作している。さらに、公電によると、米国のウォルト・ディズニーはインドのヤシュ・ラージ・フィルムスとアニメ映画の共同制作契約を結ぶと同時に、インドのUTVモーション・ピクチャーズの株式を取得して筆頭株主となった。ディズニーとヤシュ・ラージ・フィルムスの共同制作とは「Roadside
Romeo」(2008年)のことを指している。この映画も大してヒットしなかったが、インドのアニメ映画史上では重要な作品である。また、公電によると、20世紀フォックスの子会社フォックス・サーチライト・ピクチャーズは、「The
Namesake」(2006年)をUTVモーション・ピクチャーズと共同制作し、さらに「My Name Is Khan」(2010年)のグローバル・マーケティング配給権を取得した。その他、公電には、米国のラッパー、スヌープ・ドッグ、豪州の女優カイリー・ミノーグ、米国の男優シルベスター・スタローンがボリウッド映画に参加したことについても触れられているが、その作品はそれぞれ、「Singh
Is Kinng」(2008年)、「Blue」(2009年)、「Kambakkht Ishq」(2009年)である。「Singh Is Kinng」は大ヒット、「Blue」は大失敗、「Kambakkht
Ishq」はヒットしたものの批評家から酷評という結果であったが、ハリウッドとのコラボレーションが興行収入や映画の出来に影響したとは言えない。
公電では、20世紀フォックスとスターがインドに設立した合弁会社フォックス・スター・スタジオのことが抜け落ちている。つい先日フォックスとラメーシュ・スィッピー・エンターテイメントの共同制作作品「Dum
Maaro Dum」が公開された。また、奇遇であろうが、同日に公開された子供向け映画「Zakkkomon」はウォルト・ディズニーのプロデュースである。このように、最近のボリウッド映画には、ハリウッドの資金が入った作品が非常に多くなっている。だが、公電でも語られているように、ボリウッドとハリウッドの共同制作作品で興行的に成功した作品はほとんどなく、インド市場進出の難しさが浮き彫りとなっている。
公電の情報によると、ハリウッドのプロダクションがなかなかインドで地盤を固められない大きな理由のひとつは、インドのプロダクションがハリウッドの大規模な参入を望んでいないからである。インド側はハリウッドに対し、資金提供は歓迎するが、それ以上の参加は好ましく思っていない。例えばUTVモーション・ピクチャーズのスィッダールト・カプールCEOは、「ボリウッドのプロダクション・スタジオはハリウッドを競争相手と見ている」と端的に述べている。小さなプロダクションの場合はより資金難である場合が多く、大きなプロダクションに比べてハリウッドとの資本提携に積極的な面があるが、ハリウッド側としても現地の大手プロダクションと共に大規模な作品を作ってインドでのプレゼンスを高めたいというのが本音であり、なかなか双方の意志が合致しないようだ。また、ハリウッドと違ってインドの映画産業はオーガナイズされておらず、ハリウッドのプロダクションがインドの映画人と協力するためには、機転の良さと柔軟性が求められるとも助言されている。
よりリスクの少ない提携法としては、インドでの撮影や編集のアウトソーシングである。だが、公電によると、これらも効果的ではない。例えばハリウッド映画のロケをインドで行うにしても、撮影許可を取得するために多くの関係機関からクリアランスを得る必要がある上に賄賂も支払わなければならず、なかなかスムーズな撮影にはならない。インドの映画制作者たちですら、その煩雑さを敬遠して、インド本国ではなく、オーストラリア、ニュージーランド、スイス、米国などでロケを行っている有様である。それでもインドロケのハリウッド映画は近年いくつか見られる。最近ではジュリア・ロバーツ主演「Eat
Pray Love」(邦題「食べて、祈って、恋をして」;2010年)が記憶に新しいが、一部インドロケであり、全編インドロケというハリウッド映画はほとんど聞かない。ほぼ全編インドロケの外国映画と言うと最近では「The
Darjeeling Limited」(邦題「ダージリン急行」;2007年)や「Slumdog Millionaire」(邦題「スラムドッグ$ミリオネア」:2008年)ぐらいか。また、編集のアウトソーシングにしても、技術的にはインドは米国に劣っていないものの、一部のシーンの編集ならアウトソーシングすることはあるが、全てのシーンの編集をアウトソーシングするような大胆なコストカットをする監督はいないとのことである。
プレプロダクションから、特殊効果やメイクアップなどの裏方、国際マーケティングや配給などのポストプロダクションなどの分野でのパートナーシップはもっとも将来性があると公電は書いている。既に、ハリウッドの人材がボリウッド映画を裏で支える事例はいくつもある。「Krrish」(2006年)では特撮やアクションにおいてハリウッドや香港の人材が起用されているし、海をテーマにしたユニークなヒンディー語映画「Blue」(2009年)にはハリウッドの水中撮影エキスパート、ピーター・ズッカリーニが参加している。インド国外におけるマーケティングや配給での提携例はさらに多く、上で挙げた「My
Name Is Khan」の世界配給などがその一例である。
また、逆にインドのプロダクションが世界進出への野望からハリウッドに進出する例も見られるようになった。もっともアクティブなのがアニル・アンバーニー率いるリライアンス・ビッグ・ピクチャーズである。同社はスティーブン・スピルバーグのドリームワークスの株式50%を取得した他、ニコラス・ケイジ、ジム・キャリー、トム・ハンクス、ブラッド・ピット、ジュリア・ロバーツ、ジョージ・クルーニーらハリウッド・スターたちが所有するプロダクションともパートナーシップを築いている。また、同社はインド系移民が多い地域の映画館を買収し、ボリウッド映画やその他インド諸語の映画を上映している。UTVモーション・ピクチャーズも、20世紀フォックスとMナイト・シャーマーラン監督「The
Happening」(2008年)を共同制作したりしている。
最近インドの先進的映画監督たちは、しきりに「インド映画のグローバル化」を主張している。「グローバル化」の意味は様々である。伝統的インド映画のフォーマットから脱却して、ハリウッド的なフォーマットの娯楽映画を作ろうとする監督もいれば、インド国内よりも海外の観客を意識したメッセージを込めた映画を作る監督もいる。だが、僕自身その方向性には懐疑的であるし、米外交公電でも否定的な見解が見られる。KPMGのタッカル氏の発言として記されているのは、「インドの映画産業はまだグローバルな観客に向けたユニバーサルなアピール力のあるコンテンツ作りが出来ていない」という言葉である。以下、そのまま引用する。
「インド映画のジャンルはハリウッド映画と大きく異なる。インド映画は長く、多くの歌や踊りがあり、西洋の観客にとってドラマチック過ぎる。インドの商業映画のいくつかは旧ソビエト連邦やアフリカなど一部で成功しており、少数のアート映画プロダクションは利益を上げているが、インド映画の海外収入は依然としてインド系移民観客に依存している。新しい監督の中には、西洋の映画作りに影響を受け、世界の映画界の中でより広範な観客にアピールするため、欧米人の感覚に配慮しながらインド映画を作っている者もいる。しかしながら、総じて、インド映画界の中では誰も、インド人観客に人気の映画が真の意味でグローバルな観客に受けるとは考えていない。これを考慮するに、インドの娯楽企業は、インド国外の観客にアピールするような、インド人観客と切り離したコンテンツ開発を望んでいる。」
ただ、公電のこの見解は多少時代遅れに感じる。一線で活躍する監督やプロデューサーはさらに進んだ見解を持っている。例えばラーケーシュ・オームプラカーシュ・メヘラー監督は、2010年9月17日付けタイムズ・オブ・インディア紙掲載のインタビューの中でこんなことを語っている。
「我々は娯楽をさらにインディアナイズする方向へ舵を取るべきだ。よりインド的になれば、よりグローバルなアピールになる。・・・インドは自分たちの文化を映画を通して輸出できるだろうか?我々は音楽、文学、料理を通してそれを成し遂げたが、映画ではそれほど成功していない。しかし、西洋人好みのカレーを作るためにスパイスを減らさなければならなかった。おそらく映画にもそれが必要だろう。」
つまり、スパイスを減らしながらも、よりインドらしい映画にして行くような、一見矛盾した映画作りの方向性が、今後のインド映画の国際戦略の要となって行くと予想している。そのような映画を作ることは困難であるが、「Peepli
[Live]」(2010年)などを見る限り、徐々に完成形に向かいつつあると考えられるし、その予想は間違っていないだろう。そしてこのレス・スパイス・モア・インディアンな映画作りに真っ先に挑戦しているのがヒンディー語映画界であり、そういう意味ではやはりインド映画産業をリードするのはヒンディー語映画界以外にないことになる。
最近公開された米外交公電に書かれていたボリウッド関連の記述は以上である。特に新事実があった訳ではなく、インド映画を丁寧に観察して来ている人なら誰でも書けるような内容である。ただ、これよりもむしろ個人的にショッキングだったのは、今年2月3日にウィキリークスによって公表された、在ロンドン米国大使館からの公電である。その公電のReference
IDは07LONDON4045で、作成日は2007年10月25日。題名は「EUR SENIOR ADVISOR PANDITH AND S/P ADVISOR COHEN’S
VISIT TO THE UK, OCTOBER 9-14, 2007」。これは、米国国務省のムスリム代表ファラー・パンディト(インドのジャンムー&カシュミール州生まれ)と政策企画室のジャレッド・コーエン(米シンクタンク、グーグル・アイデアズの現ディレクター)が英国を訪問したときの文書である。その中に「ボリウッド」という見出しの章があり、こんなことが書かれている。
「10月10日、パンディトとコーエンは映画関係の南アジア系コミュニティーの代表と会談し、アンチテロのメッセージを伝達するために、ボリウッドと呼ばれるインド映画産業との協力についてその可能性を議論した。・・・活発な議論の中で多くのアイデアが出された。例えば、既存のアンチテロ映画のプロモーションや、同様の作品制作のための資金集めなどの方法についてである。ひとたびこのようなアンチ過激派ジャンルが確立すれば、参加者の信じるところによれば、ボリウッドの大御所たちもこの問題について言及するようになるだろう。」
また、冒頭のサマリー部分ではさらに踏み込んだことが書かれている。
「ボリウッドの俳優たちや重鎮たちは、サードパーティーの俳優たちを通してアンチ過激派メッセージを推進するために米国政府と協力することで合意し、ハリウッドとのパートナーシップ案にも乗り気である。」
これが2007年のことである。その後、どんなアンチテロ映画がインドで作られて来たか。テロリストを悪役にしたアクション映画は増えたが、それは911事件後しばらく経ってから自然と見られるようになった現象であり、この公電とは関係ないと思われる。思い当たるのは、米国のムスリム・コミュニティーを主人公にした映画群の方だ。2009年には「New
York」と「Kurban」、2010年には「My Name Is Khan」と、似たようなテーマの映画が続けて公開された。特に「My Name
Is Khan」は必要以上にオバマ大統領に肩入れした内容になっており、当時は違和感を覚えたものであった。ボリウッドの映画界が米国政府の政策の影響下に映画作りをしているとしたら、非常にショッキングなニュースである。
さらに、2010年12月16日に公表された米外交公電(Reference ID: 07NEWDELHI1485、Subject: OPPORTUNITIES FOR INDIAN SOFT POWER IN AFGHANISTAN、作成日:2007年3月28日、作成者:在ニューデリー米国大使館)では、アフガーニスターンでボリウッドが人気であることから、ボリウッドのセレブリティーの中から有志を募ってアフガーニスターンに旅行してもらい、アフガーニスターン統治に役立てる方策が提案されている。アフガーニスターン・ロケのインド映画というと「Kabul
Express」があるが、公開年は2006年で、この公電が作成されたときには既に公開されている。その後、米国外交官の思惑通りアフガーニスターンを訪問したボリウッドのセレブリティーは、僕の記憶の中にはいない。だが、ウィキリークスによってリークされたこれらの外交公電からは、米国がボリウッドの動向を常に注視しており、あわよくばその人気や影響力を米国のために役立てようとしている様子が容易に見て取れる。ボリウッドは日本人や一般の米国人の目から見たら局地的な人気を誇っているに過ぎない映画産業かもしれないが、ハリウッドとは重ならないその市場の特異性と影響力の強さから、ちゃんと国際情勢裏マップに載っているのである。
一種の流行であろうか、ヒンディー語映画界では、映画スターの妻が映画を監督・プロデュースすることが目立って来ている。シャールク・カーンの妻ガウリー・カーン、アクシャイ・クマールの妻トゥインクル・カンナー、アーミル・カーンの妻キラン・ラーオなどなど、急に「内助の功」が表舞台に立つようになって来た。その一方で、面白いことにその逆転現象も出現した。元ミス・ユニバースの女優ラーラー・ダッターの夫でテニス選手のマヘーシュ・ブーパティが映画プロデュースに乗り出したのだ。その第1作が本日より公開の「Chalo
Dilli」。もちろん主演はラーラー・ダッター。なぜかクレジットにプロデューサーとしてマヘーシュ・ブーパティの名前が載っておらず、代わりにカヴィター・ブーパティ・チャッダーなる人物の名前が出ているが、マヘーシュ・ブーパティのプロデュースであることは確実のようである。
「Chalo Dilli」とは、かつてインド国民軍(INA)を創立し日本軍と協力したスバーシュ・チャンドラ・ボースが掲げた反英スローガンである。元来の意味は「デリーへ行こう」であるが、軍事的なスローガンであり、「(英領インドの首都)デリーへ攻め込め」というニュアンスが強い。だが、この映画の内容はチャンドラ・ボースとやINAとは全く関係ない。監督は隠れた名作「Dasvidaniya」(2008年)のシャシャーント・シャー。アクシャイ・クマールのサプライズ出演もあり、意外に話題性に富んだ作品である。
題名:Chalo Dilli
読み:チャロー・ディッリー
意味:デリーへ行こう
邦題:レッツゴー・デリー
監督:シャシャーント・シャー
制作:クリシカー・ルッラー、ラーラー・ダッター、カヴィター・ブーパティ・チャッダー
音楽:ゴウロヴ・ダースグプター、アーナンド・ラージ・アーナンド、サチン・グプター、ローヒト・クルカルニー、ローシャーン・バールー
歌詞:マンタン、アーナンド・ラージ・アーナンド、クリシカー・ルッラー、シャッビール・アハマド、ニシャー・マスカレナス
出演:ラーラー・ダッター、ヴィナイ・パータク、アクシャイ・クマール(特別出演)、ヤーナー・グプター(特別出演)
備考:PVRプリヤーで鑑賞。
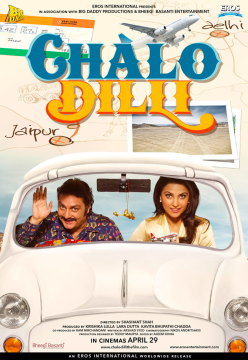
ヴィナイ・パータク(左)とラーラー・ダッター(右)
| あらすじ |
大手投資銀行ムンバイー支店の頭取を務めるキャリアウーマンのミヒカー・バナルジー(ラーラー・ダッター)は、デリー経由でロサンゼルスへ行くことになった。その途中、デリーで夫と誕生日をそそくさと祝うことにしていた。
ところがミヒカーはデリー行きの飛行機に乗り遅れてしまう。その原因となったのが、同じくムンバイーからデリーへ向かっていたチャーンドニー・チャウク在住の商人マンヌー・グプター(ヴィナイ・パータク)であった。マンヌーが道の真ん中でスーツケースの中身をこぼしてしまったために渋滞が発生し、時間内に空港に辿り着けなかったのだった。ミヒカーは代わりの飛行機に乗り込んだが、近くにはマンヌーも乗っていた。マンヌーが大声で隣の席の乗客とたわいもない話を始めたため、ミヒカーは無理矢理眠ることにしたのだった。
空港に着いたミヒカーは、そこがデリーではなくジャイプルであることにやっと気付く。何らかの原因でデリー空港に着陸できず、飛行機はジャイプルに来てしまったのだった。ミヒカーは機内で眠っていたためにアナウンスを聞き逃していた。既に夜中になっていたが、ミヒカーはタクシーを雇ってデリーまで行くことにした。ところがその運転手がノロノロと運転するために喧嘩になってしまう。そこにちょうどいたのがまたもマンヌーであった。マンヌーは勝手にタクシーに乗り込んで来て、運転手に代ってタクシーを運転し始める。ところが途中で道を間違えてしまい、デリーへ行くはずが正反対のアジメールへ向かっていた。しかも途中でタクシーが故障してしまう。マンヌーはトラックをヒッチハイクし、ミヒカーを連れて近くのダーバー(安食堂)まで行く。そこで2人は腹ごしらえをし、一眠りする。
翌朝、2人はラクダ車と乗り合いジープを乗り継いでヌーアー駅まで行く。ヌーアー駅からは早朝デリー行きの列車が出ていた。ミヒカーはこれで無事デリーに着くと思ったが、いつの間にか財布をすられており、一文無しになっていた。しかも既にマンヌーと別れており、列車に乗り遅れそうになる。しかし、それに気付いたマンヌーが緊急停止用チェーンを引っ張り列車を止め、ミヒカーを列車に入れる。また、車掌を言いくるめてキセル乗車になってしまったミヒカーを助ける。しかし、彼が緊急停止用チェーンを引いたことが車掌にばれてしまい、2人はジュンジュヌー近くの警察署に連行される。ところがそこで警察署は地元ギャングの襲撃を受ける。マンヌーはギャングの車に乗せてもらう。ミヒカーの持っていたノートPCがギャングに奪われてしまったものの、何とか2人は無事にジュンジュヌーまで辿り着いた。
ジュンジュヌーでミヒカーは夫のヴィクラム(アクシャイ・クマール)と連絡が付き、迎えに来てもらうことになった。ところがそのホテルで地元ギャング同士の争いが起き、それが町中に飛び火して、町に外出禁止令が発令されてしまう。これではヴィクラムも町に入って来られないのではないかと危惧したミヒカーであったが、夫は軍人であり、特別に入って来ることが出来た。ヴィクラムはミヒカーと共にマンヌーも連れてデリーへ向かう。
ヴィクラムとマンヌーはチャーンドニー・チャウクでマンヌーを下ろし、別れる。その後、ミヒカーは、明日の誕生日パーティーにマンヌーを招待することを思い付き、チャーンドニー・チャウクまで引き返してマンヌーの家を訪ねる。そこで見たものはマンヌーの植物人間状態の妻の姿であった。マンヌーは一言もそれを彼女に話さなかった。他人を悲しい気持ちにさせたくないというマンヌーの配慮からであった。マンヌーは誕生日パーティーへの招待を快く受け取る。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
死期を迎えようとする朴訥な男性を主人公とした「Dasvidaniya」を見て、シャシャーント・シャー監督は日本人好みのハートに響く繊細な映画を作ることの出来る人物だと感じたが、この「Chalo
Dilli」ではさらにその印象を深くした。ハートに響くだけではない。今回はロードムービー仕立てであり、インドの旅情がよく出ていた。それもバスや列車を乗り継ぐような、地べたを這った形の旅情である。それを、普段はビジネスクラスやファーストクラスの飛行機で移動するキャリアウーマンの視点から描いており、外国人の視点と近いものがあった。当然、万事がうまく行くとは限らず、次々とトラブルが発生する。ジャイプルからデリーへ約250kmを陸路で行くだけなのに、主人公ミヒカーはなぜかトラック、ラクダ車、乗り合いジープ、列車(しかもエアコンなしの一般車両)を乗り継ぐ形になり、挙げ句の果てにギャングの抗争にまで巻き込まれる。だが、思い通りに進まなければ進まないほど、新たな出会いが積み重なって行き、人々の親切や温情に触れることになる。このような体験は、インドを貧乏旅行した人なら誰でもひとつやふたつはしたことがあるのではなかろうか?そういうインド旅行の楽しさがよくスクリーン上に再現された映画であった。
また、「Chalo Dilli」は、キャリア志向で既婚ながら子供を持つことを避けている女性に対するアンチテーゼでもあった。主人公のミヒカーは絵に描いたようなキャリアウーマンであり、仕事中心の生活をしていた。仕事の関係で夫ヴィクラムとも別居しており、ミヒカーはムンバイーに、ヴィクラムはデリーに住んでいた。ムンバイーからデリー経由でロサンゼルスに出張することになり、ちょうど彼女の誕生日も来ていた。普通ならデリー在住の夫と誕生日を祝うところであり、ヴィクラムはパーティーを企画していたが、仕事中心のミヒカーは夫と自分の誕生日を祝うことすらフォーマルに済まそうとしていた。しかし、チャーンドニー・チャウク在住で、どんな人ともすぐに仲良くなってしまう人情味溢れた下町気質のマンヌーと旅する内に、彼女の心にも変化が訪れた。マンヌーと別れ、ヴィクラムと再会した後、彼女はロサンゼルス行きを遅らせ、夫と誕生日パーティーを開くことを決める。そして言外に子作りの意志も匂わせる。そういう意味では、いかにもインド映画らしい、家族を第一とする保守的なメッセージが込められた映画だと言える。
映画は基本的にコメディータッチで進んで行く。笑いの中心は間違いなくマンヌーであり、彼の言動の中でも特におかしいのが彼の口癖「カォーン・スィ・バリー・バート・ホー・ガイー(何も大事じゃないだろう)」である。潔癖症のミヒカーは当初マンヌーのがさつな行動ひとつひとつに嫌悪感を覚え、自分が突如として置かれてしまった酷い状況に絶望するのだが、マンヌーはそれらを上記の口癖で片付けてしまう。中盤にさしかかった辺りで観客の脳裏にも自然にその口癖がこびりついてしまい、マンヌーがそのフレーズを口にするたびにおかしさがこみ上げて来る。だが、映画の笑いを一手に引き受けるこの言葉に、涙の結末の伏線が隠されていたのは見事だった。一度マンヌーと別れた後、ミヒカーは引き返して彼の家を訪ねる。そこには彼の妻が植物人間状態で横たわっていた。彼は、他人にはそのことを教えず、誰にも悲しみを露わにせず、仕事をしながら賢明に彼女を支えて来たのだった。彼にとって、確かにミヒカーが直面した問題は「大事」ではなかった。ミヒカーは彼の口癖の秘密を解明できた喜びと共に、一気にマンヌーの人間性に感服してしまう。
ヴィナイ・パータクは「Dasvidaniya」の主演男優で、既に堅実な演技が出来る個性派男優としてヒンディー語映画界において地位を確立している。「Chalo
Dilli」でもキャラクターに入り込んだ絶妙の演技を見せており、今一度実力を証明した。だが、この作品は何と言ってもラーラー・ダッターのためにある。ミスコンでの栄冠を経て映画界デビューする女優は多いものの、必ずしも成功する訳ではない。最近ではアイシュワリヤー・ラーイ・バッチャンを筆頭に、スシュミター・セーンやプリヤンカー・チョープラーなどが成功を手にしたと言えるが、その他のミスコン出身女優はパッとしない。2000年のミス・ユニバースに輝いたラーラー・ダッターもいまいち代表作に恵まれなかったのだが、「Billu」(2009年)辺りからいい役をもらえるようになり、この「Chalo
Dilli」で正にピッタリの役に巡り会えたと言っていい。この映画がヒットするかどうかは現時点で分からないが、彼女の代表作の1本となるであろう。
驚いたのはアクシャイ・クマールが終盤でサプライズ出演していたことである。ミヒカーの夫ヴィクラムを演じていた。どういうつながりで彼の特別出演が成立したのかは不明である。他にヤーナー・グプターがアイテムナンバー「Laila
O Laila」にアイテムガール出演していた。
音楽はゴウロヴ・ダースグプター、アーナンド・ラージ・アーナンド、サチン・グプター、ローヒト・クルカルニー、ローシャーン・バールーなど多数の音楽家による合作となっている。アイテムナンバー「Laila
O Laila」と、ミヒカーとマンヌーが列車に乗り込んだときに流れる「Chalo Dilli」ぐらいしか挿入歌はなく、音楽やダンスは二の次の映画となっている。
劇中ではジャイプルからデリーへ向かうはずが反対方向、ラージャスターン州の奥深くへ行ってしまう。デリーやジャイプルは実在の地名であるが、その他映画中に登場するヌーアーやジュンジュヌーと言った地名も実際に存在する。しかし本当に現地でロケが行われたかどうかについては疑問である。ラージャスターン州で撮影されたことは間違いないと思うが、それ以外場所を特定できるようなランドマークが映っていなかった。特にジュンジュヌーは壮麗な壁画のハヴェーリーや寡婦殉死の悪名高いサティー寺院などで有名だが、それらは全く出て来なかった。
「Chalo Dilli」は、ラーラー・ダッターとヴィナイ・パータクの「パーフェクト・ミスマッチ」と、インドの旅情溢れるロードムービー風展開が楽しい佳作である。インド映画らしさは希薄だが、インドらしさは満点。インド旅行好きな人に特にお勧めしたい。



