以前、「サヴィター・バービー」というインド初のオンラインエロ漫画サイトを紹介したことがある(参照)。紹介と言っても、インドの法律に抵触する恐れがあったため、URLは公開しなかった。「サヴィター・バービー」は、インド人男性のフェティシズムを直撃する巧みな設定やストーリー展開のおかげで、日常的にネットを利用している層のインド人の間で密かな大ヒットとなっていたのだが、今年6月にインド政府によって突然アクセスを禁止されてしまった。その後もサイトは続いていたようだが、インドからは、プロキシをかませたり、勝手に転載しているサイトなどを探し出したりして、工夫しなければ、閲覧は不可能な状態であった。
最近、その「サヴィター・バービー」が、新しいドメインと共にカムバックを果たしたとのニュースが駆け巡った。新ドメインはkirtu.com。しかし、政府の対応も早かったようで、既にインドからアクセスは出来ない状態となっている。多分日本からはアクセスできるのではなかろうか?
漫画の国、日本に生まれ育って来たので、インドにおける漫画の現状には常に関心を持って見て来た。インドに漫画がないことはないが、新聞漫画の域を出なかったり、宗教漫画に徹していたり、オリジナル性がなかったりして、日本のようなバラエティーに富んだ展開は見られない。21世紀に入ってからは、サールナート・バナルジーらによるグラフィック・ノベルが新たな風を呼び込んだが、それも一部で話題となったのみで、文化と言えるほど定着はしていない。山松ゆうきち氏による漫画普及の努力は再三ここでも紹介して来たが、少なくともインド人には何のインパクトも与えなかったと言っていい。よって、インドを漫画後進国と呼んでも差し支えはないだろう。そもそも大半のインド人は漫画を子供の読むものと考えており、芸術として真剣に取り扱おうとする気がない。僕は、日本における漫画の役割は、インドでは映画が果たしており、無理にインドで漫画を広める必要はないと考えている。各民族の気性に合ったメディアというものがあるはずで、インド人には映画がもっとも適したメディアなのであり、そうならそれでいいと思う。
そんな逆境の中、オンライン漫画の「サヴィター・バービー」は、かなりインド人男性の心理に食い込むことに成功した漫画だと言える。もし、インドで漫画を広めようとしたら、オンライン漫画がもっとも見込みがありそうだ。「サヴィター・バービー」の他にもインド人やインド系移民によるオンライン漫画がいくつかネット上で人気を博しているようである。もっとも、ほとんどのオンライン漫画は無料で公開されており、作者は趣味の一環として公開している状態であるため、これをビジネスにして行くことは困難であろう。
「サヴィター・バービー」を除くと、もっとも成功しているインド製オンライン漫画は、おそらくFly, You Fools!というサイトである。作者はサード・アクタルというITエンジニアで、アハマダーバードの国立デザイン学校卒、デリー在住。フォトショップを使った写真加工によって読み切り漫画を作成し、数日に1回のペースでアップデートしている。基本は風刺で、ユニバーサルなネタも多いが、インド在住、特にデリー在住の人々の琴線に触れるようなものが秀逸である。
転載はフリーとのことなので、いくつか面白かったものをピックアップしてみようと思う。やはりITエンジニアなだけあり、コンピューター関連のネタを結構取り上げており、それには思わず頷いてしまうものも多い。例えばパスワードをネタにした以下の漫画。
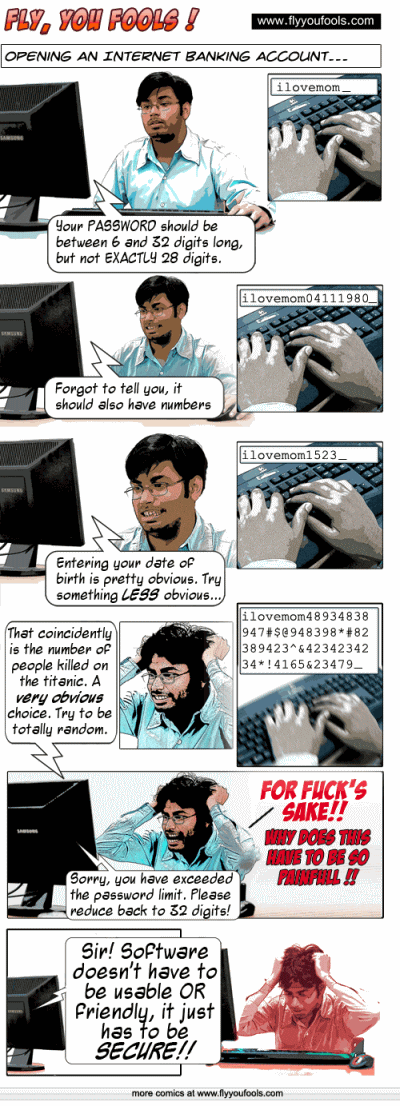
世界中で人気のツイッターをネタにした漫画も分かりやすい。シャシ・タルールについては、インドでもTwitter旋風を参照のこと。

かなりの著名人も登場させてしまっている。以下はターター・グループのラタン・ターター会長がネタになっている。
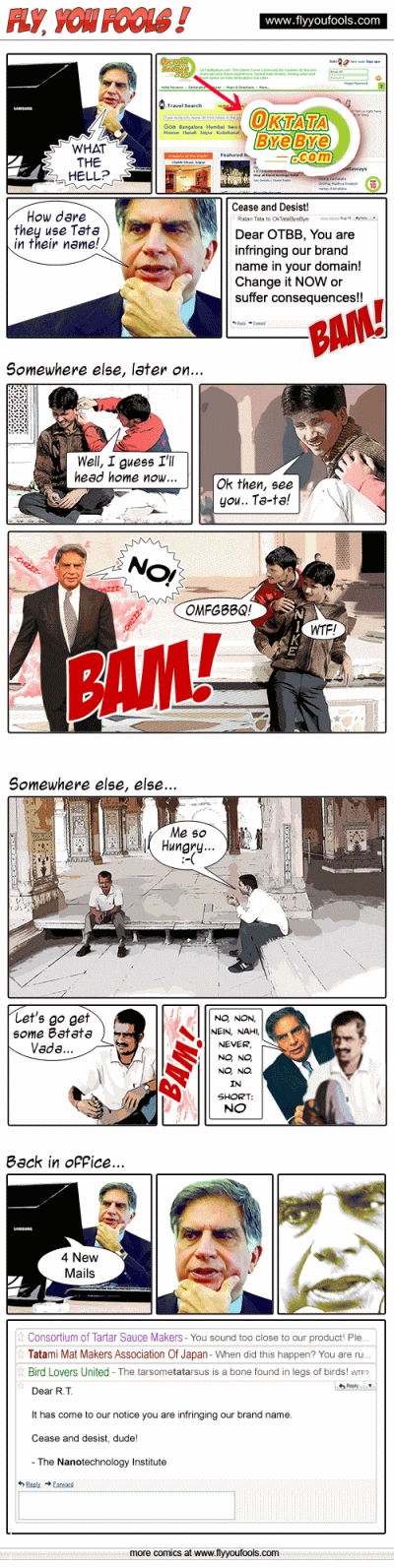
さらには、インドのマンモーハン・スィン首相とパーキスターンのアースィフ・アリー・ザルダーリー大統領までも登場してしまう。2008年11月26日のムンバイー同時テロ事件で生け捕りされたテロリストがネタになっている。ただしこれはサード・アクタル自身の作品ではなく、ゲストによる作品のようだ。
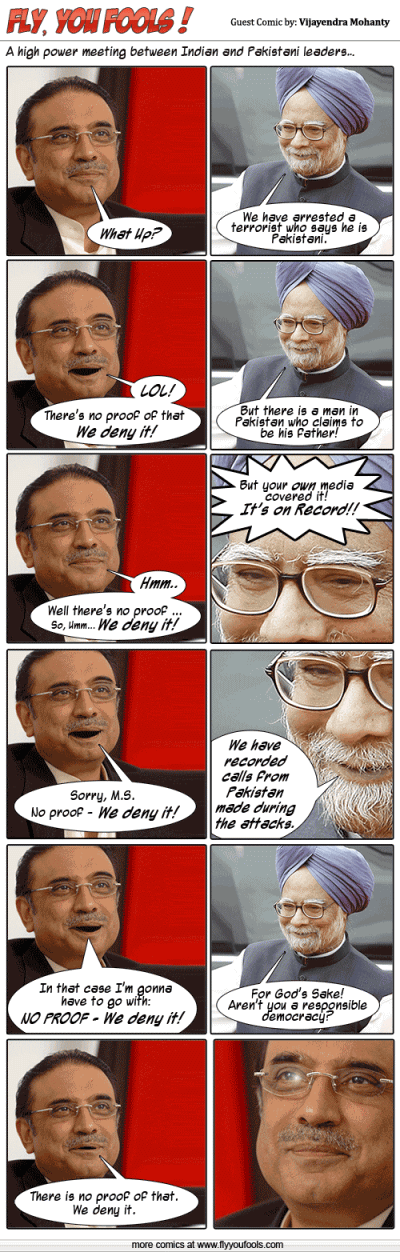
これらはインドに住んでいなくても大体理解できるだろうが、以下のものはインド在住者でないと素直に笑えないかもしれない。まずはインドのニュース番組を皮肉った一本。

下のものは、人気女優カトリーナ・カイフが出演しているマンゴージュースのCMをネタにしている。
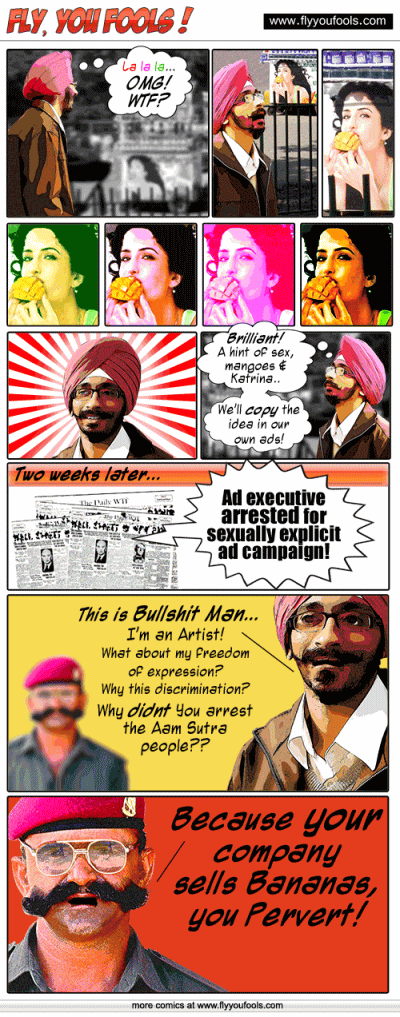
作者がデリー在住なだけあり、デリーをおちょくった作品もいくつかある。以下のものは、バンガロール在住者を馬鹿にしているようで、実際はデリー在住者を馬鹿にしている。
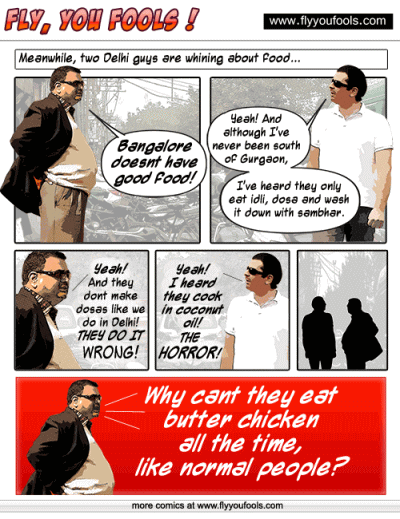
以下はデリー観光をネガティブに捉えたネタ。

はっきり言って、「サヴィター・バービー」と「Fly, You Fools」以外のインド製オンライン漫画は、日本人に紹介するレベルのものではなく、「インドでオンライン漫画が流行中」とはまだまだ言えない状態なのだが、今後発展の余地は十分ありそうである。インドではインターネットから漫画が普及して行くかもしれない。
かつてインド中でヒメーシュ旋風なるものが吹き荒れたことがあった。ヒメーシュ・レーシャミヤーは、音楽監督や歌手として人気を集め、遂に俳優業にまで進出したマルチタレントの人物である。赤いキャップ、泥棒髭、黒いロングコートという独特の出で立ちにして、マイクを逆さに持ち、鼻にかかった歌声で熱唱する姿が大流行した。とは言っても、彼の作る歌はどれも同じに聞こえるという大きな欠点を抱えており、冷静に見たら決して天才的な音楽家ではない。むしろ、ヒメーシュ旋風絶頂期には、「ケッ、またヒメーシュか。こんな歌のどこがいいんだ」とけなしていたぐらいである。しかし、けなしながらもなぜか気付くとヒメーシュの歌をうっかり口ずさんでいるという不思議な現象が繰り返された。ヒメーシュは決して天才ではないかもしれないが、彼の作る歌には、聴く者の脳裏にしがみついて離れない何かがあることは確かである。
ヒメーシュの音楽については様々な角度から議論する余地があるが、彼の演技については一言で断言できる。はっきり言って大根役者である。ヒメーシュはこれまで、「Aap
Kaa Surroor」(2007年)、「Karzzzz」(2008年)と主演して来た。「Aap Kaa Surroor」の方は、その大根役者振りが批判の的となったものの、ヒメーシュ旋風の勢いに乗ってヒットとなった。2作目の「Karzzzz」では、思い切ってトレードマークだった帽子を捨て、ヘンテコな髪型をして登場した。演技に一応の進歩が見られたものの、過去の大ヒット作の単純なリメイクだったこともあり、こちらはフロップに終わった。この頃にはヒメーシュ旋風もだいぶ落ち着いて来ており、彼の新作を耳にすることもめっぽう少なくなった。
そのヒメーシュが久々にスクリーンに登場することになった。主演3作目となる「Radio」を引っさげて。「Karzzzz」で帽子を捨てたヒメーシュだが、今度はなんと鼻声を捨て、さらなるイメチェンを図っており、大きな話題となっている。噂では鼻の手術を受けたらしい。確かに先行発売された「Radio」のサントラCDを聞くと、声が変わっている。CDのジャケット自体に「ヒメーシュの新声」と書かれている。
題名:Radio
読み:ラジオ
意味:ラジオ
邦題:ラジオ
監督:イシャーン・トリヴェーディー
制作:ラヴィ・アガルワール
音楽:ヒメーシュ・レーシャミヤー
歌詞:スブロート・スィナー
振付:ロンジネス・フェルナンデス
衣装:プレールナー・ジャイン
出演:ヒメーシュ・レーシャミヤー、シェヘナーズ・トレザリーワーラー、ソーナル・セヘガル、パレーシュ・ラーワル、ザーキル・フサイン、ダルシャン・ジャリーワーラー
備考:PVRアヌパムで鑑賞。
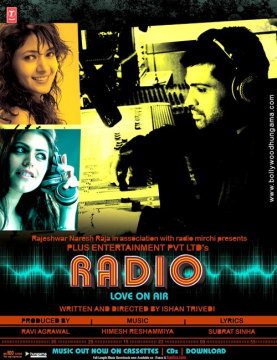
左はソーナル・セヘガル(上)とシェヘナーズ・トレザリーワーラー(下)、
右はヒメーシュ・レーシャミヤー
| あらすじ |
ヴィヴァーン・シャー(ヒメーシュ・レーシャミヤー)はラジオジョッキーで、リスナーの悩みを聞いては気の利いた助言をし、人気を集めていた。だが、ヴィヴァーン自身の人生は非常に混乱していた。ヴィヴァーンは、5年連れ添った妻プージャー(ソーナル・セヘガル)から一方的に離婚を突き付けられ、裁判所からも離婚を認められてしまった。その日にヴィヴァーンは、シャナーヤー(シェヘナーズ・トレザリーワーラー)という女の子と出会う。シャナーヤーと仲良くなったヴィヴァーンは、最近低迷していたラジオ番組を活性化させるため、シャナーヤーをラジオに登場させる。ヴィヴァーンとシャナーヤーの間に恋が芽生えていることにし、2人の会話によってリスナーの関心を引き寄せた。瞬く間にシャナーヤーも人気ラジオジョッキーの仲間入りする。
シャナーヤーの父親ディングラー(ザーキル・フサイン)は警察官僚の大物であった。ディングラーは最初、ヴィヴァーンと娘の仲を疑う。ヴィヴァーンも、番組のために恋人の振りをしているとは言えず、プロデューサー(ダルシャン・ジャリーワーラー)の圧力もあって、シャナーヤーと付き合っていると語る。一転してディングラーはヴィヴァーンを受け容れ、以後彼は家族の一員のような扱いとなる。2人の恋愛はメディアによって大きく取り上げられ、ヴィヴァーンとシャナーヤーの公開結婚式がテレビ中継された。
一方、プージャーは自分から希望して離婚したものの、やはりヴィヴァーンがいなければ寂しいことに気付く。ヴィヴァーンとプージャーは何となくまた会うようになる。シャナーヤーもヴィヴァーンが離婚したことを知っており、プージャーと面識になる。こうしてヴィヴァーン、プージャー、シャナーヤーは3人で会うようになり、奇妙な三角関係が生まれる。プージャーはヴィヴァーンへの思いを再燃させており、ヴィヴァーンとシャナーヤーがいちゃつく様子に嫉妬する。一方、シャナーヤーはヴィヴァーンとの仲が作られたものであることに次第に不満を感じるようになって来る。だが、プージャーとシャナーヤーの仲は良好であった。
シャナーヤーは次第にストレスをため込むようになる。ヴィヴァーンもシャナーヤーが家族に秘密をばらしたと思い込み、彼女を避けるようになる。とうとう絶え切れなくなったシャナーヤーはラジオ番組を降板することを決める。シャナーヤーの最後の出演を、ヴィヴァーンとプージャーは一緒に聞いていた。偶然シャナーヤーのところには、リスナーから恋愛の三角関係に関する質問が来ていた。シャナーヤーは、もし好きな人が別の人を好きなら、潔く身を引くべきだと答える。
それを聞いたプージャーは、自分がヴィヴァーンとシャナーヤーの仲の障害になっていることに初めて気付き、思い切ってヴィヴァーンを突き放す。晴れて自由な立場で考えることができるようになったヴィヴァーンは、シャナーヤーに今まで言えなかった愛の告白をする。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
映画はいくつかのチャプターに分かれており、主人公ヴィヴァーン自身のナレーションによって進行して行く。プロットにはいくつか盛り上がる部分があるものの、大半の重要な展開がチャプター分けとナレーションによって説明されており、映画的な面白味に欠けた。最後の告白のシーンにしても、あまりに説明的で、雰囲気を台無しにしていた。映像で語れば十分なことをわざわざ言葉で語り直すため、野暮ったい恋愛映画になってしまっていた。ヒメーシュの演技も相変わらずで、彼の下手な演技をカバーするために編集を工夫してこのようにせざるをえなかったのではないかと邪推してしまった。もし、大根役者ヒメーシュが真っ当な演技をしているように見えるように工夫して作った映画ということなら高い点数をあげたいが、一般のロマンス映画として土俵に立つなら、失敗作の烙印以外は押せない。
ストーリー自体はそんなに悪くない。離婚したはずだがなかなか腐れ縁の切れない妻と、仕事上の都合から付き合っていることになってしまった女性との間に板挟みになる男性が主人公ながら、お決まりのドロドロとした三角関係フォーミュラにはギリギリのところで乗せず、かなり新鮮な関係に持って行っていた。すなわち、元妻と偽恋人が仲良くなってしまうのである。また、主人公自身も一方的に離婚されたときのショックが残っており、正常に人間関係を分析する能力を失っていた。だから、元妻とよりを戻せばいいのか、偽恋人とこのまま本当の恋人になって結婚すればいいのか、理解できなかった。この混乱状態をもっと丁寧に描写することが出来たら、一級のロマンスになっていたのではないかと思う。
しかし、映画はチャプターに分割されたせいでぶつ切れ状態となっており、チャプターが変わるごとにせっかく出来た流れが途切れてしまっていた。それに加えてナレーションによってストーリーが進んだり、登場人物の心情が事細かに解説されてしまうことが多く、まるで映画のオリジナルを見ているのではなく、ダイジェスト版を見ているようなつまらなさを感じた。
主演のヒメーシュは音楽畑出身の俳優であり、主演作では必ず音楽とメインボーカルを務めているため、彼の今までの主演作は、その背景を活かせるように、職業はミュージシャンという設定であった。今回はラジオジョッキーということで、少し気色の違った役柄だと思ったが、劇中でミュージシャン・デビューをしてしまい、今までとそう変わらない状態となってしまっていた。それでも、ヒメーシュが自ら作曲した「Radio」の曲の数々は、いつもの鼻声がないものの、ヒメーシュ節は健在で、いいものが揃っている。「Mann
Ka Radio」や「Teri Meri Dosti Ka Aasmaan」などが名曲である。
ヒロインはシェヘナーズ・トレザリーワーラーとソーナル・セヘガルの2人。2人ともそれほど知名度の高い女優ではない。だが、元気溌剌のシェへナーズに影のあるソーナルの対比は良く、キャスティングはうまく行っていると感じた。他には、パレーシュ・ラーワルが、ラジオで一発ギャグをかます「ジャンドゥー・ラール・ティヤーギー」としてカメオ出演していたのが特筆すべきである。
「Radio」は、「ヒメーシュ映画」というひとつの独立したジャンルの映画だと考えた方がいいだろう。ヒメーシュ・レーシャミヤーのファンなら文句なく必見である。音楽も悪くないし、ヒメーシュの新声を聞いてみるのもいい。だが、映画としての出来は中の下で、一般の観客には退屈に思えるだろう。
2007年末に公開されて大ヒットとなったアーミル・カーン初監督作「Taare Zameen Par」は、ディスレクシア(失読症)という病気を扱った作品であった。特定の難病を扱った映画が割と簡単に一定の感動を呼ぶドラマとなることは周知の事実で、洋の東西を問わず、そういう映画は多いし、その中には名作も多い。現在公開中の「Paa」も、ハッチンソン・ギルフォード・プロジェリア症候群という奇病をテーマにした作品である。これは、早老症という異称が指し示す通り、正常な子供に比べて身体が急速に老いて行く遺伝子異常の病気だ。その老化のスピードは、正常な子供の1年がプロジェリア患者の10年にあたると言う。脳機能などは正常に発達するため、年齢が進むにつれて精神と肉体の剥離が激しくなって行く。プロジェリア患者の平均寿命は13歳で、今までの最高齢が17歳。治療は不可能。現在まで146症例が確認されており、生存者は40名ほどらしい。アシュリー・ヘギというカナダ人のプロジェリア患者の症例が有名で、「アシュリー
~All About Ashley~」(扶桑社)という自伝も出ている。
とは言っても、「Paa」は最初からプロジェリアをテーマにして企画された映画ではないらしい。「Cheeni Kum」(2007年)のRバールキー監督が、あるときアミターブとアビシェークのバッチャン親子が一緒にいる様子を見ていたところ、父親のアミターブの方が子供っぽくて、息子のアビシェークの方が大人っぽい態度を取っていた。監督はその様子から着想を得て、アミターブをアビシェークの息子として映画に出せないか考えたと言う。調べてみたところ、プロジェリアという病気があり、この企画にピッタリであった。バッチャン父子も大いに父子逆転というその斬新なアイデアを気に入り、乗って来た。このようにして「Paa」は肉付けされていった映画であり、つまりはまずキャスティングありきの映画である。還暦を過ぎたスーパースター、アミターブ・バッチャンが子役を演じるということで話題性は高く、デリーで行われたロケ時にも注目を集めていた。「Introducing
アミターブ・バッチャン」の売り文句も憎い。
題名:Paa
読み:パー
意味:お父さん
邦題:パー
監督:Rバールキー
制作:ABコープ、リライアンス・ビッグ・ピクチャーズ、スニール・マンチャンダー
音楽:イライヤラージャー
歌詞:スワーナンド・キルキレー
衣装:サビヤサーチー・ムカルジー、アキ・ナルラー、ファールグニー・タークル、ヴィジェーヤター・マンチャンダー、ラーフル・アガスティ
出演:アミターブ・バッチャン、アビシェーク・バッチャン、ヴィディヤー・バーラン、パレーシュ・ラーワル、アルンダティ・ナーグ、タルニー・サチデーヴァ、プラティーク・カターレー、ニミト・ダイヤー、ヴァルン・シュクラ、ドルヴィン・ドーシー、カラン・ビワーンドカル、ガウラヴ・バジャージ、ジャヤー・バッチャン(特別出演)
備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。
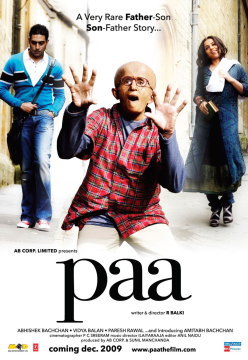
左から、アビシェーク・バッチャン、アミターブ・バッチャン、ヴィディヤー・バーラン
| あらすじ |
ラクナウーの名門校に通うオーロ(アミターブ・バッチャン)は、プロジェリアという奇病に冒され、12歳なのに既に高齢者の肉体を持っている特別な子供であった。だが、ひょうきんなオーロは学校中の人気者であった。
ある日、学校の設立50周年式典に地元選出の若き国会議員アモール・アールテー(アビシェーク・バッチャン)が来賓としてやって来る。アモール議員は二世政治家で、政界を引退した父親(パレーシュ・ラーワル)に見守られながら、着々と人気を集めている人物であった。アモール議員は子供たちがこの式典のために作った「未来のインド」をテーマにした作品を鑑賞する中で、真っ白な地球儀を見て「国境のない世界」だと感心し、この作者に最優秀賞を与えることにした。それこそがオーロであった。アモール議員はオーロの姿を見て多少驚くが、彼にトロフィーを手渡す。
オーロの母親で産婦人科医のヴィディヤー(ヴィディヤー・バーラン)は、テレビでオーロがアモール議員からトロフィーを受け取ったことを知り、驚く。実はアモールこそがオーロの父親であった。
13年前・・・ヴィディヤーは英国ケンブリッジ大学で医学を学んでいた。そのとき同大学で政治学を学んでいたアモールと出会い、恋に落ちる。しかし、避妊しなかったために妊娠してしまう。ヴィディヤーからそのことを聞いたアモールは、堕胎するように言う。ヴィディヤーは政治家を目指すアモールの重荷になりたくないと考え、アモールの前から姿を消し、子供を産んで1人で育てることを決める。母親(アルンダティ・ナーグ)も早くに夫を亡くして女手ひとつでヴィディヤーを育てて来た経験を持っており、娘の子育てを応援した。オーロがプロジェリアであることが発覚した後も、ヴィディヤーは母親と共に気丈に息子を育てて来たのだった。この間、アモールは政治家として羽ばたくが、ヴィディヤーは彼と接触しようとはしなかった。
オーロは、式典でテレビに映ったためにメディアに追いかけられるようになり、生活が困難となってしまう。オーロが怒っていることを知ったアモール議員は裁判所に訴え、メディアがオーロに近付かないように法的措置を執る。だが、まだオーロの怒りは収まっていなかった。オーロはアモール議員に、大統領官邸に行きたいと伝える。アモール議員はそれを承諾し、11日にデリーに一緒に行くことを約束する。
一方、ヴィディヤーはオーロにアモール議員こそが父親であると伝えようかどうか悩んでいた。悩んだ挙げ句、13歳の誕生日にヴィディヤーはオーロにそのことを明かす。オーロは驚きながらも、母親の気持ちを尊重し、決してアモール議員にそのことは言わないと約束する。
11日にデリーに行く約束であったが、アモール議員はスラム再開発という厄介な問題に巻き込まれており、すっかりオーロのことを忘れていた。だが、デリー出張時に大統領官邸を見てオーロとの約束を思い出し、今度こそはと再びオーロと約束する。
とうとうデリー行きの日がやって来た。アモール議員とオーロは飛行機でデリーへ飛ぶ。アモール議員は大統領官邸の中まで案内する準備を整えていたが、オーロは大統領官邸を外から見ただけで帰ると言い出す。その代わりオーロはアモール議員と一緒にデリーを観光したいと主張し、アモール議員もそれを受け容れる。2人はひとときの楽しい時間を過ごす。
ところが、オーロの寿命は次第に近付いて来ていた。入退院を繰り返すようになり、主治医もオーロの容体に警鐘を鳴らし続けていた。とうとうオーロは危篤状態となり、入院する。アモール議員はそのことを知り、病院に駆けつけるが、そこでヴィディヤーと再会してしまう。アモール議員は初めてオーロが自分の息子であることを知る。
アモール議員の隠し子のニュースはたちまち世間を駆け巡るが、アモール議員は自らの過去の過ちを素直に認め、ヴィディヤーにプロポーズをする。オーロも母親も2人の結婚を望んでいたが、ヴィディヤーはアモール議員に対して心を閉ざしており、なかなかそれを受け容れようとしなかった。しかし、今にも死のうとするオーロの前で、間違いを犯した人間は間違いを犯された人間よりも傷付いているという言葉を聞いて考えを改め、アモール議員と手を取り合う。それを見たオーロは、アモール議員に「お父さん」とつぶやき、息を引き取る。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
プロジェリアという奇病と、12~3歳の子供となったアミターブ・バッチャンのビジュアルが注目を集めているが、プロットの核心は、離れ離れとなった男女を、2人の間に出来た子供がキューピッドとなって結び付けるというもので、敢えて言うならば、名作「Kuch
Kuch Hota Hai」(1998年)と近い筋の作品であった。また、死に行く人が男女を結び付けるという点に注目すれば、これまた名作「Kal
Ho Naa Ho」(2005年)にも共通するものがある。つまり、「Paa」は、ボリウッドで培われて来た黄金の方程式に則ったプロットの上に成り立った作品であり、主人公のオーロがプロジェリアでなくてもストーリーは何とか成立した。それでも、オーロの愛らしい姿(ポスターなどでは気色悪く見えるかもしれないが、不思議とスクリーン上では愛らしかった!)は映画に大きな力を与えており、単に小綺麗にまとまっているだけでなく、ユニークなドラマに仕上がっていた。Rバールキー監督の才能も大したもので、前作「Cheeni
Kum」同様に、透明感ある映像が、映画に暗い雰囲気が立ちこめるのを防いでいた。
「Paa」は単なる家族ドラマでもない。アビシェーク・バッチャン演じるアモール・アールテー議員の設定自体が、映画に社会的なメッセージを加味していた。見る人が見れば一目瞭然のように、アモール・アールテー議員は明らかに国民会議派の「ユース・アイコン」ラーフル・ガーンディーがモデルになっている。汚職でまみれたインドを改革しようと日々東奔西走するアモール議員の姿が劇中で描かれていた他、政府の敷地を勝手に占拠して成立したスラムの再開発に特に焦点が当てられていた。アモール議員は、不衛生な生活を続けるスラムの住民に、スラムの土地に清潔な住宅地を造営するから、そこに移住することを承諾するよう、誠意を持って訴え続ける。だが、スラムを票田とするライバル政治家は、スラム住民を貧困の中に閉じ込めておかなければ地位が危うい訳で、スラムの住民に、アモール議員がスラム住民を騙して一儲けしようとしていると吹き込み、扇動する。民間メディアもライバル政治家に荷担し、アモール議員を責め立てる。業を煮やしたアモール議員は、国営放送ドゥールダルシャンを使って、民間ニュース番組のレポーターたちの偽善を国民の前で暴き、今や強大な影響力を誇りつつあるメディアに対して、「大きな力を持つ者は大きな責任も負う」と訴えかけ、逆風をはねのける。インドの報道番組は熾烈な視聴率競争の末に非常に下劣な報道を繰り返すようになっており、それに対する批判も強まっている。「Paa」では、それが中心的テーマではなかったものの、道徳を欠いた報道への一石が投じられており、興味深かった。
登場人物は多くなかったが、皆非常に優れた演技を見せていた。まずは何と言ってもアミターブ・バッチャンである。還暦を越えて子役を演じるとは本人も夢にも思っていなかっただろうが、この挑戦に堂々と立ち向かい、優れた子役振りを発揮していた。アミターブの息子アビシェークも、父親の父親になるという稀な体験を楽しみながら演じていたようで、アミターブとの共演シーンではいつになく生き生きとしていた。それだけでなく、政治家アモール・アールテーの場面でも、若く、理知的で、ユーモアのある青年政治家像をうまく体現していた。
元々演技力に定評のあるヴィディヤー・バーランは、今回も貫禄の演技を見せており、若手女優の中で演技力ナンバー1であることを雄弁に主張していた。母親を演じたアルンダティ・ナーグはインド演劇界の重鎮である。パレーシュ・ラーワルも面白い役所であった。アミターブの妻にしてアビシェークの母親であるジャヤー・バッチャンが冒頭のクレジットシーンで特別出演しているのも注目である。
音楽はイライヤラージャー。特に南インド映画界で活躍する音楽監督で、時々ボリウッドにも顔を出しており、Rバールキー監督の前作「Cheeni Kum」でも音楽を担当していた。「Paa」は、所々にコメディーシーンが挿入されていたものの、基本的には真面目なドラマで、ダンスシーンなどの混入はなかったのだが、Rバールキー監督の透明な映像に合わせた透明な音楽が映画を盛り上げていた。
「Paa」は、アミターブ・バッチャンの奇妙なビジュアルが先行しているが、真面目なドラマであり、今年もっとも感動できる作品となっている。全ての人にオススメできる必見映画だ。
10月4日の日記で、とあるボリウッド映画に日本人役で出演することが決まり、もう1人の日本人出演者タジマ ハル子さんとそのマネージャー、オバマさんと共にムンバイーまで出掛けたが、突然の大雨で野外セットがグチャグチャになって撮影がキャンセルになり、無為にデリーに帰って来たトホホ話を書いた。聞くところによると、撮影がキャンセルとなったのはロケ最終日になるはずの日だった。我々のみでなく、関係者全員にとってかなりの不運だったと言える。一応11月に再度ロケが行われる予定だと伝えられたものの、もしストーリーに支障がないならば、我々が出演予定だった日本人登場シーンは全面カットされてしまうかもしれないと予想していた。
何の連絡もなく11月が過ぎ去ったため、やはりあの映画は日本人抜きで何とか仕上げることになったのだろうと思っていた。かなり長い間ボリウッド映画を見続けて来ているし、ただ鑑賞するだけでなく、ボリウッド映画の普及のためにも一応の貢献はして来ていると自負しているので、そのボリウッド映画に出演する機会を与えていただいたのは何か天の恵みのようなものだと感じる。前半でも書いたように、ヒンディー語への思い入れからもボリウッド映画出演は僕にとって意味あるものになるはずであった。しかし、いざボリウッド映画の一部になるとなると、かなりの不安もあった。今まで客観的に見て来たものの一部に取り込まれることによって、今まで通りの見方が出来なくなってしまうのではないかとの不安もあったし、昔のTVCM出演ですっかり自分の演技力には自信を失っていたので、さらに恥をさらして落ち込むことになるのではないかとの不安もあった。だから、どうも映画出演の話がお流れになったみたいだと予感し始めたとき、残念な気持ちよりもホッとした安堵の気持ちの方が強かった。
しかし、毎度の通り、仕事の話は突然の不意打ちのようにやって来た。12月の第1週であっただろうか、突然助監督から電話があり、12月10日にロケをすることになったと伝えられた。つまりその日に来いということだ。こっちの予定などお構いなしである。僕はもともと時間を自由に使える立場にいるので問題ない。共演者のタジマ
ハル子さんもスケジュール的に都合のいい日であった。とうとうこのときが来てしまったかと生唾を呑み込みつつ、2人でムンバイーへ行くと返答をした。前回は1泊2日だったが、今回は日帰りになっていた。タジマ
ハル子さんのマネージャーのオバマさんは前回に懲りて同行しなかったが、デリーからは陸上競技の専門家で今回映画のアドバイザーとなっているサティヤパール氏も同じ旅程でムンバイーに向かうことになっていた。サティヤパール氏とは前回会っており、既に顔見知りであった。まだ若いが、インドの陸上競技界でかなり重要な役割を担っているようで、来年デリーで開催予定の英連邦スポーツ大会(コモンウェルス・ゲームス)にも深く関わっている。タジマ
ハル子さんは撮影後そのままムンバイーに数日滞在する予定であったため、僕とタジマ ハル子さんとサティヤパール氏の3人で早朝デリーからムンバイーへ向かい、夜に僕とサティヤパール氏の2人がデリーに戻って来るという旅程であった。
行きは午前6時発のエア・インディアIC688。午前3時起きで準備をし、午後4時にタクシーで家を出て、タジマ ハル子さんをピックアップして空港へ向かった。チェックインを済ませ、サティヤパール氏と合流し、飛行機に乗り込んだ。飛行機は定刻に離陸し、定刻にムンバイーのチャトラパティ・シヴァージー空港に到着。空港からは、助監督の送ってくれた自動車に乗って、ロケ地へ直行した。
ロケ地は、アンデーリー・ウエストのアンデーリー・スポーツ・コンプレックス。今まで明かしていなかったが、今回出演する映画の題名は「Paan Singh
Tomar」と言う。パーン・スィン・トーマルという実在の人物の一生を描いた伝記映画で、主人公は個性派男優のイルファーン・カーンが演じる。パーン・スィン・トーマルは、陸上競技の障害走(ステープルチェイス)の選手で、軍人でもあったが、退役後は盗賊として暴れ回った特異な人物である。パーン・スィン・トーマルは1958年に東京で開催された第3回アジア大会に出場しており、アンデーリー・スポーツ・コンプレックスのスタジアムではその東京のシーンが撮影されていた。脚本の中にパーン・スィン・トーマルが日本人の女の子と交流するシーンがあり、その関係で日本人エキストラが必要となっていたのである。監督はティグマーンシュ・ドゥーリヤー。過去に「Haasil」(2003年)や「Charas」(2004年)などの映画を撮っているが、それほど知名度のある監督ではない。監督デビューする前の下積み時代に、「Bandit
Queen」(1994年)でキャスティング・ディレクターを務め、「Dil Se..」(1998年)で台詞作家を務めたことぐらいが特筆すべきか。

「Paan Singh Tomar」のポスター
イルファーン・カーン
ロケ地に到着すると既に撮影班が来ており、撮影も始まっているようであった。2ヶ月前に大雨で破壊されてしまったセットも復元されていた。あの大雨のせいで400万ルピーの損失が出たと助監督が明かしてくれた。そこにはスタジアムの観客やアジア大会の係員として、東洋人顔をした人々も大量に動員されていた。彼らは「バックグランド」という可哀想な名称で呼ばれていた。後から知ったことだが、彼らはネパール人であったり、インド東北部から来た人々であったり、インド在住の中国人(華僑)であったりした。日本人の目からすると明らかに日本人に見えない人ばかりなのだが、日本ロケでも行わない限りこれだけ大量の日本人を集め、しかも長時間拘束することは不可能であり、仕方のないことであろう。彼らにとって、「日本人」などとしての映画出演はいい小遣い稼ぎになっているようだった。
助監督に迎えられた後、早速コスチュームに着替えることになった。僕は通訳役で、アジア大会のユニフォームとして、お笑い芸人みたいな黄色いスーツを着させられた。あらかじめ身体のサイズなどを伝えていなかったのだが、現場には仕立て屋が常駐しており、僕の身体のサイズにあった服を用意してくれた。タジマ
ハル子さんは向こうが用意したワンピースを着ることになったのだが、1958年当時の日本人女性の服装と言うよりは、そこらのインド人が着ているような服であった。変なスカーフも付けさせられていた。日本人のイメージってこんななのかなぁと思わせられる。しかも仕立て屋はやたらと「これぞチャイニーズ・スタイルでグッドだろう」とつぶやいていた。やっぱり日本と中国を勘違いしているみたいだ。コスチュームに着替えた後は、メイクアップ・アーティストらによって髪型やメイクなどのセッティングが行われた。ちなみに、インドではメインキャスト以外の出演者のことを「アーティスト」と呼ぶ。よって我々は「アーティスト」と呼ばれていた。とは言え、観客や背景として動員されていた「バックグランド」とは区別されており、我々専用の控え室が用意されていた。トラックの荷台の上に控え室が2室載っている移動式控え室だが、トイレやエアコンが完備されており、豪華であった。

控え室
このとき初めて出演部分の台本も渡された。パーン・スィン・トーマルはスパイクを履いて走るのが苦手で裸足で走り出すのだが、それを見た日本人の女の子が彼のファンになり、競技を終えた彼に話しかけるというシーンであった。どうもこの女の子の存在がラストへの伏線になっているらしく、カット出来なかったようである。出演は限られているが、重要な役だ。女の子は日本語しかしゃべれず、パーン・スィン・トーマルはヒンディー語しか分からないという設定であるため、通訳役の僕がそれを通訳する。つまり僕はそれほど重要な役ではない。僕に与えられた主な台詞は2つ。「श्रीमान
आपका शुभनाम क्या है? बताने का कष्ट करें(ミスター、あなたのお名前は何ですか?)」と「ये आपसे प्रेम
करती हैं(彼女はあなたのことが好きです)」であった。いわゆるシュッド・ヒンディー(純ヒンディー語)である。僕がもっとも忌み嫌っているタイプの言い回しだ。そんな台詞を映画でしゃべることになるとは、これまたかなりの皮肉であった。ただ、日本人のヒンディー語通訳がそういうシュッド・ヒンディーをしゃべるという設定自体、シュッド・ヒンディーに対するジョークなのであろう。そう考えれば幾分慰められた。また、ヒンディー語の語学力必須ということで、どんな台詞を話させられるのかと思っていたのだが、結局はヒンディー語初学者でも十分こなせるような役であった。ちなみに、台本は英語とヒンディー語のミックスで書かれていた。台詞の部分がヒンディー語で、ト書きは英語であった。
準備が終わった後、グランドで行われているロケを見に行った。よく見たら既にイルファーン・カーンも来ており、撮影の真っ最中であった。しかし、壁に貼られていた看板を見て愕然とした。英語で「Thir
Asian Games - Tokyo - 1958」「Help Desk」「Inquiry」などと書かれている下に、日本語が書かれているはずであったが、それは一見すると中国語であり、しかもよく見ると、中国語として見ても何の意味もない、単なる漢字の羅列であった。「日本人の知らない日本語」(メディアファクトリー)とかmixiアプリのサンシャイン牧場の日本語とか、そういうレベルではない。僕はかねてから、日本に対する誤解を助長するような、ボリウッド映画のこういういい加減な部分をなるべく改善して行きたいと思っていた。それに、日本に関わる何らかの事象が出て来るボリウッド映画は日本でもプロモートしやすくなると思うのだが、その映画の中の「日本」自体がトンチンカンチンだとかえって逆効果になってしまう。今回はわざわざデリーから日本人を呼び寄せて日本人役をやらせているので、その辺には比較的こだわりがあるのではと期待していたのだが、そうでもなかったようだ。と言うより、せっかく日本人を呼び寄せたのだし、2ヶ月前に一度ムンバイーに来ているのだから、こういう小道具を作る前に一言相談してくれれば良かったのに・・・寄りによって自分が出演する映画にこのような見苦しい失態が、しかも今まで見た中で一番酷い「日本語」があることは残念であった。一応監督やイルファーンにそのことを伝えた。ちょっとショックを受けていたが、既にこの看板と共に数シーンを撮影してしまっており、今から直すことは不可能であった。どうやら助監督の1人がネットから適当に拾って来て作ったようで、彼が怒られていた。彼らは僕が指摘するまでこれを日本語だと思い込んでいたのである。

日本語でも中国語でも何でもない・・・
陸上競技がテーマの映画であり、しかもデリーからわざわざ陸上競技専門家のサティヤパール氏が呼ばれているだけあり、エキストラの中には本物の陸上選手も含まれていた。彼らはサティヤパール氏の教え子であった。しかし、イルファーン・カーンのガタイは長身の上に陸上選手たちよりも立派で、一人だけやたら浮いていた。暇があればタバコをプカプカ吸っていた。かなりのヘビースモーカーだと思われる。

髭の男がイルファーン・カーン
ちょっと待っていたらすぐに我々の出演シーンの撮影が始まった。まずは監督、イルファーン、タジマ ハル子さんと僕の4人で打ち合わせがあった。しかし予め渡されていた台本よりも短縮されていた。元々は、パーン・スィン・トーマルに話しかけるもコミュニケーションに困った日本人の女の子が通訳を探して連れて来るという流れになっていたが、監督は、そういう面倒なシーンはカットして、最初から女の子は通訳同伴で来ることにしたと言っていた。そうなると僕が一体何者なのか、観客に分かりづらいような気がする。また、女の子はパーン・スィン・トーマルと一緒に写真に写るのだが、それを撮影するのも僕の役目になっている。1958年という設定であるため、用意されていたのは非常に旧式の大型ポラロイド・カメラであった。女の子がカメラを持って来て、通訳に渡して撮影してもらうという方が分かりやすいのだが、やはり監督はそれも簡略化しており、僕が最初からカメラを持って来ているという設定になっていた。ますます僕の役が分からなくなる。だが、アーティストの分際であれこれ文句を言うのはおこがましいと感じたので、何のアレンジも加えず、向こうの言う通りに演技をすることにした。
ティグマーンシュ・ドゥーリヤーという監督がどの程度の才能を持った人物なのか最終的な判断はしかねるが、少なくともそのときは、そんなに有能な監督ではないのではないかと感じた。ろくに演技指導もしてもらえなかったし、ヒンディー語の発音なども直してもらえなかった。数テイク取っただけでOKが出てしまった。もっとうまい監督なら、出演者に分かりやすく状況を説明してベストの演技を引き出すと思う。実はタジマ
ハル子さんはつい最近、「Rang De Basanti」(2006年)や「Dilli 6」(2009年)で有名なラーケーシュ・オームプラカーシュ・メヘラー監督と仕事をしているのだが、やはりメヘラー監督の方が出演者を乗り気にさせるのがうまかったと語っていた。僕が2003年にTVCMに出演したときも、台詞はなかったが、かなりの回数撮り直しさせられたのを覚えている。また、操作を任せられた旧式ポラロイドカメラの取り扱いが結構難しく、実は演技や台詞よりもカメラの方に気を遣ってしまっていた。
ところで、監督の指示もあり、写真を撮る際に僕はついつい日本の慣習に従って「ハイ、チーズ」と言ってしまったのだが、後から気になって調べたところでは、「ハイ、チーズ」が日本で一般化したのは、1963年に放送された雪印乳業のTVCMで使われたことがきっかけだったらしい。この撮影シーンは1958年という設定なので、時代考証がおかしいことになる。もし完成作品でも「ハイ・チーズ」が使われていたら、それは全て僕の責任である・・・。いろいろ文句を付けておきながら、とんでもないことをしでかしてしまった。でも、「ハイ、チーズ」以前に日本人が写真撮影時に言っていた掛け声なんて、知っている人そんなにいないだろう・・・。
幸運にもイルファーンと共演することが出来たが、イルファーンと対面することに不思議と緊張感はなかった。よく映画館のスクリーンで見ている顔なので、映画を見ているような感覚で向き合えたような気がする。一応台詞はピンマイクで録音されていたが、僕がしゃべったヒンディー語の台詞はもしかしたら吹き替えになるかもしれない。その辺は、トップ女優ながらヒンディー語が苦手なカトリーナ・カイフやディーピカー・パードゥコーンと勝負になる。

記念撮影
映画中でこういうシーンはなかったが記念のために
我々の出演シーンが終わった後も2時半頃まで撮影が続き、やっと昼食休憩となった。当然ケータリングサービスもある。バックグランドや他のエキストラたちはセルフサービスのビュッフェ形式であったが、タジマ
ハル子さんと僕はこの点でもちゃんと別格扱いされており、控え室までターリー(インド風定食)が届けられた。

昼食
チキン(ドライとグレービー)、チャナー(ヒヨコマメ)のカレー、ダールなど
撮影は午後6時頃まで続いた。辺りが薄暗くなった後も、照明を使って撮影をしていた。遠目に見学していたが、撮影は当事者にとっては大変なハードワークだが、傍観者にとっては案外退屈なものである。報酬はパックアップ後に現金で渡された。この出演の話が来たとき、仲介者の貪欲さもあり、当初は報酬で大もめしたのだが、それが収まった後は、大雨による撮影キャンセルを除けば、何のトラブルもなく進んだ。意外に映画関係者たちはプロフェッショナルかつ親切だった。イルファーン・カーンやティグマーンシュ・ドゥーリヤー監督には、特に僕がボリウッド映画ファンだということは明かしておらず、一般のインド人と話すのと同じ感覚で会話をした。インドのスターというのは、スターでもやっぱりインド人で、一般のインド人と変わらない質問をしてくるものだ。イルファーンは、日本人と中国人の違いは何だとか、空手とテコンドーの違いとか、そういうことを聞いて来た。ティグマーンシュ・ドゥーリヤー監督はもう少し専門的で、ウォン・カーウァイのことを聞いて来た。どちらにしろ、日本に対する正確な知識には乏しかった。別れ際にイルファーンに「あなたと会えて嬉しかったです」と言ったら、「オーケー、ババイ」と言われた。そのそっけなさがスクリーン上で見るイルファーンそのものであった。

撮影の一幕
オンボロ扇風機を使ってインドの国旗をなびかせようとしている
インド映画の撮影現場は人力が主役である
ちなみに国旗は全部手書きか手作り・・・
帰りの飛行機は午後9時発のエア・インディアIC605で、サティヤパール氏と共にチェックインして待っていたが、これが1時間遅れで散々であった。いろいろ改善されたものの国営航空会社エア・インディアはやはりどこまで行ってもエア・インディアで、全くアナウンスもないし、何で遅れているのか問い合わせようにも係員すらいなかった。観客の怒りは頂点に達していたが、紆余曲折の挙げ句、何とか飛び立ってデリーにも無事着いた。カールカージーの家に着いたのは午前1時半頃であった。今日は午前3時起きだったので、長い1日であった。後は「Paan
Singh Tomar」がいい映画になってくれることを祈るばかりである。公開は2010年の2月か3月の予定。
| ◆ |
12月12日(土) Rocket Singh - Salesman of the Year |
◆ |
ランビール・カプールの勢いが止まらない。往年の名優リシ・カプールの息子として「Saawariya」(2007年)で大々的デビューを果たしたランビールであったが、同作品がフロップに終わった上に劇中で見せた裸踊りが散々ネタにされてしまい、好調な滑り出しとは言えなかった。しかし、その後は「Bachna
Ae Haseeno」(2008年)、「Wake Up Sid」(2009年)、「Ajab Prem Ki Gazab Kahani」(2009年)など良作に恵まれ、順調にキャリアを伸ばしている。ランビールは、泣く子も黙る映画カーストの家系に生まれながら、意外にも落ちこぼれ役が板に付いて来ており、それが彼の醸し出すホンワカとしたイメージとうまく融合して、現代のインド人中産階級の若者の典型として存在感を確立しつつある。昨日から公開の新作ヒンディー語映画「Rocket
Singh - Salesman of the Year」でも、中産階級の典型であるセールスマン役を演じている。監督は「Chak De! India」(2004年)のシーミト・アミーンである。
題名:Rocket Singh - Salesman of the Year
読み:ロケット・スィン・セールスマン・オブ・ザ・イヤー
意味:ロケット・スィン:セールスマン・オブ・ザ・イヤー
邦題:ロケット・スィン:セールスマン・オブ・ザ・イヤー
監督:シーミト・アミーン
制作:アーディティヤ・チョープラー
音楽:サリーム・スライマーン
歌詞:ジャイディープ・サーニー
衣装:ニハーリカー・カーン
出演:ランビール・カプール、プレーム・チョープラー、ムケーシュ・バット、Dサントーシュ、ガウハル・カーン、ナヴィーン・カウシク、マニーシュ・チャウダリー、シャザーン・パダムスィー(新人)
備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。

ランビール・カプール
| あらすじ |
ハルプリート・スィン・ベーディー(ランビール・カプール)は何とか大学を卒業し、PC販売会社AYSにセールスマンとして入社した。しかし、正直者のハルプリートは、売り上げアップのためには手段を選ばない会社の方針に馴染めず、同僚からいじめられるようになっていた。しかしハルプリートは辞めずに会社に勤務し続ける。
AYSの受付嬢コーエナー(ガウハル・カーン)はハルプリートに同情し、問い合わせをして来た顧客の連絡先をひとつ渡す。訪ねてみると、そこはシェーラーン(シャザーン・パダムスィー)という女の子が立ち上げたばかりの会社であった。ハルプリートはシェーラーンを個人的に助けることにし、彼女のために格安PCを準備する努力をした。その過程で、PCというのは実は結構安く組み立てられるもので、PC販売会社が売っているものはかなり高価な値段設定がされていることに気付く。
AYSのプリー社長(マニーシュ・チャウダリー)から「お前はゼロだ」と辱めを受けたハルプリートは一念発起し、会社のメカニック、ギリ(Dサントーシュ)と組んで、ロケット・セールス社を秘密で立ち上げる。ハルプリートはさらに、受付嬢コーエナー、雑用係チョーテーラール(ムケーシュ・バット)、上司のニティン(ナヴィーン・カウシク)、そしてガールフレンドになっていたシェーラーンも仲間にする。彼らは日中はAYS社員として見せかけだけ働き、実際はロケット・セールス社のために働いた。ロケット・セールス社の売りは、正直さと24時間サービスであった。ロケット・セールス社は瞬く間にAYSを脅かすほど成長する。
ロケット・セールス社という謎の新興企業にビジネスを脅かされるようになったプリー社長は、ロケット・セールス社に探りを入れ始める。ハルプリートらは何とか隠し通そうとするが、とうとう社長に真実がばれてしまう。示談としてハルプリートらは会社を1ルピーでAYSに売却し、今後3年間PC販売業に関わらないことも約束させられた。
プリー社長は社名をロケット・セールスAYSに改め、ロケット・セールス社の旧顧客を取り込んで事業をさらに拡大しようとしたが、ロケット・セールス社の旧顧客はロケット・セールスAYS社の旧態然とした売り方を拒否し、契約を次々と解除した。プリー社長は誤りに気付き、ハルプリートを再び雇用しようとするが、ハルプリートはそれを受け容れなかった。するとプリー社長はロケット・セールス社をハルプリートに返し、合弁を解消した。ハルプリートは再び仲間たちを集め、ロケット・セールス社を再立ち上げする。やがてハルプリートはそのセールスマン・オブ・ザ・イヤーを受賞する。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
もしかしたら今年もっとも野心的な作品のひとつかもしれない。今までのインド映画のどのジャンルにも当てはまらないストーリーながら、そのメッセージはインドの芸能の中心テーマである「悪に対する正義の勝利」であった。ここまでインド映画らしさから脱却しながら、同時にインドらしさを残している映画を見るのは稀な体験であった。企業を舞台にしている点では、マドゥル・バンダールカル監督の「Corporate」(2006年)が想起されるが、これらの映画の味付けは全く違う。いわゆる「ブラック企業」に入社してしまった若者の物語だとすれば、最近日本で公開された「ブラック会社に勤めてるんだが、もう俺は限界かもしれない」(2009年)に似た部分があるかもしれないが、映画に込められたメッセージはだいぶ違うのではないかと思う。
信心深い親に育てられ、学校の成績は芳しくないが実直な若者が、成功のためには他人を蹴落とすことも厭わず、賄賂も常套手段となっており、同僚間の信頼関係すら存在しない「ブラック企業」に入社してしまい、苦労しながらも、自分の信念を曲げず、詐欺と欺瞞に満ちたPC販売ビジネス界の中で、正直さ一本で顧客の信頼を勝ち取って行こうとする物語が「Rocket
Singh - Salesman of the Year」である。主人公のハルプリートは、大学を卒業して社会に出た途端、不正や不道徳がビジネスと処世術の名の下に堂々とまかり通るのを目にし、なかなか馴染めない。なぜ人々は「ラーマーヤナ」から何も学んでいないのか?ハルプリートは父親に悪態をつくが、社会は彼の一言で変わるような代物ではなかった。しかしハルプリートは諦めなかった。ロケット・セールス社という会社を立ち上げ、良心的価格と真摯なサービスを提供する努力をする。会社内に秘密裡に会社を立ち上げたのは多少道徳的に問題があったものの、ハルプリートはそれも後から精算しようとしていた。ハルプリートの熱意と実直さによって次第に仲間の輪は広がり、顧客の信頼も勝ち取って行った。一旦は社長によってハルプリートの会社は壊滅させられてしまうものの、最終的にはハルプリートの正直さが勝ち、社長も彼に会社を返さざるをえなくなる。悪に対する正義の勝利の瞬間であった。こういう展開はボリウッド映画によくあるのだが、その裏には、マハートマー・ガーンディーのサティヤーグラハ(真理の主張)やアヒンサー(非暴力)の哲学の影響も感じる。僕はそれをインド映画の良心と呼んでいる。これを説教臭い映画として受け止めるか、それとも正義の勝利を素直に受け止めるかで、インド映画に対する評価は大きく分かれるのではないかと思う。
もうひとつの重要なメッセージは、数字主義に対する批判であった。ハルプリートは、数字上は学校でも会社でも無能であった。だが、彼は人々の幸せや悲しみをよく理解していた。常に人々を幸せにしようと努力していた。それが彼の底なしの正直さにつながり、やがてはロケット・セールス社の成功に結び付いていた。ハルプリートはプリー社長に、成功の秘訣を「数字ではなく人を見ること」と語る。インドは日本以上の学歴社会であり、もっと言えば数字社会であるが、「Rocket
Singh - Salesman of the Year」はその危険性を訴えていた。今インドに必要なのは、プリー社長のような実力主義の人間ではなく、ハルプリートのような人間主義の人間であると主張されていた。
一般のインド娯楽映画に比べて派手さがなかったのは映画の欠点になりうる。登場するのはごくごく普通の人々ばかりで、淡々としたストーリーテーリングである上に、スターパワーもランビール・カプール1人頼みで、ダンスシーンもなかった。だが、要所要所をしっかりと押さえた、コンパクトで分かりやすい展開だったし、退屈ではなかった。結果として、インド映画離れした完成度を誇る映画になっていた。
おそらくそれには監督の経歴も関係しているのだろう。シーミト・アミーン監督は、ウガンダ生まれ、米国育ちのインド人で、ロサンゼルスで独立系映画の編集に長年携わって来た人物である。「Bhoot」(2003年)でラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督と仕事をしたことがきっかけでボリウッドにも関わるようになり、「Ab
Tak Chhappan」(2004年)や「Chak De! India」などを監督した。「Ab Tak Chhappan」は、プロデューサーのラーム・ゴーパール・ヴァルマーの個性が強かったし、「Chak
De! India」はヤシュ・ラージ・フィルムスの色が濃かったが、監督3作目となる「Rocket Singh - Salesman of the
Year」では、シーミト・アミーン監督の独自色が出ているのではないかと思う。それは米国の独立系映画界で培った経験に基づいたものなのかもしれない。きっと今後もボリウッドに新しい風を呼び込んでくれる監督になるだろう。
主演のランビール・カプールが演じたハルプリートは、ターバンをかぶったスィク教徒である。スィク教徒が主人公の映画と言うと、大ヒットとなったコメディー映画「Singh
Is Kinng」(2008年)が記憶に新しい。ボリウッドにおける典型的なスィク教徒像は実直さであり、それは「Singh Is Kinng」でも「Rocket
Singh - Salesman of the Year」でも変わらない。ランビール・カプールはパンジャービーの家系だけあってスィク教徒姿がよく似合っており、演技も非常に落ち着いていて良かった。地味な作品であったが、ランビールの良さがよく出た出演作の1本として数えられることになるだろう。
ランビール以外は特に著名な俳優は出ていなかったのだが、一応ヒロイン扱いとなっていたのは新人のシャザーン・パダムスィーである。出演シーンは限られていたが、テニス選手サーニヤー・ミルザー似のかわいい女優であった。彼女は、著名な演劇人アリーク・パダムスィーとポップ歌手シャローン・プラバーカルの娘とのことである。他にはハルプリートの父親役を演じたプレーム・チョープラーがよく知られているぐらいだ。だが、脇役陣の演技もとても良かった。
音楽はサリーム・スライマーン。ダンスシーンなしのストーリー中心映画だったため、音楽監督の見せ場は少なかった。
意外に言語は難解だった。主人公がパンジャービーであるため、パンジャービー語訛りのヒンディー語をしゃべる他、他の登場人物たちも癖のある言葉遣いをするため、聴き取りは困難だった。また、インド企業内の専門用語が結構飛び交っていたのも理解を妨げていた。
「Rocket Singh - Salesman of the Year」は、一般のインド娯楽映画のような派手さはないが、しっかりと作り込まれた映画である。むしろインド映画離れしており、新鮮さがある。それでいて、その中心テーマはとてもインドらしく、地味ながら野心作だと感じた。インド映画をあまり見ない人には、インド映画の典型からかけ離れているため、敢えて勧められないが、今まで何本もインド映画を見て来た人には、インド映画の意外な進化を目撃するために、勧めることができる。
| ◆ |
12月21日(土) インドも遂にアライバル・ヴィザ導入か |
◆ |
ここ3ヶ月間ほど、インドの新聞に毎日必ず登場するキーワードとなっているのが、デーヴィッド・コールマン・ヘッドレー(David Coleman
Headley)という人名である。10月3日に米国シカゴでFBIによって逮捕された人物で、逮捕の理由は、デンマークにおいてテロを計画していたとの容疑である。名前からするとユダヤ系米国人だが、実は彼はパーキスターン系米国人であり、元の名前はダーウード・サイイド・ギーラーニーと言う。ヘッドレーと共に逮捕されたタハッウル・フサイン・ラーナーの方はパーキスターン系カナダ人である。一部ではラーナーの方が大物とされているが、報道ではなぜかヘッドレーの方がメインで扱われることが多い。
米国における2人のテロリスト容疑者の逮捕がインドで話題になっているのには大きな理由がある。それは、2人がパーキスターンのテロ組織ラシュカレ・タイイバ(LeT)に所属しており、昨年11月26日にムンバイーで発生した同時テロ事件に関与していた可能性が高いからである。ヘッドレーもラーナーもテロ前にインドを訪れており、その足取りから察するに、テロの標的を下調べをしていたのではないかと考えられている。捜査によると、彼らはデリー、ムンバイー、プネー、ゴア、プシュカルなどにおけるテロを計画していたとされる。12月8日にはFBIが公式にヘッドレーがムンバイー同時テロ計画に関わったと認めた。
インド側はヘッドレーらの逮捕が明らかになったときから米国に対して彼らの事情聴取や引き渡しを希望しているが、未だに実現していない。米国があまりに頑なに拒否するため、インドの識者の間では、ヘッドレーは実は二重スパイだったのではないかとの噂も出て来た。ヘッドレーは1998年に麻薬密輸の容疑で米国で逮捕されているのだが、その噂によれば、そのときに司法取引があり、刑の軽減と引き替えに、CIAのスパイとしてパーキスターンに潜入し、麻薬ネットワークの情報収集を任されることになったとされている。ヘッドレーはLeTのキャンプへの潜入にも成功したのだが、そこで主をCIAからLeTに鞍替えしてしまい、それが今回の逮捕につながった。二重スパイを易々と他国に引き渡すことが出来ないため、米国はヘッドレーへのアクセスを極力抑えているのではないかというのが疑念である。CIAはその疑いを否定しているが、真偽は当然のことながら不明である。
ヘッドレーのテロ計画が徐々に明るみに出るにつれ、「ラーフル」という人物がテロの標的になっていたのではないかとの情報が巷に流れた。すぐにその特定が行われ、有力候補がピックアップされた。最有力候補は国民会議派のソニア・ガーンディー党首の息子で、若者から絶大な支持を集めるラーフル・ガーンディーであった。その他、ボリウッド俳優のラーフル・ボース、ラーフル・カンナー、ラーフル・デーヴなどの名前が挙がって行ったのだが、彼らは正直に言ってしまえばテロの標的になるほど大きな影響力を持った人物ではない。とすると他に誰が当てはまりそうか?マスコミの素人推理は加速し、大穴として大人気俳優のシャールク・カーンが候補として挙げられた。なぜならシャールクは映画の中で「ラーフル」という名前の役を演じることが多いからである。つまり「ラーフル」は暗号で、それはシャールク・カーンのことを指していたのだ!まるで鬼の首を取ったような報道の仕方であった。
しかし、意外なところからヘッドレーと関わりを持つ「ラーフル」が出て来た。有名映画プロデューサー、マヘーシュ・バットの息子のラーフル・バットである。ラーフル・バットはムンバイーでジムを経営しているのだが、そのジムにヘッドレーが訪れており、ヘッドレーとも会っていたのである。ラーフル・バットは、ヘッドレー逮捕のニュースを見て自ら警察にそのことを明かした。ラーフル自身はボリウッドと直接つながりがなかったが、彼の経営するジムにボリウッドの俳優が多数通っていたため、ヘッドレー事件は映画界にも激震をもたらすことになった。しかし、単にヘッドレーと接触した映画関係者がいるだけで、彼らがテロリストを支援していたりしたという事実は出て来ていない。ラーフルも、ヘッドレーがまさかテロリストだとは知らずに交遊していたようで、それは嘘ではないだろう。
このようにヘッドレー逮捕は各界に大きなショックを与えているのだが、外国人もその蚊帳の外にはいれなさそうである。まず、ヴィザの発行にちょっとした影響が出そうだ。ヘッドレーはシカゴのインド総領事館でヴィザを取得したのだが、元パーキスターン国籍の人物にノーチェックでヴィザを発給してしまったことがインド政府によってセキュリティー上の重大な過失と認識されており、それがどうして起こってしまったのか、調査されている。今後、現国籍だけでなく、以前の国籍も厳重にチェックが行われ、もし過去にパーキスターン国籍を持っていた場合、細心の注意をもって取り扱われることになるのは確実だ。だが、この点はほとんどの日本人には関係ないだろう。
また、ヘッドレーはマルチプル・エントリー(複数回入国可)のビジネス・ヴィザを使ってインドに入国を繰り返していた。インドを旅行する外国人観光客にも普通にマルチプル・エントリーのヴィザが発行される。このマルチプル・エントリー・ヴィザのシステムが持つ潜在的危険性が浮上しており、見直しが行われている。とりあえず、マルチプル・エントリー・ヴィザ保有者の外国人は、最後のインド出国から2ヶ月の期間をおかなければ再入国できないような制度になりそうだ。もしこれが厳格に適用されると、インドを拠点にネパールなど隣国を旅行するのが難しくなるかもしれない。インド在住の外国人にも多大な影響が出る。一応、再入国許可の取得など、抜け道は用意されるみたいだが、面倒なことになるのは変わりない。
インドにおいて外国人旅行者へのチェックが以前に増して厳しくなるという点は、全ての外国人に影響が出るだろう。ヘッドレーはデリーの安宿街パハールガンジに宿泊していたことが分かり、パハールガンジにおける宿泊者のチェックが強化されそうだ。今でもレセプションに監視カメラを設置することが義務づけられていたりするのだが、今後は宿泊者の身元確認のため、本国の実家に電話を掛けたりすることも辞さないようである。また、外国人宿泊者の情報を到着から24時間以内に毎日警察に届け出る規則も作られる見込みである。このような面倒な規則が実行されると、ホテル側は外国人の宿泊を歓迎しなくなってしまう恐れがある。ただし、インドでは、規則は厳しくてもその実行がルーズであることが多いので、それほど心配する必要はないのかもしれない。だが、頻発するテロの影響で、外国人に対する警戒が強まり、以前に比べてインドの旅行がしにくくなって来ていると感じることはある。
このように、テロとの戦いの上で、世相は徐々に規制強化の方向へ向かっているのだが、ここに来てそれを一気に覆すようなニュースもあった。12月18日にチダンバラム内相が発表したアライバル・ヴィザ導入の方針である(12月19日付けのザ・ヒンドゥー紙による)。内相は、「年間約500万人の外国人がインドを訪れているが、その数は国の規模から見たら少なすぎる」と述べ、それを打開するために、ヴィザなどの規則を緩和する意向を示したのである。それを実現するため、まずは世界169ヶ所の大使館、全国77ヶ所の出入国審査所(IPC)、5ヶ所の外国人地域登録局(FRRO)、600ヶ所以上の外国人登録局(FRO)を中央政府の外国人管理局とネットワークで結び、インドを訪れる外国人の情報を共有するシステムを構築する。そして試験的に限定5ヶ国の外国人に対して、出入国審査所においてアライバル・ヴィザの発行を1年の期限付きで行う。
気になる5ヶ国だが、シンガポール、日本、ニュージーランド、ルクセンブルグ、フィンランドである。ありがたいことに日本が入っている!どういう基準で選ばれたのか分からないが、その国民の信頼性というのが一番大きいのではないかと思う。日本人が長年世界中で培って来た信頼の賜物であろう。もしアライバル・ヴィザが導入されたら、インド旅行が格段に便利になることは間違いない。多分観光ヴィザなど短期のヴィザ限定になるだろうし、現在普通に申請すれば6ヶ月もらえる観光ヴィザも、オン・アライバルではそれほど長くもらえないかもしれないが、是非、この方向で話を進めて行ってもらいたいものである(追記:2010年1月1日よりアライバル・ヴィザの試行運用が開始された)。
ヒンディー語映画界の中で、その徹底した完璧主義から、「ミスター・パーフェクト」と一目置かれる俳優アーミル・カーンは、ここのところ1年1作のペースを堅実に守っており、しかも出演作が年末に公開されることが恒例となって来ている。一昨年の最後を締めくくった「Taare
Zameen Par」(2007年)では初めてメガホンを取り、主演も果たした上に、興行的にも批評的にも成功した。昨年末に公開された「Ghajini」(2008年)は、ボリウッドでは久々となる本格的アクション映画で、記録的大ヒット作となった。そして2009年末、アーミルは意外な方向転換を見せ、軽妙なコメディー映画と共に帰って来た。人気小説家チェータン・バガトの小説「Five
Point Someone」をルーズにベースとした「3 Idiots」である。監督は「Munnabhai」シリーズで有名なラージクマール・ヒーラーニー。12月25日公開だが、前日にデリー各地の映画館で有料プレビューが行われていたため、一足先に鑑賞することが出来た。結論から先に言うと、必ずしも豊作ではなかった2009年のボリウッドを一気に潤す恵みの雨のような傑作である。さすがアーミル・カーンと言ったところか。今年必見の映画だと言っていい。
題名:3 Idiots
読み:スリー・イディヤッツ
意味:3人の馬鹿
邦題:スリー・イディヤッツ
監督:ラージクマール・ヒーラーニー
制作:ヴィドゥ・ヴィノード・チョープラー
原作:チェータン・バガト「Five Point Someone」
音楽:シャーンタヌ・モーイトラ
歌詞:スワーナンド・キルキレー
振付:ボスコ・シーザー
衣装:マニーシュ・マロートラー、ラグヴィール・シェッティー
出演:アーミル・カーン、Rマーダヴァン、シャルマン・ジョーシー、カリーナー・カプール、ボーマン・イーラーニー、モナ・スィン、ジャーヴェード・ジャーファリー
備考:サティヤム・ネルー・プレイスでプレビュー鑑賞、満席。
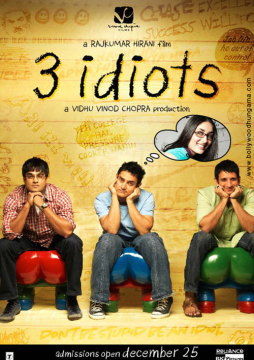
左から、Rマーダヴァン、アーミル・カーン、
カリーナー・カプール(上)、シャルマン・ジョーシー
| あらすじ |
デリー在住のファルハーン・クレーシー(Rマーダヴァン)とラージュー・ラストーギー(シャルマン・ジョーシー)は、ある日突然、大学時代の同級生チャトゥル・ラーマリンガム(オーミー)から呼び出され、大学へ向かう。チャトゥルは大学時代の恨みを晴らすためにファルハーンとラージューを呼び出したのだが、2人はランチョー(アーミル・カーン)が来ると聞いて飛んで来たのだった。だが、その場にランチョーはいなかった。ランチョーはファルハーンとラージューのルームメイトだった人物で、3人は大の親友であった。しかし、ランチョーは大学の卒業式以来消息不明となっていたのだった。
ガッカリするファルハーンとラージューであったが、チャトゥルはランチョーがシムラーにいることを知っていた。早速3人はランチョーに会いにシムラーへ向かう。
ランチョー、ファルハーン、ラージュー、チャトゥルはかつて、インド有数の工科大学インペリアル・カレッジ・オブ・エンジニアリング(ICE)に通う学生であった。彼らは皆、厳しい受験戦争を勝ち抜いて来たエリートだったが、ランチョーだけは他のどの学生とも違っていた。彼は競争に勝ち抜いて成功を掴む人生を理解せず、好きなことを突き詰める人生を信じていた。ところが、ICEの学長ヴィールー・サハストラブッデー、通称ウイルス(ボーマン・イーラーニー)は、弱肉強食の競争による切磋琢磨を美徳とする教育者で、学校の教育方針も彼の信念に沿っていた。初日からウイルスとランチョーの間で意見の対立が見られたが、それは日に日に増して行った。だが、ファルハーンとラージューはランチョーを尊敬しており、彼と波瀾万丈の学生生活を満喫していた。一方、チャトゥルは典型的ガリ勉君で、ランチョーを馬鹿にしながら勉強に専念していた。だが、なぜか期末試験のトップはランチョーであった。
ランチョーはある日、潜り込んだ結婚式でピヤー(カリーナー・カプール)という女医と出会い、恋に落ちる。だが、ピヤーは天敵ウイルスの娘であった。ピヤーは、フィアンセがいたこともあり、最初はランチョーに冷たく当たるが、彼の純真さや発想力に惹かれ、徐々に2人は仲良くなる。ある晩、ファルハーンとラージューに背中を押されたランチョーは、酔っぱらっていたこともあり、思い切ってウイルスの家に忍び込んでピヤーに愛の告白をする。そのとき同行していたファルハーンとラージューは、ここぞとばかりにウイルスの家の玄関で小便をしたりして鬱憤を晴らす。ウイルスに気付かれそうになって逃げ出したのだが、そのときにラージューだけ顔を見られてしまう。ラージューはウイルスに呼び出され、停学処分にされそうになる。普段からランチョーを敵視していたウイルスは、もし罪をランチョーになすりつけるなら許すと逃げ道を提示する。貧しい家庭に育ったラージューの肩には家族の生死がのしかかっており、停学処分は一家破滅を意味した。だが、ランチョーを裏切る訳にも行かなかった。板挟みになったラージューはその場で飛び降り自殺を図る。
ラージューは一命を取り留めたが打ち所が悪く、植物人間状態となってしまった。しかし、ランチョーらの必死に努力により意識を取り戻し、身体も動くようになった。この事件により、ラージューの停学処分も取り消しとなった。退院時にはちょうど就職の面談が行われており、車椅子姿のままラージューは面談へ向かう。そこでラージューは正直に怪我をした理由を企業の面接官に語る。面接官もラージューを気に入り、彼の採用を内定する。
一方、ファルハーンは元々動物写真家を夢見ていたが、父親の意志で無理矢理工科大学に入学させられていた。ランチョーはファルハーンの写真の腕を認めており、彼に再三エンジニアを目指すのを辞めて写真家を目指すべきだと助言していた。ファルハーンは、もしランチョーがピヤーに告白したら自分も写真家の道を歩むと約束しており、とうとう思い切って父親に自分の意志を打ち明ける。最初は戸惑った父親も最終的には息子の決断を受け容れる。ランチョーのおかげでファルハーンとラージューの人生は好転し始めた。
ラージューの就職内定を知って驚いたのはウイルスであった。彼はもしラージューが就職できたら髭をそり落とすとランチョーに対して宣言していた。あとはラージューを落第させて蹴落とすしか助かる道はなかった。ウイルスは自ら試験問題を作り、絶対にラージューが合格しないように画策した。しかし、それを知ったプリヤーは試験前日にランチョーのところへ学長室の合い鍵を持ってやって来る。ランチョーとファルハーンは真夜中学長室に忍び込んでテストをコピーするが、それがウイルスにばれてしまう。ウイルスは3人を即時停学とし、寮から追い出す。
ところがその日デリーは大雨に見舞われており、交通が麻痺していた。ウイルスの娘でピヤーの姉が急に産気づいてしまい、ウイルスは必死に救急車を呼ぼうとするが、洪水のためどこからも断られてしまった。それを知ったランチョーは、そのときちょうど病院にいたピヤーとウェブカメラで連絡し合い、寮のホールで姉の出産を行うことにする。停電により一時連絡が途絶えてしまうが、ランチョーの発明したインバーター装置により電気を復旧させ、難産となった出産を、これまた掃除機を改造した即席吸引器によって成功させる。生まれた子供は最初息をしていなかったが、これもランチョーの口癖「オール・イズ・ウェル」が魔法の合い言葉となり、息を吹き返す。その土壇場の応用力に舌を巻いたウイルスは初めて彼を認め、3人の停学処分を取り消す。
卒業式の日。ランチョーは主席での卒業となった。だが、その日を最後にランチョーは姿を消してしまったのだった。
シムラーに着いたファルハーンとラージューは、ランチョーの本名ランチョールダース・シャーマルダース・チャーンチャルを頼りに彼を捜す。すると地元の人々は誰でも彼のことを知っていた。なぜなら当地の有力者の御曹司だったからである。しかし、そこにいたランチョールダースは全くの別人(ジャーヴェード・ジャーファリー)であった。そして彼は本物のランチョールダースであった。どういうことか問い詰めてみると、実はファルハーンらがランチョーと呼んでいたのは、彼の家の庭師の息子であった。彼は子供の頃から学問に興味があり、学校に忍び込んでは授業を受けていた。それをいいことにランチョールダースは彼に宿題をやらせていた。そのまま彼はランチョールダースの代わりに大学まで進み、学位を取ったのだった。ランチョールダースはファルハーンらに彼の居所を教える。彼は現在ラダックのとある学校にいるとのことであった。
ファルハーンとラージューは、抵抗するチャトゥルを拘束してそのままラダックへ向かう。チャトゥルは勤務先企業のために天才的科学者プンスク・ワンドゥと商談しなければならなかったため、そんなところへ行く余裕などなかった。だが、ファルハーンとラージューはそんなことお構いなしであった。と、途中で2人はランチョーの恋人ピヤーのことを思い出す。どうせならピヤーも呼ぼうと思い付き彼女に電話するが、その日はちょうど彼女の結婚式で、マナーリーで結婚式を挙げていると知らされる。ランチョーに取り残されたピヤーは、かつてのフィアンセとの結婚を決めたのだった。ファルハーンとラージューはまずはマナーリーへ向かうことにする。
マナーリーでファルハーンとラージューはピヤーの結婚式に潜入し、彼女を説得して式場から連れ去る。そして一路ラダックへと向かう。学校に着くと、ランチョーらしい発明品で溢れかえっていたが、ランチョーの姿が見当たらなかった。しかし、そこにはかつて大学の寮で小間使いをしていた男の子がいた。彼に教えられて、湖の畔で飛行機を飛ばすランチョーを発見する。ピヤー、ファルハーン、ラージューはランチョーとの再会を喜ぶ。そこへチャトゥルが進み出る。そもそもチャトゥルは、同級生の中で誰が一番成功しているか確認するために皆を招集したのだった。チャトゥル自身は大企業に勤め、高額の月給を得ていた。ラダックの片田舎でしがない教師をしているランチョーを見てチャトゥルはほくそ笑み、負けを認めさせる。ところが、ランチョーの本名を知ってチャトゥルは態度を一変させる。なんとチャトゥルが会おうとしていた科学者プンスク・ワンドゥがランチョーだったのだ! |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
インドの伝統的モチーフに敢えてほとんど触れずに、これほどまでインドらしく、インド映画らしい映画が作れるとは!おまけに現代のインドの若者が直面している問題にも深く踏み込んでおり、単なるお馬鹿なコメディー映画ではなく、社会的メッセージのある有意義な映画になっていた。2009年のボリウッドは不作だったかもしれないが、この1本の存在だけでそれが吹き飛んでしまうぐらいである。正に有終の美。間違いなく今年のベストである。純粋に娯楽映画と見ても申し分ない。
この映画の中心的なメッセージは受験戦争システムへの痛烈な批判だ。自分の夢を子供に押しつける親、学生に弱肉強食の競争を強いる教師、数字至上主義の学校、そしてそれらのプレッシャーに押しつぶされ塗りつぶされて行く若者たち。そんな現代インドが抱える問題が赤裸々に描き出されていた。映画の主な舞台となっていたのは架空の工科大学だが、これは明らかにインド工科大学(IIT)がモデルとなっている。IITと言えば、優秀なインド人ITエンジニアを輩出する名門校であり、エンジニア志望のインド人学生の最大の目標である。IITに入学すれば世界中の大企業が向こうからスカウトにやって来るほど引っ張りだこの存在となり、バラ色の人生が待っている・・・しかし、その華々しいイメージとは裏腹に、競争に勝ち残れなくて潰れて行ったり、人生で本当に大切なものを失って行ったりする若者も少なくない。学生時代から数字に追われる人生を送って来ているため、卒業後も年収という数字を人生のバロメーターとして考え、視野の狭い人間になって行く。IITほどの大学に入学を目指すなら、受験勉強は小学生の頃から始めないと間に合わないとされる。そしてIITほどの大学に入学に入った後も、テストに次ぐテストをこなす毎日で、大きな重圧がかかる。もちろん、それに耐えきれなくなる若者も出て来る。劇中でも1人の学生が大学の厳しい教育制度のせいで自殺してしまった。
そのシステムに真っ向から戦いを挑むのが主人公のランチョーである。ランチョーは優れた発想力と頭脳を持った天才タイプの人間で、大学で正義となっていたトップのみを目指した競争や教科書丸暗記の知識を理解していなかった。何よりランチョーは他の学生と違って学位のために大学で勉強している訳ではなかった。ただ単に知識を得たいという純粋な動機の下に勉強していた。ランチョーの座右の銘は「何事も好きなものを極限まで磨き上げて行けば成功は嫌でも後から付いて来る」であった。好きなこと、自分に合ったことをとことん突き詰めて生きることに価値を見出しており、自分の夢を捨てて工学を学ぶファルハーンに、夢を追うように働きかけていた。そしてランチョーは何より友人思いの純真な人間であった。仲間を蹴落としてトップを目指すことが半ば公認となっている大学内で、彼の存在は希有だった。インド人の子供は猫も杓子も将来の夢をエンジニアと答える傾向にあるとされるが、本当にそれは彼ら自身の夢なのか?その過酷なレースに参加している若者の内のどのくらいが本当に学問自体を愛しているのか?もし嫌々勉強しているなら、そこにどうして創造性が生まれようか?若い頃に夢を諦めてしまったら、いくら経済的に成功しても一生後悔することにならないだろうか?コメディー仕立ての展開の中で、そんな問い掛けが何度も観客に投げかけられていた。
BRICsの一角として急成長を遂げるインドだが、本当にそのまっしぐらな成長戦略が若者のためになっているのか、社会全体の安定のためになっているのか、ヒンディー語映画界ではここに来てそんな問い掛けがなされるようになって来たように思う。先日見た「Rocket
Singh - Salesman of the Year」も突き詰めればその点に行き当たるし、アーミル・カーン監督作品「Taare Zameen
Par」も本質は似通っていた。社会の発展がスピード過多となっており、振り落とされる人もいれば、しがみつくのに必死で回りが見えない人も出て来ている。ここらで一度ブレーキを踏んで来た道を冷静に振り返ってみよう、失ってはいけないものを失ってしまってはいないだろうか考えてみようと訴える動きが出て来るのはしごく自然であり、また意味のあることだと思う。
「3 Idiots」は、回想シーンではあるが、大学が主な舞台となっており、インドの大学生活を絶妙に再現した作品の1本と言える。特に寮の雰囲気などは現実そのもので、インドで大学生活を送って来た身としては個人的にとても身近に感じた映画であった。シャワーを浴びているときに水が出なくなるシーンなどは身をもって体験した!しかし、ラギングが否定的トーンなしに描かれていたのは多少問題視されるかもしれない。ラギングとはインドの学校で慣例化している新入生いじめである。上級生と仲良くなる必要悪の儀式だと肯定的に捉える人もいるが、ラギングが原因で死亡する若者も毎年出ており、世論は完全撲滅を求めている。ラージクマール・ヒーラーニー監督は「Munna
Bhai M.B.B.S.」(2003年)でもラギング・シーンを入れており、どうもラギングに特別な思い入れのある監督みたいだが、ラギングの美化は批判されて然るべきであろう。だが、紙面を賑わすものの、部外者はなかなかラギングを目撃できない。特にインドで学生生活を送ったことのない大半の日本人にはイメージが沸きにくいだろう。ラギングがどんなものなのかを垣間見るためには、「3
Idiots」は「Munna Bhai M.B.B.S.」と並んでいい作品である。また、ラギングと関連して、多少お下品なシーンもいくつかあるのは注記しておきたい。
完全に海外が舞台のボリウッド映画が増えている中、「3 Idiots」は北インドに密着した作品であった。主な舞台はデリーで、そこからシムラー、マナーリー、ラダックへと北に北に移動する。そのロードムービー的な展開も売りで、ヒマーラヤ山脈の圧倒的な景色が映画に美を添えている。やはりインドの地に足の着いた映画は特別である。
前作「Ghajini」でマッチョな肉体を創り上げたアーミル・カーンは、今回は一気に筋肉をそぎ落とし、学生らしい姿になっていた。アーミルは既に44歳になっているが、生来の低身長をうまく利用して学生らしさを醸し出すのに成功していた。それだけでなく、七面相の演技を見せており、彼の変幻自在の演技が映画の大きな見所となっている。また、アーミルは主演作を変わった方法でプロモートすることでも知られている。例えば「Ghajini」のときはデリーで床屋になってガジニー・カットを広めた。今回は変装してヴァーラーナスィー、コールカーター、パンジャーブ州の農村、チェンナイなどに出没し、話題となった。
他の「イディヤット」も持ち味を活かした素晴らしい演技だった。シャルマン・ジョーシーは「Rang De Basanti」(2006年)でアーミルと共演しており、今回も息がピッタリであった。今まででベストの演技と言える。南インド映画界の名優Rマーダヴァンも「Rang
De Basanti」にカメオ出演していたが、今回はフルでアーミルと馬鹿騒ぎを繰り広げていた。
だが、やはり笑いの中心にいるのはヴィールー・サハストラブッデー学長である。彼は名前の先頭「Viru Sahastrabuddhe」を取って学生たちから「Virus(ウイルス、インド風発音だとヴィールス)」と呼ばれていた。人生弱肉強食のレースがモットーで、1分たりとも時間を無駄にしないように生きており、学生たちにも同じ生き方を強いる怖い先生であった。映画は、ボーマン・イーラーニー演じるこのウイルスと、アーミル演じるランチョーの対決を中心に展開する。この構造は、ラージクマール・ヒーラーニー監督の「Munna
Bhai M.B.B.S.」や「Lage Raho Munnabhai」(2006年)と共通しており、徐々にワンパターン化している嫌いがあるが、効果的な方程式であることに変わりがない。
ヒロインはカリーナー・カプールであったが、通常の映画に比べてヒロインの重要性は低かった。カリーナーも多少迷い気味の演技だった印象を受けた。映画の題名が「3
Idiots」で、馬鹿が主人公の作品であるため、カリーナーも馬鹿の一味なのかと思いきや、必ずしもそうでなく、結果的に中途半端で損な役回りになっていたと思う。特に真夜中酔っぱらってランチョーの部屋を訪ねて来るシーンは、酔っぱらう必要性があったのかと思う。最終試験の答案用紙が収められた学長室の鍵を盗むためには酒の力が必要だったと一応説明されてはいたが、そんな危険なことをするのに逆に酔っぱらっていては不利だろう。三馬鹿に対してどのような位置づけなのか、もう少しはっきりさせた方が彼女の役が生きたと思う。それに彼女の化粧やファッションも変なことが多かった。
音楽はシャーンタヌ・モーイトラ。挿入歌の曲数は多くないが、物語の伏線となっている「Aal Izz Well」、軽快なダンスナンバー「Zoobi
Doobi」など、ハチャメチャな大学生活を象徴するようなハチャメチャな楽曲が印象的だった。だが、もっとも心に響くのは、競争に負けた学生が自殺する前に歌う「Give
Me Some Sunshine」であろう。競争の内に幼年時代も青春時代も無為に過ごしてしまったことを後悔するアコースティックギター・ベースの悲しい曲だ。
言語はデリーの大学生の言葉遣いが最大限再現されており、英語とヒンディー語の自然なミックスとなっていた。ムートラヴィサルジャン(尿の放出)のようなシュッド・ヒンディー(純ヒンディー語)も冗談交じりで使われていた。中盤の最大の盛り上がりとなっているのが、ティーチャーズ・デー(教師感謝の日)式典におけるチャトゥルのヒンディー語演説だ。ウガンダ生まれでヒンディー語が不得手という設定のチャトゥルは、図書館の司書に演説内容を書いてもらい、暗記するが、ランチョーの悪戯によっていくつかの単語が致命的なものに置き換わっていた。例えばチャマトカール(奇跡)がバラートカール(強姦)、ダン(資金)がスタン(乳首)と言った具合に。だが、それに気付かずチャトゥルは得意になって学長や来賓の大臣の前で演説をし、大恥をかき、学長にも大恥をかかせてしまう。このときの恨みが、10年後の招集につながっていた。ティーチャーズ・デーはインドでは9月5日に祝われる。だから9月5日にファルハーンとラージューはチャトゥルによって大学に呼ばれたのだった。チャトゥルのスピーチ解説も参照のこと。
少子化が進み、いわゆる「ゆとり教育」が主流となった日本では、もしかしたらもう過去のような熾烈な受験戦争はないのかもしれない。だが、未成年人口が多く、学歴社会の傾向が顕著なインドの若者はますます熾烈な受験戦争にさらされている。その中で、競争だけが人生ではない、成功を追うことだけが成功の近道ではない、年収だけが人間の価値ではないという価値観を示す「3
Idiots」は、現代インド社会が向かう先への警鐘が込められた鋭い映画となっていた。もちろん皆が皆ランチョーのような人生を歩むことは出来ない。しかし、ランチョーのような生き方、考え方が公に認められる社会を作って行くことは急務であろう。インドの大学生活の様子がスクリーン上でうまく再現されていた点も個人的な体験から楽しめた。そして何より映画の語り口が斬新で飽きが来ず、3時間丸々スクリーンに釘付けになった。アーミル・カーンやボーマン・イーラーニーの演技も素晴らしい。「3
Idiots」は一応チェータン・バガトの小説が原作ということになっている。原作は未見なのだが、映画は原作の大枠を翻案しただけで、ほとんど別のストーリーになっているようだ。原作を読まない方が楽しめる作品かもしれないが、きっと「スラムドッグ$ミリオネア」(2008年)とヴィカース・スワループ原作「Q&A」のように、どちらもそれぞれ楽しめる作品になっているのだろう。今年最後の作品となってしまったが、文句なく今年ベストの映画であり、全ての人に勧めたい必見の映画である。
(追記:イディヤット論争も参照のこと)



